履歴書の敬語は「ですます」「である」どっち?正しい使い方やNG表現
「履歴書の敬語って、『ですます』と『である』、どっちが正解なんだろう…?」と迷った経験はありませんか?文体の選び方によって、あなたの人柄や志望の真剣度が企業にどう伝わるかが変わってきます。
そこで本記事では、「ですます調」と「である調」それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、履歴書にふさわしい敬語の使い方や避けたいNG表現までをわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書の敬語は「ですます調」「である調」どちらを使うべき?

履歴書では、「ですます調」でも「である調」でも問題はありません。それぞれに印象や使いどころの違いがあるため、適切に使い分ける意識を持ちましょう。
迷ったときは「ですます調」を選ぶのが無難です。学生の履歴書ではよく使われており、丁寧で柔らかい印象を持たれやすくなります。
一方で、「である調」は職務経歴書や論理性が求められる文書で使われることもあり、きっぱりとした印象を与えるでしょう。企業の社風や応募する職種によっても、適した語調は異なります。
大切なのは、「自分がどんな人物に見られたいか」「どんな印象を持ってもらいたいか」という視点から語調を選ぶことです。また、語調の選択よりも重要なのが、文全体で語尾を統一することです。
企業によっては文章力や論理性も見ているため、語尾の不統一はマイナス評価につながるおそれがあるのです。文体の一貫性を意識しながら、履歴書を作成しましょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
【ですます調】で履歴書を書くメリット

履歴書の文体は、採用担当者に与える印象を大きく左右します。その中でも「ですます調」は、多くの就活生が選んでいる文体です。
ここでは、「ですます調」を使うことで得られるメリットをわかりやすく紹介します。
- 丁寧な印象を与えられる
- 採用担当者が読みやすい文体になる
- 一般的な印象で安心感を与える
- エントリーシートとの整合性を保ちやすい
- 敬語が自然に使いやすい
① 丁寧な印象を与えられる
就活では、最初に読まれる履歴書で良い印象を与えることが大切です。「ですます調」を使うと、柔らかく丁寧な印象を相手に伝えられます。
まだ顔を合わせていない段階だからこそ、言葉づかいには気を配りたいものです。同じ内容でも、「である調」では少し堅苦しく感じられることがありますし、上から目線に見えてしまうおそれもあります。
相手に不快感を与えず、誠実な印象を届けたいと考えるなら、「ですます調」を使うほうが安心です。
② 採用担当者が読みやすい文体になる
「ですます調」は、採用担当の読む負担が少ない文体といえます。特に採用担当者は、日々大量の履歴書に目を通しているため、読みやすさは重要です。
「である調」は堅くなりやすく、文のリズムも単調になりがちなため、内容が頭に入りにくいと感じられる場合があります。
反対に、「ですます調」で書かれた文章は自然な流れで読み進められ、伝えたい内容がスムーズに届きやすいでしょう。
③ 一般的な印象で安心感を与える
「ですます調」は多くの応募者が使っている文体です。そのため、採用担当にとっても違和感がなく、スムーズに読み取れる点が魅力です。
「である調」を使うと、論文のような硬い印象になることがあり、内容よりも文体の印象が強く残るケースも少なくありません。
一方で「ですます調」は、形式として一般的であるため、文体が注目されることは少なく、自然と内容に目が向くでしょう。応募書類で余計な印象を残さないためにも、安心感のある文体が求められます。
④ エントリーシートとの整合性を保ちやすい
履歴書とエントリーシートを同じ文体で統一しておくと、採用担当に一貫した印象を与えることができます。企業側としても、統一感のある応募書類は好感を持ちやすいものです。
もし履歴書が「ですます調」で、エントリーシートが「である調」だった場合、違和感を持たれることもあるでしょう。細かい点ですが、文体が一致しているかどうかは、書類全体の完成度に影響します。
丁寧に作られた印象を残したいなら、文体は揃えておくのが得策です。
⑤ 敬語が自然に使いやすい
「ですます調」は、敬語を含めた文章をスムーズに書きやすいのも利点のひとつです。普段から使い慣れているため、言い回しに悩むことが少なく、自然な文章に仕上げやすいでしょう。
反対に、「である調」は敬語との相性がやや難しく、文のバランスが崩れることがあります。語尾の処理に迷ったり、敬語が不自然になったりすることも少なくありません。
とくに文章作成に自信がない就活生にとって、「ですます調」はミスを減らし、丁寧さも保てる安全な選択といえるでしょう。
【ですます調】で履歴書を書くデメリット

「ですます調」は丁寧で一般的な表現ですが、使い方を間違えると逆効果になることがあります。親しみやすさの一方で、内容がぼんやりとしたり、読みづらく感じられるケースも少なくありません。
ここでは、「ですます調」が持つ代表的なデメリットを5つの観点から紹介します。
- 単調で個性がうすくなる可能性がある
- 文章が冗長になりやすい可能性がある
- 語尾が繰り返されて読みにくい可能性がある
- 意志や主体性が伝わりにくい可能性がある
①単調で個性がうすくなる可能性がある
「ですます調」は丁寧な印象を与える一方で、似たような表現が多くなりがちです。そのため、他の応募者と文章の雰囲気が重なってしまい、個性が伝わりにくくなるおそれがあります。
とくに自己PRや志望動機のように自分らしさをアピールしたい場面では、文体だけで埋もれてしまうこともあるでしょう。
文構成や語彙選びに工夫を加えることで、「ですます調」でも自分らしさをしっかり表現できます。伝え方にも気を配ることが大切です。
②文章が冗長になりやすい可能性がある
「ですます調」は丁寧さを重視するぶん、文が長くなる傾向があります。
たとえば「〜いたします」「〜させていただきます」といった表現は、文字数が多くなりやすく、文章全体がくどく感じられることもあるでしょう。
履歴書では、限られたスペースの中で簡潔に情報を伝える力も求められます。丁寧さを保ちつつ、言葉をそぎ落として読みやすい構成に整えるよう心がけてください。
③語尾が繰り返されて読みにくい可能性がある
「〜です」「〜ます」といった語尾が続くと、文章に抑揚がなくなり、単調で読みにくい印象を与えることがあります。とくに、同じ語尾が何文も連続するような書き方は避けたいところです。
接続詞を工夫したり、体言止めを取り入れたりすることで、文章にリズムが生まれます。語調を変えずに読みやすさを向上させる工夫をしてみてください。
④意志や主体性が伝わりにくい可能性がある
「〜と思います」「〜したいです」といった表現は丁寧ですが、少し控えめに聞こえる場合があります。
強く伝えたい内容や、自分の意志をはっきり示したい場面では、言い切る形のほうが適しているかもしれません。
「〜します」「〜と考えています」などのように、やや強めの語尾に変えることで、熱意や自信が伝わりやすくなります。語調に頼るのではなく、言葉選びや文の構成で意思表示を工夫しましょう。
【である調】で履歴書を書くメリット

履歴書の文体は、自分の印象を左右する重要なポイントです。「である調」は堅い印象を持たれがちですが、伝え方によっては評価につながる強みもあるでしょう。
ここでは、「である調」を使用するその主なメリットを紹介します。
- 論理的で説得力がある印象を与える
- 意志の強さや主体性をアピールできる
- 文章量をコンパクトにまとめられる
- ビジネス文書に近いスタイルで好印象を与える
- 専門性の高い内容に自然にマッチする
① 論理的で説得力がある印象を与える
履歴書では、内容だけでなく表現方法も評価の対象になります。「である調」を使うと、文章が簡潔になり、筋の通った印象を持ってもらいやすくなるでしょう。
特に研究成果やインターン経験など、論理性が求められる場面では効果的です。「ですます調」は丁寧で親しみやすい一方、やわらかさが前面に出るため、主張がぼやけてしまうこともあります。
その点、「である調」は言い切りの表現が多いため、読み手に説得力を持って伝えることができるでしょう。理知的で明快な印象を与えたいときに向いています。
② 意志の強さや主体性をアピールできる
企業は就活生の主体性や意志の強さを重視します。「である調」は断定的な言い回しが多いため、自分の考えをはっきり伝えやすくなります。
たとえば「○○を経験したことで、~と考えるようになった」といった表現でも、「である調」を使うことでブレのない言葉に仕上がるのです。
自分の意見や判断を明確に伝えることで、行動力や覚悟を感じ取ってもらえるでしょう。リーダー経験や挑戦の話題では、特に相性が良い文体です。
③ 文章量をコンパクトにまとめられる
「である調」は語尾が短くなるため、全体の文章量を抑えやすくなります。履歴書は限られたスペースで自分を表現しなければならないため、このコンパクトさは大きな武器になります。
同じ内容でも、言い回しによって文字数に差が出るものです。文章を削りすぎて内容が薄くなるのは避けたいですが、伝えたい情報を過不足なく収めるには、「である調」のほうが便利な場合もあるでしょう。
すっきりした印象も好印象につながります。
④ ビジネス文書に近いスタイルで好印象を与える
「である調」は、ビジネス文書や報告書のようなフォーマルなスタイルに近いため、社会人としての意識を感じさせることができます。
特に理系や専門職を志望している場合は、文体の整然さがプラスに働くでしょう。社会人になると、客観的で論理的な文章が求められる場面が多くなります。
そのため、履歴書の段階からそうした文章に慣れておくことで、担当者に「社会人としての準備ができている」と思ってもらえるかもしれません。業界や職種によって、あえて選ぶ価値があります。
⑤ 専門性の高い内容に自然にマッチする
学術的な内容や専門的な知識を伝えるとき、「である調」はとてもなじみやすい文体です。必要以上に飾らず、事実を淡々と伝えることで、内容そのものの重みが伝わりやすくなります。
たとえば「○○を用いてデータを分析し、△△という結果が得られた」といった文章も、「である調」でまとめると論理の流れが自然になり、説得力も高まります。
エンジニアや研究職を目指す人には特に適しており、専門性をしっかり伝える手段として有効です。
【である調】で履歴書を書くデメリット

「である調」は論理的で簡潔な印象を与えやすく、知的なイメージを持たれる一方で、書き方によっては逆効果になることもあるのです。
ここでは、「である調」を使う際に注意したい代表的なデメリットを4つの観点から紹介します。
- 堅苦しく冷たい印象になる可能性がある
- 丁寧さに欠ける印象を持たれる可能性がある
- 断定的すぎる表現になる可能性がある
- 読みにくくなる可能性がある
①堅苦しく冷たい印象になる可能性がある
「である調」はすっきりした文章に向いていますが、場合によっては冷たく感じられることがあります。とくに熱意や共感を伝えたい場面では、表現が硬すぎて感情が伝わりにくくなることもあるでしょう。
採用担当者によっては、冷静すぎる人だと受け取るかもしれません。少しやわらかさを出したいときは、言葉の選び方や語尾に配慮して、印象を調整してください。
②丁寧さに欠ける印象を持たれる可能性がある
「である調」はビジネス文書では定番ですが、履歴書は丁寧さや配慮も見られる文書です。そのため、「〜である」と断定する語調が、強すぎると感じられる場合もあります。
初対面の相手に渡す書類だからこそ、適度にやわらかさを含んだ語り口のほうが安心感を与えることもあるでしょう。相手にどう受け取られるかを意識して書くことが大切です。
③断定的すぎる表現になる可能性がある
「〜である」は自信や信念を表すのに適していますが、強く断定する印象が続くと独りよがりに見られるおそれがあります。
たとえば、「私は貴社に大きく貢献できる人物である」と書いたとき、その根拠が示されていなければ、ただの自己主張と受け取られてしまうかもしれません。
伝えたい内容には理由や背景を添えて、読み手に納得してもらえる形に整えてください。
④読みにくくなる可能性がある
「である調」は語尾のバリエーションが少なく、長文になると単調になりやすいです。その結果、文が硬く感じられ、読みづらさにつながることもあります。
応募書類では読みやすさも評価の対象ですので、文章の構成や文の長さを意識して調整するとよいでしょう。ときには句読点の使い方を工夫し、スムーズに読み進めてもらえるよう配慮してください。
履歴書で「ですます」と「である」の敬語を使い分けるコツ

履歴書を書くときに、「ですます」と「である」のどちらを使うべきか迷う人は多いでしょう。
どちらかに統一する方法もありますが、文の内容や目的に応じて使い分けることで、より効果的に自分の魅力を伝えられるのです。
ここでは、使い分けのコツを具体的に紹介します。
- 与えたい印象で語調を使い分ける
- 志望動機や自己PRで役割を分ける
- 文字数や文章構成で判断する
- 内容のフォーマルさで選び分ける
- 企業文化や業界に合わせて調整する
① 与えたい印象で語調を使い分ける
語調は、読み手に与える印象に直接影響します。やわらかく丁寧な雰囲気を出したい場合は「ですます調」、論理的で自信ある印象を届けたいときは「である調」が向いています。
たとえば、チームワークや気配りを伝えたいなら「ですます調」が適しているでしょう。一方で、判断力や主体性をアピールしたい場合は「である調」の方が説得力を持たせやすくなります。
まずは、自分がどう見られたいかを考えることが大切です。
② 志望動機や自己PRで役割を分ける
履歴書にはさまざまな項目がありますが、その内容に応じて語調を使い分けると、より伝わりやすくなります。たとえば、志望動機では「ですます調」を使うと、企業への敬意が伝わりやすくなるでしょう。
一方で、自己PRでは「である調」を使うと、意見をはっきり表現でき、自信のある印象につながります。ただし、項目ごとに語調がバラバラだと違和感があるため、全体の調和も意識して調整してください。
③ 文字数や文章構成で判断する
履歴書は記入スペースが限られているため、文章の長さも重要なポイントになります。「である調」は語尾が短く、文章をコンパクトにまとめやすいため、多くの情報を盛り込みたいときに便利です。
逆に、「ですます調」は丁寧さを表現できる反面、文が長くなりやすいです。書きたいことがうまく収まらない場合は、「である調」を使うことで文章が引き締まり、構成もしやすくなるでしょう。
④ 内容のフォーマルさで選び分ける
文の内容がフォーマルであるほど、「である調」が自然に合います。たとえば、研究成果やインターンでの取り組みなどを説明する場合は、客観的で整った表現が求められます。
そのようなときは、「である調」を使うと読み手に信頼感を与えることができるでしょう。
反対に、自己紹介や志望企業への思いなど、感情を込めたい場面では「ですます調」のほうが親しみやすく、温かみを伝えやすくなります。
⑤ 企業文化や業界に合わせて調整する
語調は自分の好みだけでなく、応募する企業や業界に合わせて選ぶことも大切です。たとえば、金融やコンサルなどの堅めの業界では、「である調」が信頼を得やすいでしょう。
一方、広告やベンチャー企業などでは、「ですます調」の方が自然で柔軟な印象を与えることができます。企業のホームページや社員の言葉などを参考に、どちらの文体がふさわしいか見極めてください。
相手に合わせる工夫も、評価につながります。
履歴書で「ですます」の使用例文
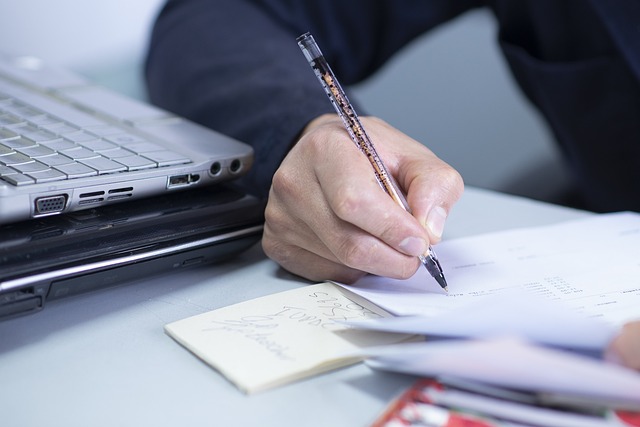
履歴書を「ですます調」で書くと、柔らかく丁寧な印象を与えやすいですが、実際にどんな表現にすればよいのか悩む方も多いでしょう。
ここでは、志望動機や自己PRで使いやすい具体例をテーマ別に紹介します。
①丁寧で親しみやすい印象を与えたい場合
応募先に対して、真面目さや人柄の良さが伝わるような表現を心がけたい方に向けて、丁寧で親しみやすい文章例を紹介します。敬語を自然に使いながらも、やわらかさや誠実さがにじむ内容を意識しました。
《例文》
| 私は人と関わることが好きで、アルバイトでは常にお客様との会話を大切にしてまいりました。 特に、子ども向けイベントの受付業務では、初めて来場された方にも安心して楽しんでいただけるよう、笑顔を心がけて接しております。 小さな気配りや丁寧な対応を積み重ねることで、お客様から「また来たい」と言っていただけたことが大きな喜びでした。 この経験を通して、人と信頼関係を築くことの大切さを学び、今後も相手の立場に寄り添う姿勢を大切にしていきたいと考えております。 |
《解説》
「笑顔」や「気配り」など、具体的な行動を交えて丁寧な印象を作っています。親しみやすさを出すには、やわらかい語り口と相手目線の工夫が効果的です。
②熱意や感謝を表現したい場合
企業に対して強い志望動機や感謝の気持ちを伝えたいときには、真摯な言葉選びと自分の思いを丁寧に言語化することが重要です。ここでは、熱意と感謝が自然に伝わる例文を紹介します。
《例文》
| 貴社の企業理念に深く共感し、説明会に参加した際には社員の方々の温かさと誠実な姿勢に感銘を受けました。 私自身も人との信頼関係を大切にしており、貴社の一員として社会に貢献したいという思いが一層強まっております。 大学ではボランティア活動を通じて、多様な立場の方々と協力しながら目標を達成する経験を積んできました。 この経験を生かし、常に感謝の気持ちを忘れず、周囲と協力しながら行動していきたいと考えております。 |
《解説》
企業との出会いや体験をきっかけにした言及は、感謝や熱意を伝える際に効果的です。ありきたりな表現ではなく、具体的な経験を交えて伝えることがポイントです。
③協調性や柔らかさを伝えたい場合
チームでの経験や周囲との協力を重視する姿勢をアピールする際は、柔らかな表現で自身の性格や行動が伝わるよう工夫しましょう。ここでは、協調性と優しさが感じられる例文をご紹介します。
《例文》
| 大学ではサークル活動の中で、イベントの企画や運営に携わっています。特に、メンバー全員が気持ちよく参加できるよう、意見を聞きながら進行役を担うことを意識してきました。 自分の意見を主張するだけでなく、相手の立場を考えて対応する姿勢が、メンバーの信頼につながったと感じたのです。 今後もチームの中で役割を見極め、周囲と連携しながら成果を出していけるよう努めてまいります。 |
《解説》
協調性を示すには、他者の意見に配慮した行動や関係構築のエピソードを盛り込むと効果的です。自分の行動に対する周囲の反応も添えると、説得力が増します。
履歴書で「である」の使用例文
履歴書に「である調」を使いたいけれど、どのように書けばよいか迷っていませんか?
ここでは、伝えたい印象に応じた「である調」の具体的な例文を紹介します。
論理性や自信、冷静さなど、自分の強みを的確に伝える表現を学びましょう。
①論理的で誠実な印象を与えたい場合
論理的かつ誠実な印象を与えたい場面では、物事の経緯や結果を整理して伝えることが大切です。ここでは、具体的なエピソードを踏まえて、自分の姿勢や考え方を伝える例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学でのゼミ活動において、地域課題の調査プロジェクトに参画している。 活動の初期段階では、調査対象となる住民からのアンケート回収が思うように進まず、協力を得る難しさに直面していた。 このままでは成果につながらないと判断し、説明内容を再構成。調査の目的や個人情報の取り扱いについて、住民が安心できるよう丁寧な説明を心がける方針へと転換した。 その取り組みにより、回答数は着実に増加し、信頼性の高いデータの収集にも成功する。 こうした経験から、相手の視点に立ち、真摯に向き合う姿勢が信頼関係の構築に不可欠であることを強く認識した。 今後も、どのような課題に直面しても、状況を冷静に見極めたうえで、誠実な行動によって道を切り開いていきたいと考える。 |
《解説》
因果関係を整理し、具体的な行動と結果を明確に述べることで、論理性と誠実さの両方が伝わります。対人関係や改善のプロセスが含まれるテーマを選ぶと効果的です。
②自信や主体性を示したい場合
自信や主体性をアピールする際は、自ら考え行動した経験を具体的に述べることで説得力が高まります。ここでは、自主的な挑戦とその成果を示す例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学2年時、学園祭の実行委員会において初めて広報チームのリーダーを務めることとなった。 例年以上の集客を実現するには何が必要かを検討した結果、SNSの活用が効果的であると考え、自ら企画立案から運用までを担うことにした。 チーム内にはSNSに不慣れなメンバーも含まれていたが、投稿ルールやスケジュールを共有し、明確な役割分担を図ることで協力体制を構築。 投稿内容についても試行錯誤を重ねながら改善を継続した。その結果、フォロワー数は前年比の2倍に達し、来場者数の増加にも寄与する成果となる。 この取り組みを通じて、目標達成に向けて主体的に行動する力と、周囲を巻き込みながら成果を導く力が培われたと実感している。 |
《解説》
目標に対して自分の判断で行動した点や、成果に至るまでの工夫を盛り込むと、自信と主体性の両方が伝わります。リーダー経験だけでなく、小さな挑戦でも具体性が大切です。
③冷静さや客観性を強調したい場合
冷静さや客観性をアピールするには、感情的にならずに状況を分析し、判断・行動できた経験を具体的に伝えることが重要です。ここでは、そうした姿勢が伝わる例文を紹介します。
《例文》
| 私は学内のディスカッション型授業において、意見の対立が顕著なグループの進行役を務めた。 議題は日常に関する身近なテーマであったものの、各メンバーの主張がぶつかり、話し合いは一時的に停滞する局面を迎える。 そうした状況においても、私は冷静さを保ち、発言内容を整理して全体に共有することにより、論点の可視化と意見の橋渡しを意識した。 加えて、相手の視点に立つ重要性を提示し、建設的な議論へと再び軌道を戻す工夫を重ねた。最終的には、全員が納得できる形で結論に到達し、グループ全体の満足度も高まる。 この経験を通じ、感情に左右されず全体を俯瞰する姿勢こそが、円滑な対話と合意形成を生む基盤であると実感している。 |
《解説》
冷静さを伝えるには、対立や混乱の場面でどう対応したかを具体的に書くと効果的です。感情を抑えつつ周囲に働きかけた行動に注目して構成しましょう。
履歴書で敬語を使う際の注意点

履歴書では、正確で適切な敬語が求められます。丁寧なつもりで書いたつもりでも、実は間違っていたというケースは意外と多いものです。
読み手に違和感を与えないためにも、基本的なポイントを押さえておくことが大切になります。
ここでは、履歴書でありがちな敬語の注意点を5つに分けて紹介します。
- 尊敬語と謙譲語の使い分けを意識する
- 「〜させていただく」の多用を避ける
- 「御社」ではなく「貴社」を使う
- 話し言葉ではなく書き言葉で記載する
- 全体を通して敬語の統一を図る
①尊敬語と謙譲語の使い分けを意識する
敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類がありますが、違いを理解し、正しく使うことが重要です。
なかでも尊敬語と謙譲語の使い分けを意識しましょう。たとえば「拝見する」は謙譲語、「ご覧になる」は尊敬語です。また、相手の行動には尊敬語、自分の行動には謙譲語を用いるのが基本です。
これらを混同すると、失礼な印象を与えてしまうかもしれません。履歴書を書く前に、一度自分の敬語表現を見直してみてください。
②「〜させていただく」の多用を避ける
「〜させていただく」は丁寧に聞こえる表現ですが、多用すると読みにくくなる原因になります。本来この表現は、相手の許可や恩恵を受けた行動に限定して使うのが適切です。
たとえば、「拝見させていただきました」は「拝見しました」と言い換えたほうが自然でしょう。文の丁寧さを保ちつつ、無理に敬語を重ねないよう意識してください。
③「御社」ではなく「貴社」を使う
履歴書や職務経歴書といった文書では、「御社」ではなく「貴社」を使うのが適切です。「御社」は口頭でのやりとりにふさわしく、面接などの場面で使われます。
一方で、「貴社」は書き言葉としての表現にあたります。混同しやすい表現ですが、書類では「貴社」を用いるようにしましょう。
この違いを理解しているかどうかで、敬語の基本が身についているか判断されることもあります。
④話し言葉ではなく書き言葉で記載する
履歴書は会話文ではなく正式な文書であるため、話し言葉は使用しないようにしましょう。たとえば「〜じゃない」「〜とか」「〜なんで」といった話し言葉は避けるべきです。
「とても頑張ったんで成果が出ました」という表現は、「努力を重ねた結果、成果が出ました」と書き換えるほうがふさわしいでしょう。読み手に失礼のないよう、整った書き言葉を意識してください。
⑤全体を通して敬語の統一を図る
敬語は文全体で統一感があることが大切です。「〜でございます」と「〜です」が混在していると、不自然に感じられることがあります。
最初に「です・ます調」でいくのか、「である調」で書くのかを決めてから書き始めましょう。途中で語調が変わると、読み手に違和感を与えてしまうかもしれません。
文章の統一感を意識して、最後まで整った文体で書き上げてください。
履歴書で使ってはいけない言葉使い

履歴書では、丁寧な言葉を意識するあまり、間違った敬語や不適切な表現を使ってしまうことがあります。誤った言い回しはマイナス評価につながる可能性があるため、事前に確認して避けるようにしましょう。
ここでは、特に注意すべき言葉遣いの例を紹介します。
- 二重敬語
- 役職名に「様」をつける
- さ入れ言葉
- あいまいな表現
- 略語やくだけた言い回し
① 二重敬語
二重敬語とは、すでに敬語になっている表現にさらに敬語を重ねる言い回しです。たとえば「おっしゃられました」や「ご覧になられました」などが該当します。
一見丁寧に見えても、実際には誤用であり、不自然さを感じさせる表現です。履歴書でこのような言葉を使うと、敬語の理解不足と判断されるおそれがあります。
正しく伝えるためには、「おっしゃいました」や「ご覧になりました」といった表現を使うようにしてください。丁寧すぎる表現が逆効果になるケースもあるため、注意が必要です。
② 役職名に「様」をつける
敬意を表そうとして「部長様」や「課長様」と書く人がいますが、これは間違った使い方です。役職自体に敬意が含まれているため、あえて「様」をつける必要はありません。
正しくは「〇〇部長」や「部長の〇〇様」と表記します。過剰な敬語は逆にマナー違反と見なされることがあります。
丁寧に見せようとしすぎると、かえって不自然に感じられることがあるため、気をつけてください。
③ さ入れ言葉
「行かさせていただきます」や「拝見させていただきます」のような「さ入れ言葉」は、本来不要な「さ」が加わっているため、文法的に正しくありません。
就活では違和感を与える表現になってしまいます。たとえば「拝見させていただきます」は「拝見いたします」、「説明させていただきます」は「ご説明いたします」が自然な形です。
正確で簡潔な敬語を使うことで、相手にも好印象を与えやすくなるでしょう。
④ あいまいな表現
履歴書は自分の考えや経験を明確に伝える書類です。「だと思います」「〜かもしれません」などのあいまいな言い回しは、自信のなさを感じさせてしまいます。
たとえば「自分は責任感が強いと思います」と書くより、「私は責任感が強いと自負しています」と言い切る表現の方が、説得力と積極性を伝えられます。
言い切ることで熱意が伝わり、評価につながりやすくなります。
⑤ 略語やくだけた言い回し
履歴書は正式な書類ですので、「バイト」や「サークル」などの略語、「やばい」「すごかった」といった日常的な口語表現は避けましょう。
「アルバイト」や「学生団体」、「とても印象に残った」「非常に有意義だった」など、正確で落ち着いた言葉を選ぶことが求められます。
言葉づかいひとつで印象が大きく変わるため、丁寧で適切な表現を心がけてください。
履歴書で敬語を正しく使うために意識したいこと

履歴書で使用する敬語には、「ですます調」と「である調」があり、どちらも間違いではありません。ただし、それぞれが与える印象は異なります。
丁寧さや親しみやすさを重視するなら「ですます調」、論理性や主体性を強調したい場合は「である調」が向いているでしょう。重要なのは語調を統一することと、履歴書全体のバランスを整える意識です。
履歴書では敬語の正確さだけでなく、「尊敬語」と「謙譲語」の区別、「貴社」といった適切な表現の選択も大切。
使い分けのコツを押さえたうえで、自分の伝えたい印象に合わせた語調を選び、違和感のない丁寧な文章を心がけてください。就活では細かな言葉づかいの積み重ねが、信頼感にもつながります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










