全商資格は履歴書に書かない方が良い?判断基準と注意点を解説
「全商の資格って、履歴書に書かない方がいいのかな…?」
商業高校出身の学生にとって、全商検定は頑張りの証。しかし、企業によっては評価のされ方が異なるため、書くべきか迷う人も多いでしょう。
そこで本記事では、全商資格と履歴書をテーマに、書く・書かないの判断基準や注意点、記載する際のコツをわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
全商資格を履歴書に書くべきか悩む人も多い

就職活動の準備を進める中で、「全商資格って履歴書に書くべきなのかな」と迷う学生はとても多いです。
高校時代に取得したものの、大学や志望業界とのつながりが見えにくく、書くことで印象が良くなるのか、それとも逆効果になるのか判断が難しいと感じる人も少なくありません。
特に初めての就活では、資格欄の書き方ひとつで印象が変わることもあるため、慎重になるのは自然なことです。
実際、全商資格をめぐっては「書かないほうがいい」という意見もあれば、「アピールにつながる」と考える人もいます。
ネット上でもさまざまな情報があふれており、何を信じればいいのか分からなくなる学生も多いでしょう。ここでは、そうした不安や迷いを少しでも軽くし、全商資格と履歴書の関係を整理していきます。
自分にとって最適な判断ができるよう、一緒に考えていきましょう。
全商資格とは?
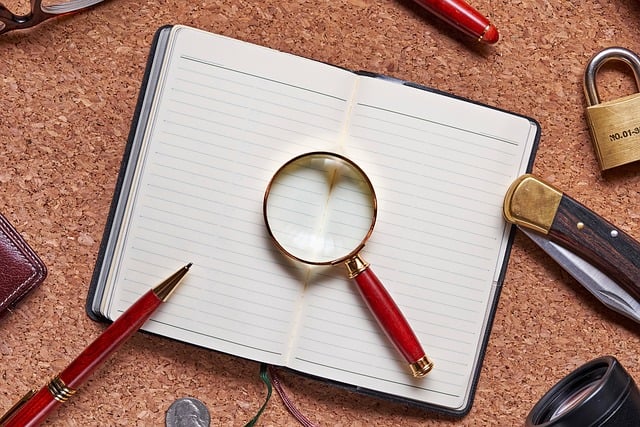
全商資格とは、「全国商業高等学校協会(全商)」が主催する検定試験で、高校の商業系学科に通う生徒を対象としています。主にビジネスや会計、情報処理など、社会で役立つ基礎スキルを証明する資格です。
就職や進学時に評価される場合もありますが、一般企業の採用担当者の間では知名度が限定的であることも少なくありません。
そのため、履歴書に記載するかどうかは、応募先や職種との関連性を踏まえて判断する必要があります。
たとえば、事務職や経理職を志望する場合、全商簿記検定やビジネス文書実務検定は業務に直結するスキルとして評価されやすいでしょう。
一方で、営業職や技術職など、資格内容との関連が薄い職種では、無理に記載しなくても問題ありません。つまり、全商資格は「書く・書かない」で答えが分かれる資格です。
大切なのは、資格そのものではなく「その資格をどう活かせるか」を明確に示すこと。履歴書に記載する場合は、取得した目的や学んだ内容を面接で説明できるようにしておくと、より好印象を与えられます。
全商資格を正しく理解し、自分の強みとして活用できるよう意識してください。
全商資格は履歴書に書くかの判断基準

履歴書に全商資格を記載するかどうかは、多くの就活生が悩むポイントです。
資格を取った意味を最大限に伝えるためには、応募先や職種との相性、資格のレベル、ほかの資格との兼ね合いなどを考慮する必要があるのです。ここでは、判断の基準となる5つの視点を紹介します。
- 全商資格が応募職種と関連しているか
- 全商資格の級や難易度が適切か
- 全商資格と他の資格のバランスが取れているか
- 全商資格が学生時代の活動や専攻と関連しているか
- 全商資格のアピール効果が十分にあるか
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①全商資格が応募職種と関連しているか
履歴書に全商資格を書くかどうかを判断するうえで、最も重要なのが「応募職種との関連性」です。資格の内容が仕事内容に直結する場合、強力なアピール材料になります。
たとえば、事務職や経理職を希望する場合、全商簿記検定やビジネス文書実務検定などは実務スキルとして高く評価されるでしょう。
一方で、営業職や販売職など、業務で直接活用しない資格の場合は、書かない選択も自然です。採用担当者は履歴書を短時間で確認するため、応募職種に関係のない情報が多いと印象がぼやけてしまいます。
ただし、関連が薄い場合でも、学びに取り組む姿勢や努力を伝えられるケースもあります。
その際は、「どのように役立てたか」や「資格取得で得たスキル」を具体的に説明できるようにしておくと効果的です。全商資格を書くかどうかは、「資格が仕事とどうつながるか」を軸に判断してください。
②全商資格の級や難易度が適切か
全商資格には複数の級があり、難易度によって評価が変わります。一般的に2級以上の資格であれば、履歴書に記載しても十分にアピールできるレベルです。
反対に3級以下は基礎的な知識の証明としては有効ですが、大学生の就活ではやや印象が弱いと感じられる場合があります。
企業の採用担当者は、資格そのものよりも「どの程度のレベルで理解しているか」を重視しています。難易度が高い資格であれば、努力や専門性が伝わりやすくなり、面接でも話題を広げやすいでしょう。
もし取得した資格が初級レベルであれば、単に書くだけでなく「そこから得た学び」や「他のスキル習得につなげた経験」を補足的に伝えることをおすすめします。
資格の級は単なる数字ではなく、努力と成長を示す指標でもあるのです。履歴書に書く際は、自分の強みを引き立てる級を意識しましょう。
③全商資格と他の資格のバランスが取れているか
資格は多ければ良いというものではありません。全商資格と他の資格とのバランスを見て判断することが大切です。履歴書の資格欄に似たような内容を並べすぎると、焦点がぼやけてしまうことがあります。
たとえば、全商簿記検定と日商簿記検定を両方持っている場合、企業側から見れば「どちらを主に活かせるのか」がわかりにくくなるでしょう。
そのような場合は、より上位の資格や実務的に評価されやすいものを中心に記載し、全商資格は補足的に扱うのが効果的です。
また、資格欄は「自分がどんなスキルを持っているか」を整理して見せる場所でもあります。バランスを意識することで全体の印象がすっきりし、採用担当者に伝わりやすくなるでしょう。
自分の強みを明確にするためにも、全商資格をどの位置づけで書くかを考えてみてください。
④全商資格が学生時代の活動や専攻と関連しているか
履歴書で資格を効果的に見せるには、取得の背景も重要です。特に、全商資格が学生時代の専攻や活動内容と関連している場合は、大きな強みになります。
たとえば、商業系の学科やゼミで会計・経営を学んでいた場合、全商資格は「学びを実践に活かした証拠」として評価されるのです。
また、資格取得に向けて努力した経験を通じて、計画性や継続力といった強みも伝えられるでしょう。一方で、専攻と関係のない分野の資格でも、興味を持って学び取った姿勢を示せれば好印象です。
企業は学びに積極的な人材を求める傾向があるため、「なぜこの資格を取ろうと思ったのか」を語れるようにしておくと効果的。
資格を単なる成果としてではなく、「学びの延長線上にある行動」として位置づけることが、説得力を高めるポイントです。
⑤全商資格のアピール効果が十分にあるか
全商資格を履歴書に書く目的は、自分の能力や姿勢を相手に伝えることです。しかし、資格をただ並べるだけでは印象的なアピールにはなりません。
大切なのは、資格が「どんな強みを示すのか」を明確にすることです。
たとえば、全商簿記検定なら数字に強く正確な処理能力があることを、情報処理検定ならパソコン操作やデータ分析が得意であることを伝えられます。
これらを志望職種と関連づけて説明することで、企業に「このスキルを活かせる人材だ」と感じてもらいやすくなるでしょう。また、全商資格は学生時代の努力を可視化できる証拠でもあります。
特に複数の資格を計画的に取得している場合は、目標設定や自己管理能力を評価される可能性も高いでしょう。
履歴書に書く際は、「資格を取った理由」や「得たスキルをどう活かすか」を意識して伝えることが、アピール効果を最大化するコツです。
履歴書に記載するメリット

全商資格を履歴書に書くことで、企業に良い印象を与えられる可能性があります。高校時代に取得した資格であっても、努力やスキルの証明として活かせる場面は少なくありません。
ここでは、全商資格を履歴書に記載することで得られる主な5つのメリットを紹介します。
- 資格取得への努力や向上心をアピールできる
- 基礎的なビジネススキルを証明できる
- 事務職や会計職などで評価されやすい
- 面接で話題のきっかけを作れる
- 他の学生との差別化につながる
①資格取得への努力や向上心をアピールできる
全商資格を履歴書に書く大きなメリットは、努力と継続力を示せる点にあります。
高校時代に目標を立てて勉強し、資格を取得した経験は、採用担当者に「計画的に行動できる人」という印象を与えるでしょう。
特に段階的に級を上げて取得している場合は、粘り強さや成長意欲を伝えるチャンスになります。また、全商資格の勉強は授業だけでなく、自主的な復習や演習を求められることが多いです。
そのため、「与えられた課題をこなす力」や「地道に取り組む姿勢」を評価されやすいでしょう。こうした姿勢は、どの職種でも求められる社会人基礎力です。
履歴書に書くことで、学業以外での努力を具体的に示すことができます。
②基礎的なビジネススキルを証明できる
全商資格には簿記やビジネス文書、情報処理など、社会で役立つ内容が多く含まれています。履歴書に記載することで、「基本的なビジネススキルを身につけている人」として評価されやすくなるでしょう。
企業が新卒に期待するのは専門知識よりも「基礎力」と「柔軟な吸収力」です。全商資格はそのどちらもアピールできる資格。たとえば全商簿記なら数字への理解力や論理的思考を示せます。
ビジネス文書検定であれば、社会人としての文章力や礼儀を伝えることができるでしょう。これらのスキルは、どんな業種にも共通して求められる要素です。
全商資格を持っていることで「ビジネスの基礎を理解している学生」と印象づけられるでしょう。
③事務職や会計職などで評価されやすい
事務職や会計職を目指す学生にとって、全商資格は特に効果的。これらの職種では、正確さや数字への理解、文書処理能力が求められるため、全商簿記や情報処理検定は高い評価につながりやすいです。
企業側から見ても、基本的な業務知識を持つ学生は教育コストが少なく、即戦力として期待できるでしょう。
さらに、複数の資格を組み合わせて記載すれば、「幅広い分野に興味を持って学んできた人」として印象を強められます。
応募先企業の業務内容と関連性がある資格を選んで記載することで、より効果的なアピールが可能です。事務系職種を志望するなら、全商資格を履歴書に書いて損はありません。
④面接で話題のきっかけを作れる
履歴書に全商資格を記載しておくと、面接で自然な話題づくりにつながります。
面接官が「この資格は高校で取得されたんですね」「どんな勉強をされたんですか」と質問してくれることが多いため、緊張を和らげつつ自分の努力を伝えられるでしょう。
また、資格取得までの過程で得た経験――たとえば「苦手な分野を克服した」「友人と学び合いながら勉強した」など――を具体的に話せば、あなたの人柄や行動力を印象づけることも可能です。
面接で会話が広がることで、面接官に覚えてもらいやすくなります。資格は単なる記載事項ではなく、自分を語るきっかけになるのです。
⑤他の学生との差別化につながる
全商資格を履歴書に記載することは、他の学生との差別化にも有効です。大学生活では資格を取らない学生も多く、高校時代からスキル習得に励んできたことを示せるため、印象に残りやすいでしょう。
採用担当者は短時間で多くの履歴書を確認するため、何か一つでも目を引く要素があると有利に働きます。
たとえ資格のレベルが高くなくても、「努力を継続できる人」「学びに前向きな人」という印象を与えることが大切です。全商資格は、そうした姿勢を裏づける証拠になります。
地道な努力を評価してもらうためにも、積極的に活用してください。
全商資格の正しい履歴書への書き方

全商資格を履歴書に記載するときは、正しい形式で書くことが重要です。せっかく取得した資格でも、書き方を間違えると印象を下げてしまうことがあるでしょう。
ここでは、全商資格を正確でわかりやすく記載するための4つのポイントを紹介します。
- 正式名称で書く
- 取得年月を正確に書く
- 複数の全商資格は取得順に書く
- 勉強中の資格は「取得予定」と書く
①正式名称で書く
履歴書では、全商資格を略さずに正式名称で書くことが基本です。たとえば、「全商簿記検定」ではなく「全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定試験」と記載するのが正しい書き方になります。
正式名称を使うことで、採用担当者が資格の内容を正確に理解しやすく、信頼感のある印象を与えられるでしょう。また、資格によっては似た名称のものも多く、省略すると誤解されることがあります。
特に「日商簿記」と「全商簿記」は混同されやすいため、正式名称で明確に区別してください。書き方の例としては「全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定試験 2級合格」と記載するとよいでしょう。
履歴書は自分の経歴を正式に伝える書類です。小さな部分まで丁寧に記入する姿勢が、誠実さを感じさせるポイントになります。
②取得年月を正確に書く
資格欄には、取得年月を正確に記入することが大切です。履歴書では「年」と「月」を明記するのが基本で、たとえば「2023年7月 全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定試験 2級合格」といった形が適切。
取得年月を正しく記載することで、努力の時期や学びの過程が伝わります。
採用担当者は資格の内容だけでなく、「いつ取得したか」も確認しており、学生時代に積極的に学んでいた姿勢を評価してくれるでしょう。古い資格でも年月を省略せず、正確に書くことが大事です。
あいまいな表現や省略は、履歴書全体の印象を損ねてしまいます。小さな点にも注意を払い、丁寧な書き方を心がけてください。
③複数の全商資格は取得順に書く
全商資格を複数持っている場合は、取得した順番で書くのがおすすめです。時系列で並べることで、努力の積み重ねや成長の過程を自然に伝えられます。
たとえば、簿記実務検定・情報処理検定・ビジネス文書実務検定を持っている場合は、取得した順に「2022年7月~2024年2月」のように並べましょう。
最新の資格を先に書く方法もありますが、資格欄では一貫性を持たせることが読みやすさのカギです。また、複数の資格を記載するときは、1行ずつ改行して整理してください。
資格の数が多くても、同じ書式で統一すれば見やすい履歴書になります。視覚的に整った履歴書は、読み手に好印象を与えやすいものです。
④勉強中の資格は「取得予定」と書く
まだ合格していない資格を履歴書に書く場合は、「取得予定」と明記するようにしましょう。
たとえば「全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定試験 1級 取得予定(2025年3月)」のように書くと、具体的な目標や意欲を伝えられます。
ただし、実際に受験予定がないのに「取得予定」と書くのは避けてください。誤解を招く可能性があります。
「勉強中」や「受験予定」といった表現も使えますが、できるだけ日付を添えると信頼性が高まるのです。資格取得に向けて努力している姿勢は、企業に好印象を与えます。
たとえ合格前であっても、目標を明確にしていることを伝えられれば、「成長意欲のある学生」として評価されるでしょう。
履歴書には、これまでの成果だけでなく、今後の取り組みも積極的に反映させてください。
履歴書の免許・資格欄に全商資格を書くときの注意点

全商資格は履歴書の印象を左右する大切な要素です。しかし、書き方や記載の判断を誤ると、せっかくの資格が逆効果になる場合も。
ここでは、全商資格を履歴書に書くときに気をつけたい5つのポイントを紹介します。
- 応募職種と関係がない場合は書かない
- 資格欄のスペースを埋めるためだけに書かない
- 資格名を間違えない
- 略称や省略表現は使わない
- 他の資格との優先順位を誤らない
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①応募職種と関係がない場合は書かない
全商資格を履歴書に書く際は、志望する職種との関係性を確認することが大切です。
たとえば、経理や事務、販売職など数字や資料を扱う仕事であれば評価されやすいですが、デザイン職やエンジニア職のように専門分野が異なる場合は、強みとして伝わりにくいかもしれません。
採用担当者は履歴書から「どんなスキルを持っているのか」「どう仕事に活かせるのか」を見ています。そのため、関連性の低い資格を並べると「方向性が定まっていない」と思われる可能性があるのです。
記載する際は「数字に強い」「事務処理が得意」など、仕事に結びつく形で伝えるようにしましょう。資格は書くこと自体よりも、どう活かせるかを意識することが重要です。
②資格欄のスペースを埋めるためだけに書かない
履歴書の資格欄を埋める目的で全商資格を書くのは避けたほうが良いでしょう。履歴書の目的は、自分の強みを効果的に伝えることです。
関係のない資格を無理に並べても、印象が良くなるどころか「見栄えを意識しすぎている」と受け取られてしまうことがあります。スペースが空いていても問題ありません。
むしろ、関連性の高い資格を厳選して書くことで、整理された印象を与えられます。
もし全商資格に触れたい場合は、志望動機や自己PRで「高校時代に基礎を学んだ経験が今につながっている」と補足すると自然です。資格欄を「埋める」よりも、「伝える」意識を持ちましょう。
③資格名を間違えない
全商資格を記載する際は、正式名称を正確に書くよう注意してください。「全商簿記検定」と略してしまう人が多いですが、正式名称は「全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定試験」です。
略称のままだと、注意不足な印象を与えるおそれがあります。また、資格等級(例:2級・1級など)を省略しないことも大切です。
特に事務職や経理職など、正確さが求められる仕事を志望する場合は、細かい部分で信頼を損ねる可能性もあります。
履歴書を提出する前に、公式サイトなどで名称を確認し、正しい表記になっているかを必ず見直してください。小さな違いですが、丁寧さが伝わるポイントです。
④略称や省略表現は使わない
履歴書に資格を書くときは、略称や省略形を使わずに正式名称で記載しましょう。たとえば「全商簿記」や「全商情報処理検定」などと短縮して書くと、採用担当者が理解できない場合があります。
全商資格に詳しくない人にも正しく伝わるよう、「全国商業高等学校協会主催 ○○検定試験 2級」と正式な書き方を心がけてください。
多少文字数が増えても問題ありません。むしろ、正確で丁寧に書かれた履歴書は、誠実な印象を与えます。略称は簡潔に見えますが、就職活動の場面では「読み手に分かりやすい」ことを優先しましょう。
採用担当者に正しく伝わる記載が信頼につながります。
⑤他の資格との優先順位を誤らない
履歴書の資格欄には、ただ時系列で書くのではなく「伝えたい順」で整理することをおすすめします。
たとえば「日商簿記2級」と「全商簿記1級」を持っている場合は、一般的に日商簿記のほうが評価されやすいため、先に書くほうが自然です。全商資格は基礎を示す資格として位置づけるのが効果的。
上位資格や実務的な資格と組み合わせて書くことで、「段階的にスキルを伸ばしてきた人」という印象を与えられます。
資格欄は単なる一覧ではなく、自分の努力や成長を伝えるストーリーとして活用してください。優先順位を意識して書くことで、履歴書全体の印象がより引き締まるでしょう。
全商資格を効果的にアピールするポイント

全商資格は、履歴書に書くだけでなく、自己PRや面接での伝え方によって印象が大きく変わります。資格そのものよりも「どう活かせるか」を具体的に示すことが大切です。
ここでは、全商資格を効果的にアピールするための5つのポイントを紹介します。
- 自己PR欄で学んだ内容やスキルを伝える
- 志望動機に資格取得の背景を盛り込む
- 面接で資格取得の努力や工夫を話す
- 業務にどう活かせるかを具体的に示す
- 他の資格や経験と組み合わせて強みを示す
①自己PR欄で学んだ内容やスキルを伝える
自己PR欄では、資格名を並べるだけでなく、学びを通して得たスキルや成長を具体的に伝えることが重要です。
たとえば、全商簿記検定を通じて「数字を扱う正確さ」や「論理的な思考力」を身につけたなら、それをどのように活かせるかを説明すると説得力が増します。
また、資格取得までの努力や計画的に学習した経験をアピールするのも効果的です。採用担当者はスキル以上に「学び続ける意欲」や「粘り強さ」を重視する傾向があります。
具体的なエピソードを添えるとリアリティが生まれ、印象に残りやすくなるでしょう。全商資格は社会人としての基礎力を示す手段です。
「何を学び、どう成長したのか」を中心に書くことで、より魅力的な自己PRになります。
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
②志望動機に資格取得の背景を盛り込む
志望動機に全商資格を取得した背景を盛り込むことで、説得力のある内容にできます。
たとえば、「経理職を志望したきっかけが簿記の学びだった」「情報処理を学ぶ中でデータ分析に興味を持った」といったように、自分の進路と資格取得のつながりを示すと良いでしょう。
「資格を持っている」だけでは印象に残りにくいものです。資格取得の動機や過程を伝えることで、主体的に学び行動する姿勢が伝わります。
企業は目的を持って努力できる人材を評価する傾向があるため、学びの背景を具体的に説明してください。
また、資格内容と企業の業務を結びつけることで、「入社後にどのように活かせるか」を自然に伝えられます。志望動機に資格を盛り込むことで、一貫性のある自己紹介ができるでしょう。
③面接で資格取得の努力や工夫を話す
面接では、全商資格を取得するまでの努力や工夫を話すと、前向きな印象を与えられます。
たとえば、「放課後の時間を活用して毎日1時間ずつ勉強した」「苦手分野を克服するために模試を繰り返した」など、具体的な体験を交えると効果的です。
資格取得の過程には、時間管理や問題解決の工夫など、多くの成長要素があります。これらを話すことで、「資格を持っている学生」から「自ら課題を見つけて取り組める人」へと印象を高められるのです。
さらに、資格を取ったことで得られた気づきや成長を添えると、話に深みが出ます。面接官は「資格をどう活かしてきたか」「今後どう使うか」に注目しているのです。
努力と成果の両面を意識して伝えるようにしましょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
④業務にどう活かせるかを具体的に示す
全商資格をアピールする際は、資格内容を実際の業務にどう活かせるかを具体的に伝えることが大切です。
たとえば、簿記検定なら「経費管理や正確な数値処理に役立つ」、情報処理検定なら「データ分析やパソコン業務で活かせる」といった形で職種と結びつけて話しましょう。
企業は「この資格が仕事でどのように活用できるのか」を知りたいと考えています。そのため、資格名を伝えるだけでなく、「具体的なスキル」として説明することで印象に残りやすくなるのです。
また、資格を通じて培った「正確さ」「計画性」「分析力」などを整理して伝えると、より明確な強みになります。資格を“知識の証明”ではなく、“実践力の一部”として示すことが、効果的なアピールのコツです。
⑤他の資格や経験と組み合わせて強みを示す
全商資格は、他の資格や経験と組み合わせてアピールすることで、より説得力を高められます。
たとえば、「全商簿記検定2級とMOS資格を取得している」「部活動で会計係を担当した」など、資格を実践や他のスキルと関連づけて伝えると効果的です。
企業は、知識だけでなく「現場で活かせるスキルの組み合わせ」を重視します。そのため、資格を軸に自分の経験やエピソードを一緒に伝えることで、印象に残る自己PRができるでしょう。
さらに、複数の資格を計画的に取得している場合は、向上心や学びの姿勢を示すことが可能です。
全商資格を中心に、他のスキルとの相乗効果を意識して伝えることで、「成長し続けられる人材」として強くアピールできるでしょう。
全商資格を履歴書に書くか迷ったときの考え方

全商資格を履歴書に書くべきか悩む人は多いですが、結論としては「応募職種との関連性」を軸に判断するのが最も重要です。
全商資格は、努力や基礎的なビジネススキルを示す有効な資格であり、事務職や会計職などでは高く評価されるでしょう。一方で、職種や業界によってはアピール効果が薄くなる場合もあります。
そのため、全商資格を履歴書に書くか迷ったときは、「仕事にどう活かせるか」「他の資格や経験とのバランスは取れているか」を意識して考えることが大切です。
正式名称で正確に記載し、略称を避けるなどの注意点も押さえておくと安心。全商資格は、使い方次第であなたの努力と誠実さを伝える強力な武器になるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










