履歴書の資格欄の正しい書き方|評価される資格や役立つ資格を一覧で紹介
「履歴書に書くべき資格って、どんなものが評価されるんだろう?」就職活動をする際、資格欄は自分の知識やスキルを効果的にアピールする絶好のチャンスです。
企業が求める資格や、履歴書に書く際に気をつけるべきポイントを知ることで、より魅力的な自己PRができます。
本記事では、採用担当者が注目する資格や、評価される資格一覧、資格欄の正しい書き方などを解説します。資格を通じて、自分の強みをしっかりアピールして、就活を成功に導いてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書の資格欄は知識やスキルのアピールポイント

履歴書の資格欄は、自分の知識やスキルを具体的かつ客観的に示す絶好のアピール機会です。
企業は履歴書を通して、限られた時間で応募者の能力や適性、ポテンシャルを見極めようとしています。
その中でも資格欄は、努力の積み重ねや専門性、継続的な学習姿勢を伝える手段として注目されやすい項目の1つです。
たとえば、IT企業に応募する学生が基本情報技術者試験を取得している場合、プログラミングやシステム設計に関する基礎力を証明できます。
また、サービス業志望であれば、接遇検定や語学資格などが評価対象となるでしょう。このように、資格は「何を学び、どのように努力してきたか」を第三者にもわかりやすく伝えるものです。
さらに、資格を通して得た知識は、志望動機や自己PRと連動させることも可能です。たとえば「取得のために毎日2時間の学習を3か月間継続した」といったエピソードを交えれば、計画性や粘り強さも印象づけられるでしょう。
就活では、どんな資格を選び、どのように書くかが評価を大きく左右します。形式的に埋めるのではなく、自分の強みを伝える戦略的なツールとして資格欄を活用してください。
採用担当者が資格欄で見るポイント

資格欄は、単なる資格の一覧ではなく、スキルや価値観、人物像を読み取るための重要な情報源です。
採用担当者は以下のような観点から資格欄を確認しています。
- 業務関連性
- 意欲の有無
- 一貫性
- 継続力
- 記入マナー
① 業務関連性
履歴書に記載された資格が、志望職種や業種とどれだけ関係しているかは、採用担当者がまず注目するポイントです。
たとえば、経理職を目指している学生が日商簿記2級を取得していれば、会計業務の基礎を理解していると評価されるでしょう。
逆に、志望職種と関連性のない資格ばかり並べていると、「方向性が定まっていない」といった印象を与えてしまいかねません。
資格を選ぶ際は、「この資格が将来の仕事にどう役立つか?」を自分なりに整理し、その上で履歴書に記載することが大切です。志望動機と資格欄が一貫していると、説得力のあるエントリーシートになります。
② 意欲の有無
資格の取得は、その人がどれだけ前向きに努力してきたかを表す証拠でもあります。
採用担当者は、勉強やアルバイトと並行しながら時間を割いて取得した背景から、「意欲」や「主体性」を読み取ろうとしています。
たとえば、「営業職に就きたいのでビジネス実務法務検定を取りました」といったように、目的を持って取得したエピソードがあれば、それだけで面接官の目を引く材料になります。
難関資格でなくても、「準備期間をどのように工夫したか」や「どうしてその資格を選んだのか」を伝えることで、努力の過程に説得力を持たせられます。
ただ資格を持っているだけでなく、「何を思ってその資格に挑戦したのか」まで話せるよう準備しておくと、より印象に残りやすくなるでしょう。
③ 一貫性
資格欄に並んだ内容に一貫性があるかどうかも、採用担当者は細かくチェックしています。これは、就活生のキャリア観や価値観がブレていないかを判断する材料になるからです。
たとえば、IT系職種を志望している学生が、基本情報技術者試験やMOSなど、関連する資格を複数取得していれば、「本気でこの分野を目指しているんだな」と感じてもらえるでしょう。
一方で、英検、保育士、簿記とバラバラの資格ばかり記載されていると、何を目指しているのかが見えにくくなってしまいます。
「将来どうなりたいか」「そのためにどんな準備をしてきたか」という軸を持って資格を選ぶことで、資格欄に一貫性が生まれ、履歴書全体にストーリーが感じられるようになります。
④ 継続力
資格取得は一朝一夕では終わらない取り組みであるため、採用担当者はそこに「継続力」や「計画性」を見出します。
特に、段階的に資格を取得していたり、長期的に努力が必要な内容に取り組んでいた場合、その粘り強さは高く評価される傾向があります。
たとえば、簿記3級から2級、さらには1級を目指してステップアップしているような場合、その努力の積み重ね自体が強力なアピールポイントになりますよ。
また、勉強時間の確保や勉強法の工夫といった裏側も、面接などで話せるようにしておくと、より人柄や姿勢が伝わりやすくなるでしょう。
忙しい学生生活のなかで、地道に取り組んできた経験は、どんな職種でも役に立ちます。資格欄を通じて、日々の積み上げができる人間であることを自然に伝えてください。
⑤ 記入マナー
せっかく取得した資格でも、記載方法が雑だと採用担当者の印象は大きく下がってしまいます。
資格欄の記入ミスは、ビジネスマナーや注意力の欠如と受け取られることがあるため、細部まで丁寧に仕上げることが欠かせません。
具体的には、資格名を略さず正式名称で書くこと、取得年月を省略せず記載すること、和暦と西暦を混ぜないことなどが基本ルールです。また、取得順や関連度を考慮した並び順にすると、見やすく整理された印象になります。
特に履歴書は、社会人としての第一歩を示す大切な書類です。「丁寧に作られている」と思わせることで、内容以上に信頼感を与える可能性もあります。
自分の強みを正確に伝えるためにも、記載ルールを守って正確に仕上げてください。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
履歴書の資格欄の正しい書き方

履歴書の資格欄は、学生生活の中で得たスキルや努力の成果を示す重要なアピール要素です。
特に新卒の就活では職務経験がないぶん、資格が唯一の客観的な証明になり得ます。正しいルールに沿って書けていないと、本来伝えたい魅力が伝わらず、評価が下がってしまう恐れも。
ここでは、採用担当者に正しく伝えるために押さえておくべき5つの基本ポイントを紹介します。
- 正式名称で書く
- 取得年月を記入する
- 合格・取得を正確に使う
- 取得順・重要度順で並べる
- 和暦・西暦を統一する
① 正式名称で書く
資格の名前は、略さずに正式な名称で記入してください。
たとえば「英検」ではなく「実用英語技能検定」、「漢検」ではなく「日本漢字能力検定」といったように記入しましょう。
採用担当者はすべての資格に詳しいとは限らないため、略称では正確な内容が伝わらない可能性があるためです。
どのように書けばいいかわからない場合は、試験を実施している公式サイトや証明書に記載されている表記を参考にしましょう。読み手に迷いを与えず、誤解を防ぐためにも、資格名の記載は丁寧に行ってください。
② 取得年月を記入する
資格を記載する際は、いつ取得したのかの「年月」も必ず明記してください。たとえば「2024年10月取得」のように書くことで、どのタイミングで努力を重ねたかが伝わります。
たとえば大学2年生で取得した場合は「早い段階から就活を意識していた」と評価されることもありますし、直近で取得した場合は「準備をしっかりしている」と印象づけられますよ。
年月がないと、資格の新しさや取得タイミングが読み取れず、努力の背景が伝わりにくくなります。特にTOEICやMOSなどのスコア系資格は、古いスコアと判断されるとマイナスに働くこともあるので注意が必要です。
③ 合格・取得を正確に使う
「合格」と「取得」は似ている言葉ですが、意味が異なるため正確に使い分けてください。就活生の多くがこの違いを曖昧にしてしまいがちですが、採用担当者は細かい表現にも目を通しています。
具体的には、「日商簿記検定」や「漢字検定」など、試験に合格することで認定されるものは「合格」と書きましょう。
一方で、運転免許や危険物取扱者のように、免許証や資格証を“取得”する形式のものは「取得」と記載するのが正解です。
たとえば「普通自動車第一種運転免許 取得」「秘書検定2級 合格」というように、それぞれ正しい表現を使いましょう。
このような細かい配慮が、文書作成能力やビジネスマナーの理解度として評価されるケースもあります。気になる場合は、過去に発行された証明書の文言を見直して確認しておくと安心です。
④ 取得順・重要度順で並べる
複数の資格を記載する場合は、ただ思いついた順に書くのではなく、取得した順番か、志望職種との関連性が高い順に並べるようにしてください。
履歴書は限られたスペースで自分を伝える文書なので、情報の「見せ方」も大切になります。
取得順に並べると、成長の過程や努力の積み重ねが自然に伝わります。一方で、志望職種と直接関係のある資格がある場合は、それを最上段に配置することで、より印象を強められます。
たとえば、IT業界を志望しているなら「基本情報技術者試験」を一番上に書くと効果的です。また、同じジャンルの資格が複数ある場合は、「上位資格を先に書く」といった工夫も有効ですよ。
読み手の目線に立って、どの資格から伝えると自分の強みが伝わりやすいかを考えて配置しましょう。
⑤ 和暦・西暦を統一する
履歴書全体を通して、和暦(令和・平成など)と西暦(2024年など)は、どちらか一方に統一してください。混在していると非常に読みづらく、読み手の理解を妨げる原因になります。
たとえば「令和5年6月」と書いた後に「2023年10月」と続けてしまうと、時系列が一見して分かりづらいですよね。
どちらを使っても問題ありませんが、選んだ形式は資格欄だけでなく、学歴や職歴欄も含めて統一する必要があります。
統一感のある履歴書は、それだけで丁寧さや読みやすさが増し、内容もより伝わりやすくなります。
「細かいことだから気にしなくてもいいだろう」と思わず、小さな点にも目を配ることが、社会人としての基本姿勢を示すことにつながります。
印象アップにつながる資格欄の工夫
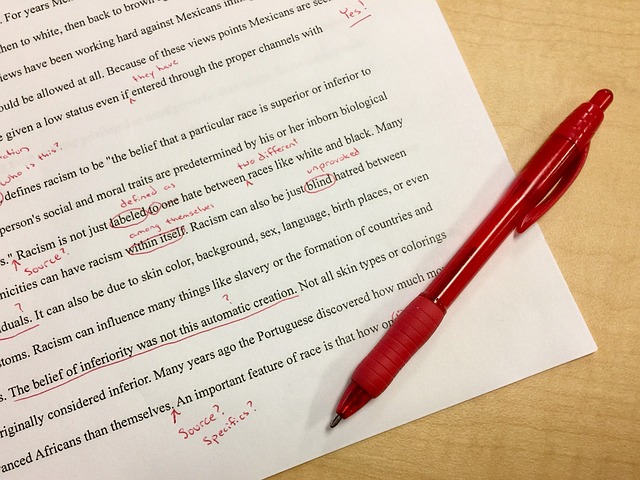
資格欄は、取得した資格を単に記載するだけでなく、伝え方を工夫することで、あなたの印象をより良くできます。
とくに就活では、書類選考で初めて自分の情報が相手に伝わる場面だからこそ、以下の工夫を取り入れて「見やすさ」や「関連性」といった要素を意識することが重要です。
- 関連資格を上に書く
- 補足情報を添える
- 他欄と差別化する
- 全体バランスを整える
- 読みやすく記入する
① 関連資格を上に書く
資格欄では、志望先の業種や職種に関連した資格を上位に記載することが効果的。
なぜなら、関連性の高い資格は、業務への理解や適性、さらには就職への本気度を伝える材料となるからです。
採用担当者は多数の履歴書に目を通しているため、ひと目で「自社とマッチしている」と感じられる要素があると、それだけで印象が残りやすくなります。
たとえば、IT企業を志望している場合、「基本情報技術者試験」や「MOS(Microsoft Office Specialist)」を先に記載することで、実務とのつながりが伝わりますよ。
反対に「英検3級」など業務と関係が薄い資格が先に来ると、アピールポイントとしては弱く見えてしまう可能性があります。取得した順ではなく、志望先との関連度を重視して並び替える視点を持ちましょう。
② 補足情報を添える
資格の記載には、簡潔な補足を加えることで、単なる資格名以上の意味を持たせましょう。
たとえば「TOEIC 750点(2025年5月取得)」のように、点数や取得時期を加えると、スキルレベルや現在の能力が伝わりやすくなります。
また、「宅建士試験 合格(登録予定)」や「ITパスポート勉強中」といった表現も、継続的な努力や向上心のアピールにつながりますよ。
就活初心者の方ほど、資格を「並べること」だけに意識が向きがちですが、読み手に伝わるかどうかを意識するだけで印象は大きく変わります。
ただし、文章が長くなりすぎると逆に読みにくくなるため、情報は要点を押さえてシンプルに添えるようにしましょう。
③ 他欄と差別化する
資格欄は、自己PR欄や志望動機欄と異なり、「客観的な証明」に特化した項目です。
だからこそ、「資格欄にも自己PRのようなアピール文を書いた方がいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それは逆効果になることも。
自己PRでは人柄や経験を、志望動機では意欲や考えを語る一方、資格欄ではスキルや知識を証明する情報が求められます。
たとえば「英語に関心があります」よりも「TOEIC750点取得(2025年5月)」と書くほうが、実力の裏付けとして説得力がありますよ。
すべての欄をアピール一辺倒にせず、役割を明確に分けて記載することで、履歴書全体の読みやすさと完成度が高まるでしょう。
④ 全体バランスを整える
資格をたくさん持っている方は、「できるだけ全部書いたほうが印象がいい」と思いがちですが、情報量が多すぎると逆に読みにくくなる場合もあります。
一方で、記載数が少なすぎるとアピールが弱いため、「伝えるべき情報を絞り込む」視点が重要です。
たとえば、IT系企業を志望しているのに、語学資格ばかり記載しているとミスマッチな印象を与えてしまうかもしれません。
関連性の高い資格を絞って記載し、それに関する経験や学びを自己PR欄で補完するなど、他の欄との連動も意識して構成すると全体にまとまりが生まれます。
履歴書全体を一枚の企画書だと考えると、読み手の目線で構成を調整することの大切さがわかるはずです。
⑤ 読みやすく記入する
どれだけ良い資格を持っていても、読みづらい書き方では内容が伝わりません。
だからこそ、資格欄では「見やすさ」や「統一感」を大切にする必要があります。具体的には、資格の正式名称・取得年月・レベル(級や点数など)をそろえて記載し、略称や口語的な表現は避けましょう。
また、和暦と西暦が混在していると読み手の混乱を招くため、表記はどちらかに統一してください。記載の丁寧さは、就活に対する姿勢や細やかさの証として受け取られます。
特別なスキルがないと感じている方でも、記載方法の工夫次第で好印象を与えられますので、「読み手に優しいか」という視点を常に持っておくと良いでしょう。
就活で役立つ代表的な資格
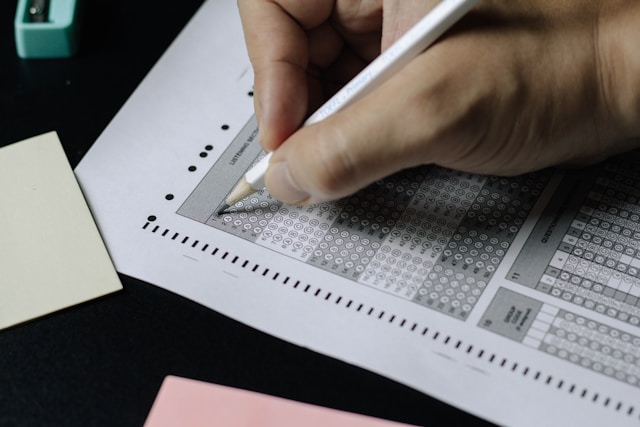
就活では、資格は知識やスキルの証明だけでなく、努力や関心の方向性を伝える手段として活用できます。
ここでは、就職活動で特に評価されやすい代表的な資格を10個紹介します。
それぞれの強みや向いている学生像を理解し、志望業界に応じた資格選びの参考にしてください。
- TOEIC
- 簿記
- ITパスポート
- MOS
- 普通自動車免許
- 秘書検定
- 漢検
- FP
- 宅建
- 英検
① TOEIC
TOEICは、英語の「聞く・読む」スキルを評価する試験で、英語力を数値で客観的に示せる点が大きな強みです。
外資系企業や海外展開を進める企業だけでなく、社内に外国人社員がいる企業や、将来的にグローバル事業に関わる可能性がある企業でも重視される傾向にあります。
とくに英語を専攻している学生や、国際系の業界に関心がある人にとっては、英語力の証明手段として効果的です。
また、英語を業務で使わない企業でも「学習への継続力」や「コミュニケーション力への意識」を評価する材料になります。
業界問わず一定の汎用性があり、履歴書に記載しておくと信頼感につながりやすい資格です。
② 簿記
簿記は、企業活動におけるお金の流れを理解するための基礎力を示す資格です。
とくに経理・財務系の職種を志望する学生にとっては必須レベルとされることが多く、数字への強さや業務理解への関心をアピールできます。
一方で、営業や企画、総合職を目指す学生にとっても、収益やコストの仕組みを理解していることは評価の対象です。
企業は、利益構造や損益に基づいた提案ができる人材を求めており、簿記の知識は実践力の裏づけになります。
文系・理系問わず幅広く活かせる汎用性があり、ビジネスの基礎を押さえておきたいと考える学生におすすめです。
③ ITパスポート
ITパスポートは、ITに関する幅広い基礎知識を証明する国家資格です。情報処理、ネットワーク、セキュリティのほか、経営や会計に関する知識も含まれており、ITとビジネスの接点を理解していることを示せます。
理系学生はもちろん、文系であってもIT分野への関心やデジタルリテラシーをアピールしたい学生に有効です。
とくに、DX推進中の企業やベンチャー・IT企業などでは、業務理解が早い人材として期待されやすいでしょう。
専門職志望でなくても、ITの素養は業界問わず重宝されるため、就職活動を通じて「時代に合った素養を持つ学生」として印象づけられます。
④ MOS
MOS(Microsoft Office Specialist)は、WordやExcelなどの操作スキルを証明する資格で、日々の業務に直結する実用性が特徴です。
とくにExcelは、関数・グラフ・データ整理といったスキルが業種問わず求められるため、事務職や営業職だけでなく、多くの総合職でも高評価を得られます。
「パソコンが使える」というレベルでは伝わらない実務能力を、客観的に伝えられるのが強みです。大学生活でのレポート作成や研究発表の延長として取得しやすいため、文理問わずおすすめできます。
基本的なPCスキルを可視化してアピールしたい就活生には、業界を選ばず活用しやすい資格といえるでしょう。
⑤ 普通自動車免許
普通自動車免許は、特定の業務に必要というだけでなく、「移動手段を自力で確保できる人材」としての柔軟性を伝える資格です。
営業職や地方勤務の可能性がある企業では、取得済みであることが歓迎される傾向があります。
とくにインフラ系企業やメーカーの地方拠点など、社用車での移動が業務に含まれる職場では「すぐに戦力化できる」人材として見られることもあります。
都市部の大学生などでは意識が向きにくいかもしれませんが、取得しておくことで選考時の選択肢が広がりますよ。必須スキルというよりも、基本装備として持っておくと安心できる資格です。
⑥ 秘書検定
秘書検定は、社会人としての基本的なビジネスマナーや、敬語、来客応対、文書作成のスキルを体系的に学べる資格です。
とくに一般職やサポート業務を志望する学生には有効で、「基礎が身についている人材」としての信頼を得やすくなりますよ。
また、総合職であっても社内外のやり取りを円滑に進めるためにビジネスマナーは重要であり、面接時の所作にもその効果が表れます。就活マナーに不安がある学生や、第一印象を良くしたい人にとっても心強い資格です。
実務経験がなくても「社会人としての素地がある」と印象づけることができ、職種に応じて高い汎用性を発揮します。
⑦ 漢検
漢検(日本漢字能力検定)は、語彙力や正しい言葉遣いをアピールできる資格です。
とくに文書作成が重視される職種や、教育・出版・行政などの分野では、「文章力の裏付け」としての信頼につながります。
文章を読む力、書く力があることを証明できるため、企画書作成や報告書の作成が業務に含まれる総合職にも適していますよ。
また、社会人としての基本的な教養を示す意味でも効果があり、堅実で知的な印象を与えられるでしょう。文系学生だけでなく、文章表現に自信をつけたい理系学生にもおすすめです。
⑧ FP
FP(ファイナンシャル・プランナー)は、保険・年金・税金・資産運用など、暮らしに関わる金融知識を体系的に学べる資格です。金融業界を目指す学生にとっては、実務理解や志望意欲のアピール材料になります。
さらに、一般企業の人事・総務部門や営業職でも、ライフプランや福利厚生の理解に役立つため、業界を問わず汎用的な資格といえるでしょう。
就活生にとっては、生活に直結する知識を学びながら「数字に強い」「制度に明るい」人材としての印象づけも可能。幅広い分野で応用できるバランスの取れた資格です。
⑨ 宅建
宅建(宅地建物取引士)は、不動産業界での必須資格でありながら、契約や法律の知識を証明できる点から、他業種でも高い評価を得ています。
とくに不動産、金融、保険、建設といった業界を志望する学生にとっては、即戦力としての期待が高まる資格です。
試験の難易度もある程度高いため、「努力を積み重ねられる人材」「論理的思考ができる人材」としての評価にもつながります。法務や営業など、複数部門で応用できる点も大きな魅力でしょう。
⑩ 英検
英検(実用英語技能検定)は、「読む・聞く・話す・書く」の4技能を総合的に測定する資格で、特にスピーキングを含む点で総合力をアピールできます。
教育、観光、エアライン、外資系企業など、英語を使った対人対応が必要な業界ではとくに評価されやすい傾向がありますよ。
また、英語系学部に所属している学生がその知識を証明する手段としても有効で、英語に取り組んできた背景を面接で語る際の説得力も増します。
英語力の広がりを示したい就活生にとって、実践的な資格の1つといえるでしょう。
履歴書に書いていい資格のレベル

履歴書に記載する資格は、一定の評価基準を満たしていないと、かえって逆効果になる場合があります。
ここでは、就活で実際に評価されやすい資格レベルについて紹介します。なぜその点数や級が求められるのか、就活生の立場から理解しておきましょう。
- TOEIC600点以上
- 簿記2級以上
- 秘書検定2級以上
- 漢検2級以上
- FP2級以上
- 英検2級以上
① TOEIC600点以上
TOEICは点数で英語力を示せるため、客観性が高い指標とされています。
ただし、400~500点台では「大学の授業で少し対策した程度」と見なされることが多く、学習意欲や実用性の面で評価されにくい傾向がありますよ。
600点以上でようやく「基礎的なビジネス英語を理解している」と判断され、履歴書に記載する意義が出てきます。
とくに英語を使わない職種でも、「継続して勉強してきた姿勢」や「異文化コミュニケーションへの関心」が伝わるため、アピールにつながるでしょう。
② 簿記2級以上
簿記は級によって評価の度合いが大きく変わる資格です。3級では日常的な家計レベルの内容が中心となるため、「ビジネスで活かせる知識」としてはやや物足りなく映ることも。
一方、2級は企業の財務諸表や原価計算など、実務にも通じる内容が含まれており、数字への理解力や分析力のアピールにつながります。
経理職に限らず、営業や企画でも「利益に対する感度がある人材」として印象づけられれるでしょう。
③ 秘書検定2級以上
秘書検定は「社会人としての基礎力」の証明となる資格ですが、3級では基本マナーの一部にとどまり、就活でのアピール力はやや弱い傾向にあります。
2級以上であれば、より実践的なビジネス対応や文書作成力を身につけていると判断され、「即戦力に近い土台がある学生」として評価されやすくなりますよ。
とくに一般職やサポート職を志望している場合は、2級を基準に取得を目指すとよいでしょう。
④ 漢検2級以上
漢検は「文章力の土台」を測る資格ですが、3級以下だと高校レベルの基礎知識にとどまり、履歴書に記載しても評価されにくい傾向があります。
2級以上であれば、公的文書や社内文書に必要な語彙力・表記力を持っていると見なされ、ビジネス文書の読解や作成に強い人材として評価されるでしょう。
特別な志望業界がなくても、「教養のある人物」「表現力の高い人物」として印象づけられる点が魅力です。
⑤ FP2級以上
FPはお金に関する幅広い知識を証明できる資格ですが、3級では生活レベルの内容が中心であり、「業務に活かせる知識」としてはやや弱い印象を与える場合があります。
2級以上であれば、税金や保険、資産運用など企業でも必要とされる知識を網羅しているため、「数字に強い」「制度に詳しい」学生としての信頼感につながるでしょう。
とくに金融系を志望する場合は、2級以上を取得しておくことで志望度の高さを示せます。
⑥ 英検2級以上
英検は英語4技能を測る資格として評価されていますが、3級や準2級では中学生~高校初級レベルと見なされるため、履歴書でのインパクトは限定的です。
2級以上であれば、高校卒業相当以上の英語力があるとされ、企業にとっても「実務で最低限使える水準」として一定の信頼感があります。
とくに英語を専攻している学生や、英語力をアピールポイントにしたい人は、2級以上の取得が前提になると考えておくと安心です。
履歴書に書かなくてもいい資格

履歴書に記載する資格は、自分の知識やスキルを企業にアピールするための重要な情報です。しかし、すべての資格が有効とは限らず、内容によっては評価を下げてしまう可能性もあります。
とくに、実務に直接関係のない資格や信頼性に乏しいものを記載すると、採用担当者にマイナスの印象を与えることもあるため注意が必要です。
ここでは、履歴書に書かないほうがよい資格の具体例を5つ紹介します。
- 趣味系の民間資格
- 幼少期に取得した資格
- 古い名称のままの旧資格
- 企業が認知していない独自検定
- 資格名が不明瞭な講座修了証
① 趣味系の民間資格
趣味や娯楽の一環で取得した資格は、たとえ自分にとっては努力の証であっても、履歴書には基本的に書かないほうがよいでしょう。
たとえば、カラーセラピーやタロット占い、ペット関連の検定などが挙げられます。こうした資格は仕事の能力や実務スキルとは関係が薄く、採用担当者が評価しづらいためです。
とくに志望する業界や職種に関係がない場合、「自己満足で書いている」と思われてしまう可能性があります。
どうしても触れたい場合は、自己PR欄などに趣味として簡潔に述べる程度にとどめるとよいでしょう。
② 幼少期に取得した資格
小中学生の頃に取得した資格も、履歴書では省略するのが一般的です。理由は明確で、現在のスキルや能力を示す材料にはならないからです。
たとえば、小学生のときに取得した英検3級や珠算4級などは、今の自分のレベルや成長を正確に伝えるものではありません。
また、古い情報を持ち出すことで、「最近は何も学んでいないのか」と誤解される恐れも。
企業は直近の努力や成果を重視する傾向にあるため、履歴書には大学生以降に取得した資格や、現在の学習状況がわかる情報を優先して記載しましょう。
③ 古い名称のままの旧資格
制度変更によって名称や内容が変わった資格を、昔の表記のまま記載してしまうと、「情報が古い」「最新の知識がない」といった印象を与えてしまう場合があります。
とくに法律や制度に関係する資格では、最新の情報へのアンテナが求められるため、表記ミスが致命的になる場合も。
たとえば、「介護福祉士補」や「初級システムアドミニストレータ」など、すでに廃止された資格名を使っていると、履歴書全体の信頼性にも関わります。
古い資格であっても、現行制度での正式名称や相当する資格に置き換えて記載することが重要です。
④ 企業が認知していない独自検定
特定の企業や団体が独自に認定している検定は、広く知られていない場合、履歴書に書いても採用担当者に伝わらない可能性があります。
たとえば、地元の商店街組合や小規模団体が発行している資格は、内容や評価基準が不明瞭なことが多く、「この資格は何を証明しているのか」が伝わらないままスルーされてしまうこともあります。
評価されにくいだけでなく、場合によっては「信頼性の低い情報をあえて書いてきた」という悪印象につながるおそれもあるため注意が必要です。
履歴書には、第三者機関によって認定されており、業界内で一定の信頼を得ている資格のみを記載するようにしましょう。
⑤ 資格名が不明瞭な講座修了証
通信講座や短期セミナーなどで発行される「修了証」「受講証明書」は、基本的に履歴書の資格欄には適しません。
とくに講座名が曖昧で内容が伝わりにくい場合、採用担当者が「これは正式な資格なのか?」と判断に迷うかもしれません。履歴書では、資格の正式名称や等級が明確であり、第三者が評価可能なものが望まれます。
こうした修了証は、あくまで自己研鑽の記録にとどまるもので、アピールしたい場合は自己PR欄や志望動機で「こんな分野に興味があり、自主的に学んだ経験がある」という文脈で伝えるようにしてください。
形式にとらわれず、本質的な学びや姿勢を見せるほうが効果的です。
履歴書で書ける資格がない場合の対処法

就活中に「履歴書に書ける資格がない」と悩む方は少なくありません。
とはいえ、資格がないからといって不利になるとは限らず、むしろその状況をどう説明するかが評価につながります。
ここでは、資格を持っていない場合に就活生としてどのように対応すればよいか、4つの具体的な方法を紹介します。
- 「特になし」と記入する
- 勉強中の資格を記入する
- スキルや経験で補う
- 自己PR欄で補足する
① 「特になし」と記入する
現時点で取得済みの資格がない場合は、無理に欄を埋める必要はありません。空白のままではなく、「特になし」と記入するのが基本です。
履歴書は形式的な整いも見られる書類であるため、空欄だと記入漏れと見なされる可能性も。「現在の時点では該当資格なし」と明記することで、形式への理解や誠実な姿勢が伝わりやすくなります。
たとえば、特定の資格が必要でない職種や業界を志望している場合は、無理にアピール材料を作るよりも、他の項目でしっかり自己表現したほうが自然です。
履歴書全体のバランスを意識し、正直さを大切にした記載を心がけましょう。
② 勉強中の資格を記入する
今まさに資格取得に向けて勉強中であれば、その事実を履歴書に書いて問題ありません。
たとえば「TOEIC 700点を目指して学習中(受験予定:11月)」のように、具体的な目標や受験時期を明記することで、就活に対する前向きな姿勢が伝わります。
企業は現時点のスコアや合格実績だけでなく、努力のプロセスや目標に向かう行動力も見ていますよ。特に新卒採用ではポテンシャルを重視する傾向があるため、勉強中の資格も十分アピール材料になります。
ただし、「いつか取りたい」「興味はある」といった漠然とした表現ではなく、実際にどのように準備を進めているかを具体的に記載することが大切です。
③ スキルや経験で補う
資格がなくても、実際の経験や身につけたスキルで十分に補えます。むしろ、企業によっては形式的な資格よりも、実践的なスキルや対人能力を重視している場合も多くありますよ。
たとえば、アルバイトで長期間リーダーを務めた経験や、イベント運営を通じて培ったマネジメント力、部活動でのチームビルディングなどは、どれも実社会で役立つ力です。
これらを履歴書の資格欄で補うことは難しいかもしれませんが、職務経歴欄や自己PR欄で積極的に言及すれば、十分に評価される要素になります。
資格がないからといって臆する必要はなく、自分の強みを「伝える力」のほうが重要になるでしょう。
④ 自己PR欄で補足する
資格がないことを気にするよりも、「なぜ今持っていないか」「その分どんな経験を積んできたか」を自己PRで補足することが効果的です。
たとえば、「資格取得には至っていませんが、〇〇の活動を通して××の力を身につけました」と書けば、評価軸を資格以外に移せます。
また、今後どのように学んでいきたいか、将来への展望を示すことで、意欲的な姿勢を伝えることも可能です。
就活においては、現時点の完成度よりも「伸びしろ」や「成長の意欲」を見ている企業も多くあります。履歴書の他項目と連動させながら、資格以外の強みをしっかりアピールしていきましょう。
履歴書の資格欄に関するよくある質問

履歴書の資格欄には何をどこまで書けばよいのか迷う方は多く、就活生の間でも悩みやすいポイントの1つです。
ここでは、特に質問の多い3つのケースについて、採用担当者の視点やアピールのコツもふまえながら詳しく解説します。
- 業種と関係ない資格を書いても良いか
- 取得中の資格を書いても良いか
- 実務経験がない資格を書いても良いか
① 業種と関係ない資格を書いても良いか
業種や職種に直接関係しない資格であっても、履歴書に書いて問題ありません。とくに、その資格があなたの価値観や努力の積み重ねを伝えるものであれば、採用担当者に好印象を与える可能性も。
たとえば、理系の学生が秘書検定を取得していれば、ビジネスマナーへの関心や対人スキルの高さがうかがえるでしょう。
企業はスキルの即戦力性だけでなく、視野の広さや学ぶ姿勢も重視しています。とはいえ、資格によっては「単なる趣味?」と受け取られるケースもあるため注意が必要です。
応募先企業で活かせる場面をイメージできるかどうか、自問してから記載しましょう。
面接で「なぜこの資格を取ったのか?」と聞かれたときに、志望動機やキャリア観と自然につながる説明ができれば、強いアピール材料になります。
② 取得中の資格を書いても良いか
現在勉強中の資格でも、履歴書に記載して構いません。その際は「○○資格 取得予定(2025年8月)」のように、明確に予定であることを記載してください。
企業は、努力を継続している姿勢や、将来に向けた意欲の高さを評価します。特に志望業界に関連のある資格であれば、「すでに準備を始めている学生」として前向きに受け止められるでしょう。
ただし、取得予定と書いても、その後の結果が伴わなければ信頼を損なう恐れも。確実に受験の意思があり、ある程度の見通しが立っている場合に限定して書くのが安心です。
また、いくつも予定資格を記載すると、逆に「手を広げすぎている印象」を与えることもあるため、優先順位をつけて記載してください。
就活全体の戦略と照らし合わせながら、どの資格が自分の武器になるかを見極めましょう。
③ 実務経験がない資格を書いても良いか
実務経験がなくても、取得済みの資格であれば履歴書に書いて問題ありません。むしろ、「知識の証明」として就活初期には大きなアピール材料になります。
たとえば、日商簿記3級やITパスポートは、業界問わず基礎的な業務理解ができることを示す資格として、多くの企業が注目していますよ。
企業は「資格=即戦力」とは見ていませんが、「学習意欲」や「計画性」を推し量る指標として資格欄をチェックしています。
そのため、未経験分野であっても資格があれば「この分野に関心を持っているのだな」と評価されることもあるでしょう。
ただし、実務経験がないことを補うためにも、大学の授業や自主的な取り組み、インターンでの体験など、資格以外のアピールポイントもセットで伝えることが重要です。
資格だけに頼らず、自分なりの学びをどう深めてきたかを語れるようにしておくと安心です。
資格欄の活用で履歴書の印象を高めよう!

履歴書の資格欄は、知識やスキルを客観的に伝える絶好のアピールポイントです。
採用担当者は、業務関連性や意欲の有無、一貫性・継続力などを資格欄から見極めています。そのため、正式名称や取得年月を正確に記入し、重要度順に並べるなど基本ルールを守ることが重要です。
また、関連資格の配置や補足情報の添え方を工夫することで、印象をさらに向上させられます。
TOEICや簿記、ITパスポートなど、就活で評価されやすい代表的な資格を中心に、履歴書にふさわしいレベルを見極めて記載しましょう。
たとえ資格がなくても、勉強中のものやスキルで補うことで十分アピール可能です。正しい知識と書き方を身につけ、自分の強みを最大限に活かしましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










