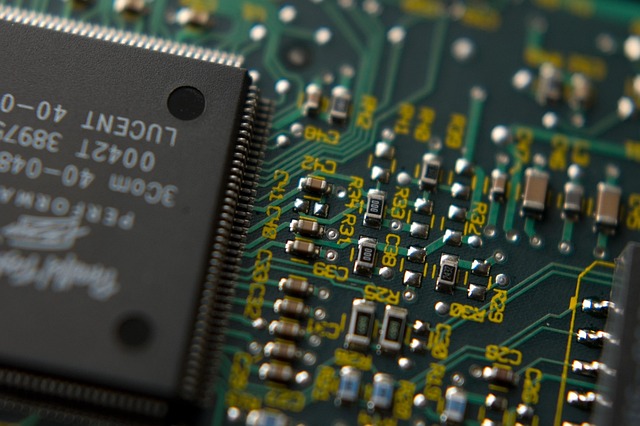就活で差がつく!「大学で学んだこと」の伝え方と例文11選
就活の面接やエントリーシートでは、「大学で学んだこと」をよく聞かれますよね。しかし、「大学で学んだことがない」「うまく伝えられる自信がない..」などと悩む人も多いのではないでしょうか。
本記事では、理系・文系それぞれの例文や、「大学で学んだことがない」と感じたときの対処法、大学で学んだことを活かす志望動機の書き方など、ポイントをわかりやすく解説します。
具体的な文系例文・理系例文も掲載しているため、自信をもって自己PRにつなげられるようになるでしょう。
無料アイテムで就活を効率的に進めよう!
- 1自己PR作成ツール|自動作成
- あなたの自己PRを代わりに作成
- 2ESをAIに丸投げ|LINEで完結
- 完全無料でESを簡単作成
- 3志望動機テンプレシート|簡単作成
- カンタンに志望動機が書ける!
大学で学んだことはなぜ面接で聞かれるのか?企業の意図を解説

就職活動中の面接で「大学で学んだことを教えてください」と聞かれたとき、どう答えればよいか悩む方は少なくありません。
とくに「学びと志望動機がつながらない」「そもそも何を学んだのかうまく思い出せない」と感じている場合、この質問の意図がわからず、不安になるのも当然でしょう。
しかし、企業がこの質問を通じて何を見ているのかを理解できれば、面接に対する自信も持てるようになるはずです。ここでは企業がこの質問で評価している主なポイントを紹介します。
- 能力やスキルを確認するため
- 学業への向き合い方から人柄や強みを知るため
- 自社で活躍できる人材かを見極めるため
① 能力やスキルを確認するため
企業は、大学での学びを通じてどのような能力やスキルを身につけたのかを確認したいと考えています。
なぜなら、実際の仕事では知識の有無以上に、課題にどう向き合い、どのように行動するかという姿勢やプロセスが問われる場面が多いためです。
たとえば、ゼミの研究活動を通して課題設定力や論理的思考力を養った経験や、授業でのディスカッションを通じて表現力や傾聴力を高めた経験は、実践的なスキルとして評価されます。
つまり、大学で「何を学んだか」だけでなく、「その学びから何を得たのか」を具体的に伝えることが、企業からの評価につながるのです。
② 学業への向き合い方から人柄や強みを知るため
企業は、学業にどのように向き合ってきたのかという姿勢から、応募者の人柄や価値観、強みを見極めようとしています。
課題への取り組み方によって、その人の考え方や行動スタイル、職場での適応力が垣間見えるためです。
たとえば、苦手な分野にも粘り強く取り組んできた経験からは、努力を惜しまない姿勢が伝わります。逆に、興味のあるテーマを深く掘り下げてきた経験からは、探究心や主体性を読み取ることができるでしょう。
そのため、日々の授業や課題に対してどのように取り組んできたかを振り返り、自分の強みや特性を企業にしっかり伝えることが重要です。
③ 自社で活躍できる人材かを見極めるため
企業は、大学での学びを通じて「自社で活躍できる人物かどうか」を見極めようとしています。
これは単に知識やスキルを評価するだけでなく、「企業のカルチャーに合っているか」「実務に応用できる力を持っているか」「将来にわたって成長していけるか」といった観点を重視しているからです。
たとえば、グループワークやゼミ活動で他者と協力して成果を出した経験は、柔軟性やチームで働くための適応力を示せるでしょう。
さらに、そのような経験をもとに「これからどのように成長していきたいか」を語ることで、将来的な可能性も評価されやすいですよ。
「大学で学んだこと」を見つける方法

就職活動が本格化すると、面接やエントリーシートで「大学で学んだこと」を聞かれる場面が増えてきます。
ただ、「正直、大学で学んだことがない気がする」「学びと志望動機がうまく結びつかない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、自分の大学生活から語れる“学び”を見つけるためのステップを4つに分けて紹介します。
- ゼミ・講義・課題など学習したことを一覧化する
- 成績の良かった講義や人から褒められた経験を思い出す
- 印象に残っている取り組みから考える
- 大学入学前の価値観との変化を洗い出す
① ゼミ・講義・課題など学習したことを一覧化する
まずは、自分が大学でどんなことに取り組んできたかを思い返してみるところから始めてみましょう。
まずはあれこれと考えて判断するのではなく、量を出すことが重要です。ゼミの研究テーマ、印象に残った講義、レポートやプレゼン、グループワークなどを自由に書き出してみてください。
理系なら実験や実習、文系なら文献研究やディスカッションも含めて問題ありません。
このように、自分が時間をかけたことや関心を持った分野が見えてくると、就活で語る素材のベースができあがるはずです。
② 成績の良かった講義や人から褒められた経験を思い出す
続いて、自分が得意だったことや、他人から評価された経験にも目を向けてみましょう。こうした体験は、自分の強みを見つけるヒントになってくれます。
たとえば、「この講義で特に良い成績を取った」「先生にプレゼンを褒められた」などのエピソードがあれば、それは努力や成果の証でしょう。
理系なら論文や研究結果、文系なら発表やレポートの内容も挙げられます。
また、「どうやってその結果を出したのか」を振り返ることで、自分の行動スタイルや考え方も明確になっていくでしょう。
③ 印象に残っている取り組みから考える
強く印象に残っている体験があるなら、その出来事にこそ学びの本質が隠れているかもしれません。印象に残るということは、それだけ感情が動き、何かを感じ取ったという証拠です。
たとえば、「苦手なことにあえて挑戦した」「何度も失敗しながらも最後までやり抜いた」といったストーリーには、自然と自分らしさがにじみ出ます。
また、このような自分らしさが出るエピソードを語ることで、他の就活生との差別化につながりますよ。
④ 大学入学前の価値観との変化を洗い出す
大学生活で得た変化に注目することも、大切な学びを見つける手がかりになります。入学前と比べて、自分がどう変わったかを言葉にしてみてください。
たとえば、「以前は受け身だったが、自分から学びに行く姿勢が身についた」「人前で話すのが苦手だったけれど、今ではプレゼンも得意になった」といった変化は、成長の証です。
このような価値観の変化を丁寧に振り返ることで、知識以上に大切な「学ぶ力」や「成長する力」を企業にアピールできるようになりますよ。
大学で学んだことの効果的な伝え方

就職活動が本格化すると、面接やエントリーシートで「大学で学んだこと」を尋ねられる機会が増えてきます。
ここでは、自分の大学生活から語れる“学び”を見つけるための4つのステップをご紹介します。
- 学んだことを端的に伝える
- 概要やエピソードを伝える
- 学びから得た気付きや考えを伝える
- 自己PRや志望動機に繋げる
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
① 学んだことを端的に伝える
面接やエントリーシートでは、まず最初に「大学で何を学んだのか」を端的に伝えることが重要です。結論から話すことで、相手が内容をつかみやすくなり、その後の具体的な説明にも集中してもらいやすくなります。
たとえば、「国際経済を学び、異文化理解力を養いました」といったように、主な学びと得られた力を一文で提示するのがおすすめです。そのうえで、具体的なエピソードや背景を続ければ、説得力とわかりやすさの両方が備わります。
最初に何を伝えるかで印象が決まることも多いため、「私は大学で◯◯を学び、△△という力を身につけました」といった構成を意識してみてください。
② 概要やエピソードを伝える
次に、学びの内容に説得力を持たせるには、エピソードや具体例を交えて伝えることが効果的です。
特に印象的だった授業や、成果が認められた経験などがあれば、それが自分の強みを示す手がかりになります。
たとえば、「成績が特に良かった講義」や「プレゼンで先生に褒められた体験」などは、努力や成果を裏付ける具体的な材料になります。
具体的には、理系であれば研究や論文、文系であれば発表やレポートなどを振り返ってみるのがおすすめですよ。
③ 学びから得た気付きや考えを伝える
さらに一歩踏み込んで、その経験を通してどのような気づきや考えを得たのかを振り返ってみましょう。
たとえば、「苦手なことにも挑戦し続けた」「失敗を経て最後までやり切った」などの体験は、自分の価値観や行動スタイルを映し出すはずです。
また、「気づきの抽象化」という視点も効果的ですよ。
たとえば、「部活動で後輩の話を丁寧に聞いた」という経験を、「多様な価値観を尊重する姿勢」や「対話による合意形成力」といった汎用的な力に言い換えることで、社会人としても通用する資質として伝えられます。
このように、自分だけの体験を普遍的な学びに変換できると、他の応募者との差別化にもつながりますよ。
④ 自己PRや志望動機に繋げる
最後に、大学での学びを自己PRや志望動機にうまく結びつけることが求められます。
せっかく良い経験をしていても、企業との接点が示されなければ、それはただの思い出話で終わってしまいますよね。
たとえば、「国際経済を学び、異なる文化や考え方を理解する力を養いました。その経験を活かし、グローバルに展開する御社で、多様な顧客ニーズに応える営業を目指したいです」といった形で、経験から志望理由への流れを意識するとよいでしょう。
学びがどのように企業の業務や価値観と重なるのかを明確にすることで、「この人なら活躍できそうだ」と感じてもらえる確率が高まります。
「大学で学んだこと」が志望企業と結びつかないときの対処法

大学で学んだ内容と企業活動との間に明確なつながりが見えないと、志望動機をどう書けばよいか悩みますよね。
ここでは、そうした不安を解消し、「大学で学んだことを活かす志望動機」に変えるための考え方や工夫をご紹介します。
- 学びから得た考え方から企業との共通点を見出す
- 志望企業を選び直す
- 志望企業に合わせて学んだことを選び直す
① 学びから得た考え方から企業との共通点を見出す
大学での学びが業務内容と直接結びつかない場合でも、心配する必要はありません。
企業が注目しているのは、学問そのものではなく、「その学びからどのような思考力や価値観を培ったのか」という点です。
たとえば、文系の方が歴史学を学ぶ中で論文を通して情報整理力や仮説検証力を磨いたとします。これらはマーケティングや企画といった職種でも十分に活かせる力として評価されます。
理系でも同様に、実験や研究を通じて培った論理的思考力や粘り強さは、多くの企業で求められる素質でしょう。
つまり「どんな学問を学んだか」ではなく、大学で学ぶ上で「どう考え、どう成長したか」を伝えることが重要です。
② 志望企業を選び直す
どうしても大学での学びと志望企業との接点が見つからないときは、志望先そのものを見直すのもひとつの方法です。
学びと無関係な企業を選んでいる場合、どれだけ努力しても志望動機がうまくつながらず、苦しいと感じるかもしれません。
大学で学んできたことは、自分自身の関心や価値観がある分野である可能性が高いです。その軸から大きく外れている企業を選んでいるなら、「なぜその企業なのか」という問いに対して、答えにくくなってしまうのは自然なことでしょう。
企業研究を進める中で違和感を覚えた場合は、それを無視せず、いったん立ち止まってみてください。自分に合う企業を選び直すことで、学びと志望動機が自然につながるケースも多いものです。
③ 志望企業に合わせて学んだことを選び直す
大学生活で経験したことはひとつではありません。視点を変えることで、より企業にマッチする学びを見つけ直すことも可能です。
複数の学びの中から「どのエピソードが志望企業にもっとも適しているか」を見極め、最適な内容を選んで伝えていきましょう。
たとえば、心理学を学んでいた方が、人の行動を観察・分析する視点を活かして営業職や人事職に関心を持ったという場合、学問そのものよりもその姿勢をアピールすることが有効です。
また、理系で研究に取り組んでいた方であれば、データの扱い方や計画性といったスキルは、多くの業務に転用可能な強みとして語れます。
このように、ひとつの経験に固執せず、志望企業の求める人物像に合わせて伝える内容を柔軟に選び直すことが、説得力のある志望動機につながりますよ。
【文系】学部別・大学で学んだことの例文
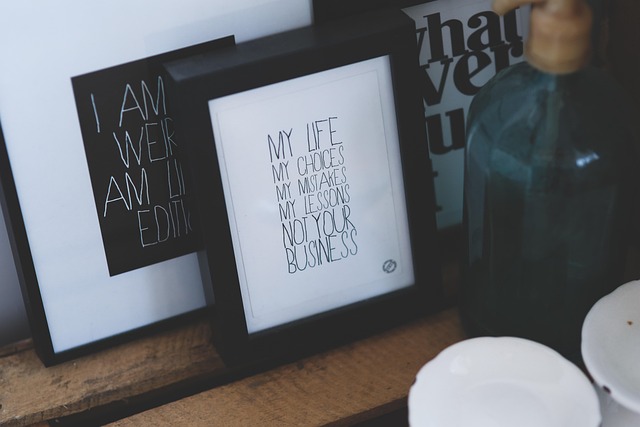
文系学部に所属している方の中には、「大学で学んだことをどう伝えればよいかわからない」と感じる方も多いでしょう。学問の性質上、企業の業務内容と直接結びつきにくいと考えるかもしれません。
しかし、それぞれの学部で得た知識や考え方には、ビジネスの現場で十分活かせる要素が含まれています。
ここでは、文系学部別に「大学で学んだこと」の例文を紹介します。
1. 経営学部
2. 経済学部
3. 文学部
4. 法学部
5. 社会学部
6. 教育学部
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】
赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①経営学部
経営学部では、企業運営や組織管理について学びます。
ここでは、得た知識やスキルがプロジェクトやチーム活動でどのように生かされたかを示す例文を紹介。
| 経営学部でマーケティングの知識を学び、消費者目線で物事を考える力を身につけました。 大学2年次には、ゼミ活動で地域商店街の活性化プロジェクトに取り組みました。来客数減少の原因を探るため、アンケート調査とヒアリングを実施しています。 データ分析の結果、ターゲット層と施策内容にズレがあると判明しました。そこで若年層向けのイベントを企画し、提案を行いました。 その施策により、来客数は前年同期比で20%増加。地域の方々からも感謝の言葉をいただいています。この経験を通じて、マーケティングにおいてデータに基づく視点の重要性を深く実感することができました。 今後は、こうして培った分析力と顧客視点を活かし、貴社の商品やサービスの魅力を最大限に引き出すマーケティング施策を提案してまいります。 |
この例文では、学びと実践、さらに成果まで一貫して描かれています。行動→結果の流れを示すと、説得力が一気に高まるでしょう。
②経済学部
経済学部では、社会や市場の動きを捉える視点を養います。
ここでは学んだ理論やデータ分析力を、現実の課題に応用した事例を取り上げました。
| 経済学部で経済理論を学び、物事を客観的に分析する力を磨きました。 大学1年次には、地域経済の研究プロジェクトに参加しています。地元商店街の売上低迷について、過去データと周辺環境の変化を比較・分析する作業を担当しました。 調査を進める中で、郊外型ショッピングモールの進出や人口減少が売上減少の大きな要因であると仮説を立てています。 レポートにまとめた結果、「データに基づく考察ができている」と教授から高く評価され、学内コンペでも入賞することができました。 今後は、この分析力と論理的思考を活かし、貴社の商品開発やマーケティング戦略に貢献したいと考えています。 |
この例文は、知識だけでなく実践を通じた成長をしっかり伝えています。学びと行動がどのようにつながったかを示すと効果的です。
③文学部
文学部では、豊かな思考力と表現力を培います。
ここでは読解力や深い思考が、人や文化を理解する力へ発展した過程を例文で表しています。
| 文学部で読解力と表現力を高め、多角的に物事を見る力を養いました。 ゼミ活動では、日本文学と西洋文学を比較する研究に取り組んでいます。共通テーマである「愛」の描かれ方について、双方の作品を分析しました。 それぞれの文化や時代背景に触れる中で、柔軟に物事を捉える重要性を実感しました。その考察をまとめた卒業論文は、教授から「幅広い視点で分析できている」と高く評価されています。 これからは、この多角的視点と表現力を活かし、貴社のお客様やチームメンバーとのコミュニケーションを円滑にしながら、よりよい提案やサポートに努めていきたいと考えています。 |
この例文では、学びが思考や行動にどのように反映されたかを具体的に示しています。単なる知識披露ではなく「活かした事例」を描きましょう。
④法学部
法学部では、論理的思考や問題解決力を磨きます。
ここでは論理力や交渉力が、具体的な場面でどのように発揮されたかを例文にまとめました。
| 法学部で論理的思考を磨き、筋道立てて物事を考える力を身につけました。 大学2年次には、模擬裁判の授業で弁護側を担当し、証拠や証言を整理しながら、主張を組み立てる役割を担いました。 相手側の反論も想定し、主張の強化に努めた結果、論理の一貫性を高く評価されています。チームとしても最優秀賞を受賞することができました。 この経験を通じて、冷静に問題を分析し、分かりやすく伝える力が養われたと感じています。 今後は、この論理的思考力とコミュニケーション力を活かし、貴社の課題解決やプロジェクト推進に貢献してまいります。 |
この例文では、学びと実践の結びつきを具体的に示しています。志望動機を書く際には、知識にとどまらず、行動と成果もアピールしましょう。
⑤社会学部
社会学部では、社会構造や人々の行動原理を深く理解します。
ここでは観察力や洞察力をもとに課題提起や提案へつなげた過程を紹介しました。
| 社会学部で観察力と分析力を養い、多様な価値観を尊重する姿勢を身につけました。 大学3年次のフィールドワーク授業では、地域コミュニティの活動を取材し、町内会の防災活動に参加しました。 調査の結果、高齢者と若い世代で防災意識に大きな差があることを発見し、それをもとに提案書を作成しました。この提案は教授と地域の方々から高く評価され、防災計画の見直しに活用されました。 今後は、こうした観察力と分析力を活かして、貴社のお客様やチーム内の多様なニーズに柔軟に応えていきたいと考えています。 |
この例文は、学びと実践が自然につながっています。経験から得た具体的な成果も合わせて示しましょう。
⑥教育学部
教育学部では、人の成長に寄り添うための知識と実践力を養います。
ここでは対人理解や支援の力が、現場で発揮され相手に変化をもたらした事例を示しました。
| 教育学部でコミュニケーション力を高め、一人ひとりに寄り添う姿勢を身につけました。 大学2年次の教育実習では、小学校のクラス運営を担当し、子どもたちとの距離感に悩む場面もありました。 休み時間や授業準備の中で一人ひとりと対話を重ねた結果、信頼関係が築かれ、発言が少なかった児童も積極的に手を挙げるようになりました。 この経験を通して、相手の気持ちに寄り添う重要性を実感しました。 今後は、このコミュニケーション力を活かして、貴社で多様な人々と信頼関係を築きながら、チームの成長に貢献してまいります。 |
この例文では、学びだけでなく行動とその成果も描かれています。行動→成長→成果の流れを意識すると効果的です。
【理系】学部別・大学で学んだことの例文
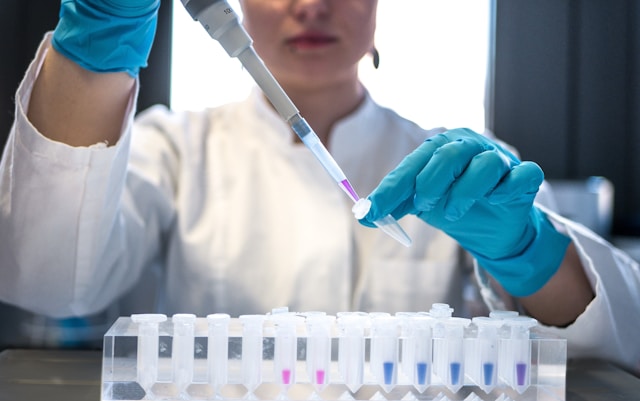
理系の学生が面接やエントリーシートで「大学で学んだこと」を伝える際には、学部ごとの専門性をどう表現するかが重要です。
しかし「研究内容が専門的すぎて、どう説明すればいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、理系の主な学部別に、実際に使える例文を紹介します。自分の学部に該当する例文を参考にしながら、自身の経験に合わせてアレンジしてみてください。
1. 理学部
2. 工学部
3. 情報学部
4. 医学部
5. 薬学部
「エントリーシート(ES)が選考通過するか不安….ESを誰かに添削してほしい….」そんな就活生の声に答えて、就活マガジンでは無料ES添削サービスである「赤ペンES」を運営しています。
第一志望である企業の選考に通過するためにも、まずは就活のプロにES添削を依頼してみましょう!LINE登録3分で満足が行くまで添削依頼ができますよ。
①理学部
理学部では、自然現象の仕組みを探究し、問題を解明する力を磨きます。
ここでは、探究心と粘り強さを実践で発揮した例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 理学部で探究心と問題解決力を高め、困難に直面しても粘り強く取り組む姿勢を養いました。 大学3年次には、研究テーマに取り組む中で、思うような実験結果が出ない壁に直面しています。 材料の性質を調べる実験で予想と異なる結果が続いたため、文献を読み直し、条件を一つずつ見直す地道な作業を重ねました。 その結果、測定装置の設定ミスに気づき、無事に正しいデータを得ることができました。この経験から、失敗を恐れず試行錯誤を続ける重要性を実感しています。 今後は、こうして培った粘り強さと課題に向き合う姿勢を活かし、貴社の製品開発や研究活動に貢献したいと考えています。 |
この例文では、失敗から学び成長したプロセスを具体的に伝えています。理系課題解決に向けた行動とその結果をセットで示すと説得力が格段に高まるでしょう。
②理学部
工学部では、モノづくりの基礎知識と実践力を身につけます。
ここでは、チーム活動を通じて成果を上げた例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 工学部で設計力と問題解決力を培い、現場で実践的に対応する力を養いました。 大学3年次のグループプロジェクトでは、小型ロボットの設計・製作に取り組んでいます。 チームのリーダーとして、設計から試作、改良までをメンバーと協力しながら推進しました。 試作段階では動作の不安定化というトラブルも発生しましたが、原因を徹底的に分析し、配線やプログラムの調整を重ねた結果、発表会では動作安定性が高く評価されています。 この経験から、試行錯誤を重ねながら目標に向かう重要性を深く体得することができました。 今後は、この実践力とチームで課題に取り組んだ経験を活かし、貴社の製品開発やプロジェクト推進に貢献してまいります。 |
この例文では、チーム活動を通じた行動力と成果を具体的に伝えています。工学部の課題に直面したときの対応や結果を詳しく書くと説得力がより高まるでしょう。
③情報学部
情報学部では、プログラミングやデータ分析を通じて問題解決力を磨きます。
ここでは、ユーザー視点を重視した改善プロセスを描いた例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 情報学部で論理的思考力と粘り強さを養い、課題に直面しても冷静に対応する力を身につけました。 大学3年次、アプリケーション開発プロジェクトに取り組んだ際には、利用者ニーズに応えるスケジュール管理アプリの開発を目指しました。 当初は、機能面のバグや使いにくさという課題に直面。ユーザーインタビューを重ねながら改善を図り、試行錯誤を続けています。 最終発表では、「ユーザー視点を意識した設計」として高い評価を受けました。この経験を通して、ユーザーの声を反映しながら課題解決を進める力を鍛えることができました。 今後は、この課題発見・改善力を活かし、貴社のサービス開発に貢献したいと考えています。 |
この例文では、プロジェクト経験をもとに成長ポイントを明確に伝えています。情報系技術だけでなく「ユーザー視点」や「改善プロセス」を意識するとより好印象になります。
④医学部
医学部では、医療知識だけでなく、人と向き合う姿勢を徹底的に学びます。
ここでは、臨床実習で得た気づきを中心に、学びを活かした例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 医学部で観察力と傾聴力を養い、患者さん一人ひとりに寄り添う姿勢を身につけました。 大学4年次の臨床実習では、患者さんとのコミュニケーションの重要性を強く実感しています。 ある患者さんが体調だけでなく精神的な不安も抱えていたため、担当医と相談しながら丁寧な説明と傾聴を重ねました。 その結果、患者さんは積極的に治療に取り組むようになり、回復に向け前向きな変化を見せてくださいました。 この経験を通して、医療には知識や技術以上に信頼関係を築く姿勢が欠かせないことを学んでいます。 今後は、この観察力と傾聴力を活かし、貴院で患者さんに最適な医療を提供していきたいと考えています。 |
この例文は、医学知識だけでなく患者対応にフォーカスしている点が特徴です。医学部の「人に寄り添う姿勢」を具体的に示すとより好印象を与えます。
⑤薬学部
薬学部では、薬の専門知識だけでなく、患者さんに寄り添うコミュニケーション力も重視します。
ここでは、実務実習の中で得た成長をアピールする例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 薬学部で専門知識と傾聴力を培い、患者さんに信頼される薬剤師を目指す意識を養いました。 大学4年次の実務実習では、調剤薬局で服薬指導のサポートに取り組んでいます。 高齢の患者さんに薬の説明をする際、単に情報を伝えるだけでなく、不安や疑問に耳を傾けることを心がけました。すると、「安心して薬を飲めるようになった」と感謝の言葉をいただいています。 この経験から、薬の知識を伝えるだけでなく、相手の気持ちに寄り添うコミュニケーションの大切さを実感しました。 今後は、この知識と傾聴力を活かし、貴社の薬局や病院で患者さん一人ひとりに安心と信頼を届ける薬剤師を目指してまいります。 |
この例文では、薬の知識とともに患者対応の工夫を伝えています。薬学部の知識面だけでなく「患者に寄り添う姿勢」を具体的に示すことが大切です。
場合は、うまくいかなかった経験も隠さず書き、その後どう乗り越えたかを具体的に伝えましょう。
「大学で学んだこと」を話すときのNG例と注意点

就職面接で「大学で学んだこと」を聞かれたとき、面接官の質問意図とずれた回答をしてしまうと、せっかくのアピールチャンスを逃してしまうかもしれません。
そうならないためにも、ありがちなNG例を事前に知っておくことが大切です。
ここでは、面接でよくある3つのミスと、その改善ポイントをご紹介します。
- 学んだ知識だけを話してしまう
- 学業に関係ない内容を軸にしてしまう
- 専門用語を多用してしまう
① 学んだ知識だけを話してしまう
「大学で学んだこと」として、講義名や知識の内容だけを伝えるのは避けましょう。
なぜなら、単に「心理学を学びました」「統計学を学びました」と伝えるだけでは、自身の人柄が面接官に伝わらないからです。
たとえば、どんなきっかけでその講義に興味を持ったのか、どのように取り組んだのか、そこからどんな気づきや成長があったのかを交えて伝えることで、より人となりが伝わる回答になります。
知識そのものではなく、「どう学び、何を得たのか」を言語化することが、面接官の印象に残る鍵となります。
② 学業に関係ない内容を軸にしてしまう
大学で学んだことが思い浮かばないとき、ついサークルやアルバイトの話に逃げてしまうことがあります。もちろん、これらの経験自体が悪いわけではありません。
ただし、「大学で学んだこと」という問いに対して学業に一切触れない回答をしてしまうと、質問の意図を理解していない印象を与えてしまう可能性があります。
専攻内容には、その人がどういう分野に関心を持っているのか、どのような考え方をするのかといった個性が表れます。
そのため、「大学で学んだこと」を聞かれた際には、学業での取り組みを少しでも織り交ぜて話すことを意識しましょう。
③ 専門用語を多用してしまう
せっかく深い学びを積み重ねてきた方ほど、専門的な言葉をそのまま使ってしまうことがあります。
ただ、面接官が同じ専門知識を持っているとは限りません。内容が難しすぎると、話の本質が伝わらず、もったいない結果になってしまいます。
そこで大切なのが、やさしい表現に言い換えたり、日常的なたとえを使ったりする工夫です。
たとえば、「RNA干渉を用いた遺伝子発現の制御方法」よりも、「遺伝子の働きをコントロールする仕組みの研究」と言い換えた方が、イメージしやすくなります。
またこうした説明の工夫は、「相手目線で伝える力がある人だ」と評価されやすくなりますよ。
「大学で学んだこと」は絶好のアピールチャンス

面接やエントリーシートで頻繁に問われる「大学で学んだこと」は、企業が応募者の人柄やスキルを知り、自社での活躍可能性を見極めるための重要な質問です。
しかし「大学で学んだことがない」と感じてしまう場合でも、理系・文系それぞれの特徴を踏まえ、「大学で学んだことの例文」を参考にすれば効果的なアピールは可能ですよ。
専攻内容だけでなく、学びの過程や変化、さらには「大学で学んだことを活かす志望動機」まで具体的に伝えることで、説得力のある自己PRにつながるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。