初任給とは?平均額や基本給との違いを徹底解説
「初任給ってどのくらいもらえるの?」と気になっている就活生や新社会人は多いのではないでしょうか。
社会人としての第一歩となる初任給は、生活設計やキャリアを考えるうえで大切な指標ですが、基本給や手取りとの違いが分かりにくく、平均額も業界や企業規模によって大きく異なるのが実情です。
そこで本記事では、初任給の定義から最新の平均額、業界別の特徴、さらには支給タイミングまで詳しく整理しました。
「初任給とは何か」を正しく理解することで、就職活動や今後のキャリア選択にきっと役立つはずです。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
初任給とは?定義と基本的な考え方

初任給とは、新卒として入社した社員が最初に受け取る給与のことです。生活水準や将来設計を考える重要な要素として、多くの就活生が入社前から関心を寄せています。
金額の大小だけでなく、その意味を正しく理解することで、不安を減らし安心して働き始められるでしょう。初任給は、企業が新入社員に対して一律で定める給与を指します。
一般的に学歴や雇用形態によって金額が異なり、大卒や院卒では差が設けられているケースが多く、業界や企業規模によっても基準が変わるため、自分に合った企業選びの目安としても重要です。
就職活動中に企業研究をする際には、この金額が持つ意味を確認し、将来の働き方や生活のイメージづくりに役立ててください。
初任給と基本給・手取りの違い

就活生にとって「初任給」という言葉はよく耳にしますが、基本給や手取りとどのように違うのか、知っていますか?
初任給は「会社が新入社員に最初に支払う給与」で、その基盤となるのが基本給です。基本給は職務や等級に応じて設定される固定の部分であり、手当や残業代の計算の基準になります。
一方で手取りとは、初任給など月給から社会保険料や税金が差し引かれた、手元に残るお金を指します。
求人票にある「初任給20万円」などの額面と、口座に振り込まれる金額には大きく差が出ることもよくあり、この仕組みを理解していないと、生活費の計算を誤り、入社後に資金繰りで悩む可能性があります。
逆に言えば、基本給と手取りの関係を事前に知っていれば、生活設計をしやすくなり安心感も得られるでしょう。初任給の意味を正しく理解することは、社会人生活を安定して始めるための第一歩です。
初任給の平均額【最新データ】

初任給は、社会に出て初めて受け取る給与のことです。金額だけでなく、手取りの差や支払いのタイミング、賞与や住宅手当の有無によって印象は大きく変わります。
ここでは、厚生労働省などが発表する最新の動きをふまえ、平均額の見方と注意点をわかりやすく整理しました。知っておくと比較がしやすくなるでしょう。
- 学歴別の初任給平均額
- 企業規模別の初任給平均額
①学歴別の初任給平均額
学歴によって初任給の水準は異なる傾向が強いですが、数字だけにとらわれると本質を見失いかねません。企業は人事制度に基づき、学部卒、修士卒、博士卒、専門・短大卒などに給与テーブルを分けています。
学部卒は基準額が最も多く設定され、修士や博士課程を修了している場合は初任給が上がる傾向にあります。しかし学歴よりも、職種や勤務地、企業によってその差は異なります。
また、固定残業代を含む求人は月給が高く見えても、実際の残業時間が多ければ時給換算で低くなりますし、社会保険料や税金を差し引かれることも忘れてはいけません。
加えて、給与の支給日は会社によってさまざまで、入社月の初任給が満額支給されないケースもあります。さらに、住民税は翌年から引かれるため、入社初年度は手取りが比較的多く感じられるでしょう。
このように平均額は参考になりますが、将来の昇給スピードや賞与の有無、長期的なキャリアの成長機会と併せて検討することが賢明です。
②企業規模別の初任給平均額
企業規模が大きくなるほど初任給の平均は高い傾向がありますが、必ずしも「大企業=有利」とは言い切れません。
大企業は制度や福利厚生が充実し、住宅補助や地域手当、家族手当などが整備されているため、待遇が安定している反面、基本給は必ずしも高額ではなく、年功序列型でゆるやかなケースが見られます。
一方で、中小企業やベンチャーは基本給が控えめに見えることもありますが、成長産業や外資系、IT、コンサルなどの分野では初任給が高水準に設定されることがあります。
また、固定残業代制度の有無や残業時間の設定によって手取りが変動します。例えば、ある企業は月給が高いように見えても、住宅補助がなかったり、残業代が込みであったりする場合があります。
さらに、支給日のタイミングや締め日の違いにより、入社初月の給与が満額にならないことも考えられます。したがって、企業規模の大小や平均金額の高さだけで判断するのは危険でしょう。
【参照元】
・厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
・厚生労働省「新規学卒者の初任給」に関する公表データ
・各種求人票・企業採用情報
業種・職種別の初任給を比較

多くの学生が気になるのは「業種や職種によって初任給がどのくらい違うのか」という点でしょう。大卒の平均的な初任給はおよそ22万~23万円程度ですが、実際には業界や職種によって差があります。
金融業界は平均で24万~25万円と高めで、特に総合商社や外資系はさらに上回る場合も少なくありません。IT業界やメーカーは23万円前後が一般的で、安定感がありながら成長環境も期待できます。
一方、教育や福祉は平均20万~21万円程度と低めですが、人の役に立つ実感を得やすい点が魅力です。
職種で見ると、営業職は歩合やインセンティブが加わる可能性があり、初任給後の伸びが大きい傾向があります。技術職や研究職はスタートは23万円前後でも、専門性を高めることで昇給が見込めるでしょう。
単に金額だけで比較するのではなく、自分がどんなキャリアを築きたいかを重ね合わせて考えることが大切です。
【参照元】
・厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
・厚生労働省「新規学卒者の初任給」に関する公表データ
・各種求人票・企業採用情報
初任給が高い業界

就活生にとって「どの業界なら初任給が高いのか」は気になるテーマです。平均額だけでなく、業界ごとの特徴を知ることで将来のキャリア選びにもつながるでしょう。
ここでは、初任給が高いと言われる代表的な業界を整理しました。
- 総合商社
- コンサルティング
- 金融(銀行・証券)
- 不動産
- IT・通信
- メーカー(自動車・電機)
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①総合商社
総合商社は、数ある業界の中でも特に初任給が高い業界です。世界中の資源や製品を取り扱い、巨大な商取引を成立させるため、社員には早期から大きな役割が期待されています。
高い給与はその期待の裏返しであり、入社直後から責任ある仕事を任されることも少なくありません。
さらに、若いうちから海外赴任やプロジェクトへの参加があり、短期間で多くの経験を積める環境が整っています。
その一方で、成果を出せば大きな評価が得られる反面、成果が伴わなければ厳しい指導を受けることもあります。長期的に高収入を維持するには体力と精神力が必要でしょう。
初任給の高さだけで判断せず、仕事内容や将来のキャリアパスを含めて考えることが重要です。待遇の裏側にあるハードワークを理解し、覚悟を持って選択してください。
②コンサルティング
コンサルティング業界は、戦略・人事・ITなど多様な分野で企業の課題解決を担い、初任給が高いことで注目されています。
給与が高い理由は、限られた期間で顧客に成果を提供するため、若手であっても即戦力としての役割が求められるからです。
実際に入社1年目から大企業の経営層と接する機会があり、短期間で大きなスキルアップが期待できる反面、高い成果を維持する必要があり、プレッシャーや長時間労働に直面することも少なくありません。
高待遇の背景には激しい競争と成果主義があるため、安易に「給与が高いから」と選ぶのは危険です。
自分がどの分野で専門性を磨きたいのか、将来のキャリアをどう描きたいのかを考え、高い初任給のメリットと過酷な現実を正しく理解することで、納得感のある選択ができます。
③金融(銀行・証券)
銀行や証券といった金融業界も、初任給が高い業界として知られています。金融の仕事は人々や企業のお金を扱うため責任が重く、その分給与にも反映されています。
特に証券会社では、営業の成果がダイレクトに収入へつながる仕組みがあり、20代から年収が大きく伸びる可能性があります。
高い成果を出した人にはインセンティブも大きく、若くして高収入を得られる人もいます。しかしノルマが厳しく、数字を追う日々に疲れてしまう人がいるのも事実です。
銀行は比較的安定した給与と福利厚生が魅力で、長期的に腰を据えて働けるでしょう。一方で証券は挑戦的で実力主義色が濃く、自分の性格や目指すキャリアによって向き不向きが分かれます。
給与水準だけでなく、働き方やストレス耐性を含めた自己分析が必要です。金融業界は収入とプレッシャーが表裏一体であることを理解したうえで検討してください。
④不動産
不動産業界は契約単価が高いため、初任給も他業界に比べて高めに設定されています。
特に大手デベロッパーや仲介企業は成果報酬型の仕組みを導入しており、初任給に加えて歩合給が支給されるケースも多くあります。成果が出れば同世代の平均を大きく上回る収入を得られるでしょう。
さらに景気が良いときは成約件数が増え、短期間で大きな収入を得られる可能性もあります。ただし不動産業界は景気の影響を受けやすく、成約が取れない時期は収入が安定しない点がリスクです。
営業職では土日や夜に商談が入ることも多く、ライフスタイルが崩れる可能性もあります。給与の高さに惹かれて入社したものの、働き方に合わず退職してしまう人も少なくありません。
大切なのは「自分が営業スタイルを楽しめるかどうか」であり、収入と働き方をバランスよく考える姿勢が欠かせません。
⑤IT・通信
IT・通信業界はデジタル化の流れにより需要が急速に高まっており、初任給も上昇傾向にあります。
大手IT企業や外資系では給与の高さに加え、福利厚生や教育制度も充実しているため、安心して働ける環境が整っています。
特にエンジニア職ではスキルがそのまま市場価値につながるため、若いうちから高収入を狙える可能性があります。ただしスキルを磨き続けなければすぐに取り残されるため、自己研鑽が欠かせません。
プロジェクトごとにハードな働き方が求められる場合もあり、成果主義の側面が強い企業では評価が厳しくなることもあるでしょう。
給与だけを基準にせず「成長できる環境か」「自分のスキルを活かせるか」を重視することが大切です。IT・通信は変化が速い分、学ぶ意欲と適応力がある人に向いています。
⑥メーカー(自動車・電機)
自動車や電機といった大手メーカーも、安定して初任給が高い業界に分類されます。研究開発や生産技術の職種では理系出身者が多く、給与に加えて福利厚生の充実度が魅力です。
経営基盤が安定しているため、長期的に安心して働けることもメリットでしょう。また、昇給や賞与が制度として整っているので、着実に年収を上げていけます。
ただし昇給スピードは緩やかで、若いうちから急激に収入を伸ばすのは難しい場合があります。さらに勤務地が地方工場になることも多いため、生活環境に柔軟に対応できるかを考える必要があります。
メーカーは「堅実なキャリア」を歩みたい人には適していますが、短期で大幅な収入増を求める人には不向きかもしれません。
安定感と成長機会のどちらを重視するかを意識し、自分に合ったキャリア選択をすることが後悔のない就職につながります。
※参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、経済産業省「産業別雇用動向調査」、主要企業各社の採用ページ情報
初任給が支払われるタイミング
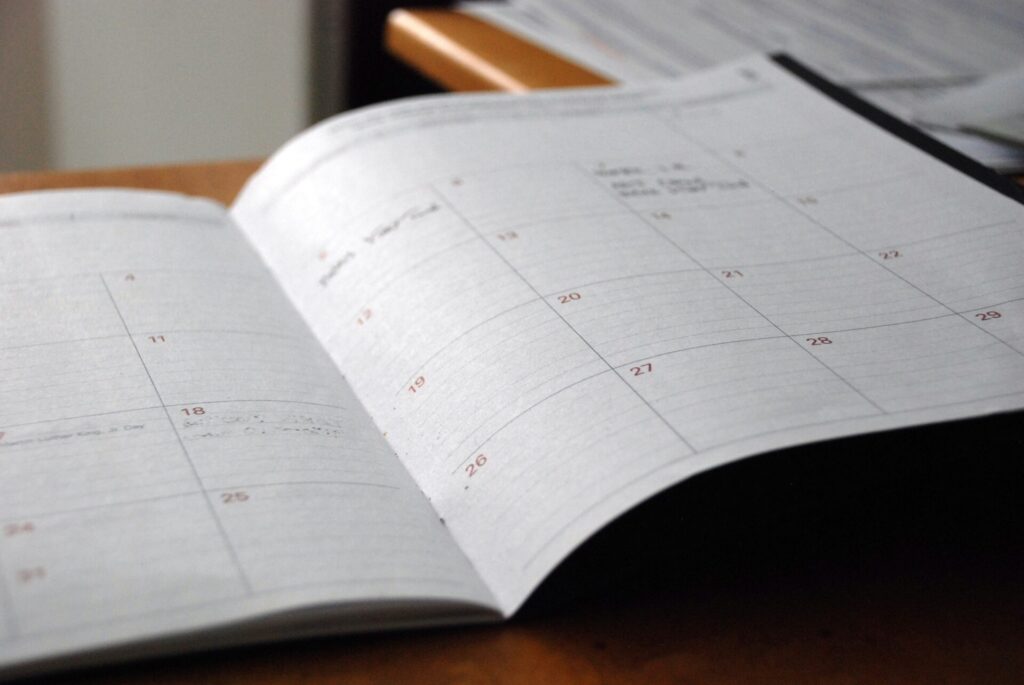
初任給は就職後に最初に受け取る給料であり、その支払いタイミングは会社ごとに異なります。入社前に確認しておかないと、生活資金のやりくりに影響することもあるでしょう。
ここでは主に3つの支払いパターンを取り上げ、違いと注意点を整理しました。
- 当月末締め当月払い
- 当月末締め翌月払い
- 当月日締め当月払い
①当月末締め当月払い
この方式は「その月に働いた分を同じ月の末日に受け取る仕組み」です。例えば4月に入社した場合、4月30日に初任給が支給されます。
最大の特徴は、働き始めてすぐに給料が入るため、早い段階から安心して生活を組み立てられる点でしょう。特に一人暮らしを始める人にとっては大きな安心材料になります。
ただし、残業代や手当の一部は翌月に繰り越される場合もあるため、最初の給与が想定より少ないと感じることもあります。少なくとも2か月分は給与明細を確認して実際の手取り額を把握する必要があります。
また、支払いが早い分だけお金を使いすぎてしまう人もいるため、初任給を受け取った段階から計画的に家計管理を始めることが重要です。
早めに支給される安心感に加えて、収入の流れを正しく理解しておくと、入社直後から安定した金銭感覚を身につけられるでしょう。
②当月末締め翌月払い
最も一般的で多くの企業が採用しているのがこの方式です。「その月に働いた分を翌月末に支払う」という仕組みになります。例えば4月に入社した場合、最初の給与は5月末に受け取ります。
企業にとっては給与計算が正確にでき、経理処理が安定するというメリットがあるため、多くの会社が導入しているのです。
一方で新社会人にとっては、働き始めてから実際に給与を手にするまで約2か月近く空くため、生活費や家賃をどう確保するかが課題になります。
そのため春休み中にアルバイトで貯金をしておいたり、入社前に親と相談して一時的に資金を借りるなどの備えが求められます。実際に「初任給までの生活資金が足りなかった」という声も少なくありません。
こうした仕組みを理解したうえで入社に臨めば、金銭的な焦りを感じずに新しい仕事へ集中できます。給与日を把握して、必要な生活費を逆算しておくことが安心した社会人生活につながるのです。
③当月日締め当月払い
この方式は「月の途中で締め日を設け、その月の後半に給与を受け取る仕組み」です。例えば「15日締め25日払い」であれば、1日から15日までに働いた分を25日に支給されます。
初任給の場合は4月1日から15日までの勤務分が対象となり、4月25日に給与が入るケースが多いです。翌月を待たずに比較的早くお金を受け取れる点が大きな特徴でしょう。
ただし、締め日があるため初任給は日割り計算になることです。最初の給与は満額ではなく思ったより少ないと感じ不安になる人もいますが、翌月からは通常どおり満額が支給されるため心配いりません。
むしろこの時期を新しい生活リズムを整える練習期間ととらえると良いでしょう。また、入社前に支払いサイクルを確認しておくことで、実際に給与が入る日を把握でき、支出計画も立てやすくなります。
初任給の金額だけに注目せず、今後の収入の流れを理解しておくことが、安定した社会人生活の土台になります。
就活生が初任給以外にチェックすべきポイント

就活の場では「初任給」ばかりに注目しがちですが、実際の社会人生活ではそれ以外の条件が将来に大きく影響します。
ここでは、ボーナスや昇給、福利厚生など、長期的な視点で確認すべき項目を整理しました。自分に合った会社を選ぶ参考にしてください。
- ボーナス(賞与)の有無を確認する
- 昇給や昇進のスピードを把握する
- 残業代やみなし手当の内容を確認する
- 福利厚生や制度の充実度を確認する
- 年収やキャリア全体の成長性を考慮する
- 勤務地や配属先の条件を確認する
- 教育研修やスキルアップ制度を活用する
- 離職率や定着率の実績を確認する
①ボーナス(賞与)の有無を確認する
ボーナスは企業ごとに支給の有無や金額、回数が異なるため、年収全体に大きな影響を与える要素です。
特に住宅や車の購入、留学や資格取得といった将来的なライフイベントを考えると、賞与の有無は計画性に直結するでしょう。
ただし「賞与あり」と記載があっても、業績次第で大幅に減額されるケースや、ほぼ支給されない年がある場合もあります。
したがって確認すべきなのは単なる有無ではなく、過去の実績や平均支給額、支給基準の透明性です。OB訪問や説明会で実際の金額レンジを聞いておくと、より現実的に判断できます。
初任給だけにとらわれず、長期的な収入設計を意識して調べてください。
②昇給や昇進のスピードを把握する
昇給や昇進は初任給以上に将来の生活水準を左右します。多くの企業では毎年少額ずつ昇給がありますが、中には成果を出せば20代で大幅に収入が伸びる環境もあります。
逆に、初任給が高くても昇給幅が小さければ、数年後には同世代の平均を下回ることもあるでしょう。
また昇進のスピードも重要で、入社5年で管理職を目指せる会社と、10年以上かかる会社ではキャリアの見え方が全く異なります。
就活時に確認しておくべきは「平均昇給率」「役職登用の年齢モデル」「評価制度の内容」です。数字が公開されていない場合でも、先輩社員のキャリア例を参考にできます。
将来どの程度の収入を得られるかだけでなく、責任ある立場で挑戦できる機会があるかどうかも判断材料にしてください。長い社会人生活を見据え、成長速度が合う会社を選ぶことが大切です。
③残業代やみなし手当の内容を確認する
残業代やみなし手当は、給与の実質的な価値を大きく変える要素です。
みなし残業制度では、一定時間分の残業代が最初から給与に含まれており、その範囲を超えて働いた場合に追加で支給されるかどうかが大きなポイントになります。
例えば「月30時間分の残業込み」と記載されていれば、30時間以内なら追加支給はありません。そのため実際の残業時間が多いと手取り額が思ったほど増えない可能性があるのです。
逆に残業代が全額別途支給される会社では、働いた分がそのまま収入に反映されるので透明性が高いでしょう。ただし残業時間が極端に多い企業では、健康面やワークライフバランスに悪影響が出ます。
確認の際には「超過分は支給されるのか」「平均残業時間はどの程度か」を意識してください。制度の仕組みを正しく理解し、自分の生活スタイルに合う働き方を選ぶことが重要です。
④福利厚生や制度の充実度を確認する
福利厚生は、給与に表れにくい部分で生活を支える大切な条件です。例えば住宅手当や家賃補助があると、年間で数十万円分の負担軽減になります。交通費や昼食補助、社員寮の有無も同じです。
また最近ではリモート勤務制度やフレックスタイム制度、特別休暇制度といった柔軟な働き方を支える制度が注目されています。こうした環境があると、ライフスタイルに合わせて働きやすいでしょう。
さらに、健康診断の充実度や保険加入制度、出産・育児支援などは長期的に働く上で安心材料となります。企業によっては、スポーツジムの法人契約や資格取得費用の補助などもあります。
給与額だけで判断せず、福利厚生を含めて「実際の生活の豊かさ」を想像してください。充実度の差は、入社後の満足度を大きく左右します。
⑤年収やキャリア全体の成長性を考慮する
就活生にとって初任給はわかりやすい指標ですが、それだけに目を向けるのは危険です。大切なのは入社後の年収の伸び方と、キャリア全体の見通しです。
初任給が低めでも、毎年着実に昇給し役職に就けば、30歳で大幅に収入を伸ばせる会社もあります。一方、初任給が高くても昇給がほとんどなければ、数年で伸び悩んでしまうでしょう。
さらに、スキルアップの機会や異動の可能性、キャリアパスの多様性は、将来的な市場価値を決める要因です。
10年後にどんなポジションで働いていたいかを逆算して考えると、企業ごとの成長性を見極めやすくなります。転職や独立を視野に入れるなら、キャリア全体で得られる経験の幅が重要でしょう。
目先の金額だけでなく「長期的にどんな力を身につけられるか」を意識してください。
⑥勤務地や配属先の条件を確認する
勤務地や配属先は日々の生活と直結するため、軽視できません。例えば通勤時間が片道1時間半を超えると、年間で数百時間を移動に費やすことになり、仕事やプライベートの充実度に影響します。
また配属先の部署やエリアによって、仕事内容や得られる経験の幅も変わるでしょう。
都市部の本社勤務で幅広いプロジェクトに関わる場合と、地方支社で地域に密着した仕事を経験する場合では、キャリアの方向性も異なります。
さらに転勤制度の有無や、本人の希望がどの程度反映されるかも重要です。家庭の事情やライフスタイルによって、勤務地は大きな意味を持ちます。
事前に企業へ質問したり、先輩社員の話を聞いたりして実情を確認してください。働く場所が自分の生活設計に合うかどうかを考えることは、給与額以上に大切です。
⑦教育研修やスキルアップ制度を活用する
教育研修やスキルアップ制度の充実度は、入社後の成長スピードを大きく左右します。新入社員研修で基礎をしっかり学べる会社では、業務への適応がスムーズで、その後の活躍につながりやすいでしょう。
また、資格取得支援や外部研修への参加補助があれば、自分の市場価値を高める大きな助けになります。さらに、メンター制度やキャリア相談窓口があるかどうかも確認すべきです。
これらが整っている会社では、不安を抱えたときに支援を受けやすく、離職率も低い傾向があります。研修制度を軽視すると、入社後に「思ったより成長の機会が少ない」と感じてしまうかもしれません。
長期的に見て、自分がどんなスキルを磨きたいかを考え、それに合う制度を持つ企業を選んでください。
⑧離職率や定着率の実績を確認する
離職率や定着率は、働きやすさを測る客観的な指標です。初任給が高くても、数年で多くの社員が辞めている企業では、働く環境に問題がある可能性が高いでしょう。
特に新卒3年以内の離職率は重要で、この数字が高ければ教育やサポート体制に課題があると考えられます。
逆に、定着率が高い企業は社員が安心して働ける仕組みを持っているケースが多く、長期的に働くうえで心強いです。
もちろん数字だけでは判断できないため、企業説明会や口コミ、OB訪問を通じて実際の雰囲気や理由を確認してください。
離職率が高い場合でも、成長が早くスキルが磨ける環境という側面を持つ場合もあります。自分に合った環境かどうかを見極めることが大切で、長期的なキャリアの安定性を考えるうえで欠かせない情報です。
初任給を理解してキャリア選択に活かそう

初任給とは社会人として最初に受け取る給与であり、就職活動や企業選びにおいて重要な判断材料となります。
基本給や手取りとの違いを理解し、最新データから平均額や業種別の水準を把握することで、現実的な期待値を持つことが可能です。
また、総合商社やコンサルティングなど初任給が高い業界に目を向けつつ、支給タイミングやボーナス、昇給制度、福利厚生などの条件を総合的に確認することが大切です。
なぜなら、初任給の金額だけでなく、年収やキャリア全体の成長性が将来の満足度を大きく左右するからです。
つまり、初任給とは単なる給与額ではなく、就活生が長期的な視点で企業を選ぶための重要な指標だと言えます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










