金融業界の将来性に迫る|課題・魅力・向いている人まで全網羅【2025年版】
「将来性のある業界で働きたい」「経済や社会を支える実感のある仕事がしたい」そんな思いから、金融業界に興味を持つ方も多いのではないでしょうか。
銀行・証券・保険・クレジットなど、お金の流れを担う金融業界は社会に欠かせない“インフラ”とも言える存在で、昨今はテクノロジーの進展により新たなサービスや働き方も生まれています。
とはいえ、「10年後にはなくなると聞いたことがある」「就職先としての魅力は本当にあるの?」「自分に向いているかわからない…」と不安を感じている方も少なくないでしょう。
本記事では、金融業界の基本構造から最新の動向、構造変化や課題、将来性、働く魅力、向いている人の特徴までをわかりやすく解説します。
金融業界への就職を検討している方が、自分に合ったキャリアを考えるためのヒントが得られる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
金融業界とは?|基本構造と役割

金融業界とは、お金が「余っている人」と「必要な人」をつなぐ仕組みを担う業界です。銀行、証券会社、保険会社、クレジット会社などが代表的な存在で、社会全体のお金の流れを支える役割があります。
金融の仕組みは「直接金融」と「間接金融」に分けられます。
| 区分 | 内容の説明 | 主な例 |
| 直接金融 | 投資家が企業や国に直接お金を出資する仕組み | 株式購入・債券購入 |
| 間接金融 | 銀行などを通じて間接的にお金が貸し出される仕組み | 顧客の預金 ↓ 預金を財源として銀行が個人や企業に融資・貸出 |
こうした仕組みによって、個人の生活や企業の成長、さらには社会全体の経済活動が支えられているのです。
近年はフィンテックやAIの登場により業界の形も変わりつつありますが、「お金の流れを整える」という本質的な役割は今も変わっていません。
金融業界の最新動向

近年の金融業界は、テクノロジー化とグローバル化が加速しています。
AIによる業務自動化、フィンテックやインシュアテックといった革新的サービスの拡大、そして海外市場を見据えた戦略的展開の3つが、金融業界における最新トレンドだと言えるでしょう。
①AIと自動化が進む金融業務
金融業界では、AIやロボティクスを活用した業務の効率化が本格的に進んでいます。
たとえば、三菱UFJ銀行では紙書類の電子化を目的にAIとロボットを導入し、事務作業の自動化を推進中です。
また、融資審査やサイバー攻撃の検知といった分野でもAIを活用し、これまで人間が担っていた判断業務まで、徐々にシステムへと置き換えています。
現段階では「人の業務を支援する」レベルでの導入が主流ですが、今後は業務そのものがAIに代替されていく可能性も高く、金融業界の構造自体が大きく変化していくでしょう。
参照元:三菱UFJ銀行
②フィンテック・インシュアテックによる技術革新
フィンテック(FinTech)とは、「Finance(金融)」と「Technology(技術)」を掛け合わせた言葉で、QRコード決済やオンライン融資、ロボアドバイザーによる資産運用のことを指します。
インシュアテック(InsurTech)は保険業界でのテクノロジーの革新を指し、ウェアラブル端末で取得したデータをもとに健康状態を可視化したり、ドライバーの運転傾向に応じて自動車保険の保険料を変動させたりすることです。
このように、金融とテクノロジーの融合は、単なる業務の効率化にとどまりません。
従来にはなかった新しい金融サービスを生み出す原動力となっており、業界全体に大きな変化をもたらしているのです。
③国際展開を視野に入れた成長施策
国内市場は少子高齢化や人口減少の影響で成長が鈍化しており、それに伴い多くの金融機関が海外市場への展開を加速させています。
特に、東南アジア・中東・アフリカなどの経済成長が著しい地域への進出が活発で、日本の金融機関は現地法人の設立やM&Aを通じて海外での収益源を確保していますよ。
こうした取り組みは、単なる市場拡大にとどまりません。今後の金融業界で求められる人材像にも大きな影響を与えるでしょう。
金融業界の将来性を知るなら業界分析は必須!1冊で完結する「業界分析大全」を受け取ろう
金融業界に将来性があるかを知るためにも、まずは金融業界の構造や、業界全体の最新動向の全体像を理解しておきたいところですよね。そのために必要なのが業界分析です。
加えて、業界構造を捉えてアピールできる就活生は少ないため、業界分析は他の就活生との差別化にもなります。しかし、各企業の資料やニュースを細かく集めて分析するのは非常に手間がかかるもの……
そこで就活マガジン編集部では、業界分析が1冊で完結する「業界分析大全」を無料配布しています!
業界分析大全では、金融業界も含めた20の業界について業界構造から最新の成長率、主要な企業まで徹底的に解説。これ1冊で、気になる業界が今どんな状況なのかがまるっと理解できますよ。
「金融業界の今の課題や成長率は?」「主要企業は安定している?」「各企業のシェア率や売り上げは?」など、金融業界について気になる点もまとまっているため、ぜひ、下のボタンからLINE登録ののち、特典をダウンロードしてみてくださいね。
\ 業界分析はこれ1冊で完結! /
金融業界の構造変化と現状

ここでは、金融業界の構造変化と現在の動きをわかりやすく解説します。
デジタル化やキャッシュレス決済の広がりによって金融機関のあり方が急速に変わりつつある今、「どんな変化が起きているのか」を知っておくことが、キャリア選択のヒントになるでしょう。
①ネオバンクやキャッシュレス化の影響
金融業界は、ネオバンクやキャッシュレス化の影響を受けています。
ネオバンクとは、物理的な支店を持たず、低コストかつスピーディーなサービスを実現するインターネット専用銀行のことです。
たとえば、住信SBIネット銀行は、提携企業に銀行機能を提供する「BaaS(Banking as a Service)」モデルを展開し、金融サービスの内製化を後押ししています。
一方、政府も公共料金の電子納付やクレジットカードの利用拡大を通じて、現金に頼らないキャッシュレス決済の社会づくりを進めています。
参照元:住信SBIネット銀行
②支店削減や人員整理の動き
銀行各社では、支店の統廃合や人員削減が進められています。
たとえばみずほフィナンシャルグループは、業務の自動化を背景に、2026年度末までに約1万9,000人の人員削減を宣言しました。三菱UFJ銀行や三井住友銀行も同様に、支店の縮小や業務の効率化に取り組んでいます。
こうした動きの背景には、低金利の継続や人口減少による収益の鈍化があります。また、デジタル技術の進化によって、業務そのものの見直しが進められているのも大きな要因です。
銀行はこれまでの労働集約型モデルから脱却し、より効率的で柔軟な組織体制への転換を目指しています。
参照元:東洋経済新聞
「金融業界はなくなる」「将来性がない」と言われる5つの理由
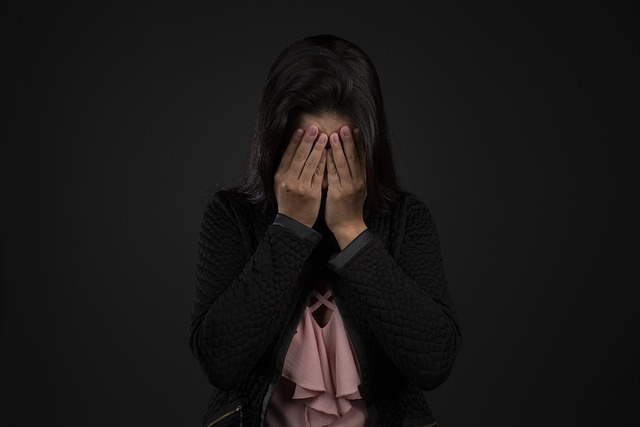
ここでは、「金融業界はなくなる」「将来性がない」と言われる理由を5つ解説します。
今、金融業界は100年に一度とも言われる大きな転換期を迎えています。伝統的なモデルでは限界が見え始め、新しい価値観や技術にどう向き合うかが問われているのです。
志望先として検討しているなら、こうした現実をきちんと把握しておきましょう。
- 日本銀行による低金利・マイナス金利政策の長期化
- 地方の人口減少・高齢化により地方銀行の経営が困難に
- IT業界・異業種の台頭による顧客の流出
- AI・RPAによる業務の自動化と雇用の縮小
- 若者からの人気の低下・就職先としての魅力減退
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①日本銀行による低金利・マイナス金利政策の長期化
銀行などの金融機関は、もともと「お金を預かって、それよりも高い金利で貸し出すことで利益を得る」という“利ざや”型のビジネスモデルで成り立っています。
しかし、2016年に日本銀行が「マイナス金利(政策銀行が日銀にお金を預けると、逆に手数料を取られる政策)」を導入してから、この仕組みに大きな変化が起こりました。
企業や個人に貸し出す際の金利も引き下げざるを得なくなった銀行が、これまでのように利ざやで十分な利益を出せなくなってしまったのです。
多くの金融機関では、収益源を分散させるために、投資信託や保険商品の販売や海外市場への展開などの新たな収益モデルを模索しています。しかし、根本的な構造の変化に対応しきれていません。
②地方の人口減少・高齢化による地方銀行の経営難
金融業界の中でも特に厳しい状況にあるのが、少子高齢化と人口流出によって顧客そのものが年々減少している地方銀行です。
高齢者の割合が多い地域では、キャッシュレスやネットバンキングの浸透が進まず、非効率な店舗運営を強いられているケースも少なくありません。
その一方で若年層は都市部やネットバンクに流れるため、地域との接点は薄れていく一方です。
こうした背景から、地銀の再編や統合も加速しています。実際に、ふくおかフィナンシャルグループと十八親和銀行の経営統合など、広域でのグループ化も進行中です。
③IT業界・異業種の台頭による顧客流出
現在、金融業界にはIT業界や異業種からの参入が相次いでいます。楽天銀行・PayPay銀行・LINE Bankといったネオバンクのほか、AppleやGoogleなどのビッグテック企業が代表的な例です。
これらの企業は、スマートフォンを軸にした使いやすいアプリ・ポイント還元・スピーディーなサービス提供など、従来の銀行にはなかった新たな価値を提供し、特に若年層の支持を集めています。
さらに、柔軟な開発体制を持ち、ユーザーニーズへの対応も迅速です。支店や複雑な承認プロセスを必要としない分、運営コストを抑えられる点も強みとしています。
こうした競合の台頭により、既存の銀行は顧客離れを防ぐために、ビジネスモデルやサービスの在り方そのものを見直す必要に迫られているのです。
④AI・RPAによる業務の自動化と雇用の縮小
近年では、AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入が進んでおり、銀行の業務は急速に効率化されています。
ローン審査や顧客対応、事務処理など、かつて人間が行っていた業務をシステムが自動で処理できるようになってきました。
その結果、これまで必要とされていた人材が過剰となり、大手銀行の中には数千人単位の人員削減を進める動きも見られます。
新卒採用も「多く取って現場で育てる」時代から、「優秀な人材を最小限確保し、高度な業務を任せる」方向へとシフトしつつありますよ。
⑤若者からの人気低下・就職先としての魅力減退
かつての金融業界は、「安定していて社会的信用も高い」という理由で就職人気ランキングの上位に君臨していました。しかし現在では、その地位が大きく揺らいでいます。
「給与水準は高くない」「ノルマが厳しい」「将来のビジョンが見えにくい」といったネガティブな印象が広がり、学生の志望離れが進んでいるのです。
また、終身雇用の崩壊や業務のデジタル化による人員削減も、「安心して長く働ける業界」というイメージを失わせています。
その結果、成長性やスピード感を求める学生はコンサル・IT・スタートアップなどを志望する傾向が強まり、銀行は「避ける業界」になりつつあるのが現実です。
金融業界が抱える3つの課題をわかりやすく解説
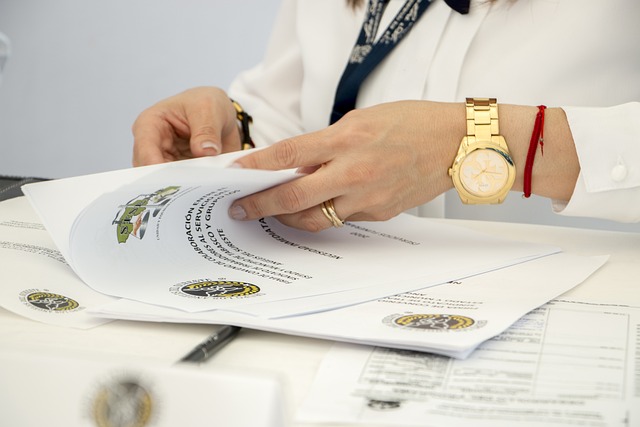
ここでは、金融業界が抱える3つの課題について、わかりやすく解説します。
かつては「安定した業界」の代表格だった金融業界ですが、今は業界全体が深刻な構造的課題に直面していますよ。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①低収益構造からの脱却
金融業界の1つ目の課題は、「低収益構造」から脱却することです。
銀行は預金金利よりも高い金利で貸出を行うことで利益を得ています。しかし、超低金利が続くいま利ざやが大きく縮小し、資金運用による収益が得にくい状況に陥ってしまいました。
この課題に対応するため、多くの銀行はビジネスモデルの転換を進めています。
たとえば三菱UFJは、信託・証券部門との連携を強化して投資信託や資産運用などの手数料収入型のビジネスを育てることで、収益を確保しようとしています。
②過度な貸し渋りの是正
近年の景気低迷による金融機関の「過度な貸し渋り」も、是正すべき重要な課題の1つですよ。
過度な貸し渋りの結果、企業の成長が妨げられたり、個人の生活再建の機会が失われたりと、経済全体の停滞を招いているからです。
融資を控えることで銀行自身も金利収入を得にくくなり、業績の悪化に陥っている現状もあります。
金融業界を健全に活性化させるためには、過度なリスク回避から脱却し、将来性のある事業や個人に対して適切な融資を行う必要があるでしょう。
③IT・キャッシュレス時代への柔軟な対応
金融機関が直面する3つ目の課題は、IT化・キャッシュレス化が進む時代への柔軟な対応です。
たとえばLINE PayやPayPayといったスマホ決済サービスは、送金や支払いが手軽にできるうえにポイント還元という付加価値もあり、特に若年層から高い支持を集めています。
このようなサービスの普及により、「スマホ決済にお金を預けておく=銀行口座を使わない」という流れが加速し、銀行にとっては預金残高の減少や資金運用力の低下といった影響が出始めているのです。
この状況に対抗するため、みずほ銀行はスマホ決済サービス「J-Coin Pay」を展開し、銀行ならではの高額決済や信頼性を強みに独自の価値を打ち出そうとしています。
今後の金融機関には、外部環境の変化にただ対応するだけでなく、自らの強みを活かしながら時代に合ったサービスを創出していく力が求められるでしょう。
参照元:みずほ銀行
それでも金融業界に将来性があると言える5つの理由

ここでは、将来性に不安の声があがる一方で、金融業界にまだ多くの可能性が残されている理由を解説します。
大手金融機関が持つ収益力に加え、テクノロジーとの融合で生まれる新たな展開や海外市場への進出など、金融業界にはポジティブな要素も少なくありません。
- メガバンクの安定した業績と海外展開の強化
- フィンテックの進展と個人投資の拡大
- 保険業界の収益改善と海外M&Aによる成長戦略
- キャッシュレス化の進展とクレジット業界の成長
- AI・デジタル技術の活用による業務効率化と新サービスの創出
①メガバンクの安定した業績と海外展開の強化
まず注目すべきは、三菱UFJ・三井住友・みずほの3大メガバンクが、現在も安定した業績を維持している点です。
2025年3月期の決算では、3メガバンクの連結純利益が合計で3兆9,263億円となり、前年同期比で25.3%増という大幅な伸びを記録しました。
好調の背景には、国内市場だけでなく、東南アジア・中東・オーストラリアなどの成長市場への積極的な展開があります。
日本市場の縮小に対応するかたちで海外収益の比率を高めてきたことが、安定した業績につながった大きな要因と言えるでしょう。
参照元:時事通信
②フィンテックの進展と個人投資の拡大
次に注目したいのは、金融分野におけるフィンテック(FinTech)と呼ばれる技術革新の進展です。
スマホアプリを活用したオンライン証券取引・資産運用サービス・AIによるロボアドバイザーなどが普及し、これまで金融機関の窓口でしかできなかったことが誰でも手軽に行えるようになりました。
一方で、「貯蓄から投資へ」という流れも加速しています。新NISA制度の導入によって投資のハードルが下がり、若年層や投資初心者も市場に参入しやすくなりました。
証券業界では、資産運用をプロに任せられる「ラップ口座」などのサービスが拡大しており、信託銀行や証券会社の役割もより専門的な方向へと広がりつつあります。
こうしたフィンテックの進展と個人投資の拡大は、金融業界全体の成長を支える大きな原動力となるでしょう。
③保険業界の収益改善と海外M&Aによる成長戦略
生命保険・損害保険分野は、収益改善の傾向が見られます。円安や株高の影響により、国内大手の生命保険会社の多くが「逆ざや」状態からの脱却に成功しつつあるのです。
さらに、保険業界は国内市場の成熟を見越して、海外企業のM&Aによる収益拡大にも注力しています。特に、大手損害保険会社は欧米の再保険会社を買収し、世界市場での存在感を高める動きを加速させていますよ。
また、ネット保険・銀行窓口・保険ショップなど、販売チャネルの多様化も進行中です。
今後は、医療保険や介護保険といった「第三の保険」市場の成長が見込まれており、超高齢社会を支える仕組みとして、保険の役割はさらに重要になると考えられます。
④キャッシュレス化の進展とクレジット業界の成長
クレジットカード業界も、キャッシュレス化の波に乗って成長中です。株式会社ジェーシービーの調査では、2024年度のクレジットカード保有率は87%と高水準を維持しています。
経済産業省の発表によれば、2024年のキャッシュレス決済額は141.0兆円に達し、そのうちクレジットカードによる決済額は116.9兆円で、全体の82.9%を占めました。
カードの多機能化も進み、交通系IC・マイレージ・公共料金の決済など、あらゆるシーンでの利便性が向上しています。これらの動きは、金融業界の裾野をさらに広げる要因となるでしょう。
参照元:経済産業省|株式会社ジェーシービー
⑤AI・デジタル技術の活用による業務効率化と新サービスの創出
AI・デジタル技術の活用も、金融業界に革新をもたらしました。
たとえば、AIによるローン審査の自動化、チャットボットによる顧客対応、RPAによる事務処理の省力化などは、業務の効率化を加速させています。
デジタルバンクの設立やバンキングアプリの強化、顔認証や生体認証を使ったセキュリティ技術の導入も、ユーザー体験を向上させました。
単なるコスト削減にとどまらない、新たな価値を提供する“金融サービス”へと進化する可能性に、金融業界の将来性を感じている若手人材も少なくありません。
「有名企業でなくてもまずは内定を目指したい…」「隠れホワイト企業を見つけたい」方には、穴場求人も紹介しています。第一志望はすでに決まっているけど、他の業界や企業でも選考に参加したい方は非公開の穴場求人を確認してみてくださいね。キャリアアドバイザーがあなたに合う求人を紹介してくれますよ。
金融業界で働く4つの魅力とは?

ここでは、金融業界で働く4つの魅力を紹介します。
金融業界は厳しい業務や専門知識が必要なイメージがある一方で、安定性・専門性・成長性の3つを兼ね備えた非常に魅力的な業界です。
「安定も挑戦もどちらも大切にしたい」就活生にとって、金融業界は前向きに検討する価値のある選択肢です。
①安定した収入と手厚いサポート体制
金融業界で働く魅力の1つに、安定した収入と手厚いサポート体制があります。
国税庁の調査によれば、金融業・保険業に従事する給与所得者の平均年収は652万円で、全業種の平均年収460万円を大きく上回る結果となりました。
大手企業では年収1,000万超えも珍しくありません。さらに、給与だけでなく賞与や各種手当、退職金制度も充実しています。福利厚生や休暇制度も整っており、有給の取得率も高い傾向です。
また、企業によっては資格取得支援や社内研修制度も充実しているため、スキルアップのサポート体制も万全だと言えるでしょう。
参照元:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
②ライフステージに応じた柔軟な働き方ができる
金融業界は、長く働きやすい環境が整っている点も大きな魅力です。
土日祝休みが基本であるほか、産休・育休制度の整備、有給休暇の取得推奨など、ライフステージの変化に対応しやすい職場が多くあります。
時短勤務やフレックスタイム制度を導入している企業もあり、結婚や子育てを経てもキャリアを継続しやすい環境が整っていると言えるでしょう。
ワークライフバランスを重視したい人にとって、金融業界は非常に働きやすい業界の1つです。
③経済を読み解く知識と実践的なスキルが身につく
金融業界で働くことで得られる専門知識は、自分自身の人生にも大いに役立ちます。
資産運用・保険・ローン・税金などの金融リテラシーが自然と身につくため、将来のマネープランやライフプランを立てる際に大きな武器となるでしょう。
業務では企業の財務状況を分析したり経済動向を読んだりと、実践的なスキルも磨かれます。研修や資格取得支援制度も豊富にあるため、意欲のある人ほど成長できる環境です。
このように、金融業界は「働きながら学べる」場であり、知識を蓄えるほど市場価値の高い人材として活躍できますよ。
④成果が正当に評価され、実力次第でスピード出世も可能
金融業界は成果が正当に評価されやすく、実力次第でスピード出世も可能です。
特に、外資系・証券・投資銀行などの金融機関では実力主義の風土が色濃く残っているため、成果を出せば年齢や年次に関係なく高収入が得られるでしょう。
「やった分だけ返ってくる」やりがいを感じやすい環境のため、挑戦を楽しめる人や成長意欲の高い人にとっては、これ以上ないフィールドだと言えます。
金融業界に向いている人の特徴とは?

ここでは、金融業界に向いている人の特徴を7つに分けて紹介します。
金融業界は専門性が高く、責任の重い仕事も多い一方で、やりがいや成長機会も大きな業界です。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①数字やデータに強い人
金融業界は、数字やデータに強い人が向いています。日々の業務の中で、為替・金利・株価・企業の財務諸表などを読み解き、そこから判断を下すことが求められる場面が多くあるからです。
たとえば、法人営業であれば企業の決算書から経営状況を分析し、最適な融資提案を行う必要があります。
また、投資運用部門ではマーケットデータを常にチェックし、秒単位で判断を下すこともあるでしょう。
計算が得意な人だけでなく、「数字から意味を読み取るのが好き」「データを比較して考察するのが得意」といった人は、金融業界に適性があります。
②几帳面で正確性を重視する人
金融業界は、几帳面で正確性を重視する人が向いています。1円の差や1ケタのミスが、大きな損失や信用失墜につながる可能性があるからです。
たとえば、顧客の資産情報を扱う際や融資審査の書類をチェックする際には、細部まで確認を怠らず、ミスなく業務を遂行する必要があります。
そのため、規定やルールに忠実で、着実に物事を進められる「几帳面な人」は、信頼されやすく重宝されるでしょう。
③情報収集力が高い人
金融業界には、情報収集力が高い人が向いています。経済情勢・政策・国際情勢・業界ニュースなど、日々変化する情報を収集して整理し、ビジネスの判断材料として活用することが求められるからです。
そのため、「ニュースを見るのが習慣」「気になることはすぐに調べる」という情報感度の高い人は、業務の中でも強みを発揮できるでしょう。
特に、時事ニュースや経済動向に興味がある人には向いている業界です。
④コミュニケーション能力がある人
金融業界は、顧客や社内の人と密に連絡を取り合いながら進めていく仕事が多いため、コミュニケーション能力がある人が向いていますよ。
たとえば、保険営業では顧客の人生設計をヒアリングし、最適な商品を提案するための信頼関係が求められます。
法人営業では、経営者と事業課題を共有し、資金調達や金融商品の活用方法について提案することもあるでしょう。
相手のニーズを正しく引き出し、分かりやすく説明できる力があれば、大きな成果につながります。
⑤向上心と学習意欲がある人
金融業界は、向上心と学習意欲がある人が向いています。変化のスピードが速く、常に知識のアップデートが必要とされる業界だからです。
特に近年では、フィンテック・キャッシュレス・暗号資産といった新しい技術やサービスの登場により、学ぶべき内容も多岐にわたっています。
その分、証券外務員・FP・宅建など、資格の取得を会社が支援してくれる制度も多くあるため、学ぶ意欲があればどんどんスキルアップできる環境です。
「勉強するのが苦ではない」「新しいことに挑戦するのが好き」という人は、金融業界との相性が良いでしょう。
⑥自己管理能力が高い人
金融業界は、自己管理能力が高い人が向いています。時間管理・タスク管理が非常に重要で、期限厳守の書類提出やミスの許されない処理業務などを的確にこなす必要があるからです。
プレッシャーが大きい場面でも自分自身のコンディションを整え、冷静に業務に向き合う力が求められます。
そのため、スケジュールを管理して計画的に動ける人や、ストレスとの向き合い方を自分なりに持っている人は、長く活躍できるでしょう。
⑦リーダーシップや主体性がある人
金融業界は、リーダーシップや主体性がある人が向いています。
個人の実力や成果が正当に評価されやすい業界で、特に証券・投資・外資系金融などでは積極的に行動できる人ほど成果を出しやすく、キャリアアップも早い傾向にあります。
「言われたことだけをやる」のではなく、「自分で考えて動ける」「チームを引っ張るのが得意」といった主体性やリーダーシップがある人には、大きなやりがいと成長のチャンスが待っているでしょう。
金融業界の将来性について理解を深めよう
金融業界は今、デジタル化・グローバル化・価値観の多様化といった大きな波の中で、急速な変革を求められています。
確かに、低金利や業務の自動化、他業界からの参入など、将来を不安視する声も少なくありません。一方で、変化を受け入れ、新しい価値を生み出そうとする動きも活発化しています。
テクノロジーとの融合や海外展開、資産運用ニーズの拡大など、金融業界にはまだまだ大きな可能性が広がっているのです。
「自分の強みを活かして社会に貢献したい」そんな想いを持つ方は、ぜひこの業界でのキャリアを検討してみてはいかがでしょうか。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












