留年したら内定取り消し?就職活動の重要ポイントを解説
「留年が決まったら、せっかく得た内定は取り消されてしまうのだろうか……?」
学業や進級の事情で留年する可能性は、誰にでも起こり得るものです。しかし、就職活動においては「留年=内定取り消し」と不安に感じる方も少なくありません。
実際には企業ごとに対応が異なり、事前の報告や説明の仕方によって結果が変わることもあります。
そこで本記事では、留年と内定取り消しの関係や企業が重視するポイント、取るべき対応策について詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
留年した場合、内定はどうなる?

留年が決まったとき、多くの就活生が真っ先に心配するのは「内定が取り消されるのではないか」という点でしょう。
結論から言えば、留年=即内定取り消しにはなりません。企業によっては卒業年度の変更を受け入れ、内定をそのまま維持してくれる場合もあります。
ただし、就業開始時期や配属計画に影響が出るため、すべての企業が柔軟に対応できるわけではありません。
留年理由が健康上の問題や不可抗力であれば理解を得やすい一方、単位不足や自己管理不足の場合は評価が下がる可能性もあります。
重要なのは、早い段階で人事担当者に連絡し、正直に事情を説明することです。あいまいなまま放置すると、誠実さや信頼性に疑問を持たれ、結果として取り消しのリスクが高まります。
留年しても内定取消しにならないケース
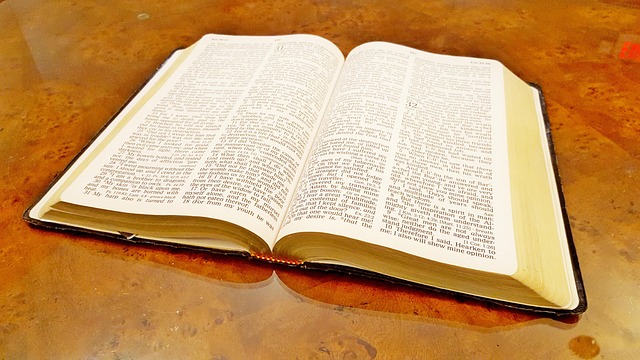
就活中や内定後に留年が決まると、多くの学生が「内定は取り消されるのでは」と不安になるでしょう。しかし、すべてのケースで取り消しになるわけではありません。
企業の採用方針や雇用条件によっては、留年しても内定が維持される場合があります。ここでは、留年しても内定取消しにならない代表的な3つのケースを紹介します。
- 卒業まで待ってもらえる場合
- 翌年の内定にしてもらえる場合
- 大卒が条件になっていない場合
①卒業まで待ってもらえる場合
企業によっては、留年が決まっても卒業まで雇用を待ってくれることがあります。これは採用時点で学生の能力や人柄を高く評価しており、多少入社時期が遅れても採用価値があると判断される場合です。
例えば、業務開始時期が固定されていない部署や、長期的な育成を重視する企業では柔軟に対応してもらえることが多いでしょう。
一方で、報告が遅れると信頼を損ね、対応してもらえなくなる恐れがあります。そのため、留年が確定した時点で早めに人事担当へ事実と理由を正直に伝えることが欠かせません。
率直なコミュニケーションが、結果として内定維持の可能性を高める行動となります。
②翌年の内定にしてもらえる場合
留年が1年程度の場合、企業によっては内定を翌年入社として持ち越す提案をしてくれることがあります。これは新たに採用をやり直すよりも、既に評価済みの人材を翌年迎え入れるほうが効率的と判断されるためです。
ただし、この対応は企業の採用計画や人員状況によって変わります。翌年入社に変更する場合、再度健康診断や面談が行われることもあるでしょう。
また、翌年までの時間をどう過ごすかも重要です。学業だけでなく資格取得やインターン参加など、成長につながる活動を見せることで信頼を保てます。
翌年入社が決まったからと安心せず、自己研鑽を続ける姿勢をもちましょう。
③大卒が条件になっていない場合
内定の条件が必ずしも「大学卒業」ではない企業も存在します。
例えば、専門性や技能を重視する職種や、高卒・専門卒・短大卒など幅広い学歴の社員を受け入れている企業です。この場合、留年しても採用条件に直接触れないため、内定取消しの可能性は低くなります。
しかし、留年によって就業開始が遅れる場合は業務体制に影響が出ることもあるため、スケジュール調整は必要です。
また、学歴条件がないからといって報告を怠ると、信頼関係が崩れ結果的に内定が取り消されることもあります。条件の有無だけで安心せず、誠実な対応を心がけてください。
留年による内定取消しを回避するための行動

留年が確定すると、内定が取り消される可能性は少なからずあります。ただし、事前に行動を起こせばそのリスクを減らせるでしょう。
ここでは、回避のために有効な3つの行動について説明します。
- 担当教授に相談する
- 資格取得で単位に変えられないか確認する
- 内定先の企業に相談する
①担当教授に相談する
留年の可能性が出てきたら、まず担当教授に早めに相談してください。
教授はカリキュラムや単位認定の柔軟な対応について知っていることが多く、補講や追加課題で単位取得の道が開ける場合もあります。
行動を遅らせると、教授や学部の裁量で対応できる期間を過ぎ、打つ手がなくなるかもしれません。逆に早期相談によって、ぎりぎりでも必要単位を満たし、留年を免れた例もあります。
内定は就活生にとって大きな安心材料です。まずは大学内部で問題を解決し、取り消しのリスクを減らすことが大切です。
②資格取得で単位に変えられないか確認する
資格試験の合格を単位に振り替えられる制度は、多くの大学で導入されています。特に語学検定やIT関連資格は対象になりやすく、すでに取得している資格でも申請すれば単位として認められることがあります。
この制度を使えば、不足している単位を補える可能性があります。ただし、制度の存在を知らずに申請期限を過ぎてしまう学生も少なくありません。
資格認定による単位補填は留年回避の有力な手段です。大学の教務課や学科事務に必ず確認し、期限内に手続きを済ませましょう。
制度を活用できれば、内定取消しの回避につながる可能性は高いでしょう。
③内定先の企業に相談する
留年が避けられない見込みになったら、内定先企業に正直に状況を伝えることも有効です。
企業によっては卒業時期の延長を受け入れてくれる場合があり、入社時期を翌年度に変更してくれることもあります。
黙って留年を迎えると、信頼を損ない、取り消しにつながるおそれがあります。事前に相談すれば、内定保留や条件付き入社などの対応を受けられる場合もあるでしょう。
全ての企業が柔軟に対応するわけではありませんが、話し合わなければ可能性は広がりません。誠実な情報共有は、信頼関係を保ちつつ進路の選択肢を増やす大事な行動です。
留年確定後、内定取消し回避を回避するための行動

留年が決まっても、適切に行動すれば内定取消しを防げる可能性は十分あります。焦って間違った対応を取るよりも、企業との信頼関係を守ることが大切でしょう。
ここでは、評価を下げずに卒業と入社を目指すための3つの行動を紹介します。
- 留年が決まったことを企業に報告する
- 追加レポートや追試を受ける
- 内定先に卒業見込みの状況を説明する
①留年が決まったことを企業に報告する
留年が確定したら、できるだけ早く内定先へ連絡してください。企業は入社や配属の計画を事前に立てており、卒業時期の変更は直接影響します。報告を後回しにすると「誠意がない」と思われかねません。
伝えるときは、留年の理由を事実に基づき簡潔に説明し、卒業への意欲や対応策を具体的に示すことが重要です。
例えば「不足単位を補うために必要科目を履修し、来年度卒業を確実にする」などの具体案があると安心感を与えられます。
留年そのものよりも、誠実な態度や迅速な対応が評価を左右します。行動のタイミングと伝え方が、内定維持の成否を決めるでしょう。
②追加レポートや追試を受ける
単位不足や成績不振が原因の場合、大学から追加レポートや追試の機会が与えられることがあります。これは単位を取る最後のチャンスになるため、必ず全力で取り組みましょう。
結果がすぐに出なくても、「与えられた機会を活用している姿勢」を企業へ報告すれば評価低下を防げます。企業は困難への対応力や粘り強さも見ています。
提出期限や条件を事前に確認し、計画的に進めることが重要です。このような取り組みは、内定維持だけでなく入社後の信頼にもつながります。
③内定先に卒業見込みの状況を説明する
卒業時期が変更になる場合は、現状と見込みを丁寧に説明してください。
企業は入社時期を正確に把握する必要があるため、「〇月に卒業見込み確定予定」「残り単位は◯単位で履修登録済み」など、数字や時期を明確に伝えることが信頼につながります。
あいまいな表現を避け、進捗や見通しを定期的に報告する姿勢が大切です。こうした情報共有は「計画性と責任感がある」という印象を与え、契約解除の判断を避ける後押しになるでしょう。
結果的に、卒業時期のズレを理由にした内定取消しを防ぐ有効な方法となります。
留年で内定取消しが確定した場合にすべきこと

留年により内定取消しが決まっても、そこからの行動次第で将来の可能性は大きく変わります。落ち込むだけでは状況は改善しないため、次の一歩を踏み出すことが大切です。
ここでは、学業の立て直しから再就活、資格取得まで、回復と成長につながる具体的な行動を紹介します。
- 勉強して単位を取得する
- もう一度就職活動に取り組む
- 就職に役立つ資格を取得する
①勉強して単位を取得する
留年が決まった場合、まず優先すべきは単位の取得です。卒業できなければ再び就職活動のチャンスを逃すことになるため、計画的に履修し学習時間を確保してください。
苦手科目は早めに対策し、教授や先輩に相談するなど効率的な勉強方法を取り入れるとよいでしょう。
また、この期間を「基礎を固める時間」と考えれば、専門知識や課題解決力の向上にもつながります。こうして得た力は、再び就活に挑む際の自信にもなります。
留年をマイナスだけで終わらせず、学び直しの機会として活用することが重要です。
②もう一度就職活動に取り組む
内定取消し後の再就活は精神的負担が大きいかもしれません。しかし、自分に合った企業を探し直す好機でもあります。
まずは前回の就活での成功点と改善点を整理し、応募企業の選定基準を明確にしましょう。
OB・OG訪問やインターン参加によって職場環境や仕事内容を具体的に理解できるはずです。
留年理由や学び直しの姿勢を正直かつ前向きに伝えれば、人事担当者からの評価も変わる可能性があります。焦らず準備を重ねることが、納得できる内定への近道です。
③就職に役立つ資格を取得する
留年期間を有効に使う方法として資格取得があります。業界で評価されやすい資格や汎用性の高い資格は、就職活動で大きな武器になるでしょう。
例えば、TOEICや簿記、ITパスポートなどは多くの企業で評価されます。
計画を立てて勉強を進めれば、就活本番までに実用的なスキルを習得できます。資格は努力の成果が形として残るため、面接での説得力も増します。
さらに、資格取得で培った知識や時間管理能力は社会人になってからも役立つでしょう。留年を待機期間にせず、将来のキャリアを強化する準備期間に変えることが大切です。
留年で内定取消しになった場合の選択肢

留年が原因で内定を取り消されたとき、多くの学生は将来への不安や焦りを感じるものです。ですが、視野を広げれば新しい進路はいくつも見つかります。
ここでは、就職留年や就職浪人、フリーランス、起業といった選択肢を解説し、次のチャンスにつなげるためのヒントをお伝えします。
- 就職留年をする
- 就職浪人になる
- フリーランスになる
- 起業する
①就職留年をする
就職留年とは、卒業をあえて延ばし、在学中に再び就活を行う方法です。最大の強みは、学生という立場を保ちながら応募できることにあります。
留年で内定を失っても、履歴書に就業空白を作らず、採用担当の印象を損ねにくいでしょう。
一方で、追加の学費や生活費がかかるほか、同級生との差を感じる場面も出てきます。それでも、大学のキャリアセンターやOB・OG訪問など学生限定の支援を活用できる点は大きな利点です。
経済的に可能であれば、安定した環境で再び就職活動を進められる現実的な選択肢といえます。
②就職浪人になる
就職浪人は、卒業後に次年度の就活へ再挑戦する方法です。アルバイトや資格取得など、自分の弱点を補う時間が確保できるのはメリットでしょう。
ただ、社会人経験はないものの既卒扱いになるため、新卒枠では不利になる場合があります。
一部の企業は既卒でも新卒と同じ枠で採用することもあります。ただし、空白期間の過ごし方は必ず説明を求められます。
目的を持って時間を使えば、就職浪人はキャリアの再構築につながる有効な方法となるでしょう。
③フリーランスになる
フリーランスは、スキルや専門知識を活かして独立して働く道です。クラウドソーシングやSNSを使えば、在宅で始められる案件も多くあります。
特にWeb制作、デザイン、ライティング、プログラミングなどは比較的参入しやすい分野でしょう。
ただし、安定収入を得るまで時間がかかり、自己管理も欠かせません。社会的信用やローン審査で不利になる可能性もあります。
それでも、若いうちに経験を積めば、将来の転職や起業において強力な武器となるスキルを身につけられるでしょう。
④起業する
留年による内定取消しをきっかけに、自ら事業を立ち上げる選択もあります。起業はリスクが高い一方で、やりたいことを形にできる大きなチャンスです。
大学の起業支援制度や助成金、インキュベーション施設を活用すれば、初期投資を抑えて挑戦できます。
必要なのは、資金調達やマーケティング、経営など幅広い知識です。失敗の可能性も考え、再就職できる道を残しておくことが大切でしょう。
覚悟と計画を持てば、起業は自分の可能性を大きく広げる道になります。
留年した人が内定を得るための心構え
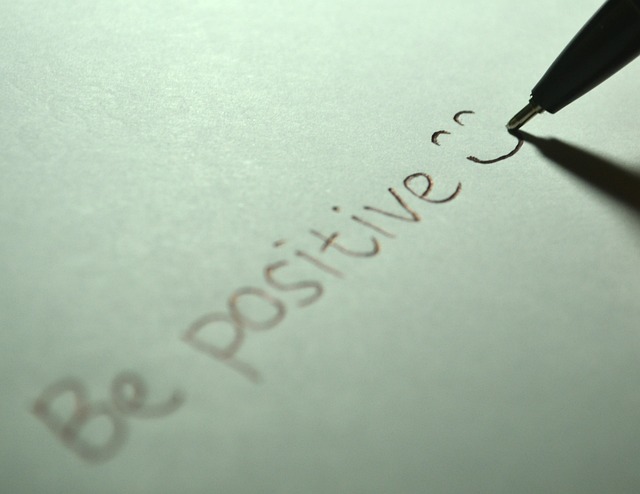
就活で留年経験がある場合、採用担当者にどう受け止められるか不安になる方は多いでしょう。実際には、理由や伝え方次第で評価は変わります。
ここでは、留年経験をプラスに転換するための具体的な考え方や、面接での立ち振る舞いについて解説します。
- 納得させられる留年の理由を考える
- 面接では嘘をつかない
- ネガティブな印象にならないよう気を付ける
- 留年の克服について具体的に伝える
①納得させられる留年の理由を考える
留年した事実は変えられませんが、その背景をどう説明するかで印象は大きく変わります。採用担当者が納得できる理由を準備することが大切です。
たとえば、ゼミや研究に集中した結果や、海外留学など成長につながる活動であれば、むしろ評価される場合があります。
一方で、単位不足などマイナス要因の場合でも、そこから何を学び、どう改善したかを明確にすれば成長意欲を示せます。
理由を正当化するのではなく、課題を自覚して行動した姿勢が重要です。理由が曖昧だと計画性がないと見られる恐れもあります。
過去の経験を振り返り、自分の言葉で説明できる準備をしておくことが、面接突破への第一歩です。
②面接では嘘をつかない
留年経験を隠すのは逆効果です。学歴や在籍期間は卒業証明や履歴書で明らかになるため、事実と異なる説明は信頼を失います。正直に話しつつ、その後の行動や成長を具体的に伝えるほうが好印象です。
たとえば、留年中に資格取得やインターン参加でスキルを磨いた経験は、主体性や粘り強さを示せます。企業は過去の失敗よりも、その後の改善努力を評価します。
嘘で一時的に印象を良くするより、誠実さと行動で信頼を得るほうが長期的に有利です。結果として、自分を正しく理解してくれる企業と出会える可能性も高まります。
③ネガティブな印象にならないよう気を付ける
留年は話し方によってマイナス評価になりやすいですが、伝え方を工夫すればプラスにできます。理由は短くまとめ、その後の努力や成果に話を移すのがポイントです。
弁明が長いと「言い訳が多い」と受け取られかねません。
「当時は計画が甘く単位を落としましたが、その反省を活かして時間管理能力を向上させました」と簡潔に述べ、改善事例を説明すると効果的です。
また、表情や声のトーンも大切で、自信を持って話すことで前向きな印象を与えられます。自分をどう評価しているかが、そのまま面接官にも伝わると覚えておきましょう。
④留年の克服について具体的に伝える
留年をどう乗り越えたかを具体的に語ることで、「成長できる人材」という印象を与えられます。克服の過程は数字や事実を交えて説明すると説得力が増します。
たとえば、「1年間で不足していた単位をすべて取得し、TOEICで200点アップしました」のように成果を明確に示すとよいでしょう。
克服ストーリーには、課題の発見→計画→実行→結果という流れを入れると理解しやすくなります。
さらに、その経験を社会人生活にどう活かすかまで述べれば、将来性の評価も高まりやすいです。留年はマイナスからの出発に感じるかもしれませんが、努力の証拠を示せばプラス評価に変えられます。
よくある質問

留年が決まったとき、多くの学生はインターンや入社時期、待遇への影響を心配します。
ここでは、よくある質問を整理し、誤解や不安を解消するための情報を紹介します。
- 留年してもインターンは参加できるか?
- 留年後の入社時期にはいつになるか?
- 留年した場合の給与や待遇への影響はあるか?
①留年してもインターンは参加できるか?
留年しても、多くの場合はインターンに参加できます。ただし、企業によっては対象学年や卒業年度を明確に指定しているため、事前の確認が欠かせません。
多くの企業は、卒業予定年度や学年で参加条件を設定しています。そのため、留年により募集条件から外れる場合があります。一方で、長期インターンや通年型インターンでは学年不問のものも多いのでオススメです。
参加可否は、企業の採用担当に直接確認しましょう。その際、留年理由や今後の学びの計画を簡潔に説明すると好印象です。
留年をマイナスではなく成長期間と捉え、行動を起こすことが就職活動の幅を広げるポイントになります。
②留年後の入社時期にはいつになるか?
留年すると、多くの場合は入社時期が1年後にずれます。ただし、業界や企業によっては柔軟な対応が可能なケースもあります。制度や条件を正しく把握することが欠かせません。
一般的に新卒採用は卒業時期と連動しており、留年すれば卒業予定が翌年度に延びるため、入社も1年後になります。
しかし、近年は採用方法が多様化し、中途採用枠や秋入社枠を活用して早期入社できるケースも見られます。
重要なのは、留年が決まったらすぐに内定先へ連絡することです。卒業時期の変更による手続きや入社時期の選択肢を確認しないまま進めると、条件や期限を逃す恐れがあります。
誠実かつ迅速な対応が、信頼関係を保ち入社スケジュールを調整する鍵となります。
③留年した場合の給与や待遇への影響はあるか?
留年によって入社時期が変わった場合、給与や待遇が変わるのかは多くの学生が気になるところでしょう。結論として、新卒枠で入社する限り、大きな変化はほとんどありません。
企業は新卒採用において、入社年度ごとに給与や福利厚生を設定しています。留年による待遇差は法律上も不適切であり、基本給や福利厚生は原則同じです。
ただし、入社年度が変わると給与テーブルや制度が更新され、わずかな差が生じることがあります。
また、同期や研修制度が変わるため、スタート時点の環境が異なる点には注意が必要です。待遇だけに目を向けるのではなく、入社後にどのように成長機会を確保するかを意識してください。
留年で得た経験やスキルを明確にし、それを入社後の活躍に結びつける姿勢が将来の評価や昇進にも影響します。
留年の危険性が出たタイミングで企業にすぐ相談しよう!

留年が内定取り消しに直結するとは限りませんが、状況によっては大きな影響を受ける可能性があります。重要なのは、早期に担当教授や内定先企業へ相談し、卒業見込みや代替案を明確に示すことです。
卒業まで待ってもらえる場合や翌年入社に切り替えられる場合もありますが、対応が遅れると選択肢は狭まります。
万が一、内定取消しが確定した場合でも、再就職活動や資格取得、フリーランス・起業といった道があります。
留年理由を前向きに説明し、面接では正直かつ具体的に克服策を伝えることが、次のチャンスを掴む鍵となります。
つまり、留年はキャリアの終わりではなく、計画的な対応と行動次第で新たな可能性を開くきっかけになり得るのです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












