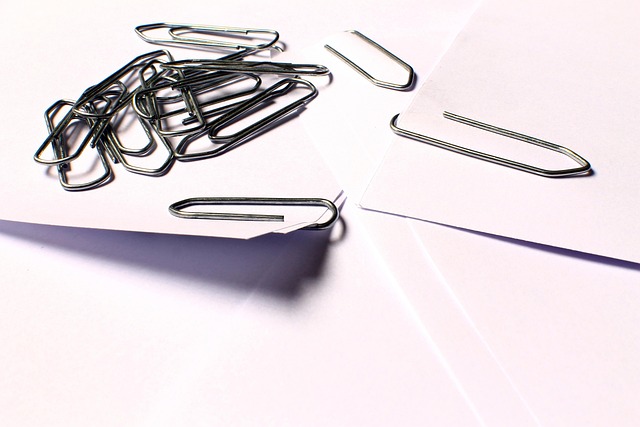内定保留できる期間の目安と企業への伝え方|注意点も紹介
「内定は嬉しいけれど、すぐに決めてしまっていいのか不安…」
そんな時に選択肢となるのが「内定保留」です。とはいえ、内定保留期間には目安があり、対応を誤ると内定取り消しなどのリスクもあります。
本記事では、一般的な内定保留期間の目安や注意点、企業への上手な伝え方を例文付きで解説します。納得のいく就職先を選ぶための参考にしてみてください。
内定保留への理解を深めて選択しよう

就職活動では、複数の企業から内定をもらうこともあります。
そんなとき、「どこに入社するべきか迷っている」「第一志望の結果を待ちたい」といった理由から、内定の返事を保留したいと考える学生も少なくありません。
内定を保留することで、より納得のいく選択ができるメリットがあります。その一方で、企業側も採用スケジュールや他の候補者との調整を行っているため、常識的な期間内での対応が求められるでしょう。
自分の将来に関わる大切な判断だからこそ、保留の意図や理由は正直かつ丁寧に伝えることが大切です。企業との信頼関係を損なわないように配慮しながら、前向きな選択を進めてください。
内定保留は可能?

就活を進める中で複数の企業から内定をもらう場合を考慮し、「内定保留をしたいけれど、それは可能なのかな…?」と不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、内定保留は、基本的に可能です。企業は学生の自由な職業選択を尊重する立場にあり、法律上も内定承諾を強制することはできません。
そのため、「もう少し検討したい」「他社の選考結果を待ちたい」といった理由で保留を申し出ることに問題はないでしょう。
ただし、企業側にも採用スケジュールや人員計画があります。企業からの信頼を損ねないためにも、保留を申し出る際には、いつまでに返答するかを明確に伝えることが大切です。
また、誠意のない対応と受け取られれば、内定取り消しなどのトラブルにつながることもあります。誠実な態度で理由と期限を明示することが、円滑な対応につながるでしょう。
内定保留期間の目安
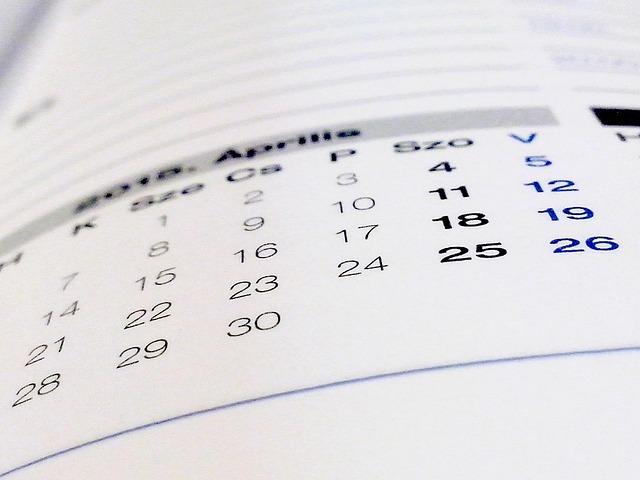
内定を保留するとき、どのくらいの期間なら失礼にならないのか不安に感じる人は多いでしょう。企業の事情も考慮しつつ、自分にとって納得できる選択をするには、適切な対応が必要です。
ここでは、一般的な目安と、時期や学年によって変わるケースについて解説します。
- 一般的には1週間〜10日が目安
- 時期や学年により保留期間は変わる
① 一般的には1週間〜10日が目安
内定の返事を保留する場合、一般的には7日から10日ほどが妥当とされています。
この期間は、学生が冷静に考えて判断できるだけでなく、企業側の採用スケジュールにも大きな影響を与えにくいとされるからです。ただし、保留したいときは黙って放置せず、必ず企業に連絡してください。
何も伝えずに返答を遅らせると、印象が悪くなり、場合によっては内定を取り消されることもあります。企業によっては、あらかじめ返答期限を提示してくるケースも。
その際は、その日までに決めるのが基本です。ただ、やむを得ない事情があるときは、早めに相談することで、延長に応じてもらえることもあるでしょう。
大切なのは、相手への配慮を忘れず、誠実な姿勢でやり取りすることです。信頼関係を築きながら、自分にとって後悔のない選択を進めてください。
② 時期や学年により保留期間は変わる
保留の許容期間は、就活の時期や自分の学年によって変わることがあります。たとえば、3年生の早期選考であれば、企業も長めの保留を理解してくれる場合があるでしょう。
一方で、4年生の秋以降など、採用活動の終盤に差しかかる時期は、企業も返答を急いで求めてくる傾向があります。また、企業の規模によっても対応は異なるのです。
大手企業は比較的余裕のあるスケジュールを組んでおり、保留にも柔軟に応じてくれることが多いでしょう。
反対に、中小企業では人員確保が急務となるため、早期の返答を強く求められる場合があるかもしれません。このように、状況ごとに適した対応を見極めることが重要です。
自己都合だけで判断せず、企業側の事情にも目を向けた上で、丁寧な対応を心がけてください。
内定保留によるリスク

内定を一度保留したいと考える就活生は少なくありません。ただ、その際には思わぬリスクが潜んでいることもあります。伝え方を誤ると、企業側に悪印象を与えてしまうおそれもあるため注意が必要です。
ここでは、内定保留によって生じやすい代表的なリスクを5つ紹介します。
- 入社意欲を疑われることがある
- 対応が不誠実だと悪印象を与えることがある
- 内定を取り消されるリスクがある
- 入社後の評価に影響が出ることもある
- 希望する就職先から不利な扱いを受けることがある
① 入社意欲を疑われることがある
内定を保留することで、企業側から「本当にうちで働きたいのか?」と疑問を持たれることがあります。
企業は志望度の高い人材を確実に採用したいため、理由を伝えず返事を先延ばしにすると熱意がないと受け取られやすいです。その結果、これまでの評価が下がってしまう可能性もあるでしょう。
きちんと事情を説明し、返答の期限を明示すれば誠実さは伝わります。伝え方ひとつで、相手の受け取り方は大きく変わるものです。
② 対応が不誠実だと悪印象を与えることがある
連絡が遅れたり、態度がはっきりしなかったりすると、誠実さに欠けると判断されることがあります。特にビジネスマナーを重視する企業では、その印象が入社後にも影響するかもしれません。
保留を申し出る際は、理由と期限を明確に伝えるよう心がけましょう。正直で丁寧な対応は、信頼関係を築く第一歩です。就活の時点から社会人としての振る舞いを意識することが求められます。
③ 内定を取り消されるリスクがある
返答をあまりにも遅らせると、最悪の場合、内定を取り消される可能性もあります。法的にすぐの取り消しは難しいとはいえ、企業が採用計画を見直すことは十分あり得るでしょう。
企業にもスケジュールや人員の都合があります。だからこそ、必要以上に保留を引き延ばすのは避けたほうが無難です。スムーズに対応する姿勢が、結果的に自分を守ることにつながります。
④ 入社後の評価に影響が出ることもある
内定保留の対応次第では、入社後の印象に影響を与えることがあります。たとえば保留の連絡が雑だったり、誠意が感じられなかったりすると、「入社後も自己中心的では?」と懸念を持たれるかもしれません。
もちろん評価は業務で決まるものですが、人間関係のスタート時点での印象は大切です。丁寧な対応を心がけることで、良好な関係を築く土台になるでしょう。
⑤ 希望する就職先から不利な扱いを受けることがある
他社の選考結果を待つために本命以外の内定を保留する場合、その伝え方によっては、企業から不信感を持たれるおそれがあります。
特に中小企業では個々の対応が印象に残りやすく、保留への対応が今後の扱いに影響するケースもあるでしょう。内定を維持できたとしても、入社後に冷遇される可能性はゼロではありません。
将来その企業で働くかもしれないという意識を持って、真摯な姿勢で臨んでください。
内定保留をしたい理由

就職活動では、すぐに内定の返事を出せない理由があることも珍しくありません。迷っているというだけでなく、学生それぞれに大切な判断材料があります。
ここでは、代表的な保留理由とその背景について整理しました。
- 第一志望の選考結果を待ちたい
- 他社の内定と比較して決めたい
- 内定先の条件に不安を感じている
- 家族や周囲に相談してから決めたい
- 進学・留学・他の進路と迷っている
① 第一志望の選考結果を待ちたい
もっとも多い理由のひとつが、第一志望の企業の結果待ちです。すでに他社から内定をもらっていても、本命企業の選考が終わっていなければ、すぐに決断するのは難しいでしょう。
そのため、いったん内定を保留するのは自然な判断です。ただし、企業にもスケジュールがあります。待ってもらいたいときは、その理由を簡潔かつ丁寧に伝えてください。
中には「〇月〇日までに返事をください」と明確に伝えてくる企業もあります。その期限内に判断することが基本です。無理な引き延ばしは、相手の信頼を損なう可能性があります。
納得のいく選択をするためにも、誠意ある対応を意識しましょう。しっかりと理由を伝えれば、企業も理解を示してくれるはずです。
② 他社の内定と比較して決めたい
複数の企業から内定をもらうと、それぞれの条件を比較して決めたいと考えるのは当然です。仕事内容、勤務地、制度、雰囲気など、重視する点は人によって異なります。
焦って決めてしまえば、「やっぱり違ったかも」と後悔する可能性も。納得のいく判断をするには、比較に時間をかけることも必要でしょう。
ただし、保留の理由が「悩んでいるから」だけでは、相手に迷いが伝わり、マイナス印象になることがあります。「より良い選択をするために比較している」という前向きな伝え方が望ましいです。
冷静に見極める姿勢と、相手への敬意を持った連絡を両立させることが、最終的な満足度にもつながるでしょう。
③ 内定先の条件に不安を感じている
内定を受けても、給与や勤務地、勤務時間などの条件に疑問や不安を感じることがあります。想定していた内容と異なる点があれば、即答するのはためらわれるでしょう。
そのまま入社を決めてしまうと、後悔やミスマッチの原因になりかねません。気になる点があれば、一度立ち止まって見直す時間をとってください。
保留の連絡を入れる際には、「不安がある」ではなく、「〇〇の点について確認したい」と具体的に伝えると、相手にも真剣さが伝わります。
納得して選ぶためにも、自分の気持ちに正直になりながら、丁寧に確認を進めていくことが大切です。
④ 家族や周囲に相談してから決めたい
就職は自分だけでなく、家族にも影響を与える選択です。特に遠方の勤務地や初めての一人暮らしなど、家族の理解が必要なケースもあるでしょう。
そうした場合、家族と相談してから最終判断をしたいという理由で保留するのはごく自然なことです。ただし、その気持ちがしっかり伝わらなければ、「ただ迷っている」と誤解されるかもしれません。
「家族と話すために〇日まで時間をください」と伝えるようにしましょう。具体的な日付を示すことで、相手にも安心感を与えられます。
丁寧な対応を意識すれば、企業との信頼関係を保ちながら判断できるはずです。
⑤ 進学・留学・他の進路と迷っている
大学院への進学や留学など、就職以外の道と迷っている場合も、すぐに内定の返事を出せない理由になります。将来の方向性をしっかり考えることは、とても大切です。
このような選択には時間がかかるため、焦って決めるべきではありません。ただし、企業側にまったく伝えずに待たせるのは避けたほうがよいでしょう。
「進学も視野に入れており、もう少し検討する時間が必要です」といったように、現状を率直に伝えることが重要です。
自分の人生に真剣に向き合っていることが伝われば、企業もその姿勢を理解してくれる可能性が高いでしょう。誠実なコミュニケーションを忘れず、納得のいく決断をしてください。
内定保留のメリット

就職活動では、内定をもらったあとにすぐ決断を求められることも多く、迷ってしまう学生も少なくありません。そんなときに選択肢となるのが「内定保留」です。
ここでは、内定を保留することで得られる主なメリットを5つ紹介します。
- 納得したうえで就活を終えられる
- 第一志望の企業の結果を待てる
- 複数企業を比較検討できる
- 周囲と相談する時間を確保できる
- 内定をすぐに承諾しなくて済む安心感がある
① 納得したうえで就活を終えられる
内定保留のもっとも大きな利点は、納得感を持って就活を終えられる点にあります。焦って承諾してしまうと、後から「やっぱり他の企業を選べばよかった」と後悔する原因になりかねません。
保留の時間を活用すれば、自分の気持ちを落ち着いて整理したうえで判断できるため、将来への不安も軽減されます。
また、納得して選んだ企業であれば、入社後のモチベーションにもつながりやすく、前向きなスタートが切れるでしょう。
自分の決断に自信が持てることで、環境への適応や仕事への集中力も高まり、長期的に見ても良い影響が期待できます。
「とりあえず」で決めてしまわないように、保留という選択肢を使って冷静に自分の意思と向き合う時間を取ることは、非常に価値がある行動です。
② 第一志望の企業の結果を待てる
すでに内定をもらっている企業があっても、第一志望の選考がまだ終わっていないというケースは珍しくありません。
そんなときに内定保留を使えば、他社の結果を待ちながら判断できるというのが大きなメリットです。特に第一志望は志望度が高く、準備に時間をかけてきた分だけ思い入れも強くなりやすいもの。
その結果が出る前に他社の内定を承諾してしまうと、「本当にこれで良かったのか」と後悔する可能性があります。
保留によって待機の余地をつくることで、もし第一志望に通らなかったとしても、選択の理由に納得が持てるようになるのです。比較検討のうえで出した結論であれば、前向きに進めるでしょう。
選考スケジュールが重なりやすい就活だからこそ、保留という手段で時間を調整することが有効です。
③ 複数企業を比較検討できる
複数の企業から内定をもらった場合、すぐにどれか1社に決めるのは難しいと感じる学生が多いでしょう。どの企業にも魅力や特色があるからこそ、慎重な比較検討が必要になります。
内定保留を活用すれば、焦らずに情報を整理しながら考える時間が確保できるでしょう。たとえば、仕事内容や職場環境、福利厚生、評価制度、社員の雰囲気など、比較したいポイントはさまざまです。
それぞれの情報を丁寧に見比べることで、自分の価値観により合う企業を選ぶことができます。また、短期間で意思決定を迫られる場面では見落としがちな点にも目を向ける余裕が生まれるでしょう。
入社後のギャップや後悔を減らすためにも、比較検討の時間は非常に重要です。自分にとってベストな選択をするには、落ち着いて考えられる時間の確保が鍵になります。
④ 周囲と相談する時間を確保できる
就職は人生に大きく関わる決断だからこそ、一人で抱え込まずに誰かと相談することがとても大切です。
とはいえ、返答期限が短いと、家族や大学の先生、キャリアセンターなどに相談する時間さえ確保できないこともあります。
内定保留を申し出れば、その分だけ気持ちと時間に余裕ができ、第三者の意見をじっくり聞くことができるでしょう。
自分では気づかなかった視点や、長期的な将来を見据えた助言を得られるのも、大きなメリットです。
家族や先輩など、信頼できる人たちの意見をもとに冷静に考え直すことで、自信を持った判断がしやすくなります。特に大きな環境の変化が伴う就職において、周囲の理解とサポートは欠かせません。
⑤ 内定をすぐに承諾しなくて済む安心感がある
「早く返答してください」と急かされる状況は、精神的に大きなプレッシャーを感じやすいものです。そうした中で判断を迫られると、本来の意思と異なる選択をしてしまう可能性もあります。
保留を申し出ることで、一時的にそのプレッシャーから解放され、冷静に考える時間が持てるのは大きな安心材料です。
期限が明確になることでスケジュールも立てやすくなり、選考中の他社とのバランスも取りやすくなります。
また、安心感があることで、感情的な迷いに流されず、論理的かつ客観的に企業選びを進めることができるでしょう。緊張からくる焦りを和らげることは、納得のいく決断のためにとても重要です。
「今すぐ決めなければならない」という状況から一歩距離を取ることで、自分らしい選択ができる余地が広がります。
内定保留のデメリット

内定を保留することには一定のメリットがありますが、その一方で注意すべきデメリットも存在します。
何も知らずに行動すると、後悔や不利益を招くおそれがあるため、あらかじめリスクを理解しておくことが大切です。ここでは、内定保留に伴う代表的な5つのデメリットを紹介します。
- 内定取り消しのリスクがある
- 企業担当者に悪い印象を与える可能性がある
- オワハラなどの圧力を受ける場合がある
- 内定承諾期限に追われるストレスがある
- 他社の選考にも影響するリスクがある
① 内定取り消しのリスクがある
内定を保留している間に、企業から内定を取り消される可能性があります。
企業も採用スケジュールに沿って動いており、返答が遅れると「この学生は本当に入社する気があるのか」と不安を抱かせてしまうかもしれません。
法律上、企業が内定を取り消すには正当な理由が必要ですが、実際には「期日を過ぎても返事がない」「連絡が不十分」といった理由で取り消されるケースもあります。
こうした事態は、学生側に責任があると判断されると争いにくくなるのです。このリスクを避けるには、「○日までに返答します」と具体的な期限を伝えたうえで、誠意ある対応を心がけてください。
連絡を後回しにするほど、信頼は損なわれやすくなります。大切なのは、企業に配慮したやり取りを意識することです。
② 企業担当者に悪い印象を与える可能性がある
内定を保留すると、企業側に「志望度が低いのではないか」「対応が不誠実ではないか」といった印象を与えてしまうことがあります。
特に、理由を説明せずに返事を引き延ばすと、マイナス評価につながりかねません。企業は学生の対応も評価材料にしています。
保留する場合は、「他社と比較している」「家族と相談中」といった理由を丁寧に説明することで、不信感を与えにくくなるのです。
また、返答を待っている間に他の内定候補者が承諾した場合、企業側がそちらを優先してしまうこともあり得ます。その結果、自分の内定が取り消されることも考えられるでしょう。
企業との信頼関係を保つためにも、連絡のタイミングや内容には十分注意してください。
③ オワハラなどの圧力を受ける場合がある
内定を保留しようとした際に、「今すぐ決めてください」「他社の選考は辞退してください」など、企業から強い圧力をかけられるケースがあります。
これは「オワハラ(就活終われハラスメント)」と呼ばれ、問題視されているのです。学生側にきちんとした理由があっても、強引な対応をされると冷静に判断しにくくなるでしょう。
精神的な負担も大きく、焦って誤った選択をしてしまうかもしれません。こうした状況に直面したら、「キャリアを真剣に考えているので、少し時間をください」と落ち着いて伝えてください。
それでも解決しない場合は、大学のキャリアセンターなど第三者に相談することも検討しましょう。大事なのは、外部のサポートも活用しながら、自分にとって納得のいく選択ができるようにすることです。
④ 内定承諾期限に追われるストレスがある
保留中は、企業から提示された返答期限が常に気になります。複数の内定を持っている場合、各社の期限が重なることもあり、落ち着いて検討する余裕がなくなることもあるでしょう。
プレッシャーにより焦って決断し、「もっと考えておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。自分に合った進路を見つけるには、ある程度の時間が必要です。
ストレスを減らすためには、保留を申し出る際に「返答期限を延ばすことは可能ですか」と事前に相談してみてください。誠意ある姿勢であれば、配慮してもらえることもあるでしょう。
無理に一人で抱え込まず、周囲のサポートも活用して冷静に判断することが重要です。
⑤ 他社の選考にも影響するリスクがある
内定を保留している間に、他社の選考とスケジュールが重なることがあります。たとえば、保留中の企業との連絡や確認に時間を取られ、本命企業の選考準備が十分にできなくなることもあるでしょう。
また、保留中のやり取りに気を取られるあまり、他社の面接や提出書類の準備に手が回らなくなるケースも考えられます。結果として、志望度の高い企業で実力を出し切れないというリスクも生じるでしょう。
このような事態を防ぐためには、スケジュール管理を徹底し、優先順位を明確にしておくことが大切です。特に就活後半では、1つの判断ミスが全体に影響することもあります。
保留中でも気を抜かず、就活全体のバランスを意識して行動してください。
内定保留を伝える際のポイント
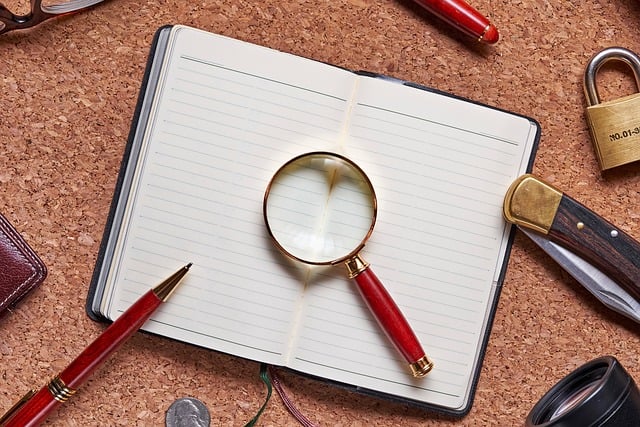
内定を保留したいと考えたとき、最も大切なのは「どのように伝えるか」です。誠実な対応を心がければ、企業に不快感を与えることなく、信頼関係を保ちながら調整できるでしょう。
ここでは、内定保留を企業に伝える際に押さえておきたい6つのポイントを紹介します。
- 企業にはできるだけ早めに連絡する
- 内定を保留する理由は正直かつ簡潔に伝える
- 入社意欲があることを必ず添える
- 保留期間は自分から明確に提示する
- 電話とメールを併用して丁寧に対応する
- 感謝と謝罪の気持ちを忘れずに伝える
① 企業にはできるだけ早めに連絡する
内定を保留したいと思ったら、できるだけ早めに企業へ連絡することが基本です。企業にも選考や配属、他の候補者との調整といったスケジュールがあるため、返事が遅れると担当者を困らせてしまいます。
連絡が遅くなればなるほど、「本気で検討していないのではないか」「誠意が感じられない」といった不信感を抱かれるリスクも高まるでしょう。
たとえ判断に迷っていたり、結論が出ていなかったりしても、その時点での状況を率直に伝えることで、企業側も誠実な対応だと受け取ってくれる可能性が高まります。
早めに動くことが、結果的に信頼を得る近道になるのです。「迷っているから何も言わない」のではなく、「迷っているからこそ丁寧に伝える」姿勢が、社会人としての第一歩につながります。
② 内定を保留する理由は正直かつ簡潔に伝える
内定を保留したい理由は、なるべく正直に、そして簡潔に伝えることが大切です。「他社の結果を待っている」「家族と相談したい」など、素直な気持ちを端的に述べることで、企業側も納得しやすくなります。
わかりやすい理由であれば、相手も冷静に受け止めてくれるでしょう。
反対に、あいまいな表現や余計な言い訳を重ねてしまうと、「本音を隠しているのでは?」といった疑念を持たれてしまう可能性があります。
誤解を避けるためにも、「正直さ」と「簡潔さ」のバランスが重要です。
ただし、あくまでも相手に対する配慮は忘れず、柔らかい言い回しや前向きな姿勢を添えると、より好印象を与えることができるでしょう。信頼される伝え方を意識してください。
③ 入社意欲があることを必ず添える
たとえ他社と比較している段階であっても、「御社に対しても強い関心があります」や「魅力を感じているため、慎重に検討したいと思っています」など、
入社への意欲を示す一言は必ず添えるようにしましょう。このひとことがあるかないかで、企業側の受け取り方は大きく変わります。
ただ「保留させてください」とだけ伝えると、「うちには興味がないのかもしれない」と思われてしまう可能性があります。
そうした誤解を防ぐには、前向きに検討していること、内定をいただけたことを嬉しく思っていることなど、自分の気持ちをしっかり伝えることが欠かせません。
企業側も、誠実に向き合ってくれる学生に対しては柔軟な対応をしてくれる場合が多いため、入社意欲の表明は、結果的に自分を守る手段にもなります。
④ 保留期間は自分から明確に提示する
内定の返事をいつまでにするか、期限を自分からはっきり伝えることも重要です。
たとえば「〇月〇日までにご連絡いたします」といった具体的な日付を提示すれば、企業も安心してスケジュールを組むことができます。
期限があいまいだと、「いつまで待てばいいのか分からない」と不安を与えてしまい、信頼関係が揺らぐ原因になるのです。
また、自分で返答期限を決めて伝えることで、主体的に動いているという印象も与えることができるでしょう。判断に必要な期間を見極めて、そのうえで無理のないスケジュールを提示してください。
仮に状況が変わった場合でも、その都度報告すれば問題ありません。大切なのは、途中で音信不通にしないことです。
⑤ 電話とメールを併用して丁寧に対応する
内定保留を申し出る際は、電話とメールの両方を使って連絡するのが望ましいです。
まずは電話で直接伝えることで誠意を示し、その後にメールで記録を残しておけば、万が一の行き違いも防ぎやすくなります。電話だけだと記録に残らず、メールだけでは一方通行になりがちです。
双方の手段を併用することで、コミュニケーションの精度が上がり、企業にも丁寧な印象を与えられるでしょう。メールでは、日時や担当者名、内容を明記しておくと安心です。
また、伝えた内容に加え、感謝やお詫びの気持ちも忘れずに記載してください。こうした細やかな配慮が、社会人としての評価につながる場合もあります。
⑥ 感謝と謝罪の気持ちを忘れずに伝える
内定を保留することは、企業にとっては想定外の対応が必要になる場合もあり、少なからず負担をかけることになります。
そのため、内定を出してくれたことへの感謝と、返答を保留させてもらうことへの謝罪は、きちんと言葉にして伝えるようにしましょう。
同じ内容を伝えるにしても、「ありがとうございます」と「申し訳ありません」のひとことが添えられているだけで、相手の印象は大きく変わります。
形式的な言い回しではなく、自分の言葉で丁寧に表現することを意識してください。感謝と謝罪をバランスよく伝えることで、真剣に就職活動に向き合っている姿勢が相手に伝わりやすくなります。
信頼関係を築くうえで、こうした心遣いは決して小さなものではありません。
内定保留を伝える際の例文

内定を保留したいと考えていても、「どう伝えればいいかわからない」と悩む人は多いでしょう。ここでは、さまざまな状況に応じた内定保留の伝え方を、具体的な例文とともに紹介します。
電話やメールでの伝え方、理由ごとの表現方法まで網羅しているので、安心して参考にしてください。
電話で内定保留を伝える例文
ここでは、内定を保留したい場合に企業へ電話で伝える際の例文をご紹介します。口頭でのやり取りに不安を感じる方も多いですが、ポイントを押さえて丁寧に話せば、誠実さはしっかり伝わるでしょう。
| 「お忙しいところ恐れ入ります。○○大学の○○と申します。○月○日に内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 大変ありがたいお話であり、前向きに検討させていただいておりますが、現在、他社の最終選考結果を待っている状況でして、少しだけお時間をいただけますでしょうか。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、○月○日までには必ずご返答いたしますので、何卒ご理解いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」 |
電話では、感謝・理由・期限の3点を簡潔に伝えることが重要です。緊張しても、あらかじめ話す内容を整理しておけば落ち着いて伝えることができます。
メールで内定保留を伝える例文
ここでは、企業からの内定に対して、メールで保留の意思を伝える際の例文をご紹介します。メールは記録が残る分、丁寧で失礼のない表現が求められます。
特に学生らしい素直さと誠実さを意識することが大切です。
| 件名:内定のご連絡に関するお礼とご相談(○○大学 ○○) 株式会社〇〇 人事部 ○○様 お世話になっております。○○大学○○学部の○○と申します。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。 貴社の業務内容や社風に大変魅力を感じており、前向きに検討させていただいております。 誠に恐縮ですが、現在他社の選考結果を待っている状況にあり、慎重に判断したく思っております。 つきましては、〇月〇日までお時間をいただけますでしょうか。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
メールでは、件名・宛名・署名まで丁寧に記載しましょう。結論を先に伝えたうえで、理由と期限を明記するのが基本です。
第一志望の選考結果を待ちたい場合の例文
ここでは、すでに内定をもらった企業に対して、第一志望の選考結果を待ちたい旨を丁寧に伝える例文をご紹介します。
多くの就活生が経験する悩みだからこそ、相手への敬意と誠実さが伝わる表現が重要です。
| お世話になっております。○○大学○○学部の○○と申します。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。貴社の事業内容や理念には深く共感しており、選考を通じてより一層関心を高めました。 大変心苦しいお願いではございますが、現在、第一志望として志望している企業の最終選考結果を待っている状況です。 貴社に対する入社意欲は変わらず高く、真剣に検討しておりますが、慎重に判断したく、少しお時間をいただけませんでしょうか。 ご迷惑をおかけし恐縮ではございますが、〇月〇日までに必ずご返答いたしますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 |
「第一志望を待っている」という内容でも、企業への敬意と入社意欲をしっかり伝えることが大切です。言い回しは丁寧に整えましょう。
家族と相談したい場合の例文
ここでは、内定の返答を保留したい理由として「家族との相談」を挙げる場合の例文をご紹介します。実家暮らしや地元就職を考えている学生にとって、家族の理解を得ることは重要な要素のひとつです。
| お世話になっております。○○大学○○学部の○○と申します。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。貴社の選考を通じて社風や業務内容に魅力を感じ、入社を前向きに検討しております。 つきましては、今後の人生にかかわる重要な決断となりますので、家族とも相談のうえで最終的な判断をしたく思っております。 大変恐縮ではございますが、〇月〇日までお時間をいただけますと幸いです。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 |
家族との相談を理由にする際は、「前向きに検討している」という意志を明確に伝えるのがポイントです。柔らかい言い回しで丁寧に伝えましょう。
進学や他の進路と迷っている場合の例文
ここでは、内定を受けたものの、進学や留学などの他の進路と迷っている状況で保留を伝える例文をご紹介します。
就活と並行して別の進路も検討していた学生にとって、進路決定の時間を確保することは重要です。
| お世話になっております。○○大学○○学部の○○と申します。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。貴社の事業内容や理念に大変魅力を感じており、前向きに検討させていただいております。 現在、大学院への進学も含め、将来の進路について家族とも相談しながら慎重に考えているところです。大変恐縮ではございますが、〇月〇日までご返答の猶予をいただけますでしょうか。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 |
他の進路と迷っている場合は、迷いを正直に伝えつつも入社への関心をしっかり示すことが大切です。期限の明示も忘れずにしましょう。
内定保留のトラブルに対する対処法

内定を保留する際は、意図せずトラブルが起きてしまうこともあります。企業との連絡のすれ違いや一方的な判断、期日を過ぎてしまうなど、避けたい場面は少なくありません。
ここでは、代表的な6つのケースとその対処法を紹介します。
- 企業に保留を断られた
- オワハラを受けた
- 内定取り消しを受けた
- 連絡が遅れてトラブルになった
- 伝え方の誤解で辞退と受け取られた
- 承諾期限を過ぎて内定が失効した
① 企業に保留を断られた
内定を保留したいと伝えたところ、企業から断られてしまうことがあります。これは企業側の事情によるもので、あなたに非があるわけではありません。ただ、戸惑ってしまうのも無理はないでしょう。
そのようなときは、まず理由を丁寧に尋ねたうえで、自分の状況や考えを具体的に説明してみてください。
「迷っている」だけでは伝わりづらいため、「〇〇の点を比較して検討中です」といった明確な言葉を選びましょう。もし保留が認められない場合は、優先順位を整理して早めに判断する必要があります。
感情的にならず、相手の立場にも配慮したうえで冷静に対応することが大切です。
② オワハラを受けた
「今すぐ承諾してください」「他社の選考はやめてください」など、強い圧力を受けることがあります。いわゆるオワハラと呼ばれるもので、精神的な負担になりやすい問題です。
このような場面では、焦って答えを出さないように注意しましょう。「将来を真剣に考えているため、時間をいただきたい」と落ち着いて伝えてください。
それでも圧力が続く場合は、大学のキャリアセンターなど信頼できる第三者に相談するのが有効です。一人で抱え込まず、客観的な視点を借りながら対処することで、冷静に選択できるようになります。
企業の対応から社風を見極める材料にもなるでしょう。
③ 内定取り消しを受けた
内定を保留していたところ、突然取り消されるケースもあります。企業が一方的に内定を取り消すには、法的に正当な理由が必要です。
ただし、連絡の遅れや印象の悪化が原因で、形式的に取り消されることもあり得ます。これを防ぐには、返答期限を自分から明確に伝え、途中経過もこまめに連絡することが基本です。
もし納得できない取り消しが起きた場合は、メールなどのやり取りを保存しておき、大学のキャリアセンターや労働相談機関に相談してください。冷静な対応と証拠の保全が、解決への第一歩です。
④ 連絡が遅れてトラブルになった
忙しさのあまり企業への返答が遅れ、「辞退したものとみなされました」と言われてしまうことがあります。こうした誤解は、避けられるトラブルのひとつです。
解決策はシンプルで、こまめに連絡を入れること。「検討中のため、〇日まで時間をください」と一言伝えるだけでも、企業は安心します。
返事をギリギリまで待たせるのではなく、進捗を共有する姿勢が信頼につながるのです。連絡を後回しにするのは、相手への配慮に欠ける行為と受け取られやすいです。
誠意を持って対応するよう意識してください。
⑤ 伝え方の誤解で辞退と受け取られた
「少し考えさせてください」と言ったつもりが、企業側には辞退と受け取られてしまうことがあります。このようなすれ違いは、意図せず起きてしまう厄介なトラブルです。
防ぐには、「保留を希望している」「〇日までに返答する予定です」とはっきり伝えることがポイント。電話やメールでは伝わり方に差が出ることもあるため、内容をよく見直してから送信してください。
可能であれば、第三者に確認してもらうと安心です。伝え方一つで誤解は防げます。自分の意図が正しく伝わるよう、丁寧な表現を心がけましょう。
⑥ 承諾期限を過ぎて内定が失効した
返事を出すのを忘れていて、承諾期限を過ぎてしまい内定が失効することもあります。これはスケジュール管理のミスによって起こる、避けたいトラブルです。
まず、企業から提示された期限は必ず把握し、スケジュール帳などに明記してください。期限が厳しいと感じたときは、早めに連絡して相談することが肝心です。
連絡がないまま期限を過ぎると、企業に不誠実な印象を与えてしまいます。状況によっては柔軟に対応してもらえる可能性もあるため、早めの相談が大切です。
就活成功のカギは、丁寧な対応とタイミング。日々の管理を怠らず、トラブルを未然に防ぎましょう。
内定保留という選択を正しく判断するために

内定を保留することは、就活生にとって重要な判断のひとつです。結論として、内定保留は可能ですが、保留期間の目安やリスクを理解したうえで行動することが必要になります。
一般的な保留期間は1週間から10日ほどですが、時期や状況によって柔軟に考えるべきでしょう。
第一志望の結果を待ちたい、他社と比較したいなどの理由から保留を希望する場合でも、伝え方次第で印象は大きく変わります。
内定保留にはメリットがある一方で、リスクやデメリットもあるため、企業への連絡は早めに行い、丁寧に意志を伝えることが大切です。
保留によるトラブルを避けるためにも、正しい知識とマナーを身につけたうえで判断してください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。