内定の返事はいつまで?承諾・辞退・保留の正しい伝え方
「内定の返事、いつまでにどう伝えればいいの?」と迷っている人も多いのではないでしょうか。
返事のタイミングや伝え方は、今後の第一印象や信頼関係に大きく影響します。
そこで本記事では、内定の承諾・辞退・保留それぞれの正しいマナーや例文、電話・メール・手紙での伝え方まで詳しく解説します。
迷わずスムーズに対応できるよう、基本から応用までしっかり押さえていきましょう。
内定をもらったら返事をしよう

内定をもらったあと、どう返事をすればよいか不安に感じている人もいるかもしれません。
内定の返事は単なる形式的な連絡ではなく、社会人としての基本的なマナーであり、あなたの誠実さや責任感を示す大切な機会です。
企業は、内定者の返答をもとに今後の採用計画や配属スケジュールを進めているため、反応がない状態はトラブルの原因となります。
また、大学の就職担当者や今後の後輩にも影響を与える可能性もあるので、内定の返事は、承諾であっても辞退や保留であっても、必ず早めに、そして自分の言葉で丁寧に伝えましょう。
就活の最後は「気が抜けがち」なタイミングですが、だからこそ一つひとつの対応が信頼につながります。社会人としての第一歩を踏み出すためにも、最後まで誠実な姿勢で行動してください。
内定の返事に関する連絡基本マナー

内定をもらったあと、どのように返事をすればいいのか戸惑う就活生は多いものです。
社会人としての第一歩でもあるため、返答の仕方次第で印象が大きく変わってしまいます。
ここでは、就職活動を終えようとしている学生が知っておくべき、内定返事の基本マナーを5つの観点から丁寧に解説します。
- 連絡手段に合わせて対応する
- 返事は早めに伝える
- 感謝と意欲を表現する
- 丁寧な言葉遣いを意識する
- 誤解のない表現を心がける
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
① 連絡手段に合わせて対応する
内定の返事は、電話かメールかによって対応が変わります。たとえば、当日中や急ぎで返答する必要がある場合は電話が適しています。
一方、履歴を残したいときや指定された場合はメールが便利でしょう。企業側から特定の連絡手段を指定されているときは、必ずそれに従ってください。
電話では、周囲が静かな場所を選び、ゆっくり落ち着いて話すことが大切です。名乗りから始め、用件を簡潔に伝えると好印象を与えられます。
メールの場合は、「宛名」「本文」「署名」の3点を丁寧に構成しましょう。特に件名には「内定のご連絡について」など、相手が内容を把握しやすいタイトルをつけるのがおすすめです。
学生のうちは電話に慣れていない方も多いですが、練習することで不安を軽減できます。自信のある伝え方を選ぶことが、誠実な姿勢として伝わるポイントです。
② 返事は早めに伝える
内定をもらったら、できるだけ早く返答することが基本的なマナーです。多くの企業は内定者の数や配属を調整しており、返答が遅れるとスケジュールに影響を与えるおそれがあります。
特に人気企業や少人数採用の企業では、他の候補者への連絡にも関わるため注意が必要です。
具体的には、当日〜2日以内の連絡が理想的でしょう。たとえ迷っている場合でも、「検討中のため◯日までにご連絡いたします」と一報を入れることで、誠実な印象を残せます。
無断で放置するのは絶対に避けましょう。
就活後半では、複数の内定を同時に受けるケースもありますが、決断に時間をかけすぎるとチャンスを逃すこともあります。早めの連絡は自分自身の選択肢を広げることにもつながります。
③ 感謝と意欲を表現する
企業からの内定は、あなたの努力や人柄が評価された結果です。その感謝の気持ちをしっかり伝えることは、ビジネスパーソンとしての大切なマナーと言えるでしょう。
たとえば「このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます」「貴社の一員として働けることを心より嬉しく思います」など、感謝と前向きな気持ちを添えることで、より印象の良い返答になります。
内定承諾の返事は単なる「Yes」ではなく、熱意や思いを込める場面と考えてください。
一方、辞退する場合でも、感謝を伝えることは必要です。「選考過程でのご配慮に深く感謝申し上げます」など丁寧な言葉を使いましょう。
相手の時間と労力への敬意を忘れないことが、長期的に見ても良好な人間関係につながります。
④ 丁寧な言葉遣いを意識する
言葉遣いは、あなたの印象を決定づける大きな要素です。特に内定の返事は、社会人としての第一声ともいえる場面。だからこそ、敬語や表現には細心の注意を払いたいところです。
「内定ありがとうございます」ではなく、「内定を賜り、誠にありがとうございます」といったように、少し言い回しを工夫するだけでも印象が大きく変わります。
また、電話では語尾が曖昧にならないよう、最後までしっかり発音することも重要です。
メールでは「お世話になっております」から始め、「何卒よろしくお願い申し上げます」で結ぶなど、ビジネスメールの基本を押さえた文面が好まれます。
まだ慣れていない就活生にとっては不安もあるでしょうが、事前に例文を用意したり、先輩に添削してもらったりすると、自信がつきやすくおすすめです。
⑤ 誤解のない表現を心がける
返答内容があいまいだと、企業側に誤解を与えてしまうリスクがあります。
「前向きに検討します」「伺いたいと思います」といった表現は、承諾なのか保留なのかが読み取りにくいので、「内定をお受けいたします」「辞退させていただきます」といった明確な表現を使いましょう。
特に保留する場合は、「他社の選考状況を踏まえて◯日までにご返答いたします」と具体的に伝えることが大切です。
また、メールでは主語と述語の対応を丁寧に見直し、「貴社」「御社」「当方」などの使い分けにも注意してください。
伝える内容が正しくても、伝わり方にズレがあると、かえって不信感を生むこともあります。自分の意図が正確に伝わる言葉選びを心がけましょう。
内定の返事の種類

就活では、内定の返事をどう伝えるかによって、企業との信頼関係や今後の就職活動に影響が出る可能性があります。
特に学生にとっては、はじめての社会的な意思決定となるケースも多く、正しい対応が求められます。
返事の種類によって対応方法が異なるため、それぞれのケースで何を意識すべきかを知っておくことが大切です。
- 内定の承諾
- 内定の辞退
- 内定の保留
① 内定の承諾
内定を承諾する場合は、「この会社で働きたい」という強い意思をしっかりと伝えることが第一です。企業側は、あなたの返事をもとに採用活動を終了し、配属や入社後の準備を進めていきます。
そのため、曖昧な返答や返事の遅れは避けるべきでしょう。
たとえば「貴社よりいただいた内定を、ありがたくお受けいたします」といった丁寧で前向きな言葉を使いましょう。また、電話やメール、書面など、連絡手段は企業の指示に従うのが基本です。
就職活動が一区切りつく瞬間でもあるため、「本当にこの会社で良いのか」と自分に問いかけ、納得したうえで返答してください。
承諾の意思を明確に伝えることは、社会人としての第一歩となります。誠意と責任を持って対応することが、信頼につながるはずです。
② 内定の辞退
内定を辞退する際には、「断る=失礼」という気持ちを持つ学生が多いですが、無理に入社して後悔するよりも、早い段階で正直に意思を伝える方が、結果的にお互いのためになります。
辞退の連絡は、可能な限り早く、かつ丁寧に行うことが鉄則です。
たとえば「ご期待に添えず申し訳ございませんが、他の進路を選択することといたしました」といった言い回しで、感謝と丁重な断りをセットで伝えると印象が良くなります。
連絡手段に指定がない場合は、電話の方がより誠意が伝わるでしょう。
企業とのやりとりは、今後の人生で何かの縁につながることもあります。たとえ辞退という選択でも、相手への配慮を欠かさず、礼儀正しい姿勢を貫いてください。
③ 内定の保留
内定の保留は、ほかの企業の選考結果を待っているなど、就活終盤によくあるシチュエーションです。
ただし、保留は当然の権利ではなく、企業に負担をかける可能性もあるため、対応には十分な配慮が求められます。
単に「もう少し考えたい」と伝えるだけでは不十分で、「現在、他社の選考が継続中であり、○月○日までに必ずご返答いたします」といったように、理由と期限を明確に示すことが重要です。
企業によっては保留が認められない場合もあるため、無理に引き延ばすのではなく、相談ベースで進める意識が必要です。
また、提示した期日を過ぎることは絶対に避けてください。約束を守る姿勢が、社会人としての信頼を築く第一歩になります。誠実な対応を心がけましょう。
内定の返事をする方法

内定の返事は、社会人としての第一歩を踏み出す重要なやりとりです。
正しい手段で適切に伝えることによって、あなたの誠実さやコミュニケーション能力が伝わり、今後の関係にも好印象を与えられます。
ここでは、就活生がよく用いる3つの方法について、実践的なポイントを詳しく解説します。
- 内定を電話で伝える
- 内定をメールで伝える
- 内定を手紙で伝える
① 内定を電話で伝える
内定の承諾や辞退などは誤解が生じやすく、相手の反応をその場で確認できる電話が安心です。急ぎの案件や即答が求められる場面では、電話のスピード感が信頼感につながります。
かける前に内容を整理し、メモに要点を書き出しておくと、緊張しても焦らず話せます。担当者が不在の場合に備え、折り返し先や伝言の伝え方も準備しておきましょう。
最初に「○○大学の△△と申します。内定の件でお電話いたしました」と丁寧に名乗り、用件を簡潔に伝えます。
始業直後・終業間際・昼休憩は避け、午前10時〜11時半、午後2時〜4時の時間帯を選ぶのが比較的好ましいとされています。
声のトーンや言葉遣いに注意し、ゆっくり落ち着いて話すことで誠実さが伝わります。電話での対応はあなたの印象に直結するため、丁寧かつ明るく対応しましょう。
② 内定をメールで伝える
メールは最も一般的で企業側も受け取りやすい手段です。
件名は「内定承諾のご連絡(○○大学・氏名)」などが一目でわかるようにし、本文冒頭で企業名・担当者名・自分の所属と氏名を明記し、まずは連絡に対する感謝を伝えましょう。
続けて「貴社からの内定を、ありがたく承諾させていただきたくご連絡差し上げました」など、結論を最初に述べます。
辞退の際は「貴社に魅力を感じつつも、熟考の末、他の進路を選ぶことといたしました」など前向きな理由を添えましょう。保留は「○月○日(○曜)までにご返答いたします」など期限を必ず明示します。
最後に署名欄(氏名・所属・連絡先)を整え、誤字脱字と敬語を確認してください。メールでの印象は文面がすべてなので、言い回しや構成には細心の注意を払いましょう。
③ 内定を手紙で伝える
手紙での返事は少数派になりつつありますが、フォーマルさが求められる場面では効果的です。特に官公庁や歴史ある企業では紙のやり取りを重視する傾向があるため、特に好まれます。
手紙を書くときは白の無地の便箋と封筒を用意し、縦書きで丁寧に記してください。
文頭には「拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」などの時候の挨拶を入れ、続けて「このたびは内定のご通知をいただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べます。
その後、「貴社からの内定をありがたく承諾いたします」と結論を明確に伝えます。署名欄には氏名と日付を記載し、封筒には正式な部署名と敬称を忘れずに書いてください。
提出前には封筒の中身が正しくそろっているか確認し、誠実な文章と整った形式で書くことで、相手に安心感と信頼を感じてもらえるでしょう。
内定の返事の例(メール編)

内定の連絡を受けたものの、返信の文面に迷っている方も多いかもしれません。ここでは、メールを使って内定の承諾・辞退・保留を伝える際の具体的な例文をご紹介します。
自分の状況に合ったパターンを参考に、丁寧かつ適切に対応しましょう。
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
メールでの承諾例文
内定を承諾する旨をメールで伝える際には、感謝の気持ちと今後への意欲を明確に示すことが大切です。
以下は、大学生がアルバイトやゼミでの経験をきっかけに志望企業への思いを強めたケースをもとにした例文です。
| 件名:内定承諾のご連絡(〇〇大学・山田太郎) 株式会社〇〇 人事部 採用ご担当者様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の山田太郎と申します。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。 慎重に検討した結果、貴社の内定を正式に承諾させていただきたくご連絡いたしました。 大学時代に経験した飲食店でのアルバイトを通じて、現場とお客様の声をつなぐやりがいを感じ、説明会や面接を通じてその想いが貴社の理念と重なっていることを確信いたしました。 今後の手続きなどについてご指示をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 ―― 山田 太郎 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 電話:090-1234-5678 メール:taro.yamada@example.com |
この例文では、内定承諾の意志を明確に示したうえで、志望動機に自然なエピソードを盛り込んでいます。自分の経験と企業の特徴を結びつけることで、誠実な印象を与えることができます。
メールでの辞退例文
内定を辞退する際には、丁寧さと感謝の気持ちを忘れずに伝えることが大切です。ここでは、アルバイトやゼミ活動との両立を通じて価値観が変化したという、ごく一般的な学生の背景を想定した例文を紹介します。
| 件名:内定辞退のご連絡(〇〇大学 氏名) 〇〇株式会社 人事部 採用ご担当者様 いつも大変お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の山田太郎です。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。 慎重に検討を重ねた結果、他社で自分の目指すキャリアにより近い環境が見つかったため、誠に恐縮ではございますが、御社の内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。 ゼミでの研究活動やアルバイト経験を通じて、自分の興味や適性を改めて見つめ直すことができたことが大きな理由です。 ご多忙の中、面接や選考の機会をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。 貴社の今後のご発展をお祈り申し上げます。 ―― 山田 太郎 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 電話:090-1234-5678 メール:taro.yamada@example.com |
学生らしい体験を踏まえて辞退理由を伝えると、納得感のある印象になります。迷った末の決断であることを示すことで、誠実な印象も与えられます。
メールでの保留例文
内定通知を受け取ったものの、他社の選考も進行中で判断に悩む学生は少なくありません。ここでは、丁寧に保留をお願いするメールの例文をご紹介します。
| 件名:内定のご連絡に関するご返信(○○大学 氏名) ○○株式会社 人事部 採用ご担当者様 お世話になっております。○○大学〇〇学部の山田太郎です。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。貴社からの評価をいただけたことを、大変光栄に感じております。 大変恐縮ではございますが、現在他社の選考も並行して進めており、人生の大きな決断として慎重に検討したく存じます。 つきましては、返答までに少しお時間をいただくことは可能でしょうか。 ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。 お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 ―― 山田 太郎 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 電話:090-1234-5678 メール:taro.yamada@example.com |
この例文では、感謝の気持ちを伝えたうえで、保留の理由を簡潔に説明しています。志望度が高いことを伝えつつ、丁寧に猶予をお願いするのがポイントです。
確認事項がある場合の例文
内定の連絡をもらったあとに、勤務開始日や配属先などについて確認したい場合の例文をご紹介します。確認事項がある場合でも、まずは内定への感謝を伝えたうえで、丁寧に質問する姿勢が大切です。
| 件名:内定のご連絡ありがとうございます【〇〇大学・山田太郎】 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の山田太郎です。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。貴社で働けることを大変光栄に思っております。 一点、確認させていただきたいことがありご連絡差し上げました。 今後の流れや初出社日、配属部署などにつきまして、現時点でご教示いただける内容がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。 お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ―― 山田 太郎 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 電話:090-1234-5678 メール:taro.yamada@example.com |
確認したいことがある場合でも、冒頭で感謝の気持ちと入社意欲をしっかり伝えることで印象がよくなります。質問は簡潔にまとめ、相手の都合を配慮する表現を忘れずに入れましょう
内定の返事の例(電話編)

内定の連絡を受けたあと、電話でどのように返事を伝えるべきか悩む方も多いでしょう。
口頭でのやりとりは緊張しやすいため、事前に適切な言い回しを把握しておくことが大切です。
ここでは、電話で内定の返事を伝える際の例文を承諾・辞退・保留の3パターンに分けて紹介し、急な対応が必要な場合の言い回しもカバーしています。
電話での承諾例文
内定の連絡を電話でいただいた場合、感謝の気持ちを伝えつつ、入社の意思を明確に伝えることが大切です。ここでは、丁寧な言葉遣いを意識した承諾の例文をご紹介します。
| お忙しいところお電話いただき、ありがとうございます。 〇〇大学〇〇学部の山田と申します。このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 貴社で働かせていただけることを大変光栄に感じております。ぜひ入社させていただきたく、ここに正式にお受けいたします。 今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。なお、必要書類の提出などにつきまして、ご指示いただけましたらすぐに対応させていただきます。本日は誠にありがとうございました。 |
電話での承諾では、「ありがとうございます」「よろしくお願いいたします」といった基本の礼儀がポイントです。落ち着いた声で丁寧に伝える練習をしておくと安心です。
電話での辞退例文
こちらでは、内定を辞退する際に電話で伝える場合の丁寧な例文をご紹介します。やむを得ない理由で辞退する場面を想定し、感謝の気持ちと迷惑をかけない配慮を込めた表現がポイントです。
| お忙しいところ恐れ入ります。○○大学の山田と申します。先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。 大変光栄に思っておりましたが、熟慮の末、他社に進むことを決意いたしましたため、誠に勝手ながら内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。 貴社には選考の際も丁寧に対応していただき、大変感謝しております。このたびはご期待に沿えず申し訳ございません。 何卒ご了承いただけますと幸いです。今後の貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
辞退理由を簡潔に述べつつ、相手企業への感謝とお詫びを丁寧に伝える構成が重要です。「他社に進むことを決意」といった表現にすることで、具体的すぎず失礼にならない断り方になります。
電話での保留例文
内定の連絡を受けたものの、他社選考がまだ残っている場合、即答を避けたい学生も多いでしょう。ここでは、電話で保留の意向を丁寧に伝える例文を紹介します。
| お世話になっております。○○大学○○学部の山田と申します。先ほどは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。貴社からこのようなお話をいただき、大変光栄に思っております。 たいへん恐縮ではございますが、現在ほかにも選考中の企業があり、自身の将来についてもう少しだけ慎重に検討したいと考えております。 つきましては、正式なご返答まで数日お時間をいただくことは可能でしょうか。 ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、〇日までには必ずご連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 |
この例文では、感謝の気持ちを先に述べたうえで、保留の理由と返答期限を明確に伝えています。「返事が遅れる=悪印象」とならないよう、丁寧な姿勢と誠意を意識しましょう。
その場で返事できない場合の対応
面接や電話の場で内定を伝えられても、即答できず戸惑うことがあります。そんなときに失礼のない対応ができるよう、丁寧な保留の伝え方の例文を紹介します。
| このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。大変光栄に存じます。現在、ほかの企業の選考も進んでおり、人生の大きな選択となるため、慎重に判断したく存じます。 つきましては、御社からのご内定について、熟慮のうえで正式にお返事させていただきたく、数日お時間をいただけますと幸いです。 ご迷惑をおかけして恐縮ですが、〇月〇日までに必ずご連絡いたします。何卒よろしくお願いいたします。 |
内定の即答を避けたいときは、感謝の気持ちを伝えた上で「検討したい」という意志を丁寧に伝えましょう。具体的な期限を明記するのが信頼につながるポイントです。
担当者が不在時の対応
電話で内定の返事をしようとした際、担当者が不在だった場合の伝え方についての例文です。不在時でも丁寧かつ的確に要件を伝えることが大切です。
| お世話になっております。○○大学△△学部の山田と申します。先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。 本日は御社のご担当者様に内定のお返事をお伝えしたくお電話いたしましたが、あいにくご不在とのことでしたので、要件をお伝えいたします。 内定について、前向きにお受けしたく存じます。詳細については、担当の○○様に改めてご確認いただければ幸いです。 後ほど再度お電話させていただくか、折り返しをいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。 |
担当者が不在の場合でも、名乗ったうえで「内定の返事を伝えたい」という意図を明確にし、折り返しの依頼や再度連絡する旨を入れるのがポイントです。
曖昧な伝言ではなく、前向きな姿勢を伝える文面を意識しましょう。
内定承諾書の添え状の作り方
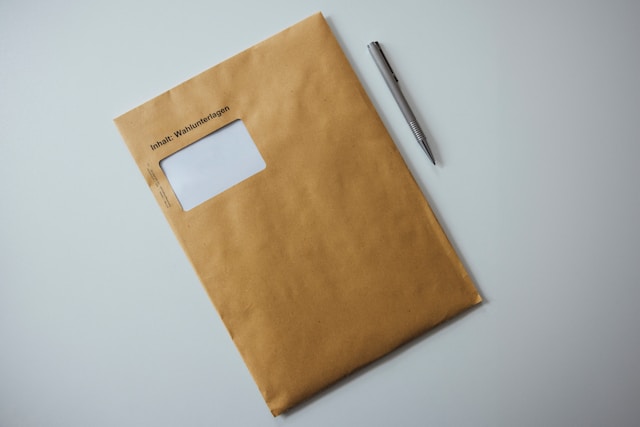
企業から内定通知を受け取ったあと、承諾書を提出する際に添える「添え状」は、社会人としての基本的なマナーです。
添え状は単なる形式的な書類ではなく、自分の誠意や丁寧さを伝える重要なコミュニケーション手段です。就職活動の最後の印象を左右する場面だからこそ、しっかりと整った内容で提出しましょう。
- 書き出し文を書く
- 本文を書く
- 結びの言葉を書く
- 氏名と連絡先を書く
- 用紙の形式を整える
①書き出し文を書く
冒頭では、時候の挨拶と企業への感謝を丁寧に伝えることで、社会人としての礼節を示せます。
たとえば「盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」といった一般的な挨拶文がよく使われます。
このような定型的な表現であっても、丁寧に書かれていれば、読み手に好印象を与えることができます。
急いで本題に入るのではなく、まずは落ち着いた挨拶で始めましょう。こうした細やかな配慮が、就活生としての誠意や丁寧さを伝える鍵となります。
②本文を書く
本文では、内定をいただいたことへのお礼と、承諾の意思をはっきりと記載することが重要です。
たとえば「このたびは内定のご通知を賜り、心より感謝申し上げます。貴社に入社させていただきたく、承諾の意思を固めましたので、所定の書類を同封いたします」といった形で述べると、丁寧かつ明確に伝えられます。
文章はくどくならないよう、簡潔でありながら要点を押さえることを意識しましょう。学生の立場からすれば書き慣れない文面かもしれませんが、「感謝」「意志」「送付」の3点が伝われば問題ありません。
③結びの言葉を書く
本文のあとには、企業への配慮や今後の関係構築を意識した言葉を添えると、好印象を残せます。
たとえば「末筆ながら、貴社のさらなるご発展をお祈り申し上げます」や、「今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」といった一文が一般的です。
その後には「敬具」などの結語を忘れずに記載してください。締めの言葉は、手紙全体の印象を整える役割も果たします。
特に社会人としての第一歩となる文書なので、型どおりであっても丁寧さを意識しましょう。
④氏名と連絡先を書く
最後に、あなたの氏名や大学名、連絡先などを明記することで、書類としての完成度が高まります。
氏名だけでなく、所属する大学・学部・学科名、電話番号、メールアドレスなどを記載するのが一般的です。これにより、企業側が確認や連絡をしやすくなります。
記載漏れや誤字脱字があると、マナー面で不安を与える原因になりかねません。必ず提出前に確認を行いましょう。
学生のうちはこうした書式に慣れていないことも多いので、見本を参考にしながら整えると安心です。
⑤用紙の形式を整える
添え状の用紙は、A4サイズの白無地用紙に縦書きで記載するのが一般的とされています。
印刷する場合は黒インクで出力し、手書きする場合も黒のボールペンなどを使用してください。封筒のサイズは角形2号が適しており、添え状と承諾書を三つ折りにして封入します。
企業名や担当者名は略さず正式名称で書きましょう。形式面の乱れや記入ミスは、印象を損なう大きな原因となるため、細部まで丁寧に仕上げてください。
ビジネスマナーに慣れていない就活生だからこそ、慎重に整える姿勢が大切です。
内定承諾をする前にやるべきこと

内定の返事を出す際には、気持ちが高ぶって即答したくなるかもしれませんが、重要なのは冷静に状況を見極めることです。
社会人生活のスタートを後悔のないものにするためには、判断前に押さえておくべきポイントがいくつかあります。以下の5つの観点を確認し、納得したうえで内定を承諾しましょう。
- 労働条件の確認
- 入社予定日の確認
- 他社の選考状況の整理
- 将来のキャリアとの整合性
- 家族や大学への相談
① 労働条件の確認
就活中は内定の事実に安心し、つい詳細を見落としてしまう人も少なくありませんが、内定を承諾する前には、提示された労働条件が自分の希望と合致しているかをしっかり確認することが不可欠です。
特に給与、勤務地、勤務時間、休日制度、配属部署、福利厚生など、細かい条件まで確認しておくことが重要になります。
特に「話していた内容と書類の記載が違う」といったケースもあるため、内定通知書や雇用契約書の内容を慎重に読みましょう。
気になる点があれば、遠慮せず企業に問い合わせる姿勢も必要です。不明点を放置したまま承諾してしまうと、入社後のミスマッチに悩む原因になります。
納得できる状態で初日を迎えるためにも、契約条件は自分の目でしっかり確認し、不安を残さないようにしましょう。
② 入社予定日の確認
入社予定日をきちんと把握しておくことは、卒業までのスケジュール管理と新生活の準備に直結します。
内定通知書や別紙で提示される入社日には、入社式だけでなく研修や事前提出書類の締切などが含まれている場合もあります。
引っ越しや卒業旅行、アルバイトのシフト調整、卒業論文の提出など忙しくなりがちな大学生活終盤の中でも、「入社日までに何をすべきか」「どれくらい余裕を持てるか」を逆算して考えておきましょう。
また、事情がある場合は、早めに企業に相談することで柔軟に対応してもらえることもあります。連絡を先延ばしにすると、信頼を損なうおそれがあるため注意が必要です。
余裕を持った行動が、社会人としての第一歩を安心して踏み出す鍵になるでしょう。
③ 他社の選考状況の整理
内定をひとつもらったとしても、すぐに決断するのではなく、他社の選考状況を整理して全体を見渡すことが大切です。
本命企業の最終面接が控えている、結果待ちの企業があるといった場合は、その動向を踏まえて慎重に判断する必要があります。
企業側は承諾期限を設けていることが多いため、スケジュールをカレンダーなどにまとめて見える化するのがおすすめです。
焦って承諾したあとに、もっと志望度の高い企業から内定をもらって後悔する…という事態を避けるには、冷静な判断が欠かせません。
将来の方向性に納得できる選択をするためにも、情報を整理し、現時点での優先順位を明確にしておきましょう。
④ 将来のキャリアとの整合性
就職は人生の長い道のりの中でも大きな節目です。内定先の企業が、自分の描く将来像と一致しているかを今一度確認する必要があります。
目の前の条件だけを見て判断してしまうと、「思っていた仕事と違った」「やりたいことができない」といった不満につながることがあります。
たとえば、海外志向が強い人が国内限定の配属方針の会社を選んだ場合、自分の志向とのズレが生じる可能性があります。
企業のビジョン、育成制度、ジョブローテーションの有無、キャリアパスの事例などをリサーチし、自分の将来イメージに照らし合わせてください。
「10年後にどうなっていたいか」という視点で考えることで、より長期的な納得感のある決断ができるでしょう。後悔のない社会人生活を送るためには、自分の軸を明確にしておくことが不可欠です。
⑤ 家族や大学への相談
内定承諾は個人の意思で決めるものですが、就職は生活スタイルや家計、住まいなどにも関わる大きな変化を伴います。だからこそ、信頼できる周囲の人に相談することも忘れてはいけません。
たとえば、遠方への配属が予定されている場合や、奨学金の返済が必要な場合、家族にとっても生活に影響が及びます。事前に説明し、理解を得ておくことで、不安やトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
また、大学のキャリアセンターやゼミの教員からは、過去の内定者の事例や就職後の情報など、実践的なアドバイスが得られることもあります。
自分だけで決めようとすると視野が狭くなりがちですが、他者の意見に耳を傾けることで、新たな気づきを得られることもあるでしょう。
自分の将来の選択に自信を持つためにも、周囲のサポートをうまく活用してください。
内定の返事をする際の注意点

内定の返事は、学生生活の延長ではなく、社会人としての第一歩を踏み出す瞬間です。
ただの連絡だと軽く見てしまうと、思わぬ失敗につながるおそれがあります。企業との信頼関係や自分の評価に直結する場面だからこそ、慎重かつ丁寧に対応することが大切です。
ここでは、内定の返事をするときに特に注意すべき5つのポイントを紹介します。
- 返事期限の厳守
- 意思表示の明確化
- 保留の回数制限
- 承諾後の辞退リスク
- 社会人としての責任意識
①返事期限の厳守
内定の返事は、期限を守ることが何よりも重要です。企業側は、内定者の返答をもとに採用人数の最終調整や入社準備を進めているため、遅れが生じれば他の学生にも影響を及ぼすことになりかねません。
返事の締切は、企業によって「◯日まで」や「1週間以内」など異なりますが、期限ギリギリまで引き延ばすのではなく、できるだけ早めに対応したほうが印象も良くなります。
どうしても都合が合わず期限を守れそうにない場合は、事前に電話やメールで一言伝えるだけでも、誠実な姿勢を示せるでしょう。学生としてではなく、社会人の自覚を持った対応が求められます。
②意思表示の明確化
内定の返事をあいまいに伝えると、企業側に不安を与えてしまいます。
たとえば「前向きに検討しています」「気持ちはあるのですが…」などの表現は、結果的に返事を先延ばしにしている印象を与えがちです。
企業はあなたの返事を待って、次の内定出しや研修計画などを進めています。そのため、承諾・辞退・保留のいずれかをはっきり伝えることがマナーです。
とくに承諾する際は、「入社を希望いたします」と言い切ることで、相手も安心して受け入れ準備を進められるでしょう。率直かつ丁寧な意思表示は、信頼される社会人になる第一歩です。
③保留の回数制限
複数社から内定をもらっている場合、選択に迷ってしまうのは自然なことです。
ただし、返事を保留にする場合は、その回数と期間に注意が必要です。何度も保留を申し出たり、期限を曖昧にしたりすると、企業からの印象が悪くなるおそれがあります。
一般的には、保留の申し出は1回程度が限度で、期間も1週間程度が妥当とされています。もしそれ以上に時間が必要な場合は、「◯月◯日までに必ずお返事いたします」と具体的な日付を伝えましょう。
その際には、「貴重な機会をいただいているので、納得のいく決断をしたい」など、誠実な気持ちを添えることで、印象を損なわずに済むはずです。
④承諾後の辞退リスク
内定を承諾した後に辞退することは、信頼を大きく損なう行為です。
就活を続ける中で、「やっぱり別の企業が良いかも」と思うこともあるかもしれませんが、承諾は単なる返事ではなく、事実上の契約行為として扱われます。
それをあとになって翻すというのは、企業にとって大きなダメージですし、あなたの評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。
やむを得ず辞退せざるを得ない場合には、できるだけ早めに、誠実に謝罪と理由を伝えるようにしてください。
承諾前に本当にこの企業で良いのか、慎重に見極めてから意思表示することが、最終的には自分を守ることにもつながります。
⑤社会人としての責任意識
内定の返事をする行為そのものが、すでに社会人としてのマナーが問われる瞬間です。
メールであっても、文面の丁寧さや誤字脱字の有無、返信タイミングなどが細かく見られています。たとえば「御社」「貴社」の使い分け、語尾の丁寧さ、言葉遣いの配慮など、注意すべき点は少なくありません。
これまでの学生生活では気にしなかった些細な点も、社会人になると評価の対象になります。こうした責任感をもって内定の返事を行うことで、入社前から企業との信頼関係を築くことができます。
自分の行動が「社会人としての第一印象」になることを意識しながら、対応してください。
内定の返事に関するよくある質問

内定をもらえたことは嬉しいことですが、その後の対応に迷う場面も少なくありません。
「本当にこれで合っているのか?」「こんなときどうすれば?」と不安になることもあるでしょう。
ここでは、就活生から特に多く寄せられる代表的な質問と、その解決策について、実例を交えて詳しく解説します。
- 内定が口頭で通知された場合はどうしたらよいか
- 採用担当者と連絡が取れないときはどうしたらよいか
- 内定を承諾したあとに辞退したくなったらどうすればよいか
- 保留の期限に間に合わないときはどうしたらよいか
- 電話で伝えたあとにメールも送るべきか
①内定が口頭で通知された場合はどうしたらよいか
面接の最後に「内定です」と言われたものの、文書での通知が来ないまま数日が経ち、不安になるという声はよく聞かれます。
口頭だけで正式な内定と判断するのは危険で、何かの行き違いで記録に残っていないというケースもあるからです。
このようなときは、「お忙しいところ恐れ入りますが、正式なご通知をメールか文書で頂戴できますでしょうか」と、丁寧な確認を行いましょう。
聞きづらさを感じるかもしれませんが、自分の身を守るうえで大切なステップです。連絡を遠慮してしまって後悔するより、早い段階で確認をとっておくほうが確実です。
企業側も対応に慣れているため、失礼にはあたりません。
②採用担当者と連絡が取れないときはどうしたらよいか
「内定の返事をしようと思っても、電話がつながらずメールの返信もない…」そんな状況に焦ってしまうこともあるでしょう。
ですが、まずは冷静に対応することが大切です。メールだけでなく、企業の代表電話や、別の部署に問い合わせるといった方法も検討してください。
その際、「〇月〇日に電話・同日にメール送信済」など、試みた連絡の記録を残しておくと安心です。また、SNSなどの非常手段に頼るのは逆効果なので避けるのが無難です。
どうしても返事が遅れる場合でも、自分からきちんと連絡を取ろうとした履歴を残しておけば、企業にも誠実さが伝わります。あわてず、粘り強く連絡手段を探ってください。
③内定を承諾したあとに辞退したくなったらどうすればよいか
内定を承諾した後でも、「やはり進学したい」「他に納得できる企業が見つかった」など、気持ちが変わることもあります。もちろん、辞退は簡単な決断ではありませんし、申し訳なさもあるはずです。
それでも、無理に受け入れるより、誠意を持って早めに辞退の連絡をするほうが、企業にとってもあなたにとってもよい結果につながります。
まずは電話で直接伝え、その後「このたびはご迷惑をおかけし申し訳ありません」と謝意を込めたメールや手紙を送っておくと丁寧です。
辞退の理由をきちんと説明すれば、相手も納得しやすくなります。採用担当者も人間です。誠実な態度で向き合えば、大きなトラブルになることはほとんどありません。
④保留の期限に間に合わないときはどうしたらよいか
「もう少し考えたい」「他社の結果を待ちたい」と思って保留をお願いしたものの、提示された期限までに決断がつかない場合もあるかもしれません。
そんなときは、ギリギリまで迷って黙っているより、早めに連絡を入れて正直に相談することが大切です。
「〇〇日までに返答予定でしたが、他社の選考が長引いており、あと数日お時間をいただけないでしょうか」といった丁寧な文面でお願いすると印象も悪くなりません。
期限を過ぎてしまってからの連絡では、信頼を損ねてしまいます。判断が難しいときほど、誠意のあるコミュニケーションを心がけましょう。企業側も柔軟に対応してくれることが少なくありません。
⑤電話で伝えたあとにメールも送るべきか
「電話だけで済ませて大丈夫かな…」と不安になる気持ちはもっともです。特に内定承諾や辞退といった重要な連絡をした場合は、電話の内容を補足するメールを送るのが望ましい対応です。
たとえば「先ほどはお電話にてご連絡差し上げました件につきまして、念のためメールでもご報告いたします」といった形で送れば、相手にも安心感を与えられます。
メールは記録として残るため、後日の誤解も防げますし、ビジネスマナーの面でも好印象です。こうした小さな心がけが、社会人としての信頼につながっていくでしょう。
内定返事の伝え方を正しく理解しよう

内定をもらったら、速やかに誠意ある返事をすることが社会人としての基本です。
その際には、連絡手段や言葉遣いに注意し、感謝や意欲を伝えることが大切です。また、承諾・辞退・保留のいずれを選ぶ場合も、それぞれのマナーと具体的な伝え方を押さえておく必要があります。
電話・メールでの例文を参考にすれば、状況に応じた適切な対応が可能です。さらに、内定承諾書の添え状の書き方や返事前の確認事項、返事をする際の注意点も見落とせません。
返答は単なる形式的な行動ではなく、今後の信頼関係を築く第一歩です。ポイントを押さえて、悔いのない返事を心がけましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













