【新卒向け】履歴書で「在学中」を記載する時の注意点と記入例
「履歴書の学歴欄って“在学中”って書いても大丈夫なのかな…」
そんなふうに悩んだことはありませんか?とくに就活を始めたばかりの大学生にとって、「卒業見込み」や「在学中」といった表現の違いは意外とわかりにくいものです。
本記事では、履歴書における「在学中」の正しい書き方や使い分けのポイントを、例文や注意点とあわせてわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書に「在学中」と書いてもいいの?

履歴書を作成する際、「在学中」と記載してもよいのか不安に感じる方は少なくありません。特に初めて履歴書を書く学生にとっては、最終学歴欄の正しい書き方に戸惑うのも当然です。
「在学中」という表現は、現時点で学校に在籍していることを示す言葉です。ただし、就職活動で提出する履歴書では、卒業予定が明確であれば「卒業見込み」と記載するのが一般的です。そのため、両者の違いを正しく理解して使い分けることが重要になります。
見た目の印象を良くしたいからといって、事実と異なる表記をするのは避けるべきです。自分の状況に合った正確な表現を選ぶことで、企業からの信頼を得る第一歩となります。
なお、「在学中」という記載が完全に間違いというわけではありません。ただし、正社員採用を目的とする履歴書では適さないケースもあるため、応募先や目的に応じて判断することが求められます。
不安がある場合は、大学のキャリアセンターに相談したり、企業の採用担当者に確認をとるのも一つの方法です。誠実で正確な履歴書の作成は、あなたの信頼感を高める強力なアピール材料となるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
「在学中」「卒業見込み」「卒業予定」の違い

履歴書の学歴欄に「在学中」と書いてよいのか悩む方は多いでしょう。実は、「在学中」「卒業見込み」「卒業予定」には明確な使い分けがあります。
表現を誤ると選考で不利になる可能性もあるため、適切な使い方を理解することが大切です。ここでは、それぞれの違いと状況に応じた記載方法を整理して紹介します。
- 基本的に履歴書には「卒業見込み」と書く
- 「在学中」はアルバイトやインターン応募時に使う
- 「卒業予定」は履歴書では使わず、会話で使用する
- 卒業が確定していない場合は、正確な見通しを記載する
① 基本的に履歴書には「卒業見込み」と書く
就活で提出する履歴書には、「在学中」ではなく「卒業見込み」と書くのが一般的です。企業は入社時点で卒業していることを前提に選考を進めるため、「卒業見込み」と記載するほうが信頼されやすくなります。
一方、「在学中」と書くと、卒業できるかどうか不透明な印象を与えてしまうおそれも。「卒業見込み」は大学が発行する証明書とも一致しており、企業にとっても安心材料になります。
卒業予定であるならば、履歴書には「卒業見込み」と明記し、年月も忘れずに記入しましょう。表記の統一にも気を配ると、より丁寧な印象を与えられます。
② 「在学中」はアルバイトやインターン応募時に使う
「在学中」という表現は、就職活動における履歴書には基本的に適していませんが、使いどころがまったくないわけではありません。
たとえば、アルバイトや短期インターンなど、卒業が条件になっていない応募では「在学中」の記載が自然です。
企業側も学業との両立を前提に採用するため、正直に現在の状態を伝えるほうが信頼を得やすいでしょう。ただし、新卒採用など正社員を前提とする場面では、「卒業見込み」と表記することが望ましいです。
応募先の目的や職種に応じて、表現を正しく選ぶことが大切でしょう。相手に合わせた書き方が、伝わる履歴書につながります。
③ 「卒業予定」は履歴書では使わず、会話で使用する
「卒業予定」という表現は日常会話でよく耳にしますが、履歴書には適していません。その理由は、証明書などの正式文書に「卒業予定」という言葉が使われることがないためです。
一方、「卒業見込み」は大学が発行する証明書と対応しており、企業側もそれを確認する前提で選考を進めます。履歴書では、こうした正式な表現を使うことで、企業からの信頼を得やすくなるでしょう。
「卒業予定」は面接などの口頭説明では使っても問題ありませんが、書類では避けてください。書面では証明可能な言葉を使うことが、トラブルを防ぐカギです。
④ 卒業が確定していない場合は、正確な見通しを記載する
単位不足や卒業論文の遅れなどで、卒業が不確定な場合に「卒業見込み」と書くのはリスクがあります。もし卒業できなかった場合、内定の取消しなど思わぬ事態につながるかもしれません。
そのようなときは、無理に「卒業見込み」とせず、「在学中」と正直に記載するのが適切です。そして、卒業が確定した時点で表記を変更するようにしましょう。
企業も、正直で誠実な情報開示を好む傾向があります。自分の状況をしっかり把握し、確実な情報に基づいた履歴書を作成してください。信頼を築くうえで、誤解のない表現がもっとも大切です。
就活での履歴書における最終学歴の定義とは?

履歴書を書くとき、「最終学歴はどこを指すのか」と迷う就活生は少なくありません。正確に理解していないと、意図しない誤解を招きかねません。
ここでは、就職活動における履歴書での最終学歴の扱いについて、正しいルールと考え方を紹介します。
- 「卒業」または「修了」した最終課程を記載する
- 中退や休学の場合は記載するのを避ける
- 記載できるのは、公的に認可された教育機関に限る
① 「卒業」または「修了」した最終課程を記載する
履歴書における最終学歴とは、実際に卒業または修了した最終課程を指します。たとえば大学卒業者であれば「大学卒業」、大学院修了者であれば「大学院修了」と書くのが基本です。
在学中であっても、最終学歴としては含まれません。在学の事実を記載したい場合は、別途「在学中」と明示してください。
また、記載する際は卒業年月とあわせて「卒業」や「修了」と明記し、正確さを意識すると丁寧な印象になります。
② 中退や休学の場合は記載するのを避ける
最終学歴として、中退や休学中の学校を記載するのは避けたほうがよいでしょう。大学を中退している場合、最終学歴は直前に卒業した高等学校となります。
学歴欄に「中途退学」や「休学中」といった形で状況を説明するのは問題ありませんが、企業側の誤解を避けるためにも、明確かつ事実に沿った記載が必要です。
見栄を張ってしまうより、正確な情報を提示する姿勢のほうが信頼されます。
③ 記載できるのは、公的に認可された教育機関に限る
履歴書に記載できるのは、文部科学省や都道府県などの公的機関から認可を受けた正式な教育機関に限られます。
無認可のスクールや民間のカルチャーセンター、通信講座などは学歴として認められません。
履歴書に学歴を記載する際は、後日「卒業証明書」の提出を求められる場合もあるため、在籍している学校が正規の教育機関であるかを事前に確認しておくことが大切です。誤った記載は選考で不利になる可能性があるので注意してください。
履歴書に記入する学歴の正しい書き方
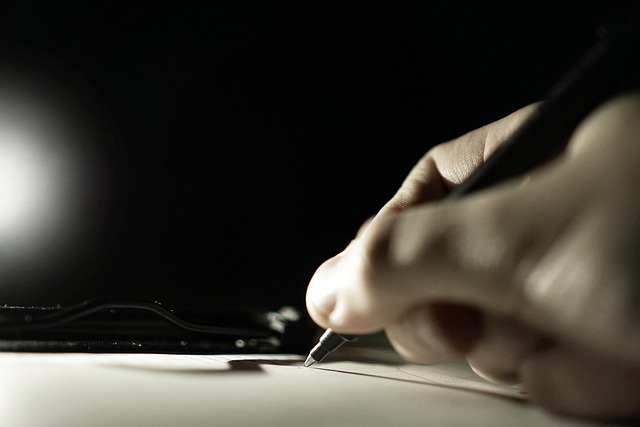
履歴書の学歴欄は、これまでの教育歴を伝える大切な情報です。見やすく正確に記載することで、採用担当者に良い印象を与えることができるでしょう。
ここでは、就活生が間違えやすいポイントを押さえて、正しい学歴の書き方を具体的に解説します。
- 「学歴」は1行目中央に記載する
- 中学校卒業から時系列で記入する
- 西暦または和暦で統一して記入する
- 学校名・学科は正式名称で記載する
- 大学院は「修了見込み」と記載する
- 留年・休学・中退もきちんと記載する
- 留学経験は英語で記載する
① 「学歴」は1行目中央に記載する
履歴書の学歴欄は、1行目の中央に「学歴」と記載するのが基本です。このひとことがあるだけで、どこから学歴の記載が始まるのかが明確になり、採用担当者にとっても見やすくなります。
省略してしまうと形式を守れていない印象を与えてしまうかもしれません。丁寧さを伝えるためにも、必ず記入してください。
文字を中央に配置する際は、定規や罫線の中心を意識して、バランスよく配置しましょう。フォーマットによっては中央がずれて見える場合もあるため、仕上がりの見た目も確認しておくと安心です。
② 中学校卒業から時系列で記入する
学歴は、中学校の卒業から順番に記載します。高校や大学など、進学した順に書いていくことで、自然な流れになります。途中で中退や転校があった場合も、正直にその順に書くことが大切です。
順番が前後すると、内容が不自然に見えたり、空白期間に不審を持たれたりする可能性があります。正確に時系列で記入しましょう。
時系列に沿った記入は読み手への配慮にもなり、選考における理解のしやすさや信頼性にもつながります。
③ 西暦または和暦で統一して記入する
入学や卒業の年月を記載する際は、西暦か和暦のどちらかに統一してください。書類全体で年号が混在していると読みづらく、注意力に欠ける印象を与えるおそれがあります。
特に、指定がなければ西暦が無難ですが、企業が和暦指定の場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
統一感は履歴書全体の整った印象につながるため、記載ルールの一貫性には細心の注意を払いましょう。
④ 学校名・学科は正式名称で記載する
学校名や学部・学科名は、略さずに正式名称で書くようにしましょう。たとえば「〇〇大」ではなく「〇〇大学」、「経済」ではなく「経済学部経済学科」と記載してください。
略記では伝わりづらく、誤解を招くおそれがあります。公式サイトなどで正しい名称を確認し、信頼感のある記載を心がけてください。
特に、学科名が似ている場合は混同されやすいため、明確に表記することで内容の正確性が高まります。
⑤ 大学院は「修了見込み」と記載する
大学院に在学中の場合、「修了見込み」と記載するのが基本です。「在学中」と書くよりも、修了の予定があることを明確に伝えられます。
あわせて「〇〇大学大学院〇〇研究科 修了見込み(20XX年3月)」のように、修了予定年月も記載しておくと親切です。
選考担当者にも伝わりやすくなります。書き方に迷った場合は、大学からの書類や公式な学籍情報を参考にすることで、誤りを防げるでしょう。
⑥ 留年・休学・中退もきちんと記載する
履歴書では、留年や休学、中退といった経歴も省略せず記載することが望ましいです。たとえば「〇〇大学〇〇学部 休学(20XX年4月~20XX年3月)」といったように、期間と状況を明確に記載しましょう。
空白があると疑念を持たれることもあるため、率直に書いたほうが誠実さが伝わります。マイナスと捉えられがちな経歴でも、明確に書くことで説明責任を果たし、信頼性が高まります。
⑦ 留学経験は英語で記載する
1年以上の正規留学や交換留学をしていた場合は、学歴欄に記載できます。その際は、留学先の大学名を英語で記載すると丁寧です。「University of California, Berkeley」など、正式な学校名を用いましょう。
期間やプログラム名も添えると、具体的な経験が伝わりやすくなります。短期の語学研修などは備考欄に記載するのがおすすめです。
また、取得した資格や履修内容も簡潔に記載することで、より説得力のある学歴欄になります。
履歴書の学歴欄を書く際のポイント

履歴書の学歴欄は、企業が応募者の学習歴や人物像を把握するうえで重要な情報です。正しく丁寧に記載することで、内容以上に誠実な印象を与えることができるでしょう。
ここでは、就活生が押さえておきたい学歴欄の基本ポイントを紹介します。
- 履歴書に記入する学歴欄の目的を理解する
- 手書きの場合は丁寧な文字を心がける
- 読み手に伝わるレイアウトを意識する
- 最終学歴の前に空白を空けないようにする
- 誤字脱字がないか必ず見直す
- 学歴が少ない場合でも空欄を残さない工夫をする
① 履歴書に記入する学歴欄の目的を理解する
学歴欄は、単に通った学校を記録するだけでなく、応募者の人生の歩みや価値観を伝える手がかりになります。企業はこの欄を通して、継続力や選択の理由などを読み取ろうとしています。
つまり、学歴欄は重要なアピールポイントのひとつです。目的を理解せずにただ埋めるだけでは、せっかくのチャンスを無駄にしてしまうかもしれません。
だからこそ、自分の経歴を正確に、そして分かりやすく伝える意識が必要です。
② 手書きの場合は丁寧な文字を心がける
手書きの履歴書は、文字そのものがあなたの人柄を映し出します。雑な字や急いで書いた印象が伝わると、それだけで誠実さを疑われてしまうおそれも。
字に自信がない場合でも、丁寧にゆっくりと書くことを意識すれば、読み手に好印象を与えることができるでしょう。
少しでも良い印象を与えるために、修正ペンは避け、誤字があれば最初から書き直す姿勢も大切です。
③ 読み手に伝わるレイアウトを意識する
履歴書の学歴欄は、見やすく整ったレイアウトにすることが大切です。年月と学校名をそろえる、表記方法を統一するなど、細かい部分への気配りが読み手の信頼を得ることにつながります。
また、改行や余白の使い方にも配慮し、全体のバランスを整えることを意識してください。情報そのものに加えて、伝え方の丁寧さも企業は見ているのです。
④ 最終学歴の前に空白を空けないようにする
最終学歴の直前に空白を入れてしまうと、不自然な印象を与える可能性があります。
企業によっては「中退や空白期間を隠しているのではないか」と疑念を抱くこともあるため、必要のないスペースは避けるべきです。
学歴は時系列で一貫して並べ、空白のない自然な流れを意識してください。ちょっとした見た目の違いが、印象に大きく影響します。
⑤ 誤字脱字がないか必ず見直す
誤字や脱字は、書類全体の信頼性を損なう要因になります。特に学校名や学部名の誤記は、採用担当者に不誠実な印象を与えてしまうかもしれません。
書き終えたあとは必ず見直し、可能であれば第三者に確認してもらいましょう。小さなミスほど注意が必要です。正確に書かれていることが、あなたの誠実さを裏付ける証拠になります。
⑥ 学歴が少ない場合でも空欄を残さない工夫をする
学歴が中学卒業や高校中退などで短くなる場合でも、履歴書の学歴欄を空白のままにしてはいけません。空欄があると、内容に不足があるように見えてしまいます。
そんなときは、通信教育や資格取得など、学びの姿勢を伝えられる内容を補足して記入してください。空白を埋める工夫をすることで、前向きな意欲を伝えることができるでしょう。
【ケース別】履歴書の学歴の記入例

履歴書の学歴欄には、在学中・中退・休学・留年など、さまざまなケースが想定されます。それぞれの状況に応じて、適切に記載することで、採用担当者に正しく伝えることができるでしょう。
ここでは、6つの具体的なケースごとに記入例と注意点を紹介します。
- 大学在学中の場合の記入例
- 大学院在学中の場合の記入例
- 大学を中退した場合の記入例
- 休学・留年した場合の記入例
- 大学を転部・転学した場合の記入例
- 大学在学中に留学した場合の記入例
① 大学在学中の場合の記入例
大学在学中の場合は、学歴欄に「在学中」と記載して問題ありません。卒業予定年月が確定しているなら「卒業見込み」と記入しても構いません。
<記入例>
| 2021年4月 ○○大学△△学部△△学科 入学 2025年3月 卒業見込み |
② 大学院在学中の場合の記入例
大学院在学中であることを記す場合は、学部名・研究科・専攻などを正確に書いたうえで、下に「在学中」と加えてください。その場合は、以下のような記載が適切です。
<記入例>
| 2023年4月 ○○大学大学院△△研究科○○専攻 入学 2025年3月 修了見込み |
③ 大学を中退した場合の記入例
大学を中退したときは、その事実だけを簡潔に記載してください。その場合は、以下の記入例のように書きます。退学理由を履歴書に書く必要はありません。
<記入例>
| 2020年4月 ○○大学△△学部 入学 2022年3月 中途退学 |
④ 休学・留年した場合の記入例
休学や留年をしている場合は、履歴書への記載は任意ですが、卒業が遅れる場合には明記すると丁寧です。以下のような書き方が、一般的でしょう。
<記入例>
| 2021年4月 ○○大学△△学部 入学 2023年4月~2024年3月 休学 2026年3月 卒業見込み |
⑤ 大学を転部・転学した場合の記入例
転部や転学を行った場合は、入学から転部・転学の流れを順に記載します。そして、「卒業見込み」と記入してください。その場合は、それぞれ以下の記入例のように書きましょう。
<記入例(転部)>
| 2020年4月 ○○大学△△学部 入学 2022年4月 □□学部へ転部 2024年3月 卒業見込み |
<記入例(転学)>
| 2020年4月 ○○大学 入学 2022年4月 △△大学 編入学 2025年3月 卒業見込み |
⑥ 大学在学中に留学した場合の記入例
在学中に留学をした場合は、留学期間と留学先を記載します。以下のような書き方が適切です。元の大学に引き続き在籍している旨も併記しましょう。
<記入例>
| 2021年4月 ○○大学△△学部 入学 2022年9月~2023年6月 ○○大学(アメリカ)へ留学 2025年3月 卒業見込み |
履歴書の学歴を書くときの注意点

履歴書の学歴欄は、正しく書かないと採用担当者にマイナスの印象を与えることがあります。特に「在学中」の記入方法は、学生が迷いやすいポイントでしょう。
ここでは、履歴書の学歴欄を書く際の重要な注意点について、具体的に説明します。
- 学歴欄に誤りがないようにする
- 「以上」の使い方に注意する
- 転記やコピペによる間違いに気をつける
- 学歴欄の記入順序を守る
① 学歴欄に誤りがないようにする
履歴書の学歴欄に間違いがあると、企業から「注意力が足りない」と判断されることも少なくありません。
特に、在学中の大学を記載するときは、入学年月や卒業見込み年月を誤らないよう気をつけてください。
たとえば、「〇〇大学△△学部 在学中」と書くときに、入学年月が抜けていたり卒業見込み年を書き間違えたりするケースが多く見られます。
さらに、「在学中」や「卒業見込み」を明記せず、「〇〇大学△△学部」とだけ記入すると、すでに卒業しているように誤解されかねません。
卒業の有無や見込み年月は企業にとって重要な情報です。学歴は正確に記載し、自分自身でも必ず見直すようにしましょう。
② 「以上」の使い方に注意する
履歴書の学歴欄で多い誤りの一つが、「以上」の使い方です。「以上」は、最後の学歴を書き終えた次の行に、右寄せで記載します。
「〇〇大学卒業以上」「在学中以上」のように学歴自体に直接「以上」をつけるのは誤りです。
たとえば、大学に在学中の場合、「〇〇大学△△学部 在学中」と書いたら、その次の行の右端に「以上」と書きましょう。
正しく使うことで、「記入はここで終わりです」と企業側に伝わります。書き方を間違えると、企業側から「基本的な書式も守れないのか」と評価が下がるかもしれません。
決して軽視せず、丁寧に確認してください。
③ 転記やコピペによる間違いに気をつける
履歴書を書く際、ネットや就活本などの記入例を参考にするのはよくあることです。しかし、転記やコピペで情報を移すときには注意が必要でしょう。
なぜなら、自分の状況に合わない情報をうっかりそのまま使ってしまうことがあるからです。特に「在学中」や「卒業見込み」などは、自分の現在の状況に合った表現でなければなりません。
他人の記載をそのまま使ってしまうと、「卒業済み」と企業が誤解し、経歴詐称と見なされることもあります。
また、大学名や学部名、日付を間違えてそのまま転記するケースもよくあります。必ず自分自身で最新の情報を確認し、何度もチェックしましょう。
④ 学歴欄の記入順序を守る
履歴書の学歴欄は、中学から現在まで、古い順に記入します。大学在学中の場合、まず中学の卒業年月を書き、その次に大学の入学年月と卒業見込み年月(または在学中)を書くのが基本です。
この順序を間違えて大学を先に書いてしまうと、読み手の採用担当者は混乱してしまいます。ときどき、大学を強調したいという理由で順序を逆にしてしまう学生がいますが、それは逆効果でしょう。
学歴欄の順序は、企業側が学歴を理解しやすくするためのルールです。ルールを守れるかどうかで、社会人としての常識やマナーを判断されることもあります。
順番は必ず守り、読み手が理解しやすいよう工夫しましょう。
履歴書で卒業証明書や在学証明書が必要な場合の対応

就職活動では、企業から卒業証明書や在学証明書の提出を求められることがあります。書類の取得方法や注意点を理解しておけば、いざというときも慌てずに対応できるでしょう。
ここでは、証明書に関する重要なポイントを6つ紹介します。
- 証明書は大学の教務課またはWebで申請する
- 卒業予定者は「卒業見込み証明書」を申請する
- 提出先の企業に合わせたフォーマットで用意する
- 発行された証明書は封を開けずに提出する
- 有効期限がある場合は提出タイミングに注意する
- 再発行や紛失時の対応方法も確認しておく
① 証明書は大学の教務課またはWebで申請する
卒業証明書や在学証明書は、多くの大学で教務課や学生課などの窓口を通じて申請・発行することができます。
最近では、オンライン申請にも対応している大学が多く、申請フォームを大学の公式Webサイトで公開中です。ただし、オンライン申請の場合、受け取り方法が郵送限定のケースもあるため注意しましょう。
窓口では即日発行が可能な場合もありますが、混雑時期には数日かかるケースが珍しくありません。特に、就職活動のピーク時には申請が集中するため、急ぎの場合は事前に問い合わせると安心です。
また、証明書申請に手数料が必要な大学もあります。申請方法や手数料について、事前にしっかり確認しておくと、スムーズに証明書を入手できるでしょう。
② 卒業予定者は「卒業見込み証明書」を申請する
就職活動中で、まだ大学を卒業していない場合には、企業から「卒業見込み証明書」の提出を求められることがあります。
卒業見込み証明書は、あなたが予定通り大学を卒業する見込みであることを大学が正式に証明する書類です。企業にとっては、採用後に確実に入社できるかどうかを判断するための重要な材料となります。
大学ごとに申請期間や発行までの日数が異なり、なかには卒業年度の秋以降しか発行できないという場合も。そのため、自分の大学がいつから発行可能かを早めに調べておきましょう。
企業側の提出期限ぎりぎりにならないよう、余裕を持ったスケジュール管理が大切です。事前準備をしっかりしておけば、提出に関して慌てることもないでしょう。
③ 提出先の企業に合わせたフォーマットで用意する
証明書のフォーマットは、基本的に大学側が定めた標準形式を利用します。しかし、企業によっては英文表記の証明書や専用の書式での提出を求める場合もあるでしょう。
特に、外資系企業や海外での就職活動、公的機関などでは、指定書式や特別なフォーマットでの提出が求められることがあります。
こうした指定書式の証明書を用意する場合、通常より発行に時間がかかることが多いため、早めに大学の担当窓口へ相談するとよいでしょう。
指定フォーマットがあるかどうか不明な場合は、企業の採用担当者に直接問い合わせることをおすすめします。確認を怠ると再発行の手間や時間がかかるため、余裕を持った事前準備が大切です。
④ 発行された証明書は封を開けずに提出する
大学から証明書を受け取ったら、封筒に「厳封」の文字が記載されているか確認しましょう。この「厳封」と書かれた封筒は、中身を取り出さず、封がされたまま企業に提出するのが正式な方法です。
万が一自分で開封してしまった場合、企業によっては書類として無効になることもあります。特に、公務員や大手企業では厳しくチェックされる可能性があるでしょう。
ただし、企業側が特別に「封筒から取り出しても構わない」と指定している場合もまれにあります。その場合は指示に従ってください。
一般的には、証明書は開封しないことが基本です。就職活動のときは、封筒の取り扱い一つにも細かな配慮が必要ですから、慎重に扱うよう心掛けましょう。
⑤ 有効期限がある場合は提出タイミングに注意する
証明書の中には、発行日からの有効期限を設けている企業も少なくありません。特に「発行から3か月以内」といった期限が一般的です。
証明書の発行タイミングが早すぎると、有効期限が切れてしまい、再提出を求められる可能性があります。
そのため、企業に書類を提出する時期や選考スケジュールを考慮しながら、証明書を申請する必要があるでしょう。
複数企業を受ける場合は、同じタイミングで複数枚申請し、期限切れを避けるために必要なときに必要な分だけ取得するという方法もあります。
また、期限がギリギリの場合は念のため企業に確認し、再提出が必要かどうかをあらかじめ明確にしておくことのがおすすめです。
⑥ 再発行や紛失時の対応方法も確認しておく
証明書を紛失してしまったり、何らかの理由で再発行が必要になったりすることもあるでしょう。その場合に備え、事前に大学の再発行手続きの方法や所要日数を確認しておくと安心です。
多くの大学では、再発行に手数料が必要となる場合があり、発行までに日数がかかるケースもあります。
たとえば、申請から再発行まで数日から1週間程度必要な大学が多いため、急ぎの場合には特に注意しましょう。大学によっては、再発行に本人確認書類や紛失届の提出が必要な場合もあります。
再発行に関する詳細は、大学の公式Webサイトや窓口であらかじめ確認しておけば、万が一の場合にも迅速に対応できるでしょう。
履歴書の学歴の書き方に関するよくある質問

履歴書の学歴欄には、学校名や在学期間などを正確に記載する必要がありますが、状況によって書き方が異なることもあります。
ここでは、就活生が迷いやすいポイントについて、よくある質問をもとに具体的に解説しています。
- 高等専門学校や専門学校の記載方法は?
- 学歴欄を間違えた場合の修正方法は?
- 履歴書の学歴欄が足りないときはどうする?
① 高等専門学校や専門学校の記載方法は?
高等専門学校や専門学校を履歴書に記載する際は、正式な学校名と学科名を正確に書くことが大切です。
略称や通称ではなく、「○○工業高等専門学校」や「○○専門学校○○学科」といった形が望ましいでしょう。たとえば以下のように記載します。
| 2020年4月 ○○専門学校○○学科 入学 2022年3月 ○○専門学校○○学科 卒業 |
また、専門課程やコース名がある場合、それらも正確に記載するとさらに丁寧な印象を与えられます。「情報処理コース」や「経営実務専攻」などが該当します。
さらに、高等専門学校の場合は5年制や専攻科の記載方法に迷うこともあります。5年制課程を卒業した場合は「本科卒業」、専攻科を修了した場合は「専攻科修了」と明記しましょう。
記載する際は、書き間違いや省略によるミスを防ぐためにも、必ず学校の公式Webサイトや卒業証明書などで正式な表記を確認してください。
② 学歴欄を間違えた場合の修正方法は?
履歴書の学歴欄に誤りがあった場合は、修正液や修正テープ、二重線で訂正するのは避けましょう。たとえ小さなミスであっても、修正の跡が残ると、採用担当者に対して丁寧さや誠実さに欠ける印象を与えてしまう可能性があります。
そのため、誤字や記載ミスに気づいたら、面倒でも新しい履歴書用紙を用意して、最初から書き直すのが基本です。これは、手書きの履歴書だけでなく、パソコンで作成したものにも当てはまります。
パソコンで作成した履歴書であっても、印刷後に誤りを見つけた場合は、必ず修正して再印刷しましょう。見た目の清潔感や読みやすさは、履歴書全体の印象に大きく関わってきます。
履歴書を丁寧に仕上げるためには、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。細かい部分にも注意を払う姿勢が、採用担当者からの評価につながります。
③ 履歴書の学歴欄が足りないときはどうする?
記載すべき学歴が多く、履歴書の欄に収まりきらない場合は、別紙を用意して補足する方法があります。
その場合は履歴書の学歴欄の最後に「(以下、別紙参照)」と記載し、別紙に同じ書式で学歴をまとめましょう。
別紙を作成するときは、履歴書本体と同じフォーマット・書体を使用し、見やすく整った体裁にしてください。用紙サイズも履歴書本体に合わせると統一感が出て好印象です。
ただし、実際には、大学入学から卒業までを書いても学歴欄が足りないケースは稀でしょう。
そのため、自分が記載しようとしている内容が本当にすべて必要か、改めて見直してみるのも大切になります。特に高校以前の学歴は通常省略可能ですので、無理にすべてを記載しないよう気をつけてください。
履歴書の学歴欄で「在学中」と記載する方法を理解しておこう!

履歴書に「在学中」と記載しても問題ありませんが、就活の場では「卒業見込み」が基本であることを押さえておくべきです。
「在学中」は主にアルバイトやインターンで使う表現であり、正確な学歴や卒業見通しを企業に伝えることが重要です。
学歴欄には、公的に認可された教育機関で「卒業」または「修了」した課程を記入し、中退や休学は最終学歴とはしません。
また、学歴は正式名称で、時系列に沿って記載し、誤字脱字のないよう丁寧に書くことが求められます。ケース別の記入例や学歴証明書の準備も大切です。
これらのポイントを押さえて、履歴書を正しく整え、自信をもって提出しましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












