【例文5選】公務員になりたい理由を伝えるときの注意点と構成術
「公務員になりたい理由って、正直うまく言葉にできない…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
安定性や福利厚生の魅力だけでは、面接官に響く志望理由としては不十分です。とはいえ、公務員という職業の魅力をどう自分の経験や価値観と結びつければよいのか、迷ってしまいますよね。
そこで本記事では、公務員になりたい理由を明確にするための考え方や、面接で評価されやすい伝え方のコツを例文つきで詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員になりたい理由はなぜ面接で聞かれるのか?

就職活動の面接では「なぜ公務員になりたいのか?」という質問が、ほとんどの場面で投げかけられます。
この質問には、単なる志望動機の確認にとどまらず、応募者の内面や適性を見極める重要な意図があります。
面接官はその答えを通じて、あなたの価値観や、公務員としての適性を判断しようとしているのです。ここでは、質問の背景にある3つの視点を分かりやすく解説します。
- 応募者の価値観や志望動機の深さを確認するため
- 公務員として活躍できる人材かを判断するため
- 民間企業との違いを理解して志望しているかを見るため
①応募者の価値観や志望動機の深さを確認するため
「なぜ公務員を目指すのか?」という問いを通して、面接官は応募者の価値観や志望動機が本質的なものかどうかを見ています。
つまり、自分の経験や考えと結びついた理由があるかが重視されるのです。
「地域の課題を解決したい」「行政の立場から社会に関わりたい」といった理由であれば、説得力が増し、自己理解の深さも伝わるでしょう。
一貫性のある志望動機を作るには、自己分析は避けて通れません。自分がどのような場面でやりがいを感じるのか、人や社会との関わり方にどう向き合いたいのかを、具体的な経験と照らし合わせながら言語化してください。
②公務員として活躍できる人材かを判断するため
面接官がこの質問で見極めたいのは、公務員として活躍できる素質があるかどうかです。希望や興味だけでなく、職務への理解と覚悟も求められます。
公務員の仕事は利益ではなく公共の利益を優先します。業務は幅広く、理不尽な場面にも冷静な対応が必要です。短期的な成果より、地道な継続が重視されます。
この特徴を踏まえ、「市民の声を拾い制度改善につなげたい」「粘り強さを地域課題の解決に活かしたい」といった動機が効果的です。方向性が明確なら説得力が増します。
また、大学の学びやアルバイト、ボランティアから、公務員と重なる要素を見つけるのも有効です。
こうした説明ができれば、職務に主体的かつ現実的に向き合っている姿勢が伝わり、面接官に強い印象を残せるでしょう。
③民間企業との違いを理解して志望しているかを見るため
公務員と民間企業では、仕事の性質や目標、評価の仕方まで大きく異なります。面接官は、その違いを理解したうえで応募しているかを確認しています。
たとえば、民間では収益を重視した成果が求められる一方、公務員は公平性や持続性を意識した意思決定が求められます。
また、利益が出なくても必要なサービスを担うのが公務員の役割であり、非効率に見える業務にも重要な意味があります。
この違いを踏まえ、「営利目的ではなく市民の安心や生活の質に貢献したい」「制度設計者として持続的な仕組みを作りたい」といった理由を伝えれば、真剣さが伝わるでしょう。
志望理由を考える際は、民間企業の研究も並行して行い、自分の価値観がどちらに合うかを比較してください。それにより、納得感のある志望動機が作れます。
公務員になりたい理由が思い浮かばない原因

公務員を目指しているものの、「なぜ公務員になりたいのか?」と聞かれると答えに詰まってしまう方は多いのではないでしょうか。
面接で必ずといっていいほど問われるこの質問にうまく答えるには、自分の中にある曖昧な部分を明らかにしておく必要があります。
ここでは、志望理由が浮かばない原因を整理し、それぞれに対するヒントを紹介します。
- 条件面の魅力だけで選んでしまっているから
- 公務員の業務内容を十分に理解できていないから
- 将来像やキャリアビジョンが明確になっていないから
- 自己分析が浅く、自分の価値観を把握できていないから
- 民間企業と比較して考えていないから
- 周囲の影響でなんとなく公務員を志望しているから
①条件面の魅力だけで選んでしまっているから
公務員に「安定している」「福利厚生が整っている」といった条件面の魅力を感じる人は多く、就活中に安定性を重視するのは自然です。しかし、それだけを志望理由にすると、「誰にでも当てはまる動機」と見なされ、価値観や背景が伝わりにくくなります。
大切なのは、なぜその条件を重視するようになったのかを掘り下げることです。たとえば、家族に持病があり、安定した収入や勤務体制の必要性を感じたなら、それは個別性のある理由です。こうした事情に基づく動機は説得力があり、表面的な印象を回避します。
さらに、「安定した環境で自分はどう働きたいか」と視点を広げ、理想の働き方や職務への姿勢を言語化できれば、自分らしい動機として面接官にも伝わるでしょう。
②公務員の業務内容を十分に理解できていないから
公務員という職業は身近な存在である一方、その仕事内容については意外と知られていません。自治体の行政職でも、福祉・教育・防災・産業振興など多岐にわたる分野で業務が行われています。
また、国家公務員となると、国全体の政策に関わる立案業務など、さらにスケールの大きな職務も含まれます。
職員のインタビュー動画や業務説明会、自治体の政策資料などは非常に参考になります。
特に、具体的な事例を通じて仕事内容を知ることで、「自分もこういう貢献がしたい」という実感が芽生えやすくなります。業務内容の理解が深まれば、自分の目指す方向がより明確になり、面接での発言にも自信を持てます。
③将来像やキャリアビジョンが明確になっていないから
将来の自分がどうありたいのか、どのように社会に関わっていきたいのかというビジョンが描けていないと、職業選びも曖昧になりがちです。
そこで大切になるのが、長期的な視点からのキャリア設計です。5年後、10年後にどんな仕事をしていたいか、どんな社会貢献をしていたいかをイメージしてみてください。
地域に根ざした活動をしていたいのか、制度づくりに関わりたいのか、それによって志望職種や勤務地も変わってくるはずです。
また、公務員には定期的な異動があるため、幅広い分野に関われるという特徴もあります。これは、自分のキャリアを柔軟に形成できるチャンスでもあります。
④自己分析が浅く、自分の価値観を把握できていないから
志望動機を考えるうえで、自己分析は欠かせません。価値観や強みを理解していなければ、「なぜその職業を選んだのか」を説得力ある言葉で伝えるのは難しくなります。
効果的な自己分析の一つが、過去の経験を振り返ることです。アルバイトやボランティア、部活動などを思い出し、「やりがいを感じた場面」「困難をどう乗り越えたか」を深掘りしてみましょう。
また、他人からの評価も自己理解に役立ちます。友人や家族に「あなたらしい」と言われた言動や性格は、自分では気づきにくい強みのヒントになります。
経験と他者の視点を振り返れば、公務員の仕事と自分の特性との接点も自然に見えてくるはずです。動機を自分の言葉で語るには、こうした自己分析の積み重ねが重要です。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
⑤民間企業と比較して考えていないから
就職活動では、特定の業界や職種ばかりに目を向けてしまいがちです。しかし、公務員という選択肢だけに絞ると、自分にとっての意義や適性が見えにくくなることがあります。
そこで、民間企業と比較してみることは、自分の価値観や働き方の軸を明確にするうえで有効です。両者の違いを知ることで、合った仕事の方向性が見えてきます。
たとえば、成果主義やスピード感を重視するなら民間が向いているかもしれません。一方、地域に長く関わりたい、公共性を大切にしたいなら、公務員という働き方が合う可能性があります。
このように、重視する働き方を明確にすれば、「なぜ公務員か」という問いにも具体的に答えられます。比較を経て導いた選択であれば、意思に裏付けられた動機として、面接でも説得力をもって伝えられるでしょう。
⑥周囲の影響でなんとなく公務員を志望しているから
志望動機を自分の言葉で語るには、自分自身の意思を再確認することが大切です。「なぜそのアドバイスに納得したのか」「どこに共感したのか」といった視点で振り返ってみてください。
他人の言葉の中にも、自分の価値観と一致する部分があるはずです。なんとなくの選択が「確かな選択」に変わるきっかけは、説明会への参加や職員の話を聞くといった情報収集の行動にあります。
そうした経験を通じて関心が明確な意志に変われば、最初の動機が曖昧でも、自信を持って志望理由を語れるようになるでしょう。
すぐにできる!公務員になりたい理由が思い浮かばないときの対処法
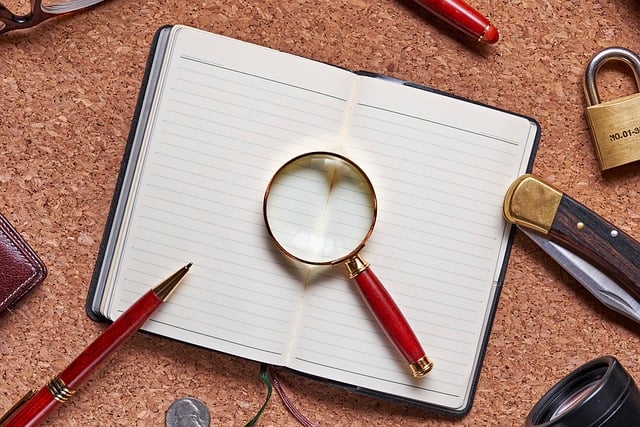
公務員を目指すと決めたものの、「なぜなりたいのか」と改めて聞かれると、自分の中で理由がはっきりしていないと感じることもあるでしょう。
せっかく努力して試験対策を進めるなら、納得できる動機をしっかりと持っておきたいものです。ここでは、公務員を目指す理由を整理するためにすぐ試せる5つの方法を紹介します。
- 公務員以外の進路も視野に入れて考え直してみる
- 自治体や公務員の活動を調べて興味を広げる
- 身近な公務員や先輩に話を聞いてみる
- ボランティアやイベントに参加して実感を持つ
- 職業診断ツールなどを使ってヒントを得る
①公務員以外の進路も視野に入れて考え直してみる
「とにかく公務員になりたい」と考える人もいますが、それだけでは説得力ある志望理由にはなりません。思い込みのまま進むと、適性や動機を見失いがちです。
一度立ち止まり、公務員以外の進路と比較することで、「働く意味」や「大切にしたい価値観」が見えてくることがあります。視野を広げることは、動機を深めるうえで有効です。
たとえば、成長や裁量を重視するなら民間、社会貢献を重視するならNPOに魅力を感じるかもしれません。そうした選択肢と向き合う中で、「やはり地域に根ざした安定した仕事が合う」と気づくこともあります。
他の選択肢と向き合い、果たしたい役割を多角的に見直せば、志望動機の軸が定まり、面接でも説得力をもって語れるようになります。
②自治体や公務員の活動を調べて興味を広げる
説得力のある志望動機を作るためにおすすめなのが、志望する自治体や官公庁がどのような活動を行っているのかを具体的に調べてみることです。これにより、自分の興味や関心がどこにあるのかを知るヒントになります。
自治体によって、施策の特徴に大きな違いがあります。各自治体ごとの方針を知ることで、「自分もこうした取り組みに携わりたい」といった明確な理由が浮かんでくるはずです。
また、行政計画や市民向け広報誌を読むことでも、自治体の考えやビジョンを深く知ることができます。
単なる知識の習得にとどまらず、「どう関わりたいか」という視点を持って調べることで、オリジナル性のある動機づけが可能になります。
③身近な公務員や先輩に話を聞いてみる
情報収集を行う際に特に効果的なのが、実際に公務員として働いている人の話を直接聞くことです。現場のリアルな声に触れることで、ネットや資料だけでは得られない気づきを得られます。
実態とのギャップだけでなく、公務員としてのやりがいやキャリアの展望についても学べます。また、仕事の具体的な側面と、自分の価値観や志向とを結びつけて考える材料にもなります。
また、実際の会話を通じて得たエピソードは、面接時に説得力のある志望理由を語るうえで強力な根拠となります。信頼できる人から直接聞くことで、より深く納得感のある志望動機を導き出せるはずです。
④ボランティアやイベントに参加して実感を持つ
「公務員として働く自分が想像できない」と感じている場合は、まず実際の現場に足を運んでみることをおすすめします。机の上での情報収集だけでは得られない、リアルな気づきが得られるからです。
ボランティア経験を通して、「地域の人々に直接関わることで生まれるやりがい」や「問題解決に向けた連携の重要さ」といった、現場ならではの気づきを得られます。行動に移すことで、自分の適性や価値観にも改めて気づくことができます。
このような経験に裏打ちされた志望理由は、面接でも自信を持って語ることができ、言葉に説得力が生まれます。ただ調べるのではなく、「体験する」ことの大切さを実感できるはずです。
⑤職業診断ツールなどを使ってヒントを得る
自己分析が苦手、あるいは自分の強みや向いていることがよく分からないという人は、職業診断ツールを活用してみるのがおすすめです。
特に、地方公務員と国家公務員でも求められるスキルや業務内容が異なるため、自分の特性と照らし合わせることで、ミスマッチを防ぐことにもつながるでしょう。
もちろん、診断結果はあくまで参考程度に考えるべきですが、自分自身では気づけなかった視点に出会える点が大きな魅力です。
また、診断結果を起点にして、さらに深く自己分析を進める材料として活用することもできます。
迷って手が止まってしまったときこそ、ツールを上手に活用し、新たな気づきを得てみてください。自分の適性や価値観を言語化する一歩として、大いに役立つはずです。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
納得感ある「公務員になりたい理由」を導くための自己分析

公務員を目指す気持ちはあるけれど、面接でその理由を言葉にしようとすると意外と難しいと感じることがあります。ただ漠然と「安定していそうだから」では、面接官に本気度が伝わりません。
そこで必要になるのが、自分の考えや経験と向き合う自己分析です。ここでは、公務員という仕事と自分との接点を見つけるための5つの視点を紹介します。
- 公務員を目指すきっかけや原体験を深掘りする
- これまでの経験から見つけた自分の強みを言語化する
- 志望先の自治体や職種について具体的に調べる
- 公務員の仕事と自分の価値観の接点を整理する
- なぜ民間企業ではなく公務員を選ぶのかを明確にする
①公務員を目指すきっかけや原体験を深掘りする
面接で納得感のある志望動機を伝えるには、「なぜその職業を選ぶのか」という問いに自分なりの言葉で答えることが大前提です。
ここで役立つのが、過去の体験を振り返ることです。
たとえば、高校時代に地域ボランティアへ参加した経験や、災害時に行政の対応に助けられたことがきっかけとなっているかもしれません。小さな体験であっても、心が動いた背景を掘り下げることで、他の人とは異なる「自分らしい動機」が見つかります。
さらに、自分が公務員を目指すに至った気持ちの変化やタイミングを思い出してみてください。
「いつ、どんな場面でその思いが芽生えたのか」「その時どんな行動を取ったのか」などを具体的に書き出すと、より深い自己理解につながるはずです。
②これまでの経験から見つけた自分の強みを言語化する
公務員を目指す理由を語る上で、自分の強みを明確にし、それを言葉にできるかどうかは大きなポイントです。
自分がどんな場面で力を発揮できたのか、どんな行動が成果につながったのかを分析することで、自分ならではの強みが見えてきます。
また、自分では気づきにくい特徴もあります。周囲の人に「自分の良いところ」を聞いてみるのも効果的です。他人の目を通して自分を客観的に捉えることができれば、自己分析の幅が広がります。
こうして見つけた強みと、公務員として求められる資質(協調性、責任感、粘り強さなど)がどう重なるかを意識しながら言語化することが、説得力ある動機づけにつながるでしょう。
③志望先の自治体や職種について具体的に調べる
説得力のある志望動機を伝えるために、志望先の自治体が掲げている重点政策や、近年取り組んでいる事業を調べましょう。
それを把握することで、自分の関心や経験とリンクする要素が見つかるはずです。職種についても同様です。行政職や技術職など、職種ごとに業務の内容や関わる住民層が違います。
どのような立場で地域と関わり、どのようなスキルを活かしたいのかまで考えておくと、より深みのある志望動機になります。
また、職員インタビュー記事や自治体の広報誌をチェックするのもおすすめです。リアルな仕事内容や働く人の声に触れることで、自分の志望理由に具体性が加わります。
④公務員の仕事と自分の価値観の接点を整理する
自分の価値観と、公務員としての役割や働き方がどのように重なるのかを整理することは、職業選択の納得感を高めるうえでとても大切です。
価値観というのは、何に喜びを感じ、何に違和感を覚えるのかといった「自分の行動の基準」となるものです。過去の出来事を思い出しながら自分の価値観を洗い出してみてください。
それらの価値観が、公務員のどんな仕事や使命とつながるかを考えてみると、自分にとっての「やりがい」や「働く意義」が見えてくるでしょう。
たとえば、行政サービスを通じて市民生活を支える姿勢や、長期的な視点で地域課題に取り組む点に共感できるなら、それは十分な動機となります。
自分の中にある価値観と、公務員という職業が担う役割との接点を見つけることで、面接でも自信を持って語れるようになるはずです。
⑤なぜ民間企業ではなく公務員を選ぶのかを明確にする
「民間企業ではなく、なぜ公務員なのか」という質問は、就活の中で必ずと言っていいほど問われるポイントです。表面的な違いを述べるのではなく、自分の思考や価値観との関連性を具体的に説明することが求められます。
民間企業は利益を重視し、スピード感のある競争の中で成長していく組織が多い一方で、公務員は公平性や継続性、住民サービスの提供などを大切にしています。
長期的な視点で地域に貢献したいという気持ちが強い人や、過去に組織内の利害調整やチーム運営に喜びを感じた経験がある人は、公務員の業務特性と相性が良い可能性もあります。
公務員になりたい理由を伝える際の注意点

志望動機がしっかりしているかどうかは、面接の評価に直結する重要な要素です。公務員試験では、回答の内容次第で面接官の印象が大きく変わることもあります。
ここでは、公務員になりたい理由を伝える際に気をつけたいポイントを具体的に解説していきます。
- 福利厚生や安定性だけを理由にしない
- 自己中心的な動機だけで語らない
- 民間企業を否定するような表現は避ける
- 抽象的な表現だけで終わらせない
- 志望動機が他の職種にも通じる内容になっていないか見直す
- 経験やエピソードが結びついていない理由にしない
- 自己PRや他の回答とズレないようにする
①福利厚生や安定性だけを理由にしない
「安定しているから」「福利厚生が良いから」といった理由は、公務員の代表的な魅力のひとつといえます。
面接官は本人の意思や適性を知ろうとします。そのため、安定性は一つの要素として軽く触れる程度にとどめ、それをどう活かして社会や地域に貢献していくのかを語る必要があります。
たとえば、「安定した環境だからこそ、短期的な成果ではなく長期的な課題に腰を据えて取り組める」といった伝え方が効果的です。
あくまで自分の志や価値観とリンクさせて表現し、公務員としての役割を理解していることをアピールしましょう。
②自己中心的な動機だけで語らない
「自分にとって働きやすそうだから」「休みが多いから」といった理由だけで志望動機を構成すると、社会人としての意識が足りないと見なされやすくなります。
自己中心的な思考は「公のために働く」という職業の本質とズレているため、志望理由としては不十分とされる可能性が高いでしょう。
ただし、自分の希望を否定する必要はありません。重要なのは、自分の性格やスキルをどう活かして社会に役立てるかを考えることです。
たとえば、「人前で話すのは得意ではないが、書類作成などの正確な作業に集中する力を活かして、行政手続きの効率化に貢献したい」というように、自分の特徴と業務内容を結びつけることが求められます。
③民間企業を否定するような表現は避ける
「民間企業は競争が激しすぎる」「利益ばかりを追い求めている」といったネガティブな発言は、公務員への志望動機として適切ではありません。
他の選択肢を下げるような話し方は、面接の場では慎むべきです。
民間で働く人やその価値観を否定する姿勢は、協調性の欠如と受け取られることもあります。本当に伝えるべきなのは「なぜ自分が公務員として働きたいと思ったのか」という部分です。
そのためには、他と比較して欠点を挙げるのではなく、公務員の仕事に対して魅力を感じた点や、仕事を通じて実現したいことを中心に伝えるのが効果的です。
「目先の成果よりも、長期的に住民の暮らしを支える仕事に携わりたい」など、自分の志向性とマッチした部分を明確にするようにしましょう。
④抽象的な表現だけで終わらせない
「社会に貢献したい」「人の役に立ちたい」という思いは多くの人が持っていますが、それだけでは他の応募者と差がつきません。
抽象的な表現にとどまると、具体的に何をしたいのか、どのように貢献するのかが伝わらず、印象に残りにくくなってしまいます。
大切なのは、抽象的な思いを支える具体的な経験やエピソードを添えて語ることです。
たとえば、「地域のイベントでボランティアをした際、住民との交流の中で行政の存在の大きさを感じた」という体験をもとに、将来的に果たしたい役割を伝えることで、志望理由に現実味が加わります。
漠然とした理想を述べるのではなく、なぜそう思ったのか、そのきっかけは何だったのかを具体的に掘り下げて話しましょう。リアルな背景があることで、面接官にも真剣さや誠実さが伝わります。
⑤志望動機が他の職種にも通じる内容になっていないか見直す
「人と関わるのが好き」「協調性を活かしたい」といった言葉は、公務員だけでなく多くの職種で当てはまる内容です。
志望動機には、公務員でなければ実現できないことや、公務員という職業の特徴を踏まえた内容を盛り込みましょう。
たとえば、「法制度を通じて住民の安心を支える仕事に関心がある」や「地域行政の最前線で課題に向き合いたい」といった具体性のある表現が望まれます。
他の職種と比較して、公務員という立場だからこそ実現できる点を明確にすると、志望動機に説得力が生まれます。
⑥経験やエピソードが結びついていない理由にしない
志望理由に説得力を持たせるには、自分の過去の体験や価値観と結びつけることが欠かせません。
どんなに立派な動機でも、自分の経験とつながっていなければ「借りもの」のように聞こえてしまい、面接官には響きません。
リアルな体験があるかどうかで、言葉の重みや信頼性が大きく変わってくるのです。
たとえば、「災害時に役所の職員が迅速に対応している姿を見て、公務員という仕事に強い関心を持った」といったように、具体的な出来事をきっかけに志望動機を語ると、一貫性が出て信頼感も高まります。
普段の生活や学生時代の経験を振り返り、なぜその職業を選んだのか、自分なりのストーリーとして語れるように準備しておきましょう。
⑦自己PRや他の回答とズレないようにする
面接全体を通して一貫した人物像を示すことが、合格への近道です。
回答のブレは、「本当にこの人が言っていることは信頼できるのか」と疑念を持たせる原因になります。
自己PR、ガクチカ、志望動機など、それぞれの回答が互いに関連し、補い合っているかを確認しましょう。
自分の強みがどのように職務で活かせるのか、どんな価値観を持っているのかを軸にして、それぞれの回答に共通するテーマを持たせるのがコツです。
一貫性があることで、面接官はあなたに対して納得感を持ちやすくなり、評価にもつながりやすくなるでしょう。
タイプ別に参考になる!公務員になりたい理由の例文

「公務員になりたい理由」を考える際、自分の目指す職種や価値観に合った表現が分からず悩む方も多いはずです。
ここでは、目指すタイプ別に例文を紹介し、自分に合った伝え方のヒントを得られるように構成しています。
例文①:市役所で地域に貢献したい場合
市役所を志望する理由としては、「地元への愛着」や「地域活動への参加経験」などが王道の切り口になります。
ここでは、大学時代のボランティア活動をきっかけに、地域との関わりを深めたいと考える学生の例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学時代、地元の子ども食堂でボランティア活動をしてきました。活動を通じて、地域にはさまざまな課題や支援を必要としている人々がいることを知りました。 特に、行政のサポートがあることで安心して暮らせる人が多いことを実感しました。 この経験から、自分も将来は地域の方々が安心して暮らせる環境をつくる仕事がしたいと考えるようになりました。 市役所職員として、福祉や子育て支援など、住民に寄り添う仕事を通じて地域に貢献したいと強く思っています。 |
《解説》
地域貢献の志望動機は、実体験をもとに「なぜそう思ったのか」を明確に伝えることが重要です。ボランティアなどの具体的な行動と気づきがあると、説得力のある文章になります。
例文②:都道府県庁で幅広い政策に関わりたい場合
都道府県庁を目指す場合、広域的な視点や多様な行政分野に関心があることを伝えるのが効果的です。
ここでは、大学で学んだことや実習経験を通じて、多角的に地域課題に取り組みたいと考える学生の例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学で地域社会について学ぶ中で、人口減少や高齢化、観光振興など、地域ごとに異なる課題があることを知りました。 特にゼミで参加した地域振興に関する実習では、行政・企業・住民の三者が連携することで課題解決が進むことを実感しました。 この経験から、1つの分野に限らず幅広い分野で地域を支える仕事に魅力を感じ、都道府県庁で働きたいと考えるようになりました。 広い視野を活かして、県全体の課題に取り組みながら、住民の暮らしをより良くする政策づくりに関わっていきたいです。 |
《解説》
都道府県庁の志望動機では、広域性や多様な課題に触れる視点がポイントです。ゼミや実習などの学びから動機につなげると説得力が高まります。
例文③:国家公務員として国の課題に取り組みたい場合
国家公務員を目指す理由では、「広い視野で社会全体に関わりたい」という意欲をどう伝えるかがカギになります。
ここでは、社会問題への関心と、国全体に関わる仕事への憧れが芽生えたきっかけを描いた例文を紹介します。
《例文》
| 大学で経済格差について学ぶ中で、地域によって受けられる行政サービスの差が大きいことを知り、衝撃を受けました。 これをきっかけに、全国規模で課題解決に取り組む国家公務員の役割に興味を持つようになりました。 また、公共政策を学ぶ中で、国の制度づくりが地域や生活に与える影響の大きさを実感し、より多くの人の暮らしに関わる仕事がしたいと考えるようになりました。 国家公務員として、多様な立場の人々にとって公平で持続可能な社会を築くための政策に携わりたいです。 |
《解説》
国家公務員の志望理由は「国全体への関与」と「制度設計への関心」をセットで語るのが効果的です。きっかけとなる社会課題への気づきを丁寧に書きましょう。
例文④:地元の公務員として地域に恩返ししたい場合
「地元への恩返し」は公務員志望理由の中でも特に共感を得やすいテーマです。
ここでは、地元での経験や育った環境をふまえて、地域に貢献したい想いを表現した例文をご紹介します。
《例文》
| 私は地元で生まれ育ち、地域の人々に温かく支えられてきました。 学校行事や地域のイベントでは多くの思い出があり、進学して地元を離れてからも、そのありがたさをより強く感じるようになりました。 大学では福祉について学び、行政のサポートが生活に直結していることを知り、地元の役に立てる仕事をしたいと考えるようになりました。 これまで受けた恩を、今度は自分が地域に返していきたいという思いから、地元の公務員として福祉や地域支援の分野で貢献したいと思っています。 |
《解説》
恩返しをテーマにする際は、「どんな恩を受けたか」を具体的に描くと説得力が増します。地元とのつながりを自分の言葉で伝えることが大切です。
例文⑤:地元以外の地域で新しい視点から貢献したい場合
生まれ育った地域とは異なる場所で働くことを希望する場合は、「なぜその地域なのか」と「どんな視点で貢献したいのか」を明確にすることが重要です。
ここでは、縁のない地域で新たな貢献をしたいことを表現した例文をご紹介します。
《例文》
| 私は大学進学を機に地元を離れ、他の地域で暮らす中で、新しい土地の文化や課題に触れる機会がありました。 特に地域活動に参加した際、外から来た自分だからこそ気づける視点があると実感しました。それ以来、他の地域で自分の経験を活かして役に立ちたいと考えるようになりました。 地元以外の自治体で働くことで、これまでの常識にとらわれない柔軟な発想を活かし、地域の課題解決に貢献したいと思っています。 異なる背景を持つからこそできる提案や視点を大切にしながら、公務員として地域づくりに関わっていきたいです。 |
《解説》
地元以外で働きたい理由には、外部の視点を強みにする表現が有効です。その地域を選んだ具体的な背景や動機も忘れずに書きましょう。
公務員になりたい理由でやりがちなNG例文

「公務員になりたい理由」を面接で伝える際、誰もが一度は無難な表現に頼ってしまいがちです。しかし、それが逆にマイナス評価になることも。ここでは、避けるべきNG例文とその理由を具体的に解説します。
NG例文①:安定性や待遇だけを理由にした内容
公務員志望の理由として「安定しているから」「福利厚生が良いから」といった待遇面だけを挙げるのはNGです。以下は、その典型的な例です。
《例文》
| 私は大学で将来のキャリアについて考える中で、やはり長く安心して働ける職場に就きたいと思うようになりました。 民間企業では景気の影響で倒産やリストラのリスクがありますが、公務員であればそのような心配が少なく、安定して働くことができます。 また、有給休暇や育休制度など福利厚生も整っており、将来的に家庭を持ったときにも両立しやすいと感じました。 このように、公務員は他の職種に比べて安定しているという点で、自分にとって最も理想的な働き方だと考えています。 |
《解説》
この例文では「安定性」「福利厚生」といった待遇面の話しかなく、「なぜ公務員として働きたいのか」という職務への関心が見えてきません。
評価される志望動機を書くには、仕事内容や社会貢献への思い、やりがいなどにも触れることが重要です。
特に若い学生は待遇面を重視しがちですが、志望先での活躍意欲や適性を伝えることが、説得力ある文章にするためのポイントです。
NG例文②:具体的な職務内容や貢献意欲が見えない内容
公務員として働きたいという気持ちがあっても、具体的な仕事内容や貢献の姿勢が見えないと説得力に欠けます。以下は、その典型な例です。
《例文》
| 私は昔から人の役に立つ仕事がしたいと思っており、公務員という職業はその思いを叶えられると考えました。 公務員は多くの人々の生活を支える大切な仕事であり、やりがいも大きいと思います。 自分もその一員として、人々の生活を支え、地域社会に貢献していきたいです。 将来は責任ある立場になって、多くの人に頼られるような存在になりたいと思っています。 |
《解説》
「人の役に立ちたい」「貢献したい」という抽象的な言葉ばかりで、どの職種にどう関わり、何をしたいのかが伝わってきません。
公務員にも多種多様な職務があります。志望先の業務内容を調べたうえで、自分の経験や関心と結びつけて書くことが重要です。
NG例文③:民間企業を否定するような言い回しを含んだ内容
公務員を志望する理由の中で、民間企業を引き合いに出して否定するような表現は避けるべきです。比較するならば、公務員の魅力に焦点を当てましょう。以下は、その典型的な例です。
《例文》
| 民間企業では利益を優先しなければならず、数字ばかりを追いかける仕事に魅力を感じませんでした。 その点、公務員は地域や人のために働くことができ、自分が社会に役立っていると実感できると思います。 ノルマに追われることなく、落ち着いた環境で地道に努力を続ける働き方が、自分には合っていると感じました。 民間では感じられないやりがいを、公務員という仕事に見出しています。 |
《解説》
民間企業へのネガティブな言及は、志望理由の印象を大きく損ねる原因になります。
「何が嫌か」ではなく「何に魅力を感じたか」に焦点を当てることで、前向きな動機を伝えることができます。比較する場合も否定的な表現は避けましょう。
NG例文④:プライベートの充実を強調しすぎた内容
ワークライフバランスに言及するのは悪いことではありませんが、それが主な志望理由になってしまうと、働く意欲が低いと受け取られかねません。以下は、その典型的な例です。
《例文》
| 私は仕事だけでなく、プライベートの時間も大切にしたいと考えています。 公務員であれば、勤務時間が安定しており、休日もしっかり取れるため、自分の趣味や家族との時間も充実させることができます。 ワークライフバランスの取れた働き方を実現するために、公務員という選択が自分には最適だと感じました。 長く安定して働けることも魅力で、安心して人生設計ができる点にも惹かれています。 |
《解説》
この例文では「自分がどう働きたいか」ばかりに焦点が当たり、仕事に対する姿勢や社会への貢献意欲が見えてきません。
あくまでプライベート重視は補足的な要素に留め、まずは仕事内容や役割への関心を軸に動機を語ることが評価されやすくなります。
NG例文⑤:曖昧な言い回しで内容がぼやけている例文
志望理由がふんわりとした言葉だけで構成されていると、印象が弱くなり、選考者に本気度や理解度が伝わりません。以下は、その典型的な例です。
《例文》
| 私は人と関わることが好きで、誰かの役に立てる仕事をしたいと思い、公務員を志望しました。 昔から地域に密着した仕事に関心があり、公共の場で働くことに意義を感じています。 公務員は多くの人を支えられる仕事だと思うので、自分もそんな仕事を通じて成長したいと考えています。 社会に貢献しながら、自分自身も成長していけるよう努力したいです。 |
《解説》
「誰かの役に立ちたい」「意義を感じる」といった抽象的な表現が多く、具体性に欠けるのがこの例文のNGポイントです。
実体験や明確な志望職種を絡めることで、「なぜその仕事なのか」「自分に何ができるのか」を伝えられる文章にしましょう。
公務員になりたい理由を明確に伝えて、合格を手に入れよう!

公務員になりたい理由が面接で問われるのは、応募者が持つ価値観や公務員という職業への理解度を深く見極め、公務員として適性のある人材かを判断する目的があります。
そのため、業務内容や民間企業との違いを明確に理解した上で、説得力ある動機を伝える必要があります。
しかしながら、多くの人が自己分析を十分に行わず、安定性や待遇面など表面的な魅力だけで公務員を志望しがちです。
こうした状態では具体的で納得感ある志望理由を導き出すことは困難になります。
公務員への志望動機をしっかりと組み立てるためには、まず自己分析を徹底し、自身が公務員を目指す理由や価値観、将来のキャリアビジョンを明確に整理することが重要です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














