地方公務員になるには?流れと試験対策を徹底解説
安定した職場環境や地域貢献のやりがいから、多くの人が目指す地方公務員。実際には、職種や試験、対策方法が多岐にわたり、何から始めるべきか迷ってしまう人も多いはずです。
本記事では、地方公務員になるための基本的なステップから試験対策、職種ごとの特徴、求められる人物像や資格、エントリーシート作成のコツまで、徹底的に解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
地方公務員とは?

地方公務員とは、都道府県庁や市区町村役場など、地域に根ざした行政機関で働く職員のことを指します。
国家公務員と大きく異なるのは、担当する業務の範囲と影響のスケールです。
国家公務員は中央省庁などに所属し、全国的な政策の企画・立案や制度づくりに携わる一方、地方公務員は地域の実情に即した施策を実行する立場にあります。
国が決めた法律や制度を、住民の状況に合わせて運用するのが地方自治体の役割であり、それを担うのが地方公務員です。また、勤務地についても違いがあります。
国家公務員は全国転勤の可能性が高いですが、地方公務員は原則として採用された自治体内で勤務するため、地元で長く働き続けやすい傾向にあります。
地元への愛着や地域社会への貢献意欲がある人にとっては、魅力的な選択肢といえるでしょう。
地方公務員の代表的な職種

地方公務員には、行政職をはじめ、技術や福祉、公安など、さまざまな専門分野に分かれた職種があります。
それぞれ仕事内容や求められるスキルが異なるため、自分に合った職種を見極めることが大切です。
ここでは、代表的な職種を挙げて、それぞれの仕事内容についても紹介します。
- 行政職
- 技術職(土木・建築・電気など)
- 心理職
- 福祉職(ケースワーカー・福祉指導員など)
- 公安職(警察官・消防官)
- 医療職(保健師・看護師・臨床検査技師など)
- 教育職(公立学校の事務職員・教育行政職)
- 事務職(市町村役場などでの一般事務)
- 農林水産職(農業・林業・水産分野の技術系職員)
- 環境職(環境保全・廃棄物処理関連業務)
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
① 行政職
行政職は、地方自治体のあらゆる分野で活躍する職種で、住民の生活に直結する施策を企画・実施する重要な役割を担っています。
福祉、教育、税務、都市計画、観光など、配属先によって業務内容が大きく異なり、事務処理だけでなく現場とのやりとりも多くあります。
例えば、住民からの相談を受けて手続きを案内したり、地域イベントの運営を支援したりする場面もあります。自治体職員としての柔軟な思考力や協調性が求められるでしょう。
特定の専門知識がなくても挑戦できる職種ですが、地域の課題を解決したいという意欲があると、よりやりがいを感じやすくなります。
市民の声に耳を傾けながら、よりよい行政サービスの提供を目指す姿勢が大切です。
② 技術職(土木・建築・電気など)
技術職は、自治体のインフラや公共施設の整備・維持管理を通じて、地域社会の安全と快適な暮らしを支える専門職です。
土木職は道路や河川、上下水道といった公共構造物の計画・施工管理を行い、建築職は公共施設の設計・耐震改修・修繕などを担当します。
また電気職では、庁舎や街灯などの電気設備に関する設計や保守業務が中心となります。民間企業とは異なり、公共性や住民の利便性が重視されるのが大きな特徴です。
設計図を描くだけでなく、住民説明会や地元業者との調整業務も発生するため、対人スキルも必要になります。
理系分野で学んだ知識を、地域の未来づくりに活かしたいと考える方にとっては、大きなやりがいが得られる職種です。
③ 心理職
心理職は、子どもや保護者、高齢者、障がいのある人など、心のケアが必要なさまざまな人々を支援する専門職です。
主な勤務先は学校や児童相談所、福祉施設などで、公認心理師や臨床心理士の資格を活かして業務にあたります。
たとえばスクールカウンセラーとして、不登校やいじめなどの問題に対して、本人だけでなく保護者や教員と連携して対応する場面もあります。
ほかにも、発達障がいをもつ子どもの支援計画の作成や、認知行動療法を取り入れたカウンセリングなど、多様な手法が求められます。
一人ひとりの課題に真摯に向き合う姿勢と、冷静に状況を判断する力が欠かせません。メンタルヘルスへの関心が高まる中、今後さらに必要とされる分野といえるでしょう。
④ 福祉職(ケースワーカー・福祉指導員など)
福祉職は、生活に困っている人や支援が必要な人々と直接関わりながら、課題解決に向けて支援を行う職種です。
代表的なのがケースワーカーで、生活保護を受ける世帯の相談・訪問指導・就労支援などを担当します。
単に制度を説明するだけではなく、相手の気持ちに寄り添いながら、長期的な視点で自立を支援していくことが求められます。
福祉指導員は、障がいのある人や児童・高齢者への支援計画づくりや、関係機関との調整を行う役割を担います。
状況によっては、緊急性の高い案件や対応が難しいケースもあり、強い責任感と冷静な判断力が必要です。
人の役に立ちたいという思いが強く、社会の課題に真正面から向き合いたい方には非常に適した職種です。
⑤ 公安職(警察官・消防官)
公安職は、地域の治安と安全を守ることが使命であり、危機的状況において迅速かつ冷静に対応する力が求められます。
警察官は、犯罪の予防や捜査、交通指導、地域パトロールなどを通じて安心できるまちづくりを支えます。
一方、消防官は火災や自然災害への対応、救急活動、予防指導といった多岐にわたる業務に従事します。
いずれの職種も、高い身体能力と精神的な強さ、そして協調性や判断力が問われる仕事です。
厳しい訓練や不規則な勤務にも耐える覚悟が必要ですが、その分、命を守るというやりがいは非常に大きいでしょう。
地域の安心を第一に考え、率先して行動できる人にこそ、向いている仕事です。
⑥ 医療職(保健師・看護師・臨床検査技師など)
医療職は、地域全体の健康維持や感染症対策など、公衆衛生に関する幅広い業務を担当する専門職です。
保健師は、乳幼児健診や高齢者の健康相談、家庭訪問による生活支援を行い、看護師は学校や保健所などでの応急処置や健康教育を担います。
臨床検査技師は、検査業務を通じて健康診断や病気の早期発見を支える重要な役割です。
病院勤務とは違い、予防医療や地域密着型の支援が中心であり、対象者の生活全体を見守る視点が求められます。
感染症や災害発生時には保健所業務が過重になることもあるため、柔軟な対応力やストレス耐性も重要です。
医療系資格を活かし、地域で健康づくりに貢献したい方には非常にやりがいのある分野といえるでしょう。
⑦ 教育職(公立学校の事務職員・教育行政職)
教育職は、子どもたちが安心して学べる環境を整える裏方として、学校や教育委員会の業務を担います。
事務職員は学校の会計や物品管理、人事手続きなどを担当し、教育行政職は教育政策の企画や教員支援、施設整備の計画立案などを行います。
児童生徒と直接接する機会は少ないものの、教育活動の土台づくりを担う点で非常に重要です。
教育委員会においては、地域の教育方針やカリキュラムの策定、研修企画などにも関わるため、教育全体を見渡す視野が必要になります。
教育に関心があり、制度や仕組みの改善に貢献したい方にとって、長期的な視点で取り組める職種といえるでしょう。
⑧ 事務職(市町村役場などでの一般事務)
事務職は、市民生活に密接に関わる手続きを担当し、最も住民と近い立場で行政を支える役割を果たします。
住民票や戸籍の発行、税金に関する手続き、地域イベントの企画運営など、業務は多岐にわたります。
部署によって業務内容が大きく異なり、時には観光や防災などの現場に出ることもあります。幅広い業務に対応する必要があるため、正確性と柔軟性が求められます。
また、窓口対応が多いため、人と話すことが苦にならない人には向いているでしょう。地方公務員の中でも採用数が多く、安定性の高さも魅力です。
特別な専門性がなくても挑戦しやすく、長く働ける環境を求める方にはおすすめです。
⑨ 農林水産職(農業・林業・水産分野の技術系職員)
農林水産職は、地域の自然資源を守りながら、産業振興や環境保全に取り組む専門職です。
農業技術者は、農作物の生産技術指導や病害虫対策、品種改良などを通じて農家を支援します。
林業職員は森林の整備や治山事業の計画、水産職員は水質調査や漁場整備、資源保護活動を行います。
いずれもフィールドワークが中心となり、自然環境や気象条件に合わせた柔軟な対応が必要です。
地元の産業に深く関わりながら、持続可能な地域づくりを実現したい方にとっては、非常に魅力的な職種といえるでしょう。
⑩ 環境職(環境保全・廃棄物処理関連業務)
環境職は、持続可能な地域社会を実現するために、大気・水質・廃棄物などに関する施策を進める職種です。
具体的には、環境基準に基づいたモニタリング、産業廃棄物の適正処理指導、リサイクルの促進、環境教育の企画などを行います。
気候変動や脱炭素社会への移行が求められる今、再生可能エネルギーの導入や環境負荷軽減のための取り組みも増えています。
法令や技術知識だけでなく、住民や事業者との調整力も不可欠です。理系分野の知識を活かしながら、地域と自然の共生を目指したい方に適した分野です。
地方公務員のメリット

地方公務員は就職先として人気があります。その理由は、安定性や社会貢献性、働き方の柔軟さなど、さまざまなメリットがあるからです。
とくに就活生にとっては、将来の生活をイメージしやすい職業の一つといえるでしょう。ここでは、地方公務員ならではのメリットについて詳しく紹介します。
- 安定した年収と手厚い福利厚生がある
- 職務内容が社会貢献に直結している
- 異動やキャリアパスが多様で柔軟性がある
- プライベートと両立しやすい働き方ができる
① 安定した年収と手厚い福利厚生がある
就職活動中は、どれくらいの収入が得られるのか、将来にわたって生活が安定するかといった点が気になるものです。地方公務員はその点で非常に安心感があります。
収入は年功序列に基づいて定期的に昇給し、景気の変動による影響をほとんど受けません。
加えて、民間企業に比べて初任給も大きく劣ることはなく、長期的に見れば安定した収入が得られる職業といえるでしょう。
また、福利厚生が手厚いのも大きな特徴です。各種手当(住居手当・通勤手当・扶養手当など)が整備されており、実質的な可処分所得も高くなります。
収入と生活基盤の安定は、見落とされがちですが、キャリアを築くうえで重要な土台になります。
② 職務内容が社会貢献に直結している
地方公務員の最大のやりがいの一つは、自分の仕事が地域社会の役に立っていることを日々実感できる点にあります。
道路や公共施設の整備、福祉サービスの提供、地域防災など、業務は多岐にわたりますが、いずれも住民の生活に直結した重要な役割を担っています。
民間企業では利益の最大化が目標となることが多いのに対して、地方公務員は「公共の利益」を最優先に行動します。
特に高齢化や子育て支援、防災対策など、時代とともに社会課題が変化していくなかで、常に地域のニーズに対応しながら仕事を進めていく必要があります。
公務員の仕事は「地味」だと思われがちですが、実際には地域を動かす最前線で働く責任と影響力を持つ仕事です。
人のために尽くしたい、社会に貢献したいという気持ちがある人にとって、非常にやりがいのある選択肢といえるでしょう。
③ 異動やキャリアパスが多様で柔軟性がある
地方公務員には「一度配属されたら同じ仕事を続ける」というイメージを持たれがちですが、実際には定期的な人事異動があり、多様な業務を経験できます。
行政事務、教育、福祉、土木、商工振興、観光など、配属先は幅広く、経験を積むことで視野もスキルも大きく広がります。
また、同じ自治体内で異なる部署を経験することで、組織全体の流れを理解できるようになり、管理職やリーダーを目指す上でも有利に働きます。
近年では、自分の希望や専門性に応じた異動も取り入れられるようになってきており、成長意欲に応える仕組みも整っています。
自治体によっては、海外研修や大学院への派遣、外部機関への出向など、キャリアアップのための支援制度も充実しています。
新しい分野に挑戦したい方、自分の可能性を広げたい方にとっても、大きなやりがいが見込める職業といえるでしょう。
④ プライベートと両立しやすい働き方ができる
働き方における柔軟性は、地方公務員の大きな魅力の一つです。
基本的に勤務時間は決まっており、定時で退勤できるケースが多いため、残業に追われることはあまりありません。
もちろん繁忙期や緊急対応が必要な場面もありますが、恒常的に激務になることはまれです。有給休暇の取得も推奨されており、職場全体に休みを取りやすい雰囲気があります。
育児や介護との両立も可能で、育児休業や時短勤務、看護休暇などの制度がしっかりと機能しています。
地元志向の方や、将来的に家族との時間を大切にしたいと考える方にとって、大きなメリットになるはずです。
人生全体をバランスよく設計したいと考える就活生には、非常にフィットする働き方でしょう。
地方公務員に向いている人の特徴

地方公務員を目指すなら、自分の性格や価値観が仕事に合っているかを知っておくことが大切です。
安定性や福利厚生といった表面的な魅力だけで選ぶと、入庁後にギャップを感じることもあるでしょう。
後悔のない選択をするためには、自分が本当に公務員に向いているかを把握することが重要です。ここでは、地方公務員に向いている人の特徴を4つ紹介します。
- 地域貢献や人の役に立ちたいという思いが強い人
- 責任感があり、コツコツと仕事に取り組める人
- 幅広い業務に対応できる柔軟性のある人
- チームで協力しながら働くのが得意な人
① 地域貢献や人の役に立ちたいという思いが強い人
地方公務員の主な役割は、地域住民の暮らしを支えることです。
道路や上下水道の整備、福祉・子育て支援、教育や防災といった分野で、人々の生活を下支えする業務を担っています。
そのため、誰かのために働きたいという気持ちが強い人にとっては、仕事そのものが大きなやりがいにつながるでしょう。
また、地域に根ざした課題に対して、自分の関わりによって改善できる点も地方公務員ならではの魅力です。「自分がここにいて良かった」と思える瞬間があることは、大きなモチベーションになります。
一方で、人と関わることに関心がなかったり、業務の社会的意義を感じにくい場合は、やりがいを見出すのが難しいかもしれません。
地方公務員は日々の業務の中で「ありがとう」と言われる場面が多いとは限らないため、目立たなくても地域の一員として貢献している実感を持てるかどうかがカギです。
地域のために働きたいという思いは、面接やエントリーシートでもアピール材料として有効です。その動機が自然ににじみ出るような行動や言葉がある人は、公務員としての素質があると言えるでしょう。
② 責任感があり、コツコツと仕事に取り組める人
地方公務員の業務は、日々のルーチンワークが多く、目立たない作業の積み重ねが中心です。
住民からの問い合わせ対応や、申請書類の受付・審査、地域イベントの調整など、表舞台には出にくい地道な仕事が非常に多くあります。これらの業務では、正確に、期限内に進める力が求められます。
また、公務員は法令や条例に従って仕事を進めなければなりません。民間企業に比べると自由な裁量は少なく、ルール通りに業務を進める姿勢が必要です。
加えて、変化が少ない職場環境においても、集中力を維持しながら継続的に仕事を進められる人ほど長く活躍できます。
毎日の業務に新鮮味を感じにくい場面でも、丁寧に対応する姿勢が住民の信頼につながるためです。反対に、スピード感のある変化や派手な成果を求める人は、物足りなさを感じやすいかもしれません。
ルーチンワークや細かい確認作業を軽視してしまうと、ミスによって住民に迷惑がかかることもあります。
だからこそ、裏方的な役割に誇りを持てる人、誰に見られていなくても手を抜かずに取り組める人は、公務員にとって非常に重要な存在です。
責任感と地道な努力が評価される職場でこそ、その力が真価を発揮するでしょう。
③ 幅広い業務に対応できる柔軟性のある人
地方公務員の業務は部署によって内容が大きく異なります。福祉、環境、都市計画、教育、農林業など、自治体が抱える課題の幅広さに比例して業務内容も多岐にわたります。
また、定期的な人事異動があるため、1つの分野に長く携われるとは限りません。配属先によって仕事内容が一変することもあり、それに柔軟に対応できるかどうかが重要です。
例えば、最初は保健福祉課に配属されていた人が、数年後には財政課や防災関連部署に異動することもあります。
その度に新しい知識や関係者との連携が求められます。こうした変化に対して前向きに取り組める姿勢がある人ほど、幅広い現場で力を発揮しやすくなります。
また、前例が通用しないようなケースにも対応しなければならない場面があります。地域住民の声やニーズが多様化している現代において、マニュアル通りに進まない業務も少なくありません。
柔軟に考え、臨機応変に行動できる人は、周囲からの信頼も得やすくなります。苦手意識を持たずに学ぼうとする姿勢が大切です。
新しい環境や分野に対して好奇心を持ち、変化を恐れず対応していける人は、公務員にとって頼れる存在になるでしょう。
④ チームで協力しながら働くのが得意な人
地方自治体の仕事は、複数の関係者と連携しながら進めることが多くあります。部署内でのチームワークはもちろん、他部署、関連機関、住民団体や企業などとの連携が必要なケースもあります。
そのため、協力して仕事を進める姿勢が不可欠です。特に大きなイベントや施策を進める際には、調整業務が中心になります。
関係者の意見をまとめたり、トラブルを未然に防いだりするためには、高いコミュニケーション能力が求められるでしょう。
また、公務員の仕事は一人で完結することが少ないため、自分の担当外の業務にも協力する場面が出てきます。
そうした際に、チームの一員として柔軟にサポートできる姿勢が大切です。さらに、トラブル時に冷静に対処できるかも重要なポイントです。
住民からのクレーム対応など、感情的なやり取りが避けられない場面でも、チームでフォローし合える職場環境の中で落ち着いて対応できるかどうかが問われます。
人との関係性を大切にしながら仕事を進めることができる人は、協力体制の要となります。チームとしての成果を喜び合える人こそ、公務員として長く活躍できる人材だといえるでしょう。
地方公務員になるうえで評価される資格

地方公務員を目指す学生にとって、資格は選考時に有利に働く要素の一つです。特に専門職や技術職では、業務に直結する資格があると即戦力として期待される可能性が高まります。
ここでは、分野ごとに評価されやすい資格を紹介します。
- 技術・専門職で評価されやすい資格
- 福祉・医療職で評価されやすい資格
- 語学系・国際対応で評価されやすい資格
- IT・デジタル分野で評価されやすい資格
- 災害対応・防災分野で評価されやすい資格
- 環境・エネルギー分野で評価されやすい資格
- 財務・会計分野で評価されやすい資格
- 法律・行政手続きで評価されやすい資格
- 教育・生涯学習分野で評価されやすい資格
① 技術・専門職で評価されやすい資格
地方公務員の技術・専門職では、実務に即したスキルや専門知識が強く求められます。
特に土木施工管理技士、建築士、技術士補といった資格は、インフラ整備や都市開発を担う部署で重宝されます。
自治体によっては、資格の有無で採用時に加点制度を設けているところもあり、明確なアドバンテージになります。
さらに、これらの資格を取得していることで、専門性を持った人材として長期的なキャリア形成も見込まれやすいでしょう。
採用担当者は、単なる資格の保有だけでなく、「なぜその資格を選んだのか」「将来どのように役立てたいのか」といった視点にも注目しています。
大学在学中に取得可能な資格もあるため、学科や志望先に合わせて計画的にチャレンジしてみてください。
② 福祉・医療職で評価されやすい資格
福祉・医療職に就くには、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などの国家資格が必要となることが多く、これらは応募要件にも含まれているケースがあります。
これらの資格は単なる知識の証明だけでなく、現場での実践力や対人支援能力の裏付けとしても重視されます。
例えば、高齢者福祉や児童相談、精神障がい者支援など、多様な支援分野で対応力が問われるため、資格の取得に加えて現場実習やインターンを通じた経験が評価されやすくなります。
また、近年では地域包括ケアや多職種連携が進んでおり、資格に裏付けされた専門性を持った職員の需要が高まっています。
志望理由を伝える際には、資格取得の動機や、どのように地域に貢献したいかを具体的に言語化することが大切です。
③ 語学系・国際対応で評価されやすい資格
地方でも国際交流や外国人支援のニーズが増加しており、語学力のある人材への評価は年々高まっています。
英検やTOEIC、TOEFLなどのスコアは、英語力を可視化するうえで有効ですが、それに加えて通訳案内士や日本語教育能力検定といった、より実践的な資格があると一層の強みになります。
特に、国際課や観光課などでの業務では、外国人住民や観光客との対応を求められる場面が多く、語学力を生かした柔軟なコミュニケーション能力が不可欠です。
また、多文化共生の観点から、地域住民と外国人の架け橋として活動できる資質も求められるため、語学の運用力に加え、異文化理解や地域活動への関心も重要になります。
資格取得の際は、単なる試験対策にとどまらず、実際に使う機会を想定した準備が効果的でしょう。
④ IT・デジタル分野で評価されやすい資格
自治体でもデジタル化が加速しており、情報システムやデータ活用に対応できる人材の確保が急務となっています。
基本情報技術者やITパスポート、応用情報技術者といった国家資格は、ITに関する基礎知識を証明するうえで非常に有効です。
近年では、行政手続きのオンライン化、庁内の業務効率化、AI・RPA導入の検討など、デジタル人材に求められる役割は広がりを見せています。
こうした背景から、文系出身であってもITスキルを持つことは評価ポイントになり、特に情報化推進部門やデジタル政策課などの部署で重宝されます。
また、IT系資格は比較的独学でも対策しやすいため、早めに挑戦しておくことで差をつけることができるでしょう。知識だけでなく、実務との接点を意識した学びが望まれます。
⑤ 災害対応・防災分野で評価されやすい資格
日本各地で自然災害が頻発する中、自治体の防災体制はますます重要視されています。
防災士や危機管理士などの資格は、災害対策やリスクマネジメントへの意識が高い人材であることを示す証になります。
こうした資格を持っていると、防災部門や地域危機管理課などで即戦力として期待されることが多いです。
避難所運営のマニュアル整備、ハザードマップの作成、防災訓練の実施など、自治体業務のなかでも実務的な取り組みが数多くあります。
資格取得の過程では、災害リスクの分析や住民への啓発手法も学べるため、実務にそのまま役立つ知識が多いです。
防災意識の高まりを背景に、こうしたスキルを持った人材は今後さらに求められるでしょう。
⑥ 環境・エネルギー分野で評価されやすい資格
環境問題への関心が高まる中、地方自治体でも持続可能なまちづくりや再生可能エネルギー導入に取り組む動きが広がっています。
環境カウンセラー、エネルギー管理士、ビオトープ管理士などの資格は、環境行政に貢献するための実践的なスキルを示すものとして評価されます。
これらの資格を通じて、自然との共生を目指した取り組みや、住民との協働による啓発活動への参画も期待されます。
地域ごとの課題に応じて施策を柔軟に考える姿勢が求められるため、資格をきっかけに地域課題への関心を深めることが大切です。
また、気候変動対策やゼロカーボン目標の達成に向けて、自治体内での役割も増えています。そのため、資格とともに時事的なトピックにも敏感であることが望まれます。
⑦ 財務・会計分野で評価されやすい資格
自治体の財政運営では、計画的かつ正確な数値管理が欠かせません。日商簿記2級以上の資格をはじめ、公認会計士や税理士などの専門資格も高く評価されます。
とくに日商簿記は会計の基礎を体系的に学べる資格であり、予算の作成、決算処理、資産管理など幅広い業務に活かすことができます。
財務部門では、単に帳簿を扱うだけでなく、各部門との連携や説明責任を果たす場面も多く、数字の裏にあるロジックを理解し、丁寧に伝える能力が求められます。
資格取得を通じてそうした姿勢を養っておくことで、実務対応力の高い人材として認識されやすいでしょう。
加えて、財政健全化を目指す自治体では、会計知識とともに経営的視点を持つ職員が求められています。
⑧ 法律・行政手続きで評価されやすい資格
行政対応に関わる部署では、正確な法令知識と手続きの理解が必要不可欠です。行政書士やビジネス実務法務検定などの資格は、業務への適性の証明として活用できます。
特に住民相談や許認可対応を行う場面では、正確な情報をもとに適切な判断が求められ、資格によってその信頼性を補うことができます。
法律系資格は独学でも学びやすく、文系理系を問わず挑戦しやすいのが特徴です。
加えて、個人情報保護やコンプライアンスといった現代的なテーマにも通じており、自治体業務のさまざまな場面で活かされます。
日常的に接する法制度に関心を持ち、制度運用の裏側まで理解しておくと、採用後の実務にもスムーズに適応できるでしょう。
⑨ 教育・生涯学習分野で評価されやすい資格
公民館や図書館、学習センターなどを通じて、住民の学びや交流を支援するのも地方公務員の大切な役割です。
司書、学芸員、社会教育主事といった資格は、施設での活動に直結する知識や技能を示すものとして評価されます。
地域住民の生涯学習を支えるうえでは、教育的視点と実務的運営スキルの両方が求められるため、企画・運営能力も併せて磨いておくとよいでしょう。
また、イベントの立案や講座の企画など、住民のニーズに応じた取り組みが必要になる場面も多いため、柔軟な発想力や協働する力が問われます。
資格を通じて示す専門性と、現場での積極的な関与ができる姿勢の両方が評価されるポイントです。
地方公務員になるには?基本的な流れとステップ
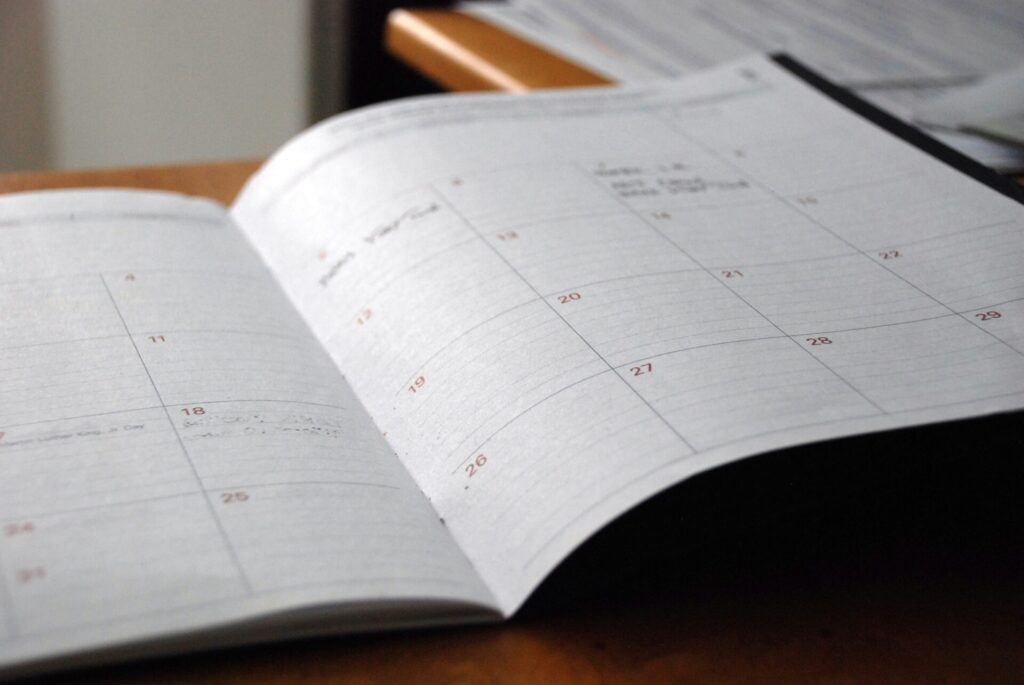
地方公務員を目指すには、明確なステップを踏むことが大切です。準備のタイミングや必要な情報を知らずに進めてしまうと、チャンスを逃してしまうおそれがあります。
ここでは、地方公務員になるために必要な流れを段階ごとに紹介します。
- 地方公務員試験の日程と申込方法を確認する
- 希望する自治体や職種を決めて情報収集をする
- 募集要項や受験資格をチェックする
- 筆記試験・面接・適性検査のステップを把握する
① 地方公務員試験の日程と申込方法を確認する
地方公務員試験の日程や申し込み方法は自治体によって異なります。試験日をうっかり見逃してしまうと、1年を無駄にすることにもなりかねません。
そのため、スケジュールの確認は最優先で行いましょう。
一般的には、上半期(6~7月)と下半期(9~10月)に試験を実施する自治体が多いですが、すべての自治体がこのスケジュールに当てはまるわけではありません。
中には独自の日程で行う場合もあり、特に政令指定都市や東京都特別区は別枠で試験を実施しています。
申込方法はオンラインが主流ですが、紙の書類提出が必要な自治体もあります。入力ミスや書類不備で受験できなかったという事例もあるため、提出前には必ず確認してください。
試験案内は毎年春頃から公開されるため、大学3年の2月頃から定期的に各自治体の採用ページを確認しておくと安心です。
試験情報の収集には「公務員試験ガイドブック」や「自治体のLINE公式アカウント」なども活用できます。申し込みの締め切りは意外と早いため、スケジュール帳にメモしておくとよいでしょう。
② 希望する自治体や職種を決めて情報収集をする
地方公務員と一口にいっても、その業務内容や求められる資質は大きく異なります。
漠然と「安定しているから」という理由だけで進路を決めてしまうと、入庁後に仕事とのギャップを感じることもあるでしょう。
例えば、県庁と市役所では扱う業務のスケールも異なります。県庁職員は広域的な政策を担当することが多く、市役所職員は住民対応や地域密着型の施策を進めることが中心です。
また、同じ自治体内でも、事務職、福祉職、技術職などに分かれており、適性や興味によって向いている職種は変わってきます。
希望する職種や分野が定まっていない場合は、合同説明会や自治体主催のセミナー、インターンシップに参加するのがおすすめです。
職員の話を直接聞ける場では、公式サイトだけではわからないリアルな仕事内容や雰囲気を感じ取ることができます。
情報収集を通じて自分がどんな地域課題に関心があるのか、どんな形で地域に関わりたいのかを考えてみてください。志望動機の深掘りにもつながり、試験対策にも役立つはずです。
③ 募集要項や受験資格をチェックする
受験資格や募集要項は、地方公務員試験において最も見落としやすく、かつ致命的なミスにつながるポイントです。
受験できると思っていたのに資格要件を満たしておらず、不合格以前に応募すらできなかったというケースもあります。まず確認すべきは年齢制限です。
多くの自治体では「採用年度の4月1日時点で30歳未満」といった条件がありますが、詳細なカウント方法は自治体ごとに異なります。
誕生日が基準日と重なるかどうかで結果が変わることもあるため、注意が必要です。次に学歴や資格要件ですが、職種によっては特定の資格が必須になることもあります。
保育士や技術職では国家資格の取得が前提となる場合があるほか、福祉系では社会福祉士などの資格が求められることもあります。
さらに、障がい者枠や経験者採用枠などの募集がある自治体もあります。これらは選考内容やスケジュールも異なるため、通常枠と混同しないよう気をつけましょう。
募集要項は毎年更新されるため、前年のデータを参考にするだけでは不十分です。必ず最新の試験要項を確認し、自分が応募できる区分を正しく選ぶことが、無駄のない受験準備につながります。
④ 筆記試験・面接・適性検査のステップを把握する
地方公務員試験は複数の選考ステップで構成されており、それぞれに対策のポイントがあります。
どこか一つでつまずいてしまうと次の選考に進めないため、全体の流れを把握して計画的に準備を進める必要があります。
筆記試験には「教養試験」と「専門試験」があり、教養試験はすべての受験者が対象です。
一般知能(数的処理、文章理解など)や一般知識(時事、社会科学など)から出題されるため、幅広い学習が求められます。
専門試験は経済、法律、行政など職種に応じた内容が出題されますが、実施しない自治体もあります。面接試験は、人物重視の傾向が年々強くなっています。
グループディスカッションやプレゼンテーションを取り入れる自治体もあり、単なる受け答えだけでは評価されません。地域課題への理解や、自分がどのように貢献できるかを明確に伝える力が問われます。
適性検査では、性格診断やストレス耐性、論理的思考力などがチェックされます。一見簡単そうに見えますが、結果が面接評価に影響することもあるため、軽視してはいけません。
各ステップの目的を理解したうえで、効率よく対策を行っていくことで、合格の可能性は着実に高まります。独学が不安な場合は、公務員試験対策講座の利用も検討してみてください。
地方公務員試験の内容
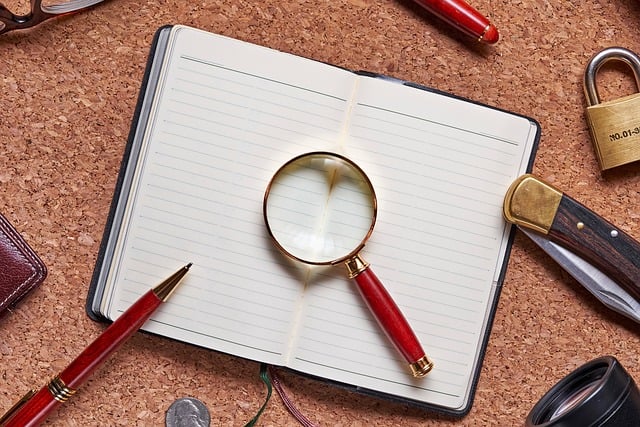
地方公務員になるには、複数の試験を通過する必要があります。筆記や面接に加えて、論文や討論といった評価も含まれており、幅広い能力が求められます。
ここでは、地方公務員の主な試験内容について詳しく紹介します。
- 教養試験
- 専門試験
- 論文試験
- 面接試験
- 集団討論
- 地方試験(上級・中級・初級)
① 教養試験
教養試験は、すべての地方公務員試験で実施される基本的な筆記試験です。一般常識や時事、文章理解、数的処理など幅広い分野から出題され、基礎的な知識と判断力が問われます。
とくに全受験者に共通するため、得点差が出やすく、苦手分野をそのままにしていると不利になる可能性があります。
出題範囲が広いため、何から手をつければいいのか迷う人も多いですが、まずは過去問の演習から始めるのがおすすめです。
出題傾向を把握したうえで、自分の苦手分野を把握し、動画解説や参考書を使って繰り返し練習すると着実に力がついていきます。
数的処理などは解法パターンを理解することでスピードも上がるため、日々の積み重ねがカギとなります。
試験直前になって詰め込むのではなく、早期からコツコツと準備を進めていくことが最終的な得点力の差につながるでしょう。
② 専門試験
専門試験は、受験する職種に応じた専門知識を問う筆記試験で、事務職では法律や経済、技術職では土木や機械などが対象になります。
自治体や職種によって出題範囲は異なりますが、大学で学んだ知識がそのまま活かせる場合もあります。
教養試験に比べて範囲が限定的なため、対策が立てやすい一方で、問題の難易度は高く、深い理解が求められます。
単なる暗記では対応できない問題もあるため、理論や考え方をきちんと理解しておくことが必要です。
出題傾向や頻出テーマを知るには、過去問分析が非常に有効です。志望自治体がどの分野から多く出しているのかを確認し、重点的に対策することで効率よく点が取れるようになります。
また、自治体によっては専門試験を課さない場合もあるため、受験案内を事前によく確認してください。
③ 論文試験
論文試験は、公務員としての資質や思考力、文章表現力を評価する重要な試験のひとつです。
出題されるテーマは「人口減少社会への対応」や「防災・減災の取り組み」など、地域行政と関わりの深い課題が多く見られます。
この試験では、与えられたテーマについて自分の意見をわかりやすく論理的にまとめる力が求められます。
書き慣れていないと主張がぼやけたり、話が飛んだりするため、構成をしっかり意識することが大切です。
PREP法(結論→理由→具体例→再主張)を用いると、読み手に伝わりやすい文章になります。
また、事前にいくつかの想定テーマを用意し、それに対する自分の意見を下書きしておくと、本番でも落ち着いて書くことができるでしょう。
自治体の取り組みや地域特性を調べて自分の意見に絡めると、より現実的かつ説得力のある内容になります。論文は一朝一夕では身につかないため、継続的な練習が不可欠です。
④ 面接試験
面接試験は、筆記試験の合格後に行われる人物評価の場であり、公務員としてふさわしい人柄や姿勢が見られます。
質問は志望動機や自己PRにとどまらず、「チームで働いた経験」「困難をどう乗り越えたか」など、行動や考え方を深掘りされるものが多く出題されます。
自己分析が不十分なまま臨むと、回答に一貫性がなくなったり、志望理由が薄く見えてしまう恐れがあります。
過去の経験を振り返り、どのように成長したか、どのように地域貢献につなげたいかを明確にしておくことが大切です。
模擬面接は、緊張感のある環境で練習できるため非常に効果的です。客観的なフィードバックをもとに改善を重ねることで、話す内容も自然と洗練されていきます。
また、面接官は受け答えの内容だけでなく、表情や姿勢、声のトーンなども含めて総合的に評価しています。自信を持って話せるように、事前準備と反復練習を欠かさないようにしましょう。
⑤ 集団討論
集団討論は、他の受験者とグループで行う形式の選考で、個人では測れない協調性や問題解決能力、論理的思考などが評価されます。
テーマは「地域の魅力向上策」「若者の地方定住促進」など、自治体が抱える現実的な課題が取り上げられることが多いです。
討論では、一方的に話し続けるよりも、他人の意見をよく聞きながら自分の意見をわかりやすく伝えることが重要です。
また、議論が偏りそうなときに視点を広げたり、議論を整理する役割を買って出るなど、全体に貢献する姿勢が高評価につながります。
日常的に新聞や自治体の広報誌などを目を通しておくと、討論で話す材料が増え、話題に深みが出ます。
何を話すか以上に、どう関わるかが見られる場なので、発言量だけにこだわらない柔軟な姿勢が必要です。
初対面の人と短時間で協力しながら成果を出すという場面は、公務員の仕事においても多いため、その資質を評価される重要な試験といえるでしょう。
⑥ 地方試験(上級・中級・初級)
地方公務員試験は、学歴や職種に応じて「上級」「中級」「初級」の3つに分かれています。それぞれで求められる知識や能力が異なり、試験の構成も自治体によって変わります。
上級は大卒程度が想定され、試験内容は難易度が高く、筆記・論文・面接すべてにおいて広範な準備が必要です。
一方、中級・初級は短大卒や高卒レベルが対象となり、出題範囲は比較的狭くなっています。
ただし、同じ「上級」でも県庁と市役所では求められる人物像が異なる場合があるため、過去の採用試験情報や募集要項を丁寧に確認することが欠かせません。
また、自治体によっては試験の回数や日程も違うため、複数の自治体を併願する際にはスケジュール調整にも注意が必要です。
自分の現在の学歴や希望する職種に合った試験区分を選び、無理のない計画を立てて臨んでください。
地方公務員試験の対策ポイント
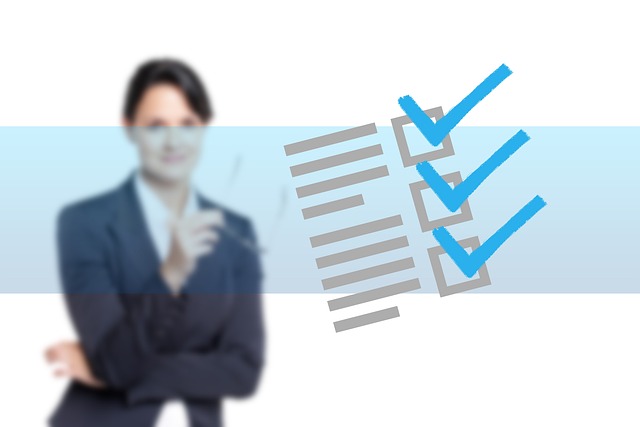
地方公務員試験は受験者が多く、競争も激しいため、事前の準備が合否を大きく左右します。効率のよい学習と計画的なスケジューリングが欠かせません。
ここでは、試験対策に役立つ具体的なポイントを3つ紹介します。
- 早めに勉強を始めて、学習スケジュールを立てる
- 自分に合った学習方法(独学・予備校)を選ぶ
- 過去問を繰り返し解いて出題傾向をつかむ
① 早めに勉強を始めて、学習スケジュールを立てる
地方公務員試験に合格するには、できるだけ早い段階から計画的に勉強を始めることが重要です。
なぜなら、出題範囲が幅広く、主要科目だけでなく一般教養や時事問題なども対策する必要があるため、短期間で網羅するのは困難だからです。
実際、1日に使える勉強時間が限られている学生も多いでしょう。そこで、まずやるべきことは「いつまでにどの範囲を終えるか」を明確にし、逆算して月ごと、週ごとの目標を設定することです。
例えば、4か月後に主要科目を終わらせると決めたら、各週の進捗が遅れないよう定期的に振り返りを入れると効果的です。
また、単に教科書を読むだけでなく、インプットとアウトプットのバランスを意識した学習サイクルも大切です。
インプットに偏ると知識が定着しづらく、模試や問題演習での得点に結びつかないことがあります。毎週、理解度を確認するミニテストを自作するのもよい方法です。
さらに、学習時間だけでなく、睡眠や食事といった生活リズムも整えることで集中力が持続します。試験本番まで無理なく続けられるスケジュールを立てて、日々の習慣として定着させましょう。
焦らず、でも着実に学習を重ねることで、安心して本番に臨めるはずです。
② 自分に合った学習方法(独学・予備校)を選ぶ
公務員試験は、独学でも予備校でも合格可能です。しかし、大切なのは「自分に合っているかどうか」をしっかり見極めることです。
なぜなら、他人にとって最適な方法が、自分にとっても同じとは限らないからです。独学を選ぶメリットは、自分のペースで進められることと、費用を抑えられる点です。
教材やスケジュールを自由に選べるので、マイペースに取り組みたい人に向いています。
ただし、自己管理能力が求められるため、途中で計画がずれたりモチベーションが下がったりすると、挫折するリスクも高くなります。
一方で、予備校は講義や教材が体系化されており、学習の流れが分かりやすいです。
講師に質問できる環境や、模試などのサポートも充実しているため、何から手をつけていいかわからない人には安心でしょう。
特に、周囲に同じ目標を持つ仲間がいることで、学習意欲が保たれるという利点もあります。ただし、予備校に通う場合は費用や通学時間も考慮する必要があります。
経済的な負担やスケジュールの柔軟性の少なさがストレスになる場合もあるため、自分の生活スタイルや価値観に照らし合わせたうえで選択してください。
どちらの方法にも長所と短所があり、重要なのは「続けやすい」ことです。性格や学習習慣に合った方法を選び、無理なく継続することが、結果として最も効率的な対策になります。
③ 過去問を繰り返し解いて出題傾向をつかむ
公務員試験の合格者の多くが共通して実践しているのが、過去問を繰り返し解くという勉強法です。本番と同じ形式の問題に慣れることで、得点力が飛躍的に伸びやすくなります。
まず、過去問を解くことで、どの分野が頻出なのか、どういった出題パターンがあるのかが見えてきます。これにより、優先順位をつけた効率的な学習が可能になります。
例えば、繰り返し出題されている憲法や経済原論などの科目に重点を置き、確実に得点できる分野を増やすことができます。
また、重要なのは「なぜその答えになるのか」を理解することです。正解していても、解法を説明できない場合は本当の意味で理解できていないこともあります。
そこで、解説をじっくり読み込み、ノートにまとめるなどして、知識を深めるようにしましょう。さらに、制限時間を意識した演習も欠かせません。
本番では限られた時間の中で解答を求められるため、普段から時間配分を意識して過去問に取り組むことが必要です。模試形式で実施することで、本番と近い緊張感を体感することもできます。
繰り返し演習する中で、知識の定着度も高まり、応用力も養われていきます。正しく使える知識として頭に残すには、過去問の活用が最も近道といえるでしょう。
地方公務員を目指す人のエントリーシート(ES)を書くコツ

地方公務員を目指す就活生にとって、エントリーシートは採用試験の重要な第一歩です。評価される内容にはいくつかのコツがあり、自己PRや志望動機を的確に伝える力が求められます。
ここでは、ES作成の基本から具体的な書き方までを解説していきます。
- 自己PR・志望動機・ガクチカを分かりやすく書く
- PREP法を使って論理的に伝える
- 自治体や職種に合わせた具体的な内容にする
① 自己PR・志望動機・ガクチカを分かりやすく書く
ESで読み手に好印象を与えるためには、自己PR・志望動機・ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)をそれぞれ明確に、かつ簡潔に伝えることが欠かせません。
特に地方公務員の場合、「安定しているから」といった曖昧で一般的な理由だけでは熱意が伝わらず、選考で不利になるおそれがあります。
そこで大切なのが、「なぜ公務員になりたいのか」「その中でもなぜ地方自治体なのか」といった部分を掘り下げて表現することです。
自己PRでは、自分の性格や行動の特長を伝えるだけでなく、どのような場面でその力を発揮したのかを具体的に説明しましょう。
たとえば「責任感がある」と書くだけでは弱く、アルバイト先で新人教育を任された経験や、サークル活動での役割などを通じて具体的なエピソードを交えると、読み手に伝わりやすくなります。
志望動機では、地方公務員として働く動機に加え、その自治体の取り組みや地域性に触れたうえで、自分の価値観や将来の目標とどのように結びつくのかを説明することが効果的です。
行政の取り組みに関心を持って調べていることが伝わると、説得力が増します。ガクチカでは、成果を強調しすぎず、取り組む中で感じたことや学んだことに焦点を当てることが大切です。
困難をどう乗り越えたか、周囲とどのように連携したか、自分の考えをどう活かしたかといった点に言及すると、人柄がより具体的に伝わるでしょう。
② PREP法を使って論理的に伝える
エントリーシートで印象を左右する要素のひとつが、文章の構成力です。いくら良い経験をしていても、それを筋道立てて表現できなければ、相手には伝わりません。
そこで有効なのが、「PREP法(プレップ法)」と呼ばれる文章の型です。
この方法は、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(まとめ)の順番で構成するもので、内容に一貫性を持たせつつ、説得力を高める効果があります。
たとえば、「私は責任感のある人間です」と述べたとします。
その場合、「なぜそう言えるのか」という理由を簡潔に述べた後、「アルバイトで売上管理を任され、月末には在庫と伝票の整合性を確認していた」などの具体的な行動を記述しましょう。
これにより、読み手は根拠と裏付けをもってあなたの強みを理解できます。PREP法の魅力は、情報の優先順位が整理されているため、読みやすく、印象に残りやすい点にあります。
面接でも質問が掘り下げられることが多いため、PREPを使って論理的な伝え方に慣れておくと、面接対策としても役立つでしょう。
たとえば志望動機では、「○○市を志望するのは地域住民の声を政策に反映している点に共感したからです」とまず結論を述べましょう。
「他市に比べて市民参加型の政策づくりに力を入れていると感じたからです」と続け、「実際に市民会議に参加した経験を通じて、その姿勢に感銘を受けました」と具体例を示すことで、深みが生まれます。
PREP法は一見シンプルですが、効果的に使うためには主張と根拠を明確にし、経験に裏打ちされた事実を簡潔に伝える練習が必要です。
事前に何度か文章を作り直し、声に出して読み上げることで、自然な構成に仕上がるでしょう。
③ 自治体や職種に合わせた具体的な内容にする
エントリーシートで差がつくポイントのひとつが、「その自治体や職種にどれだけ関心を持ち、理解しているか」という点です。
多くの就活生が陥りがちなのが、どの自治体にも当てはまるような、抽象的な志望動機や自己PRを書いてしまうことです。
これでは、自分の思いや適性が相手に伝わらず、結果的に埋もれてしまう可能性が高いでしょう。
まず、自治体については、人口規模や地域の課題、近年取り組んでいる施策などを具体的に調べることが大切です。
たとえば、高齢化や子育て支援、地域活性化、災害対策など、自治体ごとに重点を置いている政策は異なります。
志望する自治体が注力している事業や活動に、自分の経験や関心を結びつけて語ると、「この人はうちの仕事に本気で関心を持っているな」と思ってもらえるはずです。
さらに、職種によって求められる資質やスキルは大きく異なります。事務職であれば、調整力や計画性、正確性が重視される一方、土木職であれば専門知識や現場対応力が求められます。
職種ごとの業務内容を理解したうえで、自分がどのように活躍できるかを具体的に示すことが重要です。
たとえば、「地域イベントの企画運営に携わった経験を活かし、地域住民と行政の橋渡し役として貢献したい」といった表現は、経験と職務の接点を示すよい例でしょう。
大切なのは、自治体や職種の特性を理解したうえで、自分の意欲と一致点を具体的に示すことです。
抽象的な表現ではなく、「なぜあなたでなければならないのか」を読み手に納得させられるような内容に仕上げてください。
地方公務員の志望動機の例文

「地方公務員として働きたいけれど、どんな志望動機を書けばよいか分からない」と悩んでいませんか?
ここでは、受験する自治体や職種ごとに適した志望動機の例文を紹介します。
公務員試験の志望理由作成で迷ったときに、ぜひ参考にしてください。
- 市役所・町村役場向けの志望動機例文
- 都道府県庁(行政職)向けの志望動機例文
- 専門職・公安職向けの志望動機例文
- 大学での学びを活かした志望動機例文
- 民間企業との違いを意識した志望動機例文
- 自治体の政策や取り組みに共感した志望動機例文
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①市役所・町村役場向けの志望動機例文
ここでは、市役所や町村役場を志望する方に向けた志望動機の例文をご紹介します。地域密着型の公務員として、どんな想いを伝えるとよいかの参考にしてください。
《例文》
| 私が市役所を志望する理由は、地元であるこの街に恩返しがしたいと考えたからです。 大学時代、地域のボランティア活動に参加し、高齢者の見守りや清掃活動を通じて、住民同士のつながりの大切さを実感しました。 この経験から、暮らしやすい地域づくりには行政の力が欠かせないと感じ、市役所で地域福祉の分野に携わりたいと考えるようになりました。 住民の声に耳を傾け、課題をひとつひとつ解決していくことが、市の未来を支える力になると信じています。 地元に密着した行政の現場で、地域の安心と活気を支える一員として貢献していきたいです。 |
《解説》
地域への想いや、学生時代の具体的な体験を通じて公務員を志した背景を伝えると、説得力が増します。地元との関わりや、自分の目指す分野を明確にすることがポイントです。
②都道府県庁(行政職)向けの志望動機例文
ここでは、都道府県庁の行政職を目指す方に向けた志望動機の例文をご紹介します。県全体の課題に向き合い、広い視野で行政に関わりたい方は参考にしてください。
《例文》
| 私が都道府県庁の行政職を志望するのは、広域的な視点から地域全体の課題に取り組みたいと考えたからです。 大学で地域経済について学ぶ中で、人口減少や産業の空洞化といった課題が、都市部だけでなく中山間地域にも大きな影響を与えていることを知りました。 実際にゼミのフィールドワークで県内の農村地域を訪れた際、高齢化による担い手不足や交通の課題を目の当たりにし、自分にできることは何かを考えるようになりました。 都道府県庁の行政職として、地域間のバランスを考慮した政策づくりや調整役としての役割を担い、暮らしやすい県づくりに貢献したいと考えています。 |
《解説》
大学での学びと現地での体験を組み合わせることで、課題への理解と行動意欲をアピールできます。広域的な視点や調整力を重視する姿勢が効果的です。
③専門職・公安職向けの志望動機例文
ここでは、専門職や公安職を目指す方に向けた志望動機の例文をご紹介します。専門知識や使命感をどう志望動機に落とし込むかがポイントです。
《例文》
| 私が公安職を志望するのは、地域の安全を守るという使命感に強く惹かれたからです。 大学時代に、地域の防犯ボランティア活動に参加し、通学路の見守りや夜間パトロールを経験しました。 その中で、住民の方から「ありがとう」と声をかけてもらったことがきっかけで、安全な暮らしを支える仕事に誇りを持てるようになりました。 特に、災害時や事件発生時に迅速に動ける判断力と冷静さを身につけたいと考え、公安職として日々の訓練にも全力で取り組みたいと思っています。 社会の安心と秩序を守る一員として、責任感を持って職務に励みたいです。 |
《解説》
志望動機には、具体的な体験と「なぜこの職種か」の理由を明確に入れましょう。使命感や責任感を伝えることが重要です。
④大学での学びを活かした志望動機例文
大学で学んだ内容を、公務員としてどう活かしたいかを述べる志望動機は説得力が高まります。ここでは、学問と行政のつながりを意識した例文をご紹介します。
《例文》
| 大学で福祉政策について学ぶ中で、支援が必要な人に届きにくい制度の仕組みに課題を感じました。 特に、子育て支援や高齢者福祉では、制度は整っていても情報が届かないことや、地域によって支援に差がある現状を知りました。 ゼミ活動で行った調査では、住民の声を直接聞くことで、制度の「使いやすさ」が重要であると実感しました。 私は地方公務員として、住民にとってわかりやすく、利用しやすい制度づくりに関わりたいと考えています。 大学で培った知識と分析力を活かし、現場の声を反映した政策立案に貢献していきたいです。 |
《解説》
大学での専門分野と志望先の業務をつなげて説明すると、志望動機に具体性が出ます。「何を学び、何に気づいたか」が明確だと印象が良くなります。
⑤民間企業との違いを意識した志望動機例文
民間企業との違いに着目した志望動機では、「安定」だけでなく「社会貢献」や「公共性」に注目しましょう。ここでは、民間企業との違いを意識した内容の例文をご紹介します
《例文》
| 就職活動を進める中で、民間企業と公務員の違いについて深く考えるようになりました。 民間企業では利益を追求する一方、公務員は利益を超えた公共性を大切にしている点に惹かれました。 大学時代、地域イベントの企画に携わった際、行政の支援によって多くの住民が安心して参加できた経験が印象に残っています。 一人ひとりの暮らしを支えるために、利益を度外視してでも必要な支援を行う姿勢に感銘を受け、地方公務員として人の生活に直接関わる仕事がしたいと強く思いました。 地域に根ざし、持続可能なまちづくりに貢献したいと考えています。 |
《解説》
民間と公務員の違いを具体的に述べると説得力が増します。その上で、公務員ならではのやりがいや志向性を示すと良い印象を与えます。
⑥自治体の政策や取り組みに共感した志望動機例文
自治体の特色ある取り組みに共感したことを伝える志望動機は、志望度の高さをアピールするのに有効です。ここでは、自治体の政策や取り組みに強く共感した内容の例文をご紹介します
《例文》
| 私がこの自治体を志望した理由は、子育て支援に力を入れている姿勢に深く共感したからです。 大学で少子化問題について学ぶ中で、自治体独自の取り組みが出生率に影響を与えることを知りました。 貴市では、産後ケアや地域子育て支援センターの設置など、実際に子育て家庭の声を政策に反映させている点に魅力を感じました。 将来的には、現場の声を活かした政策立案や運営に携わり、安心して子育てできる地域社会の実現に貢献したいと考えています。 自治体の方針に共感し、その実現に自らも関わりたいという想いが志望の大きな動機です。 |
《解説》
自治体独自の取り組みに言及することで、企業研究や志望度の高さを示せます。具体的な施策を挙げて自分の想いと結びつけましょう。
地方公務員を目指す上で知っておくべきポイントを押さえておこう!

地方公務員になるには、職種の理解から試験対策、志望動機の作成まで、幅広い準備が必要です。
まず、地方公務員とは何かを理解し、自分に合った職種(行政職や技術職、福祉職など)を見極めることが大切です。
また、安定した年収や社会貢献性など、公務員ならではのメリットを踏まえ、自分が地方公務員に向いているかを見つめ直すことも重要です。
加えて、試験日程の確認や受験資格のチェック、エントリーシートの作成まで、段階的なステップを踏むことで合格に近づけます。
地方公務員を目指すには、明確な目的意識と計画的な準備が不可欠です。PREP法を活用しながら、自分の志望を論理的に整理して挑戦しましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










