公務員の福利厚生を完全網羅|手当・保険・年金制度まで詳しく解説
「公務員って福利厚生がいいって聞くけど、実際どんな制度があるの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
公務員は法律に基づいた制度設計により、全国共通かつ手厚く安定した福利厚生が整っています。
この記事では、手当・休暇・保険・年金・祝い金や見舞金まで、公務員の福利厚生を網羅的に解説します。
安定した働き方を重視したい方は、ぜひ参考にしてください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
福利厚生とは?

福利厚生とは給料とは別に、働く人の生活や健康を支えるために企業や団体が提供するさまざまな制度やサービスのことを指します。
健康保険や年金といった「法定福利」はすべての企業に導入が義務付けられており、住宅手当や社員食堂、育児支援などの「法定外福利」は各組織が独自に整備している内容です。
公務員の場合、この福利厚生が安定して充実している点が大きな特徴で、制度の差は将来の生活や働き方に直結するため、給料や仕事内容だけでなく福利厚生の中身も確認することが自分に合った働き方を見つける手助けになるはずです。
民間企業と公務員の福利厚生の違い

公務員と民間企業の福利厚生には、大きな違いがあります。制度の成り立ちや保障の内容、そして継続性など、それぞれの特徴を知っておくことで、自分に合った就職先を見極めやすくなるでしょう。
ここでは、3つの観点からその違いを整理して紹介します。
- 福利厚生の制度設計
- 福利厚生の手厚さ
- 福利厚生の安定性と継続性
① 福利厚生の制度設計
公務員と民間企業では福利厚生の制度設計そのものが根本的に異なっています。
公務員の福利厚生は国家公務員法や地方公務員法などの法令に基づき全国共通の基準で運用され、職場や地域による格差がほとんどなく、誰もが一定水準の制度を受けられる安心感があるでしょう。
一方、民間企業は各企業が独自に設計し、業種や企業規模、企業文化によって制度の内容や充実度に大きなばらつきがあります。
公務員は平等性や安定性が重視され、民間企業には柔軟性や独自性という魅力があるため、制度の有無だけでなくその設計意図や実態もよく見ておく必要があるでしょう。
② 福利厚生の手厚さ
福利厚生の手厚さでは、公務員のほうが安定して充実しているといえます。
公務員は法律により住宅手当・扶養手当・通勤手当など多岐にわたる手当が明確に整備され、育児休業や介護休暇も取得率が高く安心してライフイベントと向き合える環境です。
民間企業にも独自のサポート制度やユニークな福利厚生を設ける企業は多いものの、制度の実態にはばらつきがあり、名目上存在していても使いにくいケースもあります。
公務員は制度が法律で定められているため公平性が高く利用しやすい環境が整っており、見かけだけでなく制度が実際に機能しているかどうかを見極めることが重要でしょう。
③ 福利厚生の安定性と継続性
福利厚生の安定性や継続性では公務員の制度は非常に優れています。 公務員の福利厚生は国や自治体が直接管理し、景気変動や企業業績に左右されにくく、経済悪化時でも急に手当が廃止される可能性は極めて低いです。
制度改正があっても法令や条例の見直しによる透明性のある手続きが踏まれます。一方、民間企業の福利厚生は経営状況に影響を受けやすく、業績悪化時には制度が削減・廃止されることも珍しくありません。
公務員は長期的に安定した環境で働ける可能性が高く、民間企業にはスピード感のある制度改革や時代の変化への柔軟対応力があるため、どちらを選ぶかは個人の価値観やライフプラン次第といえるでしょう。
公務員の福利厚生の全体像(共済組合・互助会・自治体の制度)

公務員の福利厚生は、民間企業とは異なり、共済組合や互助会、自治体独自の制度など複数の仕組みによって支えられています。就職を考えるうえで、その全体像を理解しておくことはとても大切です。
ここでは、それぞれの制度がどのような役割を果たしているのかを、わかりやすく解説します。
- 自治体による福利厚生
- 共済組合による福利厚生
- 互助会による福利厚生
- 職員厚生会による福利厚生
① 自治体による福利厚生
自治体による福利厚生はその地域に住む職員の生活に密着した支援を提供する制度で、全国一律ではなく自治体ごとに特色があります。
主な支援には、住宅手当・通勤手当・扶養手当・育児支援制度があり、都市部では高い家賃負担軽減のための手厚い住宅手当や、子育て支援として保育園との提携や補助金支給を行うケースもありますよ。
勤務時間の柔軟化や時短勤務制度など育児・介護と仕事の両立支援も進められており、民間企業と比べて制度の継続性と信頼性が高く、志望する地域がある場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
② 共済組合による福利厚生
共済組合は公務員の生活基盤を支える根幹的な存在で、医療・年金・保険に関する制度を中心に幅広いサポートを行っています。
民間の健康保険組合に相当しますが、医療費補助が手厚く、外来・入院・手術費用の一部負担軽減や高額療養費制度がありますよ。
育児休業中や病気療養中でも一定の給付が受けられ、結婚祝金や出産手当金などライフイベント支援も含まれており、年金についても一定の厚生年金水準が維持されているため、目立たない存在ながらも非常に重要な制度といえるでしょう。
③ 互助会による福利厚生
互助会は同じ職場で働く職員同士が自発的に支え合う仕組みで、共済組合とは異なる側面から生活をサポートしています。
結婚・出産・入学・退職などの節目の祝金や、病気・災害・不幸時の見舞金制度がありますよ。
職員交流促進のための日帰り旅行・忘年会・スポーツ大会なども開催され、職場内の人間関係構築が進み円滑なコミュニケーションやチームワークにつながります。
とくに若手職員にとってはこうしたつながりが仕事への安心感や帰属意識になり、長く働き続けるうえでの重要な要素となるはずです。
④ 職員厚生会による福利厚生
職員厚生会は職員の余暇や生活の質を高めるための福利厚生を提供する組織で、仕事以外の時間を豊かに過ごすことを目的としています。
レジャー施設の割引・映画鑑賞助成・スポーツ観戦チケット優待・旅行パッケージや宿泊施設割引など多岐にわたり、金銭的負担軽減だけでなく仕事への意欲や心の余裕にも直結するでしょう。
厚生会主催のクラブ活動や文化講座もあり職員同士の交流機会が増え、特に新規採用者には職場へのなじみやすさを高めるきっかけとなります。
仕事と生活のバランスを整えながら安心して働き続けられる環境づくりに大きく貢献しているのが、職員厚生会の役割といえるでしょう。
公務員の福利厚生「手当」について

公務員の手当は、給与とは別に支給される補助金で、勤務環境や生活状況に応じてさまざまな種類があります。民間企業とは異なる特色があり、安定した生活を支えるための重要な仕組みです。
ここでは、代表的な公務員の福利厚生における手当の内容を紹介します。
- 地域手当
- 特殊勤務手当
- 時間外勤務手当(超過勤務手当)
- 期末手当・勤勉手当
- 管理職手当
- 扶養手当
- 住居手当
- 単身赴任手当
- 特地勤務手当
- 通勤手当
- 退職手当
① 地域手当
地域手当は、勤務地による物価や生活費の違いに対応して支給されます。
たとえば東京23区内や大阪市内など、物価が高い地域で勤務する職員には、地方の職員よりも高めの手当が支給される仕組みです。
これは公平性を保つ目的もあります。同じ職務であっても、住む地域によって家賃や食費などが大きく異なるため、生活の基盤を支える制度として機能しています。
公務員は全国に配置される可能性があるため、勤務地が変わると手当も変動します。配属先を希望する際や将来的な異動を考える際にも、地域手当の仕組みを知っておくと安心です。
地域による生活費の差に配慮された制度であり、生活の安定を図るための重要な支援策といえるでしょう。
② 特殊勤務手当
特殊勤務手当は、通常の業務と比較して特別なリスクや負担を伴う業務に対して支給される手当です。たとえば災害対応業務、夜間や早朝の勤務、感染症が蔓延する環境での業務などが対象となります。
これらの業務には肉体的・精神的なストレスがかかることが多く、職員のモチベーションや安全への配慮が欠かせません。
特殊勤務手当があることで、そうした厳しい現場でも職員が安心して働ける環境づくりに繋がるでしょう。
また、災害派遣や危険物の取り扱いなど、一般の人が避けたがるような仕事でも、責任を持って対応する職員の努力に報いる制度でもあります。
③ 時間外勤務手当(超過勤務手当)
時間外勤務手当は、定められた勤務時間を超えて働いた時間に応じて支給される手当です。特に年度末や予算関連の業務、緊急対応などにより、残業が発生することは少なくありません。
一般には「公務員は残業がない」というイメージがありますが、実際には業務の繁忙期や災害・事故対応などで長時間勤務になる部署もあります。
そのようなケースでも、時間外勤務手当があることで、労働に対する正当な対価が保障されているのです。
また、労働時間を正確に記録する体制が整っており、サービス残業を抑制する意識も高まっています。就職先を選ぶうえで、残業時間に関する制度や実態は重要な判断材料になるでしょう。
働いた分がしっかり評価される仕組みがあることで、職員の負担を適正に分配し、長期的な勤務継続にもつながっています。
④ 期末手当・勤勉手当
期末手当と勤勉手当は、公務員のボーナスに相当する支給制度で、通常は年2回に分けて支給されます。期末手当は固定的に支給される一方、勤勉手当は勤務成績や評価に応じて変動する仕組みです。
この制度は、日頃の業務に対するインセンティブを与える役割も担っています。努力や成果が正当に評価されることは、働く上での大きなモチベーションになるでしょう。
また、公務員のボーナスは民間企業のように業績に大きく左右されることが少ないため、将来の生活設計が立てやすいという利点があります。
就職活動中の学生にとって、安定的に支給される手当があることは、経済面での安心材料となるでしょう。働きがいと生活の安定を両立させる制度として、多くの公務員にとって重要な支えになっています。
⑤ 管理職手当
管理職手当は、係長、課長、部長など、一定の役職に就いた職員に支給される手当です。組織の運営に関わる意思決定や、部下の指導・マネジメントといった責任の重さに見合った報酬といえます。
公務員の世界でもキャリアアップが求められ、年齢や経験に応じて昇進の道が用意されています。その中で、管理職になることで業務量が増える一方、報酬面でもそれをカバーする仕組みが整っているのです。
役職者には、通常の業務に加えて人材育成や組織運営の能力が求められます。そうした能力や努力が適切に評価される点は、公平性のある制度といえるでしょう。
将来的に上位職を目指す場合には、この手当の存在も意識してキャリアを描くことが大切です。
⑥ 扶養手当
扶養手当は、配偶者や子ども、高齢の親などを扶養している場合に支給される手当です。家族構成や扶養人数に応じて金額が決まるため、それぞれの生活に合った支援が受けられます。
特に子育て世帯や介護を抱える家庭では、経済的な支援として大きな助けになるでしょう。
また、配偶者が働いていない場合や、子どもが一定年齢未満である場合など、状況に応じた加算もあります。就職後のライフイベントに備え、家族の支援体制がしっかり整っていることは安心材料です。
この手当を活用すれば、仕事と家庭の両立もより現実的なものになるでしょう。
⑦ 住居手当
住居手当は、賃貸住宅に住む職員に対して家賃の一部を補助する制度です。月々の家賃が一定額を超える場合、その負担を軽減するための支援として活用されています。
とくに都市部では家賃が高くなりがちですが、この手当があることで生活コストを抑えられます。新社会人として一人暮らしを始める際や、転勤によって住まいを変更する場合にも役立つでしょう。
上限はありますが、家計を支える補助としては心強い存在です。自宅通勤が難しい勤務地を希望する際や、希望勤務地が高額家賃エリアの場合は、この制度の活用が現実的な選択を広げてくれますよ。
⑧ 単身赴任手当
単身赴任手当は、家族を残して遠方の勤務地へ一人で赴任する職員に支給される手当です。住居費や交通費、生活費が二重にかかるケースが多いため、それを補う目的で設けられています。
公務員は全国に異動の可能性がある職種であり、転居を伴う配属も珍しくありません。その際、家族の事情などで一緒に引っ越すことができない場合、この手当が大きな支えになります。
手当の対象には、家賃の補助だけでなく、定期的な帰省のための旅費補助なども含まれる場合があり、離れて暮らす家族とのつながりを維持するうえでも、心強い制度といえるでしょう。
⑨ 特地勤務手当
特地勤務手当は、離島、山間部、寒冷地など、生活条件が厳しい地域で働く職員に支給される手当です。
こうした地域は物資の輸送費や暖房費が高く、生活そのものにコストがかかるため、その負担を軽減するという目的があるのです。
また、都市部に比べて医療機関や公共サービスが限られている場合もあり、生活の不便さを補うための意味合いも含まれています。
勤務地が限定されない公務員にとって、この手当は働く場所の選択肢を広げる要素のひとつになります。地方や離島での仕事を前向きに考える際にも、心のハードルを下げてくれる制度といえるでしょう。
⑩ 通勤手当
通勤手当は、自宅から職場までの通勤にかかる交通費を補助する手当です。
この手当の目的は、職員の経済的負担を軽減すると同時に、通勤の継続性を支援することにあります。
通勤費が高額になる地域では、手当の有無が生活に直接影響することも少なくありません。
自動車通勤が認められている自治体では、ガソリン代相当の補助が出る場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
毎日の通勤を快適に、かつ負担を抑えて行えることは、働き続けるうえで非常に大切な要素です。制度を理解して、自分に合った通勤スタイルを見つけてください。
⑪ 退職手当
退職手当は、公務員としての勤続を終える際に支給される一時金で、いわばキャリアの集大成としての報酬です。
支給額は、勤続年数や最終的な給与額をもとに算出され、長く働いた人ほど金額も大きくなります。
この手当は、退職後の生活基盤を支える重要な資金源の1つです。とくに年金が支給されるまでの空白期間を埋める資金としても有効に使われています。
若いうちは退職後の生活を実感しにくいかもしれませんが、将来的な安定を見据えた長期的視点で見ると、非常に頼れる制度だといえるでしょう。
公務員の福利厚生「休暇制度」について
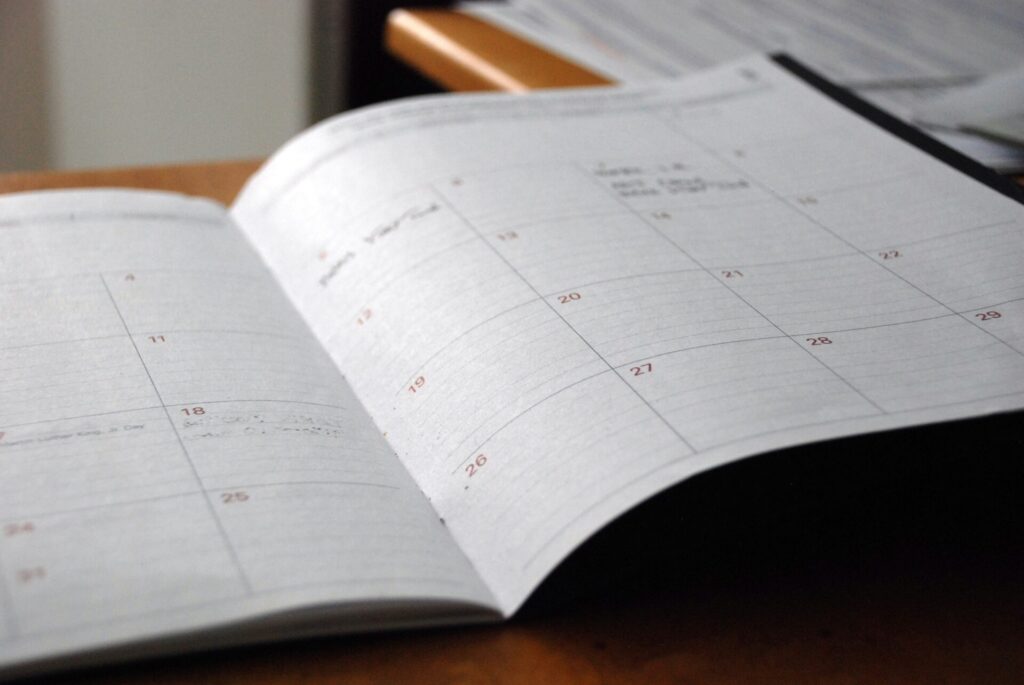
公務員の福利厚生の中でも、休暇制度は安定志向の就活生にとって特に関心の高い要素です。年間休日の多さや有給の取りやすさ、ライフイベントや育児への対応まで、その手厚さには多くの魅力があります。
ここでは、公務員の代表的な休暇制度についてわかりやすく解説します。
- 年間休日
- 年末年始や夏季の休暇日数
- 年次有給休暇
- 病気休暇
- 結婚・忌引・出産などの休暇制度
- 育児や看護、ボランティアなどに対応した休暇制度
① 年間休日
公務員は、一般的に土日祝日がしっかり休める体制が整っており、年間休日は120日から125日程度確保されています。
これは民間企業の中でも休みが多いとされる企業と見劣りしない水準で、休日がカレンダー通りに設定されているため予定が立てやすく、家族や友人と過ごす時間も確保しやすいでしょう。
ただし警察や消防、医療関連などの現場では交代制勤務や24時間対応の必要があるため、希望する職種の勤務体系を事前確認することが大切です。
安定した休日が得られる点で公務員は働きやすさの面でも魅力的な選択肢といえるでしょう。
② 年末年始や夏季の休暇日数
公務員は、年末年始は原則12月29日から1月3日までの6日間が確保され全国の行政機関で一律実施されています。
夏季休暇は一般的に5日程度の特別休暇が与えられ、7月から9月の間で希望に応じて取得可能で、帰省や旅行などプライベートの充実にも役立ちます。
繁忙期には希望通りの日程で取得できないこともありますが、別の日に振り替えて取得可能で、分散取得を奨励する職場もあり柔軟に対応できます。
一定のタイミングで確実に休める制度があることは、働くうえでの精神的な余裕にもつながりますよ。
③ 年次有給休暇
年次有給休暇は公務員として働くうえで重要な福利厚生のひとつで、公務員の職場では取得率が比較的高く、実際に使いやすい環境が整っているのが特徴的です。
採用から6か月経過すると15日間の有給休暇が付与され、その後は毎年20日ずつ加算され、最大40日まで繰り越し可能で計画的に活用すれば長期休暇としてまとめて取得できます。
昨今では、体調不良や私用だけでなく自己啓発や家族行事など多様な理由での取得も認められ、組織として有給取得を促進する動きがありますよ。
また、公務員は気兼ねなく申請できる雰囲気があり、公務員の有給休暇制度は安心材料のひとつといえるでしょう。
④ 病気休暇
公務員には体調を崩した際に安心して療養できるよう、病気休暇の制度が用意されており、突然の発熱やケガなど短期間の休養から長期間の治療を要する病気まで対応できる制度が整っています。
短期であれば医師の診断書なしで数日間の取得が可能なケースもあり、長期の休養が必要な場合は診断書提出により長い期間の休暇が認められ、必要に応じて復職支援なども併用できますよ。
給与面でも一定期間は全額または一部が支給され経済的負担を軽減でき、自分や家族の健康が不安なときでも無理せず働き続けられる環境が整っていることは公務員という職業の大きな魅力のひとつです。
⑤ 結婚・忌引・出産などの休暇制度
公務員には人生のさまざまな節目に対応する特別休暇が設けられています。
例えば、結婚の場合は5日間程度の結婚休暇、家族に不幸があった際は親族の続柄に応じて2日から7日程度の忌引休暇、配偶者の出産時には「出産補助休暇」などの制度が用意されていますよ。
これらの休暇は実際に取得されやすい雰囲気や文化が根づいている点で他の職種とは一線を画しており、仕事と生活のバランスを大切にしたい人にとって公務員の働き方は理想に近いといえるでしょう。
⑥ 育児や看護、ボランティアなどに対応した休暇制度
公務員の休暇制度は、育児や介護といった家庭の事情、さらに社会貢献活動にも柔軟に対応しているのが特徴です。
育児休業は子どもが3歳になるまで取得可能で状況に応じて延長もでき、小学校入学までは短時間勤務制度や看護休暇など育児と両立しやすい働き方が選べます。
例えば、介護を必要とする家族がいる場合は、「介護休暇」や「部分的な勤務時間短縮制度」があり、地域活動や災害支援などのボランティアに対しても特別休暇が与えられる環境が整っていますよ。
キャリアを重ねながら家庭や地域とも関わりたい人にとって。公務員の休暇制度は非常に心強いサポートとなるでしょう。
公務員の福利厚生「保険制度」について

公務員が受けられる保険制度は、安心して長く働ける環境づくりの大きな要素となっています。とくに病気やケガ、育児、災害など人生の節目で支援が得られる点は、民間企業との大きな違いです。
ここでは、公務員の保険制度における代表的な3つの給付内容を紹介し、それぞれの仕組みやメリットを詳しく解説します。
- 保険給付
- 休業給付
- 災害給付
① 保険給付
保険給付は、公務員が病気やケガで医療機関を受診したときに支給される保障のことです。公務員は民間の健康保険ではなく「共済組合」に加入しており、そこから医療費の一部を補助してもらえます。
自己負担は原則として3割ですが、高額な医療費がかかる場合には高額療養費制度が適用され、負担額が一定の上限を超えないようになっています。
さらに、医療費だけでなく出産育児一時金や、本人や家族の死亡時に支給される葬祭費などの給付も含まれているのが特徴です。こうした給付は、家庭の経済的負担を大きく減らしてくれるでしょう。
② 休業給付
休業給付は、公務員が業務以外の理由で休職せざるを得ない状況になった際、一定の収入を確保できるよう支援する制度です。
たとえば、病気やケガによる療養、出産後の育児、家族の介護といった事情があるときに利用されます。
具体的には、休業手当や育児休業給付金、介護休業給付金などが含まれており、それぞれ共済組合を通じて支給されますよ。
民間企業でも似たような制度は存在しますが、公務員のほうが給付率が高かったり、支給期間が長かったりすることが多いのが特徴です。
③ 災害給付
災害給付は、公務員が勤務中や通勤中に事故や災害などに巻き込まれ、ケガや病気を負った場合に支給される保障制度です。
このようなケースは「公務災害」として扱われ、共済組合から治療費や療養手当が支給される仕組みとなっています。
治療にかかる医療費は原則として全額が給付対象となるため、自己負担がなく、長期的な療養を要する場合でも経済的な心配は少なくて済むでしょう。
また、障害が残った場合には障害補償があり、死亡時には遺族への給付金も支給されるなど、非常に手厚い保障内容です。
公務員の福利厚生「年金制度」について

公務員として働く上で、将来の生活設計に関わる「年金制度」はとても大切なポイントです。民間企業とは仕組みが異なる部分もあるため、あらかじめ正しく理解しておくことで安心につながるでしょう。
ここでは、公務員の年金制度について、仕組みや違いをわかりやすく紹介します。
- 共済年金
- 厚生年金
- 長期給付事業
① 共済年金
かつて公務員の年金制度といえば「共済年金」が中心で、公務員や教職員など特定の職業に就いている人を対象にした独自の制度として民間の厚生年金とは分離して運用されていました。
2015年10月の年金制度改革で厚生年金に統一されるまで長らく公務員の老後を支える基盤で、給与水準が安定している公務員に合わせて設計され受給額も高くなる傾向がありました。
民間にはない「職域加算」という上乗せ給付も存在していましたが現在は廃止され、過去に加入していた人の中には一定条件下で加算が続く場合もあります。
② 厚生年金
現在の公務員は民間企業の会社員と同様に厚生年金に加入し、2015年の制度統一によって従来の共済年金が廃止され、厚生年金へ一本化されたことによるものです。
制度としては公務員と民間の年金制度は原則同じ枠組みで、保険料の支払いや受給の仕組みも共通しており、転職や異動の際にも年金記録が引き継がれやすく制度上の不都合が生じにくい点は安心材料でしょう。
ただし公務員には「年金払い退職給付」と呼ばれる上乗せ制度が存在し、以前の職域加算に代わる形で退職金相当額を年金形式で受け取れますよ。
民間と同等の年金制度でありながら公的な立場ならではの安定感や制度の信頼性があり、今もなお公務員の大きな強みとなっています。
③ 長期給付事業
長期給付事業は、公務員共済組合が実施している独自の給付制度で、老齢・障害・遺族といった状況に応じて金銭的な支援を行う仕組みです。
国の年金制度と連携しつつも共済独自の内容で構成され、「障害共済年金」や「遺族共済年金」などが含まれ、通常の厚生年金だけではまかないきれない事態に備えるために設けられています。
長期給付事業の対象者は2015年以前に共済年金に加入していた人に限られる場合が多く、制度改革以降の新規採用者には適用されないこともありますが、過去に整備された制度が一部残っている背景には公務員制度の継続性や組織的安定性への配慮があるでしょう。
公務員の福利厚生「祝金・見舞金・弔慰金」について

公務員の福利厚生は、給与以外にも生活を支える制度が充実しています。特に「祝金」「見舞金」「弔慰金」は、人生の大きな節目や思いがけないトラブル時に経済的な支えとなる重要な仕組みです。
ここでは、それぞれの支給制度の内容や具体例を紹介しながら、公務員という働き方が持つ安定性と安心感についても触れていきます。
- 結婚や出産などで支給される祝金
- 入院や災害時に支給される見舞金
- 身内の不幸の際に支給される弔慰金
① 結婚や出産などで支給される祝金
公務員には人生の節目を祝うための「祝金」制度が整備されており、結婚祝いとして多くの自治体で3〜5万円程度、出産時も子ども1人につき数万円の祝金を受け取れます。
民間企業では会社ごとに制度の有無や支給額に差がありますが、公務員は制度が全国的に整備され内容も安定しているため、長期的なライフプランを立てやすいという点でも大きなメリットとなるでしょう。
② 入院や災害時に支給される見舞金
公務員には病気による入院や自然災害による被害など、予期せぬトラブルに備えて「見舞金」が支給される制度があります。
業務外の病気やケガによる入院が7日以上続いた場合に数千円から数万円、自然災害で住宅被害が出たときには被害の程度に応じて見舞金が支給されます。
民間企業では運用が不透明だったり業績次第で支給されないこともありますが、公務員の制度は規程に基づいており透明性と継続性が確保されているため、公務員という働き方が多くの人に支持される理由の1つとも言えるでしょう。
③ 身内の不幸の際に支給される弔慰金
公務員には、両親・配偶者・子どもなどが亡くなった場合、数万円〜10万円前後の弔慰金が支給され葬儀費用や供養費用として活用できます。
民間でも弔慰金制度が存在する場合はありますが内容や支給条件にばらつきがある一方、公務員の制度は公平でかつ明文化されているため信頼性が高く、安心して働ける環境を求めるなら公務員という選択肢は有力でしょう。
公務員の福利厚生について正しく知っておこう!
公務員の福利厚生は、民間企業と比較して制度設計が整っており、手厚さと安定性に優れています。
これは、共済組合や自治体、互助会など多層的な制度が連携し、公務員とその家族を長期的にサポートしているからです。
実際に、手当や休暇、保険、年金、祝金や見舞金など、公務員にはあらゆるライフステージに対応した支援が用意されています。
これにより、職員は安心して働き続けることができ、長期的なキャリア形成が可能です。福利厚生の充実度という観点から、公務員という働き方は非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










