公務員の平均給料と年齢別の推移を解説!
「公務員って安定してるって聞くけど、実際の給料はどれくらいもらえるの?」
そんな疑問を持つ方に、平均年収や年齢別の推移、ボーナスや手当の詳細までわかりやすく解説します。
さらに、民間企業との違いや福利厚生、公務員になるまでの流れも網羅しています。
就職・転職を検討している方にとって、今後のキャリア選択に役立つ内容をお届けしていきますね。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員の平均年収はどれくらい?

就職先として安定した人気を集める公務員ですが、実際にどのくらいの年収が得られるのかは、多くの就活生にとって関心事です。
ここでは、国家公務員と地方公務員に分けて、それぞれの平均年収の実態について詳しく解説します。
- 国家公務員の平均年収
- 地方公務員の平均年収
① 国家公務員の平均年収
国家公務員の平均年収は約680万円です^1。年齢や職種によっても差が出るものの、安定性の高さが魅力といえるでしょう。
大企業の総合職と同等か、やや下回る水準ですが、景気に左右されにくく、長期的に見て堅実なキャリアパスが期待できます。
公務員は年功序列型の昇給制度を基本としており、入省後は一定のペースで給与が上がっていきます。
また、残業手当や住居手当なども明確に支給されるため、将来設計が立てやすい点も利点です。家族を持つタイミングなどでの支援が手厚く、生活の安定を重視する人には向いています。
② 地方公務員の平均年収
地方公務員の平均年収はおおむね650万円前後となっています^2。
国家公務員と比較して大きな差はありませんが、所属する自治体によって支給額に幅があります。
例えば、東京都や横浜市など財政規模の大きい自治体では高めの傾向が見られますが、人口の少ない地域や財政状況が厳しい自治体では、相対的に低くなる場合もあります。
年収という表面的な数字だけで判断せず、自分がその地域や業務にどう向き合えるかを考えることが、公務員としての満足度を高める第一歩です。
- 出典1:https://www.jinji.go.jp/kankou/toukei/toukei-nenpou.html
- 出典2:https://www.soumu.go.jp/main_content/000901187.pdf
民間企業と公務員の給料・年収の違い

公務員の給料は「安定重視」、民間企業の給料は「成果連動型」と言えるでしょう。
初任給は国家一般職の大卒で約21万円程度と、民間と比べて控えめですが、そのぶん収入が大きく落ち込むリスクが少ない点が魅力です。
また、公務員は住宅手当や通勤手当のほか、育児休業制度、共済組合による医療支援など、働き続けやすい環境が整っています。定年後の年金や退職金が保証されている点は安心材料ですね。
民間企業でも大手になれば福利厚生は手厚い傾向にありますが、会社ごとの差が大きく、制度変更も起こり得る点には注意が必要です。
このように、公務員と民間企業では、給料の性質や将来の安定性に明確な違いがあるのです。
公務員の給料の仕組みと特徴

公務員の給料は民間企業とは異なるしくみで決まっており、安定した収入を期待できる点が特徴です。
ここでは給与制度の基礎を知るために、等級・号俸・俸給表の考え方や、給与調整に関わる人事院勧告制度、実際の給料日などをわかりやすく解説します。
- 等級・号俸・俸給表の仕組み
- 人事院勧告制度
① 等級・号俸・俸給表の仕組み
公務員の給料は、「俸給表」というルールに基づいて支給されます。この俸給表は「等級」と「号俸」の組み合わせによって基本給を決定するもので、非常に公平で透明性のある仕組みとなっています。
等級は職務の内容や責任の重さによって分けられ、号俸は勤続年数や実績に応じて段階的に昇給する設定です。
以下は、国家公務員(行政職)の俸給表(抜粋)です:
| 等級 | 号俸 | 月給(円) |
|---|---|---|
| 1級 | 1号 | 165,300 |
| 1級 | 5号 | 181,200 |
| 1級 | 10号 | 203,900 |
| 2級 | 1号 | 197,100 |
| 2級 | 5号 | 219,700 |
例えば、大学卒業後に国家公務員一般職として採用された場合、多くは「1級1号俸」からスタートします。その後、勤務年数が増えるごとに号俸が上がり、定期的に基本給が増加していきます。
また、昇任による等級アップは、上司からの推薦や試験、配置転換などによって決まる場合が多く、目指す役職によってそのプロセスは異なります。
将来的にどのポジションを目指すかによって、年収の見通しも変わってくるでしょう。
② 人事院勧告制度
人事院勧告制度とは、公務員の給与が民間企業の給与水準と大きくかけ離れないように調整するための仕組みです。
公務員の給与は民間の動向に応じて見直されます。例えば、ある年に景気が好調で多くの企業がベースアップ(基本給の引き上げ)を実施していたとします。
この場合、人事院は「公務員の給与を引き上げる」と指示し、それに従って国家公務員や地方公務員の給料も翌年度以降に調整されるのです。
特定の政権や幹部の意向で不当に給与が上がったり下がったりすることがないよう、公正かつ中立な立場で運用されています。
- 出典1:https://www.jinji.go.jp/saiyo/salary/kyuyo_1.html
- 出典2:https://www.jinji.go.jp/kankoku/kankoku/r05/2023gaiyou.pdf
年齢別に見る公務員の給料推移

公務員の給料は年齢とともに安定して上昇する傾向にあります。ここでは、20代から50代までの平均年収を年代別にご紹介します。
将来の生活設計に役立てくださいね。
- 20代公務員の平均年収
- 30代公務員の平均年収
- 40代公務員の平均年収
- 50代公務員の平均年収
① 20代公務員の平均年収
20代の公務員の平均年収は、280万円から400万円程度です。
新卒で入庁したばかりの段階では、年収300万円前後からのスタートとなるケースが多く、初任給の面では民間企業と大差ないか、やや劣ると感じるかもしれません。
しかし、公務員の給与は定期昇給制度に基づいて安定的に上がっていくため、数年後には確実に収入が増えていく見通しが立ちます。
勤続3年を超える頃には、職務内容が少しずつ専門的になり、それに応じた手当が支給されるため、実際の年収も目に見えて伸びていくでしょう。
② 30代公務員の平均年収
30代になると、公務員の平均年収は400万円から550万円ほどに達します。
この年代では、役職に就く人が増えはじめるタイミングでもあり、主任や係長といった肩書が付くことで役職手当が加算され、給与水準が上がる傾向があります。
さらに、配偶者や子どもがいる人には扶養手当が支給されるほか、住宅を購入した場合には住居手当やローン控除の対象になることもあります。
これらの制度が整っていることで、30代の生活基盤をより安定させられるでしょう。
③ 40代公務員の平均年収
40代に入ると、公務員の平均年収は600万円から700万円前後まで上がります。
この時期には、係長から課長補佐、課長クラスへの昇進も増え、責任範囲が拡大するのに伴って給与も増額されるのが一般的です。
医療費補助や育児・介護支援制度も充実しているため、生活面での支援を実感できる場面が増えるはずですよ。
今後のライフプランを立てるうえで、将来の退職金や年金額などを含めた総合的な収入設計を意識していくことが大切です。
④ 50代公務員の平均年収
50代の公務員になると、年収は750万円から850万円程度でピークを迎えます。多くの人が課長や部長などの管理職に就き、組織運営の中核を担う立場になります。
これにより役職手当や管理職手当が増え、実質的な収入が大きくなります。この年代は、定年後の人生設計を視野に入れる時期でもあります。
退職金や再任用制度、公的年金の受給見込みなど、今後の経済的基盤について具体的に考える機会が増えるでしょう。
一方で、年齢による昇給の伸びは緩やかになり、役職に就けなかった場合には年収が頭打ちになるケースも少なくありません。
職種別・種類別に見る公務員の給料

公務員といっても、職種や所属によって給料には違いがあります。
就職活動を進める中で、自分に合った働き方や将来設計を考えるためには、各職種ごとの収入の傾向を理解しておくことが大切です。
ここでは、国家公務員と地方公務員に分けて、給料の特徴を解説します。
- 国家公務員の給料の特徴
- 地方公務員の給料の特徴
① 国家公務員の給料の特徴
国家公務員の給料は、職務の専門性や役職に応じて決定されるため、個々のポジションによって収入の幅が大きく異なります。
中央省庁に所属する総合職では、国の政策立案に関わる業務が多く、責任も重いため、昇進のたびに大きく年収が上がる傾向があります。
一方、事務職などの一般職では、日々の行政運営に欠かせない実務を担い、昇給も比較的安定しています。
高収入を目指すのであれば、計画的なキャリアアップが不可欠ですね。
② 地方公務員の給料の特徴
地方公務員の給料は、各自治体が策定する給与表に基づいて支給されます。
東京都や横浜市、大阪市といった政令指定都市では、30代後半で年収600万円を超える例もあります。
一方、地方の中小自治体では、同じ年代でも年収が500万円前後にとどまるケースも見られます。地方公務員の大きな特徴として、地域密着型の業務が多い点が挙げられます。
これらの自治体では市民対応や福祉、教育、インフラ整備など、日常生活に密接に関わる分野で働け、住民の声を直接聞きながら仕事を進める場面も多くありますよ。
公務員のボーナス・手当
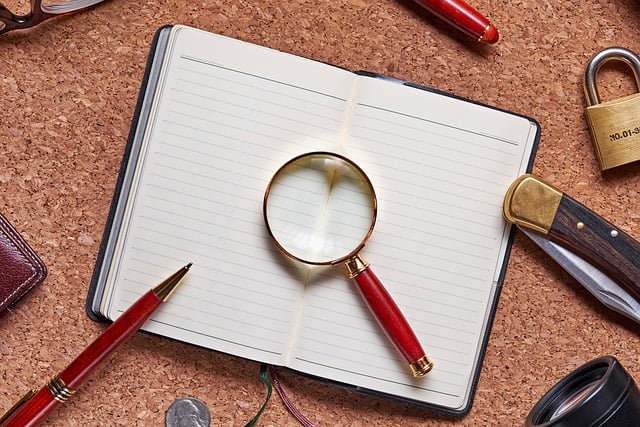
公務員は安定した職業という印象がありますが、実際のボーナスや手当の内容はあまり知られていません。
ここでは、公務員のボーナス支給額や手当の種類について詳しく解説します。収入の仕組みを理解することで、将来設計に役立つはずですよ。
- 公務員のボーナス支給額
- 公務員の手当の種類
① 公務員のボーナス支給額
公務員のボーナスは、年に2回(6月と12月)支給されるのが基本です。
平均的な年間支給額は140万〜170万円ほどで、景気による変動が比較的小さく、長期的に安定した収入の柱となっています。
ボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」で構成され、期末手当は役職・等級・勤続年数に応じて決定される一方、勤勉手当は勤務成績(人事評価)によって大きな差が生じます。
このため、同じ部署でも評価が異なれば支給額も異なるという仕組みになっています。
② 公務員の手当の種類
公務員の給与は、基本給だけでなくさまざまな手当から構成されています。
これらの手当は、勤務地・家族構成・通勤手段など職員の個別事情に応じて支給されるものであり、実際の手取り額に大きな影響を与えています。
代表的な手当には以下のようなものがあります。
| 手当名 | 概要 | 補足 |
|---|---|---|
| 地域手当 | 物価や生活費が高い地域に勤務する場合に支給 | 都市部では基本給の15〜20%が加算されることもある |
| 住居手当 | 賃貸住宅に住んでいる職員に家賃補助を支給 | 上限は約27,000円。持ち家は対象外 |
| 通勤手当 | 交通機関・通勤手段に応じて支給 | 公共交通機関以外に徒歩や自転車でも支給される場合あり |
| 扶養手当 | 配偶者や子どもを扶養している場合に支給 | 子ども1人につき月額1万円弱。配偶者の年収により対象外も |
これらの手当は、年間に換算すると数十万円規模に達する場合もあり、収入の実態を正確に把握するうえで無視できない要素です。
公務員を目指す際には、基本給だけでなく手当込みで実質収入を試算することが大切ですね。
公務員の福利厚生
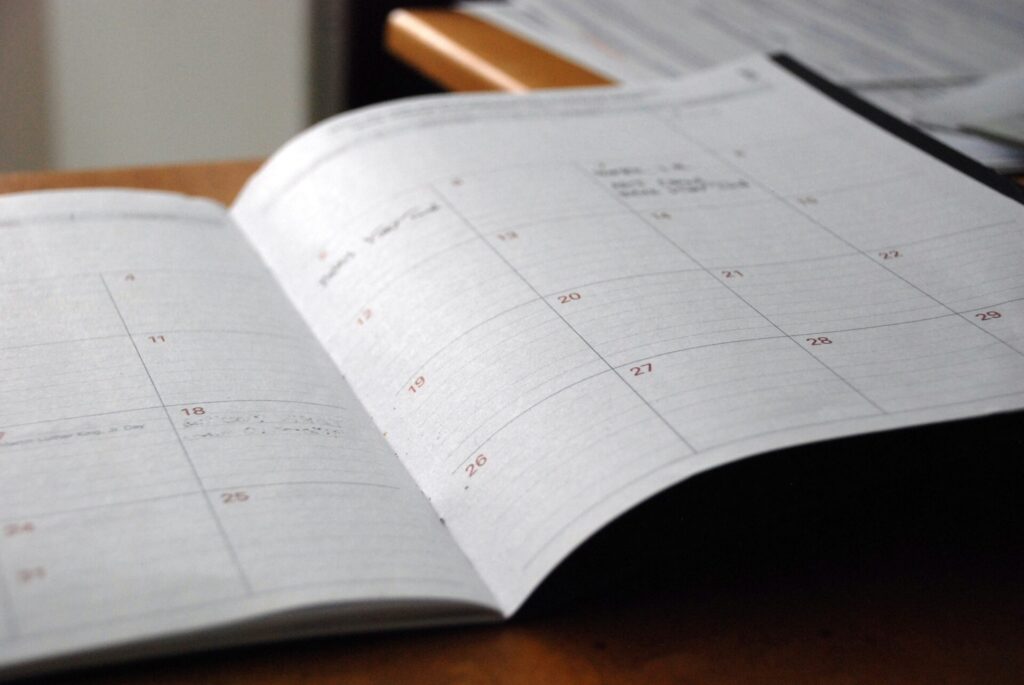
公務員の魅力のひとつは、充実した福利厚生制度にあります。民間企業と比べて制度が整っており、仕事と私生活の両立がしやすい環境が整っています。
ここでは、公務員の豊富な福利厚生について具体的に紹介します。
- 年次有給休暇・特別休暇
- 病気休暇・介護休暇・育児休業
- 共済組合制度
- 互助会制度
- 福利厚生施設の利用制度
- 退職金制度
① 年次有給休暇・特別休暇
公務員は、年20日間の年次有給休暇を取得する権利があり、これは初年度から発生します。未使用分は翌年度まで繰り越しが可能で、最大で40日分を保有できる制度設計になっています。
加えて、夏季休暇・結婚休暇・忌引・裁判員休暇などの特別休暇も種類豊富に用意されており、ライフイベントや緊急事態に対して柔軟に対応できます。
特に結婚休暇は最大で5日間の取得が可能で、民間企業と比べても優れた内容です。
また、職場によってはリフレッシュ休暇(節目年休)など、独自の休暇制度を導入している場合もあり、勤続年数に応じた特別な休みが得られることもあるのです。
② 病気休暇・介護休暇・育児休業
公務員には、健康や家庭の事情に対応するための休暇制度が幅広く用意されています。まず、病気休暇は原則有給で最大90日取得でき、うつ病やガンなど長期療養を要する病気にも対応可能です。
介護休暇は、家族の一時的な介護が必要なときに年5日(対象が2人以上なら10日)取得でき、さらに長期の支援が必要な場合は介護休業として最大6カ月程度の分割取得が可能です。
介護施設の利用や訪問介護との併用も認められています。育児休業については、原則1歳まで、保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長できます。
③ 共済組合制度
共済組合は、公務員にとって民間企業の社会保険に相当する制度であり、健康保険・年金・医療補助・貸付などを一体で運用しています。
特に医療費に関しては、一般の健康保険では対象外となる附加給付が存在し、自己負担分の一部が還付されます。
高額療養費制度も適用され、手術や長期入院でも負担が抑えられます。3割負担でも、一定金額を超えた分が戻る仕組みが整備されているのです。
④ 互助会制度
互助会は、公務員の職場で組織される相互扶助制度で、福利厚生の補完的役割を果たします。全国の官公庁や自治体ごとに設置されており、会員となることで多様な支援を受けることができます。
慶弔金としては、結婚・出産・子どもの入学などに対して祝い金が支給されるほか、不幸があった場合には弔慰金が支給されます。
また、チケット割引や共同購入制度など、日常生活に役立つ支援も用意されており、金銭的な負担を減らすだけでなく、精神的な安心感にもつながっています。
⑤ 福利厚生施設の利用制度
公務員は、共済組合や自治体が運営する保養所や研修施設、スポーツクラブなどの福利厚生施設を利用できます。
保養施設は全国にあり、観光地や温泉地などのリゾートに位置していることが多く、一般ホテルと比べて非常にリーズナブルな価格で宿泊可能です。
1泊数千円で利用できる施設もあり、家族旅行や友人とのレジャーに活用されています。
さらに、スキー場や温泉施設、フィットネスクラブと提携した割引制度も利用でき、健康増進やストレス解消に役立ちますね。
⑥ 退職金制度
公務員の退職金制度は、勤続年数と最終的な給与水準に基づいて支給額が決定されます。
30年以上勤務した場合、2,000万円以上の退職金を受け取ることもあり、民間企業と比べても安定性が高いのが特徴です。
退職理由に応じて支給額が異なり、定年退職の場合が最も多く、自己都合退職や勧奨退職などでは減額されるケースがあります。
加えて、共済組合からは退職共済年金や一時金の支給もあり、老後の生活資金としての役割を果たしますよ。
公務員になるには?採用までの流れと必要な準備

公務員を目指す就活生にとって、まず知っておきたいのは「どのようにして公務員になれるか」という具体的なステップです。
民間企業とは異なる選考プロセスや対策方法があるため、段階ごとのポイントを押さえて準備を進めることが大切でしょう。
ここでは、公務員になるまでの流れと必要な準備について、わかりやすく解説します。
- 志望先の選定
- 試験区分の確認
- 試験対策の準備
- 一次試験(筆記試験)
- 二次試験(面接・人物試験)
- 最終合格と採用手続き
① 志望先の選定
公務員といっても、国家公務員や地方公務員など職種はさまざまです。志望先を明確にすることは、効率的な準備を進めるうえで欠かせません。
国家総合職と地方初級職でも試験内容が異なり、求められる能力も違ってきます。
多くの就活生がイメージだけで志望先を選びがちですが、それでは入庁後にギャップを感じるかもしれません。業務内容や勤務地、待遇などを比較して、自分に合った進路を見つけてください。
志望先が定まれば、学習スケジュールや対策内容も具体的になります。モチベーションを保ちやすくなる点でも、早めに方向性を決めておくとよいでしょう。
② 試験区分の確認
志望先が決まったら、次は試験区分の確認です。公務員試験には、総合職・一般職・専門職などの区分があり、内容や難易度が大きく異なります。
大学生に人気の国家一般職や地方上級は、試験範囲が広く、長期的な準備が必要です。試験区分を誤ると、時間と労力を無駄にする可能性があります。
また、試験によっては年齢や学歴などの受験資格が設定されていることもあるため、募集要項をよく確認してください。
自分に合った区分を早い段階で把握することで、合格への近道になるでしょう。
③ 試験対策の準備
公務員試験は範囲が広く、科目数も多いため、計画的な対策が重要です。独学か予備校かで迷う学生も多いですが、大切なのは「自分に合った学習スタイル」を選ぶことです。
予備校は情報やサポートが充実している一方で、費用がかさみます。独学なら費用は抑えられますが、自己管理力や情報収集力が求められます。
いずれの場合も、過去問の分析と基礎の反復は欠かせません。特に教養試験対策では、毎日の積み重ねが得点力に直結します。
数的処理や文章理解などは慣れが重要なので、日々の練習を怠らないようにしましょう。
④ 一次試験(筆記試験)
一次試験では、主に筆記による教養試験や専門試験が行われます。教養試験では、数的処理や文章理解など、論理的思考力が問われます。苦手な分野がある場合は、早めの対策が必要です。
専門試験では、法学や経済学など、学部での知識が活かされることもありますが、試験特有の形式に対応するには過去問の研究が不可欠でしょう。
出題傾向や配点を把握しておくと、効率よく得点を狙えます。合格ラインは決して低くありません。安定して得点を重ねるためには、早期から計画的な学習を積み重ねることがカギです。
⑤ 二次試験(面接・人物試験)
筆記試験を通過すると、次は面接や人物試験が行われます。ここでは、知識よりも「人柄」や「志望動機」が重視される傾向があります。
公務員は、地域住民や国民と関わる機会が多いため、協調性や責任感を持った人物かどうかが見られます。表面的な回答ではなく、自分の経験や考えを具体的に語れるようにしておきましょう。
また、面接カードに記載した内容と、当日の話に矛盾がないよう注意してください。模擬面接を繰り返して練習し、柔軟に対応できる力を養っておくことが大切です。
⑥ 最終合格と採用手続き
二次試験に合格すれば、最終合格となりますが、手続きはまだ続きます。健康診断や書類提出のほか、自治体や機関によっては面談や説明会がある場合もあります。
スケジュールは細かく決められており、見落とすと内定を逃す恐れがありますので、注意が必要です。
複数の自治体に合格した場合は、勤務地や業務内容、将来のキャリアパスも含めて慎重に判断しましょう。
採用までの過程を丁寧に進めることが、公務員としてのスタートに直結します。焦らず、しっかり確認しながら進めてください。
公務員の給料事情を総合的に理解しよう

公務員の給料は安定性が魅力ですが、年収や支給体系、民間企業との違いなど、実際の仕組みを正しく把握することが大切です。
公務員の平均年収は職種や年齢によって異なり、国家公務員と地方公務員で差があります。
また、等級や俸給表、人事院勧告制度といった独自の仕組みにより給料が決定され、年齢とともに段階的に上がるのが特徴です。
民間企業に比べて手当や福利厚生も充実しており、ボーナスの安定性も魅力の一つ。これらの点を踏まえると、公務員は長期的に安定した収入を望む人に適した職業だと言えるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














