公務員におすすめの資格23選!試験や就職で活かす方法とは
公務員試験は競争が激しく、就職活動も厳しいものです。そのため、自分の強みを証明できる資格が重要になります。
しかし、「公務員を目指しているけれど、どんな資格を取得すれば有利になるのか分からない…」 と悩む方も多いですよね。
この記事では、公務員試験に役立つ資格を分かりやすく紹介し、それぞれの資格をどう活かすかを解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員を目指す人が活用できる資格を知ろう

資格は自分の志望職種や将来の業務に関連するものを選ぶことが大切でしょう。
資格が直接的な評価対象になることはほとんどありませんが、志望動機の裏付けや、専門性を証明する材料として有効に働くことがあります。
たとえば、法律系の資格を持っていれば行政職や法務関連の部署で強みを発揮できますし、英語やIT分野の資格は国際対応が求められる部署やデジタル施策に関わる業務で重宝されるでしょう。
また、資格取得を通して得た勉強習慣や論理的な思考力は、公務員試験の筆記や面接においても大きな武器となります。
資格は単なる履歴書上の飾りではなく、実務にもつながるスキルの証明として活用できるのです。公務員の仕事では幅広い知識と柔軟な対応力が求められます。
公務員試験における受験資格

公務員試験は誰でも受けられるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
特に「欠格条項」や「年齢制限」といった基本的な受験資格を知らずに準備を進めてしまうと、せっかくの努力が無駄になるおそれがあるのです。
ここでは、公務員試験に必要な各種条件について、就活生が見落としやすいポイントとあわせて詳しく解説していきます。
- 欠格条項
- 年齢制限
- 学歴条件
- 資格
- 身体条件
①欠格条項
欠格条項とは、公務員として任用される際に不適格と判断される理由を示したものです。たとえば、禁錮以上の刑を受けた経験がある人や、懲戒免職後に一定期間が経過していない人などが該当します。
こうした条件は、試験に合格しても採用されない原因となるため、事前に確認しておくことが大切です。多くの学生には関係のない項目がほとんどですが、念のため募集要項をしっかり読みましょう。
さらに、精神的な疾患がある場合など、身体的・精神的な適性が求められることもあるため、健康状態に不安があるなら医師の意見を聞くのがおすすめです。
少しでも気になることがあれば、自治体や人事院へ問い合わせてみるのがよいでしょう。
②年齢制限
公務員試験には、受験可能な年齢が決まっているケースがほとんどです。たとえば、多くの地方公務員試験では「30歳未満」や「29歳まで」といった上限が設定されています。
国家公務員総合職の場合、「21歳以上30歳未満」とされていることが一般的ですが、学歴によって条件が異なることもあります。
注意したいのは、年齢要件の基準日です。「試験年度の4月1日時点」や「申込時点」など、指定された日付があるため、自分の誕生日と照らし合わせて確認しておく必要があります。
また、社会人経験者向けの採用区分では、年齢の上限が引き上げられている場合も。もし民間企業を経てから公務員を目指すなら、こうした区分も視野に入れて選びましょう。
申し込もうと思ったときに年齢制限に引っかかっていた、という事態は避けたいところです。
③学歴条件
公務員試験には「学歴不問」の区分が意外と多くあります。たとえば、地方公務員の初級試験や国家公務員一般職(高卒区分)では、高卒や中卒でも受験できるケースがあるでしょう。
一方で、国家公務員総合職などの上級職は、大学卒業見込み者や既卒者が対象になることが多いです。見落としがちなのが「卒業見込み」の定義です。
大学4年生でも必要な単位を取得していなければ、卒業見込みとして認められない場合があります。また、大学院修了者向けの試験もあるため、自分の学歴にあわせた受験区分を確認しましょう。
なお、学歴以上に重要なのは筆記試験の実力です。たとえ有名大学の出身でも、しっかりと試験対策をしなければ合格は難しいでしょう。
学歴に関係なく、誰でも努力次第でチャンスをつかめるのが公務員試験の魅力とも言えます。
④資格
公務員を目指す学生の中には、「何か資格がないと受けられないのでは」と心配する人もいます。しかし、実際のところ多くの試験では特別な資格がなくても受験できるのです。
たとえば、市役所職員や国家一般職などでは、無資格でも合格すれば採用されます。とはいえ、資格があると有利になることはあります。
行政書士やTOEICの高スコア、ITパスポートなどは、専門性や意欲の証明として評価されることがあるでしょう。ただし、資格取得にこだわるあまり筆記試験の対策がおろそかになるのは避けてください。
資格はあくまでも補足的な強みと捉えるのが妥当です。なお、職種によっては資格が必須な場合もあります。たとえば、保健師や建築士などの専門職は、該当する国家資格を持っていなければ応募できません。
こうした職種を目指す場合には、早い段階から進路を明確にしておくことが重要になります。
⑤身体条件
警察官や消防士、自衛官などの職種では、身体的な条件が採用基準に含まれています。視力や聴力、色覚、体力測定などが代表的な項目です。
これらの条件を満たせないと、筆記試験に合格していても採用されないことがあります。特に注意が必要なのは、矯正視力や色覚に関する基準です。
視力はメガネやコンタクトで矯正できれば問題ない場合が多いですが、職種によっては矯正しても不適格とされるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
身体条件は、書類選考だけでなく健康診断や面接時にもチェックされることがあります。健康に不安がある人は、医師の診断を受けておくと安心です。
不安な点がある場合は、志望先の人事担当に直接問い合わせると、より正確な情報が得られるでしょう。
公務員になる方法

公務員になるには、国家公務員と地方公務員で試験の仕組みが異なります。どちらも試験に合格することが前提で、それぞれの制度に合った準備が必要です。
ここでは、それぞれの試験の特徴を比較しながら、目指す進路に応じた対策のポイントを紹介します。
- 国家公務員:国家公務員試験の合格
- 地方公務員:地方公務員試験の合格
①国家公務員:国家公務員試験の合格
国家公務員になるには、人事院が実施する「国家公務員試験」に合格しなければなりません。試験は総合職・一般職・専門職に分かれており、それぞれ求められる知識や役割が異なります。
たとえば、政策立案を担当する総合職は、大学卒業程度の学力と高い論理性が求められるでしょう。国家公務員試験の特徴は、筆記に加えて人物評価も重視されることです。
筆記試験での得点だけでなく、面接での自己表現力や志望動機の明確さも評価されます。また、語学力やITスキルなど、業務に直結する専門資格を持っていると、配属後に活かせる可能性があるでしょう。
受験対策には一定の準備期間が必要です。多くの学生は大学3年のうちから勉強を始めており、過去問の演習や模擬面接などを通じて本番に備えています。
自分が目指す職種の試験区分を早めに確認し、効率的に学習を進めてください。採用後は、中央省庁や出先機関で働き、国の政策や制度づくりに関わる仕事に携わることになります。
②地方公務員:地方公務員試験の合格
地方公務員になるためには、自治体ごとに行われる「地方公務員試験」に合格する必要があります。採用は都道府県や市区町村ごとに行われ、職種や試験日程も異なるでしょう。
行政職・技術職・福祉職など、幅広い分野から自分に合ったものを選べるのが特徴です。
地方公務員試験では、教養試験や論作文、個別面接などが行われます。また、自治体によってはSPI方式や民間経験者枠など、独自の採用方式を導入している場合もあります。
試験の難易度は国家公務員試験よりやや低めですが、その分、面接での人柄や志望動機の説得力がより重視される傾向があるのです。特に「なぜその自治体を志望するのか」を明確に答えられることが大切でしょう。
最新情報は各自治体の公式サイトで随時確認し、自分に合った選考ルートを見つけてください。採用後は、地域の課題に向き合いながら、住民に寄り添った行政サービスを提供する役割を担います。
公務員を目指す学生が資格を取得するメリット

公務員試験は筆記と面接の総合評価で合否が決まるため、資格の取得は必須ではありません。ただし、実際には資格があることで選考で有利になる場面も多く、アピール材料として活用できます。
ここでは、公務員を目指す学生が資格を取ることで得られる具体的なメリットを5つ紹介しました。
- 面接やESでアピール材料になる
- 実務で活かせるスキルを先取りできる
- 志望動機や自己PRに具体性が出る
- 競争率が高い場合に差別化できる
- 入庁後のキャリアアップに役立つ
①面接やESでアピール材料になる
公務員試験では人物評価が重要とされています。そのため、資格を持っておくと、面接やエントリーシート(ES)でアピール材料として効果的です。
たとえば、行政書士やITパスポート、TOEICなどの資格は、学業とは別に自発的に取り組んだ実績として評価されます。
「なぜその資格を選び、どんな意図で取得したのか」を話せると、面接官の印象に残りやすくなるでしょう。もちろん、資格があるからといって必ず合格できるとは限りません。
ただ、目的意識を持って行動してきたことを伝えられれば、評価を高めるきっかけになります。
②実務で活かせるスキルを先取りできる
公務員として働くうえで役立つ知識やスキルを、学生のうちから学んでおくことには大きな意味があります。資格を通じて得た内容が、実際の業務にそのまま生きるケースもあるのです。
たとえば、IT系の資格があれば庁内システムやDX関連の業務で活躍できる場面が増えるでしょう。簿記の知識があると、会計や予算管理の場面でも役立ちます。
これらのスキルを新人研修で初めて学ぶより、事前に理解しているほうが現場での習熟が早くなるでしょう。
上司や同僚からの信頼も得やすくなるため、入庁後のスタートをスムーズに切りたいなら、資格取得は有効です。
③志望動機や自己PRに具体性が出る
公務員を目指す学生の志望動機は、「地域に貢献したい」など抽象的かつ、似通ったものになりがちです。しかし、資格を持っていれば、志望動機や自己PRに具体性が出せます。
たとえば、福祉系の資格を持っていれば、「高齢者福祉に関心があり、知識を実務に生かしたい」といった具体的な動機が伝えられるのです。
自己PRにおいても、「〇〇の資格取得を通じて計画的に学ぶ力を身につけた」と話すことで、意欲や能力を客観的に示せるでしょう。内容が具体的であるほど、面接官の記憶に残りやすくなります。
④競争率が高い場合に差別化できる
公務員試験は倍率が高いことが多く、人気の自治体や職種では10倍以上になるケースもあり、わずかな違いが合否を分けることも少なくありません。資格があると、周りと差をつける材料になります。
とくに、志望職種と関連性がある資格であれば、選考官に強い印象を与えられるでしょう。
資格取得の背景や活用の意図を語ることができれば、より効果的です。資格だけで合否が決まるわけではありませんが、総合的な判断において一歩リードできるのは確かです。
競争を勝ち抜くための手段として、資格は心強い味方になってくれます。
⑤入庁後のキャリアアップに役立つ
資格の価値は、試験合格のためだけにとどまらず、入庁後のキャリア形成にも大きく貢献します。
職場では異動や昇任のたびに新しい知識が求められることも多く、若いうちから学んでおくと役立つでしょう。
たとえば、ITスキルがあればデジタル政策や情報管理部門での活躍が期待できます。語学力があれば、国際関係業務への挑戦も視野に入ってくるのです。
また、特定の資格が昇任要件になる場合もあります。資格を持っている人は自己成長意欲が高いと評価されやすく、上司や人事からの信頼も得られるでしょう。
将来の選択肢を広げるためにも、早いうちから資格取得を検討しておくことをおすすめします。
公務員試験で有利になるおすすめ資格

公務員試験は資格がなくても受験できますが、持っていると選考や面接でアピールしやすくなります。ここでは、就活生に役立つ「おすすめの資格」を紹介します。
自分の志望職種や興味に合った資格を選び、効果的に活かしてください。
- TOEIC・英検
- 日商簿記
- ITパスポート
- MOS
- ファイナンシャルプランナー
- 自動車運転免許
- ビジネス実務法務検定
- 秘書検定
- VBAエキスパート
- 基本情報技術者試験
- 色彩検定
①TOEIC・英検
公務員試験に直接の必須資格ではありませんが、英語力を証明できるTOEICや英検は、面接や配属先での業務に活かせる場面が多くあります。
特に国際交流、外国人支援、観光振興などを担う部署では、英語のスキルが求められることも増えてきました。TOEICはスコアで実力を客観的に示せる点が魅力です。
最低でも600点以上、可能であれば730点以上を目指すと、語学力を強みにできます。英検の場合、準1級以上であれば、実務にも十分活用できる英語力とみなされるでしょう。
また、英語力は将来的なキャリアにもつながります。海外との交流事業や国際会議対応など、英語ができる職員に任される仕事は広がっているため、語学スキルを磨く意義は大きいです。
②日商簿記
日商簿記は、自治体の財政管理や会計業務に直結する知識が学べる資格です。特に財政課、税務課、会計検査対応などの部署では、予算や収支の仕組みを理解している職員が求められます。
3級は基本的な商業簿記の知識が中心ですが、公務員としての実務に生かすなら、2級以上を目指したいところです。
2級では原価計算や複式簿記といった応用内容も扱われ、数字に対する感覚を持っていることをアピールできます。
また、簿記の学習を通して論理的思考力やミスを見逃さない注意力が鍛えられる点も魅力です。これらのスキルは、事務全般に活かせるため、財政部門を目指す方だけでなく広くおすすめできる資格でしょう。
③ITパスポート
ITパスポートは、経済産業省が認定する国家資格で、ITに関する基礎的な知識を幅広く学べます。
行政のデジタル化が進む中、パソコン操作だけでなく、情報管理やネットワークの知識を持った人材のニーズが高まっているのです。
この資格では、ハードウェアやソフトウェアに加え、セキュリティやプロジェクトマネジメントなどの分野もカバーされており、ITに詳しくない文系の学生でも学びやすい設計。
1日1~2時間の学習を継続すれば、数か月で合格を目指せるでしょう。ITの知識はどの部署でも求められる汎用スキルです。
特に、情報システム課や庁内のICT関連業務に携わりたい場合には、持っておくと安心。資格を通じて、IT活用に前向きな姿勢も伝えられるでしょう。
④MOS
MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)は、WordやExcel、PowerPointなどの事務ソフトを使いこなす力を証明できる民間資格です。
公務員として資料作成、報告書の整理、データ処理を行ううえで、これらの操作スキルは非常に重要。
とくにExcelは、関数や表の作成にとどまらず、グラフ化や並べ替えなども日常業務で使用されることが多いため、基本的な操作に加えて応用力まで身につけておくと強みになります。
Wordも公文書作成や議事録作成で頻繁に使われるのです。MOSは比較的短期間で取得可能であり、パソコン操作に苦手意識がある方も、基礎から自信をつけるのに最適でしょう。
実技形式の試験のため、取得しておけば即戦力としての評価も受けやすくなります。
⑤ファイナンシャルプランナー
FP(ファイナンシャルプランナー)は、家計管理や税金、保険、年金、資産運用など、暮らしに関する幅広いお金の知識を身につけられる資格です。
市民の生活に関する相談を受ける業務では、特に役立つ場面が多くあります。FP3級は初心者向けの内容で、学生でも取り組みやすい難易度です。
2級まで取得できれば、保険制度やライフプランニングなどに関する応用知識が身につき、相談業務や福祉関連の部署での信頼性が増します。
金融や社会保障に対する理解を深めておくことは、公務員としての説明責任を果たすうえでも重要です。自分の生活にも役立つ内容なので、将来の備えとしても一石二鳥の資格といえます。
⑥自動車運転免許
普通自動車運転免許は、全国の自治体で業務遂行に必要とされることが多い必須資格の一つです。
特に中山間地域や郊外の役所では、住民訪問や現地確認のための移動手段として公用車を使用する場面が日常的にあります。
また、消防・福祉・建設・農林業関連の部署など、現地調査や外回りを含む業務では、運転免許の有無が応募条件となっていることも少なくありません。
実際に採用情報を見ると、「要普通免許」と明記されている職種も見られます。就職活動が本格化する前に取得しておくことで、応募できる職種の幅も広がるでしょう。
⑦ビジネス実務法務検定
ビジネス実務法務検定は、企業活動に必要な法律知識を幅広く身につけることができる資格です。
契約、会社法、知的財産、消費者保護などの法的リスクに対する理解を深めることができ、公務員として行政手続や契約事務に携わる際に役立ちます。
3級は法律初学者でも挑戦しやすく、民間・公的機関問わず汎用性が高い点が特徴です。文書作成や行政処分に関する基礎知識を学べるため、総務課や法務系の部署を志望する方に特におすすめします。
また、法的根拠をもとに行動する訓練にもなり、信頼感を与える人材として評価されやすくなります。
さらに、試験勉強を通じて、法的な読み取り能力や文書の正確性も向上するため、公文書の作成や内部規定の整備を行う業務でも効果を発揮するのです。
⑧秘書検定
秘書検定では、ビジネスマナーや電話応対、文書作成、上司のスケジュール管理など、社会人としての基礎力を体系的に学ぶことができます。
礼儀作法、敬語の使い方、名刺交換など、面接や社会人生活で即活用できる知識が詰まっています。窓口業務や来庁者の対応を行う自治体職員にとって、こうしたスキルは欠かせません。
面接試験では言葉づかいや所作がチェックされるため、この資格で身につけたスキルが自信に変わるでしょう。
また、秘書検定を取得しておくことで、コミュニケーション能力やホスピタリティの高さをアピールできます。
とくに接遇マナーは、窓口対応や苦情処理など、住民との関係づくりにも直結するため、実務でも評価されやすいスキルです。
⑨VBAエキスパート
VBAエキスパートは、Microsoft ExcelのマクロやVBA(Visual Basic for Applications)を活用して業務の自動化ができるスキルを証明する資格です。
公務員の事務作業は繰り返しの多い業務も多く、自動化による業務効率化は現場で非常に喜ばれます。Excelを使って集計表を作成したり、ルーチン作業を簡略化したりする場面では、VBAが活躍します。
データベース管理や複雑な処理にも応用できるため、情報システム課以外の部署でもその有用性は高いといえるでしょう。
VBAスキルを持っていることで、「IT活用に強い人材」「業務改善の提案ができる職員」として評価されやすくなります。
MOSよりも一歩踏み込んだスキルであり、実務でも即戦力として期待されやすいため、PCスキルに自信がある方にはぜひ挑戦してほしい資格です。
⑩基本情報技術者試験
基本情報技術者試験は、IT関連の国家資格の中でも専門性の高い試験であり、プログラミング、アルゴリズム、ネットワーク、セキュリティなど幅広い知識が問われます。
ITパスポートよりも高度な内容で、行政のIT化推進に関わりたい方には強くおすすめできる資格です。
試験内容は理論だけでなく、実際のコーディング問題やロジカルな思考力が必要になるため、準備には一定の時間がかかります。
しかしその分、IT分野への理解の深さを示す証明になり、「デジタルに強い公務員」という印象を持たれやすくなるでしょう。
情報政策課やシステム運用部門に限らず、総務や企画、危機管理部門でもITの知識は活かせます。行政DXの流れが加速する中で、この資格の重要性は今後さらに高まると考えられるでしょう。
⑪色彩検定
色彩検定は、色の基礎理論や配色ルール、視覚心理などを学べる資格で、視覚表現に関わる業務で活用できます。
観光課や広報課、地域振興の部署などでは、パンフレットやポスター作成に携わる機会があり、デザインセンスを持つ職員が重宝されるのです。
検定では、色の分類方法、色の組み合わせのルール、トーンの使い分けなど、視覚的に魅力のある資料づくりに欠かせない知識を習得できます。
とくに住民向けに情報を伝える広報資料は、見た目のわかりやすさが重要で、色の効果を理解していると伝達力も高まるでしょう。
芸術系出身やデザインに興味がある方はもちろん、広報・観光分野での活躍を目指す方にとって、色彩検定は自分の感性とスキルをアピールする有力なツールになります。
専門性を高めたい人におすすめの資格

公務員として働くうえで専門性を持つことは、大きな強みになります。
特定の分野に関する資格を取得していれば、採用段階でアピールしやすくなるだけでなく、入庁後の業務でも役立つ場面が増えるでしょう。
ここでは、専門性を深めたい学生に向けて、おすすめの国家資格や専門職資格を紹介します。
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 技術士
- 一級建築士
- 電気主任技術者
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 保健師
- 看護師
- 臨床心理士
- 中小企業診断士
- 税理士
①社会保険労務士
社会保険や労働法の知識を活かせる社会保険労務士は、人事・福祉・年金関連の業務に関わる職種で重宝される資格です。
公務員として福祉事務所や労働関係の部署を志望する場合、取得しておくと評価されやすくなります。
この資格に合格するには、法律全般に対する体系的な理解が必要ですが、公務員試験の出題範囲と重なる部分も多いため、学習の相乗効果が期待できます。
相談対応や制度運用といった実務でも活かせるため、入庁後も即戦力としての活躍が見込めるでしょう。
また、面接で「なぜこの資格を取ったのか」「どう役立てたいか」を語ることで、目的意識や行動力を伝えられます。専門性の高さを印象づける手段として、十分に価値ある資格です。
②行政書士
行政書士は、行政手続きや法律文書に関する知識を証明する資格です。とくに、地方自治体の職員として住民対応や許認可業務を担当する可能性がある場合に、非常に役立ちます。
この資格は独学でも合格を目指せるため、学生のうちから取り組む人も少なくありません。民法や行政法など、公務員試験と共通する科目が多いため、効率的に学べる点も魅力です。
「行政に関わる仕事がしたい」という志望動機を、より説得力のある形で伝える手段にもなります。法制度を扱う部署を希望している方には、特におすすめです。
③技術士
技術士は、技術系国家資格の中でも最上位に位置づけられており、土木・機械・電気・情報など多くの分野で活用できます。
技術職の公務員としてインフラ整備や設計業務を目指す人にとって、非常に有用な資格です。取得には一定の実務経験が求められますが、大学在学中でも技術士補の資格は取得可能。
これをきっかけに将来的なステップアップを見据えた準備ができるでしょう。国や自治体の技術系部門では、技術士資格を持つ職員が多数在籍しており、専門性の証明として強く評価されます。
技術分野での活躍を視野に入れている方は、早めの学習を始めておくと有利です。
④一級建築士
都市計画や公共施設の設計に携わりたい方には、一級建築士の資格が最適です。建築分野における唯一の国家資格であり、構造・法規・意匠に関する高い専門性を証明できます。
この資格を取得していれば、建築職としての採用に限らず、都市整備や耐震対策などを担当する部署でも活躍の場が広がるのです。
勉強の難易度は高いですが、それだけに希少性もあり、就職活動でも強みとしてアピールできるでしょう。
将来的に、街づくりや公共インフラに関わる仕事を希望する方には、取得を検討する価値が十分にあります。
⑤電気主任技術者
電気主任技術者(いわゆる電験三種)は、電力設備の管理や保守に必要な国家資格です。公立の学校や庁舎、水道施設など、電気設備の安定稼働が求められる職場で活かせます。
この資格では、電気理論や法規、電力機器など幅広い知識が必要となるため、電気工学系の学部出身者との相性が良いでしょう。取得することで、専門性を備えた人材として高く評価されるはずです。
将来、設備管理やエネルギー政策に関わる仕事を希望する方にとって、現場で頼られる存在になるための一歩となります。
⑥社会福祉士
社会福祉士は、生活に困難を抱える人々を支援するための国家資格です。高齢者、障がい者、生活保護受給者など、さまざまなケースに対応できる福祉の専門職として、多くの自治体で活躍しています。
この資格を持っていれば、福祉事務所や介護保険課などの配属先で即戦力となる可能性が高まります。
また、法律や制度に関する知識だけでなく、相談援助の技術も求められるため、人と関わる仕事を志望する方に向いているでしょう。
福祉に関心があり、現場で直接住民を支えたいと考えている方にとって、この資格は強力な武器になります。資格の取得を通して、自己PRや志望動機に説得力を持たせることもできるでしょう。
⑦精神保健福祉士
精神保健福祉士は、心の病気や障がいを持つ方々をサポートする専門職です。医療機関や保健所、障害者支援施設など、メンタルヘルスに関わる公的機関でのニーズが高まっています。
公務員として精神保健福祉の分野に関わるなら、この資格を持っていると実務に直結するスキルとして評価されるでしょう。
特に、精神疾患への理解や支援方法を学んでおくことで、相談対応の質が高まります。
面接では「人に寄り添う姿勢」「専門知識への探究心」などをアピールできる材料にもなるため、志望動機に深みを加えたい場合にも役立つでしょう。
心のケアに携わる仕事を目指す方には、非常に有意義な資格です。
⑧保健師
保健師は、地域住民の健康管理や保健指導を行う専門職です。保健所や市町村の保健センターで勤務する公務員として、多くの女性に人気があります。
看護師資格を基礎として、さらに専門的な公衆衛生の知識と技術が求められるこの資格は、健康づくりや感染症対策といった行政サービスに直結するです。
地域住民と接する機会も多く、信頼される存在となるためには、専門性の高さが重要。
「人の健康を支えたい」「地域と深く関わる仕事がしたい」という思いを持つ方にとって、保健師は理想的なキャリアといえるでしょう。
⑨看護師
看護師は医療現場だけでなく、公務員として保健所や学校、福祉施設などでも活躍の場があります。
特に、保健師や養護教諭の補助的な立場で勤務するケースが多く、健康相談や応急処置など、幅広い業務に対応できるでしょう。
国家資格としての看護師免許は、基礎的な医療知識と実践力の証明でもあります。地域住民の健康管理や医療と行政の連携を必要とする場面で、看護師の視点を持つ人材は非常に貴重です。
医療や福祉と行政の架け橋となりたい方には、公務員看護師という選択肢もぜひ検討してみてください。
⑩臨床心理士
臨床心理士は、心理的な支援が必要な人々を対象に、カウンセリングや心理検査を行う専門職です。教育機関や児童相談所、家庭裁判所など、さまざまな分野で需要が増えています。
この資格は公認心理師と並ぶ心理系資格の代表格であり、公務員として働く際にも専門性の高さが評価されやすいです。
メンタルヘルスの重要性が社会全体で見直されている今、公務員としての役割も拡大しています。
心の問題に寄り添う職業に興味がある方や、人の内面を理解しながら支援したいという思いがある方にとって、非常に魅力的な資格です。
⑪中小企業診断士
中小企業診断士は、経営戦略や会計、マーケティングなど幅広い知識を活かして企業支援を行う国家資格です。
商工会議所や中小企業支援センターなど、行政と企業をつなぐ役割を担う公務員として重宝されます。
資格取得の過程で学ぶ内容は、公務員試験科目とは異なる分野もありますが、それがかえって経済系職種での専門性の裏付けとなるのです。企業支援に関心がある学生にはぴったりの資格でしょう。
経済の活性化に貢献したいと考えている方は、将来的な武器として検討する価値があります。
⑫税理士
税理士は、税務・会計の専門家として企業や個人に助言を行う資格ですが、国税専門官や地方税務職員として働く際にも評価される資格です。
この資格を持っていることで、税制や会計に関する高度な理解を示すことができ、財政部門や税務課での業務に直結します。
取得には複数科目の合格が必要で難易度は高めですが、そのぶん就職後の評価にもつながるでしょう。税に関わる仕事を希望している方は、取得を目指してみてはいかがでしょうか。
資格試験の対策方法

「資格の必要性はわかったけれど、どう対策すればいいかわからない…」と悩む方もいますよね。ここでは、資格取得を目指す就活生に向けて、効果的な勉強方法をご紹介します。
自分に合った方法を選び、計画的に取り組んでください。
- 独学で勉強を進める
- 通信講座を活用する
- 資格スクールに通う
- 勉強スケジュールを立てる
①独学で勉強を進める
独学は、最も手軽に始められる方法です。参考書や問題集、公式サイトの情報を活用すれば、自分のペースで自由に学習を進められます。
特にコストを抑えたい方や、すでに学習習慣が身についている人には向いているでしょう。独学は、自分で内容を取捨選択しながら進める必要があるため、学ぶ力そのものも鍛えられます。
一方で、わからない部分を誰にも相談できず、途中で手が止まってしまう可能性もあるでしょう。
理解があいまいなまま進んでしまうと、得点につながらないだけでなく、学習のモチベーションも下がってしまいます。
こうしたリスクを避けるには、進捗や理解度を記録に残し、定期的に振り返る習慣を持つことが大切です。スケジュール管理ツールや学習記録アプリの活用も効果的でしょう。
②通信講座を活用する
通信講座は、効率と柔軟性を兼ね備えた学習手段です。動画授業や添削課題を通じて、専門家の解説を受けながら体系的に学べます。
自宅で取り組めるため通学の手間もなく、時間や場所にとらわれず勉強できるのが最大のメリットでしょう。独学に不安がある方、学習のペースメーカーが欲しい方にとって、非常に心強い方法です。
また、多くの通信講座ではスマホ対応の学習アプリや、質問サポート機能も用意されています。スキマ時間を活用して学べる点は、忙しい就活生にとって大きな利点です。
ただし、通信講座にもいくつか種類があり、価格や講義の内容、教材の質に差があります。選ぶ際には無料体験や資料請求を活用し、自分に合った講座を見極めるようにしてください。
サポート内容や合格実績を確認してから申し込むと安心です。
③資格スクールに通う
資格スクールに通うことで、直接指導を受けながら学べる点が最大の魅力です。講師にその場で質問できるため理解が深まりやすく、難解なポイントも効率よく消化できます。
授業スケジュールがあることで学習ペースを保ちやすく、モチベーションの維持にもつながるでしょう。特に「一人で勉強するのが苦手」「強制力があったほうが継続しやすい」という人に適した方法です。
さらに、同じ目標を持った仲間と切磋琢磨できる環境は、精神的な刺激にもなります。模試や演習の機会も豊富にあり、実践力を磨くのにも最適です。
ただし、通学には時間や交通費がかかるうえ、受講料も比較的高額になるケースが多いため、費用面での検討は欠かせません。立地や開講時間も含め、通いやすさを重視して選びましょう。
④勉強スケジュールを立てる
どの勉強方法を選んでも、合格に向けて最も重要なのは「継続できるスケジュール作り」です。公務員試験や資格試験は範囲が広く、短期間で詰め込むだけでは対応しきれません。
試験日から逆算して、1週間単位や1日単位で無理のない計画を立てることが大切です。まずは全体の学習期間を決め、過去問演習・理解の確認・暗記といった要素を段階的に組み込んでください。
また、自分が集中しやすい時間帯を把握し、その時間に難しい科目や苦手分野を組み込むと効率が上がります。勉強記録をつけることで、やったつもりを防げるだけでなく、達成感も得られるでしょう。
スケジュールは「立てるだけ」で終わらせず、週ごとに振り返りながら必要に応じて調整してください。計画倒れを防ぐためにも、余白を持たせた柔軟な設計がカギになります。
資格をアピールする際の注意点
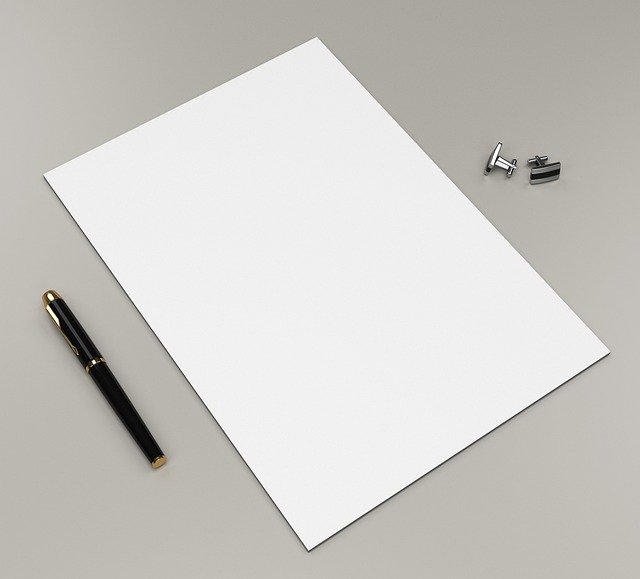
資格は自己PRの材料になりますが、伝え方を誤ると逆効果になってしまうこともあります。
ここでは、公務員試験や面接で資格をうまく活かすために、気をつけたいポイントを紹介しました。
採用担当者に響くアピールの工夫を意識してみてください。
- 志望職種に関連性のある資格を選ぶ
- 取得した背景や学びもアピールする
- 難易度の低い資格だけを取らないようにする
- 資格取得ばかりを強調すると逆効果になる
- 資格以外の経験やスキルとのバランスも意識する
①志望職種に関連性のある資格を選ぶ
採用担当者は「この資格が実際の業務でどう活かされるのか」を重視しています。そのため、自分が志望している職種において、実務で使える・関連性があると判断される資格を選ぶことが効果的です。
資格を持っていても、それが志望する職種と無関係であれば、方向性にズレがあると受け取られ、評価の対象にならないことがあります。
しかし、職種と一致していれば、「業務理解がある」「将来像を意識している」などのプラス評価につながるはずです。
資格を選ぶ際は、ただ取得しやすいものではなく、自分の進みたい方向とリンクするかどうかを意識して選んでください。
②取得した背景や学びもアピールする
資格の取得そのものよりも、それに至るまでの経緯や学びの過程に注目する面接官は少なくありません。ただ資格名や級を並べるだけでは、表面的な印象になってしまいます。
たとえば「なぜその資格に挑戦しようと思ったのか」「どのような困難を乗り越えたのか」「学んだことをどのように自己成長に結びつけたのか」といった背景を語ることで、
あなたの意欲や問題解決力、主体性をアピールできるでしょう。さらに、知識をどのように公務員の仕事で活かしていきたいかまで言及できると、より具体性が増します。
資格を通じて得た経験が、単なる学習ではなく自分の将来につながっていることを示すことが、信頼感と説得力につながるのです。
③難易度の低い資格だけを取らないようにする
短期間で取得できる資格や、初歩的な資格だけをそろえても、高評価にはつながりにくい場合があります。
もちろん、入門レベルの資格は基礎を固めるうえで有用ですし、学習の第一歩としては十分に意味があるのです。
ただし、それだけで終わってしまうと「深掘りしていない人」という印象になってしまうおそれもあるでしょう。
できれば、ステップアップとして中級以上の資格にもチャレンジし、継続的に学んでいる姿勢を見せることが大切です。
難易度の高い資格を持っていることで、計画性・努力・専門性といったポイントも同時に評価されやすくなります。複数資格を取得する場合も、内容やレベルのバランスを意識しながら選んでください。
④資格取得ばかりを強調すると逆効果になる
たくさん資格を持っていると、それだけで「勉強熱心」と思われがちですが、伝え方を間違えると「実践経験がない」「机上の知識に偏っている」といったマイナス印象を与える可能性があります。
資格だけをアピール材料にしてしまうと、「この人は本当に現場で活躍できるのか?」と疑問を持たれてしまうかもしれません。大切なのは、資格取得が目的化していないかを振り返ることです。
その資格を通じて何を考え、何を経験し、どう成長したのか。そういったプロセスを伝えることで、実践的な価値を感じてもらいやすくなります。
資格の数よりも、そこから得た行動や成果を明確に伝えることが評価につながると意識しましょう。
⑤資格以外の経験やスキルとのバランスも意識する
就職活動では、資格の有無だけでなく、人間性や行動力、現場での対応力なども重視されます。資格はあくまで補足的な強みであり、他の経験と組み合わせて初めて説得力を持つものです。
たとえば、アルバイトでの接客経験、ゼミでのプレゼンテーション、地域活動での運営経験など、実際の行動で身につけたスキルを積極的に伝えてください。
資格と実体験の両方が語れることで、より厚みのある人物像を提示できます。
また、実務で活かせる力があることを示すためにも、資格に依存しすぎず、全体のバランスを考えたアピールを意識することが重要です。
自分を多面的に伝えることで、面接官の記憶に残る自己PRができるでしょう。
公務員の志望者が資格をどう活かすかが合否のカギを握る

公務員を目指すうえで資格は必須ではありませんが、戦略的に活用すれば選考を有利に進める武器になります。
受験資格や職種ごとの条件を理解し、志望動機や自己PRに説得力を持たせるためにも、自分に合った資格を選んで取得しておくとよいでしょう。
特に公務員試験で有利になるおすすめ資格や、専門性を高める国家資格は、就職活動や入庁後のキャリア形成において大きな強みになります。
さらに、資格を取得するだけでなく、取得の背景や学びをどう伝えるかも重要です。独学・通信・スクールなど対策方法を工夫し、自分の目標に合わせた準備を進めてください。
公務員と資格の関係を正しく理解し、自分らしい形で活かしていく姿勢が、最終的な結果につながるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














