短期インターンのメリット・デメリットを徹底解説|インターンの探し方や選考対策も紹介
この記事では、短期インターンの探し方や選考対策を徹底解説しています。
また、長期インターンとの違いや、参加するメリットとデメリットも紹介しているので、自身に合っているかも確認してみましょう!
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る短期インターンシップとは?

短期インターンシップとは、企業が学生に向けて実施する、数日から1週間程度の職業体験プログラムです。
実際の仕事を一部体験したり、社員と交流したりすることで、業界や企業への理解を深められる場として注目されています。主に夏休みや春休みなどの長期休暇を中心に開催されるため、学業と両立しやすいのも特徴です。
参加することで、本選考前に企業の雰囲気や方針を知ることができ、就職活動での判断材料として役立つでしょう。
短期インターンシップの目的は企業によって異なりますが、多くは学生に自社の魅力を伝えることを目的としています。一方、学生にとっては、自分に合った業界や職種を見極めるための機会になります。
内容としては、企業説明・グループワーク・社員との座談会などが中心で、本格的な業務よりも「企業理解」を深める要素が強めです。
短期間で多くの情報を得られる反面、内容が詰め込まれているため、目的を明確にしたうえで参加することが大切です。
なお、短期インターンといえども、ほとんどの場合に選考があります。「数日だけなのに選考するの?」と思うかもしれませんが、企業側も限られた枠の中で意欲的な学生と出会いたいと考えています。
エントリーシートの提出や面談があることも多く、場合によっては志望動機を聞かれることもあります。
気軽に参加できる印象を持たれがちですが、ある程度の準備は必要です。「とりあえず行ってみよう」ではなく、しっかり目的意識を持って臨むことで、有意義な経験となるでしょう。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
短期インターンと長期インターンの違い
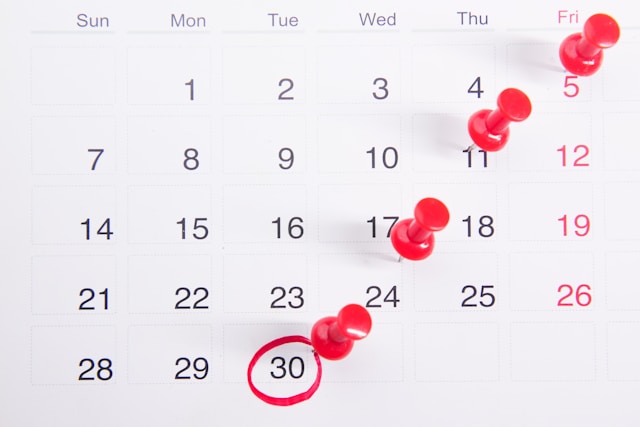
短期インターンと長期インターンは、一見似ているように感じられますが、実際にはその目的や内容、参加条件などに明確な違いがあります。
それぞれの特徴を理解することで、自分に合ったインターンを選ぶ判断材料になります。
- 開催目的の違い
- プログラム内容の違い
- 参加対象の違い
- 開催時期の違い
- 本選考との関係性の違い
- 給与支給の有無
① 開催目的の違い
短期インターンの主な目的は、学生に企業や業界への関心を持ってもらうことです。
企業の魅力を広く伝えるためのPR的な側面が強く、採用よりも認知度向上を重視しています。そのため、気軽に参加できる内容で構成されていることが多いです。
一方、長期インターンは実践的な業務を通して、企業が学生の実力や適性を見極める場でもあります。将来の採用候補としての評価対象になるケースもあり、社員と同じ目線で仕事をすることも求められます。
短期か長期かを選ぶ際は、自分が「情報収集したい段階」なのか、「実力を試したい段階」なのかを考えると、選びやすくなるでしょう。
② プログラム内容の違い
短期インターンでは、会社紹介や業界説明、グループワークなどの体験型プログラムが中心です。基本的には1~5日程度で完結するため、複数社を比較しながら参加する学生も多く見られます。
それに対して長期インターンは、実際の業務に近い作業を任されるため、プログラムというよりも日々の仕事を通して学ぶスタイルになります。
たとえば営業同行、資料作成、プロジェクト支援など、配属部署によって内容は大きく異なります。
自分の就活のフェーズや興味関心に応じて、体験重視なのか実務重視なのかを見極めることが重要です。
③ 参加対象の違い
短期インターンは、大学3年生を中心に、1・2年生の参加も歓迎されることが増えています。
特に知名度の高い企業では、早期から学生との接点を持つことを目的に、多学年向けの短期プログラムを複数用意していることもあります。
一方、長期インターンは平日に一定時間勤務する必要があるため、時間的な融通が利く学生に限定されがちです。大学4年生や大学院生が比較的多く、就活準備が進んでいる層が中心です。
自分の学年や生活リズムを考慮し、無理のない範囲で参加できる形式を選ぶことが、継続的な取り組みにつながります。
④ 開催時期の違い
短期インターンは、大学の長期休暇にあたる夏(8月~9月)や冬(2月~3月)に集中して開催されます。多くの学生がスケジュールを調整しやすく、集中的に就活準備を進める機会として活用されています。
一方、長期インターンは通年で実施されることが一般的です。1社に数カ月〜半年以上コミットするケースもあり、平常授業期間中のスケジューリングが求められます。
そのため、部活動やアルバイト、卒業論文とのバランスをとる必要があり、計画性が重要になります。まずは短期から始め、慣れてきたら長期へ移行するのも現実的な方法です。
⑤ 本選考との関係性の違い
短期インターンは直接的に本選考に結びつかないことが多いですが、企業によっては参加者限定で早期選考に招待されることがあります。
こうしたチャンスを活かすことで、他の学生より一歩リードできる可能性があります。
長期インターンは、実務でのパフォーマンスが評価され、内定直結のケースも少なくありません。企業にとっても採用コストを抑えられるため、長期参加者に対しては選考優遇がなされやすい傾向にあります。
採用とどの程度リンクしているのかを事前に確認しておくことで、期待値のズレによるミスマッチを防げるでしょう。
⑥ 給与支給の有無
短期インターンは原則無給で実施されることが多く、報酬の代わりに交通費や昼食が支給される程度です。企業としても「広報」の一環と位置付けているため、コストを抑えた運営が一般的です。
長期インターンでは、学生が戦力として関わるため、時給制または月給制で給与が支払われるケースが大半です。学生側にとっても収入源となり得る点は大きなメリットでしょう。
報酬の有無だけで判断せず、経験として得られるものや将来的なリターンも含めて、参加の意義を考えてみてください。
短期インターンに参加するメリット

短期インターンは、就活を有利に進めるうえで、さまざまな価値を提供してくれます。
時間が限られていても、得られる経験や気づきは非常に多く、自分の適性や進むべき方向性を見定めるうえでも役立つはずです。
ここでは、短期インターンに参加することで得られる代表的なメリットを5つ紹介します。
- 業界や企業理解が深まる
- 本選考が有利になる
- 短期間で両立しやすい
- 選考の練習ができる
- 職業適性が見えてくる
① 業界や企業理解が深まる
短期インターンに参加すると、企業や業界のリアルな姿を自分の目で確かめることができます。説明会やウェブ情報では見えにくい、実際の働く現場や社員の雰囲気に触れられるのが大きな魅力です。
業界ごとの文化や職場の人間関係、業務の流れなどを体験することで、「自分がこの環境で働けそうか」を判断しやすくなります。特に、まだ志望業界が定まっていない場合には、比較材料として非常に有効です。
たとえば、広告業界に興味がある学生がインターンを通じて裏方の仕事の重要性やスピード感を体験し、「華やかさだけではない現実」を理解できたというケースもあります。
こうした体験は、就活において軸を明確にするうえで非常に役立ちます。
結果として、自分に合った業界や企業を選ぶための判断力が養われ、就職後のミスマッチを防ぐ助けにもなるでしょう。
インターンでは「説明会では聞けないこと」を肌で感じる場面が多くあります。私たちも、インターンの参加後に「実際に現場を見て業界イメージが変わった」と話す学生を多く見てきました。特に社員同士のやりとりや、空気感に触れることが判断材料として非常に大きいんです。
また、現場体験によって「この業界には向いていないかもしれない」と気づけるケースもあります。それは後ろ向きなことではなく、むしろ軸を明確にするための前向きな一歩。選択肢を広げながら、不要なミスマッチを減らす視点として大切ですよ。
② 本選考が有利になる
短期インターンへの参加は、志望企業の本選考を有利に進めるためのきっかけになります。インターン参加者限定で早期選考の案内が届いたり、ES提出や一次面接が免除されたりする例も少なくありません。
また、インターン中に企業の社員や人事担当者と直接接点を持つことで、自分の印象を残すことも可能です。
志望度の高さや積極性が自然と伝わり、本選考で「既に知っている学生」として見てもらえる可能性があります。
たとえば、ある学生が短期インターン後にOB・OGとの関係を築き、面接前に業界情報を共有してもらえたという話もあります。このように、本選考に向けて情報戦でも一歩リードできるのです。
単なる就業体験にとどまらず、企業との距離を一気に縮める機会になるのが短期インターンの強みです。
③ 短期間で両立しやすい
短期インターンは、日程的に参加しやすい点も大きなメリットです。多くのプログラムが2~5日程度のスケジュールで設計されており、学業やアルバイトとの両立がしやすくなっています。
特に、授業が少ない夏休みや春休みを活用すれば、スケジュール的な無理なく参加できるため、就活準備の一環として効率よく経験を積めるでしょう。
また、最近ではオンライン形式のインターンも増えており、遠方の企業にも自宅から参加できる環境が整っています。
たとえば、地方の学生が都心企業の短期インターンに参加し、「現地に行かなくても企業の雰囲気や業務を理解できた」といった声もあります。物理的な制約が小さいため、複数の企業を比較することも可能です。
限られた就活期間を有効に活用するためにも、短期インターンは非常に実用的な手段といえるでしょう。
④ 選考の練習ができる
短期インターンの参加には、事前にエントリーシートを提出したり、面接を受けたりするプロセスがある場合も多く、それ自体が選考対策になります。
とくに、就活を始めたばかりの時期には、本番さながらの緊張感を経験できる貴重な場となるでしょう。
志望動機や自己PRの準備、言語化、企業への伝え方を実践的に学ぶことで、自分の課題が見えやすくなります。
中にはフィードバックを受けられる企業もあり、客観的な視点からのアドバイスが就活準備に直結します。
たとえば、「話すスピードが速すぎる」「エピソードが抽象的」などの具体的な指摘を受けることで、本番の面接に向けた改善点を明確にできたという学生もいます。
早い段階でこうしたトライ&エラーを積んでおくことは、内定獲得への近道につながります。
短期インターンの選考で得られる実戦経験は、本番の面接に向けた基礎づくりとしてとても有効です。特に自己PRや志望動機を「実際に話してみる」ことの大切さは、頭で考えるだけでは気づけない課題を浮き彫りにしてくれます。
そのため、実際の業務の体験ができたり、アウトプットに対してフィードバックがあるインターンなら、改善の精度も一段と高まりますよ。
私たちも、「話が長い」「表情が硬い」といった気づきをインターンで得て、本番で修正して成果につなげた学生を多く見てきました。トライ&エラーを重ねる場として、早期にこうした練習機会を持つ意味は大きいですよね。
⑤ 職業適性が見えてくる
短期インターンに参加すると、自分がどんな仕事に向いているか、またどのような働き方に魅力を感じるかを具体的に確認できます。
ただ漠然と「営業職が良さそう」と思っていても、実際にその業務を体験してみると「思ったより対人の気遣いが多い」と感じるなど、気づきがあるものです。
このように、実体験を通じて得た感覚は自己分析を深めるうえでも非常に役立ちます。自分が自然体で取り組める業務はどのようなものかを知ることは、将来のキャリア選択に直結します。
たとえば、インターン中にプレゼン資料の作成を任され、「数字をもとに論理的に整理する作業が楽しかった」と感じたことが、後の企画職志望につながったという例もあります。
向いている・向いていないを早い段階で見極めることができれば、進路選択の精度が高まり、納得のいく就活を進めやすくなるでしょう。
実際に体を動かして業務を体験してみないと、向き不向きってなかなか見えてこないものです。短期インターンに参加する中で「楽しさ」や「ストレスを感じない瞬間」に気づける経験こそが、自分に合った仕事のヒントになりますよ。
私たちも、「思っていた仕事と違った」という違和感から、志望職種を変えた学生を数多く見てきました。こうした気づきは、自己分析だけでは得られないリアルな判断材料になるはずです。
短期インターンに参加するデメリット

短期インターンは手軽に参加できる反面、注意すべきデメリットも複数存在します。
参加前にあらかじめ理解しておかないと、「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性もあります。ここでは、就活生が見落としがちな代表的なデメリットを5つに分けて解説します。
- 業務の全体像がつかみにくい
- 報酬が発生しないことが多い
- 倍率が高く参加しにくい
- 短期間では理解が浅くなる
- 業務体験が制限される
① 業務の全体像がつかみにくい
短期インターンでは、実務に触れる時間が非常に限られているため、仕事内容の全体像をつかむのが難しい傾向があります。
特に1~3日程度の超短期プログラムでは、座学や会社紹介が中心となり、実際の仕事に関する具体的な体験がほとんどできないこともあります。
このような状況では、企業で働く自分の姿を想像することが難しくなり、「自分に合っているかどうか」の判断がつきにくくなります。
企業も限られた時間で魅力を伝えようとするため、業務の詳細までは深掘りしきれない場合が多いです。
たとえば、営業職のインターンで資料作成の説明だけに終始し、顧客対応の実態に触れる機会がなかったというケースもあります。こうした不完全な情報で職種や業界を判断してしまうのは危険です。
インターンで得られる情報はあくまで一部に過ぎないという前提で、OB訪問や説明会などの情報も併用しながら、業務理解を補完していくことが重要です。
短期インターンでは「雰囲気は分かったけど、実際の業務内容はピンとこなかった」という声もよく聞きます。プログラムの構成によっては、職種理解に必要な情報が不足することもあるんですよ。
そのため、短期インターンの参加前にはインターンで実際に何をやるのかを確認しておきましょう。プログラムや構成を聞くことで無駄な時間を過ごすことが減りますよ。
② 報酬が発生しないことが多い
短期インターンでは、報酬や交通費の支給がないプログラムがほとんどです。
とくに地方在住の学生が都市部のインターンに参加する場合、移動費や宿泊費を自己負担することになり、経済的なハードルが高くなります。
募集要項に報酬の有無が明記されていない場合もあるため、「参加してみたら完全に無償だった」といった事後的なトラブルも起こりがちです。
学生の立場では、お金よりも経験を重視する傾向がありますが、金銭面の準備が不十分だと、交通費の出費だけで数万円になることもあります。
たとえば、東京の企業の1dayインターンに参加するために、新幹線代や宿泊費を負担した結果、アルバイト収入が一気になくなってしまったという声もあります。
複数回参加する場合は、合計金額が想定以上になる可能性もあるでしょう。
事前に報酬や費用負担の有無をしっかり確認し、必要であれば日帰り参加や近場の企業を選ぶなど、金銭面とのバランスを考えた選択が大切です。
③ 倍率が高く参加しにくい
短期インターンは就活初期段階での人気も高く、応募者が集中しやすいため、倍率が非常に高くなる傾向にあります。
とくに知名度の高い企業や外資系企業のプログラムは、数千人の応募に対して数十人しか参加できないことも珍しくありません。
多くの学生は「とりあえずインターンに参加しておこう」と考えますが、書類選考やWEBテスト、オンライン面接などを通過しなければならず、思ったよりもハードルが高いと感じることもあるでしょう。
落選が続くと、就活への自信をなくす要因にもなりかねません。たとえば、エントリー数5社中すべて落ちてしまった学生が「何がダメだったのか分からない」と悩み、自己分析からやり直すことになった例もあります。
選考に挑む前に、企業の採用ページや過去参加者の体験談をチェックし、エントリーの戦略を立てることが成功のカギになります。
また、倍率の低い中小企業や地方企業も選択肢に入れると、チャンスが広がるでしょう。
④ 短期間では理解が浅くなる
短期インターンは1日から1週間程度で終了することが多いため、企業理解や業務理解が浅くなる傾向があります。
限られた時間では、企業文化や社内の雰囲気を十分に把握することができず、表面的な印象に留まってしまう可能性があるのです。
たとえば、「社員の人柄が良さそう」という印象だけで志望度を上げたものの、後で深く調べると実は業務が非常にハードだったというケースもあります。
短期では仕事の厳しさや責任の重さまで実感することが難しく、理想だけが先行してしまう危険性もあります。
また、短期間ではフィードバックも限られがちで、自分の強み・弱みに気づく機会も少ないかもしれません。
何を学んだかを振り返る時間も取れないまま終わってしまえば、単なる「参加実績」にとどまってしまいます。
短期の情報だけで志望業界や職種を絞るのではなく、他の機会も併用しながら総合的に判断する姿勢が大切です。
短期インターンでは、得られる情報がどうしても断片的になりやすいんですよね。そのため、「良い印象だった」で終わらせず、どこまで実態がつかめたかを自分で整理しておくことが大切です。
短期インターンに参加する前に、まずは短期インターンで何を得たいのかをまとめてから参加するようにしましょう。目的を決めておくことでただ参加している他の就活生と圧倒的な差をつけられますよ。
⑤ 業務体験が制限される
短期インターンでは、業務の実体験が制限されることが多くなります。
守秘義務やセキュリティの観点から、企業が学生に触れさせられる仕事には限界があり、表面的な作業や模擬体験にとどまるケースが一般的です。
たとえば、実際のプロジェクトには関われず、過去の事例を使ったグループワークのみで終わってしまったというケースもあります。
それだけで企業や職種を判断しようとすると、現場のリアルな感覚からズレてしまうことがあるでしょう。
企業にとっても短期間での教育や業務提供にはリスクがあります。そのため、参加者にはあくまで「雰囲気の理解」や「チームワーク体験」など、限定的な内容しか提供できないのが現実です。
そうした制約の中でも、自分から積極的に質問をしたり、観察したりする姿勢を持つことで、得られる情報量は大きく変わってきます。
「短期だからこそできる最大限の吸収」を意識することが、価値ある体験につながります。
短期インターンの探し方

短期インターンに参加したいと考えたとき、最初に悩むのが情報の探し方です。
手段によって得られる情報の範囲や信頼性に差があるため、複数の方法を組み合わせて探すことがポイントになります。
- 企業の採用ページ
- 就活サイト
- 大学のキャリアセンター
- 内定者やOB・OG
- SNSや就活イベント
① 企業の採用ページ
短期インターンを探す際は、まず企業の採用ページを確認してみてください。企業が自社の情報を直接発信しているため、正確かつタイムリーな内容を得ることができます。
採用ページには、インターンの目的やプログラムの詳細、応募方法、開催時期などが網羅されているケースが多く、公式な情報源として信頼できます。
企業理念や職場の雰囲気も合わせて発信されていることが多く、応募前の企業研究にも役立つでしょう。
たとえば、ある企業では「1Dayインターン」や「実務体験型プログラム」などの情報が特設ページにまとめられています。
一方、中小企業やスタートアップではページの構成が簡素だったり、情報の掲載自体がないこともあるため注意が必要です。
気になる企業がある場合は、定期的に採用ページを確認し、最新情報を見逃さないようにしましょう。
② 就活サイト
就活サイトは、多数の短期インターン情報を一括で検索・比較できる便利なプラットフォームです。自分に合ったインターンを探したいときに、まず活用すべき手段のひとつといえます。
条件検索機能を使えば、業界・職種・エリア・開催時期などから自分の希望に合うインターンを絞り込めるため、効率的に情報収集が進みます。
また、過去の選考フローや体験談、ESの例などが共有されている場合もあり、選考対策にもつながるでしょう。
多くのサイトでは、インターン募集情報が定期的に更新されており、UIも学生向けに設計されているため、初めての方でも使いやすくなっています。
ただし、すべての企業が掲載されているわけではないため、ひとつのサイトに頼りすぎず、複数の情報源を併用することが重要です。
比較しながら選びたい就活生にとって、就活サイトは効率的な探し方のひとつです。
③ 大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターは、公的かつ学生向けに特化した情報提供機関であり、信頼性が高い探し方のひとつです。特に初めて短期インターンに参加する場合は、ここからの情報収集がおすすめです。
キャリアセンターでは、大学と連携している企業のインターン情報が多く、応募のハードルが比較的低いことが特徴です。
また、職員による個別相談やES添削、面接練習など、選考対策の支援も受けられるため、準備面でも心強い味方となってくれます。
たとえば、「学内合同企業説明会」や「キャリアガイダンス」などで紹介された企業が、インターンの募集を大学経由で行っているケースもあります。
ただし、情報が掲示板や紙ベースに限られている場合もあるため、こまめなチェックが必要です。安心して応募できるインターンを探したい場合は、キャリアセンターの情報に一度目を通してみてください。
④ 内定者やOB・OG
短期インターンについてのリアルな情報を得たいなら、内定者やOB・OGから話を聞くのが効果的です。実際に経験した人からの声には、ネット上では得られない具体性や信ぴょう性があります。
選考で重視されるポイント、インターン中の雰囲気、社員との距離感、さらには就活全体におけるインターンの影響など、実体験に基づくアドバイスは非常に参考になります。
特に、自分と同じ大学や学部出身の先輩であれば、より身近な視点から話を聞くことができ、親近感を持って受け取れるでしょう。
たとえば、OBOG訪問制度を利用したり、就活SNSやキャリアイベントでの交流を通じてつながりをつくることで、より多くの情報を得られます。
ただし、あくまで個人の経験であることを忘れず、複数の情報を照らし合わせて判断することが重要です。
迷いや不安がある場合こそ、先輩たちの声をヒントにしてみてはいかがでしょうか。
⑤ SNSや就活イベント
SNSや就活イベントは、思わぬインターン情報をキャッチできる柔軟な情報源です。特に情報感度の高い学生には、非常に相性の良い方法といえます。
TwitterやInstagramでは、企業の広報アカウントや採用担当者が最新情報をリアルタイムで発信していることがあり、他の媒体よりも早く情報にアクセスできる可能性があります。
また、学生団体や就活系インフルエンサーの投稿も意外と参考になります。加えて、インターンフェアや企業説明会といったイベントでは、複数企業と直接対話できるため、興味の幅を広げるチャンスにもなります。
たとえば、「キャリアフォーラム」や「逆求人イベント」では、企業とのマッチングやその場での選考案内が行われることもあります。
ただし、SNSの情報は玉石混交で、正確性に欠ける場合もあるため、公式ソースと照らし合わせながら使うことが大切です。
情報を自分から取りに行きたいタイプの学生には、SNSとイベントの併用が特におすすめです。
短期インターンの就活への役立て方

短期インターンは、就職活動における気づきや準備に大きく貢献する貴重な機会です。
業界や企業への理解を深めたり、自分の適性を確認したりと、多くのメリットがあります。ここでは、短期インターンを通じて就活にどう活かすかを具体的に紹介します。
- 複数企業の比較
- 社員や学生との交流
- フィードバックを活かす
- ESや面接でのアピール
- 選考への慣れ
① 複数企業の比較
短期インターンでは、複数の企業を比較することで、自分に合った業界や職場環境を見極めることができます。
限られた日数でも実際に働く体験ができるため、企業研究では分からない「現場の空気感」や「働く人の雰囲気」を知ることができるのです。
特に就活生にとっては、「自分がどのような環境で力を発揮できるのか」「どんな社風に居心地のよさを感じるのか」といった判断軸を持つことが重要になります。
インターンに参加することで、例えば同じ業界でも大手とベンチャーで意思決定のスピードや業務の進め方に大きな違いがあるといった、実感を伴う理解が得られます。
こうした比較を通じて、自分にフィットする企業像がはっきりしてくるため、志望業界や企業の絞り込みがしやすくなり、結果として効率的な就職活動につながるでしょう。
短期インターンを通じて複数企業を比較した経験は、その後の志望動機に深みを持たせる材料になります。「なぜこの企業を選んだのか」という問いに説得力を持たせるには、他社との違いを語れることが強みになります。
なので、気になる業界や職種などが決まっている場合は、その業界や職種の中でも複数の短期インターンに参加することをお勧めしています。短期なので、様々な企業を見れることが1つのメリットですよ。
② 社員や学生との交流
短期インターンは、社員や他大学の学生との貴重な交流の場でもあります。就活の情報収集だけでなく、自分の視野を広げたり、他者との違いから学びを得たりするうえで非常に有効です。
企業の公式情報やWEBサイトだけでは分からないリアルな声を聞くことで、たとえば「実際の残業時間」「上司との距離感」「入社後のキャリアパス」といった気になる点も確認できます。
また、参加者同士でのディスカッションやチームワークを通して、他の学生がどのように考え、行動しているのかを知ることができ、刺激にもなるでしょう。
こうした関わりの中で、自分の立ち位置や強み・弱みに気づくことができれば、今後の就活準備にも前向きな影響が期待できます。積極的に会話のきっかけを作る姿勢も大切です。
インターン中の社員や他の学生との交流は、職場の雰囲気だけでなく「価値観のすり合わせ」ができる貴重な場です。
特に社員との対話で得られる「働くリアル」は、企業研究では得られない経験になるでしょう。
③ フィードバックを活かす
短期インターンでは、グループワークやプレゼンテーションのあとに社員から直接フィードバックを受けられる場面が多くあります。
これを上手に活かすことで、自分の課題と成長ポイントを明確にできます。
自分では「うまくできた」と思っていた場面でも、第三者から見ると改善すべき点があるものです。たとえば「発言のタイミングはよいが、論理がやや飛躍している」といった細かな指摘は、自力ではなかなか気づけません。
こうしたコメントをメモに残し、帰宅後に振り返ることで、次の行動につなげる意識も自然と芽生えてきます。選考で求められるスキルや姿勢を、実践を通じて理解できる点も魅力です。
改善点を素直に受け入れる姿勢が、今後の成長のカギを握るでしょう。
フィードバックを受ける場面では、何を指摘されたかだけでなく「なぜそう言われたのか」まで振り返ることが大切です。その解像度の高さが、次の改善につながるかどうかを大きく左右しますよ。
私たちも、過去の指摘をもとに自ら修正した経験を語る学生には、成長意欲や行動力を感じます。受けっぱなしで終わらせず、自分の言葉で消化する習慣を意識してみてください。
④ ESや面接でのアピール
短期インターンでの体験は、エントリーシートや面接で具体的に語れる貴重なエピソードになります。
応募書類では「何を経験し、どう感じ、どんな学びがあったか」を一貫して伝えることが求められますが、その材料としてインターン経験は非常に有効です。
たとえば「短い期間の中で目標を設定し、仲間と協力して達成した経験」や「課題に直面し、どう乗り越えたか」といった話は、主体性や課題解決力をアピールするうえで説得力があります。
実際の業務に触れた上で語る言葉には、リアリティが生まれるため、聞き手にも届きやすくなります。
さらに、「なぜこの企業を志望するのか」という問いにも、インターン経験に基づいた具体的な動機が語れると、評価が高まる傾向にあります。
表面的な憧れやイメージではなく、自分の体験を通じた実感として伝えることが鍵になります。
インターン経験を語るときは、「ただ体験しました」ではなく、その経験から何を学び、どう成長につなげたのかを「具体的に言えるかどうか」に差が出ます。
私たちも、業務に触れたからこそ語れるリアルな気づきを軸に話す学生には、納得感を覚えます。言葉に実感があるかどうかは、面接官の印象を大きく左右します。
⑤ 選考への慣れ
短期インターンの選考では、書類審査や面接など本選考に近いプロセスを経験することが一般的です。この経験は、就職活動本番での緊張を和らげ、余裕を持って臨むための準備にもなります。
「面接ではどのようなことを聞かれるのか」「エントリーシートにどんな情報を書けばいいのか」といった不安を、実際に応募することで解消できるのです。
また、失敗した経験も貴重な財産になります。たとえば、「面接でうまく答えられなかった質問」を振り返ることで、自分の伝え方や考え方を整理することができます。
このように、選考に慣れることは単なる場数を踏むという意味だけでなく、自分の就活軸や伝え方をブラッシュアップする絶好の機会です。
早い段階から経験を積んでおくことで、本番の選考で実力を発揮しやすくなるでしょう。
面接で緊張してしまう理由の多くは、「場慣れしていない」ことなんです。そのため、短期インターンで場数をこなしていると、就活での経験値が増えて本選考の面接は自信を持って臨めるでしょう。
様々な短期インターンに参加することで選考に慣れて、自身の良さを最大限に活かしましょう!
短期インターン中の企業へのアピールポイント

短期インターンは、企業と接する時間が短いため、限られた機会をいかに活かすかが重要です。
一つひとつの行動が評価の対象となるため、目的意識を持った姿勢が企業への好印象につながります。以下の場面では、自然な形で自分をアピールしやすくなります。
- 会社説明会での質問
- 実務体験での改善行動
- ワーク中のリーダーシップ
- 社員との積極的な交流
①会社説明会での質問
会社説明会では、あらかじめ企業研究を行ったうえで、具体的かつ建設的な質問をすることで、企業への関心の高さや主体性を伝えることができます。
企業側も、「自社をしっかり調べたうえで参加している」という姿勢を評価します。
たとえば、単に「福利厚生について教えてください」ではなく、「御社の働き方改革の取り組みが印象的でしたが、具体的にどのような成果が出ていますか」といった質問にすると、情報収集の深さや考察力が伝わりやすくなります。
また、同じ説明会に参加している他の就活生も多いため、質の高い質問を投げかけることで、担当者の印象にも残りやすくなるでしょう。
緊張してしまう方も多いですが、事前に質問を紙にまとめておくなど、準備を工夫することで落ち着いて臨めます。
短期インターン中の質問の数は、意欲や志望度の高さに比例します。そのため、実際に会社説明会での質問の機会がある場合はぜひ発言しましょう。
採用担当者も会社説明会の段階で質問をたくさんしてくれる志望者の印象は格段によくなるため、事前に会社のことを調べて最低3つは質問を用意しておくと良いですよ。
②実務体験での改善行動
実務体験中は、与えられた業務をこなすだけでなく、問題点を自ら発見し、よりよくするための工夫や提案を行うことがアピールにつながります。
企業は、自ら考えて動ける人材を求めており、主体的な姿勢を評価する傾向があります。
たとえば、資料作成の作業中に、「このテンプレートを使えば入力の手間が減らせそうです」と提案したり、整理整頓されていない備品棚を見て、「ラベルを貼ったら探しやすくなるのではないでしょうか」と声をかけてみたりするのも一つの方法です。
こうした改善行動は、必ずしも成果が求められるわけではなく、「気づき」と「提案の姿勢」が見られることが大切です。
自分が気づいた点をどう表現するか、どのように伝えるかも含めて、現場の空気を読みながら臨機応変に対応しましょう。
改善提案は、成果よりも「気づいて動いたかどうか」が重要なんです。自分なりの工夫を小さくても実行に移す行動力は、想像以上に印象に残るものですよ。
実際に短期インターンでは、インターン自体が短いので、成果を出すことではなく取り組み方を注意深く見ています。「報告・連絡・相談」(報連相)を意識して積極的に行動しましょう。
③ワーク中のリーダーシップ
短期インターンでは、グループワークを通じてリーダーシップを発揮できる場面も多くあります。
ここで求められるのは、周囲を引っ張るような強引なリーダー像ではなく、チーム全体を意識して動けるバランス感覚のある姿勢です。
たとえば、進行役を務めて時間配分を気にしつつ、議論が偏っていれば「〇〇さんの意見も聞いてみたいです」と発言を促したり、話が散らかったときに「一度、意見を整理してみましょう」とまとめたりする役回りが有効です。
実際に「私は意見をまとめることが得意なので、進行役に立候補しました」と自己申告してリーダーを引き受けた学生が、社員から「冷静に全体を見ている姿勢が印象的だった」と評価されるケースもあります。
自分に合った形のリーダーシップを考え、無理のない範囲で貢献することがポイントです。
リーダーシップは「引っ張る力」だけじゃなく、場の空気を整える調整力や傾聴力も大切な資質として評価されます。
たまにリーダーシップを「自分が全部やる」と勘違いしているケースもあるのですが、自己中心的な行動はマイナス印象になってしまいます。「周りを引っ張る」ではなく、「チーム全体で前に進む」意識を持っておくと良いですよ。
④社員との積極的な交流
社員と直接話せる機会は、企業理解を深めると同時に、コミュニケーション力をアピールする絶好のチャンスです。
質問する内容や会話の仕方によって、「主体性がある」「話しやすい人だ」といった印象を与えることができます。
たとえば、業務の合間に「今回のインターンで感じたことを伝えてもいいですか」と話しかけ、気づいた点や感謝の言葉を述べると、前向きな姿勢が伝わります。
また、「新卒入社後、どんな経験をされましたか?」といった質問は、相手の実体験を引き出しつつ自然な会話につながります。
交流に積極的になると、社員が自分に興味を持ってくれることもあります。結果として、次回の面接時に「インターンで話した〇〇さんですね」と認識されるなど、良い影響が出るケースもあるでしょう。
遠慮せず、敬意を持って一歩踏み出す姿勢が評価される場面です。
社員との会話では、緊張しながらも自分の言葉で話そうとしている姿勢に、こちらも自然と好感を持ちます。
注意点としては、話しかけるタイミングです。交流会のような場ではもちろん積極的に話しかけるべきですが、社員の方が別の仕事をしている際などは無理に話しかけないようにしましょう。
短期インターンへの応募方法
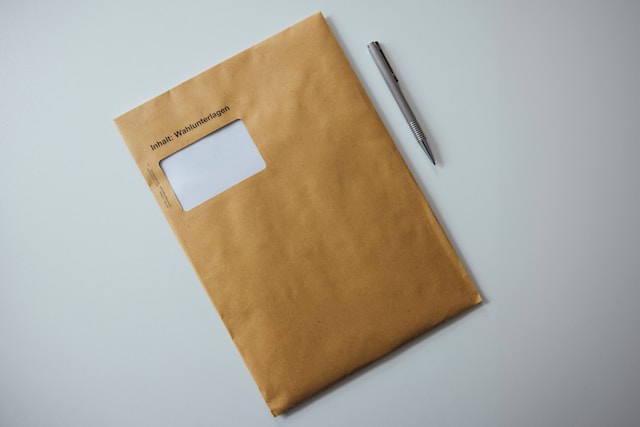
短期インターンに参加するには、エントリーから書類提出、連絡対応までの流れをしっかり把握することが大切です。
選考期間が短いため、段取りよく行動しないと、チャンスを逃してしまうこともあります。以下の5つのステップを押さえて、準備を進めていきましょう。
- エントリーの実施
- エントリーシートの提出
- 提出書類の確認
- 応募締切の確認
- 応募後の連絡
① エントリーの実施
短期インターンに参加するには、まずエントリーの手続きから始める必要があります。
ほとんどの企業はWebサイトやマイページを通じて応募を受け付けており、フォームに必要事項を入力すればエントリーは完了します。
ただし、入力項目の中には志望理由や希望職種など、内容次第でそのまま選考に反映されるものも含まれます。
たとえば「なぜその企業に興味を持ったのか」などは、面接時に深掘りされることもあるため、後から困らないよう丁寧に記入しておくことが重要です。
また、複数のインターンにエントリーする場合は、Excelなどで管理表を作成し、応募先や締切日を整理しておくとミスを防げます。
最初の段階でしっかり準備しておくことで、全体の応募活動がスムーズに進むでしょう。
② エントリーシートの提出
エントリー後、多くの企業で求められるのがエントリーシート(ES)の提出です。ここでは、自分の強みや志望理由を文章で伝える力が問われます。
特に短期インターンは応募数が多く、ESの内容で一次選考が行われるケースも少なくありません。ポイントは、抽象的な表現を避け、できるだけ具体的なエピソードを交えて記述することです。
たとえば「リーダーシップがあります」だけでなく、「アルバイトで新人指導を任され、マニュアルを自作して定着率を高めた経験があります」といった形にすると、説得力が増します。
また、締切直前は焦りがちになるため、自己分析や志望企業の研究は前もって済ませておくと安心です。
提出前には誤字脱字や文法ミスをチェックし、第三者に読んでもらうのも効果的です。内容の完成度が合否を左右するため、手を抜かずに丁寧に仕上げてください。
③ 提出書類の確認
ESのほかに、企業によっては履歴書・成績証明書・志望理由書などの追加書類を求める場合があります。これらは形式や提出方法が多様なため、企業の指定をきちんと確認する必要があります。
たとえば、PDF形式での提出が必要なのにWordのまま送ってしまう、成績証明書をスキャンせず写真で済ませるなど、些細なミスがマイナス評価につながることもあります。
大学を経由して参加するタイプのインターンでは、大学指定の書類や捺印が必要になることもあるため、キャリアセンターへの相談も忘れずに。
また、提出前にファイル名の付け方やデータ容量にも注意しましょう。ビジネスの基本でもある「指示に従う力」が、こうした提出物からも見られています。
提出書類は“第一印象”を左右するため、慎重に対応してください。
④ 応募締切の確認
インターン選考では、応募締切の確認が非常に重要です。なぜなら、短期インターンは実施時期が限られており、選考スケジュールも短い傾向があるためです。
たとえば、夏のインターンでは6月中旬〜下旬に締め切りが集中し、提出が数日遅れただけで参加できなくなるケースも珍しくありません。
しかも、一部企業では募集枠が埋まり次第、締切前でも受付を終了してしまうことがあります。
そのため、エントリー開始のタイミングで情報を収集し、できるだけ早めに提出を済ませておくことが大切です。
応募の集中する時期は、システムエラーやファイルアップロードのトラブルが起こりやすいため、締切ギリギリの行動は避けましょう。計画的なスケジュール管理が、選考突破のカギとなります。
⑤ 応募後の連絡
応募を終えたあとも、企業とのやりとりには注意が必要です。多くの場合、マイページやメールを通じて次の選考ステップや結果通知が届きます。
返信期限が短いことも多く、連絡を見逃すと辞退扱いになる可能性もあるため、こまめな確認が欠かせません。
通知が届いたら、内容をよく読み、できるだけその日のうちに対応しましょう。特に返信メールは、件名・敬語・署名などビジネスマナーに気を配り、誠意が伝わる文面を意識してください。
また、迷惑メールフォルダに振り分けられることもあるため、設定の見直しも忘れずに。短期インターンでのやりとりは、社会人としての姿勢も見られている場です。
丁寧で迅速な対応が、企業からの信頼にもつながります。
短期インターンの選考対策
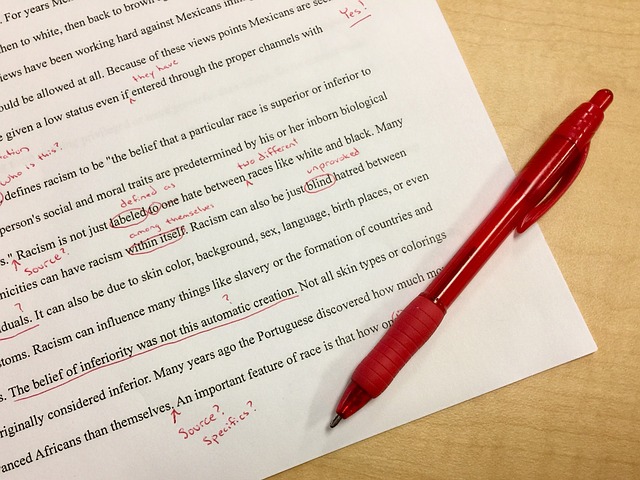
短期インターンの選考は短期間で判断されることが多く、事前準備の有無が合否を分けると言っても過言ではありません。
特に初めてのインターン参加では、不安や疑問が多いもの。ここでは、選考を突破するために必要な5つの対策と、その具体的な実践方法について詳しく解説します。
- 自己分析の実施
- 業界・企業研究の実施
- 志望動機を整理
- 面接練習の実施
- グループワーク対策の実施
① 自己分析の実施
選考で「あなた自身をどう説明するか」が問われる場面は非常に多くあります。
そのため、自己分析を通じて、自分の価値観や強みを客観的に理解しておくことが重要です。たとえば「責任感がある」「行動力がある」などの特性を、実際の経験をもとに説明できるように準備しましょう。
実施方法としては、自己分析用のワークシートやフレームワーク(例:モチベーショングラフ、他己分析、ジョハリの窓など)を活用するのがおすすめです。
ノートやPCに自分の経験を時系列で書き出し、「なぜそのときそう行動したか」「何を感じたか」まで深掘りすることで、より自分らしさが明確になります。
また、家族や友人に「自分ってどんな人?」と聞いてみると、意外な一面を知るヒントになるでしょう。他者の視点を取り入れることで、より立体的な自己理解につながります。
自己分析は「強みを並べる作業」ではなく、行動の背景にある自身の価値観を深掘りすることが本質です。実際に面接で質問を受けた際にエピソードと結びつけて語れるかどうかが、選考結果を大きく左右します。
就活サポートをする中で、自己分析をかなりしっかりと行っていますが、自己分析をする中で今までは考えていなかった価値観や強みが見つかるケースも多いですよ。
② 業界・企業研究の実
短期インターンといえども、業界や企業への理解が浅ければ、説得力のある志望理由を伝えるのは難しくなります。
どんな価値を提供しているのか、どのような課題を抱えているのかを事前に調べておくことが不可欠です。
まず業界研究では、業界地図や新聞・ビジネス誌の記事、大学のキャリア講座資料などを活用しましょう。情報収集を進めながら、自分の関心がどこに向くのかも見極めていくと、志望の軸が明確になります。
企業研究では、公式サイトのIR情報や採用ページを確認するほか、過去のインターン体験記や口コミサイトも参考にできます。
特に「なぜこの企業なのか」に答えるためには、競合との違いや独自性を見つける視点が役立ちます。
さらに、OB・OG訪問も非常に有効です。話を聞く際は、仕事内容だけでなく、職場の雰囲気や大切にされている価値観など、テキスト情報だけでは分からない部分に注目してみてください。
企業理解が浅いまま志望理由を語ると、どうしても表面的に聞こえてしまいます。「なぜこの企業なのか」に具体的に答えられるかが志望度の高さを表すので、評価の分かれ目になりますよ。
ありがちなのが、志望している企業のことだけを調べているケースですが、企業研究はいくつかの競合他社を比較しながら検討しましょう。その中で、他の企業にはない志望動機が見つかりますよ。
③ 志望動機を整理
「なぜこの企業でインターンをしたいのか」を明確に伝えるには、自分の過去の経験や関心と企業の特徴を結びつけた動機を構築する必要があります。具体的であるほど、企業にとっても評価しやすくなります。
そのためには、まず紙やWordなどに「自分がやってきたこと」「そのとき感じたやりがい」「どんなスキルを身につけたか」を箇条書きにして整理しましょう。
そのうえで、「企業の提供する業務や学び」との共通点や接点を探します。
たとえば、接客アルバイトで感じた課題解決へのやりがいや、人を喜ばせる楽しさを、企業の取り組みに結びつけるといった具合です。実際に文章に起こしてみることで、話の流れや構成の不足にも気づけます。
また、他の企業の志望動機と見比べて、言い回しが似ていないか、他社にも通じる内容になっていないかを確認してください。
志望動機の「練習用フォーマット」を使って、何パターンか書き分けてみるのも効果的です。
志望動機は、「企業理解」と「自己理解」の接点を見つける作業なんです。そのため、どちらか一方だけでは説得力が弱くなってしまうので、難しさを感じ得る就活生が多いんですね。
ただ短期インターンでは、「就活のための経験として参加している」方が多いので、志望動機はづしても浅くなってしまいます。その際は、就活のためではなく、今後の自身のために個の能力を高めたいなどの志望動機を伝えると好印象になりやすいですよ。
④ 面接練習の実施
面接の場では、自分の考えを端的に、かつ自然に伝えることが求められます。緊張でうまく話せないことを避けるためにも、繰り返し練習を重ねることが大切です。
まずは家族や友人に面接官役をお願いし、想定質問に答える練習をしてみましょう。客観的なフィードバックをもらえることで、自分では気づきにくい癖や弱点が見えてきます。
対面での練習が難しい場合は、スマートフォンで自分の回答を録画し、あとで再生して確認する方法もおすすめです。
その際、「声のトーンは聞き取りやすいか」「表情が硬くなっていないか」「話が長くなりすぎていないか」など、多角的にチェックしましょう。
また、大学のキャリアセンターや自治体が提供する就活支援サービスで模擬面接を受けるのも有効です。
練習の回数を重ねることで、緊張に強くなり、自然体で面接に臨めるようになります。
面接練習は「話す」だけでなく、「どう伝わっているか」を確かめる作業でもあります。録画やフィードバックを活用して、第三者視点を取り入れるのがコツですよ。
短期インターンの参加する場合は、面接経験がゼロの就活生が多いので、事前に面接練習をしておくことで周りに差をつけることができますよ。
⑤ グループワーク対策の実施
グループワークでは、自分の意見を述べる力だけでなく、他者との協働姿勢や課題解決能力が見られます。そのため、本番前に形式に慣れておくことが極めて重要です。
まずは、大学のゼミや就活イベントなどで開催されるワークショップに参加してみましょう。オンライン型のグループディスカッション練習サービスなどもあり、手軽に体験を積むことができます。
練習の際は、テーマに沿って発言するだけでなく、「意見をまとめる」「他人の発言を引き出す」「制限時間を意識する」など、さまざまな役割を経験するようにしてください。
また、議論後にはグループ内で「どうすればもっと良いチームになれたか」を振り返る時間を設けると、実践的な学びにつながります。
日頃からニュース記事を読んで社会課題に関心を持っておくことも、議論の引き出しを増やすうえで効果的です。いざ本番となったときにも、自然に意見を出せる状態にしておくことがポイントです。
グループワークで評価されるのは発言の多さではなく、チームの成果にどう貢献したかという「関わり方の質」なんです。役割に応じた行動を意識するとバランスの良い印象になりますよ。
また、グループワークでは輪を乱す人もたまにいますが、そのような人の評価はもちろん良くありません。居合わせてしまったら、その人も含めてチーム全体でゴールを目指す姿勢をアピールするとうまくかわせますよ。
短期インターン選考時の注意点

短期インターンの選考は形式的なものに見えても、基本的なマナーや対応姿勢が評価の対象となります。
準備不足や軽率な行動は、思わぬマイナス評価につながることもあるため、細かな点まで意識して臨むことが大切です。
- 締切厳守
- 連絡手段の確認
- 服装や言葉遣い
- 結果確認後の対応
- 辞退時の連絡
① 締切厳守
選考書類の提出やエントリーフォームの入力など、定められた期限を守ることは最低限のマナーです。締切を守れない応募者は、それだけで社会人としての信頼性に疑問を持たれてしまいます。
とくに短期インターンは募集期間が短く、応募が集中する傾向があります。早めに行動しないと定員オーバーで受付が終了してしまうケースもあります。
就活が本格化する前の段階でも、「早めに動ける人材かどうか」は企業にとって注目されるポイントです。
たとえば、「締切当日に出そう」と思っていたところに大学の課題が重なり、結果としてエントリーが間に合わなかったという例は珍しくありません。万全を期すなら、提出物は2日前までに完成させておくのが理想です。
締切を守る姿勢は、スケジュール管理能力や責任感の有無を企業に伝える重要なサインとなります。余裕を持った行動を常に心がけましょう。
② 連絡手段の確認
企業との連絡は、メールを中心にLINEや電話など複数の手段が使われることがあります。連絡が取れなかっただけで選考が無効になることもあるため、常に連絡手段を確認できる体制を整えておくことが大切です。
短期インターンの案内は、急に届くことも多く、通知の見落としや迷惑メールへの振り分けに気づかないまま締切を過ぎてしまうこともあります。
連絡ミスは「確認不足=注意力が低い」と評価される要因になるため、細心の注意が必要です。
たとえば、Gmailを使っている就活生で、企業のドメインが迷惑メールフォルダに自動分類され、返信が遅れて不参加扱いになってしまったという例があります。受信設定や通知確認の習慣化が重要です。
大切な連絡を確実に受け取れるよう、メールアプリの通知をオンにし、迷惑メールフォルダもこまめにチェックする習慣をつけておきましょう。
③ 服装や言葉遣い
第一印象は数秒で決まるといわれるほど、外見や話し方は選考に大きな影響を与えます。選考当日は「その場にふさわしい姿勢」で臨むことが信頼につながります。
たとえば、「私服可」と案内されても、スーツを着用することで誠実な印象を与えられます。逆にカジュアルすぎる服装は「TPOの判断が甘い」と受け取られる可能性があります。
また、オンライン選考であっても服装は上半身だけでなく、全身を整えておくと安心です。
言葉遣いに関しても、基本的な敬語を使い、語尾まで丁寧に話すことが重要です。たとえば「〜っすね」といった砕けた言葉や、「あざっす」など略語は避けましょう。
話し方で社会人基礎力が伝わることを意識してください。
服装と話し方は、自己管理能力や常識の有無を判断される要素です。どんな場でも通用する振る舞いができるよう、日頃から意識しておくと安心です。
④ 結果確認後の対応
合否の連絡が届いた後は、返信の早さと内容の丁寧さが印象を左右します。とくに合格の連絡をもらった場合、参加意思の返信がなければ、辞退とみなされることもあるため注意が必要です。
就活では「連絡のスピード=誠意」と捉えられる傾向があり、返信が早いだけで印象が良くなることもあります。逆に、返信が遅いと「やる気がないのでは?」と疑念を持たれる場合があります。
たとえば、「2日以内に返信してください」と記載されていたにもかかわらず、3日後に返信したために参加権が無効となったケースも見られます。
通知を受け取ったら、可能な限りその日のうちに返信を済ませておくのがベストです。
合否結果を受けたあとの対応も、企業はしっかり見ています。短期インターンとはいえ、本選考と同じ意識で丁寧にやりとりしましょう。
⑤ 辞退時の連絡
参加を辞退する場合も、就活マナーとして誠実な連絡が求められます。特に短期インターンは人数が限られていることが多く、無連絡での辞退は他の参加者や企業に迷惑をかけてしまいます。
辞退連絡はできるだけ早めに行い、簡潔かつ丁寧に理由を伝えることが基本です。「他社と日程が重なったため」「大学の都合で参加が難しくなった」など、事実を端的に伝えるだけでも問題ありません。
たとえば、体調不良で前日に辞退した就活生が、早朝に電話とメールの両方で謝罪を入れたことで、企業から「丁寧な対応だった」と評価されたケースがあります。
辞退はマイナス評価ではなく、対応の仕方で印象が決まります。
社会人としての姿勢は、こうした小さな場面でも問われます。辞退する際も、相手の立場に立った行動を心がけましょう。
短期インターン参加時の注意点

短期インターンに参加する際は、「学生だから多少は大目に見てもらえるだろう」と思いがちですが、実際には社会人としての振る舞いが強く求められます。
特に企業側は、短期間でもインターン生の素養や姿勢を細かく見ています。ここで信頼を得られれば、本選考時の評価にも好影響を与える可能性があります。
逆に、基本的なマナーや配慮が欠けていれば、印象が大きく下がることもあるため要注意です。ここでは、参加前に意識すべき5つのポイントを紹介します。
- 社会人としてのマナー
- 言葉遣い
- 企業ごとのルール
- 体調管理
- スケジュール調整
① 社会人としてのマナー
短期インターンであっても、ビジネスの場においては社会人と同様のマナーが求められます。たとえば、集合時間の10分前には到着し、元気な声で挨拶をするだけでも好印象につながります。
実際、「時間を守れるか」「挨拶ができるか」といった基本動作は、仕事の能力以前にチェックされている項目です。とくに短期インターンでは一人ひとりの印象が短期間で決まってしまうため、マナーの差が目立ちやすい傾向にあります。
「学生だから」ではなく、「企業の一員としてどう振る舞うべきか」を意識することで、自然と相手に信頼感を与えることができるでしょう。
短期インターンでも「時間を守る・挨拶をする」は当たり前に厳守しましょう。仮に時間を守れなかったり、挨拶ができていない場合はそれだけで、印象がかなり悪くなってしまいます。
事前に基本的なビジネスマナーは網羅しておき、実践できるレベルまで準備しておいてやっとスタートラインですよ。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
② 言葉遣い
短期インターンでは、社員との会話やミーティングへの参加など、社会人と接する場面が少なくありません。そのため、言葉遣いの丁寧さと正確さが大切です。
たとえば、「了解しました」はビジネスではやや軽い印象を与えるため、「承知いたしました」といった表現が好まれます。また、「〜でよろしかったでしょうか?」のような曖昧な過去形も避けた方が無難です。
初めは緊張して言葉が出にくいかもしれませんが、事前にビジネス敬語の基本を押さえておくだけでも、落ち着いて受け答えしやすくなります。
言葉遣いはあなたの印象を左右する大きな要素です。自然に使えるよう、日頃から意識しておくと安心です。
③ 企業ごとのルール
短期インターンに参加すると、「会社ごとにこんなにルールが違うのか」と驚くこともあるでしょう。
たとえば、社内での服装基準、私物の取り扱い方、社外への情報発信に関する注意など、学校では体験できない細かな規定が存在します。
こうした企業独自のルールを軽視すると、たとえ悪気がなくても「空気が読めない学生」と見られてしまう可能性があります。企業文化を尊重し、説明された内容をきちんと理解しようとする姿勢が求められます。
もし疑問点があればそのままにせず、上司や担当者に確認する習慣を持つことが大切です。ルールを守ろうとする姿勢は、誠実さや責任感のある人物として評価されやすくなります。
企業ならではのルールは必ずあるので、まずはルールを確認することを意識しましょう。
まだ社会人として歴が浅い時に自己判断でルールを認識していると方向性を間違えてしまうケースがほとんどです。まずは確認して理解したら厳守を徹底しましょう。
④ 体調管理
インターン当日に体調を崩してしまうと、参加できないだけでなく、企業側にも迷惑がかかるため注意が必要です。とくに短期インターンではスケジュールに余裕がないため、欠席が大きな機会損失になることもあります。
事前に睡眠や食生活を整えておくことはもちろん、感染症が流行する時期にはマスクや消毒の徹底も意識しておきたいところです。
万一、当日体調が悪くなった場合は、早めに連絡を入れ、対応を仰ぐことも社会人としての対応力の一つといえるでしょう。
元気に最後まで取り組めることが、結果として良い評価につながります。参加前からのコンディション調整を怠らないように注意しましょう。
⑤ スケジュール調整
短期インターンは、参加日数が少ない分、一日一日の重みが大きくなります。そのため、授業やアルバイトとの調整が甘いと、「自己管理ができない学生」という印象を持たれてしまうリスクがあります。
インターンのスケジュールが決まった時点で、他の予定をすぐに確認し、調整しておくことが重要です。また、交通手段や移動時間にも余裕を持ち、予期せぬトラブルにも対応できるようにしましょう。
Googleカレンダーなどのアプリを使って通知設定をするのも一つの方法です。
社会人になるとスケジュール管理は基本的な能力として見られるため、インターン期間中から意識して習慣づけておくと本選考でも役立ちます。
体験談から学ぶ短期インターンの選び方とは?
短期インターンと一口に言っても、企業ごとにその内容や雰囲気は大きく異なります。「せっかく参加したのに、あまり得るものがなかった…」という声も珍しくありませんよね。
ここでは、そうしたギャップに直面した就活経験者が、どのようにしてインターンの選び方を見直し、自分にとって価値のある経験を得たのかを紹介します。
今回は、事前に得られる情報だけでは見抜きにくい「参加してみて分かったリアルな違い」と、そこから導き出された判断基準について語ってくれた体験談を紹介しています。
| Kさん(21歳・私立大学3年・経済学部)の体験談 |
|---|
| 私は大学3年の夏に、3日間の短期インターンに参加しました。最初は「有名企業だし行っておけば安心かも」くらいの軽い気持ちだったんですよね。でも、いざ参加してみると説明中心でグループワークもなくて、正直ほとんど印象に残らなかったんです。 その反省を活かして、次は「社員の方と直接話せる」「アウトプットの場がある」と明記されていた別の企業の短期インターンに参加しました。そこでは、実際の業務をテーマにしたディスカッションや発表の場が用意されていて、社員の方からフィードバックももらってしまいました。 そのとき、初めて「自分は人前で話すときに論点がズレやすいんだな」とか、「チームの中でどう役割を取るかが大事なんだ」っていうことに気づけて短いインターンの中でも学びを得られたなと感じました。 そして、単に企業を知るだけじゃなくて、自分の課題や強みにも向き合える機会になったなと思っています。 短期インターンって数日しかないけど、選び方次第で得られるものは本当に違うんだなと実感しました。 |
Kさんの体験談では、「参加しやすさ」や「知名度」だけを軸に短期インターンを選んだ結果、得られる経験が非常に限定的だったみたいですね。
一方で、目的意識を持って選んだ2社目のインターンでは、数日間でも大きな気づきを得ることができました。これは、短期であっても実践的なプログラムや社員との接点が設けられているかどうかが、学びの質に直結することを示しています。
初めの失敗を経て、「どんな経験ができるか」を見極める目を養った点も見逃せません。ただ参加するだけでなく、事前情報の中から「フィードバックの機会があるか」「自ら発信する場があるか」といった要素を見極められれば、短期でも本質的な成長につながるインターンを選べるようになります。
限られた時間の中で自身の成長につながるインターンを選択できるかが短期インターン参加への重要な判断基準になりそうですね。
実は、学生向けに公開されているインターン情報の中には、内容が薄い説明会型のものが紛れていることがあります。
見極めの際は、募集要項に「ワーク」「フィードバック」「発表」といったように、アウトプットの場が設けられているのかをしっかりと確認しておきましょう。
また、応募時点でプログラム構成を問い合わせたり、過去参加者の声を探したりするだけでも、得られる情報の精度はぐっと上がるので、事前調査はしっかりと行いましょうね。
短期インターンの参加前にメリットとデメリットを理解しておこう!

短期インターンは、業界理解や自己分析の深化に直結する貴重な機会です。
特に、長期インターンとの違いを把握したうえで目的を明確にし、探し方や選考対策を早めに行うことが成功のカギとなります。
例えば、企業の採用ページや就活サイトを活用することで効率よく情報収集ができ、ESや面接準備にも役立ちます。また、実際に参加する際は、企業ルールや社会人マナーに配慮した行動が求められます。
短期インターンのデメリットにも目を向けつつ、選考時や参加中の注意点を踏まえて行動することで、本選考でのアピール力が高まりやすくなります。
就活の一環として短期インターンを効果的に取り入れることで、自分の適性や志望企業への理解が一層深まるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










