出版社のインターン選考対策を徹底解説|予備知識やES対策も紹介
この記事では、出版社インターンに受かるための対策と準備法を徹底解説しています。
また、インターンの選考で活かせる業界の傾向や仕事内容の知識や、エントリーシート(ES)対策も紹介しているので、出版社が気になっている方は必見の内容ですよ。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る出版社のインターンシップへ参加するには対策が必要
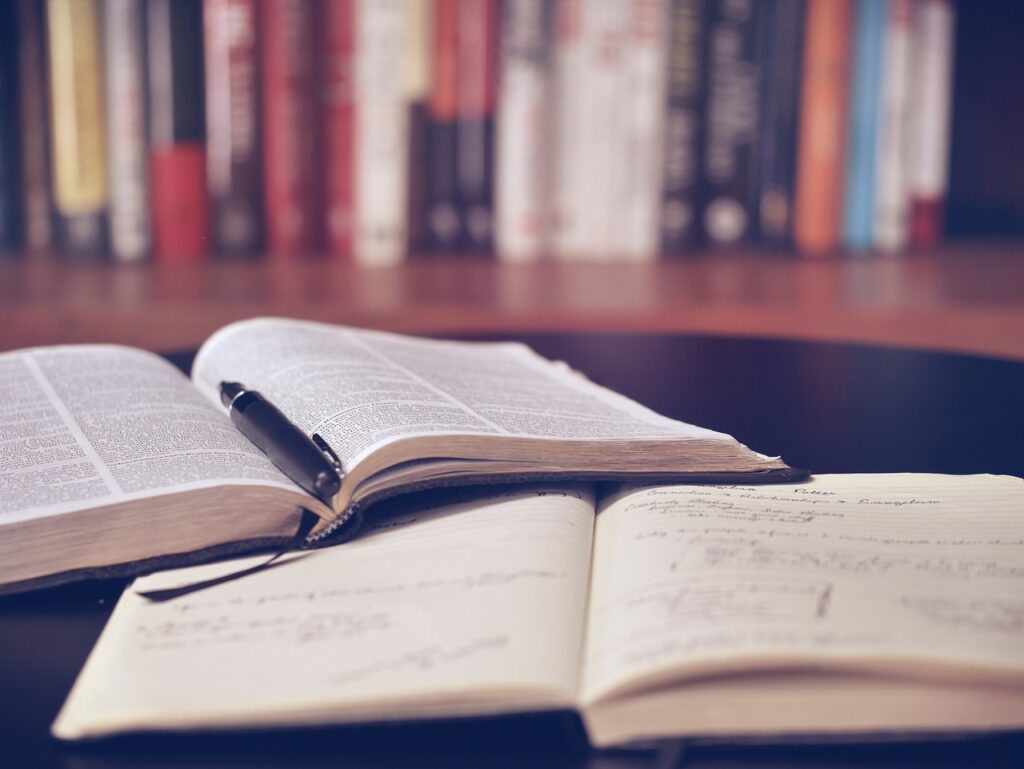
出版社のインターンシップに参加するには、しっかりとした準備が欠かせません。
というのも、出版業界は志望者に人気がある一方で、インターンの募集人数が限られているケースが多く、選考は簡単ではないからです。
まずは業界研究を行い、各出版社の特徴や得意ジャンルを把握しておくことが重要です。さらに、志望理由や自己PRに一貫性を持たせれば、より説得力のある応募書類を作成できます。
また、過去のインターン内容やES(エントリーシート)の傾向を調べておくと、準備が具体的になります。対策をしないまま選考に臨むと、自分の力を十分に発揮できないまま終わってしまうかもしれません。
万全の準備でインターンに臨み、出版業界への第一歩を確実に踏み出してください。
出版系では、本が好きという熱意だけでなく「文章を正確に伝える力や論理的思考力」が合否を分ける鍵になります。ESを書く際も、一貫性のある伝わりやすい文章を意識しましょう。
また、過去のインターン情報やESの傾向は、OB・OG訪問や説明会での質問から掴むのがおすすめです。ここで得た一次情報は差別化に直結しますし、具体性のある準備につながりますよ。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
出版業界の傾向
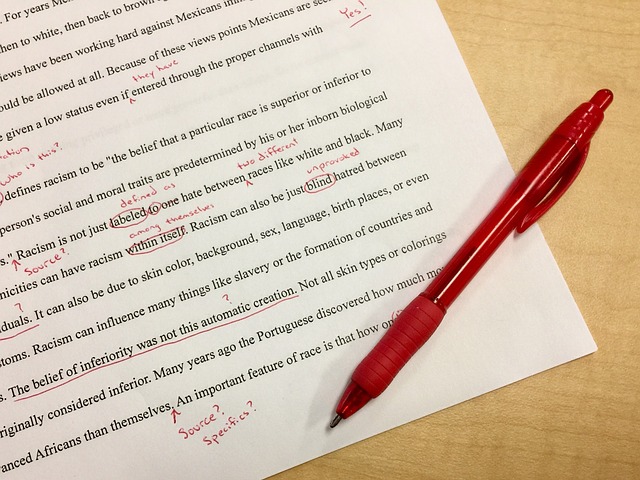
出版業界に関心を持つ就活生にとって、今の動向を正しく理解しておくことは非常に大切です。ここでは、知っておきたい主要な3つの傾向を紹介します。
- 紙媒体の減少と電子書籍の成長
- Web・SNS・動画など発信手段の拡大
- 大手出版社への売上集中と中小の専門特化
① 紙媒体の減少と電子書籍の成長
出版業界では、紙の本や雑誌の販売が年々減少しています。一方で、スマートフォンやタブレットの普及により、電子書籍が急速に広がっています。
移動中や空き時間に手軽に読める点が、多くの読者に支持されているのでしょう。この変化に対応するため、出版社もデジタルコンテンツの制作や配信に力を入れ始めています。
出版といえば紙という固定観念を持ち続けると、就活時のアピールが時代とズレてしまうおそれがあります。紙と電子の役割を整理し、どちらにも目を向ける視点を持っておくことが大切です。
② Web・SNS・動画など発信手段の拡大
情報を届ける手段として、紙に加えてWebサイトやSNS、YouTube、TikTokといった動画メディアの活用が広がっています。
出版各社は、より多くの人に作品や作家を知ってもらうため、こうしたデジタルツールを戦略的に使い始めているのです。
文章力だけでなく、発信の仕方そのものが変わってきている今、編集者にはマーケティング感覚やデジタル知識も求められるでしょう。
ただ「本が好き」と伝えるだけでは足りません。多角的な視点を持つことで、企業が本当に求めている人材像に近づけるはずです。
③ 大手出版社への売上集中と中小の専門特化
集英社や講談社といった大手出版社に売上が集まっている一方で、中小出版社は独自の専門分野に特化することで存在感を保っています。
たとえば、学術書や趣味系ジャンルに強みを持つ出版社は、特定の読者層に根強く支持されているのです。就活においては、企業の規模だけでなく、自分が関わりたい分野や働き方にも注目することが重要。
大手には大手の魅力があり、中小には中小の良さがあります。先入観にとらわれず、視野を広く持って企業を選んでみてください。
出版社の仕事内容

出版社には複数の職種があり、それぞれが出版物の完成に向けて重要な役割を担っているのです。ここでは、就職活動をする学生が押さえておきたい主な仕事内容を紹介します。
- 編集職
- 営業職
- 校閲・校正
- 制作・進行管理
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
① 編集職
編集職は、出版物の企画から完成までを一貫して担う、いわば作品のプロデューサーのような存在です。
具体的な業務には、企画立案、著者とのやりとり、原稿の校正、レイアウトやデザインの指示、印刷所との調整などがあります。読者のニーズをとらえる力と、それを形にする企画力が求められる仕事です。
また、制作スケジュールを調整したり、関係者とのやりとりを円滑に行ったりする調整力も不可欠です。自分の関わった本が店頭に並ぶ瞬間は大きな達成感があります。
責任も大きいですが、その分やりがいを強く感じられるでしょう。出版業界を志すうえで、まず理解しておきたい中心的な職種です。
編集職は、著者やデザイナー、営業部門との橋渡しを担います。売れる本に仕上げるには、市場動向や書店の傾向を読み取る力が必要で、単なる校正以上に戦略的な視点が求められますよ。
また、現場では突発的な原稿遅延やデザイン変更などのイレギュラー対応が頻発することも。こうした場面で臨機応変に動ける人材は編集職で重宝され、柔軟さや交渉力が養われるのです。
② 営業職
営業職は、出版社と書店・取次・流通の橋渡しをする役割を担い、出版物が広く読者に届くよう働きかける仕事です。
主な業務は、書店や取次店への販売提案、販促企画の立案、売上データの分析など。売れ筋の把握や市場動向の読み取りを通じて、次に売れる本を見つける役割も担っています。
さらに、編集部と連携して発売前から情報を共有し、効果的なプロモーションにつなげることもあります。ただ本を配るだけではなく、本の価値をどう伝えるかというマーケティング視点も重要です。
人と話すのが得意な方や数字に強い方には、非常に向いている職種といえるでしょう。
営業職では、「どの本を推すか」の判断が必要不可欠です。売上データだけでなく、店員やお客様の声もヒントにし、その両方を踏まえて考察できる人が重宝されますよ。
また、発売前の仕掛け次第で売れ行きが左右されるため、発信力や企画力も必要です。自分の提案が全国の売上につながる実感が得られるのは大きなやりがいになります。
③ 校閲・校正
校閲・校正は、出版物の正確さを支える重要な仕事です。原稿の誤字脱字や表記の統一はもちろん、固有名詞の誤りや事実確認まで細かくチェックします。
読者に誤った情報を届けないために、非常に高い集中力と粘り強さが求められる職種です。たとえば、歴史や科学、法律など専門的な内容が含まれる場合には、知識を活かして誤りを正す場面もあります。
華やかさはないかもしれませんが、ミスのない信頼される本づくりには欠かせません。地道な作業をコツコツ積み重ねることが得意な方にとっては、大きな強みを発揮できる仕事です。
④ 制作・進行管理
制作・進行管理は、出版物の制作がスムーズに進むよう、スケジュールや工程を管理する役割を担っています。
編集者、デザイナー、印刷会社など、さまざまな関係者と連携しながら、納期通りに本が完成するよう全体をコントロールします。
たとえば、進行に遅れが出た場合のリスケジュールや、印刷所への入稿準備など、細かな調整業務が多く発生します。特にトラブル時の対応力や、冷静に物事を判断する力が求められるのです。
目立つ存在ではありませんが、出版現場を支える縁の下の力持ちです。複数の作業を同時進行できるマルチタスク力が活かされる仕事でしょう。
出版社インターンシップの種類

出版社のインターンシップには2つの形式があり、期間や内容によって得られる経験が異なります。自分の目的やスケジュールに合ったインターンを選ぶことで、就活のアピール材料としても効果的です。
ここでは、代表的なインターンの種類を2つ紹介します。
- 短期インターン
- 長期インターン
① 短期インターン
短期インターンは、1日から数日間で実施されることが多く、出版社の仕事をコンパクトに体験できるのが特徴です。
編集部や営業部でのワークショップ形式が中心で、業務の全体像をつかむには良い機会といえるでしょう。ただし、期間が短いため、深い実務経験を積むのは難しいかもしれません。
その分、企業ごとの雰囲気や方針を知るには十分です。特に業界研究や企業選びの初期段階では、効率よく情報を得られる手段といえるでしょう。
参加後は、自分なりの気づきを振り返り、エントリーシートや面接でしっかり言語化して伝えることが重要です。
短期インターンでは、インターン中の評価をそのまま選考に反映させるケースもあります。体験型であっても評価の対象になることを意識しましょう。
また、短い時間で得られる情報は限られるので、参加後にどれだけ振り返りを深められるかで差が出ます。「具体的に学んだこと」を整理することが大切ですよ。
② 長期インターン
長期インターンは、数週間から数か月にわたり、実際の業務に深く関わることができます。編集会議への出席や企画立案、原稿の確認や校正など、出版のリアルな現場を経験できるのが魅力です。
実践的なスキルを身につけたい方には非常に有益ですが、選考は短期よりも厳しく、参加には一定の覚悟が必要です。学業やアルバイトとの両立も考慮しながら、無理のない計画を立ててください。
内容が濃いため、志望度が高い企業での参加には特におすすめです。自身の適性を確かめる貴重な機会となるでしょう。
長期インターンでは成果を求められることも多いです。編集業務以外にも営業やマーケティングとの連携を経験することもあるため、出版業界を立体的に理解できますよ。
また、評価が選考に直結することも多くあります。現場で信頼を得られるかどうかが、内定の影響することも少なくないため、誠実さを意識して取り組みましょう。
出版社インターンシップに参加する前に知っておきたいこと

出版社のインターンシップは就活生からの人気が高く、参加するには早めの準備が欠かせません。ここでは、エントリー前に押さえておきたい基本情報を紹介します。
- 募集時期は夏と冬が中心
- 倍率は高く募集枠は少ない
- エントリーには早めの情報収集が重要
① 募集時期は夏と冬が中心
出版社のインターンは、例年夏(8月前後)と冬(2月前後)に行われることが多いです。通年で募集している企業は少なく、タイミングを逃すと半年以上待つことになるかもしれません。
講義や試験と重なりやすいため、早めにスケジュールを確認しておくと安心です。特に大手では、夏のインターンが本選考につながるケースも見られます。
参加を目指す場合は、企業の公式サイトや就活情報サイトを定期的にチェックしておきましょう。早めの準備が、確実なエントリーにつながります。
② 倍率は高く募集枠は少ない
出版業界のインターンは志望者が多く、募集枠が限られているため、非常に倍率が高い傾向にあります。企業によっては数名しか採用しない場合もあり、対策なしでは通過が難しいでしょう。
大手出版社では、1つの枠に数百人が応募することも珍しくありません。他の就活生と差をつけるためには、自分の強みや志望動機を明確にし、説得力のあるESを準備することが重要です。
早い段階から選考対策を始めてください。
出版インターンの倍率は一般的な企業よりも突出して高いのが実情です。大手になるほど知名度や人気も相まって応募が殺到し、エントリーシート通過率が1割を切るケースも。
選考の第一関門を突破できるかどうかが大きな分岐点になります。出版業界の中でもなぜその会社なのか、どんな本や企画に携わりたいのかまで掘り下げることが、選考通過の上で重要です。
③ エントリーには早めの情報収集が重要
出版社のインターンに申し込むには、情報収集のタイミングが結果を左右します。
採用情報は企業の公式サイトや大手ナビサイトに加え、SNSで突発的に告知されることもあるため、こまめなチェックが必要です。
特に、興味のある出版社が決まっているなら、公式アカウントをフォローしておくと安心です。また、過去のインターン参加者の体験談を調べておくことで、エントリー後の準備にも役立ちます。
早めに動いた人ほど有利になりやすいのが実情です。
出版社のインターンの募集は一斉公開ではなく、告知タイミングが企業ごとに異なります。エントリーは早い者勝ちになるケースも多いので、情報を常にチェックする姿勢が大切です。
私たちも相談を受ける中で「募集が出ていたのに気付けず、締切後だった」という声を耳にします。公式サイトやSNSの情報をリスト化するなど、情報の取得経路を整理しておくと安心ですよ。
インターンができる出版社

出版社のインターンに参加する前に、どの企業が実施しているかを把握しておくことが大切です。自分の関心や志望に合った企業を選ぶことで、応募準備もしやすくなるでしょう。
ここでは、代表的なインターン実施企業を4社紹介します。
- 株式会社講談社
- 株式会社集英社
- 株式会社光文社
- 株式会社KADOKAWA
「有名企業でなくてもまずは内定を目指したい…」「隠れホワイト企業を見つけたい」方には、穴場求人も紹介しています。第一志望はすでに決まっているけど、他の業界や企業でも選考に参加したい方は非公開の穴場求人を確認してみてくださいね。キャリアアドバイザーがあなたに合う求人を紹介してくれますよ。
① 株式会社講談社
講談社では、短期のワークショップ型インターンが行われています。実際の編集業務を模した企画立案や誌面づくりなどを体験でき、出版社の仕事を具体的に理解できるでしょう。
応募者が多いため選考は厳しめですが、そのぶん内容は濃く、得られる学びも大きいです。選考ではエントリーシートや面接があり、企画力や志望理由の明確さが重視されます。
本気で出版業界を目指す人にとって、参加する価値のあるインターンといえるでしょう。
② 株式会社集英社
集英社のインターンは、書籍や雑誌などジャンルごとに実施されるケースが多く、自分の興味に合った分野を選べるのが特徴です。
課題に取り組みながら、編集やプロモーションなど出版の工程を学ぶことができます。プログラムには、座談会やケーススタディが含まれることもあり、現場の雰囲気をつかみやすい点が魅力です。
応募時には、企業研究と業界理解を十分に行っておくことをおすすめします。
③ 株式会社光文社
光文社は、女性誌やライフスタイル系雑誌で知られる出版社です。インターンでは、それらの媒体に関する企画や編集体験を行うプログラムが中心となっています。
少人数制のため、担当者からの丁寧なフィードバックが受けやすい環境です。企業ごとに求められる人物像は異なるため、事前に媒体や社風を理解しておくことが重要です。
志望動機では、具体的にどの雑誌に関心があるかを伝えると効果的でしょう。
④ 株式会社KADOKAWA
KADOKAWAは、出版だけでなくアニメや映画、Webメディアなど幅広い事業を展開する総合コンテンツ企業です。そのため、インターン内容も編集にとどまらず、マーケティングや企画など多岐にわたります。
現場に近い業務体験を通じて、エンタメ業界全体の流れを学べる点が特徴です。応募には柔軟な発想力や協調性が求められるため、自己PRの際にもそれらの資質を具体的に示しておくと良いでしょう。
出版社インターンに参加するコツ

出版社のインターンは競争が激しく、ただ応募するだけでは通過が難しいのが実情です。ここでは、少しの工夫でチャンスを広げる3つのポイントを紹介します。
- 大学1〜2年生のうちから準備を始める
- 有名出版社以外も選択肢に入れる
- Webメディアや電子書籍系も選択肢に入れる
① 大学1〜2年生のうちから準備を始める
出版社のインターン選考は本番さながらに厳しいケースが多いため、早めの準備が差を生みます。
大学1〜2年生のうちから、出版に関係するアルバイトやライティング経験を積んでおくと、自己PRで具体的な実績を語れるようになるはず。
また、業界や企業の情報を先に集めておけば、自分に合った会社が見つかりやすくなるでしょう。時間をかけた分だけ自信もついてきます。急に対策を始めるより、少しずつ準備を進める方が効果的です。
大学1〜2年生のうちから出版関連の経験を積んでいる人は、選考時に「熱意」だけでなく具体的な根拠を示せます。実績の裏付けがあると差別化にもつながるので、時間のあるうちに挑戦するのがおすすめです。
私たちも面談をする中で、慌てて準備した学生ほど視野が狭くなりがちだと感じますね。早めに業界研究を始めれば、自分に合う企業を見極めやすくなるため、余裕を持った準備を心がけてください。
② 有名出版社以外も選択肢に入れる
多くの学生が大手出版社を志望しますが、枠が非常に限られており倍率も高くなりがちです。そこで、中堅や専門出版社も視野に入れることが重要ですよ。
こうした企業では、実務に近い体験ができたり、社員と距離が近かったりと、学びの多い環境に出会えることがあります。知名度だけで判断せず、自分が何を学びたいのかを基準に探してみてください。
視野を広げることがチャンスを増やすコツです。
有名出版社にこだわらず専門出版社や業界誌を扱う会社に目を向けると、自分の適性や興味を確認できることがあります。複数社受けることで様々な業務を体験できる点もメリットですね。
実際に、大手以外の出版社も受けたインターン生から「幅広い業務に関わり成長できた」という声を聞きます。ネームバリューより成長機会を軸にすると、質の高い学びを得られますよ。
③ Webメディアや電子書籍系も選択肢に入れる
出版と聞くと紙媒体を思い浮かべる人も多いですが、近年ではWebメディアや電子書籍を中心に事業を展開する企業も増えています。
これらの企業では、SNS運用やコンテンツ企画などデジタル領域のスキルも学べるでしょう。スピード感がある現場では、学生でもアイデアを出しやすく、実践の場が多いのも特徴です。
紙に限定せず業界全体の変化を捉えておけば、就活の選択肢も広がります。
出版社インターンのエントリーシート(ES)対策

出版社のインターンに応募する際は、エントリーシート(ES)の内容が合否を大きく左右します。熱意を伝えるには、自分の経験や考えを分かりやすく表現することが大切です。
ここでは、ESを作成するときに意識したいポイントを5つ紹介します。
- 出版物や編集方針を調べて志望動機を深める
- インターンでの目標と学びたいことを明確にする
- 具体的な経験を用いて熱意と主体性を伝える
- 自己分析を通じて出版社との適性を伝える
- 言葉選びや構成に気を配り読みやすく仕上げる
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
① 出版物や編集方針を調べて志望動機を深める
説得力のある志望動機を伝えるには、応募先の出版社がどんなジャンルの本を出し、どんな価値観を持って編集しているのかを事前に調べることが欠かせません。
「本が好き」だけでは印象に残らず、他の応募者と差がつきにくくなります。たとえば、特定の作品や雑誌に感銘を受けた経験があれば、その理由を含めて自分の言葉で説明してください。
「〇〇という連載で、日常を丁寧にすくい取る視点に共感した」といった具体性があると、業界理解への姿勢が伝わります。
編集方針に共感した理由と、自分の関心がどこで結びついたのかを明確にすることが大切です。読み手に「この人はうちの本を本気で読んでいる」と思ってもらえるよう意識しましょう。
直近の新刊や売れ筋だけでなく、過去作や長年続く雑誌の特集傾向もチェックしましょう。企業の価値観や編集スタンスを把握することが、説得力のある志望動機につながりますよ。
また、企業説明会やOB・OG訪問では、公式HPだけではわからない情報や「なぜその本を世に出したのか」の背景なども聞けます。実際の社員の声を参考することが差別化において重要です。
② インターンでの目標と学びたいことを明確にする
エントリーシートでは「なぜこのインターンに参加したいのか」「何を学びたいのか」をはっきり書く必要があります。熱意だけでなく、目的意識があることが選考通過の鍵です。
「編集会議に参加して、どのように企画が立ち上がるのかを知りたい」「校正業務を体験し、自分の細かい性格が現場でどう役立つかを確かめたい」といった具体的な学びの視点があると、印象が強くなります。
目標が曖昧だと、インターン中に何を得たいのかが不明確になってしまうでしょう。また、事前に仕事内容を調べていることもアピールにつながります。
自分の関心と企業の提供内容が合っていることを示せれば、マッチ度の高い応募書類に仕上がるでしょう。
③ 具体的な経験を用いて熱意と主体性を伝える
熱意や主体性は「あります」と書くだけでは伝わりません。自分の言葉で、過去の経験と結びつけて語ることで、ようやく説得力が生まれます。
たとえば、大学のサークルで広報誌を制作した経験や、SNSで本の感想を定期的に投稿してきた行動などは、自発的な取り組みとしてアピールできるでしょう。
「〇〇という作品を紹介した投稿が、〇人から反応をもらえた」といった実績も効果的です。
また、「なぜその活動を始めたのか」「そこから何を学んだのか」まで掘り下げると、より厚みのあるエピソードになります。
単なる経験の列挙ではなく、出版社を志望する理由と一貫性があるように構成すると、読み手にも熱意が伝わりやすくなるでしょう。
経験を語るときに忘れがちなのが「数字」や「成果」です。エントリーシートでは、読者数の伸びやフォロワーからの反応といった「定量的な実績」が説得力を大きく左右します。
また、エピソードの締めくくりでは「その経験が出版社でどう活きるか」を意識しましょう。一貫性のある志望動機や自己PRを意識すると、読み手に明確なイメージを伝えられます。
④ 自己分析を通じて出版社との適性を伝える
自己分析を通じて、自分がどんな性格や強みを持っているかを整理し、それが出版社の仕事にどう活かせるかを具体的に書きましょう。
「細かな確認作業を苦にしない性格」や「アイデアを出すことにやりがいを感じる」など、自分の資質を具体的に示すことが大切です。
たとえば、「グループワークで意見をまとめる役割を任されることが多い」なら、編集職の調整力に結びつけて説明できます。ありきたりな長所を並べるよりも、自分の経験を踏まえた根拠ある自己評価が求めらるのです。
企業は「この学生が現場でどう貢献できるか」を見ています。適性を伝えることで、志望理由にリアリティが生まれ、印象にも残りやすくなりますよ。
抽象的な強みだけでは説得力が弱くなりがちなので、自分の経験と業務内容の繋がりを具体的に書くことが重要になりますよ。
また、出版社の仕事では地道さや調整力が重視されるため、誤字脱字に気づける几帳面さや意見をまとめる力といった、一見地味な特性も立派な強みになります。自分の過去を振り返ってみてくださいね。
⑤ 言葉選びや構成に気を配り読みやすく仕上げる
良い内容でも、文章が読みにくいと伝わりません。選考担当者にとってESは数多く読むものなので、短く、明確に書く工夫が必要です。
文の構成は「結論→理由→具体例」の順番を意識し、ひとつの段落にはひとつの話題をまとめましょう。たとえば、「私は〇〇が得意です。その理由は~」のように展開するとスムーズです。
誤字脱字はもちろん、同じ言葉の繰り返しにも注意してください。最後に声に出して読んでみると、違和感のある部分が見つけやすくなります。
伝えたい気持ちが強くても、読み手への配慮がなければ届きません。「伝わる」ことをゴールにして、読みやすく整えましょう。
出版社インターン向けエントリーシートの例文

「出版業界で働きたい」という気持ちはあるものの、エントリーシートに何を書けば良いのか分からず手が止まっていませんか?
ここでは、志望動機のタイプ別に役立つ例文を紹介します。自分に近いケースを参考に、説得力のある文章作成に役立ててください。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
①未経験でも伝わる志望動機例文
出版業界に直接関わった経験がない学生でも、日常の中で得た気づきや興味から志望動機を構築することは可能です。ここでは、未経験でもしっかりと熱意を伝えられる例文を紹介します。
《例文》
| 私は文章が人の気持ちを動かす力に魅力を感じ、出版に興味を持つようになりました。大学では読書サークルに所属し、メンバーで本を選んで感想を共有する活動を行っています。 意見を交わす中で、言葉の受け取り方が人によって大きく異なることに気づきました。 その経験から、「誰にでも伝わる表現を届ける」ことの難しさと大切さを実感し、自分もそうした仕事に関わりたいと考えるようになったのです。 貴社の出版物は、日常の中で読者に寄り添うテーマが多く、私も言葉を通して誰かの支えとなるようなコンテンツづくりに携わりたいと考えています。 未経験ではありますが、日々の学びを大切にし、柔軟に吸収していく姿勢で臨みたいです。 |
《解説》
出版経験がなくても、言葉への関心や読書習慣などから動機を導くことができます。「なぜ出版か」を自分の行動と結びつけて書くことがポイントです。
未経験の人は、日常の体験をどう志望動機につなげられるかが重要です。「なぜ出版なのか」を自分なりの言葉にできるかどうかが選考通過に大きく影響してきますよ。
私たちがよく伝えているのは、「気づき→学び→志望理由」の流れを意識すると、論理的に内容が伝えられて説得力が増すということです。小さな経験も筋道が一貫していれば、しっかり評価されますよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②編集職に特化した志望動機例文
ここでは、出版社の編集職を志望する際に使える例文を紹介します。編集の仕事に必要な視点や姿勢が伝わるよう、経験や気づきを交えて書くのがポイントです。
《例文》
| 私は文章を通じて誰かの気持ちを動かすことに魅力を感じ、編集の仕事に強く興味を持つようになりました。 大学では学生向けの情報冊子を作成するプロジェクトに参加し、テーマ設定から構成の組み立て、原稿の確認までを担当しています。 読者の反応を意識しながら文章を調整する中で、ただ書くだけでなく「どう伝えるか」を考えることの難しさと面白さを実感しました。 編集職は、表には出にくいけれど作品の根幹を支える存在だと考えています。貴社の出版物は、企画や構成にこだわりを感じるものが多く、そうした現場で編集の基礎を学び、自分の力を試してみたいと思いました。 細かな作業にも粘り強く取り組み、チームの一員として貢献したいと考えています。 |
《解説》
編集職に必要な「調整力」や「読者視点」への意識を具体的な経験をもとに語ると説得力が増します。裏方的な役割への理解を示すと好印象です。
編集職は、「読者を意識した文章づくり」と「裏方として支える姿勢」が重要です。この2つをバランスよく志望動機に盛り込めると、志望理由の説得力が増します。
また、出版社ごとに特色があるため、企業の強みと自分の経験を結びつけて書くことも大切です。自分の経験を伝える際は「出版社でどう活かすか」まで示しましょう。
③学びたいことを明確にした志望動機例文
ここでは、「インターンで何を学びたいか」を具体的に示すことで志望動機に説得力を持たせる例文を紹介します。目標がはっきりしていると印象に残りやすくなるでしょう。
《例文》
| 私は、編集の現場で実際にどのように本づくりが進められているのかを学びたいと思い、今回のインターンに応募しました。 大学の授業で出版に関する基礎を学ぶ中で、編集者の仕事が単に文章を整えるだけでなく、企画や著者とのやりとり、読者のニーズを考えることまで多岐にわたることを知り、興味を持ったからです。 なかでも、実際にどのように企画が立ち上がり、形になるまでのプロセスに強い関心があります。貴社のインターンでは、その一端に触れられる機会があると知り、ぜひ参加したいと考えました。 将来的には、自分の提案が形になるような企画力のある編集者を目指したいため、この経験を通じて実務のイメージを具体的に掴みたいです。 |
《解説》
「どの業務を経験したいか」「何を得たいか」を明確にすると、目的意識のある応募者として評価されやすくなります。授業や調査など具体的な興味のきっかけを入れるといいでしょう。
④自己分析から適性を伝える志望動機例文
ここでは、自分の性格や強みを自己分析によって整理し、それが出版業界や編集の仕事にどうつながるかを明確にした志望動機の例文を紹介します。
《例文》
| 私は、細かい作業を丁寧に積み重ねることや、人の話をよく聞いて意図をくみ取ることが得意です。 大学ではゼミの資料作成を任されることが多く、読み手が理解しやすい構成や言い回しを意識しながら文章をまとめてきました。 仲間から「説明がわかりやすい」と言われることもあり、言葉で伝えることにやりがいを感じています。 こうした自分の特性は、読者の目線に立って内容を整理する編集の仕事に活かせるのではないかと考えるようになりました。 貴社の出版物は、情報の質や構成に対する丁寧な姿勢が印象的で、自分もそうした現場で経験を積みたいと思っています。強みを生かして、正確でわかりやすいコンテンツづくりに貢献したいです。 |
《解説》
自己分析から見えた強みが、職種の適性とどう結びつくかを明確に伝えると説得力が増します。抽象的な長所ではなく、具体的な行動で裏付けましょう。
自己分析は長所を業務でどう活かすかに説得力を持たせることが重要です。例えば「丁寧さが強み」と言うより「丁寧な確認で誤植を防げる」と具体化すれば、編集適性を伝えられますよ。
また、出版業界では文章力や読解力だけでなく、進行管理や調整力も評価されます。自分の強みを複数の観点から活かせること伝えましょう。
⑤本業との両立に悩んだときの志望動機例文
ここでは、学業やアルバイトなど本業との両立に悩みながらも、出版社のインターンに挑戦したい気持ちを素直に伝える志望動機の例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学での学業とアルバイトの両立に日々取り組んでおり、インターンに参加するかどうか迷いもありました。 しかし、出版の仕事に携わりたいという気持ちは変わらず、少しでも早く現場の雰囲気を知りたいと考えるようになったのです。 時間の制約がある中でも、限られた機会を大切にしながら真摯に取り組みたいと思っています。 以前、授業で書評を提出する課題があり、自分の文章が紹介されて人の読書意欲を刺激できた経験が印象に残っています。 この体験を通じて、情報をわかりやすく届けることの面白さを感じました。貴社のインターンでは、自分の強みを活かしながら、仕事との向き合い方を見つめ直したいと考えています。 限られた時間でも全力で学び、吸収したいです。 |
《解説》
両立への不安がある場合は、迷いを素直に書きつつ、参加への意欲を明確に示すことが大切です。過去の経験と結びつけて前向きな姿勢を伝えましょう。
出版社インターンに向けて意識したいポイント

出版社のインターンシップに参加するためには、業界の傾向を理解し、仕事内容や企業ごとの特徴を把握したうえで、早めに対策を講じることが重要です。
紙媒体の減少やWeb・電子書籍の拡大といった変化を踏まえると、編集や営業、校正などの職種にも新たなスキルが求められるようになっています。
また、倍率の高いインターンを突破するには、大学1〜2年からの準備や視野を広げた企業選びがカギとなるでしょう。
エントリーシート(ES)では志望動機や自己分析の深さが問われるため、丁寧な準備が欠かせません。
出版業界を目指すなら、情報収集と実践的な対策を通じて、インターンを貴重な一歩に変えていきましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











