面接で趣味が音楽鑑賞と答えるときの効果的なアピール方法
「趣味は音楽鑑賞です」と面接で答えたとき、「ありきたりすぎて印象に残らないのでは?」と不安に思ったことはありませんか。
実際、音楽鑑賞は多くの学生が挙げる趣味の一つですが、伝え方次第で人柄や強みを効果的にアピールできる題材にもなります。
そこで本記事では、音楽鑑賞を趣味とする学生が面接で好印象を与えるための伝え方や例文を、具体的に紹介します。
履歴書・ESに書く際の構成ポイントや、避けたいNG回答、差をつけるコツまで解説しているので、「音楽鑑賞を効果的にアピールしたい!」と考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
面接で音楽鑑賞を趣味としてアピールするなら伝え方が大切

就職活動で趣味を聞かれたときに「音楽鑑賞」と答える学生は多いですが、そのまま伝えるだけでは印象に残りにくいものです。
なぜなら、音楽鑑賞は一般的でありふれた趣味に見えるため、個性や強みを感じさせにくいからでしょう。
ただし工夫を加えれば、感性の豊かさや集中力、ストレスの解消法などを示す題材として効果的に使えます。
また、音楽鑑賞を通じて人との交流や新しい価値観に触れていると説明すれば、協調性や柔軟性の高さも示せるでしょう。
つまり「好きだから聞いている」で終わらせず、自己成長や社会人としての資質にどう結び付いているかを話してください。面接官が知りたいのは趣味そのものではなく、そこから見える人柄や強みです。
この視点を意識することで、音楽鑑賞は十分に魅力的なアピールにつながります。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
企業に趣味を質問される意図

就職活動の面接で企業が趣味を質問するのは、単なる雑談ではありません。実際には応募者の人柄や価値観、さらに仕事との向き合い方を知るための大切な手段です。
例えば、音楽鑑賞という趣味が「一人で静かに楽しむもの」なのか「友人とライブに行く社交的な活動」なのかによって、面接官が抱く印象は変わるでしょう。
つまり質問の裏には、応募者が日常をどのように過ごしているか、コミュニケーション力や好奇心の広がりをどう培っているかを測る意図があります。
ここで重要なのは、趣味をただの好きなこととして答えるのではなく、自分の強みや成長と結びつけて話すことです。
音楽鑑賞なら「多様なジャンルを聴くことで柔軟な考え方を養っている」といった伝え方が効果的ではないでしょうか。
このように質問の狙いを理解し、自分をより良く見せる視点で答えることができれば、他の学生との差別化にもつながります。
音楽鑑賞を趣味と答えたときの企業からの印象

就活の面接で趣味を聞かれたときに「音楽鑑賞」と答える学生は多いです。一般的な趣味に見えるため、印象に残りにくいと思うかもしれません。
ただし伝え方を工夫すれば、企業に好意的に受け取られるでしょう。ここでは、音楽鑑賞を趣味と答えた場合に企業が持ちやすい印象を整理します。
- ストレスコントロールができる人材と見られる
- 感受性や情緒が豊かな人と評価される
- 積極性や行動力があると判断される
- 個性的で人柄に魅力があると伝わる
- 自己理解が深い人と印象付けられる
①ストレスコントロールができる人材と見られる
音楽鑑賞は気持ちを整える効果があるため、心の安定につながる習慣だと受け止められます。
企業は社会人に求められるストレス耐性を重視するので、音楽で気分を切り替えられる人は安定して働けると判断されるでしょう。
単に「好きだから聴いている」と答えるより、「勉強やアルバイトで疲れたときに音楽で気持ちをリフレッシュしている」と説明すると説得力が増します。
逆に「暇つぶしで聴いている」と伝えると、だらしない印象を与えるおそれがあります。目的を意識した聴き方を強調してください。その工夫が、自己管理ができる人材としての評価につながるのです。
②感受性や情緒が豊かな人と評価される
音楽は感情を揺さぶり、人の心を豊かにする力があります。そのため趣味にしている人は感受性が高いと見られやすいでしょう。
たとえば「歌詞から人の気持ちを想像している」「クラシックを通じて表現の多様さに気づいた」と話すと、表面的ではない深い関心が伝わります。
企業は感受性を持つ人を、相手に配慮できるコミュニケーション力のある人材と評価するものです。一方で「流行りの音楽をなんとなく聴いている」と伝えると、浅い趣味に受け取られかねません。
音楽から得た学びや気づきを具体的に言葉にすることが大切です。その結果、相手の立場を理解できる社会人としての資質を示せるでしょう。
③積極性や行動力があると判断される
音楽鑑賞は受け身の趣味に思われがちですが、伝え方次第で行動力を示せます。
例えば「好きなアーティストのライブに積極的に参加している」「友人とイベントに出かけて新しいジャンルに触れている」と話すと、新しい環境に挑戦する姿勢を示せるのです。
企業は挑戦心や行動力を持つ学生を評価するので、能動的に楽しんでいることを伝えてください。また「知らない音楽に触れることで柔軟な発想を養っている」と加えれば、成長意欲も伝わります。
反対に「イヤホンでひとりで聴くだけ」と答えると閉鎖的に見える可能性があるのです。能動的なエピソードを交えることで、行動力を裏付けられるでしょう。
④個性的で人柄に魅力があると伝わる
音楽の趣味は人によって大きく異なるため、選ぶジャンルや楽しみ方がその人の個性を映します。
たとえば「ジャズを聴いて独自の感性を養っている」「民族音楽を通じて異文化を学んでいる」と具体的に話せば、個性的で魅力的な人柄として印象付けられるでしょう。
企業にとって個性はチームに新しい刺激を与える要素となるので、プラスに評価されます。ただし「周りと違うことがかっこいい」といった表現では自己満足に聞こえかねません。
大切なのは、自分の趣味を通して周囲にどう貢献できるかを示すことです。そうすれば音楽鑑賞は人柄の魅力を伝える強い材料となります。
⑤自己理解が深い人と印象付けられる
音楽は感情や考えを整理する助けになるため、何を好むかにその人の価値観が表れます。自分がなぜその音楽に惹かれるのかを説明できれば、自己理解の深さを伝えられるでしょう。
例えば「歌詞に共感することで考えを整理できる」「クラシックで集中力を高める方法を学んだ」と話すと、音楽を通じて自己成長していると示せます。
企業は自己分析ができる学生を、入社後の成長が期待できる人材と見るでしょう。逆に「なんとなく聴いている」では説得力を欠きます。
自分の価値観と音楽を結び付けて語ることが、他の学生との差別化につながるのです。
趣味として音楽鑑賞をアピールできる基準

就活の面接で趣味として音楽鑑賞を話すときは、単に「好きだから」と答えるだけでは説得力に欠けます。
採用担当者が注目しているのは、そこからどんな学びや価値観を得て、どのように自分を成長させてきたかという点です。ここでは音楽鑑賞を効果的にアピールできる基準を紹介します。
- 音楽鑑賞で価値観が変わった経験があること
- 自分の人生に影響を与えるアーティストや楽曲があること
- 音楽が行動や努力の原動力になっていること
- 音楽鑑賞から得た学びを具体的に語れること
- 音楽鑑賞を仕事や将来像に結び付けられること
①音楽鑑賞で価値観が変わった経験があること
音楽鑑賞を趣味として語るときに効果的なのは、自分の価値観が変化した経験を示すことです。なぜなら、単なる娯楽としての趣味ではなく、自己成長に影響を与えた証拠になるから。
例えば、海外のアーティストの曲に触れて異文化への関心が高まり、多様性を尊重する姿勢を持つようになったと話せば、柔軟な考え方が伝わります。
逆に「気分転換になります」だけでは、誰でも言える内容で印象に残りません。具体的なエピソードを通じて変化のきっかけを語ってください。
このように価値観の変化を示せると、面接官に「成長意欲がある学生だ」と認識され、評価につながるでしょう。
②自分の人生に影響を与えるアーティストや楽曲があること
強い印象を残すには、自分の人生に大きな影響を与えたアーティストや楽曲について話すのが有効です。
特定の歌詞やメロディーに支えられた経験を語ることで、あなたの人柄や考え方がより鮮明に伝わります。
例えば、挫折したときに勇気を与えてくれた曲があるなら、そのときの状況や自分がどう変われたのかを具体的に説明すると良いでしょう。
単なる好き嫌いではなく、心の支えになったことを語れば説得力が増します。こうした話は「困難を乗り越える力を持っている」という印象を与えられるため、面接官の共感を得やすいはずです。
③音楽が行動や努力の原動力になっていること
音楽鑑賞が行動や努力のきっかけになっていると伝えると、積極性や前向きさをアピールできます。
例えば、受験勉強のときに音楽を聴いて集中力を高めた、部活動で試合前に聴くことで気持ちを切り替えられた、などのエピソードが効果的です。
ただ「励まされた」という一言では浅いため、「音楽を通して自分を奮い立たせた結果、最後までやり抜けた」と具体的に話すことが重要。
音楽を原動力として行動に移せた経験は、就職後も努力を続けられる人材だと印象づけるでしょう。
④音楽鑑賞から得た学びを具体的に語れること
音楽鑑賞を通じて得た学びを語れると、ただの娯楽ではなく成長につながる趣味だと示せます。
例えば、クラシックを聴く中で歴史や作曲家の背景に興味を持ち、探究心が養われたという話は説得力があるのです。
また、異なるジャンルに触れることで「違いを受け入れる柔軟さ」を得られたと話せば、多様な考えを尊重できる姿勢を伝えられます。
重要なのは、学びを自分の言葉で整理し、面接官にわかりやすく説明することです。音楽を単に楽しむのではなく、そこから新しい知識や視点を得たことを具体的に伝えると、印象に残りやすいでしょう。
⑤音楽鑑賞を仕事や将来像に結び付けられること
最後に大事なのは、趣味を将来の仕事やキャリアにどう結び付けられるかを示すことです。趣味と仕事は別と考える人もいますが、面接の場では「自分の強みを活かせるか」を判断されます。
例えば「幅広い音楽に触れてきたことで、多様な価値観を理解できるようになり、将来は人と協力する仕事に生かしたい」と語れば、趣味が自己成長の延長線上にあることを示せます。
抽象的な理想論ではなく、自分の体験を基に具体的に話してください。趣味とキャリアを結びつけられると、面接官に「長期的に成長できる人材だ」と評価されるでしょう。
履歴書・エントリーシートに書く際の構成
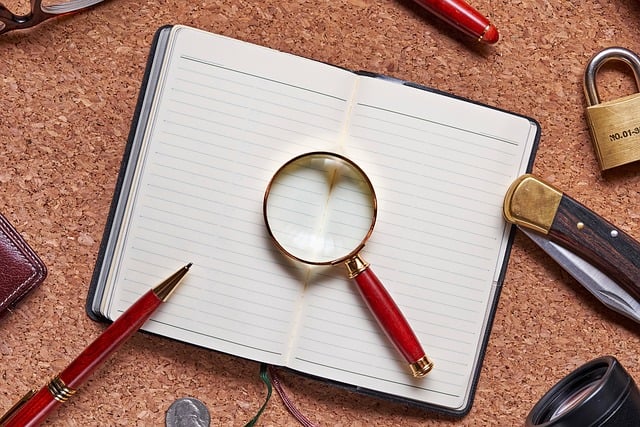
履歴書やエントリーシートに趣味として「音楽鑑賞」と書くときは、ただ事実を並べるだけでは印象に残りません。文章の組み立て方を工夫すれば、自己理解の深さや仕事への適性を伝えられるでしょう。
ここでは効果的な書き方の流れを紹介します。
- 結論から「音楽鑑賞が趣味」と明記する
- 音楽鑑賞が好きな理由を明確に書く
- 数字や頻度を使って具体性を加える
- 音楽鑑賞によって得た経験や成長を示す
- 仕事にどう活かせるかを最後にまとめる
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①結論から「音楽鑑賞が趣味」と明記する
履歴書やエントリーシートでは、まず結論をシンプルに伝えることが大切です。冒頭で「趣味は音楽鑑賞です」と書けば、読み手がすぐに理解でき、無駄な推測をさせません。
その後に理由やエピソードを加えると自然な流れになります。結論を後回しにすると文章が分かりにくくなり、印象が弱くなるでしょう。
面接官は短い時間で多くの書類を読むため、端的に伝えることが評価につながります。最初に趣味を明記し、次に具体的な背景を補足する形にすると関心を引きやすいはずです。
②音楽鑑賞が好きな理由を明確に書く
結論を示したあとは、なぜ音楽鑑賞が好きなのかを説明してください。理由を書くことで、趣味が単なる気分転換ではなく、自分にとって意味のある活動だと伝わります。
例えば「音楽を聴くことで集中力が高まり、勉強にも良い影響があった」と書けば、趣味と自己成長を結び付けられるでしょう。理由が曖昧だと表面的に受け取られ、印象に残りません。
「リラックスできるから好きです」とだけ書くと弱く感じられるので、具体的な体験を盛り込むことが大切です。好きな理由を言葉にすることで、自己分析ができる学生と評価されやすくなります。
③数字や頻度を使って具体性を加える
説得力を持たせるには、数字や頻度を取り入れるのが効果的です。
例えば「毎週末に2時間ほど音楽を聴いている」「年間10回以上ライブに参加している」といった表現は、「よく聴いている」よりも具体的で伝わりやすいでしょう。
数値があることで熱意や継続性も示せます。企業は継続して取り組む姿勢を評価するため、数字を使った表現は強みになるでしょう。
逆に「たまに聴いている」では真剣さが伝わりません。適度に数値を入れることで、音楽鑑賞を自己PRの材料として活かせるはずです。
④音楽鑑賞によって得た経験や成長を示す
音楽鑑賞を単なる趣味で終わらせず、自分の成長にどうつながったかを伝えることが重要です。
例えば「歌詞から人の気持ちを考えるようになり、相手の立場を想像する習慣がついた」と書けば、コミュニケーション力をアピールできます。
「異なるジャンルの音楽に触れることで新しい価値観を取り入れられた」と説明すれば、柔軟性や多様性の理解を示せるでしょう。
企業は学びを重視するので、趣味から得た成果を具体的に語れる学生を評価するのです。「楽しいから聴いている」とだけでは不十分です。経験や変化を盛り込むことで、文章全体の説得力が高まります。
⑤仕事にどう活かせるかを最後にまとめる
最後に、音楽鑑賞が仕事にどう役立つかをまとめてください。例えば「音楽を通じて培った集中力を業務に活かしたい」と書けば、趣味と仕事を結び付けられます。
「音楽で学んだ多様な価値観をチームワークに活かしたい」と伝えると、協調性や柔軟性を示せるでしょう。趣味を自己成長の源泉として位置付けることで、面接官に好印象を与えられます。
結論、理由、具体例、成長、仕事への応用という流れで書けば、説得力のあるアピール文に仕上がるはずです。
履歴書・エントリーシートに書くポイント

履歴書やエントリーシートに趣味として音楽鑑賞を書くときは、ただ「好きです」と伝えるだけでは印象に残りません。採用担当者は趣味の内容から人柄や強みを知ろうとしているのです。
ここでは音楽鑑賞を効果的に伝えるための書き方の基準を紹介します。
- できるだけ具体的な内容を述べる
- 音楽鑑賞のメリットや学びを説明する
- 音楽鑑賞から得たスキルを強調する
- 企業に関連する能力に結び付けて書く
①できるだけ具体的な内容を述べる
履歴書やエントリーシートでは、抽象的な表現よりも具体的な経験を示すことが大切です。単に「音楽鑑賞が趣味です」と書いただけでは、面接官に何も伝わりません。
例えば「洋楽を聴いて歌詞の意味を理解するために英語を勉強した」「クラシック音楽をきっかけに歴史や文化を調べるようになった」と書くと、自分の主体性が表れます。
具体性を持たせることで、音楽鑑賞がただの余暇ではなく、学びや成長につながる行動だと理解されやすいでしょう。
②音楽鑑賞のメリットや学びを説明する
音楽鑑賞を趣味として記載するときは、自分が得たメリットや学びを説明してください。
例えば「さまざまなジャンルを聴くことで柔軟な発想ができるようになった」「歌詞を通して異なる価値観を理解できるようになった」といった体験は評価されやすいです。
ただ楽しんでいるだけでは印象が薄いままで終わります。学びを言葉にすることで、成長意欲や好奇心がある人物だと伝わり、将来性を感じてもらえるでしょう。
③音楽鑑賞から得たスキルを強調する
趣味を効果的にアピールするには、音楽鑑賞から得たスキルを強調することが有効です。
例えば「長時間集中して聴くことで集中力が鍛えられた」「多様なジャンルを整理する中で情報をまとめる力が身についた」と書けば説得力が増します。
また、演奏者や作曲者の思いを想像することで「相手の考えを理解しようとする姿勢」が伝わるでしょう。スキルとして表すと、面接官に「仕事でも役立つ力だ」と思わせられるはずです。
④企業に関連する能力に結び付けて書く
最も重要なのは、音楽鑑賞を企業が求める能力にどうつなげるかです。趣味をいくら語っても仕事との関連が見えなければ評価は高まりません。
例えば「多様な音楽を聴くことで柔軟な考え方を身につけ、異なる価値観を受け入れる力が養われた。これを御社でのチームワークに活かしたい」と書けば、企業にとって魅力的な人材として映ります。
趣味から得たことを分析し、将来の活躍に結び付けて伝えることが大切でしょう。
音楽鑑賞を趣味とアピールする際の例文

就活で「趣味は音楽鑑賞です」と答えても、具体的なエピソードがなければ説得力に欠けてしまいます。
ここではジャンル別の例文を示し、どのように自分の強みや成長を伝えればよいかをわかりやすく解説します。
- クラシック音楽が好きで集中力を磨いた例文
- 洋楽が好きで語学力向上を示す例文
- K-POPが好きで行動力や積極性を示す例文
- J-POPが好きで感受性の豊かさを伝える例文
- ロックやバンド音楽でチャレンジ精神を示す例文
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①クラシック音楽が好きで集中力を磨いた例文
クラシック音楽を趣味とする場合は、学習や日常生活にどのように役立ったかを示すと説得力が増すでしょう。ここでは集中力を高めた経験を例文として紹介します。
| 私はクラシック音楽を聴くことが好きで、特に試験前やゼミ発表の準備をするときによく利用していました。静かな曲調に耳を傾けると気持ちが落ち着き、集中して取り組めるようになります。 実際にクラシックを聴きながら学習することで、長時間でも集中力を維持でき、効率よく課題を終えることができました。 また、演奏会に行くことで演奏者の真剣な姿勢から刺激を受け、自分も最後まで努力を続ける大切さを学びました。 こうした習慣は大学生活全体を通じて身につき、物事に粘り強く向き合う姿勢へとつながっています。 |
趣味と成果の関係を具体的に伝えると、単なる好きなこと以上の印象を与えられます。エピソードに数字やシーンを盛り込み、説得力を高めてください。
②洋楽が好きで語学力向上を示す例文
洋楽を趣味としてアピールする際は、楽しむだけでなく語学力の向上につながった経験を伝えると効果的です。ここでは英語学習との関連を示す例文を紹介します。
| 私は洋楽を聴くことが好きで、特に歌詞を理解したいという思いから自然と英語に興味を持つようになりました。 気に入った曲を繰り返し聴きながら意味を調べることで、日常的に英単語や表現を覚える習慣が身についたのです。 また、耳から入る言葉を意識したことでリスニング力が鍛えられ、大学の英語授業やTOEICのテストでも成果を実感できました。 さらに、好きなアーティストのインタビュー動画を見るうちに、自分も会話で使いたい表現が増え、積極的に英語を話そうとする姿勢につながっています。 洋楽を通じて培った学びは、今後の仕事で必要となるコミュニケーション力にも役立つと考えています。 |
語学力の向上と趣味を結び付けると、自主性や成長意欲が伝わりやすくなります。成果や変化を数字や具体的な場面で補強するとさらに説得力が増すでしょう。
③K-POPが好きで行動力や積極性を示す例文
K-POPを趣味として伝える場合は、ただ楽しんでいるだけでなく、その熱中が行動力や積極性につながった経験を話すと効果的です。ここでは具体的な行動に移したエピソードを紹介します。
| 私はK-POPが好きで、好きなグループの曲をきっかけに韓国語を少しずつ学び始めました。 歌詞の意味を理解したいと感じたため、授業以外の時間を使って独学で勉強し、簡単な会話ができるようになったのです。 また、同じ趣味を持つ友人を誘ってイベントに参加したり、SNSで情報交換をしたりする中で、自分から積極的に人と関わる姿勢が身につきました。 その結果、大学でのグループワークでも意見を出すことに抵抗がなくなり、仲間をまとめる経験にもつながったのです。 趣味を通して得た行動力は、今後の仕事で新しい挑戦に臆せず取り組む力になると考えています。 |
行動力や積極性は企業が重視する要素です。趣味をきっかけに行動に移した体験を盛り込むと、前向きな姿勢を効果的に伝えられます。
④J-POPが好きで感受性の豊かさを伝える例文
J-POPを趣味として伝える際は、ただ聴いて楽しむだけでなく、歌詞やメロディーから得た感情や学びをどう自分の成長につなげたかを語ることが大切です。ここでは感受性をアピールできる例文を紹介します。
| 私はJ-POPを聴くことが好きで、特に歌詞の内容に共感しながら聴くことが多いです。 大学受験で思うように成果が出ず落ち込んでいたとき、前向きな歌詞に励まされ「自分も諦めずに挑戦しよう」という気持ちを取り戻すことができました。 また、失敗や悩みを描いた曲に触れることで、自分だけでなく周りの人も同じように悩みを抱えていることに気づき、人の気持ちを考えて行動するようになりました。 その経験から、友人の相談を親身に聞く機会が増え、相手の立場を理解しようとする姿勢が自然と身についたと感じているのです。 J-POPを通して培った感受性は、将来の仕事においても相手の立場を尊重する力につながると思います。 |
感受性を伝えるときは、音楽に触れた具体的な場面や心境の変化を入れると説得力が増します。自分と他者の両方にどう影響したかを示すと効果的です。
⑤ロックやバンド音楽でチャレンジ精神を示す例文
ロックやバンド音楽を趣味として話すときは、音楽の力に後押しされて挑戦した経験を語ると、チャレンジ精神を効果的に伝えられます。ここでは挑戦と成長を示す例文を紹介します。
| 私はロックやバンド音楽を聴くことが好きで、その力強さに背中を押されることがよくあります。 特に大学の学園祭で友人とバンド演奏に挑戦したとき、最初は人前で演奏する自信がなく不安でしたが、好きな曲を練習するうちに「失敗しても挑戦してみよう」と思えるようになりました。 当日は多くの人の前で演奏する緊張感がありましたが、全力でやりきったことで達成感を得ることができたのです。この経験を通じて、新しいことに挑戦する姿勢や困難を乗り越える力を学びました。 ロックやバンド音楽に触れる中で養ったチャレンジ精神は、就職後も新しい環境で前向きに取り組む力になると考えています。 |
挑戦の場面を具体的に描くことで、音楽と行動のつながりを明確にできます。成果だけでなく、挑戦する前の不安や変化も盛り込むと説得力が高まります。
趣味が音楽鑑賞の場合に避けたいNG例

就活の面接で趣味を聞かれたときに「音楽鑑賞」と答える学生は多いですが、答え方を間違えると逆効果になることがあります。
企業は人柄や考え方を知りたいので、受け答えによっては消極的に見られたり自己分析不足と判断されたりするでしょう。ここでは、避けたいNG例を具体的にまとめました。
- 「特に理由はない」と答えてしまう
- 「他に趣味がないから」と答えてしまう
- 具体的なエピソードを語れずに答えてしまう
- 「ライブで騒いでストレス発散」と答えてしまう
①「特に理由はない」と答えてしまう
「なぜ音楽鑑賞が趣味なのか」という問いに「特に理由はありません」と答えると、自己分析が浅いと受け止められます。企業が知りたいのは趣味そのものではなく、そこから得た考え方や成長です。
理由を示さなければ、受け身な印象を持たれてしまうでしょう。例えば「歌詞から新しい考え方を学んだ」など具体的な理由を加えれば、主体的に取り組んでいることが伝わります。
理由を持たない答え方は印象を弱めるため、自分なりの根拠を必ず言葉にしてください。
②「他に趣味がないから」と答えてしまう
「他に趣味がないから」と答えると、消極的で受け身な人と判断されやすいです。企業は幅広い経験や興味を持つ人を評価するため、「仕方なく選んだ趣味」という伝え方はマイナスになるでしょう。
たとえ他に趣味がなくても、「音楽を通じて集中力を高めている」「多様なジャンルを聴いて新しい視点を得ている」と説明すれば前向きな印象を与えられます。
趣味の数は重要ではなく、どう取り組んでいるかが評価の基準です。自信のなさを見せる表現は避けてください。
③具体的なエピソードを語れずに答えてしまう
「音楽鑑賞が趣味です」とだけ伝えても印象には残りません。面接官は趣味を通じてどんな経験や学びを得たのかを知りたいからです。
例えば「試験前にクラシックを聴いて集中力を高めた」「ライブに行き、新しい環境に挑戦する積極性を得た」といった体験を加えれば、具体的に伝わります。
エピソードがなければ「ただ聞いているだけ」と受け取られ、成長意欲がないと見られるおそれがあるでしょう。小さな体験でもかまわないので、自分に与えた影響を言葉にしてください。
④「ライブで騒いでストレス発散」と答えてしまう
「ライブで騒いでストレス発散しています」と答えると、遊び好きで落ち着きがない人と誤解される可能性があります。
音楽イベントを楽しむこと自体は悪いことではありませんが、伝え方を間違えると軽い印象を与えてしまうでしょう。
同じ体験でも「ライブに参加して仲間との協力を学んだ」「一体感を通してコミュニケーション力を磨いた」と話せば前向きに評価されます。
大切なのは楽しさだけを強調せず、そこから得た学びや成長を示すことです。伝え方ひとつで評価は大きく変わるため、表現には注意してください。
面接で趣味が音楽鑑賞と回答する際のコツ

就活の面接で趣味を聞かれたときに「音楽鑑賞」と答えるのは一般的ですが、話し方や内容次第で印象は大きく変わります。
採用担当者は音楽の知識そのものではなく、人柄や考え方を知ろうとしているのです。ここでは音楽鑑賞を魅力的に伝えるためのコツを解説します。
- 質問の意図を理解して答える姿勢を見せる
- 表情や声のトーンで楽しさや熱意を伝える
- 面接官に合わせてジャンルや話題を柔軟に選ぶ
- 想定される追加質問に備えて具体的なエピソードを準備する
①質問の意図を理解して答える姿勢を見せる
面接で趣味を聞かれるのは、応募者の人柄や価値観を知りたいからです。したがって「好きです」とだけ答えるのは不十分でしょう。
例えば「音楽を聴くことで気持ちを切り替え、勉強や課題に集中できました」と伝えると、生活や行動にどう影響しているかが伝わります。
重要なのは、趣味を通じて得た経験や成長を具体的に語ることです。その姿勢を示せば、面接官に「この学生は自己分析ができている」と感じてもらえるでしょう。
②表情や声のトーンで楽しさや熱意を伝える
趣味を話すときは、言葉だけでなく表情や声のトーンも印象を左右します。同じ内容でも淡々と話すと熱意が伝わりません。
少し笑顔を見せたり、声に抑揚をつけたりすることで「本当に楽しんでいるのだな」と相手に伝わります。特に音楽鑑賞は感情に直結する趣味なので、自然に楽しさを表現することが大切です。
大げさにする必要はありませんが、自分が夢中になっている様子を意識して伝えてください。
③面接官に合わせてジャンルや話題を柔軟に選ぶ
面接では相手に合わせた話題選びが印象を良くします。例えば、面接官がクラシックに詳しそうであればその話題を選び、一般的な流行音楽の方が親しみやすいと感じればそちらを話す方が効果的です。
趣味の話は自分中心になりがちなので、相手の反応を見ながら柔軟に対応しましょう。また幅広いジャンルを聴いていると伝えれば、好奇心や柔軟性をアピールできます。
共通点を意識すると会話も弾みやすいでしょう。
④想定される追加質問に備えて具体的なエピソードを準備する
音楽鑑賞を趣味と答えると、「好きなアーティストは誰ですか」「最近聴いた曲は何ですか」などの追加質問をされることがあります。そのときに答えに詰まると、趣味としての信頼性が薄れてしまうでしょう。
あらかじめ具体的なエピソードを用意しておくことが大切です。例えば「試験前には同じ曲を聴いて気持ちを落ち着けた」といった日常の経験は印象に残りやすいでしょう。
準備をしておけば安心感も増し、自信を持って答えられます。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
音楽鑑賞を趣味にすることで就活で差をつける方法

音楽鑑賞を趣味として就活で伝える際には、単に「好きです」と言うだけでは効果が薄いです。企業は趣味から人柄や強みを知ろうとしています。
だからこそ「音楽を通じて学んだこと」や「行動の原動力になった経験」を具体的に語ることが重要です。
例えば、履歴書には音楽鑑賞を趣味と明記した上で、その理由や頻度、得た成長を具体的に書き、最後に仕事との関連性を示すと説得力が増します。
また、面接では質問の意図を理解し、表情や声のトーンで楽しさを伝えることが評価につながるでしょう。音楽鑑賞は単なる余暇活動ではなく、感受性や積極性を示せる強力なアピール材料になります。
正しい伝え方を工夫すれば、他の就活生と差をつけられるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











