就活対策|入社後にしたいことの例文・見つけ方・答え方の完全ガイド
「入社後にしたいことを聞かれても、正直どう答えればいいのか分からない……」
面接でよく出る質問の一つですが、準備不足だと自己PRや志望動機と答えが重なってしまいがちです。採用担当者はあなたの将来像や成長意欲を見極めているため、ここでの答え方次第で評価が大きく変わります。
そこで本記事では、「入社後にしたいこと」をテーマに、見つけ方のポイントから具体的な答え方、実際に使える例文まで詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
入社後にしたいことを企業が質問する理由

入社後にしたいことは、何を伝えればよいか不安になるものです。
ここでは、企業がこの質問をする理由を整理し、どのような観点で見られているかを理解できるようにまとめました。意図をつかめば答えは組み立てやすくなるでしょう。
- 企業理念や仕事内容の理解度を確かめるため
- 入社後のミスマッチを防ぐため
- 就活生のキャリアビジョンを確認するため
- 入社後の仕事への具体的なイメージを知るため
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①企業理念や仕事内容の理解度を確かめるため
企業は、この質問であなたが自社をどれほど理解しているかを確認します。理念や事業に沿った目標を話せる人は、配属後の成長が早く、周囲との連携もしやすいからです。
たとえば「御社の『○○を通じて社会をよくする』という理念に共感し、△△事業で□□の課題に取り組みたい」と述べれば、理解と意欲を同時に示せます。
会社の強みやサービス、顧客を短くまとめ、それに自分の行動計画を加えると説得力が増すでしょう。結論として、理念や仕事内容に沿った答えを出せば、企業から合致度の高い人材と見られます。
②入社後のミスマッチを防ぐため
面接官は「入社後にギャップで悩まないか」を見ています。早期離職は本人にも会社にも大きな負担になるため、期待値をそろえることが重要だからです。
ESでは、働き方や評価基準、配属の幅など、自分の希望と会社の実情がどう重なるかを明確にしてください。「数字で成果を見る文化で成長したい。
まずは○○部で月△件の受注をめざし、先輩に同行して提案の型を身につける」と書けば、働き方のイメージを具体的に伝えられます。
他社でも通じる一般論だけにせず、会社の制度や流れと自分の価値観の接点を示すことが大切です。結果として、現実との整合を示せば安心感が生まれるでしょう。
③就活生のキャリアビジョンを確認するため
企業は「成長の道筋を描ける人」を求めています。短期の目標と中長期の役割像を持つ人は学びを続けやすく、成果にも結びつきやすいからです。書き方は、三段階が効果的でしょう。
1年目に身につけるスキル、3年目に担う仕事、5年目以降に果たす役割を順に示しましょう。
例として「1年目は提案の基礎と顧客理解を深める。3年目には小規模案件を主担当として成功させる。5年目以降は新人育成や改善提案を通じて売上に貢献する」とすれば、成長の流れが伝わります。
数字や期間を入れることで、想像しやすくなるのも利点です。まとめると、道筋を言葉にすれば将来性を評価してもらえるでしょう。
④入社後の仕事への具体的なイメージを知るため
企業は、あなたが日々の業務をどれだけ描けているかを確かめています。仕事像が具体であれば、行動に落とし込みやすく、早い段階で成果を出せるからです。
面接やESでは、1日の流れに沿って「何を学び、どの場面で工夫するか」を短く示すとよいでしょう。
たとえば「朝は前日の商談を振り返り、午前は顧客ヒアリングを2件、午後は提案書の修正と上長の確認。帰社後に次回アクションを決める」と書けば、働く姿が浮かびます。
結論として、具体的なイメージを語れる人は実行力があると評価されるはずです。
「入社後にしたいこと」と「志望動機」の違い

就活でよく混同されやすいのが「入社後にしたいこと」と「志望動機」の違いです。ここを正しく理解していないと、エントリーシートや面接で伝えたい内容があいまいになってしまうでしょう。
志望動機は「なぜその企業なのか」、入社後にしたいことは「その会社で何を実現するのか」を伝える場といえます。
この違いを意識できれば、面接官に一貫したメッセージを届けやすくなり、エントリーシートでも評価につながるでしょう。
志望動機は過去から現在の流れを意識し、入社後にしたいことは現在から未来への展望を描くと整理しやすいです。
入社後にしたいことを見つける方法

就活でよく聞かれる「入社後にしたいこと」を自信を持って答えるには、自分の将来像や過去の経験を整理することが欠かせません。
ここでは、考え方の流れを紹介します。事前に準備しておけば、エントリーシートや面接でも落ち着いて話せるでしょう。
- 理想の将来像から逆算して考える
- 過去の経験や強みを整理して活かせる仕事を探す
- やりたくないことを明確にして方向性を絞る
- ロールモデルや先輩社員のキャリアを参考にする
①理想の将来像から逆算して考える
入社後にしたいことを考えるときは、まず理想の将来像から逆算するのが効果的です。
5年後や10年後にどんな姿で働いていたいかをイメージしてください。理想を描くことで、必要なスキルや経験が見えてきます。
たとえば「海外で活躍したい」と思うなら、語学力や異文化理解を高められる業務を希望するのが自然です。反対に目先の希望だけを伝えると、計画性がないと判断されることもあります。
長期的なゴールを軸にすると説得力が増し、不安も減って納得感を持ちながら行動できるでしょう。
②過去の経験や強みを整理して活かせる仕事を探す
これまでの経験や強みを整理することは、入社後にやりたいことを考える大きな手がかりになります。アルバイトやゼミ活動、サークルで得た力は社会人としても活かせるものです。
接客で培ったコミュニケーション力は営業や販売に、研究で身につけた分析力は企画やエンジニア職に結びつけられるでしょう。
ただ「得意です」と言うだけでは弱いため、具体的なエピソードを添えると効果的です。経験を振り返り、強みを言葉にすると自然に方向性が定まり、面接でも一貫性のある回答ができるようになります。
③やりたくないことを明確にして方向性を絞る
入社後にしたいことを考える際には、やりたくないことを洗い出すのも有効です。やりたくないことを明確にすると、自分が大切にしている価値観が見えやすくなります。
もし、「一人で黙々と作業するのは向いていない」と感じるなら、チームで協力する仕事が合っていると分かるでしょう。これを曖昧にしたまま就職すると、入社後にミスマッチを感じやすくなります。
あらかじめ整理しておけば、選択肢が多い中でも迷わず決めやすく、納得できるキャリアにつながるはずです。結果として、面接での回答にも一貫性が生まれるでしょう。
④ロールモデルや先輩社員のキャリアを参考にする
入社後の姿をイメージしにくいときは、実際に働いている人を参考にするのが効果的です。会社説明会やOB・OG訪問を通じて先輩社員の話を聞くと、現実的なキャリアパスを描けます。
たとえば「入社3年目でプロジェクトを任されている」という話を知れば、自分もそうなりたいと具体的に思えるでしょう。
独自の考えだけでは説得力に欠けますが、実例を踏まえれば目標として伝えやすくなります。
さらにロールモデルを持つことで努力の方向性も定まり、面接でも熱意を伝えやすくなるでしょう。現場の声を取り入れる姿勢は、企業とのミスマッチを防ぐ大切な工夫です。
入社後にしたいことの質問に答える際の構成

就職活動では「入社後にしたいこと」を聞かれることが多く、答え方によって印象が大きく変わります。
ここでは、答えを組み立てる基本の流れを紹介しています。順序を意識することで、説得力のある自己PRにつながるでしょう。
- 結論:入社後にしたいことを簡潔に伝える
- 理由:その業務や目標を選んだ背景を説明する
- 根拠:経験やスキルをどのように活かせるか伝える
- 意欲:企業で実現するための姿勢や熱意を示す
①結論:入社後にしたいことを簡潔に伝える
最初に大切なのは、入社後にやりたいことを短くはっきり伝えることです。話の出だしが長いと、相手は結論を待つうちに集中力を失ってしまいます。
たとえば「営業として顧客課題を解決できる人材になりたいです」と端的に述べれば、意図がすぐに伝わるでしょう。曖昧な表現は避け、聞かれた問いに直接答えることが信頼感につながります。
面接官は多くの学生と接しているため、要点を押さえた答えは記憶に残りやすいはずです。自分の希望を短い言葉で言い切ることで、その後の理由や根拠にも一貫性を持たせられます。
②理由:その業務や目標を選んだ背景を説明する
結論を伝えたら、なぜその業務を希望するのか理由を加えることが大切です。背景を語ることで、単なる願望ではなく納得できる動機に変わります。
「ゼミ活動で企業と連携した経験から、課題を解決する営業に魅力を感じたためです」と説明すれば説得力が増すでしょう。理由を語る際は、自分の経験や学びを自然に結びつけることが大切です。
ただ「憧れています」と話すだけでは弱いので、過去の体験を根拠として提示してください。理由を明確にすることで志望動機全体に一貫性が生まれ、面接官に安心感を与えられます。
③根拠:経験やスキルをどのように活かせるか伝える
理由を示したあとは、過去の経験やスキルを根拠として示すと効果的です。
たとえば「アルバイトで培った接客経験を営業での顧客対応に活かしたいです」と話せば、自分がどのように貢献できるかが具体的に伝わります。
スキルと仕事の関連性を意識することで、単なる自己紹介ではなく企業にとってのメリットとして受け止められるでしょう。また、根拠を挙げることで実現可能性が高まり、面接官の評価も上がります。
重要なのは誇張せず、実際の経験を基に語ることです。根拠がしっかりしていれば、答え全体の信頼性が自然と強まります。
④意欲:企業で実現するための姿勢や熱意を示す
最後に、入社後に希望を実現するための意欲をアピールしてください。どれだけ魅力的な目標を語っても、努力する姿勢が伝わらなければ説得力は弱くなります。
「入社後は先輩から積極的に学び、早い段階で成果を出せるよう努力します」などと述べれば、前向きな姿勢が伝わるでしょう。
意欲を示す際は単なる熱意だけでなく、学ぶ姿勢や挑戦への準備を具体的に語ると効果的です。企業は成長を期待して採用するため、この部分でやる気が伝われば高く評価されます。
ES・面接で伝えるときのポイント

入社後にしたいことをESや面接で伝えるときは、ただ希望を語るだけでは弱くなりがちです。ここでは、採用担当者に納得感を与えるための4つの視点を紹介します。
答えの軸を整理することで、一貫性がある印象を持たせやすくなるでしょう。
- 具体的な仕事内容に結びつけて話す
- 企業の強みや特徴と関連づけて伝える
- 自己分析を踏まえて説得力を持たせる
- 将来のキャリアビジョンと一貫性を持たせる
①具体的な仕事内容に結びつけて話す
入社後にしたいことを伝えるときは、企業で実際に行われる仕事内容に結びつけることが大切です。漠然とした目標よりも、具体的な業務をイメージできる方が現実味があるからです。
たとえば「営業職で顧客の課題解決を支援したい」と話すと、採用担当者は日々の仕事ぶりを想像しやすくなります。反対に「社会に貢献したい」だけでは抽象的で伝わりにくいでしょう。
自分が希望する職種で果たしたい役割や、学んできた経験をどう活かすかを整理してください。実際の業務内容に沿って語ることで、答えに説得力と信頼感を持たせられるでしょう。
②企業の強みや特徴と関連づけて伝える
入社後にやりたいことを効果的に伝えるには、企業独自の強みや特徴と結びつけることが欠かせません。採用担当者は「なぜ当社なのか」を重視しているため、他社でも言えるような目標では響きにくいのです。
もし、IT分野に強みを持つ企業であれば「システム開発を通して顧客の業務効率化に貢献したい」と述べると一貫性が生まれます。
企業研究で得た具体的な情報を盛り込むことで、志望動機との関連性の強調も可能です。その会社だからこそ実現できる目標を示すことが、理解度の高さを伝えるうえで効果的でしょう。
③自己分析を踏まえて説得力を持たせる
入社後にしたいことを語るときは、自己分析に基づいた説明を加えると説得力が増します。自分の強みや経験を根拠にすることで、単なる希望ではなく「実現可能な目標」として伝えられるからです。
たとえば「アルバイトで培った接客力を活かし、顧客と信頼関係を築ける営業を目指したい」と話せば、実体験に裏打ちされた言葉として相手に届きます。
一方で、根拠を示さず「挑戦したい」とだけ伝えると抽象的で弱い印象になりかねません。過去の体験と未来の目標を自然に結びつけることが、採用担当者の信頼を得るための重要なポイントでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
④将来のキャリアビジョンと一貫性を持たせる
入社後にやりたいことを語る際は、将来のキャリアビジョンとの一貫性を意識することが必要です。それは、短期的な目標と長期的な成長イメージが結びついている方が、採用担当者に安心感を与えられるから。
「まずは営業として成果を上げ、その後はマネジメントを経験して組織の成長に貢献したい」などと伝えると、将来の道筋が明確になるでしょう。
逆に場当たり的に希望を述べると「長く働く姿が見えない」と受け止められてしまう可能性があります。自分の将来像を描き、その実現に向けた第一歩として入社後に何をしたいかを説明してください。
筋道を示すことで、面接官の信頼を得やすくなるでしょう。
【業界別】入社後にしたいことの例文

業界によって求められる役割やキャリアの描き方は大きく異なるため、就活生にとって「入社後にしたいこと」を具体化するのは難しいものです。
ここでは、各業界に応じた例文を紹介し、答え方の参考にできるようまとめています。
面接でどんな質問が飛んでくるのか分からず、不安を感じていませんか?とくに初めての一次面接では、想定外の質問に戸惑ってしまう方も少なくありません。
そんな方は、就活マガジン編集部が用意した「面接質問集100選」をダウンロードして、よく聞かれる質問を事前に確認して不安を解消しましょう。
また、孤独な面接対策が「不安」「疲れた」方はあなたの専属メンターにお悩み相談をしてみてください。
①コンサル業界の例文
コンサル業界に応募する際には、課題解決力や論理的な思考力を示せるエピソードが効果的です。ここでは、大学生活での経験をもとに入社後にしたいことを具体的に伝える例文を紹介します。
| 入社後は、クライアントの課題を正しく把握し、実行可能な解決策を提案できるコンサルタントとして成長したいと考えています。私は大学のサークル活動で、部員の参加率低下という課題に直面しました。 私はアンケートを行い原因を明確化し、練習内容を改善する提案をしました。その結果、参加率は大幅に向上し、サークル全体が活気を取り戻しました。この経験を通じて、問題を分析し解決策を形にする力を培うことができたのです。 入社後は、この経験を活かし、企業が抱える多様な課題に対して冷静に分析を行い、効果的な戦略を提案することで、クライアントに信頼される存在を目指します。 |
この例文は「課題発見→改善策の提案→成果」という流れを盛り込むことで、コンサル業界に必要な力を明確に示しています。同じテーマで書く際は、成果を数字や具体的な変化で表すと、より説得力が高まります。
②金融業界の例文
金融業界では、数字を扱う正確さや責任感、さらに顧客の信頼を得られる姿勢が重視されます。ここでは、学生生活で培った経験をもとに入社後にしたいことを伝える例文を紹介しましょう。
| 入社後は、お客様に寄り添いながら最適な金融サービスを提供し、信頼される存在として成長したいと考えています。私は大学時代に学園祭の会計を担当し、大きな責任を持って資金管理を行った経験があります。 限られた予算を有効に使うために支出の優先順位を整理し、複数の部署と協力して計画的に運営したことで、前年より黒字幅を増やすことができました。この経験から、数字を扱う責任感や計画性の重要さを学びました。 入社後は、この力を活かして顧客の資産形成をサポートし、将来の不安を安心に変える存在を目指して努力していきたいと考えています。 |
この例文は「責任を持った経験」から「入社後の希望」へ自然に展開している点がポイントです。同じテーマで書く場合は、数字や成果を入れることで説得力が増し、金融業界の志望動機として効果的になります。
③商社の例文
商社を志望する場合は、幅広い分野での挑戦意欲や人と人をつなぐ力を示すと効果的です。ここでは、大学生活での経験を通じて、入社後に挑戦したい思いを伝える例文を紹介します。
| 入社後は、世界を舞台に多様な人や企業をつなぎ、新しい価値を生み出す商社パーソンとして成長したいと考えています。私は大学時代、留学生との交流イベントを企画・運営した経験があります。 当初は言葉の壁や文化の違いから参加者が打ち解けられず、盛り上がりに欠けていました。そこで私は、双方が理解しやすいテーマを取り入れ、意見交換や共同作業の場を増やす工夫をすることに。 その結果、参加者同士の交流が深まり、イベント終了後も継続的な交流が続く関係を築くことができました。 この経験から、人や文化をつなげる喜びを学びました。入社後は、この経験を活かし、取引先との信頼関係を築きながら新たなビジネスを生み出す力を磨いていきたいです。 |
この例文は「人と人をつなぐ経験」をベースにしているため、商社が求める資質を自然にアピールできます。同じテーマで書くときは、課題と工夫、成果を順に描くことで説得力が増すでしょう。
④広告・マスコミ業界の例文
広告・マスコミ業界を志望する場合は、人の心を動かすアイデアや情報発信への熱意を示すことが重要です。ここでは、大学生活の経験をもとに、入社後に挑戦したいことを伝える例文を紹介します。
| 入社後は、人々の共感を呼び起こし、社会に影響を与えるような広告やコンテンツを発信できる人材として活躍したいと考えています。 私は大学時代、学園祭の広報担当を務め、SNSを活用して来場者を増やす施策に挑戦したことがあります。 最初は発信内容が一方的で反応が少なかったのですが、ターゲット層の関心を分析し、写真や動画を取り入れた投稿に改善しました。 その結果、前年より来場者数を増やすことができ、参加者から「情報がわかりやすくて行きやすかった」との声をいただきました。 この経験を通じて、情報を工夫して届ける重要性を学びました。入社後は、この姿勢を活かし、多くの人に届く広告づくりに貢献していきたいです。 |
この例文は「工夫→改善→成果」の流れが明確で、広告・マスコミ業界が求める発想力や発信力を伝えやすくなっています。
同じテーマで書く場合は、工夫した点と結果を具体的に描くことで説得力が高まるでしょう。
⑤メーカー業界の例文
メーカー業界を志望する場合は、ものづくりに対する関心や改善への姿勢を伝えると効果的です。ここでは、大学での経験をもとに、入社後に実現したい思いを表した例文を紹介します。
| 入社後は、お客様の生活をより便利で豊かにする製品づくりに携わりたいと考えています。私は大学時代、サークルで使う備品が使いづらいと感じたことをきっかけに、改善案をまとめて提案した経験があります。 単に新しい物を購入するのではなく、既存のものを工夫して使いやすくする方法を考え、みんなで改良を重ねました。その結果、コストを抑えつつ利便性を高めることができ、周囲から感謝の声を多くいただきました。 この経験から、身近な課題に気づき改善につなげる姿勢の大切さを学びました。 入社後は、こうした視点を持ちながら社会のニーズに応える製品づくりに貢献し、メーカーの強みを広げていきたいです。 |
この例文は「課題に気づく→改善策を考える→成果につなげる」の流れを意識しており、メーカー業界に必要な視点を自然に伝えられるでしょう。具体的な改善内容を示すと、説得力がさらに高まります。
⑥食品業界の例文
食品業界を志望する際は、人々の健康や食生活を支えたいという思いを明確にすることが大切です。ここでは、大学での身近な経験をもとに、入社後に実現したい目標を表現した例文を紹介します。
| 入社後は、安全で安心できる食品を提供し、人々の生活をより豊かにする仕事に携わりたいと考えています。私は大学時代、アルバイトで飲食店の調理補助を担当したことがあります。 最初はスピードを重視していましたが、盛り付けや衛生面に注意を払わなかったことでクレームにつながったことがあります。その経験をきっかけに、見た目や衛生管理の重要性を学び、一つひとつの作業を丁寧に行う姿勢を意識しました。 その結果、店長やお客様から「安心して食べられる」と評価されるようになり、大きな達成感を得ることができました。 入社後もこの姿勢を活かし、食の安全性を守りながら多くの人に喜ばれる製品づくりに貢献したいです。 |
この例文は「失敗→改善→成果」の流れがあるため、成長意欲や責任感を自然に伝えられます。食品業界を志望する際は、食の安全や安心を軸に書くと説得力が高まるでしょう。
⑦インフラ・交通業界の例文
インフラ・交通業界を志望する場合は、人々の生活を支える使命感や安全を守る意識をアピールすると効果的です。
ここでは、大学時代の経験を基に、入社後に実現したい思いを表現した例文を紹介します。
| 入社後は、人々の生活を支える社会インフラの安定運営に貢献し、安全で快適な環境を提供できる存在になりたいと考えています。私は大学時代、通学中に度々交通の遅延を経験しました。 その際に「多くの人の生活は交通網に支えられている」と強く実感。また、アルバイト先で混雑する店舗の運営補助を行い、利用者に安心してもらえるよう丁寧な対応を心掛けました。 その結果、お客様から「安心して利用できた」との声をいただき、信頼を築く喜びを感じました。これらの経験を通じて、人々の日常を支える仕事の大切さを学びました。 入社後は、安全と利便性を両立させる取り組みに尽力し、利用者に安心感を届けられる人材を目指したいです。 |
この例文は「気づき→行動→成果」の流れでまとめており、交通やインフラ業界に必要な責任感や使命感を強調できます。同じテーマを書く場合は、自分の経験と社会への貢献を関連づけることがポイントです。
⑧IT・通信業界の例文
IT・通信業界を志望する場合は、技術を通じて社会を便利にする姿勢や、新しい仕組みを学び活用する意欲を示すことが大切です。
ここでは、大学生活の経験を基に、入社後に挑戦したい思いを表現した例文を紹介します。
| 入社後は、IT技術を活用して人々の暮らしをより便利にし、社会に貢献できるエンジニアとして成長したいと考えています。私は大学でプログラミングの授業を受けた際、仲間とチームを組んで簡単なアプリを開発しました。 最初は思うように動かず苦労しましたが、試行錯誤を繰り返し、メンバーと役割分担を工夫することで、利用者が使いやすい形に仕上げることができました。 そのときに感じた「自分が作ったものが人の役に立つ」喜びは今でも忘れていません。 入社後も新しい技術を積極的に学び、利用者の目線を大切にしながら、便利で安心して使えるサービスを提供できる人材を目指したいです。 |
この例文は「挑戦→工夫→成果」の流れで描かれており、IT・通信業界に必要な学習意欲やチームでの取り組みをアピールできます。同じテーマで書く場合は、開発経験や工夫した点を具体的に盛り込むと効果的です。
⑨不動産・建設業界の例文
不動産・建設業界を志望する場合は、街づくりや暮らしを支える役割への関心と、人との信頼関係を築く姿勢をアピールすることが効果的です。
ここでは、大学での経験を基に入社後に実現したい思いを表現した例文を紹介します。
| 入社後は、人々の生活基盤を支える建物や街づくりに携わり、安心して暮らせる環境を提供できる社会人として成長したいと考えています。私は大学時代、アルバイトで住宅展示場の案内を担当した経験があります。 当初は来場者への対応に緊張していましたが、丁寧に話を聞き、わかりやすく説明することを意識するようにしました。 その結果、お客様から「安心して相談できた」と感謝の言葉をいただき、大きなやりがいを感じました。この経験を通じて、住まいに関する仕事が人の安心につながることを学びました。 入社後は、顧客との信頼関係を大切にしながら、安全で快適な住環境を提供するために努力していきたいです。 |
この例文は「経験→学び→入社後の希望」の流れが明確で、不動産・建設業界が重視する信頼性や責任感を伝えやすくなっています。書く際は、接客や信頼を築いた経験を具体的に盛り込むと説得力が高まるでしょう。
⑩サービス業界の例文
サービス業界を志望する際は、お客様に寄り添う姿勢や人を笑顔にすることへのやりがいを中心に伝えると効果的です。
ここでは、学内での活動経験を通して培った気づきと入社後の希望を組み合わせた例文を紹介します。
| 入社後は、利用される方に安心と満足を提供できる社会人になりたいと考えています。 大学時代には図書館の運営をサポートする学生スタッフとして活動し、貸し出しや返却の手続きだけでなく、初めて利用する方に分かりやすく説明することも担当しました。 最初は事務的な対応にとどまっていましたが、利用者の要望に先回りして案内するよう心がけると、「ありがとう、助かりました」と直接声をかけていただける機会が増えました。 その経験から、相手の立場に立ち、一歩先の行動を取ることがサービスの価値を高めると学びました。入社後はこうした姿勢を大切にし、期待以上の満足を届けられる存在を目指します。 |
この例文は「学内活動→利用者からの感謝→入社後の姿勢」という流れで、サービス業界に必要な気配りや主体性を伝えられています。
飲食以外の経験を書く場合も、相手からの反応を具体的に盛り込むと説得力が増します。
【職種別】入社後にしたいことの例文

就職活動においては、志望する職種に合わせた将来像を描くことが重要です。
ここでは、代表的な職種ごとに「入社後にしたいこと」の具体例を紹介します。自分の経験や強みを、どのように重ね合わせればよいかを理解しやすくなるでしょう。
①営業職の例文
営業職では、お客様の信頼を得ながら成果を上げていくことが求められます。ここでは「入社後にしたいこと」を冒頭に明確に述べつつ、大学時代の経験を根拠として示した例文を紹介しています。
| 入社後はお客様に信頼される営業担当として、一人ひとりに合った提案を行い、会社の成長に貢献したいと考えています。 大学時代、私はサークルの新入生勧誘を担当し、積極的に声をかけて説明を工夫することで前年より多くの新入部員を集めることに成功しました。 その際、相手の関心に合わせて話し方を変えることで納得を得られた経験から、人と誠実に向き合う大切さを学びました。 入社後はこの経験を活かし、お客様の課題や要望を丁寧に聞き取り、最適な提案につなげていきたいです。そして成果を積み重ね、将来的には後輩の育成にも力を注ぎ、組織全体の成長に寄与したいと考えています。 |
例文の冒頭で「入社後にしたいこと」を簡潔に伝えることで、文章全体の方向性が明確になります。根拠となる経験を続けて述べると、説得力が高まるでしょう。
②事務職の例文
事務職では、正確さや丁寧さだけでなく、チーム全体の業務を円滑に進めるためのサポート力が求められます。
ここでは「入社後にしたいこと」を冒頭に明確に述べながら、学生時代の経験を根拠として表現した例文を紹介しましょう。
| 入社後は、正確で迅速な事務処理を通じて周囲の方々を支え、チーム全体が安心して業務に集中できる環境づくりに貢献したいと考えています。 大学では学園祭の実行委員として会計を担当し、予算管理や支出の記録を任されました。当初は複数の担当者から提出されるデータがばらばらで混乱していましたが、私はフォーマットを統一し、誰でも分かる形に整理することに。 その結果、支出の把握が容易になり、スムーズに会計報告が行えるようになりました。この経験を通じて、裏方の努力が組織全体の成果につながることを実感しました。 入社後も正確さと工夫を大切にし、円滑な業務運営を支える存在を目指します。 |
冒頭で「入社後にしたいこと」を述べると、文章に一貫性が生まれます。経験部分は数字や工夫を交えて具体的に書くと、説得力がさらに増すでしょう。
③製造職の例文
製造職では正確さや効率性が求められるため、入社後にどのような形で貢献したいのかを具体的に示すことが重要です。ここでは、身近な経験を通して製造現場に役立つ姿勢を伝える例文を紹介します。
| 入社後は、製造工程における正確な作業と効率的な工夫を通じて、製品の品質と納期の両立に貢献したいと考えています。大学時代には研究室で行った実験で、試薬の準備やデータの記録を担当していました。 作業に少しでも誤りがあると結果に影響が出てしまうため、私は確認リストを作成し、手順を一つひとつ丁寧に進めることにしたのです。 その結果、作業の正確性が高まり、全員が安心して研究を進められる環境を整えることができました。この経験から、丁寧さと工夫の積み重ねが信頼を生み出すことを学びました。 入社後もこの姿勢を活かし、確かな品質を支える一員として成長していきたいです。 |
正確さや工夫の経験を製造現場に結びつけると説得力が高まるでしょう。数字や改善点を加えると、さらに現実味のあるアピールになります。
④企画職の例文
企画職の志望理由や入社後にしたいことを伝える際には、自ら考えて形にした経験をエピソードとして示すと効果的です。ここでは、学生生活でのイベント企画を題材にした例文を紹介します。
| 入社後は、自らのアイデアを形にし、周囲を巻き込みながら新しい価値を生み出せる企画を実現したいと考えています。大学では学園祭の実行委員として、新しいステージイベントを提案したことがあります。 当初は参加者が集まらず課題が残りましたが、私はアンケートを行って学生の関心を探り、人気のある企画を取り入れるよう改善しました。その結果、多くの学生が参加するイベントに成長し、予想以上の来場者数を記録しました。 この経験から、課題を把握して改善しながら企画を練ることの大切さを学びました。入社後もこの姿勢を活かし、顧客や社会のニーズを踏まえた企画を提案し、形にしていける存在になりたいです。 |
「提案→改善→成果」の流れを明確に示すと企画職らしさが伝わります。数値や成果を入れると、より具体的で信頼性のある文章になるでしょう。
⑤研究職の例文
研究職を志望する場合は、好奇心や探究心を基盤にした学びの姿勢を示すことが大切です。ここでは、大学での研究活動を通じて学んだ経験を題材にした例文を紹介します。
| 入社後は、自ら課題を見つけて深く掘り下げ、社会や企業に役立つ研究成果を出せる研究者として成長したいと考えています。大学ではゼミで植物の成長条件に関する研究に取り組みました。 当初は思うような結果が出ず行き詰まりましたが、関連する論文を調べ直し、教授や仲間と議論を重ねて新しい実験方法を試すことに。 その結果、従来よりも成長速度が高まる条件を見つけることができ、学会で成果を発表するまでに至りました。 この経験から、困難に直面しても粘り強く考え続ける姿勢の大切さを学びました。入社後も失敗を恐れず挑戦し、チームと協力して新しい発見を追求していきたいです。 |
研究過程での工夫や、粘り強さを強調すると説得力が増します。結果だけでなく、試行錯誤や学びの姿勢を具体的に伝えるのがポイントです。
⑥エンジニア職の例文
エンジニア職では、自分の強みと学んだことをどのように実務で活かしたいかを示すことが重要です。ここでは、大学のサークル活動でのシステム作成を題材にした例文を紹介します。
| 入社後は、培った基礎力をもとに実務を通して知識を深め、より便利で使いやすいシステムをつくれるエンジニアになりたいと考えています。 大学時代、所属していたサークルでイベントの参加者管理を効率化するために、友人と一緒に簡単なWebシステムを制作しました。当初は入力画面の不具合が多く、参加者から使いにくいとの声もありました。 しかし、試行錯誤しながら改善を続けることで、最終的には誰でも簡単に操作できるシステムに仕上げることができたのです。 この経験を通じて、利用者目線で工夫する大切さと、問題に直面しても粘り強く解決する姿勢を学びました。入社後も改善を恐れず挑戦し、利用者に喜ばれるシステム開発に取り組みたいです。 |
ユーザー体験や仲間との協力を軸にすると、エンジニアとしての成長意欲を具体的に伝えられます。特に「工夫した点」を盛り込むのが効果的です。
⑦コンサルタント職の例文
コンサルタント職では、課題を見つけて解決策を提案する力をアピールすることが大切です。ここでは、大学でのグループ活動を通じて得た経験を題材にした例文を紹介します。
| 入社後は、お客様の課題に寄り添い、解決に導けるコンサルタントを目指したいと考えています。大学時代、ゼミで地域商店街の活性化をテーマに調査を行った経験があります。 初めは意見がまとまらず議論が進まないことも多くありましたが、商店主への聞き取りを重ねる中で「若い世代の来訪が少ない」という共通の課題を発見しました。 そこで私たちはSNSを活用した広報案を提案し、実際にイベントの来場者数が増加しました。この経験を通じて、問題を整理し根本的な課題を捉えることの大切さを学びました。 入社後も現場の声に耳を傾け、解決策を一緒に考え、成果につなげるコンサルタントとして成長していきたいです。 |
「課題発見」と「改善の提案」を一連の流れで書くと、コンサルタントに必要な素養を伝えやすくなります。特に、自らの行動で成果が出た点を具体的に示すと効果的です。
⑧マーケティング職の例文
マーケティング職では、情報を集めて分析し、工夫を凝らした取り組みにつなげる姿勢をアピールすると効果的です。ここでは、大学生活の経験をもとにした例文を紹介します。
| 入社後は、消費者のニーズを的確に捉え、商品やサービスを多くの人に届けられるマーケティングに挑戦したいと考えています。 大学時代、サークルで学園祭の模擬店を担当した際、前年の来場者数やアンケート結果を調べることで「並ぶ時間が長い」という不満が多いことを知りました。 そこで私たちはメニューを絞り、事前注文の仕組みを導入することにしたのです。その結果、販売数は前年より大幅に増え、売り切れまでの時間も短縮できました。 この経験を通じて、課題を分析し改善策を打ち出す力の大切さを学びました。入社後はお客様の声や市場の動きをしっかり把握し、戦略を考え、成果につなげるマーケティング担当者として成長したいです。 |
マーケティング職では「調査→分析→改善→成果」という流れを盛り込むと説得力が増します。特に数値や結果を具体的に書くことで、実行力を強調できるでしょう。
⑨販売職の例文
販売職では「お客様と直接向き合い、信頼関係を築く姿勢」を伝えることが重要です。ここでは、大学生活での身近な経験を交えた例文を紹介します。
| 入社後は、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、信頼される販売員として活躍したいと考えています。 大学時代、学園祭で模擬店を運営した際、ただ商品を売るのではなく、お客様に楽しんでもらう工夫が必要だと感じました。 そこでメニューを説明するときに「おすすめの食べ方」を添えたり、小さな会話を心がけたりすることにしたのです。その結果、リピーターとして何度も立ち寄ってくださる方が増え、売上も前年より伸びました。 この経験から、販売は単なる商品の提供ではなく、人との関わりを大切にする仕事だと実感しました。入社後もお客様にとって心地よい体験を提供し、また来たいと思っていただけるよう努力していきたいです。 |
販売職の例文では「お客様への気配り」と「成果につながった具体的な工夫」を書くと印象的です。体験談に小さな工夫を加えることで説得力が高まります。
⑩人事・総務職の例文
人事・総務職では「組織を支える役割を果たしたい」という姿勢を、学生時代の経験を交えて伝えると効果的です。ここでは、部活動やサークル運営のエピソードを用いた例文を紹介します。
| 入社後は、社員の方々が安心して働ける環境づくりに貢献したいと考えています。大学時代、所属していたサークルでは会計やイベント運営の裏方を担当した経験があります。 仲間が活動に集中できるよう、予算管理や会場の手配を進める中で、前に出ることよりも縁の下で支える大切さを学びました。 特に、定期公演の準備では意見が食い違う場面もありましたが、全員の意見をまとめて日程を調整することで、無事に開催することができました。 この経験から、働く人々のパフォーマンスを高めるには、安心できる仕組みやサポートが必要だと実感しました。入社後も組織全体を支える役割を担い、働きやすい環境づくりに尽力したいです。 |
人事・総務職の例文では「支える姿勢」と「調整力」を強調すると効果的です。自分が前に立つよりも、裏方で支えた経験を具体的に書くと説得力が増します。
避けるべきNG回答例
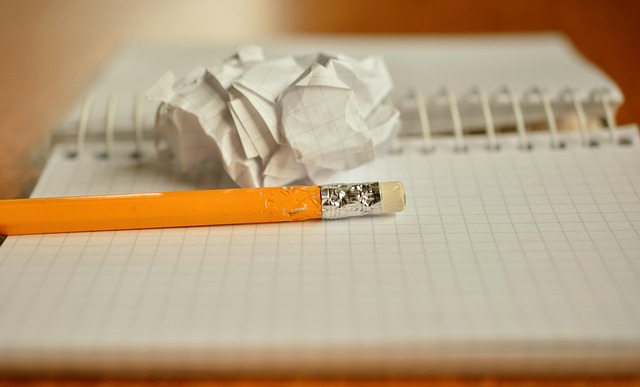
入社後にしたいことを伝える場面では、前向きな印象を与えることが大切です。しかし、多くの就活生が選考で不利になる答え方をしてしまうことがあります。
ここでは、特に注意したいNG回答を5つ紹介します。事前に知っておけば、面接やESで安心して答えられるでしょう。
- 仕事内容と関係のない回答をする
- 個人的すぎる目標を伝える
- 目標が非現実的または低すぎる
- 他の企業でも実現可能なことを答える
- ネガティブな言い回しを使う
①仕事内容と関係のない回答をする
仕事内容と無関係なことを答えるのは避けてください。採用担当者は、学生がどのように仕事へ向き合うかを知りたいと思っています。
たとえば「海外旅行に行きたい」「趣味を充実させたい」といった内容では、会社で働く姿が見えてきません。
その一方で「営業職として顧客の課題解決に取り組みたい」と答えれば、職務と直結しており評価されやすいです。
入社後の希望は仕事を通じて達成できることを中心に話すと、安心感を持たれるでしょう。
②個人的すぎる目標を伝える
就活の場では、自己都合だけの目標を挙げるのは好ましくありません。理由は、採用側が会社への貢献意欲を重視しているからです。
「早く結婚したい」「一人暮らしをしたい」といった話は、働く姿勢が伝わらず評価につながりません。
その代わりに「事務職として正確な処理で業務効率を高めたい」と答えれば、組織に貢献したい気持ちを示せます。個人的な願望ではなく、自分の成長と会社の成長を重ねた目標を話してください。
③目標が非現実的または低すぎる
入社後にしたいことは、現実的であることが求められます。「すぐに海外支社の責任者になりたい」といった大きすぎる夢は、計画性がなく見えてしまうことも。
逆に「遅刻をしない」といった低すぎる目標では、成長意欲が不足している印象になります。適切なのは「1年目で基礎を学び、3年目には後輩を指導できるようになりたい」といった段階的な目標です。
無理がなく前向きな成長を示すことで、信頼を得られるでしょう。
④他の企業でも実現可能なことを答える
どの会社でも言えるような答えは避けましょう。「社会に貢献したい」「成長したい」といった答えは一見良さそうに見えますが、志望理由の薄さを疑われやすいです。
その代わりに「貴社の製造技術を学び、品質向上に貢献したい」と具体的に伝えれば、企業研究を踏まえていると分かります。
ここで重要なのは「その会社だからこそ実現したいこと」を示すことです。具体性と独自性があるほど、熱意は伝わりやすくなります。
⑤ネガティブな言い回しを使う
ネガティブな表現は、せっかくの意欲を弱めてしまいます。「失敗しないようにしたい」「怒られないように努力する」といった答えでは、守りの姿勢が目立つだけです。
面接官は挑戦する姿勢を評価するため、評価につながりにくいでしょう。その代わりに「ミスを減らし、正確な業務で信頼を得たい」と言い換えれば、改善意識と前向きさを同時に示せます。
伝え方を工夫することで、積極性のある答えに変わるはずです。
入社後にしたいことを答える際の注意点

就活の面接やESで「入社後にしたいこと」を聞かれたとき、何を話せばよいのか迷う学生は多いです。
ここでは、回答を考えるうえで注意したいポイントをまとめました。採用担当者に伝わりやすく、自分の強みや意欲を自然に示せるように意識してください。
- 簡潔にわかりやすくまとめる
- 曖昧な表現を避けて数字や事例で示す
- 短期的な目標と長期的な目標をバランスよく述べる
- 再現性のあるエピソードを活用する
①簡潔にわかりやすくまとめる
「入社後にしたいこと」を答えるときは、できるだけ簡潔にまとめることが大切です。面接官は多くの学生と対話するため、長すぎる説明は逆効果になりやすいでしょう。
たとえば「営業力を高めたい」と先に結論を伝え、その後で「学園祭の企画でスポンサー営業を担当し、相手に合わせて提案方法を工夫した経験がある」と具体的に補足すると理解されやすくなります。
結論を先に述べ、その後に理由や背景を示すことで、話の筋が明確になるでしょう。自分の考えを整理することにもつながり、信頼を得る一歩になるはずです。
②曖昧な表現を避けて数字や事例で示す
就活では「努力します」や「頑張ります」といった抽象的な表現だけでは評価されにくいです。面接官が知りたいのは実現可能性や根拠なので、数値や具体的な体験を交えることが必要になるでしょう。
たとえば「売上を上げたい」と言うより「3年以内に営業成績で上位20%に入りたい」と伝えれば、成長意欲が明確になります。
さらに「ゼミで発表回数を増やし、説明力を伸ばしてきた」と過去の実績と結びつければ信頼性が高まるでしょう。具体的に表現することで「この学生は実行力がある」と感じてもらいやすくなります。
③短期的な目標と長期的な目標をバランスよく述べる
「入社後にしたいこと」を答える際は、短期と長期の目標を組み合わせると説得力が増します。
短期的には「まずは基本業務をしっかり習得する」、長期的には「新規プロジェクトのリーダーを担う」といった形で段階的に説明すると、成長の道筋が伝わりやすいです。
短期だけだと視野が狭く見え、長期だけでは現実味が薄れるため両方を取り入れるのが効果的でしょう。
「1年目で基礎を固め、3年目には成果を出して後輩の育成に関わりたい」と時間軸を加えると、採用担当者に具体的な成長イメージを与えられます。
④再現性のあるエピソードを活用する
回答を考えるときには、自分の経験をもとにした再現性のあるエピソードを盛り込むと効果的です。採用担当者は「この学生が本当にやれるか」を見極めているので、根拠となる実体験があると説得力が増します。
たとえば「アルバイトで新人教育を任され、マニュアルを作って業務効率を改善した経験がある。その経験を活かして、入社後もチームで成果を出す工夫をしたい」といった伝え方です。
過去の行動をもとに将来を語れば、実現可能性が高く見えます。自分の強みを自然に示しつつ、組織にどう貢献できるかも表現できるでしょう。
入社後にしたいことが見つからないときの対処法

就活で「入社後にしたいこと」を問われても、すぐに答えが浮かばず不安になる人は少なくありません。漠然とした思いのままではESや面接で説得力を欠いてしまうでしょう。
ここでは身近な経験や研究の進め方から、方向性を見つける具体的な方法を整理しました。
- インターンやアルバイト経験からヒントを得る
- 業界研究や企業研究を改めて行う
- 小さな興味から仕事につながるテーマを見つける
- キャリアの方向性をフレームワークで整理する
- キャリアセンターや就活サービスを活用する
①インターンやアルバイト経験からヒントを得る
過去の実体験は「入社後にしたいこと」を見つけるうえで大きなヒントになります。なぜなら、自分が行動して成果や学びを得た経験は強みと再現性を持ち、企業への貢献イメージにつながるからです。
飲食以外のアルバイトで業務効率化の工夫したことや、チームの連携を改善した経験を振り返ってみてください。
「課題に気づいた」「試行錯誤した」「結果が出た」という流れを言葉にすれば、入社後も同じ姿勢で取り組みたいことを具体的に語れるでしょう。
経験をストーリーに落とし込むことで、説得力のある自己PRへ発展します。
②業界研究や企業研究を改めて行う
企業や業界の最新情報に触れることで「入社後にしたいこと」の具体像を描きやすくなります。事業の強みや成長分野を理解すれば、自分の関心や能力と結びつけやすいからです。
企業のIR資料やニュースを読み、さらに商品やサービスを実際に体験してみてください。もし、IT企業なら導入事例や利用者の声を調べ、自分が関わりたい課題解決の形を考えましょう。
その過程で「顧客視点で改善を提案したい」など具体的な目標が見えてきます。研究を重ねたうえで導き出した答えは自然に説得力を持ち、面接官にも納得してもらえるはずです。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
③小さな興味から仕事につながるテーマを見つける
身近な関心ごとを、職務に結びつけることが大切です。日常で楽しんでいることは継続性があり、入社後も強みとして発揮できるからです。
SNSでの情報発信が好きなら、その分析や改善をマーケティングに生かせます。整理整頓が得意であれば、事務や管理の正確性に役立つでしょう。
小さな興味を仕事に翻訳するコツは、行動のプロセスを細かく分け、どのスキルに置き換えられるかを考えることです。
その結果「自分はこういう分野で成長したい」という未来像が自然に形づくられます。
④キャリアの方向性をフレームワークで整理する
WILL・CAN・MUSTのフレームワークを活用すると、自分の方向性を整理しやすくなります。
やりたいこと(WILL)、できること(CAN)、社会や企業から求められること(MUST)の3点を重ね合わせれば、現実的で納得度の高い目標が見えてくるでしょう。
「人の役に立ちたい」というWILLに対し、「資料作成やデータ整理が得意」というCAN、さらに「企業が求める業務効率化」というMUSTが重なるなら、事務やバックオフィス業務での活躍が導き出されます。
フレームを使えば抽象的な悩みを具体的な行動指針に変えられ、入社後の成長イメージを描きやすくなるでしょう。
⑤キャリアセンターや就活サービスを活用する
迷ったときは、第三者の意見を積極的に取り入れてください。自分では気づかない強みや可能性を、客観的に示してもらえるからです。
大学のキャリアセンターではES添削や模擬面接が受けられ、表現や構成の改善につながります。OB・OG訪問を通じて実際の仕事の流れや評価基準を知れば、将来像と照らし合わせやすいでしょう。
さらに、就活サービスの適性診断やスカウト機能を利用すれば、新しい業界との接点も生まれます。外部の支援を活用すれば、入社後にしたいことの方向性を客観的に固めることが可能です。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
入社後にしたいことに関するよくある質問

入社後にしたいことは就活の中でよく聞かれる質問ですが、答え方に悩む学生は多いものです。
ここでは代表的な疑問を取り上げて、伝え方の工夫や注意点を解説します。安心して答えられるようにヒントをつかんでください。
- 複数のやりたいことがある場合の伝え方は?
- 企業研究が浅いときにどうやって答えを作ればいい?
- エントリーシートと面接で答える内容は同じでも大丈夫?
①複数のやりたいことがある場合の伝え方は?
入社後にやりたいことが複数あると、どのように伝えるか迷う人は多いでしょう。そのまま並べると焦点が定まらず、結果的に印象が薄れてしまいます。
そこで大切なのは、共通する軸を見つけて一貫した方向性にまとめることです。もし、「人を支えること」に関心があるなら、営業でも企画でも「顧客に価値を届けたい」と表現できます。
複数の興味を無理に切り捨てる必要はなく、根本にある価値観を一つの軸にすることで説得力が高まるでしょう。面接官はブレない姿勢を感じ取り、信頼感を持ちやすくなるはずです。
②企業研究が浅いときにどうやって答えを作ればいい?
企業研究が不十分だと、自信を持って「入社後にしたいこと」を語れないと感じるかもしれません。しかし、まずは自分の経験や強みを整理し、それを基準に答えを作る方法があります。
たとえば、チームで工夫して成果を出した経験があるなら「入社後は協働を通じて改善に取り組みたい」と表現できます。そこに企業の事業内容や理念を重ねれば、自然に説得力が生まれるでしょう。
つまり、自己分析を土台にしておけば研究が浅くても答えを形にできますし、調べを深めるほどにより具体的で実践的な内容に成長させられます。焦らず段階を踏むことが大切です。
③エントリーシートと面接で答える内容は同じでも大丈夫?
エントリーシートと面接で全く同じ内容を繰り返すのはあまりお勧めできません。
ESでは「入社後は〇〇に挑戦したい」と簡潔にまとめ、面接ではその背景や具体的な経験を加えて広げるとよいでしょう。
両者に一貫性があることが何より大切で、書面と口頭で矛盾がないと安心感を与えられます。
内容の核は同じで構いませんが、表現の仕方や深さを変えることで、相手に誠実さと熱意を伝えられるでしょう。その結果、面接官から「本当にやりたいことを持っている学生だ」と評価されやすくなります。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
入社後にしたいことを効果的に伝えるために

入社後にしたいことを明確にすることは、就職活動において非常に重要です。なぜなら、企業はこの質問を通して理念への理解度や仕事内容との適性を見極めているから。
具体的な答え方としては、将来像から逆算した目標や自身の経験を根拠にした計画を述べることが効果的でしょう。また、志望動機との一貫性を持たせることで説得力が高まります。
さらに、ESや面接では企業の特徴に結びつけて伝えることで相手の納得感を得られるはずです。業界・職種別の例文を参考にすれば、イメージを具体化しやすくなります。
入社後にしたいことを答える際には、曖昧さを避けて数字や事例を交え、短期と長期の目標をバランスよく示してください。その結果、面接官に成長意欲と実現可能性を感じてもらえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













