面接で「最後に質問はありますか?」逆質問例20選と答え方のコツ
最後に求められる質問は単なる形式的なものではなく、入社意欲や志望度、さらにはコミュニケーション能力まで見極められる重要な場面です。
この記事では、「最後に質問はありますか?」と聞かれる理由や準備方法、差別化につながる逆質問のコツ、さらには実際に使える例文20選を詳しく解説します。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
面接で「最後に質問はありますか?」と聞かれる理由

面接の最後に必ずといってよいほど投げかけられるこの質問には、複数の意図があります。採用担当者は応募者の姿勢や考え方、価値観を知るために重要な場面として活用しています。
ここでは、その理由を理解し、適切な逆質問につなげるための視点を整理します。
- 入社意欲を確認するため
- 志望度の高さを見極めるため
- コミュニケーション能力を評価するため
- 社風や価値観との相性を知るため
- 入社後の働く姿をイメージするため
- 質問力や思考力を測るため
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①入社意欲を確認するため
面接官が逆質問で最も注目するのは、入社意欲の高さです。企業は長期的に活躍できる人材を求めており、その判断材料として質問内容を見ています。
意欲がある応募者は、企業研究に基づいた具体的な質問を準備し、自分の希望や将来像を自然に盛り込みます。反対に、浅く曖昧な質問は「準備不足」や「志望度が低い」と受け取られかねません。
業務内容やキャリアパスについての質問は、前向きな印象を与えます。事前に業界動向や企業方針を把握し、自分がどう貢献できるかを踏まえた質問を用意しておくことが大切です。
こうした準備は、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
②志望度の高さを見極めるため
企業は限られた枠で採用するため、本当に志望度が高い人材を選びたいと考えます。逆質問では、どれだけ企業情報を調べ、自分なりに考えてきたかが問われます。
具体性や独自性のある質問は、志望度の高さを裏付けます。一方、ホームページに載っている情報や表面的な質問は、興味の薄さを示す恐れがあります。
将来の事業計画や部署間の連携体制など、内部事情に近いテーマを尋ねると効果的です。
説明会やOB・OG訪問で得た情報を踏まえ、自分のキャリアビジョンと重ねた質問を準備すれば、評価は高まりやすくなります。
③コミュニケーション能力を評価するため
逆質問は疑問解消だけでなく、応募者の会話力や思考整理力を測る場でもあります。面接官は、質問の構成や回答への反応からコミュニケーション能力を判断します。
的確で論理的な質問は、業務での会話も円滑に行えると評価されます。さらに、回答を受けて追加の質問や共感を示せれば、対話力の高さが際立ちます。
一方で、長すぎる質問や抽象的すぎる内容は流れを妨げます。事前に質問の意図を明確にし、簡潔で答えやすい形に整えておくことが重要です。こうした準備が信頼獲得につながります。
④社風や価値観との相性を知るため
企業はスキルや経験だけでなく、社風や価値観に合う人材を求めます。逆質問は、その相性を確認する機会です。質問の切り口から、応募者が大切にしている働き方や価値観が伝わります。
たとえば、チームワークの進め方や評価制度を尋ねると、職場環境への関心が表れます。価値観が一致すれば長期的な活躍が期待できますが、合わない場合はストレスや離職の原因にもなります。
自分に合う職場かを見極める視点を持つことで、双方にとって良い関係を築けます。
⑤入社後の働く姿をイメージするため
逆質問は、企業が応募者の将来像を描くきっかけになります。
具体的な業務やプロジェクトに関する質問は、関心分野や挑戦意欲を示します。たとえば「入社1年目に関わる可能性が高い案件」や「新人に求められる成果」などを聞くと、成長意欲が明確になります。
このような質問は、採用後の配属や教育計画にも影響します。自分自身も働き方を具体的に想像でき、ミスマッチ防止につながります。
企業の事業内容や職種別業務を事前に調べ、質問に落とし込む準備が必要です。
⑥質問力や思考力を測るため
面接官は逆質問から応募者の思考の深さや情報処理能力を見ます。論理的で一貫性のある質問は、問題解決力や分析力の高さを示します。
業界課題や新規事業への取り組みなど、広い視野を持った質問は評価されやすいです。一方で、漠然として意図が不明な質問は評価を下げます。
質問力を高めるには、事実と自分の意見を組み合わせ、背景や理由を簡潔に述べることが重要です。また、回答への適切な反応も好印象を与えます。
知的な印象を残す逆質問は、内定獲得への一歩となります。
逆質問に回答するための準備

面接で「最後に質問はありますか?」と聞かれたとき、即座に適切な質問ができるかどうかは事前準備の質で決まります。
企業や業界の情報を集め、自己アピールや入社後の働き方につながるテーマを整理すると、高評価につながる逆質問が可能です。ここでは、準備の手順を順番に解説します。
- 企業・業界情報の収集
- 気になる疑問点の洗い出し
- 自己アピールにつながるテーマ設定
- 入社後のギャップを減らす質問選定
- 質問内容の優先順位付け
- 端的かつ具体的な質問文の作成
- 面接官の役職や立場を想定した準備
①企業・業界情報の収集
効果的な逆質問の土台は、徹底した情報収集です。企業の公式サイトや採用ページを読み込み、事業内容や理念、最新ニュースを把握しましょう。
さらに、業界全体の動きや競合企業の状況も調べると、質問の背景に説得力が生まれます。浅い情報しか持っていないと、一般的すぎる質問や調べれば分かる質問になり、評価を下げる恐れがあります。
例えば「御社の強みは何ですか?」ではなく、「新製品Aの市場投入で想定する課題は何でしょうか?」のように、事実を踏まえた質問にすることが大切です。
この準備が「よく調べている学生」という印象を与える第一歩になります。
②気になる疑問点の洗い出し
逆質問は、本当に知りたいことを軸に考えることで自然で熱意のある会話につながります。
説明会や企業研究で疑問に思った点、仕事内容やキャリアパスについて知りたいことを事前に書き出しておくと、当日に迷わず質問できます。
特に業務の進め方やチーム体制など、入社後の働き方に関わる項目は重要です。
「働くうえで大切にしている文化は何か」や「若手社員が挑戦できる場はあるか」といった質問は、自分の軸を示すことにもなります。
整理しておくことで、面接中に新たな質問も派生させやすくなります。
③自己アピールにつながるテーマ設定
逆質問は、情報収集だけでなく自己アピールの機会としても活用できます。
例えば「御社で英語を活かせるプロジェクトの事例はありますか?」のように、自分の強みや関心に関連するテーマを選ぶと、自然に能力を示せます。
重要なのは、企業への興味だけでなく、成長意欲や将来像を感じさせる質問にすることです。
自己分析と企業研究を組み合わせてテーマを設定すると、面接官に「将来のビジョンを描いている学生」と伝わりやすくなります。
④入社後のギャップを減らす質問選定
入社後に「思っていた職場と違う」と感じないためには、職場環境や評価制度、働き方の実態を事前に確認することが大切です。
「リモートワークと出社の割合はどのくらいですか?」や「評価面談はどのように行われますか?」といった具体的な質問が有効です。
こうした情報を得ておけば、入社後のミスマッチを防ぎ、モチベーションを保ちやすくなります。また、企業理解を深めるきっかけにもなるでしょう。
⑤質問内容の優先順位付け
限られた時間で逆質問を行うためには、あらかじめ優先順位を決めておく必要があります。面接の流れや面接官の立場によっては、すべての質問ができないこともあります。
優先度の高い質問から順にメモしておき、時間があれば補足的な質問をする形が望ましいです。この準備により、慌てず落ち着いて面接に臨めます。
⑥端的かつ具体的な質問文の作成
質問は短く明確にすることが大切です。長すぎる前置きや曖昧な表現は、意図が伝わりにくくなります。
例えば「御社の研修制度について詳しく教えていただけますか?」のように、対象と目的をはっきりさせましょう。簡潔な質問は相手に好印象を与えやすくなります。
⑦面接官の役職や立場を想定した準備
同じ質問でも、相手の立場によって答えは変わります。人事担当者なら採用方針や研修制度、現場の管理職なら業務内容やチームの雰囲気など、相手の経験に合わせた質問を用意しましょう。
立場を想定することで、会話の深みが増し、配慮ある印象を与えられます。
逆質問で意識すべきポイント

面接での逆質問は、応募者の姿勢や準備度を示す大切な場面です。適切な質問は評価を高めますが、配慮を欠いた質問は逆効果になる場合があります。
ここでは、言葉遣いや礼儀、質問の意図、時間の使い方、質問のまとめ方など、就活生が意識すべきポイントを解説します。
- 言葉遣いと礼儀を意識する
- 質問の背景や意図を明確にする
- 時間配分を考慮する
- 質問内容を簡潔にまとめる
①言葉遣いと礼儀を意識する
逆質問では、まず面接官への敬意を示すことが大切です。丁寧な敬語や適切な表現は、相手に好印象を与えます。
例えば「御社」や「〜していただけますでしょうか」といった表現を使えば、誠意が伝わりやすくなります。反対に、くだけすぎた口調や命令形は評価を下げる要因になりかねません。
また、姿勢や声のトーンも礼儀の一部です。落ち着いた声量と視線を保てば、誠実さを印象づけられるでしょう。
適切な言葉遣いは、質問内容以上に「この人と一緒に働きたい」と思わせるきっかけになります。
②質問の背景や意図を明確にする
逆質問の質は、背景説明で大きく変わります。
単に「研修制度はありますか」と聞くよりも、「入社後のスキル習得計画を立てたいと考えており、御社の研修制度について具体的に知りたいです」と前置きすれば、目的が明確になります。
背景を添えることで面接官は質問の意図を理解しやすくなり、より具体的で有益な回答を得られる可能性が高まります。
就活では、受け身ではなく能動的に情報を取りに行く姿勢が評価されるため、質問前のひと言が印象を左右するでしょう。
③時間配分を考慮する
面接の終盤に行われる逆質問では、限られた時間をどう使うかが重要です。質問が長くなれば、面接全体のスケジュールを圧迫してしまいます。
そのため、事前に2〜3個の質問候補を用意し、優先順位を決めておくと安心です。また、面接官の表情や時間を確認しながら質問数を調整する柔軟さも必要です。
時間配分を意識できれば、全体の流れを乱さず最後までスマートな印象を保てます。
④質問内容を簡潔にまとめる
逆質問は、短く明確にすることで相手の負担を減らせます。冗長な説明や複雑な構造は避け、聞きたいことを一文で表すのが理想です。
例えば「新規事業の今後の展望についてお伺いしたいです」と端的に切り出せば、面接官も答えやすくなります。
簡潔な質問は、論理的思考力や配慮のあるコミュニケーション力を示すことにもつながります。就活では、限られた時間で的確に意図を伝える力が評価されるため、質問の組み立てにも注意してください。
逆質問で差別化するためのポイント

面接の逆質問は、単に疑問を解消する場ではなく、他の候補者との差を生む好機です。適切な質問は面接官に強い印象を残し、入社意欲や理解度を効果的に伝えられます。
ここでは差別化のために意識すべきポイントを紹介します。
- 入社後の活躍を想起させる質問をする
- 回答からさらに深掘りする
- 企業の経営方針やビジョンへの理解を示す
- 自身の経験や考えを反映する
- 業界動向を踏まえた質問をする
①入社後の活躍を想起させる質問をする
面接官が求めているのは、入社後に活躍できる人材です。そのため、質問内容で将来の働きぶりをイメージさせることが重要になります。
例えば「新入社員が最初の1年間で任される業務にはどのようなものがありますか」と尋ねると、成長意欲と仕事内容の理解を同時に示せます。
こうした質問は、将来を見据えて準備している姿勢を伝える効果があります。結果として、採用側は入社後の姿を具体的に想像できる候補者と感じるでしょう。
事前に企業の仕事内容や育成方針を調べ、自然につながる形で質問することが鍵です。
②回答からさらに深掘りする
面接中のやり取りから新たな質問を展開できれば、柔軟な思考力と傾聴力をアピールできます。
例えば面接官が「当社はチーム制で案件を進めます」と答えた場合、「チーム編成はどのように決まりますか」と掘り下げることで理解の深さを示せます。
この姿勢は、用意した質問だけでなく、その場の会話から関心を持って質問できることを証明します。事前準備は大切ですが、当日の状況に応じて臨機応変に質問を作れるかが差別化のポイントです。
相手の発言を聞き逃さず、ヒントを見つけて掘り下げる意識を持ちましょう。
③企業の経営方針やビジョンへの理解を示す
企業理念や将来の方向性への関心は、志望度の高さを強く印象づけます。
例えば「中期経営計画で掲げている海外展開について、新入社員が関わる可能性はありますか」という質問は、事前に企業情報を深く調べた証拠です。
経営方針への理解を示すことで、単なる業務理解にとどまらず、企業全体に貢献したい姿勢を伝えられます。また、このタイプの質問はビジョンへの共感度を測る指標にもなります。
公式サイトやニュースリリースから情報を収集し、自分なりの視点を交えた質問にすると効果的です。
④自身の経験や考えを反映する
自分の経験を踏まえた質問は、個性や強みを自然にアピールできます。
例えば「学生時代にゼミで進めたプロジェクトでは短納期で成果物を作成しましたが、御社の開発プロセスではスピード感を重視する場面はありますか」と尋ねれば、経験を具体的に示しながら関心を表現できます。
この方法は、履歴書や自己PRの内容と面接での発言に一貫性を持たせられる点も魅力です。事前に自分の強みや経験を整理し、それを質問に組み込むことで、他の候補者との差別化につながります。
⑤業界動向を踏まえた質問をする
最新の業界ニュースや市場動向を背景にした質問は、情報感度の高さを示せます。
例えば「最近の業界再編の動きが御社の事業戦略にどのような影響を与えていますか」という質問は、表面的な興味を超えた理解を示します。
このような質問は、業界全体を見据えた視点を持ちつつ企業への適応力を示せるため、専門性や将来性を評価されやすくなります。
日頃から業界紙やニュースサイトで情報収集し、面接直前にも最新情報を押さえておく習慣が有効です。
面接で好印象を与える逆質問の例文集

面接で「最後に質問はありますか?」と聞かれた際、的確な逆質問はあなたの関心や意欲を効果的に伝えます。ここでは、企業理解を深めつつ好印象を与える質問例を具体的に紹介します。
- 企業の今後の事業方針に関する質問
- 配属予定部署の業務内容に関する質問
- 社内の教育制度や研修内容に関する質問
- キャリアパスや昇進の流れに関する質問
- 評価制度や人事考課に関する質問
- チーム構成や職場の雰囲気に関する質問
- 新規事業やプロジェクトへの参画機会に関する質問
- 社内で活躍している社員の共通点に関する質問
- 働き方やリモートワーク制度に関する質問
- 入社後に期待される役割に関する質問
面接でどんな質問が飛んでくるのか分からず、不安を感じていませんか?とくに初めての一次面接では、想定外の質問に戸惑ってしまう方も少なくありません。
そんな方は、就活マガジン編集部が用意した「面接質問集100選」をダウンロードして、よく聞かれる質問を事前に確認して不安を解消しましょう。
また、孤独な面接対策が「不安」「疲れた」方はあなたの専属メンターにお悩み相談をしてみてください。
企業の今後の事業方針に関する質問
企業の将来像や方向性を尋ねる質問は、入社後の成長意欲や長期的な関心をアピールする絶好の機会です。
特に就活生が企業研究を進める中で抱く素朴な疑問をもとにすれば、自然で好印象な逆質問につながります。
《例文》
| 御社の新規事業について、説明会で拝見した際に非常に興味を持ちました。特に環境に配慮した製品開発の取り組みが印象的で、大学でのゼミ活動でも環境問題に関連する調査を行ってきました。 今後、この分野の事業をどのように拡大していく予定なのか、また社員としてどのような形で貢献できるのかをお聞きしたいです。 |
《解説》
自分の経験や関心と企業の事業方針を関連づけて質問すると、志望度の高さが自然に伝わります。
事前に企業の公式サイトや説明会で得た情報を引用し、質問の背景を簡潔に示すことで、会話の流れがスムーズになります。
配属予定部署の業務内容に関する質問
配属後のミスマッチを避けるためには、部署ごとの具体的な仕事内容や関わる人々について知っておくことが大切です。
特に就活生の場合、事前に得られる情報には限りがあるため、面接の逆質問で補うことで安心して入社を決められます。
《例文》
| 御社の中で私が配属予定と伺っている部署では、日常的にどのような業務が中心になりますか。 また、その業務を進める上で他部署や社外とどのような関わりがあるのかも教えていただけると嬉しいです。 大学のゼミ活動ではチームでデータ分析を行い、外部の協力者ともやり取りをする機会がありました。 その経験から、業務内容や関係者との連携の流れを事前に理解しておくことで、自分の役割をスムーズに果たせると感じています。 |
《解説》
この例文は、配属予定部署の仕事内容と関係部署との連携を同時に尋ねています。過去の経験を軽く添えることで、単なる情報収集ではなく前向きな姿勢を示せます。
作成時は、具体的な業務内容への興味と自分の経験との関連を自然につなげることを意識しましょう。
社内の教育制度や研修内容に関する質問
面接の最後に教育制度や研修内容を質問することで、学びへの意欲や成長志向をアピールできます。特に、入社後のスキル習得やキャリア形成に関心がある学生に適したテーマです。
自分の経験や目標と絡めて質問すると、より説得力が増します。
《例文》
| 私は大学のゼミ活動でプレゼンやグループワークを通じて、自分の意見を分かりやすく伝える力を養ってきました。 ただ、その過程で論理的に話を組み立てる力や専門的な知識の深さに課題を感じています。 御社の研修制度について、特に入社1年目に受けられる研修の内容や、日々の業務とどのように結びついているのかを伺いたいです。 入社後も成長を続けられる環境があるかを知り、将来のキャリアプランに活かしたいと考えています。 |
《解説》
この例文は、自分の成長課題を示したうえで研修内容を質問しており、学びへの前向きな姿勢が伝わります。
書く際は、漠然と「研修内容を教えてください」ではなく、具体的な経験や課題を添えて質問することが効果的です。
キャリアパスや昇進の流れに関する質問
面接の最後に、入社後の成長や昇進のステップを確認する質問は、意欲と将来設計の明確さをアピールできます。
特に就活生の場合、自分のキャリア像と企業の制度が一致するかどうかを確かめることは重要です。以下の例文は、一般的な大学生が納得感を持って尋ねやすい内容にしています。
《例文》
| 私は大学時代、学園祭の実行委員会で役職を経験し、責任のある立場でチームをまとめるやりがいを感じました。 入社後も同じように、責任ある業務や役割を任されることを目指しています。 そこで、御社では入社から3年以内にどのような業務を経験し、どのような基準で昇進が判断されるのかをお伺いできますでしょうか。 |
《解説》
具体的な経験を交えながら将来像を示すと、質問の背景が伝わりやすくなります。自分の目指すキャリアと企業の昇進制度を関連付けることで、志望度の高さと前向きな姿勢をアピールできます。
評価制度や人事考課に関する質問
評価制度や人事考課に関する逆質問は、入社後の働き方や成長機会を理解するうえで重要です。
特に就活生にとっては、自分の努力がどのように評価され、昇進やキャリア形成につながるのかを知ることは安心感にもつながります。
ここでは、面接官に好印象を与えながら、自分の成長意欲も伝えられる例文を紹介します。
《例文》
| 大学のゼミ活動で、目標に向けてメンバーと協力しながら取り組み、その成果を発表する経験を積んできました。入社後も同じように目標を立て、成果を出すために努力したいと考えています。 そこで、御社では成果や努力をどのような基準で評価し、昇進や昇給につなげているのかお伺いできますでしょうか。 |
《解説》
この例文は、自分の経験を簡潔に述べたうえで質問につなげている点が効果的です。成長意欲や前向きな姿勢を伝えつつ、評価制度に興味を持っていることを示せます。
同じテーマを書く場合は、自己PRの延長線上で質問を組み立てると自然になります。
チーム構成や職場の雰囲気に関する質問
面接の最後に「質問はありますか?」と聞かれたとき、職場環境やチームの雰囲気に関する質問は、入社後のミスマッチを防ぐために有効です。
特に大学生活でのサークル活動やアルバイト経験を絡めると、自然で説得力のある逆質問になります。
《例文》
| 大学時代、アルバイト先で先輩や同僚との関係性が良く、安心して働けた経験があります。そのため、働く環境の雰囲気はとても大切だと感じています。 御社では部署ごとにどのようなチーム構成になっているのか、また日々の業務の中でメンバー同士がどのようにコミュニケーションを取っているのかをお伺いしたいです。 |
《解説》
この例文は、自分の経験を簡潔に伝えたうえで質問につなげているため、自然な流れが生まれます。
作成の際は「過去の経験」→「価値観」→「質問」という順序を意識すると、面接官にも好印象を与えやすくなります。
新規事業やプロジェクトへの参画機会に関する質問
企業の将来性や自分の成長の場を確かめるためには、新規事業やプロジェクトへの参画機会について質問することが効果的です。
特に、挑戦心や前向きな姿勢をアピールできるため、面接官の印象にも残りやすいでしょう。
《例文》
| 学生時代、ゼミで地域活性化イベントを企画し、限られた予算内で新しいアイデアを形にする大変さと面白さを実感しました。 御社でも同じように、新規事業やプロジェクトに主体的に関わる機会があると感じています。 そこで、入社1年目や2年目の社員でも、新規プロジェクトの立ち上げや企画段階から参画できるチャンスはありますか。 |
《解説》
この例文は、学生時代の経験を通じて得た学びを企業の活動に結び付けています。
同じテーマを書く場合は、まず自分の経験を簡潔に示し、それを「この会社でどう活かせるか」に自然につなげることを意識しましょう。
社内で活躍している社員の共通点に関する質問
面接でこの質問をすることで、自分が入社後にどのような姿勢で働けば評価されるのかを知るきっかけになります。
特に就活生にとって、社内で評価される人材像を理解することは入社後の成長スピードを高めるうえで重要です。以下は、自然で前向きな印象を与える質問例です。
《例文》
| 御社で特に活躍している社員の方には、どのような共通点がありますか。 学生時代、ゼミ活動で成果を出していた先輩方は、周囲との協力を大切にしつつ自ら課題を見つけて行動していた印象があります。 そうした経験から、自分も周囲と連携しながら能動的に行動する姿勢を大事にしています。 御社で成果を上げている方の特徴を知ることで、入社後にどのような姿勢や行動を意識すべきか学びたいと考えています。 |
《解説》
この例文は、自分の経験と質問内容を関連づけることで、単なる情報収集ではなく成長意欲をアピールしています。
作成時は、過去の経験を簡潔に示しつつ「なぜその質問をするのか」という理由を明確にすると好印象につながります。
働き方やリモートワーク制度に関する質問
企業の働き方やリモートワーク制度について質問することで、入社後の働く環境をより具体的にイメージできます。
特に、柔軟な勤務形態やオンラインでのコミュニケーション方法は、働きやすさや生産性にも直結します。ここでは、大学生が自然に使える例文を紹介します。
《例文》
| 大学時代、オンライン授業やゼミの活動を通して、リモートでの作業効率や意思疎通の難しさを実感しました。 御社ではリモートワークを取り入れていると伺いましたが、在宅勤務時のチーム間の連絡方法や進捗管理の仕組みについて教えていただけますか。 |
《解説》
この例文は、自分の経験を簡潔に述べたうえで、企業の制度や運用方法に焦点を当てています。
同じテーマを書くときは、「自分の経験」→「企業への質問」という流れを意識すると、自然で説得力のある質問になります。
入社後に期待される役割に関する質問
入社後にどのような役割を担うことになるのかを質問することで、具体的な業務イメージを持ちやすくなります。
また、事前に知っておくことで入社後のギャップを減らし、自分の適性や強みを発揮できる準備にもつながります。ここでは、大学生が自然に聞ける逆質問例を紹介します。
《例文》
| 学生時代はゼミ活動でプロジェクトの進行役を担当し、メンバーの意見をまとめながら目標達成に向けて動く経験を積みました。 御社に入社した際には、この経験をどのような場面で活かせるのか知りたいです。また、入社後すぐに任される業務や役割についても教えていただけますか。 |
《解説》
この例文は、自分の経験を踏まえて入社後の役割を具体的に尋ねる形になっています。経験→質問の順で構成すると、自然に自己アピールを含められます。
同じテーマを書く場合は、自分の強みと企業の業務内容を結びつけて質問すると効果的です。
面接で避けるべき逆質問のNG例文集
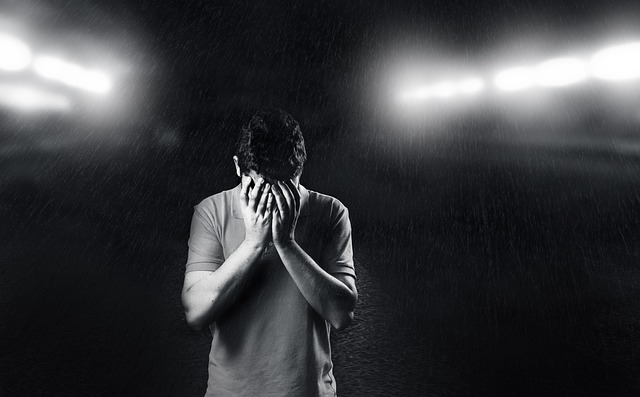
面接での逆質問は、印象を左右する重要な場面です。しかし、聞き方や内容を誤ると、評価を下げてしまう可能性があります。ここでは避けるべき逆質問のパターンを具体例とともに紹介します。
- 特に質問はないと答える
- 給与や待遇に関する質問
- 調べればわかる基本情報に関する質問
- 既に説明された内容を再度聞く質問
- 「はい・いいえ」で答えられる質問
- 漠然とした意図の見えない質問
- 同業他社と比較する質問
- ネガティブな印象を与える質問
- 面接官が答えられない専門的すぎる質問
- 責任回避を感じさせる質問
特に質問はないと答える
面接の最後に「質問はありますか?」と聞かれたとき、あえて質問しない選択をする場合でも、好印象を残す工夫が必要です。
単に「ありません」と答えるのではなく、これまでの説明に満足している姿勢や、会社への理解度の高さを示すことが大切です。以下は、感謝と納得感を伝えつつ、前向きな印象を与える回答例です。
《例文》
| 本日の面接で業務内容や今後のキャリアパスについて詳しく説明いただき、十分に理解できましたので、現時点で質問はございません。 本日お話を伺う中で、改めて貴社で働きたいという気持ちが強まりました。 これまでに培ってきたゼミでの企画運営の経験を活かし、貴社の新規プロジェクトにも積極的に貢献していきたいと考えております。本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 |
《解説》
「質問はない」と答える場合でも、感謝の言葉と志望意欲を盛り込みましょう。納得している姿勢を伝えることで、準備不足ではなく、理解度の高さとして評価されやすくなります。
給与や待遇に関する質問
面接で給与や待遇について質問する際は、直接的に金額を尋ねるよりも、制度や評価基準を確認する形が望ましいです。これにより、条件面への関心と同時に、長期的な働き方への意欲も伝わります。
学生時代の経験や将来のキャリアプランに触れながら聞くことで、自然な流れで質問ができます。
《例文》
| 学生時代、サークル活動で後輩の育成を担当する中で、成果に応じた評価制度の重要性を感じました。御社での評価は、どのような基準やプロセスで行われるのでしょうか。 また、その評価が給与や賞与にどのように反映されるのか教えていただけますか。 |
《解説》
金額ではなく評価基準や制度に焦点を当てると、現実的かつ前向きな印象を与えられます。自分の経験と関連づけて質問すると、単なる条件確認ではなく、成長意欲をアピールする流れにできます。
調べればわかる基本情報に関する質問
企業HPや求人票などを読めば分かる情報は、逆質問では避けたいところです。
しかし、事前に下調べしたうえで、その情報を踏まえてさらに深堀りする形の質問なら、理解度の高さや主体性をアピールできます。
ここでは、企業の基本情報に関する質問を、自然で好印象な聞き方の例文としてご紹介します。
《例文》
| 御社のホームページで、若手社員の研修制度が充実していることを拝見しました。特に入社1年目のサポート体制に力を入れていると知り、安心感を持ちました。 もし可能であれば、実際に研修を受けた先輩方がどのように業務に活かしているのか、具体的なエピソードを教えていただけますか。 |
《解説》
事前に調べた事実を前置きし、その情報を踏まえた発展的な質問にすることで、準備の丁寧さを示せます。
同じテーマを書くときは、「調べた事実+自分の感想や興味+具体的に知りたい点」という三段構成を意識すると、自然で深みのある質問になります。
既に説明された内容を再度聞く質問
面接中に説明を受けた内容を改めて確認する質問は、理解度の高さや真剣さを示す効果があります。特に重要なポイントや、自分の志望理由と関係が深い部分を掘り下げると、印象がより良くなります。
《例文》
| 先ほどご説明いただいた新人研修について、配属後の業務内容とのつながりをもう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。 私は大学時代、ゼミ活動でプレゼンや資料作成を担当することが多く、基礎スキルをしっかり学べる環境に魅力を感じています。 研修で得た知識やスキルが、配属先でどのように活かされるのかを具体的に知ることで、自分の成長イメージをより明確にしたいと考えています。 面接でのお話を踏まえて、自分の力を最大限発揮できる方法を考えたいと思っておりますので、ぜひお聞かせください。 |
《解説》
この例文は、説明内容の再確認を通して「理解を深めたい姿勢」と「自分の経験との関連性」を示しています。
同じテーマを書く場合は、単に質問を繰り返すのではなく、自分の背景や関心と結びつけて聞くことで、意欲や目的意識を効果的に伝えられます。
「はい・いいえ」で答えられる質問
面接で「最後に質問はありますか?」と聞かれた際、会話を広げにくい「はい・いいえ」で終わる質問は避けたいものです。
ここでは、シンプルながらも面接官との対話が続くような、工夫を凝らした質問例をご紹介します。
《例文》
| 大学のゼミ活動で企業訪問を行った際、社員の方が「現場の雰囲気は実際に来てみないと分からない」とおっしゃっていました。 その経験から、御社でも入社前後で働く環境や仕事内容に変化を感じる場面があるのか気になっております。 もし差し支えなければ、実際に入社した社員の方々が最初に驚いたことや、想像との違いについて教えていただけますか。 |
《解説》
背景となる経験を交えて質問することで、「はい・いいえ」だけでは終わらない会話を引き出せます。ポイントは、質問の前に理由や関心のきっかけを短く伝えること。
こうすることで面接官も具体的に答えやすくなり、自然なコミュニケーションが生まれます。
漠然とした意図の見えない質問
面接の最後に質問を求められた際、意図があいまいなまま尋ねてしまうと、企業側に「準備不足」と受け取られる可能性があります。ここでは、質問の目的や背景が不明確になってしまった例を示します。
《例文》
| 本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。えっと…御社の業務って、やっぱり忙しいんですか?あ、忙しいというか…大変というか…。 すみません、うまく言えないのですが、仕事の雰囲気とか、その…実際の感じを知りたいです。 |
《解説》
この例では質問の意図が整理されておらず、面接官に「何を知りたいのか」が伝わりにくくなっています。
テーマが漠然としないよう、事前に質問の目的と背景を明確にし、具体的な言葉に置き換えて伝えることが重要です。
同業他社と比較する質問
面接の場では、自社の強みや特徴を引き出す質問をすることで、業界理解の深さや志望度の高さをアピールできます。
特に同業他社との違いに注目した質問は、企業研究をしっかり行っている印象を与えるため効果的です。以下は、そのような質問を行う際の具体例です。
《例文》
| 本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございます。企業研究を進める中で、御社と同じ業界の他社の取り組みについても調べました。 その中で、御社は特に新人教育や研修制度に力を入れていると感じています。例えば、同期が他社で1週間の研修を受けたと話していたのに対し、御社は3か月間の研修期間があることに驚きました。 こうした長期研修を設けている理由や、その研修で特に重視している点についてお聞かせいただけますでしょうか。 |
《解説》
この例文は、他社との比較を通じて企業の独自性を引き出す構成です。事実ベースの比較を入れると質問の説得力が増し、相手も答えやすくなります。
作成時は「比較対象」「企業の特徴」「質問内容」の3要素を意識すると効果的です。
ネガティブな印象を与える質問
面接の最後にする質問は、志望意欲や前向きな姿勢を示す場です。しかし、条件面や不満を連想させる内容は避けるべきです。
ここでは、就活生がうっかり口にしてしまいがちな、ネガティブな印象を与える質問の例文を紹介します。
《例文》
| 御社の残業時間はどれくらいありますか?大学の授業やサークル活動で忙しい日もあり、あまり残業が多いと続けられるか不安です。 以前、アルバイトで夜遅くまで働くことが多く、体調を崩した経験があるので、同じ状況になるのは避けたいと思っています。 |
《解説》
条件面や不安要素を前面に出す質問は、意欲不足や自己都合と受け取られやすいです。企業に配慮した言い回しに変え、「働き方を理解したい」という前向きな意図を強調すると良いでしょう。
面接官が答えられない専門的すぎる質問
専門的すぎる質問は、面接の場で相手を困らせる可能性が高く、避けるべきです。
特に就活生の場合、自分の知識や関心をアピールしようとするあまり、業界の細部や高度な技術内容に踏み込みすぎることがあります。
ここでは、一般的な大学生がやってしまいがちな失敗例をもとに、避けたほうがよい質問例を紹介します。
《例文》
| 御社の製品で採用されている〇〇技術について、具体的なアルゴリズムや数値モデルはどのようになっていますか。 また、開発工程で使用されるツールやプログラミング言語のバージョン管理の方針も教えていただけますか。 |
《解説》
この例では、面接官でも即答できない専門的な内容を尋ねてしまっています。質問は企業の公式情報や公開資料で調べられる範囲にとどめ、相手が答えやすく会話が広がる内容にしましょう。
責任回避を感じさせる質問
面接では、応募者が自分の責任を避けるような質問をしてしまうと、評価が下がることがあります。
特に「自分に有利な条件や環境だけを求める質問」は、採用担当者にネガティブな印象を与えやすいです。ここでは、責任回避と受け取られかねない質問例を紹介します。
《例文》
| もし配属された部署で自分の希望と違う仕事内容だった場合、他の部署にすぐ異動することは可能でしょうか。 大学時代もアルバイトで希望シフトが通らないときは、すぐに別の店舗に移って働いていました。 自分の力を最大限発揮できる環境で働きたいので、配属が合わない場合の対応について事前に知っておきたいです。 |
《解説》
この質問は、自分に合わない環境では努力を続けない印象を与える恐れがあります。
エピソードを話す場合も「逃げる姿勢」ではなく「改善や適応の努力」を伝える内容にすると、面接官に前向きな印象を残せます。
面接の逆質問が思いつかないときの対処法

面接で「最後に質問はありますか?」と聞かれたとき、質問が浮かばずに戸惑うことがあります。この場合でも、事前準備や会話の流れをうまく使えば、印象を下げずに対応できます。
ここでは具体的な方法を紹介します。
- 企業研究で見つけた疑問を活用する
- 面接中の説明内容から質問を作る
- 業界ニュースや最新動向を参考にする
- 面接官の回答から関連質問を派生させる
- 自己アピールにつながる切り口で質問する
- 共感や興味を示す質問に置き換える
①企業研究で見つけた疑問を活用する
逆質問が浮かばないときは、事前の企業研究で得た情報から疑問を作るのが有効です。新規事業や社内制度、研修内容などに関する質問は、入社意欲や準備度を示せます。
公式サイトや採用ページ、IR情報などを確認し、他社との差や特徴的な取り組みを整理しておきましょう。
面接では「御社の〇〇制度について伺いたいのですが」と具体的に話すと調査の深さが伝わります。この方法は事前準備が必要ですが、その分だけ前向きな印象を与えやすいです。
企業も自社への関心の高さを感じやすく、評価につながる可能性が高まります。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
②面接中の説明内容から質問を作る
面接中に説明された内容をもとに、その場で質問を組み立てる方法です。話をよく聞く姿勢を示せるため、傾聴力や柔軟性を評価されやすくなります。
例えば、仕事内容や業務の進め方が出た場合、「先ほどお話にあった〇〇の業務で特に大切にしていることは何でしょうか」と尋ねると自然です。台本的にならず、会話の流れに沿ったやり取りができます。
聞き逃しを防ぐために、メモを取りながら臨むとさらに効果的です。その場での思考力や対応力も示せます。
③業界ニュースや最新動向を参考にする
業界の最新ニュースや動向を踏まえた質問は、興味や勉強意欲を示す手段になります。例えばIT業界なら生成AI、食品業界なら健康志向商品の開発など、話題性のあるテーマを選びましょう。
「最近の〇〇の動きについて、御社ではどのように取り組んでいますか」と聞くと印象的です。事前に業界誌やニュースサイト、公式SNSなどで情報収集しておくことが重要です。
この方法は知識の豊富さを伝えられるだけでなく、入社後の情報感度の高さも期待させられます。
④面接官の回答から関連質問を派生させる
面接官の回答を受けて、さらに掘り下げる質問をすることで会話が自然に広がります。
例えば「研修制度が充実している」という答えを受け、「研修後のフォロー体制はどのようになっていますか」と尋ねると積極性が伝わります。
準備がなくても会話に集中すれば使える方法で、臨機応変な対応力を示せます。ただし、表面的な繰り返しではなく、相手の話を理解したうえで深掘りすることが大切です。
質問が会話の延長線上にあるため、不自然さがありません。
⑤自己アピールにつながる切り口で質問する
逆質問を自己アピールにつなげる方法です。
例えば、学生時代にチームでの活動経験が豊富なら、「御社のチームワークに関する評価制度について教えていただけますか」と質問し、その後に自分の経験を関連付けて話せます。
これにより、自分の強みを自然に提示できます。事前に自分のアピールポイントと企業の特徴を照らし合わせて、関連する質問を複数用意しておくと安心です。
押し付け感がなく、自然な会話の中でアピールできます。
⑥共感や興味を示す質問に置き換える
どうしても質問が浮かばない場合は、相手の話や企業の取り組みに共感を示しながら質問に変える方法があります。例えば「御社の〇〇の取り組みにとても共感しました。
今後さらに広げていく計画はありますか」といった形です。これは質問というより感想に近く、自然な雰囲気で面接を終えられます。相手が話しやすくなるため、和やかな終盤にできるのも利点です。
事前準備が十分でないときや、面接中に話題が出た場合にも使える万能な方法です。
「最後に質問はありますか?」に関するよくある質問

面接の最後に聞かれる「最後に質問はありますか?」という問いは、就活生にとって悩ましい場面です。
質問の有無や内容は、志望度や理解度を示す重要な要素であり、答え方次第で評価が変わるでしょう。ここでは、逆質問にまつわるよくある疑問と考え方を整理します。
- 逆質問はいくつ用意すべきか
- 逆質問をしない場合の印象はどうなるか
- 待遇や給与に関する質問はしてもよいか
- 最終面接で逆質問の内容は変えるべきか
- 逆質問が被った場合の対応方法
- 逆質問を面接の流れで自然に行う方法
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①逆質問はいくつ用意すべきか
逆質問は、最低でも2〜3個は準備しておくことが望ましいです。理由は、面接中に説明された内容と重なってしまう可能性があるためです。
例えば、1つしか用意していない場合、その質問が既に説明されていれば沈黙することになります。複数の質問を用意しておけば、面接官の話や流れに合わせて適切な内容を選べるでしょう。
必ずしも全てを使う必要はありませんが、臨機応変に取り出せる状態にしておくことで柔軟さと意欲を示せます。
②逆質問をしない場合の印象はどうなるか
逆質問をしないと、「興味が薄い」「準備不足」と見られる可能性があります。特に志望度や入社意欲を確認する場面で質問がないと、熱意が伝わりにくくなるでしょう。
もちろん面接中の説明で疑問が解消される場合もありますが、その際は「本日は説明が非常に分かりやすく、現時点で疑問はありません。
入社後に取り組むべきことが明確になりました」と感謝と意欲を伝えることが大切です。質問しない場合でも、印象を損なわない工夫が必要です。
③待遇や給与に関する質問はしてもよいか
待遇や給与は重要な条件ですが、一次面接や企業理解が浅い段階では避ける方が無難です。
条件面を先に聞くと「待遇重視」と受け取られ、志望動機や適性よりも条件だけで判断していると誤解されかねません。
確認が必要な場合は、最終面接や内定後の面談など適切な時期を選ぶのが望ましいです。聞く場合も「自己成長や働き方と関係する文脈」で質問すると、前向きな印象を与えやすくなります。
④最終面接で逆質問の内容は変えるべきか
最終面接では、これまでの選考で得た情報を踏まえた深い質問が効果的です。
初期段階では仕事内容や社風に関する質問が多くなりますが、最終面接では経営方針や事業戦略、配属後の業務方針など中長期的な視点を持つ質問が望ましいでしょう。
これにより、入社後の活躍を見据えた本気度を伝えられます。質問の質を変えることで、理解度と成長意欲を同時に示せます。
⑤逆質問が被った場合の対応方法
他の応募者や面接中の先行質問者と内容が被ることは珍しくありません。その場合は「先ほどのお話を踏まえると」という形で自分なりの視点を加えて深掘りするのが効果的です。
同じテーマでも「具体的には〜」や「志望部署の場合はどうなりますか?」と切り口を変えることで独自性を出せます。重複を恐れるより、その場で柔軟にアレンジする姿勢の方が評価されやすいです。
⑥逆質問を面接の流れで自然に行う方法
自然に逆質問を行うには、面接中に気になった点をメモし、興味を持った部分を引き出す形が有効です。
「先ほどのお話に関連して伺いたいのですが」という言い回しを使えば、会話の延長としてスムーズに質問できます。
事前に用意した質問と、その場で生まれた質問を組み合わせることで、臨機応変さと積極性を同時にアピールできるでしょう。結果として会話の流れを止めずに自然なやり取りが可能になります。
面接で「最後に質問はありますか?」への効果的な対応方法

面接での逆質問は、志望度や入社意欲を示す重要な機会です。特に企業や業界に関する理解、自己アピールに直結する質問、そして社風との相性を確かめる切り口は高評価につながります。
そのためには、事前の企業研究や疑問点の整理、質問内容の優先順位付けが欠かせません。また、言葉遣いや礼儀、質問の背景説明など、伝え方にも配慮することが大切です。
さらに、経営方針や業界動向に基づいた質問を盛り込み、差別化を図ることで印象を強められます。一方で、待遇面や調べればわかる質問などは避けるべきです。
事前準備と柔軟な対応力を兼ね備えることで、「最後に質問はありますか?」という問いを自己PRの場に変えられるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













