公務員がクビになる時代到来?免職の種類・事例・予防策まとめ
「公務員は一度なれば一生安泰」と思っていませんか?
実は近年、人事評価制度や不祥事対応の厳格化により、公務員でもクビになるケースが増えています。公務員でも、業務の質や環境を改善していく姿勢が求められるようになっているのです。
本記事では、公務員の免職に関する3つの種類や具体的な事例、そして職を守るための予防策まで詳しく解説します。
公務員という職と安定を守るために必要な知識を、ぜひ押さえておきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員もクビになる?その現実と誤解

「公務員は安定していて、一度なれば定年まで安心」というイメージを持つ人が多いでしょう。ですが、実際には法律や制度に基づいて一定の条件を満たすと免職、つまりクビになる可能性があります。
加えて近年は労働基準の厳格化により、さらにその可能性が高まっています。また、能力不足や心身の不調によって職を失う場合も考えられるのです。
たしかに公務員は「身分保障」という制度である程度守られ、民間企業と比べれば解雇は稀ですが、決してゼロではありません。
懲戒免職や分限免職は法律で定められた正式な手続きで行われ、重大な不祥事や長期的な成績不良などが対象になります。
公務員だから安泰と思い込まず、その現実を知っておくことで、仕事の姿勢や健康管理、スキル磨きに自然と力が入り、クビになるリスクを減らせるでしょう。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
公務員のクビは主に3種類

公務員がクビになる場合、その形態は大きく3つに分けられます。懲戒免職・分限免職・人事評価による免職です。それぞれの特徴や適用条件を知っておくことで、就活時の不安を減らせるでしょう。
ここでは、懲戒・分限・人事それぞれの免職の概要と、その対象となるケースを整理します。
- 懲戒免職
- 分限免職
- 人事評価による免職
① 懲戒免職
懲戒免職は、公務員にとって最も重い処分で、重大な規律違反や不祥事があったときに適用されます。汚職や横領、飲酒運転など、社会的に影響の大きい行為がこれにあたります。
この処分を受けると即日失職となり、退職金が支給されない場合も少なくありません。さらに、多くのケースで公務員としての再就職は不可能になります。
こうした厳しい措置は、公務への信頼を守るための仕組みです。就活の段階から法令や規則を守る姿勢をしっかり持つことが、長く働くための第一歩といえるでしょう。
② 分限免職
分限免職は、能力不足や心身の不調などで職務を続けられない場合に適用されます。業務に必要なスキルを著しく欠いている、長期の病気で回復の見込みがないといったケースです。
懲戒免職とは異なり、不祥事ではなく適性や健康状態に関わる理由が中心です。これを避けるには、日ごろからスキル向上を意識し、心身の健康を保つ努力が欠かせません。
体調の変化には早めに対応することで、職務継続の可能性を広げられるでしょう。
③ 人事評価による免職
人事評価による免職は、評価制度で勤務成績が長期間改善しないときに行われます。民間企業より頻度は低いものの、働きぶりが基準を下回り続ければ対象になることがあります。
この制度は、組織全体のパフォーマンス維持を目的として導入されています。回避するには、与えられた業務を着実にこなし、改善点を指摘された場合はすぐに対応することが大切です。
上司とのやり取りを欠かさず、評価のポイントを把握して行動してください。
懲戒免職とは|公務員がクビになる最も重い処分
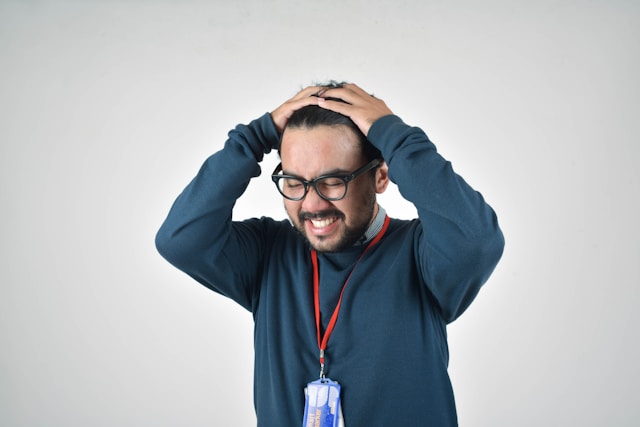
懲戒免職は、公務員の免職の中で最も重い処分です。重大な不祥事や規律違反を行った場合に適用され、職を失うだけでなく、その後の生活にも大きな影響を与えます。
ここでは、懲戒免職の内容や条件、手続き、事例を順に解説します。
- 懲戒免職の内容と適用される条件
- 懲戒免職の手続きと判断基準
- 懲戒免職に至る具体的な事例
① 懲戒免職の内容と適用される条件
懲戒免職は、公務員に科される懲戒処分の中で最も重く、適用されると即時に職を失います。退職金が支給されないことも多く、その後の再就職にも大きな制限がかかります。
対象となるのは、汚職や横領、飲酒運転、ハラスメントなど社会的信頼を著しく損なう行為です。こうした行為は、公務員の立場や職務の信頼性を根底から揺るがすため、厳しい処分が科されます。
就活の段階から、法律や規則を守るだけでなく、日常の行動や発言にも注意を払う意識が必要でしょう。
② 懲戒免職の手続きと判断基準
懲戒免職は、事実確認や事情聴取、証拠の収集などを経て行われます。判断では、行為の重大性や影響範囲、再発の可能性などが総合的に考慮されます。
たとえば不正行為であれば、被害額や関係者の数、社会的な反響の大きさも評価の対象です。この手続きは法律で定められており、適正な進め方が保障されます。
ただし、弁明が不十分な場合は誤解や不利な判断につながるおそれがあります。日頃から記録や証拠を残す習慣を持つことが、自分を守る備えになります。
③ 懲戒免職に至る具体的な事例
懲戒免職の事例には、横領や詐欺、わいせつ行為、重大な交通違反などがあります。
例えば、庁舎内での金銭横領や業務情報の不正利用による詐欺事件、飲酒運転による重大事故は、ほぼ例外なく懲戒免職となります。
こうした事例はニュースや行政の発表で公表され、社会的信用を一気に失います。就活生にとって無関係に思えるかもしれませんが、小さな規律違反の積み重ねが重大な処分につながることもあります。
公務員を目指すなら、社会人としての基本的な倫理観を身につけてください。
分限免職とは|能力不足や心身の不調による公務員のクビ
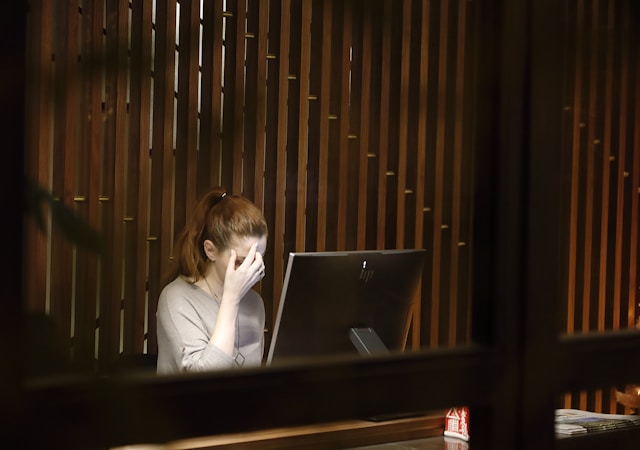
分限免職は、公務員が職務を続けられなくなった場合に適用される制度です。懲戒免職のように不祥事が原因ではなく、能力や健康状態が主な理由になります。
ここでは、分限免職の内容や条件、手続き、実際の事例を順に解説します。
- 分限免職の内容と適用される条件
- 分限免職の手続きと判断基準
- 分限免職に至る具体的な事例
① 分限免職の内容と適用される条件
分限免職は、公務員が業務を遂行できない状態が続く場合に行われます。代表的な理由は、職務遂行能力の著しい不足や長期の心身不調です。
たとえば、必要な技能や知識を身につけられず改善が見込めない場合や、病気やけがで長期間休職し回復が難しい場合が該当します。
懲戒免職とは異なり、不正や規律違反は含まれませんが、組織運営に支障をきたすため免職が必要になるのです。
こうした事態を避けるには、日々スキルを磨く努力と健康管理を怠らないことが大切でしょう。
② 分限免職の手続きと判断基準
分限免職は突然行われるのではなく、一定の手続きを踏んで決定されます。まず所属部署や人事部門が状況を確認し、改善のための指導や研修、医療的な支援を実施します。
それでも改善が見られない場合に、分限免職の検討が始まります。判断基準は、職務遂行能力の回復見込みや業務への影響度、職場の安全確保などです。
手続きには本人への説明や意見聴取も含まれ、公正さが求められます。ただし、指導を軽視すれば免職が現実味を帯びるため、早めの対応が欠かせません。
③ 分限免職に至る具体的な事例
分限免職の事例には、長期のうつ病による勤務困難、重大な事故による身体機能の喪失、専門知識不足で業務遂行ができないケースなどがあります。
例えば、心身の不調で休職を繰り返し、復職後も職務を全うできない場合は分限免職になることがあります。また、新しい業務システムに対応できず必要なスキル習得が不可能と判断された場合も該当します。
これらは本人にも組織にも望ましい結果ではありません。だからこそ、日頃から健康を維持し、学び続ける姿勢が将来の安定につながるのです。
人事評価による公務員のクビの可能性

公務員は安定しているイメージがありますが、人事評価の結果によって免職になる場合もあります。頻度は高くありませんが、人事評価制度の仕組みや基準を理解しておくことは重要です。
ここでは人事評価制度の概要と、クビに直結するケースを解説します。
- 人事評価制度の概要
- 人事評価がクビに直結するケース
① 人事評価制度の概要
公務員の人事評価制度は、勤務成績や能力、行動特性などを客観的に把握し、昇進や昇給、人事異動、研修計画などに反映する仕組みです。
評価は上司による業務の観察や面談を通じて行われ、年度ごとに記録されます。評価項目には業務の正確さや効率、協調性、責任感などが含まれます。
多くの場合は能力向上や配置見直しに活用されますが、成績が著しく低く改善も見られない場合は免職の判断材料になることもあります。
評価は単なる採点ではなく、日々の姿勢や成果が反映されるため、継続的な努力と改善意識が必要でしょう。
② 人事評価がクビに直結するケース
人事評価が免職につながるのは、成績が長期間最低水準にとどまり、改善の見込みがないと判断された場合です。
例えば、業務の質や量が著しく基準を下回り続ける、改善指導を受けても行動が変わらない、勤務態度に問題があるなどが該当します。
また、職務怠慢や報告・連絡・相談の欠如が続けば、組織運営に支障をきたし評価もさらに悪化します。こうした状態が複数年続くと、分限免職の理由として正式に扱われることがあります。
改善には、上司からの指摘を真摯に受け止め、業務の優先順位を見直すなど、日々の行動を変える努力が欠かせません。
公務員がクビになる主な事例

公務員は民間企業に比べて解雇される可能性が低いですが、特定の行為や状態が続くと免職になることがあります。自分には関係ないと思っていても、日常の積み重ねがクビにつながる場合があるのです。
ここでは公務員がクビになる代表的な5つのケースを挙げ、それぞれの特徴や背景を解説します。
- 不祥事(ハラスメント・金銭不正等)による公務員クビの事例
- 犯罪行為(収賄・窃盗・飲酒運転等)による公務員クビの事例
- 無断欠勤・職務放棄による公務員クビの事例
- 勤務成績不良・能力不足による公務員クビの事例
- 心身の故障・長期休職による公務員クビの事例
① 不祥事(ハラスメント・金銭不正等)による公務員クビの事例
職場でのハラスメントや金銭の不正使用は、公務員としての信用を著しく損ないます。例えば部下へのパワハラ、同僚へのセクハラ、経費の不正請求などが該当します。
これらは懲戒免職になることが多く、再就職も極めて難しくなります。小さな不正でも繰り返せば重大な処分につながるため、日常の行動や言動には常に配慮してください。
信頼の失墜は一瞬ですが、回復には長い時間がかかります。
② 犯罪行為(収賄・窃盗・飲酒運転等)による公務員クビの事例
収賄や窃盗、飲酒運転による重大事故など、刑事罰に問われる行為は即座に懲戒免職となる可能性が高いです。特に飲酒運転は社会的非難が強く、刑事処分と同時に職を失う事例も珍しくありません。
公務員は職務外の行動でも社会的責任を問われるため、私生活においても慎重な判断が必要です。軽率な行動が職を奪う結果になることを忘れてはいけません。
③ 無断欠勤・職務放棄による公務員クビの事例
正当な理由なく長期間欠勤を続けたり、職務を放棄したりすると、分限免職や懲戒免職の対象となります。数日の無断欠勤でも繰り返せば悪質と判断され、厳しい処分に至る場合があります。
欠勤の必要がある場合は、必ず上司や人事部門に連絡し、事情を説明してください。黙って職務を放棄することは、自らクビを招く行為です。
④ 勤務成績不良・能力不足による公務員クビの事例
業務の質や量が基準を大きく下回り、改善の見込みがない場合は分限免職になることがあります。例えば指導や研修を受けても業務の改善が見られない、与えられた仕事を期限内に終えられないケースです。
評価は一時的なミスではなく、長期的な傾向をもとに判断されます。改善するには、指摘された点を真摯に受け止め、具体的な行動に移してください。
⑤ 心身の故障・長期休職による公務員クビの事例
長期の病気やけが、精神的な不調により職務が困難な場合も分限免職の対象です。休職と復職を繰り返し、業務に復帰できる見込みが立たない場合は、やむを得ず免職となります。
心身の健康は日々の業務の土台です。定期的な健康診断や早めの医療相談、生活習慣の見直しが、職を守るための大切な予防策になります。
公務員がクビにならないための心がけ

公務員は民間企業に比べると免職の可能性は低いものの、決してゼロではありません。日々の行動や意識次第で信頼を守ることで、安定した土台を築くことができるのです。
ここでは、公務員職を失わないために意識したい5つのポイントを紹介します。
- 法律や規則を遵守する
- 職務責任を果たす
- 公務員としての信用を維持する
- 心身の健康を維持する
- 公私の線引きを守る
① 法律や規則を遵守する
公務員は法令や内部規則を守る義務があり、違反は懲戒処分や免職につながります。小さな違反でも繰り返せば信用失墜となりかねません。
業務だけでなく私生活でも交通規則や情報管理のルールを徹底してください。常に規範を意識することで、不注意による過ちも防げるでしょう。
② 職務責任を果たす
与えられた業務を期限内に正確に行うことは、公務員としての基本です。責任を果たさない状態が続くと勤務成績不良と判断され、分限免職に至る場合もあります。
業務の優先順位を整理し、必要なら上司や同僚に相談してください。小さな遅れやミスも放置せず、早めに修正する姿勢が信頼を高めます。
③ 公務員としての信用を維持する
信用は一度失うと回復が難しいものです。職務中の態度や言葉遣いはもちろん、SNSでの発言や交友関係も評価の対象となります。
公務員は公私を問わず公的な立場で見られるため、不用意な行動は避けてください。自分の行動が周囲にどう映るかを意識しましょう。
④ 心身の健康を維持する
長期間の病気やメンタル不調は職務遂行に支障をきたします。休職や復職を繰り返す状態が続けば、分限免職の対象になる可能性もあります。
健康診断の結果を放置せず、必要に応じて医療機関を受診してください。十分な睡眠や適度な運動、バランスの良い食事を心がけ、安定した体調を保ちましょう。
⑤ 公私の線引きを守る
私生活と職務の区別を明確にすることは、信用維持のために欠かせません。勤務中の私用電話や私的なSNS投稿は評価を下げる要因になります。
職務で得た情報を私的に利用することも重大な規律違反です。時間と行動の区別を意識し、公私混同を避けることが大切です。
公務員の職を守るために大切なこと

公務員は安定した職業と思われがちですが、懲戒免職や分限免職、人事評価の結果によってクビになる可能性はあります。
実際には、不祥事や犯罪行為、長期の職務放棄や健康上の問題など、具体的な事例も存在します。これらは法律や規則に反する行為や職務遂行に重大な支障がある場合に適用されます。
反対に、日頃から法令遵守や責任ある行動を心がけ、信用と健康を維持することで、そのリスクは大きく減らせます。
公私のけじめを守り、信頼される行動を積み重ねることが、公務員としての安定したキャリアを築く鍵となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










