公務員試験の集団討論を完全攻略|流れと対策法を徹底解説
公務員試験の集団討論って、何を準備すればいいのか全然わからない…といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、討論の基本的な流れから、評価されるポイント、頻出テーマ、具体的な対策・練習方法まで、初めての方でもわかりやすく徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員試験の集団討論は対策をしっかりしよう

公務員試験における集団討論は、知識だけでなく協調性や論理的思考力、発言のタイミングといった実践的な力も問われます。
準備をせずに本番に臨むと、自分の意見をうまく伝えられなかったり、議論に埋もれてしまうおそれもあるでしょう。
特に注意したいのは、集団討論では「勝つこと」ではなく「協力して建設的な結論を出すこと」が求められている点です。発言内容だけでなく、グループとの関わり方や話の聞き方も評価の対象になります。
さらに、実際に話す練習を積むことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。相手の話をよく聞き、論理的に自分の意見を伝える力を少しずつ磨いていきましょう。
公務員試験の集団討論とは?

公務員試験における「集団討論」は、複数人でテーマについて議論し、結論を導く形式の選考ステップです。
筆記や個別面接では測りきれない、協調性や論理的思考力、コミュニケーション力などが試されます。
集団討論とは、5~8人ほどの受験者が制限時間内に与えられたテーマについて議論し、グループとして意見をまとめる試験です。
試験官は議論には加わらず、発言内容や姿勢、聞く態度などを客観的に観察しています。ここで重要なのは、「正解」を出すことではなく、集団の中でどう貢献できるかという姿勢です。
集団討論に慣れていない場合でも、基本的な流れや評価ポイントを理解しておけば、冷静に対応できます。しっかりと準備をして臨めば、自信を持ってアピールできるでしょう。
公務員試験の集団討論で評価されるポイント

公務員試験における集団討論では、知識の正確さだけでなく、協調性やリーダーシップ、発言の仕方など、複数の観点から総合的に評価されるのです。
ここでは、特にチェックされやすい5つのポイントについて、それぞれの評価基準や注意点を分かりやすく解説します。
- リーダーシップを発揮して議論をまとめられるか
- 協調性を持ってメンバーと円滑に関われるか
- 発言や提案など討論への貢献度は高いか
- 論理的な思考で一貫性のある発言ができているか
- 人柄や態度が評価基準に適しているか
①リーダーシップを発揮して議論をまとめられるか
集団討論では、目立つだけではなく、場をうまくコントロールする力が見られます。
リーダー役になった場合、メンバーの意見を引き出し、議論の方向性を整理する姿勢が求められるのです。
自分の意見ばかりを押し通すのではなく、「一度論点を整理しましょう」や「○○さんの考えも聞いてみたいです」といった発言が評価されやすい傾向にあります。
全体のバランスを意識し、メンバー全員が発言しやすい雰囲気を作ることが、リーダーとして重要な役割といえるでしょう。
②協調性を持ってメンバーと円滑に関われるか
集団討論では、自分の意見を持つこと以上に、他の参加者とどのように関わるかが重要視されます。公務員はチームで業務を進める機会が多いため、柔軟に対応できる姿勢が必要です。
異なる意見が出たとき、「それも一理ありますね」と受け止めつつ、自分の考えを続けて述べるようにすると、協調性のある印象を与えられます。強く否定したり、無視したりするような態度は避けましょう。
討論では時間が限られているため、焦って発言を急いでしまうこともありますが、落ち着いて周囲の話を聞きながら進めていく姿勢が評価されます。
他者と共により良い結論を導こうとする態度が、結果的に高評価につながるはずです。
③発言や提案など討論への貢献度は高いか
討論の場では、積極的な参加が基本です。ただ座っているだけでは、評価されることはありません。自分の役割を理解し、チームの中でどう貢献できるかを考えることが重要です。
発言が貢献というわけではなく、議論の流れを整理したり、他人の意見をまとめる役割も高く評価されます。「今の話をまとめるとこうなりますね」といった発言は、討論全体を前に進める力になるのです。
また、発言のタイミングや雰囲気も大切です。誰かが話している最中に割り込むのではなく、相手の話が終わった後に意見を伝えると、丁寧な印象になります。
聞く姿勢と話すタイミングを意識して行動してください。
④論理的な思考で一貫性のある発言ができているか
発言の内容が一貫していて論理的であるかどうかも、評価のポイントです。たとえ独自の視点でも、話に筋が通っていなければ説得力はありません。
意見を述べるときは、「理由→具体例→結論」の順で話すと、相手にも理解されやすくなります。これはPREP法にも通じる基本的な話し方です。
反対意見を述べるときも、感情ではなく事実に基づいて冷静に話すと、印象がよくなります。本番で焦らないためにも、日頃から論理的に話す練習を積んでおくとよいでしょう。
一貫性のある発言ができるようになると、思考力の高さを自然と伝えられます。
⑤人柄や態度が評価基準に適しているか
集団討論では、発言内容と同じくらい、態度や人柄も見られています。市民と接する機会が多い公務員にとって、信頼される人間性は欠かせない要素です。
まずは見た目の印象が大切。姿勢を正し、相手の話にうなずいたり、目を合わせたりすることで、前向きな姿勢が伝わります。腕を組む、視線をそらすといった行動は、控えたほうがよいでしょう。
最終的には、「この人と一緒に働きたいかどうか」が評価の基準になります。知識や技術だけではなく、人柄のよさが合否を左右する場面もあるため、普段から好印象を意識しておくと安心です。
公務員試験の集団討論の流れ

公務員の集団討論は、ただ話すだけではなく、一定の流れとルールに沿って進行されます。基本を押さえておくことで、本番でも落ち着いて対応しやすくなるのです。
ここでは当日の進行手順を順を追って解説していきます。
- 試験当日のテーマを発表される
- 個人で意見をまとめる
- 司会・書記・タイムキーパーなどの役割を決める
- 順番に自分の意見を発表する
- メンバー同士で活発に討論をおこなう
- グループとしての結論を協力して導き出す
①試験当日のテーマを発表される
討論の冒頭では、試験官からその場でテーマが発表されます。事前に知らされることはほとんどなく、初めて目にする内容に即座に対応できるかが問われます。
テーマは時事問題や社会性のある話題が多く、「少子化対策」や「在宅勤務の是非」などがよく見られます。
ここで求められるのは、正解を出すことではなく、限られた時間内に自分の考えを整理し、論理的に説明できる力です。
焦らずテーマの意図を把握し、自分なりの切り口を考えてみてください。日ごろから新聞やニュースに触れておくと、初見のテーマでも慌てずに対応できるでしょう。
②個人で意見をまとめる
テーマが提示されたあとは、5〜10分ほどの個人思考の時間が設けられます。この時間に、自分の立場や根拠、論点を簡潔にメモにまとめることが重要です。
考えを深めるには、「なぜそう思うのか」を自問自答しながら構成しましょう。賛成・反対の立場だけでなく、反論への対応や具体例まで整理しておくと安心です。
この準備が討論全体の発言に直結するため、気を抜かずに取り組んでください。
③司会・書記・タイムキーパーなどの役割を決める
各自の意見がまとまった段階で、グループ内の役割分担を決めましょう。主な役割には、全体の進行を担う司会、議論内容を記録する書記、時間配分を管理するタイムキーパーなどがあります。
特に司会は、議論の方向性を整理し、全員が発言できるよう配慮する立場です。自信がある場合は、積極的に立候補することでリーダーシップをアピールできるでしょう。
一方で、自分が得意とする役割に徹するのも一つの戦略です。無理せず、自分の強みが生かせるポジションを選んでください。
④順番に自分の意見を発表する
役割が決まったあとは、各自が順番に意見を発表します。ここでは、立場と理由を簡潔に伝えることが求められるでしょう。
話が長くなりすぎないように注意しながら、要点を押さえて話しましょう。すでに出た意見と同じ立場でも、自分ならではの視点や具体的な体験を加えると差別化につながります。
他のメンバーの話をよく聞きながら、自分の考えをどう展開するかも意識しておくとよいでしょう。
⑤メンバー同士で活発に討論をおこなう
一通りの意見が出そろったら、意見をもとに自由な討論が始まります。質問や補足、反論を通じて議論を深めていくフェーズです。
大切なのは、他人の意見を受け入れながら、自分の考えもしっかり伝える姿勢です。否定から入るのではなく、「なるほど、ただ私は~」のように、柔らかい切り返しを意識しましょう。
また、話し合いのバランスを意識して発言回数を調整することも、チーム全体の印象を良くするポイントです。
⑥グループとしての結論を協力して導き出す
討論の最後には、グループとしての結論を出します。全員が納得できる内容にまとめることで、チームワークや合意形成力が評価されるのです。
結論は誰か1人の意見に偏らず、多角的な視点を取り入れて調整するとよいでしょう。
時間内にまとめられないと評価に影響する可能性があるため、タイムキーパーの指示を意識しつつ、効率的に進めてください。
最後まで全員で協力する姿勢を忘れず、納得感のある結論で締めくくることが大切です。
公務員試験の集団討論のポイント

公務員試験の集団討論では、意見を出すだけではなく、周囲との関わり方や議論の進め方も評価対象となります。
チームで進める討論だからこそ、個人の発言力に加え、全体の流れを意識した行動が求められるでしょう。ここでは、集団討論で特に意識すべき5つのポイントについて解説します。
- 発言時間をコントロールして議論を円滑に進める
- 伝えたい意見を的確に表現する力を意識する
- 相手に安心感を与えるコミュニケーションを意識する
- 相手の意見を受け入れつつ自分の立場も示す
- 議論がずれたら自然に話題を修正する
①発言時間をコントロールして議論を円滑に進める
集団討論では、時間配分を意識した発言が重要です。話しすぎると他の人が発言できなくなり、発言が短すぎると消極的に見られてしまいます。適切な時間で簡潔に意見を伝える力が求められます。
目安として、1回の発言は30秒から1分程度が適切です。伝えたい内容を事前に整理し、結論を先に述べることで、効率よく伝えられます。
話の途中で要点がずれると、聞き手に伝わりづらくなるため注意が必要。また、自分の番を待ち、他の人の発言を遮らない姿勢も評価されます。
こうした配慮は、自分だけでなくグループ全体の印象を良くし、全体の進行にも貢献できるでしょう。
②伝えたい意見を的確に表現する力を意識する
討論では、自分の考えをわかりやすく伝えることが評価の鍵になります。曖昧な表現や話の順序が整理されていないと、せっかくの意見も伝わりにくくなってしまうでしょう。
効果的に伝えるには、PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を使うと構成が明確になります。また、誰でも理解しやすい言葉を使い、専門用語や回りくどい言い回しは避けたほうがよいでしょう。
言葉づかいも印象を左右します。丁寧で落ち着いた話し方を心がけることで、信頼感を与えやすくなります。的確な表現は、自分の意見を強く印象づけるためにも効果的です。
③相手に安心感を与えるコミュニケーションを意識する
集団討論では、相手との信頼関係を築くようなコミュニケーションが評価されます。安心感を与える話し方や反応ができる人は、協調性や柔軟性のある人材と見なされやすいでしょう。
安心感を与えるためには、まず相手の話を真剣に聞いている姿勢が欠かせません。うなずきや相づち、目を見て話すといった非言語の工夫も有効です。
また、発言時には落ち着いたトーンを意識し、感情的にならずに話すことを意識しましょう。
このような対応は、評価者に対しても好印象を与えます。安心感のあるやり取りは、信頼される公務員像につながる要素です。
④相手の意見を受け入れつつ自分の立場も示す
討論の中で意見が食い違う場面は避けられません。そんなとき、相手を否定するのではなく、自分の立場を丁寧に示す力が問われます。
まず相手の意見を受け入れる姿勢が重要です。「その考え方も理解できます」と一度認めたうえで、「ただ、私は別の視点からこう考えます」と述べると、対立せずに意見を主張できます。
このように相手の話を尊重しながらも、自分の意見をはっきりと伝えることで、協調性と論理的思考の両面が伝わります。
対話力が求められる公務員試験においては、こうした姿勢が非常に重視されます。
⑤議論がずれたら自然に話題を修正する
討論中に話が本題からずれてしまうことはよくあります。そんなとき、さりげなく話題を元に戻せるかどうかも、評価ポイントです。
話題を修正するには、「少し話が広がってきたので、もう一度テーマに戻しましょう」といった柔らかい言い回しを使いましょう。
また、修正のタイミングにも注意が必要です。議論の流れをよく観察し、適切なタイミングで声をかけましょう。
全体の流れを自然に整えることができれば、ファシリテーション能力が高いと判断されやすくなります。
話題修正は、リーダー役でなくても意識しておきたい行動のひとつです。
公務員試験の集団討論での注意点

公務員の集団討論では、発言の内容や議論の進め方だけでなく、態度や言葉遣いなど細かな部分も評価の対象になります。
見落とされがちなポイントに事前に気づいておくことで、全体の印象を良くしやすくなるでしょう。ここでは、討論中に特に気をつけたい点をわかりやすく解説します。
- 相手の意見を真っ向から否定しない
- 発言がかぶらないように順番やタイミングを意識する
- 役割に偏りが出ないようにメンバー全体を見渡す
- 討論中の態度や言葉遣いにも注意を払う
①相手の意見を真っ向から否定しない
討論では、意見が分かれることも自然なことですが、相手を否定する言い方には注意が必要です。たとえば「それは間違っています」といった表現は、冷たい印象を与えてしまう可能性があります。
代わりに「その考え方も理解できますが、私はこう考えています」といった言い回しにすることで、協調性や柔軟さを示すことができるでしょう。
相手の意見を一度受け止める姿勢が、円滑な議論につながります。正しいことを主張するだけではなく、どう伝えるかが評価の分かれ目になると心得ておいてください。
②発言がかぶらないように順番やタイミングを意識する
発言のタイミングを誤ると、ほかの参加者と話が重なってしまい、議論の流れを妨げてしまうおそれがあります。焦って発言するのではなく、相手の話が終わるのを待ってから話し始めるようにしましょう。
自分の番を取りに行くときは、軽くうなずく、手を少し挙げるなど、周囲に意思を示す工夫をしてみてください。会話の流れを読みながら発言することで、落ち着きのある印象も与えられます。
こうした配慮ができるかどうかも、社会人としての資質を測る材料になっていると意識することが大切です。
③役割に偏りが出ないようにメンバー全体を見渡す
討論の場では、司会や書記といった役割を1人に任せきりにするのではなく、全員が適度に関わることが望まれます。特定の人に負担が集中してしまうと、グループとしてのバランスが崩れやすくなるからです。
たとえば、発言の少ない人に「○○さんはどう思いますか」と声をかけたり、司会役をサポートするように話題を整理したりするなど、周囲への配慮が必要です。
自分の発言だけに集中するのではなく、グループ全体の動きを見ながら進めていくことが、評価されるポイントになっていきます。
④討論中の態度や言葉遣いにも注意を払う
どれだけ内容がしっかりしていても、態度や言葉遣いが悪ければ評価が下がってしまいます。
目を合わせない、腕を組む、無表情で話すといった態度は、無意識のうちに相手に冷たい印象を与えてしまう場合があるでしょう。
また、言葉づかいも丁寧すぎずくだけすぎず、聞き手に配慮したバランスが必要です。
自信を持ちつつも謙虚さを忘れずに参加することで、誠実な印象を与えやすくなります。討論の場では、言葉だけでなく雰囲気も含めて自分を評価されていることを意識してください。
公務員の集団討論でよく出る頻出テーマ
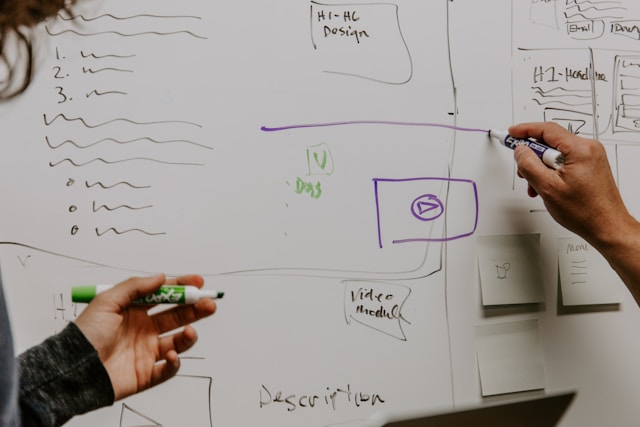
公務員試験の集団討論では、社会や地域の課題を題材としたテーマが頻繁に出題されます。どれも身近でありながら、深く考える必要があるものばかりです。
ここでは、よく取り上げられる5つのテーマについて、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
- 少子高齢化に対する自治体の取り組み案について
- 環境問題に対する効果的な対策について
- 地域経済の活性化につながる政策について
- 教育格差や教育環境の改善について
- 働き方改革や多様な人材活用の是非について
①少子高齢化に対する自治体の取り組み案について
少子高齢化は、全国の自治体が直面している深刻な課題です。とくに地方では、人口の減少や高齢化のスピードが速く、地域の活力低下にも直結しています。
集団討論では、こうした課題に対し、どのような施策が有効かが問われるでしょう。例えば、子育て支援の充実、高齢者の社会参加促進、若年層の定住を促す移住支援策などが挙げられます。
討論では、自分の意見だけでなく、異なる立場や視点を理解することも大切です。
②環境問題に対する効果的な対策について
環境問題は世界的な課題ですが、地域の行政とも深く結びついています。ごみの分別徹底、再生可能エネルギーの導入、地域住民と連携した緑化活動など、自治体レベルで取り組めることは多くあるのです。
討論では、ただ理想を語るのではなく、実行可能な内容かどうかも見られます。誰がどのように取り組むのかを明確にして、実現性を意識した提案を心がけてください。
また、環境対策は一時的なものではなく、継続性が求められます。学校や企業と連携しながら地域全体で取り組む体制づくりについても考えておくと、議論に厚みが出るでしょう。
③地域経済の活性化につながる政策について
地域経済の活性化は、人口流出や産業の衰退を食い止めるうえで非常に重要です。集団討論では、その地域に合った具体的な提案ができるかどうかが評価されるでしょう。
農業・観光・地場産業の強化や、若者のUターン支援、テレワーク環境の整備などが例に挙げられます。地域の特性を活かした政策であることが大切です。
経済だけでなく、住民の満足度や暮らしやすさへの配慮も忘れてはいけません。
「収入を増やすだけでなく、住み続けたいまちにすることが本質である」といった視点を持てると、より説得力のある討論になります。
④教育格差や教育環境の改善について
教育の問題は、子どもたちの将来に直結するだけでなく、地域の持続性にも関わる重要なテーマです。集団討論では、格差をどう埋めるか、どのように平等な学びの機会を保障するかがポイントとなります。
ICTの活用や放課後学習支援、家庭の経済状況に応じた支援制度など、さまざまな施策が考えられるでしょう。
地方と都市部での教育環境の違いや、教員の働き方改革といった観点も視野に入れることで、広がりのある議論が可能になるでしょう。子どもを取り巻く環境を丁寧に捉えることが重要です。
⑤働き方改革や多様な人材活用の是非について
働き方改革は、民間企業だけでなく行政にも求められるテーマです。集団討論では、公務員という立場をふまえた現実的な議論が求められます。
たとえば、テレワークや時短勤務、副業の容認などがありますが、それをどう公務に適用するのかは議論の分かれやすい点です。また、制度だけでなく、意識改革や組織文化の変化も不可欠でしょう。
高齢者、女性、外国人といった多様な人材の活用についても、公平性と効率性をどう両立させるかが鍵となります。一方的な主張ではなく、多面的な視点で議論できるように準備しておくことが大切です。
公務員の集団討論の対策方法

公務員試験の集団討論では、事前準備が合否を左右する大きな要因になります。即興で対応するのではなく、過去の傾向や知識を踏まえたうえで、自分の意見をしっかり持っておくことが大切です。
ここでは、効果的に対策を進めるための具体的な方法を紹介します。
- 過去に出題されたテーマを事前に把握する
- 自治体ごとの特徴や施策をリサーチする
- 討論で使える統計やデータをストックする
- 日頃から時事問題に関心を持つ
- 自分の意見をまとめるノートや資料を作成する
①過去に出題されたテーマを事前に把握する
過去に出されたテーマを確認することで、出題の傾向がつかめます。地域福祉、教育、少子高齢化など、公共性の高いトピックが多く扱われてきました。
自分ならどう答えるかを考えながら準備しておけば、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。
また、志望先ごとに傾向が異なる場合もあるため、希望する自治体や職種に関する情報を優先的に確認しておくと効果的です。
内容をただ暗記するのではなく、「なぜこのテーマが選ばれたのか」という背景まで理解することが、発言に深みを持たせるポイントです。
②自治体ごとの特徴や施策をリサーチする
志望先の自治体がどんな課題を抱えているかを把握しておくと、討論での発言に説得力が生まれます。子育て支援や防災対策など、力を入れている取り組みは自治体によって異なるのです。
そのため、ホームページや広報誌などの公式資料を使って、地域の現状をリサーチしておきましょう。実際の政策に基づいた発言ができれば、現実を意識した思考ができる人材として評価されやすくなります。
ただ知識を持つだけでなく、活用する視点が重要です。
③討論で使える統計やデータをストックする
自分の意見に説得力を持たせるには、客観的なデータが有効です。
例えば、「高齢化が進んでいる」という発言だけでなく、「2023年時点で65歳以上の人口比率が約29%」といった具体的な数値を添えることで、発言の信頼性が高まります。
普段から内閣府や総務省などの公的な統計をチェックし、信頼できる情報を集めておくと安心です。資料をただ集めるだけでなく、「いつ」「どこで」使えそうかを意識して整理しておいてください。
データの引き出しが多いほど、柔軟な対応がしやすくなります。
④日頃から時事問題に関心を持つ
討論のテーマは時事的な話題と深く関係しています。そのため、日々のニュースに関心を持つ習慣が欠かせません。テレビや新聞だけでなく、インターネットやSNSからも幅広く情報を得ることが大切です。
ただ情報を読むだけでなく、「自分はどう思うか」「賛成・反対どちらの立場か」といった視点で考えることで、討論時に使える思考力が自然と鍛えられます。
複数の立場から物事を見られるようになると、議論でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
⑤自分の意見をまとめるノートや資料を作成する
集めた情報や考えを整理するには、自分だけのノートや資料を作成するのがおすすめです。テーマごとの意見、根拠、データ、反論への対応例などをまとめておくと、直前の確認にも役立ちます。
手書きでもデジタルでも、自分が見やすく使いやすい形で整理しておくことがポイントです。準備が整っていれば、討論中も安心して発言できるでしょう。
「思いつく」ではなく「備えておく」ことで、自信と落ち着きを持って本番に臨めるようになります。
公務員の集団討論の練習方法

公務員試験の集団討論では、意見の中身だけでなく、話し方や姿勢、周囲との関わり方なども評価対象になります。それらを本番で発揮するためには、実践を想定した練習が欠かせません。
ここでは、効果的な練習方法を5つに分けて紹介します。
- 模擬討論で本番を意識した練習をおこなう
- グループワークで役割分担を実践してみる
- 時間内に意見をまとめて発言する練習をする
- 録画して自分の話し方や姿勢を客観的に見直す
- フィードバックをもらって改善を繰り返す
①模擬討論で本番を意識した練習をおこなう
本番を想定した模擬討論は、最も基本かつ効果的な練習です。テーマを設定し、できるだけ初対面に近い人と議論することで、本番さながらの空気に慣れることができます。
模擬討論では、発言の内容だけでなく、他の人の意見をどう受け止めるかや、議論の流れにどのように貢献するかといった点も評価につながるのです。
自分の話だけに集中せず、周囲の動きにも意識を向けてください。何度か繰り返すことで緊張が和らぎ、議論の進め方にも慣れてきます。
可能であれば、他大学の学生や就活仲間と練習してみると、さまざまな考え方に触れられて視野が広がるでしょう。
②グループワークで役割分担を実践してみる
集団討論では、進行役や書記、意見まとめ役など、いくつかの役割をこなす場面が出てきます。それぞれの立場を経験しておくと、討論全体を冷静に捉えられるようになるでしょう。
進行役の場合は、話の整理や意見の引き出し方に注意が必要です。一方、発言者として参加する際には、意見を端的に伝える力が求められます。
グループワークで役割を交代しながら練習することで、全体の流れやチーム内での振る舞いを身につけられるでしょう。どの役割にも意味があり、得意不得意が分かれる部分でもあります。
自分に合ったポジションを見つける手助けにもなるため、ぜひ実践しておきたい練習方法です。
③時間内に意見をまとめて発言する練習をする
限られた時間で要点を整理し、伝わりやすく話す力は、集団討論に欠かせません。話が長引くと他の参加者の機会を奪ってしまいますし、逆に短すぎると内容が薄くなってしまうおそれがあります。
目安としては、1回の発言を30秒から1分程度にまとめるのが理想です。練習では、PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を意識して話すと、構成がわかりやすくなります。
テーマを1つ決めて、自分の考えを時間内にまとめる練習を繰り返すことで、考えるスピードと伝える技術が磨かれていくのです。緊張した場でも落ち着いて話せるようになるでしょう。
④録画して自分の話し方や姿勢を客観的に見直す
自分では気づきにくい話し方の癖や表情、姿勢などをチェックするには、録画による振り返りが効果的です。動画を見返すことで、客観的に自分の印象を確認できます。
例えば、声が小さい、目線が落ちている、早口になっているといった点は、録画しないと気づきにくいものです。また、表情や姿勢が固いと、協調性に欠ける印象を与えてしまうこともあります。
録画を通じて得た気づきを次回の練習に活かせば、改善のスピードが早まるでしょう。慣れないうちは抵抗があるかもしれませんが、継続することで自分の変化も実感しやすくなります。
⑤フィードバックをもらって改善を繰り返す
自分だけで気づけない点を補うには、第三者からのフィードバックが欠かせません。客観的な意見をもらうことで、新たな課題や改善点が見えてきます。
もらった意見をもとに、改善を繰り返すことで、確実に成長できるはずです。また、フィードバックは受けっぱなしでは意味がありません。
自分でしっかりと受け止め、次の練習に活かす意識を持って取り組んでください。地道な積み重ねが、自信となって本番での力につながっていきます。
公務員の集団討論で合格に近づくために大切なこと

公務員試験の集団討論で評価されるには、事前準備と実践練習が欠かせません。
なぜなら、集団討論はリーダーシップや協調性、論理性など多角的に見られる選考であり、短時間で自分を的確にアピールする力が求められるからです。
過去の頻出テーマを押さえ、討論の流れや評価ポイントを理解したうえで、練習を通して改善を重ねれば、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。対策を丁寧に行い、自信を持って討論に臨んでください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










