公務員試験の作文対策|評価基準と書き方のコツを徹底解説
公務員試験では筆記や面接だけでなく、「作文」も重要な評価ポイントの1つです。
テーマに沿って自分の考えを論理的にまとめる力が求められるため、苦手意識を持つ人も多いのではないでしょうか。
本記事では、公務員試験の作文で見られる評価基準や基本ルール、構成の書き方、実際の例文、そして対策方法までを網羅的に解説します。
しっかりと準備をして、合格につながる作文力を身につけましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員試験では作文課題がある

公務員試験では、筆記試験や面接だけでなく、作文課題が出題される場合があります。
作文課題では、知識を問うのではなく、自分の意見を筋道立てて述べられるかが重視されるため、相手に伝わる文章を意識して書く必要があるのです。
とはいえ、高校時代の現代文や小論文とは異なる点も多く、評価基準や書き方のルールを理解しないまま取り組むと、思ったより点が伸びないかもしれません。
しかしながら、作文課題は事前に対策するほど得点につながりやすく、準備不足の受験者との差が出やすい分野。
筆記の勉強ばかりに気を取られて作文を後回しにする人も多い中で、早めに準備を始めておけば大きな差をつけられるでしょう。
公務員試験の作文の評価ポイント

公務員試験の作文では、ただ文章を書けばよいというわけではありません。評価には複数の観点があり、それぞれが重要な役割を果たしています。
ここでは、採点者がどのようなポイントに注目しているのかを明らかにし、作文対策の方向性を整理しました。
- 正確にテーマを捉えているかどうか
- 内容が一貫して論理的に展開されているか
- 自分の意見が明確に述べられているか
- 誤字脱字や表記ミスがないか
- 語彙力や表現力が豊かかどうか
- 原稿用紙の使い方・体裁が整っているか
①正確にテーマを捉えているかどうか
公務員試験の作文で最も基本的かつ重要なのは、テーマを正しく読み取り、それに沿って書くこと。どれほど文章力があっても、テーマから外れていれば高評価は望めません。
たとえば「地域社会への貢献」というテーマに対して、自分の将来像や夢ばかり語ってしまうと、論点がずれていると判断されてしまいます。
まずは与えられた言葉や設問の背景を丁寧に読み取り、何が求められているのかを分解して考えることが大切です。
テーマの把握力は文章力だけでなく、公務員としての素養を示すポイントにもなるのです。
②内容が一貫して論理的に展開されているか
公務員試験では、作文の内容が一貫していて論理的であるかも評価の対象になります。話が飛んでしまったり、途中で論点がずれてしまったりすると、読み手に伝わりにくくなるのです。
こうした問題を防ぐには、PREP法を使って文章の流れを整えると効果的。
PREP法とは、主張(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→再主張(Point)の順に構成する方法で、論理的な流れを自然に作れます。
また、段落ごとに話題をしっかり絞ることも大切です。1つの段落に複数の話題が混在すると、読みにくくなるだけでなく、論理展開が不明確になってしまいますよ。
③自分の意見が明確に述べられているか
作文では、自分の考えをはっきりと述べることが大切です。
試験では、自分なりに物事を考えられるかどうかが見られています。ただの情報や事実を並べるだけでは、採点者に印象を残せません。
たとえば、「〜と思います」や「〜と考えます」といった表現で、自分の立場を示すことが求められます。ただし、その意見にはしっかりした根拠が必要です。
根拠のない主張は、説得力を欠いてしまいます。たとえば「地域と信頼関係を築くことが大切だ」と書いたなら、
「地域イベントに参加することで住民と顔の見える関係が生まれるからです」といった具体例を添えると、より伝わりやすくなるでしょう。
④誤字脱字や表記ミスがないか
どれだけ内容が良くても、誤字脱字や助詞の間違いがあると評価は下がってしまいます。こうしたミスは読み手に違和感を与え、集中力をそいでしまうからです。
また、注意力や丁寧さに欠ける印象も持たれかねません。こうしたミスを防ぐためには、書き終えたあとに必ず見直しをする習慣をつけておきましょう。
特に「は」と「が」、「を」と「に」など、間違いやすい助詞の使い方に注意することがポイントです。音読をしながら確認するのも効果的。
声に出すことで、文のリズムや言葉の抜けに気づきやすくなります。こうした工夫をすることで、誤字脱字をかなり防ぐことができるはずです。
⑤語彙力や表現力が豊かかどうか
作文の評価では、語彙や表現の豊かさも見られます。同じ内容でも、言葉選びひとつで読み手に与える印象は大きく変わるものです。
「大切だと思います」よりも「必要不可欠だと考えます」など、より具体的な言葉を使うだけで説得力が増します。ただし、難しい語句を無理に使う必要はありません。
大切なのは、伝わりやすさと自然さのバランスです。言い換え表現や接続語をうまく使いながら、リズムのある文章に仕上げていきましょう。また、同じ言葉を繰り返すと単調な印象を与えてしまいます。
「重要」「意義がある」「価値が高い」など、意味が近い表現を複数持っておくと便利です。
⑥原稿用紙の使い方・体裁が整っているか
公務員試験の作文では、原稿用紙の使い方や見た目の整い具合も評価に影響します。形式が守れていないと、それだけで減点されてしまうこともあるため注意が必要です。
たとえば、段落の冒頭では1マス空ける、句読点は1マスに1つだけ入れる、数字は算用数字を縦書きで使うなど、基本的なルールはしっかり確認しておく必要があります。
また、文字が読みにくい、行が飛んでいる、余白の使い方が不自然といった見た目の乱れもマイナス要素になる恐れも。読みやすく整った原稿は、それだけで好印象を与えるものです。
公務員試験の作文における基本ルール

公務員試験の作文では、内容だけでなく原稿用紙の使い方や形式も評価されます。形式的なミスがあると、どれほど中身が良くても減点されるおそれがあるのです。
ここでは、最低限押さえておきたい基本ルールを5つに整理しました。
- 題名は3マス空けて記入する
- 本文は全体の8割以上を埋める
- 文末表現は統一させる
- 句読点は行頭に置かない
- 600〜1,200字以内で収める
①題名は3マス空けて記入する
題名は、原稿用紙の1行目に3マス分の空白を取ったうえで、4マス目から書き始めてください。この形式は公務員試験に限らず、多くの作文で共通する基本です。
簡単なようで忘れがちなポイントなので、あらかじめ意識しておくと安心でしょう。見出しの位置がずれていたり、空白が足りなかったりすると、形式の理解不足と判断される可能性があります。
特に公務員の仕事では、細かなルールに従えるかが求められるのです。題名の位置ひとつで印象が左右されるため、軽視しないようにしましょう。
慣れていないうちは、練習用の原稿用紙を使って実際に書いてみると感覚がつかめます。
②本文は全体の8割以上を埋める
指定された原稿用紙に対して、文字数が明らかに少ないと、内容が不十分と判断される可能性があります。目安としては、原稿用紙の8割以上を埋めることが求められるのです。
そのため、普段から文章量を意識しながら練習しておき、自分の意見を適切なボリュームで伝える力を身に着ける必要があります。
また、練習の段階で何文字書けたかをチェックする習慣をつけておくと、本番でも安心して対応できるでしょう。
③文末表現は統一させる
作文全体の印象を整えるためには、文末のスタイルを統一することが欠かせません。「〜です」「〜ます」で終わる敬体と、「〜だ」「〜である」といった常体が混在すると、読みづらく感じさせてしまいます。
また、同じ語尾が続きすぎると単調になるため、「〜です」「〜ます」だけでなく、「〜でしょう」「〜してください」「〜かもしれません」などを使い分けると、より自然な文章になりますよ。
書き終わったら、文末だけを見直す読み返しをするのも効果的です。文末のクセやブレに気づくきっかけにもなるでしょう。
④句読点は行頭に置かない
原稿用紙で気をつけたいポイントのひとつが、句読点の位置です。「。」や「、」などが行の先頭にきてしまうのは避けましょう。
行頭の句読点は視認性が悪く、読み手に違和感を与えるため、マイナス評価になる恐れも。とくに注意したいのは、文章の修正後です。
書き換えたり削除したりした際に、句読点だけが行頭に残ることがあるのです。目立たないミスですが、公務員試験では細かな点まで見られていることを忘れてはいけません。
対策としては、書いたあとに一度全体を見渡して確認することです。パソコンで練習している場合も、改行位置に注意を向けるようにしておくとよいでしょう。
⑤600〜1,200字以内で収める
公務員試験では、作文の文字数に明確な指定がある場合が多く、600〜1,200字という範囲が一般的です。
この指定を守れていないと、内容に関わらず減点されたり、評価対象から外されたりする可能性も。
定められた文字数でスムーズに書くためには、あらかじめ構成を練っておくのが効果的です。
序論・本論・結論の3段構成を意識して、それぞれのパートに何文字使うかイメージしておくと、書いている途中で迷わずに済むでしょう。
公務員試験の作文の書き方

公務員試験の作文では、評価ポイントを押さえたうえで、読みやすく論理的に書くことが求められます。ここでは、基本的な構成や書き方のポイントを紹介し、対策の手がかりをまとめました。
- 「序論・本論・結論」の構成を意識する
- テーマと自分の経験や考え方を結びつける
- 主張と根拠を明確に記述する
①「序論・本論・結論」の構成を意識する
作文を論理的に仕上げるには、「序論・本論・結論」の三部構成を意識することが大切です。この構成を守ることで、内容の流れが自然になり、読み手にも伝わりやすくなります。
具体的には、序論で自分の意見を端的に示し、本論で理由と具体例を挙げて根拠を補強し、結論で主張を簡潔にまとめてください。
試験では論理的な思考力も見られているため、文章の構造を整えることは評価アップにも直結するのです。
また、あらかじめ構成を考えてから書き始めることで、スムーズにまとめられるようになります。そのため、文章に苦手意識がある方も、まずはこの型から意識してみてください。
②テーマと自分の経験や考え方を結びつける
作文の内容に説得力を持たせるためには、テーマと自分自身の経験や考えを関連づけることが効果的です。
たとえば「地域とのつながり」がテーマの場合、自分が地域活動に参加した経験や印象に残った出来事などを交えるのがおすすめ。
体験を通じて得た気づきを共有することで、内容が具体的になり読み手の共感も得られやすくなるでしょう。
「なぜこのテーマを重要だと考えるのか」「どのように将来に活かしたいのか」といった視点を意識することがポイントです。
③主張と根拠を明確に記述する
自分の意見を述べるだけでは説得力のある作文にはなりません。その意見がなぜ成り立つのか、どのような背景や事例があるのかを示すことで、主張が強く伝わります。
たとえば「市民との信頼関係が大切だ」と述べる場合、「信頼があることで行政の施策に対する理解や協力が得られるから」と理由を示すと、内容に納得感が生まれますよ。
さらに具体的な体験例があれば、説得力はさらに増すでしょう。主張→理由→具体例→まとめという順番で構成するPREP法を活用すれば、論理的な文章が自然に書けますよ。
公務員試験の作文を書く際のコツ
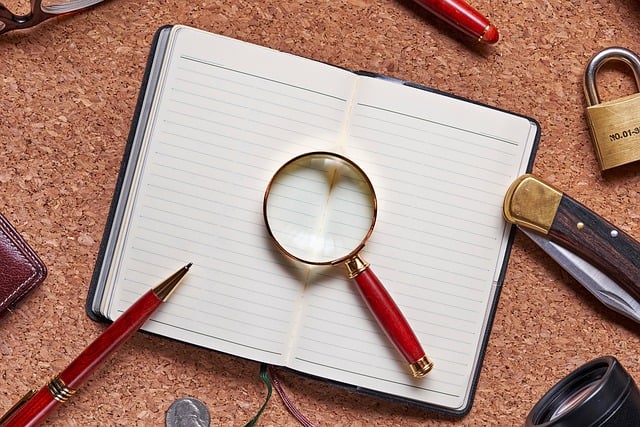
公務員試験の作文では、ルールや構成を理解するだけでなく、実際に書くときの工夫が重要です。
ここでは、文章に自信がない人でもすぐに取り入れられる実践的なポイントを5つ紹介します。
- 本文がテーマからズレないようにする
- 意見には必ず根拠を添える
- 例文を参考にしすぎず、自分の言葉で書く
- 時間配分を意識して書く
- 書き終えたら全体を読み直す
①本文がテーマからズレないようにする
作文でまず重視されるのは、テーマにきちんと沿っているかどうかです。どれだけ文が丁寧に書かれていても、テーマと無関係な内容になってしまえば評価は得られません。
設問の意図をしっかり読み取り、書くべきことを明確にしましょう。まずは設問文をよく読み、キーワードや問いの構造をつかんでください。
構成を考える段階で「なぜこのテーマが出されたのか」を考える習慣を持つと、テーマとの一貫性が保たれやすくなります。書き出しの部分でテーマに触れておくと、全体の軸もブレにくくなるでしょう。
②意見には必ず根拠を添える
自分の意見を述べるだけでは、読んだ人に納得感を与えられません。意見を主張する際は、必ずその理由や背景を説明するようにしてください。
たとえば「〇〇が大切だと思います」と書いたなら、「その理由は〜」と続けることを忘れないようにしましょう。この構成を意識するだけで、作文全体の説得力は大きく変わってきます。
根拠には、自分の経験、社会の動き、統計などが使えるでしょう。とくに実体験を絡めたエピソードは印象に残りやすく、読み手にも伝わりやすいです。
ただし話を誇張しすぎると逆効果になるため、事実をベースに表現してください。書いた後に「なぜそう考えたのか」を振り返って、根拠が不足していないか確認しておくと安心です。
③例文を参考にしすぎず、自分の言葉で書く
例文を読むことは大切ですが、内容や言い回しをそのまま真似るのは避けましょう。
どれだけ整った文章でも、他人の表現をなぞっただけでは評価されにくいでしょう。例文は構成や展開の仕方を学ぶために使うのが基本です。
本番では、自分の経験や視点をもとに、できる限り自分の言葉で書いてください。少しぎこちなくても、あなたらしさが出ている作文のほうが印象に残ります。
とくに近年の試験では、型にはまった作文よりも、自分の考えを誠実に伝える文章が評価される傾向があるのです。例文を丸写ししても、採点者にはすぐに見抜かれてしまいます。
練習のときから、自分の言葉で書くクセをつけておくと、本番でも迷わず書けるでしょう。
④時間配分を意識して書く
試験では限られた時間内で作文を書く必要があります。多くの場合、50〜90分の制限があるため、時間配分を誤ると書ききれなかったり、見直しの時間が取れなくなったりするでしょう。
効率的に進めるためには、あらかじめ「構成10分・本文執筆40分・見直し10分」などと時間の目安を立てておくとよいです。
練習のときからストップウォッチを使って書くことで、自然と時間感覚も身に付きますよ。
また時間内に収めるには、書くスピードだけでなく、書きすぎてしまったときに、どの情報を省略するか判断する練習をしておきましょう。
⑤書き終えたら全体を読み直す
書き終えた後の見直しを怠ると、誤字や文のねじれなど、細かなミスに気づかないまま提出してしまう可能性があります。
読み直すときは、まず文章全体の流れに違和感がないかを確認しましょう。
次に、文末の語尾が統一されているか、句読点が適切な位置にあるか、表現がくどくなっていないかなどもチェックしてください。
できれば声に出して読んでみると、読み手の視点に立って確認でき、文章の不自然な部分が見つかりやすくなります。
自分の考えが相手にきちんと伝わる内容になっているか、客観的に見直すことが大切です。
公務員試験の作文例
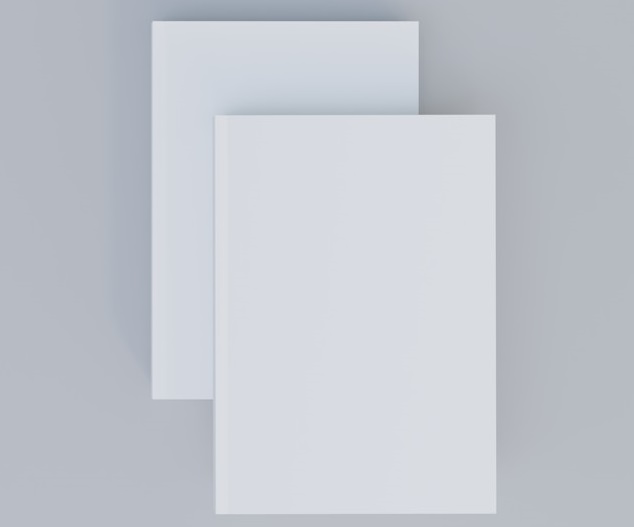
初めて公務員試験の作文を書く方にとって、どのような内容を盛り込むべきか悩むことも多いでしょう。
ここでは実際の出題傾向に沿ったテーマ別の例文を紹介し、構成や表現の参考になるよう整理しました。
①志望動機と公務員像についての例文
公務員を志望する理由や、どのような公務員像を描いているかを述べる例文を紹介します。個人の原体験を通じて、動機に一貫性を持たせることがポイントです。
《例文》
| 私は高校生のときに経験した大規模な台風被害をきっかけに、公務員という職業に関心を持つようになりました。 自宅が一時的に停電・断水し、地域全体が混乱するなか、避難所で対応していた市職員の方々は、冷静に状況を整理しながら住民一人ひとりに寄り添い、行動していたのです。 その姿に大きな安心感を覚え、強い憧れを抱くようになったのを今でも鮮明に覚えています。その後、大学では地域社会について学び、防災ボランティアにも積極的に参加するようになったのです。 被災された方々の声に耳を傾けるなかで、公務員は非常時に限らず、日常においても暮らしを支える存在であると気づかされました。 私は、人と地域をつなぐ役割を果たし、災害時だけでなく平時から安心を届けられる職員を目指したいと考えています。 |
《解説》
動機と将来像に一貫性があることが重要です。体験と結びつけながら、公務員の役割に対する理解を具体的に表現するように心がけてください。
②社会問題に対する自分の考えについての例文
ここでは、社会問題に対する自分の意見や価値観を問われた場合の例文を紹介します。自身の体験と社会課題を結びつけることで、説得力を高めることができるでしょう。
《例文》
| 私は食品ロスの問題に強い関心を持っています。きっかけは、大学のサークル活動で地域の子ども食堂を支援した経験です。 調理や配膳の手伝いをするなかで、まだ十分食べられるにもかかわらず、多くの食品が日々捨てられている現実を知りました。 同時に、経済的な理由から栄養のある食事を満足に取れない子どもたちの姿にも触れ、大きな衝撃を受けたのです。 このようなギャップを前に、私自身の無関心さを痛感するとともに、身近な問題として食品ロスを捉えるようになりました。 それ以来、買いすぎを防ぐ工夫や期限前の食材の活用など、自分にできる取り組みを意識的に続けています。 将来は行政の立場から、食品ロス削減に向けた制度や啓発活動に携わりたいと考えています。持続可能な社会の実現には、一人ひとりの行動と仕組みの両面からのアプローチが欠かせません。 私はその橋渡し役として、地域と向き合いながら貢献していきたいです。 |
《解説》
社会問題を扱う際は、自分の体験や背景としっかり結びつけると説得力が増します。問題提起だけでなく、自分なりの意見や行動への意志も忘れずに示してください。
③学生時代に学んだことをどう活かすかについての例文
ここでは、学生時代に取り組んだ経験を今後の社会人生活にどうつなげるかを示す例文を紹介します。経験と学びの具体性がポイントです。
《例文》
| 私は大学時代、飲食店でのアルバイトを通じて、接客の難しさと同時にやりがいも感じるようになりました。 とくに忙しい時間帯には、笑顔を絶やさず、さまざまなお客様の要望に的確に応える力が求められます。 最初は注文の聞き間違いや対応の遅れに悩むこともありましたが、先輩のアドバイスを受けながら少しずつ慣れていきました。 やがて、自分の接客に対して「ありがとう」と声をかけていただける機会が増え、そのたびに喜びを感じたのです。 ただ作業をこなすのではなく、相手の立場に立って行動することの大切さを、現場で肌で学んだように思います。 この経験を通じて身につけた「傾聴」と「思いやり」は、公務員として地域の方々と接する際にも欠かせない姿勢だと考えています。 今後は住民一人ひとりに丁寧に向き合い、信頼関係を築ける職員を目指していきたいです。 |
《解説》
身近な経験から得た学びを、具体的にどう活かすかを明確に書くと伝わりやすくなります。公務員の職務とつなげて展望を示すことがポイントです。
④将来の目標と地域への貢献についての例文
将来の目標と、それを通じて地域社会にどう貢献したいかをテーマにした例文を紹介します。理想だけでなく、具体的な行動への意欲が重要です。
《例文》
| 私の将来の目標は、地域の高齢者が安心して暮らせるまちづくりに貢献することです。 祖母が一人暮らしをしていたこともあり、買い物や病院の通院など、日常生活に不安を抱える高齢者が多いことを、身近に感じてきました。 大学では地域福祉を専門に学びながら、高齢者宅への訪問活動や見守りボランティアにも参加しています。 活動を通じて実感したのは、制度やサービスだけでなく、顔の見える人間関係や地域のつながりが、高齢者の安心感につながるということでした。 公務員として働く際には、そうした声を丁寧に拾い上げ、机上の理論だけに頼らない支援を届けていきたいと考えています。 声なき声にも耳を傾け、小さな課題を一つひとつ丁寧に解決することで、地域に信頼される存在を目指したいです。 |
《解説》
「なぜその目標を持つに至ったか」という背景を交えることで説得力が増します。地域貢献を語るときは、身近な体験からの動機づけを意識すると良いでしょう。
⑤困難を乗り越えた経験と成長についての例文
ここでは、学生時代に直面した困難をどのように乗り越え、そこから何を学んだかを表現した例文を紹介します。課題に向き合う姿勢と成長の軌跡が重要です。
《例文》
| 私は大学のゼミでプレゼン発表を担当した際、極度の緊張からうまく話せず、大きな悔しさを味わいました。 発表後は自信を失い、「自分には向いていないのでは」と落ち込んだことをよく覚えています。しかし同時に、もう一度挑戦したいという気持ちも心の奥に残っていました。 そこで、人前で話す経験を意識的に増やそうと考え、学生会のイベントで司会を務めたり、話し方に関するセミナーに参加しました。 最初は戸惑いもありましたが、実践を重ねるうちに少しずつ自信が芽生えてきたのです。 次のゼミ発表では、堂々と話せただけでなく、発表内容についても聴き手から前向きな評価をいただくことができました。 この経験を通じて、苦手なことから目を背けず、積極的に取り組む姿勢が成長につながるのだと実感しています。 |
《解説》
困難をきっかけに行動を変えたプロセスを具体的に描くと、説得力が増します。問題をどう乗り越えたかを丁寧に書くよう意識しましょう。
公務員試験の作文の対策方法

公務員試験の作文対策では、文章力の向上だけでなく、日頃の準備や意識の持ち方が大きな差になるのです。ここでは、具体的に取り組むべき方法をわかりやすく紹介します。
- 作文練習を繰り返して慣れる
- 毎回書いた作文を読み直す習慣をつける
- 第三者に添削してもらう
- 時事問題や社会問題に日頃から関心を持つ
- 作文対策講座や書籍を活用する
①作文練習を繰り返して慣れる
作文力向上には繰り返し練習が最も重要です。最初は時間をかけて丁寧に、慣れてきたら試験時間を意識してスピードも重視しましょう。
テーマを変えながら毎日1本でも書く習慣をつけることで、様々な角度から考える力も養われます。
継続することで自分の癖や弱点にも気づけるようになり、文章構成のパターンも身につくでしょう。
②毎回書いた作文を読み直す習慣をつける
書いた作文をすぐに見直す習慣を持つことで、表現や構成の精度が高まります。文章を書いた直後は満足してしまいがちですが、少し時間をおいて読み返すと改善点がよく見えてくるのです。
たとえば、主張が分かりにくい箇所や、接続語の使い方が不自然な部分、誤字などに気づきやすくなります。客観的な視点で読み返すことで、より説得力のある文章へと修正できるでしょう。
音読するのも効果的です。声に出して読むことで、文章のリズムや違和感のある表現に気づきやすくなります。
③第三者に添削してもらう
作文試験は、自分だけでは見逃すミスや課題があるため、第三者に添削してもらいましょう。例えば、先生、キャリアセンター職員、信頼できる友人にお願いするのがおすすめです。
具体的なフィードバックにより次回の課題も明確になり、成長のきっかけとなるでしょう。
「この表現は伝わりにくい」「論理のつながりが弱い」といった客観的な意見は、文章力向上に役立つはずです。
④時事問題や社会問題に日頃から関心を持つ
作文試験では社会の動きや課題がテーマになることが多いため、日常的にニュースや新聞に触れることが重要です。
ただ読むだけでなく、「なぜ起きたのか」「自分はどう考えるか」という視点を持つことで考察力が深まり、公務員としての素養にもつながります。
具体的な事例やデータを知っていることで、文章の説得力に大きな差が生まれるでしょう。
⑤作文対策講座や書籍を活用する
独学に限界を感じる場合は、専門の講座や書籍を活用しましょう。出題傾向や評価基準に基づいた指導が受けられ、豊富な例文や構成例で具体的な参考になります。
オンライン講座や通信添削サービスも充実しているので、自分のライフスタイルに合った方法を選んで継続しましょう。
特に初学者にとっては、プロの指導により安心感と自信を得られる効果的な方法ですよ。
公務員試験の作文で合格を引き寄せるために

公務員試験では、作文課題を通じて受験者の思考力や表現力が評価されます。
高評価を得るには、原稿用紙の使い方をはじめとした基本ルールを守りつつ、論理的かつテーマに沿った構成で書くことが求められるのです。
また、正確にテーマを捉え、主張に根拠を持たせることも重要。さらに、例文を参考にしながらも自分らしい言葉で書く姿勢が、差を生むポイントになります。
作文力は短期間では身につきにくいため、日頃からの練習と見直し、そして第三者による添削を取り入れることが効果的です。
これらの対策を地道に積み重ねることで、公務員試験の作文で確かな得点源を築けるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














