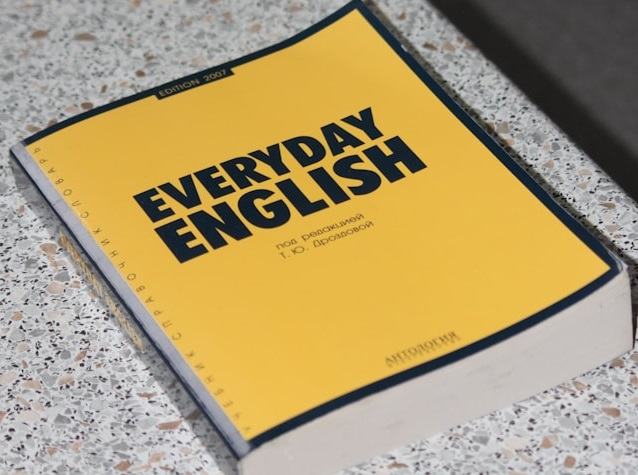就活のやり方がわからない大学生必見!初心者向け完全ガイド
「就活のやり方がわからない…」と感じている大学生は少なくありません。
情報が多すぎて整理できなかったり、何から始めればよいのか分からず不安になるのは当然のことです。
ですが、就活には基本の流れと押さえるべきステップがあり、それを理解すればスムーズに進められます。
この記事では、就活の始め方からスケジュール、準備すべき持ち物やマナー、評価されるポイントまでを初心者にもわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活とは?「就職活動」の意味と目的を理解しよう

就活は単に仕事を探す活動ではなく、自分の将来を考え、社会人としての第一歩を踏み出すための大切な期間です。しかし、「就活のやり方がわからない」と感じている学生も多くいます。
学生は自分の興味や価値観に合う企業を探し、企業は自社の理念や方向性に共感できる人材を求めています。その相性を確かめる機会が就活なのです。
つまり、就活は一方的な選考ではなく、双方が納得できるマッチングの過程なのです。就活の目的は「内定を取ること」ではなく、「自分が納得して働ける職場を見つけること」です。
そのためには、まず自己分析を通して自分の価値観や得意分野を把握することが重要です。さらに業界研究を行い、自分の将来像に合う企業を見極めていきましょう。
また、就活は社会人としての基礎力を身につける貴重な機会でもあります。ビジネスマナー、計画性、論理的な思考力など、選考を通じて学ぶことは社会に出てからも役立つでしょう。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
就活のやり方がわからない理由

就活は多くの学生にとって初めての本格的な社会活動です。そのため、「何から始めればいいのか」「どんな順序で進めるのか」がわからず、混乱してしまう人が少なくありません。
ここでは、就活のやり方がわからないと感じる主な原因を整理し、解決のヒントを紹介します。
- 情報が多すぎて整理できない
- 何から始めればよいかイメージできていない
- やりたい仕事や業界が定まっていない
- 周囲の就活状況と比較して焦っている
- 自己分析や企業研究の方法を知らない
- 将来に対する漠然とした不安がある
- 大学や家族からのサポートが少ない
①情報が多すぎて整理できない
インターネットやSNS、大学のガイダンス、就活アプリなど、就活に関する情報は日々あふれています。その膨大な情報量に圧倒され「どれが本当に役立つのかわからない」と感じる人も多くいるでしょう。
特にSNSでは他人の成功体験が強調されやすく、自分との比較によって焦りや不安を生むこともあります。解決の第一歩は、情報源を厳選することです。
信頼できる公式サイトや、大学のキャリアセンター、就活エージェントなどを中心に活用しましょう。
情報を集めたら、エクセルやノートに「企業名・特徴・選考時期」などを整理しておくと、自分に必要な内容が明確になります。
情報の取捨選択ができるようになると、就活全体の見通しが一気に立てやすくなるでしょう。
②何から始めればよいかイメージできていない
就活の進め方がイメージできない学生は少なくありません。
「自己分析」「業界研究」「エントリー」「面接準備」など、流れが理解できていないと、何を優先するべきか判断できず、時間だけが過ぎてしまいます。
これは、就活全体像を把握できていないことが原因のひとつです。最初にやるべきは、就活スケジュールの把握です。
大学3年生の夏にインターンシップ、冬に自己分析やエントリーシート作成、春に本選考が始まるという大まかな流れを理解しましょう。
全体の流れが見えると、今の自分に必要な行動が自然とわかります。焦らず段階を踏むことで、自信を持って行動できるようになります。
③やりたい仕事や業界が定まっていない
「自分のやりたいことがわからない」という悩みは、就活生の中でも特に多いものです。興味のある業界が見つからないと、志望動機が書けず、面接でも説得力が欠けてしまいます。
しかし、最初から明確な目標を持っている人の方が珍しいのです。この問題を解決するには、自己分析と業界研究を並行して進めることが有効です。
過去の経験や得意分野を振り返り、「自分がどんなときにやりがいを感じたか」を書き出してみましょう。そのうえで、複数の業界説明会やインターンに参加すると、自分に合う分野が少しずつ見えてきます。
最初は興味本位でも構いません。行動を通して方向性を探ることが、理想のキャリアを見つける第一歩になります。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
④周囲の就活状況と比較して焦っている
友人が次々と内定を得ている姿を見ると、「自分は遅れているのではないか」と不安に感じる人も多いでしょう。SNSでは「〇社から内定!」といった投稿も目に入り、焦りが増してしまうのが現実です。
しかし、就活には個人差があります。業界・職種・志望企業によってスケジュールは異なるため、他人と比べても意味がありません。焦りを感じたときこそ、自分の現状を見直すチャンスです。
やるべきことをリスト化し、今週中にできることを明確にすると、気持ちが落ち着きます。また、信頼できる友人や大学のキャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。
周囲と比べず「自分のペース」を保つことが、結果的に納得のいく内定につながります。
⑤自己分析や企業研究の方法を知らない
就活の基本とされる自己分析や企業研究ですが、具体的なやり方がわからず、手をつけられない学生は多くいます。自己分析では、自分の強みや弱みを明確にすることが目的です。
「どんな経験で成長を感じたか」「なぜその選択をしたのか」といった質問を掘り下げていくと、自分の価値観が見えてきます。
企業研究では、業界全体の動向をつかんだうえで、個々の企業の特徴を理解することが重要です。
会社の公式サイトや採用ページだけでなく、ニュースサイトや社員インタビューを読むとリアルな情報が得られます。さらに、OB・OG訪問を活用して現場の声を聞くと、ミスマッチを防ぐことができます。
正しい情報の集め方を身につけることが、納得できる企業選びにつながります。
⑥将来に対する漠然とした不安がある
「社会人としてやっていけるのか」「仕事が自分に合うのか」といった将来への不安は、ほとんどの就活生が感じています。明確な答えがないため、考えれば考えるほど不安が大きくなる傾向があります。
しかし、不安の正体は「行動不足」にある場合が多いのです。まずは小さな行動から始めてみましょう。オンライン説明会やインターンに参加することで、社会人のリアルな話を聞けます。
経験を積むうちに、具体的なイメージが湧き、不安は自然と軽くなります。また、不安を抱える自分を責めず、「誰でも最初は初心者」と受け入れることも大切です。
行動と経験の積み重ねが、自信と安心感を育てます。
⑦大学や家族からのサポートが少ない
就活を進めるうえで、周囲の支援が得られないと孤独を感じやすくなります。
大学のキャリアセンターに行きづらかったり、家族が就活に理解を示してくれなかったりすると、すべてを一人で抱え込んでしまう人もいます。そんなときは、外部のサポートを積極的に利用しましょう。
特に就活エージェントは、書類添削や面接練習、企業紹介などを無料で受けられる便利なサービスです。自分専任のアドバイザーがつく場合もあり、相談しながら進められるため安心感があります。
また、OB・OG訪問やオンラインコミュニティを通して、社会人の先輩と話すのも効果的です。サポートを受けることは弱さではなく、成功への近道です。
信頼できる人や機関に頼る勇気を持つことが、就活をスムーズに進める大切な一歩になります。
就活の全体スケジュールを理解しよう【大学3年〜4年生向け】

就活は長期戦に見えますが、時期ごとにやるべきことを明確にすればスムーズに進められます。大学3年の夏から4年の秋まで、流れを理解しておくことで焦らず効率的に行動できます。
ここでは、就活の全体スケジュールを時期別に詳しく解説します。
- 大学3年生の夏:インターンシップ準備期間
- 大学3年生の秋:業界・企業研究を深める時期
- 大学3年生の冬:エントリーシート準備・自己分析の強化
- 大学3年生の3月:会社説明会・エントリー開始
- 大学4年生の6月:選考解禁・面接本格化
- 大学4年生の10月:内定式・入社準備期間
①大学3年生の夏:インターンシップ準備期間
大学3年の夏は、就活のスタートラインです。多くの企業がインターンシップを実施するため、この時期から参加の準備を始めるのが理想です。
インターンは業界研究や仕事理解に直結する貴重な機会であり、将来の志望業界を決めるきっかけにもなります。まずは自分の興味分野を整理し、エントリーできる企業を調べましょう。
参加する前に「どんなスキルを学びたいか」「どんな業界に関心があるか」を明確にしておくと、経験がより実りあるものになります。
短期・長期インターンの違いも確認し、自分の予定に合わせてスケジュールを立てることが大切です。インターンで得た経験は、今後の面接や自己PRにも活かせます。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
②大学3年生の秋:業界・企業研究を深める時期
秋は「情報を集め、理解を深める」時期です。インターンやイベントで得た印象をもとに、業界全体の動向や企業の特徴を詳しく調べましょう。特にこの時期は、志望業界をしぼりこむ準備期間でもあります。
業界研究では、売上構造や成長性、業界内での企業ポジションを把握することが重要です。一方、企業研究では、企業理念や社風、求める人材像を理解しておくと面接対策にも役立ちます。
OB・OG訪問を行うと、ネットにはないリアルな情報を得られます。秋のうちに知識を深めることで、冬以降の選考準備が格段に進めやすくなるでしょう。
③大学3年生の冬:エントリーシート準備・自己分析の強化
冬は、就活準備の「仕上げの時期」です。エントリー開始に向けて、自己分析と書類作成の両方を本格的に進めます。
自己分析では、自分の強み・弱みを明確にし、志望動機につながるストーリーを組み立てることがポイントです。エントリーシート(ES)は、企業が最初にあなたを評価する重要な書類です。
志望動機・ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)・自己PRなど、よく聞かれる項目を事前にまとめておきましょう。時間をかけて練習すれば、書類選考の通過率が上がります。
また、ESは複数の企業で内容を使い回せるため、テンプレート化して効率よく作成するのがおすすめです。
④大学3年生の3月:会社説明会・エントリー開始
3月は、いよいよ本格的な就活シーズンがスタートします。多くの企業が会社説明会を開き、エントリー受付を開始します。この時期は情報量が一気に増えるため、計画的に行動することが大切です。
会社説明会では、企業の理念や採用方針を直接聞ける貴重な機会です。興味のある企業は積極的に参加し、印象に残ったポイントをメモしておきましょう。
エントリー後は、すぐに書類提出や筆記試験が始まる場合もあるため、スケジュール管理を徹底してください。短期間で多くの企業に応募することもあるので、体調管理にも気を配る必要があります。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
⑤大学4年生の6月:選考解禁・面接本格化
大学4年の6月になると、多くの企業が正式に採用選考を開始します。この時期は、面接対策とスケジュール調整が重要なポイントになります。
エントリーした企業ごとに選考方法や日程が異なるため、早めの準備が欠かせません。面接では、自己PRや志望動機を一貫性のある内容で伝えることが求められます。
過去の経験を具体的に語り、あなたの人柄や価値観をしっかりアピールしましょう。また、複数の企業の面接が重なる場合もあるため、優先順位をつけて行動することが大切です。
面接は場数を踏むことで上達します。失敗を恐れず、経験を積み重ねていく姿勢が内定への近道になります。
⑥大学4年生の10月:内定式・入社準備期間
10月には、多くの企業で内定式が行われます。内定式は単なる形式的なイベントではなく、「社会人としての第一歩」を踏み出す重要な節目です。
企業側から今後のスケジュール説明や配属の方針が伝えられることも多いため、しっかり参加しましょう。また、この時期からは入社に向けた準備も始まります。
社会人としての基本的なマナーや、ビジネスメール・電話対応などを確認しておくと安心です。引っ越しや卒業論文など、生活面でも忙しくなる時期ですが、健康管理を怠らずに過ごしてください。
就活を通して得た学びを活かし、次のステージへの準備を整えましょう。
就活の始め方:やり方がわからない人が最初にすべきこと

就活は「何から始めればいいのかわからない」と感じる人が多いですが、正しい順序で行動すれば誰でも着実に前進できます。まずは情報を集め、準備を整え、自分の方向性を明確にしていくことが重要です。
ここでは、就活の第一歩としてやるべきことを段階的に解説します。
- 就活サイト・エージェントへの登録
- 自己分析で自分の軸を明確にする
- 業界・企業研究の基本を理解する
- インターンシップや説明会への参加
- 履歴書・エントリーシートの書き方を知る
- 面接練習で自信をつける
- 大学キャリアセンターや先輩に相談する
①就活サイト・エージェントへの登録
就活を始めるうえで、まず欠かせないのが就活サイトやエージェントへの登録です。登録することで、求人情報や説明会の案内、選考スケジュールなどを効率よく集められます。
複数のサイトを併用することで、自分に合う企業と出会える可能性も高まります。また、就活エージェントはマンツーマンでサポートを受けられる点が魅力です。
書類添削や面接練習、企業紹介などを無料で利用できるため、初めての就活でも安心して進められます。登録後は、プロフィールを丁寧に入力しておくと、スカウトや企業からのオファーを受けやすくなります。
まずは行動の第一歩として、情報の入り口を整えることが大切です。
②自己分析で自分の軸を明確にする
自己分析は就活の土台となる重要なステップです。自分の強み・弱み・価値観を明確にすることで、志望業界や職種を選びやすくなります。
具体的には、「過去に頑張った経験」「達成感を得た瞬間」「つらかったけど乗り越えた経験」を振り返ってみましょう。そこから共通する思考パターンや行動傾向が見えてきます。
さらに、自分の価値観を整理すると、将来どんな環境で働きたいかが明確になります。自己分析ができていると、面接やエントリーシートでも一貫性のある回答ができ、企業に好印象を与えやすくなります。
焦らずじっくりと時間をかけて、自分の“軸”をつくり上げることが成功のカギです。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
③業界・企業研究の基本を理解する
業界研究と企業研究は、志望先を決めるうえで欠かせません。まずは興味のある業界をいくつか選び、それぞれの特徴や将来性を調べましょう。
業界全体の動向を知ることで、どんなスキルが求められているかがわかります。企業研究では、会社の理念やビジョン、働く環境などをチェックします。
採用サイトやIR情報(投資家向け情報)を読むと、企業の姿勢や強みが理解しやすいです。さらに、実際に働いている社員の声を聞くことで、自分に合うかどうか判断しやすくなります。
情報を整理しながら比較することで、自分にとって納得のいく志望先を選べるようになります。
④インターンシップや説明会への参加
インターンや説明会は、企業理解を深める絶好のチャンスです。実際の職場を体験することで、業務内容や職場の雰囲気がリアルにわかります。
また、企業の採用担当者と直接話せる機会も多く、選考での印象にもつながります。短期インターンでは、複数業界を比較するのに最適です。
長期インターンでは、実際の業務に関わることでスキルを身につけられます。説明会では、企業の強みや求める人材像を聞き取り、自分との相性を確認してください。
参加後は学んだことをメモにまとめ、自己分析や志望動機づくりに活かすと効果的です。
⑤履歴書・エントリーシートの書き方を知る
エントリーシート(ES)や履歴書は、企業に自分を知ってもらうための第一関門です。内容の良し悪しで面接に進めるかどうかが決まるため、早い段階で書き方をマスターしておくことが大切です。
ポイントは、「読みやすく、具体的に書く」ことです。自己PRでは、自分の強みを示すエピソードを1つに絞り、数字や具体例を交えて説明すると説得力が増します。
志望動機では、企業の特徴と自分の価値観を結びつけて伝えると効果的です。また、誤字脱字があると印象が悪くなるため、提出前に必ず第三者にチェックしてもらいましょう。
練習を重ねるほど完成度が上がります。
⑥面接練習で自信をつける
面接は就活の中でも最も緊張する場面ですが、事前準備をすれば自信を持って臨めます。まずは基本的な質問(自己紹介・志望動機・学生時代に力を入れたことなど)をスムーズに話せるよう練習しましょう。
回答は丸暗記ではなく、要点を押さえた「話の流れ」で覚えるのがコツです。練習は一人でもできますが、友人や大学のキャリアセンター職員と模擬面接を行うと、より実践的です。
話し方や姿勢、表情などもチェックしてもらうと改善点が見つかります。面接は経験を積むほど慣れるので、場数を踏んで自然体で話せるようになりましょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
⑦大学キャリアセンターや先輩に相談する
就活で悩んだときは、一人で抱え込まずに大学のキャリアセンターや先輩に相談しましょう。キャリアセンターでは、ESの添削、面接練習、求人紹介などを受けられます。
特に大学独自の求人情報は見逃しやすいので、定期的にチェックするのがおすすめです。また、先輩から直接アドバイスをもらうのも効果的です。
実際に就活を経験した先輩は、リアルな体験談や面接のコツを教えてくれることがあります。SNSやOB・OG訪問ツールを使えば、気軽に話を聞く機会も作れます。
信頼できる人に相談することで、迷いが減り、自信を持って就活を進められるでしょう。
就活準備で必要なものリスト【アイテム・書類・身だしなみ】

就活をスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。必要なアイテムや書類、そして身だしなみの整え方を理解しておくことで、慌てずに選考へ臨めます。
ここでは、就活に必要な持ち物や準備のポイントを7つの項目に分けて解説します。
- 就活スーツと靴
- カバン・腕時計・文具などの基本アイテム
- 履歴書・エントリーシートなどの書類準備
- 証明写真とデータ管理
- メールアドレス・手帳・スマホ設定の整備
- オンライン面接で必要な機材と環境
- 就活費用と資金管理
①就活スーツと靴
就活では第一印象が非常に重要です。そのため、スーツや靴の選び方には気を配る必要があります。スーツは黒や紺の無地が基本で、体にフィットしたサイズを選ぶことが大切です。
派手なデザインや光沢のある素材は避け、清潔感を重視しましょう。男性は白いワイシャツにシンプルなネクタイ、女性は膝丈のスカートやパンツスタイルが好印象です。
靴は黒の革靴が基本で、汚れや傷がないよう定期的に手入れをしてください。新品の靴は慣らしておくと当日も安心です。全体的に「清潔・誠実・控えめ」を意識すれば、印象を大きく高められます。
リクルートスーツ、0円で手に入るよ!
リクルートスーツは就活生にとって必須アイテムですが、実は「就活でしか」使用しません。しかし、リクルートスーツの購入には平均で2万~3万円が必要になり「高いな…」と感じる人もいますよね。
そこでおすすめなのが「Caricuru (カリクル)」という「リクルートスーツを無料でレンタルできるサービス」です。
無料ですが、レンタルできるスーツは「SUIT SELECT」のおしゃれなスーツで、しかも丁寧な採寸までセットですべて無料です。
就活が終わるまでずっとレンタルできるので、気になる方はまずはLINE登録でリクルートスーツのレンタル予約をしましょう。先着500名様限定のキャンペーン中なのでお早めに!
②カバン・腕時計・文具などの基本アイテム
就活で使用する小物類は、実用性と印象の両方を意識しましょう。カバンはA4サイズの書類が入る黒やネイビーのシンプルなビジネスバッグがおすすめです。
型崩れせず自立するタイプを選ぶと、面接時にも見栄えが良くなります。腕時計は派手なデザインを避け、文字盤が見やすいものを選ぶのがポイントです。
スマホで時間を確認するよりも、社会人らしい印象を与えられます。筆記用具は黒・青のボールペン、ノート、スケジュール帳をそろえておくと便利です。
いずれもシンプルで清潔感のあるものを選ぶと安心です。
③履歴書・エントリーシートなどの書類準備
履歴書やエントリーシート(ES)は、企業があなたを知るための最初の資料です。誤字脱字や書き損じがあると印象を下げるため、丁寧に作成しましょう。
手書きの場合は黒のボールペンを使用し、文字を整えて書くことを意識してください。パソコン作成の場合は、フォントやレイアウトを統一して読みやすさを重視しましょう。
また、複数の企業に応募する場合は、志望動機や自己PRを使い回せるようにテンプレートを用意すると効率的です。提出前には必ずコピーを取り、面接時に内容を確認できるようにしておくと安心です。
④証明写真とデータ管理
証明写真は採用担当者が最初に目にする「あなたの顔」です。清潔感と誠実さを伝えるためにも、服装や表情に注意してください。スーツを着用し、明るい背景で撮影するのが基本です。
表情は自然な笑顔を意識し、姿勢を正して写ると好印象になります。撮影は写真館を利用すると、プロによる明るさ調整や修正で仕上がりが整います。
データも必ず保存し、オンラインエントリー用にも活用できるようにしましょう。ファイル名を統一して管理すると、複数企業への提出時に迷わず使えます。
スマホではなく、パソコンにバックアップを取っておくのがおすすめです。
⑤メールアドレス・手帳・スマホ設定の整備
就活では、企業とのやり取りをスムーズに行うための連絡手段を整えることが大切です。
まず、メールアドレスは大学やフリーメールを使用しても構いませんが、「本名+数字」などビジネスにふさわしい形式にしましょう。ニックネームや絵文字入りのアドレスは避けてください。
また、手帳やスケジュールアプリでエントリー日程や面接予定を一元管理することも重要です。通知設定を活用し、見逃しを防ぎましょう。
スマホは着信音を控えめに設定し、ビジネスメールアプリを導入すると便利です。就活期間中は、社会人に近い意識で連絡環境を整えることが信頼につながります。
⑥オンライン面接で必要な機材と環境
オンライン面接が主流となった現在、機材や通信環境の整備は必須です。パソコンはカメラ付きのものを使用し、マイクやイヤホンの音声チェックを事前に行いましょう。
照明は顔全体が明るく映るよう、自然光またはライトを調整します。背景は生活感を感じさせないシンプルな壁やカーテンの前がおすすめです。
通信環境は安定したWi-Fiを使用し、途中で途切れないよう確認してください。また、面接前にはビデオ会議ツール(Zoom・Teamsなど)の操作練習をしておくと安心です。
環境を整えることは、準備力と誠実さを示す大切な要素です。
⑦就活費用と資金管理
就活には交通費、スーツ代、証明写真、通信費など、意外と多くの出費が発生します。全体で5万円〜10万円ほどかかることも珍しくありません。
無理なく活動を続けるためには、事前に予算を立てておくことが大切です。まず、必要な費用をリスト化し、優先順位をつけて支出を管理しましょう。
交通費は早割や回数券を活用し、オンラインイベントを併用すると節約できます。支出をアプリで記録しておくと、どこにお金がかかっているか可視化できます。
節約しながらも、必要な部分にはしっかり投資する意識が、就活を成功させるカギになります。
就活マナーの基本:印象アップにつながるポイント

就活では、マナーの良し悪しが印象を大きく左右します。どれほど能力や熱意があっても、基本的なマナーが欠けていると評価は下がってしまいます。
ここでは、面接官や採用担当者に好印象を与えるための就活マナーを7つの視点から解説します。
- 敬語と話し方のマナー
- 電話・メール・チャットでのマナー
- 服装・身だしなみの基本
- 面接時の立ち居振る舞い
- オンライン面接のマナー
- 日程変更・辞退時の連絡マナー
- SNSやネット上のマナー
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①敬語と話し方のマナー
就活での会話は「丁寧で誠実な印象」を与えることが大切です。敬語は相手への尊重を示す基本であり、間違えると信頼を損ねてしまいます。
特に「ご苦労さま」「了解しました」は目上の人に使わないよう注意しましょう。「お疲れさまです」「承知いたしました」といった表現が適切です。
話すときは、結論を先に伝え、声のトーンは落ち着いて明るくすることを意識してください。早口にならないように、相手が聞き取りやすいペースで話すと印象が良くなります。
敬語だけでなく、姿勢や表情も言葉と同じくらい大切です。正しい言葉遣いと丁寧な態度で、信頼されるコミュニケーションを心がけましょう。
②電話・メール・チャットでのマナー
企業とのやり取りは、社会人としての基本的なマナーが試される場です。電話では、まず「お忙しいところ恐れ入ります。〇〇大学の△△と申します」と名乗りましょう。
要件を簡潔に伝え、最後に「よろしくお願いいたします」で締めると印象が良くなります。メールは件名・宛名・本文・署名の構成を整えることが重要です。
件名は簡潔に内容を表し、本文は敬語で丁寧に書きましょう。チャットやオンライン連絡ツールを使う場合も、敬語と誤字脱字に気を配る必要があります。
返信はできるだけ早く、遅くとも24時間以内を意識してください。誠実な対応が信頼関係を築く第一歩です。
③服装・身だしなみの基本
清潔感は就活における最重要ポイントです。服装や身だしなみが整っていないと、どれほど話の内容が良くてもマイナス評価になりかねません。
男性は黒・紺のスーツに白シャツ、シンプルなネクタイが基本です。女性はスーツまたはオフィスカジュアルで、派手なアクセサリーやメイクは避けましょう。
髪型は顔がはっきり見えるように整え、爪や靴の汚れもチェックしてください。香水や柔軟剤の香りが強すぎるのもNGです。身だしなみは「相手に不快感を与えないこと」が基準になります。
自分をよく見せるよりも、清潔で誠実な印象を与えることを意識しましょう。
④面接時の立ち居振る舞い
面接では、話す内容と同じくらい立ち居振る舞いも重要です。入室から退室までの動作一つひとつが、あなたの印象を左右します。
入室時はドアをノックしてから「失礼いたします」と一言添え、背筋を伸ばして入室しましょう。着席は「どうぞ」と言われてから行い、座る際には静かに腰を下ろします。
目線は面接官に合わせ、うなずきながら話を聞く姿勢が大切です。話すときは手を組み、落ち着いた声で丁寧に答えましょう。退室時も「本日はありがとうございました」と挨拶を忘れずに。
こうした基本動作が自然にできることで、誠実で信頼できる印象を与えられます。
⑤オンライン面接のマナー
オンライン面接では、対面とは違うマナーが求められます。まずは通信環境を整え、静かで明るい場所を選びましょう。背景は白やベージュなどの無地がおすすめです。
カメラの位置は目線の高さに合わせ、画面越しでも自然な表情が見えるよう調整します。服装は対面面接と同じくスーツが基本です。開始前にはマイクとカメラをテストし、余裕を持ってログインしてください。
面接中は話すとき以外ミュートにして、相手の話にうなずくなどリアクションを取ると好印象です。終了後は「本日はありがとうございました」とはっきり伝え、退室後にお礼メールを送ると丁寧です。
⑥日程変更・辞退時の連絡マナー
体調不良や予定の重複などで面接日を変更・辞退する場合は、早めに連絡を入れることがマナーです。無断欠席は絶対に避けましょう。
連絡はメールまたは電話で行い、「ご迷惑をおかけし申し訳ございません」と誠意を伝えたうえで、再調整をお願いしてください。
辞退する場合も感謝の気持ちを忘れず、「貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と添えると印象が良くなります。
誠実な対応を心がければ、今後の選考や他社での印象にも良い影響を与えます。ビジネスの場では「報連相(報告・連絡・相談)」が信頼の基本です。
⑦SNSやネット上のマナー
近年、企業は採用前に応募者のSNSをチェックすることがあります。投稿内容や写真、コメントなどが評価に影響する場合もあるため、ネット上での言動にも注意が必要です。
炎上や悪口、過度な自慢投稿は避けましょう。また、面接や内定に関する情報をSNSに投稿するのも控えるのが無難です。採用機密や企業情報をうっかり漏らすとトラブルになりかねません。
アカウントの公開範囲を見直し、プロフィール写真や投稿内容が社会人としてふさわしいものか確認しておきましょう。ネット上でのマナーを守ることも、現代の就活では「見えない第一印象」といえます。
就活で評価につながる行動と意識すべき項目

就活で評価されるポイントは、単に学歴やスキルだけではありません。企業が重視するのは、社会人としての基本姿勢や成長意欲、そして周囲と協力しながら成果を出せる力です。
ここでは、選考で好印象を与える行動と意識すべきポイントを7つに分けて解説します。
- 主体的に行動する姿勢
- コミュニケーション能力と協調性
- 企業理解と志望動機の一貫性
- 自己PRで伝える強みの具体性
- 社会人マナー・身だしなみの整え方
- 面接での印象を高める態度と表現
- PDCAを回して成長を示す工夫
①主体的に行動する姿勢
企業は「自ら考えて行動できる人」を高く評価します。就活でも、情報を待つだけでなく、自分から動く姿勢が大切です。
たとえば、興味のある業界を調べて説明会に参加したり、OB・OG訪問で現場の声を聞いたりするなど、行動の積み重ねが信頼につながります。また、主体的な行動は面接でも伝わります。
「こう感じたからこう行動した」というエピソードを話すと、思考力と実行力をアピールできます。小さな一歩でも、自分で判断して動く経験を増やしておくことが、社会に出たときの成長につながるでしょう。
②コミュニケーション能力と協調性
企業が重視するスキルの上位に必ず入るのが「コミュニケーション能力」と「協調性」です。これは話す力だけでなく、相手の意見を聞き、適切に反応できる力も含まれます。
就活では、グループディスカッションや面接でその姿勢が見られます。意見が対立したときも、相手を否定せず尊重しながら話すことが大切です。
また、協調性はチームで成果を出す経験によって示すことができます。アルバイトやサークル活動などで、自分がどんな役割を果たし、どう貢献したかを具体的に語れるようにしておきましょう。
③企業理解と志望動機の一貫性
面接官は「この学生は本当にうちの会社を理解しているか」を見ています。企業理解が浅いと、志望動機が抽象的になり、説得力を欠いてしまいます。
事前に企業の理念・事業内容・今後の展望を調べ、自分の価値観や目標とどうつながるかを明確にしましょう。
志望動機では、「なぜその企業なのか」「どのように貢献できるか」を一貫して伝えることが重要です。他社にも当てはまる内容ではなく、その企業ならではの特徴に触れると好印象です。
具体的な根拠を示せると、真剣さと熱意が伝わります。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
④自己PRで伝える強みの具体性
自己PRでは、自分の強みを明確にし、根拠となるエピソードを添えて伝えることが求められます。抽象的な表現ではなく、「なぜそれが強みなのか」「どのように発揮したのか」を具体的に説明しましょう。
たとえば「リーダーシップがある」だけではなく、「サークルでチームをまとめ、イベントを成功させた経験がある」といった具体的な成果を述べると説得力が増します。
また、強みを企業の求める人物像と結びつけて語ると、採用担当者に「自社で活躍できそう」と感じてもらいやすくなります。
⑤社会人マナー・身だしなみの整え方
社会人として信頼されるためには、基本的なマナーと清潔感が欠かせません。あいさつや言葉遣い、時間厳守などの基本行動は、どの企業でも重視されます。
服装はTPOを意識し、スーツのシワや靴の汚れに注意しましょう。また、身だしなみだけでなく「態度」も印象を左右します。姿勢を正し、相手の話を聞く姿勢を大切にしてください。
小さな行動の積み重ねが「社会人としての意識」を感じさせます。就活は評価の場であると同時に、社会人マナーを学ぶ場でもあります。
⑥面接での印象を高める態度と表現
面接では、話す内容だけでなく「どのように話すか」が重要です。表情・声のトーン・姿勢など、非言語的な要素も評価対象になります。笑顔で明るく受け答えすることで、前向きな印象を与えられます。
また、質問に対しては簡潔かつ論理的に答えることを意識しましょう。質問の意図を理解した上で、自分の考えを具体的に伝えることが大切です。
緊張してもうまく話せなかった場合は、「もう一度言い直してもよろしいでしょうか」と落ち着いて対応できれば、柔軟性と誠実さを示せます。
⑦PDCAを回して成長を示す工夫
就活では「一度の失敗で終わらせない姿勢」も評価されます。Plan(計画)→Do(実行)→Check(振り返り)→Act(改善)の流れを意識し、次に活かす行動ができる人は成長意欲が高いと見なされます。
たとえば、面接でうまく答えられなかった質問をメモし、次回に備えて改善するなど、小さな積み重ねが自信につながります。採用担当者は「学びを行動に変えられるか」を重視しています。
経験を通して成長を見せられる人こそ、社会で活躍できる人材といえるでしょう。
就活のやり方についてよくある質問Q&A
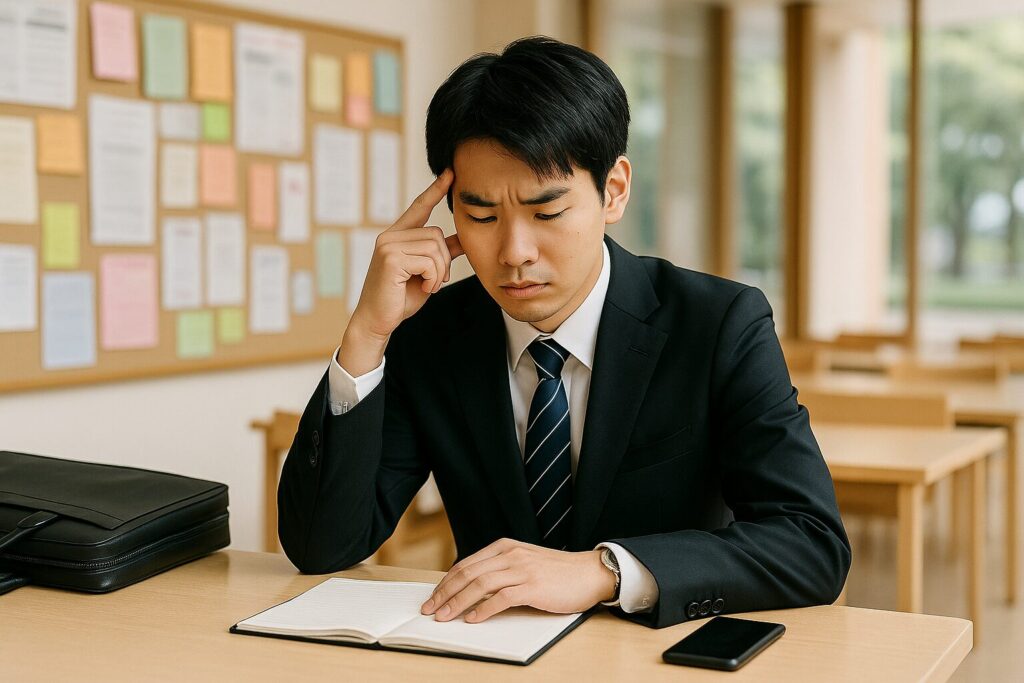
就活を進めていく中で、誰もが一度は「これで合っているのかな?」と悩む瞬間があります。ここでは、多くの学生が抱く疑問や不安に対して、具体的な解決のヒントを紹介します。
悩みを解消しながら、自分らしく就活を進めましょう。
- 就活がうまくいかないときはどうすればいい?
- エントリーシートが通らないときの改善方法は?
- 自己分析がうまくできないときはどうしたらいい?
- 面接で緊張せず話すコツはある?
- 複数の企業から内定をもらったらどう選べばいい?
- 就活で人間関係に疲れたときの対処法は?
- 就活に失敗した場合、卒業後はどうすればいい?
①就活がうまくいかないときはどうすればいい?
就活が思うように進まないときは、自分を責めるよりも「何が原因か」を冷静に見直すことが大切です。選考に落ちる理由は、スキル不足ではなく「準備不足」や「方向性のズレ」であることが多いです。
まずは自己分析と企業研究を再確認し、自分の強みや価値観と志望企業がマッチしているかを見直しましょう。
また、大学のキャリアセンターや就活エージェントに相談すると、客観的なフィードバックが得られます。就活は他人と競うものではなく、自分の納得を見つける過程です。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
焦らず一歩ずつ改善していきましょう。
②エントリーシートが通らないときの改善方法は?
エントリーシート(ES)が通らない場合、文章の「具体性」と「一貫性」に欠けている可能性があります。採用担当者は、応募者の人柄と行動の裏付けを見ています。
自己PRでは、「どんな行動をしたか」「どんな結果が出たか」を具体的に書くことがポイントです。また、企業によって求める人物像は異なるため、全ての企業に同じ内容を提出するのは避けましょう。
企業研究を行い、志望先に合わせてアピール内容を調整すると通過率が上がります。提出前には第三者に添削を依頼し、文章の分かりやすさをチェックすることも効果的です。
③自己分析がうまくできないときはどうしたらいい?
自己分析が進まないと感じたら、無理に結論を出そうとせず、まずは「自分の過去を棚卸し」してみましょう。
学生時代に頑張ったこと、楽しかったこと、悔しかったことなどを時系列で書き出すことで、自分の行動パターンや価値観が見えてきます。
それでも難しい場合は、他人からの意見を取り入れるのもおすすめです。友人や家族、先輩に「自分はどんなタイプか」を聞くと、新しい視点を得られます。
自己分析ツールや診断サイトを活用しても良いでしょう。自己理解は時間をかけて深まるものなので、焦らず少しずつ整理していくのがポイントです。
④面接で緊張せず話すコツはある?
面接で緊張するのは自然なことです。大切なのは「緊張しても伝えられる準備」をしておくことです。想定質問をリスト化し、答えを声に出して練習することで自然な話し方が身につきます。
また、事前に会場やアクセス方法を確認し、当日の不安を減らすことも効果的です。面接中に緊張したら、深呼吸をして目線を面接官に合わせましょう。笑顔で話すことで、印象も良くなります。
うまく話せなかったとしても、「すみません、言い直してもよろしいでしょうか?」と丁寧に対応すれば、誠実さが伝わります。
⑤複数の企業から内定をもらったらどう選べばいい?
複数の内定を得た場合は、「どの会社で自分が最も成長できるか」を基準に考えましょう。給与や福利厚生などの条件も大切ですが、長期的に見て自分のキャリア目標に近づけるかが重要です。
企業の社風や人間関係、仕事の内容を比較し、入社後の自分をイメージしてみてください。また、内定辞退をする場合は、できるだけ早く丁寧に連絡を入れることが社会人としてのマナーです。
感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。
⑥就活で人間関係に疲れたときの対処法は?
就活中は周囲と比較して落ち込むこともありますが、他人のペースに合わせる必要はありません。自分の軸を保つためには、情報から少し距離を置くのも有効です。
SNSや就活仲間との会話で疲れを感じたら、一度リセットしましょう。リフレッシュの時間を意識的に取ることで、気持ちを切り替えられます。
ウォーキングや趣味の時間を設けるなど、自分なりのストレス解消法を見つけてください。就活は長期戦です。無理せず、自分のペースを大切にすることが成功への近道です。
⑦就活に失敗した場合、卒業後はどうすればいい?
万が一、卒業までに内定が決まらなかったとしても、道は閉ざされていません。既卒として就職活動を続ける人も多く、第二新卒や契約社員から正社員登用を目指すケースもあります。
卒業後は、就職エージェントやハローワーク、若者向けの就職支援サービスを活用すると効率的です。また、資格取得やスキルアップの期間に充てるのも有意義です。
就活に失敗することは「人生の終わり」ではなく、「新しい選択肢の始まり」です。自分のペースで前に進めば、次のチャンスをつかめるでしょう。
自分らしく進める就活のやり方と成功へのステップ

就活のやり方がわからないと感じるのは、誰にでもある自然なことです。重要なのは、不安を放置せず、段階を踏んで行動することです。
まず、就活の目的を理解し、自分の軸を明確にすることで、情報の整理と方向性が定まります。次に、全体スケジュールを把握して計画的に進めることで、焦りや迷いを減らせます。
また、準備段階ではスーツや書類、マナーなどの基本を整え、社会人としての意識を持つことが大切です。主体的な行動や誠実な姿勢は、面接での評価にもつながります。
就活は「正解のある競争」ではなく、「自分を理解し、成長するプロセス」です。焦らず一歩ずつ進めれば、必ず納得できる就職先に出会えるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。