履歴書の証明写真の裏には何を書く?記入例と注意点を徹底解説
「履歴書の証明写真って、裏に何か書く必要があるの?」
就活を始めたばかりの人の中には、そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、証明写真の裏にはちょっとした“ひと工夫”が求められます。書く内容や記入方法を間違えると、担当者に雑な印象を与えてしまう可能性も…。
そこで本記事では、証明写真の裏に書くべき内容や記入時の注意点、万が一忘れたときの対処法などを、例文とともにわかりやすく解説します。
印象アップにつながる写真の撮り方や貼り方のコツも紹介するので、これから履歴書を準備する方はぜひ参考にしてみてくださいね。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書の証明写真の裏には何を書くべき?
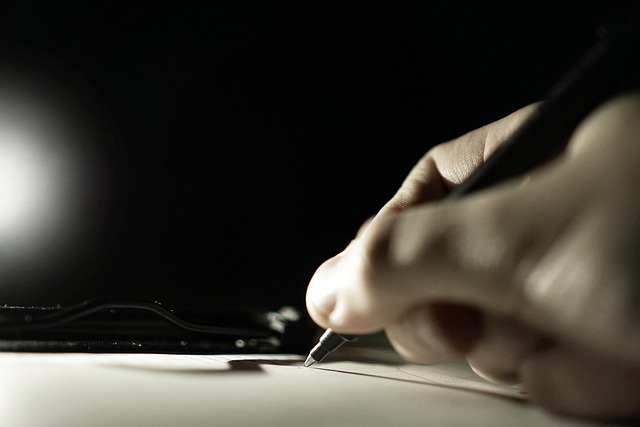
履歴書に貼る証明写真の「裏」にも、実は記入が必要です。
もし、写真が剥がれてしまった場合でも、誰のものかが分かるようにしておくために重要になります。
ここでは、裏面に書くべき3つの情報についてわかりやすく解説しましょう。
- 氏名
- 大学名
- 撮影日
①氏名
証明写真の裏には、必ずフルネームで氏名を記入してください。履歴書は郵送や持ち運びの過程で何度も開閉されるため、写真が剥がれるリスクは決して低くありません。
万一写真が取れてしまっても、裏に名前が書かれていれば、どの応募者のものかすぐに判別できます。
記入する際はボールペンではなく油性ペンを使いましょう。
文字がにじんだりこすれたりしないよう、速乾性のあるペンを選ぶと安心です。また、筆圧をかけすぎると表面に跡が出ることがあるので、適度な力で丁寧に書くことも大切になります。
②大学名
氏名に加えて大学名も記載しておくと、さらに安心です。特に大規模な企業では、同じ苗字やフルネームが一致する応募者が複数いることも考えられます。
その際に大学名が添えられていれば、写真の持ち主を即座に特定しやすくなるでしょう。
略称ではなく、正式な学校名を省略せずに書くことで、書類への丁寧さや誠実な姿勢も伝わりやすくなります。
小さなポイントのように思えますが、こうした細部への気配りは、採用担当者の記憶に残る好印象を生むきっかけになるでしょう。
③撮影日
撮影日を記載しておくことも、就活においては非常に重要です。履歴書の証明写真は、見た目だけでなく「いつ撮影されたか」もチェック対象になります。
企業によっては「3か月以内」や「6か月以内」といった基準を設けている場合もあり、撮影日の明記によって、その条件を満たしているかをすぐに判断が可能です。
特に、デジタルデータからプリントした写真は見た目だけでは日付がわかりにくいため、裏面への記載は信頼性の証になります。
日付は「2025.07.28」のように、西暦と月日を簡潔に表すと見やすく、実務的にも便利です。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
履歴書の証明写真の裏に名前を書く理由

履歴書に貼る証明写真には、裏面に名前を書くことが重要です。
ただ貼るだけでは、万が一写真が剥がれたときに誰のものか分からなくなってしまいます。
ここでは、裏に名前を記入することで得られる3つの効果を紹介します。
- 採用担当者が本人確認しやすくなるため
- 写真が剥がれたときの対策になるため
- 細部まで気を配る人物であることを印象づけられるため
①採用担当者が本人確認しやすくなるため
写真の裏にフルネームを記入しておけば、仮に写真が履歴書から剥がれてしまった場合でも、誰のものかすぐに分かります。
特に採用担当者は、毎日多くの応募書類に目を通すため、1枚の写真で複数の候補者と混同してしまうこともあるでしょう。
名前の記載があることで確認作業がスムーズになり、負担軽減にもつながるのです。
記入する際はフルネームを丁寧な文字で書くようにしましょう。判読しにくい文字では意味がありませんので、くれぐれも雑に書かないようにしてください。
②写真が剥がれたときの対策になるため
履歴書は郵送や面接時のやりとり、社内の回覧などで何度も手渡されるため、写真が剥がれてしまうケースは意外と多くあります。
そのとき、写真の裏に氏名がなければ、誰のものか分からず再添付できなくなるおそれがあるでしょう。
場合によっては、応募者に再提出を依頼する手間が発生し、マイナス印象を与えてしまうかもしれません。一方、名前を書いておけば、剥がれた写真を即座に戻せるため、余計な混乱を防げます。
このように、たった数秒の作業で信頼性のある書類に仕上がるため、必ず記入しておきたいポイントです。
③細部まで気を配る人物であることを印象づけられるため
証明写真の裏に名前を書くことは、法的に義務づけられているわけではありません。しかし、あえてその一手間をかけることで、物事を丁寧に進める姿勢が伝わります。
採用担当者は、書類の正確さだけでなく、そうした小さな配慮に気づける人材かどうかも見ているものです。
細部にまで気を配れる人は、入社後の業務でも信頼されやすく、トラブルを未然に防ぐ力があると評価される可能性があります。
裏書きという細かな配慮を忘れず実行することで、無言のアピールにつながるでしょう。小さな行動が、採用の印象を大きく左右するかもしれません。
履歴書の証明写真の裏に記入する際の注意点
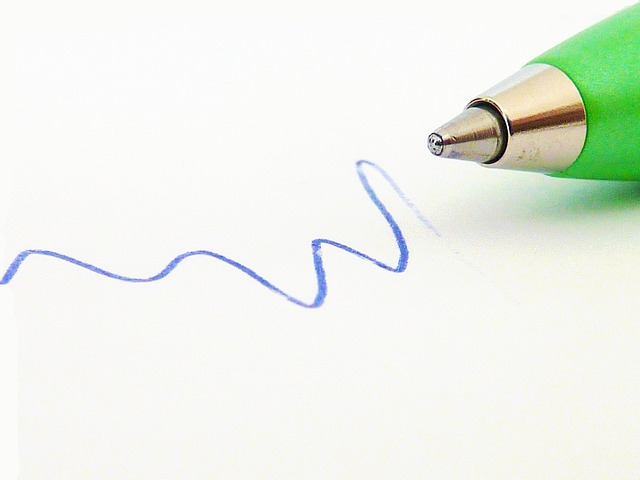
証明写真の裏に情報を記入するときは、ただ書けばよいというものではありません。にじみや透け、書く向きの間違いなど、注意すべき点はいくつかあります。
ここでは、事前に知っておきたい6つのポイントを紹介しています。
- 油性ペンを使用して文字が滲まないようにする
- 文字が写真の表面に透けないように配慮する
- 写真の向きに注意して記入する
- 記入は平らな場所で行う
- しっかり乾かしてから貼る
- のりやテープが記入部分にかからないよう気をつける
①油性ペンを使用して文字が滲まないようにする
証明写真の裏には、必ず油性ペンを使って記入してください。水性ペンはインクが紙に染み込みやすいため、時間が経つとにじんでしまい、せっかく丁寧に書いた文字が読みにくくなるおそれがあります。
特に、履歴書は提出から選考までしばらく保管されるため、文字が劣化しないよう配慮が必要です。
細字タイプの油性ペンであれば、スペースの限られた写真の裏でも見やすく、きれいに仕上がります。
必ず乾きやすいインクを選び、作業中にうっかり手でこすってしまわないよう気をつけましょう。
②文字が写真の表面に透けないように配慮する
筆圧が強すぎたり、濃すぎるインクを使ったりすると、文字が写真の表面に透けてしまうことがあります。
特に光沢タイプの写真は透けやすく、表から見ると文字の跡が不自然に見えてしまい、見栄えを損なってしまうことも。
こうした事態を防ぐには、筆圧を控えめにし、必要以上にインクを出さないよう注意してください。
黒や青といった読みやすく控えめな色の油性ペンを選ぶと、適度な視認性を保ちつつ透けも抑えられるため安心です。細部への気配りが、書類全体の印象を左右します。
③写真の向きに注意して記入する
書くときに上下を間違えると、履歴書に貼ったあとで裏の文字が逆さまになってしまうことがあります。
一度貼ってしまった写真を剥がして書き直すのは手間がかかりますし、見た目も悪くなるおそれがあるでしょう。
そうならないよう、写真の表面をしっかり確認し、上部がどちらかを把握したうえで記入してください。また、裏面に書き始める前に、印として鉛筆で軽く「↑」を仮置きするのもひとつの方法です。
ちょっとした工夫と確認で、こうした失敗は簡単に防げます。
④記入は平らな場所で行う
柔らかい場所や安定しないところで記入すると、文字が歪んだり、写真自体が折れたりする原因になります。
特に力を入れすぎると写真が曲がり、裏面にシワが残ることもあるため注意が必要です。
必ず平らで硬い机の上など、安定した作業環境を選んで記入するようにしましょう。また、落ち着いた空間で作業することで、ミスも防ぎやすくなります。
ペンや写真を清潔な状態で準備し、集中して書ける環境を整えることが、完成度の高い履歴書につながるでしょう。
⑤しっかり乾かしてから貼る
文字を記入してすぐに写真を貼ると、インクが乾ききらずににじむことがあります。そのまま貼りつけてしまうと、履歴書にもインクが移ってしまい、見た目が悪くなる可能性も否定できません。
記入後は数分間、風通しのよい場所に置いて、インクが完全に乾くのを待ってください。特に湿度の高い季節や急いでいるときこそ、乾燥時間をしっかり確保することが大切です。
ほんの少しの待ち時間で、仕上がりの美しさと印象がぐっと良くなります。
⑥のりやテープが記入部分にかからないよう気をつける
写真を貼るときに、のりやテープが裏面の文字部分に重なると、文字がにじんだり読みづらくなったりすることがあります。
さらに、のりの水分やテープの粘着力によって、インクがにじんだりかすれてしまうこともあるため注意が必要です。
写真の四隅や余白部分にだけのりを塗る、または記入箇所を避けて両面テープを使うなどの工夫をしましょう。
見た目の丁寧さはもちろん、書いた情報が正しく残るよう、貼り方にも気を配ることが大切です。
好印象を与える証明写真の撮り方

履歴書に貼る証明写真は、第一印象を左右する重要な要素です。
採用担当者は写真から清潔感や誠実さを感じ取るため、身だしなみに気を配ることが求められます。
ここでは、好印象を与えるために押さえておきたい4つのポイントを紹介しましょう。
- 服装や髪型は面接時と同様に整える
- 背景色は白・青・グレーを選ぶ
- 姿勢は背筋を伸ばして正面を向く
- 歯を見せすぎない自然な笑顔を心がける
①服装や髪型は面接時と同様に整える
証明写真では、面接と同じようにスーツの着用が基本とされています。特に襟元やネクタイのゆがみは、写真になると意外と目立つため、鏡や写真で事前にチェックしておくと安心です。
男性はひげの剃り残しや髪のハネにも注意しましょう。
女性の場合は、前髪が目にかからないように整え、顔全体がはっきりと見えるよう意識することが大切です。
髪が肩より長い場合は、まとめるとすっきりとした印象になります。第一印象に直結する部分だからこそ、細かいところまで配慮して臨みましょう。
②背景色は白・青・グレーを選ぶ
証明写真の背景には、白・青・グレーといった落ち着いた色合いを選ぶのが無難です。
これらの色は顔色を明るく見せ、就活の場にふさわしい誠実さや清潔感を演出してくれるでしょう。
白は明るく清楚な印象、青は知的で爽やかな印象、グレーは落ち着きと安定感を感じさせるといった特徴があります。
撮影時に背景色を選べる機械やスタジオも多いため、可能であれば自分に合った背景色を選びましょう。背景と服装が似すぎると輪郭がぼやけることもあるので、色のバランスも意識してください。
③姿勢は背筋を伸ばして正面を向く
姿勢は、証明写真において清潔感と誠実さを伝える大切な要素です。撮影時には猫背にならないように背筋をピンと伸ばし、肩の力を抜いてリラックスするよう心がけましょう。
顔や体がやや斜めに向いてしまうと、無意識にだらしない印象を与える可能性があります。
椅子に深く座り、あごを引いて、カメラのレンズに目線をまっすぐ向けると、自然なバランスになるでしょう。
短時間の撮影であっても、正しい姿勢を意識するだけで、印象は大きく変わるものです。
④歯を見せすぎない自然な笑顔を心がける
写真の表情は、かたすぎても緊張感が伝わってしまいますが、逆に笑いすぎても軽い印象になりかねません。理想は、口角をほんの少し上げた自然な笑顔です。
歯をすべて見せるような大きな笑いは避け、控えめで落ち着いた表情を目指しましょう。
リラックスして柔らかく微笑むことで、見る人に安心感や親しみを与えることができます。
表情に迷った場合は、事前に鏡で練習してみると、自分にとって一番自然に見える笑顔を見つけやすくなるでしょう。
証明写真を履歴書にきれいに貼るコツ

履歴書に証明写真を貼る際は、見た目の印象だけでなく、写真がしっかりと固定されているかも重要です。
雑に貼ると剥がれやすくなったり、斜めに傾いたりして印象を下げる原因になることも。
ここでは、きれいに仕上げるための4つのポイントを紹介します。
- 貼る前に写真のサイズを確認する
- スティックのりまたは両面テープを使う
- 剥がれにくく、浮かないよう丁寧に貼り付ける
- 貼る前に手や写真を清潔にしておく
①貼る前に写真のサイズを確認する
履歴書には、あらかじめ証明写真のサイズが指定されていることが多く、たとえば縦40mm×横30mmなどと細かく決まっています。
サイズが合っていないまま貼ると、枠からはみ出したり、空白が目立ったりして全体の印象を損なってしまうことも。
写真が大きすぎる場合は、余白を均等に残すように丁寧にカットしましょう。
カットする際は、角をわずかに丸くすると、剥がれ防止にもつながります。ちょっとした手間ですが、見た目の整った履歴書は、それだけで丁寧な印象を与えられるはずです。
②スティックのりまたは両面テープを使う
証明写真を履歴書に貼る際は、水のりではなく、スティックのりか両面テープの使用がおすすめです。
水のりは乾くまでに時間がかかり、のりがはみ出して履歴書の紙が波打ったり、写真がズレたりするリスクが高まります。一方でスティックのりは、乾きが早く、のりの量を調整しやすい点が利点です。
写真の四隅や中心部分にも均一に塗ると、浮きやすい角までしっかり固定できます。
両面テープを使う場合は、写真の端ギリギリまで貼るように意識すると、より密着感のある仕上がりになるでしょう。
③剥がれにくく、浮かないよう丁寧に貼り付ける
証明写真を貼るときは、貼り付け位置の確認がとても重要です。左右の余白が不均等だったり、写真が傾いていたりすると、相手に雑な印象を与えてしまいかねません。
まずは履歴書の枠内で、まっすぐ中央に配置されるように仮置きしてみてください。
位置が決まったら、ゆっくりとズレないように貼り付けます。
その後、指の腹や清潔な布で上からそっと押さえ、全体がしっかり密着するようになじませましょう。少しのずれや浮きでも印象に差が出るため、丁寧に仕上げる意識が大切です。
④貼る前に手や写真を清潔にしておく
証明写真は、見た目の印象が第一です。そのため、貼る前には必ず手を洗い、皮脂や汚れを落としておきましょう。
手の油分がつくと、写真に指紋や汚れが残りやすくなり、せっかくの写真が台無しになるおそれがあります。
特に、顔の周辺や背景が指紋で曇っていると、清潔感に欠けた印象を与える可能性も。
また、写真自体もやわらかい布で軽く拭いておくと安心です。小さなことに思えるかもしれませんが、こうした気配りが、就活書類全体の印象を左右する大きな要因になるでしょう。
履歴書の証明写真の裏に名前を書き忘れた場合の対処法

証明写真を履歴書に貼り終えたあとで、裏に名前を書いていないことに気づくと不安になるかもしれません。
しかし、焦らず落ち着いて対応すれば問題は避けられます。
ここでは、状況に応じた対処法を3つ紹介しています。
- 別の紙に記入して貼り直す
- 写真を再印刷して撮り直す
- 氏名を書いたメモを同封する
①別の紙に記入して貼り直す
すでに履歴書に貼り終えてしまった証明写真でも、慎重に扱えばきれいにはがせることがあります。
はがす際は、ドライヤーの温風を使ってのりを少し温めると、接着が緩みやすくなり、破れや傷を防ぎやすくなります。
無理に力を入れると履歴書が破れてしまうリスクがあるため、角からゆっくりとはがすようにしましょう。
写真が無事にはがれたら、裏面に氏名を油性ペンで記入し、インクをしっかり乾かしたうえで、改めて丁寧に貼り直してください。履歴書自体にシワや汚れがなければ、この方法で十分対応できます。
②写真を再印刷して撮り直す
どうしても写真をはがすのが難しい場合や、履歴書にダメージが残ってしまった場合は、新しく証明写真を用意するのがもっとも確実です。
写真の再印刷や撮影は手間と費用がかかりますが、仕上がりの美しさや印象の良さを考えると、結果的にプラスになることも多いでしょう。
新しい写真には、提出前に忘れず裏面への記入を行ってください。特に、就活では細部への配慮が評価につながる場面もあるため、こうした丁寧な対応は志望度の高さを示すアピールにもなります。
③氏名を書いたメモを同封する
もし、証明写真の貼り直しも再印刷も間に合わない場合は、やむを得ず簡単なメモを添える方法もあります。
たとえば「写真裏面に記名漏れがありましたので、氏名を記載したメモを同封いたします」といった文面で、氏名を明記した紙を添えて提出しましょう。
ただし、この方法は企業によって対応が異なるため、推奨されるものではありません。特に厳格な企業や公的な書類を求めるケースでは不備と判断される可能性もあります。
可能であれば、再撮影や貼り直しといった手段を優先的に検討したほうが安心です。
履歴書写真の裏に関するよくある質問(Q&A)

証明写真の裏にまつわるルールやマナーには、見落としやすいポイントが多くあります。
貼り方や記入の有無で評価が下がるのは避けたいところです。
ここでは、就活生が疑問に思いやすい5つの質問とその答えをまとめました。
- 写真の裏に名前を書かないとどうなる?
- 証明写真はいつ撮るのがベスト?
- 証明写真の裏に間違えて書いた場合はどうする?
- 履歴書をPDFで提出する場合、裏書きは必要?
- 裏面がシールタイプの証明写真にはどう記入する?
①写真の裏に名前を書かないとどうなる?
証明写真の裏に名前を記載していないと、写真が履歴書から剥がれてしまった際に、誰のものかが判別できなくなる可能性があります。
特に、企業では多くの応募書類が集まるため、写真と履歴書がバラバラになってしまったときに、照合が困難になるおそれも。
その結果、本人確認ができずに書類が正しく扱われないリスクもあるでしょう。
たった一言の記入でも、選考をスムーズに進めてもらうための配慮になります。提出前には、フルネームがきちんと記載されているか、必ず確認してください。
②証明写真はいつ撮るのがベスト?
証明写真は、撮影から3か月以内のものを使用するのが一般的なマナーとされています。
時間が経つと髪型や顔つきが変わってしまい、現在の印象と異なって見えることもあるため、企業側としても直近の写真のほうが安心できるのです。
エントリー開始のタイミングを見越して、余裕をもって撮影のスケジュールを立てましょう。複数の企業に提出する予定がある場合は、まとめて複数枚を用意しておくと、必要なときにすぐ対応できます。
急ぎで撮り直す必要がないよう、事前準備が肝心です。
③証明写真の裏に間違えて書いた場合はどうする?
裏面に記入した際に誤字や記入ミスをしてしまった場合、修正液やテープでの訂正は避けたほうが無難です。
修正した跡が残ると見た目が不自然になり、丁寧さや誠実さに欠ける印象を与えてしまう可能性があります。
スペースが限られている証明写真の裏では、多少の書き間違いでも目立ちやすいため、潔く写真を撮り直すか、予備の写真に差し替えるのがベストです。
こうした丁寧な対応こそが、社会人としての信頼感にもつながる行動といえるでしょう。
④履歴書をPDFで提出する場合、裏書きは必要?
オンラインでPDFとして履歴書を提出する場合、証明写真の裏に物理的な記入をすることができません。このような場合には、ファイル名を工夫して、氏名や撮影日を含めるといった代替手段があります。
たとえば、「田中太郎_証明写真_2025年7月撮影」といった形で管理しておくと、企業側も本人確認がしやすくなるでしょう。
一方で、面接時などに履歴書を紙で提出するケースも想定されるため、印刷する場合には、通常どおり裏書きをしておくとより安心です。両方のパターンに備える心がけが大切になります。
⑤裏面がシールタイプの証明写真にはどう記入する?
シールタイプの証明写真を使う場合でも、裏に記名する基本は変わりません。はがす前の状態で、シールの台紙部分に油性ペンでフルネームを記入してください。
その際、インクが乾く前に貼ってしまうと、にじんだり他の紙を汚したりする可能性があるため、必ず数分間しっかりと乾燥させましょう。
もし、どうしても記入が難しい場合は、別紙に「氏名・写真記名漏れの旨」を記して同封するなど、補足の工夫をするとよいでしょう。状況に応じて柔軟に対応することが信頼感にもつながります。
履歴書写真の裏書きで印象アップを狙うために

履歴書に貼る証明写真の裏には、氏名・大学名・撮影日などを記入するのが基本です。
これは写真が剥がれても本人を特定できるようにするためであり、採用担当者への配慮としても重要なマナーといえるでしょう。
さらに、油性ペンの使用や記入時の姿勢など、書き方にも注意が必要です。服装や表情といった写真そのものの印象づくりも大切ですが、写真をきれいに貼り付けるひと手間も見逃せません。
裏書きを忘れてしまった場合は再撮影や追記の工夫で対処できます。就活での第一印象は細部で決まります。履歴書の証明写真の裏にまで気を配り、自分らしさと丁寧さを伝えていきましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









