履歴書の証明写真の貼り方|のり・位置・注意点を完全ガイド
就活の書類選考で第一印象を左右するのが履歴書の証明写真です。貼り方が雑だったり位置がずれていたりすると、それだけでマイナス評価を受けることもあります。
この記事では、履歴書の写真の貼り方の基本からのりの使い方、Web履歴書での貼り方まで、わかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書に貼る証明写真とは?

履歴書に使用する写真には明確なルールがあります。ただの顔写真を貼るのではなく、採用担当者に好印象を与える「証明写真」であることが大切です。
ここでは、就活生が履歴書に貼るべき証明写真の基準や条件について、具体的に解説していきます。
- 履歴書に貼る写真は証明写真が必須である
- 証明写真のサイズは縦40mm×横30mmが基本である
- 証明写真は撮影から3ヶ月以内のものを使用する
- 背景は白・青・グレーなど無地である必要がある
- 証明写真はカラーで印刷する
- スマホで撮影した写真は適切な画質・形式であれば使用できる
- 提出形式によって写真は紙かデータで用意する必要がある
①履歴書に貼る写真は証明写真が必須である
履歴書に貼る写真は、証明写真でなければなりません。証明写真は就活用に適した画角や表情、構図が整っており、採用担当者が第一印象を判断するための大切な材料です。
私服やスナップ写真を使うと、マナー違反と受け取られ、書類選考の時点で不利になってしまうでしょう。スーツを着て、自然な笑顔で正面を向いた写真を選ぶことが基本です。
新卒採用では社会人としての基本が備わっているかも見られます。だからこそ、きちんとした証明写真を用意することが大切です。
②証明写真のサイズは縦40mm×横30mmが基本である
履歴書に使う証明写真は、縦40mm×横30mmが一般的です。このサイズから大きくずれていると、所定の枠に収まらなかったり、見た目のバランスが崩れてしまったりするおそれがあります。
市販の履歴書には写真枠が印刷されていることが多く、サイズをきちんと合わせる必要があります。Web履歴書でもこのサイズ感を基準にして画像を調整することが望ましいでしょう。
見た目の整った履歴書は、丁寧な人柄を印象づけるきっかけにもなります。
③証明写真は撮影から3ヶ月以内のものを使用する
証明写真は、撮影から3ヶ月以内のものを使うのが原則です。外見は短期間でも変化するため、最新の状態を正確に伝える必要があります。
たとえば髪型や表情が変わっていれば、面接時に写真とのギャップが生じて違和感を持たれるかもしれません。写真スタジオでは日付入りのデータをもらえることもあり、管理にも役立ちます。
企業によっては明確に「3ヶ月以内」と指定している場合もありますので、古い写真の使用は避けてください。
④背景は白・青・グレーなど無地である必要がある
証明写真の背景は、白・青・グレーなどの無地が基本です。背景に模様があったり、他の人物や物が写り込んでいたりすると、写真としての信頼性が下がります。
清潔感や誠実さを伝えるためにも、背景選びは意外に重要なポイントです。白は明るく爽やかな印象を、青は知的で落ち着いた印象を、グレーは無難でフォーマルな印象を与える傾向があります。
写真館やスピード写真機ではこうした背景があらかじめ設定されているので、安心して選べるでしょう。
⑤証明写真はカラーで印刷する
履歴書に貼る証明写真は、必ずカラーで印刷しましょう。白黒写真では表情や顔色がわかりづらく、相手に暗い印象を与えてしまう可能性があります。
就活では、第一印象が選考に大きな影響を与えるものです。だからこそ、自然で鮮明なカラー写真が適しています。自宅のプリンターで印刷する場合は、画質に注意してください。
できるだけ写真店やスピード写真機を利用し、安定した品質の写真を用意するのが無難です。
⑥スマホで撮影した写真は適切な画質・形式であれば使用できる
最近のスマホは高性能なので、条件を満たせば履歴書用の写真にも使えます。ただし、解像度が低い、自撮り風、背景が適切でないといった写真は避けましょう。
背景は白い壁、光の入り方も確認し、三脚を使うか、他の人に撮ってもらうのが安心です。アプリを使って背景を処理するのも構いませんが、過度な加工は逆効果でしょう。
写真館に行くのが難しい場合でも、最低限のマナーと品質を守れば、スマホ写真でも十分対応できます。
⑦提出形式によって写真は紙かデータで用意する必要がある
履歴書の提出方法によって、写真は紙で用意するか、データで準備する必要があります。郵送や手渡しなら、印刷された証明写真を貼り付けましょう。
一方で、WebエントリーではJPEGやPNG形式のデータをアップロードするのが一般的です。その際、ファイル名やサイズ、解像度にも注意が必要。
提出先の指示に従って、適切な形式で準備することで、書類全体の印象を良くすることができます。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
履歴書の証明写真の撮り方

履歴書に貼る証明写真は、ただ写っていればいいというものではありません。企業に好印象を与えるには、撮影方法や服装、表情まで意識することが大切です。
ここでは、就活生が証明写真を撮る際に気をつけたいポイントをわかりやすく整理して紹介します。
- 写真館やフォトスタジオで撮影する
- スピード写真機を利用する
- スーツなど就活に適した服装を着用する
- 髪型・メイク・身だしなみにを整える
- 表情は口を閉じた自然な笑顔を心がける
- 写真撮影に適した背景と明るさを選ぶ
- 加工のしすぎは避け、自然な印象を保つ
①写真館やフォトスタジオで撮影する
証明写真は、できれば写真館やフォトスタジオで撮影するのが安心です。プロの手によって表情や姿勢、光の当たり方まで調整してもらえるため、仕上がりの質がぐっと高まります。
特に、第一印象が大切な就活では、清潔感や誠実さをしっかり伝えることが重要です。写真館ではそれらを自然に引き出してくれる環境が整っています。
費用はかかりますが、合否に関わる印象づくりと考えれば、十分価値のある投資といえるでしょう。
②スピード写真機を利用する
コストや時間の面で、手軽に利用できるのがスピード写真機です。最近では、就活用モードを備えた高品質タイプも登場しており、それなりの仕上がりが期待できます。
ただし、自分自身で表情や姿勢を整える必要があるため、撮影前にしっかり鏡で確認してください。椅子の高さやカメラ位置にも注意し、目線がずれないよう気をつけましょう。
撮り直し可能な機種もあるので、納得いくまで何度か試すのがおすすめです。
③スーツなど就活に適した服装を着用する
証明写真の服装は、基本的にリクルートスーツが適しています。黒や紺のスーツに白いシャツが定番で、清潔感や信頼感を与えるスタイルです。
シャツの襟元やボタンの留め忘れ、スーツのシワなどは意外と目立つため、撮影前に入念にチェックしておきましょう。私服やカジュアルな服装では、ビジネスの場にそぐわない印象を与えてしまいます。
服装の整え方ひとつで、印象は大きく変わるでしょう。
④髪型・メイク・身だしなみにを整える
証明写真で見た目の印象を決めるのは、髪型やメイク、そして全体の身だしなみです。髪は顔が隠れないよう整え、前髪が目にかからないようにすると明るい印象になります。
メイクはナチュラルを心がけ、濃くなりすぎないようにしてください。男性も無精ひげや寝ぐせなどに注意し、清潔に整えてから撮影に臨みましょう。
小さな部分でも気を抜かず、全体のバランスを意識することが信頼感につながります。
⑤表情は口を閉じた自然な笑顔を心がける
証明写真の表情は、口を閉じた自然な笑顔が理想です。真顔だと硬い印象に、逆に笑いすぎると軽く見られてしまうことがあります。ポイントは、口角をほんの少し上げる程度の穏やかな笑顔です。
無理なく自然な表情を心がけると、安心感や人柄が伝わりやすくなります。撮影前に鏡で表情をチェックしたり、撮影スタッフに相談したりして、自分に合った表情を見つけましょう。
⑥写真撮影に適した背景と明るさを選ぶ
背景と明るさも、証明写真において大切な要素です。背景は白や青、グレーなど無地のものを選び、余計なものが写り込まないようにしましょう。
顔に均等に光が当たることで、肌の色が自然に見え、全体の印象も明るくなります。暗い場所や影が強い環境では撮影しないよう気をつけてください。
写真館や高性能のスピード写真機を使えば、背景や光の調整が自動で行われるため安心です。
⑦加工のしすぎは避け、自然な印象を保つ
近年はアプリで写真を簡単に加工できますが、証明写真ではやりすぎないことが基本です。目を大きくしたり、肌を極端に補正したりすると、かえって不自然に見えることがあります。
面接時に写真と印象が大きく違えば、信頼性を損ねてしまうおそれもあるでしょう。必要であれば明るさや背景処理程度にとどめてください。
あくまで「自分らしさ」を保ち、自然で清潔感のある仕上がりを目指すことが重要です。
履歴書証明写真の貼り方の基本

履歴書に貼る証明写真は、ただ貼ればよいわけではありません。貼り方ひとつで印象が大きく変わるため、正しい方法を知っておくことが重要です。
ここでは、就活生が迷わずきれいに貼れるよう、基本の手順をわかりやすく解説します。
- 証明写真は履歴書の指定欄に貼り付ける
- 証明写真の裏面には氏名・大学名・撮影日を記入する
- スティックのりまたは写真用両面シールを使用する
- 写真を貼る位置はズレや傾きがないように注意する
- 貼付後は上から軽く押さえてしっかり固定する
- 写真がはがれないよう封入前に再確認する
①証明写真は履歴書の指定欄に貼り付ける
証明写真は、履歴書に設けられた指定の欄にまっすぐ貼り付けることが基本。ずれていたり、欄からはみ出したりすると雑な印象につながるため注意が必要です。
履歴書の種類によって写真枠の大きさが微妙に異なる場合があるため、事前に確認し、サイズを調整しておくと安心でしょう。
位置合わせに自信がない場合は、軽く目印を付けてから貼ると失敗しにくくなります。第一印象を左右する部分だからこそ、丁寧な作業が大切です。
②証明写真の裏面には氏名・大学名・撮影日を記入する
証明写真の裏には、氏名・大学名・撮影日を記入しておきましょう。万が一はがれた際でも、誰の写真かすぐに判断してもらえます。
記入には、油性ペンのようなにじみにくい筆記具を使い、文字が写り込まないよう強く書きすぎないようにしてください。ペン選びを間違えると、インクが染みて表面に影響することもあります。
小さな配慮ですが、丁寧な対応が印象を左右するポイントになるでしょう。
③スティックのりまたは写真用両面シールを使用する
写真の貼り付けには、スティックのりか写真用両面シールを使用するのが最適です。液体のりは量の調整が難しく、紙が波打つ原因になるため避けたほうが無難でしょう。
スティックのりなら均一に塗りやすく、写真がずれにくいため使いやすいでしょう。両面シールは手が汚れにくく、貼り付けの手間も少ないという利点があります。
どちらを選んでも問題はありませんが、自分に合った方法で確実に固定することが大切です。
④写真を貼る位置はズレや傾きがないように注意する
写真を貼る際は、枠の中心にまっすぐ貼ることを意識してください。ズレていたり傾いていたりすると、全体の印象がだらしなく見えてしまいます。
貼る前に位置を確認し、可能であれば鉛筆で軽く印を付けると安心です。貼り直しが難しい素材もあるため、最初から正確な位置に置くよう心がけましょう。
小さなことですが、丁寧に貼られた写真は、見る人にきちんとした印象を与えてくれます。
⑤貼付後は上から軽く押さえてしっかり固定する
写真を貼り付けたら、上から指でやさしく押さえてしっかり固定しましょう。特に、四隅と中央部分を均等に押さえることで、浮きやはがれを防げます。
強く押しすぎると写真が折れたり、のりがはみ出したりするおそれがあるため、力加減には気をつけてください。
空気が入っていると見栄えが悪くなるので、貼るときに軽く中央から外側に向けて押すときれいに仕上がります。ひと手間加えることで、完成度が大きく変わるでしょう。
⑥写真がはがれないよう封入前に再確認する
履歴書を封筒に入れる前に、写真がしっかり貼れているか必ず確認してください。端が浮いていたり、接着が甘かったりすると、封入時や配送中に写真がはがれてしまうことがあります。
特に、履歴書が他の書類と一緒に扱われる場面では、思わぬ摩擦や圧力がかかることもあるでしょう。
封をする前に四隅を軽く押さえ、確実に固定されているかを確かめてから封入するようにしてください。最終チェックで安心感もアップします。
履歴書の証明写真を貼る際の注意点
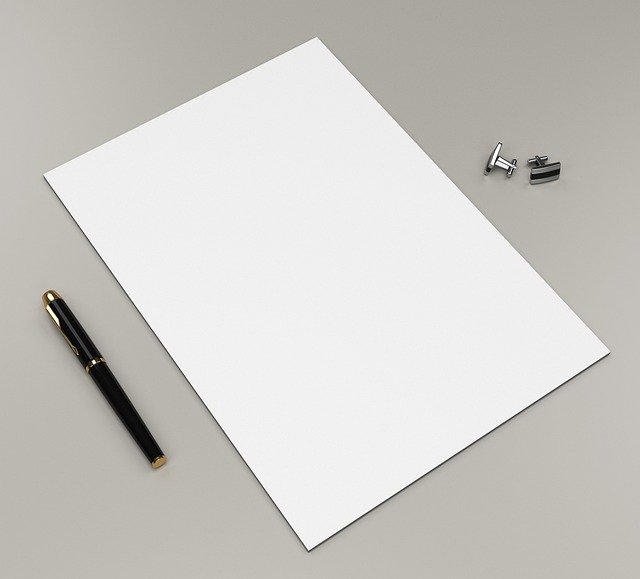
履歴書に証明写真を貼るときは、細かな配慮が重要です。小さなミスが第一印象を下げる原因にもなりかねません。ここでは、証明写真を貼る際に気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。
- 証明写真のサイズを必ず確認する
- 履歴書の余白の位置をチェックする
- 貼る前に手を清潔にしておく
- 汚れた写真やシワのある写真の使用は避ける
- のりがはみ出さないように貼る
①証明写真のサイズを必ず確認する
証明写真の基本サイズは、縦40mm×横30mmです。履歴書に印刷された枠としっかり一致しているか、貼る前に必ずチェックしましょう。
サイズが合わないと、写真が枠からはみ出したり隙間ができたりして不自然な印象を与えてしまいます。
特に、履歴書を印刷したあとに写真を貼る場合は、枠のサイズが異なることもあるため注意が必要です。万一サイズが合わないときは、余白をカットして調整しましょう。
貼り付ける前の確認が、きれいな仕上がりにつながります。
②履歴書の余白の位置をチェックする
写真を貼るときは、履歴書の見た目全体のバランスも意識しましょう。枠の中央に写真を配置できていないと、雑な印象になってしまうことがあります。
写真の上下左右の余白を均等にし、まっすぐ貼ることが大切です。枠がある場合は目安にしやすいですが、ない場合は軽く下書きをしてから貼ると安心でしょう。
③貼る前に手を清潔にしておく
証明写真を貼る前に、手をしっかり清潔にすることも忘れてはいけません。手についた皮脂やインク汚れが写真につくと、見た目が悪くなるだけでなく、紙自体を汚してしまうおそれがあります。
作業を始める前に、石けんで手を洗うか、ウェットティッシュで軽く拭き取るようにしましょう。特にのりや両面シールを扱う際は、指先の汚れが付きやすくなるため注意が必要です。
④汚れた写真やシワのある写真の使用は避ける
一度使ったものや、保存状態が悪くてシワや汚れが付いた写真は避けましょう。たとえ内容が立派な履歴書でも、写真に汚れや折れがあるだけで「雑な人」という印象を与える原因になります。
証明写真は、常にきれいな状態のものを使用することが基本です。
財布に入れて持ち歩いたり、長期間保存したりしている写真は、意外と傷や折れ目がついていることがあるので、提出前にしっかり確認してください。少しでも不安があれば、撮り直すことをおすすめします。
⑤のりがはみ出さないように貼る
証明写真を貼るときに、のりが枠外にはみ出してしまうと、仕上がりが不格好になり清潔感が損なわれます。使用するのりは、スティックタイプか、写真専用の両面テープが適しています。
液体のりはにじみやすいため、避けたほうが無難です。のりを塗るときは、写真の端まで均一に塗るようにし、貼り付けたあとはやさしく上から押さえて、しっかり固定しましょう。
しっかりと密着させることで、郵送中にはがれるのを防げます。
パソコン作成の履歴書に写真を貼る方法(Word・Excel対応)

履歴書をパソコンで作成する場合、写真の貼り方にはいくつかの注意点があります。WordやExcelで作成した履歴書は、デジタルならではの操作や配慮が必要です。
ここでは、データ形式で履歴書を提出する際の写真の貼り方について具体的に説明します。
- Wordには「挿入」機能で写真を貼り付ける
- Excelには「画像挿入」機能で写真を配置する
- 写真のサイズは、画像の比率を崩さず40mm×30mmに調整する
- 企業によっては印刷+写真貼付を求める場合がある
①Wordには「挿入」機能で写真を貼り付ける
Wordで履歴書を作成する際は、「挿入」タブの中にある「画像」機能を使い、保存した証明写真のファイルを選んで貼り付けます。
写真を挿入したら、クリックして表示される「図の書式設定」メニューからサイズや位置を調整しましょう。特に、縦横比の固定にチェックを入れておくことで、写真の形が崩れるのを防げます。
さらに、文字や表組みとの位置関係が不自然になっていないかを確認することも大切です。見た目の整ったレイアウトは、印象を大きく左右するポイントになります。
②Excelには「画像挿入」機能で写真を配置する
Excelで履歴書を作成する場合も、「挿入」タブの「画像」から証明写真を追加しましょう。
セルの中に写真を配置するケースが多いですが、そのままだとサイズ変更や移動の際にレイアウトが乱れることがあります。
写真を選択した状態で「セルに合わせてサイズを変更しない」に設定すると、位置が安定し、ズレを防ぎやすくなるでしょう。
また、Excelは自由にデザインできる反面、レイアウトが崩れると全体の印象が悪くなる可能性があるため、グリッド線や図形のガイド機能を活用して、整った配置を心がけてください。
③写真のサイズは、画像の比率を崩さず40mm×30mmに調整する
履歴書に使用する証明写真の推奨サイズは、縦40mm×横30mmです。これは紙に貼る場合だけでなく、デジタルでも同様に守る必要があります。
画像のサイズを変更する際は、四隅をドラッグして感覚的に調整するのではなく、「図の書式設定」やプロパティ画面で数値を直接入力する方法が確実です。
比率を間違えて写真が引き伸ばされたり潰れたりすると、相手に違和感を与える可能性があります。見た目の自然さを保つためにも、正確なサイズ設定を意識してください。
④企業によっては印刷+写真貼付を求める場合がある
履歴書をパソコンで作成しても、応募先の企業によっては、紙に印刷した履歴書に写真を手で貼り付けるよう指定されることもあります。
その場合は、あらかじめ写真欄を空白にして印刷し、証明写真をスティックのりや写真用両面テープで丁寧に貼りましょう。
貼付後はしっかり固定し、はがれやすくないかを確認することも忘れないでください。また、提出方法について指示がある場合は必ずそれに従いましょう。
マナー違反と捉えられないためにも、送付前の最終チェックを欠かさないことが大切です。
Web履歴書に貼る写真データのファイル名と保存形式

Web履歴書を提出する際は、写真データの形式やファイル名にも注意が必要です。不適切な形式やサイズのファイルは開けなかったり、企業側に不快な印象を与えたりするおそれがあります。
ここでは、スムーズに履歴書を提出するための写真データの保存と命名ルールを紹介しましょう。
- 証明写真はJPEGまたはPNG形式で保存する
- ファイルサイズは1MB以内に抑える
- 写真データの解像度は300dpi程度にする
- ファイル名は「姓_名_履歴書.jpg」と明記する
- ファイル名には記号や全角文字の使用を避ける
- 企業ごとの指定がある場合は必ず従う
①証明写真はJPEGまたはPNG形式で保存する
Web履歴書に使用する証明写真のデータ形式は、基本的にJPEGまたはPNGで保存するのが適切です。これらの形式は汎用性が高く、多くの企業が問題なく開けるため安心できます。
特にJPEG形式は圧縮率が高く、データ容量を抑えやすいため、提出時のトラブルを防ぎやすいのが特長です。
反対に、TIFFやBMPなど特殊なファイル形式は、閲覧できない可能性があるため避けてください。使用形式の明記がない場合は、JPEGを選ぶのが無難です。
②ファイルサイズは1MB以内に抑える
企業によっては、メール添付やWebフォームからの提出の際に、ファイルサイズの上限を設けているケースがあります。
写真データが大きすぎると、アップロードに時間がかかる、あるいは受付自体が弾かれる可能性もあるため、1MB以下に抑えておくのが賢明です。
画質を維持したまま容量を小さくするには、画像編集ソフトやオンラインツールを使って圧縮処理を行いましょう。提出前に、ファイルサイズの確認を怠らないことが大切です。
③写真データの解像度は300dpi程度にする
Web履歴書でも、印象に直結する証明写真はできるだけ鮮明なものが望ましいです。そのため、画像の解像度は300dpi前後を目安に設定するのが基本となります。
低解像度では顔の輪郭がぼやけて見えることがあり、第一印象を下げかねません。一方で、解像度を高くしすぎるとファイルサイズが大きくなり、提出が難しくなる場合もあります。
適度な画質と容量のバランスを意識しながら調整してください。
④ファイル名は「姓_名_履歴書.jpg」と明記する
提出する写真データのファイル名には、必ず氏名を含めましょう。「姓_名_履歴書.jpg」のように明確な名前をつけることで、採用担当者が、誰のデータなのかひと目で把握できます。
また、アンダーバーで姓と名を区切ることで視認性が上がり、ファイルの整理や管理も容易になるでしょう。ファイル名の末尾には拡張子を付け忘れないようにし、企業側が開けるようにしてください。
⑤ファイル名には記号や全角文字の使用を避ける
ファイル名に「@」「&」などの記号や、全角文字(例:「あ」「A」など)を使用すると、企業側の環境によっては読み込めなかったり、文字化けしてしまうリスクがあります。
特に、自動でデータを管理している企業では、文字コードの不一致によって処理が正しく行われないこともあるでしょう。
半角の英数字のみで構成された、シンプルで分かりやすい名前をつけるように心がけてください。
⑥企業ごとの指定がある場合は必ず従う
企業によっては、履歴書の提出形式に細かい指定がされていることがあります。たとえば、ファイル形式をPDFに限定していたり、写真データを別添にするよう求めていたりするケースなどが考えられます。
このような指定を無視して提出すると、内容に問題がなくても不備扱いとされる可能性があるかもしれません。
応募要項や送付前のメール、企業の採用ページをしっかり確認し、求められた通りに準備を整えてください。ミスなく提出することが、良い印象につながる第一歩です。
履歴書の写真を正しく貼るために大切なポイントとは
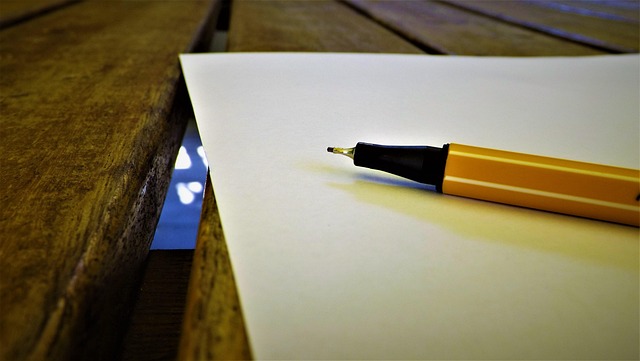
履歴書に貼る写真の貼り方ひとつで、採用担当者の第一印象が大きく変わる可能性があります。
写真は証明写真を使うのが基本であり、サイズや撮影日、背景の色にも細かなルールがあるものです。
さらに、WordやExcelで作成した履歴書、あるいはWeb履歴書においても、写真の貼り方やファイル形式に注意しなければなりません。
適切な方法で撮影・加工し、正確なサイズで貼ることで、履歴書の完成度がぐっと高まります。履歴書の写真貼り方をしっかり理解し、好印象を与える就活準備を進めてください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









