履歴書用紙サイズの基本ガイド|証明写真・印刷・封筒まで完全対応
「履歴書って、A4とB5どっちのサイズを使えばいいの?」と就活を始めたばかりの人や転職活動中の人の中には、履歴書の用紙サイズで迷う人も多いのではないでしょうか。
企業によってはサイズを指定している場合もあり、間違えると印象を悪くしてしまうこともあります。
そこで本記事では、「履歴書 用紙 サイズ」に関する基本的な知識から、それぞれのメリット・デメリット、証明写真・封筒・印刷時の注意点まで、徹底的に解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ESをAIに丸投げ|LINEで完結
- 完全無料でESを簡単作成
- 2赤ペンESで添削依頼|無料
- 就活のプロが丁寧に添削してくれる
- 3志望動機テンプレシート|簡単作成
- カンタンに志望動機が書ける!
- 4自己PR自動作成|テンプレ
- あなたの自己PRを代わりに作成
- 5企業・業界分析シート|徹底分析
- 企業比較や選考管理もできる
履歴書の適切な用紙サイズは?

就活で履歴書を提出する際、「用紙はどのサイズが良いのか」と不安に感じる人も多いでしょう。
結論から言えば、履歴書のサイズはA4かB5が一般的であるため、どちらかであれば問題ありません。ただし、それぞれに特徴があり、選び方にはポイントがあります。
近年は、A4サイズを使うケースが増えてきており、職務経歴書やエントリーシートといった他の書類と揃えやすい点でも選ばれる傾向にあります。
一方で、B5サイズは少し小さめで、志望動機や自己PRなどの記入欄も限られています。そのぶん、短時間で記入を終えたい人や、内容をコンパクトにまとめたい方には扱いやすいかもしれません。
まずは、企業からサイズの指定がないか確認してください。指定がある場合は、それに従うのが基本です。もし特に指示がなければ、A4サイズを選んでおくと安心でしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
A4サイズとB5サイズの違い

それぞれ見た目や記入量、提出時の印象にも違いがあるため、特徴を理解しておくと選びやすくなります。どちらを選ぶべきか迷っている方は、ここで違いをしっかり確認しておきましょう。
A4は記入スペースが広く、自己PRや職務経歴を丁寧に書きたい人に向いています。最近はA4を指定する企業も増えており、主流になりつつあります。
一方、B5は全体的にコンパクトで、情報が少ない場合でも空欄が目立ちにくいため、簡潔にまとめたい方に適しているでしょう。B5サイズはやや昔ながらの印象を与える可能性も否定できません。
履歴書のサイズに正解はありませんが、内容の分量や企業の指定に合わせて判断することが大切です。
A4サイズの履歴書用紙を選ぶメリット・デメリット
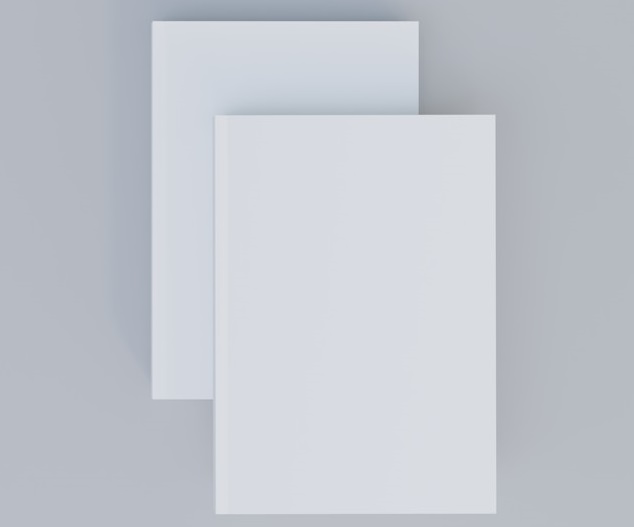
A4サイズの履歴書は、現在の就職活動で最も一般的に使われています。ただし、大きさゆえの扱いづらさやコスト面の負担を気にする人もいるでしょう。
ここでは、A4履歴書の主なメリットとデメリットをわかりやすく整理しました。
- メリット:記入欄が広く、情報を詳しく書きやすい
- メリット:企業からの指定が多く、安心して使いやすい
- メリット:PDFなど電子データとして提出しやすい
- デメリット:用紙サイズが大きく持ち運びにくい
- デメリット:封筒やファイルがやや高価・入手しにくい
- デメリット:プリンターによっては印刷しにくい
メリット:記入欄が広く、情報を詳しく書きやすい
A4サイズの履歴書は記入スペースが広く確保されているため、自分の強みや経験を余すことなく書き込めます。
志望動機や自己PRといった重要な項目に、具体例やエピソードを盛り込む余裕が生まれ、説得力を高められるでしょう。また、情報を整然と配置しやすいため、読みやすさや視認性にも優れています。
特にアピールしたいことが多い人や、職歴やスキルを丁寧に伝えたい人にとっては大きなメリットといえるでしょう。
メリット:企業からの指定が多く、安心して使いやすい
多くの企業では、応募書類を管理する際にA4サイズを前提としているケースが一般的です。そのため、履歴書をA4で提出すれば、書類が受け入れられやすく安心感があります。
特にサイズに関する指定がない求人でも、A4を選んでおけば失敗のリスクを避けられるでしょう。
また、エントリーシートや添え状といった他の書類とサイズをそろえることで、提出時の見栄えも整います。こうした点から、就活生にとっては扱いやすい選択肢といえるでしょう。
メリット:PDFなど電子データとして提出しやすい
近年、履歴書をPDFファイルとしてオンラインで提出する機会が増えています。A4サイズで作成すれば、PDF変換後もレイアウトが崩れにくく、採用担当者の画面上でも読みやすさが保たれます。
さらに、企業側の印刷にも適しているため、提出後の扱いやすさも評価されるポイントです。
紙で提出する場合との互換性も高く、デジタルとアナログの両方に対応しやすいのは、就活準備を効率化するうえでも大きな強みといえるでしょう。
デメリット:用紙サイズが大きく持ち運びにくい
A4サイズは一般的な書類よりも大きいため、移動中にかさばることがあります。たとえば、小さめのバッグや書類ケースには収まりにくく、折れ曲がりやシワがついてしまう可能性もあるでしょう。
面接当日にきれいな状態で提出したい場合は、クリアファイルなどを活用して保護することをおすすめします。また、電車内などで持ち歩く際も、形が崩れないように配慮が必要です。
こうした点では、コンパクトなB5サイズよりも不便さを感じるかもしれません。
デメリット:封筒やファイルがやや高価・入手しにくい
A4サイズの履歴書を送付・保管するには、それに対応した封筒やファイルが必要です。しかし、こうした文具はB5サイズに比べてやや高価であるうえに、すべての店舗で取り扱っているとは限りません。
特に急ぎで用意したい場合、近所のコンビニや100円ショップでは見つからないこともあるでしょう。事前に文具店やネットでまとめて準備しておくと、いざというときにも安心です。
コスト面と入手性を考慮して選ぶことが大切になります。
デメリット:プリンターによっては印刷しにくい
A4サイズの履歴書は、1枚に収まるタイプ以外では見開きで印刷するケースが多くなるため、家庭用プリンターでは対応できない場合があり、印刷時にレイアウトがずれてしまうリスクもあります。
プリンターによっては、希望通りに出力できないことがあるため注意が必要です。印刷前には必ず設定を確認し、試し刷りを行ってから本番用の用紙に印刷するようにしてください。
手間や技術的な調整が求められる点は、見逃せないデメリットでしょう。
B5サイズの履歴書用紙を選ぶメリット・デメリット
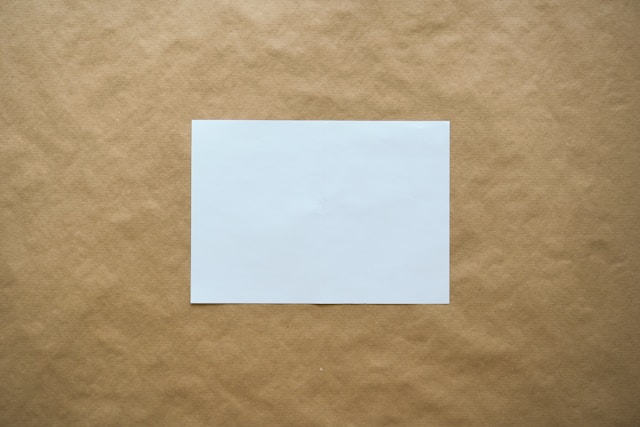
B5サイズの履歴書は、かつて多く使われていた形式ですが、近年はA4サイズを推奨する企業が増えつつあります。それでも、B5には今も選ばれる理由があるのも事実です。
ここでは、B5履歴書の特徴をメリット・デメリットの両面から整理して紹介します。
- メリット:コンパクトで提出時に扱いやすい
- メリット:情報を簡潔にまとめて伝えやすい
- メリット:封筒やファイルのサイズが手に入りやすい
- デメリット:記入欄が少なくアピールしにくい
- デメリット:最近では対応しない企業も増えてきて使いにくい
- デメリット:他の書類とサイズを揃えにくい
メリット:コンパクトで提出時に扱いやすい
B5サイズの履歴書は、A4に比べて用紙が小さいため、移動時や提出時に扱いやすいのが大きな利点です。特に、電車移動や複数社へ同日訪問する場面では、荷物がかさばらず身軽に動けるのは助かります。
また、小さめの封筒に収まることで、見た目もすっきりして印象が良くなることも。厚みのある用紙でも折り曲げずに封入でき、書類の型崩れを防げるため、状態の良いまま提出できる点も魅力でしょう。
全体として、スマートな印象を与えやすくなります。
メリット:情報を簡潔にまとめて伝えやすい
B5の履歴書は記入スペースが限られている分、自然と要点を絞る意識が働きます。そのため、冗長にならず、簡潔に伝える力が養われるでしょう。
文章が苦手な人や、内容をコンパクトにまとめるのが得意な人にとっては構成がしやすく、採用担当者も短時間で要点を把握できます。
また、書くことが少ないと感じている学生にとっては、スペースを持て余さずバランスよく仕上げられることが、安心感にもつながるはずです。
メリット:封筒やファイルのサイズが手に入りやすい
B5対応の角形4号封筒やクリアファイルは、一般的な文房具店や100円ショップでもよく見かけます。そのため、急に必要になっても手に入りやすく、購入の手間が少ないのは大きなメリットです。
価格も手頃で、必要数をまとめて準備しておいても経済的負担が軽く済みます。
特に就活が長期化した場合や、応募数が多くなる学生には、この手軽さとコスト面のバランスが大きな安心材料となるでしょう。
デメリット:記入欄が少なくアピールしにくい
B5サイズでは、志望動機や自己PRなどを書く欄が狭く、表現したい内容が制限されることがあります。
特に経験が豊富な場合や、しっかりと自己分析を行って伝えたいことが多いと、記入欄に収まりきらないこともあるでしょう。
結果として伝えたいポイントを削る必要が生じ、熱意や個性が十分に伝わらない可能性があります。文章量に制限があるからこそ、言葉選びと情報の取捨選択がより重要になるでしょう。
デメリット:最近では対応しない企業も増えてきて使いにくい
近年、企業側は履歴書や職務経歴書の保管・管理を効率化するために、A4サイズでの提出を前提とするケースが増えています。
そのため、B5サイズを使うと「読みづらい」「扱いづらい」と感じられ、不利になる可能性もあります。特に大手企業やIT・外資系の企業では、B5サイズが想定外とされることもあるため注意が必要です。
指定がないからといってB5を選ぶのではなく、企業文化や業界動向も見たうえで選択しましょう。
デメリット:他の書類とサイズを揃えにくい
履歴書の他に提出が求められる書類がA4サイズの場合、履歴書だけがB5で小さいと、封筒に収めたときに上下の長さが揃わず、書類全体の印象が乱れてしまう恐れがあるでしょう。
また、管理側から見てもサイズが混在していると扱いにくく、読まれる前からマイナス印象を与える可能性もあります。
全体の統一感に気を配ることが、細部に注意を払える姿勢として評価されることもあるでしょう。
企業から履歴書サイズの指定がある場合の対処法

まずは、応募先の企業が履歴書のサイズを指定しているかどうかを確認してください。多くの場合、募集要項や採用ページに記載されていることが多いです。
もし明記されていない場合は、事前に問い合わせて確認しておくと安心でしょう。
また、大学指定の履歴書を使う際は、企業の指示を優先するのが無難です。企業側がA4サイズを指定しているのに、大学指定のB5サイズを使ってしまうと、配慮が足りないと受け取られるかもしれません。
履歴書のサイズだけで評価が大きく変わるわけではありませんが、細やかな気配りや指示への対応力は、書類選考における印象に影響することがあります。
事前の確認と適切な対応を心がけて、万全な準備を進めてください。
その他の履歴書の用紙サイズ
履歴書といえばA4またはB5が一般的ですが、状況や用途によっては別の形式が適していることもあります。
ここでは、通常とは異なる履歴書サイズを3つ紹介し、それぞれの特徴や注意点について解説しています。
- A4サイズ1枚の履歴書
- 職歴欄がない履歴書
- インターネット応募専用のデジタル履歴書
①A4サイズ1枚の履歴書
A4用紙1枚にまとめられた履歴書は、構成がシンプルで提出や印刷も手軽に済むのが大きな魅力です。
特に職歴が少ない学生や、アルバイト・短期インターン経験のみを記載したい場合には、スペースのバランスが取りやすく、無駄な余白も生まれにくいため実用的でしょう。
採用担当者にとっても短時間で読み進めやすいという利点があります。ただし、志望動機や自己PRの欄が小さくなりがちで、伝えたい情報を絞る工夫が必要です。
伝える内容を厳選し、簡潔かつ説得力のある言葉で表現することが重要になります。
②職歴欄がない履歴書
まだ正社員としての就業経験がない場合や、アルバイト程度の職務しかない学生にとっては、職歴欄を省いた履歴書が適しています。
このタイプは、主に新卒やインターンシップ応募で使われることが多く、就活の最初のステップとして取り組みやすい書式といえるでしょう。
記入項目が少ないぶん、応募にかかる時間的・心理的な負担も軽減されます。
ただし、企業によっては「職歴欄が空白の履歴書」は好まれないこともあり、フォーマットを独自に指定している場合もあるでしょう。提出前には、必ず募集要項や応募先の指定書類を確認してください。
③インターネット応募専用のデジタル履歴書
就活のオンライン化が進むなか、PDFなどで提出するデジタル履歴書の需要が急速に高まっています。
スマートフォンやパソコンで作成・送信が可能なため、時間や場所を選ばずに提出できるのが大きな利点です。
多くの場合、A4サイズのテンプレートが標準となっており、WordやExcelで編集できるものも増えています。
ただし、企業によってはファイル形式(PDF限定、Word不可など)やファイル名のルール(氏名を含める、半角英数で作成など)に細かい指定があることも少なくありません。
送信前には、レイアウトの乱れや容量超過がないかを含め、指定要件を丁寧に確認しておくことが求められます。
パソコンで履歴書作成時の印刷方法

パソコンで履歴書を作成したあとに迷いがちなのが、どこで、どのように印刷するかという点です。
印刷の方法や仕上がりは提出時の印象にも関わるため、環境に応じてベストな手段を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な印刷方法と注意点について紹介します。
- コンビニで印刷する場合
- 自宅で印刷する場合
- 学校や図書館で印刷する場合
- オンライン印刷サービスを利用する場合
①コンビニで印刷する場合
自宅にプリンターがない場合でも、コンビニのマルチコピー機を使えば簡単に履歴書を印刷できます。
PDFファイルをUSBメモリに保存するか、専用アプリでデータを送信すれば、A4サイズでの印刷も可能です。操作は比較的かんたんで、24時間いつでも利用できる点も便利でしょう。
ただし、紙質や余白の細かい調整は難しいため、仕上がりを確認しながら印刷してください。
②自宅で印刷する場合
自宅にプリンターがある場合は、自分のタイミングで印刷できるので便利です。印刷用の厚紙やマット紙など、紙質にこだわりたい方にも向いています。
ただし、プリンターによって印刷品質に差が出やすく、設定を間違えるとレイアウトが崩れることもあるでしょう。事前にプレビューで確認したり、試し刷りをしたりしてから本番の印刷を行うと安心です。
③学校や図書館で印刷する場合
大学のキャリアセンターや図書館などに設置されているプリンターでも、履歴書の印刷は可能です。印刷コストが安く済む場合もあり、経済的に抑えたい学生にとっては便利な選択肢となります。
ただし、混雑する時間帯には順番待ちが発生することもあるため、余裕を持ったスケジュールで利用してください。利用可能なファイル形式や印刷方法も、事前に確認しておきましょう。
④オンライン印刷サービスを利用する場合
高品質な仕上がりを求める方には、オンライン印刷サービスの利用もおすすめです。テンプレートに従ってデータをアップロードするだけで、自動で印刷・裁断されて届く仕組みです。
紙質やレイアウトのバランスも美しく整い、応募書類としての完成度が高まるでしょう。ただし、納品までに数日かかる場合が多いため、提出期限に間に合うよう早めに手配することが大切です。
履歴書を印刷する際の注意点

履歴書を自宅やコンビニで印刷する際は、内容の正確さだけでなく、仕上がりの見た目や用紙の選び方も重要です。ちょっとした不備が評価を下げる原因になりかねません。
ここでは、印刷時に注意すべきポイントを6つに分けて紹介します。提出前に再確認しておくと安心です。
- 印刷前に誤字脱字を必ずチェックする
- 印刷用紙は厚すぎず上質な白紙を選ぶ
- 履歴書は必ず片面印刷で仕上げる
- 写真付き履歴書は色味・画質に注意する
- 印刷後のインクのにじみや汚れをチェックする
- レイアウトがずれていないか最終確認する
①印刷前に誤字脱字を必ずチェックする
履歴書に誤字や脱字があると、内容がどれほど優れていても評価が下がってしまうことがあります。特に、企業名や部署名、役職名など固有名詞のミスは印象を大きく損なう原因になるでしょう。
丁寧に書いたつもりでも、自分では気づきにくいことも多いため、印刷前には必ず文章を音読して確認してください。加えて、家族や友人など第三者に見てもらうことで、見落としを防ぎやすくなります。
ほんの些細なミスでも、採用担当者に「細かい点に注意を払えない人」と見なされるリスクがあるため、最終チェックは念入りに行うことが大切です。
②印刷用紙は厚すぎず上質な白紙を選ぶ
ほどよい厚みのある上質紙で、白色度が高く、マットな質感のものを選ぶことをおすすめします。
履歴書は単なる文書ではなく、あなたの人物像を伝える大切なアイテムです。そのため、用紙の質感ひとつで印象が変わってしまうことがあります。
安価なコピー用紙を使うと、ペラペラで頼りなく見えたり、裏写りしやすくなったりするため注意が必要です。
光沢が強すぎると読みづらくなるため避けたほうがよいでしょう。用紙選びは細かい点のように思えるかもしれませんが、第一印象を左右する要素のひとつとして、しっかり意識して選んでください。
③履歴書は必ず片面印刷で仕上げる
履歴書を印刷する際は、必ず片面印刷にしてください。両面印刷にすると裏側の文字が透けたり、書類を読む側がストレスを感じやすくなったりします。
実際、多くの企業では片面印刷を前提として書類を取り扱っており、両面印刷されたものはマナー違反と見なされることがあるかもしれません。
また、履歴書をスキャンして管理する場合にも、片面の方が扱いやすいため実務面でも好まれます。印刷時にはプリンターの設定を確認し、「片面印刷」になっていることをしっかり確認しましょう。
基本的なマナーとして、ぜひ押さえておきたいポイントです。
④写真付き履歴書は色味・画質に注意する
証明写真を履歴書に貼り付ける際、パソコンで挿入するデジタル写真を使う場合には、色味や画質の調整にも気を配りましょう。
画面では綺麗に見えていても、印刷すると暗すぎたり色がくすんで見えることがあります。
特に、照明の影響で顔が陰ってしまったり、解像度が低い写真だと画質が粗くなってしまったりすることがあるため注意が必要です。
印刷前にはプレビューで確認し、必要であれば明るさやコントラストを調整してください。写真は第一印象に直結する部分なので、できるだけ鮮明で自然な仕上がりになるよう工夫することが大切です。
⑤印刷後のインクのにじみや汚れをチェックする
印刷が終わった直後の履歴書をすぐに触ってしまうと、インクが乾ききっておらず、指や手のひらに付着してしまうことがあります。
それによって用紙全体に汚れが広がってしまうと、どれだけ丁寧に内容を作っても印象を大きく損なってしまうことも。
印刷後は必ず平らな場所で数分以上放置し、完全に乾かしてから取り扱うようにしてください。また、にじみが出ていないか、紙に擦れや折れがないかも目視でチェックしておくと安心です。
細かいことですが、こうした仕上がりの確認も評価に影響する要素といえるでしょう。
⑥レイアウトがずれていないか最終確認する
印刷時にありがちなのが、レイアウトのズレです。画面上では整って見えていても、印刷してみると罫線が途切れていたり、文字が枠からはみ出していたりすることがあります。
特に、WordやExcelなどからPDFに変換した場合や、コンビニプリントを利用した際に発生しやすいため、必ず事前にテスト印刷を行いましょう。
また、使用するプリンターの機種によっても印刷結果が変わることがあるので、可能であれば本番前に複数の方法で確認することをおすすめします。
履歴書は「読みやすさ」も評価の対象になるため、見た目の整合性には細心の注意を払いましょう。
履歴書のサイズに合った証明写真・封筒の選び方

履歴書を丁寧に整えるためには、用紙サイズに加えて証明写真や封筒のサイズも意識することが重要です。
サイズが適切でないと、見た目が不格好になったりマイナス印象を与えたりするおそれがあります。ここでは、履歴書に適した証明写真と封筒の選び方を4つ紹介しましょう。
- 証明写真のサイズは縦40mm×横30mmに合わせる
- A4履歴書の封筒サイズは角形2号を選ぶ
- B5履歴書の封筒サイズは角形4号を選ぶ
- 封筒の色は白を選ぶ
①証明写真のサイズは縦40mm×横30mmに合わせる
履歴書に貼付する証明写真の基本サイズは、縦40mm×横30mmです。
これはA4でもB5でも同じで、多くの履歴書フォーマットであらかじめ指定されているため、もっとも一般的かつ無難な選択といえるでしょう。
サイズが異なると、写真枠からはみ出したり、余白が不自然に残ってしまったりして、全体のバランスが崩れがちです。また、サイズ違いの写真を無理に貼ると見た目の印象も悪くなります。
証明写真を撮る際は、必ず「履歴書用」と明確に伝えると、適切なサイズで仕上げてもらえるため安心です。履歴書の第一印象を大きく左右するパーツなので、細部にも妥協せず丁寧に準備しましょう。
②A4履歴書の封筒サイズは角形2号を選ぶ
A4サイズの履歴書をそのまま折らずに送るには、角形2号の封筒を使用するのがベストです。
履歴書を折ってしまうと、紙にシワがつき、見た目が雑になったり、読む相手に手間をかけさせたりする原因になります。
特に採用担当者は多くの応募書類に目を通すため、整った状態で届いた履歴書の方が印象に残りやすいでしょう。
角形2号はA4用紙にぴったり対応しており、若干のゆとりもあるため、クリアファイルに入れたまま封入することも可能です。
見栄えだけでなく、郵送中の折れやヨレも防げるため、履歴書の保護という点でも適しています。
③B5履歴書の封筒サイズは角形4号を選ぶ
B5サイズの履歴書を折らずに送付したい場合には、角形4号の封筒が適しています。
この封筒はB5用紙に合わせて作られており、ちょうどよく収めることができるため、履歴書をきれいな状態で届けることが可能です。
もし、封筒が大きすぎると中で書類が動き、角が折れるなどして見た目が崩れるおそれもあります。反対に小さすぎる封筒を選ぶと、無理に折ることになり印象が損なわれてしまうでしょう。
角形4号であれば、適度な余白と保護力があり、文具店や100円ショップでも比較的簡単に手に入るため、手軽に準備できる点でも安心です。
④封筒の色は白を選ぶ
履歴書を入れる封筒の色は「白」を選ぶのがもっとも無難であり、ビジネスマナーとしても正解です。
茶色の封筒は一般的に事務的な印象があり、履歴書のような正式な書類を送る場合にはカジュアルすぎると受け取られてしまう可能性があります。
一方で、白い封筒は清潔感があり、フォーマルな用途にも適しているため、採用担当者に好印象を与えやすいでしょう。
特に、就職活動では第一印象が非常に大切なため、細部にまで気を配ることが求められます。封筒の色ひとつ取っても印象を左右する要素のひとつなので、慎重に選ぶよう心がけてください。
履歴書用紙サイズに関するよくある質問

履歴書のサイズにまつわる疑問は、就職活動を進める中で誰もが一度は抱くものです。
ここでは、実際によく寄せられる質問を4つ取り上げ、それぞれに対してわかりやすく解説しています。
- A4とB5で評価に差が出ることはある?
- 大学指定の履歴書サイズが企業の指定と異なるときは?
- 履歴書を英語で提出する場合、サイズはどうすべき?
- 履歴書を間違ったサイズで提出してしまったら?
①A4とB5で評価に差が出ることはある?
履歴書のサイズが評価に直接影響することは、ほとんどありません。採用担当者が重視するのは、記載された内容や読みやすさです。
そのため、自分が書きやすいと感じるサイズを選ぶのが基本といえるでしょう。ただし、企業側でサイズを指定している場合は、必ずその指示に従ってください。
指定がない限り、内容が明確に伝わることが最も重要です。
②大学指定の履歴書サイズが企業の指定と異なるときは?
大学が提供している履歴書のサイズと企業の指示が異なる場合は、企業の指定を優先する必要があります。提出書類に関するルールを守る姿勢は、社会人としての基本的なマナーとみなされるでしょう。
特に「A4に限る」と明記されているときは、誤ったサイズで出すとマイナス評価につながるおそれがあります。事前に募集要項をしっかり確認してから、準備を進めてください。
③履歴書を英語で提出する場合、サイズはどうすべき?
英語の履歴書を提出する場合は、原則としてA4サイズを使用しましょう。A4は国際的に標準とされており、外資系企業や海外の組織にとってもなじみがあるサイズです。
一方、B5は日本国内の規格であり、海外では一般的ではありません。英語で履歴書を作成する際には、サイズだけでなくフォーマットやレイアウトも国際的な基準に合わせておくと安心です。
④履歴書を間違ったサイズで提出してしまったら?
企業が特にサイズを指定していない場合であれば、多少の違いは問題視されないこともあります。ただし、明確な指示があったにもかかわらず誤ったサイズで提出した場合は、注意されることもあるでしょう。
そのようなときは、できるだけ早く正しいサイズの履歴書を用意し、事情を添えて再提出するのが誠実な対応です。事前確認を怠らないことがトラブル回避のカギになるでしょう。
履歴書の用紙サイズはどう選ぶべきか

履歴書の用紙サイズを選ぶ際は、目的や提出先に応じて判断することが大切です。一般的にはA4サイズが主流で、情報を詳しく記入しやすく、多くの企業にも対応しています。
一方、B5サイズはコンパクトで扱いやすいという利点もありますが、対応していない企業もあるため注意が必要です。
加えて、印刷方法や封筒・証明写真のサイズ、企業の指定への対応など、用紙サイズに関連するポイントも押さえておくと安心でしょう。
履歴書は内容だけでなく、形式面でも丁寧な準備が評価につながる要素になります。自分の志望先や書きやすさに合わせて、最適なサイズを選択してください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













