面接での筆記試験とは?種類や対策方法、出題例を徹底解説
この記事では、面接で行われる筆記試験の種類や出題分野、対策法を徹底解説しています。
また、SPI・玉手箱などの特徴や例題、当日の準備まで網羅的に紹介しているので、就活生が最後まで必見の内容になっていますよ。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る面接の筆記試験は正しい方法で対策しよう

就職活動では、面接時に筆記試験を実施する企業が少なくありません。準備を怠ってしまうと、本来の実力が発揮できず、思わぬ不合格につながることもあります。
筆記試験は単なる知識の確認にとどまらず、論理的思考力や文章力、性格や適性など、多角的に評価されるものです。だからこそ、事前に試験の形式や出題傾向を把握しておくことが重要です。
企業によって試験内容は異なるため、自分が受ける企業の特徴をリサーチし、それに合わせた対策を立ててください。特にSPIやWebテストのような代表的な形式には、早めに慣れておくと安心でしょう。
また、筆記試験は面接と同じ日に行われるケースもあります。当日のスケジュールや持ち物を事前に確認しておかないと、焦ってしまう原因になりかねません。
体調管理も含めて、当日にベストな状態で臨めるように整えておくことが大切です。筆記試験は、きちんと対策すれば誰でも十分に突破できる試験です。焦らず計画的に準備を進め、自信を持って臨みましょう。
就活生は面接準備だけでもやることが多く、筆記試験の対策までとなると時間が足りないと感じる方も多いでしょう。以下の記事では、就活生向けにさまざまなスケジュール管理の方法やコツを詳しく紹介しているので、ぜひ参考にして効率的に就活を進めましょう。
面接で実施される筆記試験とは

就職活動中、多くの学生が経験するのが「面接時の筆記試験」です。しかし、その内容や目的を正確に理解している人はあまり多くありません。
筆記試験の内容は企業によって異なり、単なる学力テストではなく、総合的な適性や能力を見極めるための手段として活用されています。
試験では、言語・数理・論理などの基礎学力を問うもののほか、性格診断や価値観を測る適性検査、一般常識や時事問題などが出題されることもあります。
企業側は、履歴書や面接だけでは見えにくい「考え方の傾向」や「思考力」を評価したいと考えているのです。
そのため、面接の評価が良くても、筆記試験の結果によっては通過できないケースもあるでしょう。筆記試験は、選考を左右する重要な評価ポイントであることを認識しておく必要があります。
油断せず、事前にしっかりと対策を進めておくことが、就活を成功に導く大きな鍵になります。
筆記試験では、知識を持っているかだけでなく「限られた時間内で考え、結論を出す力」も見られています。私たちも企業の方と話す中で、スピードや論理性も評価していると聞きました。
また、同じ「適性検査」でも企業によって設問の狙いや配点比率が変わることがあります。過去の出題形式を確認し、自分の弱点分野を把握しておきましょう。
自分の弱点分野を把握し、効率よく対策を進めるためにも、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。SPIの試験問題をテーマに、試験形式の特徴や出題内容に加え、学習をスムーズに進めるためのおすすめ参考書まで詳しく紹介しています。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
面接で筆記試験が行われる理由
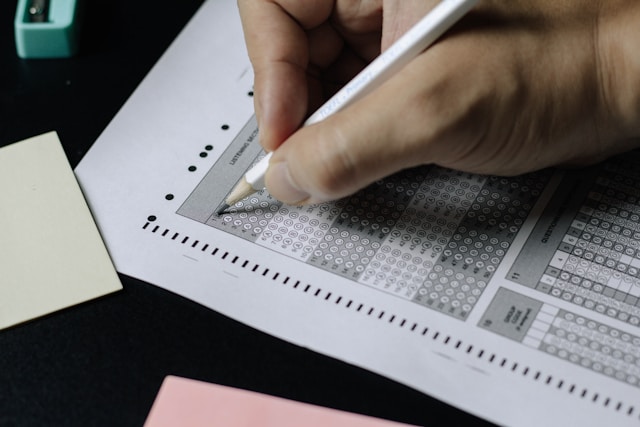
筆記試験は単なるふるい落としではなく、企業が学生を多面的に評価するための重要な選考手段です。ここでは、なぜ企業が面接時に筆記試験を実施するのか、その目的を5つの視点から解説します。
- 仕事に必要な一般常識を把握しているかを確認するため
- 企業が学生の基礎学力や知識レベルを確認するため
- 論理的思考力・文章構成力を評価するため
- 学生の性格や適性を判断するため
- 足切り・人数調整を行うため
① 仕事に必要な一般常識を把握しているかを確認するため
社会人として働くには、最低限の一般常識が求められます。筆記試験で問われるビジネスマナーや時事問題は、日常の情報収集ができているかどうかをチェックする手段です。
企業は入社後にスムーズに業務へ移行できる人材を望んでおり、社会性や知識の有無を筆記試験で見極めようとしています。
常識的な問題でつまずけば、面接の評価が高くても不安要素と捉えられるおそれがあります。日ごろからニュースや新聞に目を通し、社会全体への関心を持つことが重要でしょう。
私たちも企業の採用担当者から「筆記試験は学力よりも社会人としての常識があるかを確認している」と聞くことが多いです。一般常識を持っているかどうかが見られていますよ。
一般常識の範囲は広く、政治・経済・文化など幅広い分野から問われます。過去問やSPIだけでなく、ニュースや経済誌を見る習慣をつけることが大切です。
以下の記事では、就活における一般常識の定義から出題範囲、効率的な勉強法、役立つ問題集まで幅広く解説します。意外と対策が難しい一般常識も、ポイントを押さえて準備を進めましょう。
② 企業が学生の基礎学力や知識レベルを確認するため
どの業界でも、基本的な計算力や読解力は不可欠です。筆記試験では、数学・国語・英語などの問題を通じて、学生の学力水準を測ります。
これは、学歴や面接だけでは分からない理解力の「基礎」を知るためです。得意分野だけでなく、全体的なバランスも評価の対象になるため、特定分野に偏らず幅広く対策する必要があります。
基礎を固めたうえで、苦手分野の克服にも注力してください。
③ 論理的思考力・文章構成力を評価するため
ビジネスの現場では、論理的に考え、分かりやすく伝える力が欠かせません。筆記試験では、条件整理や因果関係の把握が必要な問題、短文作文などが出題されることがあります。
こうした問題は、筋道立てて考える力や、伝え方のセンスを見るために設けられています。
普段から日記やSNSなどで文章を書く習慣を持ち、伝えたい内容をシンプルにまとめる練習をしておくと良いでしょう。考えを整理して表現する力は、面接でも高く評価される要素です。
冗長な文章よりも「簡潔で一貫性のある文章」が高く評価される傾向にあるので、必要な情報を整理し、要点を掴んで論理的に伝えることが大切です。
私たちはアドバイスをする際に、「ニュース記事を3行でまとめる」や「友人との会話で結論から話す癖をつける」など、日常的なところから意識することをすすめています。
④ 学生の性格や適性を判断するため
筆記試験には、性格検査や適性診断も含まれている場合があります。
企業は、成績だけでなく人柄や価値観が自社と合うかどうかを重視しており、協調性・責任感・ストレス耐性などを確認するためにこうした検査を活用するのです。
正解がない設問が多いため、取り繕わず素直に答えることが大切。自分を良く見せようとしすぎると、回答に矛盾が生じてしまいます。自分の性格や傾向を理解しておくことが、結果的にプラスに働くでしょう。
性格や適性を測る検査では、志望職種に求められる人材像を事前に確認することが大切です。たとえば、営業職ならコミュニケーション力、研究職なら分析姿勢や粘り強さなどを重視する傾向にあります。
また、適性検査での結果は一次選考の合否だけでなく、その後の配属や育成方針にまで影響することも企業によってはあるため、慎重に答えてくださいね。
⑤ 足切り・人数調整を行うため
大手企業などでは、数千人単位のエントリーがある場合もあります。すべての応募者に個別対応するのは現実的でないため、筆記試験を通じて一次的に人数を絞り込むのが一般的です。
この段階で通過できなければ、その先の面接に進むことはできません。どれだけポテンシャルがあっても、筆記試験で基準を満たせなければ不合格となるリスクがあります。
過去問題を活用し、出題傾向を把握したうえで計画的に準備を進めておくことが欠かせません。
面接で実施される筆記試験の出題分野

筆記試験では、知識や能力を多面的に測るため、出題される分野が多岐にわたります。それぞれの内容を把握しておくことで、効果的に対策を進めやすくなるでしょう。
ここでは、よく出題される代表的な分野を紹介します。
- 一般常識
- 言語分野
- 非言語分野
- 性格検査・適性検査
- 小論文・作文問題
① 一般常識
一般常識の問題では、ビジネスマナーや時事ニュースなど、社会人として必要な基礎知識が問われます。敬語の使い方や社会の仕組み、最近の出来事などに関する内容が出題されることもあるでしょう。
日ごろからニュースを見たり、マナー本を活用したりすると自然に知識が身につくはずです。幅広いジャンルが出るため、苦手分野を放置せずに対策を進めておきましょう。
② 言語分野
言語分野では、読解力や語彙力を問う問題が中心です。文法の知識、文章の構成、語句の意味といった基本的な力が試されます。とくに文の並び替えや長文読解は頻出。
苦手意識がある人は、問題集を繰り返し解いて慣れておくとよいでしょう。文章に触れる習慣をつけることで、自然と対応力が身につきます。
言語分野では、文章の意図を瞬時に把握するスピードも評価のポイントです。私たちも企業から「読み解きの早さ」が評価基準の一つだという話を聞きますね。
また、言語問題は、「社内外メールや報告書の意味をしっかり理解できるか」を見るための意味もあります。問題を解くときも「仕事で使う大事な能力」という視点を持って取り組みましょう。
③ 非言語分野
非言語分野では、計算力や論理的思考が求められる問題が出題されます。たとえば、表やグラフの読み取り、図形、確率や割合の計算などが代表例です。
SPIや玉手箱といった形式ではこの分野の得点が合否に直結することもあります。計算が苦手な方も、繰り返し練習すれば慣れてくるはずです。
ミスを減らすためにも、問題形式に早めに慣れておくことをおすすめします。
非言語分野は、「事務的な業務や分析が必要な業務ができるか」を見られることが多いです。短い時間で多くの問題を解く必要があるため、解答速度を意識して解きましょう。
最初は時間が足りず解ききれないこともありますが、慣れてくると出題傾向や解き方がわかってきます。何度も問題を解いてスピードと精度の両方を上げることが大切です。
④ 性格検査・適性検査
性格検査や適性検査では、自分の考え方や行動傾向が問われます。企業はこれを参考にして、自社との相性や職務適性を判断しているのです。
正解・不正解があるわけではありませんが、回答の一貫性が重視されます。自分をよく見せようと考えすぎると、回答がちぐはぐになり、逆にマイナス評価につながる可能性も。
ありのままの気持ちで答えるようにしましょう。
性格検査・適性検査は、企業が配属やチーム編成を考える際に参考にされる可能性があるため慎重に答えましょう。例えば、リーダー向きかサポート向きかで将来の配属が変わることもあります。
対策として、事前に自己分析を深めておくと、回答に一貫性が生まれますよ。検査は点数で競う場ではなく、自分と企業の相性を見極めるための方法なので素直に回答してくださいね。
自己分析を進めても「結局自分がよく分からない…」と感じる方は少なくありません。以下の記事では、自己分析の方法を多数紹介しているので、自分に合った進め方を見つけてみましょう。
⑤ 小論文・作文問題
小論文や作文は、論理的に考えを整理して伝える力が試されます。決められたテーマに対して、自分の意見を述べ、その理由や根拠を示す構成が求められるのです。
初めはうまく書けなくても、構成を意識しながら何度か書くうちに上達していくはず。時間内に書き上げるためには、書くスピードや文字数感覚にも慣れておいてください。誤字脱字を避ける意識も大切です。
筆記試験の実施時間

筆記試験の実施時間は企業ごとに異なりますが、おおよその目安を知っておくことで、当日の不安を減らせるでしょう。ここでは、一般的な所要時間や注意点についてご紹介します。
多くの企業では、筆記試験の所要時間は30分〜60分程度です。ただし、適性検査や性格診断、論述課題などを含む場合には、全体で90分を超えることもあります。
とくにSPIや玉手箱といったWebテスト形式では、問題ごとに時間制限が設けられていることが多く、ペース配分が合否を大きく左右するポイントになるのです。
あらかじめ試験の形式や内容を調べておき、それに応じた時間感覚を養っておくことが大切です。焦らず対応できるよう、模擬問題などで練習しておきましょう。
また、筆記試験が面接と同じ日に実施される場合は、拘束時間が長くなる可能性があります。余裕を持ってスケジュールを組み、体調管理にも気を配ってください。
限られた時間内で最大の力を発揮できるよう、準備を整えておくことが大切です。
以下の記事では、種類別の特徴や勉強法、試験当日に押さえるべきポイントまで徹底解説しています。自分が受ける筆記試験の内容や時間配分を事前に把握しておくためにも、ぜひ本記事とあわせて参考にしてください。
筆記試験の合格ライン

筆記試験の合格ラインは、就活生にとってとても気になるポイントです。ただ、企業ごとに基準が異なり、数値が公開されていないことも多いため、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
目安を把握しておくと、対策の方向性が見えやすくなります。一般的には、SPIや玉手箱などの適性検査で7割以上の正答率が一つの基準とされています。
とはいえ、企業によっては8割以上が求められるケースもありますし、相対評価で平均点より上かどうかを見られることもあるため、一概には言えません。
特に競争率の高い企業では、基準が引き上げられることもあるでしょう。また、同じ企業でも年度によって合格ラインが変わる場合があります。
過去のデータを参考にするのは有効ですが、あくまで目安にとどめておいたほうが安全です。確実に通過したいのであれば、8割以上の正答率を目指して対策を進めてください。
出題傾向に慣れておくと、本番でも落ち着いて解答できるはずです。合格ラインを知っておくことで、準備の精度が高まり、不安も軽減されるでしょう。
同じ試験でも企業ごとに合格ラインが異なるので、落ちないためには安定して高い点数を取る必要があります。外資系や人気な業界では平均点に関わらず「8割以上の正答率が合格基準」なことも。
また、相対評価型の選考では、全体の出来が良ければ合格の基準が高くなる点に注意しましょう。過去問題や模擬試験で事前に練習し、評価基準に関係なく高得点を取れるようにすることが大切です。
志望業界の人気や特徴を事前に知っておくことで、求められるレベル感を把握しやすくなります。以下の記事では、就活で知っておくべき業界知識を業界一覧とともに解説しているので、企業選考に応募する前にぜひ確認しておきましょう。
筆記試験の対策方法

筆記試験に合格するためには、やみくもに勉強を始めるのではなく、出題傾向や特徴を把握したうえで取り組むことが大切です。ここでは、効率的に実力を伸ばすための具体的な方法を紹介します。
- 試験ごとの出題傾向を調べる
- 過去問や問題集を繰り返し解く
- 時間配分を意識した模試形式の演習を行う
- 一般常識や時事問題は日常的にニュースをチェックする
- 志望企業の出題傾向をOB訪問などで調査する
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
① 試験ごとの出題傾向を調べる
筆記試験の種類によって、出題される内容や形式が異なります。たとえばSPIでは、言語と非言語のバランスが重要視される一方で、玉手箱では計数や英語問題の比率が高くなる傾向があります。
自分が受ける企業の形式を確認したうえで、それに対応した対策を行ってください。対策が曖昧なままだと、試験本番で戸惑ってしまうかもしれません。
② 過去問や問題集を繰り返し解く
筆記試験対策において、過去問や市販の問題集を繰り返し解くことは非常に効果的です。1度解いて終わりにせず、2回・3回と解き直すことで、ミスの傾向に気づいたり、知識がしっかりと定着したりします。
解説を読んで理解を深めることも重要です。繰り返すほど、問題のパターンが見えてくるはずです。
私たちも面談で「過去問は一度解いて終わり」という人をよく見ますが、3回以上繰り返して完璧に答えられるレベルにするようにアドバイスしています。繰り返し解くことで解答スピードも上がるからです。
また、間違えた問題は必ず「なぜ間違えたのか」を分析することが大切ですよ。ケアレスミスなのか、知識不足なのか、自分の弱点を知ることができます。復習ノートを作るのもおすすめです。
③ 時間配分を意識した模試形式の演習を行う
本番では限られた時間の中で問題を解かなければなりません。問題の難易度だけでなく、時間配分に慣れておかないと、答えられる問題にも手が届かなくなる可能性があります。
模試形式での練習を重ねれば、自然と時間の使い方も上達するでしょう。練習の段階で時間を意識することが、当日の安定感につながります。
模試形式で練習する際は、1問あたりにかけられる時間を把握しておくことが重要です。例えば60分で30問なら、1問あたり約2分が目安。見直し時間を含めると実際はもう少し短く配分したほうが安心です。
また、時間配分の練習は問題形式や分野を変えて行うことがおすすめですよ。初見の問題での時間を意識することで、本番の緊張感や焦りに強くなれます。練習の段階から、時計を見ながら解きましょう。
④ 一般常識や時事問題は日常的にニュースをチェックする
一般常識や時事問題は短期間で対策するには限界があります。そのため、日常的にニュースや新聞をチェックして、少しずつ知識を増やしておくことが大切です。
とくに就活の時期には、政治・経済・国際情勢などの基本的な話題に目を向けておくと安心。知識は一朝一夕では身につかないため、日々の積み重ねが鍵になります。
⑤ 志望企業の出題傾向をOB訪問などで調査する
企業によっては、一般的な形式とは異なる独自の問題を出題することがあります。こうした情報はネット検索だけでは見つけにくいため、OB・OG訪問を通じて実際の体験談を聞くのが有効です。
説明会や先輩との会話から得られる情報は、信頼性が高く、具体的な対策にもつながります。早めに行動を起こすことで、ライバルと差がつくかもしれません。
とはいえ、OB・OG訪問は初めてだと「何から始めればいいの?」と不安になる方も多いでしょう。本記事では、探し方・依頼方法・当日の流れ・服装マナー・お礼の仕方まで、安心して実践できるステップをわかりやすく解説します。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
筆記試験の例題
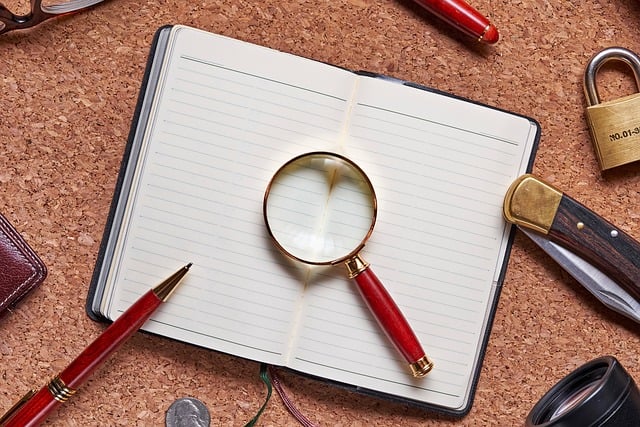
筆記試験を攻略するには、どのような問題が出題されるのかを知ることが欠かせません。ここでは、就職活動でよく見られる主要な分野ごとに例題を紹介し、出題傾向や対策のポイントを解説します。
- 一般常識問題の出題例
- 言語問題の出題例
- 非言語問題の出題例
- 適性検査問題の出題例
- 小論文の出題例
① 一般常識問題の出題例
一般常識問題は、時事ニュースや社会の基本知識についての理解が問われる分野です。政治、経済、歴史、国際関係、文化などテーマは多岐にわたります。
企業はこの問題を通じて、就活生が社会人として最低限の知識を持っているかを確認するのです。
学力ではなく「社会への関心度」が評価の基準になるため、難解な知識よりも、ニュースを自分の言葉で説明できるかが大切でしょう。
日常的にニュースアプリや新聞に触れる習慣がある人は、自然とこの分野の問題に強くなります。
| 【例題1】次のうちG7の加盟国でないものを選びなさい。 A. カナダ B. フランス C. ロシア D. イタリア 【例題2】2025年の日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマは? 【例題3】次の人物のうち、明治時代に活躍したのは誰か。 |
一般常識の問題は、日頃から社会に関心を持っているかがみられています。さらに、理由や関連情報まで整理して伝えられる力も求められますよ。
対策としては、過去問演習に加えて、日ごろからニュースの内容を友人や家族と共有するのがおすすめです。会話を通じて「自分がどのくらい理解できているか」を把握でき、記憶も定着しやすくなります。
② 言語問題の出題例
言語分野の問題では、文章読解・語彙力・文法・敬語など、日本語に関する総合的なスキルが問われます。SPIや玉手箱では、文の並び替え、空欄補充、長文読解などが頻出です。
言葉の正しい使い方や、文章の論理構成が理解できているかを問う問題が多く、ビジネスシーンにふさわしい言葉遣いも重要なポイント。
語彙力を伸ばすには、問題集での演習だけでなく、普段から新聞や本など多様な文章に触れることが効果的です。
| 【例題1】次の文章の中で、誤った敬語表現を含むものを選びなさい。 【例題2】「彼は早急に対処すべきだった」という文の「早急」の正しい読みは? 【例題3】次の長文を読んで、筆者の主張として最も適切なものを選びなさい。 |
言語問題は、解答の根拠を素早く見つけられるかが重要です。私たちも模擬試験で見ていると、意味を感覚的に捉えて誤答するケースが多いと感じますね。
問題集で練習する際は、「解説を音読する」ことをおすすめします。文章構造や用語の使い方が耳に残り、覚えやすいです。また、ニュースなどを毎日1個読むのも読解スピードと語彙力向上におすすめですよ。
③ 非言語問題の出題例
非言語問題は、計算・図表の読み取り・論理的思考などを含む問題群です。SPIや玉手箱などで出題され、問題処理のスピードと正確さがカギを握ります。
特に数字や図を扱う問題が多いため、文系学生の中には苦手意識を持つ人も少なくありません。しかし、問われるのは難解な数式ではなく、基本的な四則演算や論理整理が中心です。
問題のパターンに慣れ、短時間で情報を読み取る練習を積むことで、誰でも得点源に変えられます。
| 【例題1】ある商品を定価の2割引で販売したところ、利益は定価の1割だった。商品の原価はいくらか。 【例題2】以下の図表を見て、来年度の売上増加率を選びなさい。 【例題3】A〜Dの4人で交代勤務をする。連続勤務できるのは2日までとする。勤務表として正しいものを選びなさい。 |
非言語問題は、「問題形式に慣れること」が大切です。模擬試験で多くの学生を見てきましたが、問題形式に慣れている人のほうが解答スピードも正答率が高い傾向にあると感じますね。
また、本番では「計算の正確さ」と「設問の読み違え防止」が重要です。途中計算は省略せず、必ずメモを残す習慣をつけましょう。焦って問題を読み飛ばすより、確実に正解する方が得点が安定しますよ。
④ 適性検査問題の出題例
適性検査は、性格や価値観、行動パターンなどを測るためのテストです。選択式の質問に直感的に答えることで、応募者の人柄や職務への適性を見極めるのが目的です。
SPIや玉手箱、企業独自の検査などで幅広く使われており、嘘のない一貫した回答が求められます。
正解・不正解はありませんが、自分をよく見せようとしすぎると、回答に矛盾が生じて評価が下がることもあります。自然体で、自分の価値観に素直に向き合うことが大切です。
| 【例題1】「周囲の人からリーダーシップがあると言われることが多い」 【例題2】次の選択肢の中から、自分に最も当てはまるものと、最も当てはまらないものを選んでください。 【例題3】「休日よりも平日の方が落ち着く」「ルールを破るのは苦手だ」などの設問が続きます。 |
性格検査では似たような質問を言い回しを変えて出すことがあります。そのため、設問の傾向を知り、どんな角度の質問にも一貫した回答をすることが大切です。
また、私たちが面談する中で「正直に答えると不利では?」と聞かれることがありますが、自分をよく見せようと偽った回答をすると、入社後のミスマッチにもつながる可能性があるので注意してください。
⑤ 小論文の出題例
小論文は、自分の考えを文章で論理的に展開する力が問われる試験です。
ビジネスへの意識や社会的関心、自分の価値観などがテーマになり、「序論・本論・結論」の構成をいかに自然にまとめられるかが評価のポイントになります。
文章力だけでなく、物事を多面的に見る力や、説得力ある主張を展開する思考力も求められるでしょう。
多くの学生が苦手意識を持つ分野ですが、テーマに対する自分の意見を言葉で説明する練習を重ねることで、確実に力をつけられます。
| 【例題1】AIと人間の役割分担は今後どうあるべきか 【例題2】あなたがチームで成果を出した経験と、そこから学んだこと 【例題3】理想的なリーダーとはどのような人物か 【例題4】働くうえで、やりがいと報酬のどちらを優先するか 【例題5】SNSの普及によって変化した人間関係についてどう考えるか |
小論文では、「論理のつなぎ」や「結論の明確さ」が重要です。書き出しから結論まで一貫性を意識して書くことを心がけてください。
対策としては新聞やニュースサイトで話題になっているテーマを、自分なりに300~400字でまとめる練習がおすすめです。様々なテーマに触れ、背景知識や切り口の引き出しを増やしましょう。
以下の記事では、分野ごとの勉強方法を紹介しています。本記事でどのような問題が出題されるのか把握できたら、次は以下の記事を参考にしながら、勉強を始めていきましょう。
面接での筆記試験対策におすすめの問題集
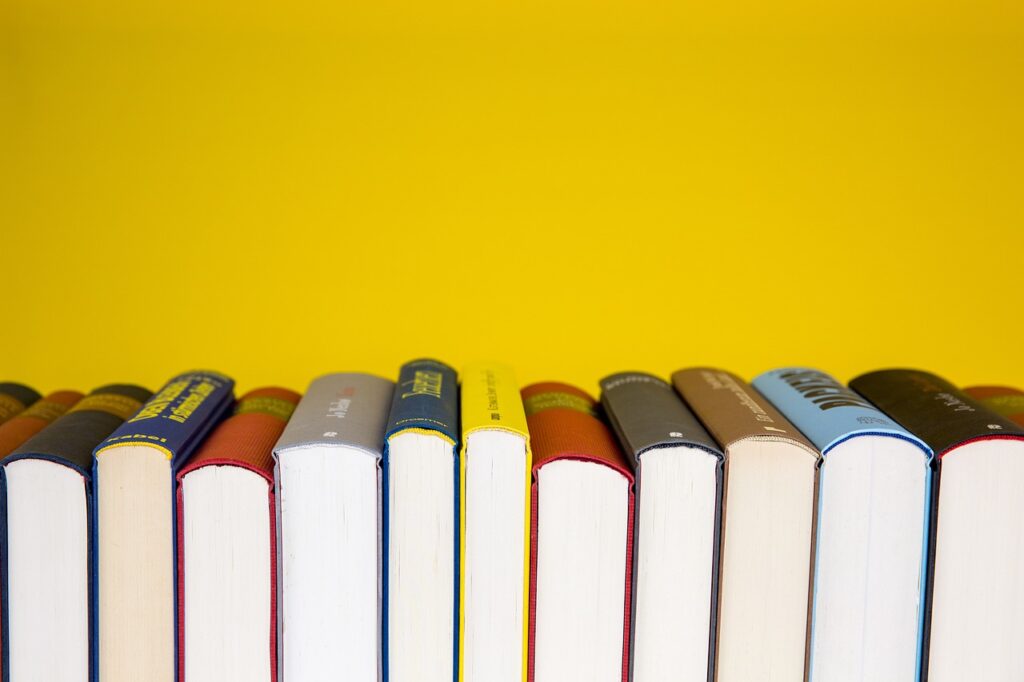
筆記試験に合格するには、出題形式に合った問題集で効率的に対策することが欠かせません。ここでは、就活生からの評価が高く、実践的な力を養えるおすすめの教材を紹介します。
- これが本当のSPI3だ! 2027年度版
- 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
- 時事&一般常識の完璧対策【就活生向け】
- これが本当のCAB・GABだ! 2027年度版 【Web-CAB・IMAGES対応】
① これが本当のSPI3だ! 2027年度版
SPI対策では定番ともいえる一冊です。問題数が豊富で、基礎から応用まで段階的に学べる構成になっています。初めて対策する方でも取り組みやすく、実力を着実に伸ばせるでしょう。
巻末に模試もついているため、本番前の力試しにも使えます。
出典元:https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000407368
② 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
実戦形式の演習を重ねたい方にぴったりの問題集です。本番さながらの問題構成で、時間配分や出題傾向に慣れるのに最適でしょう。出題分析も詳しく、対策の方向性が明確になるはず。
短期間で集中的に仕上げたい人にもおすすめです。
出典元:https://www.natsume.co.jp/np/isbn/9784816377006/
③ 時事&一般常識の完璧対策【就活生向け】
一般常識や時事問題に幅広く対応している教材です。最新のニュースからビジネスマナーまで網羅しており、筆記試験対策だけでなく面接にも役立つ知識が得られます。
空いた時間に読み進めるだけでも自然と知識が定着する構成です。
出典元:https://amzn.asia/d/56wF2ul
とはいえ、時事問題はきりがなく「どう対策すればいいの?」と悩む方も多いでしょう。以下の記事では、就活で時事問題が出題される理由から答え方のコツ、効率的な情報収集法まで徹底解説しているので、ぜひ参考にしてください。
④ これが本当のCAB・GABだ! 2027年度版 【Web-CAB・IMAGES対応】
外資系や専門職を目指す方にとっては、この分野の対策が必須になります。実際の試験に近い問題が収録されており、計数や図表読み取りが苦手な人でも繰り返すことで対応力が養われるはずです。
自分が受ける形式を確認したうえで取り入れてください。
出典元:https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000407370
筆記試験当日にやるべき準備

筆記試験当日は、小さな油断が大きなミスにつながることもあります。落ち着いて本番に臨むためには、必要な準備をしっかり整えておくことが大切です。
ここでは、当日に意識すべき5つのポイントを紹介します。
- 必要な持ち物を再確認する
- 服装は落ち着いたスーツスタイルを着用する
- 試験会場や集合時間を事前に確認する
- 試験直前に軽く問題を見直す
- 深呼吸やストレッチで緊張をほぐす
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
① 必要な持ち物を再確認する
当日の忘れ物は、試験前の不安や焦りを引き起こす原因になります。筆記用具、受験票、身分証、腕時計などは前日にまとめておき、当日出発前にもう一度確認してください。
特に予備の鉛筆や消しゴムを用意しておくと安心です。筆記具が壊れたりインクが出なくなったりしたときに備えておくことで、冷静に対応できるでしょう。チェックリストを活用するのも効果的です。
② 服装は落ち着いたスーツスタイルを着用する
筆記試験でも企業の担当者と接する機会がある可能性があります。基本は清潔感のあるリクルートスーツを選び、シャツのしわや靴の汚れにも注意してください。
季節や天候によって、インナーやコートなどを工夫する必要があります。たとえば夏場は汗対策、冬場は防寒を意識して選びましょう。
服装に気を取られず試験に集中できるよう、事前に準備しておくと安心です。
③ 試験会場や集合時間を事前に確認する
試験当日に会場の場所が分からず焦ることのないよう、前もって詳細を確認しておきましょう。住所だけでなく、最寄り駅からのルートや建物の階数まで把握しておくと安心です。
可能であれば事前に下見しておくとさらに確実。当日は早めに家を出て、集合時刻の10分前には到着するよう心がけてください。余裕を持った行動が、試験の成功につながります。
④ 試験直前に軽く問題を見直す
試験開始直前の時間は、気持ちを整える意味でも重要です。新しい問題に取り組むのではなく、これまで解いた内容を軽く見返す程度にとどめておくとよいでしょう。
特に自分が苦手と感じていた分野や、ミスしやすい箇所に目を通すと安心感が得られます。自信のある問題に触れることで、前向きな気持ちで試験に臨めるようになるはずです。
⑤ 深呼吸やストレッチで緊張をほぐす
試験前の緊張は誰にでも起こるものです。深呼吸をしたり、軽く首や肩を動かしたりするだけでも、心身をリラックスさせる効果があります。
人によっては、音楽を聴いたり目を閉じて静かに過ごしたりする方法が合う場合もあるのです。自分に合ったリラックス方法を見つけておくと、本番でも落ち着いて力を発揮できるでしょう。
筆記試験に限らず、面接そのものに「怖い」という感情を抱いてしまうと、本来の実力を出し切れずアピールポイントが伝わらないこともあります。以下では、緊張や不安を和らげるための具体的な準備と対策を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
面接の筆記試験は事前準備が重要

面接時に実施される筆記試験は、就活生にとって避けて通れない関門です。
筆記試験にはSPIや玉手箱をはじめとしたさまざまな種類があり、出題内容も一般常識・言語・非言語・適性検査・小論文など多岐にわたります。
企業はこれらを通じて学生の基礎学力や論理的思考力、さらには性格や適性までを総合的に判断しているのです。だからこそ、出題傾向を把握し、問題集や模試形式の演習を繰り返すことが大切です。
対策を怠れば、本来の実力が発揮できず、不本意な結果につながるかもしれません。筆記試験の目的や出題分野を正しく理解し、自分に合った方法で着実に準備を進めましょう。
正しい対策こそが、面接と筆記試験の両方を乗り越えるカギになります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











