【例文10選】自己PRで探究心をアピールするポイント・注意点を解説
就活の自己PRでは、どんな風に主張しようか迷うものですよね。
そして中には、「探究心」を自分の強みとして主張したいと考える方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、探究心の意味や就活の自己PRに取り入れる際のポイントなどを解説します。OK例文とNG例文も紹介しているので、ぜひ自己PR作成の参考にお役立てくださいね。
自己PRをすぐに作れる便利アイテム

記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る探究心とは物事の本質を見極め解明しようとする気持ち

探究心とは、一般的には物事の本質を自分が納得するまで調べたり見極めようとする気持ちのことを指します。
好奇心や向上心の強さをイメージさせる言葉であり、自己PRにおいても強調ポイントとして十分に活用可能です。
ビジネスにおいては、課題に対する疑問点を徹底的に追求していく姿勢が役立つためです。
探究心を発揮して問題の本質について理解が深まれば、効果的な解決法やアプローチを導き出すことが期待できるでしょう。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
探究心と探求心の違い
探究心について調べるうえでは、非常に似た言葉である「探求心」との違いについて整理することが大切です。
探求心とは、物事に興味を持って追いかけようとする気持ちを意味します。両者の違いは、以下のように整理できるでしょう。
- 探究心:知識を得たい、本質を知りたいとの気持ち
- 探求心:物事を手に入れたいとの気持ち
どちらも何かを得たいという気持ちを表す言葉ですが、上記のようにニュアンスが異なる点を理解し、漢字を間違えないようにしましょう。
探究心と探求心の違いについてより詳しく説明した以下の記事もおすすめです。それぞれの特徴や、探求心の自己PR例文も掲載しているので、興味のある方はぜひご覧くださいね。
探究心の強さが企業へのアピールになる理由3つ

就活で「探究心」を自らの強みにする場合、どんな点が企業に刺さるのかを理解しておくことが大切です。
ここでは、探究心の強さが企業へのアピールになる理由として以下の3点を紹介します。
①1つの課題と納得がいくまで向き合えるため
探究心の強さが企業へのアピールにつながる理由としては、1つの課題に対して納得いくまで向き合う人材だと感じさせられるためです。
課題が分かった際に、その理由や解決方法について深く考え明らかにしていく姿勢や能力は、仕事の現場でも十分に活用できます。
また、困難なことがあっても課題に諦めず取り組む印象も与えられることから、責任感があるとの主張にもつながるでしょう。
②常に自ら進んで勉強できるため
探究心のある人に対して、企業側が「常に自ら進んで勉強できる人材」との印象を持つ可能性もあります。
課題や問題の原因や解決法を理解するためには、基本的に一定の学びが必要です。
また自ら学ぶ姿勢を持っている人材に対しては、仕事に対しても積極的に取り組むとの印象を持たれやすいと言えます。
新卒社員の場合、入社後に担当する仕事はほとんどが初体験のはずです。未体験の業務でも前向きに取り組める姿勢を、「探究心」から強調しましょう。
③物事の本質を見極めようとする姿勢があるため
「探究心」を強調することで、企業側に物事の本質を見極めようとする姿勢を示すことにつながります。
物事の背景やあいまいな物事についてしっかりと考えて真相に迫ろうとする姿勢は、ビジネスにおいて重要です。
分からないことをそのままにしておくと、成長にはなかなかつながりません。
また、本質をとらえることで効果的な解決策や新たなアイデアを思いつきやすくなることから、やはり仕事においては重要な姿勢だと言えるでしょう。
また、上記のような強みが企業でどのように活かせるかを話せると、面接官からの評価につながりますよ。その際には入念な企業研究が必須です。こちらでそのやり方について解説しているのでぜひ参考にしてください。
プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける自己PRを作ろう
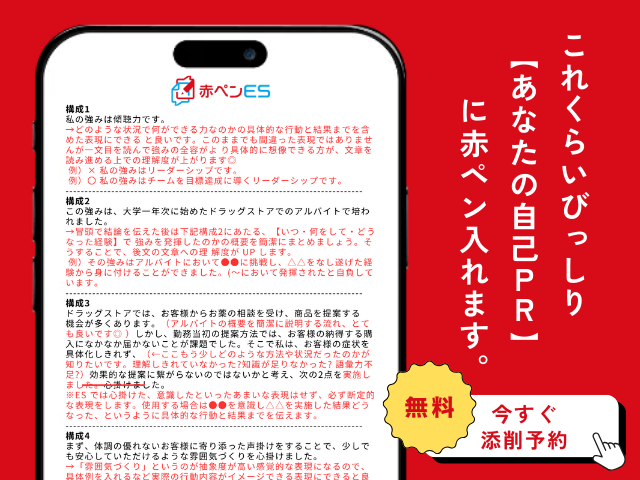
「自己PRが書けない……」「強みってどうやってアピールしたらいい?」など、就活において自己PRの悩みは尽きないものですよね。
そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの自己PRの良い点も改善点もまるごと分かりますよ。
さらに、本記事の後半では実際に、探究心を強みとした自己PR例文を添削しています!
「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。
探究心の言い換え表現8選

探究心の言い換え表現としては、以下が考えられます。
| ・粘り強い ・継続力がある ・忍耐力がある ・行動力がある ・向上心がある ・知的好奇心が強い ・職人気質(かたぎ) ・観察力がある など |
粘り強さや継続力、忍耐力などの表現からは、大変なことまであきらめずに最後までやり抜く姿勢や能力のアピールが可能です。
また行動力や向上心、知的好奇心などの表現からは、新たな物事に対して積極的に取り組み理解しようとする姿がイメージされるでしょう。
探究心を自己PRに取り入れる際には、言い換え表現を把握しておくとより具体的な内容になりやすく、他の就活生との差別化につながるためおすすめです。
「探求心」と言うだけでなく、より深く落とし込んだ言葉で説明することは非常に効果的です。どんな表現が良いか悩む方は、以下の記事を参考に、より丁寧に自己分析してみてくださいね。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
探究心をアピールする自己PRの基本構成3段階

ここでは、探究心をアピールする自己PRの基本構成を以下の3ステップに分けてそれぞれ解説します。
①結論(自分の強み)
探究心を印象付けるにはまず、結論である自分の強みを簡潔に伝えます。結論から話を始める姿勢は、ビジネスの基本であるためです。
結論を最初に伝えることで、これからどんな話をするのか相手が把握しやすくなります。
忙しい中でも要点を押さえた報告・説明を分かりやすくするためには、結論ファーストの考え方が欠かせません。
「私の強みは~です。」と、端的に自分の強みを伝えることで自己PRを始めると良いでしょう。
②具体歴(エピソード)
自分の強みを簡単に伝えたら、その根拠となる具体的なエピソードを盛り込みます。
エピソードを伝えることで具体性が増し、探究心を強みとしていることの説得力が増し、自然に他の就活生との差別化を図ることが期待できます。
エピソードの内容は、基本的にどんなものでも問題ありません。アルバイトや学業、部活動など自分らしい経験をチョイスしてみましょう。
とはいえ、「強みに結びつくエピソードが思いつかない…」と不安に感じている人もいるでしょう。そんな人には以下の記事がおすすめです。エピソード別の例文も掲載していますよ。
③入社後にどう活かすか
自己PRの最後には、自分の強みである探究心を入社後にどのように活かすのか伝えます。
採用担当者が知りたいのは、「その人材を取ることでどんなメリットが自社にあるのか」という点であるためです。
また入社後の展望を伝えることで、自分がイキイキと働いている姿を採用担当者にイメージしてもらうことも期待できます。
「御社(エントリーシートや履歴書の場合は貴社)に入社したら、○○として活躍したい」などと、入社後の展望を伝えるようにしましょう。
探究心をアピールすると受けやすい誤解3つ

ここでは、探究心をアピールすると受けやすい誤解として以下の3点を紹介します。
①柔軟性がない
探究心を強調することで受けやすい誤解としてまず挙げられるのが、柔軟性がないと思われることです。
1つのことを追求してのめりこめることは長所ではありますが、その反面で物事を客観的に見られない、俯瞰的に見られないと思われる可能性もあります。
自分の考えや嗜好に固執してしまい、周囲からの意見をないがしろにしているような印象を与えないように、自己PRでは注意しましょう。
②行動力がない
探究心をアピールする中では、行動力がないと思われるリスクもあります。
自分が納得できるまで調べる・考えることは確かに重要なことですが、その一方で考えすぎて行動が遅れてしまうことも考えられるでしょう。
実際の仕事では、とにかく手を動かしてやるべきことを前に動かしていく姿勢も一定は求められます。
また、1つのことに対して行動せず考えてばかりいるとストレスを抱え込みやすいともとられかねないので、十分な注意が必要です。
③協調性がない
探究心の強さを強調するあまりに、協調性がない人材だと思われないようにも注意が必要です。
自分が気になることだけを追究するあまりに、周囲との協調をないがしろにしてしまうリスクがあると思われる可能性があります。
協調性はどの企業でも重視する大切な資質であり、例え探究心をアピールできても協調性がないと半kん段されれば大きなマイナスになりかねません。
そのため自己PRでは、探究心を発揮しつつ周囲の人々と協力したエピソードを採用できれば理想的でしょう。
ここまで説明したように、「探求心」にはネガティブに捉えられがちな一面もあります。以下の記事を参考に、自分の強みに隠れたネガティブな点も分析することで、より納得感のある自己PRが作れますよ。
自己PRで探究心をアピールするコツ3つ

ここでは、自己PRで探究心をアピールするコツとして以下の3点を紹介します。
①数字を使って期間や成果を具体的に伝える
自己PRで探究心を強調する際には、数字をできるだけ盛り込んで期間や成果を具体的に伝えることが大切です。
具体性が増すことで強みの信ぴょう性が高まり、採用担当者への説得力も高まるためです。
たとえば「大学2年の秋まで、毎日のように頑張った」よりも、「大学1年の4月から大学2年の9月末までは週6日以上取り組んだ」の方が具体的になります。
具体性がないと説得力がないだけでなく「嘘をついている?」と思われる可能性もあるので、可能な範囲で数字を入れてみるようにしましょう。
②入社後に再現できることをアピールする
探究心を盛り込んで自己PRを作成するにあたっては、強みを入社後にも再現できる点をアピールすべきです。
採用担当者はその人材を採用するメリットを知りたがっており、例え強みがあってもそれが入社後に発揮されないと思われれば評価にはつながりません。
探究心のエピソードを考えたら、それが入社後に仕事でも同様に活かせるものなのか十分に注意して見直してみましょう。
③エピソードに協調性も盛り込む
探究心を自己PRでアピールするにあたっては、可能な範囲でエピソードに協調性も示せるものを選ぶことが大切です。
探究心を強調する中では、「自分のことばかりで協調性がない」との印象を与えてしまうリスクが一定あります。
できるだけ周囲と協力したり周囲を巻き込んだりしたエピソードを選択できたら、協調性がないと思われるリスクが減るでしょう。
無理をする必要はありません。もちろん嘘をつかないように、自分の経験の範囲でできる限り探してみてください。
「自己PRのやり方がまだよくわからない…」という人は、以下の記事を参考にしてみてください。意識すべき自己PRの型や基本構成などが、わかりやすくまとまっていますよ。
志望業界別!探究心をアピールする自己PR例文5選

業界ごとに求められる資質やスキルが異なる中で、探究心をどうアピールすれば効果的か迷う就活生は少なくありません。企業側が関心を持つのは、単なる「興味」ではなく、課題を深掘りし続ける姿勢や行動力です。
本章では、志望業界ごとの特性に応じて効果的にアピールするための、探究心の自己PR例文を紹介します。自身の志望業界に照らし合わせながら、適切な伝え方のヒントを得てください。
- IT業界志望の例文
- コンサル業界志望の例文
- メーカー(技術職)志望の例文
- 広告業界志望の例文
- 金融業界志望の例文
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①IT業界志望の例文
ここでは、IT業界志望の方向けの、「探求心」を強みとした自己PR例文を添削しています。
探究心を「どのように行動へ移したか」「成果にどうつながったか」を具体的に書くことが重要です。
| 【結論】 私の強みは、疑問を持ったことをとことん調べ、理解するまで行動を止めない「探究心」です。 |
| 添削コメント|この結論部分は、強みの本質である「探究心」が簡潔にかつ明確に伝わっており、非常に良い出だしです。抽象語に頼らず、「行動を止めない」といった具体的な姿勢まで示されている点が高評価に繋がります。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、プログラミング初心者向けの勉強会を運営することになりました。 |
| 添削コメント|元の表現は自己評価としてややネガティブで、企業側に不安感を与える可能性があります。「理解を深める必要があると感じた」と言い換えることで、前向きな問題意識と探究の起点が伝わりやすくなり、印象が良くなります。 |
| 【エピソード詳細】 その課題を克服するために、自ら基礎から学び直し、 |
| 添削コメント|行動内容に5W1Hの視点(どの教材を、どのように、なぜ使ったか)を取り入れたことで、具体性と再現性を増しています。また、PDCAサイクルに似た姿勢はIT業界で重視される思考習慣であり、評価につながります。 |
| 【成果】 その結果、回を重ねるごとに参加者の理解度が高まり、「説明が分かりやすい」といった声を多くいただくようになりました。最終的には、 |
| 添削コメント|成果は定性的な表現にとどめず、できる限り数字や客観的データを交えて具体的に示しました。人数やアンケート結果を入れることで、他者からの評価と継続性の証明ができ、説得力が大きく増します。 |
| 【入社後】 入社後もこの探究心を活かし、 |
| 添削コメント|「技術や知識の習得に積極的に取り組む」を、「学習計画」や「仕組みや背景から理解」とさらに具体的な行動に置き換えたことで、「継続的な学習姿勢」というIT業界の特性との親和性も明確にしつつ、印象に残りやすくしています。 |
【NGポイント】
探究心をアピールしたい意図は伝わっていたものの、エピソードや成果において具体性がやや不足していた点が課題でした。とくに、「教材を読み比べた」などの表現は、第三者が読んでも行動や結果の実態が見えづらく、印象が薄くなりがちでした。
【添削内容】
どのような教材を使ったのか、どのように改善を試みたのか、具体的な手段やフィードバックの活用例を加えました。成果部分では、人数やアンケート結果といった定量的な情報を補強することで、説得力と客観性を高めました。
【どう変わった?】
企業から見た際、「自ら課題に気づき、主体的に学び、改善を繰り返す力」が伝わる内容に仕上がっています。IT業界で重視される自走力や継続的学習力が自然に伝わる構成となり、入社後の活躍イメージまで持たせられる文章
に進化しました。
| ・成果をできるだけ定量的に示す ・どのように探求していたのか明確に示す ・継続的な学習意欲をアピールする |
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②コンサル業界志望の例文問題解決
ここでは、コンサル業界志望の方向けの、「探求心」を強みとした自己PR例文を添削しています。
仮説検証や情報収集の過程が分かるよう、行動と成果を因果関係で結ぶことが大切です。
| 【結論】 私の強みは、 |
| 添削コメント|「深く掘り下げる」は抽象的なため、コンサル業界では「構造的に捉える力」や「因果関係を明確にする力」が求められることを踏まえ、強みの表現をより具体的かつ業界に即した言い回しに変更しました。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動では、 |
| 添削コメント|「地域活性化に関するプロジェクト」というではやや曖昧で、課題の内容が伝わらず、アピール力が弱まります。プロジェクトのテーマを明確化することで、業務理解度の高さと自らの役割がより具体的に伝わるようにしました。 |
| 【エピソード詳細】 最初は「認知度の低さが原因」という仮説を立てましたが、SNSの分析や現地調査を重ねた結果、 |
| 添削コメント|「交通の不便さ」や「より具体的な課題」という曖昧な表現を、分析の結果としてどう結論づけたのかを論理的に示しました。加えて、行動のプロセス(定量→定性アプローチ)を具体的に記載し、「探究心=仮説検証の姿勢」が伝わるようにしています。 |
| 【成果】 調査結果をもとに「駅からの周遊バス路線案」を提案し、ゼミ内の発表会で高評価を得ました。 |
| 添削コメント|「粘り強く繰り返す」など抽象的だった成功要因を、「行動→具体的成果→第三者評価」の流れに変え、客観的で成果の伝わる内容にしました。実際の「評価者の反応」も含めることで信ぴょう性を高めています。 |
| 【入社後】 入社後も、常に情報の裏側まで |
| 添削コメント|「深く掘り下げ」や「実行可能な提案」は汎用的であり、コンサル業務との結びつきが弱く感じられます。「定量・定性」「構造化」といった専門性ある表現へ置き換えることで、探究心を業務スキルとしてアピールできる内容に昇華させました。 |
【NGポイント】
取り組みの内容や成果を曖昧に伝えていた点が課題でした。また、強みとしての探究心も抽象的な表現に留まり、実際の行動や成果と結びついていなかったため、自己PRとして説得力に欠ける構成になっていました。
【添削内容】
プロジェクトの具体的なテーマや課題設定、調査プロセス、検証手順、成果の、一連の流れが論理的に伝わるよう修正しました。特に「誰に・どのように評価されたか」「どのような行動を取ったか」が明確になるよう重点的に修正しています。
【どう変わった?】
「再現性のある行動」や「問題解決力」が、具体的なプロセスと成果によって明確に伝わるようになりました。探究心という強みが、実務でも活かせる能力であるとイメージできる内容になり、コンサル業界との親和性も格段に高まりました。
| ・行動と成果との因果関係を意識する ・仮説検証の過程を論理的に描く ・評価者の声を具体的に示す |
③メーカー(技術職)志望の例文
ここでは、メーカー業界志望の方向けの、「探求心」を強みとした自己PR例文を添削しています。
メーカー技術職向けの自己PRでは、調査手順や分析結果に一貫性を持たせ、論理的な思考力と改善への応用力を明確に示すことが重要です。
| 【結論】 私の強みは、疑問を持ったことに対して |
| 添削コメント|「納得するまで」は主観的で曖昧な印象を与え、行動の具体性が伝わりにくくなります。そこで、「論理的に理解できるまで」とすることで、技術職としての調査力や分析志向を明確にアピールできるように修正しました。 |
| 【エピソード】 大学のゼミで「製品の使用感向上」をテーマにしたグループ課題に取り組んだ際、私は |
| 添削コメント|「リーダーとして活動」は一見好印象ですが、強みである探究心との直接的な関係が弱く、アピールの軸がぶれてしまいます。調査・分析を主導したことを明確にすれば、技術職が求める「自ら問題を深掘りする姿勢」としてより効果的に伝わります。 |
| 【エピソード詳細】 既存の製品レビューを |
| 添削コメント|「多く」は曖昧な表現なので「100件以上」と具体的な数値にすることで説得力を高めました。また、「操作性の差異を比較しました」は抽象的すぎるため、「操作ステップでの使いづらさを分解して記録」と具体化し、どのように探究したかを明確にしています。 |
| 【成果】 結果的に、操作手順の一部が直感的でないことが課題であると判明し、 |
| 添削コメント|「高く評価され」だけでは誰にどう評価されたかが不明確です。そこで、修正後ではどの点が評価されて賞を得たのかを補足することで、行動と成果の因果関係を明確にしています。 |
| 【入社後】 入社後も、 |
| 添削コメント|「利用者目線に立った探究心」は抽象的で伝わりづらいため、企業での活かし方として具体的に表現する必要があります。技術職では「構造的に調査し、実行に移せる力」が求められるため、課題解決につなげる行動として描くことで実践的な印象を与えられます。 |
【NGポイント】
内容全体で探究心の表現が曖昧だった点が問題でした。「納得するまで」や「多く」などの表現は具体性に欠け、企業が期待する論理的思考や調査の深さが伝わりませんでした。また、成果も自身の探求心との繋がりが見えにくくなっていました。
【添削内容】
行動量を示す数値の明記や、改善プロセスをより詳しく表現し、探究心を活かして課題を深掘り・検証する姿勢が伝わるよう調整しました。さらに、成果や入社後の内容にも具体的な要素を加え、再現性のあるアピールに仕上げています。
【どう変わった?】
行動の具体性や成果の根拠が明確になり、「この人物なら現場で再現できそう」と感じられる内容に改善されました。特にメーカーの技術職において重要な「課題の構造化・検証プロセス」がしっかり伝わり、志望職種との親和性が高まりました。
| ・数字や工程で調査の深さを示す ・エピソードと強みの関係を一貫させる ・抽象的な表現をなるべく減らす |
メーカー、製造業の自己PRについて、さらに詳しく解説した以下の記事もおすすめです。求められる人物像や業界別の例文なども掲載しているので、製造業を志望する人は必見ですよ。
④広告業界志望の例文
ここでは、広告業界志望の方向けの、「探求心」を強みとした自己PR例文を添削しています。
広告業界では、仮説→調査→検証→提案の論理的な思考プロセスを明確に示すことで、探究心を実務にどう応用できるかを意識して書くことが大切です。
| 【結論】 私の強みは、物事を深く考え続け、 |
| 添削コメント|「納得するまで」は主観的かつ曖昧で、行動の具体性や再現性が伝わりません。「根拠や背景を把握するまで」と言い換えることで、広告業界で求められる論理的思考や分析志向を明確に伝える表現になっています。 |
| 【エピソード】 大学ではマーケティングのゼミに所属し、ある企業の若年層向け商品の購買動機を調査する課題に取り組みました。 |
| 添削コメント|業界と関連性の高いマーケティングゼミでの活動を簡潔に示しており、職種への適性が伝わりやすい良い導入です。調査対象も広告分野に直結しており、読み手に自然に強みの文脈を届けられています。 |
| 【エピソード詳細】 当初は既存の統計データをもとに仮説を立てましたが、 |
| 添削コメント|「納得できる答えが見つからず」は感覚的な表現で、行動や判断の根拠が不明瞭でした。修正後は「整合性に違和感」とすることで、情報を論理的に検証する過程が伝わりやすくなり、探究心の発揮がより明確に表現されています。 |
| 【成果】 この分析結果はゼミ内でも高く評価され、企業に提出した提案資料の中心的な内容として採用されました。 |
| 添削コメント|良い成果ですが、削除した箇所は抽象的で誰の評価か明確でなく、成果としての説得力に欠けていました。修正後は具体的な人物と評価内容を示すことで、就活生の取り組みが企業目線でも実践的だったことがより伝わる文章に改善されています。 |
| 【入社後】 貴社でも、ユーザーの本音を丁寧に探る姿勢を大切にし、 |
| 添削コメント|「背景にある行動心理を深掘り」は抽象的で、どう行動するのかが曖昧でした。具体的に「仮説とデータの照合」を通じた分析と表現することで、広告業界で重視される企画・提案力につながる実務的な思考が伝わる内容に修正されています。 |
【NGポイント】
元の文章では、「好評をいただきました」など主観的な言葉が多く、読み手に伝わりづらい印象を与えていました。また、仮説と行動のつながりが弱く、探究心がどのように行動や成果に結びついているのかが見えにくくなっていた点も課題でした。
【添削内容】
曖昧な言葉を論理的・定量的な表現に置き換えました。「整合性に違和感」「担当者からのフィードバック」など、判断や評価に根拠を持たせたことで、探究心をもとにした行動と成果の流れがクリアになりました。
【どう変わった?】
自分の強みをどのような思考と行動で発揮したのかが明確になり、企業目線での評価もしやすくなりました。特に、広告業界における「企画力」「分析力」との結びつきが強化され、実務に活かせる強みとして伝わる内容に改善されています。
| ・行動を起こした根拠を明記する ・どうしてその努力をしたのかを明確に示す ・仮説→検証→提案のプロセスをアピールする |
⑤金融業界志望の例文
ここでは、金融業界志望の方向けの、「探求心」を強みとした自己PR例文を添削しています。
金融業界を志望する場合、調査と考察の具体性を意識し、情報収集力の成果が伝わる内容に仕上げることが大切です。
| 【結論】 私の強みは、疑問に思ったことをとことん調べて理解しようとする「探究心」です。物事を表面的に捉えず、背景や仕組みにまで踏み込んで考える姿勢を大学生活で磨いてきました。 |
| 添削コメント|結論部分では、自身の強みである「探究心」を端的かつ明瞭に伝えられています。特に就活生が陥りがちな抽象的な表現を避け、「理解しようとする姿勢」まで踏み込んで説明できている点が好印象です。 |
| 【エピソード】 大学2年の時、株式投資に関する授業をきっかけに、経済全体の動きが株価にどう影響するのかという疑問を持ちました。 |
| 添削コメント|削除した箇所は「知識を深めた」という表現が抽象的で、行動の中身が見えづらい点が課題でした。金融業界では「情報をどう扱い、どう判断したか」が問われるため、改善文では探究のプロセスが伝わるよう、収集や分析といった具体的行動を明示することが重要です。 |
| 【エピソード詳細】 授業以外でも日経新聞を毎日読み、気になった経済ニュースについては、背景や関連情報を調べ、ゼミのディスカッションでも積極的に発言しました。また、 |
| 添削コメント|「調査・整理・レポートにまとめた」という元の記述は曖昧で、どのような知識をどれだけ深めたのかが見えませんでした。改善後は「いつ・何を・どのように調べて・どう発表したか」を明確にし、探究心を深掘りできた行動を具体的に示しています。 |
| 【成果】 その結果、ゼミ内で経済動向に強い学生として認識され、学外の学生討論会でもリーダー役を任されました。学内のゼミ発表では、経済分析の視点と資料の正確性が評価され、教授から学生代表として外部セミナーでの発表の機会も得ました。データや複数の視点をもとに考察する姿勢が高く評価されました。 |
| 添削コメント|元の表現は「リーダー役を任された」ことと探究心との直接的なつながりが弱く、評価の根拠も不明確でした。改善文では、教授からの推薦という客観的評価と「分析力」「発信力」が認められた具体的成果を示し、企業にとって信頼性の高い評価材料となっています。 |
| 【入社後】 貴社においても、情報の本質を見極める姿勢を活かし、常に変化する経済環境の中で最適な提案ができる人材を目指します。 |
| 添削コメント|「学びと情報収集」という抽象的表現では、入社後にどう貢献するかのイメージが曖昧でした。改善後は、調査・分析・提案といった金融業務に直結する行動を明示し、「探究心を実務でどう活かすか」という点を読み手に具体的に想像させる内容に仕上げています。 |
【NGポイント】
成果や入社後の意欲を示す部分で、「探究心」がどう企業に活かされるかが曖昧でした。また、エピソードの具体性が弱く、「経済指標を追いかけた」など抽象表現に終始していた点も問題でした。
【添削内容】
「抽象的で分かりづらい表現」を削除し、代わりに「何を調べたか」「どう分析したか」「どんなアウトプットをしたか」といった具体的な行動内容に言い換えました。また、成果部分では教授からの評価など第三者視点に置き換えました。
【どう変わった?】
探究心が「自分の内面の姿勢」だけでなく、「実際の行動」「学びの成果」「周囲からの評価」にまで結びつく構成になりました。結果として、企業が求める「自ら調べ、深く理解し、他者に価値を提供できる力」が伝わる文章へと改善されています。
| ・第三者評価で成果の説得力を補強する ・どうしてその努力をしたのかを明確に示す ・入社後の強みの活かし方は実務に結びつける |
エピソード別!探究心の強みを伝える自己PR例文5選

探究心を自己PRで伝える際、多くの就活生が「どのようなエピソードを例に出せば伝わるのか」と悩みがちです。特に具体性が求められる自己PRでは、自分の行動の裏にある思考や工夫を明確に言語化することが重要です。
そこで本章では、探究心を効果的にアピールできるエピソード別の例文を紹介します。ぜひ、自分に近いエピソードを見つけ、自分なりの自己PRを作成する際の参考にしてください。
- アルバイト経験をアピールする例文
- ゼミ・研究での活動をアピールする例文
- インターンでの経験をアピールする例文
- 留学経験をアピールする例文
- ボランティア活動をアピールする例文
ここまでいくつかの志望動機例を見てきましたが、ここではまた別のテーマの例文を添削しながら解説していきます。気になる例文を見て参考にしてみてくださいね。
また、実際に無料で志望動機を添削をしたいと思った方はまずはLINE登録してみてください!完全無料で添削依頼し放題ですよ。
①アルバイト経験をアピールする例文
ここでは、アルバイト経験をエピソードとした、「探求心」の自己PR例文を添削しています。
アルバイト経験を使う際は、探究心が強いとアピールするだけでなく、どう行動して成果に結びつけたのかまでしっかり説明することが大切です。
| 【結論】 私の強みは、課題の本質を深く探り、解決策を見出す「探究心」です。 |
| 添削コメント|結論としての文章はシンプルながら、他の強みと差別化しやすい「探究心」に的を絞れている点が良いです。抽象的すぎず、すぐに具体的なエピソードが続く構成になっており、読んだ担当者も関心を持ちやすいでしょう。 |
| 【エピソード】 大学時代、カフェのアルバイトで |
| 添削コメント|「~に気づき」は主観的で就活生本人の思い込みとも捉えられがちです。改善案では売上データという客観的な根拠を用いることで、問題意識の背景に説得力を持たせています。 |
| 【エピソード詳細】 平日と休日の来店者数や注文内容を記録し、常連のお客様にもヒアリングを行った結果、 |
| 添削コメント|元の文章だけでは論理の飛躍があり、探究心の過程が伝わりません。改善後はヒアリング内容をもとに考察を行っており、探究→仮説→検証の流れが明確にしています。 |
| 【成果】 その結果、2ヶ月後には客単価が約15%向上し、 |
| 添削コメント|数字の裏付けが弱かった点を、「アンケート結果」や「再来店者数」など明確なデータに基づく表現へ修正しました。成果に具体性と信頼性が加わったことで、アピールがより客観的になり、採用担当も納得しやすい内容になっています。 |
| 【入社後】 貴社においても、このように課題を深く掘り下げ、仮説を立てて検証する姿勢を活かし、 |
| 添削コメント|「~を活かして成果を追求します」という表現では曖昧で伝わりづらかった部分を、より具体的に業務内での行動に落とし込んだ表現に修正しました。 |
【NGポイント】
課題への気づき方や成果の伝え方が曖昧で、探究心が発揮されたプロセスが十分に伝わっていませんでした。また、因果関係が薄く、説得力のあるエピソードとして成立しにくい点も見受けられました。
【添削内容】
気づきのきっかけを売上データに基づいた表現に変更し、エピソード詳細ではヒアリングから課題特定までの流れを明確化しました。また、成果に関しても数値的な根拠と具体的な変化の説明を加えることで、行動と結果の因果関係を示しました。
【どう変わった?】
問題提起から課題発見、改善提案、成果創出の流れが論理的につながり、「探究心」の説得力が高まりました。企業から見ても、入社後に自発的に課題を掘り下げ、具体的なアクションに結びつけられる人材であると評価されやすくなったでしょう。
| ・探求心を発揮した状況背景を明記する ・業務での再現性を意識して経験をアピールする ・成果を定量的に表現する |
②ゼミ・研究での活動をアピールする例文
ここでは、ゼミ活動をエピソードとした、「探求心」の自己PR例文を添削しています。
ゼミでの活動を自己PRのエピソードにする場合、協調性のなさや独りよがりな雰囲気を感じさせないことが大切です。
| 【結論】 私の強みは、 |
| 添削コメント|もとの表現はシンプルすぎて差別化が弱く、具体性に欠けていました。改善後は「掘り下げ」「論理的に解決策を見出す」といった要素を盛り込み、企業が期待する探究心のあり方に近づけています。 |
| 【エピソード】 大学のゼミでは「地域活性化と観光」というテーマのもと、観光客の増減と地元商店街の売上との関係性について仮説を立てました。 |
| 添削コメント|この項目に大きな問題はありません。課題と仮説の流れがスムーズで、研究内容も社会的意義があるため、探究心を語る題材としてふさわしい構成です。 |
| 【エピソード詳細】 初めはインターネットや文献を通じて情報を集めましたが、 |
| 添削コメント|「実態とのズレを感じた」は主観的で根拠が曖昧でした。改善後は、情報の限界を論理的に判断したという形に修正し、探究心の発露として自然な流れにしています。また、アンケートについても目的・対象・規模を具体的に補足し、行動の説得力を高めました。 |
| 【成果】 その結果、観光客数の増加が必ずしも商店街の売上につながっていないことが判明し、 |
| 添削コメント|「ターゲット層に応じた販促施策」は抽象度が高く、施策の中身が読み手に伝わりづらい表現でした。改善後は年齢層やニーズといった具体的な視点を加えることで、考察の深さと課題へのアプローチの的確さがより明確に伝わるようになっています。 |
| 【入社後】 入社後も課題や疑問に対して深く掘り下げ、情報を自ら分析する姿勢を活かし、 |
| 添削コメント|「業務改善」や「提案」という表現だけでは、どのように活躍するかが曖昧です。改善案では、顧客視点やデータ分析といった再現可能な具体行動に言及することで、企業で活躍する姿を明確にイメージしてもらえる内容に仕上げています。 |
【NGポイント】
疑問に向き合う姿勢は伝わっていたものの、全体的に主観的な表現が多く、思考の深さや行動の具体性が弱くなっていました。また、アンケートや分析の記述に曖昧な点があり、どんな工夫をしたのかが伝わりにくい点も課題でした。
【添削内容】
結論部分では「調べて解決する」を、論理的思考を強調する内容に言い換えました。エピソードでは、判断の根拠や調査の目的、規模を具体化しました。入社後の活かし方も職務内容に近い表現に調整しています。
【どう変わった?】
探究心という抽象的な強みが、「データを精査し、仮説検証を通じて解決策を導く力」として明確化されました。また、ヒアリングやアンケートの実施背景とその工夫が明示されたことで、再現可能なスキルとして伝わる自己PRになっています。
| ・ヒアリングを行った背景を明記する ・調査対象と調査手段を明確に示す ・抽象的な表現をなるべく減らす |
③インターンでの経験をアピールする例文
ここでは、インターン経験をエピソードとした、「探求心」の自己PR例文を添削しています。
「課題→行動→成果」の流れを伝えるだけでなく、入社後にも十分に再現性があることを印象付けるようにしましょう。
| 【結論】 私の強みは、課題に対して主体的に調べ、 |
| 添削コメント|「最適な方法を探し出す」は抽象的で、他の学生の表現と差別化しづらいため注意が必要です。「自ら見つけ出し、実行する」という具体的な表現により、探究心が“行動力を伴う強み”であることが明確になり、企業にも伝わりやすくなります。 |
| 【エピソード】 大学3年次に参加した長期インターンで、業務の中で |
| 添削コメント|「気づいた」という主観的表現では、課題発見に至る根拠が弱くなります。業務の何が非効率だったかを明示し、どの業務に探究心を発揮したのかが伝わるように修正することで、企業がその行動の価値を正確に理解できます。 |
| 【エピソード詳細】 私はまず、 |
| 添削コメント|「洗い出し」や「無料ツールの活用」といった表現は曖昧で、実際にどのような工夫をしたのかが伝わりづらくなります。「可視化」「組み合わせて活用」などの具体的な行動を示すことで、探究心が“課題解決への実践力”として伝わる内容に改善されています。 |
| 【成果】 ツール導入後、分析作業にかかる時間が約50%削減され、他の業務にリソースを割けるようになりました。 |
| 添削コメント|成果の評価は「誰から、どんな場面で、どのようにされたのか」を明確にすることで説得力が増します。「社内報告会」などの具体性を加えることで、探究心が組織貢献にもつながる実績として、客観性をもってアピールできる形に仕上がっています。 |
| 【入社後】 入社後も、目の前の業務に |
| 添削コメント|「疑問を持ち〜」は抽象的で行動のイメージが曖昧になりがちです。「調べ、提案する」といった具体的な動作に置き換えることで、企業に入ってからも実務で探究心を発揮できる人材であることが明確に伝わる表現に改善されました。 |
【NGポイント】
業務に対して感じた「非効率さ」や「課題」への気づき方が曖昧で、読んだ側にとって納得感が弱い文章になっていました。また、行動や成果の記述がやや抽象的で、「探究心をどのように発揮したのか」が十分に伝わらない部分も見受けられました。
【添削内容】
問題提起の表現を客観性のある描写に変更し、読者が状況を正確に理解できるようにしました。さらに、自ら調査・提案・改善に取り組んだプロセスを具体化し、課題に対して主体的に深掘りする探究心が伝わるように調整しています。
【どう変わった?】
一連のエピソードにおける行動と成果の因果関係が明確になり、探究心が実務につながる力であることが具体的に伝わる構成になりました。企業の採用担当者にも「現場での課題発見力と改善提案力がある人物」として印象づけられる内容です。
| ・問題点に気づいた理由を具体的に説明する ・行動の流れは5W1Hで具体的に示す ・抽象的な表現をなるべく減らす |
④留学経験をアピールする例文
ここでは、留学経験をエピソードとした、「探求心」の自己PR例文を添削しています。
留学経験を通じた自己PRでは、行動の具体性と成果の客観性を意識することが重要です。特に「何を、なぜ、どのように探究したか」を明確にしましょう。
| 【結論】 私の強みは、物事を深く理解しようとする探究心です。 |
| 添削コメント|元の文は「気になったことに調べて行動した」というよくある表現になっていたため、改善後は「自分で調べ」「意見を取り入れ」「掘り下げて考える」といった具体行動を示すことで、探究心の再現性と差別性を高めました。 |
| 【エピソード】 大学2年次に、語学力を高めたいという思いから短期留学に参加しました。現地の学生と交流を深める中で、 |
| 添削コメント|「〜と感じました」を「〜に気づいた」と言い換え、探究心が芽生えたきっかけを明確にしました。また、初めの動機(語学)と後の学び(文化)をセットで示し、「異文化理解」と「探究心」の両方が軸として明確になるよう工夫しました。 |
| 【エピソード詳細】 そこで私は、相手の文化背景を理解することが関係構築の第一歩だと考え、 |
| 添削コメント|元の文は「調べた」「質問した」で終わっており、探究心の深さや具体的な行動が伝わりにくい表現でした。修正後は、どこで(図書館)、何を(宗教・伝統)、どうやって(質問・ノート・活用)という5W1Hを踏まえて明確化しています。 |
| 【成果】 その結果、 |
| 添削コメント|成果の文では、「安心できる」という主観的なフィードバックに留まっていたため、具体性に欠けていました。改善後は、会話の変化やグループ内での役割といった客観的な成果を盛り込み、行動→結果の流れを明確化しています。 |
| 【入社後】 入社後もこの探究心を活かし、新しい分野や業務に対しても |
| 添削コメント|「分からないことをそのままにせず」は汎用性が高く、他の就活生と差別化しにくい表現です。業務に応じた行動(情報収集・意見を聞く・本質を見極める)を明示することで、企業での活躍イメージが具体的に湧く内容に改善しました。 |
【NGポイント】
エピソードの一部が表面的な描写に留まり、具体的な行動や成果が伝わりにくい状態でした。特に、単に「調べた」「質問した」などの言葉を用いることで、どのような姿勢でどう掘り下げたかが不明確でした。
【添削内容】
探究心をアピールするために、「なぜそう思ったか」「どのように動いたか」「どう役立てたか」を筋道立てて補強しました。抽象的だった部分には、ノート整理や図書館での調査、グループ内での役割など具体性を加えました。
【どう変わった?】
探究心という強みが、エピソードの中で具体的にどう発揮されたかが明確になり、再現性を評価しやすい自己PRになりました。また、留学というテーマにおいて「異文化理解を深めるために自発的に動いた姿勢」が際立ちました。
| ・気づき→行動→成果の流れを意識する ・どうしてその努力をしたのかを明確に示す ・入社後の活かし方も筋道立てて述べる |
⑤ボランティア活動をアピールする例文
ここでは、ボランティア活動をエピソードとした、「探求心」の自己PR例文を添削しています。
ボランティア活動をアピールする際は、単なる参加経験にとどまらず、調査・提案といった主体的な行動が含まれているかを意識しつつ書きましょう。
| 【結論】 私は、 |
| 添削コメント|「物事の背景や仕組みを知る」は探求心の説明としては他の学生と表現が被りやすい表現でした。そこで、探究心の「行動レベルでの発揮」に焦点を当てることで、主体性と実行力を明確にした表現で追記しました。 |
| 【エピソード】 大学2年の夏、地域の清掃ボランティアに参加した際、 |
| 添削コメント|「表面的な活動」という曖昧な表現は、読者が具体的にイメージしにくいためNGです。違和感をきっかけに探究心が発揮された点を丁寧に言語化することで、行動の動機づけが明確になります。 |
| 【エピソード詳細】 そこで、1か月間にわたり地域のゴミの分布や住民の通行量を記録し、原因を分析しました。 |
| 添削コメント|この段落では、5W1Hの視点が不十分で調査の信頼性や行動の実行力が伝わりにくかったため、具体的な調査手法・対象者・得られた結果を補いました。探究心を「深く掘り下げる行動」として示すには、情報の粒度がカギです。 |
| 【成果】 この調査結果を自治体に提出し、ゴミ箱の追加設置や啓発活動の実施につながりました。 |
| 添削コメント|「やりがいを感じた」は主観的で成果の訴求力に欠けます。成果部分では、第三者からの反応や環境の変化など、客観的事実を交えることで、企業にとって「再現可能な能力」であると説得力を持たせることが重要です。 |
| 【入社後】 入社後もこの探究心を活かし、現場や顧客の声に耳を傾けながら、 |
| 添削コメント|「課題の本質を見抜く」という表現を、よりイメージしやすい「どんな行動をするか」で置き換えるため、「収集・分析・構造把握」といった具体的な行動で表現しました。 |
【NGポイント】
全体として、行動の具体性が足りず、何をどう工夫したのかが伝わりにくい構成でした。特にエピソード詳細と成果では、調査の方法や結果の影響がぼんやりとしており、企業側が評価しづらい内容になっていました。
【添削内容】
調査内容の5W1Hを明確に示し、聞き取り対象や手法も具体化しました。また、成果に関しても、住民の反応や環境の変化など第三者視点の情報を追加して、探究心が周囲に与えた影響を明確にしました。
【どう変わった?】
表現が抽象的なままでは伝わりづらかった探究心が、調査・分析・提言といったプロセスを通じて行動として伝わる内容に改善されました。企業側が再現性を感じられる、実務に近い自己PRになったと言えるでしょう。
| ・読み手が状態をイメージできるように書く ・自分の行動によって起きた変化を明確に示す ・入社後の活かし方を行動ベースで記述する |
自己PRが書けたら、添削をすることも重要です。以下の記事を参考に自身の自己PRをブラッシュアップさせていくことで、より評価を得られる自己PRが完成しますよ。
探究心を自己PRするNG例文3パターン

ここでは、探究心を自己PRする際に避けたいNG例文として以下の3パターンを紹介します。
①再現性がないと判断される
| 私は、気になったことはとことん調べないと気が済まない探究心の強さを強みとしています。 私は幼少期より恐竜が好きで、家にあった図鑑に載っている恐竜の名前はすべて覚えて絵にかけるほどでした。大学に入ってからも恐竜研究会に入り、日本全国の博物館を回っては恐竜に対する知識を深めて参りました。御社に入社した後も、持ち前の探究心の強さを活かして与えられた仕事に対してとことん理解を深めていきたいと考えております。 |
探究心の強さをエピソード付きで説明しようとしていますが、残念ながら上記のように自分の活動を羅列するだけでは仕事での再現性を感じられません。
たとえば「博物館と協力して情報発信をして○○の成果につなげた」など、仕事への活かし方を感じさせるようなエピソードが望ましいでしょう。
②柔軟性がないと思われてしまう
| 私の強みは、成果のためには何でもする探究心の強さです。 私は大学にてサッカーサークルに所属しております。大会での勝利を目標に活動していましたが、メンバーの半数が初心者であることもあり、なかなか試合で勝つことができませんでした。そこで私は練習方法を研究したうえでメンバーに徹底し、反対するメンバーは試合に出さないことで試合に勝利することができました。 御社でもこうした経験を活かし、成果のためには何でもするつもりで頑張りたいと考えております。 |
サークル活動をテーマにすること自体はもちろん問題ありませんが、探究心を強調する際の弊害である柔軟性のなさを感じさせる内容になってしまっています。
練習方法に対してメンバーからの反発を受けた際にどう乗り越えたのか伝え、より柔軟性を感じさせる内容にすることが望ましいでしょう。
企業がなぜ柔軟性を必要としているのかを理解することで、より企業のニーズにマッチした自己PRを作成することができます。こちらの記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
③具体的なエピソードが盛り込まれていない
| 私は少しでも気になることがあると、その他のことを考えられなくなってしまいます。周囲からも「知的好奇心が強い」「夢中になるとそれ以外何も見えなくなる」などとよく言われます。興味のないことに時間を使うことがあまり好きではなく、自分の大切な時間を使うのであれば気になることだけと決めているのです。御社に入社してもこの探究心の強さを活かして、業績アップに貢献したいと考えております。 |
探究心の強さを主張する際には、その根拠として具体的なエピソードを盛り込むことが大切です。
採用担当者からすると、「どうしてそう言えるの?」「どんな風に熱中するの?」と疑問が絶えないでしょう。
採用担当者の疑問を払しょくするように、具体的なエピソードを盛り込むことが大切です。
自己PRで探究心をアピールしましょう!

探究心とは物事をとことん調べて真理に近付こうとする姿勢や能力のことであり、就活の自己PRでも十分にアピールポイントになります。
自己PRの構成やポイントを押さえ、探究心の強さを採用担当者に印象付けましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













