【例文あり】内定の保留メールの書き方は?ポイントや注意すべき点を解説!
複数の企業から内定をもらったり、第一志望の企業からの結果を待たずに他社から内定を得た場合、返答を待って欲しいと思いますよね。
そのような時は、企業に内定保留をお願いするのが得策ですが、場合によってはリスクも伴うので注意が必要です。
そこで、本記事では内定の保留メールを申し出る際のポイントや注意すべき点を例文を交え解説します。
さらに、内定保留のメリットやデメリットも紹介しますので、気になる人はぜひ最後までよんでみてくださいね。
就活中のメール対応はこれだけでOK!
- ◎メールが最短3分で書けるテンプレシート
- 「このメールで失礼じゃないかな…」と悩みがちな場面でも、コピペするだけで安心してメールを送れる
そもそも内定保留できる?

内定を保留することは可能です。
企業の多くは、内定者が納得した上で入社を決めて欲しいと考えているため、企業と内定者双方で決めた期間中の返答であれば、内定保留できます。
内定保留に関する期間やリスクについて解説しましょう。
①一般的な保留できる期間
一般的に、内定保留できる期間はおよそ1週間以内です。
内定の連絡をもらった際に、いつまでに返事をすればいいのか予め確認しておくと、その後の流れもスムーズにいくでしょう。
しかし、企業側も、内定辞退者が出れば更なる採用活動を続けたり、入社手続きに遅れが生じるため、より早めの返事が好ましいです。
②保留できないケースもある
内定保留の連絡をすることで、内定が取り消しになることもあります。
特に、急に人が辞めて1日でも早く入社してほしい場合や入社意欲を大事にしている企業は、内定保留自体を認めない場合もあるでしょう。
また、双方が納得の上で決めた保留期間を過ぎても返答がない場合は、内定を取り消されることもあるので、内定の返答はなるべく早めにして下さい。
内定保留をする際は、人事担当者に入社したい気持ちをアピールし、誠実に対応する必要があります。
内定保留を考える主な理由

内定保留を考える就活生の主な理由を3つにまとめたので紹介します。
①他社の選考結果を待ちたいから
就活生の中には、他にも受けている採用試験の結果を待ってから、内定の返答をしたいと考えている方も多いでしょう。
第一志望の結果がまだなら尚更だと思いますが、だからといって、内定保留する理由に志望順位は触れてはいけません。
もし、志望順位に触れてしまうと、入社の意思が弱いと認識されてしまい内定を受諾した際にも気まずい雰囲気になってしまいます。
内定保留の理由は、「別の業界も志望しており検討したい」や「より能力を活かせる企業を見極めたい」などとお茶を濁しましょう。
②内定先企業に懸念点があるから
内定企業に何らかの懸念事項がある場合、本当に「この会社でいいのか」と迷いが生じるでしょう。
そのような場合は、懸念事項(業務内容・職場環境・労働条件など)を書き出してみて、採用担当者に質問してみて下さい。
内定先の企業も、納得したうえで入社してくれた方が長く務めてもらえる可能性が高くなるので、快く疑問に答えてくれるでしょう。
また、経営状況などは公開されているIR情報などを見て確認できます。(規模が小さな会社の場合、非公開の場合もあります)
③複数の企業から内定をもらい悩んでいるから
複数の企業から内定をもらっている場合、どこの会社にしようか悩む就活生も多いでしょう。
業務内容や労働条件を改めて比較検討し、自分のモチベーションを高められる企業を慎重に選ぶと後悔がありません。
しかし、自分では決められないくらい五分五分の場合は、家族や親しい人に相談し、客観的な意見をもらってもいいでしょう。
その上で、最終的に自分自身で後悔のない決断をして下さい。
ビジネスメールを楽に自動作成できる!【名前・大学名を入れるだけ!】
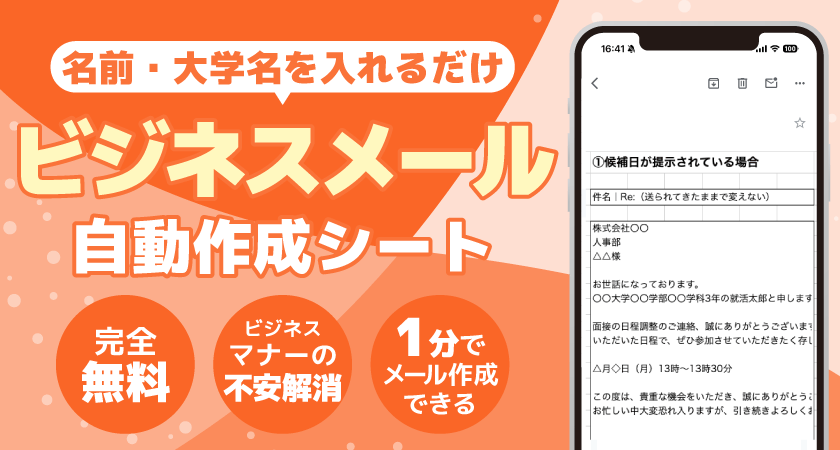
就活では、志望している企業とのメールでのやり取りが発生しますよね。例えば、面接の日程調整やリスケ・辞退の連絡を入れる際などです。
しかし、普段はLINEなどのSNSでの連絡がメインになっている学生にとっては基本的なメールマナーが分からないなんてこともありますよね。
そこで、就活マガジン編集部ではメールの作成に不安や苦手意識がある就活生のために「ビジネスメール自動作成シート」を無料で配布しています。初めてのビジネスメールの作成に不安がある場合はダウンロードしてみてくださいね。
メールマナーは調べれば出てくるものなので、企業も注意深く見ているしできていないとマイナス印象になるので、事前にマナーを押さえておくことが選考通過のコツですよ。
内定保留の3つのメリット

内定保留するメリットが3つありますので解説します。
①第一志望の結果見て判断できる
内定保留するメリットは、第一志望の結果を見て判断できることです。
また、第一志望でなくても、内定他社と比較検討できるので満足した結果を得やすいでしょう。
今後のキャリア形成や待遇面なども踏まえてどの企業に一番就職したいかを選択できます。
②ベストな選択ができ後悔しない
内定保留するメリットは、ベストな選択ができ後悔しないことです。
内定保留している間に、将来の就職先についてじっくり考えることができ、就職活動をやり切ることができるので後悔のない選択ができるでしょう。
「何も考えずに内定承諾してしまい、後悔している」または「もっと他の企業も受ければよかった」といった就活に未練を残さず入社できます。
③親しい人に相談できる
内定保留するメリットは、親しい人に相談できることです。
初めての就職の場合、実際にどの企業がいいのか分からないこともあります。
自分の性格や特性を知っている身近な家族や友人に相談し、客観的に見てどの企業の内定を受けるべきか判断してもらう方法もありますよ。
自分の判断と、親しい人の判断が合致した場合、自信につながるでしょう。
もし違っていても、周囲の意見を考慮したうえで後悔のない判断を下せます。
内定保留の4つのデメリット

内定保留するデメリットが4つあるので紹介します。
①内定取り消しの可能性がある
内定保留の最大のデメリットは、内定取り消しになることです。
企業によっては、すぐにでも来て欲しい急募の場合は、すぐに働ける人を採用したいため内定保留は認められない可能性があります。
その場合、内定承諾するか内定辞退するしか方法がないため、連絡する際に予め方向性を決めておきましょう。
しかし多くの企業では、1週間程度の内定保留なら待ってもらえる可能性が高いので、まずは相談して下さい。
②第一志望ではない事がバレる
内定保留のデメリットは、第一志望でないことがバレることです。
第一志望の場合、基本的に内定保留などする必要がないため、企業側に入社する意思が弱いと思われてしまう恐れがあります。
企業側は、入社する意欲の高い人を採用したいため、内定承諾を即答する内定者に比べ印象は悪くなるでしょう。
そのため、第一志望でなくても内定保留の際は、入社へ前向きに検討することをアピールしておきます。
③マイナスイメージになる
内定保留は、企業へあまりいい印象を与えないため、伝え方には気を付けましょう。
例えば、「一度家族と相談してお返事させていただいても宜しいでしょうか?」など相手が不快に思わない内容で丁寧な対応をして下さい。
企業が、内定保留の対応に応じるのは当然だと思わずに、不信感を抱かれないような前向きな理由で、誠実な対応を心がけましょう。
④場合によってはオワハラされる
内定保留のデメリットは、場合によってオワハラ(就活終われハラスメントの略)されることも稀にあります。
企業が他社への就活をやめるように働きかけることは、憲法22条の職業選択の自由の侵害に当たるので従う必要はありません。
また、内定を出す代わりに「他社への内定は辞退して下さい」と内定承諾を強要するようであれば、労働基準監督署へ相談しましょう。
いずれにしても、オワハラするような企業には就職しない方がいいです。
内定保留を申し出る4つのポイント

内定保留を申し出る4つのポイントを解説します。
内定保留を申し出る際のポイントを知っておけば、今後の流れがスムーズにいくでしょう。
①早めに伝える
内定保留を申し出る際は、なるべく早めに伝えて下さい。
企業が内定通知を出した後は、内定者のためにありとあらゆる準備を始めます。
内定式や入社式の段取りや、制服の手配や入社の事務手続きなどスケジュールをどんどん埋めていくので早めに連絡しないと迷惑が掛かるでしょう。
企業への迷惑を最小限に抑えるためにも、内定保留の相談は遅れてはいけません。
②電話・メールの2つの手段を使う
内定保留は、一刻も早く連絡すべき事由なので、まず電話で直接話しましょう。
電話だけでは記録に残らないため、メールでも二重に伝えておくと行き違いがありません。
しかし、担当者が不在の場合や電話で連絡が取れない場合は、メールで連絡しましょう。
メールで連絡する場合、見てくれたか確認に時間がかかるため、返信がないようであれば担当者に再度電話で連絡をとって下さい。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
③真心を込めて対処する
内定保留を申し出る時は、真心を込めて対処して下さい。
ここで言う真心を込めた対処とは、企業に対し入社意欲を示しつつも内定を待って欲しいと丁寧にお願いすることです。
たとえば、次のような言い方で対応します。
| 御社(貴社)へ入社したい気持ちは強くあるのですが、現在お約束している選考を受け切りたいので内定保留をお願いできませんでしょうか。 |
上記のような企業側が不快な気持ちにはならない言い方を心掛けて下さい。
④内定保留の期限を定める
内定保留を申し出る際は、いつまでに返答できるか内定保留の期限を明確に定めることが大切です。
一般企業の内定保留期間は、約1週間ですが、他社の選考状況を踏まえ、保留期間が長くなる場合は企業に相談して下さい。
保留期間が長くなればなるほど、企業側も不都合なことが出てくるので、必ずしも保留期間が保証されるわけではありません。
他の応募者が優先されることもあるので、企業の採用担当者と具体的な期日を決め、記録に残しておきましょう。
内定保留をする際の注意点

内定保留をする際の注意点を3つ紹介します。
①連絡する時間帯
内定保留の連絡をする時間帯は、企業の営業時間内に行いましょう。
また、始業や終業、昼休み前後の時間帯は忙しい可能性が高く、外出していることもあるため連絡は避けます。
業務が落ち着いている時間帯としては、9時半~11時半、14時半~16時半あたりが連絡を取りやすいでしょう。
連絡手段が電話やメールどちらであっても、同じように営業時間内に連絡して下さい。
②丁寧に謝罪する
内定保留は、あくまでもこちら側のわがままなので、丁寧に謝罪する必要があります。
面接で、応募者の100%入社したい気持ちに応え企業も内定を出したはずなのに、内定者からの内定保留は好ましく思われなくて当然です。
少しでも印象をよくするためにも、謝罪とともに入社したい意欲はきちんと伝え、内定保留をお願いしましょう。
③つながらない場合はかけ直す
内定保留を電話で連絡する際、つながらない場合はかけ直して下さい。
何度かけても担当者がつながらない場合は、メールで内定保留の連絡をしてもかまいません。
しかし、メールを送信しても、連絡が取れない場合は再度電話連絡して、きちんと内定保留の件を丁寧に伝えましょう。
内定を保留にする例文~電話編~

電話で内定保留にする例文を紹介しますので、参考にして下さい。
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
①第一志望の結果を待つ場合
第一志望の結果を待ちたい場合の内定保留の電話連絡は、次の通りです。
| いつもお世話になっております。 御社の採用試験で内定をいただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 お忙しいところ、突然のお電話失礼いたします。 この度は、内定のご連絡をいただきありがとうございました。 御社のような魅力的な会社から内定をいただき、とても嬉しく思っております。 しかしながら、現在お約束している面接が残っておりまして、全てをやり切った上で内定の承諾の有無をお返事をさせていただいても宜しいでしょうか。 大変勝手ではありますが、内定保留の猶予を〇月〇日までいただくことは可能でしょうか? (企業側の返答) 大変身勝手なお願いにもかかわらず、ご了承いただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。 |
②考える時間が欲しい場合
考える時間が欲しい場合の内定保留の電話連絡は、次の通りです。
| いつもお世話になっております。 御社の採用試験で内定をいただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 お忙しいところ、突然のお電話失礼いたします。 この度は、内定のご連絡をいただきありがとうございました。 御社のような魅力的な会社から内定をいただき、とても嬉しく思っております。 それ故に、御社に入社したい気持ちは十二分にあるのですが、一度家族と相談してお返事させていただいても宜しいでしょうか? また大変勝手ではありますが、内定保留の猶予を〇月〇日までいただくことは可能でしょうか? (企業側の返答) 大変身勝手なお願いにもかかわらず、ご了承いただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。 |
内定を保留にする例文~メール編~

メールで内定保留にする例文を紹介しますので、参考にして下さい。
基本的に、内定保留は電話連絡でつながらなかった場合にメールと両方で連絡します。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
①第一志望の結果を待つ場合
第一志望の結果を待ちたい場合の内定保留の連絡は、次の通りです。(メールの場合)
| 件名:【ご相談】内定保留の件(〇〇大学 就職太郎→氏名) |
| 本文: 株式会社 〇〇商事 人事部 ××××様 いつもお世話になっております。 御社の採用試験で内定をいただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 先ほど、会社にお電話いたしましたところ、〇〇様はご不在と伺いましたので、メールで連絡させていただきました。 御社の業務内容や社員の皆様の仕事への熱意に魅力を感じておりますが、現在お約束している面接全てをやり切った上で内定の承諾の有無をお返事をさせていただきたいと考えております。 また大変勝手ではありますが、内定保留の猶予を〇月〇日までいただくことは可能でしょうか? お手数をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご検討くださいますよう宜しくお願いいたします。 |
| 就活太郎 □□大学□□学部□□学科4年 携帯番号:×××-××××-×××× メール:taroshuukatu@▲▲▲▲.com |
②考える時間が欲しい場合
考える時間が欲しい場合の内定保留のメール連絡は、次の通りです。
| 件名:【ご相談】内定保留の件(〇〇大学 就職太郎→氏名) |
| 本文: 株式会社 〇〇商事 人事部 ××××様 いつもお世話になっております。 御社の採用試験で内定をいただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 先ほど、会社にお電話いたしましたところ、〇〇様はご不在と伺いましたので、メールで連絡させていただきました。 御社の業務内容や社員の皆様の仕事への熱意に魅力を感じておりますが、一度家族と相談して内定の承諾の有無をお返事をさせていただきたいと考えております。 また大変勝手ではありますが、内定保留の猶予を〇月〇日までいただくことは可能でしょうか? お手数をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご検討くださいますよう宜しくお願いいたします。 |
| 就活太郎 □□大学□□学部□□学科4年 携帯番号:×××-××××-×××× メール:taroshuukatu@▲▲▲▲.com |
内定保留後承諾する場合の例文

電話やメールで内定保留後承諾する場合の例文を紹介しますので、参考にして下さい。
①電話編
電話で、内定保留後承諾する場合の例文は、次の通りです。
| 大変お世話になっております。 先日、内定保留のご連絡をさせていただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 この度は、こちらの身勝手なお願いにもかかわらず、内定のお返事にお時間を頂きありがとうございました。 よく考えた結果、是非御社へ入社させていただきたきたいと思いご連絡いたしました。 入社後は、得意の〇〇を活かして、御社に貢献できるよう努力してまいりたいと考えております。 今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 |
②メール編
メールで、内定保留後承諾する場合の例文は、次の通りです。
| 件名:【ご確認】内定承諾のご連絡(〇〇大学 就職太郎→氏名) |
| 本文: 株式会社 〇〇商事 人事部 ××××様 大変お世話になっております。 先日、内定保留のご連絡をさせていただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 この度は、こちらの身勝手なお願いにもかかわらず、内定のお返事にお時間を頂きありがとうございました。 よく考えた結果、是非御社へ入社させていただきたきたいと思いご連絡いたしました。 入社後は、得意の〇〇を活かして、御社に貢献できるよう努力してまいりたいと考えております。 今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 |
| 就活太郎 □□大学□□学部□□学科4年 携帯番号:×××-××××-×××× メール:taroshuukatu@▲▲▲▲.com |
内定保留後辞退する場合の例文

電話やメールで内定保留後辞退する場合の例文を紹介しますので、参考にして下さい。
①電話編
電話で、内定保留後辞退する場合の例文は、次の通りです。
| 大変お世話になっております。 先日、内定保留のご連絡をさせていただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 この度は、こちらの身勝手なお願いにもかかわらず、内定のお返事にお時間を頂きありがとうございました。 御社のような魅力的な会社に内定をいただき、大変うれしかったのですが、自分の適性や今後のキャリアについて真剣に考えた結果、他社に就職することに致しました。 大変恐縮ではありますが、御社の内定を辞退させていただきます。 貴重な時間を割いていただいたにもかかわらず、このような結果になってしまい大変申し訳ございません。 大変勝手ではございますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 |
②メール編
メールで、内定保留後辞退する場合の例文は、次の通りです。
| 件名:【ご確認】内定辞退のお願い(〇〇大学 就職太郎→氏名) |
| 本文: 株式会社 〇〇商事 人事部 ××××様 大変お世話になっております。 先日、内定保留のご連絡をさせていただきました〇〇〇〇(氏名)と申します。 この度は、こちらの身勝手なお願いにもかかわらず、内定のお返事にお時間を頂きありがとうございました。 先ほど、お電話でもお伝えいたしましたが、自分の適性や今後のキャリアについて真剣に考えた結果、他社に就職することに致しました。 大変恐縮ではございますが、御社の内定を辞退させていただきます。 貴重な時間を割いていただいたにもかかわらず、このような結果になってしまい大変申し訳ございません。 今後とも貴社の更なる発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 就活太郎 □□大学□□学部□□学科4年 携帯番号:×××-××××-×××× メール:taroshuukatu@▲▲▲▲.com |
内定保留のポイントに注意して後悔のない就活をしよう!

内定保留は、応募企業から内定の連絡があった時、入社するか否かの返事を待ってもらうことです。
一般的な内定保留の期間は約1週間ですが、入社意欲を大事にしている企業は、内定保留自体を認めない場合もあるでしょう。
内定保留は、他社の選考結果を待ってベストな選択ができるメリットがありますが、内定保留の申し出の仕方を間違えれば、内定取り消しや印象が悪くなるデメリットもあります。
内定保留をうまく伝えるためには、電話とメール両方で早めに連絡し、内定保留期限を決め、誠実に対応することが大事です。
内定保留を活用する際は、企業担当者の気持ちを不快にさせないような言い方に注意して、後悔のない就活にして下さい。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














