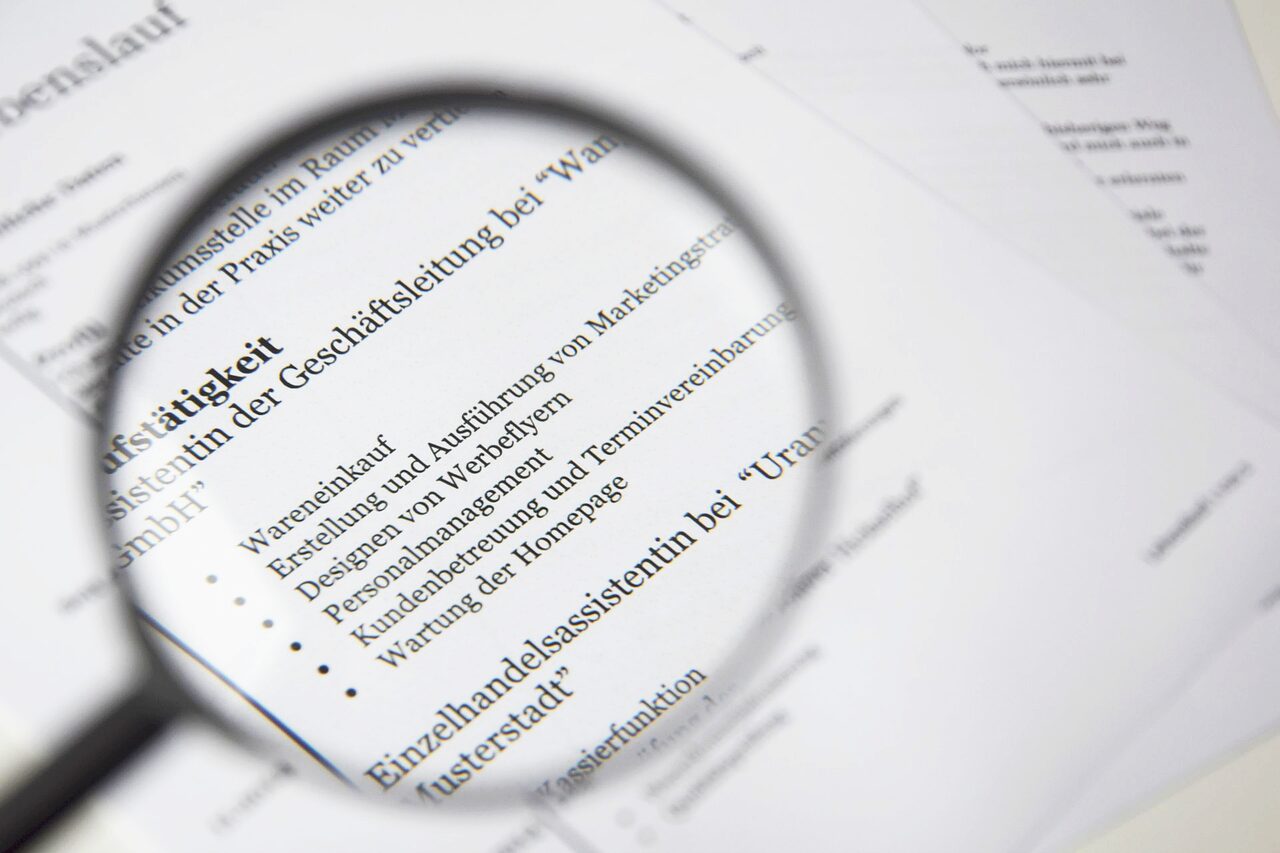テストセンターを導入する企業一覧|出題内容と試験の流れも解説
「テストセンターってどの企業が導入しているんだろう?」就活を進めるうえで、多くの学生が抱く疑問のひとつです。
適性検査の会場として利用されるテストセンターは、SPIをはじめとした選考の入口となる重要なステップ。導入企業や出題内容を知っておくことで、準備に大きな差がつきますよね。
そこで本記事では、テストセンターを採用している主な企業一覧に加え、試験の流れや出題内容についてもわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
企業がテストセンターを導入する理由

テストセンターは多くの企業で導入されており、就活生の能力を公平に評価する仕組みとして広く利用されています。
導入目的は単に学力を確認するだけでなく、効率性やコスト削減、人材の見極めにも直結しているのです。ここでは、企業がテストセンターを利用する主な理由を整理します。
- 応募者を効率的に絞り込むため
- 企業に合った人材を見極めるため
- 採用コストを削減するため
- 全国一律の基準で評価するため
- 面接前に客観的な指標を得るため
①応募者を効率的に絞り込むため
企業にとって採用活動は限られた時間と人員で数多くの応募者を評価する必要があります。そのため、テストセンターを活用すれば短時間で数百人規模の応募者をふるいにかけられるのです。
基礎的な思考力や学力を一定基準で見極められるため、効率的に候補者を選別できる点は大きな利点でしょう。
さらに、こうした仕組みを取り入れることで採用プロセス全体のスピードが向上し、優秀な人材を競合他社に先駆けて確保しやすくなります。
結果的に人事担当者は面接や人物評価といった本来注力すべき業務に集中でき、応募者にとっても選考の無駄が減り、双方にとって納得度の高い採用につながるのです。
②企業に合った人材を見極めるため
テストセンターの問題は、単なる知識量ではなく論理的思考や数的処理、読解力など業務に必要な力を測れるように設計されています。
企業はその結果を基に、自社で長期的に活躍できる人材かどうかを判断するのです。例えば金融業界では高い数的処理能力が求められ、コンサル業界では課題解決力や論理性が重視されます。
こうした検査によって、自社の業務内容と応募者の特性が合致するかを事前に把握できるのです。加えて、適性のある人材を見極められることで入社後の早期離職を防ぎ、定着率の向上にもつながります。
結果的に企業は人材育成にかかる時間やコストを減らし、より効果的に組織を強化できるでしょう。
③採用コストを削減するため
採用活動にはエントリーシートの確認、面接の実施、説明会の運営など多大な費用と人件費が伴います。特に応募者数が多い大企業では、これらの工数が膨大になりやすいものです。
テストセンターを導入することで、あらかじめ基準を満たす候補者だけを次の段階に進められるため、不要なコストを効果的に抑えられます。
さらに、会場やシステムを外部委託することで試験運営自体にかかるコストも削減できるのです。これは大企業のみならず、限られた予算で採用活動を行う中小企業にとっても大きなメリットでしょう。
④全国一律の基準で評価するため
テストセンターは全国どこでも同じ問題が出題されるため、応募者を公平に評価できます。地域や大学による差を排除し、全ての受験者を同じ基準で比べられる点が大きな特徴です。
地方の学生にとっても都市部の学生と対等な条件で挑戦する機会を得られるため、選考の公平性が一層高いものだと言えるでしょう。
企業側も地域格差や教育環境の差を超えて、多様なバックグラウンドを持つ人材を選考できるため、組織の多様性や柔軟性を高めやすくなります。
また、公平な評価基準があることで企業の採用活動全体に信頼性が増し、学生からの印象も良いです。こうした背景から、全国規模で人材を求める企業にとってテストセンターは欠かせない存在となっています。
⑤面接前に客観的な指標を得るため
面接だけで応募者の学力や思考力を正確に測ることは難しいものです。面接官の主観やその場の雰囲気に左右されるリスクもあるでしょう。
その点、テストセンターの結果は数値化されたデータとして提供され、企業は客観的な指標をもとに判断できます。採用の透明性も増し、応募者にとって納得感のある選考を受けられるメリットがあります。
さらに企業にとっても、選考過程の正当性を社内外に説明しやすくなるため、ブランドイメージの向上にもつながるでしょう。
数値化されたデータと面接での人物評価を組み合わせることで、より信頼性の高い採用活動が実現されているのです。
テストセンターの出題内容

テストセンターでは、基礎学力や論理的思考力、性格の特徴を多面的に評価するために複数の検査が行われます。
ここでは代表的な検査の種類を整理し、それぞれで求められる力や対策の考え方を紹介します。
- 言語能力検査
- 非言語能力検査
- 性格適性検査
- 英語能力検査
- 構造的把握力検査
①言語能力検査
言語能力検査は文章を正しく理解し、筋道立てて読み解く力を確認する試験です。内容は長文読解や空欄補充、語彙や表現の適切さを問う問題などが中心となります。
目的は「文章から必要な情報を的確に取り出し、論理的に考えられるか」を測ることにあります。社会に出てからは資料や契約書を読み解く場面が多く、その基礎力を試す位置づけでしょう。
日頃から新聞や専門記事を読み、要点をまとめる習慣を持つと自然に力がつきます。また、過去問題集を何度も解けば出題形式に慣れることができるはずです。
結論として、言語能力はあらゆる職種で求められるため、重点的に取り組むべき分野と言えます。
②非言語能力検査
非言語能力検査は、数的処理や論理的思考を試す問題で構成されています。割合や確率、図形の推理、グラフや表の読み取りが代表的な内容です。制限時間が短いため、正確さとスピードの両立が不可欠。
企業がこの検査を導入するのは「数値やデータを根拠に判断できる力」を重視しているからです。特に事務処理や企画業務では数値分析が欠かせないため、基礎的な計算力が求められます。
対策としては、中学から高校レベルの数学を復習し、問題演習を繰り返すのが近道でしょう。慣れれば自然と処理速度が上がります。
非言語分野を苦手のまま放置すると合格は難しくなるので、早めに練習するようにしましょう。
③性格適性検査
性格適性検査は、応募者の性格や行動の傾向を把握するためのものです。数百問の質問に答える形式で、協調性やリーダーシップ、ストレス耐性などが見られます。
この検査には正解がありません。回答の一貫性が重要で、嘘をついたり無理に良く見せようとすると不自然さが出てしまいます。
結果的にマイナス評価になりかねないので、素直に答えることが一番です。事前に質問例を確認しておけば落ち着いて取り組めるでしょう。
結論として、性格適性検査は「等身大の自分を知ってもらう」場であり、背伸びをする必要はありません。
④英語能力検査
一部の企業や職種では英語能力検査が課されます。TOEICに近い形式で、文法や読解、語彙が中心です。国際化が進む社会では、英語を使える基礎力を持つ人材が評価されやすい傾向があります。
狙いは「海外業務や国際的な取引に対応できるか」を確認することにあるのです。英語が必須でない職種でも、語学力があるとプラス評価につながるでしょう。
対策はTOEICの問題集や単語帳の活用が有効です。英文を読む習慣をつけると、自然にスピードも上がります。英語能力検査は受ける機会が限られているものの、対策しておくと差別化になるでしょう。
⑤構造的把握力検査
構造的把握力検査は、複雑な情報の関係を整理して理解する力を測ります。図表や図形を使った問題が多く、一般的な学力試験とは異なる独特の内容です。
この試験は「未知の問題に直面したときに冷静に整理し、解決策を導けるか」を評価するためが重視されます。変化の激しい社会では、新しい課題に柔軟に対応できる人材が必要とされているからです。
過去問や類題で形式に慣れておくと取り組みやすくなります。パズル的な問題やロジカルシンキングの練習も有効です。
短期集中で成果を出すのは難しいですが、継続的な演習で必ず力がつく検査といえるでしょう。
テストセンター受験の流れ

テストセンターの受験は、予約から本人確認、能力検査、性格検査まで一連の手順で進みます。流れを理解していないと当日に焦ってしまう可能性があるため、事前に把握しておくことが大切です。
ここでは受験の基本的な流れを順に紹介します。
- 受験予約を行う
- 受付で本人確認を受ける
- 試験会場で能力検査を受ける
- 性格検査を受けて終了する
①受験予約を行う
テストセンターを受験するには、まず専用サイトから受験日時と会場を予約する必要があります。
予約は先着順で埋まっていくため、希望する日程や会場がある場合は早めに行動することが安心につながりますよ。
特に就活シーズンのピークには人気の会場や時間帯がすぐに埋まってしまうので、スケジュールに余裕を持たせる工夫も欠かせません。
また、予約後に予定が変更になる場合もあるため、キャンセルや再予約の手続き方法も確認しておくと慌てず対応できるでしょう。事前に予定を整理し、柔軟に動けるよう準備することが成功への第一歩です。
②受付で本人確認を受ける
会場に到着したら、まず受付で本人確認を受けます。ここでは受験票と身分証明書の提示が必須であり、どちらかを忘れると受験できない場合があるので注意が必要です。
不正受験を防ぐ目的もあるため、確認は非常に厳格に行われるのが一般的と言えます。
到着が遅れると焦って必要書類の提示がスムーズにできないこともあるので、開始時間の30分前には到着しておくのが理想です。
書類の不備を防ぐために、前日までに必要なものをバッグに入れて確認し、忘れ物をしないよう徹底してください。こうした準備が当日の安心感につながるはずです。
③試験会場で能力検査を受ける
本人確認が終わると、試験会場の指定席に案内され能力検査が始まります。
出題されるのは言語、非言語、英語、構造把握など多岐にわたる分野で、限られた時間の中で効率よく解答していかなければなりません。
問題ごとの難易度に差があるため、1問にこだわりすぎず、解けるものを優先して進める判断力が試されます。
事前に過去問や模試で練習し、時間配分を体感しておくことで本番で焦らず対応できるでしょう。また、問題形式に慣れておくと解答スピードも上がり、全体の点数を底上げできます。
集中力を切らさない工夫も得点力を維持するカギです。
④性格検査を受けて終了する
最後に行うのが性格検査です。ここでは価値観や行動傾向を把握することが目的で、学力試験のように正解や不正解は存在しません。
大切なのは一貫した回答をすることであり、迷いすぎずに直感的に答える姿勢が求められます。
性格検査は単独で合否を決めるものではありませんが、面接の際の評価材料として活用されるため、誠実さをもって回答することが必要でしょう。
また、理想に近づけようとすると回答の矛盾が出やすくなるため、自分の考えを素直に反映させる方が評価につながります。
ありのままの自分を示すことが、将来の採用後のミスマッチを防ぐことにもなるのです。
【ES提出あり】テストセンターを実施している企業一覧

テストセンターは多くの大手企業で導入されており、エントリーシート提出と同時に受験を求められる場合もあります。
事前に実施企業を把握しておけば、限られた準備期間でも落ち着いて対応できるでしょう。以下の表にある企業は、「ESの提出後にテストセンターを受験」する方式を活用しています。
どの企業も人気が高いため、出題形式や傾向を早めに確認し、エントリーシートと並行して準備を進めてください。そうすることで余裕を持って対応でき、合格に一歩近づけるはずです。
| ・三菱UFJ銀行 ・みずほフィナンシャルグループ ・三井住友銀行 ・三井住友信託銀行 ・農林中央金庫 ・日本政策投資銀行 ・東京海上日動火災保険 ・損害保険ジャパン ・大和証券 ・野村総合研究所(NRI) ・日本総合研究所 ・伊藤忠商事 ・丸紅 ・三菱商事 ・住友商事 ・双日 ・豊田通商 ・日立製作所 ・ソニーグループ ・パナソニック ・キヤノン(一部部署) ・トヨタ自動車 ・本田技研工業(ホンダ) ・ブリヂストン ・味の素 ・花王 ・資生堂 ・NTTデータ ・富士通 ・楽天グループ ・ソフトバンク ・KDDI ・アクセンチュア ・デロイトトーマツコンサルティング ・PwCコンサルティング ・日本郵政 ・JR東日本 ・JR東海 ・東京電力 ・関西電力 |
【ES不要】テストセンターの練習受験ができる企業一覧

テストセンターは本番のみで受けるものと思われがちですが、実際にはエントリーシートの提出が不要で練習受験が可能な企業もあります。
ここを活用すれば本番形式に慣れることができ、就活生にとって大きな安心につながるでしょう。これらの企業は応募の手続きが比較的簡単で、テストセンターを受験するだけでも練習の機会になります。
本命企業を受ける前に挑戦しておけば、問題形式や時間配分の感覚をつかめるはずです。以下の表に記載のある企業で経験を積み、自信を持って本番に臨めるようにしましょう。
| ・リクルートホールディングス ・日本生命保険 ・明治安田生命保険 ・第一生命保険 ・住友生命保険 ・東京海上日動火災保険 ・三井住友海上火災保険 ・損害保険ジャパン ・オリックスグループ ・野村證券 ・大和証券 ・みずほ証券 ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ・SMBC日興証券 ・楽天グループ ・ソフトバンク ・KDDI ・伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) ・NTTデータ ・富士通 ・セコム ・日本郵政グループ ・JR西日本 ・関西電力 |
テストセンター対策の基本方法
テストセンターで良い結果を出すには、事前の準備が欠かせません。問題形式の把握から始まり、繰り返し学習や模試の活用、苦手分野の克服まで幅広く取り組むことが必要です。
ここでは基本的な対策方法を紹介します。
- 問題形式を事前に把握する
- 参考書や問題集を繰り返し解く
- 時間配分を意識して練習する
- 模擬試験や練習受験を活用する
- 苦手分野を集中的に強化する
①問題形式を事前に把握する
テストセンターでは言語・非言語・英語・構造把握など幅広い分野が出題されます。まずはそれぞれの形式を理解することが第一歩です。
形式を知らないまま臨むと、初見で戸惑い時間を無駄にしてしまう恐れがあります。公式サイトや参考書を使って出題パターンを確認し、どのような設問が多いのか把握してください。
さらに、サンプル問題を解いて実際の画面構成や操作方法に慣れておくと安心です。形式を理解した上で対策を進めれば、問題に取り組む際の心構えができ、本番でも落ち着いて解答できるでしょう。
あらかじめ準備しておけば、難問が出ても焦らず取り組めるため、合格の可能性を高められます。
加えて、形式の理解は「効率的な時間配分」や「正確さの維持」にもつながるので、総合的な対策の土台となりますよ。
②参考書や問題集を繰り返し解く
実力を伸ばすには参考書や問題集を繰り返す方法が効果的です。最初は時間がかかってもかまいませんが、同じ問題を何度も解くうちに理解が深まり、自然と解答スピードも上がります。
複数の教材に手を広げるより、1冊を徹底的に仕上げる方がおすすめです。解答後は必ず解説を確認し、自分が間違えた理由や苦手な分野を明確にするようにしましょう。
間違いをそのままにせず、復習と理解のサイクルを回すことが得点力の安定につながります。こうした積み重ねを継続することで知識が定着し、難易度の高い問題にも対応できるようになるのです。
③時間配分を意識して練習する
本番は制限時間が非常に厳しいため、1問にこだわりすぎると最後まで解き切れない危険があります。そのため練習の段階から制限時間を設定し、配分を意識することが欠かせません。
模試形式で時間を計りながら演習し、どの問題にどれくらい時間をかけるか感覚を養ってください。特に難問に固執せず飛ばす判断ができるかどうかで、得点は大きく変わります。
限られた時間の中で効率的に解答を進める訓練を積めば、緊張感のある本番でも冷静に対応でき、全体の得点を安定させやすいでしょう。
時間配分を体に覚え込ませることで、最後まで解き切れる確率を高めることが可能です。加えて、練習中から「時間切れのリスクを減らす行動パターン」を身につけておくと、本番でも安心して取り組めますよ。
④模擬試験や練習受験を活用する
模擬試験や練習受験は、本番に近い環境を体験できる貴重な機会です。特に企業が実施する練習受験では、実際のシステムや問題形式を利用できるため、本番での不安を軽減できるでしょう。
加えて、返却される成績データを分析すれば、自分の強みや課題を客観的に把握できます。
模試は1回で終わらせず、複数回受けて成績の推移を確認すると、成長実感を得やすくモチベーション維持にもつながるでしょう。
環境や時間の使い方に慣れておけば、本番で実力を発揮する確率が高まるはずです。実際の会場の雰囲気や緊張感を体験することは、本番での集中力向上にも直結します。
さらに模試を通じて「弱点の修正→再挑戦→改善確認」という流れを作れる点も大きな利点です。
⑤苦手分野を集中的に強化する
苦手分野を放置すると全体の得点が安定しません。不得意な科目を明確にし、重点的に取り組むことが必要です。
例えば非言語が苦手なら数的処理の基礎からやり直す、英語が苦手なら短文読解を毎日練習するなど、段階的に克服していきましょう。
苦手分野を少しでも底上げすれば全体の点数が上がり、合格可能性も広がります。もちろん得意分野を伸ばすことも大切ですが、試験全体のバランスを意識して苦手克服に取り組む姿勢が重要です。
日々の小さな積み重ねが大きな成果につながり、安定した得点力を支える基盤となるでしょう。苦手を克服する過程そのものが、自信にもつながります。
テストセンターで高得点を取るためのコツ

テストセンターで高得点を目指すには、勉強だけでなく試験中の工夫も大切です。正確に解くことや時間配分を意識すること、問題の特性に合わせた対応が得点向上に直結するでしょう。
ここでは実際の試験で活かせるコツを紹介します。
- 正確さを優先して誤答を減らす
- 時間がかかる問題は飛ばして進める
- 非言語問題は図やメモを活用する
- 言語問題の前半を確実に解く
- 計算の工夫やテクニックを身につける
①正確さを優先して誤答を減らす
高得点を狙うには正答率を高めることが重要です。テストセンターでは誤答による減点はありませんが、解けない問題に固執して時間を浪費すると総合的な得点が伸びません。
判断に迷う問題は潔く飛ばし、解ける問題を確実に得点に変える姿勢が必要でしょう。さらに、基礎的な問題を落とさないことが全体の評価を底上げします。
事前に出題傾向を把握し、反復練習で確実に得点できる範囲を広げておくと、本番で安定した結果が出せるはずです。
加えて、過去に失敗した問題を徹底的に復習することで「同じミスを繰り返さない力」も養えます。効率を意識しながら正答を積み重ねることが、合格への最短ルートと言えるでしょう。
②時間がかかる問題は飛ばして進める
制限時間がある試験では、1問にこだわりすぎると後半の問題に取り組めなくなります。難しいと感じたら、あきらめて解きやすい問題を優先してください。
実際に多くの受験生が「解けるはずの問題を時間切れで落とす」経験をしているのです。こうした失敗を防ぐには、問題ごとの優先順位を明確にし、戦略的に解答することが欠かせません。
練習の段階から「見切りの速さ」を意識すれば、当日も冷静に判断できます。時間を味方につける工夫を積み重ねることで、合格ラインに届く可能性が大幅に高まるでしょう。
③非言語問題は図やメモを活用する
数的処理や論理的思考を問う問題は、頭の中だけで整理しようとすると混乱しがちです。紙に図を描いたり条件を簡潔にメモへ書き出したりすることで、情報が整理されて解きやすくなります。
特に複雑な条件が絡む問題では、書き出す習慣があるかどうかで解答スピードに大きな差が出るでしょう。図解によって思考が可視化されると、見落としも減り、ケアレスミスを防げます。
さらに、練習段階から図やメモを積極的に活用しておくことで、本番でも自然に手が動くようになり、余計な緊張を和らげられるのです。
小さな工夫の積み重ねですが、この習慣が合否を左右する得点差につながる可能性は高いでしょう。効率的に正解へたどり着くために、ぜひ実践してください。
④言語問題の前半を確実に解く
言語問題は後半になるほど難易度が上がる傾向があるため、前半で得点を稼ぐことが安定した結果を出すための重要な戦略です。
短文や比較的理解しやすい問題から取り組み、時間を残して後半に挑む流れを作ってください。効率よく得点源を確保する姿勢を持てば、試験全体を余裕を持って進められます。
また、過去問や模試を通じて「自分にとって取り組みやすい問題の傾向」を把握しておくことも欠かせません。
さらに、普段から読解練習を行うことで処理スピードを向上させれば、より安定して高得点を狙えるでしょう。得点源を逃さず押さえる意識が武器になります。
⑤計算の工夫やテクニックを身につける
非言語の計算問題では、公式やパターンを覚えるだけでなく、工夫やテクニックを駆使することが得点力に大きく影響します。
暗算を利用したり、近似値で答えを絞り込んだりすることで、限られた時間の中で効率的に正答に近づけるはずです。特に時間配分が厳しい場面では、答えを素早く導き出す工夫が大切。
さらに、よく出題される典型的な問題パターンを把握し、解法を定着させておくと本番でも落ち着いて取り組めます。
スピードと正確さを両立させる練習を積むことこそが、高得点を確実にするための実践的な対策と言えるでしょう。
テストセンター活用の最終的な考え方

企業がテストセンターを導入する理由は、公平で効率的に応募者を評価し、自社に合う人材を見極めるためです。さらに全国一律の基準で客観的に比較できる点は、採用の信頼性を高める要素でしょう。
実際に出題される内容は言語・非言語の能力検査や性格適性検査、英語能力、構造的把握力など多岐にわたり、幅広い準備が欠かせません。
受験の流れも予約から本人確認、試験、性格検査という明確なステップで進みます。また、「ES不要」の練習受験ができる企業を利用することで、本番前に感覚をつかむことも可能です。
高得点を目指すには、参考書や過去問の繰り返し練習、模試の活用、時間配分の工夫が有効といえます。テストセンターを正しく理解し、計画的に対策を進めることが内定への近道となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。