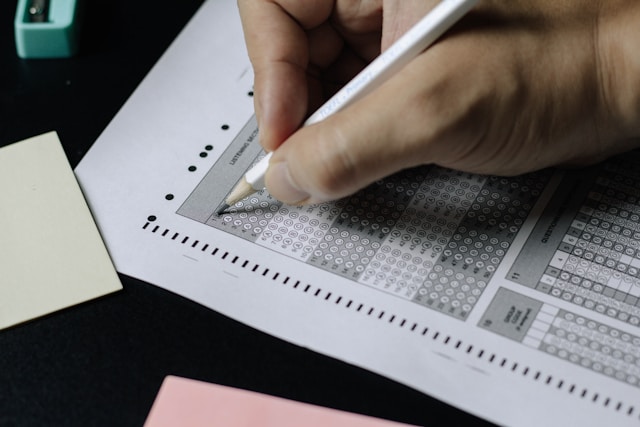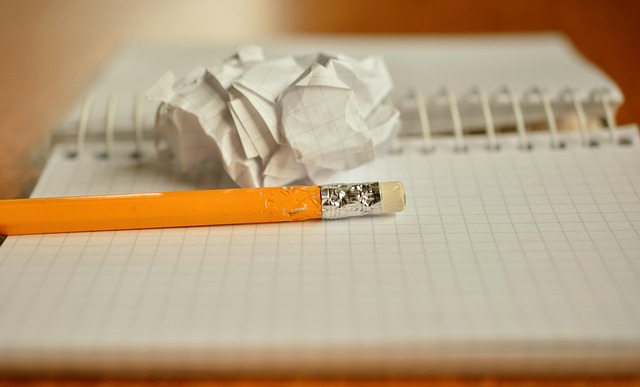SPI試験問題を網羅!受検形式からおすすめ対策本まで紹介
「SPI試験の問題って、種類が多すぎてどこから手をつければいいのか分からない……」
就活を控える多くの学生が抱える悩みのひとつです。SPIは受検形式や出題範囲が幅広く、効率的な対策をしなければ時間だけが過ぎてしまいますよね。
そこで本記事では、spiの試験問題をテーマに、試験形式の特徴や出題内容、さらに効率よく学習を進めるためのおすすめ参考書までを詳しく紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPIとは何か

就活を進める中で、多くの企業が採用選考に導入しているのがSPIです。SPIとは「総合適性検査」の略称で、応募者の基礎的な能力や性格を把握するために活用されます。
SPIは、単なる学力テストではなく、思考力やコミュニケーション力、さらに働くうえでの価値観まで幅広く評価できる仕組みです。
例えば、能力検査では数的処理や言語理解といった基礎学力を測定し、性格検査では協調性やリーダーシップの傾向などが明らかになります。
こうした結果を面接での印象と合わせて比較することで、採用のミスマッチを防ぐ効果が期待できるでしょう。
就活生にとってもSPIを受けることで自分の強みや適性を把握できるため、早めに対策を始めるほど本番に自信を持って臨めます。SPIは企業と学生の双方にとって重要な役割を果たしているのです。
SPIの活用目的

SPIは学力を測るだけでなく、性格や適性を多面的に評価し、採用の判断材料として用いられています。
企業は選考の効率化や人材配置にも活用しており、就活生にとってSPIは欠かせない存在と言えるでしょう。ここでは具体的な活用目的を紹介します。
- 受験者の能力測定
- 性格特性の把握
- 企業文化との適性確認
- 入社後の活躍予測
- 採用選考の効率化
- 人材配置の参考
①受験者の能力測定
SPIは受験者の基礎的な学力を客観的に把握するために活用されます。特に言語分野や非言語分野の出題は、論理的思考力や理解力、計算力を確認する重要な指標です。
面接だけでは判断しにくい知識面を補う役割があり、企業は職種ごとに重視する力を見極めます。営業職では言語理解力、技術職では数的処理能力などが重視されることもあります。
就活生は志望職種を意識し、重点を置いて対策を進めることが効果的でしょう。このようにSPIは、能力を裏付ける客観的な基準として重要な意味を持っています。
②性格特性の把握
SPIの性格検査は、受験者の内面を知るための大切な仕組みです。企業はスキルや知識だけでなく、性格的な傾向を理解することで組織に合うかを判断します。
協調性が高ければチーム業務に向き、挑戦意欲が強ければ営業や企画に適していると評価される場合もあります。性格検査には正解がなく、正直に答えることが大切です。
無理に取り繕うと回答に一貫性がなくなり、逆に評価を下げるおそれがあります。自己理解を深め、自分らしさを素直に示すことが最も望ましい対応だと言えるでしょう。
③企業文化との適性確認
SPIは応募者が企業文化に適応できるかを判断する材料にもなります。挑戦的で成果主義の企業では積極性が評価され、協調を重視する企業では人間関係の調和力が求められる傾向があります。
就活生が企業文化に合わなければ、早期離職のリスクが高まる可能性があります。そのため企業はSPIを用いてミスマッチを防ごうとします。
受験者側も企業研究を進め、自分の価値観や行動特性が組織に合うかを確認することが大切です。こうした準備が結果として安心して働ける環境につながるでしょう。
④入社後の活躍予測
SPIの結果は、入社後にどのように力を発揮できるかを予測する材料としても利用されます。基礎学力や性格の傾向から、成長のスピードや職場適応力を推測することが可能です。
企業はこれを参考に、教育プログラムやキャリア形成の方針を検討します。例えば数値処理に強い人材は分析や企画業務に向くと判断されやすいです。
SPIは選考のためだけでなく、将来的な成長を見据えた人材活用にも役立っている点が特徴です。就活生は自分の強みを見極めるきっかけとして前向きに取り組むとよいでしょう。
⑤採用選考の効率化
SPIを導入することで、企業は多くの応募者を短時間で評価できます。書類や面接では見えにくい部分を把握できるため、選考を効率的に進められるのが利点です。
一定の基準に届かない場合は早期に判定できるため、採用活動にかかる労力やコストを抑えられます。就活生にとってはSPIの結果が次の選考に進めるかどうかを左右する重要なポイントになるでしょう。
効率的な選考の中で埋もれないためにも、早めの準備と対策が欠かせません。
⑥人材配置の参考
SPIの結果は採用だけでなく配属の判断材料としても利用されます。能力や性格傾向をもとに、どの部署で力を発揮しやすいかを企業が見極められるからです。
たとえば分析力の高い人は企画部門に、協調性が強い人は現場チームに適していると考えられることがあります。就活生にとってSPIは「どこで活躍できるか」を企業に示す手段でもあります。
自分の適性を知る機会ととらえ、前向きに活用すると就職活動において大きな助けとなるでしょう。
SPIを企業が導入する理由

SPIは多くの企業で採用選考に取り入れられています。その目的を理解すると、就活生は試験の重要性を把握でき、効果的な準備につなげられるでしょう。
ここでは企業がSPIを導入する主な理由を整理しました。
- 人材を客観的に評価するため
- 採用ミスマッチを防ぐため
- 早期離職リスクを低減するため
- 能力別に配属を検討するため
- 公平な採用基準を確保するため
- 選考プロセスを標準化するため
①人材を客観的に評価するため
SPIの大きな役割は、人材を客観的に評価できる点にあります。面接では印象や雰囲気に左右されがちですが、試験を利用することで数値化された基準で比較可能です。
特に言語や非言語の能力検査は、応募者の基礎的な思考力を明確に示します。そのため主観的な判断に偏らず、採用の公平性を守れるのです。
学生にとっては「実力を証明できる場」でもあるので、SPIを選考の壁ではなく自己アピールの機会と考えると良いでしょう。
②採用ミスマッチを防ぐため
SPIは採用時のミスマッチを防ぐ目的にも活用されています。企業にとって、入社後に適性が合わず早期離職につながるのは大きな損失です。
SPIでは応募者の性格や思考傾向を把握できるため、求める人材像と照らし合わせやすくなります。
例えば、論理的思考力が求められる職種には数的処理が得意な学生を配置するなど、適切な人材配置が可能になります。結果として、企業と学生の双方にとって満足度の高い就業につながるでしょう。
③早期離職リスクを低減するため
企業がSPIを導入する理由の1つに、早期離職を防ぎたいという狙いがあります。入社後に「想像と違った」と感じて辞めてしまうケースは少なくありません。
SPIの性格検査では、価値観やストレス耐性といった点を測定できます。その結果をもとに、会社の風土や業務特性と合う人材を判断できるのです。
就活生にとっても、自分の特性を理解し適した職場を見つけやすくなるため、長期的に働ける環境を選びやすくなります。SPIは企業と学生双方にとって有益な仕組みといえるでしょう。
④能力別に配属を検討するため
SPIは採用だけでなく、配属の検討にも使われています。企業は社員の能力を把握することで、最適な部署や役割に配置できます。
例えば、数理的な問題解決が得意なら企画や分析部門、言語能力が高いなら営業や広報が適していると判断できます。こうした活用によって社員の強みを最大限に発揮できる環境を整えられるのです。
学生にとっても、SPIで自分の実力を示すことが希望のキャリア形成につながる可能性があるため、しっかり準備して臨む価値があります。
⑤公平な採用基準を確保するため
SPIの導入目的の1つは、公平な採用基準を作ることです。面接官の主観や偶然の印象に依存すると、不公平な結果が出る恐れがあります。
その点、SPIは標準化された問題と採点方法を使うため、応募者を同じ尺度で比較可能です。特に多くの応募者を抱える企業では、こうした基準の統一が有効に働きます。
就活生にとっても、SPIは「誰もが同じ条件で挑める舞台」となるため、努力次第で評価を得やすい仕組みといえるでしょう。
⑥選考プロセスを標準化するため
SPIは選考プロセスを標準化する効果も持っています。大手企業のように多数の応募者がいる場合、面接だけで能力や適性を見極めるのは困難です。
SPIを利用すれば、全国どこからでも同じ形式で受験でき、基準を統一して評価できます。これにより採用活動全体の効率が高まり、企業にとってはデータの蓄積や採用改善にもつながります。
就活生にとっても、どこにいても同じ条件で受験できる安心感があるでしょう。SPIは採用の公正さと効率性を両立させる重要な仕組みです。
SPIの試験内容

SPIの試験は多くの企業で採用選考に利用されており、基礎能力から性格まで幅広く評価されます。内容を理解しておけば、効率的に対策を進められ、不安も和らぐでしょう。
ここでは出題分野ごとの特徴を整理します。
- 基礎能力検査(言語分野)
- 基礎能力検査(非言語分野)
- 英語検査
- 構造的把握力検査
- 性格検査
- 合格ラインと評価基準
①基礎能力検査(言語分野)
言語分野では読解力や語彙力を確認する問題が出題されます。内容は長文読解、文法、語句の意味を問う設問などが中心です。
知識だけでなく短時間で論理的に把握する力が試されるため、普段から文章を速く読み要点をまとめる練習をすると効果的でしょう。
過去問や模試に取り組めば形式に慣れ、試験本番でも落ち着いて対応できます。言語分野は総合評価に直結するため、軽視せず早めに学習を進めることが安定した得点につながります。
計画的に準備を整えることが欠かせません。
②基礎能力検査(非言語分野)
非言語分野では数的処理や論理的思考力が問われます。割合や損益計算、表やグラフを用いた資料解釈、場合の数や確率などが代表的です。
普段の学習で触れる機会が少なく、多くの受験者が苦手意識を持ちやすい分野でもあります。克服するには解法のパターンを理解して繰り返し練習することが必要です。
時間制限が厳しいため計算の速さを意識して取り組むとよいでしょう。得点差がつきやすいので、基礎から演習を重ね確実に正解できる問題を増やすことが合格に近づく鍵です。
③英語検査
英語検査は一部の企業で導入され、特に外資系や海外展開のある企業で出題される傾向があります。内容は長文読解、文法、語彙など基本的な英語力を測る問題が中心です。
大学受験レベルの知識が求められる場合も多く、英語が得意な人にとっては強みとなります。苦手な場合は他の分野で補う必要があるでしょう。
対策としてTOEICの基礎問題や過去問演習が有効で、日頃から英文を読む習慣を持つことも役立ちます。受験企業が英語検査を導入しているか確認し、必要に応じて重点的に準備することが大切です。
④構造的把握力検査
構造的把握力検査は物事を論理的に整理し、全体像を理解する力を測定します。図表や関係図を使って条件を整理し、最適な答えを導く形式が多いです。
思考の正確さとスピードが求められるため、暗記だけでは対応できません。導入している企業は限られますが、出題されると得点差がつきやすい分野です。
パズルや論理問題に慣れておくと効果的でしょう。最初は難しく感じても練習を重ねれば対応力が高まります。構造的に考える力は実務でも役立つため、学習して損はありません。
⑤性格検査
性格検査は能力検査と異なり、受験者の価値観や行動特性を把握する目的で行われます。回答は「はい・いいえ」や「どちらかといえば~」といった形式で、協調性や責任感などを分析します。
正解のある問題ではないため、取り繕った回答は矛盾を生み評価を下げかねません。正直に答えることが基本です。設問形式に慣れておけば本番で迷うことが減り、自然体で回答できるでしょう。
自分を偽らず答える姿勢が、企業との適性を確認する上で最も効果的です。
⑥合格ラインと評価基準
SPIの合格ラインは企業や職種ごとに異なり、一律に決まっているわけではありません。一般的には正答率が一定水準を超えることが目安ですが、能力検査と性格検査のバランスも重視されます。
能力検査で高得点を取っても性格検査で矛盾が出れば評価は下がる可能性があります。特に非言語や構造的把握力は差が出やすいため重点的に準備しておくべきです。
評価は相対的に決まるため、他の受験者との比較も影響します。すべての分野をバランスよく学習し、偏りのない得点を取ることが合格への近道となるでしょう。
SPIの受検形式

SPIには複数の受検方式があり、受験環境や企業の方針によって形式が異なります。形式を理解していないと当日の準備に不安が残り、力を十分に発揮できないこともあります。
あらかじめ特徴を知っておけば、自分に合った練習方法を選びやすくなり、落ち着いて試験に臨めるでしょう。ここでは代表的な受検形式を紹介します。
- テストセンター方式
- WEBテスティング方式
- ペーパーテスト方式
- インハウスCBT方式
①テストセンター方式
テストセンター方式は、専用会場に出向いてパソコンで受ける形式です。集中しやすい環境が整っており、公平性が保たれている点が大きな特徴でしょう。
全国に会場があるためアクセスも比較的容易ですが、繁忙期には予約が取りにくいことがあります。
スケジュール調整を怠ると希望日に受けられない可能性があるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
また、会場特有の緊張感に慣れるため、本番を意識した模試や過去問を解いておくと安心できるでしょう。
②WEBテスティング方式
WEBテスティング方式は、自宅や学校などインターネット環境が整った場所で受けられる形式です。
移動の手間がかからず自由度が高いのが利点ですが、通信環境や端末の不具合が起こると対応に困ることがあります。
カンニング防止の制限もあるため、静かで集中できる環境を整えることが欠かせません。自宅受験は気楽に感じられる反面、集中力が途切れやすい面もあります。
事前に同じ環境で練習しておくと、本番での対応がスムーズになるでしょう。
③ペーパーテスト方式
ペーパーテスト方式は、紙と鉛筆を用いた従来型の試験です。地方の企業や設備が整っていない場合に実施されることが多く、直感的に解答できる点が利点といえます。
ただし、制限時間が短いため、見直しをする余裕があまりありません。時間配分を誤ると得点が伸びにくくなるため注意が必要です。
特に非言語分野では計算力と正確さが求められるため、普段から紙に書きながら練習することが効果的でしょう。時間を測って解くことで、本番でも安定した対応ができるようになります。
④インハウスCBT方式
インハウスCBT方式は、企業が用意した会場に設置されたパソコンで受ける形式です。自社選考の一環として行われることが多く、会場の雰囲気が企業文化を感じるきっかけになる場合もあります。
他の形式と比べると実施機会は限られていますが、企業理解を深められる点は魅力です。会場によって環境が異なるため、柔軟な対応が求められるでしょう。
事前に案内を確認し、不明点があれば人事担当者に確認するのがおすすめです。内容はテストセンター方式と似ているため、基本的な対策方法は共通しています。
SPI試験対策はいつから始めるべきか

SPI試験の準備は多くの就活生が悩むポイントです。早く取り組むべきか直前で集中すべきか迷う人も少なくありません。実際には時期ごとに適切な学習方法が異なります。
ここでは大学3年生の夏から冬、直前期までの流れに沿って最適な対策スケジュールを解説します。
- 大学3年生の夏からの準備
- 大学3年生の冬からの本格対策
- 受検予定の3カ月前からの開始
- 30〜60時間の学習時間確保
①大学3年生の夏からの準備
大学3年生の夏から取り組むと、余裕を持った学習計画を立てられます。早めに始めることでSPIの出題傾向を理解でき、苦手分野を確認する時間も確保できるでしょう。
夏はインターン選考でSPIが課される場合もあるため、この時期から基礎問題集を使って土台を固めると安心です。
さらに、毎日の生活に短時間の学習を組み込めば自然に習慣化でき、秋以降も無理なく続けられます。
早めに準備を進める学生は、本選考の時期に余裕を持って臨める傾向があり、焦らず試験を迎えられるのが大きな利点です。
②大学3年生の冬からの本格対策
冬から本格的に学習を始めるケースも多いです。この時期は多くの企業が本選考を控えているため、出題範囲を一通り押さえる必要があります。
夏から準備ができていない場合でも、冬から集中的に取り組めば十分間に合うでしょう。特に言語や非言語分野は反復練習で得点力が伸びやすいため、毎日一定の時間を確保することが大切です。
模試や過去問題を解きながら実戦感覚を養い、同時に時間配分の練習も行ってください。冬に集中的に取り組んでおけば、直前期に不安を抱えず自信を持って受検できるでしょう。
③受検予定の3カ月前からの開始
試験の3カ月前から集中して勉強を始める人もいます。このスケジュールなら短期間で集中的に学習できるため、効率よく得点を伸ばすことが可能です。
計算問題や読解問題は繰り返し練習するほど精度が上がるため、直前期の集中対策でも成果を出しやすいでしょう。ただし開始が遅い分、学習計画を細かく立てる必要があります。
週ごとに進捗を確認しながら弱点を重点的に補強することで、3カ月あれば基礎から応用までをしっかりカバーできます。焦らず計画的に取り組めば、直前期でも十分に効果を発揮できるでしょう。
④30〜60時間の学習時間確保
SPI対策には合計で30〜60時間程度の学習が必要といわれています。1日1〜2時間を継続すれば、1〜2カ月で達成できる分量です。
特に非言語分野は形式に慣れることが重要なので、短時間でも毎日取り組むことが効果的です。また、模試形式でまとまった時間を取って演習することも欠かせません。
学習時間を分散させることで理解度が深まり、知識が定着しやすくなります。限られた時間を有効に使うには学習範囲を絞る工夫も有効です。
結果として無理のないスケジュールで着実に得点力を高められるでしょう。
SPI対策のポイント

SPI試験は事前準備の有無で得点に差が出やすいため、効率的な対策が欠かせません。まずは出題形式を理解し、問題集を繰り返し解きながら模擬試験で仕上げる流れを意識すると良いでしょう。
ここでは押さえるべきポイントを順に紹介します。
- 出題形式の理解
- 問題集の繰り返し学習
- 暗記問題の効率的対策
- 苦手分野の重点練習
- 時間配分の意識
- 模擬試験の活用
①出題形式の理解
SPI対策は、全体の出題形式を把握することから始めるべきです。言語・非言語・性格検査はそれぞれ問われる力が異なるため、形式を理解しないまま学習すると効率が落ちてしまいます。
言語では語彙や読解力、非言語では数的処理や論理的思考力が中心です。例えば、数学が苦手でも非言語の頻出パターンを押さえておけば、解答の優先順位を立てやすくなります。
最初に公式サイトや参考書で全体像をつかみ、自分に必要な学習範囲を明確にしておくことが大切でしょう。
②問題集の繰り返し学習
得点を安定させるには、問題集を繰り返し解く方法が最も効果的です。1度解くだけでは形式に慣れず、本番で時間が足りなくなる可能性が高いからです。
繰り返すうちに解法が定着し、考える時間を短縮できます。例えば同じ問題を3回以上解き直すと、正答率が大きく向上します。
さらに答え合わせでは解説を丁寧に読み、弱点をノートにまとめる習慣をつけると学習効果が高まります。繰り返し演習こそがSPI突破への近道でしょう。
③暗記問題の効率的対策
SPIには語彙や四字熟語など、暗記で得点できる問題も含まれています。これらは短期間で成果が出やすいため、効率的に学ぶことが重要です。暗記問題を後回しにすると直前で焦る可能性があります。
例えば「二語関係」や「四字熟語」はアプリや単語カードでスキマ時間に繰り返すと効果的です。毎日5分でも続けることで知識が定着し、安定して得点源にできます。
短時間でも継続して取り入れる姿勢が成果につながるでしょう。
④苦手分野の重点練習
SPIでは総合点で評価されるため、苦手分野を克服することが全体の得点力を高めます。得意分野を伸ばすよりも、弱点を潰す方が効率的です。
例えば非言語で計算が苦手なら「速さ」「割合」「集合」といった頻出分野を集中的に練習すると効果があります。
演習で間違えた問題は必ず原因を振り返り、次に同じ失敗をしない工夫を加えることが重要です。弱点を補強することで全体の安定感が増し、合格に近づくでしょう。
⑤時間配分の意識
SPIは限られた時間で数多くの問題を解く力が求められる試験です。普段から時間配分を意識して演習することが欠かせません。
難問に固執すると得点効率が下がりますが、解ける問題から優先的に処理すれば得点を積み上げられます。例えばタイマーを使って模擬的に演習すると、自然にペース感覚が身につきます。
本番を想定した練習を繰り返すことで、時間内に安定して解き切れる力が養われるでしょう。
⑥模擬試験の活用
SPI対策の仕上げには模擬試験を活用するのが効果的です。模試を受けることで本番に近い緊張感を体験でき、時間配分や集中力を試す良い機会となります。
さらに結果を分析することで、自分の弱点を明確にできます。例えば非言語で正答率が低ければ、その分野を重点的に復習すればよいでしょう。模試は1回だけでなく複数回受けると成長が実感できます。
SPI能力検査(言語・非言語)の出題例

SPIの能力検査は、言語分野と非言語分野に分かれ、幅広い設問を通じて受検者の思考力や理解力を測定します。どのような問題が出るかを具体的に知ることで、効率的に対策を進められるでしょう。
ここでは代表的な出題形式を解説します。
- 二語関係問題
- 語句の意味と用法
- 文の並べ替え
- 空欄補充問題
- 長文読解問題
- 推論問題
- 順列・組み合わせ
- 割合と比の問題
- 損益算問題
- 速度算・旅人算
①二語関係問題
二語関係問題は、与えられた語句の関係を理解し、それと同じ関係を持つ語の組み合わせを選ぶ形式です。語彙力と論理的思考の両方が問われます。
| 「火:煙」に対応する組み合わせはどれか。 A. 雨:傘 B. 病気:薬 C. 太陽:光 D. 魚:海 |
《解説》
火があると煙が発生するように、太陽があると光が生まれるため正解はCです。2つの言葉の因果関係を見抜くことがポイントです。
②語句の意味と用法
語句の意味や使い方を確認する問題です。同義語や反対語の理解、文脈に応じた言葉の使い分けが試されます。
| 「冷静」の反対語として最も適切なのはどれか。 A. 冷淡 B. 無関心 C. 興奮 D. 穏やか |
《解説》
「冷静」の反対は感情を抑えられない「興奮」が最も近いです。単なる印象で判断せず、意味を正確に理解することが必要になります。
③文の並べ替え
バラバラに提示された文を正しい順序に並べ替えて意味の通る文章にします。
| ア:そのため彼は努力を続けた。 イ:田中さんは試験に合格した。 ウ:しかし最初は失敗も多かった。 |
《解説》
正しい順序は「イ → ウ → ア」です。接続詞の役割を確認すれば論理の流れを捉えやすくなります。
④空欄補充問題
文中の空欄に最も適切な語句を入れる問題です。
| 「彼は毎日欠かさず勉強を続けた◯◯、試験に合格できた。」 A. ので B. から C. が D. けれど |
《解説》
理由を表す「ので」が文意に最も自然で、答えはAです。前後の意味を確認し、文章全体が成立するかを考えると正答しやすくなります。
⑤長文読解問題
数百字の文章を読み、設問に答える形式です。情報を効率よく探す力が必要です。
《例題(要約)》
| 「近年、若者の読書離れが進んでいる。しかし電子書籍の普及によって新しい読書習慣が広がりつつある。」 問:筆者の主張として正しいものはどれか。 A. 若者は読書をしなくなった B. 電子書籍が読書を救っている C. 読書離れは止まらない D. 紙の本だけが重要である |
《解説》
本文は「電子書籍による新しい読書習慣」に言及しているため、正解はBです。根拠は必ず文章中にあります。
⑥推論問題
与えられた条件から論理的に結論を導く形式です。
| 「Aさんがいると必ずBさんもいる。Bさんがいると必ずCさんもいる。」 問:正しい結論はどれか。 A. CさんがいればAさんもいる B. AさんがいればCさんもいる C. BさんがいればAさんもいる D. AさんとCさんは無関係 |
《解説》
AがいればB、BがいればCなので「AがいればCがいる」ことになります。答えはBです。条件を整理して筋道を立てることが重要です。
⑦順列・組み合わせ
数学的知識を応用する典型的な非言語問題です。
| 「5人を一列に並べる方法は何通りか。 |
《解説》
順列の公式「5! = 120」を使うので答えは120通りです。公式を覚えれば素早く解けます。
⑧割合と比の問題
数量関係を把握する力を問います。
| 「定価1000円の商品を20%引きで売ると価格はいくらか。」 |
《解説》
1000円の20%は200円なので、1000−200=800円となります。基本的な計算を正確にできるかどうかが鍵です。
⑨損益算問題
売買に関する利益や損失を扱います。
| 「原価800円の商品を20%の利益で売ると販売価格はいくらか。」 |
《解説》
800円×1.2=960円です。原価と利益率の関係を整理すると解きやすいです。
⑩速度算・旅人算
距離・速さ・時間の関係をもとに解きます。
| 「Aさんは時速5km、Bさんは時速7kmで互いに向かって歩く。2人が2時間後に出会うとき、出発点の距離は何kmか。」 |
《解説》
合計速度は12km/hなので、2時間で進む距離は24kmです。よって出発点間の距離は24kmとなります。図で整理すると理解しやすいです。
SPI英語・構造的把握力の出題例

SPI試験では言語や非言語の基礎力に加えて、英語力や論理的思考力を問う問題も出題されます。
特にグローバル企業や専門性の高い職種では、英語と構造的把握力が重要視されるため、出題形式を理解しておくことが合格につながります。ここでは代表的な問題形式を具体的に整理しました。
- 英語の同意語問題
- 英語の反意語問題
- 英英辞典形式
- 英語の空欄補充
- 英語の長文読解
- 構造的把握力(言語)
- 構造的把握力(非言語)
- ロジカルシンキング問題
- 図表を用いた構造把握
- 文章構造の理解問題
①英語の同意語問題
英語の同意語問題は、与えられた単語と最も近い意味を持つものを選ぶ形式です。TOEIC形式に似ており、基礎的な語彙力を確認する目的があります。
| 次の単語と最も近い意味を選びなさい。 rapid 1.slow 2.fast 3.late 4.heavy 正解は2の「fast」です。 |
《解説》
意味をグループで覚えると、素早く判断できるようになります。単語帳を使うだけでなく、類義語をまとめて整理する学習法が有効です。
②英語の反意語問題
反意語問題は、指定された単語と反対の意味を持つ語を選ぶ形式です。語彙の幅やニュアンス理解を試すものです。
| 次の単語と反対の意味を持つ単語を選びなさい。 expand 1.grow 2.extend 3.contract 4.increase 正解は3の「contract」です。 |
《解説》
日常から「意味・同意語・反意語」をセットで覚えると、短期間でも定着します。
③英英辞典形式
英英辞典形式は、英語の説明文から該当する単語を選ぶ問題です。単なる和訳ではなく、文脈で理解する力が必要です。
| “”a place where books are kept”” 1.school 2.library 3.shop 4.museum 正解は2の「library」です。 |
《解説》
英英辞典のシンプルな定義に慣れておくと、抵抗なく対応できるようになります。
④英語の空欄補充
空欄補充は、文中の欠落部分に適切な語を入れる問題です。文法力や語彙力に加えて、文脈を読む力も求められます。
| She _ to the station yesterday. 1.go 2.going 3.went 4.gone 正解は3の「went」です。 |
《解説》
例文を声に出して覚えると記憶に残りやすく、試験本番でも自然に答えが浮かびます。
⑤英語の長文読解
長文読解は、文章を読み取り要点を把握できるかを試します。語彙力だけでなく処理速度や論理的理解が必要です。
| 短文を読んで、質問に答えなさい。 “”Tom studied hard for the exam. As a result, he passed.”” 質問: Why did Tom pass the exam? 正解は「Because he studied hard」です。 |
《解説》
段落ごとに要点をまとめる練習をしておくと効率的に解けます。
⑥構造的把握力(言語)
言語に関する構造的把握力問題は、文章や概念の関係を整理して正しい結論を導く形式です。
| 「AはBに含まれる」「BはCに含まれる」 では、AとCの関係はどれか。 1.AはCに含まれる 2.CはAに含まれる 3.AとCは無関係 4.AとCは同じ 正解は1の「AはCに含まれる」です。 |
《解説》
図にして整理すると、複雑な関係も理解しやすくなります。
⑦構造的把握力(非言語)
非言語の構造的把握力問題は、数列や図形、表データから規則を見抜く形式です。
| 次の数列の空欄に入る数字を選びなさい。 2, 4, 8, 16, ( ? ) 1.24 2.32 3.20 4.30 正解は2の「32」です。 |
《解説》
規則性を早く見抜く練習をすると、問題を効率的に解けます。
⑧ロジカルシンキング問題
ロジカルシンキング問題は、前提から矛盾のない結論を導けるかを試します。
| 「すべてのAはBである」「CはAである」 このとき正しい結論はどれか。 1.CはBである 2.CはBでない 3.AはCである 4.BはCであるとは限らない 正解は1の「CはBである」です。 |
《解説》
前提を整理し、矛盾がないか確認する習慣を持つと精度が上がります。
⑨図表を用いた構造把握
図表を読み取り、データの関係性を整理して答える問題です。
| 売上表を見て、前年より売上が上がった商品を選びなさい。 A商品: 120 → 150 B商品: 80 → 70 C商品: 200 → 190 正解はA商品です。 |
《解説》
全体像を把握し、データを比較する力が必要です。普段からグラフや統計に触れると慣れてきます。
⑩文章構造の理解問題
文章構造の理解問題は、長文や複数の文を整理して論理展開を把握する問題です。
| 「この商品は価格が安い。しかし品質が高い。そのため売上が伸びている。」 質問: 売上が伸びている理由はどれか。 1.価格が高いから 2.品質が低いから 3.価格が安く品質が高いから 4.宣伝が多いから 正解は3の「価格が安く品質が高いから」です。 |
《解説》
因果関係を意識しながら読む練習をすると対応しやすくなります。
SPI性格検査の出題例

SPIの性格検査は、知識だけでなく受験者の人柄や考え方を知るために使われます。企業は、職場での協働や適性を重視する傾向があるため、この検査の理解は欠かせません。
ここでは実際に出題される設問の種類を紹介し、自分の強みや特性をどう表現できるかを確認しておきましょう。
- 協調性に関する設問
- リーダーシップに関する設問
- ストレス耐性に関する設問
- 責任感に関する設問
- 挑戦意欲に関する設問
- 柔軟性に関する設問
- 価値観に関する設問
- 対人関係スタイルの設問
- 仕事観に関する設問
- 倫理観に関する設問
①協調性に関する設問
協調性を測る設問は、集団で円滑に行動できるかを確認するものです。例えば「チームで成果を優先するか、自分の意見を貫くか」といった質問が出ます。
企業は、入社後に仲間と協力して結果を出せる人材かどうかを見ています。回答は正直であることが大切ですが、極端に片寄ると「協調性が乏しい」と判断される場合があります。
普段から人との関わりを振り返り、バランス感覚を意識するとよいでしょう。
②リーダーシップに関する設問
リーダーシップを問う設問は、将来人をまとめる力があるかを知る狙いがあります。たとえば「率先して行動する方だと思う」や「人を導く役割を担うことが多い」といった内容です。
企業は全員に強いリーダーシップを求めるわけではなく、主体性や責任感を持てるかを確認しています。回答は実体験をもとに自然に選び、極端にならないことが重要でしょう。
③ストレス耐性に関する設問
ストレス耐性は、困難な場面で冷静に対応できるかを知るために出題されます。「プレッシャー下でも成果を出せるか」「失敗後すぐに気持ちを切り替えられるか」といった質問が典型です。
企業は長期的に働けるかを見ており、精神面の安定が評価につながります。必要以上に強がるのではなく、自分なりにストレスと向き合う工夫を示すことが望ましいでしょう。
④責任感に関する設問
責任感を問う設問は、任された仕事を最後までやり遂げられるかを確認するものです。「役割を途中で放棄しない」「期限を必ず守る」といった形式が多いです。
企業は安心して業務を任せられる人物かを見極めています。回答は実際の行動をイメージしながら、自分の性格を正直に示すことが大切です。
責任感は信頼に直結するため、普段から小さな約束を守る習慣が効果的でしょう。
⑤挑戦意欲に関する設問
挑戦意欲を測る設問は、新しい課題に積極的に取り組めるかを確認します。「未知のことに挑戦する」「変化を楽しめる」といった設問が出題されます。
企業は安定志向だけでなく、成長意欲を持つ人材を求めています。回答は過去の経験を踏まえて自然に選ぶと説得力が高まります。挑戦意欲を示すことは、入社後の成長を広げる強みになるでしょう。
⑥柔軟性に関する設問
柔軟性を問う設問では、状況や相手に応じて行動を変えられるかを見ています。「予定変更にも落ち着いて対応できる」などが代表例です。企業は変化の多い環境に適応できる人物を重視しています。
頑固な印象を与えると不利になるため、自分の性格を正直に示しながら柔軟さも表現することが大切です。普段から人の意見を受け入れる姿勢を持つとよいでしょう。
⑦価値観に関する設問
価値観を測る設問は、自分の判断基準や優先順位を知るために出されます。「安定より挑戦を優先するか」「個人より集団を重視するか」といった形式です。
企業は自社文化と応募者の価値観が合うかを見ています。正解はなく、嘘をつくと入社後にミスマッチを招きます。自分の考えを正直に反映させることが重要です。
事前に価値観を整理しておけば迷いません。
⑧対人関係スタイルの設問
対人関係スタイルを問う設問は、人との接し方や信頼関係の築き方を確認するために用いられます。「初対面でもすぐに打ち解ける」「相手を尊重できる」といった質問が多いです。
企業は良好な人間関係を築けるかを重視しています。回答は自分の性格を正直に反映させつつ、社会人としての協調性を意識するとよいでしょう。
普段のコミュニケーションを振り返って準備してください。
⑨仕事観に関する設問
仕事観を問う設問は、働く上での姿勢や大切にする価値を確認するためにあります。「やりがいを重視するか、安定を求めるか」といった質問が代表的です。
企業は応募者が仕事をどう捉えるかを確認し、自社と合うかを見ています。嘘をつく必要はなく、本音を反映させることが大切です。
普段から「働く目的」を考えておけば、自然で一貫した回答になるでしょう。
⑩倫理観に関する設問
倫理観を測る設問は、道徳心や公正さを確認するものです。「規則は守るべきだ」「不正を見過ごさない」といった形式が典型的です。
企業は信頼できる人材かどうかを重視し、倫理観の欠如はリスクと考えています。回答は普段の行動を正直に反映させることが欠かせません。
倫理観は日々の積み重ねによって示されるもので、日常の判断基準がそのまま評価に表れます。
おすすめのSPI対策本・アプリ
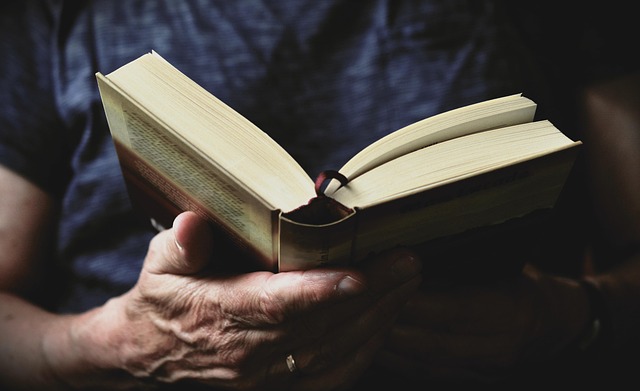
SPI対策を効果的に進めるには、自分に合った書籍やアプリを選ぶことが大切です。
特に受験形式に慣れることや、頻出問題を効率よく解く力を身につけるには、信頼できる教材を活用するのが近道でしょう。ここでは就活生に人気のある対策本とアプリを紹介します。
- SPI3&テストセンター出るとこだけ! 完全対策 2027年度版
- 2027年度版 これが本当のSPI3だ!
- 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
- SPI言語・非言語対策問題集 アプリ
- SPI対策アプリ〔キャリアパーク〕
- SPI対策アプリ〔キミスカ〕
①SPI3&テストセンター出るとこだけ! 完全対策 2027年度版
この本は出題範囲を絞り、効率的に学べる点が特徴です。SPIは範囲が広いため、すべてを対策しようとすると時間が足りません。
しかし本書は頻出問題に焦点を当てており、短期間で成果を出したい学生に役立ちます。さらにテストセンター形式にも対応しているため、本番に近い形で練習できます。
限られた準備時間の中で効率を重視する人にとって、心強い一冊といえるでしょう。
②2027年度版 これが本当のSPI3だ!
定番の人気シリーズで、多くの就活生から支持されています。丁寧な解説が特徴で、初めてSPIに取り組む人でも理解しやすい構成です。
問題数も多く収録されており、基礎から応用まで段階的に学習を進められます。また、毎年改訂版が出版されるため、最新の傾向に合わせた対策が可能です。
不安を抱える人でも、安心して取り組める総合対策書といえるでしょう。
③史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
実戦的な演習に重点を置きたい人に向いています。難易度がやや高めに設定されており、応用力を鍛えるのに効果的です。
特にテストセンター形式の問題が豊富で、制限時間を意識した練習ができる点が強みです。
時間配分の感覚は合否に直結するため、早めにこの問題集で取り組むことで、本番に自信を持って臨めるようになるでしょう。
④SPI言語・非言語対策問題集 アプリ
スマートフォンで手軽に使えるため、通学中や空き時間を有効に活用できます。アプリでは問題演習を繰り返し行えるので、苦手分野の克服や基礎固めが自然に進みます。
さらに答え合わせが即時にできるため、効率よく学習を進められるでしょう。忙しい就活期に、時間や場所にとらわれず学習できる点は大きな魅力です。
⑤SPI対策アプリ〔キャリアパーク〕
キャリア支援サイトが提供しているアプリで、最新の就活情報とあわせて利用できるのが特長です。SPIの基礎から応用まで幅広く対応しており、直前の確認用にも便利です。
さらに就活ノウハウや面接対策記事とも連動しているため、学習と情報収集を同時に進められます。単なる勉強用ツールにとどまらず、就活全般を支える役割も果たすでしょう。
⑥SPI対策アプリ〔キミスカ〕
自己分析とSPI対策を同時に行えるアプリです。性格検査を意識したコンテンツが充実しており、能力検査とあわせて総合的な準備ができます。
SPIは能力だけでなく性格面も重視されるため、このアプリを使えば効果的に対策できるでしょう。さらに企業とのマッチング機能とも連動しているため、学習の成果を就活に直結させやすい点も魅力です。
効率と実用性を兼ね備えたツールといえます。
SPI試験対策の結論

SPI試験は、企業が受験者の能力や性格特性を多面的に把握し、採用や人材配置の判断に活用する重要な試験です。
そのため就活生にとっては、出題形式や受検方式を正しく理解し、効率的な学習計画を立てることが不可欠といえるでしょう。
具体的には、問題集や模擬試験を通じた繰り返し学習や、苦手分野を重点的に克服する姿勢が合格への近道となります。
また、受験開始の時期を早めに設定することで十分な学習時間を確保でき、自信を持って本番に臨めるはずです。
SPI試験問題の全体像を理解し、計画的に取り組むことが内定獲得への第一歩といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。