SPIテストセンターの結果は見れる?確認方法と注意点を解説
SPIテストセンターを受けた後、「自分の結果は見れるの?」「通過できたか不安…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
SPIは自分に通知されない形式だからこそ、仕組みや企業の見方を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、SPIテストセンターの結果が見られない理由や企業が注目するポイント、結果を予測する方法、使い回し時の注意点、そしてスコアアップのための対策まで詳しく解説します。
SPIテストセンターに関する不安を減らし、自信を持って次の選考に臨みましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPIテストセンターの結果は見ることはできる?

結論から言えば、テストセンターで受けたSPIの結果は基本的に確認できません。
これは、SPIを提供しているリクルート社の運用方針によるもので、受験者の結果は本人には開示されず、企業へ直接送られる仕組みになっているからです。
また、SPIは単なる合否判定ではなく、応募者の性格や能力などを含めた「適性」を見る目的で使われるため、点数を公開する必要性も低いとされています。
とはいえ、全く見通しが立たないわけではありません。模試を活用したり、自分の解答の感触を振り返ったりすることで、おおよその出来栄えを予測することは可能です。
「あの問題は解けた」「時間配分がうまくいかなかった」など、試験直後の記憶をもとに改善点を見つけることが、次回以降の対策にもつながるでしょう。
企業がSPIテストセンターを実施する目的

就職活動において、多くの企業が「SPIテストセンター」を導入しています。これは単なる学力テストではなく、応募者の適性や能力を多面的に評価するためのものです。
ここでは、企業がSPIを活用する主な目的について、5つの視点からわかりやすく解説します。
- 候補者のスクリーニングを効率化するため
- 面接で確認すべきポイントを把握するため
- 職務適性や組織適性を見極めるため
- SPIの結果を参考に選考プロセスを設計するため
- 性格傾向を把握して職場のマッチングを図るため
①候補者のスクリーニングを効率化するため
企業がSPIを活用する最大の目的は、多くの応募者の中から一定の基準でふるいにかけるスクリーニングを効率的に行うことです。
とくに大手企業では、1つの募集に対して数百人の応募が寄せられることもあります。
すべての応募者に面接対応をするのは現実的ではないため、SPIによって基礎能力や性格傾向を短時間で把握し、効率的な選別が可能になるのです。
テストセンター方式であれば、実施や採点を外部に委託できるため、企業側の負担も軽くなります。
SPIは単なるペーパーテストではなく、採用活動全体をスムーズに進めるための重要なツールとして機能しているのです。
②面接で確認すべきポイントを把握するため
SPIの結果は合否の判断材料としてだけでなく、面接の質を高めるためにも使われています。
たとえば言語能力のスコアが低い学生には、「どのように考えをまとめて話しているか」といった点を意識して質問を組み立てることで、より深い理解が得られるでしょう。
また性格検査の結果をもとに、応募者の人間関係の傾向や仕事への姿勢がある程度予測できます。
こうした事前情報があることで、面接は表面的なやりとりに終わらず、より本質的な対話ができるのです。
SPIは、応募者の全体像をつかむ「予習ツール」として、面接の効果を高めるためにも役立っています。
③職務適性や組織適性を見極めるため
SPIテストは、応募者がどの職種に適しているか、または企業文化と合っているかを見極めるための手段でもあります。
たとえば、論理的思考力が高ければエンジニアや企画職に、対人力が高ければ営業や人事に向いていると判断できるかもしれません。
さらに、性格検査によってストレスへの耐性や協調性なども明らかになるため、企業はその情報を参考に、配属先や役割を検討します。
企業としては、スキルだけでなく「長く働けるかどうか」「社風に合うか」といった視点も重視しているでしょう。SPIは、そうした判断を補うためのデータとして非常に有効なのです。
④SPIの結果を参考に選考プロセスを設計するため
SPIの結果は、その後の選考ステップを調整する際の参考にもなります。たとえば高得点の学生には、面接回数を減らす、グループワークを免除するなど、選考を効率化する判断が可能です。
逆に得点が低くても、性格面で魅力があると判断された場合は、補足の選考を設けることでバランスを取ることも。
このように、SPIの結果をもとに選考プロセス全体を柔軟に設計することで、企業は適材を見逃さずにすむのです。学生にとっても、自分の強みや弱点を知るきっかけになり、自己理解の助けになるでしょう。
⑤性格傾向を把握して職場のマッチングを図るため
SPIの性格検査では、応募者の行動傾向や価値観、モチベーションの傾向などがデータとして可視化されます。
企業はこのデータを活用して、職場内のチーム構成や上司との相性まで考慮した配属を目指しているのです。
たとえば安定志向の強い学生を新規事業部に配属するとミスマッチが起きやすいですが、挑戦志向のある学生であればやる気を発揮しやすくなります。
このように、性格的な適合を重視する背景には、入社後の定着率や職場満足度を高めたいという狙いがあるのです。学生にとっても、自分の性格傾向と企業文化との相性を知る大切な手がかりになるでしょう。
企業がSPIテストセンターの試験結果で見ているポイント
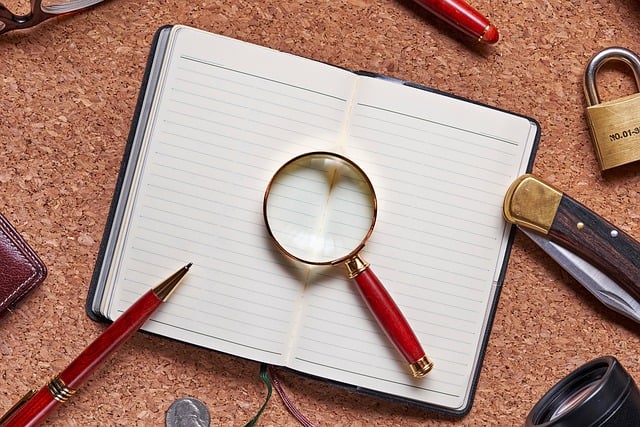
テストセンターで実施されるSPIは、単なる点数だけで判断されるものではありません。企業はその結果から、応募者の多面的な資質を見極めようとしているのです。
ここでは、企業がSPIの結果をどう読み取り、どのような観点で評価しているのかを6つの視点で紹介します。
- SPIの評価報告書で適性や傾向がバランスよく表れているか
- 能力検査と性格検査の整合性が取れているか
- 得点ではなく、応募者のタイプが企業に合っているか
- 論理的思考や数的処理の力があるか
- 協調性やチームワークへの適応力があるか
- ストレス耐性や主体性が感じられるか
①SPIの評価報告書で適性や傾向がバランスよく表れているか
企業はSPIの評価報告書を通じて、受検者の性格や思考傾向、行動パターンを読み取っています。重要なのは、一部の特性が突出せず、全体的にバランスが取れているかどうかです。
たとえば、リーダーシップが強くても協調性が著しく低いと、チームワークを重視する職場ではマイナス評価になりやすいでしょう。
自分の強みを前面に出そうとする気持ちは理解できますが、それだけでは不十分です。性格検査では、回答に矛盾がなく、極端すぎないことも求められます。
無理に理想の人物像を作ろうとすると、かえって不自然な結果になってしまうかもしれません。正直に、かつ自分を客観的に捉える姿勢が評価につながります。
②能力検査と性格検査の整合性が取れているか
SPIは大きく「能力検査」と「性格検査」に分かれており、企業はその両方の整合性を重視しています。論理力や計算力が高くても、性格面で業務に不向きだと判断されれば、評価が下がることも。
逆に、温厚で協調的な性格でも、基本的な学力が基準を下回ると、足切りされてしまう可能性があります。大切なのは、能力と人柄の両面をしっかり見せることです。
特に総合職では、どちらか一方だけが優れていても選考を突破するのは難しいでしょう。日ごろから問題演習で能力を高めつつ、性格検査ではありのままに答えることがバランスの取れた評価につながります。
③得点ではなく、応募者のタイプが企業に合っているか
SPIでは点数の高低よりも、受検者のタイプが企業に合っているかが重視されます。たとえば、高得点でも「慎重すぎて変化に弱い」と評価されると、変化の多い業界ではマイナスになりかねません。
企業は自社に合った人物かどうかを見るために、性格や価値観を重視しています。そのため、「どんな職種に向いているか」「どのような組織風土が合うか」を知っておくことも重要です。
高得点を狙うのではなく、自分の特徴を理解し、それを活かせる企業を選ぶ視点が必要でしょう。
④論理的思考や数的処理の力があるか
SPIの能力検査では、論理的思考力や数的処理力が問われます。企業はこの部分を通じて、業務に対する理解力や対応力を見ているのです。
営業職や企画職でも、資料作成や分析が求められる場面は多いため、数的感覚は重宝されます。
また、論理的に物事を整理できる人は、会議や報告の場で説得力のある説明が可能になるため、社内外問わず高評価を得やすいでしょう。
SPI対策としては、時間制限のある問題を繰り返し解き、スピードと正確さを鍛えることが効果的です。
⑤協調性やチームワークへの適応力があるか
SPIの性格検査では、協調性があるかどうかも見られています。企業は「一緒に働きやすいか」「チームの中で役割を果たせるか」を重視しているのです。
個人の能力が高くても、協調性に欠けると組織で活躍するのは難しいと判断されるでしょう。性格検査で理想像を意識しすぎると、回答の一貫性が失われることも。
無理に「よく見せよう」とすると、かえって不自然になってしまうでしょう。ありのままの自分をベースにしつつ、「周囲と協力する姿勢」を持って臨むことが信頼につながります。
⑥ ストレス耐性や主体性が感じられるか
SPIでは、ストレスにどう向き合うかや、自分から行動できるかも評価ポイントになります。社会人になると、想定外の事態やプレッシャーに直面する機会が増えるため、そこに耐える力は不可欠です。
評価報告書には、「壁にぶつかったときどう行動するか」「自ら動いて環境を変えられるか」といった傾向も反映されます。
企業はこれを見て、入社後の適応力やリーダーシップの可能性を判断しているのです。
企業からSPIテストセンターの試験結果が来ない理由
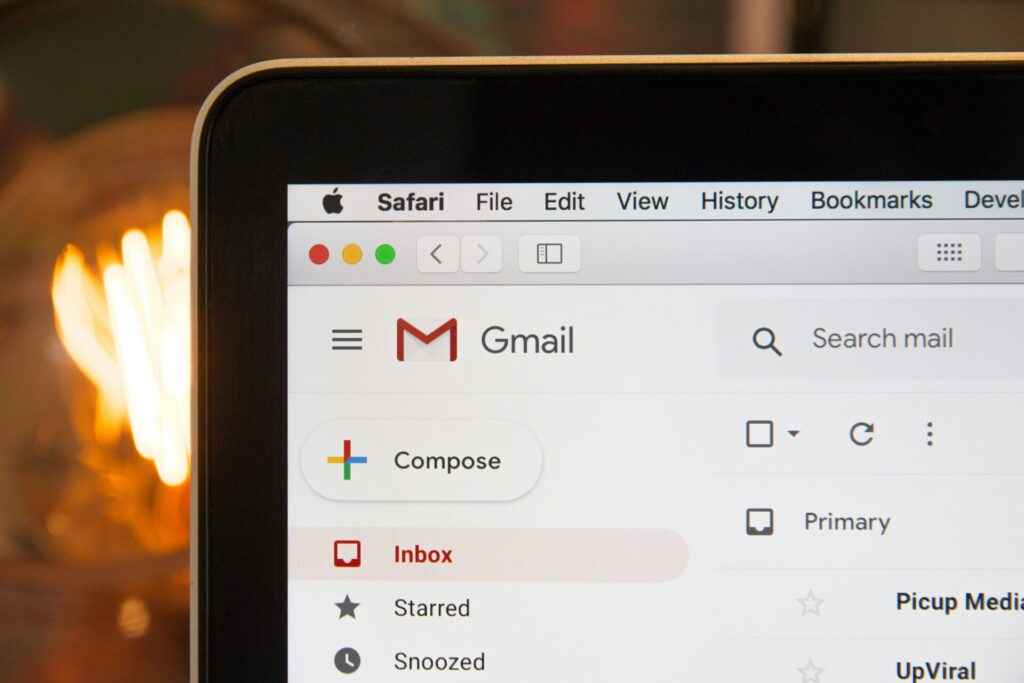
テストセンターでSPIを受けたものの、企業から結果が届かず不安になる就活生は多いです。ただし、連絡がないことがすぐに不合格を意味するわけではありません。
ここでは、結果通知が遅れる理由を4つのケースに分けてわかりやすく解説します。
- 企業へのSPI結果の到達に時間がかかっている
- 応募者数の増加で選考に時間がかかっている
- 不合格通知を出さずサイレント対応されている
- 人事担当者の多忙で通知が後回しになっている
①企業へのSPI結果の到達に時間がかかっている
テストセンターで受けたSPIの結果は、すぐに企業へ届くわけではありません。
たとえコンピューターで自動採点されていたとしても、企業ごとに個人情報と結果の照合作業があるため、若干のタイムラグが発生します。
こうした事務処理の影響で、企業側がまだ結果を確認できていないことも。特に受検日から1~2営業日程度は、通知が来なくても珍しくありません。
すぐに結果が来ないからといって慌てる必要はないでしょう。ただし、1週間以上何の連絡もない場合は、企業の処理が遅れているか、通過できなかった可能性も。
他社の選考にも並行して取り組みつつ、冷静に判断してください。
②応募者数の増加で選考に時間がかかっている
現在は就活の早期化やオンライン化が進み、多くの学生が一斉にSPIを受けています。その影響で、企業側も処理に時間を要するようになりました。
応募が集中する企業では、1人ずつ結果を確認するだけでもかなりの手間です。ときには合否に関係なく、通知までに1週間以上かかることも。
このように、通知の遅れは必ずしも不合格を意味するものではありません。企業側の事情による可能性が高いため、必要以上に気にしすぎないことが大切です。
待っているあいだも、次の選考に向けて準備を進めておくと安心でしょう。
③不合格通知を出さずサイレント対応されている
企業によっては、選考通過者にのみ連絡を行い、不合格者には通知を出さない「サイレントお祈り」を採用していることがあります。
この対応は就活生にとって精神的につらいものですが、実際には一定の割合で存在するのです。いつまでも返事が来ない理由がこれであることも十分に考えられます。
明確な合否連絡がなく不安になる場合は、応募から2週間を目安に次の選考へと気持ちを切り替えるのがよいでしょう。待ち続けることでチャンスを逃す恐れも
複数社を並行して受けることで、サイレント対応のダメージを軽減できるでしょう。
④人事担当者の多忙で通知が後回しになっている
人事担当者は、選考だけでなく日程調整や内定者対応など多くの業務を同時に進めています。そのため、SPIの結果通知が後回しになることもよくあるのです。
とくに通過者への対応を優先する場合、不合格者への連絡は後手に回るか、まったく行われないことも珍しくありません。これは意図的というより、業務の優先順位による結果といえるでしょう。
こうした事情を理解していれば、通知の遅れに過剰に不安を抱く必要はありません。選考はあくまで長期戦なので、1社ごとに振り回されず、着実に次の行動を続けていくことが成功への近道です。
SPIテストセンター結果の予測方法

SPIテストセンターの結果は本人に開示されないため、「自分の出来がどうだったのか」「合格ラインに達していたか」がわからず不安になる人も多いでしょう。
ここでは、そんな不透明さを補うために役立つ5つの予測方法を紹介します。自分なりに手応えを振り返り、今後の対策につなげてください。
- 模擬テストを活用して手応えを数値化してみる
- 他社のSPIでの通過率から間接的に判断する
- OB・OGや先輩に選考通過状況をヒアリングする
- 言語分野の手応えやミスの少なさから予測してみる
- 非言語分野の難しさや時間配分の感覚から判断する
①模擬テストを活用して手応えを数値化してみる
SPIの結果を直接確認できないからこそ、模擬テストの活用が有効です。Web模試や市販の教材を使い、繰り返し受験することで自分の得点や弱点が明らかになってきます。
特に、実際の試験に近い形式の模試を選ぶと、本番に近い手応えが得られるでしょう。スコアを記録しておけば、自分の成長や傾向も把握しやすくなります。
ただ模試を受けるだけでは意味がありません。結果を見返し、どの分野が安定しているか、どこに苦手意識があるのかを確認してください。
②他社のSPIでの通過率から間接的に判断する
SPIは複数企業で共通して使われるため、ひとつの企業で通過したかどうかが、他社での結果の目安になることも。
たとえば、ある企業でSPI後に次の面接へ進んだなら、テストの点数が一定基準を満たしていたと推測できるのです。反対に、不通過だった場合は再確認が必要かもしれません。
もちろん、企業ごとに評価の基準は異なりますが、複数社で傾向が一致すれば信頼性は高まります。このように、他社での通過実績を参考にすると、自分のSPIがどのレベルだったのか見えてくるでしょう。
③OB・OGや先輩に選考通過状況をヒアリングする
同じ大学の先輩やOB・OGの体験談は、SPIの結果を予測する上で非常に参考になります。自分と近いバックグラウンドの人の話は、評価の目安として信頼性が高いです。
たとえば、「問題は8割解けた感覚だったけど通らなかった」「非言語はミスが多かったが通過した」など、具体的な話が聞けると、自分の感触と比較できます。
また、同じ企業を受験した人の情報であれば、企業ごとの基準や傾向を知ることも可能です。ネットの情報よりも、身近な実体験のほうが有益なヒントになる場面も少なくありません。
④言語分野の手応えやミスの少なさから予測してみる
言語分野の問題は、正解・不正解が自覚しやすいため、自分の出来を予測しやすいパートです。
文章の読解や文法の問題がスムーズに解けたか、時間配分が適切だったかなどが判断材料になります。
特に、「迷わず選択肢を選べた」「読み返す回数が少なかった」などの感覚があれば、正答率も高いと見込めます。
逆に、選択肢を見落としたり、同じ問題を何度も読み直した場合は、集中力や理解力に課題があったかもしれません。
⑤非言語分野の難しさや時間配分の感覚から判断する
非言語分野は、スピードと正確さのバランスが試されるため、試験中の感覚が結果に直結しやすいです。
「どのくらい問題を解けたか」だけでなく、「時間に追われたか」「途中で焦ったか」なども大事な指標になります。冷静に解けたという自覚があるなら、結果も安定している可能性が高いです。
一方で、途中でパニックになったり、最後まで手が回らなかった感覚がある場合は、再対策が必要かもしれません。問題の難易度に関する印象も大切です。
たとえば、「簡単すぎた」と感じる場合は、全体的な正答率が高くなり、逆に差がつきにくいこともあります。
SPIテストセンターの結果を使い回す際の注意点
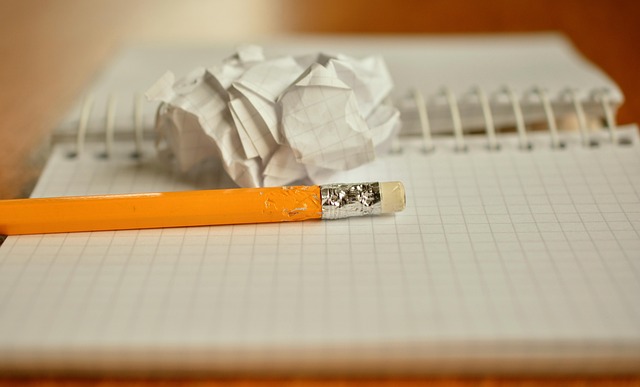
SPIテストセンターの結果は複数の企業に提出できますが、使い回す際には注意すべき点がいくつかあります。
理解が不十分なまま利用すると、選考に不利になることもあるため、次の4つのポイントを確認してください。
- SPIテストセンター結果の有効期限は約1年
- 試験の種類が異なる場合は再受検が必要
- 性格検査の結果が企業と合わないと通過しにくい
- 悪い結果のまま使い回すと不利になることがある
①SPIテストセンター結果の有効期限は約1年
SPIの結果には、約1年の有効期限があります。期限が切れると企業側は結果を参照できなくなるため、再受検が必要になるのです。
また、企業によっては「3か月以内の結果のみ有効」など独自の条件を設けている場合もあるため、応募前に確認しておくことが大切。
有効期限を把握せずに使い続けても、選考対象外となる可能性があるため注意してください。結果を利用する際は、自分の受検日や期限を確認し、最新の情報を提出できるようにしておきましょう。
②試験の種類が異なる場合は再受検が必要
SPIには複数の実施方式があります。テストセンター方式のほかに、WEBテスティングや企業内で行うCBT方式などがあり、それぞれ仕組みが異なるのです。
そのため、テストセンターで受けた結果を他の方式にそのまま使うことはできません。たとえばWEBテスティングを指定する企業に応募する場合は、改めてその方式で受検する必要があります。
結果を使い回す前に、企業がどの受検形式を採用しているか確認してください。対応していない形式の結果を提出しても無効になる可能性があります。
③性格検査の結果が企業と合わないと通過しにくい
SPIには性格検査が含まれており、企業はこの結果を参考にして応募者の人物像を判断しています。スコアが高くても性格傾向が企業と合わないと、選考で不利になる場合があるでしょう。
たとえば「挑戦より安定を好む」傾向が強く出た結果が、変化の多い部署を志望する企業の求める人物像と合わないと、通過しづらくなることも。
このように、性格検査の結果も繰り返し使われるため、誤った印象を与えたまま複数の企業に共有されることになるでしょう。もし結果に納得がいかない場合は、再受検を検討するとよいです。
④悪い結果のまま使い回すと不利になることがある
SPIのスコアが低いまま使い回してしまうと、以降の企業でも不利になる可能性も。テストセンター方式では結果が共通化されているため、最初に出した成績がそのまま複数の企業に共有されるのです。
「練習がてら受ける」つもりで臨むと、その成績が本番でも使われ続けてしまい、不利な状況になる恐れがあります。
もし満足のいく結果が出なかった場合は、早めに再受検して結果を更新するのがおすすめです。準備を整えたうえで受け直すことで、自信を持って選考に臨めるでしょう。
SPIテストセンターの結果を良くするための勉強法

SPIテストセンターの結果を少しでも良くしたいと考えるのは、就活生にとって自然なことです。ただやみくもに勉強するのではなく、ポイントを押さえた対策が必要。
ここでは、実践的かつ成果につながりやすい勉強法を5つ紹介します。自分に合った方法で効率的に取り組んでください。
- 問題集での演習を重ねて形式に慣れる
- 苦手分野を把握して重点的に復習する
- 時間配分を意識して模擬試験を解く
- 性格検査も想定して模擬テストで練習する
- 短期間でも効率よく学べる参考書を活用する
①問題集での演習を重ねて形式に慣れる
SPIでは、問題形式に慣れているかどうかが結果を大きく左右します。初見の問題に戸惑って時間を無駄にすることがあるため、繰り返し演習を行って出題パターンに慣れておくことが大切です。
とくに非言語分野はスピード勝負になるため、繰り返し解くことで処理能力が高まっていきます。
最初はうまくいかなくても、解説を読みながらつまずいた原因を理解すれば着実に力がついてくるでしょう。
②苦手分野を把握して重点的に復習する
効率よくスコアを伸ばすには、苦手分野を明確にし、集中的に取り組むことが効果的。やみくもに全範囲を勉強しても、時間が足りなくなるだけで成果につながらないことも。
まず模試や問題集を通じて、自分のつまずく部分を洗い出してください。図形問題に弱いのか、文章理解が苦手なのかを見極めることが大切です。
一度見つけた苦手は放置せず、繰り返し練習して克服しましょう。同じ種類の問題を何度も解くことで、解法が自然と身につき、全体の得点力も安定していくはずです。
③時間配分を意識して模擬試験を解く
SPIは時間制限がある試験なので、時間配分を間違えると後半の問題が解けずに終わってしまいます。そうならないためにも、模擬試験で制限時間内に解き切る練習が必要です。
解いている最中に「あと何分あるか」「どこに時間をかけるべきか」を意識することで、自然とタイムマネジメントの感覚が身についてきます。
特に非言語分野は1問に時間をかけすぎると他の問題に影響が出るため、見切りをつける判断力も求められるのです。本番で焦らないためにも、普段から時間を意識した演習を心がけてください。
④性格検査も想定して模擬テストで練習する
SPIの性格検査は見落とされがちですが、企業が人物像を評価するうえで大きな要素になっています。回答に一貫性があるか、極端な選択をしていないかが見られているのです。
「こう答えたら好印象だろう」と操作しようとすると、かえって不自然になり、マイナス評価を受けることも。だからこそ、事前に模擬テストで設問の雰囲気に慣れておくと安心です。
正直に、かつ自分らしく答えることが何よりも大切。無理に取り繕う必要はありません。
⑤短期間でも効率よく学べる参考書を活用する
就活が本格化すると、SPI対策に割ける時間も限られてきます。そんなときは、要点がコンパクトにまとまった参考書を使うのがおすすめです。
中でも頻出問題を絞って解説している参考書は、時間がないときの最終確認に役立ちます。内容を読むだけで終わらせず、実際に手を動かして解くことが理解の定着につながるでしょう。
短時間で成果を出すには、「正しい教材選び」と「集中した取り組み」の2つが鍵です。忙しい中でも工夫して学ぶことで、確実にスコアアップが目指せます。
テストセンターの結果を正しく理解し、対策につなげよう

テストセンターの結果は、就活生にとって見えづらい部分が多く、不安を感じる要因のひとつです。
しかし、企業がSPIを通じて何を評価し、どこに注目しているのかを正しく理解することで、その対策も明確になります。
実際には結果を直接見ることはできませんが、模擬テストの活用や通過実績の確認などによって、ある程度の予測は可能です。
また、結果の使い回しや有効期限、企業ごとの評価基準なども把握しておくことで、無駄な失敗を減らせるでしょう。勉強法を工夫すれば、テストセンターの結果を確実に良くなります。
テストセンターの仕組みを正しく理解し、戦略的に行動することが選考突破のカギですよ。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










