公務員試験の勉強時間は?合格者の平均と科目別対策を解説
安定した職業として人気の公務員ですが、試験内容は幅広く、合格には継続的な学習が不可欠です。特に「勉強時間」は合否を左右する大きな要因として、多くの受験者が気になるポイントでしょう。
この記事では、公務員試験の合格者の平均勉強時間や科目別の勉強法を詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員とは何か

公務員とは、国や地方自治体の組織に所属し、社会全体のために働く職業のことを指します。
警察官や消防士、税務職員、保健師などが代表的な例で、実は私たちの日常生活のあらゆる場面に関わっている存在です。
公務員という職業は「安定している」「休みが取りやすい」といったイメージが先行することも多いかもしれません。
一方、地方公務員は都道府県や市区町村で、福祉やインフラ整備、防災など、地域に密着した業務を行います。
民間と比較して選考スケジュールや試験制度も独特なため、早めの情報収集が今後のキャリア形成において大きな差を生むでしょう。
公務員試験の特徴

公務員試験は、民間企業の採用試験と比べて筆記試験の比重が高く、評価基準も明確に定められているのが特徴です。
筆記に加えて人物評価も行われるため、幅広い準備が必要です。特に就活生にとっては、試験の構造や傾向を理解することが効率的な対策につながります。
ここでは、試験科目や出題傾向、配点、評価のされ方など、公務員試験の基本的な特徴を整理して解説します。
- 試験科目の特徴
- 出題傾向の特徴
- 配点構成の特徴
- 評価基準の特徴
- 国家・地方の制度の特徴
①試験科目の特徴
公務員試験では、教養科目と専門科目が柱となり、それぞれに異なる準備が求められます。
教養科目では数的処理や文章理解、社会科学などの一般的な知識が問われる一方、専門科目では法律・経済・行政学など、より専門的な理解力が問われます。
特に国家一般職や地方上級では専門科目の比重が高く、得点源としての重要性が高いです。
出題範囲は非常に広いため、受験を決めた段階で早めに科目の全体像を把握し、得意不得意を見極める必要があります。
複数の科目を並行して学ぶスケジューリング力も、合格の鍵を握るでしょう。
②出題傾向の特徴
公務員試験は過去の出題パターンが分析しやすく、同じ形式・テーマが繰り返される傾向にあります。
例えば数的処理では、図形問題や場合の数、確率が毎年のように出題されますし、社会科学では時事問題や政策関連の問いが多く見られます。
表現や構成を変えた“応用型”の出題も増えてきています。そのため、単なる暗記ではなく、本質的な理解や応用力の養成が必要不可欠です。
また、直前期には模試や最新の時事問題にも触れ、近年のトレンドにも対応できるようにしておくと安心です。出題傾向の把握は、無駄な努力を避けるための近道といえるでしょう。
③配点構成の特徴
公務員試験では、どの科目に重点が置かれるかが試験区分ごとに異なります。たとえば国家総合職では筆記試験の配点が圧倒的に高く、地方初級では面接や人物評価が合否を左右する傾向にあります。
このように配点構成を理解していないと、学習の優先順位を誤ってしまうおそれがあります。
また、専門科目だけでなく、教養、論文、面接といった多様な評価軸が設けられているのも公務員試験の特徴です。
だからこそ、事前に配点表を調べ、自分の得点源となりうるパートを早めに固めておくことが、限られた時間の中で最大の効果を出すポイントです。
④評価基準の特徴
公務員試験の評価は、筆記・論文・面接の各段階でそれぞれ明確な評価基準が設けられている点が大きな特徴です。
筆記試験は数値評価が基本で、配点や合格ラインが公開されているケースも多いため、努力がそのまま結果に結びつきやすい構造です。
受け答えの内容だけでなく、表情や姿勢といった非言語的な要素も評価に含まれます。学生目線では、「何を言うか」だけに集中しがちですが、「どう伝えるか」まで意識することが大切です。
面接練習を通じて、自分の話し方や印象を客観的に見直すことも評価アップの鍵になります。
⑤国家・地方の制度の特徴
国家公務員と地方公務員では、試験制度や採用の流れに大きな違いがあります。
国家公務員は人事院が一括して試験を実施し、その後に各省庁が個別に面接を行います。一方で地方公務員は自治体ごとに試験が行われ、日程や出題内容もまちまちです。
さらに、国家公務員は全国転勤が前提ですが、地方公務員は地域に根ざした働き方ができる点も、志望動機に直結します。
就活生としては、それぞれの制度や働き方の違いを理解したうえで、自分に合った進路を選ぶ姿勢が求められます。制度を知ることが、後悔のない選択への第一歩となるでしょう。
公務員試験合格者の平均勉強時間

公務員試験は職種によって難易度や出題範囲が異なるため、必要な勉強時間にも大きな差があります。
ここでは、実際に合格した人のデータをもとに、国家公務員・地方公務員・市役所型・警察官消防士の4つの区分に分けて、それぞれの勉強時間の目安をご紹介します。
自身の志望先に合った勉強スケジュールを組むためにも、合格者の学習量を知ることは大きなヒントになります。
- 国家公務員の平均勉強時間
- 地方公務員の平均勉強時間
- 市役所・教養型の平均勉強時間
- 警察官・消防士の平均勉強時間
①国家公務員の平均勉強時間
国家公務員試験は難易度が高く、合格するためには1,000~1,500時間ほどの学習が必要とされています。
特に総合職を志望する場合、大学1〜2年のうちから準備を始める人もおり、長期的な戦略が不可欠です。出題科目は教養・専門・記述・面接と多岐にわたるため、計画的かつ継続的な学習が求められます。
先輩合格者の多くは、平日は2~3時間、休日は5時間以上を確保しており、1年以上かけて対策を進めています。
特別区・国家一般職・総合職など、志望区分によって求められる得点水準も異なるため、自分の進路に合わせた対策が大切です。
②地方公務員の平均勉強時間
地方上級(都道府県・政令市)を目指す場合、合格者の平均的な勉強時間はおおよそ800〜1,200時間とされています。
国家公務員と同じく専門試験が課される自治体が多く、対策にはまとまった時間が必要です。大学3年の夏からスタートし、1日3時間以上の学習を約1年間継続するパターンが主流といえるでしょう。
特に注意したいのは、地方公務員試験は筆記だけでなく、論文や面接の比重が大きい点です。
集団討論や人物評価で加点を狙うためには、早期から自己分析や時事対策にも取り組む必要があります。学習の質と持続力が合格を左右するといえるでしょう。
③市役所・教養型の平均勉強時間
市役所や教養試験のみを課す自治体では、必要な学習時間はおおよそ500〜800時間程度とされています。
大学4年の春頃から本格的に対策を始め、半年間で集中して合格を目指す人もいますが、そうした成功例はごく一部です。
多くの合格者は、大学3年の秋頃から毎日1〜2時間を積み上げ、長期的な視点で筆記力を高めています。
自分の得意・不得意を早期に見極め、効率よく分野ごとに演習を重ねることが成功のカギとなります。面接や集団討論の練習も、早い段階から取り入れておくと安心でしょう。
④警察官・消防士の平均勉強時間
警察官や消防士の試験では、教養試験に加えて体力試験・面接試験が大きなウェイトを占めます。筆記試験の難易度はやや低めといわれますが、平均的な勉強時間は400〜700時間程度が目安です。
スポーツ推薦などで受験する一部の人を除き、ほとんどの受験者が独学または講座で対策を行っています。
大学4年の春から3〜4か月で集中対策する人もいますが、一般的には半年以上前から学習をスタートし、毎日1~2時間をコツコツ積み重ねるスタイルが主流です。
体力試験の準備として、日常的にランニングや筋力トレーニングを取り入れることも欠かせません。志望先の特徴を踏まえて、筆記・体力・面接すべてのバランスを意識した学習計画を立ててください。
公務員試験の科目別の試験内容
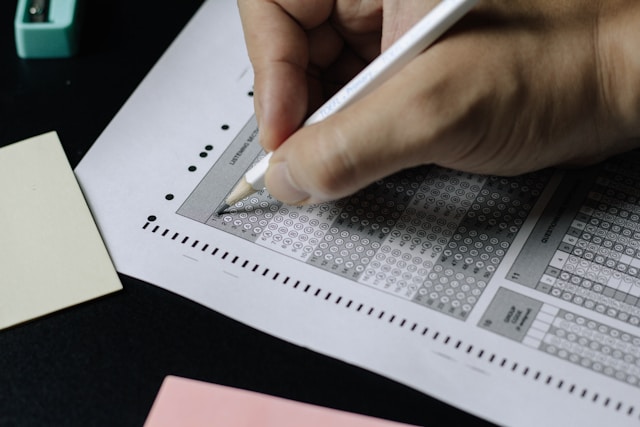
公務員試験は科目ごとに求められる力が異なり、すべてを同じように対策することは適していません。まずは各試験科目の内容や出題傾向を把握することで、自分に合った学習計画を立てやすくなります。
初めて受験を考える学生にとっては、「どんな問題が出るのか」を知ることが、最初の大きな一歩になります。
- 教養試験の試験内容
- 専門試験の試験内容
- 論文試験の試験内容
- 面接試験の試験内容
- 適性試験の試験内容
①教養試験の試験内容
教養試験では、公務員としての基礎的な知識や論理的思考力が問われます。文章理解・数的処理・判断推理など、大学で習う講義とは異なる科目が多く、最初は戸惑う学生も少なくありません。
加えて、人文科学・社会科学・自然科学などの一般常識的な知識も幅広く出題されます。
とくに文章理解や数的処理は、問題形式に慣れることで大きく得点力が伸びる分野です。出題数も多く、得意にできれば合格に近づく手応えを感じやすくなるでしょう。
就活と並行して準備を進める際も、教養試験はベースになるため、スキマ時間で継続的に取り組みやすい点も魅力です。
②専門試験の試験内容
専門試験は、行政職・技術職など志望する区分に応じて、出題される科目が大きく変わります。たとえば行政職では法律(憲法・民法)や経済(ミクロ・マクロ)、政治学・行政学などが主要科目となります。
一方、技術系は建築・土木・機械など、理工系の専門分野から出題されます。
大学で履修した内容と重なることもありますが、試験問題は独特の出題傾向を持つため、学んだ知識をそのまま活かすには工夫が必要です。
得意科目で確実に得点し、苦手科目は「落としすぎない」ラインを意識しておくと安心です。
③論文試験の試験内容
論文試験では、公務員として求められる視点や問題意識を持っているかが見られます。与えられたテーマに対して、自分の考えを筋道立てて論じる力が問われるため、論理構成力・表現力の両方が必要です。
テーマは「防災」「地域活性化」「人口減少社会」など、社会課題を扱うものが多く、時事への関心が評価に直結します。
また、読み手である面接官や採点者にとって、わかりやすく、伝わりやすい文章であるかも重要な判断材料です。
独学での対策が難しいと感じる人は、大学のキャリアセンターなどを活用して第三者に読んでもらうと、客観的なフィードバックが得られて改善につながります。
④面接試験の試験内容
面接試験は、筆記では見えにくい人柄や公務員としての適性を評価するための選考です。
志望動機や自己PRはもちろん、学生時代の経験や困難をどう乗り越えたかなど、受験者の価値観や思考の深さを問う質問が多く見られます。
また、近年では自治体の特色に応じた質問や、SDGsや防災などに関する社会的関心事への見解を問われることも増えています。
回答の内容以上に、受け答えの姿勢や語調、表情の柔らかさといった非言語的な部分も評価されるため、準備段階からそれらも意識しておくとよいでしょう。
落ち着いて臨むことで、自分らしさが伝わりやすくなるはずです。
⑤適性試験の試験内容
適性試験は、主に警察官や消防士、刑務官など、現場対応や即時判断が求められる職種で実施されます。計算問題・照合・図形認識・注意力テストなどを通じて、短時間で正確な判断ができるかを見極められます。
また、心理適性検査を通じて、受験者の性格特性やストレス耐性が数値化されることもあります。
これらは学力よりも、反応の傾向や性質に基づいて判断されるため、準備がしにくいと感じる方も多いかもしれません。
しかし、問題形式に慣れておくことで余計な緊張を減らし、本来の力を発揮しやすくなります。過去問や練習ソフトを活用して、時間感覚や出題傾向に慣れておくことが安心材料になるでしょう。
公務員試験の科目別の試験対策
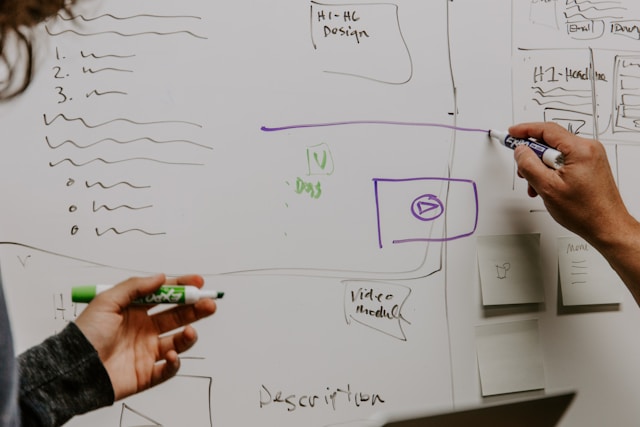
公務員試験では科目ごとに出題傾向や求められる力が異なるため、やみくもに勉強を始めると効率が下がってしまいます。
自分の得意・不得意を把握し、科目別に最適な学習法を取り入れることが合格への近道です。ここでは主要5科目について、それぞれの対策ポイントを詳しく解説します。
- 教養試験の試験対策
- 専門試験の試験対策
- 論文試験の試験対策
- 面接試験の試験対策
- 適性試験の試験対策
①教養試験の試験対策
教養試験対策では、出題分野の多さに圧倒されがちですが、頻出分野を優先的に対策することで着実に点数を伸ばせます。
特に数的処理や文章理解は配点が高く、安定した得点源となるため、早い段階で集中して取り組むべきです。
計算や論理を要する問題は、反復練習によってスピードと正確性が身につきます。一方で、人文・社会・自然などの知識系科目は暗記が中心となるため、効率的に覚える工夫が欠かせません。
基礎力を養う教養試験の攻略は、公務員試験全体の合格率を押し上げる土台になるでしょう。
②専門試験の試験対策
専門試験は、大学での専攻や志望職種に応じて出題分野が決まりますが、対策にはある程度の戦略が必要です。
範囲が広いため、全科目を完璧にこなすのではなく、頻出テーマに的を絞って重点的に取り組むことが重要です。
市販の過去問や公務員試験用テキストを活用しながら、繰り返し演習することで知識の定着を図れます。特に初学の科目は、講義動画や図解資料なども併用して理解を深めると効率的です。
自分なりにまとめノートを作成したり、問題の解説を他人に説明できるレベルに引き上げたりすることが、合格への大きな一歩となるでしょう。
③論文試験の試験対策
論文試験の対策には、文章構成力と時事的な視点の両方が求められます。
テーマに対して自分の意見を持ち、それを他人が理解できる形で表現するためには、型と練習が欠かせません。まずは「序論・本論・結論」の型を習得ましょう。
課題となりやすい社会問題に対しては、賛成・反対両方の視点で考える習慣をつけると、より多角的な文章になります。書いた文章は自己添削するだけでなく、第三者に読んでもらうことも大切です。
書き慣れていない学生ほど、早めに手を動かして練習を重ねましょう。
④面接試験の試験対策
面接試験では、人物像や志望動機が評価されるため、事前準備が合否に大きく影響します。自分の強みや経験を棚卸しし、公務員としてどのように活かしたいかを明確にすることが第一歩です。
話す内容が決まったら、実際に声に出して練習しましょう。家族や友人に協力してもらったり、録音して客観的に見直したりすると改善点が見えてきます。
また、非言語的な要素も見られるため、表情・姿勢・話すスピードなども意識してください。特に第一印象は評価に直結しやすいため、身だしなみや礼儀も含めたトータルの準備をしておくと安心です。
⑤適性試験の試験対策
適性試験はスピードや注意力を測る形式が中心で、知識の有無よりも「慣れ」が問われます。問題の形式にあらかじめ慣れておくことで、焦らずに対応できるようになるでしょう。
市販の模擬問題やWeb上の無料ツールを活用し、時間を計って解く練習を重ねることが効果的です。初めはミスが多くても、回数を重ねるごとにペースや正確さが向上していきます。
特に警察官・消防官志望の学生は、計算や判断系の問題が合否に直結するため、早期から対策を始めておくのがおすすめです。
短時間でも集中して解く訓練を積むことで、本番でも落ち着いて取り組めるようになります。
公務員試験に合格するための勉強法

公務員試験に合格するには、配点の高い科目や苦手分野を意識した効率的な学習が求められます。
大学生活や卒業研究、就活イベントなどと並行して取り組むには、時間の使い方にも工夫が欠かせません。
- 配点の高い科目を意識して勉強する
- 苦手科目を重点的に勉強する
- 過去問を繰り返し勉強する
- 試験日から逆算して勉強する
- 学習手段を選んで効率的に勉強する
①配点の高い科目を意識して勉強する
公務員試験では、すべての科目を均等に対策するのではなく、配点が高い科目を中心に効率よく学ぶことが合格のカギです。
特に、教養試験と専門試験の両方がある場合には、志望先によって重視される科目の割合が異なるため、まずは配点比率を確認することが重要になります。
時間が限られる就活生にとって、こうした戦略的な優先順位づけは無駄な学習を減らすだけでなく、精神的な負担の軽減にもつながるでしょう。
自分の目指す試験種の構成を把握し、得点源となる科目から着手してください。
②苦手科目を重点的に勉強する
「苦手だから後回しにする」――この考え方は非常に危険です。
公務員試験は科目数が多く、ひとつの分野で大きく失点すると全体の合否に響きます。そのため、得意な科目に頼りすぎず、あえて苦手な分野から手をつける勇気が求められます。
特に、数的処理や自然科学などは時間をかけても身につきづらいため、早めに基礎から復習することが大切です。
就活や卒論と並行して勉強時間が限られている今こそ、苦手なものに正面から向き合って克服する姿勢が合格への第一歩となるでしょう。
③過去問を繰り返し勉強する
過去問演習は、公務員試験対策で最も実践的かつ効果的な勉強法のひとつです。
というのも、公務員試験は出題傾向が比較的安定しており、過去問に似た形式やテーマが繰り返し出題される傾向があるからです。
例えば、数的処理では「仕事算」や「確率」など定番のパターンがあり、繰り返し解くことで処理スピードも上がっていきます。
重要なのは、解説を読んで「なぜ間違えたか」を考えるプロセスです。時間がない就活生ほど、過去問演習を軸に据えて効率よく合格力を高めていきましょう。
④試験日から逆算して勉強する
「なんとなく始める」ではなく、「試験日から逆算して勉強スケジュールを立てる」ことが重要です。
公務員試験は長丁場の準備が必要なため、事前にいつ何を学ぶかを明確にしておかないと、途中でペースを見失ってしまうリスクがあります。
また、学習進捗を毎週振り返り、計画の修正や調整をこまめに行うことで、無理のない範囲で着実に力を伸ばせます。
大学の授業や就活スケジュールと両立するには、自分の生活リズムに合った現実的な計画が求められるでしょう。
⑤学習手段を選んで効率的に勉強する
限られた時間の中で効率よく勉強を進めるには、自分に合った学習手段を見極めることが不可欠です。
例えば、「独学でマイペースに進めたい」「予備校で強制力がほしい」「動画講座やアプリでスキマ時間を活用したい」など、人によって最適な方法は異なります。
独学派は、科目ごとに評価の高い参考書を選び、計画的に取り組む必要があります。一方、通信講座や予備校は添削や模試、質問対応などが充実しており、学習の質が安定しやすい利点があります。
自分の生活スタイルや性格に合った方法を選ぶことで、学習効果は飛躍的に高まるはずです。
公務員試験の勉強を始める時期

公務員試験の勉強を始めるタイミングは、志望する職種や学年によって最適な時期が異なります。
何となく遅れてしまったと感じていても、今からできることを把握しておけば巻き返しは可能です。ここでは学年別に、それぞれの立場に合ったスタート時期と勉強のポイントを詳しく紹介します。
- 大学3年春に始める場合
- 大学3年秋に始める場合
- 大学4年春に始める場合
- 短大生が始める時期
- 大学院生が始める時期
①大学3年春に始める場合
大学3年の春に勉強を始めるのは、公務員試験における理想的なスタート時期とされています。
試験本番まで1年以上の余裕があるため、基礎からじっくり学べるだけでなく、自分に合った勉強法を模索する時間も確保できます。
特に国家一般職や専門職など科目数が多い試験区分を志望している場合、このタイミングで始めておくと、無理なく全範囲をカバーすることができるでしょう。
部活やサークル、インターンとの両立も可能で、総合的に大学生活と受験準備を両立しやすいのが特徴です。計画的に進めたい方には、最適なスタートといえるでしょう。
②大学3年秋に始める場合
大学3年の秋から勉強を始める人は非常に多く、一般的なスタート時期といえます。
秋からでも半年以上の準備期間があるため、正しい戦略と継続力があれば十分に間に合います。ゼミ活動や卒業研究が本格化する前に基礎を固めておけば、忙しくなる4年春以降にも余裕が生まれます。
ただし、春スタートの人と比べると時間に限りがあるため、苦手科目の見極めと優先順位づけが重要です。
「このタイミングで間に合うか不安…」という声もありますが、むしろ集中力のある人にとっては効率よく実力を高める好機です。
現実的なスケジュール感を持ちたい方におすすめの開始時期といえるでしょう。
③大学4年春に始める場合
大学4年の春から勉強を始める場合、時間的には厳しい戦いになることを覚悟しておく必要があります。
本試験まで3〜4か月ほどしかない中で、一気に知識を詰め込み、過去問演習までこなす必要があるため、相当な覚悟と集中力が求められます。
一方で「就活をやってみたけれど公務員に切り替えたい」「卒論や卒業研究が終わった今から挑戦したい」というケースでは、最後のチャンスとなることもあるでしょう。
この時期にスタートする場合、最初から重要科目を絞ってアウトプット重視の学習を心がける必要があります。覚悟を決めて取り組むことで、飛躍的に成長できるチャンスともいえるでしょう。
④短大生が始める時期
短大生は2年間という限られた在学期間の中で対策を行う必要があるため、早めの行動が何よりも重要です。
理想は1年生の夏頃までに勉強を開始し、2年生の春〜夏にかけて実施される試験に備えるスケジュールを組むことです。
市役所や都道府県職員といった教養試験中心の試験を目指す場合でも、問題の難易度や出題範囲の広さから、短期勝負では難しくなります。
短大生だからこそ、他の学生よりも早く動くことが合格への最大の武器になるでしょう。「早く始めた者勝ち」という意識を持って、着実に一歩ずつ進めてください。
⑤大学院生が始める時期
大学院生が公務員試験を目指す場合、研究や学会発表などとの両立をどう進めるかが大きな課題となります。
理系・文系を問わず、修士1年の秋〜冬頃には試験対策を始めておくと、2年次の本格的な研究が始まる前に基礎を固めることができます。
特に技術系や研究職系の公務員を目指す方は、専門知識が試験に活かせる場合もありますが、教養試験や論文対策が共通で必要になるケースも多いため、油断は禁物です。
限られた時間の中で「何を・いつまでに・どうやってやるか」を明確にすることで、学業と試験対策を両立しやすくなるでしょう。
公務員に向いている人の特徴

公務員は民間企業とは異なり、公共の利益のために働く職業です。そのため、向いている人の特徴にも一定の傾向があります。
「民間と迷っている」「自分に適性があるかわからない」と悩む就活生にとっては、自分の強みが公務員にマッチしているかを知る良い機会になるでしょう。
- 社会貢献に関心がある人
- 地域に愛着がある人
- コツコツ努力できる人
- 責任感がある人
- 安定志向がある人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①社会貢献に関心がある人
社会貢献に関心がある人は、公務員として大きなやりがいを感じながら働ける可能性が高いです。
公務員の仕事は、民間企業のように利益を追求するのではなく、誰かの困りごとを解決したり、地域や社会をより良くしたりすることに主眼が置かれています。
例えば、災害時の支援、生活保護の手続き、教育や福祉の充実など、目立たないけれど人々の暮らしを根底から支える業務が中心です。
短期的な成果よりも、長期的な視点で社会に貢献していくスタンスを大切にしたい人に、特に向いています。
②地域に愛着がある人
地元やゆかりのある地域に対する思いが強い人は、特に地方公務員として活躍しやすい傾向があります。
なぜなら、地方自治体の仕事はその地域で暮らす人々の生活に直結しており、日々の業務が地域の課題解決や魅力の発信につながるからです。
例えば、高齢者支援や子育て施策、地元イベントの運営、公共施設の管理など、身近な暮らしを支える役割が数多くあります。
Uターン就職やIターン就職を考えている場合にも、公務員は非常に有力な選択肢の一つといえるでしょう。
③コツコツ努力できる人
公務員の仕事は、正確さと継続力が求められる場面が非常に多いです。
例えば、住民からの申請を1件ずつ丁寧に処理する窓口業務や、法律・条例に沿った判断を行う審査業務など、注意深く進めなければならない仕事が日常的に発生します。
また、法改正への対応や新制度の導入に向けた研修など、日々の自己学習も欠かせません。
派手な結果よりも、正確性や誠実さが評価される環境で働きたいと考えているなら、長く活躍できるはずです。
④責任感がある人
責任感を持って行動できる人は、公務員として高い信頼を得ながら業務をこなせるタイプです。
行政の業務では、法令や制度に則った公平で正確な処理が求められます。たとえば、福祉の給付決定にミスがあれば、住民の生活に深刻な影響を与えてしまう可能性もあります。
そうした場面で「自分の仕事が誰かの人生に関わるかもしれない」という意識を持って取り組む姿勢を意識しましょう。
自分の判断に誇りを持ち、誠実な対応を心がける姿勢は、公務員としての大きな資質の一つです。
⑤安定志向がある人
安定した職場環境で長く働きたいと考えている人には、公務員という選択は非常に魅力的に映るでしょう。
公務員は民間企業に比べて景気の影響を受けにくく、突然の倒産や人員整理のリスクがほとんどありません。
また、育児や介護に配慮した休暇制度や復職支援制度も整っており、結婚や出産などのライフステージの変化にも柔軟に対応できます。
「家庭と仕事を両立させたい」「無理なく長く働き続けたい」と考える就活生には、公務員の安定性が強い味方になるはずです。
公務員試験に落ちた場合の進路

公務員試験に落ちたからといって、将来の選択肢が閉ざされるわけではありません。
むしろ、ここでの判断が今後のキャリアを大きく左右する重要な分岐点になります。落ち込みすぎず、今できる選択肢を整理し、前向きに行動していくことが大切です。
ここでは、公務員試験に不合格だった場合に考えられる主な進路を5つ紹介します。
- 臨時職員として働く
- 民間企業に就職する
- 翌年に再挑戦する
- 公務員浪人として備える
- 大学の支援を活用する
①臨時職員として働く
公務員試験に落ちてしまったものの、行政の現場に関わりたいと考える学生にとって、臨時職員として働くことは現実的な選択肢です。
臨時職員は、一般職のような筆記試験ではなく、比較的簡易な面接や書類選考で採用されるケースが多いため、挑戦しやすいのが特徴です。
実際には、市役所や県庁などで窓口応対、書類作成、庶務業務などを担うことが多く、住民対応や行政手続きの流れを肌で感じることができます。
希望する自治体の公式HPや就職情報サイトをこまめにチェックし、こまめな情報収集を心がけてください。
②民間企業に就職する
民間企業への進路変更も、有力な選択肢の一つです。特に「安定性を求めて公務員を志望した」「社会の役に立ちたいという思いがあった」という学生にとっては、それを活かせる業界は数多く存在します。
インフラ、金融、保険、福祉、教育、人材などの分野では、地域社会に貢献する業務が中心となるため、志向がマッチしやすいです。
また、公務員試験に向けてコツコツ努力してきた過程は、選考においても「計画的に物事を進められる人物」として評価されやすいでしょう。
民間就職は情報の量とスピードがカギになりますので、ナビサイトや学内セミナーを活用し、なるべく早い段階から動き出すことが重要です。
③翌年に再挑戦する
「どうしても公務員になりたい」という強い思いがある学生は、翌年の試験への再挑戦を目指すのがよいでしょう。
一度試験を経験したことにより、自分の苦手科目や時間配分、面接の課題などが明確になっているため、対策の精度が格段に上がります。
再チャレンジは精神的にも負担がかかるため、周囲のサポートや定期的な自己点検を行いながら、粘り強く進めていく姿勢が大切です。
④公務員浪人として備える
卒業後に就職せず、フルタイムで受験勉強に集中する「公務員浪人」という道を選ぶ学生も少なくありません。
特に1〜2点差で不合格となった場合や、筆記は通ったが面接で失敗したようなケースでは、あと少しの努力で合格できる可能性があるため、十分に検討する価値があります。
ただし、公務員浪人は想像以上に精神的・経済的な負担が大きいため、自身の生活環境や家族の理解が得られているかをしっかり確認しましょう。
覚悟を持って「本気で合格したい」と思える学生にとっては、集中力と効率を最大限に活かせる環境になるはずです。
⑤大学の支援を活用する
大学のキャリアセンターや進路指導室は、公務員試験後の進路に悩む学生にとって非常に頼りになる存在です。
就職相談、模擬面接、エントリーシート添削など、多角的なサポートが用意されており、進路が明確でない学生にも的確なアドバイスを提供してくれます。
また、大学によっては公務員試験に再挑戦する学生向けの講座やガイダンスを実施しているところもあり、学内で受験準備を続けることが可能です。
焦らず、自分に合ったサポートを選びながら、次の一歩を踏み出していきましょう。
不安を知識に変えて、公務員試験に挑もう

公務員試験に対する不安は、正しい情報と計画的な準備で確実に軽減できます。
合格者の平均勉強時間や科目ごとの特徴、効率的な対策方法を把握すれば、自分に合った戦略が立てやすくなります。
さらに、始める時期や自身の適性も知っておくことで、迷いのない学習が進められるはずです。仮に不合格となっても、進路は一つではありません。
重要なのは「やるべきことを知り、行動に移すこと」。知識は不安を打ち消す最大の武器です。公務員という目標に向けて、一歩ずつ自信をもって歩み出しましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









