公務員の懲戒処分とは?種類や基準を徹底解説
「公務員って安定しているって聞くけれど、懲戒処分されることもあるの?」そんな疑問や不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
公務員には法律や規則を守る義務がありますが、それを違反した場合には「懲戒処分」という厳しい対応が取られることもあります。
しかし、処分の内容や対象になる行為には明確な基準があり、正しく理解しておけば、過度に怖がる必要はありません。
この記事では、公務員の懲戒処分について、種類や基準、よくあるケースや疑問点まで、これから公務員を目指す方にもわかりやすく解説します。就職活動の一環としてぜひ参考にしてみてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員の懲戒処分とは

公務員の懲戒処分とは、職務上の義務に違反したり、不適切な言動を取ったりした公務員に対して、公的機関が正式に責任を問う制度です。
国家公務員法や地方公務員法に基づいて処分の種類や手続きが定められており、場合によっては減給や免職といった厳しい措置が取られることも。
この制度の目的は、公務の信用を守ることに加えて、職場全体の規律を維持し、国民からの信頼を確保することにあります。
特に、公務員は「全体の奉仕者」として公共の利益のために働く立場であり、民間企業の社員以上に厳しい倫理観や法令遵守の姿勢が求められるでしょう。
公務員の懲戒処分の種類一覧

公務員には、高い倫理観と責任感が求められ、重大な非違行為に対しては厳格な懲戒処分が下されます。
これらの処分は、国家公務員であれば「国家公務員法第82条」、地方公務員であれば「地方公務員法第29条」に基づいて行われます。
いずれの制度も共通して「戒告・減給・停職・免職」の4種類の懲戒処分を定めており、法令違反や服務義務違反があった場合に、事実に応じて段階的に処分が選択されます。
ここでは、公務員の懲戒処分の種類について、それぞれの特徴と法的根拠もあわせてわかりやすく解説します。
- 戒告とは
- 減給とは
- 停職とは
- 免職とは
- 懲戒処分に該当しない措置とは
①戒告とは
戒告は、懲戒処分の中で最も軽いものであり、非違行為に対する「注意」や「警告」にあたる処分です。
法的には、国家公務員法第82条第1項第1号、および地方公務員法第29条第1項第1号に明記されており、「その将来を戒めるための処分」として位置づけられています。
たとえば、繰り返しの遅刻、勤務態度の不良、報告義務の怠慢など、比較的軽微な服務規律違反が戒告の対象です。
書面や口頭で「反省と改善」を求められる措置であり、処分としては軽いものの、人事記録として残ることがあるため、昇進や異動の際に影響する可能性も。
②減給とは
減給は、一定期間にわたり給与の一部を減額する処分で、国家公務員法第82条第1項第2号、地方公務員法第29条第1項第2号に規定されています。
処分内容には上限があり、国家公務員法の場合、「1年間に3回を超えて行うことはできない」かつ「1回あたり俸給月額の1/10以下」が原則とされています。
対象となるのは、公金の管理不備、勤務中の職務怠慢、不適切な行為による信用失墜などで、明らかな不注意や繰り返される業務違反が主なケースです。
給与が減ることは生活面のダメージだけでなく、同僚や上司との信頼関係にも影響します。
また、将来的な昇任の候補から外される可能性もあり、短期的な制裁にとどまらない深刻な影響をもたらすことも。
③停職とは
停職は、職務に就くことを一定期間禁じる処分であり、国家公務員法第82条第1項第3号、地方公務員法第29条第1項第3号に定められています。
この期間中は原則無給となり、自宅待機を命じられることが多いです。処分期間は短くて1か月程度から、重い場合には数か月に及ぶこともあり、職場復帰後も人間関係や評価に影響を与えます。
対象となるのは、ハラスメント行為、上司の命令に対する重大な違反、重大な過失行為などです。たとえば、部下への暴言、虚偽報告、業務上の故意の怠慢がそれに該当します。
停職は単なる「一時停止」ではなく、事実上の職場内での居場所の喪失につながることもあるでしょう。
④免職とは
免職は、懲戒処分のなかで最も重いものであり、国家公務員法第82条第1項第4号、地方公務員法第29条第1項第4号により定められた「職を失う」処分です。
対象となるのは、公金横領、飲酒運転による重大事故、強制わいせつなど、社会的にも大きな非難を浴びる行為です。
免職になると、これまでのキャリアは一瞬で崩れ去り、再就職にも極めて大きな不利が生じます。
公務員としての経歴に「懲戒免職」が明記されることになり、たとえ民間企業への転職を考えたとしても、採用されにくくなる可能性も。
また、退職金が減額または不支給となる場合もあり、経済的打撃も非常に大きいです。
⑤懲戒処分に該当しない措置とは
懲戒処分には当たらないものの、行動改善を促す目的で行われる「非懲戒的措置」もあります。
これには「訓告」「厳重注意」「指導」などが含まれ、国家・地方いずれの公務員制度でも運用されています。
これらは公的記録に残らない場合もありますが、内容次第では人事評価に反映されることがあり、繰り返されれば昇進に不利になることもあります。
たとえば、書類の誤提出、備品の私的流用、職場での軽率な言動など、重大ではないが無視できない行為に対して行われます。
公務員は国民から見られる立場であり、軽率な一言や対応が信頼失墜につながることも。就活生のうちから、注意を受けた際に「なぜ言われたのか」をしっかり考える習慣を持ちましょう。
公務員が懲戒処分となる行為とは

公務員の懲戒処分は、明確に定められた法令や規則に違反した場合に科されるもので、国家公務員であれば国家公務員法、第82条を中心とした規定、地方公務員であれば地方公務員法第29条に基づいて処分が下されます。
ここでは、懲戒処分の対象となる主な行為を4つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。
- 法令違反(信用失墜・秘密漏洩・政治活動など)
- 職務義務違反(服務違反・怠慢・命令不服など)
- 非行・不適切行為(ハラスメント・暴言など)
- 公務外の不祥事(飲酒運転・窃盗・暴行など)
①法令違反(信用失墜・秘密漏洩・政治活動など)
国家公務員は国家公務員法第99条以降、地方公務員は地方公務員法第33条以降において、職務上知り得た秘密を漏らすことや、政治的中立性の保持などが義務づけられています。
たとえば、個人情報をSNSや口頭で第三者に伝えるといった行為は「守秘義務違反」となり、重大な処分の対象です。
また、政治的発言や活動に関しても、選挙運動への関与などは処分の根拠となる「政治的行為の制限」に違反する恐れがあります。
さらに、国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)や地方公務員法第33条(同様の信用失墜行為の禁止)では、公務員としての品位を保つよう求められており、「職務外でも不適切な言動を慎むべき」とされています。
②職務義務違反(服務違反・怠慢・命令不服など)
国家公務員法第98条および地方公務員法第32条では、公務員の「職務遂行義務」が定められています。これらの規定は、職務を誠実に遂行し、上司の職務上の命令に従うことを義務づけるものです。
無断欠勤や遅刻の常態化、命令に対する反抗的態度は、明確な「義務違反」と見なされ、懲戒処分の対象となります。
また、地方公務員法第35条では「職務専念義務」が規定されており、勤務時間中に私的な活動に従事することも処分の根拠となります。
職務に対する誠実な姿勢が求められる公務員にとって、こうした義務違反は組織の信頼や行政サービスの質にも直結する問題です。
③非行・不適切行為(ハラスメント・暴言など)
パワハラやセクハラといった職場内での非行は、近年ますます厳格に取り締まられるようになっています。
国家公務員法には明文化された「ハラスメント禁止規定」は存在しませんが、人事院が定める服務規律や、職場環境整備に関する指針に基づき、懲戒処分が科される場合も。
地方公務員も同様に、地方公共団体のハラスメント防止規程やコンプライアンス条例等により、厳しく対処されます。
また、信用失墜行為の一環として、日常的な暴言や威圧的な態度も懲戒処分の対象になり得ます。とくに「公的な立場を利用した圧力」は、上司・部下関係にかかわらず重大な倫理違反とされる傾向がありますよ。
④公務外の不祥事(飲酒運転・窃盗・暴行など)
国家公務員法第99条や地方公務員法第33条では、「信用失墜行為の禁止」が明記されており、この規定は勤務時間外の行為にも適用されます。
たとえば飲酒運転や暴力事件、軽微であっても刑事罰の対象となるような私的トラブルは、懲戒処分の根拠として扱われます。
実際、ニュース等で報じられる懲戒免職の事例には、プライベートでの不祥事が少なくありません。
とくに地方自治体などは地域との結びつきが強く、住民からの信頼が揺らぐと、行政サービスそのものの信頼性に関わるため、より厳しい姿勢で処分が下される傾向がありますよ。
公務員の懲戒処分の基準

公務員の懲戒処分は、単純なルール違反の有無だけでなく、行為の背景や悪質性、再発可能性などを多角的に検討して総合的に判断される仕組みです。
処分には戒告、減給、停職、免職の4段階があり、人事院や各地方公共団体が定めた指針に基づいて適用されます。
職務専念義務違反のような比較的軽度な違反には戒告や減給が、飲酒運転や公金の不正使用といった重大な非行には停職や免職といった重い処分が科される傾向があります。
また同じ違反行為でも、管理職など指導的立場にある者はより重い処分を受ける可能性も。
公務員は国民全体の奉仕者として高い倫理観が求められ、その行動一つ一つが行政への信頼に直結するため、民間企業以上に厳格な規律が要求されるのです。
公務員の懲戒処分の判断方法
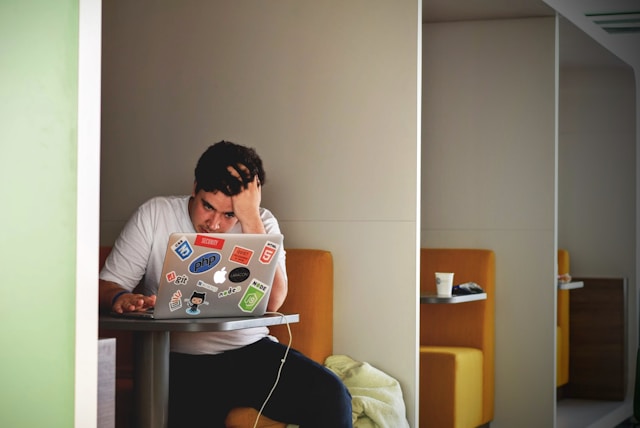
公務員は高い倫理観と公共性が求められる職業であり、不適切な行為に対しては厳正な処分が科されます。
しかし、公務員を目指す就活生にとっては「懲戒処分がどのように判断されるのか」が見えづらく、不安に感じる場面も多いでしょう。
採用後に思わぬ行動で信頼を損なわないためにも、判断のプロセスを知っておくことは大切です。
ここでは、処分が下されるまでの判断軸を3つの観点から解説します。制度への理解を深め、将来の備えにつなげてください。
- 処分の必要性の判断
- 処分の種類の判断
- 処分の妥当性の判断
①処分の必要性の判断
懲戒処分の第一段階は「そもそも処分が必要かどうか」の判断です。
公務員の行動は、国民の信頼に直結するため、職場内の規律を著しく乱したり、公務員の信用を大きく損なうような行為があった場合には、処分の検討が始まります。
ただし、どんな違反も即座に懲戒処分となるわけではありません。たとえば、軽微なルール違反や初めての不注意であれば、まずは口頭指導や訓告といった軽い措置にとどまるケースも少なくありません。
処分の必要性は、行為の内容や社会的影響、反省の態度などを総合的に見て判断されるのです。
②処分の種類の判断
処分の必要性が認められた場合、次に行為の重大性に応じて処分の種類が選ばれます。
懲戒処分には「戒告」「減給」「停職」「免職」という4つの段階があり、それぞれの重さに応じて適用される行為が異なるのです。
たとえば、勤務時間中に私的なSNSを頻繁に利用していたという程度であれば、戒告にとどまることが多いですが、職務上知り得た個人情報を漏えいしたような深刻な行為には、停職や免職といった重い処分が下される可能性があります。
人事院が示す指針や、これまでの懲戒事例などを参考にしながら、公平性と妥当性を担保した処分選択が行われますよ。
③処分の妥当性の判断
最後に、選ばれた処分が「行為に対して過剰でも不足でもないか」という観点から妥当性が検討されます。
たとえば、似たような違反をした別の職員が戒告だったのに、自分だけ停職になったという場合、不公平と受け取られかねません。
このような不均衡を避けるため、過去の処分例や組織内の対応方針と照らし合わせて判断が行われます。
また、処分を受けた職員には、不服申し立ての制度も設けられており、必要に応じて異議を申し立てられます。
公務員の懲戒処分で注意すべき点

公務員としての信頼を損なう行為は、思わぬかたちで将来に影響を及ぼします。
ここでは、公務員の懲戒処分に関して注意すべきポイントを紹介し、処分を避けるための意識づけを行います。公務員を志す就活生にとっても、将来後悔しないための大切な知識です。
- 軽微な違反への注意
- 処分歴の影響
- 誤解による処分の予防
- 再発防止の意識
- 情報公開のリスク
①軽微な違反への注意
小さなミスや不注意でも、信頼を損なえば懲戒処分の対象となる場合があります。
たとえば、私用スマートフォンの無断使用や遅刻の常習化、職場での不用意な発言など、一見些細な行動であっても、継続性や周囲への影響次第で「服務規律違反」と判断されることがあるのです。
とくに地方自治体では、具体的な処分基準が必ずしも統一されていないため、個別の判断で処分が下されるケースも多くあります。
こうした状況を踏まえると、公務員という立場は社会から常に「模範」として見られているという意識が欠かせません。
②処分歴の影響
懲戒処分を受けた事実は、昇進・異動・再任用の場面においてマイナス材料として扱われる傾向があります。
たとえば、昇任試験や人事評価の際に、過去の処分歴が足かせとなり、周囲との差がついてしまうことも珍しくありません。
さらに、再就職や他省庁への転職を希望する場合でも、処分歴があることで書類審査で不利になることがあります。
このように、たった一度の処分がその後のキャリアに長期的な影響を及ぼす点は見逃せません。公務員の仕事は安定している一方で、信頼を失うとその安定を維持することが難しくなるのです。
③誤解による処分の予防
意図しなかった行動や発言が、周囲に誤解を与え、懲戒処分につながってしまう事例もあります。
たとえば、軽い冗談のつもりがハラスメントと捉えられたり、プライベートのSNS投稿が組織の信用を損なうものと見なされたりする可能性も。
とくに近年では、情報が拡散されやすく、些細な発信でも問題視される可能性が高まっています。
こうしたトラブルを防ぐには、日頃から節度ある言動を意識し、職場内での信頼関係を丁寧に築いておくことが不可欠です。
④再発防止の意識
懲戒処分を受けた後、どのように信頼を回復していくかが、その後の評価を大きく左右します。
たとえば、服務違反をした人が、反省文だけで終わらせるのではなく、自主的に業務改善策を提出したり、日報や面談を通じて誠実な姿勢を示したりすることが、再評価につながるケースもありますよ。
実際、人事院のガイドラインでも、再発防止への取り組み状況や反省の深さが、処分内容や将来の昇任に影響することが明示されています。
⑤情報公開のリスク
懲戒処分を受けると、その内容が自治体や省庁のウェブサイトで公表される場合があります。
掲載される情報には、氏名・所属・処分内容・理由などが含まれ、1か月程度の間、誰でも閲覧できる状態になることが一般的。
とくに公務員は社会的な注目度が高いため、処分が報道されたり、SNSで拡散されたりするリスクもあります。
こうした公開情報は、本人の名誉や家族の安心、就職後の人間関係にまで影響を及ぼす恐れも。
たった一度の軽率な行為が、自分だけでなく周囲の人にも不安を与える結果につながることを押さえておきましょう。
公務員の懲戒処分に関するよくある質問

懲戒処分は、公務員としての信頼や立場を大きく左右する制度です。
これから公務員を目指す就活生にとっては、「どのような行為が処分対象になるのか」「処分されるとどうなるのか」など、不安や疑問も多いはず。
ここでは、特に知っておきたい5つのポイントについて、わかりやすく解説します。
- 処分の手続きはどう進むか
- 処分に時効はあるのか
- 退職金や年金はどうなるか
- 氏名は公表されるのか
- 分限処分との違いは何か
①処分の手続きはどう進むか
懲戒処分は、上司の主観やその場の感情で決まるようなものではありません。必ず一定の手続きを経たうえで、公正かつ慎重に判断されます。
まず、問題行動が明らかになると、組織は調査を開始します。ここで行われるのは、証拠の収集や関係者への聞き取り、そして当該職員本人からの事情聴取です。
その後、懲戒審査委員会などの第三者的な機関によって処分内容が検討され、最終的には任命権者が正式に決定します。弁明の機会が設けられることもあり、本人の主張も一定程度考慮されます。
このように、処分には透明性と正当性を保つためのプロセスが整備されているのです。
②処分に時効はあるのか
「何年も前のことならもう問題にならないのでは?」と考えるかもしれませんが、懲戒処分にも法律上の時効があります。
原則として、不正行為や違反が行われてから3年以内に処分を下す必要があります。しかし、行為の性質や発覚の経緯によっては、例外的に時効が伸びる場合も。
たとえば、背任や横領などの悪質なケースで長期間発覚しなかった場合、第三者からの通報により後から問題が明らかになった場合などは、処分対象となる可能性があります。
このように、公務員の不正行為がうやむやにされることはなく、組織は常に信頼性を保とうとしているのです。
③退職金や年金はどうなるか
懲戒処分が将来的な金銭面にどう影響するのかも、公務員志望者にとっては見逃せないポイントです。とくに「免職」処分を受けた場合には、退職金の全額、あるいは一部が支給されないことがあります。
また、退職時期や処分理由によっては、年金の受給資格や受給額にも影響を及ぼすケースも考えられます。
一方で、「減給」「停職」といった比較的軽い処分では、退職金や年金に直接的な影響はないのが一般的。
ただし、懲戒歴が記録として残ること自体が、将来の異動や昇任において不利になることもあるので、注意が必要です。
④氏名は公表されるのか
懲戒処分を受けた場合、「自分の名前がニュースや公報に載るのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。
実際、処分の内容や社会的影響度によって、氏名が公表されるケースとされないケースがあります。
たとえば、公金の横領やセクハラ・パワハラなど、社会的に大きな問題となる行為では、処分内容とともに氏名も発表される可能性が高いです。
一方、軽微な違反行為である場合や、個人情報保護の観点から公表を控えるケースも。
公務員は公共の信頼のもとに職務を行うため、その信頼を著しく損なう行為には、厳しい対応が取られるのが基本なのです。
⑤分限処分との違いは何か
「懲戒処分」と混同されやすいのが「分限処分」です。どちらも職員に対して下される措置ですが、性質はまったく異なります。
懲戒処分は、法律違反や非違行為といった、本人の行動による問題に対する制裁措置です。
これに対して分限処分は、本人に過失がない場合、たとえば病気や精神的な理由で業務に支障が出た際に行われる人事措置。
内容としては、降任や免職、休職などがあり、あくまで職務遂行の可否を基準としています。
公務員の懲戒処分を正しく理解し、慎重に対応しよう

公務員の懲戒処分は、信頼と公正を保つために必要な制度です。戒告・減給・停職・免職の4種類があり、それぞれの重さに応じて適用されます。
処分の対象となる行為には、法令違反や職務義務違反、非行や公務外での不祥事などが含まれ、処分の基準や判断方法も人事院の指針に基づき慎重に決められています。
処分歴の影響や情報公開のリスクなど、知られにくい注意点も多くあります。だからこそ、公務員本人も正しい知識を持ち、軽微な違反でも処分対象となり得るという意識を持つことが重要です。
公務員としての信頼を守るためには、懲戒処分に関する制度を正しく理解し、誤解や再発を防ぐ行動を心がけることが大切です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










