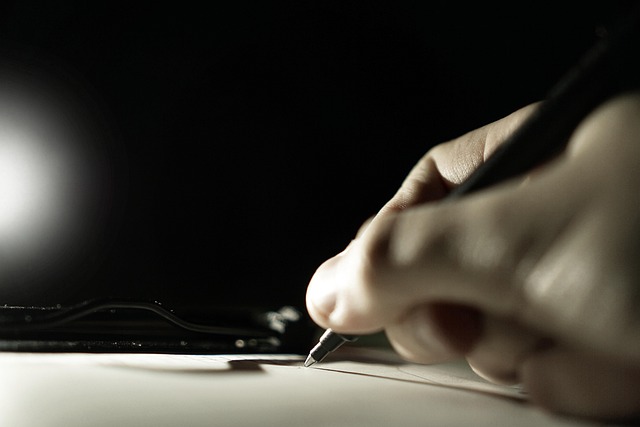履歴書の年号の書き方と西暦・和暦の使い分け完全ガイド
「履歴書に年号を書くとき、西暦と和暦、どっちを使えばいいの?」
そんな疑問を持ったまま、何となくで書き進めていませんか?履歴書は、就活における第一印象を決める大切な書類です。年号の書き方ひとつで、印象が変わってしまうことも。
そこで本記事では、履歴書の年号の書き方をテーマに、西暦と和暦の使い分けのルールや統一すべき理由、正しい記入方法まで、具体例を交えて詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書の年号は西暦と和暦どちらが正しい?
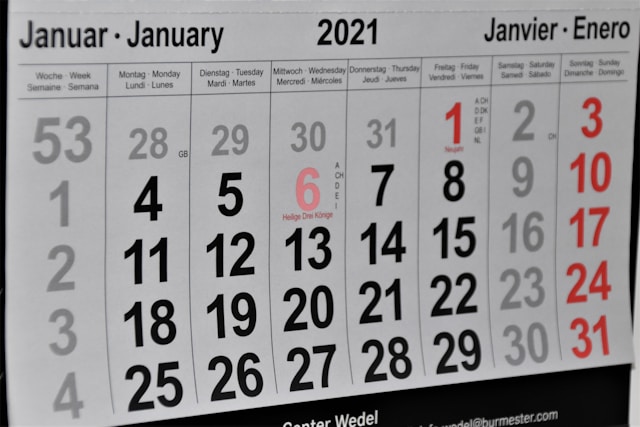
履歴書を作るとき、「年号は西暦と和暦のどちらが正解なのか」と迷う就活生は多いです。
結論としては、西暦・和暦のどちらでも問題ありません。
ただし、履歴書全体で表記をそろえましょう。たとえば、学歴欄が和暦で、資格欄が西暦になっていると、読み手に「この人は細かい点まで気を配れないのか」という印象を与えかねません。
最近では企業のデジタル対応も進んでおり、西暦での記載を推奨するケースも増えています。
どちらを選ぶにしても、履歴書内ですべて同じ年号表記にそろえることが大切です。その一貫性が、相手に誠実さと信頼感を伝えるポイントとなるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
履歴書の年号を統一するべき理由とは?

履歴書を作成する際、西暦と和暦のどちらを使うかだけでなく、「表記を統一しているかどうか」も大切なポイントです。
ここでは、年号を統一すべき理由を5つに分けて紹介します。
- 履歴書全体が見やすくなるため
- 書類内の表記ゆれを防ぎ、信頼性が高まるため
- 採用担当者にマイナスの印象を与えないため
- テンプレートの一貫した活用が可能になるため
- 年号統一をルールとしている企業があるため
①履歴書全体が見やすくなるため
年号を統一することで、書類全体の構成が整い、読みやすくなるためです。
たとえば、学歴は和暦、職歴は西暦のように混在していると、読み手にとって理解しづらく、視線の流れもスムーズではなくなることも。
応募者にとっては小さな違いでも、採用担当者は多くの履歴書に目を通しており、見やすさは評価の一部です。
年号が統一されていることで、時系列の流れも把握しやすく、丁寧な印象を与えることができます。こうした配慮は、好印象を与える大切な要素です。
②書類内の表記ゆれを防ぎ、信頼性が高まるため
履歴書の中で西暦と和暦が混ざっていると、内容に間違いがなくても「これは正しい情報なのか?」という疑念を抱かれることがあります。
たとえば「2019年卒業」と「令和元年入社」が並んでいれば、読み手によっては不自然さや混乱を感じるかもしれません。
そうした些細な違いが、不注意や雑な印象につながる可能性があります。反対に、一貫性のある記載は、細部にまで目を配る誠実さや丁寧さを伝え、信頼感を高めることができるのです。
③採用担当者にマイナスの印象を与えないため
どんなに内容がしっかりしていても、基本的な形式が整っていなければ評価を下げる要因になります。年号の統一は、書類作成における注意力や意識の高さを測るひとつの指標です。
履歴書は第一印象を左右する大切な書類です。もし年号が混在していれば、「細かい点にまで気を配れない人」と見られるリスクもあります。
内容だけでなく形式面でもきちんと整えておくことで、評価を高めることが可能です。小さな差が、選考結果に大きく影響することを意識しましょう。
④テンプレートの一貫した活用が可能になるため
複数の企業に同じ履歴書を提出する場面では、テンプレートを使いまわすことも一般的です。
その際、あらかじめ西暦または和暦のどちらかに統一しておけば、内容を更新するときにも手間がかかりません。
たとえば学歴の一部だけ修正する場合でも、他の項目との整合性を気にせずに済みます。逆に、表記がバラバラだと、修正のたびに他の箇所まで見直す必要が出てきてしまいます。
最初から統一しておくことで、完成度の高い履歴書をよりスムーズに作成できるのです。
⑤年号統一をルールとしている企業があるため
「西暦で統一すること」や「和暦で記載してください」といった指示が応募要項に明記されていることも少なくありません。
企業や官公庁の中には、履歴書の記載形式について具体的な指定を設けているケースもあります。こうした指定が守られていない場合、形式上の不備として書類選考から外される可能性もあります。
たとえ明示的な指示がなくても、年号の統一は、基本でありながら、選考結果を左右しかねない重要なポイントです。
履歴書における西暦・和暦の書き方の基本ルール

履歴書に年号を記入するとき、「西暦と和暦のどちらを使えばよいのか」「正しい形式はあるのか」と迷う方も多いでしょう。
ここでは、正確かつ見やすい年号記入のために意識すべき基本ルールを4つ紹介します。
- 西暦は算用数字で記載する
- 和暦は「元年」を正しく使う
- 和暦は略称や記号を使用せず正式に記入する
- どちらも年・月・日は省略せずすべて記載する
①西暦は算用数字で記載する
履歴書に西暦で年号を記載する際は、「2025年」「2024年4月1日」など、アラビア数字を使うのが基本です。
漢数字で「二〇二五年」などと書いてしまうと、視認性が大きく下がり、採用担当者が読みづらさを感じる可能性があります。
特に、手書きの場合は細かい字が判別しづらくなるため、読み間違いや誤解を招くリスクもあるでしょう。
また、統一された表記で全体の見た目を整えることで書類の完成度を高め、丁寧な印象を相手に与えることができます。
西暦を使う場合は、シンプルかつ正確に伝わるよう、算用数字で統一するようにしましょう。
②和暦は「元年」を正しく使う
和暦を使う場合、元号が切り替わった最初の年は「1年」と表記するのではなく、「元年」と書くのが正しいルールです。
たとえば、平成から令和に変わった2019年は「令和元年」であり、「令和1年」は誤った書き方になります。
このようなルールは、学校や企業などでも一般的なマナーとされており、社会人としての基本的な知識のひとつです。
見落としがちなポイントですが、細部にまで注意を払えるかどうかは、採用担当者にとっての評価にもつながるでしょう。
③和暦は略称や記号を使用せず正式に記入する
履歴書に和暦を使うときは、「令和元年」「平成30年」など、正式な表記で記入するのが原則です。「R1」「H30」といった略語や、「〃」などの記号を使うのは避けてください。
ビジネス文書では、正確さと読みやすさが求められるため、略記は不適切と判断される場合があります。
読み手に正しく伝わらない恐れがあるだけでなく、マナーや意識が足りないと見なされることもあるでしょう。
特に履歴書は、自分をアピールする大切な書類です。少しの手間を惜しまず、正式な形式で丁寧に記入することで、誠実さや信頼感を伝えやすくなります。
④どちらも年・月・日は省略せずすべて記載する
履歴書には「2023年」「令和5年」など年だけを記入するのではなく、「2023年4月1日」「令和5年4月1日」のように、年・月・日すべてを正確に書くのが基本です。
特定の月日が省略されていると、採用担当者がその情報をどう判断すべきか迷ってしまい、誤解やミスにつながる可能性があるかもしれません。
特に、入学・卒業、資格取得などの日時は、選考や書類確認に関わる重要な情報となるため、日付までの記載が求められます。
年月日の明記は、事実の裏付けとしての役割も果たし、応募者の誠実さを表現する方法のひとつといえるでしょう。小さな点にも気を配り、信頼される履歴書作成を意識してください。
西暦・和暦を間違えないための早見表

履歴書に年号を書くときに意外と多いのが、「和暦と西暦を間違える」ミスです。特に、元号が変わった直後の年度や、自分が学生だった年の正確な元号があいまいな場合は、誤記につながることも。
ここでは、よく使われる年を中心に、西暦と対応する和暦をまとめた早見表を紹介します。
履歴書に年号を記載する際、西暦と和暦の変換を手作業で行うとミスが起きやすくなります。特に、年号の切り替わりにあたる2019年は、「平成31年」なのか「令和元年」なのか迷う人も少なくありません。
さらに、自分が中学・高校・大学に入学・卒業した年、資格試験に合格した年などは、あらかじめ早見表を見ながらメモしておくと、履歴書の作成がスムーズになるのでおすすめです。
<西暦・和暦 早見表(主な履歴書使用年)>
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1989年 | 平成元年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2019年(4月まで) | 平成31年 |
| 2019年(5月〜) | 令和元年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
※記載内容は履歴書でよく使われる年代に絞っています。
履歴書の年号を書くときのポイント

履歴書を丁寧に仕上げるには、年号の書き方にも細かな注意が必要です。ちょっとしたミスや統一されていない表記が、採用担当者にマイナスの印象を与えることもあるでしょう。
ここでは、特に気をつけたい4つのポイントを紹介します。
- 「〃」(繰り返し記号)の使用は避ける
- 企業から指定があれば必ず従う
- 年号の前後に空白を入れずに書く
- 記入後は誤りがないか必ず見直す
①「〃」(繰り返し記号)の使用は避ける
履歴書では、同じ元号が続いたとしても「〃」という繰り返し記号の使用は避けるべきです。たとえば「平成30年」「〃31年」と書いてしまうと、略しすぎていてフォーマルな印象が損なわれます。
ビジネス文書である履歴書にはふさわしくない表現とされるため、手間を省こうとせず、毎回正式に「平成31年」と記載しましょう。
たとえ手書きであっても、省略せずにきちんと書く姿勢が大切です。読み手に丁寧さや誠意を伝えるためにも、細かい部分で手を抜かないことが好印象につながります。
②企業から指定があれば必ず従う
企業の中には、履歴書に記載する年号の形式について「西暦で統一」「和暦指定」などの明確なルールを設けている場合があります。こうした記載ルールの指示がある場合には、必ずその内容に従ってください。
もし無視して提出すると、応募要項の確認不足とみなされる可能性もあり、注意力や誠実さを疑われてしまうかもしれません。
企業ごとのフォーマットや指定があるかどうかは、事前に募集要項や公式サイトをしっかりと確認することが大切です。
細かなルールまで配慮できるかどうかが、社会人としての資質を見られるポイントにもなります。
③年号の前後に空白を入れずに書く
「2023 年 4 月」や「令和 5 年 4 月」といったように、年号や月日のあいだに空白を入れるのは誤りです。
正式な表記は「2023年4月」「令和5年4月」のように、スペースを入れずに続けて記載する形です。
特にパソコンで履歴書を作成する場合、フォントや入力ソフトの仕様によって自動的に空白が挿入されてしまうケースがあるため、入力後に必ずチェックするようにしましょう。
わずかな空白でも、書式として不自然に映ることがあり、文書の統一感を損ねてしまいます。細部にこだわる姿勢が、結果として読みやすさや信頼感の向上にもつながるでしょう。
④記入後は誤りがないか必ず見直す
履歴書を完成させたら、必ず最後に全体を丁寧に見直しましょう。特に年号の誤記や表記の混在は、意外とよくあるミスです。
たとえば2019年のように元号が切り替わった年には、「平成31年」と「令和元年」のどちらを使うか混乱しやすく、誤って両方の表記が混在することもあります。
また、書類内で和暦と西暦が混ざっていないかも重要な確認ポイントです。こうしたミスがあると、書類全体の信頼性が下がってしまいかねません。
提出前に一度冷静に全体を見渡し、誤りや不統一がないかを確認することで、安心して書類を提出できるでしょう。
英語での年号の書き方(アルファベット表記)

英語圏では、日付は通常「April 1, 2023」や「Apr 1, 2023」のように、月・日・年の順で記載するのが一般的です。
和暦(例:令和・平成など)は日本国内でのみ通用する形式であり、英語圏の相手にとっては意味が伝わらない可能性があります。
そのため、英語の履歴書では必ず西暦に変換して記載するのが基本です。たとえば、「令和5年4月1日」は「April 1, 2023」と表現するのが適切でしょう。
さらに、日付を記載する際には月と日の間にカンマ(,)を入れるのが英語圏での基本的な形式となります。「April 1, 2023」や「Aug 15, 2022」といった形にしましょう。
読み手に誤解を与えないよう、わかりやすく正しい表記を心がけることが大切です。日付ひとつの書き方にも注意を払うことで、英語履歴書全体の完成度や信頼感を高めることにつながります。
縦書き履歴書での年号の書き方
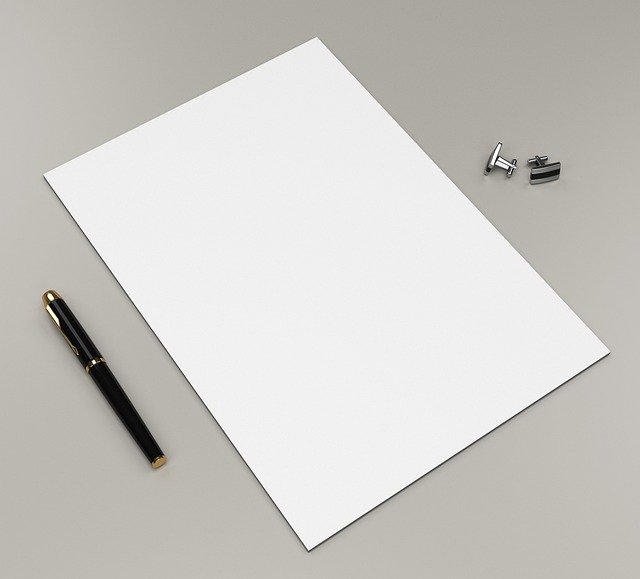
縦書きの履歴書においても、年号の記載ルールは基本的に横書きと変わりません。
ただ、縦書きでは、文字の配置やバランスが履歴書全体の印象を左右するため、見た目の整った表記を意識することが大切です。
一般的には、「二〇二四年」など漢数字での表記の方が、縦書きの形式にはしっくりなじみやすく、視覚的にも自然です。
ただし、アラビア数字(算用数字)で「2024年」と記載しても問題はありません。重要なのは、履歴書全体で年号の表記が統一されており、読み手が違和感なく読み進められるかどうかです。
手書きで作成する場合も、文字の大きさや間隔に注意しながら、整った印象を保つよう心がけましょう。
履歴書に年号を書くときの注意点

履歴書に記載する年号には、見落としがちな注意点があります。元号の切り替えや記載形式の統一に気をつけないと、書類の印象を損ねることになりかねません。
ここでは、見落としがちな注意点について4つ解説します。
- 元号の切り替え時期を正確に把握する
- 手書きの場合は数字が判読できるよう丁寧に書く
- パソコンで作成する場合は和暦・西暦の変換ミスに気をつける
- 自己判断で「平成→令和」などに書き換えないようにする
①元号の切り替え時期を正確に把握する
履歴書に和暦で年号を記載する場合、元号の切り替え時期を正確に把握しておくことが欠かせません。たとえば、平成から令和への変更は2019年5月1日に実施されました。
この日付を境に、それ以前の出来事は「平成」、それ以降は「令和」で記入する必要があります。たとえば2019年3月の卒業は「平成31年3月」、同年6月の入社は「令和元年6月」が表記として正解です。
元号の使い分けを誤ると、事実と異なる情報を記載してしまうリスクがあります。あいまいな記憶に頼るのではなく、卒業証書や資格証明書、交付書類などで正確な年月日を確認しましょう。
記載ミスを防ぐためにも、事前の調査と丁寧な確認を習慣にすることが大切です。
②手書きの場合は数字が判読できるよう丁寧に書く
手書きの履歴書では、文字の美しさよりも「読みやすさ」が何より重要です。特に年号や日付などの数字は、判読しづらいと大きなマイナス評価につながるおそれがあります。
たとえば「1」と「7」、「0」と「6」など、似た形の数字は崩して書くと混同されやすいため注意が必要です。
採用担当者は多くの履歴書を短時間でチェックするため、見づらい文字はそれだけで印象を損ねる要因になることも。
また、筆圧が弱すぎたり、斜めに傾いたりすると、読みづらさが増してしまいます。数字はできるだけ大きめに、はっきりと記入することを意識してください。
③パソコンで作成する場合は和暦・西暦の変換ミスに気をつける
パソコンで履歴書を作成するときは、変換ミスに特に注意を払う必要があります。
和暦から西暦、またはその逆に変換する際に間違えてしまうと、年号がずれて内容に不整合が生じる可能性があるでしょう。
たとえば「令和4年」は「2022年」に該当しますが、誤って「2021年」や「2023年」と記載してしまうと、学歴や職歴とつじつまが合わなくなってしまいます。
さらに、以前作成した履歴書データをコピーして使い回す場合、年号が古いままになっていることもあるでしょう。
そのまま提出すると、注意力が足りない印象を与えかねません。完成後は必ず全体を見直し、日付の正確さと表記の統一性に問題がないかを確認することが大切です。
④自己判断で「平成→令和」などに書き換えないようにする
履歴書に記載する年号は、記載対象となる事実の当時に使われていた元号を正しく使用する必要があります。
たとえば、資格証明書や卒業証書に「平成30年」と記されている場合、それを現代の元号に合わせて「令和元年」などと自己判断で書き換えることは避けてください。
証明書と履歴書の表記が一致しないと、採用担当者にとっては「事実関係に誤りがあるのでは?」と疑念を抱かせてしまいます。
信頼性を損なうリスクを減らすためにも、書類に記された年号はそのまま使用し、履歴書と整合性を持たせることが基本です。
記入内容に自信がない場合は、原本を確認するか、提出前に再チェックする習慣を持ちましょう。正確さが評価されるポイントになります。
履歴書に記載する資格取得日の年号が不明な場合の対応方法

資格取得日を記載する際に、年号が思い出せないことは珍しくありません。しかし、情報を正確に記入することが履歴書では求められます。できるだけ正確に確認するようにしましょう。
ここでは、資格取得日の年号が不明な場合の対処法を紹介します。
- 交付書類を確認して年号を把握する
- 取得年月が分かるメールや受験記録を探す
- 履歴や学歴と照らし合わせて時期を推定する
- インターネットで合格発表日や試験日を調べる
- 団体や協会に問い合わせて取得日を確認する
- どうしても不明な場合は「取得見込み」と記載する
①交付書類を確認して年号を把握する
もっとも確実で信頼性の高い確認方法は、合格証書や認定通知などの交付書類を確認することです。
多くの資格では、これらの書類に発行日が明記されており、そこから正確な年月日を知ることができます。
原本が手元にない場合でも、自宅や実家の保管場所を再確認する、または発行元に再発行の可否を問い合わせてみると良いでしょう。
正式な証明書を参照することで、履歴書全体の信頼度も高まります。
②取得年月が分かるメールや受験記録を探す
メールやマイページに残された受験関連の記録も、有力な手がかりになります。
最近は、多くの資格試験がWeb経由で申し込み・受験されるため、試験前後に届いたメールや合格通知が記録として残っている可能性があるでしょう。
Gmailなどのメールサービスでは、キーワード検索で過去のメールも簡単に探せるので、「資格名」「合格通知」「受験票」などで検索してみてください。
また、CBT方式などの試験ではマイページにログインすれば履歴が確認できることもあります。手がかりは意外なところに残っているかもしれません。
③履歴や学歴と照らし合わせて時期を推定する
過去の履歴や学歴と資格取得の時期を照らし合わせることで、おおよその取得年月を推測できます。
たとえば「大学3年の夏に受験した」「インターン前に取った」などの記憶がある場合、在籍していた学校の学年スケジュールやカレンダーを参照すると、ある程度の期間を特定できるでしょう。
完璧な日付でなくても、根拠を持って記載された年月であれば問題になることは少ないです。推定に頼る場合でも、できる限り合理的な説明がつけられるようにしておきましょう。
④インターネットで合格発表日や試験日を調べる
公式サイトや受験情報サイトなど、インターネットには過去の試験日や合格発表日の情報が多く掲載されています。
「資格名+年度+合格発表」「試験日」などのキーワードで検索すると、過去の試験スケジュールを掲載しているページが見つかることが多いです。
特に人気資格の場合、SNSや受験ブログでも記録が残っている可能性があります。こうした情報を参考にして、受験から合格までの流れを思い出すことで、取得年月の精度を高められるでしょう。
⑤団体や協会に問い合わせて取得日を確認する
資格を発行・管理している団体や協会に直接問い合わせるのも有効な手段です。
その際、登録番号や氏名、生年月日などの本人確認情報が求められることがありますが、正確な取得年月を確認するためには必要な手続きです。
団体によっては再発行や証明書の発行に対応していることもあるので、問い合わせ前に公式サイトのFAQなどを確認しておくとスムーズでしょう。
曖昧な記憶よりも、正式な情報を得ることが何よりも重要です。
⑥どうしても不明な場合は「取得見込み」と記載する
複数の手段を試しても取得年月が判明しない場合は、「取得見込み」や「〇年〇月受験予定」といった表記で対応することが可能です。
記憶に頼った曖昧な情報を記載するよりも、正直に現状を伝えるほうが信頼につながります。
すでに受験済みで合格待ちの段階であれば、「取得見込み」として記入し、面接時に補足説明を用意しておくと安心です。
採用担当者も状況を把握しやすく、誠実な対応として受け取ってもらえる可能性が高いでしょう。
履歴書の年号の書き方でよくある質問とその回答

履歴書の年号を記入する際は、「どの表記が正しいのか」「誤っていたらどうしよう」といった不安を感じる人が多いかもしれません。
特に和暦と西暦の選択や、元号が切り替わる年の扱いには注意が必要です。ここでは、実際によく寄せられる質問と、その具体的な対応方法を分かりやすく解説します。
- 「平成31年」と「令和元年」、どちらを使えば良い?
- 履歴書のテンプレートによって年号の書き方は変えるべき?
- 卒業見込みの年号はどう書くのが正解?
- 年号を書き間違えたら修正ペンを使っても大丈夫?
- 留学期間の年号は現地の表記を使っても問題ない?
①「平成31年」と「令和元年」、どちらを使えば良い?
「平成31年」と「令和元年」は、どちらも2019年を指しますが、履歴書に記載する際は統一感されていることが重要です。
たとえば、和暦で記入する場合は「令和元年」と記載することで問題ありません。
ただし、「平成31年」と「令和元年」を同じ書類内で混在させてしまうと読みづらくなり、採用担当者に混乱を与えるおそれがあります。
履歴書全体で同じ元号体系を使い、見やすさと丁寧さを意識した表記を心がけましょう。迷ったときは、使用するテンプレートに合わせて記載するのも一つの方法です。
②履歴書のテンプレートによって年号の書き方は変えるべき?
使用する履歴書のテンプレートに西暦や和暦の記載形式があらかじめ印刷されている場合は、その形式に従って統一することが自然です。
「令和〇年」と印字されているテンプレートなら、すべて和暦に揃えることで違和感のない書類になります。一方で、「20XX年」と表記されている場合は西暦に統一するのが無難です。
テンプレートの表記とズレていると、雑な印象を与える可能性があるため注意しましょう。統一感を重視することが、履歴書全体の完成度を高めることにつながります。
③卒業見込みの年号はどう書くのが正解?
卒業見込みの表記には、「年月+卒業見込み」または「卒業予定」と記載するのが一般的です。
たとえば「2026年3月 卒業見込み」のように記載すれば、読み手にも分かりやすく伝わるでしょう。
まだ卒業していない状態でも、予定としてしっかり明記しましょう。企業側は採用スケジュールの調整にも関わるため、卒業見込みの時期を正確に伝えることは非常に重要です。
記載内容に変更があった場合には、選考の途中であっても速やかに修正・報告するようにしてください。
④年号を書き間違えたら修正ペンを使っても大丈夫?
履歴書は正式な応募書類のひとつであるため、修正ペンや修正テープの使用は避けるのがマナーとされています。
特に手書きの場合、修正した痕跡があると雑な印象を与えるだけでなく、「大切な書類を丁寧に扱えない人」と受け取られる可能性もあります。
万が一ミスに気づいた場合は、面倒でも新しい用紙に書き直すことが最善です。また、パソコンで作成する場合でも、印刷前の段階でミスを修正し、きちんと最終チェックを行うことが大切になります。
履歴書は第一印象を左右する書類なので、細部まで丁寧さを意識しましょう。
⑤留学期間の年号は現地の表記を使っても問題ない?
履歴書に留学期間を記載する際は、原則として和暦か西暦のどちらかに統一することが望ましいです。
現地の暦(たとえば中国暦、イスラム暦、またはタイの仏暦など)をそのまま使用すると、採用担当者が読み取れず混乱を招く可能性があります。
特に企業側が求めているのは、日本国内で通用する一般的な表記です。多くの場合、読みやすさと国際性の両方の観点から西暦を選ぶのが無難でしょう。
記載する際には、履歴書全体での統一感にも注意し、表記が混在しないよう気をつけてください。
履歴書における年号の正しい書き方とは

履歴書の年号は、西暦でも和暦でも問題はありませんが、どちらかに統一して記載することが重要です。
なぜなら、表記の統一によって見やすさや信頼性が向上し、企業側に良い印象を与えることができるから。
また、履歴書全体で「履歴書 年号 書き方」に沿った基本ルールを守ることは、細部に気を配れる人物であるという評価にもつながります。
年号の書き間違いや表記ゆれを防ぐには、早見表を活用し、記入後に丁寧に見直すことが大切です。
さらに、和暦では略称を避け「元年」を正しく記入し、資格取得日が不明な場合の対応法も知っておくと安心でしょう。適切な年号の書き方を押さえて、完成度の高い履歴書を作成してください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。