公務員は本当に安定?就職前に知るべき実態と注意点
「安定志向」の学生や転職希望者に人気のある公務員ですが、実際には「思っていたのと違った」と後悔する人も少なくありません。
そこでこの記事では、公務員と民間企業の違いや、公務員の“安定性”の裏に潜む注意点を徹底解説。後悔しない進路選びのために、公務員の実態を正しく理解しておきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員と民間企業の違いとは?

就活では、公務員と民間企業のどちらを選ぶか迷う方が多いでしょう。それぞれの特徴を知ることで、自分に合った進路を見つけやすくなります。
ここでは、「活動目的」「業務内容」「組織構造」「雇用制度」「昇進・評価制度」の5つの視点から違いを解説します。
- 活動目的
- 業務内容
- 組織構造
- 雇用制度
- 昇進・評価制度
① 活動目的
公務員と民間企業の最も基本的な違いは、活動の目的にあります。公務員は、国民全体の利益を考えながら、公共サービスを公平に提供することを最優先としています。
利益を上げることではなく、社会全体の安定や安全の維持が仕事の根幹です。
対して、民間企業の目的は営利活動です。商品やサービスを提供して売上を上げ、競争に勝つことが生存条件となります。
このような目的の違いから、働くうえでの価値観や仕事への姿勢も変わってきます。社会貢献を重視し、安定した環境で役割を果たしたい人には公務員が適しているでしょう。
② 業務内容
公務員の業務は、法令や規則に沿った行政運営が中心となっており、定型的な手続きをこなす場面が多くあります。
日常生活に密着した業務が数多く存在するため、人々の生活を支えるインフラとしての役割が大きく、正確性と中立性が求められます。
一方、民間企業の業務は非常に幅広く、業績の最大化が日常的な目標になります。また、変化への対応力も求められるのも特徴です。
公務員が制度を守る側であるのに対し、民間企業では変化を生み出す側になるため、その姿勢も大きく異なるといえるでしょう。
③ 組織構造
公務員組織は、上下関係が明確で階層的な縦割り構造が基本です。国や自治体の規模に応じて多くの部署が存在し、各部署には厳密な役割分担があります。
そのため、業務が横断的に連携する機会は少なく、業務内容も固定されやすい傾向にあります。意思決定には複数の承認プロセスを経る必要があり、調整に時間がかかることもあります。
一方、民間企業の組織は比較的柔軟で、社内プロジェクトやチーム単位での業務が盛んに行われます。意見が言いやすい環境や、新規事業に関われる機会は民間企業の魅力です。
この違いは、日々の働き方や人間関係、自己成長のスピードにも影響を与えます。ルールに沿って着実に職務を果たす安定感を求めるなら公務員が合うでしょう。
④ 雇用制度
雇用制度において、公務員の特徴はその安定性にあります。国や地方自治体に雇われる形となり、景気や業績に左右されにくい立場にあるため、リストラのリスクが非常に低いです。
また、産休・育休などの福利厚生も充実しており、長く安心して働き続けられる環境が整えられています。
一方、民間企業では、業績に応じて人事の見直しが行われることがあります。景気の悪化や事業の失敗により、希望しない異動や雇止めが起こる可能性もゼロではありません。
雇用の安定性を優先するのか、柔軟なキャリア形成を目指すのか、自身の価値観に応じて見極めることが重要です。
⑤ 昇進・評価制度
公務員の昇進は、原則として年功序列に基づいています。勤続年数や試験の合格など、一定の基準を満たすことで段階的に昇進していく仕組みです。
評価制度も透明性が高く、公平に運用されている反面、個人の努力や実績が即座に反映されるわけではありません。そのため、スピード感を求める人には物足りなさを感じることもあるでしょう。
一方、民間企業では、成果主義に基づいた評価制度を導入している企業が多数あります。実績を上げた人が若くして管理職になるケースもあり、能力や貢献が報酬や役職に直結します。
どちらの制度が自分に合っているかを判断するためには、将来的なキャリアビジョンと照らし合わせて考えることが大切です。
公務員の種類を把握しよう!

就職活動を進める中で「公務員=安定」と考える学生は多いでしょう。ただ、公務員とひと口に言っても、その種類や役割はさまざまです。
まずは国家公務員と地方公務員の違いを理解することが、自分に合った進路を見つける第一歩となります。ここでは、公務員の種類についてそれぞれ具体的に紹介します。
- 国家公務員
- 地方公務員
① 国家公務員
国家公務員は、日本全体の制度や政策の設計・運営に関わる仕事を担います。主な勤務先は内閣府や各省庁であり、国レベルの大規模な案件に携わる機会が多いです。
国家公務員には「総合職」と「一般職」があり、前者は政策立案や幹部候補としてのキャリアを進むことが想定され、後者は各機関での実務を担当します。
総合職は人事異動が頻繁にあり、短期間で異なる地域や業務を経験するケースもあります。
安定性だけでなく、自分がどのような働き方にやりがいを見いだすのかを見つめ直してから志望先を選んでください。
② 地方公務員
地方公務員は、地域の住民に対する行政サービスを提供する役割を持ちます。
都道府県庁や市役所、町村役場などが主な勤務先で、地域密着型の業務を担当します。
勤務地が基本的に特定地域に限定されているため、引っ越しや転勤のリスクが少ない点は大きなメリットです。
ただし、部署によっては業務量が多く、繁忙期には残業が発生することもあります。
また、数年ごとに異動があるため、たとえば教育課から建設課、福祉課へと全く異なる分野の業務に就くこともあり、その都度新しい知識を学ぶ柔軟性や順応力が求められるでしょう。
業務内容や職場環境を事前によく調べ、自分に合っているかどうかを見極めることが大切です。
公務員が安定していると言われる理由

公務員という職業が「安定」の代名詞として語られるのには、いくつかの具体的な理由があります。ここでは、公務員がなぜ安定していると考えられるのかを、要素ごとに分けて詳しく解説していきます。
就活生が気づきにくい視点も含めて紹介しますので、進路選択の参考にしてください。
- 解雇リスクが低く職業がなくならないから
- 給与やボーナスが安定しているから
- 福利厚生が手厚く安心して働けるから
- 社会的信用が高く住宅ローンなどに有利だから
- 年功序列で昇給・退職金も確保されているから
- 不況や景気変動に強く安定しているから
① 解雇リスクが低く職業がなくならないから
公務員が安定職といわれる最大の理由は、「解雇されにくい」という制度的な強さにあります。
民間企業では、業績悪化などによるリストラといったリスクが常に付きまとう一方で、公務員は法律や制度に守られており、重大な非違行為がない限り、簡単に解雇されることはありません。
また、教育、福祉、税務、法務など幅広い分野で業務が存在しており、それぞれに専門性が求められるため、長期的な雇用の安定が見込まれます。
将来的にも職を失うリスクが非常に少ない点は、公務員の大きな魅力といえるでしょう。
② 給与やボーナスが安定しているから
公務員の給与は「給与法」や「人事院勧告」に基づいて決められており、民間企業と違って経営者の裁量で変動することがありません。
年功序列をベースとした昇給体系があるため、長く勤務すれば徐々に収入が増えていきます。収入の見通しが立てやすいため、将来的なライフプランの設計にも役立ちます。
ただし、能力や成果によって急激に昇給する仕組みはなく、実力主義のキャリアを望む人には物足りなく感じる場合もあるでしょう。
それでも、安定した暮らしを求める人にとっては、給与の安定性は非常に大きな魅力です。
③ 福利厚生が手厚く安心して働けるから
公務員には、充実した福利厚生制度が整っており、安心して働き続けることができます。
健康保険や共済組合による医療給付、手厚い年金制度、住宅手当、扶養手当など、生活を支える仕組みが多岐にわたって存在しています。
このような制度は民間企業でも見られますが、企業ごとに差が大きく、制度があっても実際には取りにくい環境があるのが現実です。
それに対して公務員は、制度の内容だけでなく「活用しやすさ」でも優れており、ライフステージの変化に柔軟に対応しやすい環境が整っています。
④ 社会的信用が高く住宅ローンなどに有利だから
公務員は社会的に信用が高く、その地位は金融機関からも高く評価されています。
特に、住宅ローンや自動車ローンなどの各種融資において、公務員は安定した職業とみなされ、審査通過率が高い傾向にあります。
これは、雇用の継続性と収入の安定性が保証されている点が大きな理由です。実際に、公務員向けの優遇金利ローンや、頭金なしでも融資可能な商品を取り扱う銀行も多く存在します。
社会的信用を「借りやすさ」ではなく「将来の選択肢を広げる武器」として活用することが、長く安定した生活を築くポイントです。
⑤ 年功序列で昇給・退職金も確保されているから
公務員の昇給制度は、年功序列が基本となっており、勤続年数に応じて段階的に給料が上がっていきます。
若いうちは民間と比べて低く感じるかもしれませんが、30代後半から40代にかけて逆転するケースも多く、安定的に収入を伸ばしていける職種です。
一方で、成果や能力を問わず横並びで昇給する傾向があるため、スピード感や個人の成長を重視したい人にとっては、もどかしさを感じるかもしれません。
それでも、長期的な収入の安定と退職後の生活設計を重視する人には、非常に信頼性の高い仕組みといえるでしょう。
⑥ 不況や景気変動に強く安定しているから
公務員の業務は社会基盤に直結しており、景気や外部要因の影響を受けにくいという特徴があります。
これは、税金によって財源が確保されている点が大きな理由のひとつです。
民間企業が採用縮小やリストラを進めるなか、公務員試験の応募者数はむしろ増える傾向にあり、「安定した職業」としての信頼が改めて強く意識されたといえるでしょう。
ただし、安定性が高い分、業務の革新性やスピード感に欠ける面もあります。新しいことに挑戦したい人にとっては、やや物足りなさを感じる可能性もあるでしょう。
とはいえ、経済の波に左右されず安定的に働ける職業として、公務員は非常に優れた選択肢です。
公務員=一生安定とは限らない?安定性に潜む注意点

「公務員=安定」というイメージを持つ学生は多いですが、実際には注意すべきポイントも数多くあります。
給与や雇用の安定感は魅力的な一方で、職場環境や将来性において見逃されがちなリスクもあるため、就職先として選ぶ際には慎重な検討が必要です。
ここでは、公務員の安定性に潜む注意点について具体的に説明します。
- 残業時間に大きな差がある
- 異動が多く職場環境が変わりやすい
- 業務改善が進みにくい体制になっている
- 民間企業への転職が難しい傾向がある
- 一部の仕事がAI・デジタル化で代替される可能性がある
- 終身雇用が将来的に保証されない可能性がある
- 意思決定に時間がかかり柔軟な対応が難しい
- 職場内のコミュニケーションが制約されている
① 残業時間に大きな差がある
「公務員は毎日定時で帰れる」という印象を持つ人も多いかもしれませんが、実際は職種や時期によって大きく異なります。
たとえば、生活保護や子育て支援などの福祉部門、災害対応や税務、学校教育関連の部署では、繁忙期には連日遅くまでの対応が必要になることがあります。
その一方で、部署によっては比較的落ち着いており、残業がほとんどないというケースも存在します。
こうしたギャップがあるにもかかわらず、「公務員は働きやすい」とだけ考えて就職を決めてしまうと、配属後に理想との違いに悩まされてしまうかもしれません。
安定性の裏には部署ごとの業務負担の違いがあることを理解し、自分の希望や適性と照らし合わせて考えることが必要です。
② 異動が多く職場環境が変わりやすい
公務員は3~5年おきに定期的な異動があるのが基本です。この仕組みには、特定の人に権限や情報が集中するのを防ぐという狙いや、人材育成のために幅広い経験を積ませる意図があります。
ただし、希望していない分野や遠方の勤務地に配属されることもあるため、不満を感じる場合もあるでしょう。
異動があることで視野が広がるメリットがある一方で、自分のライフスタイルや価値観と合わなければ負担に感じることもあります。
異動制度の仕組みや頻度を正しく理解し、自分に合った働き方ができるのかを冷静に見極めることが大切です。
③ 業務改善が進みにくい体制になっている
民間企業では業務の効率化や改善が経営に直結するため、積極的に改革が進められる傾向がありますが、公務員の世界ではそのスピードが遅いと感じる人が多いようです。
これは、制度や予算の制約が厳しく、新しい取り組みを始めるにも多くの承認が必要になるからです。また、過去の事例を重視する傾向が強く、却下されることもあります。
こうした環境では、自分のアイデアを活かしにくいと感じたり、やりがいを感じにくくなったりする可能性があります。
公務員という職業にどのような働き方を期待しているかを整理し、「安定」の裏側にある組織の特性を知ったうえで選択することが必要です。
④ 民間企業への転職が難しい傾向がある
公務員として働いていて「やはり合わなかった」と感じた場合、民間企業への転職という選択肢を考える人もいますが、実際にはスムーズにいかないことも多くあります。
公務員の業務は専門性が高く、外部からその内容が見えにくいため、転職市場ではスキルや実績が伝わりにくいからです。
また、長年公務員として働いていると、民間企業特有のスピード感や成果主義の文化に順応しづらく、面接などでも柔軟性が足りないと見なされることがあります。
将来転職の可能性を考えているならば、民間でも通用するスキルやマインドセットを意識して働く必要がありますし、なぜ公務員を目指すのかという動機を今一度見直してみるべきでしょう。
⑤ 一部の仕事がAI・デジタル化で代替される可能性がある
行政のデジタル化はここ数年で急速に進んでおり、各自治体や官庁でもAIや自動化システムの導入が進められています。
住民票の発行、税務処理、窓口対応など、これまで人が対応していた業務の多くが、今後は機械に置き換わる可能性があります。
安定職とされてきた公務員であっても、時代の流れに取り残されれば、配置転換や役割の見直しが必要になるかもしれません。
こうした時代の変化に対応するには、自主的なスキルアップが求められます。変化を受け入れ、成長し続ける姿勢が、公務員としての安定を持続させる鍵となるでしょう。
⑥ 終身雇用が将来的に保証されない可能性がある
かつての日本では、公務員は終身雇用が守られる代表的な職業とされてきました。しかし、現在ではその前提が崩れつつあります。
少子高齢化や地方自治体の財政悪化などにより、非正規職員の割合が増え、正規職員の採用や昇進の枠も縮小傾向にあります。
国や自治体も経費削減のため、業務の外部委託や民間企業との連携を進めており、「公務員=安泰」という考え方は時代遅れになりつつあります。
このように、公務員であっても環境の変化にさらされることは避けられません。安定という言葉の意味を広くとらえ、変化に強い働き方を目指すことが求められます。
⑦ 意思決定に時間がかかり柔軟な対応が難しい
公務員の組織では、上からの承認がなければ物事を進められないという場面が多く、意思決定に時間がかかる傾向があります。
特に新しい取り組みや改善提案などは、関係部署との調整や合意が必要となり、結果として迅速な対応ができないことがあります。
また、何か問題が起きたときも、担当者レベルでは判断できず、上層部の判断を待たなければ動けないという状況が多いため、現場で柔軟な対応を求められると苦しい場面もあります。
物事を自分で決めて進めたいというタイプの人は、こうした体質を事前に理解しておくことが必要です。
⑧ 職場内のコミュニケーションが制約されている
公務員の職場では、業務上の情報に守秘義務があることが多く、業務に関する相談や提案が気軽にできない雰囲気がある場合もあります。
情報の取り扱いに慎重になるあまり、ちょっとした報告や雑談すら控える傾向もあるのが実情です。
一方で、真面目でコツコツと業務をこなすことを求められるため、黙々と作業に集中したい人には向いている場合もあります。
自分がどのような働き方に適性があるのかを見極め、コミュニケーションの在り方が自分に合っているかどうかも確認しておきましょう。
公務員になって後悔する人に見られるパターン

公務員は「安定した仕事」として注目されやすい職業ですが、実際には後悔している人もいます。思い描いていた働き方とのギャップや、制度面の厳しさがその要因となっていることも少なくありません。
ここでは、公務員になってから後悔しがちなケースを紹介します。
- 安定性だけを重視して入職した人
- 業務内容が希望とかけ離れていた人
- 公務員のルールや体制にストレスを感じる人
- 自分に合わない部署で長期間働いている人
① 安定性だけを重視して入職した人
「安定しているから」という理由だけで公務員を目指すと、働く意味や目的を見失ってしまうことがあります。
たしかに、公務員は雇用が安定していて、景気の影響を受けにくい職種です。収入面でも大きな波がないため、長く安心して働けるといった魅力があるでしょう。
安定性は大きな利点ですが、それがすべてではありません。自分自身の価値観やキャリアの方向性を見つめ直したうえで職業選択をすることが、後悔のない就職への第一歩です。
② 業務内容が希望とかけ離れていた人
公務員の仕事は幅広く、採用された後の配属先によって仕事内容が大きく異なります。
採用試験の段階では具体的な配属が分からないことも多く、「人と関わる仕事がしたい」と思っていても、実際には窓口業務ではなく資料作成や内部調整などのデスクワークが中心になる場合もあります。
また、自治体によっては部署の数が多く、異動サイクルも短いため、ようやく業務に慣れてきた頃に別の分野へ移ることもあるでしょう。
公務員の職域の広さや業務ローテーションの特徴を踏まえたうえで、希望とのバランスを見極めておくことが重要です。
③ 公務員のルールや体制にストレスを感じる人
公務員組織は、法律や条例に基づいた運営が原則であるため、民間企業よりもルールが厳格で手続きも煩雑になりがちです。
業務一つとっても、誰かの承認を得なければ進められない場面が多く、自分の裁量で動ける範囲は限られています。
加えて、年功序列や縦割りの文化が色濃く残っている職場も存在し、若手が自由に意見を発信するのが難しいと感じる人もいます。
事前に組織文化や業務の進め方を理解し、自分にとっての「働きやすさ」と照らし合わせておく必要があるでしょう。
④ 自分に合わない部署で長期間働いている人
希望とは異なる分野に配属され、そのまま長期間異動の機会がないと、仕事への不満が蓄積していきます。
公務員の人事異動は本人の希望よりも全体の人員配置を優先するため、必ずしも思いどおりに移動できるとは限りません。
そのため、苦手な業務や関心のない分野に長く関わり続けるケースもあります。
自身の適性や希望分野と向き合い、「どこでなら力を発揮できるか」を早い段階から考えておくと、後悔のリスクを減らすことができるでしょう。
安定志向の就活生が知っておきたい公務員ミスマッチ防止のチェックポイント
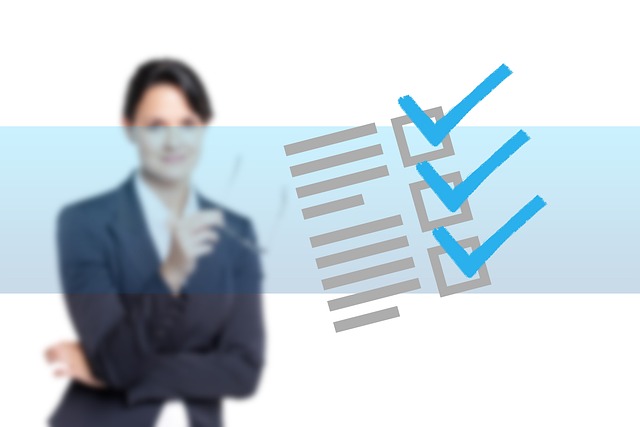
「安定しているから公務員を目指す」と考える就活生は多いでしょう。しかし、公務員は安定性ゆえにミスマッチが起こりやすい職業でもあります。
入職後に「思っていたのと違った」と後悔しないためには、自分の価値観や目的を丁寧に見直しておくことが欠かせません。
ここでは、自分に合っているかどうかを見極めるためのポイントを紹介します。
- 志望動機が安定性だけに偏っていないか?
- 公務員として実現したい目標が明確になっているか?
- 公務員の働き方・価値観が自分に合っているか?
- 民間との違いを理解した上で納得して選んでいるか?
- 困難な状況でも公務員としての責任を全うできるか?
① 志望動機が安定性だけに偏っていないか?
「安定しているから」という理由だけで公務員を志望していないでしょうか。
就活生にとって、経済的に安心感を得られる選択肢に映るのは自然なことかもしれませんが、安定性のみを目的に選んでしまうと、モチベーション維持が難しくなることがあります。
また、職場の人間関係や、社会的責任の重さに対して「想像と違った」と感じるケースもあります。
地域社会への貢献や公共サービスの質向上など、自分なりの目標を見つけておくことで、入職後も前向きに仕事へ取り組みやすくなるでしょう。
② 公務員として実現したい目標が明確になっているか?
公務員を目指すにあたって、自分が何を実現したいのかをはっきりさせておくことは非常に大切です。
目指す方向があいまいなまま採用試験を突破しても、配属先でミスマッチを感じることが多くなりがちです。さらに、公務員は異動の頻度も高く、長期的なキャリアを築く上でも方向性が重要です。
事前に自分が関心を持てる分野や地域課題を明確にしておくと、職場での学びや経験も意味あるものとして捉えられるでしょう。
漠然とした憧れではなく、「この業務で誰にどんな価値を届けたいか」という視点で考えてみてください。
③ 公務員の働き方・価値観が自分に合っているか?
公務員の働き方は、民間企業と比べて独特の特徴を持っています。その価値観が自分に合っているかどうかを理解しておかないと、就職後にギャップに苦しむ可能性があります。
小さな業務でも上司や関連部署と調整を図る必要があり、自分一人で判断を下すことができない場面が多いでしょう。
また、公務員の評価制度は年功序列や定型業務の正確性を重視するものが中心で、短期的な成果が評価される場面は限られています。
一方で、安定した環境で一歩ずつ成長し、社会全体に貢献することに価値を見いだせる人にとっては、非常に働きやすい環境です。
自分の性格や仕事への姿勢を見つめ直し、価値観がフィットするかを冷静に判断してください。
④ 民間との違いを理解した上で納得して選んでいるか?
民間企業と公務員の間には、キャリアの進め方や仕事の進行スピード、職場文化など多くの違いがあります。
民間では成果や実績に応じて昇進や評価が決まるケースが一般的です。一方、公務員は公平性を重んじるため、成果だけではなく経験年数や手続きの正確さなどが重視されます。
業務スピードにも違いがあります。民間では即断即決が求められる場面が多いのに対し、公務員では慎重な検討と合意形成が求められ、何事も時間をかけて進める傾向があります。
公務員には地域や住民と深く関わりながら、地道に社会課題を解決していくというやりがいもあります。条件だけで比較するのではなく、自分がどのような働き方に価値を感じるのかを基準に選択してみてください。
⑤ 困難な状況でも公務員としての責任を全うできるか?
公務員は平常時だけでなく、非常時にも責任ある立場での行動が求められます。
例えば、災害が発生した場合、多くの自治体職員は避難所の開設や情報提供に奔走することになります。さらに、休日出勤や長時間勤務が発生することもあり、体力的にも厳しい局面に直面します。
表向きは安定しているように見える公務員ですが、実際にはプレッシャーの大きい局面も多く、それを乗り越える覚悟が求められます。
だからこそ、安定性の裏にある責任と向き合えるかどうかを、自分に問いかけてみてください。
公務員という選択を後悔しないために知っておこう!

公務員は「安定」の象徴として多くの人に選ばれています。
実際に、解雇リスクの低さや給与の安定、手厚い福利厚生など、民間企業にはない魅力があるのは事実です。
しかし、安定性の裏には異動の多さや業務改善の停滞、民間転職の難しさなど、注意すべきポイントも存在します。
だからこそ、安定性だけを理由に選ぶのではなく、自分の価値観や働き方との相性をよく見極めることが大切です。
公務員の安定性を正しく理解し、自分にとって後悔のないキャリア選択をするためには、事前に多角的な視点から職業を検討することが成功の鍵となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














