【例文10選】履歴書で「得意な学科」を好印象に書く方法|企業の意図や注意点も紹介
「履歴書の『得意な学科』って、何を書けばいいの?」
明確な正解がないだけに、書き方に迷う人も多いこの項目。しかし、企業側は応募者の学習姿勢や業務との親和性を知るために、この欄を意外と重視しています。
本記事では、履歴書における「得意な学科」の選び方や正しい書き方をはじめ、志望職種別の具体的な例文や注意すべきポイントまで、わかりやすく解説します。
自分の強みがしっかり伝わるように、戦略的にアピールしましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書に得意な学科を書く理由とは?

履歴書の「得意な学科」欄に、何を書けばよいのか迷っていませんか?実はこの欄には、企業が知りたい「あなたらしさ」が表れます。
ここでは、企業がこの項目を通して何を見ているのかを、3つの観点からわかりやすく解説します。
- 就活生の個性や志向を知るため
- 学業への取り組み方や姿勢を評価するため
- 自己PRや志望動機との整合性を確認するため
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
① 就活生の個性や志向を知るため
得意な学科は、学生の興味や関心、ものの見方を知るためのヒントになります。たとえば経済学を選んでいれば、数字への理解や社会構造への関心がうかがえるでしょう。
このように、どの学科を選ぶかには、その人らしさが自然とにじみ出ます。だからこそ、何となく選ぶのではなく、なぜその学科に惹かれたのか、どんな点に面白さを感じたのかを言葉にしてみてください。
自分の個性や強みが伝わるように記載できれば、企業の印象にも残りやすくなります。
② 学業への取り組み方や姿勢を評価するため
企業が注目しているのは、成績そのものではありません。どのように課題に向き合ったのか、その姿勢を知りたがっています。
難しいテーマでもあきらめずに取り組んだ経験があれば、それは努力できる人だと評価されるでしょう。大切なのは、結果ではなくプロセスです。
たとえば、工夫して理解を深めた方法や、仲間と協力して課題を解決した経験などを具体的に伝えることで、学びに真剣に向き合う姿勢が伝わります。
③ 自己PRや志望動機との整合性を確認するため
履歴書に書かれている内容のつながりがしっかりしていると、企業側は納得感を持って読み進められます。得意な学科が自己PRや志望動機と結びついていれば、一貫性のある人物像が伝わるでしょう。
もし「心理学を学んで人の気持ちを考える力を養った」と書いているのなら、「その力を接客に活かしたい」という志望理由も自然に響きます。
無理にこじつける必要はありませんが、自分の経験の中に筋の通ったストーリーがないか、振り返ってみるとよいでしょう。
履歴書に得意な学科を重視する企業側の意図

履歴書の「得意な学科」欄は、単に成績の良し悪しを伝えるためのものではありません。企業はここから、あなたの考え方や人柄、仕事との相性などを多角的に判断しようとしています。
ここでは、企業がどんな視点でこの項目を見ているのかを3つのポイントに分けて解説します。
- 主体性や学習意欲を判断している
- 業務適性を見抜こうとしている
- 面接の会話を広げるネタとして活用している
① 主体性や学習意欲を判断している
企業は、得意な学科から学生の主体性や学びに対する姿勢を探ろうとしています。たとえば、なぜその学科が得意だと感じたのか、どんな努力を重ねてきたのかといった点が見られているのです。
中でも、自分でテーマを掘り下げた経験や、苦手を克服するための工夫があれば、それは行動力や向上心の証として伝わるでしょう。
結果よりも、そのプロセスにどんな思いや工夫があったのかを具体的に伝えてください。履歴書には、学科を通じて何を学び、どのように成長したかをわかりやすく書くことが大切です。
② 業務適性を見抜こうとしている
企業がこの欄を見るのは、「自社の仕事とマッチするかどうか」を確かめるためでもあります。学んだ内容が応募職種と関係していれば、業務への理解度や親和性が高いと評価されやすくなるでしょう。
たとえば、統計学を学んだ人であれば分析力やデータへの理解が強みとして活かせますし、心理学であれば対人対応や観察力のアピールにつながるはずです。
履歴書に書く際は、単に「得意だった」とするのではなく、その学びがどのように仕事に役立つかまで意識して記載してみてください。
③ 面接の会話を広げるネタとして活用している
履歴書に書いた内容は、面接での話題として取り上げられる可能性が高いです。面接官は「なぜその学科が得意なのか」「どんなことを学んだか」といった質問を通して、人柄や価値観を知ろうとします。
そのため、書いた内容があいまいだったり、深く答えられなかったりすると、印象が薄れるかもしれません。
一方で、学びの背景や具体的な経験をしっかり説明できれば、会話の流れの中で自然に自己PRや志望動機にもつなげられます。
履歴書には、ただ文字を埋めるのではなく、「会話のきっかけ」として活用される前提で書くとよいでしょう。
履歴書に書くべき得意な学科の選び方
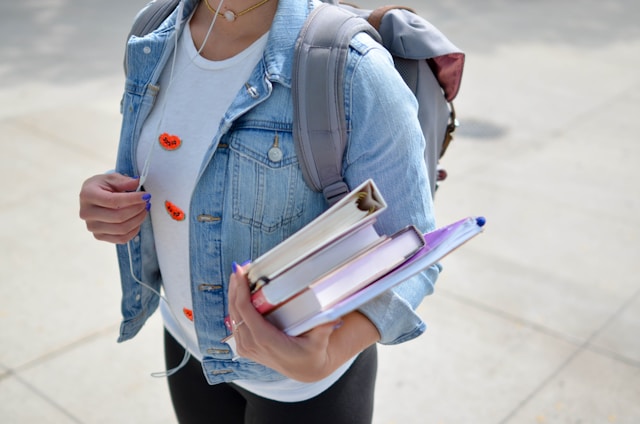
履歴書に得意な学科を書くとき、「どの学科を書けば印象がいいのか」と迷う人は多いかもしれません。
この欄は自由度が高い分、内容次第で評価が大きく変わります。
ここでは、企業に伝わりやすい学科の選び方を4つの視点で解説しましょう。
- 大学で学んだ専門分野を選ぶ
- 応募企業の業務と関連性がある学科を選ぶ
- 自己PRで話しやすい内容の学科を選ぶ
- 語学やITなど汎用性の高い学科を選ぶ
① 大学で学んだ専門分野を選ぶ
得意な学科には、自分が大学で力を入れて学んだ専門分野を選ぶのが基本です。しっかり取り組んだ経験があれば、自信を持って伝えられますし、継続力や興味の深さも評価されやすくなります。
たとえ一般的な学科名でも、「どの授業で何を学んだか」「どんな工夫をしたか」などを具体的に説明することで、自分らしさが伝わるでしょう。
学びを通じて得た気づきや成長を一言でまとめると、履歴書全体にも統一感が出ます。
② 応募企業の業務と関連性がある学科を選ぶ
学科選びの際には、応募先の企業や職種との関連性にも注目してください。たとえばマーケティング職を目指すなら経済学や統計学、システム開発なら情報処理など、業務に直結する学科は説得力があります。
完全に一致していなくても、「学びの一部が業務に通じる」と説明できれば十分です。履歴書を読む企業担当者も、実務に役立つ可能性があれば注目するため、できる限り接点を見つけてアピールしましょう。
③ 自己PRで話しやすい内容の学科を選ぶ
得意な学科は、面接で話題にされることが少なくありません。そのため、自分が話しやすい内容を選んでおくと安心です。
理解が浅い学科を無理に書くと、突っ込まれたときに困ってしまうおそれがあります。一方、実際に取り組んだ経験があれば、エピソードや工夫を自分の言葉で伝えられるでしょう。
面接で深掘りされたときのことも想定し、話を広げやすい学科を選んでください。
④ 語学やITなど汎用性の高い学科を選ぶ
語学や情報処理など、どの業界でも活かせるスキルがある学科は好印象を持たれやすいです。
たとえば英語を学んでいれば国際的な業務にも対応できると評価されますし、プログラミングの経験があれば論理的思考や実務力の証明にもなります。
直接志望職種に関係がなくても、「他の分野でも使える力」としてアピールできる点が強みです。履歴書では、そのスキルがどう役立つかまで丁寧に書くと、汎用性の高さがより伝わりやすくなります。
履歴書で「得意な学科」の好印象な書き方

履歴書に得意な学科を書くとき、ただ「〇〇が得意です」と書くだけでは魅力は伝わりません。企業が知りたいのは、その学びを通じてあなたが何を感じ、どう行動してきたのかという部分です。
ここでは、読み手に伝わる効果的な書き方を3つの視点で解説します。
- 冒頭で得意な学科を結論から述べる
- 学科に取り組んだ具体的な経験や成果を示す
- その学科の学びが志望職種でどう活きるかを明示する
① 冒頭で得意な学科を結論から述べる
まず最初に、自分が得意とする学科をはっきり伝えることが大切です。「私が得意な学科は〇〇です」とシンプルに書き出すだけで、読み手の理解が格段にスムーズになります。
導入がまわりくどいと内容が伝わりにくくなるため、結論を先に書くのが効果的です。そのうえで、なぜその学科が得意なのか、どんな経験があるのかを続けて説明すると説得力も増します。
まずは自信を持って、結論を明確に伝えてください。
② 学科に取り組んだ具体的な経験や成果を示す
得意な理由を伝えるには、実際の経験を具体的に書くことが大切です。
たとえば授業やゼミでの活動、レポートのテーマ、困難を乗り越えたエピソードなど、実体験を交えて説明しましょう。結果が数字で示せる場合は、客観性が加わりより信頼されやすくなります。
こうした情報を盛り込むことで、「好きだから得意」ではなく、「実績があるから得意」と伝えられるでしょう。読み手に納得してもらうには、できるだけ具体的に書くよう心がけてください。
③ その学科の学びが志望職種でどう活きるかを明示する
履歴書では、学びと仕事のつながりを意識して伝えることが重要です。
もし、心理学を学んだ人なら「相手の感情に寄り添う力」が接客業に活かせるでしょうし、経済学であれば「社会全体を見る視点」が企画職で役立つかもしれません。
こうしたつながりを自分なりの言葉で説明できると、企業も採用後の姿をイメージしやすくなります。
どんな小さなことでも構いませんので、仕事への応用可能性を具体的に伝えてみてください。
【学科×仕事内容】履歴書に書く得意な学科の例文集

どの学科を選べばよいか悩む就活生にとって、実際の例文は非常に参考になります。
学科の内容と仕事内容がどのように結びついているのかを明確に示すことで、説得力のある履歴書の書き方を学べるでしょう。
- 例文① 英語×営業職:国際的な取引への興味をアピール
- 例文② 心理学×販売職:顧客心理の理解を活かした提案力をアピール
- 例文③ 文学×サービス業:相手の意図を汲むコミュニケーション力をアピール
- 例文④ 統計学×マーケティング職:データ分析スキルをアピール
- 例文⑤ 生物学×研究職:探究心と継続力をアピール
- 例文⑥ 物理学×開発職:論理的思考力と応用力をアピール
- 例文⑦ 情報処理×エンジニア職:実践的な技術スキルをアピール
- 例文⑧ 経済学×コンサル職:問題解決力と全体視点をアピール
- 例文⑨ 看護学×医療職:現場対応力と責任感をアピール
- 例文⑩ 美術×デザイン職:独創性な考えと表現力をアピール
例文① 英語×営業職:国際的な取引への興味をアピール
海外とのやり取りに興味があることを、学んだ学科を通じて伝えたい方に向けた例文です。語学スキルと興味を自然に結びつけて、営業職との相性をアピールします。
《例文》
| 大学では英語学を専攻し、特にビジネス英語に力を入れて学んでいます。授業では英文メールの書き方や商談に関するフレーズを学び、実際に英語でのプレゼンを行う機会もありました。 2年次には英語ディベート大会に参加し、相手の意見を理解しながら論理的に伝える力が身につきました。 また、ゼミでは海外企業のマーケティング手法を調べる中で、国際的な視点を持って物事を考える力も養えたと思います。 英語という学科を通じて、言語だけでなく異文化理解の重要性や、相手に伝わる工夫の大切さを実感しました。 営業職では、このような学びを活かして、海外との円滑なコミュニケーションや信頼関係の構築に貢献したいと考えています。 |
《解説》
「英語=語学力」だけにとどまらず、異文化理解や論理的思考に触れた点が評価されやすいポイントです。具体的な活動や経験を挙げて、営業職との接点を意識して書きましょう。
例文② 心理学×販売職:顧客心理の理解を活かした提案力をアピール
販売職において重要な「相手の気持ちを読み取る力」や「信頼関係の構築力」を、心理学の学びからどう活かすかを伝える例文です。
《例文》
| 大学では心理学を専攻し、人の行動や思考の背景にある心理を学んでいます。特に消費者心理に関心があり、ゼミでは購買行動の傾向や売り場の演出による心理的効果について調べました。 学園祭の模擬店では、色彩や配置を工夫して商品を陳列したところ、例年よりも売上が伸びた経験があります。 このような実践を通じて、相手の立場になって考えることや、言葉にしにくい気持ちをくみ取る大切さを実感しました。 販売職では、心理学で得た知識と経験を活かし、お客様のニーズを的確に捉えた提案や、信頼関係の構築を大切にした接客を心がけたいと考えています。 |
《解説》
体験や気づきが明確な例文は、説得力が高まります。販売職との接点を意識しながら、「どんな力を活かせるか」を具体的に書くのがポイントです。
例文③ 文学×サービス業:相手の意図を汲むコミュニケーション力をアピール
サービス業では、お客様の気持ちに寄り添いながら対応する力が求められるでしょう。ここでは、文学の学びを通じて得た「相手の意図を読み取る力」を活かす例文を紹介します。
《例文》
| 大学では日本文学を専攻し、小説やエッセイを読み解く中で、登場人物の感情や背景にある意図を読み取る力を培ってきました。 読解の授業では、異なる解釈を持つクラスメイトとのディスカッションを通じて、相手の考えを尊重しつつ自分の意見を伝える力も身につけました。 学外活動ではカフェでのアルバイトを経験し、お客様のちょっとした表情や仕草からニーズを察して対応したところ、リピーターになっていただけたことが印象に残っています。 文学で磨いた観察力や気配りの姿勢を活かし、サービス業でも相手に寄り添った柔軟な対応ができる人材を目指したいと考えています。 |
《解説》
文学=読書ではなく、そこから得た“人を見る力”や“対話力”をどう仕事に応用できるかを伝えると好印象です。具体的な接客経験を交えると説得力が増します。
例文④ 統計学×マーケティング職:データ分析スキルをアピール
数字を扱うマーケティング職では、統計学の知識が大いに役立ちます。ここでは、大学での学びと実践を交えて、どのように分析力をアピールできるかを紹介します。
《例文》
| 大学では統計学を専攻し、データをもとに現象を読み解く力を養ってきました。 特にマーケティング統計の授業では、購買データの分析やアンケート結果の傾向を読み解く課題に取り組み、グラフや表を使って分かりやすく伝える力も磨けたと思います。 学園祭の実行委員では、来場者アンケートの集計と分析を担当し、前年との比較データから人気企画を抽出して改善に活かしました。 その結果、来場者数が前年比で約15%増加し、数字に基づいた提案が成果に結びつく喜びを実感しました。 統計学の学びを通じて得た分析力と実践力を、マーケティング職でも活かしたいと考えています。 |
《解説》
実体験を交えて、学びがどう成果につながったかを示すことで説得力が高まります。数値や比較を使うと、マーケティング職との親和性がより明確になるでしょう。
例文⑤ 生物学×研究職:探究心と継続力をアピール
研究職では、一つのテーマに対して粘り強く取り組む姿勢が求められます。ここでは、生物学を通して探究心と継続力をアピールする例文を紹介しています。
《例文》
| 大学では生物学を専攻し、微生物の増殖条件について研究してきました。きっかけは高校時代に読んだ科学雑誌で、菌の働きに興味を持ったことです。 大学では実験がうまくいかないことも多く、条件を変えて何度も試行錯誤を繰り返しました。その中で、問題点を細かく記録し、一つずつ検証して改善する姿勢が身についたと感じています。 3年次には研究発表の機会をいただき、自分の取り組みを言葉で伝える難しさと大切さも学びました。 これらの経験を通じて得た探究心と粘り強さを、研究職でも活かし、課題に対して根気強く向き合える人材になりたいと考えています。 |
《解説》
研究職においては「継続的な努力」や「課題解決力」の具体例が重要です。失敗や試行錯誤の経験を書くと、リアリティと誠実さが伝わります。
例文⑥ 物理学×開発職:論理的思考力と応用力をアピール
開発職では、筋道を立てて考える力や、理論を現実に応用する力が求められます。ここでは、物理学で得た論理的思考と応用力を活かした例文を紹介しましょう。
《例文》
| 大学では物理学を専攻し、身の回りの現象を理論的に理解する力を養っています。 中でも、エネルギー変換に関する実験では、理論と現実とのギャップを感じながらも、数式に頼るだけでなく、現象を多角的に観察し、実験条件を見直す工夫を重ねました。 サークル活動では、簡易的な太陽光発電装置を製作するプロジェクトに参加し、学んだ知識を実際に応用する面白さと難しさを体感しました。 物事を論理的に捉えつつ柔軟に対応する力を、開発職でも活かし、新しい技術や製品の実現に貢献したいと考えています。 |
《解説》
抽象的な学びにとどまらず、実験やプロジェクトを通じた“応用の経験”を入れると効果的です。開発職との結びつきを明確に意識しましょう。
例文⑦ 情報処理×エンジニア職:実践的な技術スキルをアピール
エンジニア職では、理論だけでなく「実際に手を動かして考える力」が重視されます。こちらは、情報処理を学んだ経験をベースに、技術スキルを活かす姿勢を伝える例文です。
《例文》
| 大学では情報処理を学び、プログラミングやシステム構築の基礎を身につけました。授業で学んだ内容を活かして、個人で簡単な家計簿アプリを作成したことがあります。 初めはエラーに悩むことも多く、試行錯誤の連続でしたが、ネットや書籍で調べながら改善を繰り返すうちに、自然と実装力と問題解決力が養われたと感じています。 また、学内のITサポートボランティアにも参加し、パソコン操作が苦手な学生や教員のサポートを通じて、伝える力や相手に合わせた対応力も学びました。 情報処理で得た知識と実践経験を活かし、エンジニア職でも柔軟に対応できる人材として貢献したいと考えています。 |
《解説》
技術力に加え「自分で動いた経験」をしっかり書くと説得力が高まります。作品制作やサポート経験など、アウトプットにつながる活動を入れるのがポイントです。
例文⑧ 経済学×コンサル職:問題解決力と全体視点をアピール
コンサル職では、課題の本質を見抜く力や全体像を意識した思考が求められます。ここでは、経済学の学びを通じて得た問題解決力をアピールする例文を紹介しています。
《例文》
| 大学では経済学を専攻し、マクロ・ミクロの視点から社会や企業の動きを学んでいます。ゼミでは「地方経済の活性化」をテーマに、過疎地域の課題分析と提案を行いました。 私は交通アクセスの不便さに着目し、現地ヒアリングを通じて住民の声を集め、データを基に改善策を考案しました。その結果、自治体主催のコンテストで優秀賞を受賞。 自分の考察が形になる経験に、やりがいを感じました。経済学を学ぶ中で、全体像を捉えつつ具体的な解決策を導く力が身についたと実感しています。 今後はコンサル職として、多角的な視点で課題に向き合い、的確な提案ができる人材を目指します。 |
《解説》
具体的な課題に対して「どう向き合ったか」を書くことで説得力が増します。提案・行動・結果の流れを意識すると、コンサル職との親和性が強調できるでしょう。
例文⑨ 看護学×医療職:現場対応力と責任感をアピール
医療職では、知識だけでなく「現場でどう動けるか」や「人を思いやる姿勢」が重視されます。ここでは、看護学の学びを通じて得た責任感と対応力を伝える例文を紹介しましょう。
《例文》
| 大学では看護学を専攻し、講義だけでなく実習を通して、医療現場の厳しさや責任の重さを実感しています。 初めての病院実習では、患者さんとの関わり方に戸惑う場面もありましたが、指導看護師の姿を見て、どんな状況でも落ち着いて対応する大切さを学びました。 患者さんの話に丁寧に耳を傾け、不安を和らげられたときに「ありがとう」と言っていただいた経験は、今でも忘れられません。 知識を使うだけでなく、人と向き合う姿勢を持ち続けることの重要性を学びました。今後は医療職として、目の前の方に安心感を与えられる存在になりたいと考えています。 |
《解説》
医療職では「人に寄り添う姿勢」と「落ち着いた対応力」がポイントです。実習での気づきや具体的なエピソードを盛り込むと、説得力が高まります。
例文⑩ 美術×デザイン職:独創性な考えと表現力をアピール
デザイン職では、自分の感性を活かしながら相手に伝わる表現をする力が求められるでしょう。ここでは、美術を学ぶ中で培った発想力と表現力を活かした例文を紹介します。
《例文》
| 大学では美術を専攻し、平面・立体の作品制作を通して表現力と構成力を磨いてきました。 課題では毎回テーマが与えられ、その解釈の幅が求められる中で、自分なりの視点や表現方法を模索することを大切にしてきました。 中でも印象に残っているのは、地域のカフェの壁面アートを手がけた経験です。依頼主との打ち合わせを重ね、コンセプトに合うデザインを提案し、実際の制作まで行いました。 完成後に「お店の雰囲気が明るくなった」と言っていただけたことが自信につながっています。美術で学んだ柔軟な発想と表現力を、デザイン職でも活かしていきたいです。 |
《解説》
感性だけでなく「実際に形にした経験」が入っていると効果的です。依頼対応や共同制作など、実践経験を交えて書くと説得力が増します。
履歴書に得意な学科を書くときの注意点
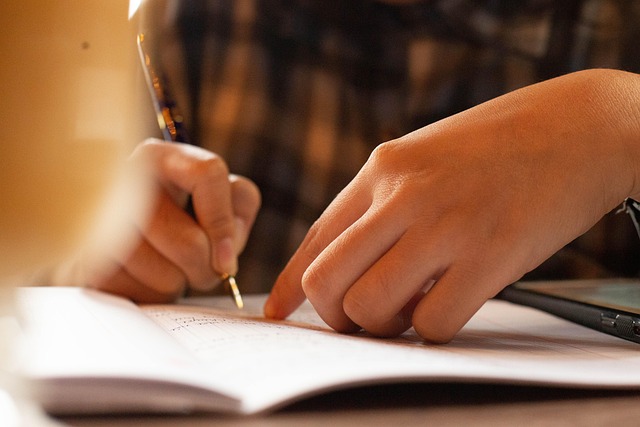
得意な学科を履歴書に書く際は、伝え方に注意しなければ逆効果になる恐れがあります。
読み手に誤解を与えたり、印象が薄くなったりするのを防ぐためにも、以下の4点には十分注意してください。
1.「特になし」と書かない
2.抽象的すぎる表現はしない
3.学科を羅列するだけにしない
4.深掘りされたときに答えられない学科は選ばない
①「特になし」と書かない
「特になし」と書いてしまうと、学業そのものに興味がなかったという印象を与えかねません。企業は学業への取り組みから、あなたの姿勢や価値観を見ています。
たとえ目立った成績を残していなかったとしても、関心を持って学んだテーマや授業があるはずです。そのなかで、特に熱意を持って取り組んだものや、印象に残っている経験を思い出してみましょう。
履歴書は、自分の人柄や学ぶ姿勢をアピールできる絶好の場です。簡単に済ませず、言葉を尽くして伝えることが大切です。
② 抽象的すぎる表現はしない
「人と関わるのが好きだから心理学が得意」などの表現では、何をどのように学んだのかが伝わりません。抽象的な理由だけでは説得力が薄く、読み手に印象を残すことも難しくなります。
たとえば「行動心理学の授業で○○に興味を持ち、グループワークで△△を試した」など、できるだけ具体的な学びの内容や経験を盛り込むことが重要です。
その学びから何を得て、どんな場面に活かせるかまでつなげて書くことで、読み手の理解も深まり、説得力も一段と増すでしょう。
③ 学科を羅列するだけにしない
「英語と経済と法律が得意です」といったように、複数の学科を並べただけでは印象に残りません。むしろ、どれも中途半端な印象を与えてしまい、自分の強みが伝わりにくくなってしまいます。
得意な学科は1つにしぼり、その学びの背景や取り組み方を詳しく記述したほうが効果的です。
また、何を学んだかだけでなく、その経験を通じて得た視点や考え方、行動の変化に触れることで、自分らしさがより際立ちます。企業側に「この人と話してみたい」と思わせる内容を目指しましょう。
④ 深掘りされたときに答えられない学科は選ばない
面接では履歴書に書かれた内容をもとに質問されることが多いため、表面的な理解しかない学科を選ぶのはリスクが高いです。
「雰囲気が好きだから」「単位が取りやすかったから」といった理由では、面接官の質問にうまく対応できず、準備不足な印象を与えてしまうかもしれません。
自分の言葉で学んだことや感じたことを説明できるか、今一度確認しておくと安心です。
履歴書に書く学科は、自信を持って語れるものにしましょう。その準備が、結果的に自分の評価を高めることにつながります。
履歴書で書ける「得意な学科」がない場合の対処法

「得意な学科が思い浮かばない」と感じている人も少なくありません。ですが、得意な学科=好成績というわけではなく、興味や姿勢も評価対象です。
以下の4つの視点から、自分らしいアピールにつながるヒントを探してみましょう。
- 成績や成果を出せた学科を振り返る
- 苦手意識がなかった学科に注目する
- 印象的なエピソードがある学科から考える
- アピールしたいスキルや価値観から逆算する
① 成績や成果を出せた学科を振り返る
最初に注目すべきは、試験や課題で良い評価を得られた科目です。高得点を取ったり、レポートで高評価をもらったりした経験は、学習理解の深さや地道な努力を裏付けるものとしてアピールできます。
仮に強い興味がなかったとしても、どうすれば成果が出せるかを自分なりに考え、工夫して取り組んだ過程があるなら、それ自体が立派な強みです。
「得意=好き」ではなく、「結果を出した=努力の証」として伝える姿勢が評価につながるでしょう。
② 苦手意識がなかった学科に注目する
明確に「得意」と感じた科目がなかったとしても、「苦手ではなかった」学科に目を向けてみてください。
講義中に苦痛を感じなかった、予習や復習に自然と取り組めたなど、無理なく学習できた経験は意外と貴重なヒントになります。
「なんとなく楽しかった」「時間を忘れて集中できた」といった感覚は、適性や興味の証拠です。このような前向きな感情は、エピソードに転換して伝えることで説得力のある自己PRに変えられるでしょう。
③ 印象的なエピソードがある学科から考える
忘れられない出来事がある授業や演習があれば、その科目を得意な学科として活用できます。
たとえばグループ発表でリーダーを務めた経験や、教員からの一言で興味が深まった場面などは、自分ならではの学びの証としてアピールできるでしょう。
その経験が「なぜ印象に残ったのか」「どんな学びにつながったのか」を丁寧に言語化することで、読み手にリアリティと共感を与えられます。
単なる科目名だけでなく、背景にあるストーリーを語ることで、履歴書の内容に深みが出るでしょう。
④ アピールしたいスキルや価値観から逆算する
自分が企業に伝えたい強みや特徴を先に整理し、それに合った学科を選ぶのも効果的です。
もし「調整力や対人スキルをPRしたい」と考えるなら、心理学や社会学が良いでしょうし、「論理性や分析力を伝えたい」なら数学や情報科学などが選択肢に入ります。
このように、自分のスキルや価値観を起点に学科を逆算することで、自己PRや志望動機との一貫性が生まれ、より説得力のある履歴書になるでしょう。
選んだ学科が、自分の強みを後押しするものであれば、面接でも安心して話せますよ。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
履歴書の「得意な学科」の項目で好印象を残す方法を知っておこう!

履歴書に得意な学科を記載することは、就活において自分の個性や価値観を伝える有効な手段です。企業はこの欄から、学業への姿勢や業務との親和性を見抜こうとしています。
だからこそ、学科は単に成績や名前で選ぶのではなく、自分の経験やスキル、志望職種とのつながりを踏まえて選ぶことが大切です。
さらに、実際に書く際には、結論を先に示し、具体的なエピソードを交えながら、どう仕事に活かせるかまで言及しましょう。
例文を参考にしながら、自分らしい学科の伝え方を工夫することで、履歴書全体の説得力が格段に高まります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









