インターンシップの種類を徹底解説|参加するメリットや探し方も紹介
この記事では、インターンシップの種類を目的別に徹底解説しています。
また、短期・長期インターンそれぞれの特徴や仕事内容、選ぶポイントまで詳しく紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
インターンシップとは?

インターンシップとは、学生が実際の仕事の現場に身を置き、職業体験を通して社会や業界への理解を深める取り組みです。
特に大学3年生から4年生の間に参加する人が多く、就職活動に向けた準備の一環として注目されています。
授業やガイダンスだけでは見えてこない職場の空気や働く人の考え方に触れることで、自分に合った職種や働き方を考えるきっかけとなるでしょう。
実際に仕事に関わることで、自分の得意・不得意を知ることができ、今後のキャリア選択にも大きなヒントを与えてくれます。
さらに、実務的な知識だけでなく、社会人としてのマナーやコミュニケーション力も身につくため、将来的に役立つスキルが自然と養われます。
また、他の学生と一緒に参加することで、互いに刺激を受けながら成長できる点も大きな魅力です。早い段階で実社会に触れる経験は、自己理解を深める貴重なチャンスといえるでしょう。
就活に向けて何から始めたらよいか迷っているなら、まずはインターンシップに参加してみましょう。
インターンシップの種類

インターンシップにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や目的があります。自分に合った形式を知らずに参加してしまうと、せっかくの経験が十分に活かせないかもしれません。
ここでは、代表的なインターンシップの形態について、メリットや注意点をわかりやすく紹介します。
- 短期インターンシップ
- 長期インターンシップ
- 超短期インターンシップ
- オンラインインターンシップ
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
① 短期インターンシップ
短期インターンシップは、1日から1週間ほどで完結するプログラムです。企業説明や業界理解、グループワークなどを通じて、企業の雰囲気や業務の一端を体験できます。
期間が短いため参加しやすく、複数の企業を比較できる点が魅力です。
就活の初期段階で業界の選び方や自分の適性を考えるきっかけにもなります。とはいえ、深い実務経験は得にくい傾向にあるため、期待しすぎないことも大切です。
また、短期とはいえ事前準備や振り返りを丁寧に行うことで、得られる学びの質は大きく変わります。
企業の求める人物像や業界の現状を自分の目で確認できる機会でもあるため、「自分にはどんな働き方が合っているのか」を探る材料としても活用したいところです。
気軽に参加できる分、自主的な姿勢を持って臨むことが大切でしょう。
② 長期インターンシップ
長期インターンシップは、数か月から半年以上の期間で実務経験を積む形式です。実際の業務に関わることが多く、ビジネススキルや仕事の進め方を身につけるチャンスといえます。
アルバイトに似た働き方をするケースもあり、職場での責任感や成果への意識も養われるでしょう。
一方で、学業や他の予定との両立が難しくなることもあるため、事前にスケジュールをよく確認しておきましょう。
採用直結型のプログラムもあり、将来の就職活動に役立つ場面が多く見られます。また、長期で関わることで社内の人間関係を深められ、社員からのフィードバックを直接受けられることもあります。
こうした実践的な経験は自己理解を深めるだけでなく、エントリーシートや面接でも具体的な話ができる材料になります。
自分の意欲をしっかりと伝えたい方には、特におすすめのインターンといえるでしょう。
③ 超短期インターンシップ
超短期インターンシップは、半日から1日程度のプログラムです。内容は会社説明や職場見学、簡単なワークが中心で、非常に手軽に参加できます。
就活の入り口として利用する学生も多く、情報収集の一環として有効な手段です。
ただし、なんとなく参加してしまうと、得られるものが少なくなってしまうかもしれません。企業の雰囲気を感じ取る、志望動機の参考にするなど、目的意識を持つことが重要です。
限られた時間の中でどれだけ情報を吸収できるかが成果の鍵を握ります。事前に企業の業界や理念について調べておくことで、質問の質も上がり、印象にもつながります。
また、オンライン開催が多いことから、場所にとらわれず参加しやすい点も魅力です。まず一歩を踏み出したい方にとって、挑戦しやすい選択肢でしょう。
④ オンラインインターンシップ
オンラインインターンシップは、自宅などからネットを通じて参加できる形式です。移動が不要で、時間や場所の制約が少ないため、多くの企業に参加しやすくなっています。
特に遠方の企業や物理的に訪問しづらい会社とも接点を持てるのは、大きな魅力です。
ただし、実際の職場の雰囲気を感じられなかったり、通信環境に左右されるといった注意点もあります。とはいえ、同時に複数の企業を比較検討できるのは大きな利点でしょう。
さらに、資料共有やチャットでのやり取りを通じて、オンラインならではの仕事の進め方を体験できます。
画面越しのコミュニケーションに慣れることも、今後のリモートワーク時代において重要なスキルとなるでしょう。
自分の興味を広げながら参加できるため、情報収集の一環としても非常に価値ある取り組みといえます。
企業がインターンシップを行う目的

企業がインターンシップを実施する理由には、採用戦略や組織づくりの観点からさまざまな狙いがあります。
単なる職業体験にとどまらず、学生との接点づくりや人材の見極め、さらには自社の魅力を伝える場としても活用されています。
ここでは、企業がインターンを行う主な目的について整理して解説します。
- 優秀な学生との接点を持つため
- 採用のミスマッチを防ぐため
- 学生への企業理解を促進するため
- 企業ブランディング・知名度向上のため
- 人材育成の場として活用するため
- 学生のリアルな評価機会を得るため
① 優秀な学生との接点を持つため
企業がインターンを実施する大きな理由の1つは、優秀な学生との早期接点をつくることです。とくに人気企業や業界では、就職活動が本格化する前に学生の関心を集めることが、採用成功のカギになります。
インターンを通じて直接学生と関わることで、興味関心を引き、将来的な志望につなげやすくなるでしょう。
また、学生にとってもインターンは、会社の雰囲気や業務の流れを肌で感じられる貴重な機会です。
これにより、入社後のイメージギャップを減らせるだけでなく、より納得感のあるキャリア選択が可能になります。
早期から接点を持つことで、企業は学生に対する印象をコントロールしやすくなり、選考に進んでもらえる可能性も高まるでしょう。
企業と学生が互いを知る第一歩として、インターンの存在は今後ますます重要になっていくと考えられます。
② 採用のミスマッチを防ぐため
採用の場面では、企業側・学生側どちらにも「思っていたのと違った」と感じるミスマッチが起きがちです。せっかく採用したのに、早期離職に至ってしまうケースは、企業にとって大きな損失です。
そこで有効なのが、インターンという仕組みです。実際に働いてもらうことで、学生自身が業務や社風をより具体的に把握できるようになります。
企業側も、インターン期間中の行動や反応から、学生の適性や考え方をリアルに観察することが可能です。面接や書類では見えない部分を知ることで、採用判断の精度が高まります。
また、インターンで好感を持ってもらえれば、そのまま選考につなげやすくなり、内定後の辞退率も下げられるでしょう。
インターンは、採用前の「お試し期間」として、企業と学生が互いの理解を深められる貴重な機会です。
③ 学生への企業理解を促進するため
インターンを通じて学生に企業理解を深めてもらうことは、採用活動において極めて重要です。
パンフレットや会社説明会だけでは伝わりにくい「リアルな業務」や「社員の人柄」「職場の空気」など、実際に体験しないとわからない情報が多く存在します。
とくに、知名度が高くない中小企業やBtoB企業では、インターンがきっかけで初めて企業を知る学生も少なくありません。
こうした体験の中で、「自分に合っている」と感じられれば、志望度は自然と高まります。さらに、業務に携わることで成長を実感できれば、その企業に対して前向きな印象を持つようになるでしょう。
企業側は、実務を体験してもらいながら魅力を伝え、学生との距離を縮める工夫が求められます。
企業理解が深まるほど、就職先としての納得感が増し、エントリーから内定までの意欲も高まっていくのです。
④ 企業ブランディング・知名度向上のため
インターンは、採用活動だけでなく、企業のブランド力を高める戦略の一部としても活用されています。
特に中小企業やスタートアップなど、学生の間での知名度がまだ低い企業にとって、インターンを通じて自社を知ってもらうことは非常に価値のある機会です。
実際に職場を訪れ、社員と関わることで、その企業の魅力が自然と学生の心に残るようになります。
加えて、インターンで得た体験を学生がSNSやクチコミで共有すれば、その情報は同世代の就活生に広がりやすくなります。
ポジティブな印象が伝われば、企業の評判やイメージアップにもつながるでしょう。企業にとっては、採用だけでなくマーケティング的な効果も期待できるというわけです。
このように、インターンは企業の認知度を高め、ブランド力を構築していく上でも有効な手段です。
⑤ 人材育成の場として活用するため
インターンは、単に学生に職場を見せるための場ではなく、将来の人材を育成する「教育の場」としての性格も持っています。
特に長期インターンの場合、学生がプロジェクトや業務に深く関わることで、実践的なスキルを身につけやすくなります。
計画立案や実行力、報連相など、社会人に求められる基本的な能力が自然と養われていくのです。また、企業側にとってもメリットは大きいです。
インターンの指導役となる若手社員にとっては、教えること自体が成長のきっかけになります。人を育てる経験を通して、マネジメント力やコミュニケーション能力も磨かれていくでしょう。
結果的に、学生も社員もともに成長できる構造ができ上がり、組織としての底力が向上します。インターンは、採用活動を超えて、企業の人材開発にまでつながる有効な取り組みといえるでしょう。
⑥ 学生のリアルな評価機会を得るため
企業がインターンを重視する理由の1つに、学生を実務の場で直接評価できる点があります。
履歴書や面接だけでは見えにくい「人柄」や「協調性」「仕事への取り組み方」などは、実際に一緒に働いてこそ分かるものです。
特にグループワークやプロジェクト型のインターンでは、学生の強みや成長の伸びしろが明確に見えてきます。
企業は、インターンで得た情報をもとに、自社との相性を多角的に判断することができます。それにより、採用のミスマッチを防ぐだけでなく、適材適所の人材配置にもつなげやすくなります。
一方、学生側も実務を経験する中で、自分の課題や得意分野に気づき、より現実的な自己分析ができるようになるでしょう。
相互に評価とフィードバックを行えるインターンは、双方にとって大きな価値を持つ選考手法です。
学生がインターンシップに参加するメリット

インターンシップは、就職活動を有利に進めるための大きなチャンスです。ただし、何となく参加するだけでは、十分な成果を得ることは難しいでしょう。
ここでは、インターンに参加することで得られる主なメリットを、以下の5つの視点から紹介します。
- 選考に有利になる可能性がある
- 企業・業界研究を深められる
- 自分の適性を知る機会になる
- 社会人基礎力が身につく
- 志望動機に具体性を持たせられる
① 選考に有利になる可能性がある
インターンシップに参加すると、就職活動の選考が有利になることがあります。企業によっては、インターンの参加者に特別選考を用意していたり、実習中の様子を採用の参考にしていたりします。
履歴書や面接だけでは伝わらない人柄や働き方を、実際の業務を通じて企業に知ってもらえるチャンスです。
また、インターン中に築いた人間関係や信頼感が、選考時の評価につながることもあります。現場で活躍すれば「ぜひうちに来てほしい」と思ってもらえる可能性が高まるでしょう。
さらに、社員と直接話す機会が増えることで、企業の求める人物像や評価ポイントについても理解が深まります。
ただし、すべての企業がインターン経験を重視しているわけではありません。選考に直結しない場合もありますので、過度な期待は控えましょう。
インターンを選考突破の手段と考えるのではなく、まずは自身の成長や企業理解のための機会ととらえて参加する姿勢が大切です。
② 企業・業界研究を深められる
企業や業界に対する理解を深めるには、実際の職場で働く体験が有効です。インターンでは、社員との交流や仕事の進め方を間近で見られるため、企業文化や業界の実情を知ることができます。
ネットやパンフレットでは得られない、リアルな情報に触れられるのが強みです。
特に、業務の中で何を重視しているのか、どんな人が活躍しているのかといった点は、実際にその場にいなければ見えてきません。また、会社ごとの風土や雰囲気の違いにも自然と気づくようになります。
たとえば、同じIT業界でも、スピード感を重視する会社と、丁寧さを求める会社では、働き方に大きな差があるかもしれません。
複数のインターンに参加すれば、そうした違いを比較することで、自分に合った企業像がより明確になります。受け身にならず、自分の目で比較・観察する意識を持つことが重要です。
経験を積むことで、企業選びに必要な「目利き力」も養われていくでしょう。
③ 自分の適性を知る機会になる
インターンに参加することで、自分の向き不向きを発見できることがあります。
大学生活では得られない実務経験を通じて、自分がどんな作業にやりがいを感じるのか、どんな環境がストレスになるのかを体感できます。
たとえば、デスクワーク中心の業務が苦にならなかった人は、集中力や正確性が強みかもしれません。一方、人との関わりを通じて充実感を得た人は、対人業務の適性が高い可能性があります。
また、インターン中のフィードバックから、自分でも気づかなかった強みを指摘されることもあるでしょう。こうした気づきは、今後のキャリア選択に大きく役立ちます。
どのような働き方が自分に合っているかを理解すれば、志望業界や職種を具体的に絞り込むことが可能になります。失敗を恐れず挑戦する姿勢が、自分を知る近道です。
実際に経験して得た実感こそ、将来の進路決定においてもっとも信頼できる材料となります。
④ 社会人基礎力が身につく
インターンは、学生生活では身につきにくい社会人としての基本的な力を養う場でもあります。
たとえば、報告・連絡・相談の徹底や、時間を守る意識、チームで動く姿勢など、働くうえで欠かせない要素を実践的に学べます。
こうした「社会人基礎力」は、どの業界・職種でも必要とされる力です。
インターンを通じて、言葉づかいやメールの書き方、仕事に対する責任感など、社会人としての基盤が少しずつ身についていくでしょう。
また、周囲との信頼関係を築くことや、自発的に行動する意識も大切なポイントです。
最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、現場でのアドバイスを素直に受け入れ、行動に反映させていくことが成長につながります。
こうした経験は自己PRの材料としても使えるため、インターン期間中の学びをしっかり振り返ることが大切です。自信を持って社会に出る準備ができるはずです。
⑤ 志望動機に具体性を持たせられる
インターンでの経験をもとにすれば、志望動機に説得力を持たせることができます。実際に見て感じたことを言葉にすることで、曖昧だった動機が具体的なエピソードを伴うものへと変わります。
たとえば、「人の役に立ちたい」と思っていた学生が、インターン中に顧客対応を経験し、「感謝されることでやりがいを感じた」と話せば、より実感のこもった内容になるでしょう。
また、「何に惹かれてこの会社を選んだのか」を語れるようになれば、企業側の評価も高まります。
さらに、困難を乗り越えた体験や、努力を重ねたエピソードを交えることで、主体性や課題解決力もアピールできます。
採用担当者は、志望動機から学生の価値観や将来のビジョンを読み取ろうとします。インターンは、魅力的な志望動機をつくるうえで有効な材料です。
実体験を通じた言葉には、自然と説得力が生まれます。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
インターンシップで経験できる仕事内容

インターンシップでは、実際の企業活動に近い体験ができるため、就職活動を控える学生にとって大切な学びの場となります。
ただし「インターン」といっても、企業によって内容はさまざまです。ここでは、代表的な仕事内容を4つに分けて紹介します。
それぞれの特徴を理解しておくと、自分に合ったインターン先を選びやすくなるでしょう。
- グループワークや課題解決型ワーク
- 職場体験・業務補助
- プレゼンや発表を通じたアウトプット
- 社員との交流やフィードバック機会
① グループワークや課題解決型ワーク
多くのインターンでは、複数の学生がチームを組んで特定の課題に取り組む「グループワーク」や「課題解決型ワーク」が取り入れられています。
企業が用意したケーススタディや実在のビジネス課題をもとに、限られた時間内で意見を出し合い、結論を導き出すという形式が一般的です。
この過程では、論理的に考える力、相手の話を理解しながら自分の意見を適切に伝える力、そして集団の中での役割理解など、社会に出てからも必要とされる力が自然と養われていきます。
初めての場では「他人と比べられるのでは」「うまく話せないかも」と不安になることもあるかもしれませんが、完璧に話すことよりも、自分なりに積極的に関与する姿勢が大切です。
企業もその姿勢や協調性を重視して見ています。さらに、グループの中での気づきや刺激が、自分の強みや改善点を知る手がかりになることも多いです。
結果だけでなく、取り組む過程を楽しみながら参加することで、大きな成長につながるでしょう。
② 職場体験・業務補助
実際の業務に関わる職場体験や、社員の業務をサポートする形式のインターンは、企業の雰囲気や仕事内容をリアルに感じ取ることができる貴重な機会です。
学生は、来客対応や電話の取り次ぎ、書類整理やデータ入力といった基礎的な業務からスタートすることが多いですが、日を追うごとにより実務的な仕事を任されるケースもあります。
こうした業務を通じて、ビジネスマナーや報連相の重要性、時間管理の感覚が自然と身についていきます。
特に長期インターンの場合、特定の部署に配属されて一定期間を過ごすため、より深くその企業の仕事の流れや人間関係、文化に触れることができます。
これは就職後のミスマッチを防ぐうえでも非常に役立つ体験です。単調に見える作業でも、そこに工夫を加える姿勢や丁寧さが評価されることもあるため、目の前の業務に誠実に取り組むことが重要です。
社会人としての基礎を身につけたい人にとって、このタイプのインターンは非常におすすめです。
③ プレゼンや発表を通じたアウトプット
多くのインターンでは、最終日にプレゼンテーションの場が設けられており、個人やグループでの成果発表を行うことが一般的です。
このプレゼンを通じて、情報を整理し論理立てて話す力、自分の考えをわかりやすく他者に伝える力、質問に対応する柔軟な思考力など、アウトプットのスキルが磨かれます。
発表に不安を感じる学生も少なくありませんが、経験を重ねることで着実に自信がついていきます。
また、プレゼンでは内容だけでなく、構成や話し方、資料の工夫なども重要なポイントです。実際に社会に出ると、提案や報告の場面でプレゼンの機会は多くあります。
その練習の場として、インターン中の発表は非常に意味のある機会となるでしょう。
さらに、多くの企業では発表後に社員からのフィードバックを受けることができ、第三者の視点から自分の課題を明確にするチャンスでもあります。
自分では気づかなかった強みや改善点を把握し、次のステップにつなげていきましょう。
④ 社員との交流やフィードバック機会
インターン中に設けられる社員との交流の機会は、学生にとって非常に有益です。
座談会やオフィスツアー、ランチミーティングなどのカジュアルな場では、働いている人たちの価値観や社内の雰囲気を直に感じることができます。
実際に働いている人たちの話を聞くことで、企業の理念や業務の裏側、入社後のキャリアパスなど、説明会やHPだけでは得られないリアルな情報を得ることができるでしょう。
また、インターン中に受けた課題や取り組みに対して、社員から個別にフィードバックをもらえる機会がある場合もあります。これは自分の思考や行動を客観的に振り返るうえで非常に貴重です。
フィードバックによって自分の強みを再認識したり、改善すべき点に気づいたりすることで、今後の行動がより具体的になります。質問があれば遠慮せず聞いてみる姿勢も大切です。
こうした双方向のコミュニケーションから、企業と自分の相性を確認し、納得のいくキャリア選択へとつなげていきましょう。
インターンシップの探し方

インターンシップを有意義なものにするには、ただ参加するのではなく、自分に合ったプログラムを見つけることが大切です。どのように探せばよいか迷っている就活生も多いでしょう。
けれども、いくつかの視点を持つことで、目標に合ったインターンを見つけやすくなります。ここでは、インターンシップの探し方について代表的な5つの方法を紹介します。
- 興味のある業界・職種から探す方法
- プログラム内容で探す方法
- 開催時期や日数で探す方法
- 自己分析から逆算して選ぶ方法
- 逆求人サイトやスカウトサービスを活用する方法
① 興味のある業界・職種から探す方法
インターンシップを探す際には、まず自分が興味を持っている業界や職種を明確にすることが出発点になります。
関心のある分野に取り組むことで、仕事に対する理解や適性を深めやすくなるからです。
たとえば、広告業界に関心があるなら、広告代理店や制作会社、マーケティング関連企業を中心に調べてみましょう。
現場でどのような仕事が行われているかを実際に体験することで、自分に合っているかどうかを肌で感じることができます。
また、業界研究と並行してインターンを探すことで、複数の企業を比較しやすくなり、就職活動全体にも役立つ知識が得られます。
ただし、知っている業界だけで選択肢を狭めてしまうのはもったいないことです。少しでも気になる分野があれば、積極的にインターン情報を探してみてください。
視野を広げることで、新たな発見や可能性に出会えるかもしれません。
② プログラム内容で探す方法
同じ業界のインターンシップであっても、その内容は企業によって大きく異なります。
プログラムの中身に注目して選ぶことで、自分が求める学びや経験をより確実に得られるでしょう。
たとえば、業務を実際に担当する「実践型」のインターンでは、職場のリアルな雰囲気や求められるスキルを体感できます。
一方で、講義や社員の話を聞くことが中心の「観察型」は、企業文化や業界全体の情報を収集するのに適しています。
自分がインターンで何を得たいのかを明確にすることが、プログラム選びの第一歩です。
実務体験を通じてスキルを磨きたいのか、業界について広く知りたいのか、その目的に応じて選ぶべきインターンも変わってきます。
また、企業のホームページや過去の参加者の体験談、SNSでの投稿などから、プログラムの具体的な内容を事前に把握しておくことも忘れないでください。
十分な準備をすることで、参加後のミスマッチを避けやすくなります。
③ 開催時期や日数で探す方法
インターンシップは時期や期間によって、その特徴や得られる体験が変わってきます。学業とのバランスを考えながら、無理のない範囲で参加できるインターンを探すことがポイントです。
たとえば、夏休みや春休みなどの長期休暇を活用すれば、1週間以上の中長期インターンにもチャレンジしやすくなります。
こうしたインターンでは、プロジェクト単位での業務や深い業界理解が得られるケースが多く、就活前の実践力を高めるのに役立ちます。
一方で、授業期間中はスケジュールの都合上、1日〜3日程度の短期インターンが参加しやすいでしょう。
企業によっては、複数回開催していたり、オンライン参加が可能な場合もありますので、公式サイトや就活サイトで詳細を確認してください。
また、同じ企業でも春・夏・秋と異なる内容で実施されるケースがあるため、参加タイミングを工夫することで、複数の体験を得られる可能性もあります。
自分のスケジュールと照らし合わせて、柔軟に選択することが大切です。
④ 自己分析から逆算して選ぶ方法
インターンの選び方に迷っているときは、まず自己分析から始めるのが効果的です。
自分の価値観、性格、強みや弱みを理解することで、「何のためにインターンに参加するのか」が明確になり、選択にブレがなくなります。
たとえば、「自分に合った社風を知りたい」と考えている場合は、ベンチャー企業と大手企業の両方を比較して体験することで、働く環境の違いを実感できるでしょう。
また、「チームで動くのが得意かどうか」や「ルールがしっかりある職場が合っているか」など、自己分析の結果から得られる仮説を検証する場としてインターンを活用できます。
目的がはっきりすれば、自然と選ぶべきプログラムも絞られてきます。自己分析は面接対策にも直結するので、インターン探しの前段階として取り組んでおくことをおすすめします。
自分軸をもって参加することで、インターンでの気づきや学びもより深いものになるはずです。
⑤ 逆求人サイトやスカウトサービスを活用する方法
近年では、企業から学生に直接オファーが届く「逆求人型」のサービスが注目されています。
プロフィールを登録しておくだけで、企業の採用担当者からインターン参加のスカウトが届く仕組みで、自分では気づかなかった魅力的な企業に出会えるチャンスもあります。
特に、プロフィールを丁寧に書いておくことで、マッチ度の高い提案を受けやすくなるでしょう。
また、企業側も学生に興味を持ってアプローチしてくるため、選考がスムーズに進みやすく、モチベーションの高い状態で参加できるケースが多いです。
通常の求人サイトと比べて、やや受け身になりやすい面もあるかもしれませんが、サービス内の企業情報や説明会などを積極的に活用することで、主体的な就活につなげることも可能です。
ただし、逆求人サービスだけに頼るのではなく、自分でも企業を調べたり、インターンの口コミを確認したりするなど、情報収集を並行して行うことが重要です。
こうしたツールをうまく使いこなすことで、効率よく理想的なインターンに出会える確率が高まるでしょう。
インターンシップを選ぶ際のポイント
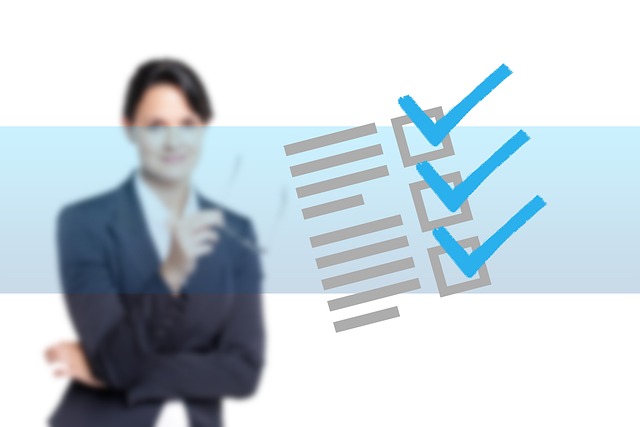
インターンシップは就職活動において欠かせない経験ですが、数が多すぎてどれを選べばいいのか悩む人も多いでしょう。ただ参加するだけではなく、自分に合ったものを見極めることが重要です。
ここでは、後悔しないインターン選びのために確認しておきたい4つのポイントを紹介します。
- インターンの目的と自分の目標が一致しているか
- 参加形式(対面/オンライン)や場所は適切か
- プログラムの内容は具体的で学びがあるか
- 企業の雰囲気や社風が自分に合っているか
① インターンの目的と自分の目標が一致しているか
インターンを選ぶ際にまず確認したいのは、そのプログラムの目的が自分の就活目標と合っているかどうかです。
企業によっては、選考直結型や業務体験重視型、グループワーク中心型など、実施するインターンの形式はさまざまです。
目的が合っていないインターンに参加してしまうと、得るものが少なく、逆に時間と労力を無駄にしてしまうことにもなりかねません。
たとえば、将来的に営業職に就きたいと考えているのに、開発職向けのプログラムに参加した場合、内容がピンとこなかったり、自信をなくすきっかけになったりする可能性もあります。
逆に、自分の関心分野やキャリア目標と一致した内容であれば、モチベーション高く取り組むことができ、実りある体験につながるでしょう。
募集要項やプログラム概要を丁寧に読み込み、自分の志向や将来像と一致しているかどうかを見極めることが、納得のいくインターン選びへの第一歩です。
② 参加形式(対面/オンライン)や場所は適切か
近年ではオンライン開催のインターンも一般的になり、形式の選択肢が広がっています。
その一方で、どちらの形式が自分に合っているかを見極めずに決めてしまうと、想像と現実にギャップを感じることもあるでしょう。
たとえば、実際の業務環境や職場の空気感を知りたいなら、対面型の方が向いていますが、時間や移動の制約が大きい人にはオンラインの方が無理なく参加できます。
また、インターンの場所も重要なポイントです。遠方での開催や交通手段が限られているエリアの場合、参加するだけで疲弊してしまい、集中力が落ちてしまうこともあります。
移動時間や費用がかさむと、他の活動との両立も難しくなるでしょう。
自身のスケジュールや生活リズム、優先したい体験内容を踏まえて、形式や場所の適切さを見極めることが、継続しやすく有意義なインターン体験につながります。
③ プログラムの内容は具体的で学びがあるか
インターンに参加する最大の目的は、就職活動や将来の仕事に役立つ「学び」を得ることにあります。
しかし、インターンによっては実質的に会社説明会の延長だったり、参加しても手応えを感じにくい内容の場合もあります。
だからこそ、プログラムの中身がどれだけ具体的か、実務に近い体験ができるかを確認することが大切です。
たとえば、社員とのワークショップや現場での業務体験、プレゼン発表などが含まれていると、実際の仕事を肌で感じながらスキルを身につけることができます。
こうした体験を通じて、自分に向いている職種が見えてきたり、志望動機の材料になったりすることもあるでしょう。
インターンの案内やスケジュールに「何をするのか」が明確に書かれているか、参加者にどのような成長を求めているのかを読み取ることで、質の高い経験につながるインターンを選ぶヒントになります。
④ 企業の雰囲気や社風が自分に合っているか
インターンに参加する目的は、業務内容だけでなく、企業との相性を見極めることにもあります。いくら仕事内容が理想的でも、職場の雰囲気が合わなければ長期的に働くイメージは持ちづらいでしょう。
インターンは、企業文化や社員の人柄を直に感じることができる貴重な機会です。
たとえば、自由な発言を歓迎する風土があるのか、上下関係が厳しいのか、若手が活躍しているのかなど、社内の空気感は企業によって大きく異なります。
説明会やインターン前の交流会を活用し、社員の話し方や振る舞いを観察することが大切です。
インターン中には、仕事内容だけでなく、「自分がこの会社にいる未来が想像できるか」という視点で振り返ってみてください。その直感は、就職先選びにも役立つはずです。
インターンシップを成功させるための対策

インターンシップは、就活に向けた大きな一歩です。ただ参加するだけで成果が得られるとは限りません。事前準備から振り返りまで、一つひとつの行動が結果を左右します。
ここでは、インターンシップを有意義なものにするための具体的な対策を紹介します。
- 事前準備として企業・業界研究をしておく
- 目的意識を持って積極的に参加する
- ビジネスマナーや基本スキルを身につけておく
- フィードバックを次に活かす姿勢を持つ
- コミュニケーションを積極的に図る
- 振り返りと記録を忘れずに行う
① 事前準備として企業・業界研究をしておく
インターンシップの前に企業や業界について調べておくことが、成功の第一歩です。企業側は、学生がどれだけ理解しているかを見ているため、事前の情報収集がそのまま評価につながる場合もあります。
表面的な知識だけでは、意欲や関心が伝わりにくく、印象が薄れてしまうかもしれません。
たとえば、企業理念、事業内容、業界内でのポジション、競合他社との違いなどを把握しておけば、面談やグループワークの場でより深い話ができるでしょう。
また、直近のニュースやプレスリリースに目を通しておけば、時事に対する感度の高さもアピールできます。
企業研究は、企業理解を深めるだけでなく、自分に合った業界や職種を見極めるヒントにもなります。インターンで得られる学びの質を高めるためにも、準備の段階から丁寧に取り組んでください。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
② 目的意識を持って積極的に参加する
インターンに参加するうえで、「なぜ参加するのか」「何を得たいのか」を自分の中で明確にしておくことは非常に重要です。
ただ指示に従って作業をこなすだけでは、自分にとっても企業にとっても意味の薄い時間になってしまう可能性があります。
たとえば、「その企業で働く人の価値観を知りたい」「実際の業務に触れて職種の理解を深めたい」など、具体的な目的があると、課題への取り組み方や行動の質にも違いが出てきます。
目的を持っていれば自然と積極的な行動につながり、企業側からも前向きな姿勢として評価されるでしょう。
目的が曖昧なままだと受け身になりやすく、チャンスを逃すことにもなりかねません。目的意識を持つことは、限られた時間で最大限の学びを得るための出発点です。
③ ビジネスマナーや基本スキルを身につけておく
インターンシップは、学生とはいえ実際の職場で業務を経験する機会です。最低限のビジネスマナーや基本スキルが備わっているかどうかは、周囲の印象を大きく左右します。
準備不足のまま現場に入ると、期待外れと見なされてしまうこともあるでしょう。たとえば、正しいあいさつや敬語、時間厳守、服装の清潔感などは、社会人としての基本です。
加えて、メールの書き方や報告・連絡・相談のしかたといった実務に必要なコミュニケーションも重要になります。
これらができていれば、安心して業務を任せられる人材と受け止められる可能性が高まります。
また、ExcelやPowerPointなどの基本操作ができると、仕事の幅が広がり、インターンでの成果にもつながります。
こうしたスキルは、就活以降にも必要になるので、今のうちに身につけておくと安心です。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
④ フィードバックを次に活かす姿勢を持つ
インターン中には、社員や指導者からフィードバックを受ける場面が数多くあります。そのとき大切なのは、内容に一喜一憂することではなく、どう受け止めてどう行動に移すかという点です。
フィードバックを上手に活かせる人は、成長のスピードが格段に早くなります。
たとえば、「報連相の頻度が少ない」と言われたら、次回以降はタイミングを意識して情報共有することで信頼につながります。
また、「論理的に話す力が弱い」と指摘された場合は、構成を整理してから話す練習を重ねると、着実に改善できるでしょう。
反発や言い訳をせず、謙虚に耳を傾ける姿勢そのものが、成長意欲の証明となります。フィードバックは自分の課題を知る貴重なチャンス。
それを糧に行動を変えることで、実りの多い経験になるはずです。
⑤ コミュニケーションを積極的に図る
インターンシップでは、社員や他の参加者とのコミュニケーションが、学びの深さを大きく左右します。
業務に集中することももちろん大切ですが、それ以上に現場の空気を感じ取り、人と接する中で多くの気づきを得ることができます。
たとえば、気になった点を質問する、仕事の進め方について相談する、ランチの時間に雑談を交わすなど、自然なかたちで関わることが信頼につながります。
こうしたやり取りの中で、社風や働き方のリアルが見えてきますし、自分の適性を判断する材料にもなります。
また、会話を通して社員との距離が縮まることで、より具体的なアドバイスを受けられることもあります。
インターンは情報収集の場でもあるので、自分から動く姿勢が、貴重な学びを引き出す鍵になるでしょう。
⑥ 振り返りと記録を忘れずに行う
インターンが終わったあと、振り返りを行い、経験を言語化して記録に残しておくことが極めて重要です。
なぜなら、どんなに良い経験をしても、時間がたてば記憶は薄れてしまい、具体的なエピソードとして語れなくなるからです。
たとえば、「どんな業務を経験したのか」「その中でどんな工夫や反省があったのか」「今後にどう活かしたいか」といった視点で書き残しておくと、自己分析にもつながります。
こうした記録は、エントリーシートや面接でのエピソードにも活用できるため、実際の就活での武器になります。
また、感情や印象も含めて記録しておけば、将来的に志望動機を深める材料にもなるでしょう。経験を知識やスキルに変えるには、振り返る習慣が欠かせません。
インターンの学びを最大限にするためにも、記録は忘れずに行ってください。
インターンシップを最大限に活かすために種類を知っておこう!

インターンシップには、短期・長期・オンラインなど多様な種類があり、それぞれに特徴とメリットがあります。
企業は優秀な学生との接点づくりや採用のミスマッチ防止、ブランディングなどを目的に実施しており、学生側も業界理解や自己分析、選考対策に役立てることができます。
実際の業務やグループワークを通じた経験から社会人基礎力も身につくでしょう。インターンシップを選ぶ際は、自分の目標と一致しているか、プログラム内容や形式も確認が重要です。
成功のためには、事前準備や振り返りを怠らず、積極的に学ぶ姿勢が求められます。
自分に合った種類のインターンシップを選び、戦略的に取り組むことで、将来のキャリア形成に大きく役立てることができるのです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










