入社承諾書に印鑑は必要?正しい押し方と印鑑なしの場合の対応を詳しく紹介
「入社承諾書に印鑑って本当に必要なの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
印鑑の押し方ひとつで「社会人としての基本マナー」が問われるため、意外と見落とせない重要なポイントです。
実印・認印・シャチハタの使い分けを誤ると、企業側に不備と判断されてしまう可能性もあります。しかし、最近では電子承諾書やサイン対応を認める企業も増えており、必ずしも印鑑が必要とは限りません。
この記事では、入社承諾書における正しい印鑑の押し方や印鑑なしの場合の対応方法を詳しく解説します。ぜひ参考にして、安心して提出できるようにしましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
入社承諾書とは?内定承諾書との違いも解説

入社承諾書は、内定を正式に受け入れる「入社の意思」を企業へ伝える大切な書類です。内定承諾書との違いを理解し、正確に記入・提出することが社会人としての第一歩になります。
まず、入社承諾書は単なる形式的な書類ではなく、企業との信頼関係を築く契約書に近い存在です。記載内容をよく確認し、印鑑の押し方や提出期限など、細部まで丁寧に対応することが重要です。
一方で、内定承諾書は選考の最終段階で提出する書類であり、「他社の選考を辞退し、御社の内定を受け入れます」という入社意思を表明するものです。
提出先や方法は企業によって異なりますが、添え状を添えて期日を守ることが基本です。印鑑を正しく押し、朱肉の状態や印影の鮮明さにも注意しましょう。
入社承諾書の扱い方を正しく理解しておけば、入社後の印象も良くなり、信頼を得る第一歩になります。誠実で丁寧な対応を心がけ、自信を持って提出しましょう。
入社承諾書で使う印鑑の種類|実印・認印・シャチハタの違い
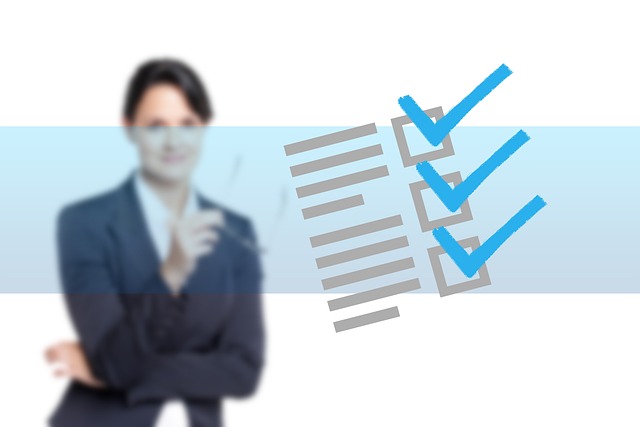
入社承諾書に押す印鑑は、社会人としての基本的なマナーが問われる重要な要素です。印鑑の種類を正しく理解しておくことで、企業からの信頼を得るだけでなく、書類提出時の不安も解消できます。
ここでは、入社承諾書に使える印鑑の種類と、それぞれの特徴・注意点を詳しく解説します。どの印鑑を使うか迷っている方は、ここを読めば正しい判断ができるでしょう。
- 入社承諾書で使用する印鑑の種類一覧
- 実印・認印・シャチハタの違いと特徴
①入社承諾書で使用する印鑑の種類一覧
入社承諾書で使用される印鑑には、主に「実印」「認印」「シャチハタ」の3種類があります。それぞれに使う場面と目的が異なり、印象を左右するポイントでもあります。
まず実印は、市区町村に登録された公的な印鑑であり、契約や法的な手続きに使われる最も正式な印章です。社会的な信頼性が高く、企業側が「本人の確実な意思」を確認する際にも用いられます。
次に認印は日常的な書類や軽微な契約などで使われる、登録不要の印鑑です。多くの企業では、入社承諾書にこの認印が使用されます。印影が鮮明で氏名がきちんと刻まれた認印を選ぶことが重要です。
最後にシャチハタですが、こちらはインクが内蔵されたゴム製のスタンプタイプで、公的文書には不適切です。文字の形が変わりやすく印影が安定しないため、正式な書類には使わないよう注意しましょう。
入社承諾書は企業と学生の「正式な合意」を確認する大切な文書です。そのため、形式や種類を軽視せず、ビジネスマナーに沿った印鑑を選ぶことが信頼につながります。
②実印・認印・シャチハタの違いと特徴
実印は本人が役所に提出している公式な印鑑で、法的な本人確認証明の際に扱われます。企業が、入社承諾書に実印を求めるケースがあるため、注意が必要です。
実印を使う場合は、印影がかすれないように注意し、朱肉を均一につけることがポイントになります。また、印面が欠けたり、インクが滲んだりしないよう、普段から清潔に保つことも大切です。
一方、認印は気軽に使えつつ、高い信頼性も兼ね備えています。市販品にはないフルネームの印鑑はさらに良いでしょう。市販品でも100円ショップのシャチハタなど安物は避け、質のいいものを選んでください。
シャチハタは、便利でスピーディーに押せるのが特徴ですが、ビジネス文書では「正式な押印」として認められません。理由は、インクの変色や印面の劣化により、同じ印影を長期間維持できないためです。
もし間違って使用してしまった場合は、すぐに企業へ連絡し、認印または実印で再提出する旨を伝えましょう。また、印影がきれいに出るように保管し、使用前に朱肉の状態も確認しておくことも大切です。
入社承諾書で印鑑を押し間違えたときの正しい対処法

入社承諾書に印鑑を押す際は緊張しがちですが、ミスをしてしまうことも珍しくありません。ここでは、印鑑の押し間違い・汚れ・修正方法など、状況別の正しい対処法を解説します。
焦って書き直す前に、落ち着いて正しい手順を理解しておきましょう。
- 誤字を訂正印で修正する
- 押印ミスを訂正印で修正する
- 印影が汚れたときに再提出を依頼する
- 担当者に連絡して状況を説明する
- 再発行を依頼して正しく提出し直す
- ミスを防ぐために事前確認を徹底する
①誤字を訂正印で修正する
入社承諾書に誤字や記入ミスがあった場合は、修正液や修正テープを使うのではなく、正式な手順で訂正しましょう。誤った部分に二重線を引き、その近くに正しい文字を記入します。
さらに、修正箇所の上または横に訂正印を押すことで、本人が修正を行ったことを証明できます。訂正印には、入社承諾書の署名に使用した印鑑と同じものを使うのが原則です。
異なる印鑑を使うと、「本人以外が修正したのでは」と疑われる可能性があります。誤字の修正後は、全体の見た目が乱れすぎていないか確認し、読みやすさを保つことも大切です。
修正が多い場合は、思い切って書き直す判断も必要でしょう。
②押印ミスを訂正印で修正する
印鑑を押す際に、位置がずれたり、印影が重なったりした場合も訂正印で対応できます。まず、間違った印影に軽く二重線を引き、すぐ近くに再度正しい印鑑を押します。
その上で訂正印を押し、修正が本人によるものであることを示しましょう。ただし、印影が大きくずれていたり、複数回押してしまった場合は、訂正ではなく書き直した方が見た目も印象も良いです。
企業側に提出する書類は第一印象が大切ですので、「丁寧に扱う姿勢」を示すことがポイントです。訂正を行った場合は、読み手が混乱しないように、修正箇所が明確にわかる形に整えることを意識してください。
③印影が汚れたときに再提出を依頼する
朱肉のつけすぎや指の接触などで印影がにじんでしまった場合、修正よりも再提出を依頼する方が適切です。印影の汚れは訂正印では修正できず、書類全体の印象を損ねてしまいます。
きれいな印影は誠実さを象徴するため、にじみや汚れが目立つ場合は、すぐに担当者へ相談してください。
連絡時は、「印影が不鮮明になってしまったため、再作成の許可をいただけますか」と丁寧に伝えると好印象です。
再発行が認められたら、落ち着いた環境で新しい書類に記入し、朱肉の量や押印位置を確認してから押すと良いでしょう。小さな気配りが、信頼感を大きく高める結果につながります。
④担当者に連絡して状況を説明する
印鑑の押し間違いや誤記入をしてしまったときは、独断で修正せず、まず担当者に報告するのが基本です。企業によっては再提出を求める場合や、訂正で済む場合など、対応方針が異なります。
自己判断で修正を行うと、かえって混乱を招くこともあるため、早めの相談が安心です。連絡の際は、「書類を誤って記入してしまった」「印影が不鮮明になった」など、状況を具体的に伝えましょう。
その上で、再提出が必要か確認してください。丁寧に対応すれば、誠実な印象を与えられます。小さなミスを正直に報告することが、社会人としての信頼につながります。
⑤再発行を依頼して正しく提出し直す
修正箇所が多い場合や印影が大きく崩れてしまった場合は、再発行を依頼するのが最も確実な方法です。
企業側も「正式な書類としての整合性」を重視するため、無理に修正するよりも新しく作り直す方が丁寧な印象を与えます。
再発行を依頼する際は、担当者に状況を簡潔に説明し、「お手数をおかけしますが、再度提出させていただきたい」と伝えましょう。
新しい入社承諾書を受け取ったら、記入・押印前に内容を再確認し、余白を確保して落ち着いて作業することが大切です。
再提出の際には、封筒や添え状なども整えて提出し直すことで、より誠実な印象を与えることができます。
⑥ミスを防ぐために事前確認を徹底する
印鑑の押し間違いを防ぐためには、事前準備が何よりも大切です。まず、清潔な平らな机の上に捺印マットを敷き、朱肉の量を確認してから押すようにしましょう。
印鑑の上下をよく見てから押すことで、傾きやズレを防げます。また、事前に練習用の紙で試し押しをしておくと、本番での失敗を大幅に減らせます。押印後は、インクが乾く前に触れないよう注意してください。
印影が乾くまで数秒待つだけでも、にじみや汚れを防げます。一度の失敗で焦る必要はありませんが、再提出や修正が重なると信頼を損ねることもあります。
落ち着いて準備し、確認を怠らないことが、スムーズな提出につながるでしょう。
印鑑を綺麗に押すコツと失敗を防ぐポイント

入社承諾書で印鑑を押す際、「にじみ」や「かすれ」があると印象が悪くなってしまいます。正しい押し方を知っておくことで、清潔で整った印影を残すことができ、書類全体の印象もぐっと良くなります。
ここでは、印鑑を綺麗に押すためのコツと、失敗を防ぐ具体的な方法を紹介します。
- 朱肉を均等につける
- 捺印マットを使って安定させる
- 印面を垂直に押し当てる
- 押印位置を正確に合わせる
- 押印後に印影を確認する
- 練習して印影を整える
①朱肉を均等につける
綺麗な印影を作る第一歩は、朱肉のつけ方にあります。朱肉はたっぷり付ければ良いというものではなく、印面全体に均等に行き渡るように軽くポンポンと数回押し当てるのがコツです。
多すぎるとにじみやムラが出やすく、少なすぎると薄くなってしまいます。理想は「ややしっとり」とした状態で、光に当てたときに均一に朱色がのっている程度です。
また、使う朱肉は古く乾燥したものではなく、柔らかく新鮮なものを選びましょう。品質の悪い朱肉を使うと印面の細かい文字がつぶれてしまうこともあります。
定期的に朱肉を入れ替える習慣をつけておくと、安定した印影を保てます。
②捺印マットを使って安定させる
印鑑を押す際には、必ず捺印マットを使うことをおすすめします。硬い机の上で直接押すと、力のバランスが崩れ、印影がかすれたり斜めになったりしやすいです。
捺印マットを敷くことで適度な弾力が生まれ、均一な圧力で押しやすくなります。専用マットがない場合は、厚紙や雑誌の表紙などを代用しても構いません。
大切なのは、押印時に手首が安定し、印面がぶれない環境を整えることです。実際に押す前にマットの上で試し押しをして、押しやすい角度や力加減を確認しておくとより安心でしょう。
ちょっとした工夫で印影の仕上がりが格段に変わります。
③印面を垂直に押し当てる
印面をまっすぐに押すことは、美しい印影を残すための基本です。印鑑を斜めに押してしまうと、上部がかすれたり、下部だけが濃くなったりしてバランスが崩れます。
押すときは、利き手で印鑑を持ち、もう片方の手で印面の上部を軽く支えると安定します。力を入れるのは一瞬で構いません。
強く押しすぎるとインクがにじみ、文字が太ってしまうため、一定の圧で素早く押すのがポイントです。押したあとに数秒間静止してからまっすぐ上に引き上げると、印影がぶれずにきれいに残ります。
細かい注意を重ねることで、見た目の美しさに差がつきます。
④押印位置を正確に合わせる
押印位置がずれると、せっかくの印影が整っていても全体の印象が悪くなります。署名の右横に押すのが一般的なルールですが、用紙のデザインに余白がある場合は、バランスを見ながら配置を調整しましょう。
事前に鉛筆で軽く印の位置を目印として付けておくと、ずれを防ぎやすくなります。また、書類を固定するために片手で軽く押さえると、紙が動かず安定します。
もし印面がずれた場合は、無理に押し直さず、担当者に相談して指示を仰ぐのが無難です。位置が整っているだけで、全体の仕上がりがぐっと引き締まります。
⑤押印後に印影を確認する
押印が終わったら、すぐに次の作業に進まず、印影の状態を確認しましょう。かすれやにじみがないか、輪郭がしっかり見えているかを確認することが大切です。
印影が不明瞭なまま提出してしまうと、再提出を求められる可能性もあります。確認の際は、光にかざして角度を変えながら見ると、インクの濃淡が分かりやすいです。
万が一、押し直す必要がある場合は、新しい用紙を使うのが基本です。小さな汚れでも「注意力が足りない」と受け取られることがあるため、細部まで丁寧に確認しましょう。
印影の最終チェックを怠らないことが、信頼を守る第一歩です。
⑥練習して印影を整える
印鑑を押すのは簡単そうに見えますが、実際にはコツが必要です。本番前に練習用の紙で何度か試し押しをすることで、自分に合った力加減や朱肉の量を把握できます。
特に実印や認印は細かな彫刻が施されているため、わずかな角度の違いでも印影が大きく変わります。練習を重ねることで、自然に美しい押印の感覚が身につくでしょう。
押印に慣れていない人ほど、練習で「自分の癖」を知ることが大切です。印影が均一で、文字の輪郭がはっきり出ている状態を目指してください。
丁寧に準備をしておくことで、本番でも落ち着いて正確に押せるようになります。
印鑑なしの入社承諾書への対応方法

最近では、デジタル化の進展により「印鑑なし」で入社承諾書を提出するケースも増えています。しかし、企業によっては依然として押印を重視している場合もあります。
ここでは、印鑑を押せない・押し忘れた場合の正しい対応方法や、サインや電子署名を使う際の注意点を詳しく解説します。
- サインで代用する
- 電子承諾書を利用する
- 押し忘れたときに企業へ連絡する
- 印鑑を後日押して再提出する
- 印鑑なしで提出する場合のリスクを理解する
- 状況に応じて担当者へ確認する
①サインで代用する
入社承諾書に印鑑が押せない場合、手書きのサインで代用できることがあります。特に外資系企業やスタートアップなどでは、サインを本人確認の手段として認めるケースが増えています。
サインを使う際は、署名欄にフルネームを丁寧に記入し、普段使っている署名スタイルを用いるのが理想です。筆記体やローマ字でも問題はありませんが、読みやすく整った文字を意識しましょう。
また、サインは印鑑の代わりに「本人の意思」を示すものであり、軽い気持ちで記入すべきではありません。正式な書類として扱われるため、慎重に行う姿勢が大切です。
②電子承諾書を利用する
最近では、紙の入社承諾書ではなく、電子データでやり取りを行う企業も増えています。電子承諾書の場合、電子署名や電子印鑑を使って本人確認を行う仕組みが一般的です。
この方法では、印鑑の押印が不要な代わりに、システム上で承諾ボタンを押したり、電子署名を入力したりすることで正式な承諾と見なされます。
企業側も法的に有効な電子署名サービスを利用していることが多く、安心して利用できます。ただし、メールでPDFを送付するだけの形式では、正式な署名と見なされない場合もあるため注意が必要です。
不明点がある場合は、提出前に担当者へ確認し、正式な手順で対応するようにしましょう。
③押し忘れたときに企業へ連絡する
印鑑を押し忘れて入社承諾書を提出してしまった場合は、すぐに企業へ連絡してください。押印忘れを放置すると、「書類不備」と判断される可能性があります。
電話またはメールで「押印を忘れてしまったため、再度提出させていただきたい」と丁寧に伝えましょう。
その際、すでに提出した書類が返送されるのか、新しい書類を再発行してもらえるのかも確認しておくと安心です。誠実に報告すれば、担当者も丁寧に対応してくれるでしょう。
また、再提出の際は同じミスを繰り返さないよう、封入前に内容と印影を確認する習慣をつけると良いです。
④印鑑を後日押して再提出する
もし印鑑を手元に持っていなかった場合や、出先で承諾書を書いた場合は、後日改めて押印して再提出する方法があります。まず、担当者に事情を説明し、「印鑑を後日押して再送してもよいか」を確認しましょう。
企業によっては「サインで構いません」と言われることもありますが、正式な書類として扱う場合は押印が求められることが多いです。
再提出する際は、添え状に「再提出の理由」を簡潔に記載しておくとより丁寧です。押印後は印影の状態を確認し、にじみやかすれがないことを確かめてから郵送してください。
誠実な対応を示すことで、信頼を失うことなくスムーズに手続きが進みます。
⑤印鑑なしで提出する場合のリスクを理解する
印鑑なしの入社承諾書は、一見問題がないように思えても、企業によっては正式な承諾と見なされない場合があります。
特に大手企業や公的機関では、印鑑を押すことで「本人が承諾した」という証明を重視しているため、押印なしでは不備扱いになるケースもあります。
また、印鑑がないと「書類の改ざん防止」が難しくなるというデメリットもあります。電子署名システムを導入していない企業では、押印が本人確認の唯一の手段である場合も多いため、慎重に判断が必要です。
印鑑を使わない方法を選ぶ場合は、必ず担当者に確認を取り、企業の規定に従うようにしましょう。
⑥状況に応じて担当者へ確認する
印鑑の要不要や代替方法は企業によって異なります。そのため、不安な場合は必ず担当者へ確認することが最も確実です。
「印鑑を押せない事情がある」「電子データで提出しても問題ないか」など、状況を具体的に伝えるとスムーズに対応してもらえます。また、自己判断でサインや電子署名に切り替えるのは避けましょう。
意図せず形式を間違えると、再提出や確認に時間がかかることもあります。担当者に確認を取る姿勢は、誠実さやビジネスマナーの表れでもあります。
正確な情報を得た上で、最適な方法で提出することが信頼につながります。
入社承諾書を提出する際のマナーと注意事項

入社承諾書は、内定を正式に受け入れる重要な書類です。提出時のマナーや注意点を正しく理解していないと、せっかくの誠意が伝わらなかったり、印象を損ねたりすることもあります。
ここでは、提出期限や封筒の書き方など、提出時に気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。
- 提出期限を守る
- 封筒に宛名を正しく書く
- 添え状を同封する
- 書類の内容を最終確認する
- 郵送方法を指定通りにする
- 提出後に受領確認を行う
①提出期限を守る
入社承諾書は、指定された期限内に提出するのが基本です。多くの企業では、書類到着までの期間を含めてスケジュールを組んでいるため、期限を過ぎると「入社意思がないのでは」と誤解されることもあります。
郵送で提出する場合は、消印日ではなく到着日が基準となることが多いため、期限の2〜3日前には発送を済ませるようにしましょう。
もしも遅れそうな場合は、事前に担当者へ連絡し、事情を説明することが大切です。早めの提出は「丁寧で信頼できる人」という印象にもつながります。スケジュール管理も社会人としての基本です。
②封筒に宛名を正しく書く
封筒の宛名は、ビジネスマナーの中でも特に見落とされがちな部分です。宛名の書き方ひとつで印象が変わるため、正確に丁寧に記載しましょう。
表面には「〇〇株式会社 人事部 御中」と記載します。個人名が指定されている場合は「〇〇様」としますが、「御中」と「様」は併用しません。
また、封筒は白または淡い色の角形2号サイズが一般的で、宛名は縦書きが好まれます。裏面には自分の住所と氏名を忘れずに記入してください。
筆記用具は黒のボールペンや万年筆を使用し、消えるボールペンは避けるのが基本です。
③添え状を同封する
入社承諾書を郵送する際は、必ず添え状(送付状)を同封しましょう。添え状は「書類をお送りしました」という報告と、「今後ともよろしくお願いします」という挨拶を兼ねたビジネスマナーの一つです。
書式はA4サイズの白い用紙に統一し、上部に宛名・日付・差出人を明記します。本文には「入社承諾書を同封いたしましたのでご確認ください」など、簡潔で丁寧な表現を使うと好印象です。
最後に「何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくると、社会人としての誠実さが伝わります。添え状の有無で印象が大きく変わるため、忘れずに添付してください。
④書類の内容を最終確認する
入社承諾書の内容確認は、提出直前に必ず行いましょう。氏名・住所・日付・印鑑の押印位置など、記入漏れや誤字がないかを確認します。
誤字や押印ミスは信頼を損ねる原因となるため、提出前に一度声に出して読み直すとミスを発見しやすくなります。また、印影がかすれていないか、書類の端が折れていないかなど、見た目の清潔さも大切です。
書類はクリアファイルに入れて封筒へ入れると、雨や折れ曲がりを防ぐことができます。最終確認を怠らず、丁寧に仕上げた書類を提出することで、信頼と安心感を与えられるでしょう。
⑤郵送方法を指定通りにする
企業から郵送方法が指定されている場合は、その指示に必ず従いましょう。普通郵便ではなく「簡易書留」や「速達」での送付を求められるケースもあります。
指定がない場合でも、確実に届いたことを証明できる「簡易書留」を選ぶと安心です。
封入時には、添え状 → 入社承諾書 → クリアファイルの順に入れ、封を閉じたら封筒ののりづけ部分に軽く印鑑を押すのが一般的です。
郵便局では控えを受け取り、万が一の紛失に備えて保管しておきましょう。正しい手順で送ることで、社会人としての基本的な信頼感を高められます。
⑥提出後に受領確認を行う
書類を送ったら、届いたかどうかを確認するのも大切なマナーです。受領確認の連絡を入れることで、誠実な姿勢を示せます。
メールで確認する場合は、「入社承諾書を本日発送いたしました。到着後にご確認いただけますと幸いです。」といった簡潔な内容で構いません。
到着後に返信があれば、丁寧にお礼を返すと印象がさらに良くなります。また、面接時や電話でのやり取りがあった担当者に対しては、直接感謝の言葉を添えるとより印象的です。
提出後の対応も「社会人としての姿勢」を示す機会なので、最後まで丁寧なやり取りを心がけましょう。
よくある質問|印鑑トラブル・書き損じ・提出時の疑問まとめ

入社承諾書に関する印鑑トラブルや提出時の疑問は、就活生の多くが抱える不安のひとつです。ここでは、よくある質問をまとめ、具体的な対処法や判断のポイントを紹介します。
焦らず冷静に対応すれば、信頼を損なうことなく提出できます。
- 印鑑を押す場所を間違えたらどうすればいい?
- 印鑑を逆さまに押してしまった場合は訂正できる?
- 内定承諾書と入社承諾書の両方に印鑑が必要?
- 印鑑を持っていない場合はどうすればいい?
- 親の印鑑を代わりに使っても問題ない?
- 押印後に気泡が入って印影が欠けた場合は再提出すべき?
- 複数枚の入社承諾書に同じ印鑑を押しても大丈夫?
- 印鑑登録をしていない印鑑でも有効?
- 郵送中に入社承諾書が汚れた場合はどう対応する?
- 印鑑の色は赤以外でも問題ない?
①印鑑を押す場所を間違えたらどうすればいい?
印鑑を誤った場所に押してしまった場合は、修正液やテープで隠すのではなく、訂正印で対応しましょう。間違えた箇所に軽く二重線を引き、すぐ横に正しい位置で押し直します。
誤りが目立つ場合や見栄えが悪い場合は、担当者に相談して新しい書類を再発行してもらうのが確実です。焦って自己判断で修正せず、丁寧に対応する姿勢が大切です。
②印鑑を逆さまに押してしまった場合は訂正できる?
印鑑を逆さまに押してしまった場合は、訂正印では修正ができません。そのため、再発行を依頼して新しい書類に正しく押し直すのが原則です。
企業に誠実に報告し、再提出の許可を得ることで、信頼を損なうことなく対応できます。軽度の傾きであれば問題ない場合もありますが、上下が完全に逆の場合は再提出をおすすめします。
③内定承諾書と入社承諾書の両方に印鑑が必要?
企業によって異なりますが、一般的には両方に印鑑を押す必要があります。内定承諾書は内定を受ける意思の確認書、入社承諾書は入社を正式に約束する契約書に近い扱いです。
それぞれに押印することで「本人の意思で承諾した」ことを証明できます。指示がない場合でも、署名の隣に印鑑を押すと丁寧な印象を与えられます。
④印鑑を持っていない場合はどうすればいい?
印鑑を持っていない場合は、早めに作成しましょう。100円ショップの簡易印鑑ではなく、氏名がきちんと彫刻された認印を選ぶのが理想です。
時間がない場合はサインで代用できる場合もありますが、必ず担当者に確認してください。入社承諾書は正式な書類のため、できる限り印鑑を用意するのが望ましいです。
⑤親の印鑑を代わりに使っても問題ない?
親の印鑑を代用するのは避けましょう。入社承諾書は本人の意思を確認するための書類であり、他人の印鑑では法的にも本人確認の意味を失います。
どうしても手元に印鑑がない場合は、企業に事情を説明して対応を相談しましょう。本人が押した印鑑こそが、正式な同意の証明になります。
⑥押印後に気泡が入って印影が欠けた場合は再提出すべき?
印影の一部が欠けた程度なら、全体の文字が読める範囲であれば問題ないこともあります。しかし、欠けが大きく名前が判読できない場合は、担当者に相談し、再提出を申し出るのが無難です。
印影がはっきりしていないと、書類の有効性を疑われることもあるため、きれいに押せたかを必ず確認しましょう。
⑦複数枚の入社承諾書に同じ印鑑を押しても大丈夫?
はい、同じ印鑑を使用して問題ありません。複数枚提出を求められた場合、同一の印鑑を使うことで「同一人物の署名」としての信頼性が保たれます。
異なる印鑑を使うと確認作業に手間がかかるため、すべて同じ印影を使用することが基本です。印影が異なると企業側で混乱を招くおそれがあります。
⑧印鑑登録をしていない印鑑でも有効?
登録していない印鑑、いわゆる「認印」でも、入社承諾書では十分有効です。登録印(実印)は法的効力を伴う契約書で必要になる場合が多いですが、承諾書レベルでは認印で問題ありません。
ただし、印影が不鮮明だったり、既製品の共通印鑑を使用すると本人確認が難しくなるため、個人名が刻印された印鑑を使用しましょう。
⑨郵送中に入社承諾書が汚れた場合はどう対応する?
郵送中に書類が汚れてしまった場合は、まず企業に状況を報告しましょう。届いた時点で汚れが目立つ場合、担当者が判断して再提出を求めることがあります。
自分で勝手に修正したり、新しい書類を送ったりするのは避け、必ず指示を仰ぐのが安全です。丁寧な対応が信頼を保つポイントになります。
⑩印鑑の色は赤以外でも問題ない?
基本的に印鑑の色は「朱色(赤系)」を使用します。黒や青のインクは公式書類には不適切とされるため避けましょう。朱肉の色は「誠実さ・正式さ」を意味するため、ビジネス書類では朱色が最も一般的です。
インクが古くなっていると色がくすむことがあるので、使用前に状態を確認し、鮮やかな印影を心がけてください。
入社承諾書と印鑑の正しい扱いを理解して信頼を築こう

入社承諾書は、内定を正式に受け入れる意思を示す大切な書類です。印鑑の扱い方や提出マナーを正しく理解しておくことは、社会人としての第一歩を踏み出すうえで欠かせません。
まず、実印・認印・シャチハタの違いを把握し、用途に応じて正しく使い分けることが重要です。また、押印を間違えた際は訂正印や再発行など適切な対応を取り、焦らず誠実に行動しましょう。
印鑑を綺麗に押すためには朱肉の量や押し方に注意し、ミスを防ぐための事前確認も欠かせません。
さらに、印鑑なしの場合でも、サインや電子署名で対応できるケースがありますが、必ず担当者に確認して企業の方針に従うことが大切です。
入社承諾書の提出時には、添え状の同封や提出期限の厳守などマナーにも気を配りましょう。正しい知識と丁寧な対応を心がければ、入社承諾書はあなたの誠実さを伝える強力なツールになります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














