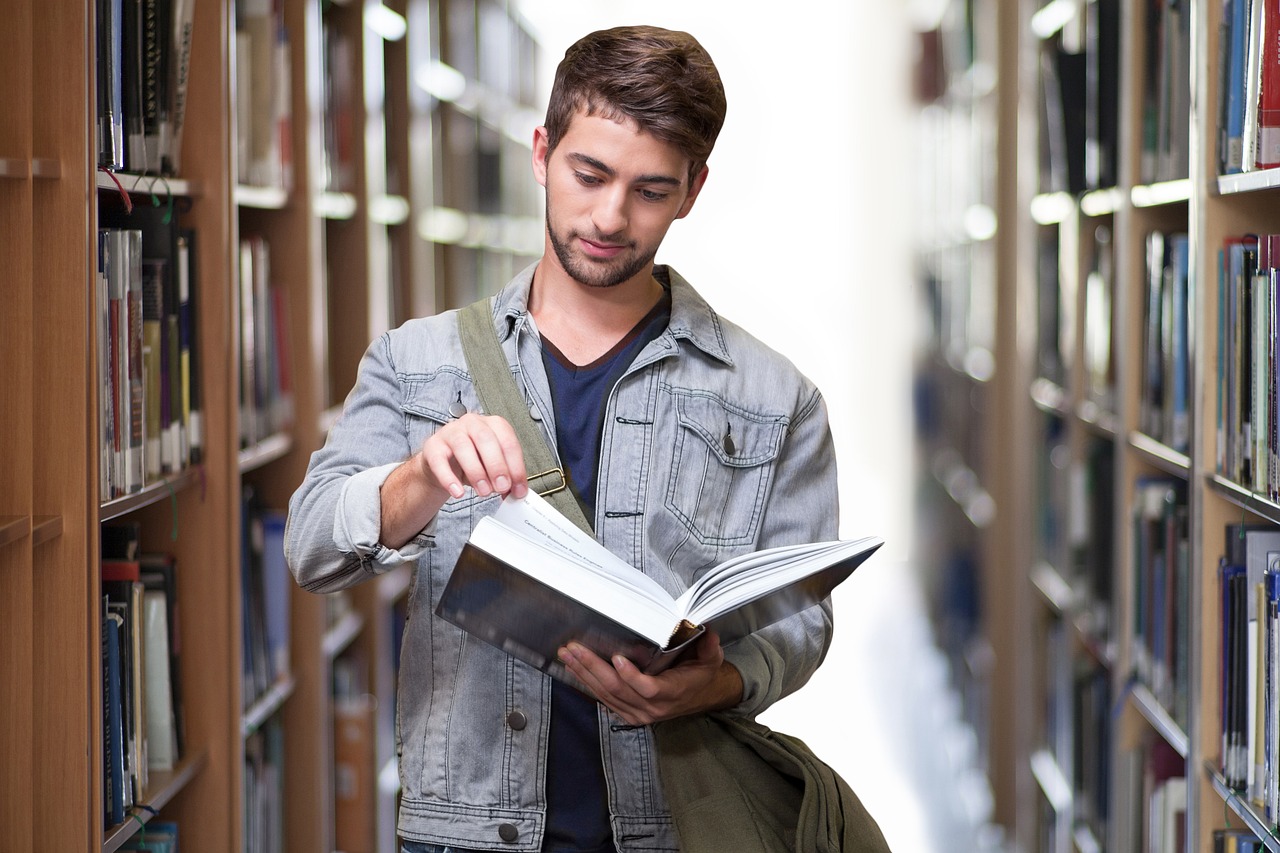理系のガクチカ完全ガイド|研究・実験・学外活動の書き方と例文
理系の就活で「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を聞かれたとき、研究テーマを挙げる学生は多いでしょう。
しかし、「専門的すぎて伝わらないかも」「成果がまだ出ていない」などの不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
実は、研究内容そのものよりも、課題発見・試行錯誤・成果に至るまでのプロセスをどう語るかが評価のカギになります。
この記事では、理系のガクチカで研究を使うメリット・デメリット・構成・書き方のコツ・例文までを詳しく解説します。
自分の研究経験を伝わるエピソードに変え、面接官に「一緒に働きたい」と思わせるガクチカを作りましょう。
ガクチカ作成のお助けアイテム
- 1ES自動作成ツール
- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成
- 2赤ペンESでガクチカを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに
- 3ガクチカのテンプレシート
- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える
- 4強み診断
- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる
理系のガクチカに研究を使うメリット

理系学生が就職活動で「ガクチカ」に研究を活用することには、さまざまな利点があります。研究は単なる成果発表ではなく、あなたの思考力・課題解決力・粘り強さを具体的に示す絶好のチャンスです。
ここでは、理系学生が持つ研究経験をどのように企業へ伝えると効果的なのかを、わかりやすく解説していきます。
- 論理的思考力をアピールできる
- 課題解決力を示せる
- 専門知識の深さを評価されやすい
- 研究過程での主体性を伝えられる
- 困難を乗り越えた経験を具体的に語れる
- 目標達成への粘り強さを証明できる
- 理系職種との親和性をアピールできる
①論理的思考力をアピールできる
研究活動では、仮説の設定、実験計画、データの分析、考察という一連のプロセスにおいて、常に論理的な思考が求められます。
ガクチカでこの流れを的確に説明することで、企業はあなたの「考え抜く力」や「筋道立てて説明できる力」を評価します。
特に理系職種では、課題を整理し、仮説を立て、結果を検証して結論に導くスキルが重視されます。
たとえば、「なぜその手法を採用したのか」「他の方法を検討した結果どう判断したのか」など、思考プロセスを明確に語ることが重要です。
自分の判断や考察がどのように成果に結びついたのかまで触れると、より説得力のある印象を残せるでしょう。
②課題解決力を示せる
研究の現場では、想定外のトラブルや実験の失敗は避けて通れません。そのたびに問題の原因を見つけ、改善策を考える姿勢が自然と身につきます。
ガクチカでは、その過程を具体的に説明することで「問題解決力」を強くアピールできます。企業は、想定外の課題に直面した際に、どのように分析し、どのように対応したかを重視します。
たとえば、データが思うように取れなかった場合に条件を変えたり、別の実験方法を試したりした経験を語ると良いでしょう。課題を冷静に整理し、論理的に対処した姿勢は、社会人になってからも通用します。
加えて、周囲と相談したり、他分野の知識を取り入れたりした経験を盛り込むと、柔軟な対応力も伝わります。
③専門知識の深さを評価されやすい
理系学生の研究経験には、専門知識と技術の裏付けがあります。ガクチカで研究テーマを取り上げることで、あなたの知識がどのように活かされたのかを明確に示せます。
たとえば、データ分析や化学反応、機械設計、プログラム開発など、研究分野ごとの具体的なスキルを例に出すと説得力が高まります。
また、知識そのものよりも「どのように使ったか」「どう応用したか」を説明することが大切です。単に専門性を語るだけではなく、それを用いて問題を発見し、改善に導いたプロセスを述べましょう。
さらに、専門外の人にもわかる言葉で説明する力も重要です。相手の理解度を考慮した伝え方ができれば、コミュニケーション力の高さも同時に伝えられます。
④研究過程での主体性を伝えられる
研究では、指導を待つだけでは成果は得られません。自分から行動を起こし、課題を設定し、進める力が問われます。ガクチカでは、この「主体的に動いた経験」を中心に語ると効果的です。
たとえば、研究の進め方を自分で提案したり、手法を見直したり、他メンバーと協力して実験効率を上げたりした経験などが該当します。企業が求めるのは「自ら課題を発見して行動できる人材」です。
そのため、主体性を伝える際には「なぜそう判断したのか」「どんな工夫をしたのか」を明確に述べると良いでしょう。
また、結果だけでなく、取り組みの背景やモチベーションも語ると、あなたらしさがより伝わります。自分の意志で行動したエピソードは、どの業界でも高く評価される要素です。
⑤困難を乗り越えた経験を具体的に語れる
研究では、失敗や行き詰まりを経験することが多くあります。こうした状況をどう乗り越えたかを語ることは、あなたの粘り強さや責任感を伝える絶好の機会です。
企業は、結果よりも「困難にどう対応したか」「何を学んだか」を重視します。
たとえば、実験結果が想定と異なった際に原因を突き止めるためデータを見直したり、仮説を修正して再挑戦したりした経験を語りましょう。
その際、「なぜ諦めなかったのか」「どのように気持ちを切り替えたのか」など、感情面も少し交えるとリアリティが増します。
困難の中でも前向きに考え、粘り強く努力したことを伝えると、信頼性のあるエピソードとして印象に残ります。
⑥目標達成への粘り強さを証明できる
研究は長期間にわたる地道な作業の積み重ねです。思うように進まない中で、モチベーションを保ち続けた経験は、社会人としての継続力を示す強いアピールになります。
ガクチカでは、粘り強さが結果としてどう活かされたかを伝えるとよいでしょう。
たとえば、実験条件を細かく変えながら何度も検証を繰り返した経験や、論文提出までのスケジュールを自分で管理した経験は、継続的な努力を示す好例です。
企業は、課題に時間をかけて向き合える人を高く評価します。困難を乗り越えながらも学びを得て前進したプロセスを丁寧に語ることで、結果以上にあなたの姿勢が伝わるでしょう。
⑦理系職種との親和性をアピールできる
研究経験は、理系職種との相性の良さを自然に示せます。データ処理、分析、検証、報告などのスキルは、企業の実務に直結しているためです。
ガクチカでは、研究を通じて得たスキルがどのように業務に活かせるのかを、具体的に結びつけて説明しましょう。
たとえば、開発職では「仮説を立てて検証する力」、品質管理職では「データの精度を保つ慎重さ」など、職種ごとに異なる要素を強調できます。
自分の研究経験が企業の目標にどう貢献できるのかを意識して話すことで、採用担当者に「入社後に活躍できる人」という印象を与えられるでしょう。
理系のガクチカに研究を使うデメリット

理系学生にとって研究は大きなアピール材料ですが、使い方を誤ると印象を下げてしまうこともあります。
研究内容に偏りすぎると、伝わりにくかったり、他の学生と差がつきにくかったりする点がデメリットです。ここでは、理系のガクチカで注意すべき落とし穴を具体的に解説します。
- 専門的すぎて伝わりにくい
- 成果重視に偏りやすい
- 他の学生と差別化しにくい
- 専門用語が多く選考官に理解されにくい
- 研究段階では成果が出ていない場合がある
- 研究以外の人間的魅力が伝わりづらい
- 内容が抽象的になりやすい
①専門的すぎて伝わりにくい
理系の研究内容は専門性が高く、採用担当者が理解しづらい場合があります。とくに人事担当者が文系出身である場合、研究内容そのものを深く理解してもらうのは難しいでしょう。
そのため、ガクチカで研究を語る際は、専門的な説明に偏らず「どんな課題に挑戦したのか」「どんな工夫をしたのか」といった本質的な部分に焦点を当てることが大切です。
専門的な話をやさしい言葉に置き換えたり、身近な例を交えたりすることで、より伝わりやすくなります。研究成果そのものよりも、思考の過程や取り組む姿勢を中心に語ることがポイントです。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②成果重視に偏りやすい
理系学生が陥りがちなのが、「成果をどれだけ出したか」を強調しすぎてしまうことです。もちろん結果を出すことは大切ですが、企業は「結果に至るまでの過程」や「努力の方向性」を重視しています。
結果だけを伝えると、チームワークや試行錯誤の姿勢といった人間的な魅力が伝わりにくくなります。研究の成果を語るときは、その裏にある課題解決の工夫や、粘り強く取り組んだ姿勢を補足してください。
過程を含めて話すことで、説得力のあるガクチカになります。
③他の学生と差別化しにくい
理系学生の多くが「研究」をガクチカに選ぶため、内容が似通いやすく差別化が難しい点も課題です。特定のテーマや実験内容に個性を出すのは容易ではありません。
だからこそ、他の学生と同じ研究分野でも「どのように工夫したか」「どんな困難をどう乗り越えたか」を具体的に話すことが差を生む鍵になります。
また、研究に取り組む姿勢や考え方、チームとの関わり方など、あなた独自の視点を盛り込むと印象に残るガクチカに仕上がります。
単なる研究紹介で終わらせず、「自分のストーリー」として語ることが重要です。
④専門用語が多く選考官に理解されにくい
理系のガクチカでは、つい専門用語を多く使ってしまいがちです。しかし、採用担当者はその分野の専門家ではないことが多いため、難しい表現が多いと理解されにくくなります。
ガクチカは「伝わってこそ意味がある」ため、専門用語を使う場合は簡単な説明を添えることを意識しましょう。
たとえば、「培養細胞を用いた検証」という表現を「細胞を使ってデータを集めた」と言い換えるだけでも伝わりやすくなります。
専門知識を相手の立場で説明できる力は、社会人になってからも重要なスキルです。
⑤研究段階では成果が出ていない場合がある
研究は長期的な取り組みであり、就職活動の時点ではまだ結果が出ていないケースも多くあります。成果が出ていないと、自信を持って話せないと感じる人もいるでしょう。
しかし、企業は結果よりも「どう取り組んだか」「どんな工夫をしたか」を評価しています。途中経過でも、試行錯誤の中で得た学びや成長を伝えれば十分に魅力的です。
研究の進行状況を正直に伝えつつ、過程で身につけたスキルや考え方を中心に語ると、誠実で前向きな印象を与えられます。
⑥研究以外の人間的魅力が伝わりづらい
研究にフォーカスしすぎると、協調性やリーダーシップなどの人間的な魅力が伝わりにくくなります。企業が求めるのは「一緒に働きたい」と思える人物像であり、学問的な能力だけでは評価されません。
そのため、研究エピソードを語る際には、チームでの連携や周囲とのコミュニケーションを意識的に取り入れることが大切です。
また、研究外での経験――サークル活動やアルバイトなど――に触れると、バランスの取れた人柄が伝わります。研究の枠を超えて、多面的な自分を表現することを意識しましょう。
⑦内容が抽象的になりやすい
研究テーマが抽象的な場合、説明がぼんやりとしてしまいがちです。たとえば「課題解決に取り組んだ」「工夫を重ねた」といった表現だけでは、具体的なイメージが湧きません。
ガクチカでは、できるだけ数字や具体例を交えて説明すると、内容に説得力が生まれます。「試行回数を増やした」「3か月間継続して改善を続けた」など、実際の取り組みを具体的に語りましょう。
抽象的な話を具体化する力は、論理的思考の証でもあります。自分の経験を具体的に伝えることで、印象に残るガクチカになります。
企業が理系学生のガクチカで見ているポイント
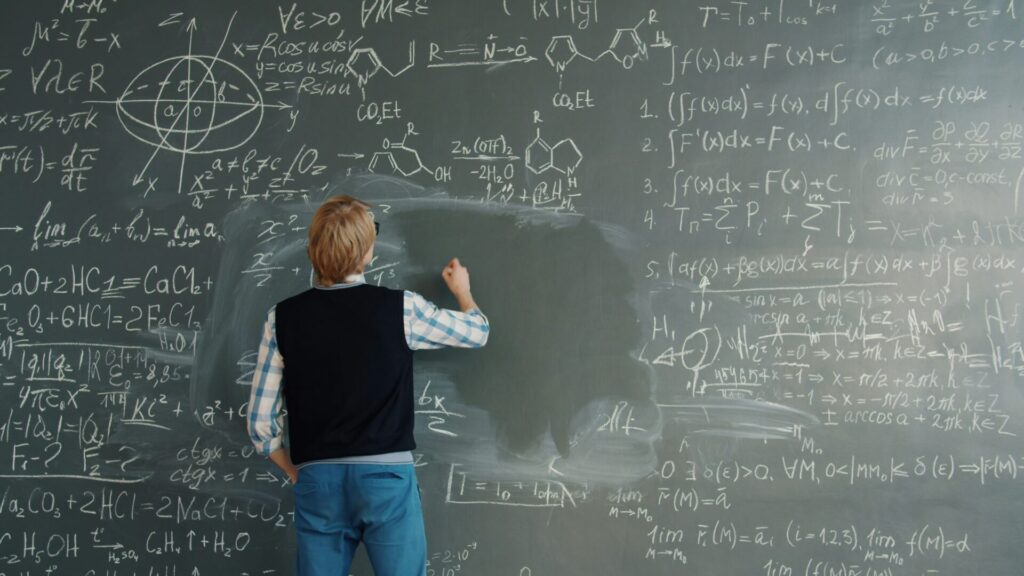
理系学生のガクチカでは、単に研究内容や成果だけでなく、「どのような姿勢で取り組んだか」「どう課題を解決したか」が重視されます。
企業は理系ならではの強みを見極めるため、行動の背景や思考プロセスを細かく見ています。ここでは、企業が注目する7つの評価ポイントを詳しく解説します。
- 課題発見力と分析力
- 行動力と主体性
- チームワークと協調性
- 粘り強さと継続力
- 論理的思考と問題解決能力
- 挑戦意欲と成長志向
- 成果よりもプロセス重視の姿勢
①課題発見力と分析力
企業は、問題を見つけ出し、その原因を的確に分析できる人材を高く評価します。理系の研究では、現象を観察して課題を抽出し、仮説を立てて検証する力が自然と身につきます。
ガクチカでは、どのように問題を発見し、なぜその点に注目したのかを明確に説明しましょう。たとえば、研究の進行中に実験データのばらつきに気づき、その要因を探った経験などは好印象です。
論理的に考え、原因を分解して改善策を導き出す姿勢は、どの業種でも求められる普遍的なスキルです。
②行動力と主体性
理系学生の研究活動は、課題を自ら設定して進める機会が多いため、主体性や行動力をアピールするチャンスが豊富です。企業は「指示を待つ人」ではなく、「自分から行動できる人」を求めています。
ガクチカでは、どのように自発的に行動したかを具体的に示すことが大切です。たとえば、研究方法を改善するために文献を調べたり、新しい実験装置を導入したりした経験などが効果的です。
主体的に動いた結果、チームの効率が上がったり、研究の方向性が明確になったりしたエピソードは高く評価されます。
③チームワークと協調性
理系の研究は一人で完結しないことが多く、共同研究やチーム実験を通じて他者と協力する力が求められます。
企業は、周囲と円滑にコミュニケーションを取り、チームとして成果を出せるかどうかを重視します。ガクチカでは、協力の中で自分が果たした役割や意識した工夫を具体的に伝えましょう。
たとえば、メンバー間で意見が対立した際に調整役として動いたり、情報共有を効率化する仕組みを作ったりした経験などです。
協調性を「受け身」ではなく「能動的なサポート」として語ることで、組織で活躍できる人物像を印象づけられます。
④粘り強さと継続力
理系の研究は長期的な取り組みが多く、思うように進まない時期を経験するのが一般的です。企業は、そうした困難な状況でも粘り強く努力を続けられる人を評価します。
ガクチカでは、試行錯誤を繰り返しながら結果を出した経験を中心に話すとよいでしょう。
たとえば、数十回の実験を経て成功にたどり着いたり、失敗のたびに原因を分析して改善策を実行したりした過程を具体的に説明します。
継続力は、仕事における「責任感」や「忍耐力」と直結しており、採用担当者の印象に強く残ります。
⑤論理的思考と問題解決能力
理系の強みとして代表的なのが、論理的に考えて課題を整理し、根拠をもとに解決策を導く力です。企業は、感覚ではなくロジックで判断できる人材を求めています。
ガクチカでは、「問題→仮説→検証→結論」という流れを意識して話すと、説得力のある内容になります。
たとえば、「実験が失敗した原因を分析し、条件を変えて再度検証した」といった経験を整理して伝えると効果的です。
論理的思考力は、理系職種だけでなく企画職やコンサルティングなどにも通じる汎用的なスキルです。
⑥挑戦意欲と成長志向
企業は、現状に満足せず、新しいことに挑戦し続けられる人を求めます。理系の研究では、未知の課題に向き合い、自分なりの方法で答えを探す経験が多いでしょう。
ガクチカでは、その挑戦の過程や、試行錯誤を通じてどんな成長を遂げたのかを具体的に語ることが重要です。
たとえば、新しい装置を扱えるようになるまで自主的に勉強したり、異分野の知識を取り入れたりした経験があれば、成長意欲を示せます。
困難な環境でも前向きに挑戦し続ける姿勢は、採用担当者の共感を呼びやすい要素です。
⑦成果よりもプロセス重視の姿勢
理系学生の多くは「成果」を中心に語りがちですが、企業はその裏にある「プロセス」をより重視します。
なぜなら、結果だけでは再現性が分からず、過程を見て初めてその人の考え方や行動特性が理解できるからです。
ガクチカでは、「どのように取り組んだのか」「どんな工夫をしたのか」「そこから何を学んだのか」を意識して説明しましょう。成果が出ていない場合でも、プロセスを丁寧に語れば評価につながります。
継続的に改善を重ねた姿勢や、そこから得た学びを伝えることで、成長可能性のある人材として印象づけられます。
理系学生がガクチカを考える際の注意点

理系学生がガクチカを作成する際は、研究に意識が偏りすぎないよう注意が必要です。企業が見ているのは「何をしたか」よりも「どう考え、どう行動したか」。
つまり、研究テーマそのものではなく、その過程で得た学びや成長を評価しています。ここでは、理系学生が見落としやすい7つの注意点を具体的に解説します。
これらを意識することで、説得力と人間味のあるガクチカに仕上げられるでしょう。
- 専門用語を使いすぎない
- 成果よりも過程を重視する
- 聞き手に伝わる表現を意識する
- 志望企業との関連性を持たせる
- 他者との比較ではなく自分の変化を語る
- 結論から話す構成を意識する
- 失敗体験もポジティブに伝える
①専門用語を使いすぎない
理系学生のガクチカでは、専門的な用語を多用してしまう傾向があります。自分にとっては当たり前の言葉でも、採用担当者にとっては難解で、かえって伝わりにくくなることが多いのです。
人事担当者は必ずしも理系のバックグラウンドを持っていないため、「わかりやすさ」を意識して話すことが何より大切です。
たとえば「分子動力学シミュレーション」を「分子の動きをコンピュータで再現する研究」と言い換えるだけで、理解度は大きく変わります。専門性を損なわずに平易な表現へ置き換えることがポイントです。
また、聞き手の反応を見ながら補足を入れたり、図や例を使って説明したりするとさらに効果的です。
②成果よりも過程を重視する
ガクチカでは、研究の結果よりも、どのような考え方で行動したかという「過程」が評価されます。成果ばかりを強調すると、運や環境に左右された印象を与えかねません。
企業が知りたいのは、「困難に直面したときにどう行動したのか」「課題をどのように解決したのか」です。
たとえば、失敗の原因をデータ分析から特定し、実験条件を調整して再挑戦したというエピソードであれば、課題解決力と粘り強さを同時に伝えられます。
過程を語ることで、思考力や成長意欲などの人間的な要素が浮かび上がります。
また、結果が出ていなくても、「過程で得た学び」や「次に生かした工夫」を添えることで、前向きな印象を与えられるでしょう。
③聞き手に伝わる表現を意識する
どんなに内容が良くても、聞き手に伝わらなければ意味がありません。ガクチカでは「伝える力」も評価の対象になります。
自分が話したいことを詰め込むのではなく、相手が理解しやすい流れと構成を意識しましょう。効果的なのは、「結論→理由→具体例→結果」という順序で話す方法です。
最初に要点を伝えることで聞き手の理解がスムーズになり、話全体の印象が整理されます。さらに、話すテンポや声のトーンも大切です。
面接中は、説明に集中するあまり感情表現が乏しくなりがちですが、表情や抑揚をつけることで伝わり方が格段に変わるでしょう。
④志望企業との関連性を持たせる
ガクチカの内容が素晴らしくても、志望企業との関連性が薄いと印象に残りません。企業は、自社の業務や文化にどう貢献できるかを知りたいと考えています。
そこで重要なのが、「自分の経験を企業の強みや事業内容に結びつけて話すこと」です。
たとえば、研究で得たデータ分析スキルを「製品開発の品質管理に生かせる」と結びつけたり、実験で培った粘り強さを「長期プロジェクトでの改善活動に活用できる」と説明したりすると効果的です。
志望企業が求める人物像を事前に調べ、それに合わせたエピソードを選ぶことが重要です。
⑤他者との比較ではなく自分の変化を語る
ガクチカでは、他の学生と比べて優れている点をアピールするよりも、自分自身の成長を中心に語ることが効果的です。
企業が知りたいのは「どれだけ成果を出したか」ではなく、「その経験を通じてどう変わったか」。
たとえば、「研究の初期は失敗が続いたが、原因を突き止めて再現性の高い手法を確立できた」など、過去と現在を比較する構成にすると説得力が増します。
また、「当初は指示待ちだったが、自分から課題を見つけて提案できるようになった」など、意識の変化を含めて話すと成長が明確になります。
自分の内面の変化を言語化できる人は、入社後も学び続ける力があると判断され、評価が高まりやすいです。
⑥結論から話す構成を意識する
面接やエントリーシートでは「結論→根拠→詳細→学び」という順序がより効果的です。
結論を最初に述べることで、聞き手が全体像を理解しやすくなり、話の流れもスムーズになります。
たとえば、「私が最も力を入れたのは〇〇の研究で、そこで課題解決力を磨きました」と冒頭で述べてから、背景や具体的な行動を補足する形が理想です。
話を整理して伝えるスキルは、社会人に必須の能力でもあります。構成を意識することで、あなたの話は簡潔かつ論理的に聞こえ、理系学生の強みである思考の明確さを最大限に引き出せるでしょう。
⑦失敗体験もポジティブに伝える
理系の研究には失敗がつきものです。ガクチカでは、失敗を「悪いこと」と捉えず、「成長のきっかけ」として前向きに語ることが大切です。
企業は、失敗そのものではなく、そこから何を学び、次にどう行動したかを見ています。
たとえば、「仮説が誤っていたため実験結果が出なかったが、分析を重ねる中で新しい発見につながった」という話は、柔軟性と探究心を同時に示せます。
失敗を隠すよりも、自分なりの工夫や改善策を添えて語ることで、成長意欲を印象づけられます。
ネガティブな経験をプラスに変換できる人は、どんな環境でも前向きに成長できる人材だと評価されます。
理系ガクチカの正しい構成と書き方(STAR+Pフレームワーク)
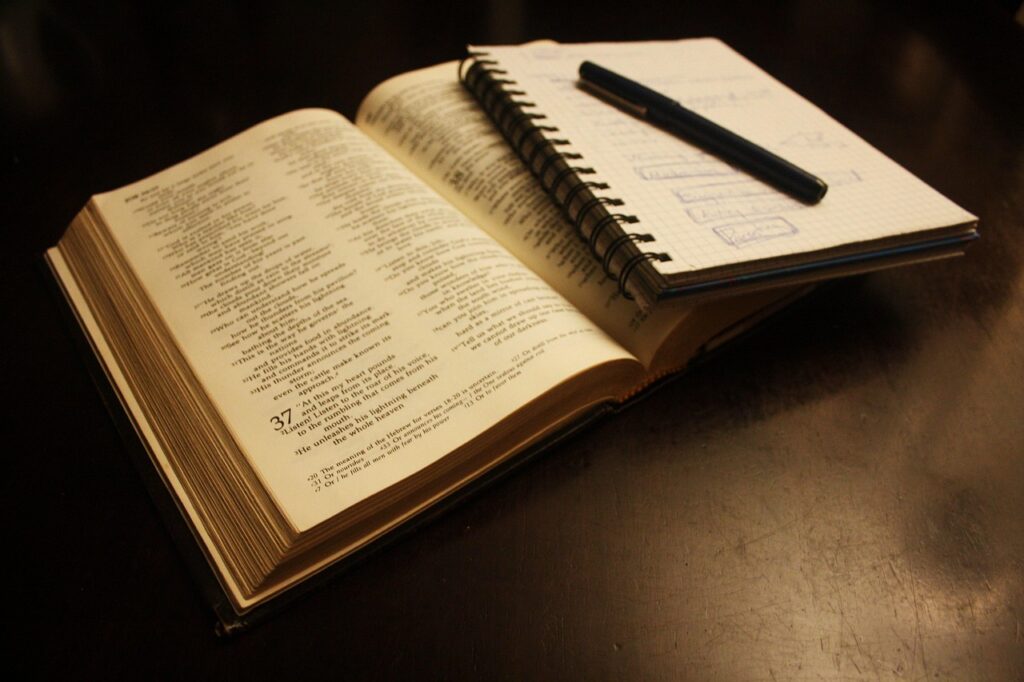
理系学生がガクチカを書く際は、研究や実験などの経験を「論理的かつわかりやすく」整理して伝えることが重要です。その際に役立つのが「STAR+Pフレームワーク」です。
これは、Situation(状況)→Task(課題)→Action(行動)→Result(結果)に加えて、Process(過程)とPersonality(人柄)を補足する構成です。
理系学生の強みである論理性と再現性を活かせる手法です。ここでは、各ステップの書き方をより深く掘り下げて解説します。
- Situation(状況設定)の書き方
- Task(課題・目的)の明確化方法
- Action(行動)の具体的な書き方
- Result(結果)の整理と伝え方
- Process(過程)の深掘り方法
- Personality(人柄・価値観)の表現方法
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①Situation(状況設定)の書き方
まずは、ガクチカの背景となる「状況(Situation)」を簡潔に説明します。
ここでは、研究の内容を細かく語るよりも、「いつ」「どこで」「どんなテーマに取り組んだのか」を短く整理し、全体像を明確に伝えることが大切です。
たとえば、「学部3年の研究で、環境負荷を減らす新素材の開発に挑戦した」など、テーマと目的を一文で伝えると印象に残ります。
そのうえで、「なぜその研究を選んだのか」「どんなきっかけで関心を持ったのか」といった動機を添えると、主体性が感じられる内容になります。
構成の中に、自分の意図や興味の方向性を自然に織り込むと、次の「課題設定」にスムーズにつながります。
②Task(課題・目的)の明確化方法
Task(課題)は、あなたがその状況の中で「何を目的に、どんな問題を解決しようとしたのか」を明確にするパートです。
たとえば、「既存の実験方法では結果の再現性が低く、信頼できるデータを得るために新しい測定手法を検討した」など、課題の本質を具体的に説明しましょう。
その際、「なぜその問題を重要だと感じたのか」という自分の考えを加えると、主体的な姿勢が伝わります。
また、課題の規模が大きい場合は、「最終的なゴール」と「自分の担当範囲」を分けて説明することで、話の焦点が明確になります。
企業は「自分で課題を見つけ、自律的に行動できる人」を求めているため、課題設定の部分で思考の深さを示すことが大切です。
③Action(行動)の具体的な書き方
Action(行動)は、ガクチカの中でも最も重視される部分です。ここでは、「自分がどのように考え、どんな行動を取ったのか」を具体的に描きます。
たとえば、「再現性の低さを改善するため、測定条件を細かく変えてデータのばらつきを分析した」「結果が安定しなかった原因をチームで共有し、新しい試薬を導入した」などがあります。
課題に対して取った具体的な行動を明確にしましょう。また、個人の努力だけでなく「チームの中での役割」や「他者との協力の仕方」を入れることで、協調性やリーダーシップも自然に伝わります。
企業は、「自分の考えを行動に移せるか」を見ているため、挑戦や工夫の過程を臨場感を持って語ることが大切です。
④Result(結果)の整理と伝え方
Result(結果)は、あなたの行動によってどんな成果や変化が得られたかをまとめる部分です。
たとえば、「測定誤差を20%減らすことに成功した」「学会で研究成果を発表した」といった具体的な数値や実績は効果的です。
さらに、「試行錯誤の中で粘り強く改善を続ける姿勢が身についた」といった内面的な成長も伝えましょう。
成功だけでなく、「思うような結果が出なかったが、データ分析の精度を高める工夫を学んだ」など、失敗を通じた学びをプラスに変換することも大切です。
また、結果を語る際は「客観性」を意識し、自分の行動との因果関係を明確に説明すると説得力が増します。企業は成果よりも「成長プロセスに一貫性があるか」を見ています。
⑤Process(過程)の深掘り方法
Process(過程)は、あなたの取り組みを「どれだけ粘り強く、論理的に進めたか」を示す部分です。理系の研究は時間がかかる分、試行錯誤の積み重ねが評価されやすいのです。
たとえば、「初期段階では仮説がうまく機能せず、条件を変えながら再検証を続けた」「エラーが出るたびに原因を分析し、数十回の再実験を重ねた」など、地道な取り組みを具体的に描写しましょう。
さらに、「改善策を立案する際にチームで意見を出し合った」「他の研究室の知見を取り入れた」といった協働のプロセスを加えると、柔軟性や学びの姿勢も伝わります。
プロセスの描写には「考える→試す→修正する→成果に近づく」という循環を意識すると、論理的かつ一貫性のある文章になりますよ。
⑥Personality(人柄・価値観)の表現方法
最後のPersonality(人柄・価値観)は、あなたのガクチカを「他の学生と差別化する鍵」となる部分です。企業は、スキルよりも「一緒に働きたいと思える人物か」を見ています。
たとえば、「失敗を恐れずに挑戦する姿勢を大切にしている」「チーム全体が成果を出せるように支える立場を意識して行動している」といった一言を添えるだけでも、あなたの人間性が伝わります。
さらに、「その価値観が形成された背景」も簡単に触れると、エピソードに深みが出ます。たとえば、「中学時代のロボットコンテストでチームで課題を乗り越えた経験が原点になっている」などです。
研究を通じて培った考え方を、自分の軸として自然に語ることで、技術と人間性の両面で魅力的な人物像を作り上げられます。
研究以外でも使える!理系学生のガクチカテーマ

理系学生のガクチカというと「研究」をテーマにしがちですが、実は研究以外の経験にも多くのアピールチャンスがあります。
企業が評価するのは「どんな分野で努力したか」ではなく、「どう考え、どう行動し、どう成長したか」です。ここでは、研究以外の経験からガクチカに使える6つのテーマを紹介します。
それぞれの経験を通して、理系ならではの強みを活かす方法を見ていきましょう。
- アルバイトでの改善活動
- サークル活動での組織運営
- 部活動でのチーム貢献
- インターンでの課題解決経験
- ボランティアでの社会貢献
- 個人開発・資格取得の努力
①アルバイトでの改善活動
アルバイト経験は、多くの学生が持つ身近なテーマですが、工夫次第で大きな強みに変えられます。
特に理系学生の場合、データや論理的な分析を活かして「業務改善に取り組んだ経験」をアピールすると高く評価されます。
たとえば、「作業効率を上げるためにマニュアルを見直した」「顧客アンケートを集計してサービス改善に役立てた」といったエピソードは、現場で課題を見つけ、改善策を実行できる力を示せます。
企業が注目するのは「受け身で働く姿勢」ではなく、「どうすればもっと良くできるかを考えた主体性」です。数字やデータを用いて効果を説明すると、理系らしい論理的なガクチカになります。
②サークル活動での組織運営
サークル活動は、ガクチカで「チームワーク」や「企画力」をアピールする絶好のテーマです。特に理系学生は、論理的な思考と計画性を活かして組織運営に関わった経験を語ると説得力が高まります。
たとえば、「イベントの参加率が低下していたため、アンケートを実施して運営方針を改善した」「学祭での出展に向けて予算とスケジュールをデータで管理した」といった取り組みがあります。
これらは、課題発見力とリーダーシップを同時にアピールできます。
また、単なる役職の説明で終わらせず、「どんな課題に直面し、どう解決したか」「チームをどのようにまとめたか」を具体的に伝えることが大切です。
理系らしい分析的な思考と柔軟な対応力を組み合わせると、実践的なマネジメント力として評価されやすくなります。
③部活動でのチーム貢献
部活動は、努力や継続力、協調性を伝えるのに最適なテーマです。
理系学生の中には体育会系の部活に所属している人も多く、研究とは異なる文脈で「目標に向かって粘り強く努力した経験」を語れます。
たとえば、「試合で勝てなかった原因を分析し、トレーニング内容をデータ化して改善した」「チームメンバーの練習参加率を上げるためにスケジュール共有の仕組みを作った」などがあります。
課題発見から解決までのプロセスを明確に話すと好印象です。企業は、組織での協調性や責任感を重視しており、「自分の努力がチーム全体にどう貢献したか」を具体的に語ると評価が高まります。
理系学生ならではの分析力やロジカルな問題解決の姿勢を部活のエピソードに落とし込むことで、個性あるガクチカになります。
④インターンでの課題解決経験
インターンシップの経験は、実際の職場での行動力や課題対応力を示せる実践的なテーマです。特に理系学生の場合、データ分析や技術提案など、成果を具体的に示しやすい点が強みになります。
たとえば、「製造現場で歩留まり改善の提案を行い、ミス率を10%削減した」「開発プロジェクトで新しい検証方法を提案し、効率を向上させた」などの経験は、企業目線での思考力と実行力を伝えられます。
インターンでは短期間でも「自分なりの考えを形にしたプロセス」を語ることが重要です。
単なる体験談ではなく、「どんな課題をどう発見し、どのように行動したか」を明確に伝えると、職務適性の高さが際立ちます。
実務経験を通じて理系の専門性を社会的価値へつなげたエピソードは、非常に評価されやすいです。
⑤ボランティアでの社会貢献
ボランティア活動は、社会的視点や主体性を示せるテーマとして注目されています。理系学生の場合、「問題解決の手段を科学的に考えた」などの要素を加えると、よりユニークで印象的なガクチカになります。
たとえば、「地域の清掃活動で廃棄物の種類を分類し、効率的な回収ルートを提案した」「子ども向け科学イベントで、実験を通じて理科の面白さを伝えた」といった取り組みが挙げられます。
こうした社会的意義のある活動を理系の視点で語ると効果的です。企業は社会貢献意識の高い学生を好みますが、特に理系職では「技術を通じて社会課題を解決できるか」が重視されます。
ボランティア経験を「自分の専門性や価値観」と関連づけて説明すると、個性と社会性の両方をバランスよく伝えられるでしょう。
⑥個人開発・資格取得の努力
個人での開発経験や資格取得への努力は、主体性や探究心を示す強力なガクチカになります。特に理系学生の場合、「自ら課題を設定して学び続ける姿勢」が評価されやすいです。
たとえば、「Pythonを独学で学び、データ分析ツールを自作した」「統計検定や応用情報技術者試験に挑戦し、実務につながるスキルを身につけた」といったエピソードがあります。
こうした経験は、自律的に成長できる人材であることを示せます。資格や開発実績は成果が明確に見えるため、客観的な評価を得やすいのも利点です。
また、学業や研究と両立して努力した点を強調すると、時間管理力や継続力もアピールできます。
企業は「学び続ける姿勢」を重視するため、自己成長を実感できる取り組みをガクチカに活用することが有効です。
理系学生のガクチカ例文【研究・実験・学外活動別】

理系学生のガクチカは、研究や実験に限らず、学外での活動にも数多くの魅力的なエピソードがあります。ここでは、研究・実験・アルバイト・サークルなど、シーン別に具体的なガクチカ例文を紹介します。
自分の経験に近いパターンを参考にすることで、より説得力のある自己PRを作成できるでしょう。
- 研究テーマを活かした例文(専門性と探究心のアピール)
- 実験をテーマにした例文(課題解決力のアピール)
- 研究成果が出なかった場合の例文(粘り強さのアピール)
- 学会発表・コンテスト参加の例文(挑戦意欲のアピール)
- アルバイト経験を活かした例文(責任感と改善力のアピール)
- サークル活動の例文(チームワークとリーダーシップのアピール)
- 部活動の例文(努力と継続力のアピール)
- インターンシップの例文(実務経験と課題対応力のアピール)
- ボランティア活動の例文(社会貢献と主体性のアピール)
- 個人開発・自主研究の例文(創造力と行動力のアピール)
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①研究テーマを活かした例文(専門性と探究心のアピール)
理系学生にとって、研究テーマは最も自然に自分の強みを示せる題材です。ここでは、専門分野への探究心や課題解決への努力を伝えることを意識した例文を紹介します。
研究の成果だけでなく、「なぜ取り組んだのか」「どんな工夫をしたのか」を中心に描くと、より魅力的なガクチカになります。
| 私は学部3年で、環境に優しい新素材の開発をテーマに研究を行いました。最初は目的の反応がうまく進まず、仮説の立て直しから始めました。 原因を探るため、先行研究を分析し、試薬の配合比率を少しずつ変えて実験を繰り返しました。 その過程で、条件を一つ変えるだけで結果が大きく変化することを実感し、データの正確性を追求する姿勢が身につきました。 半年後、安定した生成が可能になり、学内発表で成果を報告できたときは大きな達成感を得ました。この経験を通して、課題を論理的に捉え、粘り強く取り組む力を養うことができました。 |
研究をテーマに書く際は、結果よりも「どのように問題を分析し、改善していったか」を重視すると説得力が高まります。
失敗や試行錯誤のプロセスを具体的に描くことで、探究心と論理的思考力を効果的に伝えられます。
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
②実験をテーマにした例文(課題解決力のアピール)
実験をテーマにしたガクチカでは、失敗からどう立て直したかや、課題をどう解決したかを伝えることが重要です。
結果だけでなく、試行錯誤のプロセスを描くことで、理系学生ならではの課題対応力をアピールできます。
| 私は物理化学の実験で、反応速度の測定データにばらつきが生じるという課題に直面しました。最初は測定機器の精度に問題があると思い、何度も再測定しましたが改善しませんでした。 そこで、チームで作業工程を見直し、温度や溶液濃度などの条件を細かく管理する新しい手順を導入しました。その結果、データの誤差が大幅に減り、安定した結果を得ることができました。 この経験から、問題を一つの視点で判断せず、多角的に検証する姿勢を身につけました。 |
実験をテーマにする場合は、「問題の発見」と「改善策の実行」の2点を明確に書くことがポイントです。
単なる成功体験ではなく、困難をどう克服したかを具体的に描くことで、課題解決力を効果的に伝えられます。
③研究成果が出なかった場合の例文(粘り強さのアピール)
研究では、成果が思うように出ないことも多いものです。そんなときにどう考え、どう努力を続けたのかを描くことで、粘り強さや問題解決への姿勢を伝えます。
| 私は化学実験で、目的とする化合物の合成が半年以上成功しませんでした。 反応条件を変えても結果は得られず、何度も失敗が続きましたが、原因を突き止めるためにデータを細かく比較し、論文を調べながら仮説を立て直しました。 試行を重ねるうちに、触媒の保存状態が影響していることを発見し、そこを改善することで安定した結果を得られました。 この経験を通じて、結果が出ない時こそ冷静に原因を探り、粘り強く取り組む重要性を学びました。 |
成果が出なかった経験を書くときは、失敗の描写をネガティブにせず「学びや気づき」を強調することが大切です。
結果よりも努力や工夫の過程を中心に書くと、前向きで成長を感じさせる文章になります。
④学会発表・コンテスト参加の例文(挑戦意欲のアピール)
学会やコンテストの経験は、挑戦意欲や成長意識をアピールする絶好のテーマです。結果よりも、準備や発表を通じて得た気づきや努力を具体的に伝えましょう。
| 私は研究成果を学会で発表する機会を得ましたが、人前で話すことが苦手で緊張していました。発表までの1か月間、指導教員や仲間とリハーサルを重ね、専門用語をわかりやすく説明する練習を行いました。 本番では質問にも落ち着いて対応でき、理解してもらえたことに達成感を覚えました。この経験を通じて、伝える力と準備の大切さを学び、苦手意識を克服できました。 |
挑戦をテーマにする場合は、「なぜ挑戦したのか」と「その過程で何を得たのか」を明確に書くと効果的です。挑戦を通して成長した部分を伝えると、意欲的な印象を与えられます。
⑤アルバイト経験を活かした例文(責任感と改善力のアピール)
アルバイトは、身近ながら責任感や工夫を示しやすいテーマです。特に理系学生の場合、論理的な思考を活かした改善活動を取り上げると効果的です。
| 私は飲食店でアルバイトをしており、ピーク時の混雑でオーダーミスが頻発していました。そこで、注文内容をスタッフ間で共有できるメモ表を提案し、業務の流れを可視化しました。 導入後はミスが大幅に減り、作業効率も向上しました。この経験を通じて、自分の提案で職場を改善できる達成感を得るとともに、周囲と協力しながら問題を解決する力を磨きました。 |
アルバイト経験では、単に「頑張った」ではなく「課題を見つけ、どう改善したか」を示すとよいでしょう。数字や具体的な変化を加えると、より説得力が増します。
⑥サークル活動の例文(チームワークとリーダーシップのアピール)
サークル活動では、仲間と協力して成果を出した経験がアピールになります。理系らしく「データ管理」「計画性」「分析的思考」などを絡めると効果的です。
| 私はサークルで文化祭イベントの企画リーダーを務めました。当初は参加者が少なく、運営方針を見直す必要がありました。 メンバーから意見を集め、アンケート結果を基に改善策を立てたところ、来場者数が前年より1.5倍に増加しました。チーム全員が目標を共有し、役割を明確にしたことで達成感を得ました。 この経験から、協調性と責任感の大切さを実感しました。 |
サークル活動をテーマにするときは、「自分の役割」と「チーム全体への貢献」を明確に描くことが重要です。客観的な数字を加えると、説得力のあるガクチカになります。
⑦部活動の例文(努力と継続力のアピール)
部活動のエピソードは、継続力や努力を伝えるのに最適です。勝敗よりも「努力の過程」と「チームへの貢献」を重視して書くと印象が良くなります。
| 私はテニス部に所属し、最後の大会で団体戦のレギュラーを目指して練習を続けました。成績が伸び悩む時期もありましたが、フォームを撮影して改善点を分析し、日々の練習内容を記録して工夫しました。 最終的に補欠からレギュラーに昇格し、チームの勝利に貢献できました。この経験から、目標に向かって継続することの大切さを学びました。 |
部活動を書く際は、結果よりも「どう努力を続けたか」を中心に書くと好印象です。地道な工夫や成長のプロセスを具体的に描くと、説得力が増します。
⑧インターンシップの例文(実務経験と課題対応力のアピール)
インターン経験は、実務的な課題への取り組みを通して、分析力や行動力を示せるテーマです。実際の成果や学びを具体的に描くことが鍵になります。
| 私はメーカーのインターンで、製品検査工程の効率化を担当しました。作業時間のばらつきを分析し、作業手順を見直すことで、1人あたりの処理時間を10%短縮できました。 社員の方々と協力しながら改善を進めたことで、職場の雰囲気や仕事の流れを理解できました。この経験を通じて、現場での課題解決にはコミュニケーションとデータ分析の両立が重要だと学びました。 |
インターンのガクチカでは、「自分の行動がどんな成果を生んだか」を具体的に示すと効果的です。実務経験を学びに結びつける構成を意識してください。
⑨ボランティア活動の例文(社会貢献と主体性のアピール)
ボランティア経験は、社会的意識や行動力を伝えるのに適しています。理系学生は、活動に科学的視点を加えると個性を出しやすくなります。
| 私は地域の清掃ボランティアに参加し、ごみの種類ごとに分別効率を調べて改善提案を行いました。結果、回収時間を短縮でき、活動後には他の団体にも方法を共有しました。 自分の知識を活かして社会の課題に取り組めたことで、学びを実社会に応用する意識が高まりました。この経験を通して、主体的に行動し、周囲と協力して成果を出す力を磨けました。 |
ボランティア活動を書くときは、「自分の行動が社会にどう影響したか」を具体的に伝えると印象が強まります。理系的な視点や工夫を入れると差別化ができます。
⑩個人開発・自主研究の例文(創造力と行動力のアピール)
自主的な活動は、自分で課題を見つけて解決する力を示す絶好のテーマです。理系学生は、技術的な取り組みや自己成長を具体的に語ると魅力が伝わります。
| 私は独学でPythonを学び、大学の授業で扱う実験データを自動で整理できるプログラムを作成しました。初めはエラーが多く苦労しましたが、オンライン教材や書籍を参考に少しずつ改良しました。 最終的に、処理時間を3分の1に短縮することができ、研究室のメンバーからも高評価を得ました。この経験で、課題を自分で設定し、解決策を形にする力を身につけました。 |
個人開発や自主研究では、「課題を自分で設定した経緯」と「成果をどう社会や周囲に還元したか」を書くと深みが出ます。自発性と継続力を強調すると好印象です。
理系学生のガクチカで強みを最大限に伝えよう!
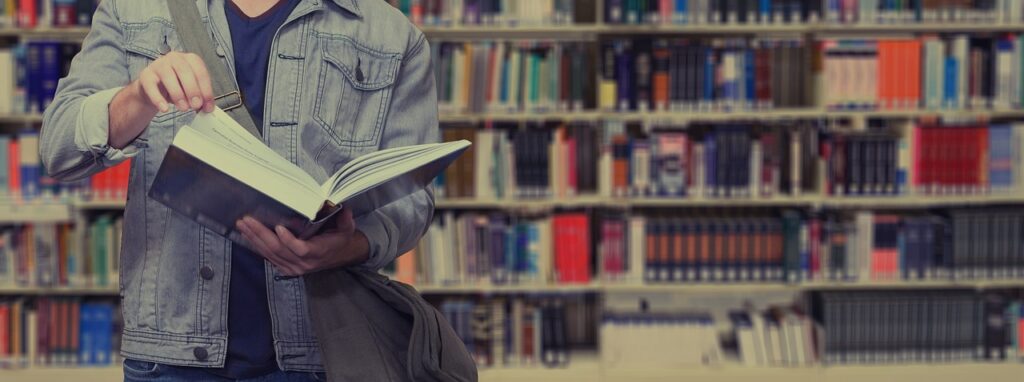
理系学生がガクチカで最も大切にすべきことは、「研究や実験などの経験を、論理的に整理して自分らしさを伝えること」です。
研究のメリットとして、論理的思考力や課題解決力、専門知識を活かしたアピールが可能な一方で、専門的すぎて伝わりにくいというデメリットもあります。
企業は成果よりも、課題発見力・主体性・継続力といった「取り組みの過程」を重視しています。
そのため、STAR+Pフレームワークを活用して、状況・課題・行動・結果・過程・人柄の流れで構成すると、伝わりやすく説得力のあるガクチカになります。
研究以外にも、アルバイトやサークル活動など多様な経験が評価されるため、自分の強みを活かせるテーマを選びましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。