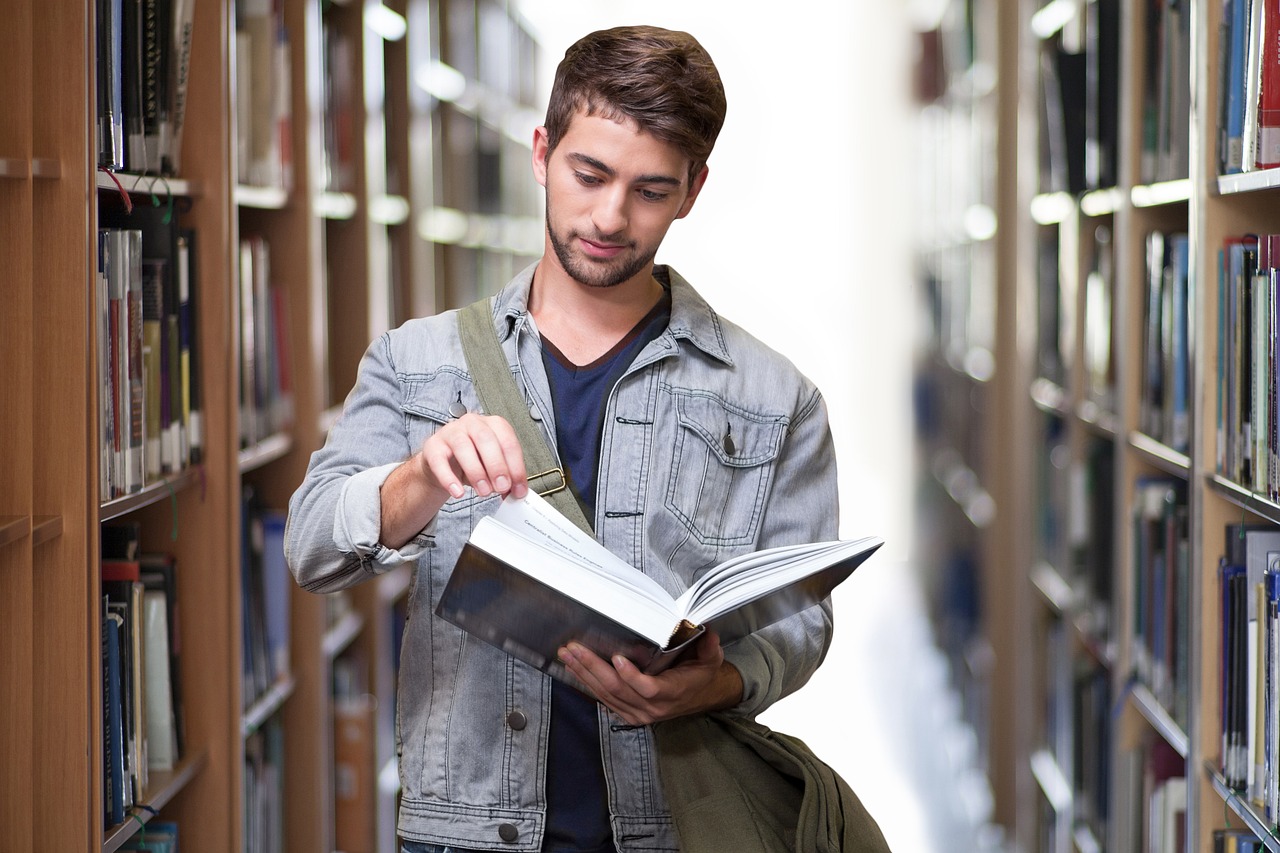ガクチカで研究を効果的に伝える方法!書き方と例文で魅力を最大化
就活の「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」で、研究活動をテーマにしようと考える人は多いでしょう。
一方で、「専門的すぎて伝わらないかも」「成果が出なかったけど話していいの?」と悩む声もよく聞かれます。実は、研究テーマそのものよりも取り組みの姿勢や課題解決力こそ、企業が注目しているポイントです。
この記事では、研究をガクチカで魅力的に伝えるためのコツや例文、注意点をわかりやすく紹介します。
理系・文系を問わず、研究経験を最大のアピール材料に変えたい方はぜひ参考にしてください。
ガクチカ作成のお助けアイテム
- 1ES自動作成ツール
- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成
- 2赤ペンESでガクチカを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに
- 3ガクチカのテンプレシート
- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える
- 4強み診断
- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる
ガクチカで研究をテーマにするメリット

ガクチカで研究をテーマに選ぶことには、多くの利点があります。研究経験は努力や課題解決力を裏付ける具体的なエピソードであり、面接官に「主体性」「論理性」「再現性」を伝える絶好のチャンスです。
ここでは、研究をガクチカにすることで得られる主なメリットを紹介します。
- 専門性の高さをアピールできる
- 研究成果以外でも努力の過程を評価してもらえる
- 学業と就活を両立できる強みがある
- 課題解決力や思考力を示せる
- 志望動機と一貫性を持たせやすい
- 他の学生と差別化ができる
- 失敗経験から成長を伝えられる
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
①専門性の高さをアピールできる
研究をテーマにしたガクチカは、専門分野に対する理解の深さや分析力を伝える絶好の機会です。
とくに理系学生の場合、実験やデータ分析などのプロセスを通して、論理的思考力と探究心をアピールできます。
研究テーマの背景や目的を簡潔に説明したうえで、どんな問題を解決するために取り組んだのか、またその結果どのような知見を得たのかを具体的に語るとよいでしょう。
単に専門知識を述べるのではなく、それを社会や企業活動にどう活かせるかを結びつけると、採用担当者に「実務で再現できる力がある」と伝わりますよ。
②研究成果以外でも努力の過程を評価してもらえる
研究は成果がすべてではなく、過程にこそ価値があります。企業は結果そのものよりも、困難に直面したときにどんな工夫をし、どんな姿勢で取り組んだかを重視します。
たとえば、実験が思い通りに進まなかったとしても、試行錯誤を重ねて原因を究明した経験を伝えると、粘り強さや課題解決力を印象づけられます。
また、チーム研究での役割や他者との協力を通して学んだことを具体的に説明すれば、協調性や柔軟性もアピールできます。
重要なのは、「何を成し遂げたか」よりも「どのように向き合ったか」を明確にすることです。
③学業と就活を両立できる強みがある
研究をガクチカにすることで、計画的に物事を進める力や時間管理能力を具体的に示せます。
研究と就職活動を両立するには、優先順位を正しく判断し、限られた時間の中で効率的に行動することが求められます。
スケジュール調整を工夫しながら、研究の進捗を保ちつつ面接や企業研究を並行して行った経験を語ると、責任感と柔軟な対応力を伝えられます。
このように、研究と就活の両立は、努力を「見える形」で証明できるエピソードとして非常に有効です。
④課題解決力や思考力を示せる
研究の中では、必ずといってよいほど壁にぶつかります。その過程でどのように課題を見つけ、原因を分析し、改善策を実行したのかを説明することで、あなたの論理的思考力と課題解決力を明確に伝えられます。
企業は、未知の問題に直面しても粘り強く考え抜ける人を求めています。研究で得た分析力や考察力は、社会人になってからも企画・営業・技術開発など幅広い分野で活かせます。
自分がどんなプロセスで課題を解決してきたのかを具体的に話すと、信頼性と説得力が高まるでしょう。
⑤志望動機と一貫性を持たせやすい
研究テーマは志望動機と自然に結びつけやすく、説得力のある自己PRにつながります。
もし直接的な関係がなくても、研究で得たスキルをどのように職場で活かせるかを具体的に語れば問題ありません。
研究で培った論理的思考、データ分析、計画遂行力などは、多くの職種に共通して求められる力です。
研究と志望先企業の共通点を意識して話すことで、面接官に「この人は仕事のイメージを持っている」と感じさせられます。一貫性のあるストーリーは、採用担当者の印象に残りやすいでしょう。
⑥他の学生と差別化ができる
研究をガクチカにする最大の魅力は、他の学生との差別化を図れる点にあります。
理系の場合は研究テーマや実験方法の独自性、文系であれば仮説の立て方や分析手法などを強調することで、独自の視点を持つ人として印象づけられます。
企業が多くの学生を面接する中で、印象に残るのは「自分の経験を具体的に社会的価値に変換できる人」です。
自分の研究を単なる学術的成果として語るのではなく、そこから得た学びを社会課題や企業活動にどう活かすかまで示せると、他の応募者との差は一気に広がります。
⑦失敗経験から成長を伝えられる
研究活動には必ず失敗や停滞がつきものですが、その経験をどう捉え、どう成長につなげたかが重要です。企業は「失敗を恐れず挑戦し、そこから学ぶ力」を持つ人材を評価します。
また、失敗を通じて学んだ改善意識やリスク管理の姿勢を伝えると、自己成長に対する前向きな姿勢が伝わります。
重要なのは、失敗を「成果が出なかった経験」として終わらせず、「次に活かすための学び」に昇華させて語ることです。成長を重ねてきた姿勢こそが、採用担当者の心に響くガクチカとなるでしょう。
企業がガクチカの研究エピソードで評価しているポイント
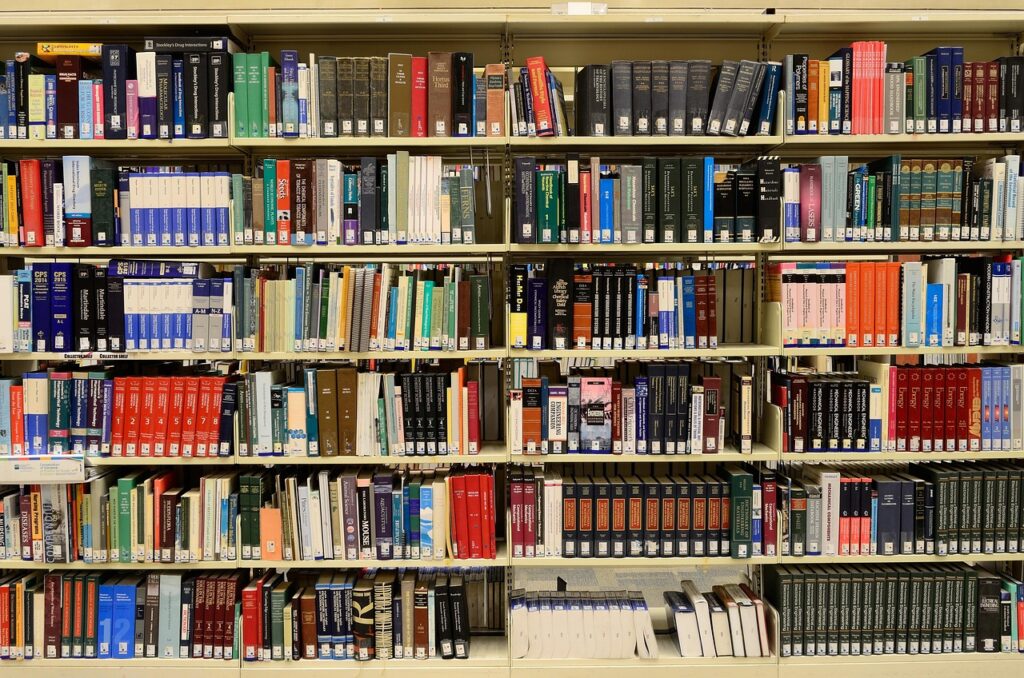
企業は、研究をテーマにしたガクチカを通じて学生の人間性や仕事に対する姿勢を見極めています。単に「何を研究したか」ではなく、「どう取り組み、どんな成長を遂げたか」を重視しているのです。
ここでは、企業が評価する主な7つのポイントを詳しく解説します。
- 課題発見力と解決力
- 粘り強さ・継続力
- チームでの協働力
- 主体性と探究心
- 論理的思考力と説明力
- 成果よりもプロセス重視の姿勢
- 企業の求める人物像との一致度
①課題発見力と解決力
企業が最も注目するのは、課題を見つけ出し、それを自らの力で解決しようとする姿勢です。研究は、正解が1つではない世界で試行錯誤を重ねる活動です。
そのため、問題の本質を見極め、原因を分析し、仮説を立てて検証する一連の流れを具体的に語れると評価が高まります。
企業は、未知の課題にも冷静に対応できる「柔軟な解決力」を持つ人を求めています。研究で培ったこの力は、業務上の問題解決にも直結するでしょう。
②粘り強さ・継続力
研究は長期的な取り組みであり、結果が出るまでに多くの時間と努力を要します。そのため、粘り強さや継続的に努力する力が自然と身につくのです。企業はこの点を高く評価しています。
途中で壁にぶつかっても諦めず、原因を探りながら進めていく姿勢は、社会人としても重要な資質です。ガクチカでは「失敗をどう乗り越えたか」「何を継続して努力したか」を明確に示すとよいでしょう。
継続力は単なる忍耐ではなく、「目的を持って粘り強く挑戦する力」として伝えることが大切です。研究を通じて得たこの姿勢は、仕事で成果を出すための基礎になります。
③チームでの協働力
研究活動には、個人作業だけでなくチームで進めるケースも多くあります。データ共有や共同実験、ディスカッションなど、複数人で協力する過程で生まれる学びは、社会で求められる「協働力」に直結します。
企業は、他者と意見を交わし、異なる考えを尊重しながら成果を出せる人を求めています。
そのため、ガクチカでは「チーム内でどんな役割を果たしたか」「どんな工夫で意見をまとめたか」を具体的に語るとよいでしょう。
自分だけでなく周囲の力を活かせる姿勢を示すことで、リーダーシップや調整力も評価されやすくなります。
④主体性と探究心
企業は、受け身ではなく自ら考えて行動する人を高く評価します。研究はまさに主体性の塊といえる活動です。
テーマ設定から手法の選定、データ分析まで、自分で考え、試し、改善を繰り返す過程そのものが探究心の証です。
ガクチカでは、与えられた課題をこなすだけでなく、「自ら課題を設定した」「新しい方法を試した」といった主体的なエピソードを盛り込むと良いでしょう。
探究心は、業務における改善提案や新しいチャレンジにもつながる重要な素質です。積極的に学び続ける姿勢を示すことで、企業に成長意欲のある人材だと印象づけられます。
⑤論理的思考力と説明力
研究を通じて培われる論理的思考力は、ビジネスの場でも非常に重要です。企業は「相手にわかりやすく説明できる力」を重視しています。
データを分析して仮説を立て、結果を踏まえて結論を導くという研究のプロセスは、まさに論理構築のトレーニングです。
ガクチカでは、研究内容を専門用語で難しく話すのではなく、「誰にでも伝わる言葉」で説明することがポイントです。
自分の考えを順序立てて整理し、端的に伝えるスキルは、プレゼンテーションや営業などでも大いに役立ちます。説明力は「知っていること」ではなく「伝える力」であることを意識しましょう。
⑥成果よりもプロセス重視の姿勢
企業は、研究の「結果」そのものよりも、「どう取り組んだか」というプロセスを重視します。結果が芳しくなくても、粘り強く分析を重ねたり、新しい手法を試したりする過程が評価されるのです。
ガクチカでは、「結果を出した」よりも「結果に至るまでの工夫や行動」を中心に語ることが重要です。
特に困難をどう乗り越えたか、そこから何を学んだかを具体的に伝えると、挑戦姿勢や成長意欲を印象づけられます。企業は「成功の裏にある努力」を見ています。
研究活動でのプロセスを通して、自分がどんな姿勢で課題に向き合う人間かを伝えることが大切です。
⑦ 企業の求める人物像との一致度
最後に、企業が特に重視するのが、自社の価値観や求める人物像と応募者の一致度です。研究テーマや取り組み方から、その人の思考傾向や仕事のスタイルを推測できます。
たとえば、チームで協力して進めるタイプなのか、個人で深く掘り下げるタイプなのかによって、適性を見極めているのです。ガクチカでは、自分の研究姿勢と企業文化の共通点を意識して話すとよいでしょう。
「自分の強みが御社の〇〇に活かせる」と具体的に伝えると、説得力が増します。研究での学びを自社の仕事にどう結びつけられるかを語ることで、マッチ度の高い印象を残せます。
ガクチカで研究内容をわかりやすく伝えるためのコツ

ガクチカで研究をテーマにする際、最も大切なのは「難しい内容をいかにわかりやすく伝えるか」です。どれほど専門性が高くても、面接官や人事担当者に理解されなければ意味がありません。
ここでは、あなたの研究を誰にでも伝わる形で説明するための7つのポイントを詳しく解説します。
- 専門用語を避けて平易な言葉で説明する
- 結論から先に述べるPREP法の活用
- 数字や具体例で説得力を高める
- 研究テーマと社会的意義をつなげる
- 企業目線で興味を引く要素を入れる
- 話す時間・文字数に合わせた要約練習
- 第三者に説明して理解度を確認する
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①専門用語を避けて平易な言葉で説明する
研究を説明するときは、専門用語を使いすぎず、一般的な表現に置き換えることが非常に重要です。面接官の多くは同じ分野の研究者ではなく、別の学部出身の人も多いからです。
たとえば「X線回折法を用いた結晶構造解析」と言うよりも、「物質の形や構造を光で調べる方法」と言い換えるだけで、理解しやすくなります。
難しい言葉を平易に説明できる人は、自分の理解度が高い証拠でもあります。また、面接官がイメージしやすいように「身近な例」や「たとえ話」を交えるのも効果的です。
たとえば「料理で味を確かめるように、データを繰り返し確認する」といった比喩を入れると、相手に親近感を与えられます。専門性を保ちながらも、聞き手が理解できるレベルに調整する意識が大切です。
②結論から先に述べるPREP法の活用
限られた面接時間の中で研究内容をわかりやすく伝えるには、PREP法(Point→Reason→Example→Point)を使うのが効果的です。
最初に結論を示すことで、相手に話の全体像を把握してもらえます。そのあとに理由や背景を説明し、具体的な事例を補足して再度結論で締める流れです。
たとえば、「私の研究は〇〇を目的に行いました。その理由は△△という課題を解決するためです。
実際に□□という方法を用いて結果が出ました。」というように構成すると、自然とわかりやすい文章になります。
PREP法は話を整理するだけでなく、伝える順序を一定に保つことで緊張してもブレない説明ができます。エントリーシートの文章構成にも応用できるので、早めにこの話法を身につけておくと安心です。
研究以外の質問でも活用できる、万能な伝達スキルといえるでしょう。
③数字や具体例で説得力を高める
研究内容を抽象的に語るだけでは、印象に残りにくくなってしまいます。説得力を高めるためには、数字や具体例を織り交ぜることが重要です。
「長期間」「多くの」「さまざまな」という言葉よりも、「6か月間」「20回の実験」「3つの手法」といったように、定量的な表現に置き換えると効果的です。
また、具体的な成果や改善率を述べると、客観的な根拠を示せます。たとえば「成功率を30%向上させた」「従来より分析時間を半分に短縮した」と伝えると、数字が努力の裏づけとして機能します。
さらに、研究テーマに関連するエピソードを交えることで臨場感を出せます。数字は単なるデータではなく、「あなたの頑張りを形にする要素」でもあります。
話の要所でうまく使うと、相手に明確なイメージを与えられるでしょう。
④研究テーマと社会的意義をつなげる
面接官が関心を持つのは、あなたの研究が社会や業界にどう役立つのかという点です。
単に研究内容を説明するだけでなく、「その研究がどんな価値を生むのか」「誰のために意味があるのか」を語ることが大切です。
たとえば「食品保存に関する研究」をしているなら、「食料廃棄の削減やサステナビリティの向上につながる」と社会的意義に結びつけると印象が強まります。
また、社会問題やトレンドに触れながら説明すると、視野の広い人だと感じてもらえます。企業は、自分の研究成果を社会や事業に応用できる人を求めています。
そのため、「研究を通じてどんな課題を解決したいか」「どんな影響を与えたいか」を自分の言葉で語れるようにしておくと良いでしょう。
研究を社会とつなげて語ることで、単なる学業ではなく「実践的な経験」として評価されます。
⑤企業目線で興味を引く要素を入れる
研究を説明する際には、自分の関心だけでなく「企業がどんな観点で価値を見いだすか」を意識することがポイントです。
たとえば、製造業なら効率化やコスト削減に貢献できる視点、IT業界ならデータ処理や自動化への応用可能性を盛り込むと良いでしょう。
企業は研究そのものではなく、「経験が仕事でどう活かせるか」を知りたいのです。自分の研究が企業の事業内容や課題解決にどう貢献できるかを明確にすることで、話がより実践的になります。
また、「その分野で求められるスキルをすでに持っている」という印象を与えられるため、評価が上がりやすいです。
業界研究を並行して行い、企業が重視するキーワードや価値観を意識して説明を組み立てると、より響く内容に仕上がります。
⑥話す時間・文字数に合わせた要約練習
面接やエントリーシートでは、限られた時間や文字数で研究内容を伝える必要があります。そのため、長い説明を短くまとめる練習が欠かせません。
まずは、自分の研究を「目的」「方法」「結果」「学び」の4要素に分け、最も伝えたい部分を決めましょう。
そのうえで、1分・3分・5分など時間を区切って説明する練習をすると、どんな場面でも対応できるようになります。
文章の場合も同様で、400字・600字・800字とバリエーションを作っておくと便利です。話す内容を録音して聞き返すと、不要な表現や言い回しが見えてきます。
こうしたトレーニングは、単に就活のためだけでなく、入社後のプレゼンや報告の場面でも大いに役立つでしょう。相手の立場に合わせて情報を取捨選択できる力こそ、社会人に求められるスキルです。
⑦第三者に説明して理解度を確認する
研究内容を効果的に伝えるためには、自分の頭の中だけで整理するのではなく、実際に他人に話してみることが重要です。
友人や家族など専門外の人に説明し、「わかりやすかったか」「どの部分が難しかったか」をフィードバックしてもらいましょう。
相手が理解できなかった部分こそ、自分の説明を改善すべきポイントです。また、他人に説明する過程で、自分の研究の本質や強みを再確認できるというメリットもあります。
話を重ねるほど、自分の言葉で語れるようになり、自然と自信もつきます。さらに、相手の反応を見ながら話のテンポや表現を調整することで、コミュニケーション力も磨かれます。
研究を「伝える力」は就活だけでなく、社会に出てからのプレゼン・営業・マネジメントなど、あらゆる場面で役立つ実践的スキルです。
研究活動をガクチカにする際の注意点
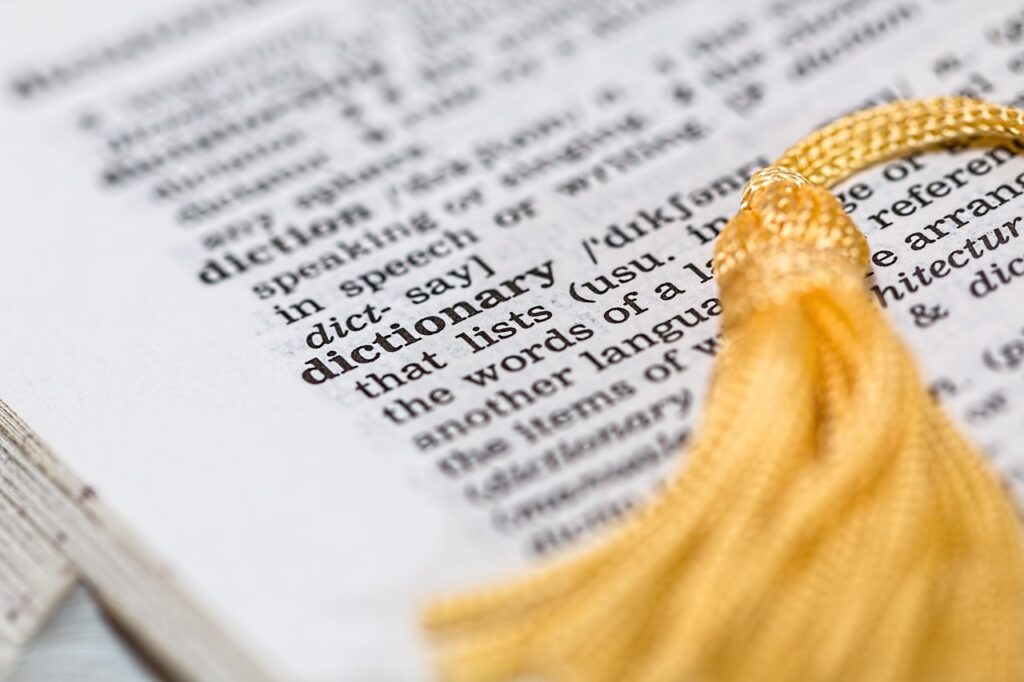
研究をガクチカとしてアピールする際は、専門的になりすぎたり、研究成果だけに偏ったりすることがよくあります。
採用担当者は研究内容そのものよりも、そこから見えるあなたの人間性や考え方、行動力を重視しています。ここでは、研究を魅力的に伝えるために気をつけたい7つのポイントを紹介します。
- 研究内容の専門性に偏りすぎない
- 成果よりも過程を丁寧に描く
- チーム貢献や他者との関わりも盛り込む
- 自己評価だけでなく客観的成果も補足する
- 研究を就職後の活躍にどう結びつけるかを示す
- 研究以外の経験とのバランスを取る
- 研究の背景や目的を簡潔に伝える
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①研究内容の専門性に偏りすぎない
ガクチカで研究を説明する際に、専門的な内容に踏み込みすぎると、聞き手が理解できなくなってしまうことがあります。特に理系の研究は専門用語が多く、文系の採用担当者には伝わりにくい場合もあります。
重要なのは、「専門性の深さ」ではなく「研究を通して何を学び、どんな力を身につけたか」です。
たとえば「実験の手法を改良した」ではなく、「困難に直面しても粘り強く取り組んだ」といった行動や姿勢に焦点を当てると伝わりやすくなります。
企業は専門知識よりも「課題解決力」「柔軟な思考」「協働姿勢」といった社会人基礎力を見ています。相手の理解を意識した説明を心がけましょう。
②成果よりも過程を丁寧に描く
研究で成果が出たとしても、それ以上に企業が注目するのは「その成果を得るまでにどのように考え、行動したか」という過程です。
結果が出なかった研究であっても、課題に向き合い、試行錯誤を重ねた姿勢を丁寧に伝えれば、十分に評価されます。
たとえば、「実験条件を何度も見直した」「仲間と議論を重ねて問題点を洗い出した」など、具体的な行動を挙げると説得力が増します。
過程を描く際は、単なる作業の説明ではなく、「なぜその行動を取ったのか」「その結果どう変化したのか」を明確にするとよいでしょう。努力の積み重ねを見せることで、あなたの成長と人間性が伝わります。
③チーム貢献や他者との関わりも盛り込む
研究は一人で進めるものではなく、指導教員や仲間との協働によって成り立っています。そのため、チームワークの中で自分が果たした役割を語ることが大切です。
たとえば「班の進捗をまとめて議論を促した」「実験データを共有して全体の効率を上げた」など、周囲に貢献した経験を交えると好印象です。
企業は個人の成果だけでなく、「チームの中でどのように動ける人か」を重視しています。自分の役割を意識して行動した経験を伝えることで、協調性やリーダーシップを効果的にアピールできます。
個人の努力だけでなく、他者とともに成果を出す力を見せることが、社会人としての評価につながります。
④自己評価だけでなく客観的成果も補足する
「自分では頑張ったつもりでも、それが相手に伝わらない」というのはよくあることです。そのため、ガクチカでは自分の主観だけでなく、第三者からの評価や具体的な成果を補足すると説得力が増します。
たとえば「教授に発表を褒められた」「学会で研究発表を行った」「研究成果が報告書に採用された」といった事実を示すとよいでしょう。これにより、努力の結果が客観的に評価されていることが伝わります。
ただし、成果を誇張するのではなく、その背景にある努力や工夫を忘れずに説明することが大切です。数字や実績を活用しながらも、バランスの取れた表現を心がけましょう。
⑤研究を就職後の活躍にどう結びつけるかを示す
ガクチカで研究内容を語る際は、「その経験が就職後にどう活かせるか」をセットで伝えることが重要です。企業は、学生時代の取り組みが社会人としての行動にどのように反映されるかを見ています。
たとえば「研究で培った分析力を活かして、御社の製品開発に貢献したい」など、経験と業務をつなげて説明すると効果的です。
単なる思い出話で終わらせず、未来への活用イメージを提示することで、論理的で前向きな印象を与えられます。
また、研究姿勢と企業の価値観を重ね合わせて話すことで、「自社とマッチしている人材」として印象づけることもできます。過去の経験から未来への展望へとつなげる意識が大切です。
⑥研究以外の経験とのバランスを取る
研究活動はガクチカとして魅力的なテーマですが、それだけに偏ると「学業しかしてこなかった人」という印象を与えかねません。企業は、幅広い経験を通して人間性を形成しているかを見ています。
そのため、研究以外の経験――たとえばアルバイト、部活動、ボランティアなど――にも触れることで、バランスの取れた印象を与えられます。
研究に全力で取り組みつつも、他の活動にも主体的に関わった姿勢を見せることが理想です。また、研究で得たスキルが他の場面でどう活かされたかを語ると、経験の一貫性を示せます。
多面的な成長を伝えることで、より人間味のあるガクチカに仕上がります。
⑦研究の背景や目的を簡潔に伝える
研究の説明を始める前に、背景や目的を端的に伝えることがポイントです。
最初に「どんな問題意識を持って取り組んだのか」「何を解決しようとしたのか」を簡潔に説明することで、聞き手が内容を理解しやすくなります。
逆に、細かい実験手順や理論から入ると、要点が伝わりにくくなります。たとえば「環境問題の解決を目的に〇〇の研究を行った」と冒頭で述べると、興味を引きやすいです。
目的を明確にすることは、あなたの考える力や問題意識の高さを示すことにもつながります。研究内容を整理してから説明することで、話全体の構成がスムーズになり、面接官の理解度も高まるでしょう。
学部卒と院卒で異なるガクチカの研究アピールの違い
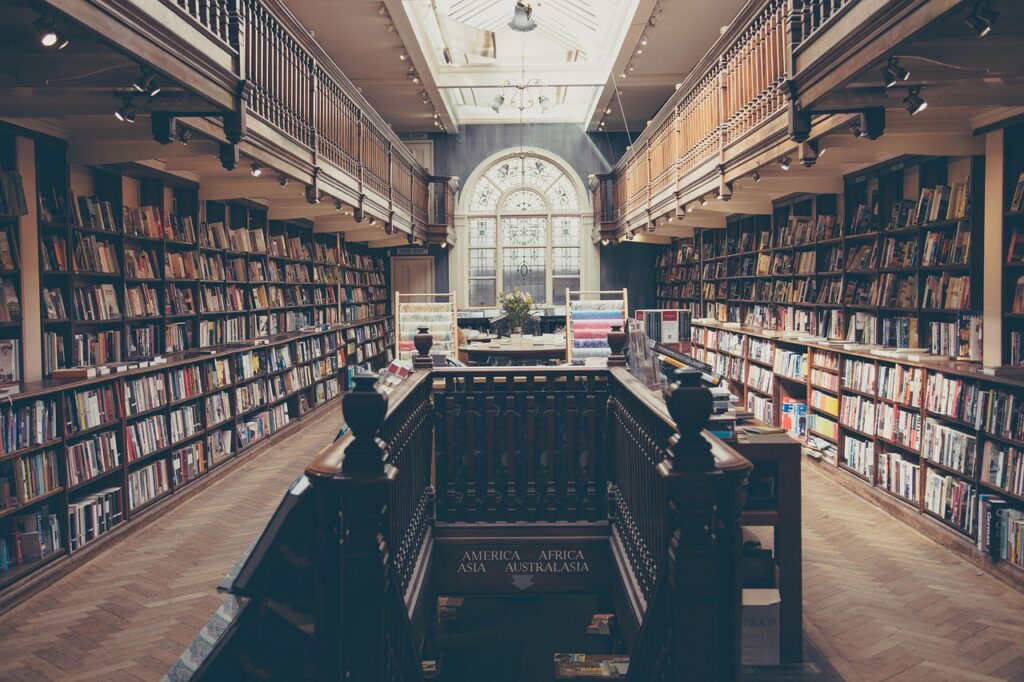
同じ研究テーマを扱っていても、学部卒と院卒ではアピールの仕方に違いがあります。企業が求める人物像や期待する役割が異なるため、それぞれの立場に合った伝え方を意識することが重要です。
ここでは、学部卒・院卒それぞれの研究ガクチカで意識すべきポイントを整理して解説します。
- 学部卒は学びの姿勢と吸収力を重視
- 院卒は専門性と研究成果の深さを重視
- 院卒は即戦力・再現性を意識した説明を
- 学部卒は柔軟性と将来性を強調
- 院卒は研究の社会貢献性を意識して語る
- 学部卒は課題への主体的姿勢を示す
①学部卒は学びの姿勢と吸収力を重視
学部卒の学生が研究をガクチカにする場合、企業は「学びの姿勢」や「吸収力」に注目しています。
研究の専門性よりも、課題に取り組む中でどれだけ成長できたか、どんな工夫を重ねたかを具体的に示すことが大切です。
たとえば、最初は理解できなかったテーマに自主的に取り組み、段階的に理解を深めて成果を上げたエピソードを語ると効果的です。企業は「未経験の環境でも自ら考え、学び続けられる人」を求めています。
したがって、「研究を通して何を学んだか」「どんな考え方が身についたか」を中心にアピールするとよいでしょう。
特に理系学生は、知識よりも行動面・学習意欲を伝えることで、ポテンシャル採用の対象として評価されやすくなります。
②院卒は専門性と研究成果の深さを重視
院卒の場合、研究の専門性や成果の深さが重要視されます。企業は、大学院で培った高度な知識や論理的思考力を業務にどう活かせるかを見ています。
そのため、研究テーマの背景や目的、得られた成果を客観的に説明できるようにしておくことが大切です。
たとえば、「特定の実験条件を変化させることで性能を20%向上させた」「論文発表や学会で成果を発信した」など、具体的な実績を交えると説得力が高まります。
ただし、専門的すぎる内容に偏ると理解されにくいため、相手に合わせて平易な言葉に言い換える工夫も必要です。
研究成果を社会や企業活動と結びつけて説明できれば、専門性の高さと応用力の両面を伝えられます。
③院卒は即戦力・再現性を意識した説明を
院卒は、社会人としての即戦力を期待される傾向があります。そのため、研究経験が仕事にどのように再現可能かを明確に伝えることが重要です。
たとえば、「データ分析の経験を通して論理的に課題を整理する力を身につけた」「複雑な課題を計画的に進める力を養った」など、業務につながるスキルを具体的に示しましょう。
企業は「この人ならすぐに成果を出せそうか」を見ています。単に「頑張った」ではなく、「研究で得たスキルを職場でどう使えるか」を描くことで、実践的な印象を与えられます。
また、研究で使用したツールや手法を業界ニーズと照らし合わせて説明すると、再現性のある能力として評価されやすくなります。
④学部卒は柔軟性と将来性を強調
学部卒のガクチカでは、まだ社会経験が浅い分、「柔軟性」と「将来の成長可能性」を重視されます。
研究中に発生したトラブルや予想外の展開にどのように対応したかを話すことで、臨機応変に考え行動できる姿勢を伝えましょう。
また、研究を通じて得た学びを「今後のキャリアにどう活かしたいか」と結びつけることで、前向きな印象を与えられます。企業は完璧な成果よりも、失敗から学び、次に活かせる人材を評価します。
学部卒のうちは「できなかったことを克服した」「考え方が変わった」など、変化と成長を具体的に語ることが効果的です。伸びしろを見せることが、学部卒にとって最大の強みになります。
⑤院卒は研究の社会貢献性を意識して語る
院卒の研究は、社会的課題や産業の発展に関わるテーマである場合が多いため、ガクチカでもその意義を意識して語ると効果的です。
たとえば「環境負荷の軽減」「医療技術の向上」「エネルギー効率化」など、研究が社会にどんな影響を与える可能性があるかを伝えることで、視野の広さと責任感をアピールできます。
企業は、自分の専門領域を社会や事業の中でどう活かせるかを考えられる人材を求めています。したがって、研究を単なる学問としてではなく、「社会に貢献できる手段」として語る姿勢が大切です。
また、研究の目的や成果を企業の理念と結びつけると、共感を得やすくなります。
⑥学部卒は課題への主体的姿勢を示す
学部卒は、研究経験の深さよりも「主体性」を示すことが重要です。
たとえば「テーマ設定に積極的に関わった」「新しい分析方法を自ら提案した」など、自ら考えて行動したエピソードを伝えるとよいでしょう。企業は、自分で課題を見つけ、行動できる人を高く評価します。
また、指示を待つのではなく、自分から動く姿勢を見せることで、社会人としてのポテンシャルを印象づけられます。
さらに、困難な場面で「どう乗り越えたか」「どんな工夫をしたか」を語ることで、実行力や粘り強さも伝わります。主体的に学び行動する姿勢は、どんな業界でも通用する基本的な強みです。
自分の行動が結果にどうつながったかを意識して話すようにしましょう。
研究をアピールするガクチカの書き方ステップ

研究をガクチカとして伝える際には、構成の順序と内容のバランスが非常に重要です。どんなに優れた研究内容であっても、伝え方を誤ると評価につながりません。
特に企業の採用担当者は、研究そのものよりも「その経験から何を学び、どう成長したか」に注目しています。ここでは、印象に残るガクチカを作るための7つのステップを詳しく解説します。
- 研究テーマと背景の説明
- 研究の目的・課題設定
- 取り組みのプロセス・工夫点
- 困難に直面した場面と乗り越え方
- 得られた成果や学び
- 就職後に活かせるスキルや展望
- 全体の流れを意識したストーリー構成
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①研究テーマと背景の説明
ガクチカの書き出しでは、研究テーマを簡潔に示すだけでなく、その背景や社会的意義も合わせて説明することが重要です。たとえば「AIを活用した画像認識の研究」と書くだけでは伝わりません。
「医療現場の診断効率を高めるために、AIによる画像認識精度の向上を目指した」と述べることで、研究の目的や意義が明確になります。
さらに、なぜそのテーマを選んだのかという“動機”を加えると説得力が増します。興味を持ったきっかけや、課題意識を持った背景を簡単に触れるとよいでしょう。
また、専門的な内容に入りすぎず、一般の読者でも理解できるレベルの言葉に言い換えることも大切です。
研究背景を丁寧に伝えることで、「この人は問題意識を持って主体的に取り組んでいる」と印象づけられます。
②研究の目的・課題設定
研究の目的を語る段階では、「何を解決したいのか」をはっきりさせることがポイントです。採用担当者は「目的設定力=仕事の課題設定力」として評価します。
そのため、研究の目的は“社会的な意義”と“自分自身の成長”の両面から説明すると効果的です。
たとえば「エネルギー消費を減らすための新素材開発を行い、実験を通して論理的思考力を養った」という形です。
また、課題設定の際にどんな情報を集め、どんな分析を行ったかを簡潔に触れると、問題解決へのアプローチ力が伝わります。
単に「テーマを決めた」ではなく、「なぜそれが重要なのか」を語ることで、研究への主体性が明確になります。自ら課題を見つけ、目的を持って取り組む姿勢を具体的に示すことが大切です。
③取り組みのプロセス・工夫点
研究のプロセス部分では、「どのように考え、どんな工夫を行ったか」を詳しく説明することが大切です。単に手順を並べるのではなく、自分が取った判断や改善策に焦点を当てましょう。
たとえば、「仮説がうまく機能しなかったため、実験条件を再設定し、異なるパラメータで再検証を行った」といったように、具体的な行動を描くと臨場感が出ます。
また、工夫した点には“他者と異なる視点”や“新しい試み”を盛り込むと、独自性が伝わります。
研究がチームで行われた場合は、メンバー間でどのように連携を取ったか、情報共有をどう工夫したかを補足するのも効果的です。
プロセスを語る際には、結果よりも「問題をどう捉え、どう乗り越えたか」というストーリーを意識しましょう。あなたの行動と思考の軌跡が、企業にとって貴重な評価材料になります。
④困難に直面した場面と乗り越え方
どんな研究にも、壁やトラブルはつきものです。このパートでは、困難な状況をどう受け止め、どんな工夫で解決したのかを具体的に描きましょう。
「装置トラブルでデータが失われたが、再現性を高めるための新しい測定手法を考案した」など、現実的な課題への対応力を伝えると評価されやすくなります。
また、困難を語るときは「感情」より「行動」を重視することがポイントです。「焦った」「落ち込んだ」よりも、「冷静に原因を分析し、改善策を立てた」といった能動的な姿勢を見せましょう。
そのうえで、「この経験から問題解決力や粘り強さを身につけた」と学びを添えることで、成長の物語として印象に残ります。企業が見ているのは“結果”ではなく、“逆境にどう向き合ったか”です。
挑戦の過程を誠実に語ることで、信頼性の高いエピソードに仕上がります。
⑤得られた成果や学び
成果や学びを伝える際は、結果の大小に関わらず「何を得たか」を具体的に言語化することが大切です。数値的成果がある場合は「データ誤差を10%削減した」「論文発表を行った」など明確に示しましょう。
しかし、すべての研究が目に見える成果を出すわけではありません。
その場合でも「課題を分解して考える力が身についた」「仲間の意見を取り入れる姿勢を学んだ」など、内面的な成長を伝えることが評価されます。
また、成果だけで終わらせず、「その結果を今後どう活かすか」にも言及すると、自己成長への意欲が伝わります。
研究を通じて得た“気づき”や“変化”を丁寧に表現することが、あなたらしさを感じさせるポイントです。
企業は「どんな結果を出したか」より、「どう考え、どう成長したか」を重視していることを忘れないでください。
⑥就職後に活かせるスキルや展望
ガクチカの締めくくりには、研究で得た経験が社会でどう活きるかを具体的に語りましょう。企業は、過去の経験を将来の行動に結びつけられる人材を求めています。
「データ分析力を活かして新製品の開発効率を高めたい」「課題解決の考え方を使って業務改善に貢献したい」といった形で、自分の強みと企業のニーズを関連づけて話すのが効果的です。
さらに、就職後にどんな姿勢で学び続けたいかを添えると、成長意欲が伝わります。たとえば「研究で身につけた探究心を活かし、常に新しい知識を吸収していきたい」といった一文を入れるとよいでしょう。
過去の経験を未来につなげることで、単なる学生時代のエピソードではなく、“社会での活躍を期待できる人材”として印象づけられます。
⑦全体の流れを意識したストーリー構成
最後のステップは、全体を一貫したストーリーとしてまとめることです。研究の流れが「テーマ→目的→行動→困難→成果→学び→展望」という順序で整理されていると、面接官にも読みやすく印象が残ります。
特に重要なのは、すべての要素を“自分の成長”という軸でつなげることです。テーマ選定から学びまでが自然に展開していくと、論理的で魅力的な構成になります。
文章を書く際には、1文ごとに主語と目的を明確にし、冗長な表現を避けましょう。また、話す場合は時間配分にも注意が必要です。序盤は簡潔に、過程と学びに重点を置くと効果的です。
ストーリー全体を通して、あなたの考え方や価値観が伝わるよう意識すると、より完成度の高いガクチカになります。
アピールポイント別|研究ガクチカの例文

研究を通じて培った強みは、伝え方次第で大きな印象を与えます。しかし、自分の経験をどう言語化すればよいか悩む就活生も多いでしょう。
ここでは、研究ガクチカでアピールできる代表的なポイント別に、効果的な例文を紹介します。自分の研究スタイルに合う表現を見つけ、より魅力的な自己PRにつなげましょう。
- 論理的思考力をアピールする例文
- 分析力・計画力をアピールする例文
- 継続力・粘り強さをアピールする例文
- チームワーク・協調性をアピールする例文
- リーダーシップ・主体性をアピールする例文
- プレゼン力・伝達力をアピールする例文
- 失敗からの成長をアピールする例文
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「AI ES」では【志望動機・ガクチカ・自己PR・長所・短所】を満足が行くまで何度も自動作成できます。実際に使用してみた感想などを以下の記事に掲載しているので、気になるけど登録するか迷っている方は記事を読んでみてくださいね。
【関連記事】
エントリーシート(ES)の作成をAIに丸投げ!「AI ES」サービスで就活
①論理的思考力をアピールする例文
研究をテーマにしたガクチカでは、問題解決に向けて「どのように考え、行動したか」を明確に示すことが重要です。
ここでは、研究活動の中で論理的思考力を発揮した場面を具体的に伝える例文を紹介します。
| 私は大学で食品保存に関する研究を行っていました。あるとき、想定していた保存期間で食品の品質が安定せず、実験がうまく進まないことがありました。 原因を探るために、実験条件をひとつずつ整理し、温度や湿度の影響を数値化して比較しました。 その結果、微小な温度変化が品質劣化に大きく関係していることを突き止め、実験環境を改善したことで、目標としていた保存期間を達成できました。 この経験から、問題を感覚ではなくデータに基づいて考えることの大切さを学び、論理的に物事を整理する力を身につけました。 |
論理的思考力を伝えるには、「課題の発生→分析→仮説→検証→成果」という流れを明確に描くことが効果的です。
感情的な表現よりも、数字や根拠を交えながら冷静に考えたプロセスを示すと、信頼性の高いエピソードになります。
②分析力・計画力をアピールする例文
研究ガクチカでは、計画を立てて課題を分析し、効率的に成果を出した経験を具体的に示すことが大切です。ここでは、課題分析から行動までのプロセスを明確に伝える例文を紹介します。
| 私は化学実験のグループ研究で、実験データのばらつきが大きく結果が安定しない課題に直面しました。そこで、全データを整理し、実験手順や使用器具の違いを要因別に分析しました。 分析の結果、温度管理のわずかなズレが原因だとわかり、作業工程を時間ごとに分けた実施スケジュールを作成しました。 その後、全員が同じ条件で測定できるようになり、再現性の高い結果が得られました。この経験を通して、問題を構造的に捉え、計画的に行動する力を磨くことができました。 |
分析力や計画力を伝えるには、「課題発見→要因分析→改善策→成果」の流れを意識しましょう。分析の過程で行った工夫や判断を丁寧に説明すると、実務にも通じる思考力を印象づけられます。
③継続力・粘り強さをアピールする例文
研究ガクチカで継続力を示すには、困難な状況でも諦めずに取り組んだ姿勢を具体的に伝えることがポイントです。ここでは、試行錯誤を重ねて成果を出したエピソードを紹介します。
| 私は生物学の研究で、実験データが想定どおりにならず、数か月間成果が出ない時期がありました。それでも原因をひとつずつ検証し、異なる培養条件を何度も試すことで徐々に改善点を見つけていきました。 途中で失敗が続いたときも、記録を詳細に残し、他の研究者の助言を取り入れて地道に実験を重ねました。最終的に、安定した再現性のある結果を得られ、卒業論文として発表することができました。 この経験から、結果が出ないときでも粘り強く取り組む姿勢の大切さを学びました。 |
継続力を伝える際は、「長期的な努力」や「試行錯誤の積み重ね」を具体的に書くことが効果的です。失敗や迷いの過程を入れることで、努力のリアリティが伝わりやすくなります。
④チームワーク・協調性をアピールする例文
研究ガクチカでは、個人の成果だけでなくチームとしてどう貢献したかを伝えることが求められます。ここでは、協力して課題を乗り越えた実体験を紹介します。
| 私は研究室での共同研究において、メンバー間の進捗に差があり、作業効率が落ちている状況を改善する役割を担いました。各自の得意分野を把握し、担当を明確に分けたスケジュールを作成しました。 また、定期的に進捗を共有するミーティングを提案し、互いの課題を相談しやすい雰囲気づくりにも努めました。 その結果、メンバー全員が同じ方向で作業を進められるようになり、研究全体の精度も向上しました。この経験から、協調しながらチームの力を最大化することの重要性を実感しました。 |
協調性を示すには、「自分がどのようにチームに貢献したか」を具体的に伝えることが大切です。全体をまとめる姿勢や他者を支えた行動を描くと、リーダーシップにもつながる印象を与えられます。
⑤リーダーシップ・主体性をアピールする例文
リーダーシップや主体性を示すには、自ら課題を見つけ、行動を起こした経験を語ることが効果的です。ここでは、研究の進行を自分の判断で改善したエピソードを紹介します。
| 私は物理学の研究グループで、実験の進捗が遅れていた時期に、スケジュール管理の見直しを提案しました。全員の作業負担を把握し、効率を高めるために実験手順を再構成しました。 具体的には、同時進行できるタスクを整理し、担当ごとの明確な目標を設定しました。その結果、予定より早く研究を進めることができ、学会発表にも間に合いました。 この経験を通じて、周囲を巻き込みながら課題を解決するリーダーシップと、状況に応じて行動する主体性を身につけました。 |
リーダーシップを伝えるには、単なる指示ではなく「チーム全体を良い方向へ導いた行動」を中心に描くことがポイントです。周囲への配慮や課題意識を示すと、信頼感のある印象になります。
⑥プレゼン力・伝達力をアピールする例文
研究ガクチカで伝達力をアピールするには、難しい内容をわかりやすく伝えた経験を中心に書くのが効果的です。ここでは、発表を通じて相手に理解を促したエピソードを紹介します。
| 私は卒業研究の成果を学内発表会でプレゼンする機会がありました。専門的な内容だったため、聴衆の理解を得るために専門用語を避け、図やグラフを多用して説明しました。 また、発表後の質問に対しても、相手の立場を意識してかみ砕いて答えることを意識しました。その結果、教授から「内容が非常にわかりやすい」と評価され、自分の伝達力に自信を持つことができました。 この経験を通して、相手の理解度を意識した発信の大切さを学びました。 |
プレゼン力を伝えるときは、「相手に伝える工夫」や「反応に応じた対応」を入れることが大切です。理解しやすい説明を心がけた姿勢を強調すると、実践的なコミュニケーション力が伝わります。
⑦失敗からの成長をアピールする例文
研究ガクチカでは、失敗をどう乗り越え、成長につなげたかを伝えることが大切です。ここでは、挫折から学びを得た経験を具体的に紹介します。
| 私は研究の初期段階で、データ分析の方法を誤り、何度も結果を出せずに悩んでいました。しかし、その原因を明確にするため、過去の研究資料を調べ、先輩に助言をもらいながら方法を一から見直しました。 その結果、正しい分析手順を理解し、再度実験を行うことで安定した結果を得られました。この経験を通して、失敗を恐れず改善に向き合う姿勢と、学び続ける重要性を実感しました。 結果として、自信を持って研究に取り組めるようになりました。 |
失敗からの成長を伝える際は、「原因分析」と「改善の行動」を中心に描くとよいでしょう。反省点を踏まえてどう成長したかを明確に書くことで、前向きで成長意欲の高い印象を与えられます。
専門性別|仕事内容との関連性を意識した研究ガクチカ例文
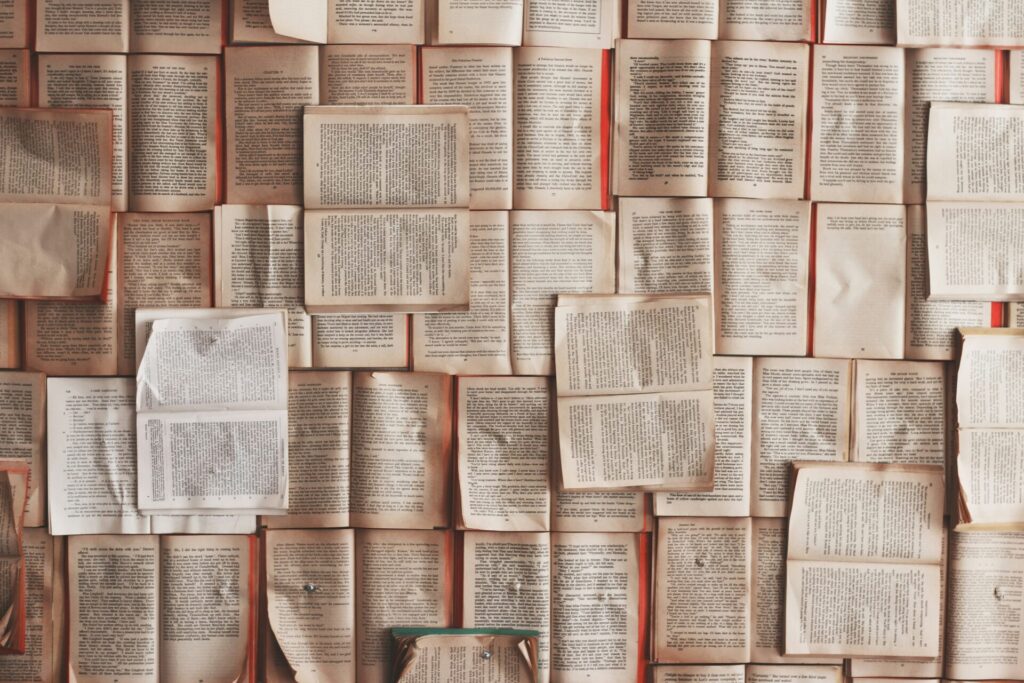
自分の研究内容が、志望する企業や職種とどのように結びつくのかを整理できていない就活生は多いものです。ここでは、研究と仕事の関連度に応じたアピール方法を例文付きで紹介します。
分野別に参考例を読むことで、自分に近いパターンを見つけやすくなるでしょう。
- 研究が業務に直結する場合の例文
- 研究と仕事内容が部分的に関連する例文
- 研究と業務が直接関係しない場合の例文
- 理系専門分野(工学・化学・情報系)の例文
- 文系研究(社会学・心理学・経済学)の例文
- 企業との親和性を強調した例文
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「AI ES」では【志望動機・ガクチカ・自己PR・長所・短所】を満足が行くまで何度も自動作成できます。実際に使用してみた感想などを以下の記事に掲載しているので、気になるけど登録するか迷っている方は記事を読んでみてくださいね。
【関連記事】
エントリーシート(ES)の作成をAIに丸投げ!「AI ES」サービスで就活
①研究が業務に直結する場合の例文
研究内容が志望職種の業務に直接つながる場合は、専門知識をどのように応用できるかを明確に伝えることが大切です。ここでは、研究が実際の仕事に直結するケースの例文を紹介します。
| 私は大学で環境工学の研究を行い、水質改善のための浄化技術を開発していました。実験では、汚染物質を効率的に分解できる新素材の性能を検証する過程で、多くの試行錯誤を繰り返しました。 その中で、データ分析と改善策の立案を通して、理論を実務に落とし込む力を身につけました。これらの経験は、御社の環境関連事業で技術的な課題を解決する際にも活かせると考えています。 研究を通じて培った分析力と応用力を、持続可能な社会づくりに貢献する形で発揮したいです。 |
研究と業務が直結する場合は、「研究テーマ→取り組み→成果→実務への応用」という流れで書くのが効果的です。専門知識を具体的にどのように活かせるかを伝えることで、即戦力としての印象を強められます。
②研究と仕事内容が部分的に関連する例文
研究内容が業務の一部や考え方に関係している場合は、どの点が共通しているかを具体的に示すことがポイントです。ここでは、部分的な関連性を活かした例文を紹介します。
| 私は大学でAIを活用した画像認識の研究を行っていました。直接的に製造業とは関係ありませんが、膨大なデータを整理し、効率的に分析するスキルを磨きました。 この経験は、御社の生産ラインにおける工程改善や品質管理の場面で応用できると考えています。 研究を進める中で、仮説を立てて検証するサイクルを何度も繰り返したことで、課題に対して柔軟にアプローチする力が身につきました。専門分野を超えて新しい分野に挑戦できることを楽しみにしています。 |
部分的な関連性をアピールする際は、「スキルや考え方の共通点」を軸に説明しましょう。分野が異なっても、業務に応用できる能力を具体的に示すことで説得力が生まれます。
③研究と業務が直接関係しない場合の例文
研究テーマが志望職種と関係ない場合でも、取り組み姿勢や学びのプロセスを通じて強みを伝えることが可能です。ここでは、研究分野と業務が異なるケースの例文を紹介します。
| 私は文学部で日本語表現に関する研究をしていました。専門分野としては志望業界と直接関係ありませんが、文章を分析する中で「伝わる言葉選び」や「読者の視点を意識する力」を身につけました。 この経験は、御社の広報や企画業務で相手のニーズを理解し、適切に伝える力として活かせると考えています。分野の違いにとらわれず、研究を通じて培った論理性と発想力を業務に応用していきたいです。 |
研究内容が業務と無関係でも、「どんな力が身につき、それをどう使うか」を明確にすれば十分に評価されます。テーマよりもプロセスや思考力に焦点を当てて書くのがコツです。
④理系専門分野(工学・化学・情報系)の例文
理系分野の研究をアピールする際は、専門的な用語に頼らず、成果や応用性を誰にでもわかる言葉で伝えることが重要です。ここでは、理系研究の例文を紹介します。
| 私は化学系の研究室で、新しい触媒材料の合成に取り組みました。研究では、反応効率を上げるために温度や圧力の条件を細かく調整し、再現性を高めることに注力しました。 その過程で、データを多角的に分析し、仮説を立てて改善策を試す力を身につけました。これらの経験は、御社の製品開発や品質管理でも役立つと考えています。 常に最適解を追求する姿勢を持ち、課題解決に粘り強く取り組む力を活かしたいです。 |
理系分野では、成果よりも「どんな方法で考え、何を工夫したか」を重視して伝えると効果的です。専門用語を使わずに説明できるかを意識すると、面接官にも伝わりやすくなります。
⑤文系研究(社会学・心理学・経済学)の例文
文系研究のアピールでは、調査・分析・考察を通じて得た洞察力やコミュニケーション力を中心に伝えることが有効です。ここでは、社会学や心理学などの分野を例に紹介します。
| 私は心理学の研究で、大学生のストレスと生活習慣の関係をテーマに調査を行いました。アンケート設計から統計分析まで自ら担当し、データを基に仮説を検証しました。 その結果、コミュニケーションの頻度がストレス軽減に大きく関係することを発見しました。この経験を通じて、課題を客観的に捉え、データをもとに結論を導く力を身につけました。 御社のマーケティング職でも、顧客の心理を分析し、データから最適な戦略を立てる際に活かせると考えています。 |
文系研究を伝える際は、調査や考察のプロセスを中心に構成し、「社会的な課題への洞察力」を示すことがポイントです。分析から行動へつなげた経験を書くとより実践的に響きます。
⑥企業との親和性を強調した例文
企業とのつながりを意識する場合は、自身の研究テーマが企業理念や事業内容とどのように共通しているかを示すことが重要です。ここでは、親和性を活かしたアピール例を紹介します。
| 私はエネルギー資源の有効活用に関する研究を行い、再生可能エネルギーの効率化をテーマに取り組んできました。 御社の「持続可能な社会づくり」という企業理念に深く共感し、研究で培ったデータ分析力や改善提案力を通じて事業に貢献したいと考えています。 特に、研究で学んだ「環境と経済の両立を意識した視点」は、御社の新規プロジェクトにおいても活かせると感じています。これまでの研究を基盤に、社会的意義のある挑戦を続けていきたいです。 |
企業との親和性を伝える際は、企業理念・事業内容・研究テーマの「共通点」を明確にすることが鍵です。自分の研究が企業の方向性にどう貢献できるかを具体的に語ると好印象を得られます。
NG例文と改善ポイント|失敗しない研究ガクチカの注意点
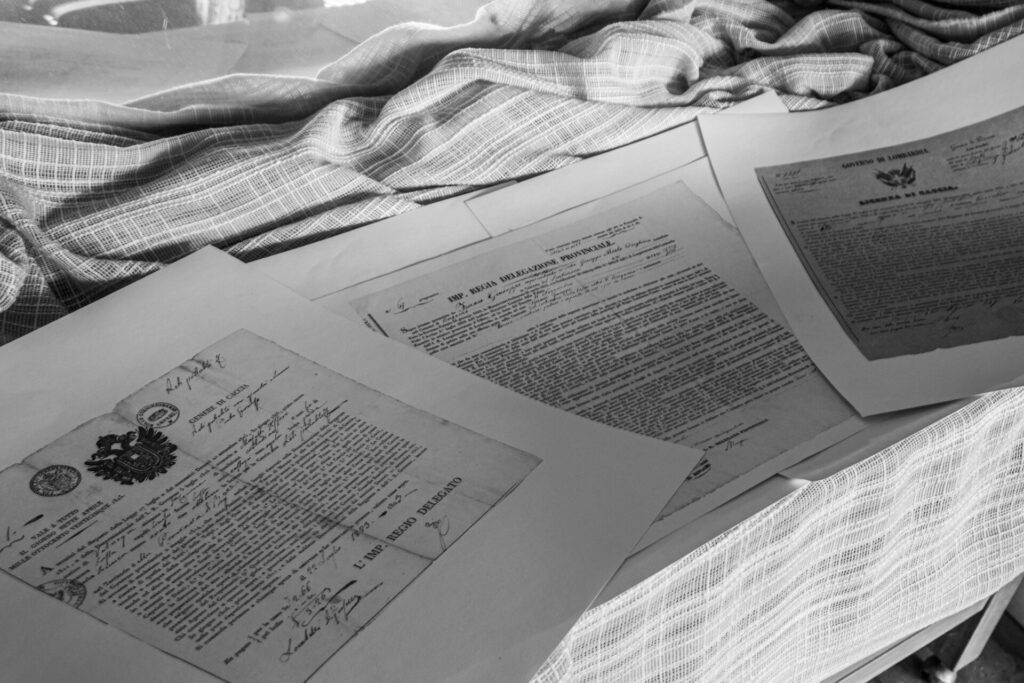
ガクチカで研究をテーマにするとき、意図せず伝わりにくい書き方をしてしまう就活生は少なくありません。ここでは、よくあるNG例文をもとに、どこが問題でどう直せば効果的に伝わるのかを解説します。
具体的な改善ポイントを知ることで、より魅力的なガクチカを作るヒントになります。
①専門用語が多く伝わりにくい例
専門用語を多用すると、採用担当者が内容を理解できず、あなたの強みが伝わらないことがあります。ここでは、難解な言葉で伝わりにくくなっているケースと、その改善例を紹介します。
| 私は有機化学分野での触媒反応の速度論的解析を行い、反応経路の最適化を実証しました。XRDおよびNMR解析により結晶構造を特定し、反応性の向上を確認しました。 さらに、遷移状態理論を応用して反応速度の定量化を行い、既存触媒との比較で優位性を明らかにしました。 |
専門用語ばかりだと、成果がすばらしくても伝わりません。「何を」「どう工夫したのか」を中学生でも理解できる言葉で書き換えましょう。具体的な行動や結果を平易に表現することが重要です。
②結果ばかりを強調して過程が薄い例
成果を伝えることに集中しすぎると、「どう努力したか」が見えず、評価につながりません。ここでは、過程が省略されてしまっている例を紹介します。
| 私は研究で新しい実験手法を確立し、他の学生よりも早く結果を出しました。その成果は学会でも評価され、教授からも高い評価を受けました。 |
結果だけでは「なぜ成果を出せたのか」が伝わりません。取り組みの工夫や苦労した点、考え方を具体的に入れることで、努力や成長の過程が見える文章に変わります。
③努力や課題解決の工夫が見えない例
成果や研究内容を説明しても、努力や改善点が見えないと印象が薄くなります。ここでは、工夫が伝わらない例を紹介します。
| 私は生物学の研究で植物の成長過程を観察し、データをまとめました。多くのサンプルを扱う中で数値を整理し、結果を発表しました。 |
作業の説明だけでは主体性が伝わりません。「どのような課題があり」「どう考えて改善したか」を具体的に入れることで、粘り強さや工夫が伝わる内容になります。
④客観性がなく自己満足で終わっている例
主観的な感想ばかりになると、研究の価値や努力が伝わりません。ここでは、客観性に欠ける例を紹介します。
| 私は研究を通して大きく成長できたと感じています。自分なりに頑張った結果、満足のいく成果を得ることができました。 |
「頑張った」「満足した」などの主観的表現は避けましょう。第三者の評価やデータ、具体的成果を添えることで、説得力のある内容になります。
⑤チーム貢献が欠けている例
個人の成果ばかりを強調すると、チームでの協働力が伝わりません。ここでは、協調性が見えないケースを紹介します。
| 私は研究で中心的な役割を担い、最も多くのデータをまとめました。自分の作業を優先し、他メンバーよりも効率的に成果を上げました。 |
チーム研究では、他者との連携も評価対象です。「どのように協力したか」「チームにどう貢献したか」を具体的に書くと、協働力のある印象を与えられます。
⑥研究以外との関連性がない例
研究内容だけに終始してしまうと、社会や仕事とのつながりが見えず、実践的な印象を持たれにくくなります。ここでは、関連性が弱い例を紹介します。
| 私は大学で物理実験の精度向上に取り組み、計測機器の扱いに習熟しました。装置の仕組みを深く理解し、正確なデータを取得することに成功しました。 |
研究自体は立派でも、「社会や企業にどう活かせるか」を補足すると印象が変わります。学びを仕事でどう応用できるかを具体的に言及しましょう。
研究ガクチカで魅力を最大限に伝えるために

ガクチカで研究をテーマにすることは、専門性や課題解決力を示す大きなチャンスです。企業は成果だけでなく、課題にどう向き合い、どんな工夫を重ねたかという「プロセス」に注目しています。
研究を通じて得た経験を効果的に伝えるには、専門用語を避け、PREP法でわかりやすく構成することが重要です。また、学部卒は柔軟性や学びの姿勢を、院卒は専門性と応用力を強調するとよいでしょう。
例文や注意点を参考に、自分の研究が社会や企業の価値創造にどうつながるかを意識することで、印象的なガクチカを作成できます。
最終的には、研究経験を「就職後に活かせる力」として一貫して伝えることが成功の鍵です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。