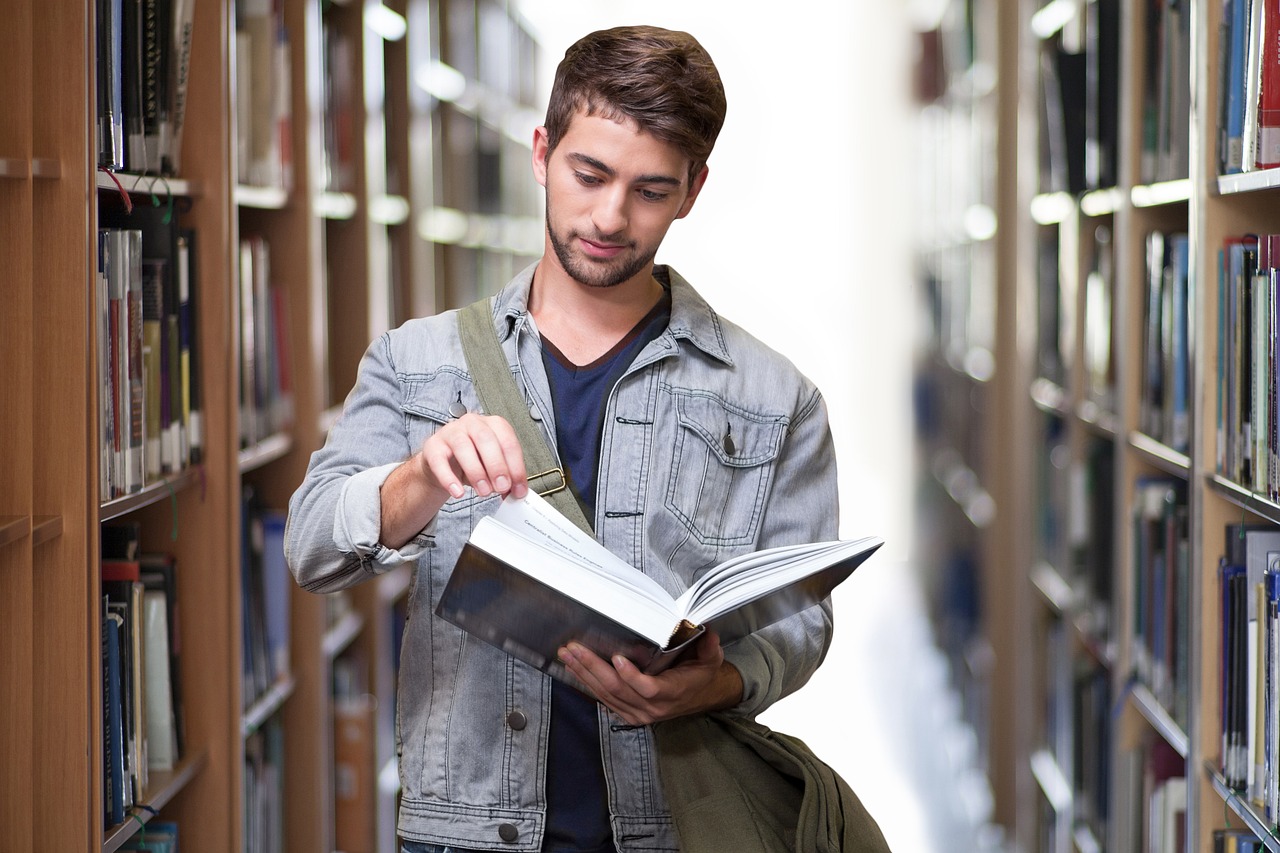ガクチカで趣味はアリ?企業が評価するガクチカの伝え方まとめ【例文付き】
「ガクチカに趣味って書いていいの?」と迷う人も多いのではないでしょうか。
一見プライベートな内容に思える趣味ですが、実は価値観や努力の姿勢、人柄を伝える大事な要素になり得ます。
しかし選び方や書き方を誤ると、軽く見られたり評価につながらなかったりするリスクもあります。
そこで本記事では、趣味を題材にしたガクチカの効果的な伝え方や避けるべきポイントを例文とともに解説します。就活の自己アピールに活かしたい方はぜひ参考にしてください。
ガクチカ作成のお助けアイテム
- 1ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 2赤ペンESでガクチカを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに
- 3ガクチカのテンプレシート
- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える
- 4強み診断
- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる
ガクチカで趣味はアピールできる?

就活でよく聞かれる「学生時代に力を入れたこと」、いわゆるガクチカにおいて、趣味を題材にしても良いのか不安に思う方は多いでしょう。
結論から言えば、趣味でも十分アピールは可能です。なぜなら企業は成果そのものよりも、取り組みに対する姿勢や考え方のプロセスを重視しているからです。
たとえばスポーツや音楽、読書など、一見就活に直接関係がなさそうな活動でも、目標設定や工夫、継続力を交えて伝えれば強みになります。
反対に「楽しいからやっていた」だけでは説得力に欠けます。大切なのは趣味自体ではなく、そこから得た学びや行動力を明確に示すことです。
この視点を持てば、平凡な趣味も独自性あるエピソードに変えられます。企業が知りたいのは努力し成長できる人材かどうかであり、その答えを示す構成が成功の鍵です。
企業がガクチカで評価しているポイント

就活生が「ガクチカ」で何を伝えればよいのか迷うのは自然なことです。採用担当者は活動内容だけでなく、その背景や考え方、成長のプロセスを重視します。
評価されるポイントは大きく分けて3つあります。価値観や志向性、課題に向き合う姿勢、そして経験からの学びや成長です。ここでは、それぞれの観点を具体的に解説します。
- 価値観や志向性の表れ
- 課題への取り組み姿勢
- 経験からの学びや成長
①価値観や志向性の表れ
ガクチカで大切なのは、活動そのものではなく「そこから見える価値観や志向性」です。例えば趣味を取り上げるなら、単に楽しいという話では十分ではありません。
なぜその趣味を続けているのか、どんな考えで取り組んでいるのかを語ることが求められます。企業は自社の価値観と合う人物かどうかを知りたいからです。
趣味を通して形成された考え方や姿勢を、具体的な行動やエピソードと結びつけて示すと説得力が増します。結局のところ、採用担当者が知りたいのは「あなたがどんな人なのか」という点でしょう。
だからこそ、表面的な活動内容ではなく志向性を伝えることが効果的です。
②課題への取り組み姿勢
採用担当者はガクチカを通して「課題への向き合い方」を確認しています。たとえ趣味であっても、困難に直面したときにどう解決したのかを語ると評価につながります。
例えばスポーツで結果が出なかった経験や、作品づくりで行き詰まった場面をどう乗り越えたのかを話すと、粘り強さや工夫が伝わりやすいです。
企業は完璧な成功よりも、問題にぶつかったときの行動を重視します。そのため課題を避けるのではなく、どう向き合ったかをエピソードとして描くことが大切です。
入社後も困難を乗り越えられる人物だと感じてもらえるでしょう。
③経験からの学びや成長
ガクチカで最後に見られるのは「経験を通じた学びや成長」です。成果を並べるだけではなく、その経験が自分にどう影響したのかを明確に伝える必要があります。
例えば趣味を続ける中で計画性が養われた、仲間とのやり取りを通じてコミュニケーション力が高まったといった学びを具体的に話すと効果的です。
さらに、その学びを今後のキャリアや志望企業でどう活かすかを結びつけると一層伝わりやすくなります。採用担当者は「この人は入社後に成長し続けるか」を見ています。
経験を振り返り、そこから得た気づきと未来への活用を示してください。
ガクチカで趣味をアピールするメリット

就活において「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」は必ず聞かれる質問ですが、テーマは勉強やアルバイトに限られません。趣味を題材にすることで、自分らしさを伝えることも可能です。
ここでは、趣味をガクチカで取り上げるメリットを3つの観点から紹介します。
- 他の就活生との差別化
- 人柄や個性の伝わりやすさ
- 面接官とのコミュニケーションのきっかけ
①他の就活生との差別化
趣味を題材にする大きな強みは、他の就活生と差をつけられる点です。サークルやアルバイトを選ぶ学生は多いですが、似たような内容では印象に残りにくいでしょう。
趣味であれば独自性があり、同じ活動でも取り組み方の工夫や努力の方向性が違います。
たとえば読書が趣味でも、「年間で100冊読み、その内容をブログで発信した」といったエピソードは継続力や発信力を示せます。
他の候補者とは異なる視点や経験を伝えられるため、印象に残りやすくなるのです。
②人柄や個性の伝わりやすさ
趣味をガクチカにすることで、人柄や価値観を自然に表現できます。なぜその趣味に惹かれたのか、どのように工夫して続けてきたのかを話せば、表面的なスキルだけでなく人間性も伝わるでしょう。
例えば料理が趣味なら「家族や友人が喜ぶ姿がやりがい」と話せば思いやりが感じられますし、レシピ開発や盛り付けを工夫した経験を伝えれば創造性も示せます。
趣味のエピソードはその人らしさを映し出す鏡であり、企業が重視する「一緒に働きたい人物像」に直結する要素といえるでしょう。
③面接官とのコミュニケーションのきっかけ
趣味を題材にすると、面接官との会話がスムーズになりやすいです。一般的なテーマでは質問が形式的になることも多いですが、趣味であれば興味を持って聞いてもらえる可能性が高いでしょう。
スポーツ観戦や旅行などは共感を呼びやすく、「私もその趣味があります」と返されることもあります。会話が広がれば緊張も和らぎ、自然体で話しやすくなるはずです。
結果として「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえる雰囲気を作り出せるのが、趣味をガクチカで話す大きな利点です。
アピールすべき趣味の特徴

就活の面接やエントリーシートで「ガクチカ」を書くときに、趣味を選んで良いのか迷う人は多いでしょう。ですが、趣味は単なる気分転換ではなく、その人の考え方や強みを伝える大切な要素になります。
大事なのは「企業が評価しやすい形」に整理して伝えることです。ここでは、スポーツやクリエイティブ、学びや日常的な趣味がどのようにアピールにつながるかを解説します。
- スポーツ・運動系の趣味
- クリエイティブ・表現系の趣味
- 学び・知識系の趣味
- 日常・実践系の趣味
①スポーツ・運動系の趣味
スポーツはチームワークや目標達成力を示すのに適しています。特に就活では「主体性」と「協調性」が評価されやすいため、部活動やサークルでの経験を具体的に伝えると効果的でしょう。
例えば、練習方法を工夫した経験や、仲間をまとめた役割を担った話を加えると説得力が高まります。
さらに、試合や大会を通して得たプレッシャーへの耐性や、結果が思うように出なかったときに立て直した工夫などもアピールポイントになります。
単に「楽しいから続けている」と説明するのではなく、課題を克服するまでの努力を語ることが重要です。スポーツ経験は「やり抜く力」の証拠でもあるため、継続性や成果を数字や具体例で示してください。
スポーツは健康管理の意識にもつながるため、社会人としての基礎力を示せる点も強みになるでしょう。
②クリエイティブ・表現系の趣味
絵画や音楽、動画制作といった趣味は発想力や表現力をアピールするのに役立ちます。
就活では「新しいアイデアを生み出せるか」が重視される業界もあるため、クリエイティブな趣味は強みになるでしょう。
作品を発表する際の工夫や、周囲からの意見を取り入れて改善した経験を話すと、成長意欲を示せます。さらに、作品作りを通して得られる時間管理能力や集中力も大切なアピール要素です。
締め切りを守るための工夫や、細部までこだわった姿勢を伝えると、実務に活かせる力として評価されやすくなります。また、継続して取り組んだ姿勢や探究心も評価されやすいです。
ただし、単なる特技紹介に終わらせず「どんな工夫をしたのか」「成果をどう活かすのか」を意識して伝えることが大切です。独創性だけでなく協調性や実行力もセットで示すと、より高く評価されるでしょう。
③学び・知識系の趣味
資格取得や語学学習、読書などの趣味は「自己成長意欲」を強調できるテーマです。企業は自ら課題を見つけ、学び続けられる人材を求めているため、このタイプの趣味は大きな武器になります。
例えば資格試験に向けて計画的に勉強した経験や、読書で思考力を養った話は効果的です。さらに学びをゼミやアルバイトに活かした例を示せば、実務への応用力も伝えられます。
語学学習なら、海外旅行で積極的に会話に挑戦したり、オンラインで外国人と交流したりしたエピソードを加えると実用性を伝えられます。
ただし、知識量だけを強調すると自己満足に見えるかもしれません。得た学びをどのように行動へ結びつけたかを必ず添えることで、説得力のあるアピールになります。
学び続ける姿勢は変化の多い社会に適応できる力としても高く評価されるでしょう。
④日常・実践系の趣味
料理や旅行、写真撮影などの日常的な趣味も十分にアピール材料になります。一見平凡に思えるかもしれませんが、工夫次第で「主体性」や「計画性」を伝えられるでしょう。
例えば料理ならレシピを工夫した経験や、仲間に振る舞って喜ばれた話を取り入れると良いです。旅行なら計画から実行までの流れや、予想外のトラブルを解決した経験を話すことで問題解決力を示せます。
さらに、写真撮影なら構図や光を意識した工夫、SNSでの発信を通して得た反応なども具体例にできます。こうした趣味は、日常にある課題を自分で見つけて工夫する姿勢を示すことにつながるでしょう。
大切なのは「ただの趣味紹介」で終わらせず、そこから得た学びやスキルを明確にすることです。身近な趣味でも、工夫して語れば立派なアピールにつながりますし、親近感を持たれる可能性も高まります。
避けた方が良い趣味の特徴

就活で趣味をガクチカに書くこと自体は問題ありませんが、内容によっては企業に誤解を与えたりマイナス評価につながる場合があります。
ここでは、避けた方が良い趣味の特徴を整理し、なぜ印象が悪くなるのかを具体的に解説します。正しく理解しておくことで、安心して自分の強みをアピールできるでしょう。
- ギャンブルやお金に関わる趣味
- お酒やタバコなど嗜好品に関する趣味
- 偏りが強すぎるオタク系の趣味
①ギャンブルやお金に関わる趣味
ギャンブルや投資などお金に直結する趣味は、就活において避けるべきです。理由は「金銭感覚が甘いのではないか」「リスクを軽視するのではないか」と不安を与えやすいからです。
特に新卒採用では誠実さや責任感が重視されるため、ギャンブル性の強い趣味は信頼性を損ねやすいでしょう。
ただし投資や金融に関心を持つこと自体は悪いことではありません。
語る場合は「経済ニュースを分析して情報収集力を磨いた」「統計データを使いリスク管理を意識した」など、学びやスキルに焦点を当てると良いです。
単なる遊びではなく成長につながる行動だと示すことで、面接官にも前向きに受け取られます。
②お酒やタバコなど嗜好品に関する趣味
お酒やタバコといった嗜好品は、社会人になれば身近な存在ですが、ガクチカに書くのは適切ではありません。
企業は「健康管理ができないのでは」「依存傾向があるのでは」と懸念する場合が多いためです。例えばサークル活動でお酒の場が多かったとしても、そのまま伝えるのは避けましょう。
「人をまとめる役割を担った」「イベントを企画して交流を深めた」など、そこで得た経験を強調してください。趣味自体ではなく、その場を通して得た力を語ることが大切です。
何を楽しんだかではなく、そこから何を学んだかを意識すると安心です。
③偏りが強すぎるオタク系の趣味
アニメやゲーム、アイドルなどの趣味は多くの学生にとって身近ですが、強くのめり込みすぎた印象を与えると「協調性がない」「仕事より趣味を優先するのでは」と受け取られる危険があります。
ただし工夫すればプラスに変えられます。例えば「アニメ研究で批評力を磨いた」「ゲーム開発に興味を持ちプログラミングを独学した」と伝えると、主体的な学びや努力を示せます。
趣味そのものを強調するのではなく、そこから得た知識や行動を中心に語ることが重要です。そうすれば一見マイナスに見える趣味も、成長体験としてアピールできるでしょう。
趣味を題材にしたガクチカを書く際のポイント

多くの学生が学業やアルバイトを題材に選ぶ中で、趣味を選ぶと差別化につながるでしょう。
ただし「好きだからやった」という説明だけでは評価されません。問題意識や工夫した点を具体的に盛り込むことが重要です。
ここでは、趣味を題材にしたガクチカを書く際のポイントについて紹介していきます。
- 力を入れて取り組んだ趣味の選定
- 強みや長所を引き出すエピソードの活用
- 成功体験と失敗経験の両方の提示
- 仕事に結び付けられる学びの整理
①力を入れて取り組んだ趣味の選定
趣味を題材にする場合、どのエピソードを選ぶかで印象は大きく変わります。企業は「結果」より「過程」を重視するので、努力や工夫が伝わる題材を選んでください。
日常的に続けてきた習慣や挑戦を通じて得た気づきが含まれる趣味なら、自分らしさを表現できます。
例えば楽器演奏なら、舞台に立ったこと自体よりも、練習を積み重ねて上達した努力に焦点を当てる方が評価されやすいです。
選び方を誤ると自己満足に映るおそれがありますが、主体性や問題解決力を示せるエピソードを選べば、就職活動で強力なアピール材料になるでしょう。
②強みや長所を引き出すエピソードの活用
趣味を通して強みを示すには、自分の行動がどのような成果や変化につながったのかを具体的に語る必要があります。
「努力した」だけでは説得力が弱く、困難をどう乗り越えたかや周囲にどんな影響を与えたかを示すことが大切です。
例えば読書が趣味なら、知識を深めてゼミの議論を活性化させた経験を語ると、主体性と知的好奇心の両方が伝わります。
エピソードを選ぶ際は、自分の成長や貢献が曖昧にならないよう注意してください。強みを自然にアピールすることで「仕事でも活躍できそうだ」と面接官に感じさせられるでしょう。
③成功体験と失敗経験の両方の提示
ガクチカで成功だけを強調するとリアリティに欠ける場合があります。むしろ失敗から学んだ過程を含めることで、主体性や成長意欲を伝えられるでしょう。
例えば資格試験の勉強を趣味として取り組んだ場合、最初は計画不足で不合格を経験したが、学習方法を改善して次回は合格した、という流れが効果的です。
このように「失敗を踏まえて改善する姿勢」は社会人に必要な資質として評価されます。失敗を隠さず、そこから得た学びを仕事にどう活かせるかまで言及すると、面接官に信頼感を与えられるはずです。
④仕事に結び付けられる学びの整理
趣味と仕事をどう関連づけるかで、ガクチカの質は大きく変わります。企業は「趣味そのもの」ではなく「そこから得た学び」を重視します。
スポーツならチームワークや継続力、クリエイティブ活動なら発想力や問題解決力など、職場で役立つ要素に結びつけると効果的です。
無理に関連づける必要はなく、関連が薄い場合でも取り組み姿勢や改善の工夫に焦点を当てれば十分評価されます。
仕事に応用できる学びを整理して伝えることで、趣味を単なる余暇ではなく、自分の成長の証明として示せるでしょう。
ガクチカに趣味を書く際の5ステップ

就活で「ガクチカ」に趣味を取り上げるときは、自己流で書くよりも段階を意識することで評価につながりやすくなります。
趣味をそのまま並べるのではなく、経験から得た成長や仕事への結びつきを論理的に伝えることが大切です。以下の5ステップに沿って整理すれば、誰でも説得力のある文章を作れるでしょう。
ここでは、ガクチカに趣味を書く際の書き方をステップ別に紹介していきます。
- 結論の提示(趣味を通じた経験)
- 趣味に取り組んだきっかけ
- 具体的な取り組み内容
- 趣味から得た学びや成長
- 将来や仕事への活かし方
①結論の提示(趣味を通じた経験)
最初に伝えるべきは、趣味を通じて得た経験や成果です。冒頭で要点を示すことで読み手が安心し、その後の内容を理解しやすくなります。
例えば「サークルで続けたバスケットボールを通じて、粘り強く課題に取り組む姿勢を身につけました」と端的に書くと効果的でしょう。
結論を明確にすれば話がぶれず、読み手に「この人は何を伝えたいのか」が伝わります。逆に背景から長々と書くと印象が弱くなることも少なくありません。
冒頭で結論を示すことで自信を持った姿勢が伝わり、選考担当者に好印象を与えやすくなるのです。
②趣味に取り組んだきっかけ
次に重要なのは、なぜその趣味を始めたのかという点です。きっかけを伝えることで、活動紹介にとどまらず自分の価値観や行動特性を表現できます。
例えば「友人に誘われて始めたが、次第に自主的に工夫して取り組むようになった」といった流れを語れば主体性の成長が自然に伝わります。
きっかけが曖昧だと「なぜ続けたのか」が伝わらず説得力が弱まるでしょう。原点を具体的に示すことで自己分析の深さや継続力を伝えられます。
ここでは単なる説明ではなく、自分の人柄や姿勢を表す大切な要素になるのです。
③具体的な取り組み内容
ここでは趣味に対してどう取り組んだかを具体的に説明することが重要です。内容を明確にすると努力や工夫のプロセスが伝わり、読み手は「行動の再現性」を感じ取れます。
例えば「週3回の練習に加えて自宅で自主トレーニングを続けた」「大会前には戦術を分析し役割を模索した」といった記述が効果的でしょう。
ただ「頑張った」とだけ伝えても差別化は難しいものです。数字や具体的な行動を盛り込むことで説得力が高まります。
こうしたプロセスを描くと課題への姿勢や努力の質を示せ、社会人としての可能性が伝わりやすくなるのです。
④趣味から得た学びや成長
趣味のエピソードを体験談で終わらせないために、そこから得た学びや成長を示すことが欠かせません。
例えば「時間管理の大切さを学んだ」「チームで成果を出すには信頼が必要だと気づいた」といった気づきを書けば、活動の意味がより深まります。
事実だけでなく、自分なりの考えを添えると考える力が伝わるでしょう。逆に「楽しかった」という表現だけでは評価にはつながりません。
趣味を通じて得た知見を社会で活かせる形に整理することで、「経験を成長に変えられる人だ」と面接官に感じてもらえるはずです。
⑤将来や仕事への活かし方
最後に、趣味で得た力をどのように将来や仕事に結びつけるかを伝えることで、自己PRとして完成します。
例えば「プレゼン大会に挑戦した経験から培った表現力を営業職で活かしたい」といった具体的な関連付けが効果的です。
大切なのは理想論ではなく、趣味から得たスキルと仕事との関係を明確にすることです。曖昧な表現では「きれいごと」に受け取られるかもしれません。
具体的な関連性を示すことで、自分の経験が社会人としての資質に直結していると伝わります。ここをしっかりまとめることで「学生時代の経験が未来に生きる」というストーリーが仕上がるのです。
スポーツ系の趣味のガクチカ例文5選

スポーツを趣味として取り組んできた経験は、自己管理能力や協調性をアピールするのに効果的です。ここでは、代表的なスポーツ系の趣味を題材にしたガクチカ例文を紹介します。
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①筋トレの例文
大学生活の中で体力づくりを目的に始めた筋トレは、努力の積み重ねを示しやすいテーマです。ここでは、その経験を題材にした例文を紹介します。
| 大学に入学した当初、友人と一緒に筋トレを始めました。最初は重りを持ち上げることすら難しく、思うように成果が出ずに諦めそうになった時期もありました。 しかし毎日少しずつ続けることを意識し、週3回ジムに通い続けることで、半年後には体力テストの記録が大きく伸びました。 その結果、自分に自信を持てるようになり、ゼミの活動やアルバイトでも積極的に意見を伝えられるようになったと感じています。 筋トレを通じて得た「継続の大切さ」は、今後の学びや仕事でも必ず役立つと考えています。 |
筋トレのエピソードは「努力の継続」と「自信の成長」をわかりやすく伝えられるのが強みです。数字や期間を具体的に盛り込むことで、説得力を高めることができます。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
②ランニングの例文
体力づくりや気分転換のために始めたランニングは、多くの学生が挑戦しやすい趣味です。努力の継続や自己成長を示す題材としても有効です。ここでは、ランニングの趣味についての例文を紹介します。
| 大学2年の春から、健康維持のために毎朝ランニングを始めました。最初は1km走るだけで息が切れ、続けることに不安を感じていました。 しかし記録を残しながら少しずつ距離を伸ばし、仲間と一緒に練習することで習慣化することができました。半年後には5kmを無理なく走れるようになり、学内マラソン大会にも参加しました。 この経験を通じて、地道な積み重ねが確かな成果につながることを実感し、日常の勉強やサークル活動でも粘り強く取り組む姿勢を持てるようになりました。 ランニングは心身の成長と自信を与えてくれた大切な経験です。 |
ランニングの例文は「習慣化」と「成長の実感」を伝えやすいのが特徴です。数字や距離などの成果を盛り込むことで、読んだ人にリアルな努力のイメージを与えることができます。
③フットサルの例文
仲間との協力やチームワークをアピールできるテーマとして、フットサルは非常に効果的です。ここでは大学生活での経験を基にした例文を紹介します。
| 大学の友人に誘われて始めたフットサルは、最初は運動不足解消のつもりでした。しかし週末ごとに練習を重ねるうちに、仲間との連携を意識してプレーすることが大切だと気づきました。 試合では個人の技術よりも声を掛け合い、ポジションを補い合うことでチーム全体の力が発揮されると実感しました。 特に大会前には戦術を話し合い、全員で工夫を重ねたことで初めて勝利を掴むことができました。 この経験を通じて、周囲と協力して目標を達成する喜びを学び、ゼミ活動やアルバイトでも積極的に周りと協力し合う姿勢を持てるようになりました。 |
フットサルの例文は「協力」や「チームワーク」を自然に表現できるのがポイントです。成果だけでなく過程での工夫や気づきを具体的に書くことで、より説得力が増します。
④バスケットボールの例文
仲間との連携や主体的な行動を伝える題材として、バスケットボールはガクチカに最適です。ここでは、大学生活での経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学に入学してから友人に誘われ、サークルでバスケットボールを始めました。 最初は基礎的な技術が未熟で試合でも活躍できず悔しい思いをしましたが、毎週の練習で基礎練習を繰り返し、上級生にアドバイスをもらいながら努力を続けました。 その過程で、個人の力だけでは勝てない競技だからこそ、声を掛け合い仲間と連携することの大切さを学びました。 特に大会では、試合中に積極的に声を出して仲間を鼓舞した結果、チームの雰囲気が高まり接戦を勝ち切ることができました。 この経験から、周囲と協力して挑戦する姿勢を身につけ、ゼミ活動やアルバイトでも主体的に周囲を巻き込む行動を意識するようになりました。 |
バスケットボールのエピソードは「協調性」と「主体性」を同時に示せるのが強みです。自分の行動がチーム全体に与えた影響を描くと説得力が増します。
⑤釣りの例文
自然の中で集中力や忍耐力を育む経験として、釣りは就活で語れる魅力的な趣味のひとつです。ここでは、大学生活における体験をもとにした例文を紹介します。
| 大学の友人に誘われて初めて釣りに出かけたとき、最初は何時間待っても成果が出ず、正直退屈に感じました。 しかし通ううちに「仕掛けを工夫する」「環境を観察する」といった小さな改善が成果につながることを学びました。 特に夏休みに何度も川へ通い、狙い通りに魚が釣れた瞬間には大きな達成感を味わいました。この経験を通じて、結果が出ないときでも粘り強く取り組む姿勢を身につけることができました。 その粘り強さは、ゼミでの研究やアルバイトの課題解決においても役立ち、自信を持って行動できるようになったと感じています。 |
釣りの例文は「忍耐力」や「工夫」をアピールできるのがポイントです。待つだけでなく改善点を示すことで、努力の姿勢を伝えやすくなります。
クリエイティブ系の趣味のガクチカ例文5選

クリエイティブな趣味は、自分の感性や表現力をアピールできる魅力的な題材です。ここでは、代表的なクリエイティブ系の趣味をもとにしたガクチカ例文を紹介します。
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①音楽の例文
音楽活動は継続力や協調性をアピールできるテーマとして人気があります。ここでは、大学生らしい日常の取り組みをもとにした例文を紹介します。
| 大学入学後、仲間と軽音サークルに入りギターを始めました。最初はコードを押さえるだけでも苦労し、練習についていけないこともありましたが、授業後や休日に繰り返し練習を重ねました。 特に学園祭に向けては、メンバーと何度も合わせ練習を行い、演奏が揃ったときの達成感は格別でした。 本番では緊張しながらも観客の前で演奏をやり切り、大きな拍手をいただいたことが自信につながりました。 この経験を通じて、目標に向けて努力を続ける大切さや、仲間と協力することで大きな成果を得られる喜びを学びました。 音楽は単なる趣味ではなく、自分の挑戦心や協調性を育ててくれた大切な経験です。 |
音楽の例文は「努力の継続」と「仲間との協力」を同時に表現できる点が強みです。練習過程や本番での成果を具体的に示すと説得力が増します。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
②絵・イラストの例文
絵やイラストは自己表現力や集中力を示すテーマとして人気があります。ここでは、大学生活での経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学に入ってから、趣味として本格的にイラスト制作を始めました。最初は思い通りに描けず何度も描き直す日々が続きましたが、毎日少しずつ練習を積み重ねました。 特に学園祭のポスター制作を任された際には、仲間からの意見を取り入れながらデザインを工夫し、完成までに多くの時間を費やしました。 仕上がったポスターが会場に掲示され、多くの学生から「分かりやすい」と評価されたとき、大きな達成感を得ることができました。 この経験を通じて、粘り強く努力を重ねる力と、人の意見を柔軟に取り入れる姿勢を学びました。イラストは自分の成長を感じさせてくれる大切な趣味です。 |
絵やイラストの例文は「表現力」と「協調性」を自然に伝えやすいのが特徴です。制作過程での工夫や他者との関わりを加えると説得力が高まります。
③カメラの例文
写真撮影は観察力や表現力をアピールできるテーマとしておすすめです。ここでは、大学生活の体験をもとにした例文を紹介します。
| 大学入学後、風景写真に興味を持ちカメラを購入しました。最初は構図や光の扱いが分からず、思い通りの写真が撮れず悔しい思いをしました。 しかし休日に何度も撮影に出かけ、撮った写真を見返しながら改良を重ねることで少しずつ上達しました。 特に学内イベントで写真係を任された際には、被写体の動きを予測しながら撮影することを意識し、仲間から「雰囲気が伝わる」と評価を得られました。 この経験を通じて、粘り強く学び続ける力と、物事を多角的に見る姿勢を身につけることができました。写真撮影は単なる趣味を超え、自分の成長を実感させてくれる大切な活動になりました。 |
カメラの例文は「観察力」と「工夫」をアピールできるのが強みです。改善の過程や他者からの評価を盛り込むと説得力が高まります。
④映画鑑賞の例文
映画鑑賞は感受性や分析力を示せるテーマとして有効です。ここでは、大学生が日常的に取り組みやすい経験を題材にした例文を紹介します。
| 大学生活の中で映画鑑賞を趣味にし、週末ごとにさまざまなジャンルの作品を観るようになりました。 最初は単純に楽しむだけでしたが、次第に監督の意図や登場人物の心情に注目し、感想をノートにまとめるようになりました。 特に海外映画を観ることで異なる文化や価値観を知ることができ、自分の考えを広げるきっかけとなりました。 また、ゼミの発表で映画を題材に取り上げた際には、自分の意見を根拠とともに伝える力が身についたと実感しました。 映画鑑賞を通じて得た「多様な視点で物事を考える力」は、今後の学びや社会生活でも役立つと感じています。 |
映画鑑賞の例文は「思考力」と「多様な価値観への理解」を伝えやすいのが特徴です。観るだけでなく、感じたことを整理する工夫を書くと説得力が高まります。
⑤ゲームの例文
ゲームは一見遊びのように思われがちですが、戦略性や協調性をアピールできる題材です。ここでは、大学生活の経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学に入学してから友人に誘われ、オンラインゲームを定期的にプレイするようになりました。最初は楽しむだけでしたが、チーム戦に参加する中で役割分担や作戦を立てる重要性に気づきました。 仲間と協力して試合を重ねることで、勝敗にかかわらず「どう改善すべきか」を話し合い、次の挑戦に活かす姿勢が身につきました。 特に大会に出場したときには、戦術を練習して臨んだ結果、予選を突破できたことが大きな達成感となりました。 この経験を通じて、課題を振り返り改善する力や、仲間と協力して成果を出す喜びを学びました。ゲームは自分の成長を感じられる大切な趣味だと考えています。 |
ゲームの例文は「協力」と「改善力」をアピールできるのが魅力です。単なる娯楽としてではなく、成長や学びにつながる視点を加えると説得力が増します。
学び・知識系の趣味のガクチカ例文5選
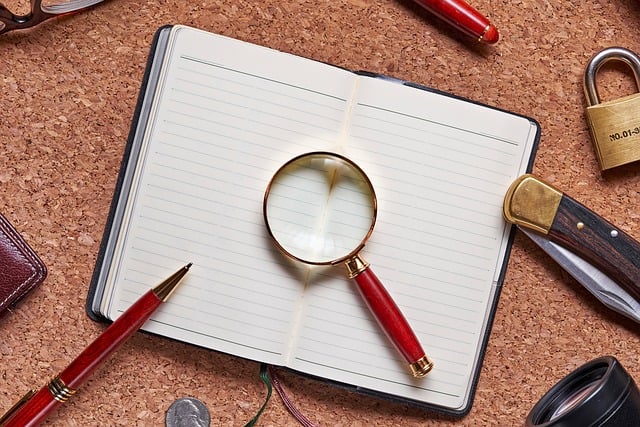
学びや知識に関する趣味は、自分の努力や成長をわかりやすく伝えられる強みがあります。ここでは、代表的な学び・知識系の趣味を題材にしたガクチカ例文を紹介します。
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①語学学習の例文
語学学習は努力の積み重ねや挑戦心をアピールできるテーマです。ここでは、大学生活の中で取り組みやすい経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学入学後、海外旅行をきっかけに英語を真剣に学ぼうと決意しました。最初はリスニングが苦手で会話も思うようにできず、悔しい思いをしました。 しかし毎日少しずつニュースを聞いたり、友人と英語で会話する機会を作ったりして練習を続けました。 特に半年間の交換留学生との交流では、自分の言葉が相手に伝わったとき大きな達成感を味わいました。その経験を通じて、学びを継続する大切さや自分から積極的に挑戦する姿勢を身につけました。 語学学習を通じて得た粘り強さや行動力は、将来のキャリアにも役立つと確信しています。 |
語学学習の例文は「継続力」と「挑戦心」を自然に表現できるのがポイントです。小さな成長を積み重ねて描くと、よりリアルで説得力のある内容になります。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
②読書の例文
読書は知識の幅を広げるだけでなく、考える力や表現力をアピールできるテーマです。ここでは、大学生活での経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学に入ってから、時間を見つけては図書館で本を読む習慣をつけました。 最初は授業に関係する本だけを読んでいましたが、次第に小説やエッセイ、歴史書など幅広いジャンルに挑戦するようになりました。 その中で特に印象に残ったのは、自分の考え方とは異なる視点に触れられることでした。 ゼミでのディスカッションでは、本で得た知識や考え方を引用して意見を述べることができ、議論を深めるきっかけになりました。 読書を通じて学んだ「多角的に物事を考える姿勢」は、学業だけでなくアルバイトや人間関係にも活かされています。読書は私にとって、成長を支える大切な習慣になっています。 |
読書の例文は「思考力」や「多様な視点」をアピールできるのが魅力です。具体的にどんな影響があったのかを加えると、説得力のある内容になります。
③旅行の例文
旅行は新しい経験や価値観の広がりをアピールできるテーマです。ここでは、大学生活での旅行体験を題材にした例文を紹介します。
| 大学2年の春休みに友人と計画して国内を一週間旅行しました。 最初は観光を楽しむことだけを目的にしていましたが、宿泊先や移動手段を自分たちで調整する過程で、計画性や柔軟な対応力の大切さを学びました。 旅の途中で電車が遅延し予定通りに進まない場面もありましたが、仲間と相談して代替案を考え、無事に目的地に到着できました。 この経験を通じて、状況に合わせて行動する力や協調性を身につけることができました。また、各地で地元の人と交流する中で、自分の視野が広がり異なる価値観を理解するきっかけにもなりました。 旅行は単なる楽しみだけでなく、自分を成長させる貴重な体験となりました。 |
旅行の例文は「計画性」と「柔軟性」を示せる点が強みです。予想外の出来事にどう対応したかを書くことで、成長がより具体的に伝わります。
④プログラミングの例文
プログラミングは論理的思考や問題解決力を示せるテーマです。ここでは、大学生が取り組みやすいエピソードを題材にした例文を紹介します。
| 大学の授業をきっかけにプログラミングに興味を持ち、独学で学び始めました。 最初はエラーが出るたびに挫折しそうになりましたが、インターネットで調べたり友人に相談したりして少しずつ理解を深めました。 特に、サークル活動で使う簡単な出欠管理アプリを作ったときには、多くの試行錯誤を重ねながら機能を完成させ、仲間から「便利になった」と喜ばれたことが大きな達成感につながりました。 この経験を通じて、地道に努力を重ねる大切さと、問題に直面したときに解決策を探し続ける姿勢を学びました。 プログラミングは私にとって、自分の成長を実感できる趣味であり、挑戦心を育ててくれる大切な活動です。 |
プログラミングの例文は「問題解決力」と「継続力」を伝えやすいのが強みです。成果物を示すと説得力が高まり、就活でも印象を残しやすくなります。
⑤勉強の例文
勉強を趣味として取り組む姿勢は、努力や向上心を強調できるテーマです。ここでは、大学生活での経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学入学後、専門科目に加えて資格試験の勉強にも取り組みました。最初は授業との両立が難しく、計画通りに進められずに挫折しそうになりました。 しかし、毎日の空き時間を有効活用するために学習計画を細かく立て、図書館で集中して勉強する習慣をつけました。 その結果、試験前には自信を持って臨めるようになり、見事に合格することができました。この経験を通じて、目標を達成するためには継続的な努力と計画性が欠かせないことを学びました。 また、勉強を続けることで自分に自信がつき、ゼミ発表やグループワークでも積極的に意見を述べられるようになりました。勉強は私にとって、成長を実感させてくれる大切な趣味です。 |
勉強の例文は「計画性」と「継続力」をアピールできるのが特徴です。努力の過程を具体的に描くと、説得力がより高まります。
日常・実践系の趣味のガクチカ例文5選

日常生活に根ざした趣味は、身近でありながらも努力や工夫を伝えやすいテーマです。ここでは、日常・実践系の趣味を題材にしたガクチカ例文を紹介します。
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①料理の例文
料理は工夫や継続をアピールできるテーマであり、ガクチカに取り入れやすい趣味のひとつです。ここでは、大学生らしい体験を題材にした例文を紹介します。
| 大学に進学して一人暮らしを始めたことをきっかけに、毎日の自炊を習慣化しました。 最初は簡単な炒め物やインスタントに頼ることが多かったのですが、健康面を考えて少しずつレシピを調べ、調理方法を工夫するようになりました。 特に友人を招いて料理を振る舞った際には「おいしい」と評価をもらい、大きな達成感を得ました。 また、料理を通じて段取り力や効率を意識するようになり、同時に複数の作業を進める力が身につきました。 この経験はゼミ発表の準備やアルバイト業務にも役立ち、限られた時間で成果を出す力へとつながったと感じています。料理は自分に自信を与えてくれる大切な趣味です。 |
料理の例文は「工夫」や「段取り力」を表現できるのが強みです。成果だけでなく過程を具体的に描くことで、説得力を高められます。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
②ボランティア活動の例文
ボランティア活動は主体性や社会貢献の姿勢をアピールできるテーマです。ここでは、大学生が取り組みやすい経験をもとにした例文を紹介します。
| 大学1年の夏休みに地域の清掃活動に参加したことをきっかけに、ボランティアに継続的に取り組むようになりました。 最初は単純に街をきれいにする作業でしたが、回数を重ねるうちに住民の方から感謝の言葉をいただき、自分の行動が地域に役立っていると実感しました。 さらに、イベントの運営を手伝う機会もあり、限られた時間の中で役割分担や協力が必要になることを学びました。その結果、仲間と協力して成功を収めたときには大きな達成感を得られました。 この経験を通じて、主体的に行動する姿勢や協調性を育むことができました。ボランティア活動は社会に貢献する喜びと、自分自身の成長を感じられる大切な経験となりました。 |
ボランティア活動の例文は「主体性」と「協調性」を強調できるのがポイントです。感謝された経験や役割分担の工夫を加えると説得力が高まります。
③DIYの例文
DIYは工夫や実践力をアピールできるテーマで、ガクチカにも活かしやすい題材です。ここでは、大学生活での取り組みをもとにした例文を紹介します。
| 大学で一人暮らしを始めた際、家具をそろえるためにDIYに挑戦しました。最初は不器用で釘をうまく打てず失敗ばかりでしたが、動画や本で基礎を学びながら少しずつ慣れていきました。 特に本棚を自作したときには、設計から組み立てまで何度もやり直しを重ね、最終的に実用的で丈夫なものを完成させました。完成した家具を使うたびに努力の成果を実感でき、達成感を得られました。 また、この経験を通じて、計画を立てて試行錯誤を繰り返す大切さや、粘り強く物事に取り組む姿勢を学びました。DIYは単なる趣味を超えて、自分の成長を支えてくれる活動となりました。 |
DIYの例文は「工夫」と「粘り強さ」を表現できるのが魅力です。完成品や具体的な工程に触れると、より説得力のある内容になります。
④ガーデニングの例文
ガーデニングは継続力や工夫をアピールできるテーマであり、ガクチカに活かしやすい趣味のひとつです。ここでは、大学生が経験しやすいエピソードをもとにした例文を紹介します。
| 大学入学後、ストレス解消のためにベランダでガーデニングを始めました。 最初は水やりの頻度を間違えて枯らしてしまうこともありましたが、植物ごとの特徴を調べて育て方を工夫するうちに少しずつ成果が出てきました。 特にミニトマトを育てた際には、毎日の世話が実を結び、自分で収穫して食べられたとき大きな達成感を得ました。 また、ガーデニングを通じて計画的に取り組む大切さや、小さな積み重ねが成果につながることを学びました。この経験は勉強やアルバイトでも粘り強く努力する姿勢に活かされています。 ガーデニングは私に根気強さを教えてくれる大切な趣味です。 |
ガーデニングの例文は「継続力」と「工夫」を伝えやすいのが魅力です。失敗から学んだ点を盛り込むと、よりリアルで説得力のある内容になります。
⑤ペットのトレーニングの例文
ペットのトレーニングは責任感や忍耐力をアピールできるテーマです。ここでは、大学生活に寄り添った一般的なエピソードをもとにした例文を紹介します。
| 大学入学後、実家で飼っていた犬の世話を本格的に引き受けるようになり、トレーニングに挑戦しました。最初はおすわりや待てなどの基本動作すらうまくできず、思うように進まないことに悩みました。 しかし、毎日少しずつ練習を繰り返し、できたときにはしっかり褒める工夫をしたことで、次第に指示を理解してくれるようになりました。 特に散歩中に引っ張らずに歩けるようになったときは、自分の努力が実を結んだと実感しました。この経験を通じて、根気強く取り組む大切さや信頼関係を築く力を学びました。 ペットのトレーニングは、忍耐と責任を養う貴重な趣味となりました。 |
ペットのトレーニングの例文は「忍耐力」と「責任感」を示せるのが特徴です。小さな成長を積み重ねて描くと、説得力のある内容になります。
趣味のガクチカでよくある質問Q&A

就活生の中には「趣味をガクチカにして良いのか」と不安に思う人も多いでしょう。ここでは、趣味を題材にしたガクチカに関するよくある質問と、その答えをまとめました。
短期間の趣味でも伝え方次第で評価されますし、初心者レベルや複数の趣味も工夫すれば十分アピール可能です。面接で深掘りされる場面や、自己PRとの違いをどう整理するかも大切なポイントです。
ここでは、趣味のガクチカでよくある質問Q&Aについて紹介していきます。
- 短期間の趣味でもアピールできるか
- 複数の趣味をまとめて伝えてもよいか
- 初心者レベルの趣味でも評価されるか
- 面接で趣味について深掘りされた場合はどう答えるか
- 学業やアルバイトと趣味の両立はどう伝えるべきか
- 趣味と自己PRの内容がかぶっても良いか
①短期間の趣味でもアピールできるか
短期間の趣味だと「深みがないのでは」と感じる人もいますが、結論から言えばアピールは可能です。評価の基準は期間ではなく姿勢にあります。
例えば3か月間集中して資格取得を目指した、短期合宿でスキルを習得したといった取り組みは、短期でも高く評価されます。
大切なのは「なぜ始めたのか」「どんな目標で工夫したのか」「どう成長したのか」を明確に話すことです。逆に期間だけを強調すると説得力に欠けます。
短期間だからこそ計画性や集中力を示せると考えれば、印象に残る自己PRになるでしょう。
②複数の趣味をまとめて伝えてもよいか
複数の趣味をまとめて話すことは可能ですが、注意が必要です。数の多さをアピールするのではなく、共通点から強みを導くことが大切になります。
例えば読書と映画鑑賞で「多様な価値観を理解する姿勢」を得た、スポーツと音楽で「継続力とチームワーク」を培った、など一貫したテーマを設定すれば説得力が高まります。
逆にただ羅列すると「浅い」と感じられる恐れがあります。趣味に共通する学びを軸に整理し、一つのストーリーとして展開することで「幅広さと深さを持つ学生」という印象を残せるでしょう。
③初心者レベルの趣味でも評価されるか
初心者だからといって評価されないわけではありません。重要なのは取り組み方と学びです。
例えばランニングを始めたばかりでも、毎朝続けるためにスケジュールを工夫した経験や、小さな目標を達成して自信を得た体験は十分なアピール材料です。
面接官は完成度よりも努力の過程や成長を見ています。単に「趣味程度です」と答えると浅く聞こえるため注意しましょう。
初心者だからこそ「挑戦心」や「新しいことに取り組む姿勢」を強調できます。結局のところ、レベルの高さではなく具体的な姿勢や学びが評価の分かれ目です。
④面接で趣味について深掘りされた場合はどう答えるか
面接で趣味を深掘りされると答えに詰まる人もいますが、準備しておけば大きなチャンスになります。深掘り質問は本音や行動パターンを知るためにされることが多いので、具体的な答えが必要です。
「なぜ始めたのか」と問われたら動機を明確に語り、「どんな工夫をしたか」と聞かれたら事実をもとに答えましょう。さらに「学んだことをどう活かすか」までつなげると説得力が増します。
表面的な返答では熱意が伝わらないため、想定問答を準備しておくことが有効です。強みと関連づけて答えられれば、評価につながるでしょう。
⑤学業やアルバイトと趣味の両立はどう伝えるべきか
学業やアルバイトと趣味の両立をどう説明するか悩む人は多いですが、ここは強みになる部分です。企業は限られた時間を効率的に使う力を求めており、両立経験は高く評価されます。
「課題が多い中でも計画的に時間を確保し、週に数回は趣味を続けた」「アルバイトと並行して効率的に学習と趣味を組み合わせた」など、具体的に話すと効果的です。
「忙しくて中途半端になった」といった表現は避け、スケジュール管理や優先順位の工夫を強調してください。両立は努力の証であり、社会人としての基礎力を示す要素になるでしょう。
⑥趣味と自己PRの内容がかぶっても良いか
趣味と自己PRがかぶることは珍しくありませんが、問題にはなりません。ただし伝え方に注意が必要です。自己PRは強みを端的に示す場であり、ガクチカはその強みを具体的な経験で深掘りする場です。
例えば「継続力」を強調するなら、まず自己PRでは「最後までやり遂げる力があります」と端的に伝えます。
その上でガクチカでは「3年間続けた趣味を通じて計画性と忍耐力を培った」と詳しく語る、といった使い分けが有効です。
同じ内容を繰り返すだけでは冗長になるため、両者の役割を意識することが大切です。一貫性を強調できれば、むしろプラスの印象を与えられるでしょう。
ガクチカに趣味を活かすために大切な考え方

ガクチカで趣味を題材にすることは十分にアピールにつながります。なぜなら、企業は経験の大小よりも「価値観」「課題への姿勢」「学びや成長」を重視しているからです。
特に、スポーツやクリエイティブ、学び系や日常系の趣味は人柄や個性を伝えやすく、他の就活生との差別化にも効果的です。
一方でギャンブルなどマイナス印象を与える趣味は避ける必要があります。つまり、強みを引き出せる趣味を選び、成功と失敗の両方を整理し、仕事に活かせる形で語ることが重要です。
このように準備することで、趣味を題材にしたガクチカは自己PRの強力な武器となります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。