ガクチカがない人必見!見つける方法とおすすめテーマ・例文を紹介
就職活動で必ずといっていいほど聞かれるのが「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」ですが、「特にすごい経験をしていない」「話せる成果が思いつかない」と悩む学生も少なくありません。
しかしながら、ガクチカは必ずしも大きな実績や派手な活動である必要はなく、日々の小さな挑戦や工夫の中にも十分アピールできる要素が隠れています。
この記事では、企業がガクチカで評価しているポイントから、ガクチカがないと感じる理由、その見つけ方、具体的なテーマや例文まで丁寧に解説します。
この記事を参考にすれば、「自分にはガクチカがない」と思っている人も、きっと自分らしい経験を見つけられますよ。
ガクチカ作成のお助けアイテム
- 1ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 2赤ペンESでガクチカを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに
- 3ガクチカのテンプレシート
- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える
- 4強み診断
- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる
そもそもガクチカとは?

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略称で、就活のエントリーシートや面接で必ずと言っていいほど聞かれる定番の質問です。
企業はこの質問を通して、応募者の行動特性や課題解決能力、成長意欲などを見極めようとしています。
多くの就活生が「特別な経験がない」と不安を感じがちですが、重要なのは経験の規模ではなく、その中でどのように工夫し、課題に向き合ったかというプロセスでしょう。
たとえばアルバイトやゼミ活動、ボランティアなど、身近な活動からも十分にアピール材料を見つけられます。
ガクチカでは、結果よりも行動の理由や努力の過程を整理し、自分の強みや価値観が伝わるように説明することが大切です。
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
企業が評価するポイント

就活で企業が重視するのは、単なる結果よりも「どのように取り組んだか」という過程や姿勢です。成果が大きくなくても、その取り組み方や考え方次第で十分に評価されるでしょう。
ここでは企業が学生を評価するポイントを5つの観点から解説します。企業が求める人物像を理解することは、自分の強みを整理しやすくする第一歩になります。
- 意欲や挑戦心を持って取り組んだ経験
- 困難や課題に向き合う姿勢
- 結果よりも努力や工夫の過程
- 協調性やコミュニケーション力
- 学びを活かし成長し続ける力
①意欲や挑戦心を持って取り組んだ経験
企業は学生がどれだけ積極的に物事へ挑戦してきたかを重視します。アルバイトやサークル、ボランティアなど、どんな場面でも「自分なりに挑戦した姿勢」が見られるかがポイントです。
たとえば、新しい役割に挑戦する、未経験の分野に取り組む、企画や改善を提案するなど、自ら動いたことが評価されやすいです。
挑戦したきっかけや工夫、結果として得た気づきまでを一貫して語れると説得力が増すでしょう。企業は未知の環境でも前向きに行動できる人材に可能性を感じています。
②困難や課題に向き合う姿勢
企業は結果よりも「困難をどのように乗り越えたか」を見ています。失敗や挫折を避けるのではなく、課題を把握し解決に向けて行動したプロセスが重視されます。
たとえば、限られた時間や資源の中で効率化を試みた経験、チームの課題を整理して改善策を立てた取り組みなどが好印象です。
困難を通して何を学び、次にどう生かしたかを説明することで、継続的に課題を乗り越える力があると伝えられます。企業は問題に直面しても諦めず前進できる人材を求める傾向が強いです。
③結果よりも努力や工夫の過程
「結果が出なかった経験」でも、企業はその過程に注目します。特に、どんな工夫をし、どれだけ粘り強く取り組んだかが評価ポイントです。
たとえば、困難な目標に挑戦する中で新しい方法を試みた、メンバーとの協力体制を強化したなど、過程での工夫が光る経験は好印象です。重要なのは、努力の過程を具体的に伝えることです。
どういう課題に対してどんな工夫をし、その結果何を学んだのかまで話せると、結果を超えた価値が伝わるでしょう。企業は挑戦を繰り返し改善を続ける姿勢に注目しています。
④協調性やコミュニケーション力
企業は個人の成果だけでなく、他者と協力して結果を出す力も求めています。特にチーム活動や共同作業において、どのように周囲と関わり、信頼関係を築いたかが重要です。
たとえば、役割分担の調整、メンバーの意見を引き出してまとめる、異なる立場の人との折衝などが評価されやすいです。
単なる協調だけでなく、問題が起きたときにどのように対処し、関係性を保ちながら解決に導いたかを語れると、協働力の高さが伝わるでしょう。企業は多様な人々と円滑に仕事を進められる人材を重視します。
⑤学びを活かし成長し続ける力
企業は、これまでの経験からどのように学び、どんな成長をしてきたかを知りたがります。単発の成果だけでなく、その後どのように活かしたか、改善に取り組んだかまで語れると説得力が増します。
たとえば、ある取り組みで得た知識を別の活動に活かしたり、弱点を認識して自ら改善に取り組んだりすることは評価されやすいです。
経験から得た知見を次につなげる力は、入社後の成長可能性を示す重要な指標となります。企業は変化の速い環境でも柔軟に学び続ける姿勢を強く求めています。
ガクチカがないと感じてしまう理由

多くの学生が同じように迷っているので、自分だけだと思い込まないことが大切です。
ここでは、ガクチカがないと感じてしまう主な理由を整理し、実は気づいていない経験や強みを掘り起こすヒントを紹介します。
- 結果や実績がないと感じているため
- 大学時代の経験に限定してしまっているため
- 自己評価が低く価値に気づいていないため
- 他人と比較してしまうため
①結果や実績がないと感じているため
「目に見える成果がない」と思うと、ガクチカを書けないと感じがちです。しかし実際には、成果そのものよりも、自分がどんな工夫や努力をしてきたかという過程に価値があります。
たとえばサークルやアルバイトでの挑戦、周囲を巻き込んで課題を解決した経験なども十分題材になります。結果だけに注目せず、そのときにどんな考え方や工夫をしたのか振り返ってみてください。
思いがけないエピソードが浮かび上がることも多いでしょう。就活前の学生にとって、過程を掘り下げることは自信を持つきっかけになり、面接で話すときの軸を作る手助けにもなります。
自分の中の小さな成長や挑戦に気づくことが、ガクチカを見つけるうえでの第一歩です。
②大学時代の経験に限定してしまっているため
ガクチカというと「大学生活の話でなければならない」と思い込みがちですが、必ずしもそうではありません。高校時代の活動や短期インターン、ボランティアや趣味など、幅広い経験が活用できます。
たとえばゼミ以外の課外活動やアルバイトの経験も十分ガクチカとして使えるものです。重要なのは「その経験で自分が何を考え、どのように行動したか」という点です。
大学以外の生活にも目を向けて、自分の価値観や行動パターンを棚卸ししてみてください。視野を広げて人生全体を振り返ることで、新しいエピソードが見つかる可能性があります。
幅広い経験を掘り下げると、他の就活生との差別化にもつながり、自分らしいストーリーが生まれるでしょう。
③自己評価が低く価値に気づいていないため
自分では「大したことない」と思っている経験でも、他人から見れば十分に価値があることは多いです。
まずは身近な人に「自分の強み」や「印象に残った行動」を聞いてみてください。意外な一面を発見できるかもしれません。
また、経験を書き出すときに「困難だったこと」「工夫したこと」「周囲からの反応」という視点で整理すると、自分の努力や成果が見えやすくなります。
さらに、他の学生の自己PRやガクチカを参考にして、自分の経験を客観的に捉えるヒントを得ることも有効です。
④他人と比較してしまうため
周囲の就活生の話を聞くと「自分は大したことをしていない」と感じることがあります。しかし、ガクチカに「正解」はありません。他人と比べるより、自分の経験を深く掘り下げることが大切です。
同じアルバイトやサークル活動でも、学びや工夫は人によって違います。比較よりも「自分らしさ」を示す方が、結果的に印象に残る自己PRになりますよ。
他人の基準ではなく、自分の挑戦や成長に目を向けることで、ガクチカはより説得力のある内容になります。
学生生活で積み重ねてきた「小さな挑戦」や「工夫の積み重ね」こそが、自分の強みを伝えるヒントになることも多いです。
ガクチカがないときの見つけ方

就活で「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」がないと悩む学生は多いですが、実は自分の体験を深く掘り下げることで必ず見つけられます。
ここでは、日常や経験を整理し、視点を広げてガクチカを見つける具体的な方法を5つ紹介します。ガクチカが見つかると自己分析や面接準備もスムーズになり、自信を持って選考に挑めるでしょう。
- 毎日の生活や習慣を振り返る
- 自分だけの工夫や独自の取り組みを見つけ出す
- 過去の行動や体験を深掘りする
- 第三者に相談して視点を得る
- 先輩や内定者の事例を参考にする
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①毎日の生活や習慣を振り返る
日常の中で行っていることを整理することは、自分が気づいていないガクチカのヒントを見つける近道です。
まず、自分の1日の流れや趣味、アルバイト、部活動などを書き出し、その中で努力や工夫をした場面を探してみてください。
たとえばアルバイトで業務改善の提案をしたり、趣味を通じてスキルを高めた経験も立派なガクチカになります。普段の習慣に注目することで、企業が評価する主体性や課題解決力が浮かび上がるでしょう。
さらに、大学生ならではの多忙な授業やサークル活動の中で、時間の使い方や工夫した点を整理すると説得力が増します。
②自分だけの工夫や独自の取り組みを見つけ出す
ガクチカを差別化するには、他人がやっていない工夫や独自の取り組みを見つけることが大切です。
自分の行動を振り返る際に「周囲と違うことをしたか」「どんな工夫を加えたか」を意識すると、エピソードが際立ちます。
たとえば同じサークル活動でも、役割を変えたり、新しい方法を導入した経験は注目されやすいものです。この視点を持つと、ありきたりな話から抜け出し、採用担当者に印象を残せます。
さらに大学生の場合、ゼミ活動やボランティアなど日常の小さな取り組みの中にも独自性が潜んでいます。
日常の行動の中で差異を見つけ、具体的な数値や成果と結びつけると説得力が増し、自分らしいガクチカを構築できるでしょう。
③過去の行動や体験を深掘りする
過去の経験を一段深く掘り下げることで、表面的なエピソードがガクチカに変わります。
多くの学生がやりがちな「単に活動内容を述べる」だけではなく、その活動を通じて何を考え、どのように行動し、どんな成果や学びを得たのかを整理してください。
具体的には「課題は何だったか」「自分は何を工夫したか」「結果どうなったか」という流れで深掘りすると、より鮮明なエピソードになります。
大学生活では授業やサークル、アルバイトなど多様な活動がありますが、その中で自分なりの課題に直面し、挑戦した経験を洗い出すことが重要です。
過去の体験を掘り下げることで、自分の価値観や強みを企業に伝える説得力が高まり、他の候補者との差別化もしやすくなります。
④第三者に相談して視点を得る
自分だけでガクチカを探すのが難しいときは、第三者に相談することで新しい視点を得られます。
友人や先輩、キャリアセンターのスタッフなど、客観的に自分を見てくれる人に話を聞いてもらうと、自分では意識していなかった強みや経験が浮かび上がることも多いです。
とくに、どんな行動が評価されるか分からない場合は、採用経験者や内定者の意見が参考になるでしょう。
大学生にとって、周囲の意見やアドバイスを取り入れることは、自分の枠を広げるきっかけになります。
人に話すことで自分の経験を整理できる効果もあるため、悩んだら一度外部の視点を取り入れてください。
⑤先輩や内定者の事例を参考にする
ガクチカのヒントを得るには、先輩や内定者の事例を参考にすることも効果的です。実際に就活を成功させた人がどのようなエピソードを使っているか知ると、自分の経験に当てはめやすくなります。
ただし、そのまま真似するのではなく、構成や話し方を参考にして自分の経験に置き換えることが重要です。
大学生にとって、同じ環境で頑張ってきた先輩の話は現実的で参考になりますし、企業がどのような視点で学生を評価しているかを知るきっかけにもなります。
事例を分析する過程で、企業が評価するポイントや強調すべきスキルも見えてくるでしょう。
ガクチカを考える際に気をつけたい注意点
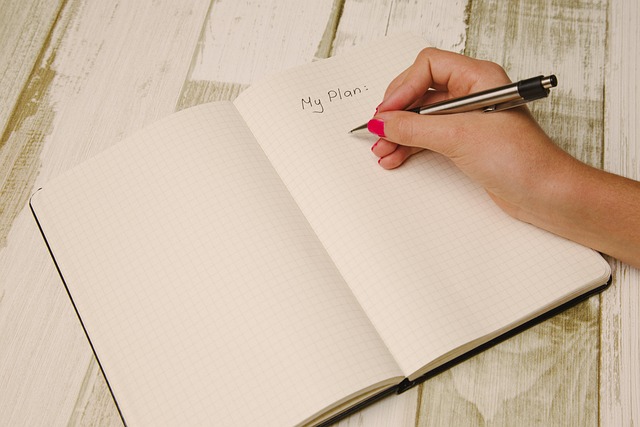
就活でガクチカは自分の強みを示す重要なポイントです。しかし準備不足や誤った選び方をすると、かえって評価が下がる場合もあります。
ここではガクチカを作成するときに特に注意したいポイントを整理し、より良い内容へつなげるヒントを紹介します。
これから就活を控える学生にとって、早めに意識しておくことで安心感を持って準備できるでしょう。
- 嘘や誇張を避ける
- 遊びや娯楽など評価されにくいテーマを避ける
- 自己PRとの差別化を意識する
- 大学時代以外の経験も柔軟に活用する
- 他人を下げて自分を上げる表現を避ける
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①嘘や誇張を避ける
ガクチカで最も大切なのは事実を正しく伝えることです。面接官は多くの学生と接しているため、不自然な表現や誇張はすぐに見抜かれるでしょう。
事実と違うことを書いてしまうと、質問を深掘りされた際に答えに詰まる危険性もあります。
成果を強調しすぎるよりも、自分がどのように工夫したかや取り組んだ過程を示す方が誠実さを伝えやすいでしょう。数字や具体的な行動を盛り込み、無理なく説得力を持たせることが評価につながります。
結果が完璧でなくても、改善や挑戦の姿勢を示せば十分に信頼を得られるので、学生生活の中での努力を自信を持って語ってください。
②遊びや娯楽など評価されにくいテーマを避ける
学生生活の中には趣味や遊びの経験も多いですが、ガクチカでは企業が仕事に活かせる資質を読み取れるテーマが求められます。
例えばゲームやカラオケなど娯楽の活動は、よほど特別な成果がない限り評価の対象になりにくいです。
もし趣味の経験を使う場合は、その活動を通じて得たスキルや課題解決力など、仕事につながる要素を意識して書くと良いでしょう。
ここで大切なのは、自分の活動をただ「楽しかった」「頑張った」だけで終わらせず、どんな工夫や挑戦を重ねたかを明確にすることです。
自分の好きなことでも「他人に価値を提供したか」「改善や挑戦をしたか」を基準に考えると、評価されやすい内容に変えられます。
③自己PRとの差別化を意識する
ガクチカと自己PRは似ているようで目的が異なります。自己PRは「自分がどのような人材か」を伝えるもので、ガクチカは「実際にどのような行動をし成果を出したか」を示すものです。
この違いを意識しないと、同じ内容を繰り返して印象が弱まることがあります。
自己PRでは自分の強みや価値観を中心に、ガクチカでは具体的な行動や結果、課題への取り組みを中心に書くと差別化できます。
また、視点を分けることで人物像が立体的に伝わり、採用担当者に「この学生は多面的な力がある」と感じてもらいやすくなります。準備段階で2つの役割を意識し、しっかり書き分けることが大切です。
④大学時代以外の経験も柔軟に活用する
多くの学生は「大学での活動」にこだわりがちですが、高校やアルバイト、インターン、ボランティアなど幅広い経験もガクチカに活かせます。
重要なのは経験した場所ではなく、そこで何を学び、どう成長したかです。特にアルバイトやインターンは、社会人に近い環境で責任や成果を得られるため評価されやすい傾向があります。
さらに大学以外の活動は他の学生との差別化にもつながるので、意識的に掘り起こす価値があります。幅広い経験を整理し、自分が最も成長した場面を選ぶことで独自性のあるガクチカを作れます。
学生のうちに行動の幅を広げておくことが、就活本番での武器になるでしょう。柔軟な発想が他の学生との差別化にも直結します。
⑤他人を下げて自分を上げる表現を避ける
ガクチカを話すとき、周囲と比較しすぎる表現はマイナス評価につながりやすいです。特に「自分だけが優れていた」「他のメンバーは頼りなかった」といった言い方は、協調性の欠如と受け取られかねません。
企業はチームで成果を出せる人材を求めるため、他人を尊重しながら自分の貢献を示すことが大切です。
「周囲の強みを活かして結果を出した」「自分が苦手な部分は他者に助けてもらった」といった協力的な表現に置き換えると、印象が良くなります。
採用担当者はチームに貢献できる人を重視するので、他者との協力や支え合いを強調することが、学生らしい真摯な姿勢として評価されるでしょう。
ガクチカが本当にない人におすすめのテーマ

就活の「ガクチカ」(学生時代に力を入れたこと)が見つからないと悩む方は多いでしょう。ですが視点を変えると、特別な活動や実績がなくても日常や小さな挑戦の中に活かせる素材が見つかります。
ここでは、ガクチカがないと感じる人に向けて幅広いテーマを示し、自分の経験を整理するきっかけを提供します。
- アルバイトでの顧客対応や業務改善の経験
- 日常の家事・家庭内での役割(家計管理・弟妹の勉強サポートなど)
- 長期間継続している趣味や特技(スポーツ・楽器・書道など)
- 健康管理や生活習慣改善(早起き・筋トレ・食生活など)
- SNS発信・ブログ運営などの自己発信活動
- 家庭や地域でのちょっとした手伝いや役割(買い物・ペットの世話など)
- 新しい習慣やチャレンジを始めた経験(読書・整理整頓・断捨離など)
- 友人や後輩へのサポート・メンター的役割
①アルバイトでの顧客対応や業務改善の経験
アルバイト経験は学生の多くが持っているテーマですが、その中での考え方や姿勢に注目することで他の人と差をつけられます。
仕事を通じて培った協調性や問題解決への取り組み方などを整理すれば、日常的な業務であっても魅力ある話にできます。
特別な成果がなくても、自分なりに改善した点や学んだことを中心に据えることで、独自性のある自己PRに変えられるでしょう。
②日常の家事・家庭内での役割(家計管理・弟妹の勉強サポートなど)
家庭内でのサポートや役割は、普段見過ごしがちな取り組みの中に強みが潜んでいます。弟妹の学習支援や家計の工夫、家事の分担なども、その過程で身につけた計画性や責任感を伝えられます。
日常的な活動ほど、課題発見や行動の積み重ねを整理すると説得力が増します。表面的な出来事ではなく、自分の判断や気づきを意識して書くと良いでしょう。
③長期間継続している趣味や特技(スポーツ・楽器・書道など)
長く続けてきた趣味や特技は、数字や期間で裏付けできるため、継続力や努力を示す題材に適しています。単に「続けてきた」だけでなく、その中で挑戦したことや工夫したことを整理してみてください。
練習や活動を通じて得た成長や気づきを言語化することで、自分の姿勢や価値観をアピールできます。結果よりも過程に焦点を当てるのも効果的です。
④健康管理や生活習慣改善(早起き・筋トレ・食生活など)
生活の中で取り入れた健康管理や習慣改善は、自己管理や目標達成の姿勢を示すのにぴったりです。朝の時間の使い方や運動の取り組み方など、続ける仕組みや工夫の部分に焦点を当ててみてください。
自分のライフスタイルに合わせて挑戦した内容を整理することで、行動力や継続力を強調できます。身近なテーマだからこそ、具体性を持たせると良い印象を与えられます。
⑤SNS発信・ブログ運営などの自己発信活動
SNSやブログなどを使った自己発信は、情報発信力や分析力を示すテーマとして有効です。
フォロワー数やアクセス数などの数字を無理に盛り込まなくても、投稿内容の工夫や継続するための取り組みを整理するだけで十分に強みになります。
内容の改善や企画の立て方、文章構成の工夫など、自分なりに考えてきたプロセスを語ると印象的でしょう。結果よりも「どう試行錯誤したか」を伝えることがポイントです。
⑥家庭や地域でのちょっとした手伝いや役割(買い物・ペットの世話など)
日常の手伝いや地域活動の中にも、責任感や思いやりを伝えられるエピソードがあります。
買い物やペットの世話といった一見小さな役割でも、その中でどのように考え、行動してきたかを整理すると価値あるテーマに変わります。
相手や環境への配慮、工夫した手順や習慣などに目を向けることで、より具体的に自分の強みを示せるでしょう。
⑦新しい習慣やチャレンジを始めた経験(読書・整理整頓・断捨離など)
新しいことに挑戦したり習慣をつくったりする経験は、自発性や柔軟さを伝えるテーマとして効果的です。
小さな挑戦でも、自分で考えて行動に移し、続けてきた過程を整理することで魅力的な話に変わります。
どのように継続の仕組みを作ったかや、どんな成長があったかを具体的にまとめると説得力が増すでしょう。新たな挑戦の背景にある考え方にも触れると深みが出ます。
⑧友人や後輩へのサポート・メンター的役割
友人や後輩を支える経験は、協調性や人を育てる力を示すうえで最適なテーマです。特別な立場がなくても、相手の課題に気づき一緒に解決策を考えた経験などを整理すると印象的です。
自分の行動で相手がどう変化したかや、そこから自分が何を学んだかに注目することで、より豊かな自己PRになります。支援を通じて得た気づきを整理することが重要でしょう。
ガクチカが本当にない人が参考にしたい例文
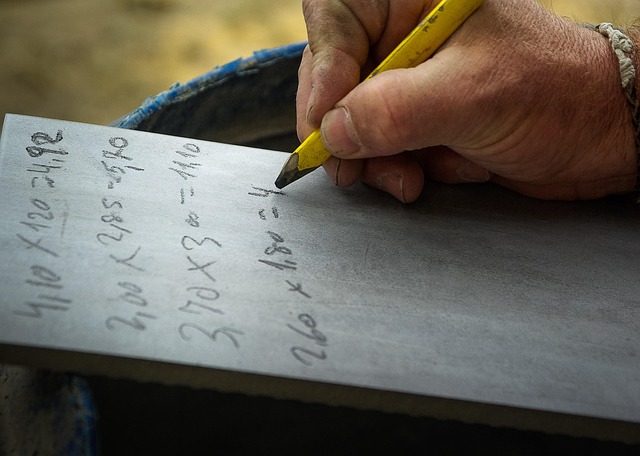
「ガクチカがない」と感じて悩むのは自然なことです。この見出しでは、学業や特別な経験がなくても活かせる事例を幅広く紹介し、自分に合う例文を見つけやすくします。
- アルバイトでの顧客対応や業務改善の例文
- 家庭内での役割・サポートの例文
- 長期間続けた趣味や特技の例文
- 健康管理や生活習慣改善の例文
- SNS発信・ブログ運営の例文
- 地域や家庭でのちょっとした手伝いの例文
- 新しい習慣やチャレンジの例文
- 友人や後輩へのサポートの例文
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①アルバイトでの顧客対応や業務改善の例文
アルバイトの経験は、多くの学生にとって自己PRの材料となる身近なエピソードです。
特別な成果がなくても、日常の中で工夫や努力を重ねたことを伝えることで説得力のある自己PRにつながります。以下は、その一例です。
| 私は大学2年生の時に、コンビニエンスストアでアルバイトをしていました。 最初はレジ対応や品出しに精一杯でしたが、常連のお客様が多いことに気づき、挨拶や声かけを積極的に行うようにしました。 その結果、名前を覚えていただいたり、商品について相談されることが増えました。 また、ピーク時間帯に混雑することが多かったため、事前に補充する品物をリスト化して、チームで共有する仕組みを提案しました。 これにより業務の効率が上がり、スタッフ全員が働きやすくなったと感じています。 |
この例文では「特別な実績がなくても、自分の行動や工夫を具体的に示す」ことを意識しています。
同じテーマを書く場合は、自分が気づいた点や改善したことを具体的に書くことで、誠実さと成長力を伝えやすくなります。
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
②家庭内での役割・サポートの例文
家庭での役割やサポートも、自分の強みを伝える題材になります。日常生活の中で積み重ねてきた行動や工夫を振り返ることで、責任感や計画性などをアピールできます。
| 私は大学時代、家計を支えるために弟や妹の世話を積極的に行っていました。具体的には、学校の送り迎えや夕食の準備、宿題のサポートなど、家族の生活が円滑に回るよう努めてきました。 最初は時間管理がうまくできず大変でしたが、スケジュールを立てて優先順位をつける習慣を身につけることで、学業との両立も可能になりました。 この経験を通じて責任感や計画性を養うことができ、今では自分から進んで課題解決に取り組む姿勢が自然と身についたと感じています。 |
家庭内での役割やサポートは、特別な活動経験がない場合でも立派なガクチカとして活用できます。
書くときは「どんな行動をしたか」「どんな工夫をしたか」「どんな力が身についたか」をセットで示すと、読み手に伝わりやすくなります。
③長期間続けた趣味や特技の例文
趣味や特技など、長期間続けてきた活動は、継続力や自己管理力を示す題材として有効です。特別な活動がなくても、普段の取り組みを軸に自己PRにつなげられます。
| 私は大学入学時から現在までの4年間、週に数回ランニングを続けてきました。最初は健康のために始めたものの、続けるうちに大会に出場するなど新しい挑戦をするようになりました。 記録を更新するために計画的に練習を重ねることで、忍耐力や目標に向かって努力する力を身につけることができました。 この経験を通して、地道に積み重ねることの大切さを学び、今後も仕事や生活の中で活かしていきたいと考えています。 |
長期間続けてきた活動は、取り組みの姿勢や継続力を示す題材として有効です。自分の成長や学びを具体的に書くことで、採用担当者に「強み」として伝わりやすくなります。
④健康管理や生活習慣改善の例文
日常生活の改善や健康管理の工夫も、自分の成長を示せる立派なテーマです。具体的な工夫や変化を示すことで、説得力のあるエピソードになります。
| 大学入学当初は夜更かしが多く、体調を崩すことがありました。そこで毎日同じ時間に就寝・起床することを決め、朝は軽い運動を取り入れるようにしました。 最初は続けることが難しかったですが、友人と一緒にランニングすることで習慣化に成功しました。その結果、授業中の集中力が高まり、生活全体が整ったと実感しています。 この経験から、小さな習慣でも続けることの大切さを学びました。 |
ガクチカがない場合でも、身近な生活改善や努力の過程を具体的に書くと説得力が増します。
数字や結果を簡単に示したり、仲間と取り組んだ工夫を盛り込むことで、より印象的な文章に仕上げられます。
⑤SNS発信・ブログ運営の例文
SNSやブログでの情報発信は、日々の学びや工夫を発信する中で身についたスキルを示せる活動です。特別な実績がなくても、継続力や表現力を伝えられます。
| 大学生活の中で特に目立った実績はありませんでしたが、自分の興味や学びをSNSやブログで発信し続けてきました。 毎週1回以上の更新を目標に、ゼミで学んだ内容やサークル活動での気づきを文章にまとめて公開することで、文章力や情報整理力が身についたと感じています。 また、読んでくれる人からの反応を参考に改善を重ねることで、相手に伝わりやすい表現や企画の立て方を学ぶことができました。 この経験から、特別な実績がなくても、自分なりの工夫と継続力を示せることを実感しています。 |
この例文は、特別な成果がなくても「継続」と「工夫」を強調することで、自分の成長を示す書き方の例です。
同じテーマで書くときは、更新頻度や改善点など具体的な数字や行動を盛り込むと、より説得力のある文章になります。
⑥地域や家庭でのちょっとした手伝いの例文
地域や家庭での手伝いの経験も、相手の立場に立って考える力や継続性を示せるテーマです。小さな活動でも、取り組み方や工夫を示すことでアピールにつながります。
| 私は大学に入ってから毎週末、近所に住む高齢の方の買い物や庭の手入れを手伝っていました。 最初は母に頼まれて行ったのですが、次第に自分から声をかけ、相手の方とも自然に会話が増えていきました。 重い荷物を運ぶだけでなく、どの順番で買い物を回ると楽になるかを一緒に考えたり、作業の段取りを工夫することでお互いに負担を減らせました。 この経験を通して相手の立場に立って物事を考える姿勢や、継続的に関わることの大切さを学ぶことができました。 |
身近な手伝いや地域活動も、視点や工夫を加えることで十分アピールできるガクチカになります。
単なる事実の羅列で終わらず、「なぜ始めたか」「どのように工夫したか」「何を得たか」を盛り込むと説得力が高まります。
⑦新しい習慣やチャレンジの例文
日常の中で始めた新しい習慣やチャレンジは、自分の努力や成長を語るうえで効果的な題材です。数字や期間を示すことで、継続力や自己管理力を強調できます。
| 大学入学当初は特に目立った活動もなく、自分に自信が持てませんでした。 しかし毎日の通学時間を使って英語ニュースを聞く習慣を始め、半年後には授業のディスカッションで自分の意見を積極的に伝えられるようになりました。 この経験を通して、コツコツ継続することの大切さを学び、自分の行動に責任を持つ姿勢が身についたと感じています。 |
特別な経験がなくても、日常の工夫や継続から成長した点を具体的に書くことが大切です。数字や期間を示すと説得力が増し、読者に努力の過程が伝わりやすくなります。
⑧友人や後輩へのサポートの例文
友人や後輩をサポートした経験は、コミュニケーション力や協調性を伝えるうえで有効です。自分の行動と相手の変化をセットで示すと、より印象的なエピソードになります。
| 大学のゼミで、同じグループになった後輩が発表準備に不安を感じていたので、自分の経験をもとに資料の作り方や発表の練習方法を一緒に考えました。 授業後に時間をつくって練習に付き合ったところ、後輩は自信を持って発表できるようになり、感謝の言葉をもらいました。 この経験から、人を支える姿勢や相手の立場に立つ大切さを学ぶことができました。 |
この例文では、特別な成果や資格がなくても、周囲を支えた行動を軸に強みを伝えています。
同じテーマを書く場合は、「自分がどんな行動をしたか」「相手がどう変化したか」を簡潔に示すことで、より印象的な文章になります。
今からでも間に合う!ガクチカを作る方法
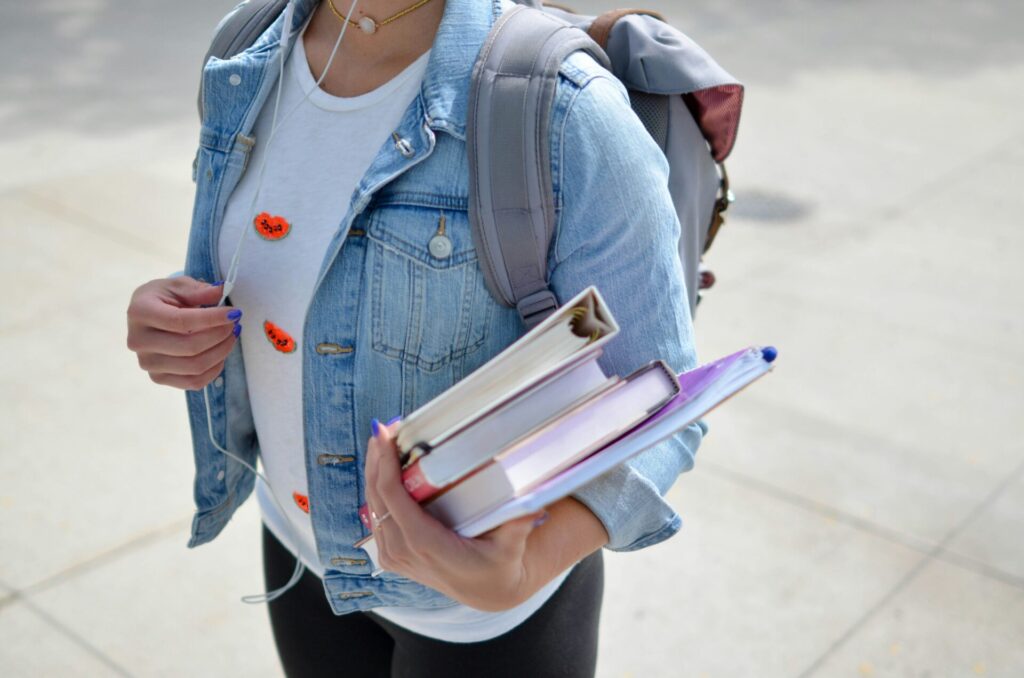
就活生の多くが「ガクチカがない」と悩んでいますが、今からでも十分間に合います。ここでは、実践しやすい具体的な方法を紹介し、自分に合った取り組み方を見つけるヒントを提供します。
大学生活の中でできることは意外に多く、視点を少し変えるだけで行動の幅が広がるでしょう。
- 長期インターンに参加する
- アルバイトやボランティアに挑戦する
- 資格取得やスキルアップを始める
- 趣味や特技に目標を設定する
- 新しい習慣を継続して実行する
- ボランティアやイベントへの短期参加を試してみる
- オンライン講座や勉強会に参加する
- 日常の行動や記録を意識的に残す
①長期インターンに参加する
長期インターンは、就活生が社会経験を積みながらスキルを磨ける貴重な機会です。特に「ガクチカがない」と悩む場合でも、半年程度の取り組みで企業が評価するエピソードを作れます。
大学生のうちから実務に近い環境に触れることは、視野が広がり社会人としての基礎を早く築くきっかけになるでしょう。実際に課題解決に取り組むことで、責任感や主体性を示せるはずです。
最初は未経験で不安を感じても、サポート体制が整っているインターン先を選ぶと安心して挑戦できます。短期間でも成果を残せるように、参加前に自分なりの目標を立てて計画的に進めてください。
こうした経験は、面接で具体的に語れるエピソードとして役立ち、周囲の学生と差をつけるチャンスになります。
②アルバイトやボランティアに挑戦する
アルバイトやボランティアは、身近で始めやすく実践的なガクチカの材料になります。特に接客やチーム運営など、人と協力する場面ではコミュニケーション能力やリーダーシップを自然に培えるでしょう。
大学生活で得た知識や考え方を現場で試せるため、学びの実践という意味でも価値が高いです。
「どこで働いたか」よりも「どのように課題に取り組んだか」が重要なので、改善や工夫した経験を意識して蓄積してください。
また、ボランティア活動では社会課題に触れられ、視野を広げるきっかけになります。アルバイトに比べて報酬はありませんが、目的意識や主体的な行動を示せるため企業に好印象を与えやすいです。
普段の生活と両立しながら取り組めるのが魅力でしょう。
③資格取得やスキルアップを始める
資格取得やスキルアップは、努力の過程がわかりやすく成果を示しやすい点が魅力です。大学生は授業やサークル活動と両立しながら挑戦でき、就活前に自分を客観的にアピールする武器になります。
「勉強が得意ではない」と思う人でも、短期間で学べる資格やオンライン講座を選ぶことで達成感を得られるでしょう。
面接では「どの資格を取ったか」よりも「なぜ挑戦したか」「その過程で何を学んだか」を伝えることが大切です。
また、学んだ知識をアルバイトやゼミ活動などで活かせば、より実践的な経験として評価されます。小さな成功体験を積み重ねることが、自信を持ってガクチカとして語れるテーマに育つ道筋になるでしょう。
学生時代の努力は面接官にとって新鮮に映ることが多いです。
④趣味や特技に目標を設定する
趣味や特技は一見ガクチカには不向きに思えますが、目標設定と工夫次第で強力なアピール材料になります。大学生は時間の使い方に柔軟性があるため、趣味を深めて発展させる余地が多いでしょう。
例えば、写真撮影が好きならSNSで作品を継続して発表する、楽器演奏ならコンクールに挑戦するなど、成果を見える形にすることがポイントです。
企業は取り組みの規模よりも、その過程で得た努力や主体性、改善の工夫を重視します。趣味に目標を加えることで、自己管理能力や計画性も示せるため、説得力のあるガクチカに変わります。
日常にある行動を価値ある経験に変換する視点が重要であり、それこそが学生らしい柔軟な発想でしょう。
⑤新しい習慣を継続して実行する
新しい習慣を取り入れて継続すること自体が、自己成長の証明になります。
例えば毎朝30分の英語学習を続ける、日記を書く、筋トレに挑戦するなど、小さな取り組みでも継続できればガクチカとして強い印象を残せるはずです。
大学生は授業や課題で忙しい中でも、時間管理や自己コントロールを鍛えやすい環境にあります。企業は「結果」だけでなく「過程」における主体性や計画性を評価するため、習慣化は非常に有効です。
さらに、継続のために工夫した方法やモチベーション維持の仕組みを語ると、自己管理能力をアピールできるでしょう。
特別な実績がなくても、日常の積み重ねが強いエピソードとなり、社会人への準備としても自信につながります。
⑥ボランティアやイベントへの短期参加を試してみる
長期間の取り組みが難しい場合は、短期ボランティアやイベントへの参加が有効です。期間が短くても、内容や役割によっては濃い経験を得られることがあります。
大学生にとっては夏休みや春休みなど、まとまった休暇を活用できるのも強みでしょう。
例えば地域イベントの運営補助や子ども向けワークショップのサポートなどは、柔軟な対応力や協調性を磨く機会になります。
ポイントは「ただ参加した」ではなく「どんな目標や役割を持って臨んだか」を整理しておくことです。短期間でも主体的な姿勢を示すことで、ガクチカとして十分評価されるエピソードになるでしょう。
限られた時間でどこまで挑戦できるかを考えること自体が成長につながります。
⑦オンライン講座や勉強会に参加する
オンライン講座や勉強会は、時間や場所に縛られずにスキルアップできる現代的な方法です。特に就活直前の時期でも取り組みやすく、最新の知識を吸収するチャンスとなります。
大学生活の中で学んだことをさらに発展させ、専門分野を深めるのにも役立つでしょう。講座内容を学ぶだけでなく、SNSやポートフォリオに成果物を公開すると企業への印象がさらに強まります。
学びの場を通じて人脈を広げられる点も見逃せません。主体的に参加した姿勢や得た知見を整理しておくと、自己PRの説得力が増すでしょう。
忙しい学生でも取り入れやすいのが最大の魅力であり、自分の成長速度を加速させる手段になります。
⑧日常の行動や記録を意識的に残す
特別な活動をしなくても、日常生活の中にガクチカの種は多くあります。
例えばゼミ活動、趣味の練習、アルバイトの改善策など、日々の行動を記録しておくことで後からエピソードとして整理しやすくなります。
継続的にメモを残すと、小さな成長や工夫が可視化され、面接時に具体的に語れる材料になるでしょう。
また、日常を振り返る習慣自体が自己管理や課題発見力を示す証拠となり、ガクチカとして十分評価される可能性があります。
日常の中で「自分だけの視点」を見つけることが、他の学生との差別化にもつながるでしょう。
ガクチカの効果的な伝え方のコツ

就活における「ガクチカ」は、面接官が応募者の人柄や成長過程を知る大切な手掛かりです。効果的に伝えることで、限られた面接時間の中でも印象に残りやすくなるでしょう。
ここでは、ガクチカをより魅力的に伝えるためのポイントを順序立てて解説します。これから就活を始める大学生にとっても、ガクチカを磨くことは自己PRの基盤をつくる重要な準備になるはずです。
- 「力を入れたこと」から話し始める
- 取り組んだ理由や背景を明確にする
- 具体的な行動や成果を示す
- 経験から得た学びや成長を伝える
- 簡潔かつ分かりやすい文章構成にする
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①「力を入れたこと」から話し始める
ガクチカを話すときは、最初に「自分がもっとも力を入れた経験」を提示することが効果的です。冒頭でインパクトを出すことで面接官の関心を引き、続くエピソードを理解しやすくなるでしょう。
たとえば「学園祭で広報チームをまとめた」や「サークルで新入生向けイベントを企画した」など、主語と動作を明確にした言い方がおすすめです。
さらに学生の立場だからこそ、アルバイトやゼミ、ボランティアなど多彩な経験から選べる強みがあります。これにより、自分がどのような役割を担い、どんな成果を出したのかが一目で分かります。
最初の数秒で相手をひきつけることが、その後の評価にもつながるはずです。話の最初に「これが私の一番の挑戦です」と自信を持って言えると、印象に残る自己PRになりやすくなります。
②取り組んだ理由や背景を明確にする
エピソードを語る際に、なぜその活動に取り組んだのか、背景や動機を整理して伝えることが大切です。
理由を述べることで、自己分析の深さや行動の一貫性が伝わり、単なる出来事報告に終わらない印象を与えられます。
「なぜ自分がその課題を選んだのか」「何を達成したかったのか」を意識して説明すると、主体性や目的意識の高さを示せるでしょう。
特に学生時代は選択の幅が広いため、あえてその活動を選んだ背景をしっかり示すことが差別化につながります。
さらに、その経験が自分の成長や将来のキャリアにどうつながっているのかまで触れると、より強い説得力が生まれますよ。
③具体的な行動や成果を示す
面接官は抽象的な説明よりも、数字や事実に基づいた具体的な行動に注目します。そこで、自分がどのように課題に取り組み、どんな成果を出したのかを明確にしましょう。
たとえば「イベントの来場者数を前年比で30%増やした」など、定量的な結果を示すと説得力が増します。
また、成果が数字で表せない場合でも、改善したプロセスや周囲からの評価などを伝えることで、結果の重みを示せます。
学生の場合は、アルバイトの売上向上やゼミ発表の質向上、チーム活動の改善など、成果を形にする方法はいくつもあります。
行動と結果をセットで語ると、問題解決能力や行動力の高さが印象づけられ、選考の場で好印象を残しやすくなるでしょう。
自分がどれだけ主体的に動いたかを示すことで、受け身ではない積極的な学生であることが伝わります。
④経験から得た学びや成長を伝える
単なる経験談にとどめず、その経験を通して得た学びや成長を明確にすることが大切です。企業は「何をしたか」よりも「そこから何を学び、どう成長したか」に注目します。
「リーダーシップを身につけた」「相手の立場を考える力がついた」など、自分の成長を具体的に述べると、自己成長力を評価してもらいやすいでしょう。
さらに、その学びを今後の仕事でどのように活かせるかまで語ると、面接官に「この人は入社後も伸びる」と思わせられます。
学生生活では、試行錯誤を繰り返す中で得られた教訓が多いはずです。そうした教訓を率直に共有することで、失敗も成長の証としてポジティブに映ります。
経験と学びをつなげて話すことで、自分の成長ストーリーをより鮮明に印象づけることが可能ですし、他の候補者との差別化にも役立つでしょう。
⑤簡潔かつ分かりやすい文章構成にする
せっかくのエピソードも、長く複雑な説明では魅力が伝わりません。短い時間でも要点が整理された話し方が求められます。
PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を意識すると、情報が整理され、相手に伝わりやすくなるでしょう。
文章構成を整えることは、自分の思考の整理にもつながり、面接の緊張時にも落ち着いて話せる効果があります。
学生のうちから練習しておくと、説明力やプレゼン力の向上にもつながり、就職後も役立ちます。また、過度な専門用語や略語は避け、誰が聞いてもイメージしやすい言葉選びを心がけてください。
限られた時間で印象的に伝えるためには、簡潔で分かりやすい構成が必要です。面接官が理解しやすい言葉と順序を選ぶことで、あなたの魅力を余すことなく伝えられるでしょう。
「ガクチカがない」と悩む前に、自分の強みを見つけよう

「ガクチカがない」と悩む就活生は多いですが、結果や実績にこだわる必要はありません。企業が見ているのは挑戦する姿勢や協調性、努力の過程、そして学びを活かして成長し続ける力です。
アルバイトや家庭内での役割、趣味や日常の工夫など、視点を変えればアピールできる経験は必ず見つかります。
まずはPREP法に沿って、自分の経験を理由→経験→結果→今後への活かし方の順に整理してみましょう。
「ガクチカがない」と感じても、日常や過去の行動を深掘りし、新しい挑戦を始めることで、今からでも十分に魅力的な自己PRを作れます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














