ガクチカと自己PRの違いを徹底解説!作成方法と差別化のコツ
「ガクチカと自己PRって何が違うの?」と感じている就活生は多いのではないでしょうか。
どちらも自分の経験や強みを伝える場面で登場しますが、実は企業が知りたい内容や評価ポイントは大きく異なります。違いを理解せずに書いてしまうと、内容が似通って印象が薄くなることも。
この記事では、ガクチカと自己PRの違いを企業側の意図から丁寧に解説し、効果的な作成ステップや差別化のコツをわかりやすく紹介します。
ぜひ、自分らしさを正しく伝えるための参考にしてみてください。
ガクチカ作成のお助けアイテム
- 1ES自動作成ツール
- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成
- 2赤ペンESでガクチカを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに
- 3ガクチカのテンプレシート
- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える
- 4強み診断
- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる
自己PRとガクチカの違いとは?

就職活動でよく問われる「自己PR」と「ガクチカ」は、どちらも自分をアピールする場面ですが、企業側が知りたいポイントには明確な違いがあります。
自己PRとガクチカは似ているようで、企業が評価する観点がまったく異なります。自己PRは、自分の強みや価値観を通じて「この人が入社後にどう貢献できるか」を伝える内容です。
それに対してガクチカは、学生時代の経験をもとに「どのような姿勢で物事に取り組む人なのか」を示すための質問といえます。
たとえば、同じアルバイト経験を話す場合でも、自己PRでは「責任感を持って改善策を提案したこと」、ガクチカでは「集客のために工夫を重ねた取り組みと結果」を中心に語る必要があります。
このように、焦点の当て方が異なるため、内容が同じでも伝え方は変わってくるのです。質問の意図を読み取り、目的に合った構成でエピソードを整理することが、説得力のある自己表現につながるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
自己PRとガクチカに求めている企業側の意図

自己PRとガクチカは、どちらも面接やエントリーシートで頻繁に求められる質問ですが、それぞれ企業が確認したい内容には明確な違いがあります。
この違いを理解せずに回答してしまうと、期待に沿わない印象を与えてしまうかもしれません。ここでは、企業がそれぞれの質問を通して何を知りたいのかを具体的に解説します。
- 自己PRに求めている企業側の意図
- ガクチカに求めている企業側の意図
①自己PRに求めている企業側の意図
企業が自己PRを通して確認したいのは、「あなたが持っている強みが、自社でどう活かせるか」という点です。つまり、性格や能力だけでなく、それが企業の業務や職場にマッチしているかどうかを見ています。
そのため、自分の強みを語る際には、できるだけ具体的なエピソードと結びつけて説明することが欠かせません。
たとえば、「リーダーシップがあります」と伝える場合でも、「どのような状況で発揮されたのか」「結果としてどう貢献したのか」までを詳しく話すことで、説得力が生まれます。
また、企業側は「その強みが入社後にどう活きるか」という将来性にも注目しているため、応募先企業の業務や社風を調べ、それに即したアピールができると好印象です。
一方で、自分本位なPRになってしまうと評価されづらくなります。企業が求める人物像と自分の強みがどう重なるのかを意識しながら、自己PRを組み立てていくことが重要でしょう。
②ガクチカに求めている企業側の意図
ガクチカで企業が重視しているのは、「その人がどのような姿勢で物事に取り組むか」という行動の特徴や考え方です。
つまり、成果そのものよりも、そこに至るまでのプロセスや努力、困難への向き合い方を通じて、人となりを知りたいと考えています。過去の経験が、仕事の場面でも再現されると企業は想定しているためです。
たとえば、部活動での経験を語る際には、「目標に対してどう計画を立て、どんな行動を取り、どんな困難をどう乗り越えたか」といったプロセスを具体的に説明する必要があります。
企業側はその内容から、あなたが仕事でも地道に努力できるか、周囲と連携できるかといった行動パターンを読み取っています。
また、ガクチカではエピソードの大小は重要視されておらず、むしろ身近な出来事でも「どう考えてどう動いたか」というプロセスを丁寧に伝えられているかが重要なのです。
ガクチカと自己PRの違いを踏まえた作成準備ステップ
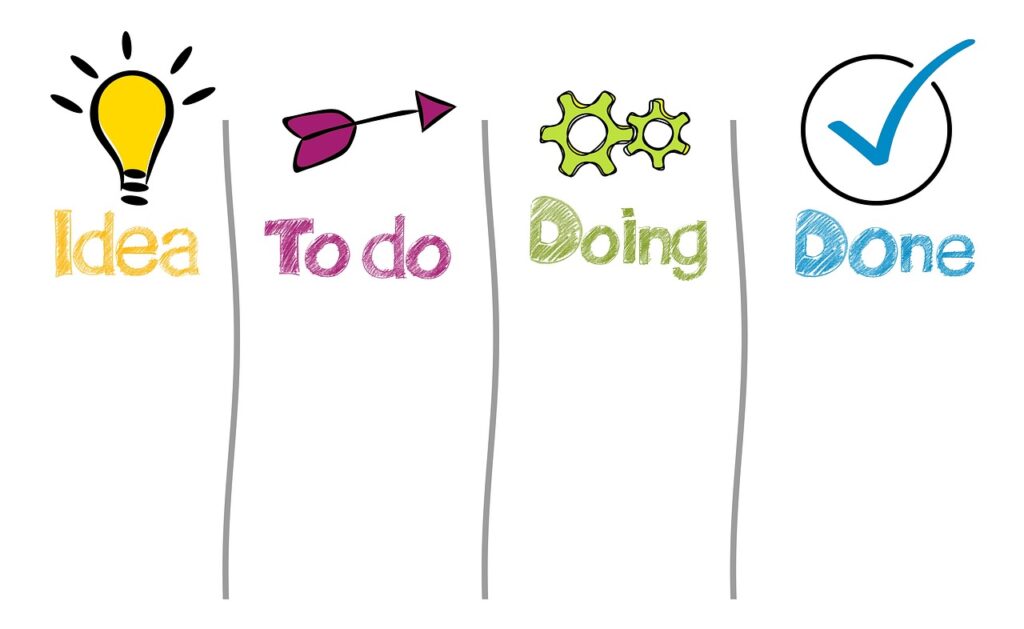
ガクチカと自己PRを効果的に書き分けるには、ただ経験を語るだけでは不十分です。それぞれの目的の違いを理解し、事前準備をしっかりと行うことが必要です。
ここでは、具体的な準備ステップを6つに分けて紹介します。
- 自己分析をして強みと経験を整理する
- 企業研究をして求める人物像を把握する
- ガクチカと自己PRの題材を選定する
- 過去の経験を構造的に整理する
- エピソードを客観的に評価する他己分析を行う
- 作成前に一貫性と方向性を確認する
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
①自己分析をして強みと経験を整理する
自己分析は、ガクチカや自己PRを考えるうえでの出発点です。自分の強みや価値観、印象に残っている経験を整理することで、説得力あるエピソードが見えてきます。
思い出せる範囲で構いませんので、小さな成功体験や失敗からの学びも書き出してみてください。強みを探す際は、何かに打ち込んだ経験や、周囲からよく言われる特徴に注目しましょう。
自分にとっては当たり前に思えることでも、他人にとっては貴重な資質であることも少なくありません。広い視点で見つめ直すことで、自分の中にある魅力を再発見できます。
こうして自分の特性を言語化しておくことで、エントリーシートや面接での表現にも一貫性が生まれ、説得力がぐっと増すでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②企業研究をして求める人物像を把握する
ガクチカや自己PRを作るとき、自分の強みだけでなく、それが企業にどう評価されるかも重要な視点です。
企業研究では、理念や事業内容、採用ページの社員インタビューなどをもとに、どのような人物が求められているかを読み取ってください。
たとえば「チームで成果を出す力」が重視されている企業であれば、協調性や巻き込み力に関するエピソードが響きやすくなります。
一方で「新しい価値を創る人材」を求めている企業であれば、自ら考えて動いた経験が求められるでしょう。
このように、企業が重視する人材像を踏まえてガクチカや自己PRを組み立てることで、「企業とのマッチ度」が高まり、印象に残りやすい内容になります。
③ガクチカと自己PRの題材を選定する
題材選びは、ガクチカと自己PRを差別化するために欠かせないステップです。同じエピソードを使うことも可能ですが、視点や強調点を変えなければ内容がかぶってしまい、評価が下がる可能性があります。
たとえば、アルバイト経験を自己PRに使うなら「リーダーとしての責任感」や「改善提案の実行力」に焦点を当てます。
ガクチカでは「困難な状況をどう乗り越えたか」「継続的に努力した姿勢」を中心に話すと、うまく差別化できます。
複数のエピソード候補がある場合は、それぞれのエピソードが持つ要素を紙に書き出し、どちらに使うのが効果的かを見比べてみてください。
④過去の経験を構造的に整理する
エピソードの内容が決まったら、それを「伝わる形」に整理することが必要です。ただ出来事を並べるだけでは相手に伝わりにくいため、PREP法やSTAR法などのフレームを活用して構成を考えましょう。
たとえばSTAR法であれば、「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」の順に整理することで、相手にわかりやすく伝えることができます。
重要なのは、どの部分に自分らしさが現れているかを意識することです。論理的に整理されたエピソードは、内容が記憶に残りやすく、面接官にとっても理解しやすくなります。
構成を整えるだけで、同じ経験でも印象が大きく変わるでしょう。
⑤エピソードを客観的に評価する他己分析を行う
自分のエピソードが本当に魅力的かどうかを判断するためには、他人の視点を取り入れることが有効です。友人や家族、大学のキャリアセンターなどに話を聞いてもらい、感想や気づきをもらってみてください。
他己分析を行うと、自分では気づかなかった強みが浮かび上がることがあります。また、伝えたいポイントがきちんと伝わっているかどうかの確認にもなり、構成の見直しにもつながるでしょう。
他人から見た印象は、実際の面接官に近い視点に近く、自己満足で終わらせないための重要なプロセスといえます。フィードバックをもとに、自分のエピソードをさらに磨いていきましょう。
⑥作成前に一貫性と方向性を確認する
ガクチカと自己PRを別々に作成しても、全体として一貫性がなければ、受け手に違和感を与えてしまうおそれがあります。
企業側は応募書類や面接のやり取りを通じて、あなたの価値観や行動傾向に一貫性があるかを見ています。
たとえば、ガクチカで「縁の下の力持ち」として努力してきた人が、自己PRで急に「リーダーシップ」をアピールすると、伝えたい人物像がぶれてしまいます。
軸となる強みや価値観がズレていないか、改めて全体を見直してみてください。書き始める前に確認しておくことで、ぶれのない印象を与えられ、全体の説得力が高まります。
一貫性のある自己表現は、企業に安心感を与える大きな武器になるでしょう。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
ガクチカの書き方のコツ

ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)は、エントリーシートや面接で頻出の質問です。しかし、ただ経験を語るだけでは伝わりません。評価されるには、構成や伝え方に工夫が必要です。
ここでは、ガクチカを効果的に伝えるための6つのコツを解説します。
- ガクチカ作成の基本構成(STAR法)
- 目的と課題の明確化
- 行動内容と工夫の具体化
- 結果と学びの整理方法
- 読み手を意識した文章構成
- 企業との関連性を意識した締め方
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①ガクチカ作成の基本構成(STAR法)
ガクチカを論理的かつわかりやすく伝えるには、STAR法が効果的です。
STARとは、Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を取ったフレームワークで、多くの企業が評価の基準としても活用しています。
まず、どんな場面で何に取り組んだのかを簡潔に述べ、次にその中で直面した課題を示します。そして、自分がどんな行動を取ったのかを具体的に説明し、最後に成果や結果、学びを伝えるという流れです。
この順序で構成することで、話に筋が通り、読み手にも伝わりやすくなります。構成に悩んだときは、まずSTARの各要素に当てはめて整理してみてください。
②目的と課題の明確化
読み手が共感しやすいガクチカにするには、なぜその取り組みを始めたのか、どんな課題があったのかを明確にすることが大切です。
目的や課題が曖昧だと、努力や行動の意義が伝わらず、インパクトが弱くなってしまいます。
たとえば、「部活動で大会優勝を目指した」や「アルバイトで接客品質を改善した」など、取り組みの動機や背景を端的に伝えると、読み手はその後の内容に関心を持ちやすくなります。
自分にとっては当たり前のことでも、第三者にとっては説明がなければ理解しづらい場合があります。だからこそ、前提となる状況や動機を丁寧に整理しておくことが重要です。
③行動内容と工夫の具体化
ガクチカでは、「どのような行動を取ったか」が最も重視されます。ただ頑張っただけでは評価されにくく、「どう工夫したか」「なぜその方法を選んだのか」などを明確にすることで、説得力が増します。
たとえば、「集客を増やすためにチラシを配った」とだけ書くよりも、「どのようなターゲット層に、どんなデザインで、どのタイミングで配布したのか」まで具体的に説明した方が効果的です。
その方が、自分の考えや行動力がより伝わります。読み手に「なるほど」と思わせるには、行動の背景にある意図や工夫を言語化することがポイントです。
自分の行動に一歩踏み込んで説明できるようにしましょう。
④結果と学びの整理方法
行動の結果としてどんな成果を得たのか、そしてそこからどんなことを学んだのかを丁寧に伝えることで、ガクチカの完成度が大きく高まります。
企業は、成果そのものよりも、そこからの「成長」や「気づき」に注目しています。
たとえば、「売上を20%改善した」などの定量的な結果があれば説得力は増しますが、それが難しい場合でも、「自分の提案でチームの雰囲気が変わった」などの変化を言語化するとよいでしょう。
また、学びについては、仕事への応用可能性が伝わる内容にするとより効果的です。「この経験を通じて粘り強さを身につけた」といった一文があるだけでも、読み手の印象は大きく変わります。
⑤読み手を意識した文章構成
ガクチカは、自分の経験を語るものですが、伝える相手がいる以上「読み手にとってわかりやすい構成」にすることが不可欠です。
主観的な語りだけでなく、客観的な視点で文章を組み立てることを意識してください。
最初に結論や成果を簡潔に伝え、そのあとに背景や行動を順を追って説明する構成にするだけでも、印象が整理されて伝わります。
特にエントリーシートでは、一文が長すぎると読みづらくなるため、1文1情報を意識するとよいでしょう。また、改行の位置や文のリズムも読みやすさに影響します。
内容だけでなく、読みやすい形にも配慮した構成が、評価を高める鍵になります。
⑥企業との関連性を意識した締め方
ガクチカの最後には、必ず「企業でどう活かせるか」「今後にどうつなげたいか」といった締めを入れましょう。
これがあることで、単なる過去の話ではなく、今後の成長や意欲として企業に伝えることができます。
例えば、「チームで協力して課題解決をした経験は、御社の業務でも必ず活かせると考えています」といった一言があるだけで、印象が大きく変わります。過去の話で終わらせないようにすることが大切です。
また、応募先企業の求める人物像と自分の経験をリンクさせて締めると、マッチ度が伝わりやすくなります。読み手が「この人に会ってみたい」と思えるような一文で締めくくりましょう。
ガクチカの例文
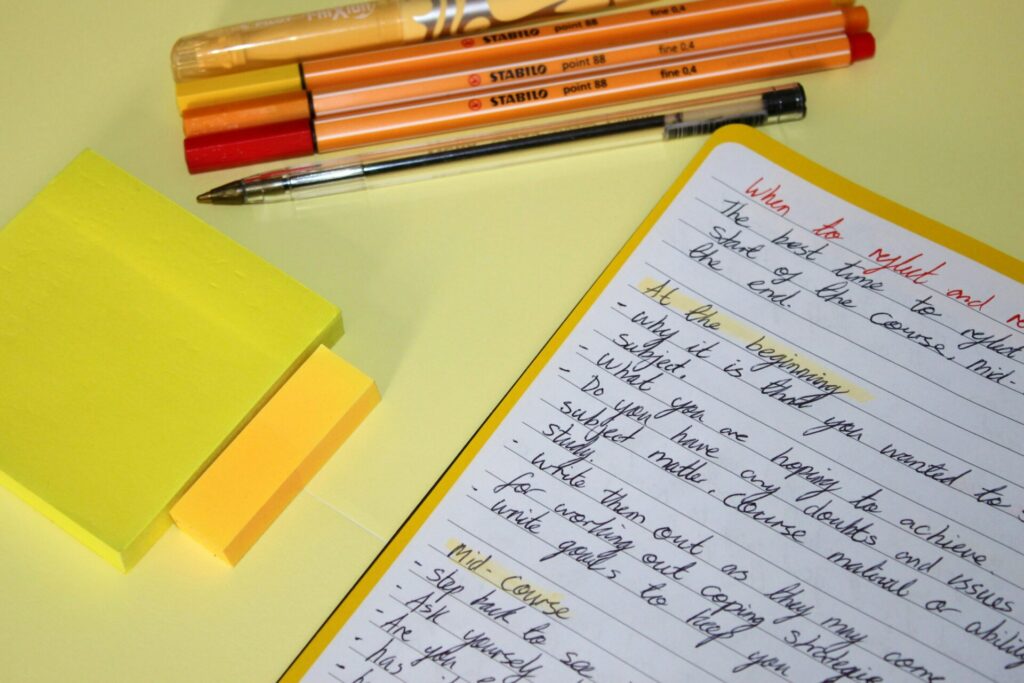
ガクチカをどのように書けばよいか悩む方は多いですよね。ここでは、学業・部活・アルバイトなど、学生生活での具体的な経験をもとにしたガクチカ例文を紹介します。
各シーンごとの特徴や伝え方を理解し、自分の強みを効果的に表現できるようになりましょう。
また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「AI ES」では【志望動機・ガクチカ・自己PR・長所・短所】を満足が行くまで何度も自動作成できます。実際に使用してみた感想などを以下の記事に掲載しているので、気になるけど登録するか迷っている方は記事を読んでみてくださいね。
【関連記事】
エントリーシート(ES)の作成をAIに丸投げ!「AI ES」サービスで就活
学業・ゼミでのガクチカ例文
大学の学業やゼミ活動は、自分の努力や成長を具体的に示しやすいテーマです。ここでは、研究や課題に真剣に取り組んだ経験をもとに、主体性と問題解決力を伝える例文を紹介します。
| 私は大学のゼミで、地域活性化をテーマにした研究プロジェクトに取り組みました。初めは資料収集が思うように進まず、メンバー間で意見がまとまらないこともありました。 しかし、私は一度議論の方向性を整理し、役割分担を提案しました。その結果、全員が主体的に意見を出し合える環境が生まれ、発表では教授から高い評価をいただきました。 この経験を通じて、チームで課題に取り組む際には「整理力」と「協調性」が重要であることを学びました。 今後も課題に直面したときは、全体を俯瞰しながら最適な解決策を見出していきたいと考えています。 |
この例文では、問題に直面してから改善策を行動に移した流れを明確に描いています。学業系のガクチカを書く際は、単なる努力の描写ではなく、「課題→行動→成果」の構成を意識すると説得力が増します。
部活動・サークルでのガクチカ例文
部活動やサークルでの経験は、チームワークやリーダーシップをアピールしやすいテーマです。ここでは、目標達成に向けて粘り強く努力した経験をもとにした例文を紹介します。
| 私は大学のサッカーサークルで副キャプテンを務め、大会での優勝を目指してチームをまとめました。当初は練習参加率が低く、士気が下がっていました。 そこで、私はメンバーと個別に話し合い、練習メニューを改善する提案を行いました。その結果、全員の意識が高まり、最終的には大会で準優勝という成果を収めることができました。 この経験から、チームの課題を把握し、行動で雰囲気を変えていく力の大切さを学びました。 |
この例文では、リーダーシップだけでなく周囲との信頼関係づくりも伝えています。部活動やサークルを題材にする場合は、「チームの課題にどう向き合ったか」を明確に示すと好印象になります。
アルバイト経験でのガクチカ例文
アルバイトは社会的スキルや責任感を示す良い題材です。ここでは、課題解決を通じて自分の成長を表現する例文を紹介します。
| 私はカフェのアルバイトで、スタッフ間の連携不足による注文ミスが多いことに気づきました。そこで、情報共有ノートを作成し、引き継ぎ内容を明確化する仕組みを提案しました。 最初は浸透に時間がかかりましたが、次第に全員が協力的になり、ミスが半減しました。この経験を通じて、自ら課題を発見し改善に取り組む姿勢の大切さを実感しました。 |
アルバイト経験を書くときは、「与えられた仕事」ではなく「自分から行動したこと」に焦点を当てましょう。小さな改善でも主体性を示すことで、採用担当者に好印象を与えられます。
ボランティア活動でのガクチカ例文
ボランティア活動では、社会貢献意識や協調性をアピールできます。ここでは、人との関わりを通して得た学びを中心にした例文を紹介します。
| 私は地域の清掃ボランティアに参加し、子どもたちと協力して公園をきれいにする活動を行いました。最初は子どもたちが積極的に動かず、どうすれば楽しんで参加できるか悩みました。 そこで、ゲーム感覚で競争する企画を提案したところ、みんなが笑顔で取り組むようになりました。この経験から、相手の立場に立って考える大切さと、工夫次第で人を動かせることを学びました。 |
ボランティア経験をガクチカにする際は、「ただ参加した」ではなく「どう工夫して貢献したか」を書くのがポイントです。主体的な行動を具体的に描くと、説得力が高まります。
留学・インターン経験でのガクチカ例文
留学やインターン経験は、挑戦心や適応力を示すテーマとして効果的です。ここでは、環境の違いを乗り越えて成長した経験をもとにした例文を紹介します。
| 私は大学3年時に、アメリカでの短期留学プログラムに参加しました。英語でのディスカッションに苦労し、初めは発言をためらっていました。 しかし、毎日授業後に復習し、友人に質問する習慣を続けた結果、自信を持って意見を述べられるようになりました。 最終日の発表では教授から「成長が著しい」と評価されました。この経験を通じて、努力を継続することで苦手を克服できることを実感しました。 |
留学やインターンのガクチカでは、異文化や新しい環境で「どう成長したか」を明確に描くことが大切です。困難に対して前向きに努力した姿勢を中心にまとめましょう。
資格・スキル取得を題材にしたガクチカ例文
資格やスキル取得の経験は、目標設定力と継続力をアピールする絶好のテーマです。ここでは、努力を積み重ねて成果を得たエピソードを紹介します。
| 私は就職を意識し始めた大学2年の頃、日商簿記2級の資格取得を目指しました。初めは専門用語が難しく、模試では合格点に届きませんでしたが、毎日1時間の学習を習慣化しました。 理解が曖昧な部分は友人と教え合い、3か月後の試験で合格を達成しました。この経験から、継続的な努力の重要性と計画的に学ぶ姿勢を身につけることができました。 |
資格・スキル取得のガクチカでは、「なぜその資格を目指したのか」と「努力のプロセス」を丁寧に描くと良いです。結果だけでなく、日々の積み重ねを強調すると真面目さが伝わります。
自己PRの書き方のコツ

自己PRは、自分の強みや価値観を企業に伝える大切な要素です。しかし、単に「こんな人間です」とアピールするだけでは、評価にはつながりません。
ここでは、印象に残る自己PRを作成するための6つのコツを紹介します。
- 自己PR作成の基本構成(PREP法)
- 強みを見つけるための自己分析ポイント
- 具体的なエピソードの展開方法
- 成果や結果の表現テクニック
- 応募企業との関連性を示す工夫
- 結論を印象的に伝える締め方
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
①自己PR作成の基本構成(PREP法)
自己PRでは、話の構成がわかりやすいかどうかが重要です。
PREP法(Point→Reason→Example→Point)は、面接官にも伝わりやすく、論理的な文章に仕上げるために役立ちます。
まず、自分の強み(Point)を一文で端的に伝え、その強みを裏づける理由(Reason)を説明します。
続けて、その強みを発揮した具体的なエピソード(Example)を紹介し、最後に再度強みをまとめて(Point)、印象づける流れです。
PREP法を使うことで話に一貫性が生まれ、相手に理解されやすくなります。自己PRがうまくまとまらないと感じたときは、まずこの構成をもとに組み立ててみてください。
②強みを見つけるための自己分析ポイント
自己PRの核となるのは「強み」です。しかし、多くの学生が自分の強みがわからず悩んでいます。そこでまずは、過去の経験を振り返り、「成果が出た行動」や「周囲に感謝された言動」に着目してください。
さらに、「なぜその行動を取ったのか」「何を意識していたのか」を深掘りすることで、自分ならではの特性が見えてきます。他人と比較する必要はありません。自分らしさを客観的に整理することが大切です。
エピソードごとに共通する考え方や行動パターンがあれば、それが強みのヒントです。紙に書き出してみると、思考が整理されて方向性がつかめるでしょう。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
③具体的なエピソードの展開方法
自己PRで説得力を持たせるには、エピソードの内容が不可欠です。重要なのは、単に「やったこと」ではなく、「なぜそれをしたのか」「どう工夫したのか」「何を得たのか」を具体的に語ることです。
たとえば「文化祭の実行委員長を務めた」だけでは印象が弱くなりがちです。
「運営の中で集客が伸び悩んだ課題に対し、SNSを活用して広報戦略を見直した結果、前年比120%の集客を達成した」といった具体的な詳細があれば、実行力や課題解決力が伝わるでしょう。
自分の行動や考え方が読み手に伝わるよう、5W1Hを意識して構成するのがポイントです。エピソードは具体性が命です。
④成果や結果の表現テクニック
自己PRの印象を左右するのが、エピソードの「成果や結果」の見せ方です。とはいえ、必ずしも数値で語る必要はありません。
定量的な成果がある場合はもちろん有効ですが、定性的な変化も工夫次第で伝わります。
例えば、「アルバイト先で売上を15%向上させた」といった数字は説得力がありますが、「店の雰囲気が良くなり、お客様から名前を覚えてもらえた」などのエピソードも、行動の価値を示す材料になります。
重要なのは、自分の取り組みによって「何がどう変わったか」を具体的に伝えることです。読み手がその場面をイメージできるように描写すると、記憶に残りやすくなります。
⑤応募企業との関連性を示す工夫
自己PRの効果を最大化するには、「自分の強みがその企業でどう活かせるか」を明確にすることが求められます。どれだけ魅力的な強みでも、企業の求める人物像とかけ離れていては響きません。
企業研究を通じて、価値観や事業内容を把握し、その中で自分の強みがどのように役立つのかを言語化してみてください。
「チームでの調整力」が強みであれば、「多職種と連携する業務で貢献できる」といったつなげ方が考えられます。
このように企業との接点を明示することで、単なる自己満足のPRではなく、「企業の中で活躍する未来」をイメージさせることができるでしょう。
⑥結論を印象的に伝える締め方
自己PRの最後は、印象的に締めくくることが大切です。
エピソードや強みの内容をまとめるだけでなく、「だからこそ私は〇〇として貢献したい」といった前向きな姿勢を示すことで、面接官の記憶に残りやすくなります。
特に、再度強みを強調しながら企業との接点にも触れると、全体の一貫性が生まれます。
「粘り強く取り組む姿勢を活かし、御社の成長を支える存在になりたい」といった一文があるだけで、文章がグッと締まります。
エピソードで得た学びを、今後どう仕事に活かすのかを意識してまとめてみてください。過去だけでなく未来を語ることで、あなたの成長意欲が伝わるはずです。
自己PRの例文
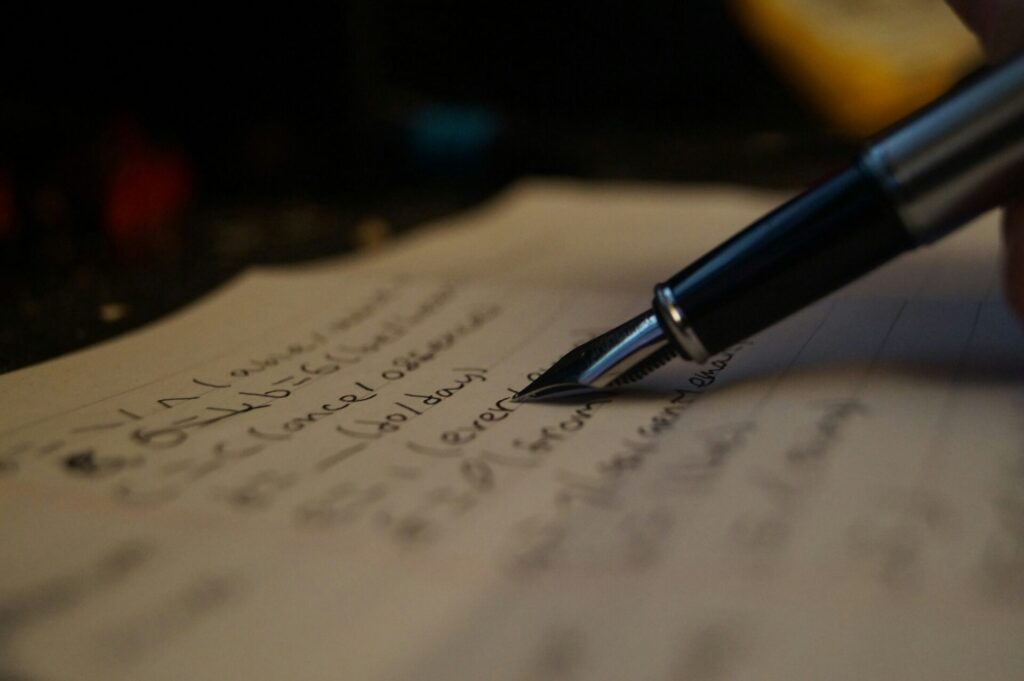
自己PRの書き方に悩む就活生は多く、自分の経験をどう言語化すれば魅力的に伝わるのか迷いがちです。
ここでは、さまざまな状況別に使える自己PRの例文を紹介し、自分に合った伝え方を見つけられるように解説します。
- 学業・研究での自己PR例文
- アルバイト・サークル活動での自己PR例文
- インターン・ボランティア経験の自己PR例文
- リーダー経験を活かした自己PR例文
- 課題克服型の自己PR例文
- 専門知識・スキルを活かした自己PR例文
また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「AI ES」では【志望動機・ガクチカ・自己PR・長所・短所】を満足が行くまで何度も自動作成できます。実際に使用してみた感想などを以下の記事に掲載しているので、気になるけど登録するか迷っている方は記事を読んでみてくださいね。
【関連記事】
エントリーシート(ES)の作成をAIに丸投げ!「AI ES」サービスで就活
学業・研究での自己PR例文
学業や研究に取り組む中で、自分の努力や成果をどう伝えるかは、就職活動での重要なポイントです。ここでは、大学での学びを通して成長を実感したエピソードをもとにした自己PR例文を紹介します。
| 私の強みは、主体性を発揮してチームに貢献できる点です。 私はゼミでの研究活動を通じて、課題解決に粘り強く取り組む姿勢を身につけました。テーマは「地域観光の活性化」で、データ収集から分析までを担当しました。 最初は仮説と結果が一致せず苦戦しましたが、教授や仲間と議論を重ね、原因を一つずつ検証しました。その結果、現地調査の方法に問題があると気づき、調査手法を改善。 再度分析を行うと、納得のいく結果を導くことができました。この経験から、粘り強く考え抜く力と、課題を前向きに解決する姿勢を培いました。 今後も目標達成に向けて自ら行動し、チームに貢献できる人材を目指します。 |
学業をテーマにした自己PRでは、「何に苦労し、どう乗り越えたか」を明確にすることが大切です。研究内容よりも、努力の過程や学んだ姿勢を伝えることで、主体性や成長意欲を印象づけることができます。
アルバイト・サークル活動での自己PR例文
アルバイトやサークル活動は、社会人としての基礎力やチームワークをアピールしやすいテーマです。ここでは、身近な経験から主体的に行動した姿勢を伝える自己PR例文を紹介します。
| 私の強みは、周囲をよく見て課題を発見する力です。 私は飲食店のアルバイトで、チーム全体の効率向上に貢献しました。忙しい時間帯に注文ミスが多発していたため、原因を探ると情報共有が不十分であることに気づきました。 そこで、注文内容をスタッフ全員が確認できる仕組みを提案し、業務フローを見直しました。その結果、ミスが大幅に減り、店長から「改善提案力がある」と評価されました。 この経験を通じて、課題を自ら発見し、周囲を巻き込みながら改善していく力を身につけました。 |
アルバイト経験を自己PRに使う場合、「自分の役割」と「周囲への影響」を意識することがポイントです。小さな工夫でも、課題解決のプロセスを具体的に書くことで、主体性や成長を伝えられます。
インターン・ボランティア経験の自己PR例文
インターンやボランティアは、社会との接点を持つ貴重な経験です。ここでは、行動力や協調性を活かして課題に向き合ったエピソードをもとにした自己PR例文を紹介します。
| 私の強みは、どんな状況でも冷静に自分の役割を把握して動ける点だと考えています。 私は大学2年の夏に参加したNPO法人でのボランティア活動を通じて、柔軟に行動する力を身につけました。地域の子ども向けイベント運営を担当し、当初は計画通りに進まず混乱しました。 しかし、参加者の声を聞きながら内容を改善し、即座に対応することで、最終的には満足度の高いイベントにすることができました。 この経験から、予期せぬ状況にも冷静に対応し、チームで協力しながら成果を出す力を養いました。 |
インターンやボランティアのPRでは、「社会的な目的の中で自分がどう動いたか」を示すのが効果的です。困難な場面をどう解決したかを具体的に描くことで、実践的な成長を印象づけましょう。
リーダー経験を活かした自己PR例文
リーダー経験は、チームマネジメントや目標達成力を伝える絶好のテーマです。ここでは、チームをまとめながら成果を出した経験をもとにした自己PR例文を紹介します。
| 私の強みは、リーダーシップを発揮できるところです。 私は大学のサークルでイベントリーダーを務め、チームをまとめながら成功に導きました。 メンバーの意見が対立し、方向性が定まらない時期がありましたが、全員の意見を丁寧に聞き、共通の目標を再確認しました。 その上で役割分担を見直し、計画を再構築した結果、イベント当日は過去最高の来場者数を記録しました。この経験を通じて、相手の意見を尊重しながら全体をまとめる調整力とリーダーシップを培いました。 |
リーダー経験をPRする際は、「どのようにチームをまとめたか」を明確にすることが重要です。成果よりも、リーダーとして取った行動や判断を具体的に描くことで説得力が高まります。
課題克服型の自己PR例文
苦手なことや失敗を克服した経験は、成長意欲や粘り強さを伝える絶好の題材です。ここでは、困難を乗り越えて成長した姿を示す自己PR例文を紹介します。
| 私の強みは、苦手なことでも真摯に向き合い改善できる力です。 私はプレゼンテーションが苦手でしたが、大学のゼミ活動を通じて克服しました。最初の発表では緊張で話がまとまらず悔しい思いをしました。 そこで、自分の話し方を録音して改善点を洗い出し、友人にも意見をもらいながら練習を重ねました。 その結果、次第に自信を持って話せるようになり、最終発表では教授から「伝わりやすい内容だった」と評価されました。この経験から、課題に真摯に向き合い、継続的に努力する姿勢を身につけました。 |
課題克服型では、「どのように課題を分析し、行動したか」を丁寧に描くことが重要です。失敗の内容を恐れず具体的に書くことで、成長のリアリティを伝えられます。
専門知識・スキルを活かした自己PR例文
自分の強みを具体的なスキルとして伝えることで、専門性をアピールできます。ここでは、学びやスキルを活かして成果を出した自己PR例文を紹介します。
| 私は情報学部で学んだデータ分析の知識を活かし、学内プロジェクトで成果を上げました。学生のアンケート結果を分析し、参加率が低い理由を数値的に検証しました。 その結果、「告知のタイミング」が課題と判明し、改善策としてSNS投稿時間の最適化を提案。実施後、参加率が1.5倍に向上しました。 この経験から、学んだ知識を現場で応用し、成果に結びつける力を身につけました。 |
スキルを活かした自己PRでは、「学んだことをどう使ったか」を具体的に示すことが大切です。知識だけでなく、その成果や工夫を伝えることで、実践的な能力を印象づけられます。
ガクチカと自己PRのエピソードがかぶるのはNG?

ガクチカと自己PRで同じエピソードを使っても良いのか、不安に感じる就活生は多いでしょう。結論から言えば、「かぶってもOK」ですが、同じエピソードをそのまま使い回すのは避けるべきです。
大切なのは、企業がそれぞれの設問を通じて何を知りたいかを理解し、それに応じた切り口で伝えることです。同じ題材でも、伝えるポイントや構成を工夫すれば、十分に差別化できるのです。
ただし、面接などでガクチカと自己PRを並べて聞かれた際に、あまりに似た内容だと印象が薄くなるリスクもあります。可能であれば別のエピソードを準備し、状況に応じて使い分けるのが理想的です。
題材がひとつしか思いつかない場合でも、視点を変えて語る力が問われていると意識しましょう。
自己PRとガクチカの差別化ポイント

自己PRとガクチカは、就職活動における重要な自己表現の場ですが、似たような内容になってしまうと採用担当者に刺さりにくくなります。
どちらも自分の魅力を伝えるための手段ですが、企業が求めている情報は異なるため、それぞれの意図に合った見せ方が必要です。ここでは、差別化のために意識すべき6つのポイントを紹介します。
- アピールする強みと経験の軸を分ける
- 使用する構成フレームを変える
- エピソードの切り取り方を工夫する
- 目的と成果の見せ方を変える
- 企業の質問意図に合わせて表現を調整する
- 文章のトーンや伝え方に違いを持たせる
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①アピールする強みと経験の軸を分ける
自己PRとガクチカで同じエピソードを使う場合でも、伝える軸を変えることで内容の重複を避けることができます。
自己PRでは「自分の強み」を中心に置き、ガクチカでは「経験を通じた学びや姿勢」に焦点を当てるのがポイントです。
たとえば、アルバイト経験を使う際、自己PRでは「継続力」や「周囲を巻き込む力」を強調し、ガクチカでは「困難にどう向き合ったか」や「課題解決に向けた行動プロセス」を伝えると効果的です。
こうした切り分けにより、同じ題材でも説得力のあるアピールが可能になります。
②使用する構成フレームを変える
文章の構成方法を意図的に変えることで、読み手に違った印象を与えることができます。自己PRでは「PREP法(結論→理由→具体例→再度結論)」を使い、端的かつ論理的に強みを伝えるのが一般的です。
一方、ガクチカでは「STAR法(状況→課題→行動→結果)」を用いると、経験の流れや背景がわかりやすくなります。これにより、それぞれの内容が整理され、読みやすさもアップします。
構成に変化をつけるだけでも、内容の印象に違いが生まれるため、活用しない手はありません。
③エピソードの切り取り方を工夫する
一つの経験から複数のエピソードを抽出する工夫が、差別化には欠かせません。
ガクチカでは「どのような課題に取り組んだか」や「具体的にどう動いたか」に焦点を当てるのに対し、自己PRでは「その行動を通して自分のどんな強みを証明できたか」を中心に構成するのが効果的です。
同じ出来事でも、視点や描写の幅を広げれば、全く別の内容として伝えることができます。エピソードの選定段階で、複数の切り口を意識しておくと、あとで使い回しが利きやすくなります。
④目的と成果の見せ方を変える
ガクチカと自己PRでは、「目指すゴール」と「結果の伝え方」を変えることが重要です。ガクチカでは、経験からどんな学びや成長があったかを中心に、プロセスの中で得た知見や反省点も交えて描きます。
一方、自己PRでは、その結果がどう強みに結びつくか、さらにその強みが応募先企業でどう活かせるかという点まで展開するのが望ましいです。
見せたい成果の種類を変えることで、自然に別の話として整理できます。
⑤企業の質問意図に合わせて表現を調整する
企業は、自己PRで「入社後に活躍できるかどうか」、ガクチカでは「仕事に対する姿勢や価値観」を見極めようとしています。
この目的の違いを理解したうえで、それぞれの設問に合った語り口を使うことが求められます。たとえば、自己PRでは「御社で○○として貢献したい」というように未来志向の表現を入れると効果的です。
一方でガクチカは、「学生時代にこう考え、こう行動した」という過去に軸を置いた記述が適しています。このように、時制や視点を意識することで、より明確な差別化につながります。
⑥文章のトーンや伝え方に違いを持たせる
同じ筆者が書いた文章でも、表現のトーンやテンポを変えるだけで、別の印象を与えることができます。
自己PRではやや論理的で簡潔な表現を使い、ガクチカでは感情や背景を丁寧に描写するなど、文体のニュアンスを調整する工夫が大切です。
また、比喩や語彙選びの幅を広げることで、より深みのある文章になります。こうした表現面での工夫は、文章に厚みを持たせ、読み手の印象にも残りやすくなります。
ガクチカと自己PRの違いに関するよくある質問

就職活動を進める中で、自己PRとガクチカに関する疑問は多くの学生が抱えるポイントです。ここでは、選考対策の精度を上げるためによくある質問に答えていきます。
評価に影響する点や、エピソードの選び方、表現の注意点など、見落としがちな点も押さえておきましょう。
- ガクチカと自己PRはどんな場面で使い分けるべき?
- ガクチカと自己PRを同じテーマで伝えるのは評価に影響する?
- 類似エピソードを使うときに意識すべきポイントは?
- 事実を盛ったガクチカや自己PRは選考に不利になる?
- 面接官が自己PRとガクチカを両方聞く理由は?
- 完成度の低いガクチカや自己PRにありがちなミスは?
①ガクチカと自己PRはどんな場面で使い分けるべき?
ガクチカと自己PRは、ESや面接などあらゆる選考シーンで使われますが、それぞれの質問意図に合わせて使い分ける必要があります。
ガクチカは「どんな経験をしてきたか」と「どのように行動して課題に取り組んだか」といった過去の具体的な行動プロセスを重視しています。
一方、自己PRは「どんな強みを持ち、それがどのような場面で発揮されたか」をアピールするものです。つまり、ガクチカは経験ベース、自己PRは能力ベースの質問と考えると整理しやすいでしょう。
混同すると意図がぼやけるため、場面ごとの意図を読み取って構成を変えることが大切です。
②ガクチカと自己PRを同じテーマで伝えるのは評価に影響する?
同じテーマを使用すること自体が悪いわけではありませんが、まったく同じ構成・視点で語ってしまうと評価が下がるおそれがあります。
採用担当者は、あなたの多面的な魅力や考え方の幅を知りたいと考えているため、伝える内容が重複していると「他にアピールできることがないのか」と受け取られる可能性があります。
同じ題材でも、ガクチカでは行動やプロセス、自己PRでは強みや成果にフォーカスを変える工夫をすると、むしろテーマに一貫性が生まれ、深い理解を与えられるでしょう。
③類似エピソードを使うときに意識すべきポイントは?
似たような経験を異なる場面で使う場合、視点の切り替えが重要です。
たとえば同じサークル活動の話でも、自己PRでは「リーダーとしての調整力」を軸にし、ガクチカでは「目標に向けたチーム運営の工夫や苦労」に焦点を置くと、異なる印象を与えられます。
時間軸や状況の変化、取り組んだ課題の視点を変えてみると、新たなエピソードとして伝えることができるでしょう。経験の抽象度を上げ下げすることで、他の話に展開しやすくなります。
④事実を盛ったガクチカや自己PRは選考に不利になる?
事実の脚色や誇張は、短期的には印象を良く見せられるかもしれませんが、面接で深掘りされた際に整合性が取れなくなり、かえってマイナス評価につながる恐れがあります。
信頼性が損なわれると、その後の選考すべてに影響するリスクがあります。
選考では成果の大きさよりも、そこに至るまでの思考や行動、姿勢が重視されるため、正直かつリアルなエピソードの方が評価されやすいです。
自分の言葉で語れる範囲にとどめ、正確に伝えることを意識しましょう。
⑤面接官が自己PRとガクチカを両方聞く理由は?
企業が両方を尋ねるのは、応募者の強みや価値観を多角的に把握したいからです。自己PRでは「何ができる人か」、ガクチカでは「どのように物事に取り組む人か」というように、見るポイントが異なります。
また、同じ人物が異なる問いに対してどう思考を切り替えて対応するかを見ることで、柔軟性やコミュニケーション力なども判断しています。
両方の回答から人柄やポテンシャルを読み取るため、内容の使い分けが非常に大切になります。
⑥完成度の低いガクチカや自己PRにありがちなミスは?
完成度が低いと感じられる文章にはいくつかの共通点があります。まず、「結論が不明確」「抽象的な表現が多い」「行動の根拠が薄い」といった点が挙げられます。
また、エピソードが単なる出来事の羅列になっていて、自分の思考や成長が見えてこないパターンも多く見られます。こうしたミスは、読み手の理解を妨げ、印象に残りにくくなる原因になります。
PREP法やSTAR法といったフレームを活用し、論理的かつ具体的にまとめるよう心がけましょう。
ガクチカと自己PRを効果的に使い分けよう!
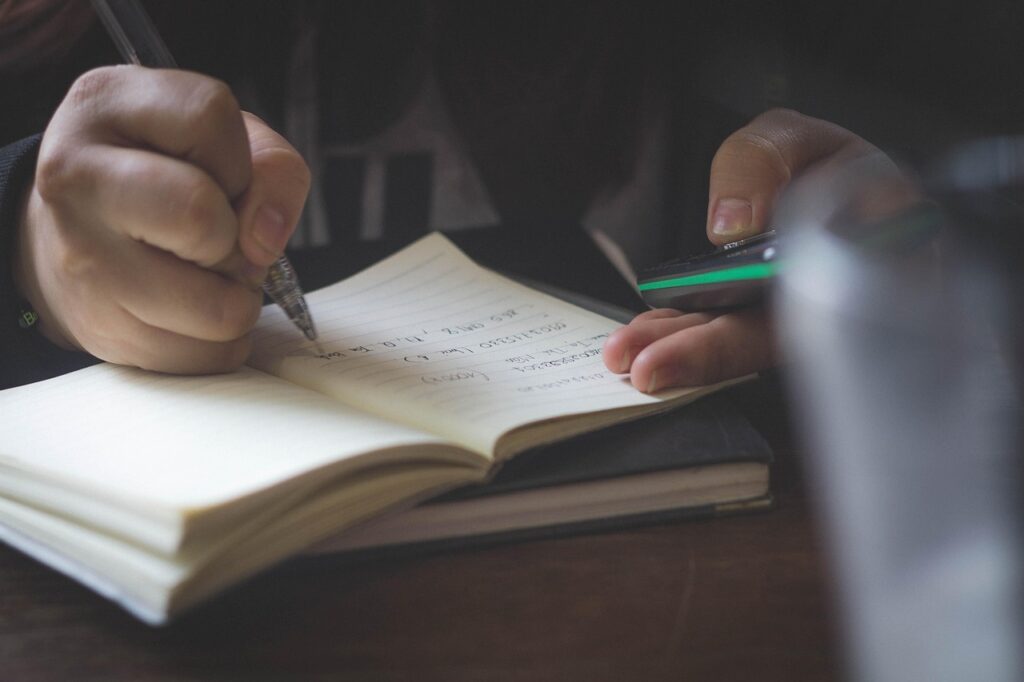
ガクチカと自己PRの違いを正しく理解し、それぞれの目的に応じた伝え方をすることが、就職活動において非常に重要です。
ガクチカは学生時代に力を入れた経験を、自己PRは自分の強みや価値観を伝えるものとして、求められる意図が異なります。
まずは自己分析や企業研究を通じて自分の軸を整理し、それぞれのエピソードを構造的に組み立てましょう。
その上で、STAR法やPREP法を活用しながら、企業が評価しやすい形で伝える工夫が求められます。
例文やフレームを参考にしながら差別化を意識することで、印象に残るエントリーシートや面接対応につながります。ガクチカと自己PRの違いを踏まえた戦略的な準備が、内定への大きな一歩となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












