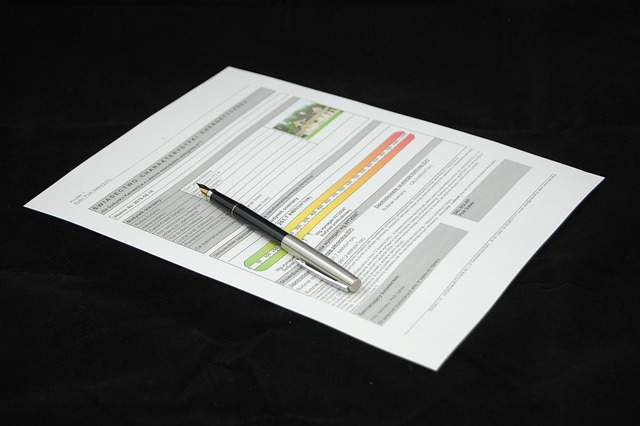入社誓約書を書く意味とは|企業の狙いと辞退時の注意点を解説
「入社誓約書へサインしてください」と言われても、なぜ必要なのか分からず戸惑うことも多いですよね。
入社誓約書は採用が決まった直後に提出を求められるケースが多いですが、そこには企業側の意図や期待が反映されています。
そこで本記事では、誓約書が持つ意味や企業の意図、そして入社を辞退する際に押さえるべき注意点も加えて分かりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
入社誓約書とは何か

入社誓約書とは、学生が内定を承諾した際に企業へ提出する書面であり、入社の意思を明確に伝える役割を持っています。
就活を進める中で初めて耳にする人も多く、名前の堅苦しさから「これにサインしたら辞退できなくなるのでは」と不安を抱くこともありますよね。
しかし、実際には法的拘束力の強い契約ではなく、あくまで入社する意思の確認やこれからの信頼関係の構築を目的としています。
学生側にとっても「自分はこの会社に進むのだ」という意識を強め、就職活動を一区切りつける節目となるはずです。ただし、提出後に家庭の事情や進路変更などで辞退せざるを得ない場合もありますよね。
その際は誠実に事情を説明すれば、大きなトラブルになるケースは多くありません。つまり入社誓約書は「縛りつけるための書類」ではなく「信頼を形にするための確認書」と考えるのが適切です。
就活生にとっては重く感じるかもしれませんが、過度に恐れる必要はないです。むしろ、今後のキャリアを真剣に考え、前向きに決断するきっかけとして受け止めることが大切です。
入社誓約書の特徴

入社誓約書は、単なる書類ではなく学生と企業の関係を明確にする役割を持っています。
ここでは「入社誓約書の役割」「内定通知書や雇用契約書との違い」「交わされるタイミング」について整理し、就活生が混乱しやすい点を解説します。
- 入社誓約書の役割
- 内定通知書や雇用契約書との違い
- 交わされるタイミング
①入社誓約書の役割
入社誓約書の役割は、学生が企業に対して「入社する意思」を正式に示すことにあります。内定の承諾を口頭で伝えるだけでは、企業側として学生が本当に入社するのか不安を抱くこともあるからです。
そこで誓約書を提出することで、採用枠を確定し、研修や配属計画を立てる準備が進めやすくなるのです。学生にとっても文書に署名することで気持ちを整理でき、入社に向けた覚悟を固めやすくなるでしょう。
さらに、家族や周囲に対しても「自分はこの企業に進む」と意思を示すことができるため、就活の区切りとして意味を持ちます。ただし、法的拘束力は弱く、辞退を完全に防ぐものではありません。
誓約書は「絶対に辞退できない契約」と誤解するのではなく、企業と学生の信頼関係を築くための象徴的な書類と理解しておくことが重要です。
②内定通知書や雇用契約書との違い
入社誓約書は、内定通知書や雇用契約書と似ているように見えても役割は異なります。内定通知書は企業が学生に内定を与えたことを知らせる文書で、採用の意思を一方的に伝えるものです。
雇用契約書は給与・労働時間・休日など具体的な条件を記載し、法的に効力を持つ正式な契約です。
これに対して入社誓約書は、学生が「入社します」と意思を示すために提出する書類であり、条件面の取り決めを行うものではありません。
ここには労働条件が書かれないことも多く、「誓約書を出したからもう条件が確定した」と思い込むのは大きな誤解です。
就活生の中には、誓約書と契約書を混同してしまい、不安を抱える人も少なくありません。しかし、違いを正しく理解しておけば、焦って判断することなく安心して対応できるはずです。
内定段階では誓約書、入社直前には雇用契約書と、それぞれ役割があると整理しておきましょう。
③交わされるタイミング
入社誓約書が交わされるのは、多くの場合、内定を受けた後に承諾の意思を明確に示す段階です。企業から内定通知書が届き、その返答として誓約書を提出する流れが一般的でしょう。
これは学生が他社へ流れることを防ぎ、採用活動を安定させる意味合いも含まれています。特に大手企業では、入社式や研修の準備を早めに行うため、誓約書を重視する傾向が強いです。
一方で、中小企業では形式的な承諾書のみで済ませる場合もあります。学生にとっては誓約書を提出することで心理的な負担が増し、「もう辞退できないのでは」と不安になるかもしれません。
ですが実際には辞退そのものは不可能ではありません。大切なのは、複数の選考を並行して受けている場合、誓約書を提出するタイミングを慎重に考えることです。
早まって署名すると後から対応が難しくなるため、納得できる状態で提出することが望ましいでしょう。
入社誓約書を書く意味とは

入社誓約書には、学生が企業に誠意を示す側面や、内定辞退の抑止につながる役割があります。また、両者の信頼関係を築く基盤ともなるため、就活生にとって理解しておくべき重要なポイントです。
ここでは入社誓約書を書く意味を3つの観点から整理して解説します。
- 誓約書を通じた企業への誠意の表明
- 内定辞退の抑止効果
- 学生と企業の信頼関係の構築
①誓約書を通じた企業への誠意の表明
入社誓約書を書く最も大きな意味は、企業に対して自分の誠意を明確に示せる点にあります。
就活では複数の内定を得る学生も多く、選択肢があるからこそ「どの企業に本気で入社したいのか」という意思を表明することが大切です。
誓約書を提出することで、入社の意思を正式な形に残せるため、採用担当者は「この学生は信頼できる」と感じやすくなります。
反対に、署名を軽んじたり提出を先延ばしにしたりすると、熱意や覚悟を疑われる可能性があります。
社会に出れば、約束を守る姿勢や誠実さが信用につながるため、学生のうちからその意識を持つことは重要です。
誓約書に署名する行為は単なる事務的な作業ではなく、入社後の姿勢を予告するものだと意識してください。
②内定辞退の抑止効果
入社誓約書には、学生が軽率に内定を辞退しないよう抑止する効果があります。企業は一人の採用に多額の費用と長期間の時間を投じているため、直前の辞退は採用計画や配属準備に大きな影響を及ぼしてしまいます。
そのため、誓約書を通じて「この決断には責任が伴う」と自覚を促しているのです。
誓約書には法的拘束力がほとんどありませんが、書面として意思を残すことで心理的なブレーキが働き、学生自身も安易に辞退を考えにくくなるはずという意図が隠れています。
複数内定を持つ場合、比較検討すること自体は当然ですが、誓約書を提出した企業には最後まで誠実に向き合うことが大切です。
結果的に、誓約書は学生と企業の双方に無駄な負担や失望を生じさせないための仕組みといえるでしょう。
③学生と企業の信頼関係の構築
入社誓約書は辞退防止の役割にとどまらず、学生と企業の信頼関係を築く第一歩でもあります。
学生が入社の意思を文書化することで、企業は安心して教育計画や配属準備を進められますし、学生側も「自分はこの会社に将来を託す」と気持ちを固められます。
こうした相互の確認があるからこそ、入社後のモチベーションや定着率も高まりやすくなるのです。
逆に誓約書がなければ、企業は「本当に来てくれるのだろうか」と不安を抱えたまま準備を進めることになり、学生も迷いを残した状態で入社日を迎えるかもしれません。
誓約書を交わす行為は、約束を守る責任感を養う訓練であり、社会人に求められる基本的な姿勢を体験する機会でもあります。
信頼関係が早期に築ければ、配属後の人間関係やキャリア形成にも良い影響を与えるでしょう。
入社誓約書の法的効力

入社誓約書は「どの程度の法的効力があるのか」と不安を抱く就活生が多いものです。特に辞退や損害賠償といったリスクを気にする人は少なくありません。
ここでは、法的拘束力の有無、損害賠償が発生するケース、そして実際に考えられるリスクと限界について整理します。誓約書の性質を理解することで、過度に恐れず冷静に判断できるようになるでしょう。
- 法的拘束力の有無
- 損害賠償が発生するケース
- 実際のリスクと限界
①法的拘束力の有無
入社誓約書は入社意思を確認するために企業が提示する書類ですが、一般的には強い法的拘束力を持ちません。
なぜなら、雇用契約は入社日から効力を持つのが基本であり、誓約書の提出段階ではまだ労働契約が成立していないからです。
そのため、たとえ署名しても労働基準法の観点から無理に入社を強制されることはありません。ただし、誓約書は形式的な意味だけでなく、企業に誠意を示す役割も担っています。
軽視すると「信頼を守る姿勢がない」と受け取られる危険があり、印象を悪くしてしまうかもしれません。
就活生としては「法的効力は限定的だが、信頼関係を築くうえで重要な書面」という認識を持つことが大切です。
②損害賠償が発生するケース
多くの場合、入社誓約書を提出した後に辞退しても損害賠償を請求されることはありません。しかし、企業が実際に損害を立証できる場合には例外的に請求される可能性があります。
例えば、あなたの採用を前提に他の候補者を断った結果、人員不足によって取引に支障が出た、あるいは研修や備品の準備費用が無駄になったなど、具体的な金銭的損失が発生した場合です。
ただし、このようなケースを法的に立証するのは非常に難しく、現実にはほとんど起こりません。
就活生にとって重要なのは「ほぼ心配はいらないが、誠実さを欠いた対応は信頼を損なう」という視点です。
辞退が必要なときは、できるだけ早く正直に事情を伝えることで不要なトラブルを防ぐことができるでしょう。
③実際のリスクと限界
入社誓約書にまつわる最大のリスクは、法的な強制力ではなく「信頼関係の喪失」にあります。
誓約書を提出してから辞退すると、企業は「約束を守らない学生」という印象を持ちやすく、今後の選考や業界内での評判に影響する可能性も否定できません。
一方で、法律的に入社を強制されることはなく、学生には進路を選ぶ自由がしっかりと保障されています。つまり、誓約書の効力には限界があり、過度に恐れる必要はないのです。
ただし、辞退する際には誠意ある対応が求められます。できるだけ早く連絡し、迷惑を最小限にする姿勢を示すことが社会人としての信用を守ることにつながります。
就活生にとっては「法的拘束力は弱いが、社会的評価への影響は強い」というバランスを理解することが安心材料になるでしょう。
入社誓約書の基本的な構成

入社誓約書は一定の形式があり、流れに沿って作成されます。細部まで理解しておくと誤解なく記載でき、企業に誠意を示せるでしょう。
就活生にとっては初めて手にする文書で戸惑うことも多いですが、あらかじめ構成を知っておけば安心して準備できます。ここでは基本的な構成要素を整理し、それぞれの役割を解説します。
- 表題と宛名
- 誓約文の導入部分
- 誓約事項の列挙
- 日付と署名欄
- 署名・押印欄
①表題と宛名
冒頭には「入社誓約書」と明記するのが一般的です。表題を正しく記すことで、文書の正式性と用途が一目でわかります。宛名には会社名や代表者名を正確に記載しなければなりません。
誤りがあると配慮不足と見なされ、印象を下げる原因になりかねません。特に企業名の略称や担当者の肩書きの省略は避けるべきです。
正式名称を必ず調べて書く姿勢が、細部にまで注意を払う誠実さとして評価されるでしょう。就活生にとっては細かい作業でも、社会人としての基本的な信頼を得る第一歩になるのです。
②誓約文の導入部分
誓約文の冒頭には「私は貴社に入社するにあたり〜」といった表現を用います。この一文によって入社の意思を明確にし、文書全体のトーンを定めます。
形式的に感じられる部分かもしれませんが、曖昧な表現では誓約の重みが伝わらず、誠実さに欠ける印象を与えてしまうでしょう。
導入部分は短くても良いので、はっきりとした姿勢を示すことが大切です。採用担当者は、学生が本当に意志を持って署名しているかを読み取ります。
就活生の立場としては、単なる書式ではなく「社会人になる自覚を示す場面」として捉えることで、内容への理解と納得感が深まります。
③誓約事項の列挙
本文の中心となるのが誓約事項です。ここには就業規則の遵守、機密保持、反社会的勢力との関係を持たないことなどが盛り込まれるのが一般的と言えます。
これらはすべて入社後のトラブルを未然に防ぐための取り決めであり、働くうえでの最低限のルールと言えるでしょう。
学生からすると「当然のこと」と感じる内容も多いですが、書面にすることで責任を明確にしています。特に情報管理や誠実な勤務態度は、今後のキャリアに直結する重要なポイントです。
誓約事項を「形式だから」と軽く受け止めず、社会人として守るべき約束事として理解してください。読み込むことで企業との信頼関係を築く意識が高まり、安心して署名できるはずです。
④日付と署名欄
文末には署名欄の前に日付を記入します。日付は誓約書を提出する日であり、効力が発生する基準日となるため正確に書くことが必要です。
提出日と異なる日付を記してしまうと、不備として扱われる可能性があります。
学生にとっては単純な作業に思えるかもしれませんが、日付の誤記は企業から「確認を怠った」と見られ、細部への注意力に疑問を持たれる恐れがあります。
だからこそ、日付を正しく記すことは社会人として求められる基本的な姿勢の表れなのです。小さな部分だからと油断せず、最後まで正確に仕上げる意識を持つことが信頼を積み重ねる行動につながります。
⑤署名・押印欄
最後に自分の氏名を記し、必要に応じて押印します。署名は本人確認の意味を持つため、楷書で丁寧に書くのが望ましいです。
企業によっては押印を求める場合もあるため、案内に従って対応してください。署名や押印は単なる形式的な行為ではなく、誓約事項に同意した証拠として法的にも意味を持ちます。
就活生の立場からすれば、自分の意思を正式に示す場面と理解すべきでしょう。署名は今後の社会生活において責任を負う行為の象徴でもあります。
形式に従うだけでなく、「自分が約束を守る」という姿勢を意識して取り組めば、より誠実さが伝わりますよ。
入社誓約書を書く際に押さえるべきポイント

入社誓約書は形式的な書類に思えるかもしれませんが、実際には企業との信頼関係を築くうえで大切な意味を持ちます。
提出方法やマナーを軽視すると、意図せず不誠実な印象を与えてしまい、入社後の評価にまで影響が及ぶ可能性もありえます。
ここでは、就活生が安心して準備できるように、具体的な注意点を整理して解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- シャチハタを避けること
- 白色封筒を使用すること
- 添え状を添付すること
- 返信用封筒の準備
- 提出期限を厳守すること
①シャチハタを避けること
入社誓約書に押す印鑑は、認印や実印を使うことが基本です。シャチハタは便利ではありますが、ゴム印なのでインクがにじみやすく長期保存に適さず、正式な文書には不向きとされています。
就活生の中には「家にあるからそのまま押してしまおう」と考える人もいますが、それは危険です。誤って使用すると「社会人としてのマナーが欠けている」と見なされ、信頼を損なうおそれがあります。
事務的に受理されても評価に響く場合があるため、事前に正しい印鑑を準備しておきましょう。印鑑の選び方ひとつで誠実さを示せることを意識してみてください。
②白色封筒を使用すること
入社誓約書を郵送するときは、必ず無地の白色封筒を選びましょう。色付きや柄のある封筒は私的な印象を与え、社会人としての常識に欠けると見なされる可能性があります。
白色は清潔感とフォーマルさを兼ね備え、最も適切な選択です。また、宛名の書き方にも気をつける必要があります。誤字や脱字があると「丁寧さに欠ける学生」という印象を与えかねません。
さらに、文字の大きさやバランスが乱れていると全体が雑に見えてしまうこともあります。細部まで配慮することで、誠実で慎重な人柄を伝えることができるでしょう。
③添え状を添付すること
入社誓約書を送る際は、添え状を必ず同封するのが望ましい対応です。添え状には簡潔な挨拶文と「入社誓約書を同封いたします」といった文言を明記してください。
書類を送る際のビジネスマナーとして添え状は重要であり、単なる形式的なものではなく、受け取る側への誠意を示す大切な役割を果たします。
就活生にとっては小さな工夫ですが、採用担当者に「配慮のできる人物」という印象を与える効果があります。
また、多くの書類を処理する担当者にとって、添え状があると内容確認がスムーズになり、結果としてあなたの印象が良くなるでしょう。
④返信用封筒の準備
企業から返送が必要な場合に備え、切手を貼った返信用封筒を同封しておくと丁寧です。例えば受領通知や確認書の返送が必要なケースでは、返信用封筒があるだけで担当者の手間を減らすことができます。
こうした配慮は「相手の立場を考えて行動できる学生」として評価されやすく、入社後の仕事の姿勢にも直結すると見なされるでしょう。
就活生は「少し面倒だな」と思うかもしれませんが、この一手間が信頼を築く大きなポイントになります。小さな気配りが社会人としての成長につながると意識して準備してください。
⑤提出期限を厳守すること
入社誓約書で最も大切なのは、提出期限をきちんと守ることです。期限を過ぎてしまうと「入社への意思が薄いのではないか」と疑われたり、企業側の管理に支障が出ることもあります。
社会人にとって期限を守るのは基本中の基本であり、就活の段階からその意識を持つことが必要です。特に郵送する場合は配送に数日かかるため、余裕をもって行動することが欠かせません。
スケジュール管理を怠らず、早めに準備しておけば不安も減り、安心して提出できるでしょう。期限を厳守する姿勢は誠実さを示すうえで最初の一歩となり、入社後の信頼関係にも良い影響を与えます。
入社誓約書の提出後に辞退する場合の対処法

入社誓約書を提出した後に辞退する必要が出てくると、多くの就活生は「もう後戻りできないのではないか」と不安になるでしょう。
けれども、正しい手順を踏めば法的な問題を避けながら誠意を示すことが可能です。ここでは辞退できるケースや伝えるタイミング、さらにマナーを整理し、安心して行動できるように解説します。
- 誓約書提出後でも辞退できるケース
- 辞退を伝える適切なタイミング
- 辞退理由の伝え方と注意点
- 電話やメールでの連絡マナー
- 謝罪文や手紙でのフォロー
①誓約書提出後でも辞退できるケース
誓約書を提出しても辞退できるケースは確かに存在します。そもそも誓約書には強い法的拘束力がなく、企業が学生に入社を強制することは難しいからです。
実際には体調の悪化や家庭の事情、進学の必要性など、やむを得ない理由があれば辞退を受け入れてもらえることが多いでしょう。
ただし「他社の内定の方が魅力的だった」といった理由は正直でも、企業にとっては不快に感じられるリスクが高くなります。
そのため辞退が認められるのは、合理的で説明可能な事情がある場合と理解しておく必要があります。
就活生としては「提出した以上、逃げられない」と思い込みやすいですが、実際には可能なケースもあるため、冷静に状況を整理し、正しい手順で動くことが大切です。
②辞退を伝える適切なタイミング
辞退を決意したなら、できる限り早めに伝えるのが望ましいです。企業は内定者数を前提に採用活動や配属計画を進めており、遅れた連絡は企業側の調整に大きな負担をかけてしまいます。
特に入社直前に辞退を申し出ると、採用活動のやり直しや現場の準備への影響が避けられず、結果として信頼関係を損なう可能性が高まります。場合によっては損害賠償を求められるリスクも生じかねません。
就活生としては「言い出しにくい」と感じるかもしれませんが、むしろ誠意を持って早く伝える方が印象は良くなります。
理想的には辞退を考えた段階で速やかに行動し、遅くとも入社日の数か月前には連絡を済ませておくことが望ましいでしょう。誠意あるタイミングでの連絡こそが、円満な関係を保つ大切な鍵です。
③辞退理由の伝え方と注意点
辞退の理由を伝えるときは、誠実さと簡潔さを両立させることが大切です。「家庭の事情」「健康上の問題」など、企業が納得しやすい説明を意識してください。
反対に「他社に魅力を感じた」という理由は本音であっても、相手の心証を悪くしてしまいかねません。
学生としては「正直に言うべきか隠すべきか」と迷う場面ですが、必要以上に細かい事情を語らず、配慮を持った表現を心がければ十分誠意は伝わります。
また、曖昧な言い方や言い訳がましい説明も避けるべきです。企業側にとって最も大切なのは「辞退が不可避であること」と「感謝と謝意を示すこと」です。
その2点を押さえれば、角が立たずに辞退できるでしょう。要するに、辞退理由は誠実さと相手への気配りを兼ね備えた内容に整えることがポイントになります。
④電話やメールでの連絡マナー
辞退を伝える手段として最も望ましいのは電話です。電話であれば自分の言葉で直接謝意を伝えられ、相手の反応を受けて柔軟に答えることも可能です。
どうしても担当者と連絡がつかない場合や、相手の都合により電話が難しい場合に限って、メールを活用すると良いでしょう。
メールを送るときは件名に「内定辞退のご連絡」と明確に書き、本文では冒頭でお詫びを述べ、理由を簡潔に説明することが求められます。さらに、連絡する時間帯にも注意が必要です。
就業時間内に連絡を行い、早朝や深夜は避けるべきです。学生の立場からすると緊張する場面ですが、誠実な姿勢を意識すれば企業に誠意は伝わります。
電話とメールの使い分け、そして時間への配慮は、辞退時の印象を大きく左右する大切な要素です。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
⑤謝罪文や手紙でのフォロー
辞退を伝えた後には、謝罪文や手紙を送ることで、最後に誠意を示すことができます。
誓約書提出後の辞退は、企業に少なからず迷惑をかける行為であるため、文書で改めてお詫びを伝えることは誠実な姿勢として評価されやすいです。
手紙には「辞退せざるを得ない事情」「迷惑をかけたことへの謝罪」「これまでの選考への感謝」を盛り込み、丁寧な言葉でまとめましょう。
就活生にとっては「もう会わない相手だから」と軽く考えがちですが、社会に出ればどこで再び接点を持つかわかりません。
最後まで誠実な対応を心がけることは、自分の将来にとってもプラスになります。結果的に、謝罪文や手紙は辞退後のトラブルを避けるだけでなく、自分自身の安心にもつながる有効な方法といえるでしょう。
入社誓約書に関するよくある質問

入社誓約書は就活生にとって馴染みが薄い書類であるため、提出や記入に際してさまざまな疑問を抱く方が多いです。
ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、安心して対応できるように解説していきます。就活生が不安を感じやすいポイントを整理し、誤解やトラブルを防ぐための知識を身につけましょう。
- 入社誓約書に連帯保証人は必要か
- 入社誓約書を提出しないとどうなるか
- 郵送時に添え状は必要か
- 返信用封筒で送る際の注意点
①入社誓約書に連帯保証人は必要か
入社誓約書に連帯保証人が必要かどうかは、多くの就活生が疑問に思うところです。結論から言えば、新卒採用で連帯保証人を求められることはほとんどありません。
企業は「入社に対する本人の誠意」を確認するために誓約書を提出させるのであり、金銭的な責任を家族などの第三者に負わせることは通常は想定されていません。
とはいえ、一部の企業や業種では、形式的に親の署名を求める場合があります。その場合でも、法的な効力は限定的であり、あくまで確認程度の意味合いにとどまります。
もし不安を感じた場合は、採用担当者に「なぜ保証人が必要なのか」を確認するのが安心につながります。過度に心配せず、基本的には必要ないと理解しておくことが就活を進める上での安心感になるでしょう。
②入社誓約書を提出しないとどうなるか
入社誓約書を提出しなかった場合、内定が取り消されるのではないかと心配する学生は多いです。
しかし実際には、誓約書は「入社の意思を改めて確認するための書類」にすぎず、提出が遅れただけで即座に内定が無効になるケースはほぼありません。
ただし、誓約書を提出しないままでいると「本当に入社する意思があるのか」と企業に疑念を抱かれる可能性があります。その結果、信頼関係が揺らぐリスクがあるのです。
もし期限内に提出できない事情がある場合は、事前に担当者へ連絡を入れて理由を丁寧に説明してください。たとえ小さな遅れであっても、誠実に対応する姿勢は社会人として高く評価されます。
就活生にとっては、このような対応力が将来の信頼構築につながることを意識すると良いでしょう。
③郵送時に添え状は必要か
入社誓約書を郵送するときに添え状をつけるべきか迷う人も少なくありません。結論としては、添え状を同封するのが望ましい対応です。
添え状には「内定への感謝の言葉」や「誓約書を送付したことの簡単な説明」を書くことで、採用担当者に丁寧な印象を与えることができます。
添え状がなくても不備とされることは少ないですが、社会人としての基本的なマナーを示すチャンスだと考えると良いでしょう。
特に就活生にとっては、ビジネス文書の書き方や礼儀を学ぶ良い機会になります。実際に添え状をつけることで「細やかな配慮ができる人物」という印象を残せるため、将来の評価にもつながるでしょう。
小さな手間ですが、積極的に添えることをおすすめします。
④返信用封筒で送る際の注意点
返信用封筒を使って誓約書を返送する際には、いくつか確認しておきたい注意点があります。まず、封筒の宛名や住所が印字されているかを確認し、企業からの指示があれば必ずその通りに使用してください。
切手が貼られていない場合は、自分で適切な料金を確認して貼る必要があります。さらに、誓約書は折れたり汚れたりしないようクリアファイルに入れて送ると、丁寧さを伝えられます。
加えて、封筒に入れる前に中身を見直し、必要な書類以外を誤って同封しないよう注意してください。
こうした細やかな気遣いは一見些細なことに思えますが、採用担当者に「安心して任せられる人物」という印象を与えます。
就活の場面では、このような小さな積み重ねが信頼形成に直結するのだと理解して行動することが大切です。
入社誓約書を理解して就活をより安心に進めよう

入社誓約書は、企業と学生の間で信頼関係を築く大切な書類です。その特徴や役割を理解しておくことで、就活を安心して進められます。
特に、内定通知書や雇用契約書との違い、交わされるタイミングを把握しておけば、不必要な不安を抱えずに対応できます。
また、誓約書は企業への誠意を示す手段であり、内定辞退の抑止や信頼関係の強化につながりますが、法的効力には限界があることも意識しておく必要があります。
さらに、宛名や署名の記入方法、提出時のマナーを守ることで、社会人としての評価も高まります。万が一提出後に辞退する場合も、適切な伝え方やフォローを徹底すれば大きなトラブルは避けられます。
入社誓約書を正しく理解し準備することが、就活をより安心して進める第一歩となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。