就活の健康診断書はいつ必要?提出時期と入手方法や注意点を徹底解説
「就活で健康診断書って本当に必要なの?」と疑問に思う学生は少なくありません。多くの企業では内定や入社のタイミングで提出を求められ、業務を安心して始められるかどうかを確認するための大切な書類です。
しかし、どの段階で必要になるのか、どこで入手すればいいのか、分かりにくい点も多いでしょう。そこで本記事では、就活における健康診断書の役割や提出の流れ、注意点をわかりやすく解説し、準備をスムーズに進められるようサポートします。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活で提出が求められる「健康診断書」とは
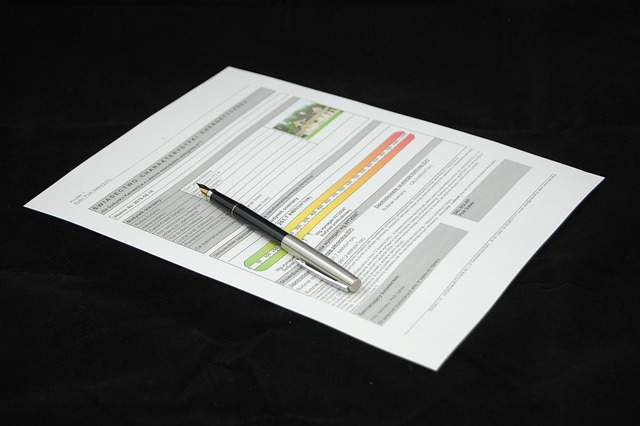
就活において健康診断書は、採用選考や入社準備で企業から提出を求められることがある重要な書類です。
多くの学生は履歴書や成績証明書に目を向けがちですが、健康診断書の準備を怠ると直前に慌てる原因になりかねません。
そもそも健康診断書とは、健康診断を受けた結果をまとめた公式な証明書で、大学の定期健診や病院での健診をもとに発行されます。
これが必要とされる理由は、企業が採用後に就業環境へ適応できるかを確認するためであり、合否そのものに直結することは少ないでしょう。しかし、提出が遅れたり不足したりすると印象を下げる恐れがあります。
準備の要点は、提出期限に余裕を持って発行しておくことと、大学や医療機関でどのように入手できるかを早めに確認しておくことです。健康診断書は単なる形式的な書類ではなく、社会人としての責任感を示す大切な手段だと理解してください。
就活で健康診断書が必要とされる理由

就活で健康診断書が必要とされるのは、企業が安心して学生を迎え入れるためです。学生からすると軽く考えがちですが、法的な義務や安全配慮とも深く関わっています。
ここでは、健康診断書が求められる主な理由をわかりやすく紹介します。
- 企業が就活生の健康状態を確認するため
- 入社後に業務を安全に遂行できるか知るため
- 法令に基づき、雇入れ時に必要なため
- 長時間労働やストレス環境に対応できるかを確認するため
- 労働災害や健康リスクを未然に防ぐため
①企業が就活生の健康状態を確認するため
企業が健康診断書を求める大きな理由は、学生の健康状態を正確に把握するためです。特に、体調や持病が業務に影響する可能性がある場合、事前に理解しておけば安心して働き始められるでしょう。
診断結果が直接的に合否に響くことは、基本的にありません。むしろ「状況を知ったうえで職場環境を整える」という意味が強いのです。
過度に不安を感じる必要はなく、正しい診断結果を提出することが大切といえます。
②入社後に業務を安全に遂行できるか知るため
健康診断書は、仕事を安全に続けられるかを確認する目的でも必要です。体力を求められる職種や夜勤がある業務では、基本的な健康状態を把握しておくことが不可欠でしょう。
企業は状況に応じて配置を工夫したり、条件を調整したりします。これは学生を守るためであり、同時に業務を安定させるためでもあるのです。
健康診断書の提出は形式的ではなく、実務的な意味を持っていると理解してください。
③法令に基づき、雇入れ時に必要なため
健康診断書の提出は、労働安全衛生法によって定められた義務でもあります。雇入れ時の健康診断は事業者に課されており、その結果を証明する書類が健康診断書です。
学生の立場では「選考とは関係ないのでは」と思うかもしれません。しかし、安全な労働環境を確保するための必須手続きといえます。
法律上の義務であることを理解すれば、なぜ企業が必ず診断書を求めるのか納得できるはずです。
④長時間労働やストレス環境に対応できるかを確認するため
現代の職場では、長時間勤務や強いストレスに直面する場面もあります。そこで企業は、学生がある程度の負荷に耐えられるかを見極めるために健康診断書を確認するのです。
決して無理を強いるためではなく、健全に働ける環境を整える参考にしています。もし慢性的な持病や注意点があれば、早めに把握してもらうことでトラブルを避けられるでしょう。
健康診断書は「働く準備が整っている証明」と考えてください。
⑤労働災害や健康リスクを未然に防ぐため
企業が健康診断書を重視する背景には、事故や健康被害を防ぐ狙いがあります。高血圧や心疾患などは無理な業務をすると大きな問題につながる可能性があるため、事前に把握することが重要です。
診断結果を共有すれば、必要に応じてサポート体制を整えたり配置を変えたりできます。その結果、学生の安全を守るだけでなく企業にとってもリスク管理になるのです。
健康診断書は、双方の信頼関係を築くうえで欠かせない書類といえるでしょう。
就活の健康診断書が求められるタイミング

就活で健康診断書が必要になる場面は多くありませんが、提出時期を理解していないと直前に慌てる原因になります。基本的には選考中ではなく、内定後や入社前に求められることが一般的でしょう。
ここでは、提出を求められる主なタイミングを整理し、準備の大切さを説明します。
- エントリーや面接時に提出を求められるケース
- 内定後に提出を求められるケース
- 入社前に雇入れ時健康診断として提出が必要なケース
①エントリーや面接時に提出を求められるケース
一部の企業では、応募や面接の段階で健康診断書を求めることがあります。これは安全面を重視する業界や、特殊な業務を行う企業に多い傾向です。
学生は、早めに大学の健康診断や病院で発行手続きを済ませておくと安心でしょう。特に、募集要項に記載されている場合は見落とさないよう注意してください。
一般的なケースではありませんが、想定して準備する姿勢が結果的に選考をスムーズに進める助けになります。
②内定後に提出を求められるケース
最も多いのは、内定通知を受けたあとに健康診断書を提出するケースです。企業は学生が入社後に問題なく働けるかを確認するために提出を求めます。
期限は会社によって異なりますが、短期間で提出を求められることも少なくありません。大学の保健センターや病院の発行方法を早めに確認しておくと慌てずに済むでしょう。
内定後に予約が取れず困る学生もいるため、余裕を持った準備が欠かせません。
③入社前に雇入れ時健康診断として提出が必要なケース
入社直前には、労働安全衛生法に基づく雇入れ時健康診断が義務づけられています。この結果を証明するのが健康診断書であり、必ず提出が求められるでしょう。
学生からすれば「なぜ再度受けるのか」と感じるかもしれませんが、安全な職場環境を整えるために必要な手続きです。
検査内容は一般的な健康診断とほぼ同じで、多くの企業は内定後に改めて受診を案内します。法律上の義務でもあるため、提出しなければ入社できません。確実に対応してください。
就活の健康診断書に記載される項目

就活で提出する健康診断書には、多くの検査結果が記載されます。これは採用後に業務へ支障がないかを確認する目的があるためです。
具体的には既往歴から血液検査まで幅広く含まれ、学生にとって不安を感じる部分もあるでしょう。ここでは、主要な項目を整理して説明します。
- 既往歴や業務歴に関する調査項目
- 自覚症状や他覚症状の有無に関する検査項目
- 身長・体重・腹囲などの身体測定項目
- 視力・聴力などの基礎的な検査項目
- 血圧測定による健康状態の確認項目
- 胸部エックス線や喀痰検査による呼吸器系の確認項目
- 血液検査(貧血や肝機能など)の主要項目
- 血中脂質や血糖値など生活習慣病に関する検査項目
- 尿検査による腎機能や糖・たんぱく質の確認項目
- 心電図検査による心臓機能の確認項目
①既往歴や業務歴に関する調査項目
健康診断書には過去の病歴や手術歴、業務上の病気に関する情報が記載されます。これは、企業が採用後に配慮すべき点を確認するために欠かせません。
特に、長期治療歴や慢性的な疾患は、仕事内容によっては支障になる可能性があるため正直に申告することが重要です。隠しても後からわかる場合が多く、かえって信頼を損ねるでしょう。
大きな問題がある場合は、医師に就労に関する意見を添えてもらうと安心できます。正確に伝えることが、信頼につながると把握しておきましょう。
②自覚症状や他覚症状の有無に関する検査項目
自分で感じる不調や、医師が診察で見つけた症状も健康診断書に記載されます。慢性的な頭痛や息苦しさが自覚症状にあたり、心音の異常や皮膚の変化は他覚症状に分類されています。
これは、働き始めてから急に悪化するリスクを把握するための項目です。小さな症状でも軽視せず、診察時に正直に伝えてください。早めの対応につながり、採用後の健康管理にも役立つでしょう。
③身長・体重・腹囲などの身体測定項目
身体測定は、基本的な健康状態を知るために行われます。身長や体重だけでなく腹囲も測定するのは、内臓脂肪の蓄積を確認するためです。
生活習慣病との関係が強く、社会人生活を見据えたチェックといえるでしょう。学生のうちからバランスのよい食事や適度な運動を心がけると、診断結果にもよい影響が表れます。
特別な準備は不要ですが、日々の生活習慣が反映されることを理解しておくことが安心につながるでしょう。
④視力・聴力などの基礎的な検査項目
視力と聴力の検査は、業務に必要な感覚機能を確認するための大切な項目です。視力は眼鏡やコンタクトで矯正できる場合が多く、聴力も軽度の異常なら大きな問題にはならないでしょう。
ただし、安全性が重視される職場では基準が厳しい場合もあります。学生の段階で異常が見つかったときは、早めに眼科や耳鼻科で診てもらってください。
診断書に結果が残ることで、適切な環境で働ける可能性が高まります。
⑤血圧測定による健康状態の確認項目
血圧は、心臓や血管の健康を示す重要な指標です。高血圧や低血圧は将来的に体調不良の原因になりやすいため確認が必要になります。
学生の段階では自覚がなくても、生活習慣の乱れによって数値が変動することがあるかもしれません。診断時に高めと指摘された場合は、塩分を控えたり睡眠を見直したりすることで改善できるでしょう。
入社前に生活を整えるきっかけにもなるので、結果を軽視しないことが大切です。
⑥胸部エックス線や喀痰検査による呼吸器系の確認項目
胸部エックス線や喀痰検査は、肺や気管支の状態を確認するために行われます。結核や慢性気管支炎など、呼吸器系の病気を早期に見つけることが目的です。
特に集団で働く環境では、感染症の有無を調べることが重要になります。異常が見つかった場合は追加検査や治療が必要ですが、早めに対応できる点で安心です。
喫煙習慣がある人は影響が出やすいため、禁煙に取り組むきっかけにもなるでしょう。
⑦血液検査(貧血や肝機能など)の主要項目
血液検査では赤血球や白血球の数値、肝機能や腎機能の状態などを確認します。貧血があると疲れやすく集中力が下がる可能性があるでしょう。また、肝機能の異常は飲酒や薬の影響で見つかることも少なくありません。
数値に異常があると、無理なく働けるかどうかに直結するため重視されます。学生時代に気づかなかった不調が明らかになることもあるため、健康管理のきっかけになるでしょう。
⑧血中脂質や血糖値など生活習慣病に関する検査項目
血中脂質や血糖値の検査は、将来の生活習慣病リスクを評価するために行われています。社会人になると食生活や運動不足から数値が悪化しやすいため、早めに把握することが予防につながるでしょう。
学生の段階で異常があっても大きな問題にはならず、生活習慣を整えれば改善できるケースが多いです。健康診断書に数値が記載されることで、自分の生活を見直すきっかけになります。
⑨尿検査による腎機能や糖・たんぱく質の確認項目
尿検査は腎臓の働きを確認するだけでなく、糖尿病や感染症の兆候を調べる役割もあります。
特に、たんぱく尿や糖尿が見つかると生活習慣の乱れや病気の可能性があるため、追加検査が必要になることもあるでしょう。
検査自体は簡単で負担も少ないですが、結果は健康状態を左右します。小さな異常でも放置すると将来的なリスクが高まるため、医師の指導に従って生活を見直すことが大切です。
⑩心電図検査による心臓機能の確認項目
心電図検査は心臓の動きを記録し、不整脈や虚血性心疾患の有無を調べます。運動量が多い仕事や長時間勤務が想定される場合、この検査結果は特に重視されるでしょう。
学生のうちは症状がなくても、検査で異常が見つかることがあります。早めに気づければ治療や生活改善でリスクを減らせるため、安心して社会人生活を始められるでしょう。
結果に異常が出ても、すぐに不採用になることは少ないので過度に心配する必要はありません。
就活の健康診断書はどこで入手できる?

就活で必要な健康診断書は、大学や病院など複数の方法で入手できます。早めに把握しておけば、直前で慌てる心配もありません。
ここでは、代表的な3つの入手方法を取り上げ、それぞれの特徴や注意点を解説します。
- 大学で発行してもらう
- 病院やクリニックで受診する
- 自治体の保健センターを利用する
①大学で発行してもらう
大学で行われる定期健康診断の結果をもとに、発行してもらう方法が最も一般的です。学生課や専用窓口で申請でき、費用も比較的安く済むでしょう。就活生にとっては、手続きが簡単で利用しやすい手段です。
ただし、発行までに数日かかる場合や、その年度の結果しか利用できないこともあります。余裕をもって申請しておけば提出期限に間に合い安心です。
さらに、原本の提出を求められることが多いため、複数枚必要なときは追加発行をお願いしておくと良いでしょう。
②病院やクリニックで受診する
大学での発行が難しい場合や急ぎで必要なときは、病院やクリニックで健康診断を受ける方法があります。予約をすれば、自分の都合に合わせて受診できるのが大きな利点です。
一般健診コースで足りる場合も多いですが、企業が指定する検査項目があるかを必ず確認してください。大学より費用は高めですが、短期間で診断書を受け取れるのは大きなメリットです。
ただし、結果が出るまで数日かかることもあるので、余裕を持って受診することをおすすめします。
③自治体の保健センターを利用する
自治体が運営する保健センターを利用する方法もあります。卒業後の学生や、病院の費用を抑えたい人に適しています。
費用が比較的安く予約も可能ですが、健診を受けられる時期が限られている点には注意が必要です。さらに、内容が生活習慣病予防に偏ることがあり、提出先の企業が求める項目を満たさない場合もあります。
就活用として利用できるかどうかは地域によって異なるため、事前にホームページや電話で確認してから手続きしてください。
就活で健康診断書を用意するときの注意点

就活で健康診断書を準備する際には、提出期限や有効期間など注意すべき点があります。見落とすと選考に影響する可能性があるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
ここでは、特に重要な4つのポイントを紹介します。
- 発行までに時間がかかることに気をつける
- 健康診断書は原本を提出する必要がある
- 有効期限があることを把握する
- 健康診断書と健康診断証明書の違いを理解する
①発行までに時間がかかることに気をつける
健康診断書は依頼してすぐ受け取れるわけではなく、検査結果の確認や書類作成に数日から1週間程度かかる場合があります。提出期限が迫ってから申請すると間に合わないこともあるでしょう。
余裕を持つためには、就活の日程が見えてきた時点で早めに健診を受けておくのが安心です。大学の保健センターや指定のクリニックを利用する場合、申込が集中して予約が取りにくくなることもあります。
スケジュールに余裕を持って行動すれば、提出の遅れによる不安を避けられるでしょう。
②健康診断書は原本を提出する必要がある
企業が求めるのはコピーではなく、必ず原本です。コピーを提出すると正式な書類として扱われず、再提出を指示されることがあります。
もし原本が1部しかなく再取得が必要になると、余計な時間や手間がかかってしまうでしょう。複数の企業に提出する予定がある場合は、最初から追加発行を依頼しておくと安心です。
多少の費用はかかりますが、就活中のトラブルを防ぐ備えとして有効でしょう。
③有効期限があることを把握する
健康診断書には有効期限があり、一般的に発行日から3〜6か月とされています。古いものでは受け付けてもらえない場合があるため、提出時期を確認せず提出すると差し替えを求められる可能性があります。
企業によっては独自に期限を設けていることもあるため、募集要項や案内文を必ず確認してください。不明点は問い合わせたほうが確実でしょう。
就活が長期化して有効期限を超えてしまうと、健診を受け直す必要があります。期限を意識したスケジュール管理が欠かせません。
④健康診断書と健康診断証明書の違いを理解する
健康診断書と健康診断証明書は、似ていますが内容は大きく異なります。健康診断書は検査結果が詳細に記載された正式な書類で、企業が提出を求めるのはこちらです。
一方の健康診断証明書は「受診した事実」を示すだけで、具体的な数値や内容は含まれていません。誤って証明書を提出すると不備とされる可能性があります。
提出先がどちらを求めているのか必ず確認し、指示がなければ健康診断書を準備するのが安全でしょう。違いを理解しておくことで余計なトラブルを防げます。
健康診断書を郵送する際のマナー

就活で健康診断書を郵送するときは、ただ送ればよいというわけではありません。書類は企業にとって大切な選考資料であり、送り方次第で印象が変わることもあります。
誤った対応を避けるために、正しいマナーを理解しておくことが大切です。ここでは、特に注意したい3つのポイントを紹介します。
- 添え状を同封して提出する
- クリアファイルに入れて破損を防ぐ
- 封筒に「健康診断書在中」と明記する
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①添え状を同封して提出する
健康診断書を送るときは、必ず添え状を同封してください。添え状には「誰から」「何を送るか」を簡潔に明記し、受け取った担当者が内容をすぐ確認できるようにしましょう。
添え状がないと事務的に不親切な印象を与え、管理の手間を増やすおそれがあります。宛先や送付日、自分の氏名や連絡先、送付物の一覧を記載しておけば安心でしょう。
企業は多くの応募書類を扱っているため、添え状を添えることでスムーズなやり取りにつながります。
②クリアファイルに入れて破損を防ぐ
郵送中の折れや汚れを防ぐため、健康診断書はクリアファイルに入れて封筒に入れるのが望ましいです。診断書はコピー不可で原本を求められることが多く、破損すると再発行の手間が発生してしまいます。
雨や輸送時の衝撃など予想外のトラブルから守るためにも、クリアファイルは必須といえるでしょう。
見た目の印象も整い、受け取る企業に丁寧さを感じてもらえます。こうした配慮は、信頼感にもつながるはずです。
③封筒に「健康診断書在中」と明記する
封筒には必ず「健康診断書在中」と赤字で記載してください。重要書類であることを示すことで、誤開封や紛失のリスクを減らせます。
企業側も仕分けや保管がしやすく、事務処理の効率化にもつながるでしょう。記載する場所は宛名の左下が一般的で、朱書きにするとさらに目立ちます。
基本的なマナーを守れば、不備を指摘される心配もなく安心して送付できるでしょう。
健康診断書が間に合わない場合の対処法

就活で健康診断書の提出が必要になることは多いですが、準備が遅れて間に合わないケースもあります。
そのままにすると信用を失いかねませんが、正しい対応をすれば印象を大きく損なうことはないでしょう。ここでは、具体的な3つの方法を紹介します。
- メールで連絡する
- 電話で連絡する
- 代替手段を伝える
①メールで連絡する
提出が遅れると分かった時点で、まずはメールで知らせるのが基本です。メールであれば相手の業務を妨げず確認してもらえるため、失礼になりにくいでしょう。
文面には「間に合わない理由」「提出予定日」「代替できる書類の有無」を簡潔に記してください。曖昧な言い回しを避け、誠意が伝わる内容にすることが大切です。
早めの報告は誠実さを示し、遅延による不安を軽減できるでしょう。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
②電話で連絡する
提出期限が目前に迫っている場合や、急ぎの対応が必要と判断できる場合は電話が適切です。直接声で伝えることで、より誠意が伝わり安心感を与えられるでしょう。
話すときは、まず謝罪を述べてから理由を端的に説明し、そのうえで「いつ提出できるか」を明確にしてください。電話をする時間にも配慮が必要で、業務の負担にならないように工夫することが望ましいです。
③代替手段を伝える
どうしても健康診断書の原本をすぐに準備できない場合は、代替書類を相談するのも有効です。大学の定期健康診断の結果票や、医療機関の診断証明書などが一時的に認められることもあります。
その際には「正式な診断書は後日提出する」と約束しておけば、柔軟に対応してもらえる可能性が高いでしょう。大事なのは遅れることを隠さず、状況を正直に伝えて代替案を示す姿勢です。
就活の健康診断書に関するよくある質問

就活で提出を求められる健康診断書については、多くの学生が疑問や不安を抱きやすいものです。診断を受けていない場合や複数企業への提出などは特に迷いやすい点でしょう。
ここでは代表的な質問を取り上げ、安心して準備できるよう解説します。
- 健康診断を受けていない場合はどうすればいい?
- オンライン診断や簡易診断は就活で使える?
- 健康診断書の内容で選考に落ちることはある?
- 複数の企業に同じ健康診断書を提出してもよい?
①健康診断を受けていない場合はどうすればいい?
健康診断をまだ受けていないときは、できるだけ早めに医療機関で予約を取ることが大切です。大学の定期健診で診断書を発行してもらえる場合もありますが、時期を過ぎると対応できないこともあります。
その際は、病院やクリニックで依頼してください。提出期限に間に合わないときは、必ず企業に連絡し、後日提出の了承を得ておくと安心です。何も伝えずに遅れると誠意を疑われかねません。
早めの行動と正直な対応が、信頼を守る一番の方法でしょう。
②オンライン診断や簡易診断は就活で使える?
オンライン診断や簡易的なチェックでは、就活に必要な正式な診断書は発行されません。企業が求める診断書には血液検査や胸部X線など、一定の検査が含まれているためです。
もし、費用や時間が心配で迷っているなら、大学の学生課に相談してみてください。安く受診できる医療機関を紹介してもらえることがあります。
制度をうまく利用すれば負担を抑えながら、安心して提出できる診断書を準備できるでしょう。
③健康診断書の内容で選考に落ちることはある?
診断書の内容が、直接選考結果に影響することはほとんどありません。企業が診断書を求める目的は、採用後に仕事を安全に続けられるかを確認するためです。
持病や体調の問題があっても、それだけで不採用になるケースは少なく、配属や勤務形態の調整に役立てられることが多いでしょう。むしろ隠すと後々トラブルになる可能性があります。
正直に提出することで安心して働ける環境が整うため、ありのままの情報を伝えることが自分を守る結果につながるでしょう。
④複数の企業に同じ健康診断書を提出してもよい?
同じ診断書を複数の企業に提出しても、基本的に問題はありません。有効期限内であれば複数利用できるため、原本を複数部発行してもらうのがおすすめです。
医療機関によっては追加料金がかかる場合もあるので、必要な部数を見込んで依頼してください。ただし、企業によっては「発行から3か月以内」といった独自の基準を設けていることもあります。
提出先の条件を必ず確認し、計画的に準備することが大切です。
就活の健康診断書に関する最終的な考え方

就活において健康診断書は、企業が応募者の健康状態を確認し、入社後に安心して働けるかどうかを判断するために重要な書類です。
診断書には身体測定や血液検査など多くの項目が含まれ、法令上の要件も関わっています。そのため発行に時間がかかることや有効期限の存在など、注意点を理解して準備することが必要です。
診断書は大学や病院、保健センターで入手できます。提出時にはマナーも求められるでしょう。結論として、就活の健康診断書は形式的な提出物ではなく、自分の健康と働く環境の双方を守る大切なものです。
早めに準備を進め、正確かつ丁寧に対応することが就活を円滑に進める大きなポイントでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










