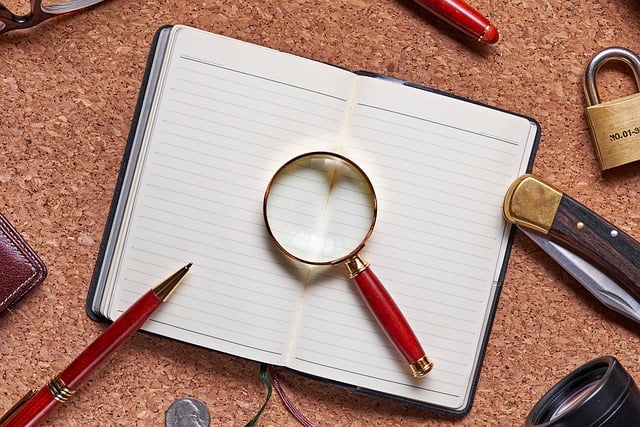就活に必須の一般常識勉強法!効率的に対策するコツと問題集を紹介
就活を進める中で「一般常識テスト」という言葉を耳にして、不安を感じたことはありませんか?
「どんな問題が出るの?」「SPIと何が違うの?」「どのくらい勉強したらいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
一般常識テストは、基礎的な学力や社会人としての素養を確認するために導入されることが多く、企業によっては選考を大きく左右するケースも。
この記事では、就活における一般常識の定義から出題範囲、効率的な勉強法、役立つ問題集まで幅広く解説します。不安を解消しながら、自信を持って選考に臨めるように準備を進めていきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活における「一般常識」とは?

就活における「一般常識」とは、企業が学生の基礎学力や、社会人としての素養を確認するために実施するテストのことです。
ここでは、就活生が知っておくべき一般常識テストの定義や、重視される場面、さらにレベル感について詳しく解説します。
- 就活における「一般常識」の定義
- 一般常識テストが重視される就活の場面
- 一般常識テストのレベル感
①就活における「一般常識」の定義
就活における一般常識とは、企業が応募者の社会人としての基礎力や、思考力を測るために実施する筆記試験を指します。
国語や数学などの主要教科に加え、時事問題や経済、政治、ビジネスマナーなどの社会常識も含まれ、幅広い知識が求められています。
これは、入社後に必要となる判断力や情報収集力、学習習慣を確認するためです。
SPIなどの適性検査とは異なり、知識そのものの定着度を重視している点が特徴。早い段階で対策を始めると不安なく臨め、自信を持って試験に挑めるでしょう。
②一般常識テストが重視される就活の場面
一般常識テストは、エントリーシートや面接と並び、採用初期に多くの企業が実施することが多いです。
特に、大手企業や公務員試験、マスコミや金融業界では、応募者が多いため筆記試験で足きりを行うケースが目立ちます。
また、配属先や教育方針を決める際の参考として、学生の基礎学力や社会常識を把握する目的で、活用されることもあるようです。
このように、一般常識テストは選考の入り口でありながら、合否に直結する重要なポイントといえます。早期から出題範囲を把握し、効率的な勉強法を取り入れると他の就活生との差をつけられるでしょう。
③一般常識テストのレベル感
一般常識テストのレベル感は「中学生から高校生レベル」が基本とされますが、単純な知識問題だけでなく、社会の動きや最新ニュースに関連する時事問題も多く出題されます。
そのため、主要教科の基礎問題に加え、ニュースや新聞、ネット記事などで情報を更新しておくことが大切です。
ビジネスマナーや社会人としての常識を問う設問もあるため、日常生活での知識の積み重ねが有利に働きます。難易度は極端に高くありませんが、出題範囲が広く時間配分が求められる試験です。
日頃から少しずつ学習習慣をつけ、試験形式に慣れておくことで本番でも安定した得点につながります。
就活で一般常識テストが行われる理由

就活で一般常識テストが行われるのは、単なる知識確認ではなく、学生の総合的な力や将来性を判断するためです。
企業は応募者の基礎力や判断力を多角的に見ており、選考の効率化や採用後のミスマッチ防止といった狙いもあります。ここでは、企業が一般常識テストを導入する具体的な理由を整理して解説しましょう。
- 応募者の基礎的な思考力や判断力を測るため
- 学力や社会常識を可視化するため
- 選考を効率化するため
- 配属や教育方針を検討するため
- 採用後のミスマッチを防ぐため
①応募者の基礎的な思考力や判断力を測るため
企業が一般常識テストを実施する大きな目的は、応募者の基礎的な思考力や判断力を知ることにあります。表面的な知識だけではなく、問題に対してどう考え、どれだけ正確に処理できるかを確認しているのです。
特に、論理的思考や文章理解、数的処理は仕事の基盤となる力でしょう。早めに対策を始めれば、知識の幅を広げつつスピードと正確性を備えた対応力を養えます。
これが本番での安定した結果につながり、自信を持って試験に挑めるでしょう。
②学力や社会常識を可視化するため
企業は、応募者の持つ基礎学力や社会常識を客観的に把握するために、一般常識テストを利用しています。履歴書や面接だけでは見えにくい知識量や、社会への関心度を測れるからです。
特に、時事問題やビジネスマナーなど、日常生活では学びにくい分野が問われることもあります。日々のニュースや書籍から情報を吸収し、幅広い知識を積み重ねることが効果的です。
自分の得意・不得意を知るきっかけにもなり、効率的に勉強の優先順位を決めやすくなるでしょう。
③選考を効率化するため
大量の応募がある企業では、限られた時間で応募者を絞り込む必要があります。一般常識テストは、そのための有効な手段として機能しており、一定の基準で客観的に評価が可能です。
特に、初期選考で実施されることが多く、短時間で多くの応募者を比較しやすいのが特徴。そのため、早めに勉強法を確立しておくことで、選考の第一段階を突破しやすくなります。
こうした準備が自信や安心感につながり、本番で力を発揮しやすくなるでしょう。
④配属や教育方針を検討するため
企業は、採用後の育成や配属先決定の参考としても、一般常識テストを使っています。
基礎学力や知識の幅を知ることで、どの部署に適性があるか、どのような教育プログラムが必要かを判断しやすくなるためです。
テスト結果を通して自分の強みや弱みを理解でき、就活後のキャリア形成に役立てられます。幅広い分野に関心を持ち、基礎知識を固めておくことが、選考だけでなく入社後の評価にも好影響を与えるでしょう。
⑤採用後のミスマッチを防ぐため
企業は、採用後のミスマッチを防ぐためにも、一般常識テストを活用しています。入社後に必要な知識や考え方にギャップがあると、早期離職やパフォーマンス低下につながる可能性があるからです。
テストを通じて、求めるレベルに達しているか、また適性を持っているかを見極めています。就活生にとっても、この試験を受けることで自分の知識不足を把握し、改善点を早めに見つけられる機会になります。
これにより入社後のギャップが減り、働きやすい環境で成長しやすくなるでしょう。
SPIと一般常識テストの違い

SPIと一般常識テストは、どちらも就活の選考で使われる試験ですが、目的や内容、受験形式が大きく異なります。違いを知ると自分に合った勉強法を立てやすくなり、効率的な対策につながるでしょう。
ここでは、出題内容・受験形式・対策方法の3つの視点から解説します。
- 出題内容の違い
- 受験形式の違い
- 対策方法の違い
①出題内容の違い
SPIは「能力検査」と「性格検査」の2本立てが基本で、言語分野・非言語分野の問題に加え、性格や適性に関する設問が出題されます。
一方、一般常識テストは国語・数学・英語・社会・理科などの主要教科や時事問題、ビジネスマナーなどの知識を問う内容が中心です。
つまり、SPIは思考力や適性を確認する試験であり、一般常識テストは知識の定着度や教養を測る試験といえます。違いを理解しておけば、自分に必要な勉強範囲がはっきりし、効率的に準備できるでしょう。
②受験形式の違い
SPIはテストセンター、ペーパーテスト、自宅受験(Webテスト)など複数の形式があります。受験環境によって、制限時間や問題数が異なることもあるため、事前に受験方法を確認しておくことが大切です。
一方、一般常識テストは多くの場合、面接当日や説明会の際にペーパー形式で行われ、短時間で基礎力を確認する傾向があります。形式の違いを把握しておくと、事前準備の優先順位を決めやすくなるでしょう。
③対策方法の違い
SPIは、スピードと正確性が求められるため、問題集や模試で繰り返し練習し、時間管理の感覚を身につけることがポイントです。性格検査は、自分の特性を把握しておくことで一貫した回答ができます。
一方、一般常識テストでは新聞やニュースで時事問題に触れたり、基礎教科の復習をしたりすることが欠かせません。ビジネスマナーや、社会常識の参考書を活用するのも有効です。
試験ごとに求められる準備が異なるため、目的に応じて対策方法を分けることが合格への近道になります。
一般常識テストの出題範囲
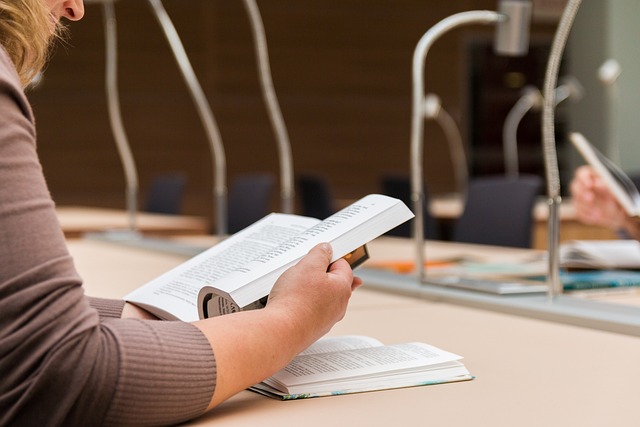
一般常識テストは、主要教科や時事問題だけでなく、ビジネスマナーや文化教養まで幅広く問われます。
出題範囲を知っておくと、自分に必要な対策が見えやすくなり、効率よく勉強法を組み立てられるでしょう。ここでは、主要教科から社会常識まで、それぞれの特徴と対策ポイントを解説します。
- 主要教科の出題範囲
- 時事問題の出題範囲
- ビジネスマナーや社会常識の出題範囲
- 文化・教養問題の出題範囲
①主要教科の出題範囲
一般常識テストでは国語、数学、英語、理科、社会などの主要教科が幅広く出題されます。
中学から高校レベルの基礎的な問題が中心ですが、単純な知識だけでなく計算力や文章読解力など、社会人として必要な基本スキルが試されることが多いです。
重点的に取り組むべきは、自分が苦手な科目や頻出分野を正確に把握することです。過去問や問題集を活用し、短時間で正確に解答する練習を繰り返すことで、試験本番のパフォーマンスが安定します。
基礎をしっかり固めておけば、他の受験者との差別化が図れ、自信を持って挑めるでしょう。
②時事問題の出題範囲
時事問題は、社会の動きやニュースへの関心度を測るために、多くの企業で必ずといっていいほど取り入れられています。政治や経済、環境、国際情勢など、幅広いテーマから出題されることが一般的です。
日常的に新聞やニュースサイト、ニュースアプリをチェックし、自分なりに要点をまとめる習慣を持つことが重要。定期的にニュースを振り返るだけでも、記憶の定着が進みます。
出題傾向を把握しておけば、限られた時間でも効率よく準備でき、試験当日も落ち着いて回答できるでしょう。
③ビジネスマナーや社会常識の出題範囲
多くの企業では、社会人としての基本姿勢やマナーを確認するための問題も出題されます。
敬語の使い方、電話応対、メールの書き方、基本的なビジネス用語、さらには会社の組織構造や社会人としての振る舞いなどが代表例です。
これらは、知識として暗記するだけでなく、日常生活やアルバイト、インターンなどで意識的に実践することが効果的でしょう。
こうした積み重ねは社会人としての基礎力を示すことにつながり、他の応募者との差別化にも大きく役立ちます。準備段階で意識的に取り入れることで、本番の対応力が格段に高まるでしょう。
④文化・教養問題の出題範囲
文化・教養問題は、歴史、地理、文学、美術、スポーツや科学技術など、非常に多岐にわたります。これは、学生の幅広い知識や興味関心の度合いを測るために用いられることが多いです。
日常的に本や記事、ドキュメンタリー番組などに触れ、文化的なイベントやニュースにも目を向ける習慣を持ってください。
特定の分野に偏らず、バランスよく学ぶことで、思わぬ問題にも柔軟に対応しやすくなります。
こうした地道な積み重ねが、自信を持って試験に臨むための確かな土台となり、長期的な教養力の向上にもつながるでしょう。
一般常識テストの勉強は必要?

一般常識テストの勉強が必要な理由は、まず選考突破のための基礎力を証明できる点です。テストは、応募者の知識や社会への関心度を数値で示すため、良い結果を残せば印象が大きく変わるでしょう。
さらに、企業は基礎力が高い学生を「柔軟に活躍できる人材」と見なす傾向があり、対策不足は不利になりかねません。
加えて、試験直前の一夜漬けでは高得点を取りにくく、準備不足が焦りや自信喪失の原因にもつながります。
早めに対策を進めれば、苦手分野の克服や問題形式への慣れが進み、安定した実力を発揮しやすくなるでしょう。
効率的な一般常識テストの勉強法
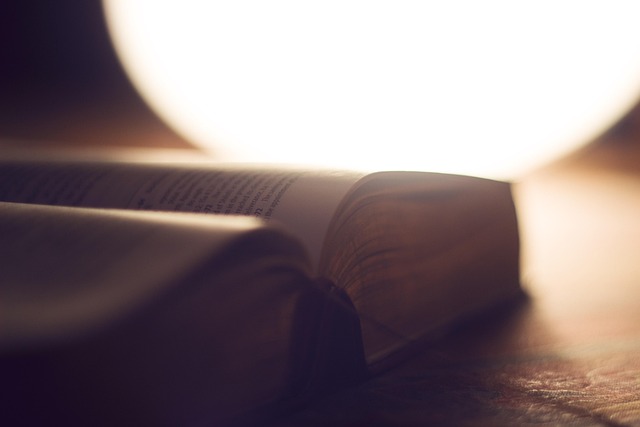
一般常識テストは範囲が広く、短期間の詰め込み学習だけでは対応が難しい試験です。効率的に準備を進めるには、自分の弱点を見極め、正しい方法で学習することが大切です。
ここでは、限られた時間の中で成果を上げるための勉強法を4つ紹介します。
- 新聞やニュースを活用する
- 過去問や問題集を使う
- 数学や英語など苦手分野を重点的に対策する
- 一般常識テスト対策アプリを活用する
①新聞やニュースを活用する
新聞やニュースは、時事問題や社会常識の対策に欠かせない重要な情報源です。日々のニュースに触れることで、政治や経済、国際情勢、さらには社会全体の動きを幅広く知れます。
ニュースアプリや新聞の要約サービスを活用すれば、通学中や休憩時間などのスキマ時間を効率よく使えるでしょう。
さらに、重要なテーマやキーワードは、自分なりにメモを取り、要点を整理してみてください。こうすることで、知識の定着が深まり、複雑なニュースでも背景を理解しやすくなります。
継続的な情報収集は、試験本番で落ち着いて対応できる自信にも直結し、他の受験者との差をつける武器となるでしょう。
②過去問や問題集を使う
過去問や問題集を繰り返し解くことは、出題傾向や自分の弱点を把握するうえで非常に効果的です。
実際の問題形式に事前に慣れておくと、試験当日の緊張もやわらぎ、時間配分の感覚もつかみやすくなります。時間を計って解く習慣をつければ、制限時間内で解答する力が自然に鍛えられるでしょう。
さらに、間違えた問題はその場で解説を確認し、なぜ誤答したのかをしっかり分析してください。
弱点を繰り返し復習することで、理解度が深まり、次に同じ問題形式が出てもスムーズに解答できるようになります。
この積み重ねが最終的に得点アップへとつながり、安定した結果を出せる土台となるでしょう。
③数学や英語など苦手分野を重点的に対策する
限られた時間で成果を最大化するには、自分が苦手な科目に優先的に取り組むことが重要です。
特に、数学や英語は、問題パターンや基本構造を理解することで得点が安定しやすくなるため、意識的に重点対策を行ってください。
公式や文法の基本を改めて見直し、演習を重ねることで、試験本番での対応力が高まります。苦手分野を克服しておくと、試験全体の得点力が底上げされ、強い自信を持って挑めるでしょう。
さらに、苦手科目を克服する過程は、論理的思考や集中力を鍛えることにもつながり、他の分野の学習効率まで高める効果があります。
④一般常識テスト対策アプリを活用する
一般常識テスト対策アプリを使えば、通学中や休憩中などのちょっとしたスキマ時間を、有効活用して効率よく勉強ができます。
問題演習や模擬試験機能が搭載されたアプリなら、本番に近い環境で実践的な練習が可能でしょう。
さらに、正答率や苦手分野を自動で分析してくれる機能があるものを選べば、自分に最適な学習計画を立てやすくなります。
紙の問題集と併用することで知識の定着度が増し、短期間でも実力を効果的に高められるでしょう。こうしたアプリの活用は、時間のない就活生にとって大きな味方となり、着実なスコアアップを後押しします。
スキマ時間を活用した一般常識テストの勉強法

就活中は授業やアルバイト、自己分析などやることが多く、まとまった学習時間を確保するのが難しいでしょう。そんなときこそ、スキマ時間をうまく使うことが重要です。
ここでは、短い時間でも効率よく知識を身につけるための方法を4つ紹介します。
- 移動中や休憩中を活用する
- 通知・ルーティンで継続する
- 一問一答形式を取り入れる
- 音声コンテンツや要約ニュースでインプットする
①移動中や休憩中を活用する
通学の移動時間や、短い休憩時間など、まとまった勉強時間を取りにくい時こそ細切れの時間を学習にあてると非常に効果的です。
単語カードや学習アプリを活用すれば、短時間でも効率的に知識を増やせます。さらに、毎日の習慣として続けることで、積み重ねた学習時間が大きな成果につながるでしょう。
特に、軽い復習や暗記科目など、短時間で反復できる内容に活用すると記憶がより定着しやすくなります。こうした工夫は、忙しい就活生にとって学習効率を大幅に高める武器になるでしょう。
②通知・ルーティンで継続する
スキマ時間を有効に使うためには、ただ時間を見つけるだけでなく、習慣化して継続する仕組みをつくることが大切です。
アプリの通知機能を活用して「毎日決まった時間に学習を始める」というルーティンを確立すると、自然に勉強のリズムが整います。
こうした仕組み化により「やるのが当たり前」という感覚が身につき、無理なく続けやすくなるでしょう。
さらに、短い時間でも毎日継続することが、知識の定着と試験対策の成果につながり、試験当日の落ち着きや自信にも大きな差を生みます。
③一問一答形式を取り入れる
一問一答形式は、短い時間でも知識を確認できる非常に効率的な学習方法です。自分で問題と答えをまとめたノートやカードを作れば、電車や待ち時間などでもすぐに取り組めます。
短時間で問題を解き、すぐに答え合わせができるため、記憶が定着しやすく復習もしやすいのが大きな特徴です。
さらにこの方法は、限られた時間内で素早く答える練習にもなり、試験本番での反応速度や思考の切り替え力を高める効果もあります。繰り返し活用することで、苦手な分野の克服にもつながるでしょう。
④音声コンテンツや要約ニュースでインプットする
移動中や家事の最中など、手がふさがっている時には、耳からの学習が特に有効です。音声コンテンツや要約ニュースを活用すれば、時事問題や社会常識を効率的に取り入れられます。
ラジオやポッドキャスト、音声ニュースアプリなどを利用すれば、通勤・通学時間をインプットの時間に変えられるでしょう。
耳からのインプットは繰り返し聞くことで記憶に残りやすく、短期間でも知識を広げることが可能です。
また文章だけでは得られないニュアンスや背景情報を理解しやすくなるため、試験で問われる応用問題にも対応しやすくなります。
就活後も役立つ教養力アップのための一般常識テストの勉強法

一般常識テストの勉強は就活のためだけでなく、社会に出てからも役立ちます。知識を更新し続けることで視野が広がり、仕事や人間関係でもプラスに働くでしょう。
ここでは、就活後も使える教養力アップの方法を4つ紹介します。
- 日々アップデートする
- 読書×ニュースで厚みを出す
- ディスカッションや勉強会で知識を深める
- 資格取得やオンライン講座で教養を広げる
①日々アップデートする
社会の情報は絶えず変化しているため、常に最新の知識を持ち続けることが仕事の基本であり、信頼にもつながります。
毎日少しずつニュースや専門サイト、業界の動向などを確認し、自分の知識を更新してください。SNSやメルマガを活用して、効率的に情報を集めるのも有効です。
こうした習慣を身につけることで、就活後の業務や人脈形成にも大きな強みとなるでしょう。常に最新情報を取り入れることが、柔軟な思考力や時代に対応する感覚を育て、キャリア形成にも良い影響を与えます。
②読書×ニュースで厚みを出す
本やニュースを組み合わせて読むことで、単なる知識にとどまらず背景や関連性を理解でき、より深い教養が身につきます。
時事問題や業界ニュースだけでなく、歴史や文化、心理学や哲学など幅広い分野に触れることが大切です。多角的に情報を吸収することで、会話力や文章力、発想力など幅広いスキルが鍛えられるでしょう。
さらに、知識の裏付けを持つことで論理的な説明力や説得力の向上にもつながり、社会人としての信頼度も高まります。読書とニュースを両立することで、知識の厚みを確実に築いてください。
③ディスカッションや勉強会で知識を深める
インプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を整理することも、教養の定着には欠かせません。
友人や同僚と時事問題や専門分野について話し合ったり、勉強会やオンラインのディスカッションに参加したりすることで、自分の考えを言語化する練習になります。
人に説明することで理解が深まり、記憶の定着率も大きく上がるものです。また、他者の意見に触れることで新たな視点が得られ、思考の幅や柔軟性も広がるでしょう。
定期的な交流を習慣にすると、自信を持って発信できる力が身につきます。
④資格取得やオンライン講座で教養を広げる
資格試験やオンライン講座を活用することで、独学では得にくい体系的な知識や実践的なスキルを習得できます。
特に、ビジネス系の資格や専門分野の講座は、日々の仕事に直結するスキルアップに役立つでしょう。
時間や場所を選ばず学べるオンライン講座は、就活後の忙しいスケジュールでも無理なく続けられる点が魅力です。
さらに、資格取得のプロセスそのものが、目標達成能力や計画性を養う機会となり、社会人としての自信と実力を高めることにもつながります。
継続的な学びは、長期的なキャリア形成や人脈拡大にも良い影響を与えるでしょう。
おすすめの一般常識問題集
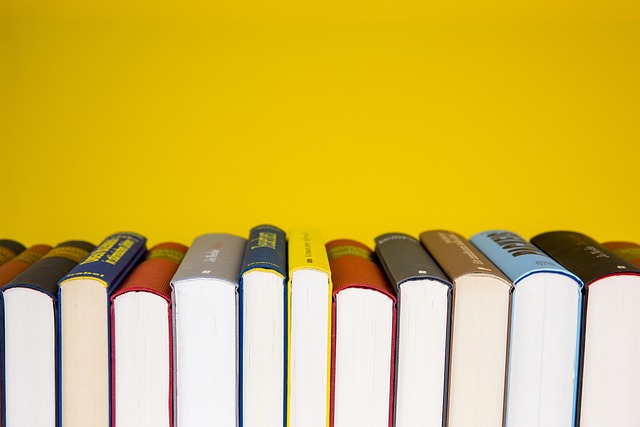
一般常識テスト対策を効率よく進めるには、自分の目的や生活スタイルに合った問題集を選ぶことが大切です。
基礎力を固めたい人、時事問題を重点的に学びたい人、スキマ時間を使って勉強したい人など、ニーズに合わせて活用すると効果的でしょう。
ここでは、おすすめの一般常識問題集を3つのタイプに分けて紹介します。
- おすすめの一般常識問題集:基礎力強化向け
- おすすめの一般常識問題集:時事問題対策向け
- おすすめの一般常識問題集:スキマ時間活用向け
①おすすめの一般常識問題集:基礎力強化向け
基礎力を固めたい人には、主要5教科や社会常識など幅広い分野を網羅した問題集が向いています。基礎から体系的に学べるため、苦手分野を見つけやすく安定した得点力を養いやすいでしょう。
初心者でも取り組みやすく、繰り返し解くことで確実に実力を高められます。
<おすすめ問題集例>
- 『就活必修!これだけで安心 一般常識の基礎問題集』
- 『大学生のための一般常識 完全対策BOOK』
- 『はじめての一般常識テスト対策 基礎からしっかり編』
②おすすめの一般常識問題集:時事問題対策向け
最新の時事問題に対応した問題集は、就活直前の集中対策に役立ちます。政治・経済・国際情勢など幅広いテーマを扱っているものを選ぶと効果的です。
ニュースや新聞だけでは拾いきれない要点が整理されており、短時間で理解を深められるでしょう。
<おすすめ問題集例>
- 『最新時事問題 一般常識テスト直前対策BOOK』
- 『時事力を鍛える!内定者のための時事問題演習集』
- 『ニュースで学ぶ就活時事問題総まとめ』
③おすすめの一般常識問題集:スキマ時間活用向け
通学や休憩時間などスキマ時間を使いたい人には、コンパクトな問題集やアプリ型の教材がおすすめです。1問1答形式や短時間で解ける問題が多く、隙間時間でも習慣化しやすいでしょう。
さらに、スマホやタブレットを使えば、持ち運びの手間もなく効率的に学習を続けられます。
<おすすめ問題集例>
- 『スマホでできる!一般常識一問一答アプリ』
- 『就活スキマ時間対策ポケット一般常識』
- 『通学中に解ける!短時間で仕上げる一般常識問題集』
一般常識テスト対策での失敗とその回避法
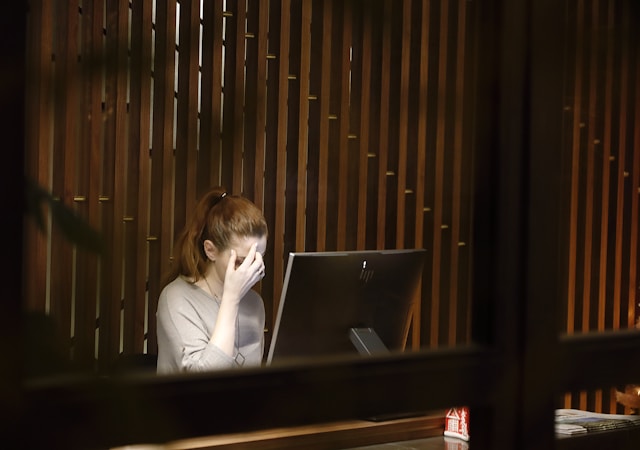
一般常識テスト対策では、方法を誤ると時間や労力が無駄になるだけでなく、本番で得点を伸ばせない原因になります。
ここでは、就活生が陥りやすい失敗と、その回避策を具体的に解説しています。事前にポイントを把握しておけば、効率的に力をつけられるでしょう。
- 出題形式に不慣れで時間が足りなくなる失敗
- 苦手分野を放置して得点が伸びない失敗
- 情報収集を怠り時事問題で失点する失敗
- 一夜漬けで定着せず落とす失敗
- 参考書・アプリを多用して散漫になる失敗
①出題形式に不慣れで時間が足りなくなる失敗
本番の試験形式に慣れていないと、問題の解き方や時間配分がうまくいかず、最後まで解き切れないことが多くなります。
特に、一般常識テストは幅広い分野から出題されるため、どこから手を付けるか迷う時間がロスにつながりやすいでしょう。
この失敗を避けるには、過去問や模試を活用し、本番同様の環境で何度も練習することが重要です。制限時間をしっかり設定して解くことで、自然と時間感覚が身に付きます。
さらに、問題を解く順序や優先順位を決める練習を重ねると、試験本番で焦らずに対応できるでしょう。
②苦手分野を放置して得点が伸びない失敗
苦手分野をそのままにしておくと、全体の得点が伸びず、合格基準に届かないことが少なくありません。一般常識テストは幅広い分野を問うため、苦手な科目だけが足を引っ張る可能性が高いでしょう。
この失敗を回避するには、早めに苦手分野を特定し、短時間でも毎日取り組むことが欠かせません。特に、基本問題から着実に取り組み、徐々に応用問題に進むと効果的です。
バランスよく学ぶ姿勢を保ち、得意科目との時間配分を調整しながら進めることで、総合力を底上げできるでしょう。
③情報収集を怠り時事問題で失点する失敗
最新のニュースや社会動向を把握していないと、時事問題で失点しやすくなります。
特に、政治・経済・国際情勢などは、短期間で大きく変化するため、直前だけでカバーしようとしても限界があるでしょう。
これを防ぐには、新聞やニュースアプリ、要約サービスなどを日常的に活用し、気になった話題をメモしておく習慣が有効です。
さらに、自分なりにまとめたり、誰かに説明したりすると知識の定着が早まります。毎日少しずつ情報を更新しておけば、試験本番で落ち着いて回答できる自信にもつながるでしょう。
④一夜漬けで定着せず落とす失敗
試験直前の一夜漬けに頼ると、知識が一時的に頭に入っても当日すぐに抜け落ちてしまい、安定した得点には結び付きません。
特に、一般常識テストのように幅広い分野を扱う試験では、一度の詰め込みで網羅することは不可能です。この失敗を防ぐには、毎日少しずつ積み上げることを意識してください。
短時間でも継続的に学ぶことで、記憶が長期間保持されやすくなり、知識が定着していきます。さらに、復習のタイミングを工夫し、忘れかけた頃に再度確認することで記憶が強化されるでしょう。
⑤参考書・アプリを多用して散漫になる失敗
複数の教材に手を出しすぎると、どれも中途半端に終わってしまい、知識が断片的になって整理されません。就活の準備期間は限られているため、教材の選び方を誤ると効率が大幅に落ちるでしょう。
これを避けるには、自分に合った問題集やアプリを1~2冊に絞り、繰り返し解いて定着度を高めることが大切です。
教材を使う前にサンプルを確認し、内容や形式が自分に合っているかを見極めるのも有効でしょう。焦っていくつも手を広げるより、厳選した教材を使い込むほうが、結果的に得点力を伸ばしやすくなります。
一般常識テストに関するよくある質問

一般常識テストは、就活生にとって避けて通れない試験ですが、勉強の始め方や時間配分、SPIとの両立など、多くの疑問を持つ人が少なくありません。
ここでは、よくある質問に答えながら効率的な対策のポイントを整理します。
- 一般常識の勉強はいつから始めるべき?
- 一般常識とSPIの勉強はどう両立する?
- 一般常識の合格ラインはどれくらい?
- 一般常識の勉強時間はどのくらい必要?
①一般常識の勉強はいつから始めるべき?
一般常識の勉強は、遅くとも就活解禁の半年前から始めておくと安心です。出題範囲が広く、直前の一夜漬けでは対応しきれないうえ、苦手分野を克服する時間も確保できません。
早めに取り組むことで、自分の得意・不得意を把握しやすく、効率的な学習計画が立てやすくなります。
さらに、新聞やニュースアプリを日常的に活用しておくと、自然に時事問題への理解が深まり、本番に役立つ知識が蓄積されていくでしょう。
短時間でも継続して積み上げることで、安定した実力を作ることが可能です。
②一般常識とSPIの勉強はどう両立する?
SPIと一般常識は、出題範囲や形式が異なりますが、基礎学力を伸ばすという点では共通しています。たとえば、SPIで身につけた計算力や読解力は、一般常識テストでも活かせる分野が多いでしょう。
両立のコツは、学習時間の区切りを明確にすることです。「午前はSPI、午後は一般常識」「平日はSPI、休日は一般常識」というようにルーティンを作れば、集中力を保ちやすくなります。
また、重複する分野(語彙力や文章理解など)を優先的に強化すると、効率的に相乗効果を得られるでしょう。
③一般常識の合格ラインはどれくらい?
一般常識テストの合格ラインは、企業や試験によって異なりますが、6~7割以上の得点を目安にすると安心です。
基礎問題で確実に得点し、応用問題で差をつける意識を持つと、安定して目標点に届きやすくなります。特に、苦手分野を放置せず、バランスよく知識を身につけることが大切です。
模試や過去問を繰り返し解くことで現状の実力を把握し、どの分野を重点的に対策すべきか明確にしていきましょう。目標点を決めて逆算する勉強法は、限られた時間の中でも成果を上げやすくなります。
④一般常識の勉強時間はどのくらい必要?
必要な勉強時間は個人差がありますが、1日30分~1時間を継続するだけでも確実に効果が出ます。短時間でも毎日触れることで、知識が定着しやすくなり、本番に強くなれるでしょう。
特に、移動中や休憩中などのスキマ時間を上手に活用すると、負担を減らしながら効率的に学べるためおすすめの勉強方法です。
さらに、週単位で学習計画を立て、進捗を確認する習慣をつけると、モチベーションの維持につながります。毎日の積み重ねが自信となり、試験当日のパフォーマンスにも良い影響を与えるでしょう。
一般常識勉強法の総合ガイド

就活で行われる一般常識テストは、学力や社会常識を可視化し、基礎的な判断力や思考力を測る重要な機会です。
SPIとの違いや出題範囲を理解し、効率的な一般常識勉強法を取り入れることで、自信を持って試験に臨めるでしょう。
新聞やニュースの活用、過去問対策、苦手分野の克服、そしてスキマ時間の活用が得点力を高めるカギです。
また、就活後も役立つ教養力アップのために、読書や勉強会、オンライン講座など継続的な学びが欠かせません。これらを組み合わせることで、就活だけでなく社会人としての基礎力も同時に磨けます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。