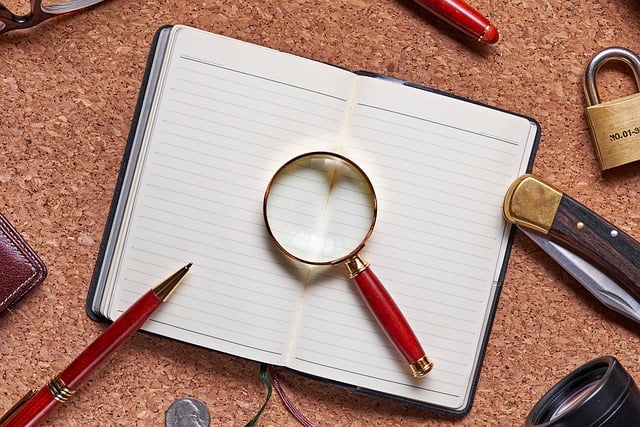玉手箱を採用している企業一覧|ESなしで受けられる練習企業も紹介
「玉手箱って、どの企業が実施しているのか分からない…」
就活を進める中で多くの学生が直面する疑問のひとつです。実際に、玉手箱は大手企業を中心に採用選考で広く用いられており、事前に把握しておくことで効率的な対策が可能になります。
そこで本記事では、玉手箱を実施している企業の一覧から練習に活用できる企業、勉強方法や注意点までを詳しく解説します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
玉手箱の実施企業を把握して高得点を狙おう

玉手箱は多くの大手企業が採用選考で導入している適性検査です。事前にどの企業が玉手箱を利用しているかを知っておくことは、効率的な就活準備に直結します。
試験の形式を理解して勉強計画を立てるだけでなく、応募先の企業が玉手箱を導入しているかを確認することで、無駄のない対策につながるでしょう。
とくにエントリーシートなしで直接玉手箱を受けられる企業もあるため、正しく情報を整理しておくことが合格への近道です。
玉手箱を課す企業を把握できれば、練習問題に取り組む際のモチベーションも高まり、自信を持って本番に臨めます。
結果的に、他の就活生との差をつけやすくなるため、企業一覧をしっかり確認しておくことが重要といえるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
玉手箱とは?

玉手箱とは、就活で多くの企業が導入しているWeb適性検査の1つであり、能力テストと性格検査を組み合わせた形式が特徴です。
特に大手企業や外資系企業では導入率が高く、エントリーシート提出の有無にかかわらず選考初期の関門として利用されることが少なくありません。
出題される問題は言語、計数、英語、性格検査など幅広く、制限時間が厳しいため、内容理解よりもスピードを重視する必要があるでしょう。
つまり、玉手箱は「学力」そのものではなく、限られた時間内で正確に処理する力を測る試験です。就活生にとって避けて通れない試験であり、企業によっては合否を左右する要因にもなります。
そのため、出題形式や傾向を早めに理解し、十分な練習を積むことが本番での焦りを防ぐ近道です。
玉手箱を実施している企業一覧

玉手箱は就活の適性検査として多くの大手企業が導入しています。金融や商社、メーカー、IT業界など幅広い分野で利用されているため、企業一覧を把握しておくことが効率的な対策につながるでしょう。
実際にどの企業が導入しているのかを具体的に理解することで、練習問題に取り組む際の優先度を決めやすくなり、就活全体の準備もスムーズに進みます。
さらに、エントリーシートを提出せずに先に玉手箱を受けられる場合もあるでしょう。
企業ごとの傾向を理解しておけば、出題形式への慣れや時間配分の調整がしやすくなり、本番でも落ち着いて対応できるはずです。
| 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほフィナンシャルグループ 日本生命保険 第一生命保険 野村證券 三菱商事 三井物産 伊藤忠商事 住友商事 丸紅 トヨタ自動車 日立製作所 ソニーグループ パナソニック キヤノン 味の素 富士通 NEC 楽天グループ ソフトバンク |
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
【ESなし】玉手箱を受けられる練習企業一覧

練習の場を活用すれば、試験慣れと同時に自信を持って本番に臨めるはずです。玉手箱をESなしで受験できる企業は、就活生にとって貴重な練習の機会になります。
なぜなら、本番と同じ形式で問題を解けるからです。たとえば人材業界や一部のベンチャー企業では、エントリーシートを出さなくてもWebテストを受けられる仕組みを設けている場合があります。
こうした仕組みを利用すれば、出題の流れを体感できるだけでなく、時間配分の感覚も身につくでしょう。
さらにESが不要なため、結果が思わしくなくても大きな影響はなく、安心して受けられる点も利点です。
ただし、このような企業は毎年固定されているわけではなく、募集状況や年度によって変わることがあります。そのため、最新情報を就活サイトや口コミで確認し、自分に合った練習先を見つけてください。
| DeNA 伊藤忠ネクサス アサヒ飲料 ANA(自社養成パイロット) コーセー 日立物流 三越伊勢丹 NTTデータ KDDI エム・シー・アイ ADL KPMGコンサルティング ニトリ |
玉手箱の勉強方法

玉手箱は多くの企業で導入されているため、しっかりとした対策が欠かせません。ここでは効率的な勉強法を整理しました。
複数の方法を組み合わせることで理解が深まり、本番でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
- 玉手箱対策におすすめの参考書を使う
- 玉手箱の練習問題を繰り返し解く
- 動画サイトで玉手箱の解法を学ぶ
- 玉手箱対策アプリでスキマ時間に学習する
- インターネット上の無料問題集を活用する
- 英語対策として過去問や多読を行う
- 性格適性検査の模擬問題で練習する
- 勉強時間の目安を決めて計画的に取り組む
- 玉手箱のボーダーラインを意識して勉強する
- 出題形式に合わせた時間配分を練習する
①玉手箱対策におすすめの参考書を使う
参考書を活用するのは玉手箱対策の基本です。市販の参考書は過去の出題傾向を踏まえて作られており、実際の試験形式に近い問題を体験できます。
特に数的処理や言語理解の分野は独学では解法をつかみにくいため、解説付きの参考書が大きな助けになるのです。
最初は問題を解くスピードよりも「解法の流れを理解する」ことを意識し、解説を読みながら丁寧に進めると良いでしょう。
そのうえで繰り返し演習を行えば知識が自然と定着し、時間配分にも慣れていきます。参考書を正しく使いこなすことで学習効率は大きく向上し、安定した得点につながるはずです。
さらに、複数の参考書を比較し、自分に合うものを選ぶことも大切でしょう。
②玉手箱の練習問題を繰り返し解く
玉手箱で高得点を取るには、練習問題を繰り返し解くことが欠かせません。模擬問題を解き続けることで出題傾向を把握し、制限時間内での対応力を鍛えることができます。
特に数的処理は時間がシビアなため、問題を何度も解くことで「解く順番」や「見極めのスピード」を体に覚え込ませる必要があるでしょう。
間違えた問題は必ず復習し、なぜ解けなかったのかを理解してください。繰り返すうちに解答のパターンが定着し、自然と処理スピードも向上します。
演習を積むことで不安が解消され、本番で冷静に判断できるようになるでしょう。練習は「質」と「量」の両方が大切で、短時間でも毎日継続する習慣を持つことが効果的です。
③動画サイトで玉手箱の解法を学ぶ
動画サイトは玉手箱の学習において有効なツールです。文章だけでは理解しづらい解法も、図や声で説明されると視覚的・聴覚的に理解しやすくなります。
特に数的処理のように手順が複雑な問題は、実際に解いている様子を見ることで理解が深まるでしょう。再生スピードを調整できる点や、繰り返し視聴できる点も大きなメリットです。
ただし視聴するだけでは実力にはつながらないため、必ず学んだ解法を問題演習で確認する必要があります。学んだ内容をその日のうちにアウトプットする習慣を持てば、知識の定着は一層早くなるのです。
動画をうまく活用することで理解の幅が広がり、学習意欲を保ちながら継続できるようになるでしょう。
④玉手箱対策アプリでスキマ時間に学習する
アプリを活用することで、通学や待ち時間といった短い時間を効率的に学習に変えられます。アプリには1問ごとに短時間で取り組める設計のものが多く、反復学習に最適です。
数的処理の基礎や暗記要素のある分野は、毎日アプリで触れることで確実に力がつきます。さらに、解答時間を自動で計測してくれる機能を備えたアプリもあり、制限時間を意識した練習が可能です。
ただし、アプリだけでは出題範囲を網羅できない場合があるため、参考書や模擬問題と併用することが望ましいでしょう。
スキマ時間を積み重ねると意外なほど大きな成果になりますので、日々の習慣に取り入れることをおすすめします。
⑤インターネット上の無料問題集を活用する
インターネットには無料で公開されている玉手箱の問題集が数多くあります。これを利用すればコストをかけずに幅広い問題に挑戦でき、まずは自分の得意分野と苦手分野を確認するのに役立つでしょう。
無料問題集は手軽ですが、解説が不十分なケースも多いため、理解できない部分は参考書や動画など他の教材で補うことが必要です。
また、最新の出題傾向に基づいた問題を提供しているサイトもあるため、常に情報をチェックして取り組むと良いでしょう。複数の無料サイトを比較して活用すれば、練習の幅が一層広がります。
コストを抑えながら効率的に学習を進めたい人にとって有効な手段です。
⑥英語対策として過去問や多読を行う
玉手箱には英語の問題が含まれる場合があり、苦手な受験生にとっては大きな課題となります。だからこそ、過去問と多読を組み合わせた勉強が効果的です。
過去問を繰り返し解けば、出題傾向を把握できるだけでなく、時間配分の感覚も磨かれます。制限時間を意識して取り組むことで、本番での焦りを防ぐ練習にもなるでしょう。
一方で、多読は読解スピードを上げるために欠かせません。英字新聞やニュース記事、短い英文コラムなどを日常的に読むことで、大意を素早くつかむ力が育ちます。
わからない単語があっても立ち止まらず、文脈から意味を推測する癖をつけることが重要です。これにより、試験中でも落ち着いて長文に取り組めるようになります。
英語力は短期間で劇的に伸びるものではないため、できるだけ早く取り組みを始めることが理想です。過去問で形式に慣れつつ、多読で基礎体力を養いましょう。
⑦性格適性検査の模擬問題で練習する
性格検査は「正解がない」と思われがちですが、企業は回答の一貫性や矛盾の有無を重視します。そのため、模擬問題を解いて慣れておくことが非常に大切です。
実際の設問に触れておくと、どういった観点で質問されるのかを事前に理解でき、当日スムーズに対応できるでしょう。
また、模擬問題に繰り返し触れることで、自分の思考パターンが整理され、一貫性のある回答ができるようになります。
性格検査は能力検査と同じくらい評価に影響を与えることがあるため、軽視せずに取り組むことが必要です。
誠実さと安定感を伝える回答は企業に良い印象を残し、選考を有利に進める大きな助けとなるでしょう。
⑧勉強時間の目安を決めて計画的に取り組む
玉手箱対策を進めるうえで、学習時間を計画的に確保することは欠かせません。漠然と勉強を始めても、十分な成果を得るのは難しいからです。
例えば「平日は1時間、休日は3時間」というように、具体的な時間を決めて取り組むと継続しやすくなります。目安を設定するだけで集中力が高まり、効率的に学習を進められるでしょう。
また、計画を立てることで学習の進捗を確認しやすくなり、「達成感」を積み重ねることができます。進めながら予定を微調整すれば、無理なく学習を続けられるのです。
勉強時間を見える化するアプリやカレンダーを利用すると、習慣化しやすいでしょう。学習の最大の敵は「だらだらと続けること」です。
時間を区切り、計画通りに進める習慣を持つことで集中力が持続し、本番で安定した得点につながります。計画性を持った学習こそが、玉手箱攻略の大きな武器になるのです。
⑨玉手箱のボーダーラインを意識して勉強する
玉手箱には企業ごとに設定される合格ラインが存在し、それをクリアできなければ次の選考に進めません。だからこそ、自分の志望先がどのレベルを求めているのかを把握することが大切です。
もしボーダーラインを意識しないまま勉強すると、必要以上に時間をかけすぎたり、逆に準備不足で落ちたりする危険があります。
事前に口コミや就活サイトなどから情報を集め、自分が狙う点数を明確にしましょう。目標を定めれば学習の優先順位が決まり、無駄を省いて効率的に勉強できます。
例えば「7割を安定して取れるようにする」といった具体的な目標を設定するだけでも、取り組み方が大きく変わります。合格ラインを意識した学習は、戦略的な就活を進めるうえで不可欠です。
限られた時間を有効に使いながら、合格点を超える力を身につければ、自信を持って試験に臨めるでしょう。
⑩出題形式に合わせた時間配分を練習する
玉手箱は制限時間が非常に厳しいため、時間配分を意識した練習が重要です。問題の解法を知っていても、時間が足りなければ得点につながりません。
だからこそ、模擬問題を解くときには必ず時計を使い、制限時間内で処理する練習を積む必要があります。さらに「どの問題から解くか」を自分の中でルール化しておくと有利です。
得意分野を先に解き、難しい問題は後回しにする戦略を試すことで、効率的に得点を稼げます。練習中に複数の方法を試し、自分に合ったスタイルを見つけてください。
時間配分の感覚は一度身につければ大きな強みになります。本番で焦らず落ち着いて解答できるようになり、結果的に安定した得点につながるでしょう。
制限時間を味方につけるための工夫を重ねることが、合格への確実な近道です。
玉手箱を受験する際の注意点
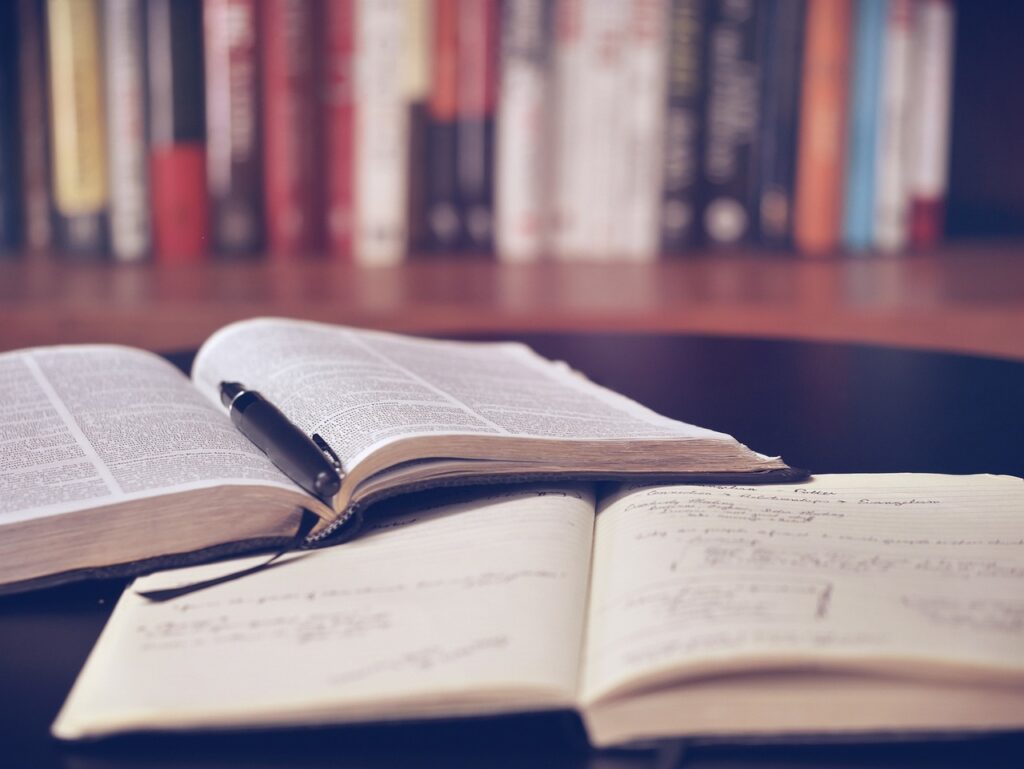
玉手箱は就活で多くの企業が導入している適性検査ですが、仕組みを理解せずに挑むと力を出し切れないことがあるでしょう。
ここでは、受験時に特に意識したい注意点を紹介します。
事前に準備を整えれば、予期せぬ失敗を防ぎやすくなるでしょう。
- 制限時間に注意して素早く解答する
- 途中で見直しできない形式に注意する
- 計数問題の計算スピードに気をつける
- 受験環境を整えて集中できるようにする
- 玉手箱の出題形式が企業ごとに違う点に注意する
- 性格検査は正直に答えて一貫性を保つようにする
- 電卓やメモ用紙の使用可否を事前に確認する
- 通信環境やパソコンの動作を事前にチェックする
- 時間切れでも空欄を残さずマークする工夫をする
①制限時間に注意して素早く解答する
玉手箱の最大の特徴は制限時間の短さにあります。設問数に対して解答時間がかなり少なく設定されているため、1問にこだわっているとすぐに時間切れになってしまいます。
重要なのは正確さを保ちつつも、全体を通して素早く処理する姿勢です。例えば難しい問題に固執すると、残りの問題を解けずに得点を大きく落とす恐れがあります。
練習段階では必ず模擬問題を解き、時間を測りながら取り組んでください。特に計数問題は複雑になりやすいため「解くか飛ばすか」を瞬時に判断する力が不可欠です。
普段から短時間で解答する訓練を積めば、本番でも冷静に対応でき、得点アップにつながるでしょう。
②途中で見直しできない形式に注意する
玉手箱はセクションごとに進行し、一度終わった問題には戻れません。この仕組みを知らないと「あとで直そう」と考えても修正できず、失点を招きます。つまりその場で答えを決めきる力が必要です。
焦って入力すると誤答する可能性があるため、問題文をしっかり読み切ることが大切でしょう。普段から「戻れない」意識を持って演習を重ね、回答後は迷わず次へ進む習慣をつけてください。
事前にこの形式に慣れておけば、余計な焦りを減らし、安定した解答ができるようになります。
③計数問題の計算スピードに気をつける
計数問題は多くの受験生がつまずくポイントです。表やグラフを読み取りながら、短時間で計算する力が問われます。ここで重要なのは暗算に固執しないことです。
メモ用紙が使える場合は、途中式を書くだけで計算効率が大幅に上がります。逆に使用できない場合は、四則演算を工夫する、桁数を簡略化するなどの練習を重ねるとよいでしょう。
さらに過去問を繰り返して頻出パターンを覚え込むことで、瞬時に解法を選択できるようになります。本番は焦りから計算ミスをしやすいので、精度を意識した練習が欠かせません。
④受験環境を整えて集中できるようにする
玉手箱はWeb形式で実施されることが多いため、受験環境の整備が結果を左右します。雑音が多い場所や通信が不安定な環境では集中力が途切れやすく、実力を発揮できません。
静かな部屋を選び、必要に応じてイヤホンやノイズ対策を取り入れてください。さらに、スマートフォンや通知が気になる端末は手元から遠ざけると良いでしょう。
小さな工夫を積み重ねることで集中力を維持しやすくなり、安定したパフォーマンスにつながります。
⑤玉手箱の出題形式が企業ごとに違う点に注意する
玉手箱といっても、出題形式は企業によって異なります。例えば、言語問題は長文読解が中心の形式もあれば、短文穴埋め形式が多い場合もあるでしょう。
形式の違いを理解せずに受けると「想定と違った」と戸惑い、無駄に時間を浪費する危険があります。そのため事前に企業ごとの口コミや体験談を調べ、出題の傾向を確認しておくことが効果的です。
幅広いパターンに対応できるように準備すれば、どの企業の試験でも落ち着いて臨めるでしょう。
⑥性格検査は正直に答えて一貫性を保つようにする
玉手箱には能力検査に加えて性格検査があります。一見すると合否に関係なさそうに思えますが、回答の一貫性は企業が重視するポイントです。
受験生の中には「企業に好かれる答え方」を意識する人もいますが、矛盾が出ると逆効果になります。正直に答えることで自然と一貫性が出て、安定した評価につながるでしょう。
自己理解を深めながら答えることが、信頼される受験姿勢につながります。
⑦電卓やメモ用紙の使用可否を事前に確認する
計数問題では計算量が多く、電卓やメモ用紙の有無が結果に大きく影響します。使用できる場合は効率を上げられますが、禁止されている場合は暗算の工夫や簡略化のテクニックが必要です。
条件は企業ごとに異なるため、案内を事前にしっかり確認してください。準備を怠ると本番で慌ててしまい、実力を発揮できない危険があります。
条件を把握して臨むことで安心して試験に集中できるでしょう。
⑧通信環境やパソコンの動作を事前にチェックする
玉手箱はオンラインで受験することが多いため、通信環境やパソコンの安定性は極めて重要です。回線が不安定だと中断や不具合が発生し、再試験が認められないケースもあります。
試験前にWi-Fiの状態を確認し、有線接続を検討するのも良い方法です。さらにパソコンは事前に再起動して不要なアプリを閉じ、動作を軽くしておきましょう。
こうした準備が集中力を保ち、安心して受験できる環境づくりにつながります。
⑨時間切れでも空欄を残さずマークする工夫をする
玉手箱では問題数が多いため、最後まで解き切れないこともあります。しかし空欄を残すのは避けるべきです。
マーク式であれば適当に選んでも正解する可能性がありますし、最後まで手を動かす姿勢が得点につながるかもしれません。終了間際に残りをまとめてマークする工夫をしておけば、無駄な失点を防げます。
本番では焦りから時間を見失いやすいため、あらかじめ終了間際の対応をシミュレーションしておくことが大切でしょう。
志望企業が玉手箱を実施しているか確認する方法

玉手箱は多くの企業で導入されていますが、すべての企業が同じ形式を採用しているわけではありません。
ここでは、志望先が玉手箱を利用しているかどうかを調べる方法を紹介します。
複数の情報源を組み合わせれば、より確実に把握できるでしょう。
- 就活サイトで企業ごとの選考情報を調べる
- 企業の採用ページで玉手箱実施の有無を確認する
- 口コミサイトや掲示板で過去の受験情報を探す
- OB・OG訪問で玉手箱を受けた経験を聞く
- エージェントや就活支援サービスに確認する
①就活サイトで企業ごとの選考情報を調べる
就活サイトは、企業の選考フローを知るうえで最初に活用すべき情報源です。
利用者が多いため最新の情報が集まりやすく、エントリーシート提出の有無やWebテストの種類が具体的に掲載されていることもあります。
特に大手のナビサイトや口コミが集まる就活サイトは信頼度が高く、全体像を把握するのに適しているでしょう。ただし注意すべきは、掲載内容が毎年必ず同じとは限らない点です。
前年は玉手箱が導入されていても、今年は別の形式に変わる場合があります。そのため、1つのサイトだけを鵜呑みにせず、複数のサービスを比較して確認することが必要です。
時間はかかりますが、異なる情報源を見比べることで正確性が高まります。最新の動向をつかむためには、就活サイトを定期的にチェックする習慣も大切でしょう。
②企業の採用ページで玉手箱実施の有無を確認する
企業の採用ページは、公式に公開される最も信頼性の高い情報源です。選考フローやエントリー手順が明記されており、玉手箱の実施が記載されているケースも少なくありません。
特に外資系企業や大手企業では、応募から内定までの流れを細かく説明していることが多いため、必ず確認する価値があります。
一方で、中小企業やベンチャー企業では採用ページに情報が十分に載っていない場合もあるでしょう。
その場合は他の情報源を組み合わせる必要がありますが、公式サイトを確認しておくことで「噂」と「事実」を切り分けやすくなります。
企業の最新方針を知るためにも、採用ページを定期的に確認する習慣を持つことは非常に有効です。これにより、不正確な情報に振り回されるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
③口コミサイトや掲示板で過去の受験情報を探す
口コミサイトや就活掲示板は、実際に試験を受けた学生の体験談を直接知ることができる貴重な情報源です。
玉手箱を受けたかどうかに加えて、難易度、制限時間、出題傾向など公式サイトには載らない生の情報が投稿されています。
こうした情報は対策を立てるうえで参考になりやすく、よりリアルなイメージを持つことができるでしょう。ただし注意点もあります。口コミは個人の体験に基づくため、必ずしもすべて正確ではありません。
年度や職種によって出題形式が変わることもあり、古い情報をそのまま信じると誤った対策につながる恐れもあります。そのため、複数の口コミを比較して共通点を探すことが重要です。
補助的な位置づけで活用し、公式情報と合わせて確認すれば、信頼性の高い判断が可能になります。
④OB・OG訪問で玉手箱を受けた経験を聞く
OB・OG訪問は、実際にその企業で働いている人から直接話を聞ける最も信頼性の高い方法の一つです。
玉手箱を受けたかどうかだけでなく、当時の準備方法や受験時の雰囲気、選考全体における位置づけなど、具体的で実践的な情報を得られます。
就活サイトや口コミにはないリアルな声を聞けるため、対策の参考になるでしょう。ただし注意すべきは、選考形式は年度によって変更される可能性がある点です。
先輩の体験がそのまま現在も当てはまるとは限らないため、「今も同じ形式かどうか」を確認しながら話を聞くと安心でしょう。
OB・OG訪問は情報収集にとどまらず、人脈づくりや企業理解を深める機会にもなりますので、積極的に活用してください。
⑤エージェントや就活支援サービスに確認する
就活エージェントや大学のキャリアセンターといった支援サービスは、多くの学生のデータを蓄積しており、志望先が玉手箱を導入しているかを調べる際に非常に有効です。
特に就活エージェントは企業と直接やり取りしている場合が多く、最新かつ具体的な情報を持っている可能性が高いでしょう。
また、単に「玉手箱の有無」を確認できるだけでなく、実際の試験の傾向や勉強の仕方についてもアドバイスを受けられることがあります。
自分で情報収集するよりも効率的で、信頼性も高いのが大きな魅力です。さらに、エージェントや支援サービスは他の受験生の動向も把握しているため、比較しながら情報を得ることも可能です。
こうしたサービスを活用することで、安心感を持って就職活動を進められるでしょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
玉手箱の企業対策の総合ガイド

玉手箱は多くの企業で導入されている適性検査であり、就活生にとって避けて通れない試験です。そのため、玉手箱を実施している企業一覧や、ESなしで受けられる練習企業を把握することが大切になります。
さらに、参考書やアプリを使った勉強方法、出題形式に合わせた時間配分の練習など、具体的な対策を積み重ねれば高得点を狙えるでしょう。
加えて、制限時間や受験環境といった注意点を理解し、志望企業が玉手箱を導入しているかを事前に調べることで無駄のない準備ができます。
総合的に考えると、玉手箱の特徴と企業ごとの導入状況を正しく把握し、計画的に学習を進めることが、就活を有利に進めるための確実な方法といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。