就活対策!フェルミ推定の例題・出題例と評価ポイントまとめ
「フェルミ推定って、難しそうで自分にはできないかも…」 と不安を抱える就活生は少なくありません。
フェルミ推定は論理的な思考力や問題解決力を面接官に示すための設問です。外資系コンサルや大手企業の面接では定番となっており、対策をしておくかどうかで評価が大きく変わります。
そこで本記事では、就活でよく出題されるフェルミ推定の例題を系統別に紹介しながら、解き方のステップや評価ポイントを分かりやすく解説します。さらに、実際の出題例や回答例文、練習に役立つ参考書籍までまとめています。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
フェルミ推定とは?就活で求められる背景と意味

フェルミ推定とは、限られた情報から論理的に数値を導く推論方法です。就活では、学生の思考力や課題解決力を確認する目的で用いられることが多く、特にコンサル業界や総合職の選考で重視されます。
ここで評価されるのは答えそのものではなく、どう考え、どう数字を積み上げていくかという過程です。つまり、企業は不確実な状況でも根拠を持って仮説を組み立てられる力を見ているのです。
一方で、「正しい答えを出さなければならない」と思い込むと、考えが硬くなり評価を下げるおそれもあります。大切なのは、面接官に筋道立った思考を伝えることです。
フェルミ推定は単なる計算問題ではなく、自分の論理を示すための道具だと理解してください。そのうえで背景を把握し、日ごろから考える練習を重ねておけば、本番でも落ち着いて取り組めるでしょう。
フェルミ推定で面接官が評価する4つのポイント

フェルミ推定は単なる計算問題ではなく、思考のプロセスを見抜かれる場面です。
面接官は正確な数値を求めているのではなく、問題をどう捉え、どう分解し、どのように説明していくかを重視しています。つまり「考える力」を示すチャンスでもあるのです。
ここでは、面接で評価されやすい4つの観点について詳しく解説します。
- 抽象的なものを具体まで分解する力
- 論理的に説明する力
- 誤りを修正する柔軟性
- 思考を楽しむ姿勢
①抽象的なものを具体まで分解する力
フェルミ推定を問われると、多くの学生が「早く答えを出さなければ」と焦ってしまいますが、面接官が見ているのは曖昧な課題をどう整理し、具体的な形に変えられるかという姿勢です。
例えば「日本にあるコンビニの数」を推定するなら、全国の人口を都市部と地方に分け、それぞれの地域にどれくらいの店舗があるかを推測する、といった段階的なアプローチが有効でしょう。
このように複雑な問題を小さな要素に分けていけば、数字に自信がなくても論理の筋道が伝わりやすくなります。面接官は「自分なりの視点で整理できる人か」を見極めています。
日頃からニュースや日常の出来事を数値に置き換えて考える習慣を持つと、思考を分解する力が自然に磨かれていくでしょう。
②論理的に説明する力
フェルミ推定で最も大切なのは、結果へ至るまでのプロセスを筋道立てて説明できる力です。
面接官は「どうしてその前提を選んだのか」「計算式をどう組み立てたのか」という点に注目しています。自分だけが理解できる説明では評価につながりません。
たとえば「1店舗あたりの利用者数を仮定した理由」を具体的に述べたり、段階ごとに根拠を補足すると、聞き手にとって納得しやすくなります。
さらに、声のトーンや話すテンポにも注意を払うと、より伝わりやすい印象を与えられるでしょう。このスキルは面接に限らず、プレゼンや議論の場面でも役立ちます。
論理の組み立て方を意識的にトレーニングすることが、将来のキャリア全般に生きる基礎力となるはずです。
③誤りを修正する柔軟性
フェルミ推定の場では、途中で計算ミスや仮定の不自然さに気づくことは珍しくありません。その瞬間に試されているのは、間違いを堂々と修正して、軌道を立て直せるかどうかです。
修正できる姿勢は「冷静に状況を見直せる人物」として評価されます。ビジネスの現場でも、初期の仮定がずれていることはよくあり、そのときに柔軟に切り替えられる人材が重宝されるのです。
面接中に「今の仮定は適切でなかったので、こちらに修正します」と一言添えるだけで、思考の柔軟さが際立ちます。
誤りを恐れるよりも、改善のために勇気を持って修正することが、最終的な印象を大きく左右するでしょう。
日常生活でも小さな失敗を振り返り、次にどう活かすか考える習慣を持つと、この柔軟性は自然と鍛えられていきます。
④思考を楽しむ姿勢
フェルミ推定では、単なる数値の推測以上に「考えることを楽しんでいるか」が見られています。
難しい課題に対しても前向きに取り組む学生は、チームで働くときにも良い影響を与える存在と見なされやすいです。
逆に、表情が硬かったり答えが投げやりだと、どれだけ論理的に考えられていても魅力が伝わりません。
面接官は「一緒に働きたいかどうか」を常に意識しており、楽しんで挑戦する姿勢はその判断に直結します。
実際に就活を通して多くの質問に向き合うなかで、考える過程そのものを楽しむことで、結果的に余裕のある態度につながるでしょう。
フェルミ推定の解法を5ステップで解説
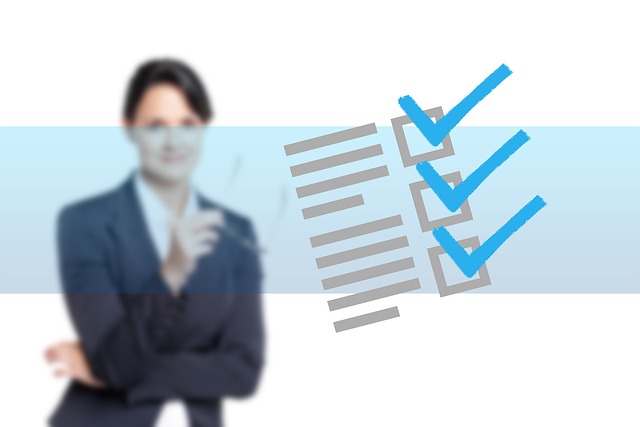
フェルミ推定は就活の面接やケース面接でよく出題されますが、実際に取り組むと何から始めればよいのか迷う人も多いでしょう。
ここでは、基本の5つのステップを順番に整理して紹介します。
流れを意識して練習することで、筋の通った答えを作れるようになるでしょう。
- 前提条件の確認
- アプローチ設定
- モデル化
- 数値計算
- 評価・妥当性の検証
①前提条件の確認
フェルミ推定を解くうえで、最初に確認すべきなのが前提条件です。ここであいまいなまま進めてしまうと、その後の計算や結論に矛盾が生じ、全体の説得力が弱まります。
例えば「日本のカフェ市場規模」を推定するなら、人口をどの数値で固定するのか、都市部と地方をどう扱うかといった枠組みをはっきりさせる必要があるのです。
さらに、利用者の年齢層やライフスタイルをどう想定するのかを補足すると、論理に厚みが出ます。前提条件を面接官に伝えるときは、「なぜその条件を選んだのか」まで簡潔に添えるとよいでしょう。
例えば「人口は1億2000万人と仮定します。最新統計との差は数%ですが、大きな影響はないと考えられるためです」と言えば、納得感を与えられるでしょう。
根拠を明確にすることが、信頼できる推定につながるのです。
②アプローチ設定
次のステップはアプローチの設定です。フェルミ推定には複数の切り口が存在し、人口から逆算するトップダウン型と、店舗数などを積み上げるボトムアップ型に大別できます。
どちらを選んでも構いませんが、説明のしやすさと時間内での展開のしやすさを基準に判断すると安心です。
例えば「利用者数」を推定する場合、人口から始めればシンプルに見えますが、店舗数から考えると地域差を反映しやすい利点があります。
このように選択肢の特徴を理解して選ぶと、質問に対応しやすくなるでしょう。また、アプローチを決めるときは「今回は人口ベースで考えます」と明言してください。
途中で方針を変えると、論理の一貫性が崩れてしまいます。あらかじめ筋道を固めておくことで、答えに自信を持って進められるようになるはずです。
③モデル化
アプローチを決めたら、現実の状況をシンプルに表現するためのモデル化に進みます。モデル化とは、複雑な要素を整理して式や構造に落とし込む作業です。
例えば「カフェの利用回数」を推定するなら、「利用人口 × 1人あたりの月間利用回数」という式にすれば、シンプルで理解しやすい形になります。
ここで大切なのは、モデルが過不足なく主要な要因を押さえているかです。変数を増やしすぎると説明が長くなり、聞き手が混乱します。逆に単純化しすぎると現実からかけ離れた結果になるでしょう。
そのため、重要な要素だけを組み込み、補足的な条件は口頭で説明するのが効果的です。また、面接官に理解してもらうには、図やイメージを頭の中で描きながら整理すると分かりやすく話せます。
論理の流れをシンプルに見せる工夫が、評価を高めるポイントになります。
④数値計算
モデルを定めたら、いよいよ数値を入れて計算します。ここで求められているのは正確な数字ではなく、桁感の妥当さです。
例えば「利用人口6000万人 × 月平均利用回数2回」と仮定すれば「1億2000万回」という推定値が得られます。大切なのは、数字の根拠を説明しつつ計算をスピーディに進めることです。
細かい計算にこだわると時間を消費し、全体像を伝える前に制限時間が終わる危険があります。そのため、四捨五入や切り捨てを活用して、おおまかな値を素早く出すことが重要です。
面接官は答えの精密さよりも、考え方の筋道や処理の合理性を見ています。
したがって「計算を簡単にするため、ここでは100万人単位にまとめます」といった工夫を添えると、論理的で実務的な姿勢を示せるでしょう。
⑤評価・妥当性の検証
最後のステップは、導き出した推定結果が現実的かどうかを検証することです。計算結果をそのまま伝えるだけでは、説得力に欠けてしまいます。
例えば「年間利用回数が12億回なら、1日あたり約3300万回になります。これは主要都市の店舗数から逆算した1日の来客数と比較しても不自然ではありません」と補足すれば、妥当性が高まるでしょう。
検証の方法は複数あります。既知のデータと照らし合わせる、常識的な範囲と比べる、あるいは別のアプローチでざっくり計算して結果を確認するなどです。
こうした工夫によって、推定の正しさだけでなく、思考の柔軟性も伝えられます。面接官が見ているのは、数字そのものよりも「数字を扱う姿勢」でしょう。
自分の答えに自信を持ちつつも、客観的に検証する態度を見せることで、論理的思考力を強くアピールできます。
フェルミ推定を解答する際のコツ
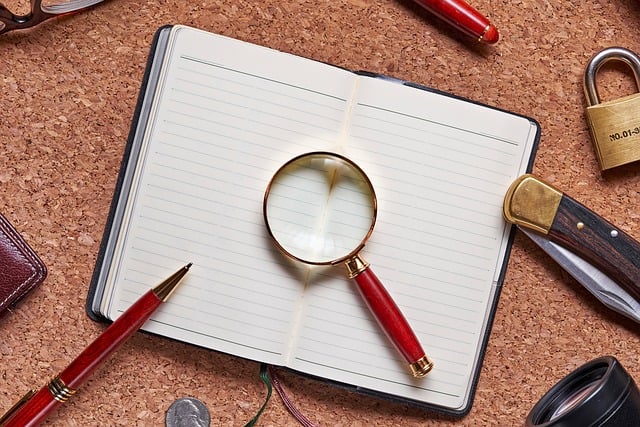
就活の面接やケース面接でよく出題されるフェルミ推定は、準備次第で大きく差がつくテーマです。
初めて挑戦する学生は「どこから手をつければいいのか」と不安を抱きやすいですが、正しい考え方と手順を理解すれば論理的に解答できるでしょう。
ここでは、基礎知識から実践的な工夫までを整理し、解答精度を高めるためのコツを紹介します。
- 基礎知識の習得
- 要素分解の方法
- 基本的な数値の暗記
- 概算での処理
- 因数分解による小分け
- 売上や利益の基本方程式
- 制限時間と配分の工夫
①基礎知識の習得
フェルミ推定を解答するうえで最初に大切なのは、基礎知識を身につけることです。知識がなければ推論の出発点に立てず、論理の説得力も弱く見えてしまいます。
日本の人口や主要都市の世帯数、一般的な商品の価格帯など、生活に直結する数値を把握しておくと有利でしょう。企業が評価するのは正確さそのものではなく、筋道の立て方です。
基礎的なデータを知っていると推論がスムーズになり、面接官に安心感を与えます。数値は暗記ではなく「感覚として掴む」ことを意識するとよいでしょう。
②要素分解の方法
複雑な問題に直面したとき、解答を導くカギになるのが要素分解です。
たとえば「国内のコンビニの年間売上」を推定する場合、店舗数×平均売上と考えると一気に見通しが良くなります。
全体を複数の因子に分ければ、考えやすくなるだけでなく論理も明確になります。さらに要素ごとに仮定を置けば、思考の筋道を相手に示せるでしょう。
普段から物事を分けて考える習慣をつけておくと、本番でも落ち着いて対応できます。
③基本的な数値の暗記
フェルミ推定は知識テストではありませんが、一定の数値を知っておくと大きな助けになります。
たとえば日本の人口は約1億2000万人、東京都の人口は約1400万人、1年は365日といった基本数値です。
これらは前提条件として頻繁に使われるため、覚えておくと計算が止まらず流れを維持できます。結果として解答スピードも上がり、制限時間内により深い推定ができるでしょう。
数字を単に覚えるのではなく、生活の実感と結びつけて記憶するのがおすすめです。
④概算での処理
フェルミ推定では細かい計算精度よりも、概算でのスピードと妥当性が重視されます。1億2000万人を「約1億人」、365日を「約360日」と置き換えるなど、端数を丸めると計算が早くなるでしょう。
正確さを犠牲にしているように思われがちですが、面接官が評価しているのは合理的な近似の工夫です。むしろ細部にこだわって時間を失うほうが不利でしょう。
数字の丸め方を意識して使いこなせば、フェルミ推定はずっと進めやすくなります。
⑤因数分解による小分け
大きな数を扱うときには、因数分解の発想が役立ちます。たとえば「全国の映画館の来場者数」を考えるなら、映画館数×スクリーン数×観客数といった形に小分けすると整理しやすいです。
全体像をざっくり把握できるだけでなく、複雑な問題でも冷静に整理された思考を見せられます。部分ごとに仮定を置きやすくなるため、論理の透明性を出すことにもつながるでしょう。
小分けの発想を持つことで、無理のない推定が実現できます。
⑥売上や利益の基本方程式
ビジネス関連のフェルミ推定では、売上や利益の計算がよく出題されますが、売上は「顧客数×客単価」、利益は「売上−コスト」という基本的な式で表せるのです。
この枠組みを知っているかどうかで、解答の説得力は大きく変わります。式に当てはめれば複雑な問題もシンプルに考えられるため、論理的に進めている印象を与えやすいです。
普段から企業ニュースや商品価格を参考にして、練習しておくと安心でしょう。
⑦制限時間と配分の工夫
最後に重要なのは、制限時間を意識した進め方です。フェルミ推定は短時間で解答をまとめる必要があるため、序盤で時間を使いすぎると全体が完成しません。
要素分解と仮定設定に適度な時間を配分し、その後は概算処理で数字を出す流れが効果的です。多くの学生が時間切れを経験しますが、それは配分を意識していないからでしょう。
練習段階から時間を測り、スピード感を体得しておくことが本番での安心感につながります。
フェルミ推定を解答する際の注意点

フェルミ推定は、就活のケース面接やインターン選考でよく出題されます。数字を使って論理的に考える力を測るために用いられますが、重視されるのは「正解」ではなく「筋道の通った考え方」です。
ここでは、解答するときに意識すべき5つの注意点をまとめました。
- 正確さにこだわりすぎない
- 問題の目的を見失わない
- 根拠のない数値を避ける
- 説明を雑にしない
- 的外れな数値を出さない
①正確さにこだわりすぎない
フェルミ推定では、細かい正確さよりも「妥当な結論」にたどり着くことが重要です。面接官は細部の正答を期待しているわけではなく、論理的に考えを積み上げる力を見ています。
たとえば「東京のコンビニ数」を推定する場合、人口や生活圏を分けて段階的に考えれば、多少誤差があっても十分に納得できます。
逆に数字の正確さにこだわると全体像を見失いやすく、時間も無駄にしてしまいます。大切なのは「現実的に納得できる範囲」で推定を行う姿勢です。
②問題の目的を見失わない
フェルミ推定では、計算に集中しすぎて「設問の目的」を忘れがちですが、出題者が評価しているのは、数字ではなく思考のプロセスや仮定の置き方です。
たとえば「日本で1年間に売れるマスクの枚数」という設問では、季節性や生活習慣といった背景を考える必要があります。
途中で「この問題は何を知りたいのか」と立ち返ることで、方向性を誤らずに進められるでしょう。数値よりもプロセスを意識することが評価につながります。
③根拠のない数値を避ける
推定の過程では仮の数値を置く場面が多くありますが、そのときは必ず「根拠を説明できる数字」にすることが大切です。根拠のない数値を使うと、それ以降の計算全体の信頼性が崩れてしまいます。
たとえば「1人あたり年間に飲むペットボトルの本数」を考える場合、自分や周囲の生活から推測すれば説得力が増します。根拠を示せない場合は、比較や代替の視点を補足するのが効果的です。
「なぜこの数字を選んだのか」を語れる準備をしておきましょう。
④説明を雑にしない
フェルミ推定では、筋道立てて解答する力と同じくらい「伝える力」も見られています。計算が正しくても説明が不十分だと評価は下がってしまうでしょう。
仮定を置いた理由や次のステップにつながる意味を明確に伝えることが必要です。また、話の順序やスピードを意識して、面接官が理解しやすい形に整えることも大切です。
丁寧でわかりやすい説明を心がければ、論理性だけでなく誠実さや安心感も伝わります。
⑤的外れな数値を出さない
最後に注意すべきは「現実離れした結論を出さないこと」です。計算の流れが正しくても、最終的な数値が常識的にありえなければ説得力はなくなります。
たとえば「東京の人口が1,000万人なのにコンビニが10万店」と推定してしまうと、現実との乖離が大きく信頼を失います。これを防ぐには最後に「常識的に妥当か」を見直すチェックが効果的です。
整合性を確かめる習慣を持てば、大きなミスを回避できるでしょう。
系統別に見るフェルミ推定の例題と回答例文

フェルミ推定を練習する際、どの切り口から考えるかでアプローチは大きく変わります。
ここでは、代表的な系統ごとに例題と回答例を整理し、理解を深められるようにまとめました。
①売上推定系の例題と回答例文
大学生の日常生活に身近なテーマとして、カフェの売上を推定する例文を紹介します。数字の根拠を一歩ずつ考えることで、フェルミ推定の考え方を実感できる内容になっています。
| 《例題》 大学近くにあるカフェの1日の売上を推定してください。 《回答例》 大学近くのカフェの1日の売上を推定すると、昼休みには学生が多く訪れるため、1時間あたりおよそ30人が入店すると考えられます。 営業は朝9時から夜9時までの12時間なので、1日の来店者数は30人×12時間で360人程度と見積もれます。さらに1人あたりの平均注文額を500円と想定すると、売上は360人×500円で18万円ほどになります。 週に6日営業しているとすると、1週間では約108万円の売上になると推定できます。 |
この例文では、学生が身近に感じられるカフェを題材にすることで推定がわかりやすくなっています。
同じテーマを書くときは、自分や友人が実際に利用した場所や体験をもとに数字を考えると、自然で説得力のある推定が作れます。
②個数推定系の例題と回答例文
ここでは、大学生がよく関わるコンビニの商品を題材に、どれくらいの個数が消費されているかを推定する例文を紹介します。日常の身近な数字を使うことで、イメージしやすい形にしています。
| 《例題》 大学近くのコンビニで1日に売れるおにぎりの数を推定してください。 《回答例》 大学近くのコンビニで1日に売れるおにぎりの数を考えると、昼休みには学生が多く利用するため、ピーク時間には1時間でおよそ40個売れると見積もれます。 ピークは3時間ほど続くと仮定すると120個程度になります。その他の時間帯は来店者が減るので、1時間に10個売れると考えると、残りの15時間で150個ほどとなります。 これらを合計すると、1日あたり約270個のおにぎりが売れる計算です。週7日営業であれば、1週間ではおよそ1,900個が販売されると推定できます。 |
この例文は、学生の生活で馴染み深いコンビニを使うことで理解しやすくなっています。
同じテーマで書く場合は、自分がよく購入する品物や目にする商品の数を観察して数字に置き換えると、自然でリアルな推定になります。
③市場規模推定系の例題と回答例文
ここでは、大学生にも身近なスマートフォンの市場を題材に、どのくらいの規模になっているのかを推定する例文を紹介します。
普段の生活から数字を拾い出すことで、市場の大きさをイメージしやすくしています。
| 《例題》 日本におけるスマートフォン市場の規模を推定してください。 《回答例》 日本のスマートフォン市場規模を推定すると、まず日本の人口を約1億2,500万人と考え、そのうちスマートフォンを使っている人を8割と見積もると、およそ1億人の利用者がいると考えられます。 さらに平均的なスマートフォンの購入額を8万円と想定すると、市場全体では8兆円の規模があると推定できます。 加えて、平均的に2~3年ごとに買い替えることを考慮すれば、年間ベースでは2.5兆円から3兆円ほどの規模になると考えられます。 |
この例文では、人口や普及率といった誰でも知っている数字を出発点にすることで、推定がスムーズになっています。
同じテーマを書く際は、身近な統計や日常的に触れるデータをもとに組み立てると説得力が増します。
企業の面接で出題されたフェルミ推定の出題例と回答例文

面接やケース面接でよく出題されるフェルミ推定は、実際にどのような問題があるのか気になりますよね。
ここでは、具体的な出題例と回答例文を通して、解法のイメージを掴めるようにまとめています。これにより、面接対策や思考トレーニングの参考にしていただけます。
- 缶コーヒーの年間市場規模を推定する出題例と回答例文
- ペットフードの年間市場規模を推定する出題例と回答例文
- 学習塾の年間市場規模を推定する出題例と回答例文
- 日本の大学生の人数を推定する出題例と回答例文
- 日本の家庭用自動車の台数を推定する出題例と回答例文
- 全国にある美容室の数を推定する出題例と回答例文
- 日本で1日に消費される卵の数を推定する出題例と回答例文
- コンビニおにぎりの年間売上を推定する出題例と回答例文
- 東京ディズニーランドの年間売上を推定する出題例と回答例文
- スターバックス1店舗あたりの年間売上を推定する出題例と回答例文
①缶コーヒーの年間市場規模を推定する出題例と回答例文
缶コーヒーの市場規模を推定する問題は、就職活動の面接でよく出される典型的なテーマです。普段から身近にある商品だからこそ、数字をどう組み立てていくかが試されます。
| 《例題》 缶コーヒーの年間市場規模を推定してください。 《回答例》 缶コーヒーの市場規模を考えると、大学生の半分くらいが週に2本程度購入すると仮定できます。大学生が全国で約300万人いるとすると、1週間で600万本、1年間で約3億本が消費される計算です。 さらに社会人や他の年代も含めると規模は数倍に膨らみ、国内全体では年間数十億本に達すると見込めます。ここから1本あたり150円とすれば、売上は数千億円規模になると推定できます。 |
この回答例では「身近な経験」から仮定を導き、段階的に市場全体へ広げています。自分の生活に根差した前提を置くと説得力が増すため、同様のテーマを書くときも日常の習慣を出発点にするのが効果的です。
②ペットフードの年間市場規模を推定する出題例と回答例文
ペットフードの市場規模を推定する問題は、身近な生活から仮定を広げる力を試す定番テーマです。飼育数や消費頻度をどう推定するかがポイントになります。
| 《例題》 ペットフードの年間市場規模を推定してください。 《回答例》 ペットフードの消費を考えると、全国で犬を飼っている世帯を800万世帯と仮定できます。1世帯あたり1日に300円程度のドッグフードを購入するとすると、1か月で約9,000円、年間で約11万円になります。 これを800万世帯に掛け合わせると約9,000億円規模となり、猫や他のペットも加えれば1兆円規模に達すると推定できます。 |
この回答例では「世帯数×日常的な支出額」で算出しており、シンプルながら現実感を出せます。似たテーマを書く場合は、家庭単位や日常の出費感覚を出発点にすると効果的です。
③学習塾の年間市場規模を推定する出題例と回答例文
学習塾は学生生活で身近に触れる機会があるため、リアリティのある推定がしやすいテーマです。受講生数と授業料をどう組み立てるかが鍵になります。
| 《例題》 学習塾の年間市場規模を推定してください。 《回答例》 学習塾の市場規模を推定すると、全国の中高生の約3割が塾に通うと考えられます。対象者を約1,000万人とすれば300万人が塾に通っている計算です。 1人あたり月2万円を支払い、年間で24万円とすると、合計で7,200億円規模の市場と推定できます。 |
この回答例では「対象人数×平均費用」で規模を算出しています。具体的な経験を踏まえて数字を置くと説得力が増し、記事全体の読みやすさにつながります。
④日本の大学生の人数を推定する出題例と回答例文
大学生の人数を推定する問題は、身近な学生生活から考えやすいテーマです。進学率や学年数を意識して整理することがポイントになります。
| 《例題》 日本の大学生の人数を推定してください。 《回答例》 日本の大学生の人数を推定するにあたり、まず高校卒業生の数を基準に考えます。毎年の高校卒業生はおよそ100万人程度と仮定します。 次にその進路を考えると、大学進学が約50%、専門学校や就職などの他の進路が残りの50%と仮定できます。すると、1学年あたり大学に進学する人数は50万人程度となります。 大学は4年制が基本なので、単純に4学年を合計すると200万人となります。ただし、一部には留年や浪人、また短大・大学院などの進路も存在します。 これらを考慮すると実際の在籍者はもう少し増え、220万人程度まで膨らむ可能性があります。したがって、日本の大学生の人数は200万〜220万人程度と推定できます。 |
この回答例では「高校卒業生数→進学率→在学年数→補正要素」という段階を踏んでいます。
さらに「短大・大学院を除外している」「留年でやや水増しされる」といった補足を入れることで、面接官に対して「単なる掛け算ではなく、実態を意識している」ことを示せます。
フェルミ推定では、こうした前提の理由付けと補正の視点が説得力につながります。
⑤日本の家庭用自動車の台数を推定する出題例と回答例文
自動車は家庭に深く関わるテーマで、世帯数をベースにした推定が効果的です。保有率をどう設定するかで説得力が決まります。
| 《例題》 日本の家庭用自動車の台数を推定してください。 《回答例》 家庭用自動車の台数を推定するにあたり、まず基準となる世帯数を考えます。日本の総人口を約1億2,500万人と仮定し、平均世帯人数を2.5人とすると、全国にはおよそ5,000万世帯があると計算できます。 次に自動車の保有率を考えます。都市部では公共交通が発達しており保有率が低い一方、地方では1世帯あたり複数台を持つ家庭も多いです。 平均すると、全国の約8割の世帯が少なくとも1台は自動車を保有していると仮定するのが妥当です。 さらに、1世帯あたりの平均保有台数を設定します。 都市部では0〜1台、地方では2台以上が一般的なので、全国平均では1.2台程度と見積もれます。 これらを掛け合わせると、5,000万世帯×0.8×1.2=約4,800万台となり、日本における家庭用自動車の総台数はおよそ4,800万台と推定できます。 なお、ここには法人車両や商用車は含んでいないため、全体の自動車保有台数はさらに多いと考えられます。 |
この回答例では「世帯数→保有率→平均台数」という3段階の推定に加え、都市部と地方の差を考慮することで、単なる掛け算に留まらない現実的な仮定を示しています。
面接で答える際には、このように地域差や生活様式を踏まえた補足を加えると、より説得力のある推定になります。
⑥全国にある美容室の数を推定する出題例と回答例文
美容室は日常生活で誰もが利用する場所で、地域の店舗数を基に全国へ展開する推定が適しています。
| 《例題》 全国にある美容室の数を推定してください。 《回答例》 美容室の数を推定するにあたり、まず身近な地域を基準に考えます。大学の最寄駅周辺を思い浮かべると、半径1km圏内におよそ10店舗ほどの美容室が見つかります。 この地域の人口を約5万人と仮定すると、「人口5万人あたり10店舗=人口5,000人につき1店舗」という比率になります。 次にこの比率を全国に当てはめます。日本の人口を1億2,000万人とすると、1億2,000万人÷5,000人=約2万4,000店舗が存在する計算になります。 ただし、美容室には地域差があります。都市部では徒歩圏内に複数店舗が集まっている一方、地方では車移動が前提で店舗密度は低めです。 そこで補正を考えると、都市部でやや店舗が多い分、全国平均としてはもう少し多く見積もれる可能性があります。仮に1.2倍程度を加味すると、全国で3万店舗前後になると推定できます。 |
この回答例では、①「身近な地域の観察」→②「全国への換算」→③「地域差による補正」という3段階で推定を行っています。
フェルミ推定の面接では、単に数字を出すよりも「なぜこの前提にしたのか」「現実的な補正をどう考えるか」を説明できることが重要です。
美容室のように身近なテーマでは、自分の生活実感と統計的な推定を組み合わせると説得力が高まります。
⑦日本で1日に消費される卵の数を推定する出題例と回答例文
卵の消費量を推定する問題は、日常の食習慣から具体的に考えやすいテーマです。家庭料理や外食を想定して計算を広げていきます。
| 《例題》 日本で1日に消費される卵の数を推定してください。 《回答例》 卵の消費量を推定すると、日本の人口を1億2,000万人と仮定し、1人あたり平均で2日に1個食べると考えられます。すると1日あたり約6,000万個が消費される計算です。 さらに飲食店や加工食品も加えると、全体では1日1億個前後になると推定できます。 |
この回答例では「1人あたりの食習慣」を基準に全国規模に展開しています。自分の生活習慣を出発点にすることで、数字に実感を持たせられます。
⑧コンビニおにぎりの年間売上を推定する出題例と回答例文
コンビニおにぎりは大学生にとって身近な商品で、日常利用を基に考えると推定しやすいテーマです。購入頻度と単価を組み合わせて考えます。
| 《例題》 コンビニおにぎりの年間売上を推定してください。 《回答例》 コンビニおにぎりの年間売上を考えると、まず購入者数を推定します。日本の人口を1億2,000万人と仮定し、そのうちコンビニを日常的に利用する層を半分程度の6,000万人と見積もります。 さらにその中で実際におにぎりを購入するのは8割程度とすると、購入者は約5,000万人となります。 次に購入頻度を考えます。多くの人は昼食や小腹が空いたときにおにぎりを買うと考えられるので、平均して1人あたり週に2個購入すると仮定します。 すると5,000万人×2個=1週間で1億個が販売される計算になります。これを1年間(52週)に換算すると、約52億個になります。 最後に単価を考えます。おにぎり1個の平均価格を150円とすると、52億個×150円=7,800億円程度となり、コンビニおにぎり市場全体は年間で約8,000億円規模と推定できます。 なお、ここには季節商品や高価格帯商品が含まれるため、実際の規模はもう少し大きくなる可能性があります。 |
この回答例では「購入頻度×人口×単価」で売上を算出しています。日常的な買い物習慣を基準にすることで、自然に読者がイメージできます。
⑨東京ディズニーランドの年間売上を推定する出題例と回答例文
東京ディズニーランドは多くの学生が訪れる人気施設で、来園者数と消費額を基に推定できます。娯楽系のテーマは数字の根拠を工夫すると効果的です。
| 《例題》 東京ディズニーランドの年間売上を推定してください。 《回答例》 東京ディズニーランドの年間売上を考えると、まず年間来園者数を3,000万人程度と仮定します。これはテーマパークとして世界的にトップクラスの集客力を持つ施設という点を踏まえた数字です。 次に、1人あたりの平均支出を分解して考えます。入園チケットが約8,000円、さらに園内での飲食やお土産などを合わせて2,000円程度と見積もると、1人あたりの支出は合計1万円になります。 したがって、3,000万人×1万円=3兆円程度が年間売上の規模になると推定できます。 なお、繁忙期と閑散期の差を考慮すると多少の変動はあるものの、大きなオーダーとしては数兆円規模であると考えられます。 |
この回答例では「来園者数の仮定」と「支出をチケット代+飲食・物販に分解」という2段階の根拠を示しています。
面接でのフェルミ推定では、ただ数字を出すだけでなく「なぜその前提を置いたのか」を説明できると説得力が増すでしょう。
また、支出を分解して考えることで、面接官に「論理的に要素を積み上げている」という印象を与えられます。
⑩スターバックス1店舗あたりの年間売上を推定する出題例と回答例文
カフェは大学生にとって身近な空間で、スターバックスの売上推定は人気のあるテーマです。客数と単価を掛け合わせて考えるとシンプルに導けます。
| 《例題》 スターバックス1店舗あたりの年間売上を推定してください。 《回答例》 スターバックス1店舗の売上を推定すると、1日あたり平均500人が来店し、1人あたりの支出を500円と仮定できます。すると1日で25万円、年間で約9,000万円になります。 ドリンク以外の商品も考慮すると、実際は1億円規模になると推定できます。 |
この回答例では「来店客数×単価×日数」で算出しています。実際に通った頻度や金額を基準にすることで、数字に現実味を持たせられます。
フェルミ推定を学ぶためのおすすめ書籍・参考資料
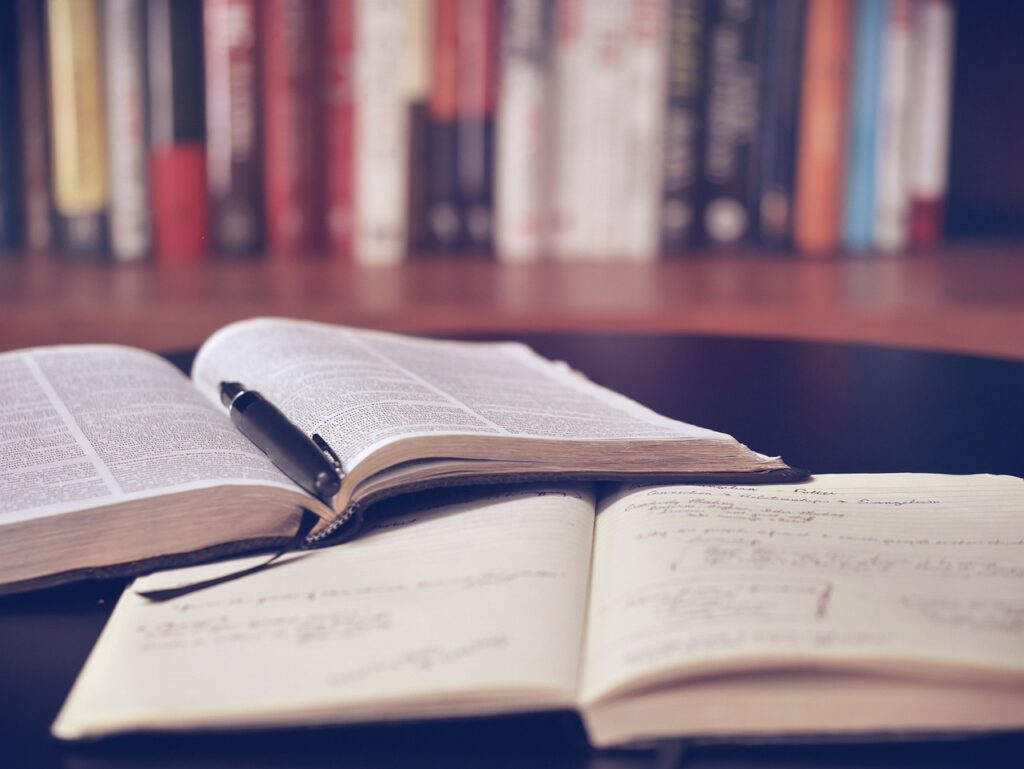
就活のケース面接ではフェルミ推定が定番テーマですが、独学だと「どこから始めればいいのか分からない」と悩む人が多いでしょう。
その不安を解消するには、自分の段階に合った書籍や資料を活用するのが効果的です。
ここでは、基礎固めから実践演習、さらに面接対策までを段階的に学べる参考書を紹介します。
- 基礎を学べる入門書
- 実践力を養う問題集
- ケース面接対策の参考資料
①基礎を学べる入門書
フェルミ推定を学ぶうえで基礎を固めることは不可欠です。考え方の枠組みや大まかな数値を導くプロセスを理解していないと、面接で論理が飛躍してしまったり、説明に説得力を欠いたりします。
入門書を読むことで「なぜ数値を大づかみに推定するのか」「どうやって仮定を置くのか」といった根本を理解できるでしょう。土台を築くことで、自信を持って次のステップに進めます。
【おすすめ書籍】
- 『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』
- 『イシューからはじめよ』
- 『考える力が身につくフェルミ推定入門』
②実践力を養う問題集
基礎を理解したあとは、実際に手を動かして解法のパターンを身につけることが重要です。時間内に論理を整理し答えを導く力は、繰り返しの演習でしか鍛えられません。
問題集に取り組むことで、自分の思考の癖や見落としがちな点に気づけます。失敗を分析し改善する経験は、本番での冷静な対応力につながるでしょう。実践演習を積むことで、応用力が自然と高まります。
【おすすめ書籍】
- 『フェルミ推定の技術』
- 『外資系コンサルが教えるケース面接突破法』
- 『ロジカル面接術』
③ケース面接対策の参考資料
フェルミ推定の最終的な活用場面はケース面接です。ここでは「答えの正確さ」よりも「論理を分かりやすく伝える力」が評価されます。
ケース面接対策の資料を活用すると、実際の出題傾向や面接官が重視するポイントを理解できます。模範回答を学ぶことで、自分の説明に説得力を持たせる工夫を知ることもできるでしょう。
資料を通じて繰り返し練習することで、本番で堂々と答えられるようになります。
【おすすめ書籍】
- 『現役コンサルタントが教えるケース面接攻略法』
- 『戦略コンサルティング・ファームの面接試験』
- 『ケース面接必勝法』
フェルミ推定に関するQ&A(よくある疑問を解説)

就活生がよく疑問に感じるフェルミ推定について、Q&A形式で解説します。出題意図や準備方法、失敗時の対応などを知っておくと安心でしょう。
ここでは、特に就活の現場で役立つポイントをまとめました。
- フェルミ推定の準備にはどのくらいの時間と方法が必要か?
- フェルミ推定は独学でも対応できるのか?
- フェルミ推定で失敗したときはどう対処すればよいか?
- フェルミ推定は文系と理系で有利不利があるのか?
- 面接本番で電卓を使うことはできるのか?
- 暗記しておくべき基礎データはどの範囲か?
- 計算が一部間違っても評価されるのか?
- フェルミ推定とケース面接は何が違うのか?
- フェルミ推定はグループディスカッションでも出題されるのか?
- フェルミ推定を練習するのにおすすめの方法は何か?
- フェルミ推定は他の選考対策にも役立つのか?
①フェルミ推定の準備にはどのくらいの時間と方法が必要か?
フェルミ推定の準備には最低でも数週間から1か月程度が必要です。基本の流れを理解するだけでなく、さまざまなテーマに触れてパターンを積み重ねる必要があります。
準備方法は、まず解法ステップを確認し、次に過去問や想定問題を繰り返し解くのが効果的です。振り返る際には正解かどうかより、分解の妥当性を重視してください。
さらに、普段の生活で市場規模や人数を推定する練習を取り入れると、着実に力がついていきます。短期間でも工夫すれば十分に成長できます。
②フェルミ推定は独学でも対応できるのか?
独学でも対応できますが、効率を意識することが必要です。まずは書籍や記事で基本を学び、次に例題を解くことで理解を深めてください。その際、自分の答えを他人と比較するのが効果的です。
違いを知ることで、自分では気づけなかった切り口に出会えるでしょう。また、1問ごとに仮説を立て、計算し、検証し、振り返る流れを繰り返せば、独学でも十分な実力を養えます。
工夫と継続があれば、一人でも実戦的な力を伸ばすことができるのです。
③フェルミ推定で失敗したときはどう対処すればよいか?
失敗しても焦らずに対応することが大切です。企業は正解を求めているわけではなく、考え方や姿勢を見ています。
計算が合わなくなった場合でも「仮定を見直します」と冷静に切り替えると、修正力として評価されます。逆に黙ってしまうと印象が悪くなるので、考えを言葉にし続けることが重要です。
想定外の問題でも、自分なりに分解して説明できれば十分にプラス要素となります。失敗を恐れる必要はなく、むしろチャンスと捉えて落ち着いて対応してください。
④フェルミ推定は文系と理系で有利不利があるのか?
文系理系で大きな差はありません。必要なのは高度な計算力ではなく、身近な数字を使って筋道を立てる力です。
理系は数値処理に慣れているため計算は速いかもしれませんが、文系でも仮定の整理力や説明力を活かせます。企業は多様な視点を評価するため、理系的な分析や文系的な発想のどちらも歓迎されるでしょう。
専攻を気にするより、論理をわかりやすく伝える力を磨くほうが効果的です。
⑤面接本番で電卓を使うことはできるのか?
電卓が使えるケースはほとんどありません。フェルミ推定は正確な計算を測る場ではなく、概算や切り捨てなどを工夫する力を評価するためです。
面接官は、電卓がなくても論理を崩さず進められるかを見ています。準備段階では、二桁や三桁の掛け算を素早く処理できるよう練習すると安心です。
大切なのは、大まかに数字を扱う力であり、計算機がなくても自信を持って答えられるようにしておきましょう。
⑥暗記しておくべき基礎データはどの範囲か?
覚えておくと便利な数値は、日本の人口や世帯数、主要都市の人口、平均的な単価や面積などです。これらを知っていると、仮定を立てるときにスムーズに進められます。
すべてを覚える必要はありませんが、よく使う数字を頭に入れておくと便利です。例えば「日本の人口は約1.2億人」「東京の人口は約1,400万人」「1世帯の人数は2〜3人」などが代表的でしょう。
基礎を押さえることで計算も速くなり、説得力のある推定が可能になります。
⑦計算が一部間違っても評価されるのか?
一部の計算ミスがあっても大きな問題にはなりません。面接官は正確な答えではなく、仮定や論理の流れを見ています。途中に誤りがあっても、思考の過程が明確なら評価されるでしょう。
さらに、小さな間違いに気づいて冷静に修正する姿勢はプラス評価になります。数字にこだわりすぎるよりも、根拠をきちんと説明することが重要です。
完璧さを求めるより、論理を途切れさせない工夫を意識してください。
⑧フェルミ推定とケース面接は何が違うのか?
フェルミ推定とケース面接は似ていますが目的は異なります。フェルミ推定は数値を通じて論理を示す練習であり、短時間で思考を整理する力が求められます。
一方でケース面接は、広いビジネス課題に対して解決策を議論する形式で、定性的な発想も重視されます。つまり、フェルミ推定は「数量的な仮定力」、ケース面接は「戦略的な発想力」を測るものです。
違いを理解しておくと準備がしやすく、両方に対応できる柔軟さが評価されるでしょう。
⑨フェルミ推定はグループディスカッションでも出題されるのか?
グループディスカッションでも出題される場合があります。特にコンサルや外資企業では、協力して論理を組み立てる力を見るために活用されるのです。
個人面接と違い、ここでは自分の意見を主張するだけでなく、他人の意見を取り込みながら進める姿勢が重視されます。
リーダーシップよりも合意形成の姿勢が評価されやすいため、練習時から意識しておくとよいでしょう。まとめ役として発言を整理できると大きな強みになります。
⑩フェルミ推定を練習するのにおすすめの方法は何か?
一番の方法は実際に例題を解くことです。日常のテーマを使い「カフェの来客数」や「駅のトイレ利用者数」などを推定してみると、自然に思考力が鍛えられます。
友人と答えを比べたり、声に出して考え方を確認したりすると理解も深まるでしょう。また、制限時間を設けて練習すると本番に近い緊張感を体験できます。
重要なのは、解いた後に振り返り、仮定の妥当性を改善していくことです。繰り返せば直感的に数字を扱えるようになり、自信につながります。
⑪フェルミ推定は他の選考対策にも役立つのか?
フェルミ推定の力は就活全体に応用できます。エントリーシートや面接で論理的に自己PRをする際や、課題解決の経験を話す場面でも役立ちます。
さらにグループディスカッションやプレゼンでも、情報を整理して伝えるスキルとして評価されるでしょう。
つまり、フェルミ推定は就活の一場面にとどまらず、社会人になってからも会議や企画立案に活かせる力です。学生のうちに鍛えておけば、長期的に強みとなるでしょう。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
練習を繰り返して自信を持って挑もう

フェルミ推定は、単なる計算問題ではなく、就活や面接で論理的思考力や柔軟性を示すための重要なテーマです。
評価されるのは「分解力」「論理性」「修正力」「楽しむ姿勢」であり、正確さよりも妥当性が重視されます。
そのためには、前提条件を押さえ、アプローチを整理し、数値を概算で導く練習を積むことが不可欠です。
売上や市場規模を推定する例題を繰り返すことで、自分なりの解法パターンが身につき、自信を持って回答できるようになります。
コツを意識しながら繰り返しトレーニングすることで、面接本番でも落ち着いて挑戦でき、論理的思考力をアピールできるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












